【137頁】
学習院大学 経済論集 川嶋ゼミナール主催 公開講演会 実施報告
話すスキルを磨く
——町おこし事例に見る話しことばの重要性——
(財)NHK放送研修センター・日本語センター チーフ・アナウンサー
肥土 貴美男
▽はじめに
いま,何故,話す能力を磨く必要があるのか?
それは,社会がコミュニケーションで成り立っているから。
コミュニケーションの目的は情報をやり取りすること。
コミュニケーションに関して気になるデータがある。
NHK日本語センターが小中高校の教諭800人あまりを対象に「話しことば」についてアンケートを実施したところ,6割を超える先生が「子どもたちはおしゃべりは得意だが,人前できちんとした話しが出来ない」と回答した。
また,「きちんとしたことばづかいで話すのが苦手」であり「人の話しを聞くことができない」子どもたちが目立つという結果だった。
更に,アンケートに協力してくださった先生方の8割近くが「話すこと・聞くことの指導に自信がもてない」と答えている。
「話しことば」について企業経営者にもアンケートを実施した。
「筋道を立てて話す力の不足している社員が目立つ」と回答した経営者が8割近くに上った。
このことから,学校でも,社会でも,「話す力」「聞く力」=コミュニケーション力の不足は気がかりな問題になっていることが類推される。
【138頁】
▽大学生にとっても,コミュニケーション力を身につけることは?
就職に必要な基礎能力として重要であり,また,大学生活を送る上でも大切な力になる。
▽町おこしで知った「コミュニケーション力」の大切さ…
●田子町との出会い
青森放送局勤務のころ。1980年代後半,さかのぼること17年前,時代状況は今日とよく似ていた。
国の財政状況は悪化,地方の景気は低迷を続け,国が地方の面倒を見ていられない,とにもかくにも財政再建に躍起になっていた頃。
「ももくり植えてハワイに行こう」という町おこしのキャッチフレーズがにわかに脚光を浴びた。
このキャッチフレーズは,大分県大山町で生まれた。
桃や栗を育て,町の特産品を作った大山町。キャッチフレーズを目標にして,町は勢いを取り戻した。
やがて,全国各地に「まちおこし」「むらおこし」ブームが巻き起こった。
●危機感漂う町を変えるヒントは「ニンニク」だった
当時,私は青森局に勤務していた。地域の情報を番組にしようと田子町(たっこまち)を訪ねた。田子町は,十和田湖に近い過疎の町。人口が1万人を割り込み,町で唯一の商店街が洪水で壊滅的な被害を受け意気消沈していた。そんなときの取材活動だった。
データを見ると全国一のものが田子にあった。それはニンニクの生産高だった。ところが,町で話しを聞いてみると「ニンニクなんて自慢になんねえ」と,役場でも農協でも言う。予想外の反応だった。
この町を再生させるための鍵を握るもの,それが「ニンニクではないか」と考えていたのだが,何故か町の人はそう思っていなかった。そこで,更に事情を把握しようと,各方面で聞いてみることにした。方言を理解する力が足りず,しんどかったが,事情が飲み込めた。
ニンニク生産農家を訪ねた。「うちは米が作れないから,ニンニク作っている。ニンニクは子牛(べこっこ)の風邪予防と,母牛が丈夫な子牛を生むために食わせて,くずニンニクは土に戻して耕作地の地力を付けるために使い,無駄にしない。そこに野菜だの豆だの作付けしている。冷涼だどこでぇ,いづ冷害に襲われるかわがらねえがらのぉ」と話してくれた。
かつてから,稲作中心の農業経営で,しかし等級の低いコメしか作れず,だから,致し方なくニンニクを栽培してきたのだという。ニンニクを作付けしているのは冷涼な山間地農業の知恵であった。ひっくり返して考えてみると,自然条件に適した環境にやさしい農業の実践例なのだが,それは当時少数派の見解だった。
「あの町はニンニクのにおいで臭い」とか,「田子町の牛乳はニンニク臭い」など,川下の町などからは意地の悪い言い方もされていたようだ。
●再生のキーウーマンに出会う
取材が進むうちに,きらっと光る人に出会った。佐野房さん。ニンニク農家の元気なおばち【139頁】ゃん。佐野さんは,ニンニク料理を町民に広めたいと考え,納屋を改造して料理の工房を建てた。
佐野さんはこの工房でニンニクの新商品を作ってしまった。その名は「にんにこちゃん」
ニンニクを味噌しょうゆダレに漬け込み瓶詰めにしたもの。この新商品は,食べてみると臭みも程よく抜けていて,おいしい。ご飯に合う。
町民が町の将来に悲観的な中で,佐野さんは農協婦人部の仲間と淡々と実行に移していった。瓶詰めは同じ青森県八戸市の生協で取り扱いが決まり,あっという間にヒット商品になった。町の一村一品第一号になった。
私は,前向きな人に会えた悦びを感じ,情報をまとめ番組にしていった。町の農業事情,佐野さんたちの暮らしの工夫。町民が気づいてこなかった食材の豊かさ。番組によって町のことが再認識され,番組に関心を持ってくださった人も少なくなかったようだ。
●バカとアホのいい関係で町おこしを…
やがて,私のところでも,田子のニンニクについて問い合わせが増え始めた。そんな折に「ニンニクでシンポジウムを企画している」という田子町役場の職員に出あった。
「最近,町民のニンニクに対する印象がガラリと変わった。町の起爆剤になりうる」と言う。
町民の間にニンニク効果が出始めたと感じた。
ニンニクを町民の自慢にするためにシンポジウムを開催しようという計画が議会で決定した。
ついに「ニンニクシンポジウム」開会の日が来た。
基調講演のテーマは「ドラキュラとニンニク」
ステージにニンニクがうずたかく積まれたホールは,満員。ちょっと不思議なタイトルだけに,町民の関心は高く,皆話しに耳をそばだてていた。
講演者は,中世ヨーロッパ史がご専門で,現在,国立西洋美術館長の樺山紘一さん。ドラキュラがニンニクに弱い理由について,樺山さんのお話しは「吸血鬼というのは,ペストなど人々が恐れた伝染病を怪人にたとえたもので」「中世ヨーロッパでは,ニンニクが伝染病を退治してくれる正義の味方だった」という内容で,町民がへーっと驚嘆する勧善懲悪の物語に仕上がっていた。まさに「町おこしのヒーローに,にんにくが駆け上がった」瞬間だった。
更に,樺山さんは「スペイン語で,牛のことを『バカ』という。そして,ニンニクのことを『アホ』という。田子はこの両方が良い関係を作っている。思いっきりバカになって町おこしに取り組もう」とおっしゃった。
シンポジウム開催が,誇りを町民が取り戻すきっかけになった。
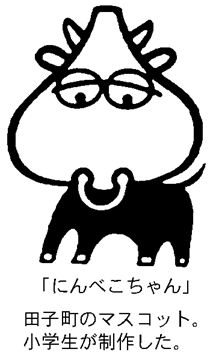
●ニンニクはコミュニティ作物
掘り探れば探るほど面白い作物「ニンニク」
私にとってもうひとつの発見は,会話を育む作物だったということ。
ニンニクは掘り出したあと乾燥させ,泥のついた薄皮をむいて真っ白いニンニクにし,箱に詰め出荷する。一人では,毎日の出荷に,とても手が回らないから,山のように積んだニンニクを真ん中に,家族皆で皮むきをする。子どもたちも学校から帰ってきたら手伝う。おじ【140頁】いさん,おばあさんも手伝う。
当然いろいろな話しをするようになる。皆で,情報を共有する,学校のことも,近所のことも話しが通じ合う。ニンニクはコミュニケーションを生み出す作物。
コミュニケーションは良いほうに回りだすと強みになることが多い。以前の「だめだ,だめだ」の連鎖が,ころっと,プラス思考の連鎖に変わった。その現場を田子で幾たびか私は見た。その中で最も印象深いのが「タプコプ町民塾」この塾は,まさに,プラス思考のすばらしい会だった。外から町を見つめてくれる人たちと町民が語り合う場として町民塾は発足した。タプコプは田子を表すアイヌ語をモチーフに命名した。
塾の初会合に私も参加した。酒屋の店主Mさんが「どぶろく」片手に立ち上がり「わだば,カリフォルニアで大工仕事を何年間かやってきた。白人大工作業員たちが建てる家が,予定よりも遅れている箇所を手直ししたり,雑に仕上げてしまっている箇所を,図面の通りに予定の工程まで進める仕事をやってきた。ヒスパニックの大工さんたちとともに転々と移動しながら働いた。カリフォルニア・ギルロイという町で家造りに取り掛かっていたとき,この市でニンニクを一日中食べるフェスティバルがあって,参加した。聞くと,ギルロイは米国でナンバーワンのニンニク産地。ニンニクのおかげで市民が元気で明るかった。
そこでだ,ギルロイに姉妹都市の縁組を結びに行かねが?」と発言した。
「アメリカのニンニクは,どんなニンニクだ?」メンバーが聞く。「パウダーだ」「パウダーのぉ?」「粉っ子けぇ?」
「へば,どんな使い方すんだべが?」…とドンドン話が飛び交って。「調べてみよう」「先遣隊を送り込もう」「姉妹都市の縁組だ」と進展してゆく。
町おこしの意識が町民に通い合ってゆく。町おこしが人間ドラマになってゆく。
「恐るべし,田子のニンニクパワー」であった。
この顛末は拙著「21みちのくロマン」の中で「ニンニクハートロード」と題して著した。
●暮らしと経済の仲をとりもつコミュニケーション
私自身,田子町が全国に知られる「ニンニクの町」になるとは思ってもみなかった。
ニンニクシンポジウムを後押しして,全国放送をたびたび出し,ニンニクの町の元気をアピールした甲斐があったと,いま改めて思う。
私にとって,この町おこしに立ち会えたことは,取材力を磨き,情報を発信することの意義を感じ,ジャーナルな仕事を積み重ねてゆくことの魅力を知るエポックメーキングな出来事であった。
ニンニクを核に,町の人と情報の輪を描いた実感があった。コミュニケーションが情報を育てた実感があった。
当時,経済的に苦しい状況なのはどの町も同じで,そこにはたくさんのやる気のある人がいたのだが…田子町が県南部のどの町よりも早くに町おこしに動き出せたのは…何故?
あらためて,人と人とのコミュニケーションがいかに欠かせないかつくづく思い返す?
コミュニケーションは,一方的に話して伝えるだけでは成立しない。人と人との…である。
【141頁】
▽講演の後半は実習で玩味する
●そこで,受講者のコミュニケーション力をチェックし,その上で話すスキルを磨く
実際に人前で話してみて,自己認識してもらう
▽具体的実習
●パブリックスピーキングを知っておこう
私的な話しことば=おしゃべり など
パブリックスピーキング=公的な場での話しことば
パブリックスピーキングとは…人前で話す基本
改まった場で,一定の内容を,一定の時間内に,筋道を立てて話すこと
皆さんは,人前でどう話しているだろうか?
●課題 次の例文を,もっとわかりやすい話しことばに。
(レクリエーションのルート選び)の説明を,あなたならどう話すか?
『軽井沢にレクリエーションで行くことになりましたが,皆さんで話し合って
欲しいのですが,これから3つルートを説明しますので,全部集合場所は
目白駅になっていまして,この中から最良のを選択して欲しいと思って
いますので,よろしくお願いします」
ワンポイント…
「届く声,短いセンテンス,やさしいことばで話す」ことを意識すること。
●日本語には「同音異義語」が多い 聞いてわかりやすい表現に
ワンポイント…科学・化学 荒天⇔好天
課題 商品説明をする店員。
ワンポイント…自分のことばで話す
課題 人の話しを聞きとる (内容を聞いて考える)
ワンポイント…長く話せば分かりやすいわけではない
※課題を整理し,受講者に発表してもらった。その上で,ポイントを押さえた。
▽やさしい敬語
最近気になる敬語から…
●「よろしかったでしょうか?」の氾濫
「よろしかったでしょうか?」は,確認や念を押すときに使うなら問題ない。
しかし「こちらのお皿,お下げしてよろしかったでしょうか?」と店員にいきなり聞かれ【142頁】たら,違和感を感じないか?
●「千円からお預かりします」
本来「千円をお預かりします」でいいはず。
そうすると,「その千円から,500円をいただきますので,500円のお返しです」
これを,省略して「千円からお預かりします」と短くいう。
●「こちらコーヒーになります」
(カップの中の液体がコーヒーにじきになるのならいい)
「コーヒーです」がぶっきらぼうに聞こえるためのぼかし表現。
敬語に慣れていない若い人に目立つ敬語表現の誤り例。
●「お箸のほうはだいじょうぶですか?」
「心配ありません」というニュアンスで「大丈夫?」としてしまう。
▽敬語には気持ちを込めて。敬語には相手を気遣う思いがこめれれている。
敬語は日本語コミュニケーションの原点
●課題 尊敬語と謙譲語の使い方
敬語の種類…小学校の教科書を参考に点検
▽終わりに
コミュニケーション力を身に付けること,それは,相手の立場に立ち,理解してもらえるように話す表現力と聞く力を磨くことにあると認識して欲しい。
今回は,簡単なスキルトレーニングを行ったに過ぎない。
皆さんには,社会に出て行く前に,話しことばを磨く機会に積極的に触れて欲しい。
音としての日本語の特性などにもこだわってみると,話しことばに新たな魅力を感じてもらえると思う。話しことばの担い手である皆さんに期待する。豊かなコミュニケーション社会の構築のためにも。
最後に,今回,講演の機会を与えてくださった川嶋辰彦教授,そして,企画提案を初め講演会開催の準備を進めてくださった川嶋ゼミナールの学生の皆様に改めて感謝申し上げます。
NHK放送研修センター・日本語センター
肥土貴美男
平成18年2月5日