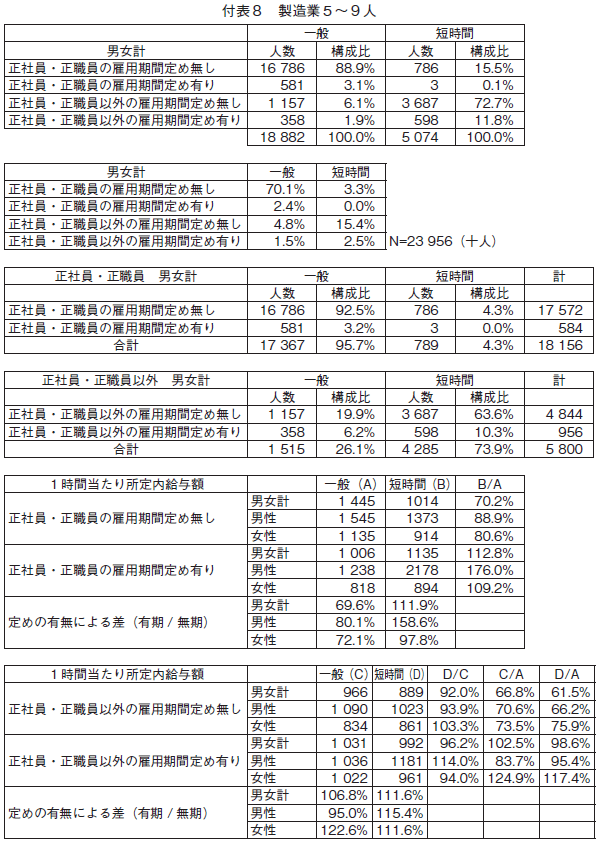�y241�Łz
���Ј��E���Ј��ȊO�̎Ј��̌ٗp���Ԃ̒�߂̗L���ƘJ�����Ԃ̒��Z
�\�\�����Z���T�X��p���ā\�\
�e��@��
1�@�͂��߂�
�M�҂́C����܂Łu�K�Ј��v�Ƃ������t�̕s�K�ؐ����w�E���Ă����i�e��2009�C2010�j�B���R�͂��������邪�C�Ƃɂ����E��̎��ԂƂ�����Ȃ�����ł���B���Ј�/ �Ј��̂Q�敪��p���C��҂̑����ƌٗp�̕s���肳�⏈���̒Ⴓ�ɂ��āC�e�����v���l�ɂ�蓖�R�̑O��Ƃ���c�_���������߂ł���B�����͑��l�ł���C���̑O��͋^�킵�����C���鎞���܂ŁC�����[�I�Ɏ����f�[�^���Ȃ��Ȃ������Ȃ������B
���̑��l���������f�[�^������C�Ȃ����������킩��B���������̊�{�I���v�ł�������\����{���v�����i�ȉ��C�����Z���T�X�j�ł́C�ٗp�`�Ԃ̑��l���̎��Ԃ�c�����邽�߂ɁC����17�N�i2005�N�j�̓��v����傫�Ȑݖ�̕ύX��������ꂽ�B
���R�c��T �������296���̓��\�i ����16�N12��10��http://www.stat.go.jp/index/singikai/2-296b.htm�j�ɂ��ƁC�����\����{���v�����̉������ɂ��āC���̂悤�ȋL�q������B�u�����\����{���v�����v�́u�����Ώۂɂ��ẮC��p�J���҂𐳎Ј��y�ѐ��Ј��ȊO�ɕ�������ƂƂ��ɁC��p�J���҂ɊY�����Ȃ��J���҂�Վ��J���҂Ƃ��ĐV���ɒ����Ώۂɒlj�����v��ł���B����ɂ��ẮC���l�����Ă���ٗp�E�A�ƌ`�Ԃ̉��ł̒����\�������I�m�ɂƂ炦�邱�Ƃ��\�ƂȂ邱�Ƃ���C�K���ł��邪�C�u���Ј��v�̌ď̂ɂ��ẮC���Ə��E��Ƃ�ΏۂƂ��鑼�̎w�蓝�v�������Q�l�ɂ��āu���Ј��E���E���v�Ƃ��邱�Ƃ��K���ł���B�Ȃ��C�u���Ј��v�ɂ͊��Ԃ��߂Čق��Ă���J���҂������v��ł��邪�C���Ə��E��Ƃ�ΏۂƂ��鑼�̎w�蓝�v�����Ƃ̐������܂��C�����Ȃ����Ƃ��K���ł���B�v
�܂�肭�ǂ��ď��X�킩��ɂ������C��p�J����1)�ɂ��Ĉ�ʘJ���ҁi�t���^�C���J�����y242�Łz�Ǝv���悢�j�ƒZ���ԘJ����2)�̋�ʂɉ����āC�E��ł̌ď̕ʂ̐ݖ��lj������B������u���Ј��v�i�����ɂ͎��Ə��ɂ����Đ��Ј��E���E���Ƃ���ҁj�Ɓu���Ј��E���E���ȊO�v�i�����ɂ͏�p�J���҂̂����u���Ј��E���E���v�ȊO�̎ҁj�ł���B�����[���̂́C���ꂾ���łȂ��ٗp���Ԃ̒�߂̗L���ʂɋL�������Ă���B���Ј��ȊO�����łȂ��C���Ј��ɂ����Ă��ٗp���Ԃ̒�߂̗L������ʂ��Ă����B���Ȃ킿�u�ٗp���Ԃ̒�߂̂��鐳�Ј��v�ɂ��Ă̏�Ƃ��悤�ɂȂ����B�����܂ł��Ȃ��C���Ј��ȊO�̎Ј��Ŋ��Ԃ̒�߂̂Ȃ��J���҂̏��킩��B
�悤����ɁC���Ј����ۂ��C�����Ċ��Ԃ̒�߂̗L���łS��ނ̘J���҂̎��Ԃ��킩��B���ꂪ��ʘJ���҂ƒZ���ԘJ���҂̂��ꂼ��ɂ킩��̂ŁC�����W��ނ̘J���҂̏����킩��B������C��ƋK�́C�Y�ƕʂ��邢�͔N���Α��N���ʂɏڂ����������݂邱�Ƃ��ł���B�����Z���T�X��p���āC�����̑��l���ɂ��ė\���I���ȒP�ȍl�@���s���̂��{�e�̖ړI�ł���B
����21�N�i2009�N�j�̒�����{�e�̑ΏۂƂ���B��p�J���҂ɂ��Ă̕��͂ł���B
2�@�K�́E�Y�ƌv�̌���
�q��ʘJ���ҁr�i�\�P�j
���c���Ə��Ŋ�ƋK��10�l�ȏ�ɂ��ăt���^�C���J���ҁi��ʘJ���ҁj��2042���l����C�������Ј��Ŋ��Ԃ̒�߂̂Ȃ��J����1707���l�ŁC83.6% ���߂�B13.7% �����Ј��ȊO�̘J���҂����C�t���^�C���̐��Ј��Ŋ��Ԃ̒�߂̂���J���҂��C54���l�i2.6%�j���݂����B54���l�́C�������Ė����ł���قǏ��������l�ł͂Ȃ��B�����j��34���l�C����20���l�ł���B���̐l�����ɂ��Ă͂T�߂ŏڂ�������B
���Ԃ̒�߂͂����Ă��C�E��Łu���Ј��v�ƈʒu�t���Ă���J���҂����݂��邱�Ƃ́C�M�҂̎����ɋ߂��B
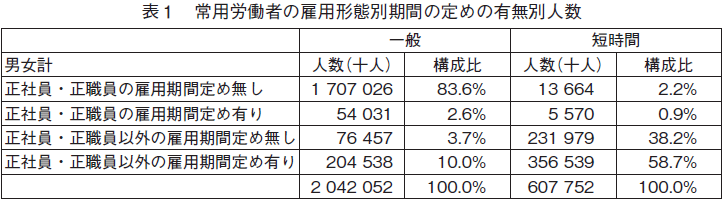
�q�Z���ԘJ���ҁr�i�\�P�j
�Z���ԘJ���҂�608���l����C�������Ј���19���l�i3.1%�j�ł���B�������Ј���14���l�C�y243�Łz�L�����Ј����U���l�ł���B�U�߂ŏڂ����݂邪�C�O�҂�14���l�������Ӗ��ł́u�Z���Ԑ��Ј��v�ł���C�L���Z���Ԑ��Ј��𑫂����킹��19���l���L�`�̒Z���Ԑ��Ј��ɂ�����ł��낤�B�L���Z���Ԑ��Ј�����ʘJ���҂Ƃ��킹��ƁC���Ј��Ŋ��Ԃ̒�߂̂���J���҂��C60���l�i���Ј���3.3%�j���݂����B�Z���Ԑ��Ј��́C�ǂ�����������������i����10���l�C�L���R���l�j�C�j�����������ď��Ȃ��͂Ȃ��B
�Z���ԘJ���҂̂Ȃ��ł͐��Ј��ȊO�����|�I�ɑ������C�L����357���l�ƂU����ŁC���Ԃ̒�߂̂Ȃ����Ј��ȊO�̒Z���ԘJ���҂�232���l��38.2% ���߂�B�Z���ԘJ���҂̂S���オ���Ԃ̒�߂��Ȃ��J���҂ł����B���̒�������C������u�p�[�g�v�Ŗ������R�`�S���Ɛ�߂錋�ʂƐč��I�ł���B
�l���̍\���������ٗp�`�ԕʂɂ݂�Ɓi�\�Q�j�C���Ј��̂���95.9% �������t���^�C���ł��邪�C�L���t���^�C����3.0%�C�Z���ԘJ���҂��L���E�������킹��1.1% ����B
���Ј��ȊO�ł́C�L���̒Z���ԘJ���҂�41.0% �Ƃ����Ƃ��������C�����ɖ����Ȃ��B�����̒Z���ԘJ���҂�26.7%�C�L���t���^�C����23.5%�C�����t���^�C����8.8% ����B
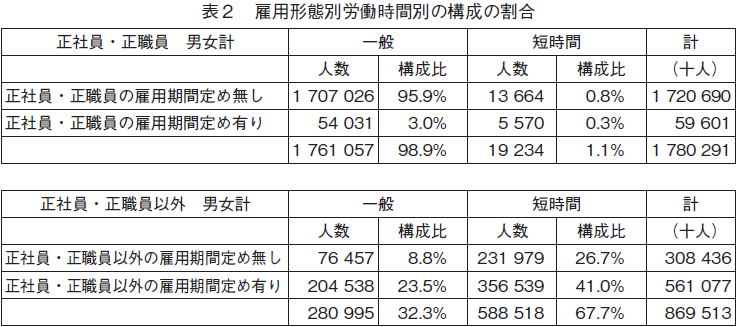
�S�J���҂̂R���̂Q�i64.4���j���t���^�C����߂Ȃ��Łi�\�R�j�C13.5% ���Z���ԗL���ł���B�c��̂Q�������ǂ���ɂ����Ă͂܂�Ȃ��J���҂ł���B
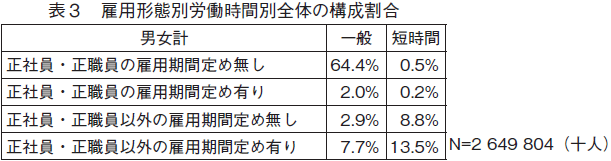
�y244�Łz
���^���r����̂ɁC���ԓ�����̏�������^���݂��i�\�S�C�\�T�j�B���Ј��̂���ɂ��ẮC���Ԃ̏�������^����������J�����Ԑ�3)�Ŋ����ċ��߂��B�\�S�ƕ\�T����ʘJ���҂̕��ς̌��ʂ́C�������Ј��i1890�~�j���L�����Ј��i1599�~�j���L�����Ј��ȊO�i1222�~�j���������Ј��ȊO�i1119�~�j�ƂȂ�B���Ј��ȊO�ł́C�킸�������L���̂ق��������������B
���ɒZ���ԘJ���҂̎��Ԃ����苋�^���݂�ƁC��ʘJ���҂Ƃ��Ȃ����C�������Ј��i1224�~�j���L�����Ј��i1120�~�j���L�����Ј��ȊO�i1009�~�j���������Ј��ȊO�i975�~�j�ƂȂ�B�������Ј��ɂ����鎞�ԓ����苋�^���C�t���^�C���̐��Ј��ȊO�̂���Ƃقړ����ł���B�܂������̐��Ј��������ƁC�L���̕������Ȃ荂�����Ƃ��킩��B
�Z���ԂŊ��Ԃ̒�߂̂Ȃ����Ј��ȊO�̘J���҂́C�]�ƈ��K��10�|99�l�̊�Ƃ�136���l�Ƒ������C970�~�ƕ��ς���≺���ɂ����Ȃ��B100�|999�l�ł́C65���l��997�~�C������1000�l�ȏ��31���l�����C952�~�ƕ��ς�肩�Ȃ艺���B���Ƃŗ��p���Ă��閳�����Ј��ȊO�̏������Ⴂ���Ƃ��킩��B
2-3-1�@�t���^�C���i��ʁj�ƒZ���Ԃ̔�r
�t���^�C���i��ʁj�ƒZ���Ԃ̔�r���s�����i�\�S��B/A�j�B���Ј��̒j���v�ł́C���Ԓ�߂Ȃ���64.8%�C��߂����70.0% �ł���B��߂Ȃ��ł́C�j��66.3% �ɑ��C����77.9% �ƍ��͏������Ȃ�B�Ȃ��j���v�̒l���C�j���ʂł݂��ǂ�������������l�ɂȂ�̂́C��ʂŒ����̍����j���������C�Z���ԂŒ����̒Ⴂ�������������߂ɐ����錻�ۂł���B
���Ј��ȊO�ł́i�\�T��D/C�j�C�j����80% ���x�Ƒ��ΓI�ɍ����傫���C�����͍����������B
2-3-2�@���Ԃ̒�߂̗L���ɂ���r�i�\�S�̂W�s�ځj
���Ԃ̒�߂̗L���ɂ���r������ƁC���Ј��j���v�ŁC��ʂł�84.6%�C�Z���Ԃł�91.5% �ł���B�Z���ԘJ���҂ł̍��͏������C�Ƃ��ɒj���ł�95.4% �ł���B����C��ʂł͒j��85.6%�C����87.6% �ł��菗���̂ق��������������B
���Ј��ȊO�ł́C���Ԃ̒�߂̂���J���҂̂ق��������������i�\�T�̂W�s�ځj�B��ʂ�9.2���C�Z���Ԃ�3.5% �����B
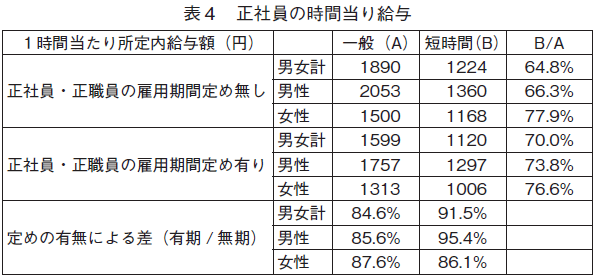
�y245�Łz
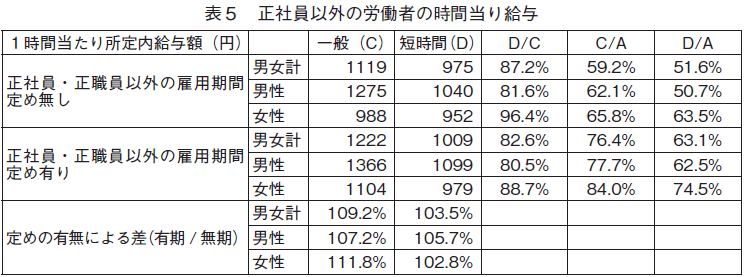
�ٗp���Ԃ̒�߂̂Ȃ��J���҂ɂ��āC���Ј��𐳎Ј��ȊO�̒������r�����i�\�T��C/A�j�B�j���v��59.2%�C�j����62.1%�C������65.8% �ł���B�L���J���҂ɂ��Ă݂�ƁC�j���v��76.4%�C�j����77.7%�C������84.0% �ƍ��͑��ΓI�ɏ������B
�Ō�ɁC�����Ƃ������̍�����ʂ̐��Ј��Ƃ����Ƃ��Ⴂ�Z���Ԃ̐��Ј��ȊO���r����Ɓi�\�T��D/A�j�C���Ԓ�߂Ȃ��J���҂�51.6%�C��߂����63.1% �ƂȂ�B
3�@��ƋK�͕ʂ̏�
�]�ƈ�1000�l�ȏ�K�͂̏��݂悤�B���Ј��ȊO�̗L�����C�K�͌v�i10�l�ȏ�j�ɔ�ׁC��ʁE�Z���ԂƂ��Ɋ�����������i�\�U�j�B�Ƃ��ɒZ���Ԃ�85.7���Ɛ��Ј��ȊO�̗L���������B�������C1000�l�ȏ�̑��Ƃł��C�t���^�C���ŗL���̐��Ј���11���l�C�����ăt���^�C�������̐��Ј��ȊO��11���l������B�܂��Z���ԂŊ��Ԃ̒�߂̂Ȃ����Ј��ȊO��31���l����B�ٗp�`�ԕʂɂ݂��̂��\�V�ł���B
�]�ƈ�1000�l�ȏ�K�͑S�̂ł݂�Ɓi�\�W�j�C�Z���ԗL���̊������C�K�͌v�̂Q�{�i23.6%�j�ɂȂ�C��ʂ̖������Ј�����⌸��i61.2%�j�B
���ԓ����菊������^���݂�i�\�X�j�B���Ј��̒j���v�Ńt���^�C���i��ʁj�ƒZ���Ԃ̔�r���s���Ɓi�\�X��B/A�j�C���Ԓ�߂Ȃ���71.7%�C��߂����57.1% �ł���B�O�҂͋K�͌v���傫���i�����������Ȃ�C��҂Ŋi�����傫���Ȃ�B�玙�Z���ԋΖ��Ȃǂ̏��������ƂŐ�������Ă��邱�Ƃ̉e�����\�z�����B���̏؋��ɁC��߂Ȃ��ł́C�j��73.3% �ɑ��C����91.4% �ł����C�玙�Z���ԋΖ��̗��p�҂̑��������ł́C�P���ȉ��̍��ƂȂ��Ă���B���Ȃ݂ɋK�͌v�̂��̊����͏�����77.9%�i�\�S�j�ł������B
���Ј��ȊO�ɂ��āC���Ԃ̒�߂̗L���̍����݂�Ɓi�\10�̂W�s�ځj�C��ʂ̒j���Ŗ����̂ق�����T�������Ȃ������C����ȊO�͗L���̂ق��������B
���K�͂̏�������ƂŐ��Ј��̃t���^�C���i��ʁj�ƒZ���Ԃ̔�r���s���ƁC���Ԓ�߂Ȃ��ł́C100�|999�l�K�͂ŁC72.6%�C10�|99�l�K�͂�71.1% �ƋK�͂��������قNJi�����傫���B���������ɂ��Ă݂�ƁC���ꂼ��82.9%�C81.4% �ł���B�������T�|�X�l�K�͂ł́C�j���v��74.0%�C������84.1% �ō��͏������B�i�t�\�P�C�Q�C�R���Q�Ɓj
�y246�Łz
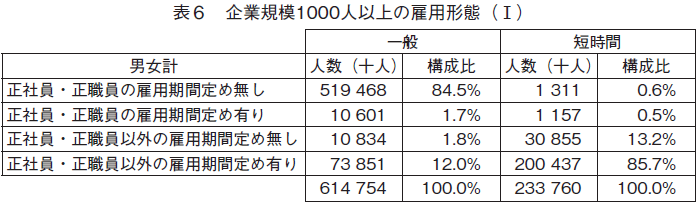
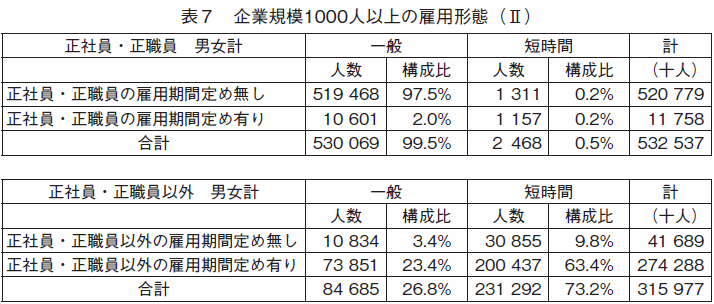
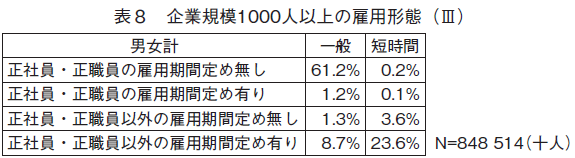
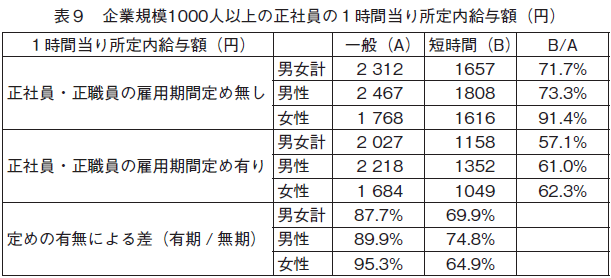
�y247�Łz
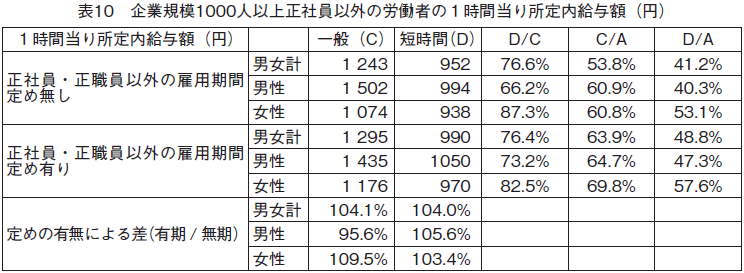
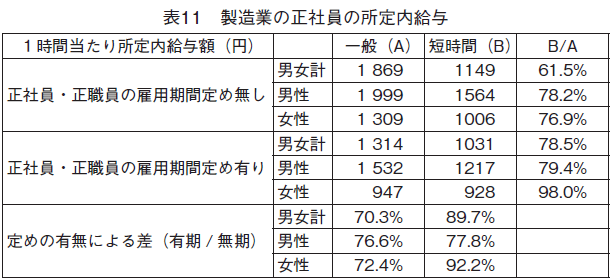
4�@�Y�ƕʂ̏�
�Y�ƕʂɂ݂邱�Ƃ��ł��邪�C����͐����Ƃɂ��Ă̂ݏW�v����B�����Ƃɂ́C�L�����Ј���11���l�i�S�̂�1.8%�j�C�����Z���Ԃ�26���l�i�S�̂�4.3%�j����B��������^�̊i�����݂�Ɓi�\11�j�C�������Ј��̘J�����Ԃɂ��Ⴂ�́iB/A�j�C�j����78.2%�C������76.9% �ł���B�Y�ƌv�ɂ���ׁC�����͂��i�����傫���C�j���ō������Ȃ菬�����Ȃ�B
�����Ƃ��K�͕ʂɂ݂�ƁC�L�����Ј��������̂́C�]�ƈ��K��10�|99�l�̊�ƂłT���l�i�S�̂�2.9%�j�ł���B�܂��C�����̖����Ńt���^�C���i��ʁj�ƒZ���Ԃ̏�������^��r������ƁC1000�l�ȏ�K�͂ł́C107.4% �ƌ�҂�����i1834�~��1708�~�j�B���̊����́C100�|999�l�K�͂ŁC88.2%�C10�|99�l�K�͂�78.8% �ł���B�i�t�\�S�`�t�\�W���Q�Ɓj
5�@�L���̐��Ј��̏�
�Q�߂ł݂��悤�ɁC10�l�ȏ��60���l�̗L�����Ј�������i����54���l����ʁj�B�K�͕ʂɂ݂�ƁC1000�l�ȏ��12���l�C100�|999�l�K��24���l�C10�|99�l�K�͂�24���l�ƁC�Ƃ��ɂǂ̋K�͂ő����킯�ł��Ȃ��B���Ȃ݂ɂT�|�X�l�K�͂ł͂S���l�ł���B
�ȉ��C��ʘJ���ҁi�t���^�C���j�̗L�����Ј��ɂ��ĕ��͂���B�Z���Ԑ��Ј��ɂ��Ă��y248�Łz�U�߂ł݂�B�܂��j���ʂɔN��z���݂悤�i�\12�j�B�j���ő傫�ȈႢ���݂ĂƂ��B�j���̃P�[�X�́C60�|64�Αw��31.1% �Ƃ����Ƃ������C55�Έȏ��51.2% �Ɣ�������B��N�O��ɗL���ƂȂ�C�X�V���J��Ԃ��Ă���p�����������B���̐l�������C�E��ł́u���Ј��v�ƌĂ�ł����B
����ɑ��āC�����̃P�[�X�́C�N��ɎU��肪�݂��C55�Έȏ��25.2% �ɂ����Ȃ��B�e�N��w�ɁC�t���^�C���L�����Ј������݂���B
���ɋΑ����z���݂�i�\13�j�B�j���ł�30�N�ȏ��13.0% ������B����������C�j���ŕ��z�̍��͏��Ȃ��B���̒j���̋Α�30�N�ȏ�4.8���l�̂����C60�|64��3.0���l�Ƒ唼���߂�B
�q�N��ʒ����r
��������^��N��ʂɕ`���Ɓi�}�P�j�C�j���̃P�[�X��40�|44���s�[�N�ŁC60�ΈȌ�̗��������}�ł���B����ɑ��āC�����̃P�[�X�́C45�|49���s�[�N�ŁC���̌�C�����邪�C���Ƃ��ƍ����Ȃ����Ƃ������āC�}���ł͂Ȃ��B
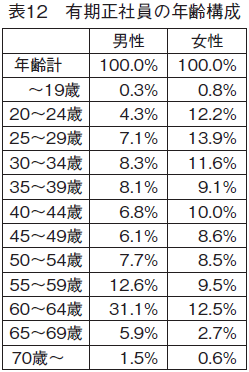
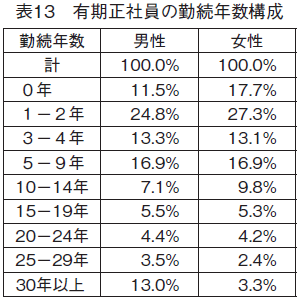
�y249�Łz
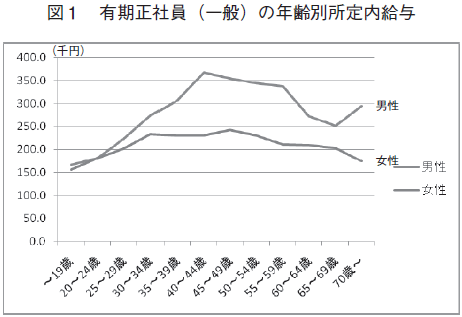
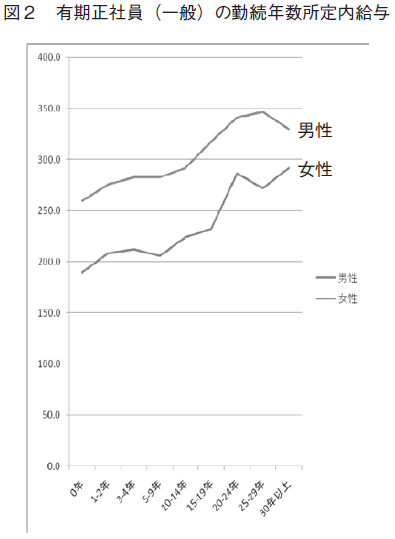
�q�Α��ʒ����r
�Α��N���ʂ̒�����`���Ɓi�}�Q�j�C�j���̃P�[�X�͏����ɏオ�邪�C30�N�ȏ�ŗ�����B�����̃P�[�X��25�|29�N�ŕs�K���ȓ��������邪�C�Ƃ��ɋΑ�10�N�Ȍ�̏オ������}�ł���B�����̋Α�20�N�ȏ�ŁC�j���̋Α��O�N�̒���������B
�y250�Łz
6�@�Z���Ԑ��Ј��̏�
�Q�߂ł݂��悤�ɁC�Z���ԂŁC�������Ј���14���l�C�L�����Ј����U���l����B�ٗp���Ԃ̒�߂̂Ȃ����Ƃ��d������C�O�҂�14���l�������Ӗ��ł́u�Z���Ԑ��Ј��v�ł����C�L���Z���Ԑ��Ј��𑫂����킹��19���l���L�`�̒Z���Ԑ��Ј��ɂ������ł��낤4)�B�l���̐��ڂ��݂�Ɓi�\14�j�C2005�N14���l�C���̌�13�|15���l�ł��������C2009�N��19���l�Ƌ}�����Ă���B�L���������������Ă���B���[�N���C�t�o�����X�̐Z����Z���Ԑ��Ј����y���Ƃ��{�i�I�ɂȂ��Ă��������ƑΉ����邪�C������ʂȂǂƂ̊W�́C��茵���ȕ��͂��K�v�ł��낤�B
2009�N�ɂ��āC�Z���Ԑ��Ј����ƗL���ɕ�����B�܂������Z���Ԑ��Ј��̔N��z���݂�ƁC�j���ő傫���قȂ�i�\15�j�B�j���̃P�[�X�́C60�Α�ɖ�R���Ƒ����C55�Έȏ��48.9% �Ɩ�����B�����̃P�[�X�͔N��ɎU��肪�݂��C55�Έȏ�ł�30.7% �ł���B
�L���Z���Ԑ��Ј��́C���̌X������茰���ɂ݂���i�\16�j�B�j���ł�60�Α�ɂU���C55�Έȏ��72.0% ���W������̂ɑ��C�����͔N��ɎU��肪�݂��C55�Έȏ��32.9% �ł���B
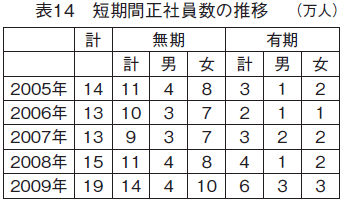
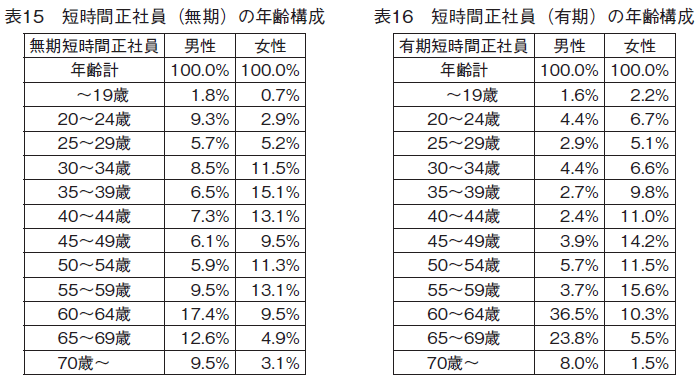
�y251�Łz
���ɖ����Z���Ԑ��Ј��̋Α��N��5)�̕��z���݂�i�\17�j�B�j���ł���قǑ傫�ȍ��͂Ȃ����C�����̂ق�����Ⓑ���C�T�N�ȏオ��������B�L���ɂ��Ă݂�Ɓi�\18�j�C�����ɂ���Α��͒Z���Ȃ�B����ǂ��L���ł����Ă��Α��̒����J���҂͏��Ȃ��Ȃ��C�j����46.2���C������37.8�����Α��T�N�ȏ�ł���B
�Α��N���ʂɎ��ԓ����菊������^���݂�i�}�R�j�B�����͋Α��ɂ���ďオ��Ȃ��P�[�X���������C�����Z���Ԑ��Ј��ɂ��ẮC�Α��T�N�ȏ�ő傫���㏸����B�j���͗L���ł����Ă��Α��ɂ��������ď㏸����B
�Ō�ɁC�Z���Ԑ��Ј����C�ǂ̋Ǝ�ɑ��������݂�i�\19�j�B�Z���Ԑ��Ј��͐����ƁC�����ƁC�����Ƃɑ����B�����̒j���ł́C���̂R�Y�ƈȊO�ɉ^�A�ƁC�X�Ƃ⌚�Ƃ������B
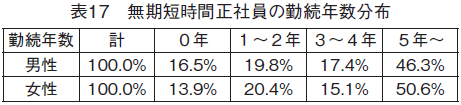
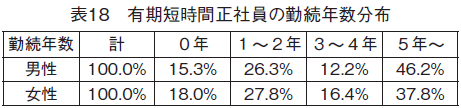
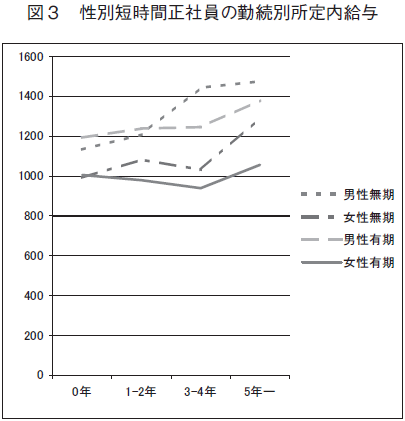
�y252�Łz
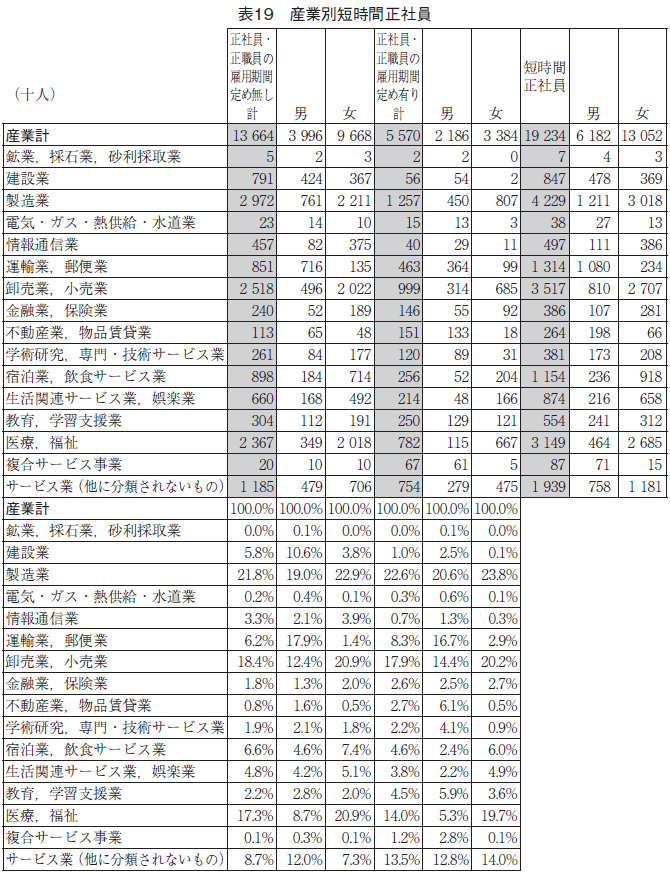
�y253�Łz
7�@��������
�{�e�͊�{�I�W�v�����������Ȃ̂ŁC���ʂ̉��߂ɂ��Ă͍ŏ����ɂƂǂ߂��B���������ϒl���ׂ������ł��C�Z���Ԃł����Ă������̍����J���҂̃O���[�v�����邵�C�L���ł����Ă��C����Ȃ�ɒ����̍����J���҂̃O���[�v���������ł��邱�Ƃ��킩�����B
����̉ۑ�́C�����̕��ς������݂�̂łȂ��C�킩�邩��������̕��z���݂邱�Ƃ��d�v�ł���B�[�͂��Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��ʂ����邪�C���Ј��ȊO�̘J���҂̑��l���́C���Ȃ�傫���B�܂��u���Ј��̑��l���v�̂ق����傫�����Ƃ����������B���\�f�[�^����ł��l�X�Ȃ��Ƃ��킩��\�����傫���B
�e�▾�i2009�j�u�w�K�x�Ј��Ƃ����Ăѕ��̔p�~�ƒZ���Ԑ��Ј��v���o�c�ҋ���w�l���J���Ǘ��̏��ۑ�x
�e�▾�i2010�j�u���l�ȓ������̌o�ϊw�v�w�o�σZ�~�i�[�x10�E11����
�y254�Łz
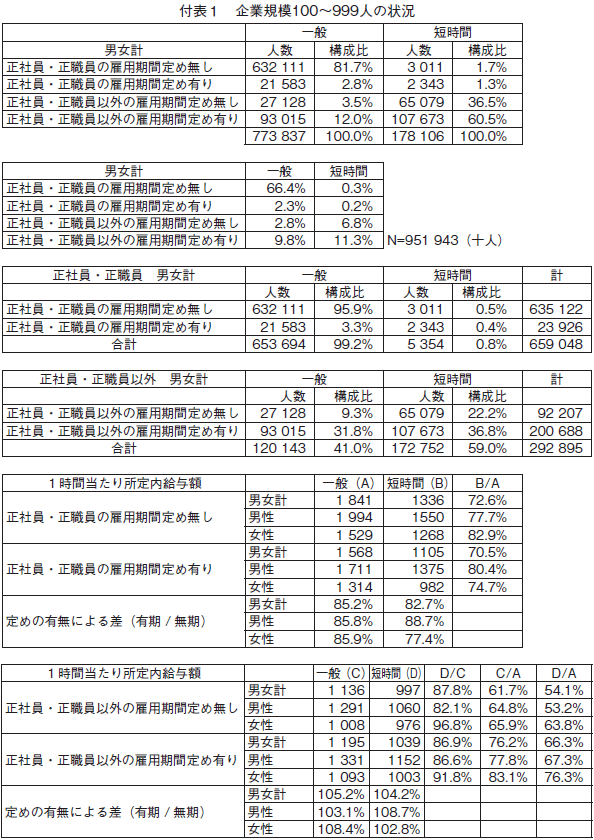
�y255�Łz
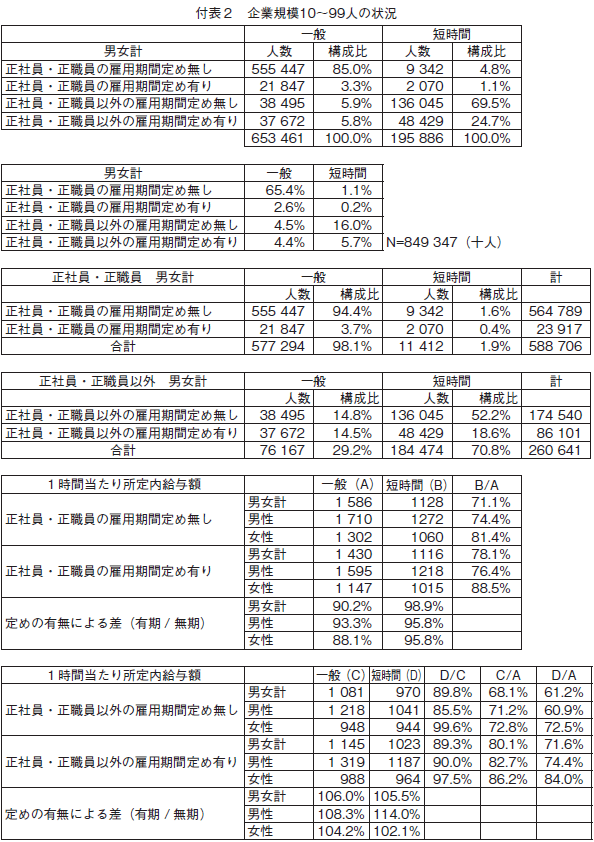
�y256�Łz
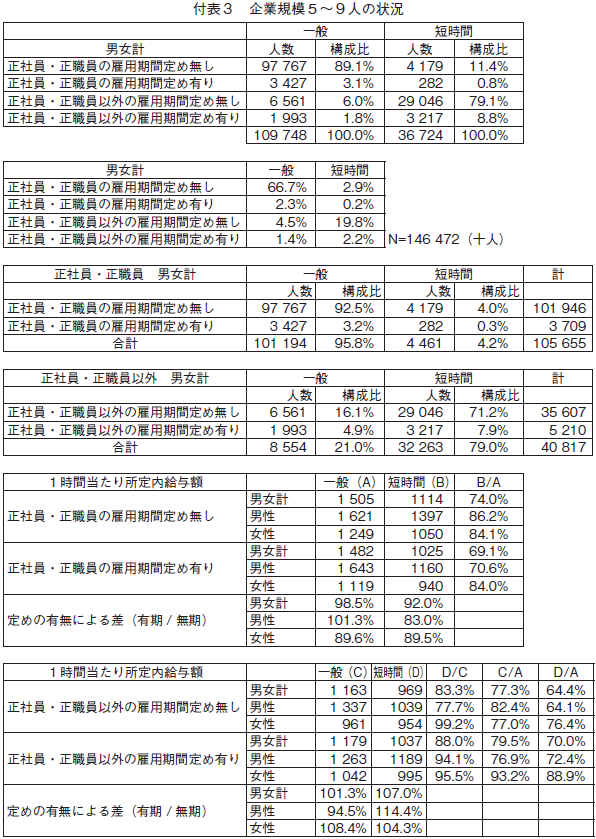
�y257�Łz
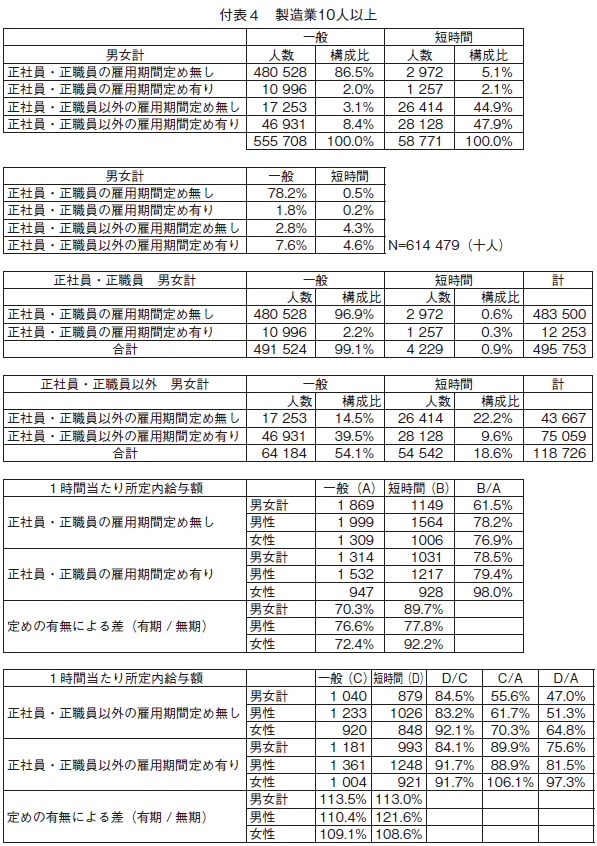
�y258�Łz
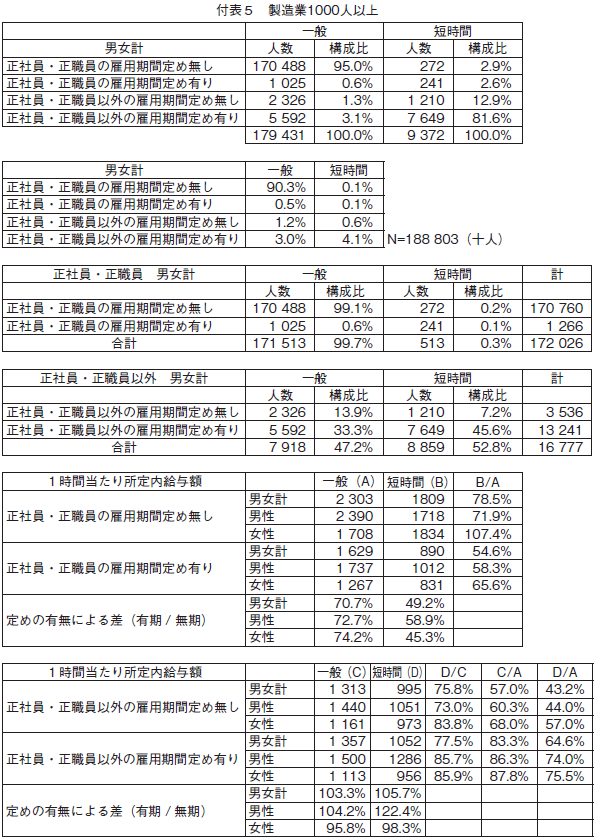
�y259�Łz
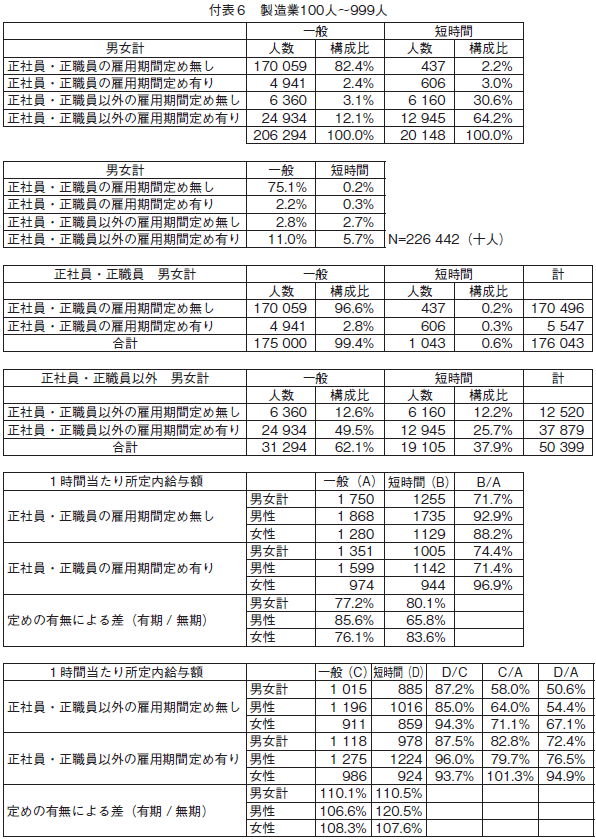
�y260�Łz
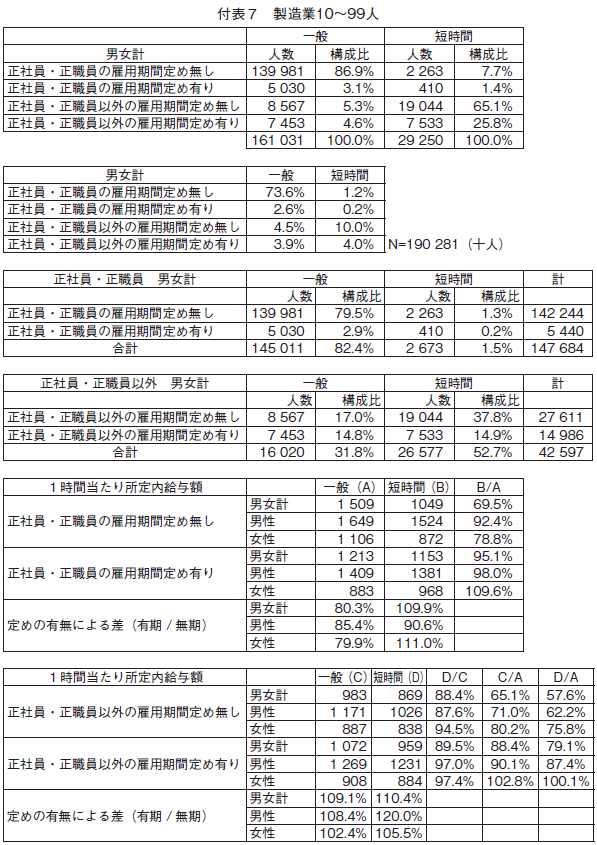
�y261�Łz