�y99�Łz
���Z�L�����e�B�̊K�w�^�����Ǘ��Ɋւ���o�ϕ��́i�U�j
�C���@����*
�{�e�͕\��Ɋ֘A���鎖���̌o�ϓI�w�i���{�̊T�O�C�����Ė��ӎ���W�J�����C���i2012�j�̌�҂ł���C�֘A���闝�_��헪���Ղ����ڂ����C�}�\�Ȃǂ�p���āC�o�ϊw�I�ɓW�J����B�ߔԍ���r���ԍ��́C����ɑ������̂ł���B�{�e�ł́C�����ς�C��ʓI�ł͂Ȃ��C�萫�I�Șg�g�݂̉���ɏW������B
�S�@�����Ǘ��̎菇�̑f�`�Ɗ�{����
�Ǘ��Ƃ������̂́C��K�͉�����C���Y�����ȂǂƂ͈���āC�Ǘ��R�X�g�͉����x�I�ɑ�����B��K�͉������łȂ��C���K�͂ł��ނ�݂ɕ��G������C�t�ɊǗ��R�X�g�͑����邱�Ƃ�����B���G�ȍ\���̂��߂ɃZ�L�����e�B��ۏł��Ȃ��Ȃ�C���Ƃ�����B����䂦�C�����Ǘ��̎d�g�݂͏\���l�@����Ȃ���Ȃ�Ȃ��C�̂ł���B
�@��Ƃ̏��Z�L�����e�B�ӔC�ҁi�b�h�r�n�j�́C�u��Ɠ����̘R�k�v����u�O������̃T�C�o�[�U���ɂ��V�X�e���̒�~�v�܂ŁC���Z�L�����e�B�ɂ�����鎖�ƃ��X�N��]�����C���X�N���ǂ��܂ŋ��e���C�ǂ̃��X�N�ւ̑�ɏd�_�I�ɓ������邩�C��Ƃ̃g�b�v�ɔ��f�ޗ�����������S���B�ށ^�ޏ����C�����Ǘ�����d�v�����\���ɔF�����Ă��C���ꂾ���ł͕s�\���ł���B�����Ǘ��ɂ͒����Ǘ����Ă��������ƈꊇ�����Ǘ���������̂Q���l�����C�ǂ���ɂ��邩���肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ȉ��ł́C���ꂼ��̌������l�@���Ă݂悤�B
�S�|�P�@�^�N�e�B�b�N�X
�܂��ȒP�ȌR���헪���Ɋ�{�������l���Ă݂悤�B�h�����̈قȂ�ꏊ�œ����ɂQ�̑�K�͂ȃg���u�����u�������ꍇ�ɁC�Ή�����^�N�e�B�b�N�X�itactics�j�͓ʐ헪�Ɠ�i�K�Ή��헪�̂Q������B
�y100 �Łz
�i�P�j�@�ʐ헪
�����Q�̃g���u���ɑ��ē����ɑΏ����C���É���}��Ƃ����헪���O�҂ł���B���������������Ă���C�����������̋K�́i���тʂ����U���Z�p�ł���ꍇ�C�����K�͂ɕϊ�����K�v������j�ɉ����Ċ���U�邱�ƂɂȂ�B���ꂼ��ɑ��ĕK�v�ŏ����̎����ʂ𓊓��ł��Ȃ��C�Ƃ��������N���肦��B
�i�Q�j�@��i�K�Ή��헪
��͂͂P�����̃g���u���ɑΉ����C�Q�����ڂ̐���ɂ̓g���u���̊g��i���邢�͐N�����Ӑ}���Ă���҂̐N�U�j��j�~���邾���̐�͂𓊓����C���P�����ڂł̏����̌�Ɏ�͂��Q�����ڂɐU�������Ƃ����헪����҂ł���B��i�K�Ή��헪�̐��s�ɂ́C�ʐ헪���C��ʂɁC���Ȃ������C���z�̎����ōςށB
�S�|�Q�@�����Ǘ��̌���
���āC�ʐ헪�͈ꊇ�����Ǘ��@�Ɖ��߂ł��C���ԍ��ōs�������i�K�Ή��헪�͒����Ǘ��@�ł���Ɖ��߂ł���B�ȉ��ł́C���ԂƂ��Č�҂���C�l���Ă������Ƃɂ��悤�B��̂S�|�P�́C�����ɓ���ʂŃg���u���������������C�g���u���ً̋}�x�͓����ł��邪�K�͂������قȂ邱�Ƃ�O��ɂ����c�_�ł���B�����I�ɂ���ɂ́C�����̑O����O�����l�@���s���K�v������B
�@�����Ǘ��̌����Ƃ́C�ŏI�I�Ɋ��S�V�X�e���ɂ��邪�C����ꂽ�����̂Ȃ��ŁC���������蓱���̗D�揇�ʂ��ǂ��l���Ă������C�Ƃ������ւ̂P�̉����@�ł���B
�i�P�j�@�Ǝ㐫�
�Ǝ㐫�̍����Ƃ��납��h����n�߂�������܂��l������B�ǂ�IT �T�u�V�X�e���ɂ��������x���ŃZ�L�����e�B�E���\�[�X��R�X�g�𓊂���̂ł͂Ȃ��C�Z�L�����e�B��̏d�v�x�ɉ��������x���ŃZ�L�����e�B�E���\�[�X��R�X�g�𓊂�������ł���B�L���Ɏ��s���邽�߂ɂ͐Ǝ㐫��m��K�v������B�Ǝ㐫��m�邽�߂ɏ��Z�L�����e�B�i�t���𗘗p����̂��P�̕��@�ł���B
�i�Q�j�@�R�X�g�
�Z�L�����e�B�E�R�X�g�̒Ⴂ�Ƃ��납��C���邢�́i�����Ӗ��ł��邪�j��Ɖ��l�����߂�ӏ�����C�Ǘ����n�߂���������ɍl������B
�@�n���s�̃V�X�e���������̓������V�X�e���ƊE�ł͒��炭���ڂ���Ă��邪�C���������Ƃ��ĉ�����Ă݂悤�B�n����s�V�X�e���������̓����̂Ȃ��ł��̃R�X�g�������Ƃ�̂́C�����C��t��s�i��t����t�s�j�C��l��s�i�V�����V���s�j�C�k����s�i�ΐ쌧����s�j�C������s�i���R�����R�s�j�C�ɗ\��s�i���Q�����R�s�j�̂T�s���琬����TSUBASA �v���W�F�N�g�̃T�u�V�X�e����s�����ł���B���Ȃ݂ɖk����s�̐V�V�X�e���J���̃x���_�[��2011�N�H��TSUBASA �v���W�F�N�g����̒E��\�������ߌ��݂̎Q���͂S�s�ł���B
�@���̃T�u�V�X�e����s�����Ƃ́C��s��n�V�X�e���ɐ�s���āC�������\�ȃT�u�V�X�e���ɂ��āC���ӂł�����s�Ԃ��狤������i�߂�`�Ԃ��w���B��p�������ފ���n�V�X�e������ɂ��āC�����ȓ����ő傫�Ȍ��ʂ���������ӃV�X�e���̋��������s������C���Ƃ��Ȃ��ꂽ�B
�@�T�u�V�X�e���̍X�������������ɓ��������s���m���狤�����ł��郁���b�g������B����ɁC�n�[�h�E�F�A�̍X�V�ƃA�v���P�[�V�����̎����͈�ʂɓ������Ȃ��P�[�X�������B���̂�
�y101
�Łz
���ȏꍇ�R�X�g��̓����b�g�̂��鋤���������ɂȂ邩������Ȃ��B
�@���̕������Z�L�����e�B�Ǘ��ɉ��p����ꍇ�C�����b�g�����邪�C����������������B�Ⴆ�C���ʂ̍U���ɑ��Ă͌����I�ɑΉ��ł��邪�C�O���[�v���̑������o�[�̐Ǝ㐫���爫���e������B
�@��Ƃ��s�̓����ł����l�Ȗ�肪������B���[�U�[�́C�Z�L�����e�B�E�x���_�[���̔����Ă���Z�L�����e�B���i���C���R�K�v�ɉ����āC�������ɓ������Ă��܂��Ă���̂�����ł���B���ʂƂ��ăl�b�g���[�N�S�̂ŃZ�L�����e�B�̈�ѐ���ۂ��Ƃ��ł����C�Ǘ��s�\�̏�ԂɊׂ��Ă��܂��Ă���ꍇ������i�V���G�b�h�i2008�j�j�B����䂦�C�Z�L�����e�B�E�R�X�g�̒Ⴂ�T�u�V�X�e������Ǘ����n�߂�C���̏�Ԃ����P�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�Ǝ㐫�̍����T�u�V�X�e��������Z�L�����e�B�������n�߂�K�v������C�̂ł���B�Z�L�����e�B�̂��߂ɂ́C�Ǝ㐫���K�{�ȏ����Ƃ��č̗p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��C�Ƃ������Ƃł���B
�i�R�j�@�U�����̎�����l�������܂Ƃ�
�U�����̋Z�p�i���������_���ŁC�������U�����̑����I�тƍU���̕p�x�������_���ł���Ƃ���ƁC�R�X�g��ł̓����ł��قڈ��S�ł���B
�@�������Ȃ���C�U���҂�����2008�N�C�c��Ȑ���Web �T�C�g����Ǝ㐫�̂�����̂������I�Ɍ��o���C�N���ł��郏�[���̃R�[�h���J�����邱�Ƃɐ��������C�ƌ�����iSource Boston Security Showcase �R���t�@�����X�iComputerworld�i2009�j�Q�Ɓj�ł̃o�[�l�b�g�iRyan Barnett�j�̕C�ȂǓ����Q�Ɓj�B����䂦�C�Z�L�����e�B�̂��߂ɂ́C�Ǝ㐫����̗p����K�v������B
�@�ً}��ÂȂǂ̕���ł́C�g���A�[�W��15�j�Ȃǂ̗D�揇�ʂ��t����ꎡ�Â���邱�Ƃ��m���Ă���B�Ǝ㐫��͈ꌩ�T�O�I�Ƀg���A�[�W���ɋ߂��B�������Ȃ���C���ً̋}��Õ���ł͈�Ñg�D�S�̂��j���U���͂Ȃ��i�����ɊY������̂́C��ÃX�^�b�t�S�����|�����ɂȂ��Ă��܂����d�NJ��҂̓����ł���j�̂��O��ł���C�v���I�ȃT�C�o�[�U��������I�ɂ�����Z�L�����e�B����ł͂���ɑΏ����邱�Ƃ�f�O���Ă��܂��Ă���̂ŁC�g���A�[�W���͏��Z�L�����e�B����ɂ͒��ړK�p�ł��Ȃ��B
�@�܂��C�e���x�Ȃǂ������C����Ă������ɑΉ�����Ƃ����P���ȊǗ����@�����邪�C�����̃T�C�o�[�U��������Ώ������ǂ����Ȃ��C�������Č����~�ς��Ă����̂ŁC�K�ȊǗ����@�ł͂Ȃ��B
�S�|�R�@�ꊇ�����Ǘ��̊��ƌ���
���ɓ����Ǘ����l���Ă݂悤�B
�S�|�R�|�P�@�ꊇ�����Ǘ��̊�
�������̊ϓ_����C�����Ǘ����₷���Z�p�I�ȃG���W�j�A�����O�̊��͐�������B �y102 �Łz �G���W�j�A�����O�̗p����g���ėv��Ǝ��̂Q���߂̂悤�ɂȂ�B
�i�P�j�@�����Ǘ��c�[���`�G���W�j�A�����O�E�A�v���[�`
Messmer �| Bort �i2009�j ���w�E����悤�ɁC�Z�L�����e�B�@�\���P�P��������͖̂ʓ|�ł���C�v�����G�ɂȂ�₷���B�܂��C�X�̃Z�L�����e�B�@�\���ʁX�̃x���_�[�̐��i����\������Ă���ƁC���̊Ǘ��ɂ͑傫�Ȏ�Ԃ�������B����ɂ́C�X�̐��i�̕ێ��p���x���_�[��SIe�ir �G�X�A�C���[�B �V�X�e���C���e�O���[�^�̂��Ɓj�Ɏx�����K�v������B�Z�L�����e�B���G�����R�X�g�Ȃ̂́C����������ԂƊǗ��ɂ��B�����ŁC�����̃Z�L�����e�B�@�\���P�̋@��ɂ܂Ƃ߂邱�ƂŊǗ����̌����}���B
�@���q�̂悤�ɁC�Z�L�����e�B�Ǘ��ɂ����ĕK�v�ƂȂ邷�ׂẴR���|�[�l���g���P�̓����R���\�[���ŊǗ����邱�Ƃ��Z�p�I�ɉ\�ƂȂ��Ă���B�|���V�[��`��O�Ǘ��C���[�U�[�Ǘ��C�g���t�B�b�N�E���j�^�����O�C�\�t�g�E�F�A�̎����A�b�v�f�[�g���͂��߂Ƃ����e��Z�L�����e�B�@�\��[����`�����S�Ƀ��W���[��������Ă���̂ł���i�V���G�b�h�i2008�j�Ȃǂ��Q�Ɓj�B
�@���Ȃ݂ɁC�G���h�|�C���g�E�Z�L�����e�B�iEndpoint Security�j�́C�ɔ�̓������������Ă���g�D������������؊O���ɘR�炵�����Ȃ��ꍇ�ɃZ�L�����e�B���A�E�g�\�[�V���O����ɂ͊m���ɓK�����Z�L�����e�B�Ǘ����@�ł���B�������Ȃ���C���O�̃Z�L�����e�B�Ǘ����ǂ��������邩���C�c���ꂽ�傫�ȉۑ�ɂȂ�C���S�ȓ����Ǘ��ł͂Ȃ��̂ł���B
�i�Q�j�@���z���ƃN���E�h�E�R���s���[�e�B���O�`�G���W�j�A�����O�E�A�v���[�`
���z���ƃN���E�h�E�R���s���[�e�B���O�ɂ���ėe�Ղ��������ł�����͐������Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B���z���ɂ���āC�P��T�[�o�[�ŕ�����OS ���ғ��ł��C�d���i���[�N���[�h�j�̗v�����ڂ�ς��ɂ�ĕ����I�ȂP��̃}�V������ʂ̃}�V���Ƀ\�t�g�E�F�A�Q���_��Ɉړ��ł���B����䂦�C���z���́C�n�[�h�E�F�A�ƃ\�t�g�E�F�A�̌��ѕt����f����C�T�[�o�[�Ƃ�荂�x�ȃ\�t�g�E�F�A�̊ԂɁC�T�[�h�p�[�e�B�[�̃e�N�m���W�[�����荞�߂邱�ƂɂȂ�B�X�ɁC�A�v���P�[�V�������C���^�[�l�b�g��̒����T�[�o�[�ʼnғ�����N���E�h�E�R���s���[�e�B���O�ł́C�e���_�Ԃ̓������͂��₷���̂ł���B
�S�|�R�|�Q�@�l�X�ȓ����Ǘ��̕���
�i�P�j�@�V�X�e�������̕���
�����Ǘ��̕������l�@���邽�߂ɁC��ʂ̃V�X�e�������̕������܂��݂Ă������B�V�X�e�������ɂ́C�ѓ��i2008�j�Ȃǂɂ��ƁC���̂悤�ɂ������̕���������B
�@�V�X�e�������̓T�^�I�Ȍ^�̈�́C�u�Њ^�v���邢�́u�������^�v�ƌĂ��C��̃V�X�e���ɍ��킹�ē�����������ł���B���̃V�X�e���ɂ��̑����ׂĂ��z������u�z���^�v�ƌĂ����������̕��ނɊ܂߂čl���邱�Ƃ��ł���ꍇ������B
�@�����ŁC������̋ɒ[�ł́C�܂������́u�V�K�J���^�v�ƌĂ��������̗p�����P�[�X������B
�@�����̊ԂɁC���Ԍ^�̐ܒ��Ă�����������B�R���|�[�����g�i���i�j���Ƃɂ��ׂẴV�X�e������ �g�����Ƃ��ǂ�h ������u�g�ݍ��킹�����^�v�ƌĂ��A�v���[�`������B���邢�́C�u�����^�v�ƌĂ��C�������s�킸�ɂ��̂��̂̃V�X�e����ʌɑ��点�C�K�v�Ȃ��̂������O�t���̌`�ŐV���ɕt������Ƃ����A�v���[�`������B
�@�����O�H��s�i���O�H����UFJ ��s�j�C�O��Z�F��s�C�݂��ً�s�̃��K��R�s���a���������ɂ́C�������D�悳�ꂽ���ʁC�V�X�e���������Ԃɍ��킸�C�����̃V�X�e���s�ғ�����
�y103
�Łz
�āC�P��̃V�X�e���̂悤�Ɍ���������u�����[�����v���Ȃ��ꂽ�B�u�����[�����v�Ƃ́C�V�X�e������{�����邱�ƂȂ��e�s�̃V�X�e����V���ɐݒu�������C���R���s���[�^�[�ɐڑ����ĉ^�p����`�Ԃł���i�}�\�P�Q�Ɓj�B
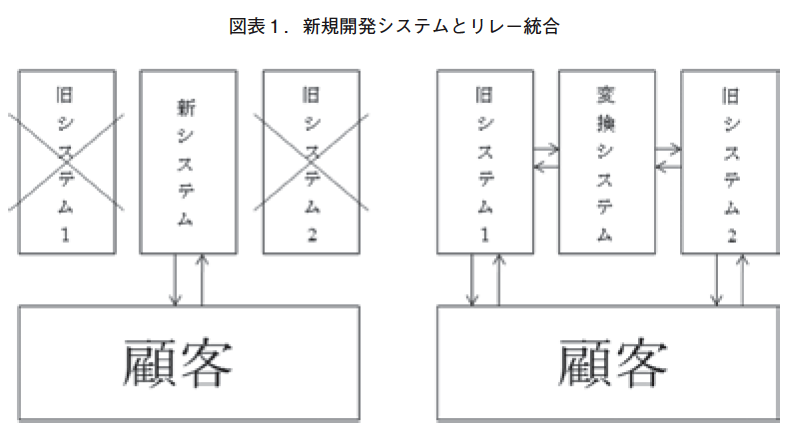
�}�\�P���E�́C�ϊ��V�X�e���Ƃ́C�R�[�f�B���O���ꂽ���𑊌݂ɕϊ�����V�X�e���ł���C�O�q�̊e�s�̃V�X�e���ԂɐV���ɐݒu�������C���R���s���[�^�[�E�V�X�e���ł���B�}�\�P���̖��̐�����킩��悤�ɕϊ��V�X�e��������ꍇ�ɂ́C�ʐM�͐V�V�X�e�����\�z����ꍇ�̐��{�ɂȂ�B
�@�����[�������C�Њ���܂ł́C�q���Ƃ���P�[�X������B2009�N10����B��s���r�c��s�ɋz����������C������̒r�c��B��s�ł̓����[�ڑ��ɂ����s�ғ����o�Ēr�c��s�̃V�X�e���ł���NTT �f�[�^�n�⋤���Z���^�[�֕Њ��ꂽ�i�ڍs������2012�N�P���ł��邪�C���s�̃V�X�e�����������������Ƃ��ăv���X�����[�X���ꂽ�j�B
�@������ɂ��Ă��C�����[�����͐V�K�J�����邢�͕Њ܂ł̎b��I�Ȍq���̕����ł���C�Ɖ��߂����̂����ʂɂȂ��Ă���B
�i�Q�j�@�|�[�g�t�H���I���_�I����݂��A�v���[�`
�|�[�g�t�H���I���_�́C���X�N�i�{�e�ł́C�Ǝ㐫���Y�����邱�ƂɂȂ�j�Ƃ����}�C�i�X�v�f�ƃ��^�[���i�{�e�ł́C�V�X�e���̃p�t�H�[�}���X���Y�����邱�ƂɂȂ�j�Ƃ����v���X�v�f���琬��Q�����̓������������̖����i�{�e�ł́C�V�X�e���ƂȂ�j���œK�ɑg�ݍ��킹��œK���̗��_�ł���B�|�[�g�t�H���I���_�͉��p�͈͂̍L����ʓI�ȍœK�����_�ł���B��ʂɃV�X�e���́C���������@�\�ȃR���|�[�l���g���琬��̂ŁC�Q�����̃|�[�g�t�H���I���_��蕡�G�ŁC����B����䂦�C�|�[�g�t�H���I���_�͊ȒP�ł��邪�C�T�u�V�X�e���i�����j�Ԃ̃p�t�H�[�}���X�i���^�[���j�̑��֊W���l���ł���_���P�̗��_�ɂȂ�B
�@��̃V�X�e�������������|�[�g�t�H���I���_�ɉ��p���Ă݂�ƁC�}�\�Q�̂悤�ɂȂ�B�Ǝ㐫�i���X�N�j�ƃ��^�[���̂Q�����Ŏ������Q�̃T�u�V�X�e���`�Ƃa������ꍇ�C����
�y104
�Łz
�Ƃ��ǂ���͍���̎l�p�Ń}�����͂����R�[�i�[�ɂȂ�B�|�[�g�t�H���I���_�͗��_�ヂ�[�����g�̐����R�����邢�͂S���܂ő��₹�C�������\�t�g���������Ă�������I�ȃ|�[�g�t�H���I�헪���f���͖����i�T�u�V�X�e���j�̐��͐����܂łɂȂ��Ă���舵����̂ŁC�������̓����Ǘ����������ł������ł���B
�@�|�[�g�t�H���I���_�ł́C�����̍œK�ۗL�䗦�����߂�B����́C�e�T�u�V�X�e���̍\���䗦���Y������B�T�u�V�X�e���������\�ȍŏ��P�ʂɂ���Ƃ���ƁC�Ђ��ẮC���ꂪ�C�����Ƃ��ǂ�������Ă��邱�ƂɂȂ�B�T�u�V�X�e���������s�\�ł���Ƃ���ƁC�ϐ��������ł��邱�Ƃ������ɂ����Q���œK���@��K�p�ł���B
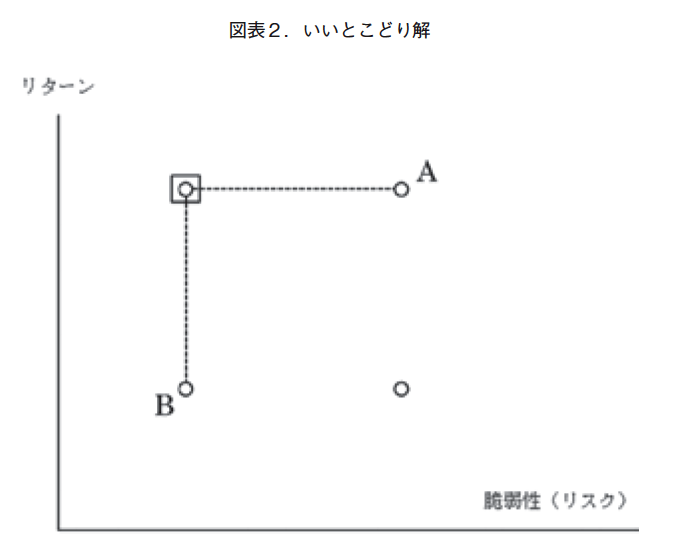
�i�R�j�@�Ǘ��R�X�g�ƃT�u�V�X�e���Ԑڑ��R�X�g�̊ϓ_�ƃZ�L�����e�B�̊ϓ_
�P�̑g�D���ɂQ�̊�T�u�V�X�e����u���P�[�X�i�}�\�R�̉E�j�ƂQ�̊�T�u�V�X�e�����Q�̑g�D�ɕ����Đݒu����P�[�X�i�}�\�R�̍��j�ł́C�Ǘ��R�X�g�ɍ����o�Ă���B��҂̕��U�ݒu�̕����C�Q�̑g�D�Ɍׂ镪�����Ǘ��R�X�g�͍����Ȃ�B���Ȃ݂ɁC�Q�̃P�[�X�ɂ����āC���g�D���̃T�u�V�X�e�������T�u�V�X�e���Ɍq���R�X�g�͋��ʂł���B�}�\�R���̓_���ł���������Ă���C���̏ꍇ�e�Q�������B
�@��ʂɁC�T�u�V�X�e���Ԃ�ڑ�����R�X�g�́C������g�D�ɂ���T�u�V�X�e�������ԕ����C�����g�D���ɂ���Q�̃T�u�V�X�e�������ԏꍇ���C�����Ȃ�B�Q�̊�T�u�V�X�e�������Ԑڑ��͂���Γ����ł���B��T�u�V�X�e������[�������Ԑڑ��͂���ΐÖ��ł���B���̚g���͉Ȋw�I�ɂ͕K�������K�ł͂Ȃ����C�d�v���������炩�ɂ��Ă���B���邢�́C������g�D�ɂ���T�u�V�X�e�������ԑO�҂͊O���C�����g�D���ɂ���Q�̃T�u�V�X�e�������Ԍ�
�y105
�Łz
�҂͓����C�ɂ��ڑ��ł���C�O�҂̊O���̕����ڑ��R�X�g�͍����Ȃ�B�@
�@���G�ȓ������̓Z�L�����e�B���������N�����B���O�̐}�\�R����킩��悤�ɁC�O���Ɠ����ł́C�Z�L�����e�B�̒��x���Ⴄ�B�O���́C�����Ɣ�r����C�T�C�o�[�U���ɑ��Ă��Ǝ�ɂȂ�\��������B
�@�ȏ�̗��R����C�u�����Ƃ��ǂ�v���́C���ۏ�C�����̃R�X�g���l�����Ύނ����_�܂ŁC�p�t�H�[�}���X���މ�����\���������C���Ƃ��\�z�����i�}�\�S���Q�Ɓj�B
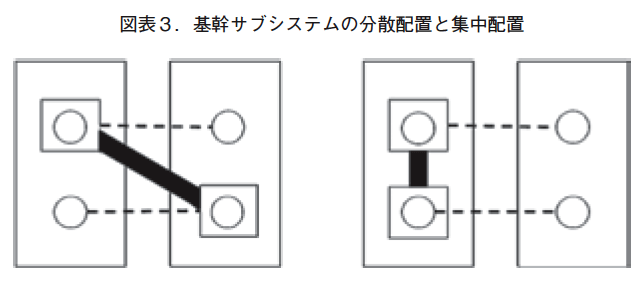
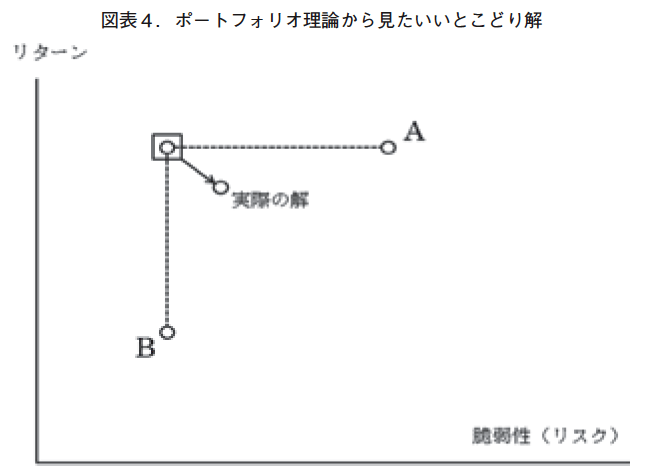
�i�S�j�@���������̑I��
��Ƃ�M �� A �����{�����ۂɁC���ƂȂ�̂͏��V�X�e���̓����ł���C�ƍl�����Ă���B����́C��Ƃ�������E�T�[�r�X�����G�ɂȂ��Ă��Ă���̂ŁC��ЂƂ̈Č���V�X�e���͂��ꂼ��������Ⴄ�C����ł���B�����V�������V�X�e���œ������悤�Ƃ���ƁC���Ȃ��ςɂȂ�B�V�X�e�������́C�����g�D���ɂ��ׂẴT�u�V�X�e�������߂�Њ�
�y106
�Łz
���łȂ���R�X�g�͔��ɍ����Ȃ�Ǝv����B�T�[�r�X��Ɩ��v���Z�X���C�������Ă���V�X�e���ɍ��킹��`�ŕW�������āC���̌�Ƀp�t�H�[�}���X��Nj�����Ƃ��������ɂ��邵���Ȃ��B
�@���q�̂悤�ɁC���ꂼ��Ǝ��̏��V�X�e�����������̊�ƁE�g�D����������ꍇ�́C�����I�ȏ��V�X�e���̓��������́u�Њ^�v�C�u�V�K�J���^�v�C�u�����Ƃ��ǂ�v������g�ݍ��킹�����^�C�̂R���l������̂ł���B�������Ȃ���C�����ɂ́C�����̏ꍇ�u�Њ^�v���̗p����Ă����B
�@�u�Њ^�v�̏ꍇ�C�}�\�Q�̂`���邢�͂a�̂����C�ǂ��I�Ԃ��́C�|�[�g�t�H���I���_�ɂ��ƁC�E�������Ɍ������ēʂ̖����ʋȐ���p����ׂ��ł���C�Ƃ������ƂɂȂ�B���X�N����^�̊�Ƃ͂a�_��I�Ԃ�������Ȃ��B�܂�Ǝ㐫�̂����Ƃ������V�X�e���a�ɕЊ���C�悤�ɂȂ邾�낤�B
�@�`���I�Ȗ����ʋȐ���p���Ȃ��Ƃ��C�I�����̐��͌����Ă���̂ŁC�Г��ŏ\����������C���l�Ȍ��_�ɓ��B�ł�����̂Ǝv����B
�i�T�j�@�g���̉\��
�|�[�g�t�H���I���_�ɂ����ẮC�^�p�Ώێ��Y�̉��i�≿�l�̕ω��������^�[���ł���C���̕W���������X�N�ł���Ɖ��߂����B
�@�|�[�g�t�H���I���_���Z�L�����e�B���ɓK�p�����ۂɂ́C����䂦�C�܂�����Ă��镨��T�[�r�X�́C�ݕ��z�ő�����C���l�����炩�ɂ����K�v������B���ł���C���̌o�ϓI���l�ł���B���ɁC����̃Z�L�����e�B�@��E�\�t�g������Ă���䗦�𐄌v���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����̍�Ǝ��̑傫�Ȍ����e�[�}�ł���̂ŁC�����ł͎w�E���邾���ŁC��������Ȃ��B
�@���ꂪ�C�|�[�g�t�H���I���_���I�[�\�h�b�N�X�ɓK�p����ۂ̎菇�ł���B���̏ꍇ�C�Ǝ㐫�́C����T�[�r�X�̉��l�̕ϓ����𑪂��Ă��邱�ƂɂȂ�B����䂦�C���l�̕ϓ�����ጸ����C�܂艿�l�̈��萫�傷��Z�L�����e�B�@��E�\�t�g�����݂��C�����Ă��ꂪ���Y���Y��T�[�r�X�̐Ǝ㐫���Ӗ�����Ƃ���C�|�[�g�t�H���I���_�����̂܂ܓK�p�ł��邱�ƂɂȂ�B
�@�������Ȃ���C���Y��T�[�r�X�̉��l�̑���ł͂Ȃ��C�����ς炻�̒ቺ���C���Y���Y�E�T�[�r�X�ɂƂ��Ă̐Ǝ㐫�ł���ꍇ�����낤�B�Z�L�����e�B�@��E�\�t�g�̋@�\�����̉��l�̒ቺ��h�����ƂɂȂ�B���Y��T�[�r�X�̐Ǝ㐫�����̉��l�̒ቺ���Ӗ����C���l�ቺ���~�߂�Z�L�����e�B�@��E�\�t�g�ւ̍œK�������_���K�v�ł���Ƃ���C�K�p����ׂ��̓|�[�g�t�H���I���_�ł͂Ȃ��C�|�[�g�t�H���I���_�`���̉ߒ��Œ�N���ꂽ�C�o�����[�E�A�b�g�E���X�N�iVaR�CValue at Risk�j�̗��_�ł��낤�B���̗��_�́C�t�@�C�i���X����ł́C�L���m���C���ۂɂ��g���Ă���BHull and White�i1998�j�CJorion�i2000�j ��Choudhry and Tanna�i2006�j �ȊO�ɂ��C�V������������������B
�@VaR �́C���v�w�I��@���g���ĎZ�o���ꂽ�C�s�ꃊ�X�N�������炷�\�z�ő呹���z�������B�����E�����E�בւȂǂ��\�z�Ɣ����铮���������ꍇ�ɁC���ݕۗL���Ă��鎑�Y�ɋ��z�Ƃ��Ăǂ�ʂ̑������o�邩���C���̊��ԂƐM����Ԃ̂��ƂŁC���v�w�I�ɎZ�o���Ă���16�j�̂ŁC
�y107
�Łz
�s�ꃊ�X�N�̊Ǘ���@�̈�Ƃ��Ă悭�g����悤�ɂȂ��Ă���B
�@�Ⴆ�C���鎑�Y�E�|�[�g�t�H���I�ɂ��āC���ۗ̕L���Ԃ��P���C�M����Ԃ�99���Ƃ���VaR ���v�Z�����ƁC���ۗ̕L���Ԓ��ɁC���̃|�[�g�t�H���I�̑�����VaR �̋��z���z����m���͂P���ƂȂ�B100���̓�99���͓���������VaR �͈͓̔��ł��邪�C100���̓��P����VaR ����\�������邱�Ƃ��Ӗ�����B
�@VaR �́C��Q�E���Q�⑹���̗\�z�z���v�Z�ł��邾���łȂ��C�⏞�z�Z��ɂ��W���B�܂��CVaR �́C�\�z�����z�Ȃǂ̌v���Ɍ�����킯�ł͂Ȃ��C�œK�����̖ړI���Ƃ��đ����C�ŏ������ɂ��邱�Ƃ��s�\�ł͂Ȃ��̂ŁC���p�͈͍͂L���B���Y�₻�̃|�[�g�t�H���I�̃��^�[�����z�̃p�����^�[�Ȃǂ�ς��邱�Ƃɂ���āCVaR �̊m�����z�������C�l�X�Ɋ��p�ł���B
�@�������Ȃ���C���������_������BVaR �͉ߋ��̃f�[�^���狁�߂����Y���l�̗\�z�ϓ����i�{���e�B���e�B�j��p���邽�߁C�p���I�Ƀf�[�^���擾�ł��Ȃ��悤�Ȏ��Y�ɂ͓K�p�ł��Ȃ��B
�@�܂��C1987�N�̃u���b�N�}���f�[��2008�N�̃��[�}���V���b�N�̂悤�Ȉُ펞�ɂ͈�ʂɓK�p�ł��Ȃ��B�X�g���X�E�e�X�g�����I�Ɏ{���Ĉُ펞�ł��ǂ��܂Ŏg���邩�C��m���Ă����K�v������B
�T�@���Z�L�����e�B�̊K�w�^�����Ǘ�
�T�|�P�@���w���ʂ̊Ǘ�
���{�̑��ʐM�Q�Ђ̃g�b�v��2011�N�T��31�����EICT �T�~�b�g2011�Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�j�c�c�h�́C���܂ł̊C��P�[�u���ɉ����C���k�����ԓ������Ƒ��d�p�̓S����ɉ����݂��C�O�d�����Ă������C�����{��k�Ђł͂��̂����Q���g���Ȃ��Ȃ����B����œ��{�C���ɂ������V�݂��C�l�d����i�߂��B�m�s�s�O���[�v�ł́C�č��ƂȂ��T�{�̊C��P�[�u���̂����C�S�{���ꂽ�B�c�����͈̂ɐ��u������o�Ă����������������B�����ł����ւ̒��p�P�[�u�����ꂽ���C�r���Ɍ������̗̂�������֎~�n�悪����C�C��������ɂȂ����B���{�C���̒��p�Ԃ�����ȂljI�[�g�̊m�ۂ��}�����B
�@�����̔��z�́C�����ꏊ���邢�͋ߕӂɓ�d�O�d�̉����݂���̂ł͂Ȃ��C�ʒu�E�ꏊ��傫���ς��ĒʐM�����ݒu����̂ŁC���w�h��iDefense In Depth�j�ɒʂ�����@�ł���B�h��́C���w���ʂłȂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��C�̂ł���B
�@�c�O�Ȃ���C�h�䂾���łȂ��C�U�������w���ʂłȂ����B���̂悤�Ȋ��̉��ł��̊Ǘ��͂ǂ̂悤�ȓ����Ǘ��ł���ׂ��ł��낤���B�������l�@����ׂ��v�����C�܂��C�����Ă݂悤�B
�@���Z�L�����e�B�̌X�̋@�\������̑w�ɕ����邱�Ɓi����͖{�e�̑O�ҁiI�j�Ŋ��ɍs�Ȃ����j�C���ׂ���Ɠ����������̏d�v�x�ŕ��ނ��邱�Ƃ��C�܂��K�v�ł��낤�B���ꂾ���łȂ��C��������舵���l�Ԃ���O�C�E�K�C�Ȃǂ������̋ǖʂŕ����邱�Ƃ��d�v��
�y108
�Łz
����17�j�B�����悤�ɁC�U������R�k������̃^�C�v�ɕ����邱�Ƃ��ł���B�U���A�N�Z�X���̑����C�U���p�x�i���ԓ�����̍U���A�N�Z�X���j�C���Y�Z�L�����e�B�E�C�x���g�̌���X�s�[�h�̑����x���C�ً}�x�C�Ȃǂŕ������18�j�B
�T�|�Q�@���w���ʂŖh�䂷��헪�̊��
�ŋ߁C���Z�L�����e�B�E�x���_�[�̐V���i�͓����Ǘ��̎��_���Ƃ��Ă���B�������Ȃ���C����ꂽ���\�[�X�ŏ��Z�L�����e�B���������ƂȂǂɂƂ��āC���z�ɂ̂ڂ���Z�L�����e�B�����Ǘ��c�[���̓����͈꒩��[�ɂ͌��f�ł�����̂ł͂Ȃ��B�l�@����ׂ������͑����B���Z�L�����e�B�@�\�̓����Ǘ��ɂ��čl������ׂ��o�ϊw�I�v�f�Ƃ��ẮC�T�����̂悤�ɍl������B
�T�|�Q�|�P�@����ƕ⊮��
�i�P�j�@�Z�L�����e�B�̃\�t�g�E�@��`�@�\���͂̕K�v��
�l�X�ȏ��Z�L�����e�B�̋@��⏤�i���Z�L�����e�B�E�x���_�[��������悤�ɂȂ��Ă���B������ł������ɂ���@��⏤�i��S�č̗p����킯�ɂ͍s���Ȃ��B�������C�������Z�L�����e�B�̋@�\�́C�Z�p�I�ɁC����ɂ͌o�ό��ʂ���݂āC�����̃O���[�v�ɕ������邪�C�قƂ�ǂ̏��Z�L�����e�B�̃\�t�g�E�@��͑��݂ɕ⊮�����������łȂ���ւ��Ă���B
�@�����������m�ɏq�ׂ�C���Z�L�����e�B�@�\���̃O���[�v�ɕ������ꍇ�C�Z�L�����e�B�E���x���͑��݂ɈقȂ邪�C�����\�t�g�E�@��̓O���[�v�̒��ŋ@�\�͑�֓I�ł���C�Ƃ������Ƃł���B��֓I�ȏ��Z�L�����e�B�̃\�t�g�E�@��́C���ǂǂꂩ�P���̗p���邱�ƂɂȂ��Ă��C������ړI�ɉ����ď����t�����邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�B���̏����t���̃v��
�y109
�Łz
�Z�X�́C����䂦�C���Z�L�����e�B�@�\�𑽑w�œ����Ǘ����邱�ƂɌq����̂ł���B
�i�Q�j�@��Ƃ̃V�X�e���E���{�ݔ��`�J�X�^�}�C�Y���ꂽ���Z�L�����e�B
�U���҂̐N���ɔ����đĂ����ɂ́C�܂��C���Z�L�����e�B�@�\�̒��������ƈꊇ�����̃����b�g�ƃf�����b�g���l���铊�����_���K�v�ł���ƍl������B
�@�Ⴆ�C����Ǝ�ɑ����邠���Ƃ��ۗL���镡���̎��{�ݔ��ԂŁC���Y�ɂ�����⊮���������Ƃ��悤�B�⊮����������C��������̐ݔ����U�������Q�ɂ����������ŁC���̂��ׂĂ̎��{�ݔ��͓����Ȃ��Ȃ�B���̂悤�ȏꍇ�C���Z�L�����e�B�@����ꊇ�������邵���Ȃ��B�����C���ׂẴV�X�e���E�ݔ�����֓I�ł���C���Z�L�����e�B�@�퓱���͈ꕔ�ōς܂��邱�Ƃ��ł���B�S�̑�֓I�ȃT�u�V�X�e���ɂ́C���̂����C�Ⴆ�Q�����ɏ��Z�L�����e�B�@�������C�Ƃ������@�����ł͂Ȃ��B
�@���̗�ł킩�邱�Ƃ́C�X�̊�ƂɂƂ��āC��������Ǝ�C�\������Ă����Ƒg�D�̌`�ԂȂǂɉ������Ǝ��̌ʏ��Z�L�����e�B���݂���Ƃ������Ƃł���B�Z�p��m�E�n�E���邢�͑g�D�̍\���Ȃǂ̊�ƁE�g�D�̃\�t�g�Ȗʂɂ��Ă��C���l�ł���B
�i�R�j�@�U���҂̍U���`���֕���
����P��̏��Z�L�����e�B�@�\���������邽�߂ɂ́C�x�X���q�̂悤�ɁC�����̗ގ��̋@��E��@�E�V�X�e�������݂���B���̂悤�ȏ��Z�L�����e�B�@�\�͕������݂���B����������Z�L�����e�B�@�\��L���Ɋ��p����ɂ́C���֕��͂Ƃ������@������B
�@�U���҂́C�s�x�h���C����ς���Ȃǂ��āC���g�����艻����Ȃ��悤�ɂ��Ă���B���邢�͕����̍U�����@���Ƃ�����C�����̍U�����_������C���čU�����m���Ȃ��̂ɂ��Ă���B�����镡�����헪���̂��Ă���B�h��҂͂���ɑ��āC�U���҂̐g���i�E�B���X����f���[���̑��M���j����U�����e�i�E�B���X����f���[���̑��M���e�j���Ȃǂ̎�ɓ���邱�Ƃ��ł�����C�\�Ȍ��葽�ʓI�ɑΉ�����K�v������킯�ł���B
�@���֕��͂̂P�ɂ́C�����̃Z�L�����e�B�@�킪�~�ς��郍�O�f�[�^�𑊊֓I�ɕ��͂����@������B�Ⴆ�C���X���x������s���A�N�Z�X�̎�@�̒��ɂ́C���ɂ͊e��Z�L�����e�B�@�킪���o�ł��Ȃ��i���邢�͍U���҂��U���ɗ��p����̂����߂��j�悤�Ȃ��̂����݂��邪�C���̎������m�F���C���m�Ȕ��f�������ɂ́C�����̃Z�L�����e�B�@��̃��O�f�[�^���番�͂��s���K�v�����邱�Ƃ�����B�܂��C�R���v���C�A���X�����߂邱�Ƃ��v������C������ăZ�L�����e�B���߂���悤�ɂȂ����C���ƂȂǂ����̂悤�ȋZ�@�����ڂ����悤�ɂȂ������R�ł�����B
�@���֕��͂ɂ���Č��o�����Z�L�����e�B�E�C���V�f���g���Ƃ��̑��̃A�i���O�Ď��������т��邱�Ƃɂ���āC�Ⴆ�T�[�o�[�_�E���̌������C�n�[�h�E�F�A��Q�Ȃ̂��C���邢�̓��[���������̃Z�L�����e�B�ɋN���������ۂȂ̂�����ʂł���C�蕪�����猴�������܂ʼn\�ƂȂ�B����ɂ́C�U���p�^�[���̔F���܂łł���悤�ɂȂ�B�Z�L�����e�B�E�C�x���g���֕��́iSEC, Security Event Correlation�j�͊�ƃl�b�g���[�N�Ȃǂ̃Z�L�����e�B��ی삷��h��I����I�Ȏ�@�ɂȂ�̂ł���B
�@�s�������E�s�����p�Ȃǂ̔����ł́C�J��Ԃ��N���郆�[�U�[�̗��g�p�p�^�[���������������ƂŁC���̃p�^�[������O�ꂽ���g�p��s�������E�s�����p�Ƃ��ē˂��~�ߒNj�����19�j�B��
�y110
�Łz
������֕��͂̈ꕔ�ł���C�N���W�b�g�J�[�h�C�ی��Ȃǂ̕s�������E���ɓK�p�����B
�@�������̃Z�L�����e�B�E�C�x���g���C�ǂ̃Z�L�����e�B�@�\��˂��U���ł��邩�C���悻����ł���P�[�X�������ł��낤�B������m���I�ɑ����邱�Ƃ��ł���C����ɁC���ʓI�ȕ��͂ɖ𗧂Ă邱�Ƃ��ł���B�h�q�����Ƃ����Ђɂ͂ǂ̂悤�ȍU������������c�����Ă���C�ǂ̃Z�L�����e�B�@�\���ǂꂾ���d������ׂ����C���m���I�ɂ킩��悤�ɂȂ�B
�T�|�Q�|�Q�@�������̉ۑ�
�i�P�j�@���֕��͂̉ۑ�`�v����̖��Ƌ������
���֕��͂ɂ́C���������_������B�E�B���X�ɂ́C���̃v���O�����̈ꕔ��ς��邾���Ŗ����̈����E�B���X�������B����䂦�C�p�^�[�����͂���{�Ƃ��鑊�֕��͂ł͏\���ɑΉ��ł��Ȃ��C�ƍl������Ƃ������B�����E�B���X���m�͕ʂ̃E�B���X�ɃJ�E���g����Ă��܂��댯�������邩��ł���B
�@�܂����֕��͂ɂ́C�U�����̍U����i�U���҂�����U�����ł��j��Ȃ������̂ǂ̂悤�ȍU������U�����邩�B�j��U���@�\�̑����i�U���҂�����@�\��ł��j��Ȃ������̂ǂ̂悤�ȋ@�\���U�����邩�B�U����@�����X�ƕς��ĕ��������U������̂��B�j�Ƃ����ʂƖh�䑤�̋Z�p�Ƃ��Ă̏��Z�L�����e�B�@�\�̑����i��Ŋ��q�j�Ƃ����ʂ̂Q������B���ꂪ��������̂́C���ւ��ǂ̂悤�ɑ���ׂ����C�̌v����̖�肪���݂��邱�Ƃł���B
�@�U����Q�́C�U�����Ɩh�䑤�̗��҂��U�h�������ʂł���C���҂̗v�������G�ɗ��ݍ����C�P���Ȕ�r�ł͈Ӗ����Ȃ��B�v�ʌo�ϊw�ł͂��̌��ۂ𑁂�����C�t���Ă���C���i�Ǝ�����ʂ̃f�[�^�n����������̗��Ȑ����v���ł��Ȃ��Ƃ����悤�Ȏ��ʐ�����ɂ��Ă���B
�@���\���ꂽ�U���f�[�^���瑊�֕��͂���ꍇ����ɕʂ̖�肪����B��Q�́C�ق�̈ꕔ��������Ȃ��B�قƂ�ǂ͔�Q���Ԃ��ɔ�ɂ����B����䂦�C�T���v���Z���N�V�����E�o�C�A�X������B���̋Ǝ҂����֕��͂���ꍇ�ɂ����Ă��C�U���͎����I�ɕ���ڍׂ����炩�ɂȂ�i���R�O���ɂ͔���J�j���C�Ǝ҂��J�o�[����̂͂��ׂẴT���v���ł͂Ȃ��̂ŁC��͂�T���v���Z���N�V�����E�o�C�A�X������B
�@�����āC���ւ̍������Z�L�����e�B�E�c�[���̊Ԃł́C�����z���Ƃ��ɑ��₷�i����𑝂₵�������������₷�j�K�v������̂��C���邢�͂Ƃ��Ɍ��炷�̂��B����ł́C��葊�ւ̒Ⴂ���Z�L�����e�B�E�c�[���Ԃł͂ǂ������Ή�������ׂ��Ȃ̂��B���̂悤�Ȗ����������ׂ��e�[�}�ɂȂ�B
�@����ɁC�U���҂͍U�������f�I�ɍs���\��������C�Ƃ������Ƃ́C�����̖h��ғ��m���������Ėh�䂷��̂��L���ɂȂ�Ƃ������Ƃł���B���̉\��������Ƃ����������ӂ݂�ƁC�ǂ̂悤�ȋ��������N�i��Ɓj�Ƒg�߂�̂��C���d�v�Ȍ����ΏۂɂȂ�B�U���҂�����̊�Ƃ�g�D�̖h�q����ł��j��Ȃ����C���̒N�i��Ɓj���ǂ̂悤�Ɍ��߂āi���艻���āj�čU������̂��C�U����@�����X�ƕς��ĕ����̌����U������ꍇ�͂ǂ��Ȃ̂��C�Ȃǂ͂��邱�Ƃ��d�v�Ȍ����e�[�}�ɂȂ邾�낤�B
�i�Q�j�@�W�I�^�U���Ƒ��֕���
�W�I�^�U���ł́C�����Ȃ��U���҂�����̂������̍U�����x�X�C�ړI��B������܂ŁC�U������B�U���҂́C�U�����ƂɃJ�X�^�}�C�Y�i����̊�Ƃ�g�D��_�����߂����ɍ쐬����
�y111
�Łz
��j�����E�B���X�i�����ȃv���O�����C�}���E�F�A�j�C����䂦���E���ɂP�������݂��Ȃ��E�B���X���g���Ă���B���̌��ʃE�B���X�͍L�͂ɂ͏o���Ȃ����߁C��\�t�g���[�J�[���T���v�������ł����C�Ή����x���B
�@�W�I�^�U���ł́C�P�̊�ƁE�g�D�ɑ��M�����W�I�^���[���̐��͂���قǑ����Ȃ��B�����܂�Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ł���Ɨ�������Ă���B2011�N�ɋN���������E�̖h�q�Y�ƃT�C�o�[�U���̏ꍇ�ɂ́C�����́C�U���e�Ȃǂ̖h�q����C�����Č��q�̓v�����g�֘A�̊J�����_���U����ɂȂ������C�����P�[�X�ł����悻500�ʂ̕W�I�^���[��������ꂽ�ɉ߂��Ȃ��B���֕��͂ɂ̓T���v���T�C�Y������������B
�@�W�I�^�U���ł́C�U��������C�������錟�́E��Q�҂��s�x�Ⴂ�C���m���ꂽ�U���Җ�������������[�U�[�ɂ���ĈقȂ�X��������B����䂦�C���ꂽ��x������Ă��������Q�l�ɂ��āC�X�̊�ƁE�g�D���Z�L�����e�B�������C���邢�́i��M�����Ă��܂��čU���ΏۋƎ�ł͂Ȃ��Ə���ɔ��f���Ă��܂��āj�܂������Z�L�����e�B�Ȃ��C���Ƃ��N����B�U���f�[�^�͏W�������Ă���C�T���v�������W�܂��Ă��C�L���ȑ��֕��͂͂ł��Ȃ��\��������B����ł̓Z�L�����e�B��Ƃ��Ă͏\���łȂ��B
�@���Ȃ݂ɁC�W�I�^�U���ւ̑�̈�Ƃ��āC�@�T�[�o�[�C�N���C�A���gPC �Ŏ��s�ł���A�v���P�[�V�������Œ艻���Ă��܂��i�_�E�����[�h�����R�ɂ����Ȃ��j���@�C�A�z���C�g���X�g�@�\�ɂ���ăA�v���P�[�V���������s�ł���l�Ԃ𐧌䂵�Ă��܂����@�C�����āC�B�N���C���C�ǂ̃t�@�C�����ǂ̂悤�ɕύX�������̏ؐՂ��擾���ۑ��i�V�X�e���ύX�����m�E�ی�j������@�C�ւ̊S�����܂����B
�i�R�j�@���{�I���s�̕��Q
�����т̓��{�I�o�ϊ��s����C�����Ђ̐��i���ǂ��ƂȂ�C���̊�Ƃ��������̂�����X�������{�ɂ͂���B���̌��ʁC�����ł͐��̋ɂ߂Č���ꂽ�Z�L�����e�B�Z�p�����y�i�ǂ����̂łȂ���Ζ����Ƃ������t���g�������悢���낤�j����悤�ɂȂ�B���������ƂɂƂ��Ă͑��݂ɂ悭�m�����Z�L�����e�B�E�c�[���Ȃ̂ŕ֗��ȏꍇ�����邪�C���А��ɐ芷����U�������܂�Ă��Ȃ��B������C�s���N�����鑤���猩��C�ꍑ�S�̂��j��₷���V�X�e���ɂȂ��Ă����B��j��C���ׂĔj���C�Ƃ����킯���B
�@���̌��ۂ𑊊֕��͂���\������ƁC�j���鎞�͊F�����ŁC�������ꂽ�Z�L�����e�B�Z�p�̑��֓x�͋ɂ߂č����Ƃ������Ƃł���20�j�B
�i�S�j�@�h�q�̋����헪
����ɁC�����h�䂪�]�܂����ꍇ�����݂���Ƃ����c�_�́C���Z�L�����e�B�͌��I�ɍs���ׂ��ł���Ƃ����C�l�����ɓ������B�U���o�H�������ɋy��ł���C���邢�͍U���K�͂��傫���Ȃ�ƁC�Z�L�����e�B��͌l��X�̊�Ƃł͂ł��Ȃ��B
�@�ߋ��ɂ����ẮC�����̍��œs����ǂň͂�Ŗh�䂵���C���Ƃ������h�q�헪�̈ꎖ��ɂ�
�y112
�Łz
��B��ǂ̂��Ƃ𗅏�C�y���ł߂č��Βz�n���i�����ׂ��j�C�ƌĂꂽ�B�����ė���ɊJ������𗅏��ƌĂB
�@�ǂ͈̔͂܂ŁC�ǂ̒��x�܂ŁC���Z�L�����e�B�̐��������I�ɍs���ׂ����낤���B���{���g���傫�ȏ��Z�L�����e�B�E�Z���^�[�����C���������ăT�C�o�[�U���ɑΛ����邱�Ƃ��C�܂�����̋ɂƂ��čl������B�����̋ɂ́C���{����͂Ȃɂ����Ȃ��C�Ƃ����P�[�X�������Ă����ƁC���Ԃɂ́C�������̃P�[�X�����݂�����B���{���B�ɂ����Ē��B��Ɉ��̃Z�L�����e�B�v�����`���t����Ώ��Z�L�����e�B�͕��y���邾���łȂ��C���Z�L�����e�B�`���������邱�ƂɂȂ�B���Ȃ��Ƃ����{���ł��鎖���ɂ́C���{���U���̏�����ƂƋ��L�����葁���x���Ԑ��Ŋ�ƂƘA�g�����肷����@�ȂǁC���܂܂��B
�T�|�R�@�K�w�^���Z�L�����e�B�����헪
����ł͋�̓I�ȑ��w�h��iDefense In Depth�j��̌������K�w�^���Z�L�����e�B�����헪�Ƃ͋�̓I�ɂǂ̂悤�Ȍ����Ȃ̂��낤���B
�@�N�������m�C�N���h�~����N���j�~����ɐN����Q�h�~�܂ő��w�ɋy�ԃZ�L�����e�B�@�\���ǂ��Ǘ����ׂ����낤���B���ׂĂ̋ǖʂŁC�e�w���ɖh�䂷��ׂ����C���邢�͂��̑��̕��@���Ƃ�ׂ��Ȃ̂��낤���B���ɂ݂��悤�ɁC�������x���̏��Z�L�����e�B�@�\���������邽�߂̋@��E��@�E�V�X�e���͕������݂��C�������C�����̋@�\�͑��i�K�ɋy�ԁB����䂦�C�K�w���헪���K�v�ɂȂ�ꍇ������B�o�ϓI�ȗ��R�ň����ȋ@�����w�ɂ������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��C�Z�p�I�ȗ��R�ŐƎ�ȋ@������������Ȃ������ꍇ�ɂ́C������J�o�[����@�����w�ɂ����˂Ȃ�Ȃ����낤�B
�@�ڋ߂ȗ���g���āC�����헪�̋@�\�Ԕz�����̈�ǖʂ�������Ă݂悤�B�����{��k�Ђ̌�N�����Ôg�Ɋւ��ē��k�n���̂���n��ł́C����h�g�炪���邩��ƉߐM���ē����Ȃ������Z��������ƕ���Ă���B�h�g��ƈ��S�ȍ���ɓ�����Ƃ����Ώ����@�͋@�\�̑S���Ⴄ�Ôg��ł���B�����O�҂����S�ł���C�m���Ɍ�҂͕s�p��������Ȃ��B�O�҂��P���ł����S�łȂ���C�S�̂Ƃ��Ċ�����ڎw���Č�҂��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ʂ̓_����݂�C�O�҂��قǂقǂɂ��āC��҂�O�ꂷ��Ƃ���������C���肦��B�����ł����O�҂Ƃ̓Z�L�����e�B�̑悉�w���Y������ƍl����ƌ�҂͑�i���{�P�j�w�ł���B
�@����ɂ�����_�_������B��Вn�ł͑�k�В���̑����i�K����C����͍���Ɉړ]����ׂ����Ƃ�������������C���ۂɂ��C���Ԃ͂����������C���̕����ɐi�B���҂͌�����Ă���̂�������Ȃ����C����ړ]�͂��ꂾ���ŒÔg�͍���100�����S�Ƃ������Ƃ��낤���B����ł́C����h�g�炪�������Ă������Ɠ����Q�ދ��ꂪ����B�T�C�o�[�U���ɂ����ẮC�P�̋@�\�����ɏW�����đ��z�̂����������Ėh�䂵�Ă������Ƃ�����_�W���헪���Y������B��_�W���헪���P�̉ł͂��邪�C�U���҂�����ǂ��ϖe���邩�C�s���ȂȂ��s�m���Ȑ헪�ł���ƌ��킴������Ȃ��C�Ƃ������ƂɂȂ�B
�T�|�R�|�P�@�K�w�^�����헪�̊T��
���̊K�w���헪�Ɋւ��ẮC�P�̃A�v���[�`�Ƃ��āC�U���A�N�Z�X���̑����C�U���p�x�C�ȂǂɊ�Â����C���̐}�\�T�̂悤�ȊK�w���헪�Ƃ����l��������肦��B
�@���Ȃ݂ɁC���������O�ɐ������Ă����ׂ�����������̂ŁC�܂��������q�ׂĂ������B��ɉ�������|�[�g�t�H���I���_��VaR �́C���̘g�g�݂̂Ȃ��̈ꕔ�Ɏg����C���Ƃɂ����Ĉȉ��𗝉����ė~�����B�����āC���ɁC�قȂ�Z�L�����e�B�@�\�̂��ꂼ���B����
�y113
�Łz
��l�X�ȋ@������悤�Ƃ���ۂɂ́C�����̌݊���21�j���S�ۂ���Ă��邱�Ƃ��ŏ����̏����ɂȂ�B�{���߂ł����ꂪ�O��ɂȂ�B
�@�t�����g�̑��w���j��ꂽ���ɔ����āC���w�̃J�o�[�Ƃ��o�b�N�A�b�v���ǂ̂悤�ɍs�����C����ɂ͑�O�w�ɂ��Ă͂ǂ�����i�Ⴆ�C��O�w�͑Ή����Ȃ��C�܂�h�����Ȃ��Ȃǂ̌���j���C�Ȃǂ��_�_�ł���B�ǂ̋@��E��@�E�V�X�e������w�ɒu�����C�����đ��w�Ɍ����@��E��@�E�V�X�e���͉����C�Ȃǂ��d�v�Ȍ��莖���ɂȂ�B����ɁC�����̌������ʂ��Z�p�i���ɉ����Ē���I�Ɍ������Ă������Ƃ��K�v�ł���B
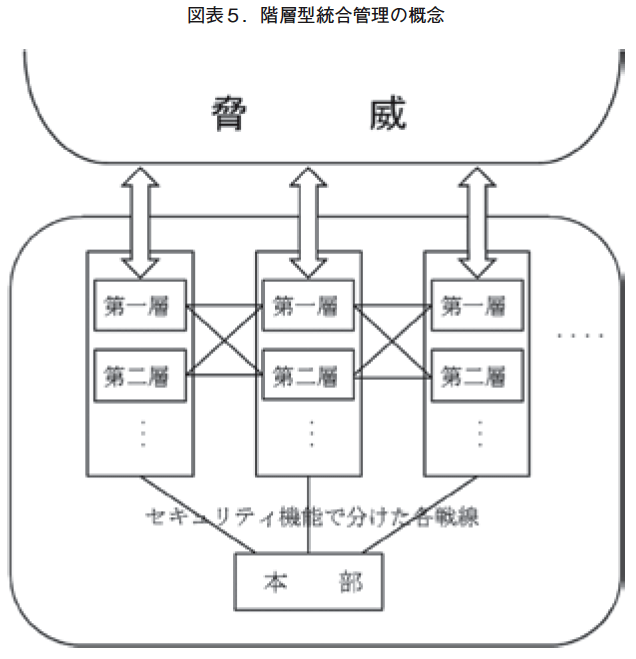
�i�P�j�@�Ǝ㐫�ƃR�X�g�̊
�P�̌������l������B�܂��C�̗v�Ȃ̂́C�U���A�N�Z�X���̑����C�U���p�x�̍����f�[�^�E���╔��́C�N���h�~�̑����i�K����C���x�ȃZ�L�����e�B�@�\�����@��E�\�t�g�Ŏ��C���Ƃł���B�����āC�U���A�N�Z�X���̏��Ȃ��C�U���p�x�̒Ⴂ�f�[�^�E���╔��ɑ��ẮC��i�̐N���j�~�E�N����Q�j�~�i�K�ŁC�ቿ�i�ȋ@��E�\�t�g�Ŏ��C�Ƃ����Ǝ�
�y114
�Łz
���ƃR�X�g�ɂ�錴���ł���B
�@���������߂邱�Ƃɂ���āC�e�Z�L�����e�B�@�\���ǂ�ʂ̃��x���܂ŒB�����邩���C���ʂƂ��āC���߂��邱�ƂƂȂ�B
�@������舵���l�Ԃ���O�C�E�K�C�Ȃǂ������̖ʂŕ���������ɂ��ẮC�Ⴆ��̓I�ɁC�ڍׂȍ��������{���ł��錠�����ے��ȏ�̌o���S���҂Ɏ�������C���̂��߂̕������l����C�Ȃǂł���B���Ȃ݂ɁC�{���҂𐧌��ł���Í������͊��ɑ��݂��Ă���B
�i�Q�j�@������
�܂��C�h��̊K�w���������I�Ɏ��s���邱�Ƃ��l������B�U�������ʂ̐��ڂ����ɁC�Z�L�����e�B�@�\�̈ړ����������s����B��葽���i���Ȃ��j�̎��ԓ�����U�����ɂȂ�C�� �i��j�@�\�@��E�\�t�g�֎����I�Ɉړ�����킯���B�Z�L�����e�B�@�\���N���E�h�ŗ��p�ł���C�܂�@��E�\�t�g�����L����̂ł͂Ȃ��C��邱�Ƃ��ł���Ȃ�C�h��̊K�w�� �������I�Ɏ��s���邱�Ƃ��\�ɂȂ�B
�T�|�R�|�Q�@�K�w�^�����헪�̂��̑��̘_�_
����X�s�[�h�̒x���C�ً}�x�Ȃǂ̊ϓ_����K�w���헪���Ƃ邱�Ƃ��l������B�����̊ϓ_������̃��x���ɕ�������B�ꍇ�ɂ���āC�����̊ϓ_�͂���Ɏ����̍����c�_����N���邩������Ȃ��B
�@���w�h��ɂ́C����܂ŏq�ׂĂ����C������G���h�|�C���g�E�Z�L�����e�B�����łȂ��C�l�b�g���[�N�E�Z�L�����e�B�C�T�[�o�[�E�Z�L�����e�B�Ƃ���������̕���ł̑��߂���B���̃��X�g�ɂ���ɍ��ڂ�lj�����C�X�g���[�W�E�Z�L�����e�B�i�f�[�^�E�����d�v�x�E���p�p�x�C�@���x�ɉ����ăJ�e�S���C�Y���C���ꂼ��ɉ������ی��K�p����K�w�^�X�g���[�W�����ڂ����j�C�\�t�g�E�F�A�E�Z�L�����e�B�C�Ȃǂ����낤�B�����Ɋւ��ẮC���ꂼ�ꗘ�p����Z�p���قȂ�C�G���W�j�A�����O�̎��_������Ɋ܂܂��B
�@2011�N�R���ɋN�����������{��k�Ђ́C���X�N���U���L��I�ɍs���ׂ����Ƃ�C�o�b�N�A�b�v�͎O�d�ł�����Ȃ��������Ƃɉ����C�l�X�ȌX�l���Ƃ��邢�͌��I�@�ւ����l�X�ȃm�E�n�E����̋��L�����K�v�Ȃ��Ƃ����肵���B�Љ�V�X�e���Ƃ��ĐV�����\�z����ۂɖY��Ă͂Ȃ�Ȃ��ϓ_�ɂȂ낤�B
�@�Ō�ɍ��{�I�Ȗ��Ƃ��āC���Z�L�����e�B����������ʂ̍s���ړI�ɂȂ邱�Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��C�Ƃ����_������B�R�X�g�팸�͓��R�̂��ƂƂ��C�g�D�{���̖ړI�i��Ƃł���C�Ⴆ�C���v�j�Ɩ������Ȃ��`�ŁC�s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B�������C���v�D��ň��S�����Ƃ����킯�ł��Ȃ��B
�U�@�܂Ƃ߁`�v��Ǝc���ꂽ�ۑ�
���Z�L�����e�B�̓����Ǘ����C�ǂ̂悤�ȊK�w�`�Ԃł��낤�ƁC�������ꂽ�łɂ́C�Z�L�����e�B�E�C���V�f���X�̔����⒲���͉~���ɐi�ށC�\���͍��܂�B�l�b�g���[�N�S�̂ʼn����N���Ă��邩���Ď����C�ُ�ȏo�����̔����͑����Ȃ�C�������̌n�I�ɍs����C�悤�ɂȂ�B
�@���Z�L�����e�B�����Ǘ��̌����Ɋ�Â��C�Z�L�����e�B���i���قȂ�x���_�[����w������̂ł͂Ȃ��C��I�ȃZ�L�����e�B�E�\�����[�V��������鑍���x���_�[����w�������悤���悢�B�����Z�L�����e�B�E�x���_�[�͍L�͂Ȑ��i���C���A�b�v�����낦�Ă����Ɋ�
�y115
�Łz
�������������Ă���i�V���G�b�h�i2008�j�j�̂ŁC�Z�L�����e�B�Ǘ����ȑf���E�������ł���B����䂦�C���Z�L�����e�B�̃R�X�g�̍팸���ł���B
�@�f�o�C�X�̋@�\�⓭���������l�����C�N���E�h�̕��y�ɂ���Ċ�Ƃ̓��ƊO���鋫�E�����B���ɂȂ����B���̌��ʁC�]���̂悤�Ȗh�q�����͂����葶�݂��邱�Ƃ�O��ɂ������Z�L�����e�B�Ǘ��͎���x��ɂȂ����C�ƌ�����B���Z�L�����e�B�̓����Ǘ��ɂ͐V�����ۑ肪�˂������Ă���B
�@�N���E�h�C�l�b�g���[�N�C�X�g���[�W�⎞�Ԏ��Ɋւ��ẮC�{�e�̋c�_���g���ł���B����ȒP�ɗv�Ă������B�Z�L�����e�B�@�\�̈ꕔ���C���������ꂾ�����N���E�h22�j������i�܂�C�w��������\�z����̂ł͂Ȃ��C�������Ďg�p���邾���ɂ���j�ꍇ���܂߂��ŊK�w�^�����헪���l������K�v������B
�@���V�X�e���̈ꕔ�ł���C�l�b�g���[�N��X�g�[���b�W�ɂ��Ă͐G��邱�Ƃ��ł��Ȃ��������C����玩�̂ɂ��K�w�\�����Ƃ肦��B�������C�������܂߂��C�K�w�^�����헪���l�@�����K�v������B
�@����ɁC���Ԏ����K�w�^�����헪�Ɏ������K�v������B���Ȃ݂ɁC���Ԃ̌o�߂Ƃ������ƂɊւ��ẮC�r�����Ђւ̓��o�ڂɍۂ��āC���ꂼ��̎��Ԃ��L�����Ă��炤�i�L������C�L�^����j�����́C����̃^�C���X�^���v�̎d�g�݂Ɏ�������Ă��邪�C�P�Ȃ�F�i�N�����m�C�N���h�~�j���āC�s�R�s���̒��㔭�����Q�ӏ��̓���E�����C�Ȃǂɖ𗧂��C�Z�L�����e�B�ɑ��đ傫�ȃ����b�g������B
�@�U���҂̍s���ɂ��Ă͖{�e�ő̌n�I�ɕ��͂��Ă��Ȃ��B�U���Ώۂɂ��ẮC���ꂪ�����ʂł��鎖�Ⴉ��C�W�I���߂čU�����鎖��܂ŁC�l�X�ł���B�{�e�œW�J�����悤�ɁC�嗬�͑O�҂����҂Ɉڂ����B�܂��C�U���҂͔��I�ȗU���ōU������ꍇ�����łȂ��C���邢�͌o�ϓI�ȍ������������s������ꍇ�����邾�낤�B�O�҂̓R�X�g�����Ă��邪�C��҂ł͌���ꂽ���\�[�X�̂Ȃ��ō����I�ɍU���s�����Ƃ��Ă��邾�낤�B���̂悤�ɍU���҂͗l�X�ȓ��@�ŗl�X�ɍs�����Ă���B���ۏ�́C���̌��ʁC���������l�����������ƂɂȂ邾�낤�B���I�ȍU���s���́C�����I�ȍs���͂�����łȂ��ƁC���̓����͖��炩�ɂȂ�Ȃ����낤�B���̂悤�ȕ��͂́C���̋@��ɏ��肽���B
�Q�l����
Choudhry, M. and Tanna, K., An introduction to value-at-risk, John Wiley and Sons, 2006.
Computerworld�u�C�O�����Web �U�����Z�L�����e�B�E�p���_�C���̕ω��𑣂��v�w����Computerworld�x�C2009�N�R��16���B
�h���b�J�[�CP. F.�iDrucker, P. F.�j�C����o�c�������w�ϖe����Y�ƎЉ�x�C�_�C�������h�ЁC1959�N�B
�h���b�J�[�CP. F.�iDrucker, P. F.�j��c�Ր��E�c�㐳����w��c���g�D�̌o�c�x�_�C�������h�ЁC1991�N�V���B
�h���b�J�[�CP. F.�iDrucker, P. F.�j�C��c �Ր���w�u�o�ϐl�v�̏I���x�_�C�������h�ЁC1997�N�T���B
�h���b�J�[�CP. F.�iDrucker, P. F.�j�C��c �Ր���w�V���������x�C�_�C�������h�ЁC2004�N�P���i���� �y116 �Łz 1989�N�j�B
Gersbach, H. and Schmutzler, A.,�i 2003�j, �gEndogenous spillovers and incentives to innovate,�h Economic Theory, Springer, Vol. 21�i�P�j, pp. 59�|79.
�� ����Y�u�u���Z�L�����e�B��10�咪���v �`�v�����[�O�`�u���Ђ�O��Ƃ����V�X�e���v�Ƃ́vScanNetSecurity, 2009�N�S��21���C28���B
Hull, J., and White, A., �gIncorporating Volatility Updating into the Historical Simulation Method for Value at Risk,�h Journal of Risk, �P, 1998, pp.�T�|19.
�ѓ��~��u�V�X�e�������̒���_�ƍl���_�\���߂���̂́u�r�W�l�X�Ƃ̓����v�Ɓu�A�[�L�e�N�`���̓����v�v�w����Computerworld�x�C2008�N�X�����B
��䔎���u�I�����C���E�o���L���O��_����������^�T�C�o�[�U���v�wITpro�x�C2009�N11���T���B
Jorion, P., Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, McGraw-Hill, 2000.
Messmer, E., and Bort, J., �u�Z�L�����e�B�E�R�X�g���팸�ɓ����u�R�̃L�[���[�h�v�F�����^SaaS�^�Z�L�����e�B�E�T�[�r�X�vNETWORKWORLD �č��ŁiComputerworld�j�C2009�N�S���U���B
���n��M�u���𗬏o�����Ȃ��u�o����v���d�����悤�v�wITpro�x�C2011�N10���S���B
Shwed, G., �i�M���E�V���G�b�h�j�u�P��G�[�W�F���g�ŃZ�L�����e�B�Ǘ����ȑf������v�w����Computerworld�x�C2008�N12���T���B
�C������E�㓡 ��i2010�j�u���Z�L�����e�B�Ƃ��̓����̕��́`�������`�v�w�w�K�@��w�v�Z�@�Z���^�[�x2010�N12���Cpp.49�|62�B
�C������i2011�j�u���Z�E�o�ϊ����ɂ�������Ȃǂ̕����C�o�b�N�A�b�v�Ə��Z�L�����e�B�`���Z�Z�L�����e�B�̌o�ϊw����iI�j�`�v�w�w�K�@��w�o�Ϙ_�W�x�C2011�N�P���Cpp.301�|321�B
�C������i2012�j�u���Z�L�����e�B�̊K�w�^�����Ǘ��Ɋւ���o�ϕ��́iI�j�v�w�w�K�@��w�o�Ϙ_�W�x�C2012�N�S���Cpp.�R�|21�B
�R�� ����Y�u�h�q�Y�Ɗ�Ƃ�_�����W�I�^�U�������o�C�u���w�h��v���l�@����v�wITpro�x�C2011�N�X��28���B
Zaytsev, V., �gW32/Winemmem - Know Your Enemy,�h McAfee Avert Labs Blog, April �X, 2009. �i�u�uW32/Winemmem�v���t�@�C�������������蔲����d�g�݁v�C2009�N�T��20���B�j
Zhuge, J., Holz, T., Song, C., Guo, J., Han, X., and Zou, W., �gStudying Malicious Websites and the Underground Economy on the Chinese Web,�h WEIS2008.�i Johnson, M. E., Ed., Managing Information Risk and the Economics of Security, Springer, December, 2008.�j