�y97�Łz
�t�@���h�̍s���C�o�ό��ʂƂ��̌��߁i�U�j
�`�t�@���h�َ͈��ȓ����Ƃ��`
�C���@����*
�t�@���h�ւ̊S�́C�o�ύĐ��C�n��Đ��ւ̊��҂����߂āC���{�ł͂��ɂȂ����܂��Ă���B��s�o�c�w�������Ă���Ȃ��ϋɓI�ɏo��Ƃ����v�|�̔��������Ă���B�����t�@���h�Ƃ����ϓ_����C�n���̌��I���傩����S���W�߂Ă���B
�@���ɉ�������s���đO�𑖂��Ă��鉢�Ăł��C���[�}���V���b�N�㑽���̒�����o�����āC�V����ƈ琬�ƃt�@���h�ւ̊S�͋ɂ߂č����B�f�[�^����������C���ؕ��͂��ϋɓI�ɂȂ���C�������錋�ʂ�����o�Ă���B���̂悤�Ȏ����ł��邩�炱���C�_�_�����������C�t�@���h�ɂ��Ă������̘_�_�ɍi���āC�[���T�����Ă݂悤�Ǝv���B
�@�{�e�̓t�@���h�Ɋ֘A����\��̎����̌o�ϓI�w�i�E������{�̊T�O�C�����Ė��ӎ���W�J�����O���̘_�l�ł���C���i2013�j���瑱����҂ł���C���ɕ���Ɋ֘A����I�v�V�������_�₻���̐헪���Ղ����ڂ����C�}�\�Ȃǂ�p���āC�֘A���邪�@���_�ł͂Ȃ��C�o�ϊw�I�ɓW�J����B�ߔԍ���r���ԍ��́C�O�҂ɑ������̂ł���B
�T�@�t�@���h�̌_��ƃI�v�V�����헪�̏ڂ������
������Ђ̋c�����ƌo�ϓI���L���̕������C�o�ώЉ�ɂƂ��ĕs�����ɂȂ邾���łȂ��C������s�s���ł���ƍl����C���ꂪ���݂���B���̂��Ƃ�������C���\���錠�����C�M�҂͔F�߂�B�������Ȃ���C������K���ɂ���đΉ����邢���Ȃ�ꍇ�ł����Ă��C�f���o�e�B�u�Ƌ�̗��_�Ɋ�Â������̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����C�����ւ̉e�����l���������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��C���낤�B�����łȂ���Ύ���̋����C���NJԈ�����l���E�{��ɂȂ��Ă��܂��C�����̈Ӑ}�͑䖳���ɂȂ��Ă��܂��B���̊ϓ_����C�I�v�V�����헪�̐��ʂ����ԓI�ɒǂ��Ă����Ă݂悤�B
�T�|�P�@�I�v�V�����헪�̏ڂ������
�t�@���h�́C���g���ۗL���銔���̒l�������]�ށC�ǖʂ����݂���B���̂��Ƃ��܂����Ă݂悤�B������C�悭�m��ꂽ��{�I�ȃI�v�V�����헪�ł���v���e�N�e�B�u�E�v�b�g�Ƃ��̎��ԍ\���ɉ����āC�I�v�V�����헪��������Ȃ���������Ă݂悤�B�����āC���̋ǖʂ͐���
�y98
�Łz
�ȃw�b�W�̉ߒ��ŏꍇ�ɂ���ĕs���ɐ����邱�Ƃɒ��ӂ��Ă��������B�܂��C�g���̎d���Ƃ��̐��ʂ��݂āC�����ɂ�����p�t�H�[�}���X�̐^���Ƃ͉������l���邱�ƂɂȂ�B
�@�������s��Ђ̌o�c�w�₻�̊���ɑ��ė��v�𑊔����铊���Ƃ́C�K�������C�����Ɣ��ڂ���i���ӂ̂���j�����Ƃł͂Ȃ��C�P�ӂ̃w�b�W���[�ł���\��������Ƃ������Ƃ�������邱�ƂɂȂ�B�Ȃ��C�����̖{�e�t�^�ł́C��������������̂��ƂŁC���l�Ȏ�����W�J����B
�i�P�j�v���e�N�e�B�u�E�v�b�g�̍\��
�����C���铊���Ƃ��������i�ȉ��̐}�ł͂P���Ƒz��j�ۗL���Ă����Ƃ��悤�B�����ɁC�����̉������X�N�����܂����C�Ƃ��悤�B�����ŁC�Ⴆ�C�v�b�g�E�I�v�V�������w������C�w�b�W�ł���B���ꂪ�v���e�N�e�B�u�E�v�b�g�iPP �Ɨ�����邱�Ƃ������̂ŁC�ȉ��ł͂���ɏ]���j�ł���B�ȉ��C�}�\�ł́C��������P�P�ʂ̎���Ɖ��肵�č�}���邱�Ƃɂ��悤�B���̎�̐}�������ł���悤�ɁC���[���s�A���E�I�v�V�����̌����i�����j�̃y�C�I�t��`���B
�@�v���e�N�e�B�u�E�v�b�g�́C�����̍w�����i�ɌW��炸�C�����̉������X�N���v�b�g�E�I�v�V�����̍s�g���i�܂łɌ���ł���B�w�b�W�E�R�X�g�̓v���~�A���������̒l�オ�藘�v�@��̑r���ł���B������ɂ��Ă��C�d�オ��̓R�[���E�I�v�V�����̃y�C�I�t�E�^�C�v�ł���B
�@��������C�܂��s�g���i�������i�����̒l�����肪�Ȃ��s�g���i�������j�����ɁC�v�b�g�E�I�v�V�������w������C�}�\�P�̂悤�ɁC�����p�t�H�[�}���X��������B�܂�C�������w���������_�ŁC�����l��������m�M���Ă���Ȃ�C�\�Ȃ�s�g���i�̍����v�b�g���Ă��ǂ��B���Ȃ݂ɁC��q�̘_�_����肵�čl����C���̂悤�ȏꍇ�C�����̃I�v�V�������ɑg������I�v�V�����헪���Ƃ��Ă��C�D�܂����p�t�H�[�}���X����������B
�@�v�b�g�E�I�v�V�������w������^�C�~���O���x��C�s�g���i�������̍w�����i�܂Œቺ���Ă���CPP�����ꍇ���}�\�Q�ł���B
�@�Ō�ɁC�v�b�g�E�I�v�V�������w������^�C�~���O���܂������x��C�s�g���i�������̍w�����i�̂͂邩���̒Ⴂ�����܂Œቺ���Ă���PP�����ꍇ�C��ʂɃv���~�A�����傫���㏸���Ă���C�}�\�R�ɂ悤�Ɂi������艺�́j�����]�[�������ɑ傫���Ȃ�B
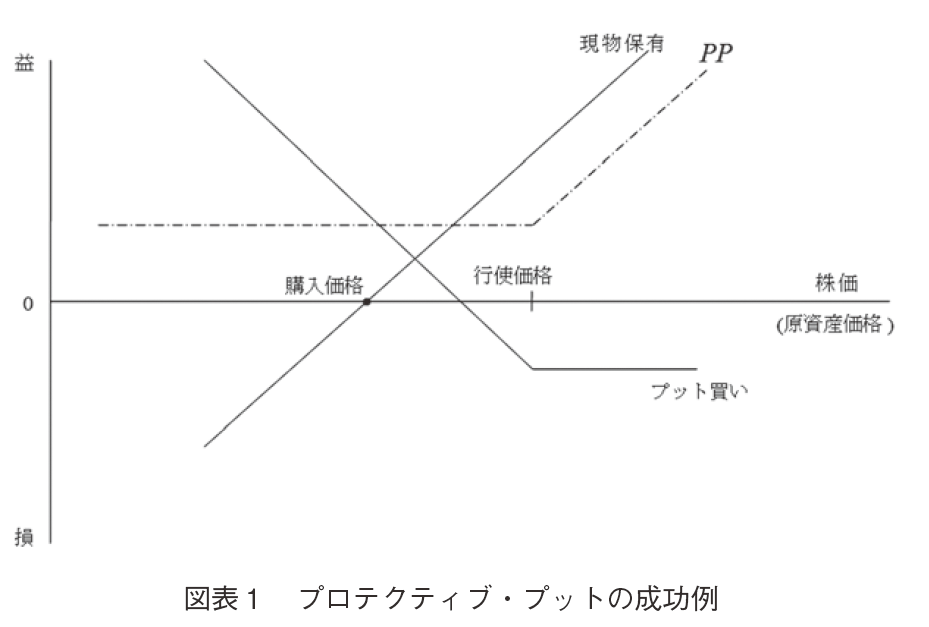
�y99 �Łz
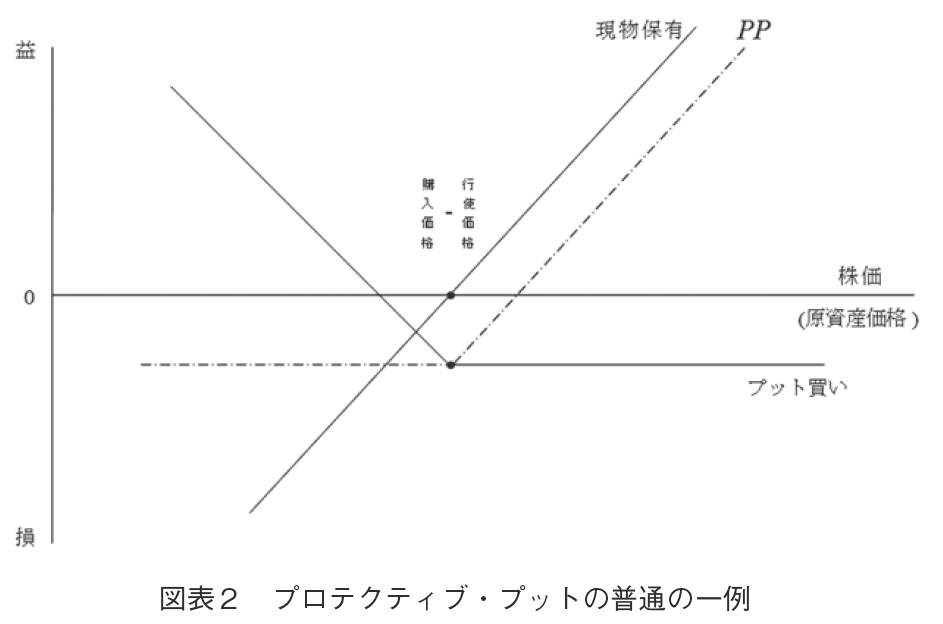
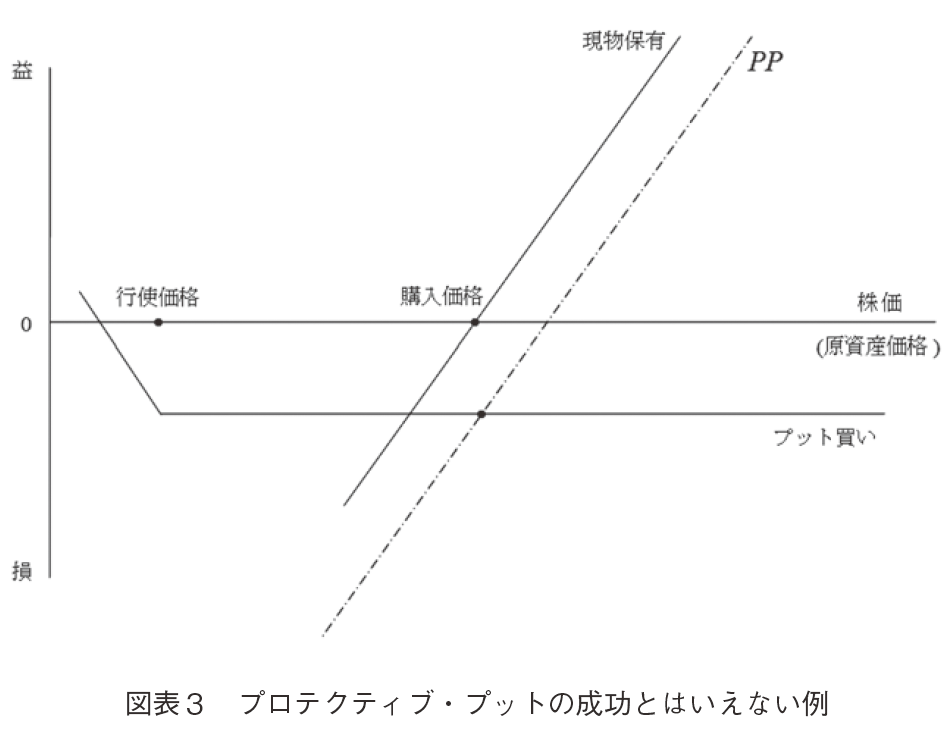
�y100 �Łz
�v��CPP �ɂ��w�b�W���O�ł́C�v�b�g�E�I�v�V�������w������^�C�~���O�����ɏd�v�ɂȂ�C���Ƃ��킩��B�܂��C�s��Ɉˑ����Ȃ��������ʂ̍����i���ꂪ����^�[���ƌĂ��j�𓊎��Ƃ�搂��Ď������W�߂�t�@���h�̏ꍇ�C�}�\�Q��R�̒�p�t�H�[�}���X�ł͓����̎��s�ɂȂ�B�ڋq�����Ƃ͂��̃t�@���h���瓦���Ă������낤�B
�i�Q�j�v���e�N�e�B�u�E�v�b�g�َ̈��ԍč\��
�v�b�g�E�I�v�V�����̍s�g���i���C�����̍w�����i�ƃv�b�g�E�I�v�V�����̃v���~�A���̘a�Ɉ�v����ꍇ�i�}�\�S�j�C�������s�g���i��艺��������PP �̑��v�̓[���ɂȂ�B
�@����䂦�C���̏ꍇ�ł��t�@���h�͓������s�̉������瓦����Ȃ��B�ڋq�����Ƃ͂�͂肱�̃t�@���h���瓦���Ă������낤�B
�@���̂悤�Ȏ��ԂɊׂ邱�Ƃ��\�z�ł���Ȃ�C�R�[���E�I�v�V������Ƃ����d�w�I�ȃw�b�W���@������B�}�\�S��PP ���o���_�ɂ��āC���̂悤�ȃw�b�W�̌��ʂ��l���Ă݂悤�B
�@�����̒l������̑����i�K�ŁC�R�[���E�I�v�V�����������C�R�[���E�I�v�V�����̍s�g���i��PP ��g�������v�b�g�E�I�v�V�����̍s�g���i��荂���ł��邩������Ȃ��B���̏ꍇ�C�������v�́C�}�\�T�̔j���̂悤�ɂȂ�B���������̂Ȃ��C�������R�[���E�I�v�V�����̍s�g���i���瓾����v���~�A�������^�[���̒������āC��r�I�����p�t�H�[�}���X���B������C�t�@���h�ɂƂ��Đ����ɂȂ�B���̂悤�ȃw�b�W�ɑ���R�X�g�́C�唽�]���Ċ������㏸����ꍇ�C�l����ł��낤�i�V��́j���v���̂Ă�Ƃ���ɂ���B
�@���̂Ƃ��C�����R�[���E�I�v�V�����ƃv�b�g�E�I�v�V�����̍s�g���i�������ɂȂ�C�����ϓ����X�N��Ȃ��i�}�\�U�̔j�����Q�Ɓj�BPP �ɃR�[���E�I�v�V�����̔�����d�˂��t�@���h�̍s���́C���̏ꍇ�C�����̕ϓ��ɑ��Ė����ʂɂȂ�B�������Ȃ���C���I�v�V�����̍s�g���i�������ɂȂ�C���̂悤�ȃP�[�X�͋H�ł���B���̐}�\�ł́C����Ȃ�̍������v���l���邪�^�͊l���Ȃ��B�������Ȃ���C�t�@���h�Ƃ��Ă͈��ׂł���B
�@�Ƃ��낪�C������������������Ȃ��C�R�[���E�I�v�V�����̔��肪�傫���x���ƁC�R�[���E�I�v�V�����̍s�g���i���v�b�g�E�I�v�V�����̍s�g���i��啝�ɉ����C�}�\�V�̂悤�ȃw�b
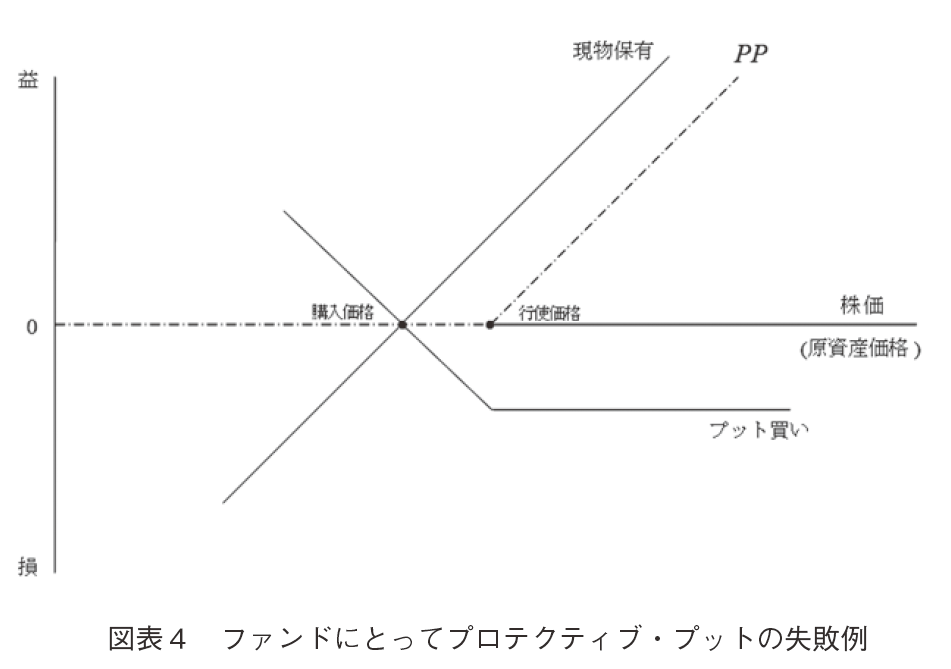
�y101 �Łz
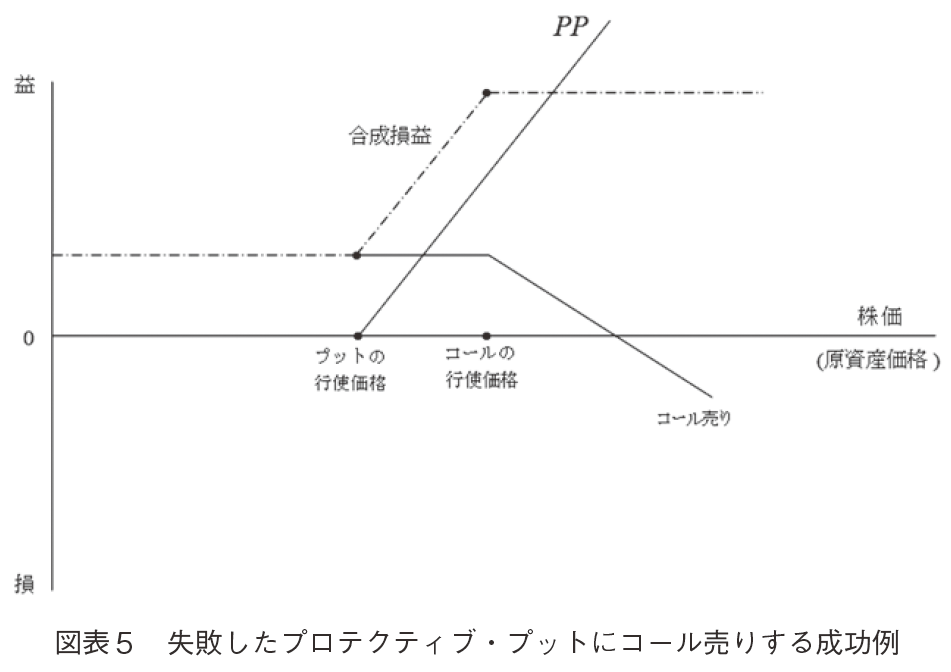
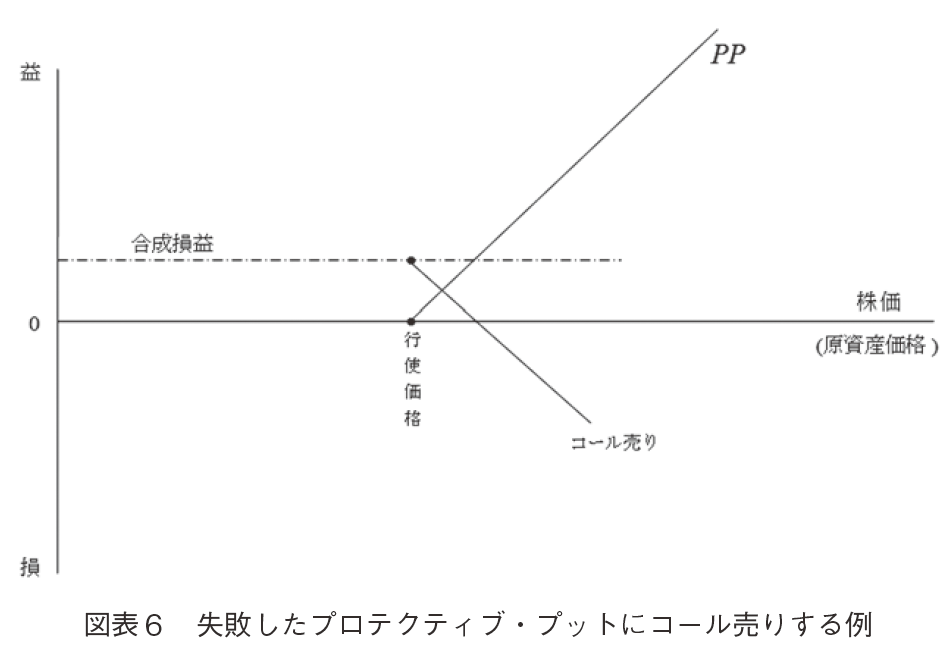
�W���ʂɂȂ��Ă��܂��B���̌��ʁC�R�[���E�I�v�V��������̊�����C�������\�z�ɔ����đ唽�]���ď㏸����C�ނ���C�呹���Ɋׂ��Ă��܂��B�Ⴂ�s�g���i�̃R�[���E�I�v�V�����͔���ׂ��ł͂Ȃ��C�����P�ɂȂ邾�낤�B
�@�����ŁC�}�\�T����}�\�U�܂ňӋ`��v��ƁC������ɂ��Ă��C�v�b�g�E�I�v�V�����̃����O�E�|�W�V�����ƃR�[���E�I�v�V�����̃V���[�g�E�|�W�V������g�ݍ��킹��C�����ϓ����X�N���R�[���E�I�v�V�����̍s�g���i������i�}�\�V�ł͉����j�C�v�b�g�E�I�v�V�����̍s�g���i�������i�}�\�V�ł͏���j�Ƃ���͈͂Ɍ��肷�邱�Ƃ��ł���B
�y102 �Łz
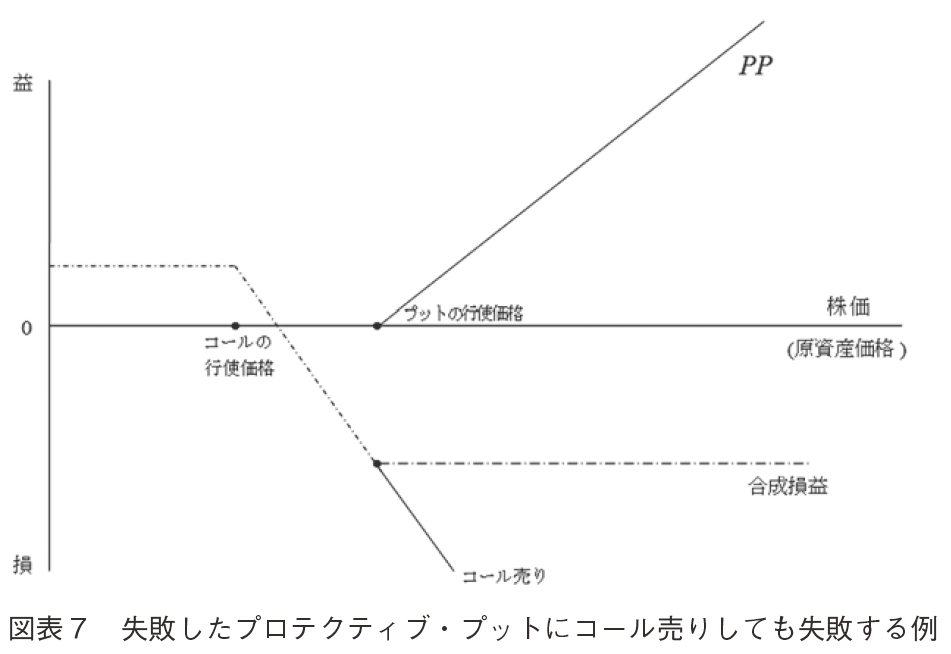
PP�ɃR�[���E�I�v�V�����̔�����d�˂��t�@���h�́C�}�\�V�̏ꍇ�C���m�Ɋ����̒ቺ��]�ނ悤�ɂȂ�B���̓_�ŁC�o�c�w�⑼�̊���Ɨ��Q����v���Ȃ��Ȃ�B���̗��R�̓t�@���h�̃w�b�W���x�ꂽ����ł���C�t�@���h�̃~�X�ł���B
�i�R�j�o���I�I�v�V�����헪�̑g�����痘�v��
PP�ɂ���đg�����ꂽ�C�����R�[���E�I�v�V�����i�����j�̍s�g���i�́C�\���㓖�R�̂��ƂȂ���CPP�̍\���v�f�̃v�b�g�E�I�v�V�����i����j�̍s�g���i�ɂȂ�B�����āC���̒i�K�Ŕ������R�[���E�I�v�V�����̍s�g���i���ǂ����ʂނ��ǂ����́C�����O�ł݂��悤�ɁC�����̃^�C�~���O�̐��ۂɂ���āC����Ă���B�^�C�~���O�ɂ���āC�R�[���E�I�v�V�����i����j�̍s�g���i�������R�[���E�I�v�V�����i�����j�̍s�g���i��荂�����Ⴂ���ɂ���ăp�t�H�[�}���X�͈���Ă���B
�@���ɂ����C���̃R�[���E�I�v�V�����̍s�g���i��PP�̍s�g���i�Ɉ�v����C�X�ɂ܂��v���~�A���������Ȃ�C�������ꂽ���v�͐����ɂȂ�B�܂�C�I�v�V�����헪�̓`�����ɂȂ�C�������Ȃ��������ƂɂȂ�B����͕ۗL���Ă������������̍w�����i�Ŕ���̂ɓ������B����ł��C������ۗL�����܂܂ł͋N����ł��낤����������邱�Ƃ��ł���Ƃ����Ӗ��ŁC�l�����ɂ���ẮC�L���ȃw�b�W�ƂȂ�B
�@���̓_�ɂ����āC�o���I�ɃI�v�V�����헪��g������Ӌ`������B���Ԃ̌o�߂ƂƂ��Ɂi�o���I�Ɂj�I�v�V�����헪��g������C�萔�͂����邪�C�^�C�~���O���悯��Α傫�ȗ��v�i�t�����l�j�ݏo����\���͂���̂ł���B
�i�S�j����Ԃ̌������ƃw�b�W�̐���
���A�N�Z�X�̃��[�g�Ǝ�i���ł��邾���ϓ��ɐݒ肵�āC���������̋@���������C���Ƃ�����Ԃ̌������ł���ƒ��҂͑�����B
�@���ɁC��������Ƒ������i����ɂ���ẮC�x�z����Ƃ������t���g����j�̊Ԃ̌��������ێ����邱�Ƃ͌��㊔���s��̈��e�[�}�ł���悤�ɂ݂���B
�@���̍ہC�w�b�W�̐��ۂ͖��ƂȂ�Ȃ��B�s�����ȓ������s���āC�Ӑ}�ɔ����āC�w�b�W��
�y103
�Łz
���s���đ��v��ւ��Ă��C�s���������������ɂȂ�킯�ł͂Ȃ��B�������o����ɁC�����ɔ�����s�ׂ��s�����ƒe�N���ꂽ��C�i�ǂ��ꂽ�肷��C���Ƃ��N����킯�ł���B
�i�T�j���S�������s���S�������`�e�ׂȕ��͂��K�v
�t�@���h�́C������ЂƔ픃����Ђ̑o���̊����ɓ��������Ă�����C�����ł͂Ȃ��G�N�C�e�C�֘A�،��ɓ��������Ă����肷�邱�Ƃ�����B���̂��߁C�c�����s�g�Ώۉ�Ђ̎c�]���l�����߂邱�ƈȊO�̖ړI�E���@�ŋc�������s�g����������Ȃ��Ƃ������Ԃ����R�̂悤�ɐ�������B
�@�������Ȃ���C���̌��ʑΏۉ�Ђ̉��l���ʑ�����C�t�@���h�����̕���������̂ŁC���̎��Ԃ�������邽�߂Ɏc�]���Y���҂Ƃ��Čo�ϓI���X�N���w�b�W���������ŁC�c�����������s�g���邱�ƂɂȂ�B���̂��Ƃ��u�G���v�e�B�E�{�[�e�B���O�v�̎�@�ƌ������킯�ł���B�G���v�e�B�E�{�[�e�B���O�Ƃ́C�u�c�����s�g�Ɍo�ϓI���v�E�s���v�������Ă��Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��ł������B
�@���S�������s���S�������̂Q���@�ŕ�����C�����܂Ō��Ă����悤�ɁC�f�J�b�v�����O�헪�͕s���S�����ł������B���X�N���w�b�W������ł̋c�����̍s�g�ł͂��邪�C���X�N���܂���������������ł̋c�����s�g�ł͒f���Ă��肦�Ȃ��B��ʂɃw�b�W�͊ȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�w�b�W�̎��s�͓���I�ɂ�����B�t�@���h�͈��ł���Ǝ咣���t�@���h�ɔ�����C�������̐�s����_�l�ł̓w�b�W�̌��ʂ�Ӗ����Ԉ���đ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�w�b�W�̒��g�̌������ɂ��Ċ��S�����ł��邩�ǂ����͋c�_�ł��Ȃ��B�w�b�W�ɂ��Ă̂��̂悤�ȑ������́C���ʂȂ��̂ł͂Ȃ��C���[�J�[�⏤�Ђ��邢�͋��Z�@�ւ̃w�b�W�S���҂ɂƂ��āC���ɂ����Ƃ��Ȍ��_�Ȃ̂ł���B
�@�܂��C�t�@���h�̖ړI�ƌo�c�҂̖ړI���傫���������Ă��邱�Ƃ͂��肦�邪�C���̃P�[�X�̐��͌�����B����䂦�C�t�@���h�ƌo�c�҂̑Η��͋����{�ʂɌ֒�����߂��Ă���̂ł͂Ȃ����C�Ǝv���B
�@�f�J�b�v�����O�헪�́C���ݍ��������Q�����āC�o�c�̌�������}��L���Ȏ�i�ɂȂ肤��B���Q�̗��݂������Ȃ���Γ|�Y�������肦�Ȃ���Ƃ��C�f�J�b�v�����O�헪�ɂ���āC�~����̂ł���B����䂦�C�M�҂͂��̐헪���o�ώЉ�̌o�ό����ɉʂ��������������]���������C�Ǝv���Ă���B
�U�@�t�@���h�َ͈��ȓ����Ƃ�
�U�|�P�@�����N���Ă���̂�
�i�P�j�����ő��������̌���
�O�X���I�������琢�I���Ɋ|���āC���{�������ېV�Ɏ��g��ł��炭�o�����C�܂��������{��`�����t���Ă��Ȃ������C�č��ł́u���L�ƌo�c�̕����v���������n�߁C���ɂ��ꂽ�B����́C���������銔��ƌo�c�҂��قȂ�o�ώ�̂Ɛ��������ۂł������B
�@�ŋߋN�����Ă��鎖���́C�����ۗL�ɂ�����u�c�����ƌo�ϓI���l�̕����v�ł���B����́C��Ɖ��l�Ɗ����̘����Ȃ̂��B����Ƃ��C�c�����Ƃ����Q�Ƃ̘����Ȃ̂��B�������������N�����Ă���̂��C�ȉ��ŁC�����l���Ă݂悤�B
�i�Q�j�������^�[���̒��Z�̘���
�c�����ɂ́C�Z���I�ɂ͊������^�[���̕ω��ƒ��ڌ��ѕt���Ȃ��ꍇ�����R���݂���B����
�y104
�Łz
���̂悤�ȏꍇ�ɖ�肪������悤�ł���B�c�����́C��Ƃ̌o�c�헪��ς�������̂ł���B�������Ȃ���C���̐��ʂ������̂Ɏ��Ԃ�v���C�ނ��는���̒������^�[���ƌW����Ă���B�c�����͏����̊������^�[���������炷��i�Ȃ̂ł���B
�@����䂦�C�u�c�����ƌo�ϓI���l�̕����v�́C���ǁC�u�������^�[���̒��Z�̘����v�ɍł��W����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv����B����䂦�C����͓����̎���̍��قɊւ���Ă���B
�@��Ƃ͖����̏����܂ő�������i�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��邱�Ƃ͊�ł���j��������̂����ʂł��邪�C��ʂ̓����Ƃ̓������Ԃ͗l�X�ł���B�N������͒������C�f�C�g���[�_�[�͋ɂ߂ĒZ���B�����C�t�@���h�͒������I�ƌ�����B���̋c�������́C�Z���̎��삵�������Ȃ������Ƃƒ������̎�����������Ƃ̊Ԃ̐킢�ł���Ƃ�����ʂ��ے�ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv����B
�@�������C���q�̂悤�ɁC���ۗL�̔�Ώ̐����C�d�v�ȗv�f�Ƃ��Ċւ���Ă���B�������Ȃ���C���p�x��������ڂ���錻��ɂ����ẮC�����ۗL�`�Ԃ̑��l�����i��ł������܂���ƁC�������Ԃ̘����̕����d�v�ł���悤�Ɏv����B
�U�|�Q�@�ǂ��������̂�
���Ԃ������������܂����܂܂ɂ��Ă���̂́C�@���Ⴆ�Ή�Ж@�������̂��C�t�@���h�������̂��B���邢�́C�X���b�v��I�v�V�����������̂��C����Ƃ���Ђ������̂��B���ɍl���Ă������B
�U�|�Q�|�P�@�@����K���̌���
�U�|�Q�|�P�|�P�@�@����K���̌��E
�i�P�j�@����K���̓���
�@����K���ɂ��ẮC�ǂ����낤���B���Z�Z�p��w�b�W�t�@���h�̎����@�i��q���邪�C����͒f���Ĉ��ł͂Ȃ��j�̐i���ɋK�����ǂ����Ă��Ȃ����Ƃ́C�N��������������ꂽ�B
�@�@����K���́C��ʂɁC�o�ώ��ۂ��N����O�́C���O�ɂ͑��݂����Ȃ��C�悤�Ɏv����B�@�������ł͂Ȃ������҂ɂƂ��āC���̂��Ƃ͌��l�Ȏ����̂悤�Ɏv����B�@����K���������͎̂���ɂȂ��Ă��܂��B����ɁC�����������O���[�o�������Ă��錻��̉��ŁC���{�����摖���Ė@�����E�K�������邱�Ƃ͑Ó��ł͂Ȃ��Ƃ������������B����䂦�C�t�Ɍ����ƁC���̂悤�ɂȂ�B�@����K���������Ă��Ȃ�����C�@����K���������킯�ł͂Ȃ��B�������Ă����悢�̂ł��邵�C�������Ă��������Ȃ��B
�@�Ώۉ�Ђ�ΏۂɂȂ肻���ȉ�Ђ̕s���͑傫���������Ă��邪�C�G���v�e�B�E�{�[�e�B���O�̋�̓I�ȕ��Q�����炩�ł͂Ȃ��C�̂������ł���B���_�̉𖾂��ς܂Ȃ��Ȃ��ł́C�@�����͈�ʂɍ���ł���B
�i�Q�j��ʕۗL�̗�
�p���C�X�C�X�C�t�����X�́C�]���C�G�N�C�e�B�E�f���o�e�B�u��������J���̑ΏۂƂ��C��ʕۗL�̑ΏۂɊ܂߂Ă���B���̌��ʁC�����I�c�����̉B���ɂȂ�悤�ȑ�ʕۗL�͋K�������B��������O����߂��Ă��邪�C���J���t�K���̎����I�ᔽ�ɑ��āC�c�����̍s�g�𐧌�����K��������B
�@���{�ɂ����Ă͉�Ж@���������̘_�_�̈�ɂȂ����ɉ߂��Ȃ����C�����̍��ł́C�ŋ߁C�G�N�C�e�B�E�f���o�e�B�u���g����hidden ownership �̎擾�ɑ��Ĉ�ʓI�ȋK����݂�����@�őΏ����悤�C�Ɠ����o�����ƕ���Ă���B
�y105 �Łz
���ۂɃh�C�c�ɂ����ẮC�O�q�́C�V�F�t���[���J�����s�����ƂȂ������̔����W�߂��s�����s�ׂ́C�K�@�ł���Ƃ��ꂽ�B���̌�C�ގ��̖��̈ꕔ�ɂ����@�I�蓖���Ȃ���铮���ɂȂ������B
�i�R�j���O�Ǝ���`���Z�Z�p�v�V�̗�
�n���I�ȐV���Z���i�J����v���i�߂���C���E�̎�v��i���{�s��ɂ����ẮC���̖@���E�K�������X�Ɛ��܂��V�������Z�Z�p�v�V������ɓ���ĕ��G��������Ȃ��B���̎����́C���Z�ɑ�����I�Ȏ��O�K�����\�z�E�������邱�Ƃ̓���������Ă���悤�Ɏv���B
�@���������Z�p�v�V��j�Q���邱�ƂɂȂ�C�����Ȃ�K����������ׂ��ł��邪�C����̖��m�𗘗p���Ė\�����l�悤�Ƃ����[�J���҂̃������n�U�[�h��U������댯���͂ʂ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���������邽�߂ɁC�K�ȍŏ����̎��O�K�����K�v�ɂȂ�B���{��`�̃��[�����ێ����Ȃ���C�������n�U�[�h��h�~����ɂ́C���x�ȋZ�p���K�v�ɂȂ�B
�@���ꂾ���łȂ��C�����O�̏��߁i�P�j�Ō����悤�ȁC�@�K���̔������Ȃ������Ƒ��܂��āC�K�Ȏ���K�����K�v�Ȃ��Ƃ������Ă���B�����āC����Ɏ���K���͎��O�K���ƓK�ɘA�g�����ׂ��K�R�������邱�Ƃ������Ă���B
�@�o�܂͂ǂ��ł���i�܂�Ӑ}���Ď��O�K���ɔ����Ă��悤�ƂȂ��낤�Ɓj�C�@�߂��邢�͋K���i�Ⴆ�Ύ����K���E��ʕۗL�K���j����u�ł������鎖�Ԃ�����Ɋώ@���ꂽ��C����I�ɂ́C���O�̖@�߂��邢�͋K���Ɉᔽ���Ă����C�Ƃ������������ꍇ�ɂ���ĕK�v�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�@����ł͎����ł����Ă��C�o�ϓI�ɂ͎����N�����͂邩�ɒ�������ɒ������Ԃɓn���āC�����͉e������̂ŁC���̂��Ƃ�O��ɂ������x��肪�K�v�ɂȂ�C�Ƃ������Ƃł���B
�U�|�Q�|�P�|�Q�@������x�̌��_�̗�
�i�P�j�݊����x�݂̍��
���q�̂悤�ɁC���{�̑݊����x�ɂ����ẮC�����̎�肪�C���ۂɌ������擾���Ȃ��ł悢���Ƃ�F�߂Ă��邩���肪������B�������Ȃ���C�h�C�c�̑݊����x�ɂ����ẮC�����̎��́C���ۂɂ͌������擾����B���̂悤�ɈقȂ鐧�x����蓾��̂ł���B�݊����x�݂̍�����L���C�V�������_���猟������ׂ���������Ȃ��̂ł���B
�i�Q�j�f���o�e�B�u�̌��ϐ��x
���q�̂悤�ɁC�V�F�t���[�R���`�l���^���^�C�������ł́C�������σf���o�e�B�u�����ɂȂ����B�������ς̃f���o�e�B�u�ƌ������ς̃f���o�e�B�u����ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�����肪���邱�ƂɂȂ�B����䂦�C�K�����������邽�߂ɂ͌X�̃f���o�e�B�u����̌��ϕ��@�܂ŗ�������K�v������B
�@���҂̍l���͎��̂Ƃ���ł���B����̌��ϕ��@���K�����邱�Ƃ͎�������ȍ�����C���Ԃ�̏��Ȃ��ɂ߂č��R�X�g�ȋK���Ȃ̂ł���B�������C��������������������̌��ϕ��@�K���͗L�j�ȗ��s��ꂽ���Ƃ��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���������K�����s���ׂ��ł͂Ȃ��C���낤�B
�U�|�Q�|�Q�@�t�@���h�̌���
����Ƃ��Ẵt�@���h�ɂ��ẮC�ǂ����낤���B
�i�P�j���̑�����̗��v�ƃt�@���h�̗��v
���呍��ɓˑR�劔��Ƃ��ďo�����C���g�ɓs���̂悢�̌�������C���̂��߂ɁC�ꕔ�ł́C�����s��ł̌��O�ޗ��ɂȂ��Ă���C�Ƃ����̂��t�@���h�ւ̔ᔻ�̂P�ł���B�u����
�y106
�Łz
�c�����v�݂̂�ۗL����҂́C��Ɖ��l�̌���Ɩ��W�Ȏ���̗��v�݂̂�}��\�����������߁C���̋c�����s�g�́u���勤���̗��v�v�ɔ����邨���ꂪ�����C�Ƃ����̂��t�@���h�ւ̔ᔻ�̂P�ł���B
�@�]�����̋c��������̘_�]�ɂ́C���ׂĂ̊��傪�����\�z��ӌ������ׂ��ł���Ƃ����O�C�M�҂ɂ́C�ǂ�������悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B����ɁC���g�ɓs���̂悢�C����̗��v�݂̂�}��s�����i���ׂẮj����́C�̂��Ă͂Ȃ�Ȃ��C�Ƃ����O�ǂ�������悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B���Ɏc�]���ɂ��āC��Ɖ��l�ő剻�������炷�c�Ăɔ����銔��̑��݂͎��{��`��ʖڂɂ���C�Ƃ����v�����݂�����C�̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�S�������Ă��C��������В�ĂɒN����������ׂ��ł͂Ȃ��C�Ƃ����O����̂ł͂Ȃ����ƁC�v���B
�@�������C�t�@���h�^���h�Ɣ��Δh�Ƃ��ɁC�ӌ��̈�v���鎖������������B�ꊔ���������Ă��Ȃ�����ɁC��ЂƖ��^�����ɂ���ׂ��ł���Ƃ����l�͂��Ȃ��i���������N���ꊔ����ɊS�������̂�������Ȃ��j�B�ꊔ����͈ꊔ�����̗L���ӔC������ɉ߂��Ȃ��B�܂��C�����ɖ��\�Ȍo�c�w�����ۂɌo�c���������Ă����Ƃ�����C���̌o�c����ɂ͔�����ׂ��ł���B�����̎����Ɉ٘_��������l�͈�ʂɂ��Ȃ����낤�B
�@�o�c�w���o�c�\�͂������Ă���̂��ǂ����C��K�ɔ��f���邱�Ƃ͑�ϓ���B�ߋ��̎��т͂��邪�C�����V�������Ԃ����ꂽ�ۂ��̔\�͂���������邩�C�ǂ������킩��Ȃ��B
�@�o�c�\�̗͂L�閳���̕]���C���f�̍��ق������ӌ��̑���������炷�����ł͂Ȃ��B����o�c�헪���邢�͊��呍��c�Ă���Ɖ��l���C���ہC�ő剻�ł��邩�ǂ����́C���������C���̐��ʂ͏����l������̂ł���C�s�m���ł���B���̓_�ł��]�����������̂ł���B
�i�Q�j�ڋq�̗��v�ƃt�@���h�̗��v
�����Ɋւ�����Z�@�ւƂ��̌ڋq�����Ƃ̊W�́C���̂悤�Ȃ��̂ł���B�ڋq�ɑ����킹�āC���Z�@�֎���͗��v���グ�Ă��C���ʁC���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���Z�@�֎���́C�l�����肵���ꍇ�ɔ����ċ�Ȃǂɂ�藘�v���グ����悤�ɂ��Ȃ���C�l������ɂ���Čڋq�ɑ����킹�邱�Ƃ������Ă��C�l������̃��X�N�����O�Ɍx�����Ă������C�ϗ���̖��������邱�Ƃ͂��肦�Ă��C���̌ڋq�͓����Ă������Z�@�ւ͌ڋq��������������Ȃ��Ƃ������ƈȊO�Ɍo�ϓI�ɂ͖��Ȃ��C�ƕM�҂͍l����B���̏ꍇ���Z�@�ւ������ɔ����ăw�b�W���āC������������Ă��Ă��C���l�ł���B
�@�������Ȃ���C�ڋq�ɑ����킹�邱�Ƃ�O��ɁC���Z�@�֎��炪����ɂ���ė��v���グ����悤�Ɍ̈ӂɎd�g�߂C�K���ᔽ��Ƃ����ƂɂȂ�B����͔ƍ߂ł���B
�@���Z�@�ւ��t�@���h�ɁC�ڋq�����Ƃ���Ђɒu��������C���R�C�����c�_�����藧�B����ɁC�����Ɋւ��锭�s��ƂƓ����Ɓi�t�@���h�Ȃǁj�̊W�́C���Z�@�ւƌڋq�����Ƃ̊W��肳��ɁC���R�ȊW�ł���ׂ��ł���B��Ђ����S�̊�@�ɂ��鎞�ɁC�t�@���h�����v���l�āC�o�ϗϗ���ȊO�́C���̖����Ȃ��B
�@�t�@���h�̂Ȃ��ɂ́C�m���ɁC���点�邱�Ƃ������ړI�̃t�@���h������B���̂悤�ȃt�@���h�́C���点�āC���������l�Ŕ������悤�ɉ�Ђɗv������B�ǂ̂悤�ȑg�D�E�ƊE�ɂ��ƍߎ҂�����̂ŁC���̎����������ăt�@���h�ɔ�����ׂ��ł͂Ȃ��B�������Ȃ���C������ǂ̂悤�ɋ�ʂ��Ή�����ׂ����́C��ʂɓ�����ł���͎̂����ł���B�P������ʂł��Ȃ�����Ƃ������ꂾ���̗��R�ŁC�t�@���h�ɔ�����ׂ��ł͂Ȃ��C�̂ł���B
�U�|�Q�|�R�@�w�b�W��i�̌���
�w�b�W��i�ɂ��ẮC�ǂ����낤���B�w�b�W��i�Ƃ��ẴX���b�v��I�v�V������������
�y107
�Łz
���ł͂Ȃ��B��ł݂��悤�ɁC�w�b�W�ɂ����x�ŏn�������Z�p���K�v�ł���C�w�b�W����ΕK����������킯�ł͂Ȃ��B�������C�����Ƃ�������̎��Ǝ��s���w�b�W���鐳���Ȍ������y�����Ă��ẮC���{��`�o�ς͗����s���Ȃ��Ȃ�B�܂��C�w�b�W���s���̃t�@���h�̑��~���i�������j�̓w�b�W��i�̗ǔۂƂ͊W�Ȃ��B
�@�܂��C�䂪���͎����̖R�������ł���C�Z�p��l�ނŁC������ׂ����ƌ����Ă����B���Z�H�w����Z�Z�p�͑ނ���̂ł͂Ȃ��C�Z�p�����̎�i�Ƃ��Đ���グ��ׂ��Ȃ̂ł���B�����́C�ނ���C�Ȋw�I�Ȑ��l�v�l���ł�����{�l�Ɍ������Z�p�Ȃ̂ł���B
�U�|�Q�|�S�@��Ђ̌���
��Ђɂ��ẮC�ǂ����낤���B
�i�P�j�o�c�҂̓w��
������ЂƂ́C�{���C���傪��Ђ����L���C��Ђ��R���g���[������c���������d�g�݂ł���B���̂悤�Ȋ�����Ђ����ė��v���グ����̂́C�������Ċ�Ɖ��l���グ�C�������p�ł��邩��ł���B����䂦�o�c�҂���Ɖ��l�����ꂼ��̎��_�ōő剻���Ă���C����ȏ�͊�Ɖ��l���グ�邱�Ƃ��ł��Ȃ�����C���������S�z�͂Ȃ��B�������z���������甃���������B���̎�����m��Ȃ����\�Ȕ����҂��C���s�����āC���l������ȏ�L�тȂ���Ƃ����Ă��C�����̏ꍇ�ނ炪�{���]�ޏo���͂Ȃ��B
�@������h�����߂ɂ́C�����납��Ɛт�ǂ����C�\�Ȍ��芔��D������Ƃ�C�\�Ȍ���z���𑝂₵�Ď������z���グ�Ă����悢�B�����h�q�����������K�v������̂́C��Ƃ������I�Ȍo�c�����Ă��Ȃ��C����ł���ꍇ�������B�o�c�҂��w�͂������ɁC�u����̓o�J�ŕ��C�Ŗ��ӔC�Ȃ悻�ҁv�ł���ƌ��������ɂȂ��Ă��܂��̂́C�܂�������Ȃ��B
�@���̋c�_�́C�t�@���h���o�c�\�͂������Ă��邩�ǂ����Ƃ͌W���Ȃ��B��Ќo�c�w�̎��Ǝ��s���̑��~���C���邢�͉ߏ�Ȃ܂ł̎��Ȗh�q�́C��ЃK�o�i���X�̌��@�̌���ł���C�\�̗͂��o�c�w�̑��₩�ȑސw�𑣂��d�g�݂���Ў��g�������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��C���낤�B
�@�o�c�҂��w�͂��Ă��āC�����ΏۂɂȂ�̂́C�����Ă݂�C�o�c�\�͂��s�����Ă��邩�炩������Ȃ��B�t�@���h������ɍ����\�͂��ǂ̂悤�ɔ�������Ǝ咣���Ă���̂��C�����X����ׂ��ł��낤�B
�i�Q�j�t�@���h�̓w��
�t�@���h�̉���̌��ʁC�ޏꂷ�邱�ƂɂȂ�o�c�ҁC���ɑn�Ǝ҂̖��O�́C��O�҂ɂ́C���肵��Ȃ����̂�����B�������Ȃ���C���{��`�̃Q�[���̃��[���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩�C�m���Ă��Ĕ��t�@���h������͔̂ڋ��ł��邵�C�����m�炸�Ɍo�c���邱�Ƃ͌o�c�Ҏ��i�ł���B�i�ׂɂ����Ắu�m��Ȃ������v���Ƃ��ؖ������Ζ��߂ł��邪�C��ƌo�c�ɂ����Ắu�m��Ȃ������v�ł͔j�]�Ɍ��т��B
�@�����Ƃ��C���s�������̏��Ȃ���Ƃ́C���̏��������ɂ��āC��������Ղ��̂��C�����ł���B�����K�̗͂D�NJ�Ƃɑ���s�K�Ȕ����ɂǂ��Ή�����ׂ����́C��ʂɓ�����ł���B�����̓_�́C�c�O�Ȃ��瑽���c�_����邱�ƂȂ��C�����h�q��̍���Ȃǂ���ƂɔF�߂���_���̂P�ɂȂ��Ă��܂��Ă���C�͎̂c�O�ł���B
�U�|�R�@�t�@���h�̂܂Ƃ�
�t�@���h��ʂ́C�ӂ��̓����ƁE�o���҂ł���Ƃ����ǖʂ������Ă���C���Ӗ��ɁC����ɋK�����Ă��C���̓����ƂɊQ���y�ڂ��C�s���j�邾���ɂȂ��Ă��܂��C���̂ł��邱
�y108
�Łz
�Ƃ��݂Ă����B
�@�������Ȃ���C���点��v�����o�c�w�ɓ˂����ĕۗL���������l�Ŕ������悤�ɗv��������C�������₷���Ƃ��������Ŕ��s�������̏��Ȃ������K�̗͂D�NJ�Ƃɔ����̑_�����߂�t�@���h�����邱�Ƃ������ł���B�ǂ̂悤�ȑg�D��ƊE�ɂ��ƍߎ҂���f�҂�����͎̂����Ȃ̂ŁC����������ăt�@���h��r������̂͑��v�ł���B
�@���̂悤�ȃt�@���h�ɑ��āC�ǂ̂悤�ɋ�ʂ��Ή�����ׂ����͈�ʂɂ͓�����ł��邪�C���������@������̂ŁC�ȉ��ɐ������悤�B
�V�@��Ƃ̂���ׂ��Ή���
����ł́C�G�ΓIM&A�����肤��Ƃ����O��œ����o�c�������Ȃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��C�Ƃ�����B����ȊO�̑�͂ǂ��ł��낤���B��Ƃ̒������I�ȗ��v������̔�r�I�Z���I�Ȉ��͂�������@�́C����������C���̊����̔��ꉻ�Ƌc�����R���g���[���̂Q�����Ȃ��B
�V�|�P�@�����̔��ꉻ
�o�c�w�Ɏc���ꂽ�I���ɂ́C�܂��C�����̔��ꂪ����B�����̃����b�g���̂ĂĖ����ɂƂǂ܂�悢�B���邢�͊����ł���Ί������ꉻ16�j
������悢�B������ɂ��Ă��C�o�c����D�悳���\���͔��ɏ��Ȃ��Ȃ�B
�@���{�ł́C2000�N�ȍ~�C�������B��ڎw���x���`���[��Ƃ�����̊ɂ��V���s��ւƗ��ꍞ�݁CIPO�i�V�K�������J�j�u�[�����N�����B�������Ȃ���C�����o�߂��C2009�N�ɂ����铌���،�������̏��p�~�����͖�80�ЂƁC2000�N�ȗ��̍������ƂȂ����B����ɂ́CM&A����݂�����B������Ƃ����x�͋t�ɁC���p�~��ڎw���g�����h���L�܂邩������Ȃ��C�Ƃ����S�z���������悤�ɂȂ����B
�@�{�߂̃g�s�b�N�X�́CM&A��MBO�ȂǂƂ��W���C���ɑ����̘_�_���܂�ł��邪�C�{�e�ł̓W�J�͈ȏ�Ɏ~�߂邱�Ƃɂ������B
�V�|�Q�@�c�����R���g���[���ƃK�o�i���X
�ǂ̊���ɂǂꂭ�炢�̋c������^���邩���C�c�����t�^���ł���C�����̓��{��Ƃɂ͂���܂Œ��ʂ��Ȃ��������ł���B
�@����\������Ȃ�C�o�c�w�͗Ⴆ�Ε��ʊ����s����߁C�D�抔���邢�͏\���̈�c�����t�^�̊����s����悢�B�܂��C�L���c���������P�P���肷��ۂɕۗL���Ԃ������t����Ɗ������s��ЂɂƂ��Čv�Z�͑�ςɂȂ邪�C�c�����s�g���ۗL����Ɍ���Ƃ������@�������L���ł���B���Ȃ݂ɁC�t�����X�ł́C�T�N�ȏ�̊��Ԋ�����ۗL���Ȃ��Ƌc�������������Ȃ��Ƃ������x���Ƃ��Ƃ�����B
�V�|�Q�|�P�@�c�����R���g���[���Ƃ��̑��̋�̓I�ȕ��@
��ފ��s����Google��Facebook�̕��@�Ƃ���ȊO�̗l�X�ȕ��@��������Ă������B
�y109 �Łz
�i�P�j10���̂P�c����
�Ⴆ�C2004�N��IPO����Google�́C�����ƂɈ��Ă����Ȃ̒��ŁC�u�V�K�����Ƃ͒����ɂ킽����Google�̌o�ϖʂ����S�ɋ��L���邱�ƂɂȂ邪�C�c������ʂ��Đ헪�I����ɉe�����y�ڂ����Ƃ́C�قƂ�ǂł��Ȃ��v�Əq�ׁC�����w����]�҂ɑ��āC���������n�Ǝ҂̈ӌ��ɒ��ӂ���悤�������B
�@�\�[�V�����E�l�b�g���[�L���O�E�T�[�r�X�iSNS�j�̕č����Facebook���C2009�N11���u�̑�Ȏ��Ƃ̊m���Ɍ����C�������������I�ɒ��͂��邱�Ƃ��\�ɂȂ�悤�C��������͓���̉ۑ�Ɋւ��ċc�����̍s�g�͂��ێ��������ӌ��ŁC���̂��߂Q��ނ̊����V�X�e��������v���Ƃ𖾂炩�ɂ����B����́C�����I�ȗ��v��Z���I�Ȉ��͂����邽�߂̎d�g�݂ł���B�Q��ނ̊����Ƃ����d�g�݂��������݂��Ȃ���C�唼�̊���́C���Ђ̑n�Ǝ҂����߂������I�Ȑ������]���ɂ��āC�Z���I�ȗ��v�̂��߂̃r�W�l�X�̌���������ɒʂ����ƂɂȂ��Ă��܂��C�Ƃ����������Ȃ���Ă���B
�@����́C2004�N�W���Ɉ���،���Ђ��o�R�����I�����C����IPO������Google���Ƃ������@�ł���B�Ȃ��CFacebook����L�ӌ���\�������ۊ������J�͍���Q�C�R�N�͂Ȃ��Ƃ̍l���������ɕ\������Ă����B���ہCFacebook����ꂵ���̂�2012�N�ŁCNadaq��IPO���������V�X�e���ɏ�Q��������n�v�j���O�t���ŁC�\�z�O�ɑ傫�����ꂽ�B
�@Google��Facebook���Ƃ����c�����R���g���[���͕č��Ȃǂ̐�i���ł͊�ȗ�ł͂Ȃ����C�K�o�i���X��肪�c�邱�Ƃ��w�E����_�҂�����B
�i�Q�j�c�����t�^�����ݒ�ɂ����@�`���ԂƑ��c����
��ɏ����G�ꂽ�悤�ɁC�Z���Ŕ������J��Ԃ����傪�唼�ɂȂ�C��ƌo�c���ނ�̔����ɑ傫�����E����鎖�Ԃ�����邽�߁C�����ɕۗL���銔�傾���ɋc������t�^������@������B
�@�t�����X�ł́C72���̊�Ƃ����炩�̈ꊔ���c�����������̗p���Ă���Ƃ��钲���iISS Europe�i2007�j17�j�j������B�t�����X�ł́C���̕t�^�̏����Ƃ��Ċ����ۗ̕L���Ԃ���߂��Ă���B�����ԁi�Q�N�j�������p���ۗL�����ꍇ�c�������Q�{�ɂȂ鑽�c�����������F�߂��Ă���C����Ə��120�Ђ̂����̖�U���̊�Ƃ��������Ă���Ƃ��������i��Ɖ��l������i2007�j�j������B
�@��̓I�ɂ݂Ă݂�C��ʓI�Ȋ��s�ł́C�S�z�������܂ꂽ��̓���̊��ԁC�ʏ�ł͂Q�N�ԁC�������喼�`�Ōp���I�ɓo�^���ꂽ�����́C�Q�{�̋c�������擾���邱�ƂɂȂ��Ă���B�Ȃ��C�������������L�������ɓ]������邩�C�������͏��n���ꂽ�ꍇ�i�����C�z��҂Ƃ̍��Y���^�C�܂��͔z��҂������͑��̎��i�̂���e���ɑ����t�Ȃǂ������j�́C�Q�{�̋c�����͎����I�Ɏ�������B
�@�c�����t�^�ɂ́C���ɁC�l�X�ȕ��@�����肦��B�Ⴆ�C�_�������B�[�i2006�j�ɂ��ƁC19���I�̕č���Ƃł́C�ꊔ��c�������������ł͂Ȃ��C�ꊔ���c�������������݂����Ƃ����B��l��[�́C�����`�ɂ������\�I�Ȍ��c�����ł���C��������Ƒ������̊Ԃ̕��������ۏ����B���ꂪ�ł������ȈӖ��Ŋ��喯���`�ł���B
�@�����ۗL���傾���ɋc������t�^������@�ɂ����_������B���̂悤�Ȍ�����ɂ���āC�t
�y110
�Łz
�ɁC�����ۗL���傾���ɂȂ��Ă��܂�����C�����̗��������Ȃ��Ȃ�C�V���ȓ����Ƃ����̉�Ђ̊������w���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�Ђ��ẮC�������ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂���������Ȃ��B
�@����䂦�C���̂悤�Ȍ�������Ƃ��Ă��C�Z�������Ŕ��p�v��_������ɈˑR�Ƃ��Ċ������w���������邱�Ƃ�F�߂���̂��C��������K�v������B
�i�R�j�c������~�ɂ����@
�t�����X��Ƃ́C�芼�ɂ���ĂQ�{�̋c�������߂��邾���łȂ��C����o�Ȃ���萔�ȏ�̊�����ۗL���銔��Ɍ��肷��C���Ƃ��F�߂��Ă���B���̌��ʁC�������傪���呍��ɏo�Ȃł��Ȃ���Ђ��t�����X�ł͑��݂��邱�ƂɂȂ�B
�@�t�ɁC���鐔�l����c�������擾���ꂽ�ꍇ�C���̒��ߕ��̋c�������s�g����̂����̊��Ԓ�~�����邱�Ƃ��ł���B���̊��Ԃɂ́C�Q�N�C�T�N���邢�͏���̏��ނ���o�����܂ŁC�ƒ�߂��Ă���18�j�B
�@�����́C�t�����X�ɂ����ẮCM&A�ɌW��锃�t�҂ɓK�p�����ꍇ�Ɍ�����B�������C���R�Ȃ���C�����h�q��Ƃ��đ��̕���ɂ��K�p�ł���\��������B
�i�S�j���c�����ɂ��R���g���[��
���c������l�X�ɐݒ肷�邱�Ƃɂ���ċc�������R���g���[�����邱�Ƃ��ł���B���Α���������ݐϓ��[���Ȃǂ��CCFA ����i2009�j�Ȃǂ̉�����Q�l�ɁC�����I�C�c�Ă��ɂ��āC�������������Ă������B������Ƃ��đI�C����邽�߂ɂ͉ߔ����̕[���l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂���ʓI�ł���B
�@�c�Ă����c����邽�߂ɂ͉ߔ����̕[���l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��鑽�������imajority voting�j����\�I�Ȍ��c���@�ł���B���̏ꍇ�ł��C�ߔ����̑�����𓊕[�����̉ߔ����C�܂��͗L���[�̉ߔ����C�Ȃǂɂ��邱�Ƃɂ���Č��c�̍s���͈قȂ��Ă���ꍇ�͑����B
�@���̈���C���Α��������iplurality voting�j�Ƃ������x�́C���Ɍ��҂����Ȃ��ꍇ�ɂ͏��Ȃ��Ƃ��P�[���l������Ύc��̋c�������^�����Ă��Ȃ��Ă������I�C�c�Ă͉�����Ƃ������c���@�ł���B�J�i�_��č��̊�ƂŖ����ɍ̗p����Ă���19�j�B
�@�ݐϓ��[�icumulative voting�j�����ł́C���傪�ۗL���Ă���e���҂ւ̕[�̂��ׂĂ��P�l�̎�������҂ɓ����邱�Ƃ��ł���B�Ⴆ�C���銔�傪100������ۗL���Ă���Ƃ��悤�B����ɁC�P���ɂP�[���^������Ƃ���ƁC����10�l�̌��҂������ꍇ�C����͊e���҂�100���[�𓊂������ɁC�P�l�̌��҂�1,000���[�𓊂��邱�Ƃ��ł��鐧�x���ݐϓ��[�����ł���B���ʂƂ��āC�������傪�������ɑ�\�҂𑗂�@������邱�ƂɂȂ�B
�i�T�j���J���v��
���䗦�̋c������L���銔��ɑ��ď��J���𐿋����錠����Ώۉ�ЂƊW��������ɕt�^������@������B����ɋ߂����x�́C�C�M���X�ōs���Ă���B
�y111 �Łz
�J��������ɁC�ۗL���@�ڊ܂߂�悢�B�����ł��Ȃ��Ă��C����𐄎@�ł������v�����邱�Ƃ��ł���C���̃v���b�V���[�ɂȂ�B
�@�������Ȃ���C���̖@�����͓���ƌ�����B�Ȃ����H�������s��ЂƂ��Ă���̓I�Ɂu�N�Ɂv�C�����ǂ���������悢�̂����킩��Ȃ��ƁC�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�̎������̊ϓ_�������肪����Ƃ̋c�_������B�܂�C��������͒����ł����킩��Ȃ����C��������̓K�ȁi���̂Ȃ��C100���������Y�������m��j�������@���s���ł���B
�V�|�Q�|�Q�@�c�����K�o�i���X
�i�P�j���啽����`�͎���Ă��錴���Ȃ̂�
�t�@���h�s���͊��喯���`�ւ̒���ł���C�Ƃ݂Ȃ���邱�Ƃ������B�����āC�����h�q�������̍ۊ�Ƃ́C���啽����`�������o���B�����h�q��͑S�Ă̊�����u�����������Ɉ����v���߂̏����ɂȂ�ƁC�_���̓W�J�⎖���̒��Ȃ��C��������B
�@�������Ȃ���C����ɑ��镽���Ȏ�舵���Ƃ������O�́C���������͏�������̎�舵���ɗR�����Ă���C�����h�q��Ƃ͊W�Ȃ����ł���B
�@���{�ł́C�O�߁i�P�j����i�S�j�łƂ肠�����[�u�́C���啽�������ɔ�����Ƃ����l��������B�������Ȃ���C���{�ł́C�����Ŗ��c�����D�抔�̑��݂�F�߂Ă���̂ŁC�����ɂ́C���̍l���͖������Ă���B���邢�́C��ފ��͍��ׂȗ�O�ł���Ƃ����������Ȃ̂��낤���B���邢�́C���啽�������ɑ���l�����͕ω����Ă����C�Ƃ����ׂ��Ȃ̂�������Ȃ��B
�@�����h�q��������Ƃ́C��s����`�ŁC���啽����`���咣���Ă���ɉ߂��Ȃ��B���{�l�͒c�̍s������X��������ƍl�����Ă���B���̂悤�ȁu������W�c��`�v�����łȂ��C�����Ȃ��W�c��`�����݂���Ƃ������������Ȃ����ꍇ������B����������ƁC���{�ł͋����̈ӎ�����p�������x��肪�Ȃ���Ă����B���̌��ʁC�����h�ɑ��Ăǂ���{�I�Ȍ�����ۏ��邩�C�����h�̊�{�I�Ȍ����Ƃ͉��Ȃ̂��C���l����w�͂����Ă��Ȃ������B���{�ł́C�����h�ɕ����Ȍ�����ۏ��邱�Ƃɓw�͂��Ă��Ȃ������C�̂ł���B
�@���匠�͕̂�ɂ���Ă��鎖��́C�ނ���C���{�ł͑����B���{�ł͊��啽����`�͌��z�Ȃ̂ł���B���啽����`�𗝗R�ɁC�l�X�ȋK��������_���͖�������Ă��Ȃ��C�Ǝv����B
�@���̗�Ƃ��āC��ɂ�������ފ����������������邪�C����ȊO�ɂ�����B���ɊO����Ƃ̏��Ɗ��匠�ی�Ɋւ�����������Ă������B�O����Ƃ���{�̎�����ɏ�ꂷ�邱�Ƃ������߂Ȃ���C���{�l����Ə��O����ƂƂ̊Ԃ̑i�ׂ�����@���͌�ł������B����Ɋւ���ċN��������莖�Ⴊ���匠�ی�ł���B
�@���{�̉�Ж@�ł́C��Ђ̒芼�ύX��g�D�ĕ҂ɔ����銔��́C��Ђɑ��Č����ȉ��i�Ŋ��������悤�����ł���B���承�i�ɕs���Ȃ�ٔ����Ɍ������i�����߂Ă��炤�悤�\�����Ă��邪�C�Ώۂ͓��{�̉�Ђ݂̂ł���B�O����Ƃɂ͓K�p����Ȃ������B�Y�����鎖��ŁC���{�@�Ɋ�Â��ē��{�̊��傪�����n�قɑi������d�g�݂�p�ӂ����̂͂���O����Ђ����ł������B
�i�Q�j�c�������̂̃K�o�i���X���K�v
�ޏꂷ��ׂ���Ƃ��C���������邽�߂ɁC�G�ΓI����������ɂ�����l�X�ɂƂ��Ă���B���̎�i�ɋc�������g���Ă����B�܂��C���セ�̎�@�͍��x�����鋰�ꂪ����B�c�����R���g���[�����s���߂���ƁC���啽�������ɔ����邾���łȂ��C��Ƃ̃K�o�i���X���������ꂪ����B��Ɖ��l������i2007�j�̒�Ă��Q�l�ɁC���̗\�h����l���Ă������B
�@�G�ΓI�����̍����h�~����ɂ��C���������@������̂ŁC���ɍl���Ă݂悤�B�T��
�y112
�Łz
�Z�b�g������u���[�N�X���[�������K�肷�邱�Ƃ��C�����h�q��𐧒肵�悤�Ƃ���i���Ă���j��Ƃɑ��āC�`���t������@���܂����݂���B�����͎��̂悤�ł���B
�@�ꊔ��c�����Ƃ��銔�呍��̓��ʌ��c���ɂ���āC�����Ԍo�ߌ�ɁC�����h�q�X�L�[���̉������\�Ƃ�����C�\�ߒ�߂����̏��������A�����ꍇ�ɔ����h�q�X�L�[�������������Ȃǂ̎d�g�݁C�܂�T���Z�b�g�����ƌĂ������C���K��ɑg�ݍ��܂���̂ł���B
�@�܂��́C�����҂���萔�̊������擾�����ꍇ���ɂ́C�����I�ɗႦ�Ύ�ފ������ʊ����ɓ]������d�g�݁C�܂�u���[�N�X���[�����ƌĂ������C���K��ɑg�ݍ��܂���C�̂ł���B
�@���c���������̉��\��h���ꍇ�ɂ́C���c���������̋c�����𑍋c�����̈�芄���i�Ⴆ�P�^�R�����j�ɐ������C���������c�ɂ��擾������t���C�Ƃ������@������B
�@�������傪�ۗL����c������ی삷�����ɑ��ẮC���x�ɉ����āC�������̕��@������B�܂��C���ΓI�ɋc�����̏��Ȃ�����ɗ^������C��Ж@322���P���ɒ�߂鋑�ی���芼�Ŕr�����邱�Ɓi���Q���j���C���������C�֎~������@���P�̋ɘ_�ł���B
�@���ꂪ�s�\�ŁC����犔��̋��ی���芼�Ŕr�����邱�ƂɂȂ�ꍇ�����낤�B���̏ꍇ�ł��C���������l�ȑΉ����@������B�����ɒ�߂�������s�����ƂŁC���Y����ɑ��Q���y�ڂ������ꂪ����Ƃ��ɁC�s���ȑ��Q���y�ڂ��Ȃ����߂̕�����̗p����̂ł���B���̕���ɂ́C��̓I�ɗႦ�C��O�҈ψ���̊��p�C�Ɨ�������O�҂ɂ��]���i�t�F�A�l�X�E�I�s�j�I���j�̎擾�C���ꂼ��̎�ނ̊���̎戵�������炩���ߒ芼�Œ�߂�C�Ȃǂ�����B�x�z���̗��p��h�~���C�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X��B������ɂ́C�ЊO����������p������@������B
�W�@�܂Ƃ�
�����`��Ƃ��҂ɑ��Č�������~�Ƃ�����������B�������̒�~�́C���{�ł͈�ʂɑI�������I�����̒�~�Ɨ�������Ă���B�֎��Y�ҁC�����ȏ�̌Y�ɏ�����ꂽ�҂��ΏۂɂȂ�20�j�B
�@�����`��Ƃ��҂Ɍ�������~������悤�ɁC�����s��̃��[����Ƃ��҂Ɋ��匠�̒�~�������Ă�����ׂ��ł���B���匠�̒�~�v�����L���c�_����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B
�@����́C�X�̊�Ƃ����R�Ɍ��߂�ׂ����C����Ƃ����ǂ�ٔ������C���O�ɒ�߂�ꂽ���[���̉��C�ŏI�I�Ɍ��肷��ׂ����B
�@�X�̊�Ƃ���߂���͈͂����g�Œ�߂邱�Ƃ��o����C���̃X�e�[�N�z�[���_�[���l�����邱�ƂȂ��C���g�ɓs���̗ǂ��悤�ɁC�s�x���߂Ă��܂��B����䂦�C������C���̔��f�͓��ǂ̔F��ɂ䂾�˂��邱�ƁC�ٔ����̎葱���o�邱�ƁC�ɂȂ炴��Ȃ��̂ł͂Ȃ����C�Ǝv���B
�@�t�@���h�́C �o�c�҂̃C���Z���e�B�u�𑝂��_������ԁB�Ⴆ�C �i�K�����istep
�y113
�Łz
investment�B�C���i2005�j�ȂǎQ�Ɓj�ȂǁC�̂悤�Ȍ_����l�X����B�t�@���h�́C����䂦�C���̓����Ƃ̎��Y�𑝂₷�C�t�����l����Ă���B�č��N���ł́C�I���^�i�e�B�u�̕��ލ��ڂɃt�@���h�ւ̓��������X�g�A�b�v����C�����̊z����������Ă���B�t�@���h��ʂ͊����s��̃��[����Ƃ��Ă͂��Ȃ��B����䂦�C�t�@���h��ʂ����匠�̒�~�̑ΏۂɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��B
�@�c�����̓R���g���[���ł���B�ނ���C�����h�q��̍s���߂��Ŋ�Ƃ̃K�o�i���X����������S�z�ł���21�j�B����͌o�ς������C���������x�点��B
�Q�l����
Brav, A. and Richmond Mathews, D., �i2011�j, �gEmpty Voting and the Efficiency of Corporate Governance,�hJournal of Financial Economics, 99, 2011, pp. 289-307.
Chen, J., Hanson, S., Hong, H. and Stein, J. C., �i2008�j, �gDo Hedge Funds Profit From Mutual-Fund Distress?�hNBER Working Paper No.w13786, February 2008.
Cole, T., Feldberg, G. and Lynch, D.,�i2007�j, �gHedge Funds, credit risk transfer and financial stability�h, FINANCIAL STABILITY REVIEW, APRIL 2007, SPECIAL ISSUE.
Dunlavy, C. A.,�i2006�j, �gSocial Conceptions of the Corporation: Insights from the History of Shareholder Voting Rights,�h Washington and Lee Law Review, Vol.63, p.1347, 2006. http://ssrn.com/abstract=964377, p.1355.
Eales, B. A. and Tunaru, R.,�i2004�j, Financial Engineering with Reverse Cliquet Options, 2004�icass. city. ac. uk/conferences/mmf2004/files/Tunaru&Eales. pdf�j
Heston, S.,�i1993�j, �gClosed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility, with Application to Bond and Currency Options,�h Review of Financial Studies, 6�i2�j, pp.327-343.
Heston, S. L. and Nandi, S.,�i1997�j, A Closed-Form GARCH Option Pricing Model�iNovember 1997�j. 97-9. �iAvailable at SSRN: http://ssrn.com/abstract=96651 or doi:10.2139/ssrn.96651�j
Hu, H. T. C. and Black, B.,�i2006�j�gThe New Vote Buying: Empty Voting and Hidden�iMorphable�jOwnership,�h Southern California Law Review, 79, 2006, pp.811-908.
Hu, H. T. C. and Black, B.,�i2007�j�gHedge Funds, Insiders, and the Decoupling of Economic and Voting Ownership: Empty Voting and Hidden�iMorphable�jOwnership,�h Journal of Corporate Finance, 13, 2007, pp.343-367.
ISS Europe,�i2007�j, ECGI, Shearman & Sterling, supra note 24, at 24, 25.
Kandani A. E. and Lo, A. W.,�i2007�j, �gWhat Happened To The Quants In August 2007?�h Journal of Investment Management, Volume 5, Number 4, Fourth Quarter 2007.
Kaplan, S. N. Martel, F. and Strömberg, P.,�i2007�j, �gHow do Legal Differences and Experience Affect Financial Contracts?�h Journal of Financial Intermediation, 2007, 16�i3�j, pp.273-311.
Kaplan, S. N. and Strömberg, P.,�i2001�j, �gVenture Capitalists as Principals: Contracting, Screening, and Monitoring,�h American Economic Review, 2001, 91�i2�j, pp.426.
�y114 �Łz
Kaplan, S. N. and Strömberg, P.,�i2003�j, �gFinancial Contracting Theory Meets the Real World: An Empirical Analysis of Venture Capital Contracts,�h Review of Economic Studies, 2003, 70�i2�j, pp.281-315.
Kaplan, S. N. and Strömberg, P.,�i2004�j, �gCharacteristics, Contracts, and Actions: Evidence from Venture Capitalist Analyses,�h Journal of Finance, 2004, 59�i5�j, pp.2177.
Kaplan, S. N. and Strömberg, P.,�i2008�j, Leveraged Buyouts and Private Equity; NBER Working Paper Series No.14207, National Bureau of Economic Research, 2008.
Kat, H. M.,�i2001�j, Structured Equity Derivatives: The Definitive Guide to Exotic Options and Structured Notes, Wiley Finance Series, 2001.
Kyprianou, A., Schoutens, W. and Wilmott, P.,�i2005�j, Exotic Option Pricing and Advanced Lvy Models, John Wily, 2005.
Lerner, J., and Wulf, J.�i2007�j. �gInnovation and Incentives: Evidence from Corporate R&D�h, Review of Economics and Statistics 89, pp.634-644.
Lerner, J., Sorensen, M. & Stromberg, P.,�i2011�j. �gPrivate Equity and Long-Run Investment: The Case of Innovation,�h Journal of Finance, vol.66�i2�j, pp.445-477.
Mackinsey �� Co.,�i2007�j, The New Power Brokers: How Oil, Asia, Hedge Funds, and Private Equity Are Shaping Global Capital Markets, October 2007.
OECD,�i2007�j, THE IMPLICATIONS OF ALTERNATIVE INVESTMENT VEHICLES FOR CORPORATE GOVERNANCE, July 2007.
http://www.oecd.org/corporate/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/39007051.pdf
Overhaus, M., Bermudez, A., Buehler, H., Ferraris, A., Jordinson, C., and Lamnouar, A.,�i2007�j, Equity Hybrid Derivatives, Wiley Finance Series, 2007.
Papademos, L. D.,�i2007�j, �gMonitoring Hedge Funds: a financial stability perspective�h, FINANCIAL STABILITY REVIEW, APRIL 2007, SPECIAL ISSUE.
Petrelli, A., Zhang, J., Siu, O., Chatterjee, R. and Kapoor, V.,�i2008�j, Optimal Dynamic Hedging of Cliquets, May 2008.
�M�ꕶ��
���c�@�B�i2007�j �uM&A�s��̊h���v���ƂȂ��Ă��� CFD�v Financial Information Technology Forum�i�쑺�����������j�C2007�N�X���Cpp.10-11�B
��J���L�i2007�j �u�G�N�C�e�B�E�X���b�v�C�݊������p���� �c�����̎擾�Ǝ����̉B���v �w���{�s��N�E�H�^�[�x Summer, 2007. www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2007/2007sum17.pdf
��c�@�m�i2008�j �u�w�b�W�t�@���h�E�A�N�e�C�r�Y���̐V�����i���j�v �w�����@��No.1842�x 2008�N�X���T���B
��Ɖ��l������i2007�j �u����Ђɂ���ފ��̔��s�Ɋւ���i�āj�v ����19�N12���Bwww.meti.go.jp/committee/materials/.../g71212f03j.pdf
�o�ώY�ƏȌo�ώY�Ɛ���ǎY�Ǝ����ہi2011�j �w�䂪���o�ς̊�������S���t�@���h�̗L�����p�Ɍ��������Ɗ������Ɍ�������b�����i���j�x �����ϑ���i���j��a�����C2011�N�R���B
�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�Ɋւ���@����茤����i2012�j �u���嗘�v�̊ϓ_����̖@�K���̘g�g�݂̍����I�Ӌ`�v �w���Z�����x ���{��s���Z�������C2012�N�P���B
CFA ����i2009�j �u���E�ɂ����銔�匠�̌���v, CFA Institute, 2009�B���{��Ŗ|��F2010�N�T���B �y115 �Łz www. cfasociety. org/japan/publications/SORM-JP. pdf
�����_�i2008�j �u�w�b�W�t�@���h�E�A�N�e�C�r�Y���̐V�����i��j�v �w�����@��No.1840�x 2008�N�W���T���B
�����_�C���R�����Y�C�����j�i2009�j �u�w�b�W�E�t�@���h�Ɖ�Ж@���w�b�W�E�t�@���h�̓����헪�� M&A�ɂ�����c�����s�g���Ʉ��v �_��T�V�ӔC�ҏW�C���c�@�l�E���{�s�ꌤ����Ғ� �w�t�@���h�@�����t�@���h���߂��錻��ƋK����̏����x ��13�́C2009�N�C���o�ڕ�ЁB
�C������i2005�j �w�X�g���N�`���[�h�E�|�[�g�t�H���I�E�}�l�W�����g����x �L��t�C2005�N�B
�C������i2007�j �uIPO�O�ɂ�����VC��BO�Ȃǃt�@���h�̍s���F���Ă̌����v �w�w�K�@��w�o�Ϙ_�W�x�C2007�N�V���CVol.44, No.�Q�Cpp.161-180�B
�C������i2009a�j �u���Z�����ɂ�������Ƌ��Z����Ɓ`�W�]�Ƙ_�]�v �w�w�K�@��w�o�Ϙ_�W�x�C2009�N�P���Cpp.303-324�B
�C������i2010a�j�uCFD ����Ɣ���`���n�́v �w�w�K�@��w�o�Ϙ_�W�x�C2010�N�P���Cpp.83-107�B
�C������i2010b�j �uCFD ����Ƃ��̊��p�헪�v �w�w�K�@��w�o�Ϙ_�W�x2010�N10���Cpp.219-239�B
�C������i2011�j �uIPO �ɂ�������ƌ��J���i��������`�u�b�N�E�r���f�B���O�����͂Ȃ��D���Ȍ��J���i��������Ȃ̂��v �w�w�K�@��w�o�Ϙ_�W�x�C2011�N�S���Cpp.23-44�B
�C������i2013�j�u�t�@���h�̍s���C�o�ό��ʂƂ��̌��߁i�h�j�`�t�@���h�͂ǂ��s������̂��`�v�w�w�K�@��w�o�Ϙ_�W�x�C2013�N10���Cpp.57-82�B
�������l�E���c�ׁE�����G�q�i2006�j �u�w�b�W�t�@���h�̓����s���ω��Ƌ��Z�s��ւ̉e���`�|�W�V�����̏W������ѓ����Ώۊg��Ǝs�ꗬ�������X�N�`�v �w����r���[�x 2006�N11��30���B
�n�ӍG�V�i2009�j �w �G�N�C�e�B�E�f���o�e�B�u��p�����u�B�ꂽ�����v�̖�� �`���B�ɂ����铮���𒆐S�Ƃ��ā` �x 2009�N�V��22���B
http://www.fsa.go.jp/frtc/kenkyu/20090722/10.pdf#search=�f%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E3%83%98%E3%83%83%E3%82%B8%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89+%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E3%81%AE%E9%89%84%E9%81%93%E4%BC%9A%E7%A4%BE+%E9%9A%A0%E3%82%8C%E3%81%9F%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BF%9D%E6%9C%89%EF%BC%88hidden+ownership%EF%BC%89�f
�y116 �Łz
�t�^�@�w�b�W�C�I�v�V�����Ɠ��I�I�v�V�����헪
�`�|�P�@�w�b�W��I�v�V�����̊�{�T�O���K
�i�P�j�w�b�W�T�O�`���S�w�b�Wvs �s���S�w�b�W
���̋]�������킸�Ƀw�b�W�o����킯�ł͂Ȃ��B�w�b�W����C�������]���ɂ��Ă���B���̋]�����w�b�W�E�R�X�g�ƌĂԁB
�@���S�w�b�W�́C���v�̋@��܂łȂ����Ă��܂��C�w�b�W�ł���B�s���S�w�b�W�́C���v�@����c���w�b�W�ł���B����䂦�C���S�i�s���S�j�w�b�W�͍��i��j�R�X�g�ł���B
�@��ʂɁC�ꌾ�Ńw�b�W�Ƃ����Ă��C�l�X�ȃ��x�������݂��邱�ƂɂȂ�B
�i�Q�j�v���~�A����s�g���i
�v���~�A���Ƃ̓I�v�V�����̉��i�ł��邽�߁C�v���~�A���̍�������߂�̂́C�I�v�V�����̎����ł���B�܂��C��������߂�̂̓A�E�g�E�I�u�E�U�E�}�l�[�܂茴���Y���i�����Ɠ��Y�I�v�V�����̓����Ƃ̊W�ł���B�{�e�Ƃ̊֘A�ł́C�{���e�B���e�B�������Ȃ�C�v���~�A���͍����Ȃ�C�_�ɒ��ڂ��Ă��������B
�@�s�g���i�́C�����Y���i�̐��ڂɍ��킹�āC�ύX�����i�X��������j�B�������Ȃ���C�����헪�ɍ��킹���s���̂悢�s�g���i�̃I�v�V�����͔����ł��Ȃ��ƍl���Ă����ׂ��ł���̂����ʂł���B���ꂪ�����o����C�D�^�Ȃ̂ł���ƍl����ׂ��ł���B
�i�R�j���̑�
���i�̉������Ƃ��čs���Ă���̂�Kat�i2001�j�ł���B�I�v�V�����C�X���b�v�C�Ȃǂƃ|�[�g�t�H���I�헪�Ƃ̊W�́C�C���i2005�j���Q�ƁBCFD �ƃ|�[�g�t�H���I�헪�Ƃ̊W�́C�C���i2010�j���Q�ƁB
�@�Ȃ��C�A�t�B���E���f���C�A�t�B���E�W�����v�ߒ����邢�̓��r�[�ߒ��i�Ⴆ�C�ŋ߂̒����ł�Kyprianou-Schoutens-Wilmott�i2005�j�Q�Ɓj�̕��͖͂{�t�^�ł͓W�]���Ȃ��B�{�e�ɂ��Ă̓W�����v�ߒ��ɂ��Ă͕K�������̌n�I�ł͂Ȃ��B
�`�|�Q�@���I�I�v�V�����헪
�I�v�V�����P�̂ł͓���Ȃ����C�����g�ݍ��킹��C���s�ƊǗ�������Ȃ�B�g�ݍ��킹�����Ԏ����ōs����ƁC�I�v�V�����헪�͈�ʂɂ���ɓ���Ȃ�B�ȉ��ł́C���Ԏ����œW�J�����I�v�V�����헪�̊�{�A�C�f�A��W�]���Ă݂悤�B
�`�|�Q�|�P�@�g���̎��ԕ��z�ɂ��I�v�V�����헪�̕���
�����̃I�v�V������g�ݍ��킹��I�v�V�����헪�͊��q�̂悤�ɕ��G�ł���B�����̐헪�̕��ނ����Ԏ����ōs���Ă����C���͂���ꍇ�ɖ𗧂B
�i�P�j�����g��
�����g���Ƃ͓����ɂQ�ȏ�̃I�v�V���������āC�������̏��i����邱�Ƃł���B��ɂ͍�������C�ȂǑ�������B��������́C�Ⴆ�R�[������ƃv�b�g�������ɂ���B���I�v�V�����̍s�g���i�ƃv���~�A���������ł���Ζ��ĂɌ����̔���������ł���B
�i�Q�j�َ��_�g��
�َ��_�g���ɂ́C�Q�l������B�����C�O�����ď����َ̈��_�Ԃ̃I�v�V������g�ݍ��킹��C�̂��P�ڂ̕��@�ł���B����ɂ̓��X�N������C����B�������C�������g��
�y117
�Łz
���킹��ƃ{���e�B���e�B�͋ɂ߂č����Ȃ�ꍇ������B
�@�Ȃ��C�������قȂ�I�v�V������g�ݍ��킹��J�����_�[�E�X�v���b�h�����C�O�ɍs�������ނƂ̊Ԃ̒��ԂɈʒu���Ă���B
�@�����ɑ��āC���Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɕ����̃I�v�V�������i�o���I�Ɂj�g�����Ă����̂��C���̕��@�ł���B�萔�͂����邪�C�헪�Ƃ��Č����I�ŁC���܂�����Η��v�ށC���Ƃ��{�e�{���̈ȏ�̐���������킩�낤�B
�i�R�j�����t���g��
���Ԏ����œW�J����I�v�V�������_��헪�͔��W���C�ŋ߂́C�����t���I�v�V��������������C�v���C�V���O���Ȃ����悤�ɂȂ����B
�@�����t���I�v�V�����C�܂艽�炩�̏��������������ƃI�v�V�������L���ɂȂ����薳���ɂȂ����肷��I�v�V�����C�����̑�\�ł���m�b�N�C���E�I�v�V������m�b�N�A�E�g�E�I�v�V�����C��g�ݍ��ރw�b�W���@������B��������p�������i�Ƃ��ẮC���{�ł́CKI�ȂǂŖ��O���m���Ă���BKI�Ƃ̓m�b�N�C���̂��Ƃł���B
�`�|�Q�|�Q�@���I�ȃI�v�V�������_�Ɛ헪
�i�P�j�J�����_�[�E�X�v���b�h
�Â�����m���e�L�X�g�u�b�N�ɍڂ��Ă���C�I�v�V�����̎��Ԑ헪�́C�J�����_�[�E�X�v���b�h�icalendar spread�j�ł��邪�C�傫�ȃ��X�N�����邱�Ƃ��悭�m���Ă���B
�@�J�����_�[�E�X�v���b�h�͂��錴���Y�ɑ�����߂̃I�v�V������C����̃I�v�V�������I�v�V�����헪�ł���B���������߂��I�v�V�����́C�������������I�v�V���������C�^�C���E�f�B�P�C�ɂ���Ă�葁���v���~�A�����҂���Ƃ������ۂ𗘗p�����헪�ł���B���ɁC���߂̃C���v���C�h�E�{���e�B���e�B������̃C���v���C�h�E�{���e�B���e�B���������ꍇ�C���v�ɂȂ�\���������B
�@�傫�ȃ��X�N�����܂�闝�R�́C���Ԃ̌o�߂Ɍ�����悤�ȃy�C�I�t�ɂȂ��Ă��邩��ł���B����䂦�C�ǂ������|�[�g�t�H���I�ɑg�ݍ��ނׂ����C�\����������ׂ��ł���B
�i�Q�j��X�^�[�g�E�I�v�V����
��X�^�[�g�E�I�v�V�����iforward start options ���邢�� forward-started options�j�́C�����̂��鎞�_t1�ɃI�v�V�������X�^�[�g����B���̌����i�����j���_��t2�Ƃ���C�I�v�V�������Ԃ́it2�|t1�j�ƂȂ�B
�@�����Y�������ł����X�^�[�g�E�R�[���E�I�v�V�����̃y�C�I�t�́C������S�it�j�ŕ\���C�����s�g���i�t�@�N�^�[�Ƃ��āC
Max�o0, S�it2�j�|S�it1�jk�p�C���邢�́iS�it2�j�|S�it1�jk�j+�C
�ŕ\�����B�i�E�j+ �́i�E�j�̃v���X�l�i�}�C�i�X�Ȃ�[���j��\���B����́C���ڕϓ��ivariable notional�j�^��X�^�[�g�E�R�[���E�I�v�V�����̃y�C�I�t�ł���B���ڌŒ�ifixed notional�j�^��X�^�[�g�E�R�[���E�I�v�V�����̃y�C�I�t�́C
Max�o0, S�it2�j/S�it1�j�|k�p�C���邢�́iS�it2�j/S�it1�j�|k�j+�C
�ƂȂ�B��X�^�[�g�E�v�b�g�E�I�v�V������Max��Min�ɑウ��Ȃǂ���Γ��l�ɒ�`�����B
�y118 �Łz
�]�����@�Ƃ��āC�����Ƃ��ȒP�Ȃ̂́C�������_t1�ȍ~�͕��ʂ̃I�v�V�����Ȃ̂ŁC�����BS���f����K�p���C���̌㌻���_�̕]���Ɉ����߂����@�ł���B�����Y���i������I�ɐ��ڂ��Ă���ꍇ�C�܂��C�������i�܂�����j�̗\�����e�Ղł���ꍇ�C���Ȃ��B�����Y���i�{���e�B���e�B������I�łȂ��ꍇ�C��q��CEV���f���Ɋ�Â����Ƃ������B
�@�w�b�W���O�Ɋւ��ẮC��X�^�[�g�E�I�v�V�����̃f���^�C�K���}�C�Z�[�^�ƃx�K�́C�I�v�V�������X�^�[�g����O�́C���R�C�[���ł���B���̎����́C���R�Ȃ���C�w�b�W���O�Ɋ��p�����B
�i�R�j�m�b�N�C���E�I�v�V������m�b�N�A�E�g�E�I�v�V����
�m�b�N�C���E�I�v�V������m�b�N�A�E�g�E�I�v�V�����͉��炩�̏��������������ƃI�v�V�������L���ɂȂ����薳���ɂȂ����肷��B
�@���̂����C�����N�^�m�b�N�C���E�R�[���E�I�v�V�����́C��߂�ꂽ���ۂ�������I�v�V�������L���ɂȂ�C�I�v�V�������ԏI����T�Ɋ��������̕ω��{��S�iT�j/S�i0�j�ɉ��������z���x������B���ۂ������Ȃ���Έ��̊z�ʂ��x����i���҂��j���B�z�ʂ��o�Ƃ��C�Y�����ۂƂ��Ċ���S�it�j���I�v�V�������Ԃɂ����Ĉ�x�ł�C�ȉ��ɂȂ�ꍇ���l���Ă݂悤�B�y�C�I�t�́C
P�E1�oS�it�j>C�p�{Max�oP, P�ES�iT�j/S�i0�j�p�E1�oS�it�j�� C�p�C
�ƂȂ�B1�o�E�p�́C�oS�it�j>C�p��oS�it�j�� C�p�Ȃǂ̏����o�E�p����������ꍇ�P�C�����łȂ��ꍇ�O��\�����w�L���C���f�b�N�X�ł���B�m�b�N�C���E�v�b�g�E�I�v�V������Max��Min�ɑウ��Ȃǂ���Γ��l�ɒ�`�����B
�@�v���C�V���O�ɂ́C�m�b�N�C���܂�oS�it�j�� C�p�ƂȂ�m���ƃI�v�V�����̃y�C�I�t��������C�܂�oS�iT�j/S�i0�j>1�p�ƂȂ�m���̂Q���W���B���̂��߁C�����Q�̎��ۂ̓������x���z�������߂�K�v������B�ȒP�ȃP�[�X�ɂ��ẮC���ɉ�͉������o����Ă���B
�@�m�b�N�C���E�I�v�V������m�b�N�A�E�g�E�I�v�V������}�ɐ��m�ɂ��K�ɕ\���ɂ́C������}�����鍢�����C��ʂɂ͓���B�{�t�^�̈ȉ��Ő}�\��`���ꍇ�́C�_���ł��̃y�C�I�t�������������Ƃɂ��悤�B
�`�|�R�@�Ή������̓I�ȏ��i�ł̕���
�`�|�R�|�P�@�N���P�b�g�̎���
�i�P�j�N���P�b�g�Ƃ�
�N���P�b�g�icliquets�j�́C�ŏ��Ƀt�����X�œ������ꂽ�ƌ����C�y�C�I�t�ipayoff�j�������YS�iti�j�̏����̃p�t�H�[�}���X�iS�iti�j/S�iti-1�j�|1�j�Ɉˑ�����{���e�B���e�B���i�ivolatility products�j�̂P�ł���B���`�F�b�g�E�I�v�V�����Ƃ�������B��̓I�ɂ́C�s�g���i����
���̃I�v�V�������Ԓ�����I�Ƀ��Z�b�g�ireset�j�\�ȁC�I�v�V�����ł���B
�@�I�v�V�������Ԃ�n�ɕ����C���Z�b�g�����K���������Ԋu�ł͂Ȃ��C0�� t0 �� t1 �� �c �� tn��T�Ƃ���ƁC�Ⴆ�t���A��2.5%�C�L���b�v���T% �̃N���P�b�g�̃y�C�I�t�́C
�i��i=1 2.5%�ɁiS�iti�j/S�iti-1�j�|1�j�� 5%�j+�C
�ƕ\�����B����n�܂ő��a����B�����ŁC�L���́Cx��y��Max�ox, y�p�Cx��y��Min�ox, y�p�ł���B���̃y�C�I�t�͒P���^�ƌĂ��B
�y119 �Łz
�N���P�b�g�ɂ́C�Q�Ǝ��Y�̉��i�����O�ɒ�߂�ꂽ�z�ʂ̈�芄����艺����Γs�x�C�z�����x������^�C�v�C�Ȃǂ�����B
�i�Q�j�N���P�b�g�̃v���C�V���O�ƃw�b�W���O
�N���P�b�g���C�����̃��Z�b�g�����Ɍʂ̐�X�^�[�g�E�I�v�V�������n�܂�ATM��X�^�[�g�E�I�v�V�����̃|�[�g�t�H���I�Ƒ����āC�]��������@������BATM�Ƃ�At The Money�̗��ł���B���̔��z�͗��t���[���N�[�|���̃|�[�g�t�H���I�Ƒ�������@�Ǝ��Ă���B�����C�����i�]�����f�������p����N���P�b�g�]�����@������B
�@�N���P�b�g��ATM��X�^�[�g�E�I�v�V�����̃|�[�g�t�H���I�Ƒ�����ƁC�N���P�b�g�̃f���^�C�K���}�C�Z�[�^�ƃx�K�́C��X�^�[�g�E�I�v�V�����̂����̑��a�ɂȂ�B���̓_���w�b�W���O�ɖ𗧂������ł���B�������Ȃ���C�f���^�C�K���}�C�Z�[�^�ƃx�K�́C�N���P�b�g�̃��Z�b�g���O��ɍs�g���i���ς����C�s�A���ł���̂ŁC�s�s����������B���̂��߁C�v���C�V���O��w�b�W���O�̕��͂͌�q��CEV���f���Ɋ�Â����Ƃ������BCEV���f���̉��C��X�^�[�g�E�I�v�V������N���P�b�g�̃v���C�V���O��w�b�W���O�́CEales-Tunaru�i2004�j�ł��W�J����_�����Ă���B
�@�N���P�b�g�̉���ƃv���C�V���O��O-B-B-F-J-L�i2007�j�Ȃǂ��Q�Ƃ̂��ƁB�v���C�V���O�̂��߂ɎQ�Ƃ��郂�f���͎s��ł͂܂��m�肵�Ă��Ȃ������iO-B-B-F-J-L�i2007�j, p.50�̎咣�j�Ȃ��ŁCO-B-B-F-J-L�i2007�j�͂P�̃v���C�V���O�E���f�������B�N���P�b�g�̃w�b�W���O��P-Z-S-C-K�i2008�j�Ȃǂ��Q�Ƃ̂��ƁB
�`�|�R�|�Q�@�m�b�N�C���E�I�v�V�����̎���
�i�P�jKI��
KI�́C�����܂łɁC����������i����x�ł���������ꍇ�i���̂��Ƃ��u�m�b�N�C������v�ƒ�`�����j�́C�����̏I�l�ɉ����Ĉ��̌v�Z���ɂ���ď��Ҋz�����肳���B��x�������Ȃ������ꍇ�ɂ́C�z��100���ŏ��҂����B���ԓ��Ƀm�b�N�C������ƁC����Ό��{���l�����肵�������t�@���h�ɂȂ�C�����ƂɂƂ��đ������o�Ă��܂��B
�@��ʂ�KI�͍������ɂȂ邪�C���̂��炭��̓f���o�e�B�u��g�ݍ��킹�Ă��邩��ŁCKI�w���҂́C�������̃m�b�N�C���E�v�b�g�E�I�v�V�������āC���̃v���~�A���i�I�v�V�������i�j�ŗ��������d�g�݂ɂȂ��Ă���B���̎����́C�ڍׂ͏Ȃ����CKI�̃y�C�I�t������킩��B
�@���Ȃ݂ɁC�m�b�N�C���E�v�b�g�E�I�v�V�����̃v���~�A���́C�m�b�N�C���Ƃ��������t���Ȃ̂ŁC�����̂Ȃ������I�v�V�������Ⴍ�Ȃ�B�����R�[���E�I�v�V�����̃v���~�A���͏����̂Ȃ������I�v�V������荂���Ȃ�B
�i�Q�j�t�@���h���m�b�N�C���E�v�b�g�E�I�v�V�����𗘗p�����
�t�@���h���C�m�b�N�C���E�v�b�g�E�I�v�V�������Ƃ���ƁC�D�܂������ʂ������炷�̂ł͂Ȃ����B�����CVC �t�@���h�̃��`�F�b�g�_��́C���q�̂悤�ɁC�m�b�N�C���E�I�v�V�������Ă��邱�Ƃɑ������Ă���B
�@����ł́C�t�@���h�͍s�g���i���ǂ��ݒ肷��ׂ����낤���B�s�g���i���i���ρj�����w�����i�i���邢�͔��s���剿�i�j�ł���C�m�b�N�C���E�v�b�g�E�I�v�V�������K�ł��낤�B��������C�ʍe�ŏڂ����������邱�Ƃɂ������B
�`�|�R�|�R�@CEV ���f��
���̂Q�����琬��CEV�iconstant elasticity of volatility�j���f���́C��ʂ̊u���E���ߒ� �y120 �Łz dS�it�j= ��S�it�jdt +��S�it�jdZ�it�j�ɂ�����g�U������ʉ�����CdS�it�j=��S�it�jdt +��S�it�j��dZ�it�j�Ȃǂƕ\�킳��邾���łȂ��C�{���e�B���e�B�����ԂɈˑ�����ϐ�v�it�j�ɂȂ�B����䂦�C�m���{���e�B���e�B�istochastic volatility�j���f���C���邢��SV ���f���Ƃ�������B
dS�it�j = ��S�it�jdt + v�it�j��S�it�jdZ�it�j,
dv�it�j = �ȁi���|v�it�j�jdt +��v�it�j��d��,
�����ŁC���̓h���t�g�E�p�����^�[�C���C�������͂��̑��̃p�����^�[�ł���BZ�it�j�����̓u���E���^���������C�����̑��ւ͈��Ccorr �idZ�it�j, d���j= ���C�Ɖ��肳���B
�@�����̎��ɂ����āC����0.5�Ƃ���ƁCHeston�i1993�j��SQR�i�Q�捪�j���f���ɂȂ�B���͂͂���SQR-CEV ���f���Ɋ�Â����Ƃ������B����ɁC�܂��C����SQR-CEV ���f���͉�͉������o����Ă���CGARCH ���f�����܂݁C�v�����\�ɂȂ�i�������Heston-Nandi�i1997�j���Q�Ɓj�B
�@�v���C�V���O��w�b�W���O�ɍۂ��Ė��ɂȂ�̂̓X�}�C���ismile�j�ł���B�{���e�B���e�B��X�}�C���Ƃ́C�����C�ב֓��̃I�v�V�����s��Ŋϑ������I�v�V�������i����BS ���f����p���Čv�Z�����{���e�B���e�B�i�C���v���C�h��{���e�B���e�B�j�ƍs�g���i�Ƃ̊Ԃɂ݂���W�ł���C�s�g���i�̗��[�Ŋώ@�����{���e�B���e�B���㏸���錻�ۂł���BCEV���f���͂��̃X�}�C��������ł���B
�@���Ȃ݂ɁC������W�����v�g�U���f���ł́C��ꎮ�ɂ�������S�it�jdN�it�j�̍����E�ӂɑ����B�����ŁCN�it�j�́C����intensity��a finite activity counting process���C���̓W�����v�E�T�C�Y���C�\���B����䂦�C�̌n�͎��̂悤�ɂȂ�B
dS�it�j =��S�it�jdt+v�it�j��S�it�jdZ�it�j+��S�it�jdN�it�j,
dv�it�j =���i���|v�it�j�jdt+��v�it�j��d���B
�`�|�S�@�m�b�N�C���E�I�v�V�����̊��p��
�m�b�N�C���E�I�v�V���������p�����Ƃ��āC�R�[���E�I�v�V�����̔�����w�b�W����C���Ƃ��l������B���̍ۂ̖��_���l���Ă݂悤�B�v�b�g�E�I�v�V��������̉������X�N���m�b�N�C���E�v�b�g�E�I�v�V�����̔����Ńw�b�W����ꍇ���C�K�ȕύX��������C���l�ł���B
�i�P�j�R�[���E�I�v�V����������w�b�W
������Ȃ��̉������X�N�̂���R�[���E�I�v�V�����̔����@���Ƀw�b�W����ׂ����B���̃R�[���E�I�v�V�����̔���肪��������傫�ȃ��X�N��������邽�߂ɂ́C���O�ɂ́C
�@�@ITM�iin the money�j�̃R�[���E�I�v�V������悤�ɂ���C����I�ɂ́C
�A�@�R�[���E�I�v�V�������C������unwind����C���邢�́C
�B�@�����̒l�オ�肪�i�ޑO�ɃI�v�V����������ւ̈��n���p�Ɍ������w������C
�Ȃǂ̕��@������B1989�N�̓��{�̊����o�u���ɂ����ẮC���ہC�B�̂��߂̌����������i�݁C�����������������邱�Ƃɍv���������Ƃ��m���Ă���B�A������ɐi�߂��`�ł���C����
�C�@�m�b�N�C���E�R�[���E�I�v�V���������p����C
���C��S�̕��@�ł���C�ȉ��œW�J���悤�B
�@�m�b�N�C���E�R�[���E�I�v�V�����Ƃ��ẮC�I�v�V�������Ԃ̖����܂łɁC�������m�b�N�C������Ɓi��������C�m�b�N�C�����������������j�C���ʂ̃I�v�V�����ɂȂ�C�Ɖ��肵�悤�B�m�b�N�C����������������Ȃ���C���̃I�v�V�����͏��ł��C�v���~�A���̎x���������ŏI���B
�y121 �Łz
�m�b�N�C�������Ƃ��ẮC�������m�b�N�C���i��j���i����x�ł��������ꍇ�Ƃ���B�m�b�N�C���i��j���i�̐����́C�����������߂��ɋc�_��i�߂Ă����C�Ō�ɍl���Ă݂悤�B
�@�}�ł́C�m�b�N�C���E�I�v�V�����̑��v��_���ŕ\�����Ƃɂ��悤�B��}�ꂷ�邽�߂ɁC�m�b�N�C���E�R�[���E�I�v�V�����̃v���~�A���̏�����R�[���E�I�v�V�����̃v���~�A���Ƃ���B
�i�Q�j�m�b�N�C���E�R�[���E�I�v�V�����̐�����
�m�b�N�C���E�I�v�V���������p���Đ������邩�ǂ����́C�܂��C�s�g���i�ɂ��B
�m�b�N�C���E�R�[���E�I�v�V�����̍s�g���i �� �R�[���E�I�v�V�����̍s�g���i�C
�̏ꍇ�C�}�\�`�P�Ɍ�����悤�ɑ�ύD�܂����������v���l����B
�@�Ⴂ�v���~�A���Ńm�b�N�C���E�R�[���E�I�v�V������������Ƃ����O��Ő}�\A�P�͕`����Ă��邪�C�v���~�A�������������Ȃ��Ă��X���͓����ł���B�������Ȃ���C�v���~�A�����ɒ[�ɍ����Ȃ�ƁC�������v�̓}�C�i�X�ɂȂ�ꍇ��������B
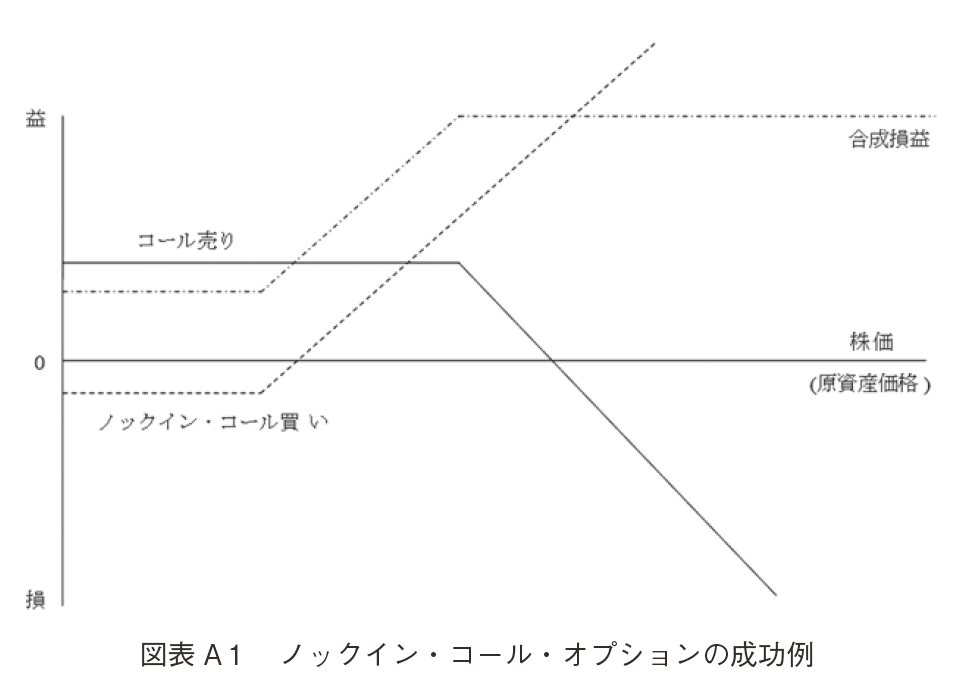
�i�R�j�m�b�N�C���E�R�[���E�I�v�V�������m�胊�^�[���������炷�P�[�X
���ɁC
�m�b�N�C���E�R�[���E�I�v�V�����̍s�g���i���R�[���E�I�v�V�����̍s�g���i�C
�Ƃ�������ȏꍇ�C�}�\A�Q�̂悤�ɁC�������v�͂��郌�x���Ŋm�肷��B�v���~�A���́C�����̃R�[���E�I�v�V��������̂�����͒Ⴂ�Ɨ\�z�ł��邪�ǂ�ʂ̃v���~�A���Ńm�b�N�C���E�R�[���E�I�v�V�������������m�胊�^�[���̍��������߁C���̐헪�����������s������B�m�b�N�C���E�R�[���E�I�v�V�����̃v���~�A�����ɒ[�ɍ����Ȃ�ƁC�������v�̓}�C�i�X�ɂȂ��Ă��܂��B
�y122 �Łz
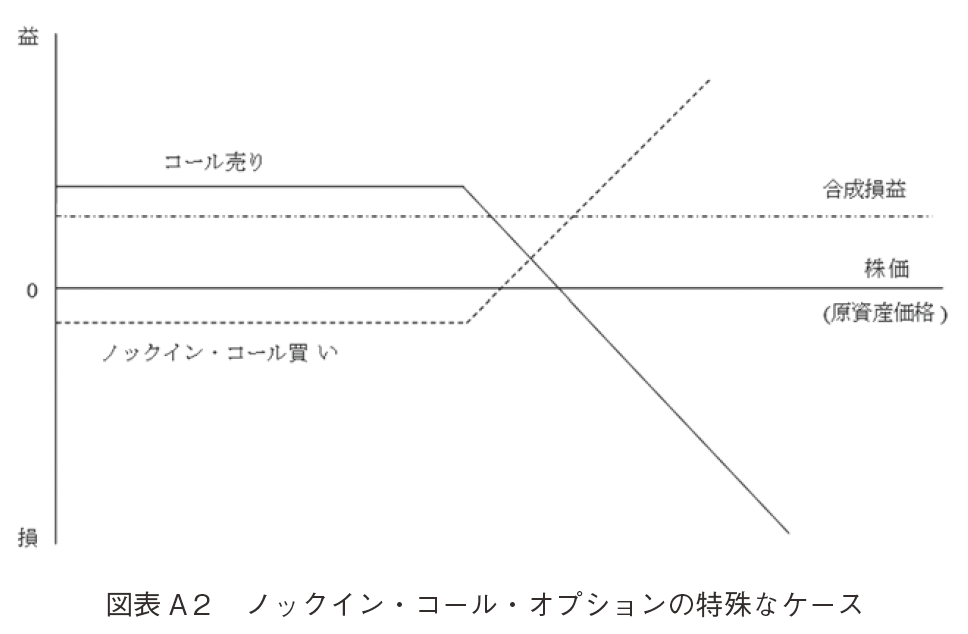
�i�S�j�m�b�N�C���E�R�[���E�I�v�V�����̎��s��
�����R�[���E�I�v�V�������肪OTM�ɂȂ��Ă���w�b�W���s�����Ƃɑ�������C
�m�b�N�C���E�R�[���E�I�v�V�����̍s�g���i �� �R�[���E�I�v�V�����̍s�g���i�C
�̏ꍇ�}�\A�R�̂悤�ɍ������v�͉E������ɂȂ�C�m�b�N�C���E�R�[���E�I�v�V�����ɂ��w�b�W�헪�͎��s�ł���B
�@�Ⴂ�v���~�A���Ńm�b�N�C���E�R�[���E�I�v�V������������Ƃ����O��Ő}�\A�R�͕`����Ă��邪�C�v���~�A�����Ⴍ�Ȃ��Ă��������v�̌X���͓����ł���B���̂悤�ȃm�b�N�C���E�R�[�������͍s���ׂ��ł͂Ȃ����ƂɂȂ�B
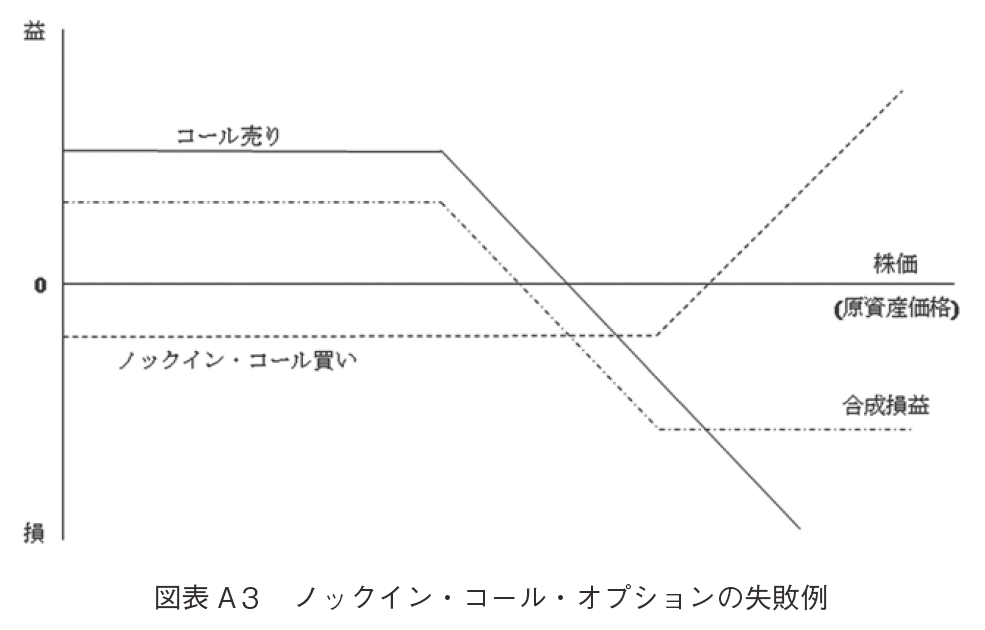
�y123 �Łz
�i�T�j�m�b�N�C�������̌���`�܂Ƃ�
�ŏ��̂Q�̐}�\�ɋ��ʂɌ��o�����̂́C�m�b�N�C���E�R�[���E�I�v�V�����̌��͂�������ŗǂ̃^�C�~���O�́C�������㏸���ăm�b�N�C���E�R�[���E�I�v�V�����̃y�C�I�t���v���X�ɂȂ鎞�_��I�Ԃ��Ƃł���B
�@�m�b�N�C�����i�����̐����ɒ�߂�C�������Ⴂ�����ɗ��܂��Ă���ꍇ�R�[������̃����b�g���c�����܂܁C���������]���ď㏸�����ꍇ�ɂ̓w�b�W���L���ɂȂ�B���Ȃ݂ɁC�m�b�N�C����������������鐅���܂Ŋ������㏸���Ȃ������ꍇ�C�m�b�N�C���E�R�[���E�I�v�V�����͗L���ɂȂ�Ȃ������̃v���~�A���͊��Ɏx�����Ă���̂ŁC�����R�[���E�I�v�V�������肩�瓾���闘�v�͂��̕�����B
�@����ł́C�s�g���i�͂ǂ����߂�悢���낤���B����́C�����̔���R�[���̍s�g���i�ȉ��̐����ɂ���悢�B
�i�ȏ�j