【103 頁】
大正期における企業家ネットワークの研究
─『日本全国諸会社役員録』(大正10年版)の分析─
鈴木 恒夫,小早川洋一
はじめに
本稿の課題は,『日本全国諸会社役員録』(大正10年版)1)に記載されている会社・役員の全体像を提示しつつ,多数の会社に役員として関与した人物に焦点を当てて,企業家ネットワークの実態を明らかにすることである。『企業家ネットワークの形成と展開』 2)では,明治31年と明治40年の 『日本全国諸会社役員録』 を用いて,当該資料に記載されているデータの範囲を 『日本帝国統計年鑑』 や 『府県統計書』 と比較して,その特徴を指摘した。そこで得られた結論を基に,両年の会社・役員の実態と企業家ネットワークの全国的な展開を明らかにしてきた。そして両年の実態の意義をその後の日本経済の発展過程の中で明らかにする為に,今回,大正10年の資料を用いて,企業家ネットワークの実態を考察することにした。その結果,企業家ネットワークは,明治期だけに固有な現象ではなく,大正期でも依然として存在していることが明らかになった。前著では,この間継続して存在していた企業家ネットワークは,東京や大阪といった大都市だけではなく,青森県や長崎県,和歌山県などでも見られたことも指摘したが,紙幅の関係で詳細な分析は出来なかった。そこで今回,大正10年での実態を明らかにしたい。全体として見ると,安田善次郎,浅野総一郎や大倉喜八郎などの全国的な規模で事業を拡大していった人物が,大正10年という時点でも確認できるばかりではなく,地方を舞台とした事業家達の活発な企業家活動が浮かび上がって来たことである。そこで大正10年の資料を用いて,改めて,前著での指摘を再確認するだけではなく,先の研究では触れることが出来なかった,新興の事業家達の実態をも明らかにしていきたいと思う。
最初に,先の研究で用いた大正10年のデータと今回,この研究で用いた大正10年のデータの違いを記すこととしたい。その際,膨大なデータベースを用いた研究では,データベースに基づく事実確認や結論のみならず,データベースの作成手順なども明らかにしておくことが必要と思われるので,可能な限り手続についても記すこととした。先の研究と今回の研究で用いた原資料は同じであるが,対象の範囲が違うとともに,データの処理作業の精度も異なる。第1点は,前著では主要なテーマの時期を明治31年と明治40年とした関係上,大正10年のデータでも,両年のデータの記載範囲に合わせて沖縄県を除く所謂本土の地域に限定したデータを用い
【104
頁】
たが,今回は,大正10年に記載されている台湾,朝鮮,満州などの,当時の植民地などのデータすべてを取り上げたことである。第2点は,多数の会社に役員として登場してきた人物のうち,10回以上の人物を取り上げて「同姓同名の他人」が含まれているか否かを,すべて調査したことである。
ここから得られた結論は,先の研究と変わることはないが,人物や会社の面で,明治期と大正期の間の断絶がより明らかになり,地方を舞台にして活躍している起業家達の姿が一層明らかになった。前者の面で言えば,主要な人物の交替が見られる一方,証券会社を舞台にして活躍してきた一群の新興の企業家達が登場してきたことが鮮明になったことである。また後者の面では,埼玉や兵庫などの都市近郊の地域のみならず,鹿児島,福岡,長崎,島根,和歌山,石川,新潟,栃木,宮城,青森など日本全国に亘って,企業家ネットワークの存在が確認できることである。しかも,その企業家ネットワークの規模は,関与した役員数や会社数からみると大きくなっているものが見られる。この意味で,企業家ネットワークの存在,その地域経済での役割は,明治期で終わったわけではない。それどころか,昭和11年の 『日本全国諸会社役員録』 3)においては,それまでよりも一層多い企業家ネットワークを確認できる。それゆえ,企業家ネットワークについては,特に,非財閥系企業や地方経済の発展を視野に入れた場合,明治期から昭和戦前期までを通した経済活動の主要なプレイヤーとして,考えなければいけないと思われる。本研究は,従って,これまでの明治31年・明治40年の時代との比較という視点のみならず,昭和11年の分析を念頭に置いた上での大正10年の特徴を明らかにしていくことを課題としたい。
以下, 『日本全国諸会社役員録』 (大正10年版)の資料の概観とデータベース化における手続を踏まえて,大正10年で多数の会社役員になっている人物と彼らの人物類型を出自の面から明らかにし,明治31年,明治40年のデータとの比較を踏まえて,断絶した人物,継続している人物,興隆してきた人物を明らかにする。そして,これら多数の会社に役員となっている人物の中から,特に多数の会社役員となっている人物,これまで研究史上で度々取り上げられてきた,安田,浅野,大倉などの人物,更には,それぞれの地方で活躍していた主要な人物を取り上げて,彼らが関わった企業家ネットワークの実態を明らかにしたい。そして最後に,なぜ昭和戦前期まで企業家ネットワークが存在したのだろうかという,素朴ではあるが根源的な問題の解決に向けての取り組みの視座を明らかにしたい。
1.『日本全国諸会社役員録』(大正10年版)の概要
『日本全国諸会社役員録』 (大正10年版)の概要を記すとともに,これをデータベース化する際の手続を明らかにしておこう。
大正10年版には,それまでの明治31年版や明治40年版と同様,日本全国に亘る株式会社,合資会社,合名会社に加えて個人会社が取り上げられ,公称資本金,払込資本金をはじめ,会社所在地などが記されている。また,会社役員等も記されているので,ここから会社に関わるデータと役員に関するデータをすべて電子データ化し,分析を行った。その際,会社によっては,役員以外にも所謂従業員とも言うべき人物が記載されている。例えば,部長や課長,支店
【105
頁】
長などの肩書きを持った人物である。そこで前回の研究同様,株式会社では,役員名簿に記載されている人物の中から,取締役を始め監査役までの人物を取り上げた。その他にも顧問,相談役などの役職名を持った人物が監査役の後に登場する。こうした役職名を持った人物の中には,例えば渋沢栄一のように著名な人物が含まれている。著名なだけでなく,こうした人物が顧問や相談役として存在していること自体,他の役員の経営判断に何らかの影響を与えたことを示唆すると言えよう。こうした顧問や相談役といった役職の次には,支店長や技師あるいは部課長という役職名を持った人物が続く場合もある。そこで,原則として,検査顧問や技術顧問のような専門的な資格ではなく,全社的な視点を有した顧問や相談役を役員として含めた。
対象となった府県は,明治31年と明治40年で対象とした一道三府四十二県の他に沖縄,樺太,台湾,朝鮮,満州を加えた51の地域である。これまで,明治31年と明治40年との連続性を重視して,この両年では取り上げられなかった樺太や朝鮮などの地域を除いて分析を行ってきたが,今回は,『日本全国諸会社役員録』(大正10年版)に記載されているすべての地域を取り上げた。また,会社形態では,日本銀行を除けば,株式会社,株式合資会社,合資会社,合名会社の他に,「準株式」,「準合名」,「無限責任」,「相互会社」,「個人会社」の9種類が記されている。具体的には,山梨県にある「大日本重石砿業者(準株式)」,愛知県にある「岡谷保善会社(準合名)」,東京にある「広部銀行(無限責任)」である。それぞれの会社数を記せば次の通りである。株式会社は13,696社,株式合資会社は9社,合資会社は781社,合名会社は698社,準株式会社は1社,準合名会社は3社,個人会社は3社,相互会社は7社,無限責任会社は4社,日本銀行を含めて合計15,203社が記載されている。90%以上は株式会社であった。
15,203社の中には,同名の会社が多数存在する。特に,合資会社や合名会社の中には,田中合名とか,原合名のように家名を冠した会社名が多く,その結果,全国では同名の会社が多数存在している。そこでこれらをすべて別会社として識別できるように,会社名の後に府県名や地域名を付して,同名の会社処理を行った。
次に,15,203社すべての業種分類を行った。原資料では,銀行は各府県の冒頭に記されているので容易に特定できるが,それ以外は,会社名と原資料に記されている会社の目的を基に,先の研究で取り上げた分類と同じ業種分類を行った。ここでその業種を記せば,農林,土地改良開発,水産業,鉱業,石油,綿紡績,綿織物,生糸,その他繊維,食品,醸造業,窯業,化学,金属,機械器具,その他工業,海上輸送,陸上輸送,倉庫,商業,貿易,取引所,銀行,保険,その他金融,電力,ガス,鉄道,水道,印刷出版,不動産,その他サービス,その他(多業種),不明の34業種である。明治40年における業種分類と大正10年における業種分類での異同を記すこととしたい。表1から分かるように,両年で最も多数の会社を擁している業種は銀行である。しかし,業種の構成から見ると,銀行は相対的に低下し,代わって,機械金属,その他工業,化学,その他繊維が増加している。明らかに,工業と化学の興隆が見て取れる。「その他繊維」には「紡織」と記された会社が多数を占めていることから,紡績業から紡織業への変化が窺われると言えよう。会社数から見た場合,小売りや銀行の時代から製造業の時代へと変化していることが特徴である。
最後に15,203社の本社所在地から見た府県分布一覧を見たのが表2である。ここから分かるように,会社数の20%以上は東京で,大阪が11%を占めていたが,公称資本金ではそれぞれ36.5%と16.3%となり,両者を併せると53%にも達する。即ち,東京と大阪の会社が会社数ではおよそ3分の1を占め,資本金では過半を占めていたのである。また,最下段に記されてい
【106 頁】
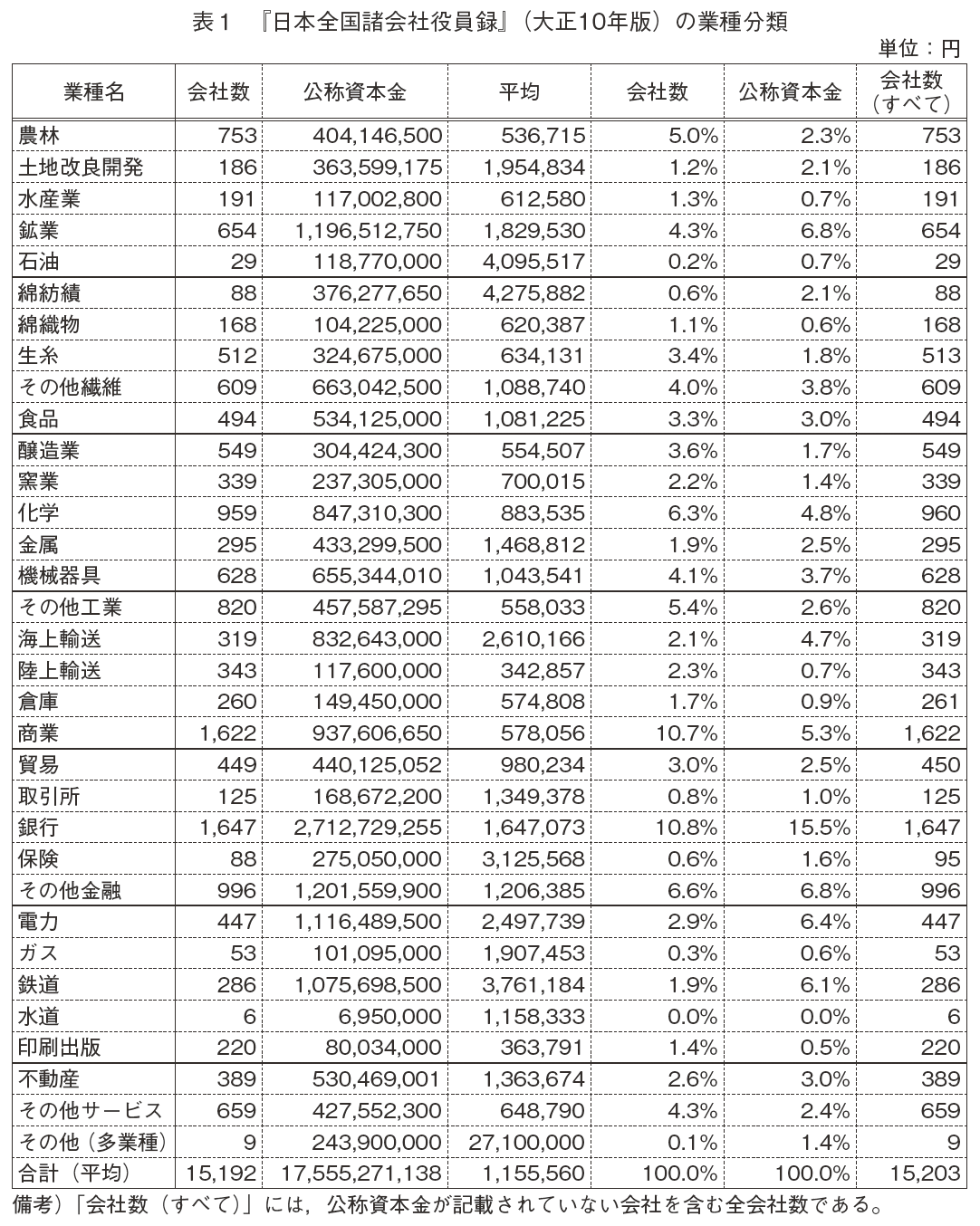
【107 頁】
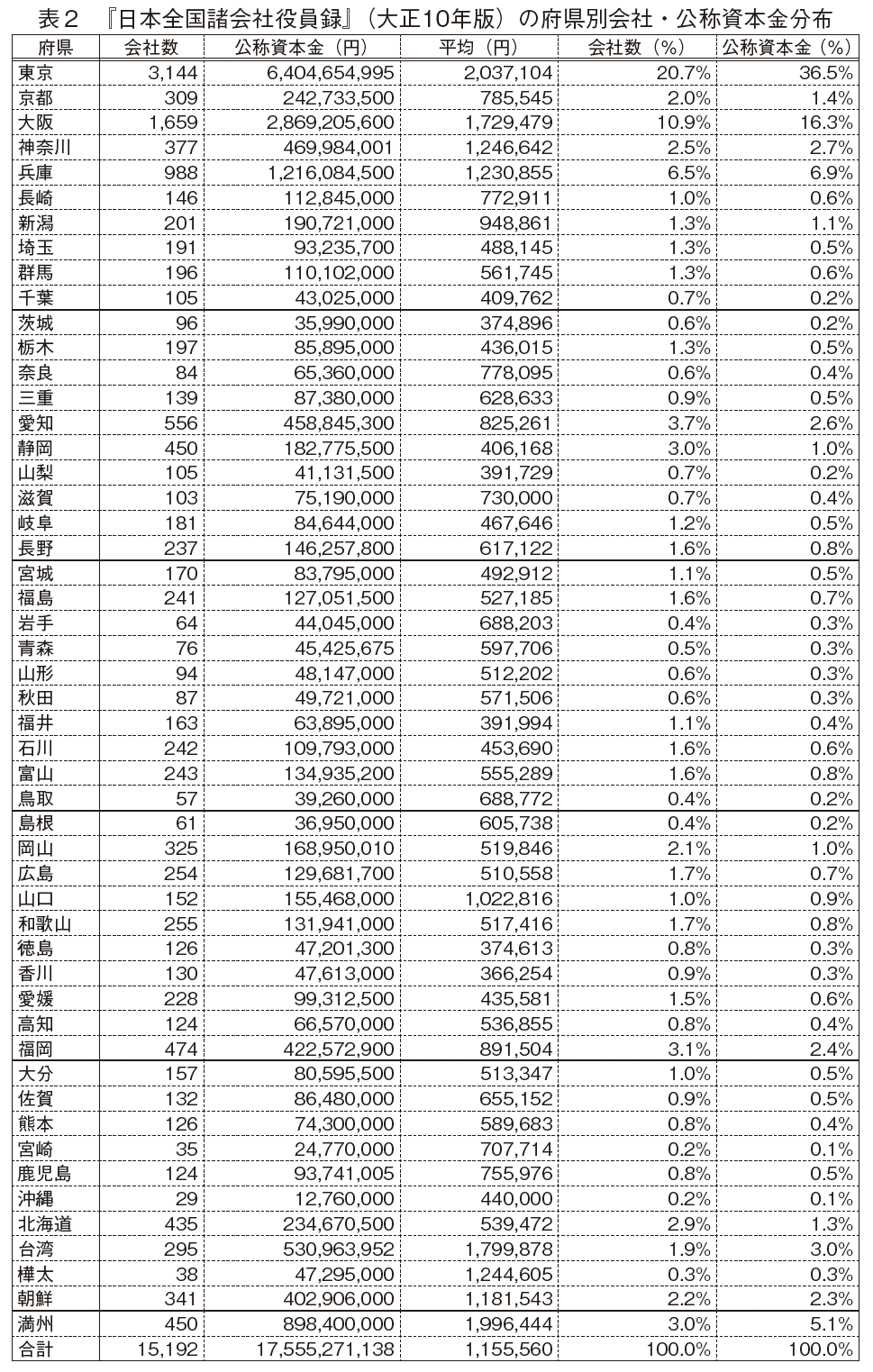
【108 頁】
る全国の1社平均の資本金額とそれぞれの府県のそれを比較すると,全国平均を上回っているのは,東京,満州,台湾,大阪,神奈川,樺太,兵庫,朝鮮の8つの地域であった。一言で言えば,関東と関西の大都市近県と植民地の会社である。
一方,15,203社に記載されている役員数は,110,794名である。この延べ110,794名を取り扱う際,先の研究でも記したように,同一人物ではあるものの,治郎,次郎,二郎などのように,表記が異なって記載されている人物もいるので,すべての役員から,1字だけ文字が異なる人物の組合せを抽出した。抽出した194,793組すべてについて,これらの人物が同一人物であるか否かを確かめた。その結果,延べ71,279名の役員が抽出できた。一方,同姓同名の他人も存在する。そこで,この71,279名の人物の中から,10回以上登場する,言い換えれば10社以上で役員となっている408名を取り上げ,同一人物であるのか,同姓同名の他人であるのかをチェックした。その結果,10回以上登場する人物は,397名となった。ここまでが,大正10年の日本全国諸会社役員録の分析を行うまでの準備作業である。次に,こうした準備を整えてから,これを用いて分析を行った。こうして作成されたファイルを基に分析した結果を,以下,記すことにしたい。
2.10社以上に登場する人物・類型およびネットワーク
今回は紙幅の関係から,主として10回以上登場する人物に焦点を当てて,彼らの人物類型を明らかにするとともに,明治40年のデータと比較し,我々が定義したネットワークの変遷を明らかにすることにしたい。
そこでまず15回以上登場する人物118名の一覧を示し,次に,10回以上登場する397名の人物類型を記すこととしたい。表3には,118名の人物と登場回数が記されている。また,明治31年や40年との比較も大切であるから,明治31年と40年の役員録で登場する回数も記した。以下,次のように記すこととした。名前の後の括弧には,(大正10年の役員数,明治31年の役員数→明治40年の役員数)の要領で記している。ここから,人物類型と同時に,明治31年と大正10年との間での企業家活動の変遷が窺われる。
10社以上で役員を兼任している人物397名について,それぞれの出自やキャリア等を調査した。その結果,人物は次の8つに分類することができそうである。(1)財閥関係者,(2)「専門経営者」(ミドル・マネジメントを含む)出身の実業家,(3)証券業者(同出身者を含む),(4)植民地(朝鮮・台湾・満州)を中心に活動した実業家,(5)官僚出身者,(6)弁護士,新聞記者,大学教授等の経験者,(7)非財閥の起業家,(8)家業・家産の継承者,(9)その他(調査中の人物を含む)。そのうち,役員就任会社数15社以上の人物について一覧表示したものが上記のように表3である。以下,それぞれのタイプに属するネットを一例ずつ紹介しておくことにしよう。
(1)財閥関係者
このタイプで15社以上の人物は次のとおりである。浅野総一郎(29社),白石元治郎(32社,総一郎女婿),浅野泰治郎(31社,総一郎長男),鈴木紋次郎(24社,総一郎女婿),浅野良三(18社,総一郎次男),大倉喜八郎(28社),門野重九郎(21社,大倉財閥専門経営者),安田善之助(20社,安田善次郎次男)。浅野系の人物が多い。そこで,浅野総一郎のネットを見てみる
【109 頁】
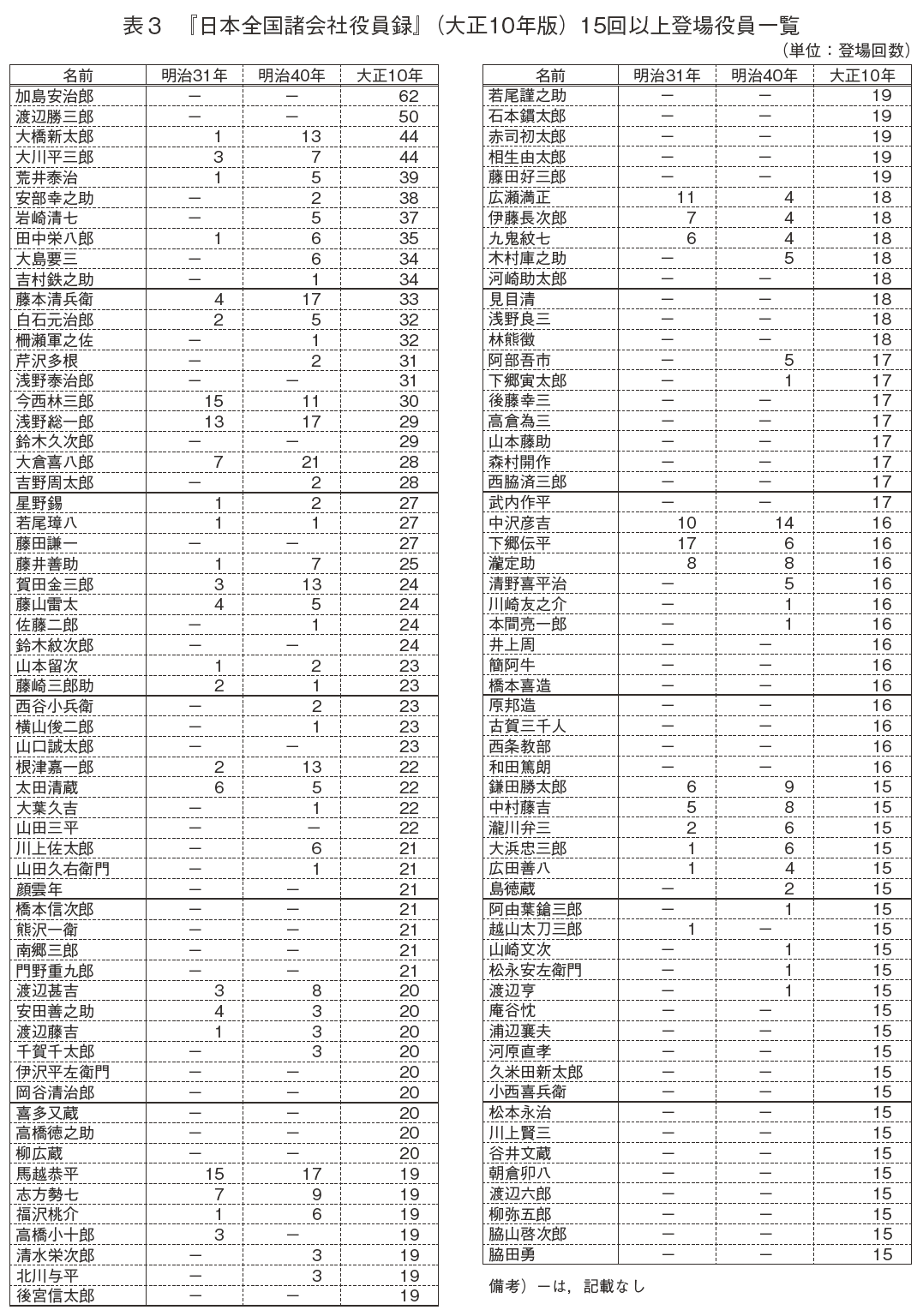
【110 頁】
と図1のとおりである。同財閥本社・持株会社の浅野同族会社をはじめ,浅野セメント・磐城炭砿・東京湾埋立・浅野造船所・浅野小倉製鋼・浅野昼夜銀行・浅野物産等の直系会社に加え,比較的資本金規模の小さな関係会社等,事業の多面的展開が示されている。同時に,かつて渋沢栄一や大倉喜八郎らとともに総一郎が設立に参加した帝国ホテルの名前も見られる。それらの会社の役員に,家族・同族および,橋本梅太郎,横山徳次郎,原正幹らの専門経営者が配置されている。金子喜代太は総一郎孫娘の婿である。また,浅野系の事業に,大川平三郎・田中栄八郎兄弟や渋沢武之助(渋沢栄一の次男),尾高幸五郎(妻は栄一夫人千代の妹くに)ら,渋沢栄一の関係者,また多大な金融支援を浅野事業体に与えていた安田善次郎,また総一郎と近しい関係にあった大倉喜八郎らが参画している。
財閥事業体では一般に,家族・同族および専門経営者たちが分担して関係会社役員に就任することが知られている。したがって,その兼任関係が,われわれの言うネットとして把握されることになるのである。
なお,役員就任会社数15社未満には,浅野系で浅野八郎(14社,総一郎三男),大倉系で大倉粂馬(12社,大倉喜八郎養子),安田系で安田善次郎(14社),同善四郎(12社,初代善四郎長男),同善五郎(11社,善次郎三男),同善雄(11社,善次郎四男),同善助(10社,初代善助養子)ら,三菱系では木村久寿弥太(10社,三菱合資会社総理事),青木菊雄(11社,同常務理事),桐島像一(12社,同地所部部長)ら専門経営者3人が含まれる(三菱合資会社社長岩崎小弥太は8社で役員に就任)。
また15社未満には寺田甚与茂(12社)・同元吉(13社),伊藤守松(11社),麻生太吉(10社)ら地方財閥のリーダーたち,野口遵(10社)と中山説太郎(11社)ら,のちの新興財閥の設立者やその母体企業の幹部の名前が見られる。
(2)「専門経営者」(ミドル・マネジメントを含む)出身の実業家(その関係者を含む)
森川英正氏は,その専門経営者台頭の歴史的研究において,「専門経営者の資本家化」について指摘し,考察した。森川氏は,『日本全国諸会社役員録』 の明治38年,大正2年,昭和5年の各版を資料に,各年時「大企業」の取締役について詳細な調査を行った4)。その結果,昭和5年時の「大企業」では広く専門経営者の勢力拡大が見られる一方で,かつての専門経営者のうち,自社株を大量に所有して大株主重役になった人物たちが出現したことについて論じた5)。われわれのここで言う「専門経営者出身の実業家」とは,森川氏が指摘したそのような経営者たちのうち,複数の会社で役員を兼任している人物たち(その関係者を含む)のことである。ただし,ここでいう専門経営者には,便宜的に,トップマネジメントばかりでなくミドルマネジメントをも含ませてある。
このタイプでは,大川平三郎(44社)と弟の田中栄八郎(35社)それぞれの役員就任会社数が圧倒的に多い(大川の44社中,26社は田中と共通の会社)。ほかに,藤山雷太(24社),喜多又蔵(20社),藤田好三郎(19社),馬越恭平(同),浦辺襄夫(同),脇田勇(同)らがいる。そして,馬越恭平を除いた人物たちは,明治末から大正10年までの間に,役員就任会社数を急増させていることがわかる。この点は,15社未満の17人の大半についても同様である。15社未
【111 頁】
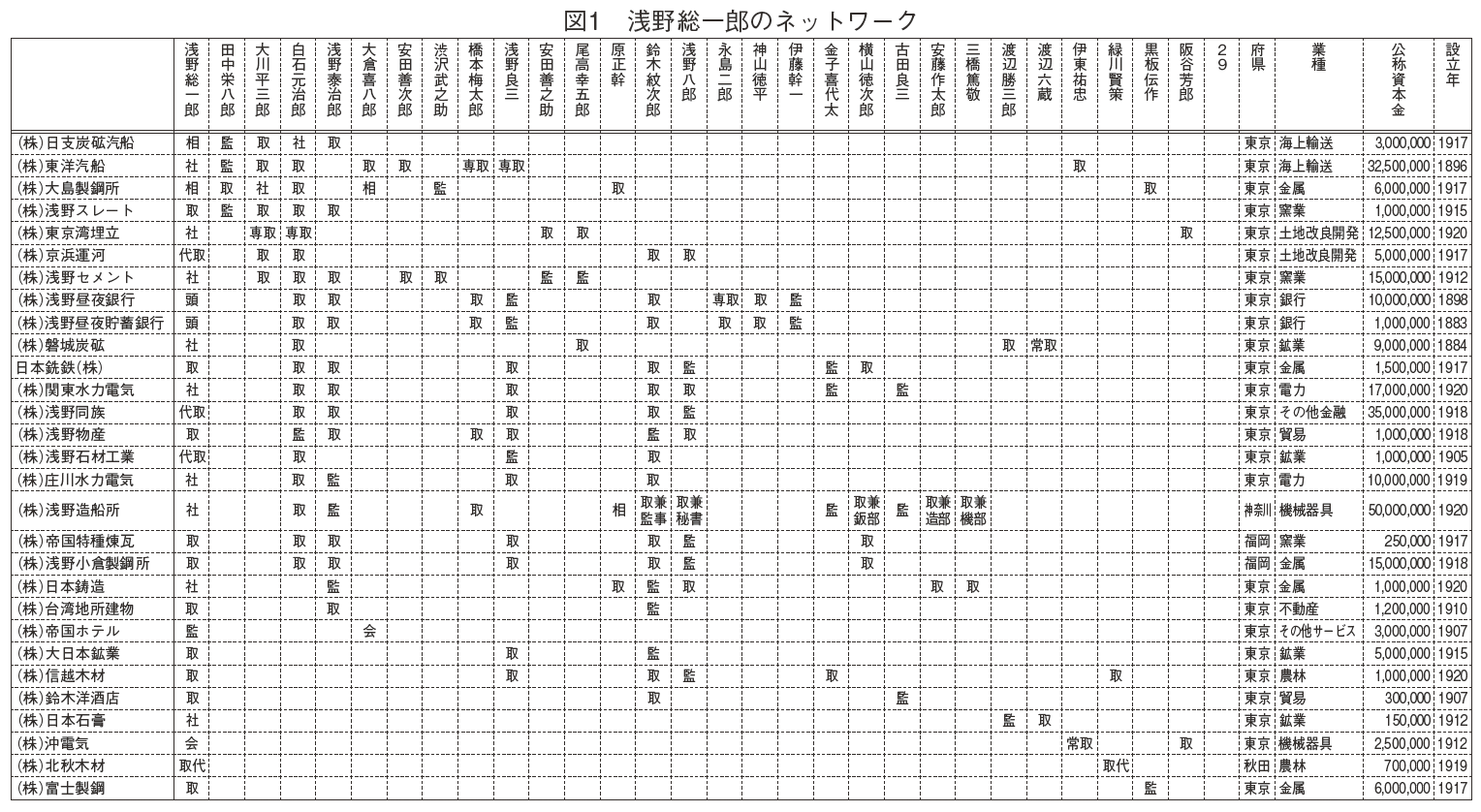
【112 頁】
満の中には,日本経営史上あまりにも有名な藤原銀次郎(14社),和田豊治(13社)らの名前が見られる。
これらの人物のうち喜多又蔵のネットをみると図2のとおりである。喜多は,大阪商業学校(大阪高商の前身)を卒業後,日本綿花に入社(明治27年)し,支配人に抜擢され(37年),その後,取締役,常務,副代表を経て大正6年社長に就任した。同表によれば,同じ日本綿花の監査役である南郷三郎(東京高商卒業後,大阪商船を経て,明治33年日本綿花入社)や証券業者の加島安治郎,台湾産業界で活動する赤司初太郎らがネットのメンバーを構成している。
(3)証券業者(同出身者を含む)
日露戦争を契機に証券市場が発展し,その担い手である証券業者が台頭したことが,野田正穂氏によって指摘されている6)。石井寛治氏は証券業者の活動実態にアプローチすべく,『日本全国商工人名録』(1921年)によって大正9(1920)年時の4都市(東京市・大阪市・京都市・名古屋市)における証券業者(仲買人・現物商)の分布を調査するとともに,有力な業者につ
いてその動向を概略している7)。われわれのデータベースからは,証券業者たちの役員就任状況と「ネットワーク」を確認することができる。
かれらのうち,役員就任会社数において,大阪株式取引所仲買人・加島商店監査役の加島安治郎が62社(全国でトップ)で,突出している。次いで柳広蔵(20社)とその弟の柳弥五郎(15社),島徳蔵(15社)となっている。15社未満には,松井伊助(13社),大島甚三(12社),小池国三(同),宮崎敬介(10社),山辺常重(同)らがいる。彼ら,株式取引所仲買人ないしその出身者たちは,日露戦争後~第1次世界大戦期において,多様な会社の大株主として役員に就任していたのである。図3は,大阪株式取引所理事長の島徳蔵のネットを示したものである。同じ大阪株式取引所の仲買人・常務理事で大阪電灯社長の宮崎敬介や,肥料商で,かつて日本綿花の社長を務めた志方勢七らとともにネットを形成している。
(4)植民地(朝鮮・台湾・満州)を中心に活動した実業家
とくに日露戦争後,朝鮮・台湾・満州に事業機会を求め,成功した人物が多い。
荒井泰治(39社),柵瀬軍之佐(32社),賀田金三郎(24社),山田三平(22社),相生由太郎(19社),赤司初太郎(19社),後宮信太郎(同),石本鏆太郎(同),古賀三千人(16社),川上賢三(15社)らである。ほかに顔雲年(21社)と林熊徴(18社)がいる。荒井,柵瀬,賀田,赤司,後宮,林ら,台湾を拠点として活動した人物が多い。台湾を拠点とした人物たちは皆,同地の商業会議所である「台北商工会」の役員(大正10年2月現在)8)に名を連ねている。外地で活動した企業家たちの大半は,明治末以降,役員就任会社数を急増させている(ただし賀田金三郎は,明治40年時,すでに13社で役員に就任していた)。
図4は大連商業会議所会頭(大正5年就任)・相生由太郎のネットである。相生は,東京高商を卒業(明治29年)したのち,日本郵船,三井物産各勤務を経て南満州鉄道大連埠頭事務所
【113 頁】
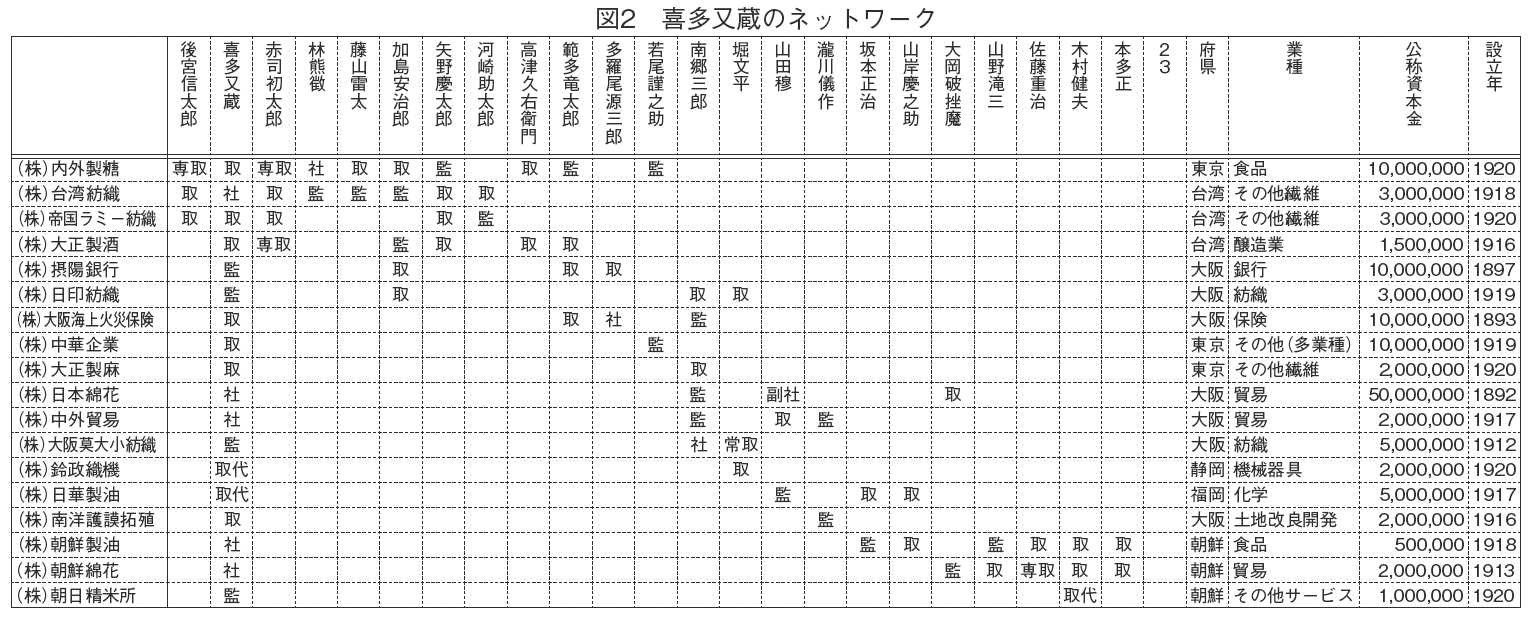
【114 頁】
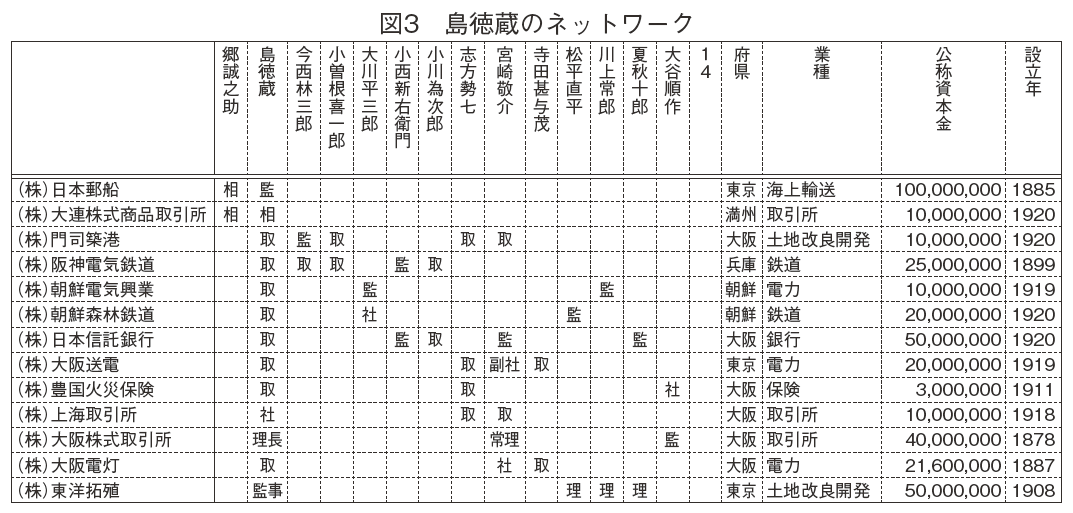
長となり(同40年),同社を退社(同42年)して独立し,倉庫・保険代理業・輸出入業等の経営を行うなど同地産業界のリーダーであった。このネットを見ると,石本鏆太郎と最も緊密であったことがわかる。石本は,帝国大学予科卒業後,支那に留学し(明治15年),日清・日露戦争に通訳として従軍した経験を持つ。日露戦後,関東州でアヘンを製造,販売して蓄財し,炭坑,銀行,学校,新聞社などを経営するとともに,大正10年時,大連市長職にある(同4年以来2度,衆議院議員に選出)。
(5)官僚出身者
官僚出身者で,大正10年時の役員就任会社数が15社以上の人物は,藤田謙一(27社)と清野喜平治(16社)の二人であるが,15社未満には次のような人物たちがいる。室田義文(13社),伊藤義平(同),川上俊介(同),坂野鉄次郎(12社),植村澄三郎(同),倉知鉄吉(同),高橋虎太(同),日下義雄(同),山本辰六郎(11社),武井守正(10社),山岡順太郎(同)。
日露戦争以前に実業界に転じて役員兼任を進めていた武井守正と植村澄三郎を除いた人物たちは,27社の藤田謙一をはじめ,ここでも明治末以降に役員就任会社数を急増させていることがわかる。仙台商業会議所会頭職(大正10年時)にあった清野喜平治のネットを見たものが図5である。清野は,宮城県庁勤務(明治11~31年)ののち,明治31年宮城商業銀行専務取締役となり,頭取に就任するとともに,仙台商業会議所副会頭(明治38年)を経て同所会頭となった。同地において,銀行はじめ,鉄道・ガス・電気等のインフラ事業その他,幅広く役員を兼任している。このネットには,仙台商業会議所の役員(大正10年3月現在)が数多く名前を連ねている。副会頭の伊沢平左衛門(20社,醸造業,宮城県多額納税者,7,044円,大正9年衆議院議員,同11年七十七銀行頭取,翌年同会議所会頭)と同佐々木重兵衛(9社,醸造業,同多額納税者),常議員中村梅三(13社,明治39年東京帝国大学法科政治科卒,明治41年七十七銀行支配人を経て大正2年取締役,同行代表者),同山田久右衛門(21社,金融業,仙台米穀取引所代表),同福島与惣五郎(11社,材木商,東北実業銀行代表者),同佐藤二郎(24社,七十七銀行代表者),同佐々木栄介(3社,宮城県農工銀行代表者)等である。また,同地出身で,39社で役員を兼任する荒井泰治の名前が見られる。荒井は,毎日新聞記者,日本銀行行員,鐘
【115 頁】
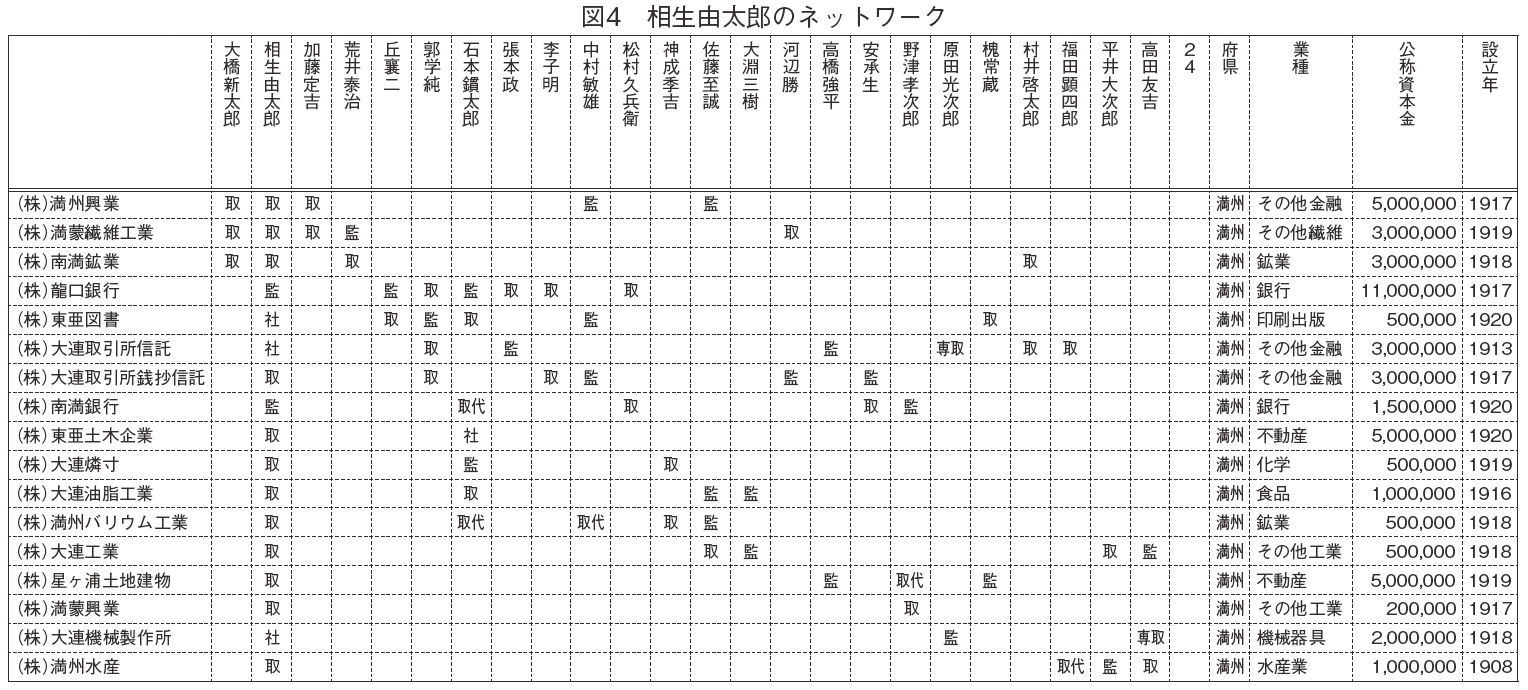
【116 頁】
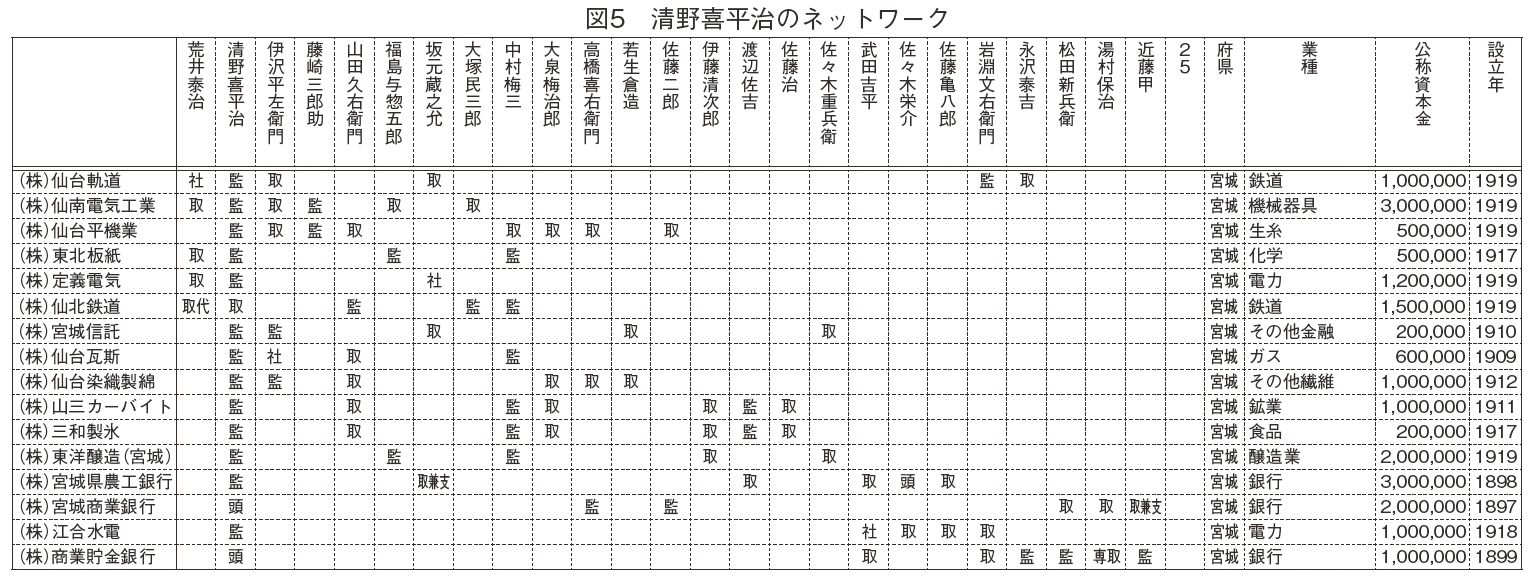
【117 頁】
紡・富士紡各支配人を経て,明治32年サミュル商会に入り,台湾支店長を9年間勤めた経験を持つ(同45年,宮城県より多額納税者の互選により貴族院議員)。
(6)弁護士,新聞記者,大学教授等の経験者
このタイプで役員就任会社数15社以上は,武内作平(17社),越山太刀三郎(15社),渡辺亨(同)の3人であるが,15社未満には次のような人物がいる。立川勇次郎(14社),山村豊次郎(同),山口恒太郎(13社),上遠野富之助(12社),指田義雄(同),塩田奥造(同),桜内幸雄(同),鈴木梅四郎(同),戸水寛人(同),長島鷲太郎(10社),森盛一郎(同)。
弁護士と新聞記者の経験者が多いが,なかに東京帝国大学教授から実業界に転じた戸水寛人のような人物もいる。ここでも,大半の人物が(鈴木梅四郎と上遠野富之助を除き),明治末から大戦期にかけて活動を活発化させていることがわかる。この類型に属する人物たちのなかで役員就任会社数17社で最多の武内作平のネットを紹介すると,図6のとおりである。愛媛県出身で大阪弁護士会会長そして衆議院議員である武内は,とくに高倉為三と緊密な連携を取っていた様子が見られる。高倉為三は,大阪の相場師として名を馳せた高倉藤平の養子であり,藤平を後継して大阪堂島米穀取引所理事長職にあり,また日本貯蔵銀行(日本積善銀行の前身)の常務として,同行に機関銀行の役割を担わせ,活発な事業展開を行っていた(日本積善銀行は1923年に経営破綻する)。また,高倉藤平と緊密であった株式仲買業者の宮崎敬介(10社)や為三と近しかった米穀問屋の上田弥兵衛(14社,大阪高等商業学校卒,衆議院議員),洋織物問屋で1921年に日本毛糸紡績を設立した河崎助太郎(同18社),さらに前記の,株式仲買業者でこの時期,役員就任会社数で全国トップ(62社)の加島安治郎らの名前が見られる。
(7)起業家(非財閥)
非財閥の起業家で15社以上の人物は25人である。うち20社以上の企業家を列挙すると次のとおり。大橋新太郎(44社),吉村鉄之助(34社),大島要三(同),藤本清兵衛(2代,33社),今西林三郎(30社),星野錫(27社),藤井善助(4代,25社),山本留次(23社),横山俊二郎(同),大葉久吉(22社),根津嘉一郎(初代,同),藤崎三郎助(21社),高橋徳之助(20社),渡辺甚吉(12代,20社)。
起業の際の業種としては,以前の勤務先から独立して同業ないし関連業種の事業を起こす者や家業継承者であるが家業とは異業種に進出する者,または最初からビジネスチャンスを求めて起業する者などがいる。各人物それぞれの参画するネットを見てみると,関係する事業(役員就任会社)としては,本業と非関連分野に関係する者が多い一方,本業中心ないし本業関連分野の事業が比較的に多い人物もいる。山本留次,大葉久吉,根津嘉一郎,松永安左エ門(15社)らが後者である。活動の地理的範囲としては,中央・東京の実業界あるいは大阪をそれぞれ中心として活動する者,または地方の諸産業に深くコミットする者,などに分けてみることができる。ここでは,土木建築請負業者で福島商業会議所会頭の大島要三(福島県多額納税者,納税額3,488円)9)のネットをとりあげてみよう。
図7の大島要三のネットを見ると,業種としては,電力と銀行が多い。また人物には,大島
【118 頁】
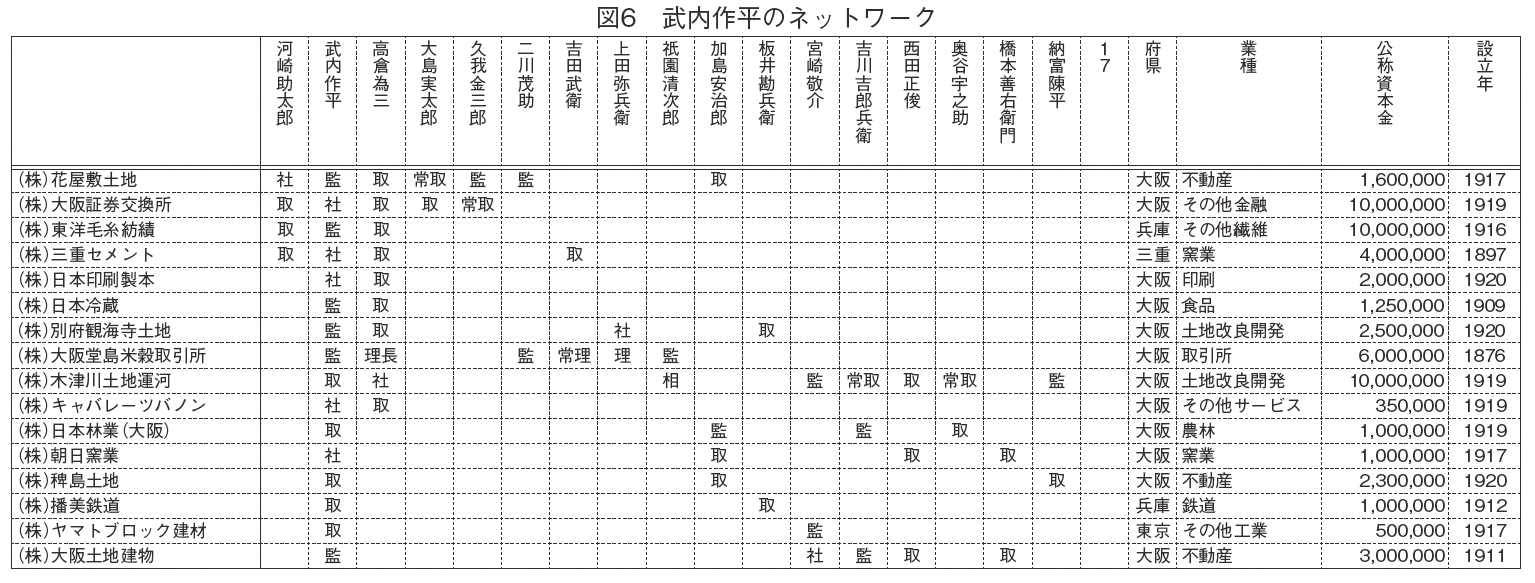
【119 頁】
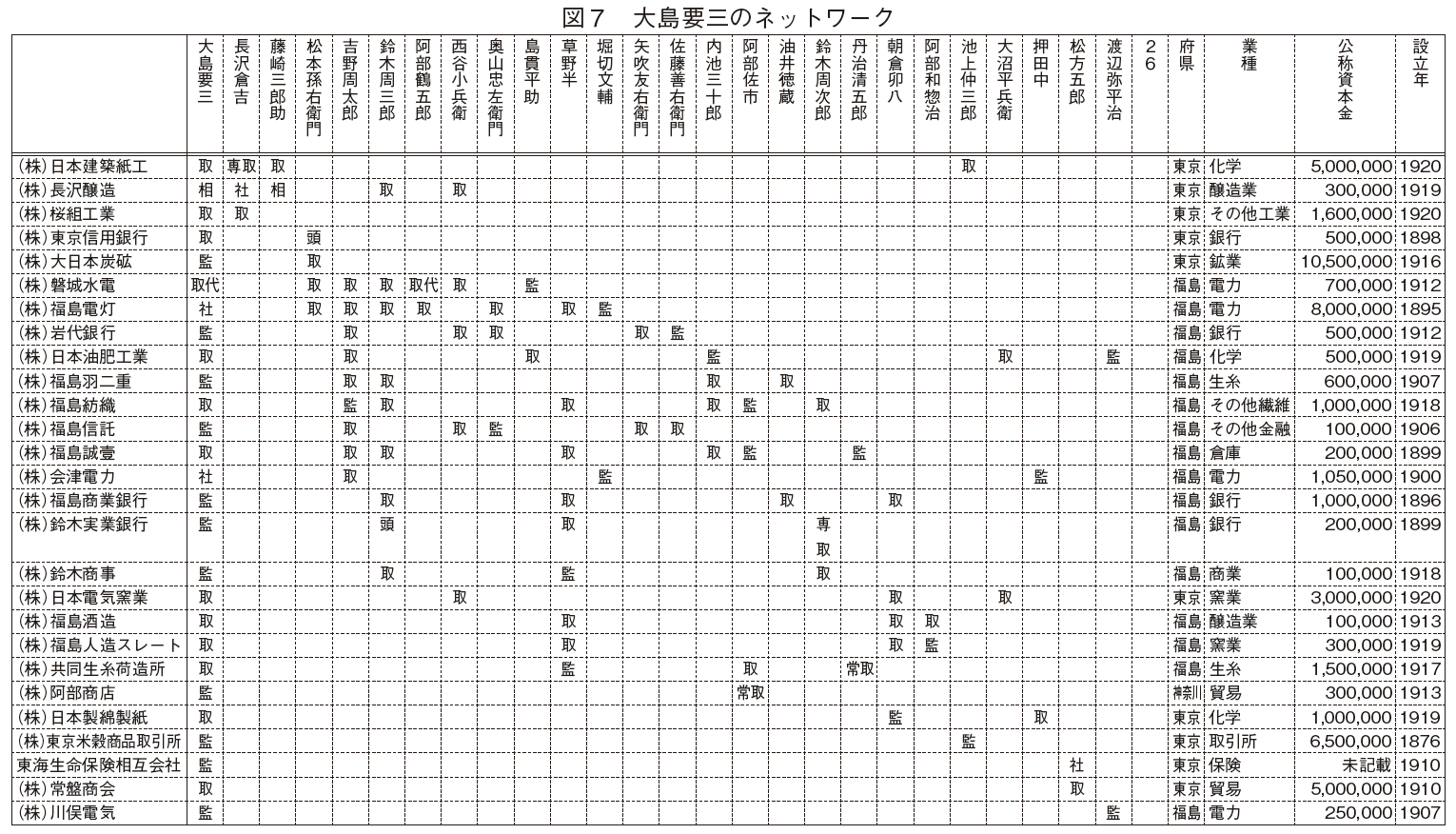
【120 頁】
を筆頭に福島商業会議所の役員が中心メンバーになっている(大正10年3月現在)。すなわち常議員の吉野周太郎(28社,農業,同多額納税者,3,865円,福島銀行頭取),同鈴木周三郎(13社,農業,同多額納税者,3,073円,鈴木実業銀行頭取),同草野半(13社),同内池三十郎(10社,醤油・味噌醸造業)と同西谷小兵衛(23社,内池三十郎次男),同朝倉卯八(15社)らである。 このネットは,大島・吉野・鈴木の3人を中核とする,福島県における最有力ネットである。
(8)家業の継承者
ここで言う家業の継承者とは,財閥のように家業の多角化を図るというよりは,家業を継承して維持ないし発展させるとともに,家業で蓄積した資本をもって多くの会社の株主となり,役員を兼任するといったタイプの人物たちである。ここに含まれる少なからざる人物たちは,それぞれの地域の経済発展そして地方財界のリーダーないし準リーダーたちであるとみてよい。
このタイプで15社以上は31人を数える。うち,20社以上の人物は次のとおり。渡辺勝三郎(50社),安部幸之助(38社),岩崎清七(37社),芹沢多根(31社),吉野周太郎(28社),若尾璋八(27社),佐藤二郎(24社),西谷小兵衛(23社),山口誠太郎(同),太田清蔵(4代,22社),川上左太郎(21社),熊沢一衛(同),橋本信次郎(同),伊沢平左衛門(20社),岡谷清治郎(同),渡辺藤吉(同)。
このタイプは圧倒的に多く,15社未満(10社以上)についてみても,50人以上がこのタイプと見られる。そのうち,地主・洋物小間物商・砂糖卸売業者で浜松商業会議所会頭(大正10年4月現在)の中村藤吉(15社,静岡県多額納税者,3,797円)のネットが図8である。中村は,鉄道,瓦斯,電気等のインフラストラクチャーや銀行,および同県の有力メーカーである日本楽器等のそれぞれ役員を兼任している。そして,このネットのメンバーには,同商業会議所副会頭の中村忠七(6社,地主・金物商,大正7年浜松市会議長),同宮本甚七(8社,織物業,浜松の有力企業・日本形染会社設立者で初代社長),常議員の鈴木幸作(9社,味噌醤油製造業),同馬淵栄一郎らが含まれ,彼らが中心的な存在であることが想定される。
以上,10社以上で役員に就任している人物たちの属性とネットの一部をみてきた。全体から言えることは,彼らの大半が,明治末以降,第1次大戦期にかけて役員就任会社の数を急増させ,ネットを形成していることである。われわれの言う「企業家ネットワーク」は,明治期においてばかりでなく,大正期になっても依然,広範に存在していたのである。
もちろん,彼らの中には,かつて高橋亀吉が指摘したように,泡沫的ともいえる会社を次々に設立して役員を兼任する人物や,株式会社を食い物にする資本家重役がいた10)ことは事実であろう。しかし,ネットワークを通じて起業し,地域経済の発展に貢献した人物たちが多数いたことを強調しなければならない。もっとも,この場合も,森川氏が指摘したように,資本家重役のもとで,日常業務を執行する専門経営者やミドル・マネジメントの存在を忘れることはできない。森川氏は述べている。「兼任大株主重役たちは,取締役に就任している会社の経営に深入りしません。業績に眼を光らせ,資金運用・利益処分等の財務政策について発言権を行使するのにとどまりました。会社の諸業務の日常的管理はもちろん,変動する環境に対応して
【121 頁】
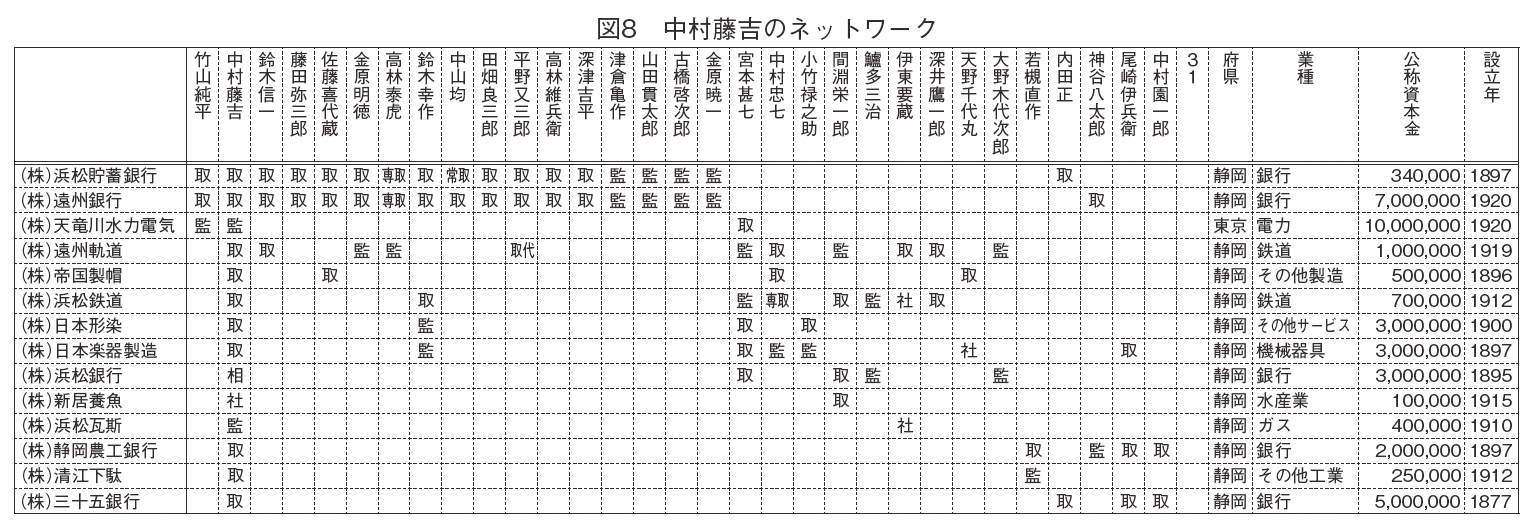
【122 頁】
会社経営の方策を立案する仕事は,給料を払って雇い入れたミドル・マネジメント以下の社員に任せました。」11)
3.地方における企業家ネットワークの継続
地方におけるネットワークの存在と継続を見ていこう。前著で,ネットワークの定義を行った。記述はやや前後するが,ここで再確認しておこう。ある二人の役員(例えば甲と乙)が共通な2社(例えばA社とB社)の役員である場合,これを要素ネットと定義した。次に,この要素ネットに含まれる,同じ二人の役員(甲と乙)が別の共通な会社(例えばB社とC社)で役員であるか,共通な2社(A社とB社)に別な二人の役員(例えば甲と丙)からなる要素ネット,即ち,人物か会社が重なっている要素ネットを抽出する。更に,新たに加わった要素ネットでも同じ作業を繰り返して,新たな要素ネットを抽出できなくなるまで行う。こうして出来上がった,役員か会社が重なり合った要素ネットの集合体をネットワークと定義した。
大正10年の役員録では,要素ネットを求めると39,203組が存在する。ここから要素ネットの重なりあったネットワークを求めると,5,710組抽出できた。前著では,同様の作業で求めた明治31年と明治40年のネットワークとの間で,二人以上の役員が共通にいるか,二社以上の会社が共通にあれば,そのネットワークは継続していると判定した。そこで,同じ基準を用いて明治31年,明治40年,大正10年で継続しているネットワークの中から,地方に存在するネットワークに焦点を当てて,その実態を見ることにしたい。先の研究では,長崎市,和歌山市,青森市のネットワークを取り上げたので,今回はそれ以外の地域を対象とした。具体的には,先の3つの市を除いた地方都市の中から,明治40年と大正10年の間で役員数や会社数の面で拡大しているネットワークの事例を取り上げ,具体的に両年における実態を明らかにしたい。本稿では,鹿児島市と山形市の2つの事例を取り上げる。その上で,大正期でも企業家ネットワークが存在しているだけでなく,関与している人物の面でも会社の面でも拡大している事実を踏まえて,その意義を考えたい。
(1)鹿児島市の企業家ネットワーク
図9,図10は,明治40年での鹿児島市における企業家ネットワークである。また図11は,大正10年の鹿児島市における企業家ネットワークである。図9は,海江田金次郎,河野庄太郎,藤安辰次郎など5人が第百四十七銀行など3社の役員となっているネットワークで,図10は,海江田金次郎,原田耕夫など5人が第百四十七銀行と鹿児島貯蓄銀行2行の役員となっているネットワークである。海江田金次郎が中心人物であることは明瞭である。海江田は米穀砂糾商を営み,鹿児島県の多額納税者(大正10年納税額2,820円)で,鹿児島商業会議所常議員(大正10年5月現在)であった。図11から明らかなように,大正10年になると,この2つの企業家ネットワークが結合しただけでなく,人物数でも会社数でも増加した企業家ネットワークに拡大している。それは15名と9社からなる企業家ネットワークである。関与している会社数から見た中心人物は愛甲兼達と藤安辰次郎である。藤安辰次郎は,当時(大正10年5月現在),鹿児島商業会議所副会頭を務めていた人物である。久米田新太郎や海江田や原田,河野の名前も
【123 頁】
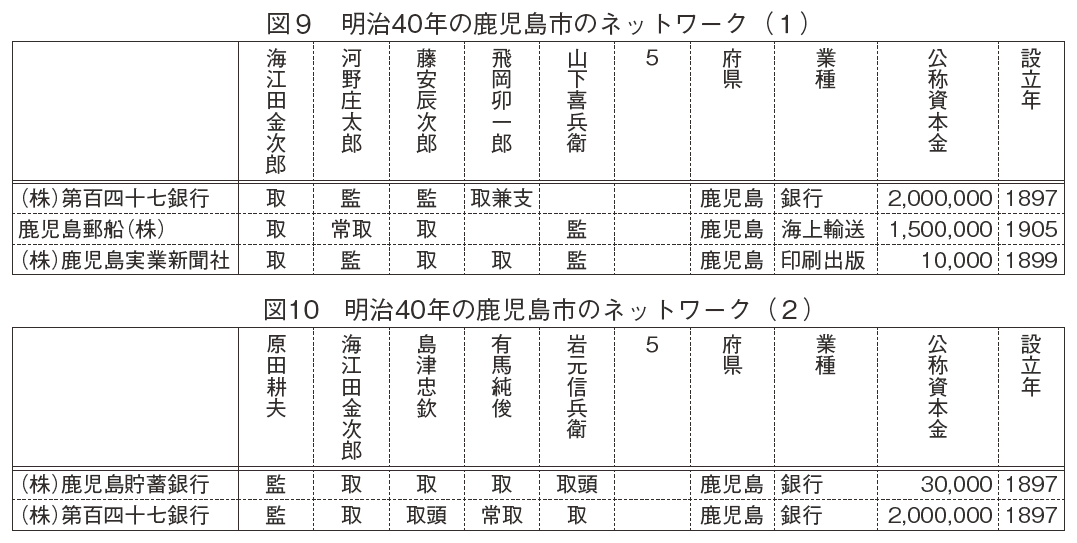
確認できる。また,第百四十七銀行と鹿児島貯蓄銀行以外にも,大隅鉄道,鹿児島電気鉄道のように地域のインフラストラクチャー産業が含まれていることが見て取れる。この点は,前著でも指摘したところである。更に,薩摩製糸や鹿児島紡織のように繊維産業も含まれていることも,明治31年や明治40年での特徴に相通じる点である。更に,日本農産工業と日本水電の本社は東京にある。積極的に東京への進出と関与が見て取れる。
(2)山形市の企業家ネットワーク
図12,図13,は明治40年での山形市における企業家ネットワークであり,図14,図15は,大正10年での山形市における企業家ネットワークである。図12は,稲田善兵衛と三浦和平を中心とした3人と両羽銀行を含み,煙草や電力会社の3社からなる企業家ネットワークであり,図13は,高梨源五郎を中心とする8名と両羽農工銀行,両羽銀行を含み,電力や倉庫等6社からなる企業家ネットワークである。形式上,この二つの企業家ネットワークは分離独立しているが,実際は,稲田善兵衛と高梨源五郎を中心とし,両羽農工銀行,両羽銀行を中核とする企業家ネットワークと考えられる。稲田善兵衛は,大正10年11月現在,山形商業会議所常議員を務める人物であった。先の研究でも記したように,地方における企業家ネットワークは,銀行と鉄道や取引所などの地域の経済活動を支えるインフラ産業に関与していると指摘した。山形市の企業家ネットワークもこの特徴を備えている。大正10年では,図14から分かるように,二つの企業家ネットワークは結合し,図12でも登場した三浦和平と三浦新兵衛を中心とした13名と両羽銀行や山形電気,米沢電気などのインフラ産業を含んだネットワークである。三浦和平は当時山形商業会議所特別議員(大正10年11月現在)であり,三浦新兵衛は先代の三浦新兵衛の養子で,東京商科大学(現一橋大学)の三浦新七教授の甥である。また,三浦新七は図13,図15に登場する山形県多額納税者の三浦権四郎(大正10年納税額5,531円)の養子である。
このネットワークは,第一次大戦期に設立された企業を多数含むとともに,地域的には山形市から米沢市まで外延的に拡大している。更に,現在で言うところの,サテライト商店である
【124 頁】
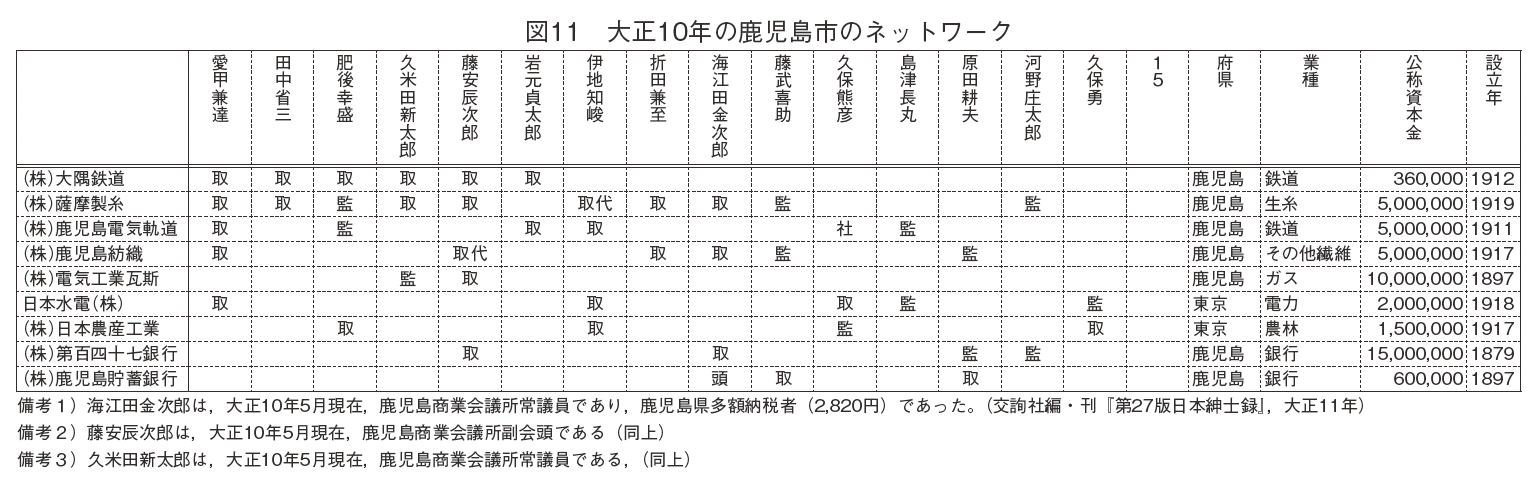
【125 頁】
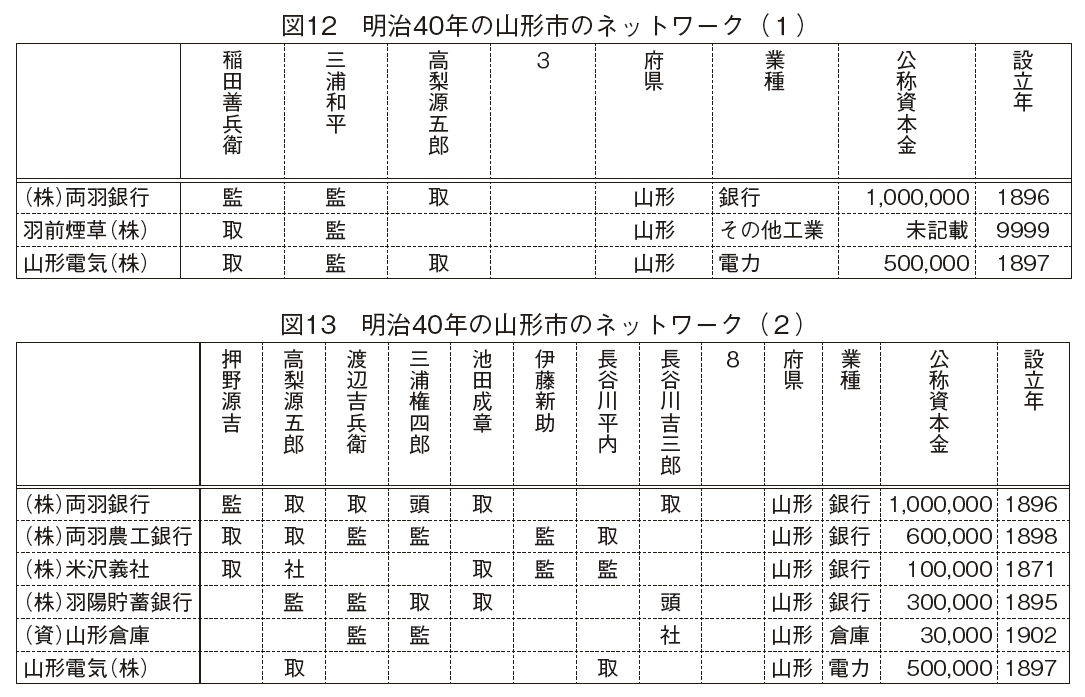
「東京寒河江商店」が含まれていることも分かる。東京寒河江商店の営業の目的は「織物製造有価証券売買金融仲介」であり,最初の事業を取り上げるという方針で作成した関係上,図では綿織物という業種分類がなされているが,必ずしも綿織物専業ではなく,我々が定めた業種で言えば,「その他金融」をも兼ねていたことに注意する必要がある。図15は,高梨源五郎と長谷川吉三郎を中心とし,両羽銀行と両羽農工銀行を中心とした山形市でのネットワークである。長谷川吉三郎は山形商業会議所特別議員を務めた人物で,多額納税者であった。図には登場しないが,長谷川吉内は,呉服太物商を営む先代の長谷川吉内の長男で,長谷川吉三郎の兄である12)。
(3)地域経済を巡る研究への本研究が有する意義
以上より,地方における企業家ネットワークの特徴が見られる。まず,人数の面でも会社数の面でも,明治40年から大正10年の間で,拡大していることである。関与した事業の面では,銀行と地域経済のインフラ産業に関わりつつ,その他の事業にまで拡張している。更に,大正10年には,地方のサテライト拠点として,東京への進出が見られる。人の面では,この間,共通な人物を確認できるものの,その役割は変化しているように思える。その反面,明治40年では必ずしも中心人物でなかった者が大正10年では中心を占めるようになっており,この間,企業家ネットワークを支えた人物についてはゆっくりではあれ,交替が見られることも指摘しておく必要がある。また,大正期における地方における企業家ネットワークの活動の意義を,当該期の地方・地域経済の研究成果を踏まえて,考察する必要がある。そこで,中村尚史 『地方
【126 頁】
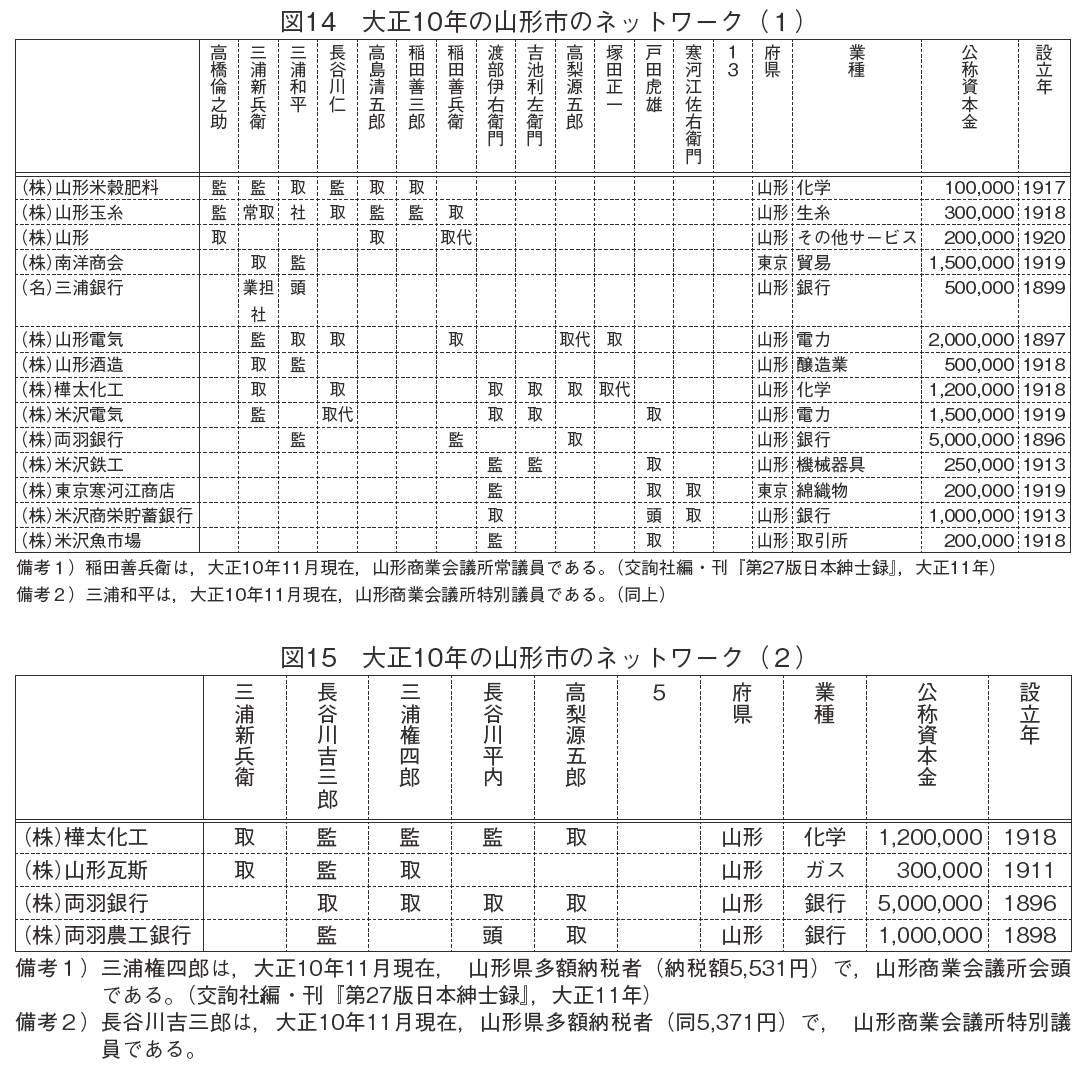
からの産業革命』 13)と石井里枝 『戦前期日本の地方企業』 14)を取り上げ,地方の企業家ネットワークの意義を考えていきたい。
中村氏は,その著書の中で,英語のlocal という意味で「地方」という用語を用いていると言い,地理的な概念ではなく,匿名性・非匿名性という人間関係を軸として分析を行っている。氏の論点を終章から整理しておこう。「明治期の地方における地域経済活性化は,地方工業化イデオロギーを共有する諸経済主体が,地域内外のネットワークを駆使して成し遂げたことが明らかになった」15)として企業家ネットワークの意義を評価する。この企業家ネットワークは,
【127
頁】
氏の考えでは,「郡レベルでの企業勃興では,工業化資金の供給をになう地方資産家と,事業計画と経営実務をになう地方企業家の双方が,互いの経営資源を持ち寄り,協力しながら事業を展開してきた」と言う。即ち,明治期には,企業家ネットワークの複合的な要素(地方資産家と地方企業家)を指摘しつつ,相互の協力によって郡や市レベルでの企業化を推進したのだという。では,この企業家ネットワークはその後,どのような軌跡を辿ったのだろうか。氏は二つのコースを提示する。第1のコースは,地方財閥の誕生である。「産業革命の進展とともに,地方企業家が資産を蓄積し,または地方資産家が経営能力を獲得して,地方にも資本と経営能力を兼ね備えた有力な企業家的資産家があらわれた」とし,そこから大規模化し多角化したものが「地方財閥」と呼ばれるようになった,と言う。第2のコースは,日露戦後から第一次世界大戦期にかけて大都市圏では,工場電化が急速に進展し,工業地帯が出現したとして,「工業地帯の形成による都市経済の急拡張は,結果的に地域経済構造における地方の地位を相対的に低下させた」16)と言う。即ち,「日露戦後に姿を現した近代日本の『都市の時代』は,以後,第二次世界大戦期にいたるまで,続くことになる」と結論する。ここでは,地方財閥以外の地方資産家は,日露戦後,都市の時代の流れの中で,一貫してその地位を低下させたと言うのである。
これに対して,石井里枝氏は,終章で「産業化に対して地方が主導的な役割を担った時期は,先行研究の多くが想定してきたような1880年代から1890年代に限定されるものではなく,少なくとも本書が対象とした1920年代までは,地方資本市場に企業発展を支えるダイナミズムが持続していた」17)とし,こうした「地方における産業化の波は,中央における近代化・産業化を下支え,その後の日本における企業発展をも強く推進する力となった」と評価する。対照的な点は二つある。第1点は,日露戦後に地方経済は低下したのか,それとも,少なくとも1920年代までは地方ではダイナミックな企業活動があったのか否か,である。第2点は,日露戦後に現れた「都市の時代」は,その後,地方経済の発展と両立して拡大していったのだろうか,それとも,地方経済の発展を取り込みつつ日本経済全体に拡がったのだろうか,という点である。
この問題に対しては,現在,我々が分析を進めている昭和11年版の『日本全国諸会社役員録』の結果を踏まえて評価を下すべきであるが,現時点での我々の考えを明らかにすることも必要であろう。『日本全国諸会社役員録』に記載されている会社数や資本金を指標にとれば,東京を中心とした「都市の時代」は確かに進行している。しかし,その反面,これまで記したように,それぞれの地方の主要地域では,人的な面での交替は見られたものの,企業家ネットワークは継続し,それぞれの地域経済の活性化に貢献していたことは疑問の余地がない。しかも,証券会社を舞台とした企業家ネットワークや朝鮮,台湾,満州と言った植民地などを舞台とした企業家ネットワークの台頭など,単純に「都市の時代」が続いたとは言えまい。しかも,それまでの渋沢栄一や,松本重太郎から,大倉喜八郎,安田善次郎,浅野総一郎への主役の交代,更には大橋新太郎,大川平三郎や田中栄八郎などの台頭,野口遵や塩原又策のような近代的な事業に関わった人物が登場する。昭和11年のデータでは,豊田利三郎や豊田喜一郎が多くの会社で役員として名を連ねているし,企業家ネットワークを作っている。このように,日本経済の発展に伴う産業構造の変化を反映して,それらの新しい産業・事業を担った人物やネット
【128
頁】
ワークにも同様の変化が見られるのである。即ち,第二次世界大戦期まで一直線に「都市の時代」に向かったと評価してしまうと,こうした産業構造の変化と会社の勃興,それら新興の事業を担った企業家の交替という側面を見失ってしまう恐れがある。
このような中心人物の交替という視点を忘れてはならない。それと同時に,中心人物の交替は,直ちに企業家ネットワークの縮小や消滅を意味するものではなく,むしろ拡大する場合もあることも忘れてはならない。これを念頭において,石井里枝氏が,終章で指摘した企業家ネットワークを実際に作成して確かめてみたい。氏は,群馬県の企業家を丹念に取り上げて分析を加えている。例えば,大澤惣蔵,大島戸一,武政恭一郎,須田宣などと並んで葉住利蔵が登場する。終章では葉住に言及して次のように記す。「地方企業家である大澤惣蔵が資金調達や役員就任のために参加を依頼した葉住利蔵は,地元群馬県におけるさまざまな要職を歴任する人物であり,かれをとりまく地方企業家・資産家のネットワークも広がった。こうした地元に基盤を有する人的ネットワークを利用することで,地方における企業設立や資金調達を容易に行うことができた」18)という。これを 『日本全国諸会社役員録』 (大正10年版)から確かめてみたい。葉住利蔵は明治40年版には,新田銀行の取締役頭取として1回登場する。この葉住利蔵の大正10年時点での企業家ネットワークを作成すると図16のようになる。ここには,武政恭一郎,須田宣,大島戸一の名前も見える。そして重要人物の根津嘉一郎の名前も見える。しかも,葉住と根津は利根発電と東武鉄道で要素ネットを形成しているのである。根津と2社以上,役員を共有している人物は葉住以外にはいない。このことからも葉住が有する人的関係,企業家ネットワークの意義は大きいことが理解できよう。この葉住も1926(大正15)年に死亡し,昭和11年のデータには登場しない。このように,中心人物の交替という視点も視野に入れながら,地方経済の発展に果たした企業家ネットワークの意義を再評価する必要があろう。
おわりに
これまでみてきた 『日本全国諸会社役員録』 (大正10年版)から明らかになったことを纏めておきたい。以前の研究でも記したように,役員録に記載されている会社は, 『帝国統計年鑑』 や 『府県統計書』 に記載されている会社と比較すると,資本金規模が大きい会社である。この
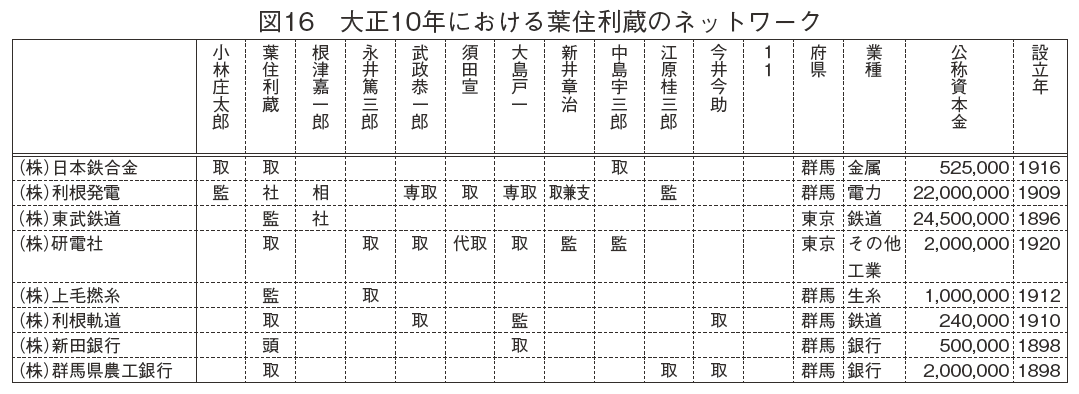
【129 頁】
ことを念頭において,大正10年の役員録で明らかになったことは,会社の面では,社数から見れば銀行や小売りが多いものの,明治40年に比べて相対的には減少していることである。一方,化学,機械器具,その他工業や紡織(その他繊維)の会社数は,相対的に増加している。即ち,この15年間の中で業種の変化が見られたことである。
次に,役員として登場する人物は,15回以上登場する人物類型から明らかなように,これまで登場してきた資産家や様々な財閥関係の者に加えて,証券会社に深く関わった人物や満州などの植民地の企業化に深く関わった人物,専門経営者や学者・公務員などの出自の人物,更には新興財閥の中心人物までもが登場している。明らかに,それまでとは違った人物が会社役員として,企業家ネットワークを作り上げているのである。
一方,地方に目を転じると,明治期から継続しているネットワークが確認できる。この間,親子への代替わりや中心人物の変化が見られたものの,一貫して企業家ネットワークは銀行やインフラ産業に深く関わっていたことが確認できた。また明治31年や明治40年で見られた企業家ネットワークが,依然として存在することである。
以上のように,大正10年でも企業家ネットワークは存在していただけではなく,数の面でも増加している。なぜ企業家ネットワークは存在していたのだろうか。
第1は,イギリスやアメリカにおける工業化では,家族企業やパートナーシップによる事業化が一般的であったが,後発国の日本では,企業家が蓄積していた資産では十分でないほどの巨額な資金が必要な産業に関わらざるを得なかったために,早期から株式会社形態を採用せざるを得なかったという資金的な制約のためである。第2に,ところが,株式会社を設立するには,7人以上の発起人が必要であると商法で規定されているために,顔が見える人間関係に基礎をおいた「仲間」を必要とする制度的な要因である。第3は,新しい産業企業が簇生する中で,信頼のおける情報源は,同業者や近隣の者という人的関係を通じて,利用できたということである。第4に,利益は,内部留保や積立金という形で企業内部に蓄積することは出来ず,配当として社外に流出せざるを得なかったために,従来の関係者を糾合して新会社を設立しなければならないという企業統治に関する問題であった。これらの4つの問題が相互に関わって,新しいビジネスチャンスが企業家ネットワークの中で意識された時,彼らの人的ネットワークを利用して新たに発起人を募って設立しなければならなかったという事情が大きかったように思われる。そうであればこそ,第1次世界大戦期のように新しい事業機会が開かれた時期では,各地でこうした人的関係を基にした企業家ネットワークが簇生していったのである。しかも,個人や家業としてではなく,共同で出資するから,多少のリスクがあってもリスクが分散するために,ビジネスチャンスに対応しやすいこともあったであろう。その結果,大正期に入っても,明治期より人物でも会社でも拡大した企業家ネットワークが生まれていった。その反面,経済が停滞したり,ビジネスチャンスがなかなか生まれにくい時代では,企業家ネットワークの拡大は見られなかったといえよう。その中で,継続した企業家ネットワークを子細に眺めると,中心となる人物の交替や親子への代替わりが見られたことに注意する必要がある。
一方,大正時代から昭和戦前期には,徐々に財閥以外にも合併を通して大会社になった綿紡績企業に見られるように,株式の分散を反映して専門経営者が台頭することになった。それに伴って収益をすべて配当に還元するのではなく,子会社の設立などにも使われるようになった。その代表が綿紡績会社によるレーヨン企業の設立である。昭和11年の役員録には,こうし
【130
頁】
た大会社の子会社も多数含まれている。従って,企業家ネットワークの中には,従来からの共同出資による会社設立を通した企業家ネットワークと並んで専門経営者達による子会社を巻き込んだ企業家ネットワークも生まれてきたことに注意することが必要である。
最後に,わが国株式発行市場の特徴と「企業家ネットワーク」との関連についてふれておきたい。ここでは正木久司氏の所論をとりあげておくこととする。正木氏は,日本の株式会社金融の分析の一環として,わが国株式発行市場の「未発達の実態」とその「原因」について考察している。氏は,戦前・戦中および戦後(昭和40年代半ば頃まで)の株式発行市場の分析を行うことにより,その構造上の特徴として,新設会社の株式発行形態が発行会社の自己募集であること,また額面発行・株主割当が支配的であることを指摘し,これらが,たとえばアメリカの発行形態に比べ未発達なものであるとする。さしあたり,われわれの関心のある戦前期に限定して氏の行論を要約すると次のようである。
わが国では,工業化の初期から,株式は「発行主体自ら発行危険を負担する直接発行,それ
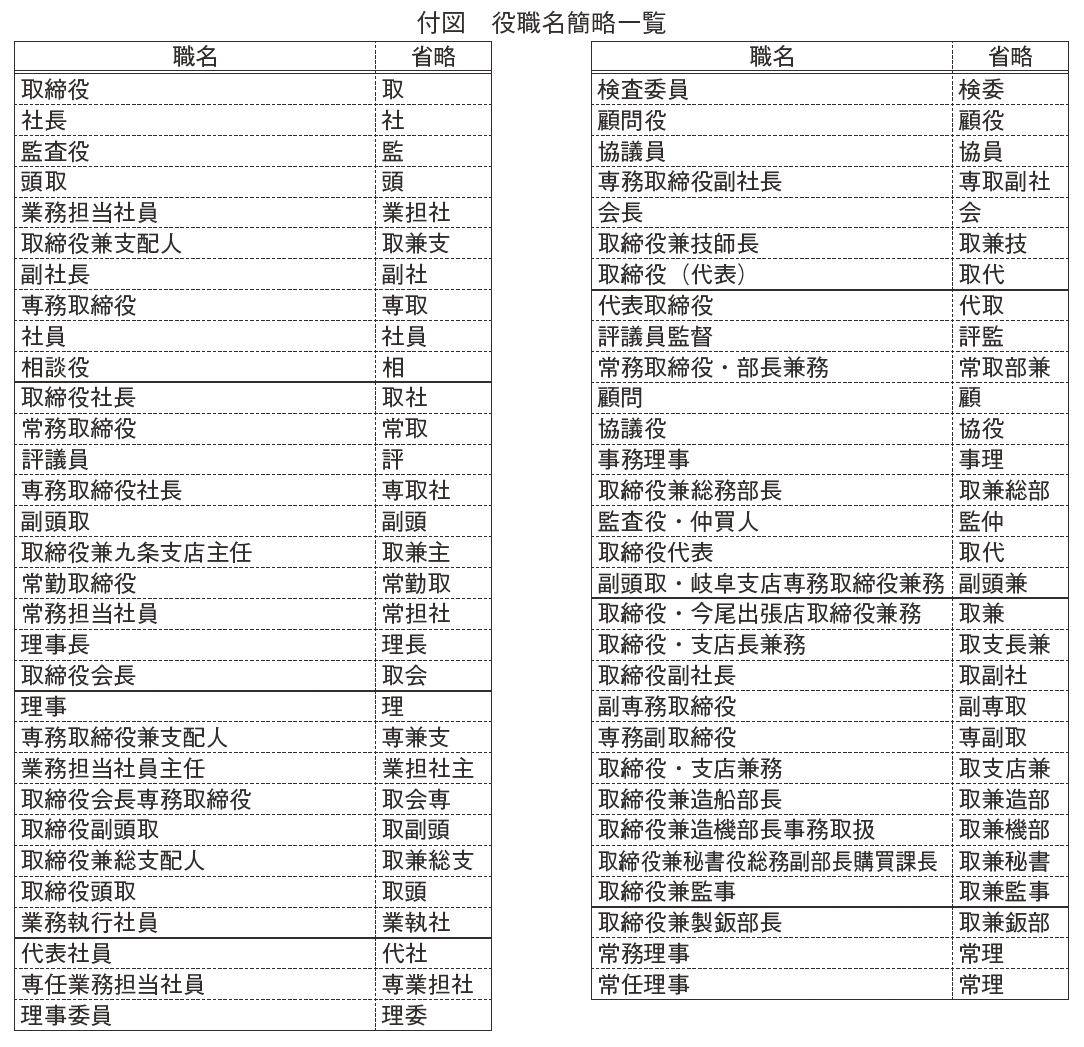
【131 頁】
も非公募発行が支配的であり」,「したがって,企業が株式発行により資本を調達するにあたって,アメリカの投資銀行のごとき役割を持つアンダーライターを,それほど必要としなかった」19)。わが国の銀行は,株式募集の取扱店として委託された募集事務の一部を取り扱ったのであり,証券業者による株式の引受業務も限定的であった。また,額面発行という株式の発行形態が慣行化しており,かつ総額引受主義は大衆資本の動員を困難にするとともに増資新株の株主割当を不可避とした。発行会社にとって,増資新株の公募消化は困難であった。
わが国株式発行市場のこうした特徴を助長したのが,「日本資本主義経済の後進性」20)であり,それにともなう「資本蓄積の貧困」であった。「株式資本の供給層は多数の大衆投資者で形成されず,一部の富裕階層および法人企業に限定され」ることになった。また富裕階層の資本の限界をカバーする措置として機能したのが,引受株式に対する株金払込の方法,すなわち分割払込制度であり,株主に対する銀行の株式担保貸付であった。
正木氏の上記の指摘と,われわれのテーマとを関連付けて論じることは今後の課題とするが,少なくとも,われわれの言う「企業家ネットワーク」こそ,株式「発行危険を負担」し,かつアンダーライターを代替した中心的な主体であった,といえるのではなかろうか。
謝辞
本稿は,商業興信所編・刊 『日本全国諸会社役員録』 (大正10年版)をデジタル・データ化し,その分析に基づき作成したものであるが,データベース化するに際し,同書(オリジナル)を,明治大学名誉教授・公益財団法人三井文庫業務執行理事,由井常彦先生にお借りしました。貴重な資料を快くお貸しくださった由井先生に対し,末筆ながら,心より御礼申し上げさせていただきます。