�y151 �Łz
�h�C�c�E�I�����_�ɂ�����_��ȓ�����
�����@����C�e��@�@��
�P�D�����̖ړI
�{�����̖ړI�́C���[�N�E���C�t�E�o�����X�i�ȉ��CWLB�j�̎�g���i�ރI�����_�ƃh�C�c�̊�Ƃɂ�����E��}�l�W�����g��l���Ǘ��ɂ��āC���{��ƂƔ�r���邱�Ƃ�ʂ��Ă킪����WLB���i�ւ̎����邱�Ƃɂ���B
�@���{���͂��߁C�C�O�����ɂ����Ă����q���⍂��ւ̑Ή��Ƃ��ď]�ƈ���WLB�x���̕K�v��������ċv�����B�������Ȃ���C���{��EU�����ł͊�Ƃœ����]�ƈ��̓������ɑ傫�ȈႢ������B���i2012�j�ɂ��C���{�ƊC�O�S�J���i�C�M���X�C�h�C�c�C�I�����_�C�X�E�F�[�f���j�̘J�����Ԃ⓭�����́C�C�O�S�J���ł͏T�̘J�����Ԃ�45���Ԗ����Ƃ���J���҂��W�`�X�����x����̂ɑ��C���{�͂U�����x�ɂƂǂ܂�B�܂��C�������ɂ��Ă����{�͂S�J���ɔ�ׂăt���b�N�X�^�C���Ζ���ݑ�Ζ��Ȃǂ̓���������ї��p�������ɒႢ�B����ɂ͂S�J���ł͎n�Ǝ��Ԃ�I�Ǝ��Ԃ̕��U���傫���̂ɑ��C���{�͓��ꎞ�ԑтɕ�X��������B�S�̂Ƃ��ē��{�͓����������I�ł���Ƃ�����B
�@���������w�i�ɂ��āC�����i2012�j�́C�����i2009�j����t�{�o�ώЉ���������i2009�j���Q�l�ɕ��i2012�j�Ɠ����f�[�^���g���C�l���Ǘ��̊ϓ_���狋�^�Əܗ^�̌���v�f�̈Ⴂ���C�O�S�J���Ɠ��{�Ŕ�r���Ă���1�j�B����ɂ��ƁC���{�͐E�����s�\�͂�l�Ɛт��d���������C���N��̋��^�̊i���͂S�J���ɔ�ׂď������C�\�͍������m�ɕt���Ȃ��X��������B����ɁC���{�ƃh�C�c�E�C�M���X�̏]�ƈ������̃f�[�^��p���Ē����x�Ǝ҂�Z���ԋΖ��҂��E��ɏo���ꍇ�̐E��l����Ɩ��̂��J����r�����Ƃ��뗼���ł͐��Ј��͂��Ƃ��C�Ј��̘J�����ԁC�ٓ��C�l������������ŋ�g������Ɩ��ʂ�Ɩ����e���������ȂǑ��l�ȕ��@��p���Ă��邪�C���{�͐��Ј��̘J�����Ԃɂ�钲���ɕ�X�����݂�ꂽ�B�킪���̐l���Ǘ��́C�_��ȓ��������\�ɂ���d�g�݂ֈڍs���Ă��Ȃ������łȂ��C�E��}�l�W�����g�ɂ����Ă��_����Ⴂ�B
�@�ȏ�̂��Ƃ܂��C�M�҂��͂��߂Ƃ���w�K�@��w�̌����`�[����WLB�Ɛ����I�Ȑl��
�y152
�Łz
�Ǘ��V�X�e�����l�@���ׂ��C2012�N�x�ɉȌ���ɂ�钲�����J�n���C2013�N�x�ɃI�����_�ƃh�C�c�̊�Ɓi�v�T�Ёj�̋��͂āC��ƂƂ��Ă�WLB�x���̎�g��Z���ԋΖ��ғ����͂��߂Ƃ���WLB�֘A���x�̗��p�҂��Ɏ���i�ɐE��}�l�W�����g�Ɋւ���C���^�r���[�����{�����B�{�e�ł́C���C���^�r���[������ʂ��Ĉȉ��̓_�𖾂炩�ɂ���2�j�B
�@���ɁC�����̊�Ƃɂ�����WLB�̎�g�ł���B��̓I�ɂ͏_��ȓ������Ɋւ��鐧�x���p�҂̑��l�����l�@����B���x���p�҂��j���Ƃ��Ɋ��p����C����E�ɂ��肪�Ȃ���ΐE���WLB�����x�͍����Ƃ�����B���i2012�j�ł́C�C�O�S�J���ł͏_��ȓ�����������J���҂��������Ƃ��w�E���Ă������C�{�����ɂ����Ă�������m�F����B
�@���ɁC�L�����A�v���Z�X���]�ƈ��i�����j�ւǂ��܂Ŗ������Ă��邩�ł���B���{��Ƃɂ́C����E�ʂɏA���܂ł̖ڈ��̔N�������邪�C��Ƃ�E�ꂪ�K����������m�ɏ]�ƈ��Ɏ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�܂��C����E�ʂɏA�����߂ɕK�v�Ȍo����\�͂��K��������������Ă��Ȃ��BKato, Kawaguchi, and Owan�i2013�j�́C���{��Ƃ̓����J���s��͒j���ŕ��f����Ă���C�����̏ꍇ�̓V�O�i�����O�ɂ��g�D�R�~�b�g�����g�̍����l��I�����Ĉ琬���Ă����̂ɑ��C�j���̏ꍇ�̓��b�g���[�X�ύt���`������Ă���C�x�����i�i�I���j�C�N���Ǘ��ɂ�蒉���S�̍����l�ނ̈琬�ɗL���ɋ@�\���Ă���Ƃ��Ă���B�܂�C���{�̓L�����A�A�b�v�ɕK�v�ȃv���Z�X���B���ł��邽�߁CWLB���K�v�Ȏ����ł����ʓI�ɏ��i�ӗ~�̍����ҁi���ɒj���j�قǁC�_��ȓ�������I���ł����C�]���ʂ�̓������ɏ]�����Ă��܂��\��������B�{�����ł́C�����Ώۊ�Ƃ̃L�����A�v���Z�X���ǂ��܂ŏ]�ƈ��ɖ������Ă��邩�ɂ��čl�@����B
�@��O�ɁC�Z���ԋΖ����͂��߂Ƃ���_��ȓ������Ɋւ��鐧�x���p�҂��E����ŏo���ꍇ�̐E��^�c���@�ł���B���ɁC�킪���ł͒Z���ԋΖ��̏ꍇ�́C�s�݂ɂ��鎞�ԑт̋Ɩ���N����ւ���̂��C���̍ۂ̕�V��]�����ǂ����邩���ۑ�ɂȂ��Ă���B�{�����ł́C�Z���ԋΖ��҂ɔz�������d�����e�����łȂ��C�Z���ԋΖ��҂��s�݂ƂȂ鎞�Ԃ̋Ɩ��̑�֕��@��v���Ǘ��ɂ��ē��{�Ƃ̈Ⴂ���l�@����B
�@�{�e�̍\���͈ȉ��ł���B���߂ł́C�����Ώۍ��ƂȂ����h�C�c�C�I�����_�̏_��ȓ������ɌW��@���x�⏼���i2012a�j�Ŏg�p�����f�[�^���ĕ��͂��C���{�C�h�C�c�C�I�����_��WLB�֘A���x�̗��p�҂̑��l���ɂ��čl�@����B��O�߂ł́C�h�C�c�C�I�����_�̊�Ƃɑ���C���^�r���[�������ʂ�萫�I�ɕ��͂��C�Ō�ɑ�l�߂ŕ��͌��ʂ̗v��Ǝ������q�ׂ�B
�Q�D���{�C�h�C�c�C�I�����_�̓�����
�{�߂ł́C�܂��h�C�c�ƃI�����_��WLB������T�ς�����ɁC�M�҂̈�l��2008�N�`2010�N�܂ŎQ�������i�Ɓj�o�ώY�ƌ�������WLB������ɂĎ��{�����u�d���Ɛ����̒����iWLB�j�Ɋւ��鍑�۔�r�����v�̃f�[�^���ĕ��͂��C���{�ƃh�C�c�C�I�����_�̓������̈Ⴂ���l�@����B
�y153 �Łz
�i�P�j�@�h�C�c�C�I�����_�̓������̏_��ւ̎�g
�h�C�c�C�I�����_��WLB����́C���[���b�p�A���iEU�j��1997�N�ɔ�y�������[���b�p�ٗp�헪�����2000�N�ɍ̑������u���X�{���헪�v�Ɛ[���֘A���Ă���B�����̐헪�́C�����⍂��҂̏A�Ɨ��㏸�ƁC���q���w�i�ɂ���CEU�����ɂ͂��̐헪�ɑ������@���̍�����̐��s���`���t�����Ă���B���ɁC���X�{���헪�����\����Ĉȍ~�CEU��������WLB����w���i���C���ł��o�Y�x�ɂ�玙�x�ɂ̊g��ƕ��y�C�玙�{�݂̏[���Ɋւ��鐭��ɗ͂����Ă���B���̌��ʁCEU�������̏����A�Ɨ��́C���[���b�p�ٗp�헪����y���ꂽ1997�N�ɂ́C��v15�J���̕��ς�50.8���ł������̂��C2007�N�ɂ�59.7���܂ŏ㏸�����B�������C�����A�J�҂̑����̓p�[�g�^�C���J���ł���B�j���́u�傽��҂���v�C�����͉Ǝ��E�玙��S������Ƃ���EU�����ɂ����邱��܂ł̍\�}�͓��{�ƕς��Ȃ��B���̒���EU�����Ɠ��{�Ƃ̈Ⴂ�́C�O�҂ł͋Ɩ����e�������ł���ꍇ�C���^�ȊO�̘J���������t���^�C���J���҂ƃp�[�g�^�C���J���҂Ƃŋύt�ɂ���|��@���ŋ`�������Ă���_�ł���B���ł��I�����_�́C1982�N�́u���b�Z�i�[���Ӂv���N�_�Ƃ��āu�p�[�g�^�C���J���̑��i�v�Ƃ�������𐄐i���CEU�����ɐ�삯�ď����A�Ɨ������߂Ă����Ɠ����ɁC����J���E���������J�����Ԃ̒Z�k�����������Ă���i��q�j�B
�@�܂��CEU�����ł́C�o�Y�x�ɂȂǂ̊g�[����łȂ��C�J�����Ԃ̒Z�k�ɌW��c�_�������ɍs���C�ߔN�͏_��ȘJ�����Ԑ��x�̓����Ɏ�g�ލ��������Ȃ��Ă���B�Z���ԋΖ����x�C������EU�����ɂ�����p�[�g�^�C���J���́C�����̏A�Ɨ������߂邽�߂̏_��ȓ������Ƃ��ĐϋɓI�ɓ������ꂽ���C�O�q�̂Ƃ���C�J�����Ԃ̒��Z�Ɋւ�炸�C�J�������̕ύX�͕ς��Ȃ����̂́C�ƒ�̎���Ńt���^�C������p�[�g�^�C���Ɉڍs����Ύ����͒Ⴍ�Ȃ�B�����������������������WLB�{��Ƃ��āC�ߔNEU�����ł́C�J�����Ԃ��_��ɂ�肭�肷���g�𐄐i����X���ɂ���B�i�Ɓj�J�������E���C�@�\�i2008�j�ɂ��C�u���B�����J���������P�c�́v�iEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Condition�j��2004�`2005�N�Ɏ��{������R���WLB��ƒ����ɉ�����Ƃ̖�95���C10�l�ȏ�̏]�ƈ��������Ƃł�48�����_��ȘJ�����Ԃ���邽�߂̉��炩�̎{������{���Ă���B�h�C�c�̓X�E�F�[�f���C�t�B�������h�C�f���}�[�N�Ȃǂ̖k�������ƕ���ōł��_��̍������x���{�s���Ă����Ƃ̔䗦�������C���ł��C�h�C�c�́u�J�����Ԓ��~���x�v�́C�V�����J�����ԃ��f���Ƃ��ď_��ȓ������̈�Ƃ��Ē��ڂ���鐭��ƂȂ��Ă���i��q�j�B
�@�ȏ�̂悤�ɁCEU�Ƃ��Ă�WLB�ɌW���g�͓���̕��j�ɉ����Ă��邪�C�e�����d�_�I�Ɏ��g�ސ���̓��e�͗l�X�ł���B�ȉ��ł́C�h�C�c�ƃI�����_��WLB����̊T�v�ɂ��ďq�ׂ邱�ƂƂ���B
�@�h�C�c�ɂ������g
�h�C�c�ɂ�����WLB�̎�g�́C1990�N�ȍ~�ɐ[���������o�����̒Ⴓ�ƁC����ɔ������q����̉����C�����J���̖͂����p�C�O���[�o���s��ɂ�����o�ϋ����͂̒ቺ�ւ̕s���Ȃǂ��w�i�ɂ���B�����ł́CWLB������I�ɎЉ�I���{�y�ѐl�I���{�⎝���I�o�ϊ�����ۏႵ�������Ă����d�v�Ȍ��ł���C�h�C�c�̎����\�ȎЉ�̎����ɂȂ��鐭��ł���ƈʒu�Â��Ă���B
�@�����ł́C�h�C�c��WLB�ɌW�錻�s�@���x�̂����C�u�q��ĂɊւ���x�ƁE�x�Ɂv�C�u�J�����ԁv�C�u�_��ȓ������v�̂R����̎�Ȏ{��ɂ��ďЉ��B
�y154 �Łz
a�D�q��ĂɊւ���x�ƁE�x��
�u�q��ĂɊւ���x�ƁE�x�Ɂv�ɂ��ẮC�u�玙�x�Ɛ��x�v�C�u�玙���Ԓ��̋��t���x�v����������B
�@�u�玙�x�Ɛ��x�v�́C�u���e���ԁv�Ƃ��Ă�C2006�N12���Ɂu�A�M�e�蓖�E�e���Ԗ@�v�̒��Œ�߂��Ă���B�����x�́C���ꐢ�тŐ������C���̎q��{�炷���p�҂Ɏq�ǂ������R�ɂȂ�܂ł̍��v36�J���̈玙�x�Ƃ𐿋����錠����^������̂ł���B���̂����P�N������ɁC�g�p�҂̓��ӂ�����Ύq�����W�ɂȂ�܂Ŋ��Ԃ��J�艄�ׂ邱�Ƃ��ł���B�����x�́C���e�̂ǂ��炩���P�ƂŁC�܂��͗��e�����Ɏ擾���邱�Ƃ��ł���ق��C�g�p�҂̓��ӂ�����C�T30���Ԉȓ��̏A�J���s�����Ƃ��ł���B
�@�u�玙���Ԓ��̋��t���x�v�ɂ��ẮC����܂ł͈玙�x�Ƃ���҂Ɏq�ǂ�������24�����ɂȂ�܂Ō�300���[�����x�����Ă������C2006�N�ɁC2007�N�P���P���ȍ~�ɐ��܂ꂽ�q�ǂ��̗{��҂ɑ��āC���e�蓖�Ƃ��Ďx��������̂֕ύX���Ă���B���e�蓖�̊�{�x�����z�́C�q�̏o�Y�O�̕��ϒ�����67���i�������C1800���[��������z�C300���[�����Œ�z�Ƃ���j���x�������B���蓖�̍Œ����Ԃ�14�J���ł��邪�C�ǂ��炩����̐e�����玙�x�Ƃ��Ȃ��ꍇ�C���Ԃ�12�J���ƂȂ�B�܂�C���e����e�̑���ɂQ�������x�̈玙�x�Ƃ܂��͈玙�Z���ԋΖ��i�T30���Ԉȓ��̒Z���ԋΖ��ł��\�j���s�����Ƃ�z�肵���u�p�[�g�i�[���v�Ɋւ���K��ƂȂ��Ă���B
�@����������g�̌��ʂɂ��C�j���̗��e�蓖����2007�N������12�����x�ł��������C�ߔN�͖�25�����x�܂ő������C�j���̏_��ȓ������̒蒅�Ɉ���Ă���B
b�D�J������
�h�C�c�̌Œ�I�Ȑ��i�̋����J�����Ԑ��x�͘J���g���̉e�������邪�C�D���Ȍo�ϐ����ɂ�蒷���Ԉێ�����Ă����B�ߔN�́C�Y�ƍ\�����d�H�Ƃ���T�[�r�X�Ƃ֕ω��������Ƃ�O���[�o�����ɔ������ۋ����͂̌����ɔ����C�J�����Ԃ̒Z�k�����łȂ��C�u�������̏_��v���e�[�}�Ƃ����V���ȘJ�����ԃ��f�����J�g�ŋ��߂���悤�ɂȂ��Ă����B
�@���ł������I�Ȑ��x���u�J�����Ԍ������x�v�ł���B�����x�́C�J���҂���ƂŎc�Ƃ������Ԃ�J�����Ԍ����ɒ��~���Ă����C������x�ɓ��̖ړI�ōD���Ȏ��Ɏg����d�g�݂ł���B�����x�́C�P���̘J�����ԁC�T�̘J�����Ԃ����̕��̒��ŕϓ������邱�Ƃ��ł���B�������C�ϓ����F�߂�����Ԃ̕��́C����C��ƁC���ƕ����ɂ��قȂ��Ă��悢���C�J�����Ԃ̉����܂��͒Z�k�̂�����̕����ւ̕ϓ��������Ԃ̊Ԃɕ��ω����C�J������܂��͌ʊ�ƃ��x���œ��ӂ��ꂽ���ϘJ�����ԂƓ��������邱�Ƃ����߂��Ă���B
�@�J�����Ԍ������x�̃����b�g�́C��ƂƏ]�ƈ����ʏ�̘J�����Ԃ̋����S������������邱�ƁC�_��ȘJ�����ԕҐ����\�ł��邱�ƁC�]�ƈ��͒Z�����Ԃ�ςݗ��ĂĎd���Ɖƒ�̗������\�ɂȂ邱�ƂȂǂ���������B�Ȃ��C�J�����Ԍ����ɂ́C�P�N�ȓ��ɐ��Z����u�Z�������v�ƁC�����I�X�p���ŘJ�����Ԓ������\�ɂ���u���������v�����邪�C��҂����Ă����Ƃ͂V�����x�Ƒ����͂Ȃ��B
c�D�_��ȓ�����
�u�_��ȓ������v�ɂ��ẮC��Ɂu�p�[�g�^�C���Ζ��v�C�u�W���u�V�F�A�����O�v�C�u�ݑ�Ζ��v����������B���̂����C�u�p�[�g�^�C���Ζ��v�C�u�W���u�V�F�A�����O�v�́C2001�N�́u�p�[
�y155
�Łz
�g�^�C���J���E�L���J���_��@�v�ɂ���������ŋK�肳��Ă���B
�@�u�p�[�g�^�C���Ζ��v�ɂ��ẮC�p�[�g�^�C���J���𑣐i����ړI����C�]�ƈ�15�l�ȏ�̎��Ə��łU�����ȏ㓭���J���҂��J�����Ԃ̏k����ύX����]�����ꍇ�́C�o�c��x�Ⴊ�Ȃ�����C�����F�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă���3�j�B�܂��C�Z���Ԃœ����Ă���p�[�g�^�C���J���҂��C�J�����Ԃ̉����i���̃t���^�C���ɖ߂�Ȃǁj����]���邱�Ƃ��\�ł��邪�C���@�ł́C�t���^�C���J���ւ̕��A���͋K�肵�Ă��Ȃ��B�������C�g�p�҂́C�t���^�C���̃|�X�g���[����ہC�����������o�c��̗��R�܂��͑��̃p�[�g�^�C���J���҂̊�]�������W���Ȃ�����C����̓K���E�\�͂ł��邱�Ƃ������ɁC���̃p�[�g�^�C���J���҂̊�]��D��I�ɍl�����邱�Ƃ��K�肳��Ă���B
�@�u�W���u�V�F�A�����O�v�ɂ��Ă��O�q�̖@���ŋK�肳��Ă���B�Ɩ��̕����̎d���́C�P���̋Ζ����Ԃ��ߑO�ƌߌ�ŕ�������@�C�P���u���Ō�シ����@�C�T���邢�͌��P�ʂŌ�シ����@�ȂǗl�X�ł���B���J���`�Ԃɂ́C�Ɩ��������ŐӔC���Ȃ���J���|�X�g������u�W���u�E�y�A�����O�v�ƁC�X�̋Ɩ����݂��ɓƗ����ċΖ�����u�W���u�E�X�v���b�e�B���O�v�̂Q�p�^�[��������B
�@�u�ݑ�Ζ��v�ɂ��ẮC�ݑ�Ζ��ɂ�����Ζ��`�ԁC�]�ƈ��̒n�ʁC����ł̋@��C�E�����e���J������⎖�Ə�����ŋK�肳��Ă���B�ߔN�̏�Љ�̔��B�ɔ����C�Ζ����Ԃ̏_������łȂ��C�Ζ��ꏊ���_����Ȃ���J�����Y�����ێ��E���シ�铭�����Ƃ��āC���̎�g�����i����Ă�����̂ł���B
�A�I�����_�ɂ������g
�I�����_��WLB����́C�ٗp�̏_��̉��v�Ƃ��Đ��J�g�O�҂̍��ӂɊ�Â��C�J�����ԋK���̊ɘa�ƃp�[�g�^�C���J���̑��i����ɐ��i����Ă����Ƃ������������B�����ł͎�ɁC�u�_��ȓ������v�ɂ�����p�[�g�^�C���J���ƃe�����[�N�i�ݑ�Ζ����x�j�ɂ��āC�u�d���ƈ玙�̗����x���v���Љ��B
a�D�_��ȓ�����
�I�����_��WLB�����̌��́C�܂��Ɂu�p�[�g�^�C���J���v�̑��i�ł���B�����ɂ�����p�[�g�^�C���J������́C1982�N�́u���b�Z�i�[���Ӂv�ɂ��n�܂��Ă���4�j�B����i2001�j�ɂ��ƁC�I�����_���p�[�g�^�C���ٗp�𑣐i�����w�i�ɂ́C�P�j���b�Z�i�[���ӂɂ������}����ɂ��C�������ɂ����������̌�����h�����Ƃ������ƁC�Q�j�I�����_�̎Y�ƍ\���ɂ����閯�ԃT�[�r�X����̐������p�[�g�^�C���J���̎M�ƂȂ������ƁC�R�j�I�����_�ɍ������c��j�����Ƃ̍l���������钆�ŁC�p�[�g�^�C���J���������̘J���s��Q���̕~����Ⴍ�������ƁC�S�j���������j�����ƈӎ��ɂ��C�����ł͕ۈ�{�݂̏[�����Ȃ��Ȃ��i�܂Ȃ��������Ƃ̂S�̗v��������Ǝw�E���Ă���B
�y156 �Łz
�I�����_�ł́C1990�N��ɂ̓p�[�g�^�C���J���Ɋւ���@���������Ȃ�i��ł������C1996�N�̘J�����ԍ����ʋ֎~�@�ɂ��C�����E�蓖�E���������E�E��P���E��ƔN���Ȃǂ̑S�Ă̘J���������C�p�[�g�^�C���J���҂ƃt���^�C���J���҂Ƃœ���̌������ۏႳ���悤�ɂȂ����B
�@����ɂ́C2000�N�́u�J�����Ԓ����@�v�ɂ��C�]�ƈ�10�l�ȏ�̊�ƂłP�N�ȏ�ٗp���ꑱ���C���ߋ��Q�N�ԂɘJ�����Ԃ̕ύX�����߂Ȃ������J���҂ɑ��ẮC���ԓ�����̒������ێ������܂܂ŁC����̘J�����Ԃ�Z�k�E�������錠�����F�߂���悤�ɂȂ����B�Ȃ��C���@�ł́C�g�p�҂͂ł��邾���t���^�C���J������p�[�g�^�C���J���ւ̓]����]�C�܂��̓p�[�g�^�C���J������t���^�C���J���ւ̓]����]���l�����ׂ��ł���Ƃ��Ȃ�����C��ƂɂƂ��Đ[���Ȗ�肪������ꍇ�́C���̐\�������ۂł�����̂Ƃ��Ă���B
�@����C�e�����[�N�i�ݑ�Ζ����x�j���ߔN�̃I�����_�ɂ�����WLB�𐄐i���邤���ł̏d�v�Ȏ�g�ƂȂ��Ă���B�����x�̓����͘J�g�̎���I��g�݂ɔC����Ă���C��ƋK�͂��傫���قǓ������͍����B2008�N�̃I�����_���v�ǂ̒����ɂ��C�����x�̓������͏]�ƈ�10�`19�l��38���C250�`499�l��87���C500�l�ȏ��91���ł���C�����ɔ�ׂč��������ƂȂ��Ă���5�j�B
b�D�d���ƈ玙�̗����x��
1991�N�Ɉ玙�x�Ɛ��x���n�݂��ꂽ���C2009�N�P���Ɏq�ǂ����W�ɂȂ�܂ł̊ԂɏT�J�����Ԃ�26�{�̎��ԁi�N�ԁj�܂ŗ��e�����ꂼ��x�Ƃł��鐧�x�֕ύX�ƂȂ��Ă���B���ۂɂ́C�T�J�����Ԃ�Z�����p�[�g�^�C���œ����Ƃ��������p���@����ʓI�ł���B�܂��C�擾���Ԃ����Ď擾���邱�Ƃ��\�ł���B�x�ƒ��̏����ۏ�̐����́C�J�g�̎���I�Ȏ�g�ɔC����Ă���C���I����ł�75���̏������ۏႳ��Ă���B
�i�Q�j�@�h�C�c�C�I�����_�ɂ�����WLB�֘A���x�̗��p��
�ȏ�̊e���̖@�I�����܂��C���{�C�h�C�c�C�I�����_�̓������̈Ⴂ���f�[�^��p���čl�@����B
�@�\�P�́C���{�C�h�C�c�C�I�����_�̃z���C�g�J���[�E�̐��Ј���Ώۂɍs�����u�d���Ɛ����̒����i���[�N�E���C�t�E�o�����X�j�Ɋւ��鍑�۔�r�����v�i�]�ƈ������j��p�������ʂł���B�Ȃ��C�I�����_�̓T���v���������Ȃ����߁C�ȉ��ł͎�ɓ��{�ƃh�C�c�𒆐S�ɔ�r����B
�@���݂̋Ζ���ł̏_��ȓ������Ɋւ��鐧�x�̗��p�o���������˂��Ƃ���C���{�͊e���x�Ƃ��h�C�c�ɔ�ׂė��p�������ɒႢ�B��̓I�ɂ́C�u�玙�x�Ɓv�́C���{�́u��E�v�v��6.6���C�u��ʎЈ��v�ł�8.5���C��E�t���ɂ��Ă͂S�����x�ł��邪�C�h�C�c�́u��E�v�v��16.0���C�u�ے��v��15.8���C�u�����ȏ�v��14.5���Ɠ��{�̂R�{�ȏ�ƂȂ��Ă���B�u�玙�̂��߂̒Z���ԋΖ����x�v�ɂ����Ă��C���{�ł́u��E�v�v��2.7���ŁC��E�t���ł͂Q�`�R�����x�ł���̂ɑ��C�h�C�c�́u��E�v�v��17.5���C��E�҂ł�20���O��ƂȂ��Ă���C�Ǘ��E�ł��_��ȓ������𗘗p�ł��Ă��邱�Ƃ��킩��B�Ȃ��C�Q�l���x���ŃI�����_�ɂ��Ă݂�ƁC�����ł��玙��玙�ȊO�̗��R�ɂ��Z���ԋΖ����x��t���b�N�X�^�C���Ζ��C�ݑ�Ζ����x�Ȃǂ�
�y157 �Łz

���p�͑����C�玙�̂��߂̒Z���ԋΖ����x��ݑ�Ζ����x�́C�����ȏ��40���������p���Ă���_�͋����[���B
���ɁC���݂̓���������{�ƃh�C�c�Ŕ�ׂ����ʂ��\�Q�ł���B���݁C�ǂ̂悤�ȓ����������Ă��邩�������˂��Ƃ���C���{�́u�t���^�C���̒ʏ�Ζ��v��������̐E�ʂł�90���ȏ���߁C�u�t���b�N�X�^�C���Ζ��v�Ɓu�ٗʘJ�����v�����ꂼ��u��E�v�v��6.8���C2.1���C�ے��╔���E�łR�`�T�����x�ƂȂ��Ă��邪�C���̂ق��̓������ɂ��Ă͂قƂ�Ǘ��p����Ă��Ȃ��B����C�h�C�c�ł́C�u�t���^�C���̒ʏ�Ζ��v���ǂ̐E�ʂł�70���O��ƍł��������̂́C�u�t���b�N�X�^�C���Ζ��v��30�����x�����p���Ă���B�܂��C�u�ݑ�Ζ��v�́C�u��ʎЈ��v��5.6���ł���̂ɑ��C�u�����ȏ�v��10���ȏオ���p���Ă��邤���ɁC�u�Z���ԋΖ��v���u��E�v�v��8.1���C�Ǘ��E�i�ے��C�����ȏ�j�ł��Q�`�R�������p���Ă���B�Ȃ��C�I�����_���Q�l���x���ł݂�ƁC20���オ�t���b�N�X�^�C���Ζ���Z���ԋΖ��Ȃǂ𗘗p���Ȃ��瓭���Ă��邱�Ƃ��킩��B
�@�ȏ�̂��Ƃ���C�h�C�c��I�����_�ł͈�ʎЈ��͂��Ƃ��C�ے��╔���Ȃǂ̖�E�҂��_��ȓ��������ł��邪�C���{�͏_��ȓ��������ł��Ȃ����Ƃ�����B
�@�܂��C�����j���ʂŌ������̂��\�R�ł���B���{�͒j���Ƃ��ɏ_��ȓ������ɌW�鐧�x�̗��p�����Ȃ��C�u�t���b�N�X�^�C���Ζ��v���j���Ƃ��U�`�V���ŁC���̏_��ȓ������ɔ�ׂĔ�r�I�����B�u�Z���ԋΖ��v�ɂ��Ă��C������2.4���ƂȂ��Ă���B����ɑ��C�h�C�c�́C�u�t���b�N�X�^�C���Ζ��v���j���Ƃ���30��������B�u�Z���ԋΖ��v�ɂ��ẮC�j����3.2���Ə��y158
�Łz
�Ȃ����C������13.6���ƂȂ��Ă���B�u�Z���ԋΖ��v�ɂ��ẮC�����ɂ�闘�p���������C���̏_��ȓ������ɌW�鐧�x�̗��p�ɂ��ẮC�j���ő傫�ȈႢ������Ƃ͂����Ȃ��B���Ȃ݂ɁC�I�����_�ɂ��Č���ƁC�����͒j���œ������ɈႢ��������B�����ł́C�����́C�u�t���^�C���̒ʏ�Ζ��v��45���C�u�Z���ԋΖ��v��40���ƁC���������Q�ɉ����Ă���Ƃ�����B����C�j���ɂ��ẮC�u�t���^�C���̒ʏ�Ζ��v��78.8�����邪�C�u�t���b�N�X�^�C���Ζ��v��21.2���C�u�ݑ�Ζ��v��15.2���ƂȂ��Ă���C�����ɔ�ׂė��p�҂̊����������B�����̒j���́C�J�����Ԃ̒����͕ς����ɓ������Ԃ⓭���ꏊ���_��ɂ��Ȃ���A�J���Ă���Ƃ�����B
�@�ȏ�̂��Ƃ���C�h�C�c��I�����_�̒j���́C���ꂼ�ꗘ�p���鐧�x�ɈႢ�����������
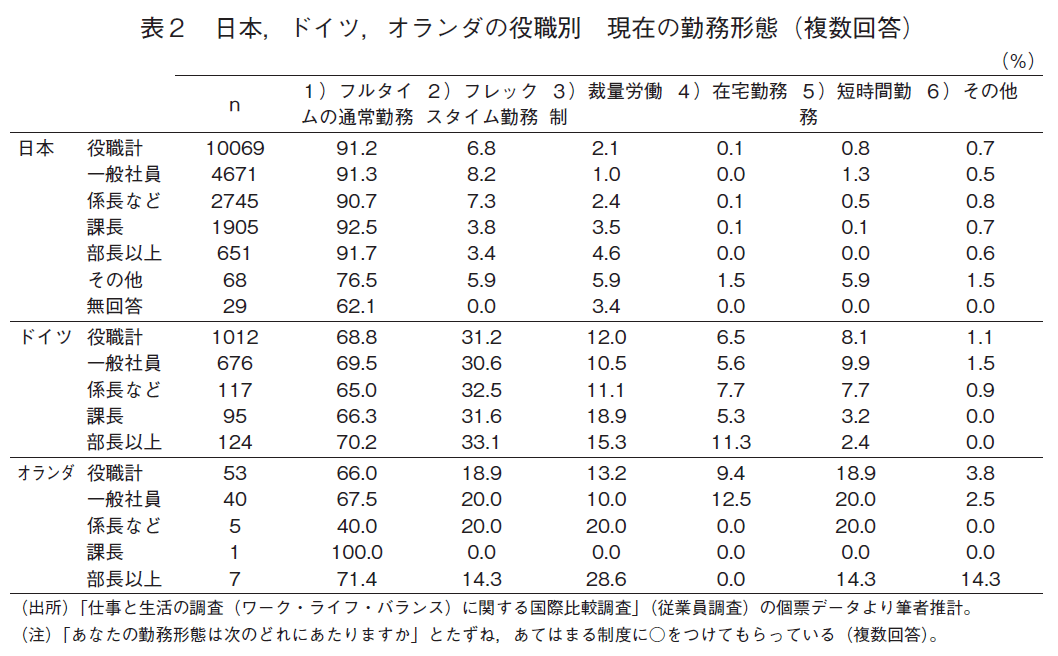
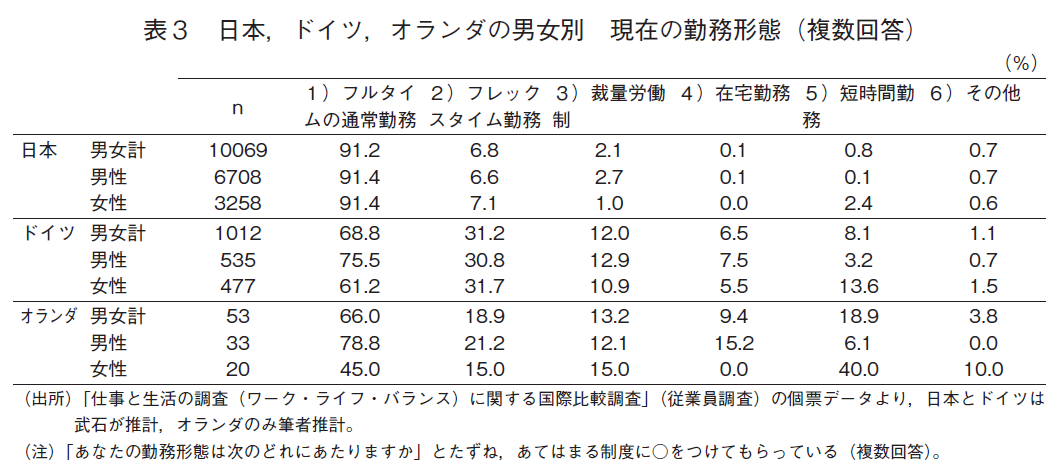
�y158 �Łz
�́C���{�̒j���ɔ�_��ȓ������ɌW�鐧�x�𗘗p���Ă���B�܂��C���������݂Ă��C���{�̓h�C�c��I�����_�ɔ�ׂĉ��I�ȓ����������Ă���Ƃ�����B
�R�D�h�C�c�C�I�����_�ɂ�����C���^�r���[��������
�i�P�j�����T�v
�h�C�c��I�����_�̂悤�ɏ_��ɓ������Ƃ��\�ɂ��邽�߂ɂ͉����K�v���𖾂炩�ɂ��ׂ��C�h�C�c�C�I�����_�����̊�Ƃ̋��͂āC��Ƃ̐l������S���҂Ə_��ȓ����������镔�������E��̃}�l�W�����g�҂�ΏۂɃC���^�r���[���������{�����B�������ł́C�l������S���҂֏_��ȓ������Ɋւ��鐧�x�̊T�v�C��ƂƂ��Ă̎�g�Ȃǂ��C�E��}�l�W�����g�҂ɑ��Ă͐E��̊T�v�i�K�́C�E�����e�j�C�_��ȓ������Ɋւ��鐧�x���p�̏C���x���p�҂ւ̋Ɩ��z���C�v���Ǘ��E�m�ۂȂǂ������˂Ă���B�C���^�r���[�����̊T�v�͈ȉ��̂Ƃ���ł���B
�@�Ώۊ��
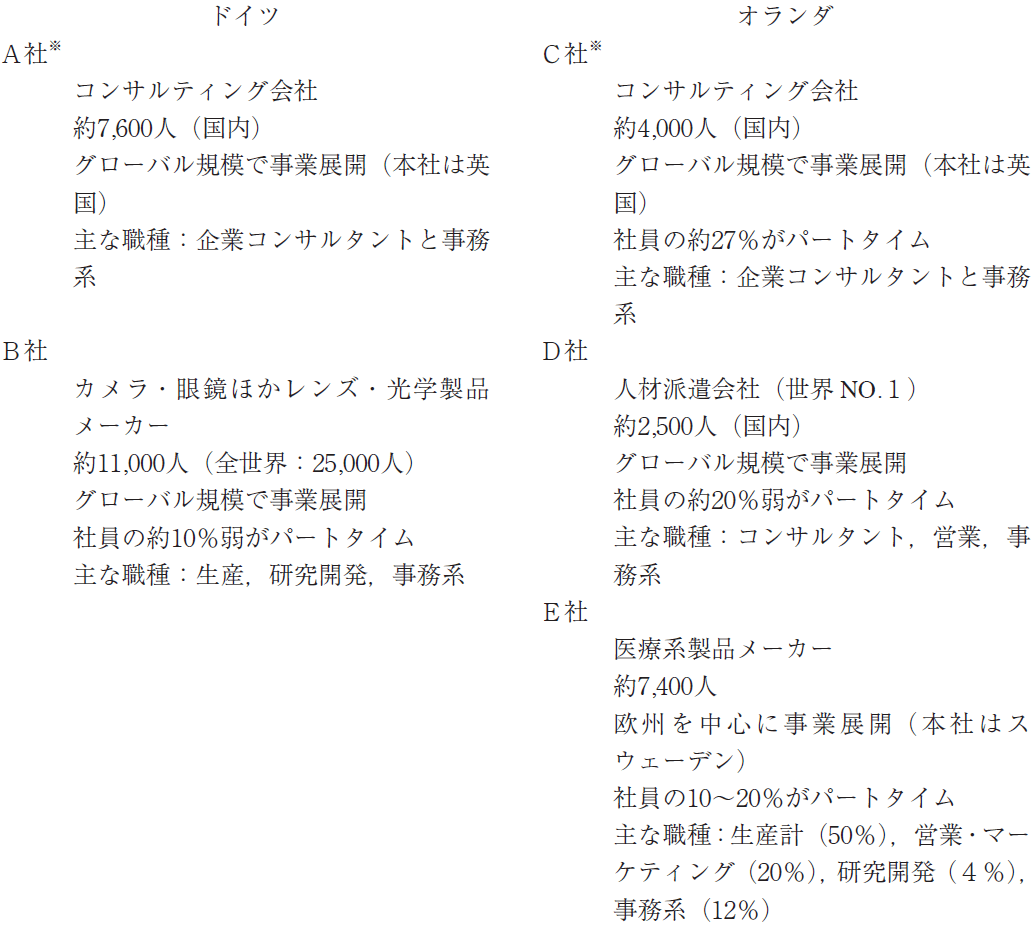
�y160 �Łz
���`�ЂƂb�Ђ́C�{�Ђ��p���Ɏ����C�O���[�o���ɓW�J���铯��O���[�v��Ђł��邪�C�������Ă���WLB�ɌW�鐧�x�ɂ��Ă͊e���ł��ꂼ��قȂ�B
�A��������
2013�N�V��
�i�Q�jWLB�ւ̎�g���R
�C���^�r���[�Ώۊ�Ƃ̑S�Ă��C����̘J���͂̌������ӂݏ]�ƈ���WLB�x�����d�v�ł���Ƃ̔F���ɗ������g��ł���B���ɂa�Ђ́CWLB����Ɛ헪�̂P�Ɉʒu�t���C�����\�͂����呲�̎Ј����m�ۂ��Ă����ɂ͖��͓I�Ȋ�ƌo�c���d�v�ł���C���̂��߂ɂ�WLB�ɂ�錻��ɍ������E������������Ă������Ƃ��d�v���Ƃ��Ă���B
�i�R�j�e�Ђ̏_��ȓ������Ɋւ��鐧�x���e
�Z���ԋΖ��ɂ��ẮC�C���^�r���[�Ώۊ�Ƃ̑S�Ă����R�����肹���ɗ��p��F�߂Ă���B�Ζ����Ԃɂ��Ă��C�T24���Ԃ���40���Ԃ̊Ԃŏ�i�Ƌ��c�̂����_��ɘJ�����Ԃ�����ł���d�g�݂Ƃ��Ă���B�܂��C�ݑ�Ζ����C���^�r���[�Ώۊ�Ƃ̊e�Ђ��������Ă����B���Ƃ��C�`�Ђ́C�]�ƈ����Ɩ��̓������l�����Ȃ���Z���ԋΖ���ݑ�Ζ���I��������C�g�ݍ��킹�ē������Ƃ����サ�Ă���B
�@�����ɂ���������́C�Z���ԋΖ��҂̑������P���̘J�����Ԃ�Z������P�[�X�����T�̏o�Г��������炵�Ă���_�ł���B�܂��C�Z���ԋΖ����x�ƍݑ�Ζ��p���C�A�����o�Γ����ݑ�ŋƖ������Ă���_�����ʂ��Ă���B�h�C�c��I�����_�ł́C�e�]�ƈ��̃��C�t�X�^�C���ɍ��킹�ē������Ԃ�ꏊ���_��ɂ��Ȃ�����C���J�����Ԃ̓t���^�C���Ζ��Ƒ傫���ς��Ă��Ȃ��Ƃ�����B
�@���̂ق��C�����I�Ȑ��x�Ƃ��ẮC�`�Ђ́u�t���[�u���b�N���x�v�ł���B�����x�́C�����ԘJ�������������Ƃɒ����x�ɂ��擾�ł��鐧�x�ł���B���Ђ́C�R���T���e�B���O���傽��Ɩ��Ƃ��Ă���C�ڋq�̏���ł͈����ԁC�����ԘJ���������P�[�X�����Ȃ��Ȃ��B���������E��ł́C�N�Ԃ̘J�����Ԃ��ς����x���]�ƈ���WLB�����������{��Ƃ��ėL�����ƌ�����B
�i�S�j�_��ȓ������Ɋւ��鐧�x���p�̏�
�����Ƃ��Z���ԋΖ����x�̗��p�������C�����]�ƈ��̂P�`�Q�����Z���ԋΖ��ł���B���p�҂̑����͏����ł��邪�j����Ǘ��E�ɂ�闘�p�����Ȃ��Ȃ��B
�@���Ƃ��C�I�����_�̂c�Ђł�15�l�̐E��̂�����12�l���Z���ԋΖ��҂ł���C�����X�l���}�l�W���[�ł���B�����Ǘ��E�̏T�J�����Ԃ�32���ԁi�T�S���Ζ��j����T36���ԂŁC�t���^�C���Ζ�����80�`90���̋Ζ����ԁi�T�S���Ζ��܂��͏T4.5���Ζ��j�ł���B�ނ�́C�I�����_�����ɂ���2400�l�̃R���T���^���g�̊e�E���K�₵�C�l���ɂ��������c�����C���̉����ƂȂ鋳��v���O�������\�z����Ɩ���S���Ă���B�Ɩ��̓˔����͂قƂ�ǂȂ����C�Ɩ��ʂ͑����C�����̓��A��o���͑����B�܂��C�b�Ђł��E�ꃁ���o�[�̂X�����Z���ԋΖ��ł���C�S�������낤���Ƃ͒������B���E��̊Ǘ��E�i�����N���X�j�Ŗ{�C���^�r���[�ɑΉ����Ă����҂��T36���Ԃ̒Z���ԋΖ��҂ł������i���T���j���̌ߌ�ɐ��x�𗘗p�C�t���^�C������
�y161
�Łz
90���Ζ��j�B���̂ق��C�h�C�c�̂`�Ђł́C��300�l�̕������������i�j���j���C�����ԘJ���������Č����I������C�R�������x�̒����x�ɂ��擾����P�[�X�������������B�܂��C��x���畜�E���������̃V�j�A�}�l�W���[�i�ے��N���X�j���C�T�R���̒Z���ԋΖ����x�ƍݑ�Ζ����x�𗘗p���Ă����P�[�X���������B�Ȃ��C���݂́C�j���̃V�j�A�}�l�W���[�i�ے��N���X�j���C���q�̏o�Y�ɔ����C�T�R���̒Z���ԋΖ����x�ƍݑ�Ζ����x�𗘗p���Ă���B
�@�Z���ԋΖ����x�̗��p���R�ɂ��ẮC�玙�𗝗R�Ƃ���P�[�X�������_�͊e�Г����ł��邪�C�h�C�c�ł́C�ߔN���m����C�m�����擾���邽�߂ɗ��p����҂��������Ă���B�`�Ђł͔��m�_���̎��M��C�m���擾�̂��߂̑�w�@�ʊw�̂��߂ɁC�Z���ԋΖ����x�i�T�S���Ζ��j�����҂������o�Ă��Ă���B
�@���̂ق��C�a�Ђł́C�o�c�҂������̋x�Ƃ��擾���͂������C�]�ƈ��ɂ��x�Ƃ�Z���ԋΖ����x�̎擾��ݑ�Ζ��Ȃǂ𐄐i���Ă���B���̌��ʂɂ��āC�a�Ђ̓V�t�g����g�ސ��Y�����l�����s�����Ă���J������������C�c�ƕ���Ȃǂł��j���Ƃ��Ɉ玙�x�Ƃ�Z���ԋΖ����x�̗��p�҂��������Ă���_�������Ă���B�܂��C�`�Ђł́C�ߔN�j�����玙�x�Ƃ��Q�`�R�������x�擾����P�[�X�������Ă��Ă���B
�@�ȏ�̂悤�ɁC�C���^�r���[�Ώۊ�Ƃł́CWLB�֘A���x�͒j�����ɗ��p����Ă���ق��C�Ǘ��E�C����ɂ͌o�c�҂ɂ���Ă����p����C���p�Ώێ҂͑��l�ł���B
�i�T�j�L�����A�v���Z�X�̖����ɂ���
���{�ł͊Ǘ��E�ɂȂ�܂łɂ͈�ʓI��10�`20�N��v���C���̊ԁC���l�Ȕ\�́i�X�L���C�m���j���K�����邽�߂ɁC�����̐E���v���W�F�N�g���o�����邱�Ƃ��Öق̗����Ƃ���Ă���i�����i2012b�j�CKato, Kawaguchi and Owan�i2013�j�j�B����ɑ��C�{�����Ώۊ�Ƃł́C�Ǘ��E��ڎw��������Ǘ��E�ɂ����������ɂ��ẮC�K�v�ƂȂ�o���₻�̂��߂ɕK�v�ȋΖ������Ȃǂ����Ă���B
�@���Ƃ��C�R���T���e�B���O�Ɩ�����Ƃ���b�Ђł́C�R���T���^���g�́C�X�^�b�t���V�j�A�R���T���^���g���}�l�W���[���V�j�A�}�l�W���[���G�O�[�N�e�B�u�E�}�l�W���[�i�܂��̓p�[�g�i�[�j�̏��ŏ��i���闬��ƂȂ��Ă���B���i����ɂ́C�l�X�Ȏd���C��ƂɊւ��v���W�F�N�g����l������10�`20�Ђ�S�����C�����ʂ��ă��[�_�[�V�b�v���o���E�K�����Ă������Ƃ����߂���B���������āC�V�j�A�}�l�W���[��G�O�[�N�e�B�u�E�}�l�W���[�ɏ��i���邽�߂ɂ́C�T�S���ȏ�̃t���^�C���Ζ������߂���B���Ђł́C�L�����A�A�b�v��ڎw���҂ɂ��ẮC��i���T�S���ȏ�̃t���^�C���Ζ����K�v�ł��邱�Ƃm�ɓ����҂Ɏ������ƂƂ��Ă���B
�@�`�Ђɂ����Ă����l�ł���C�V�j�A�}�l�W���[��ڎw���}�l�W���[�i�����j���玙�x�Ƃ��擾���C80���̒Z���ԋΖ��ŕ��E���Ă��邪�C�T�Q���̎Г��Ɩ��ƏT�Q���̃R���T���^���g�Ɩ������Ȃ��Ă���B�܂��C�c�Ђ��ڋq�ւ̃R���T���^���g���傽��Ɩ��ƂȂ��Ă���C���Ђɂ����Ă��C�V�j�A�}�l�W���[�i�ے��N���X�j�ɏA�C���邽�߂ɂ͕K�v�ȋ���v���O�����̎�u�⑽�l�Ȍڋq��S������K�v�����邽�߁C�T�S���ȏ�̋Ζ����K�v�ł��邱�Ɩ������Ă���B
�@�e�ЂƂ��ǂ̂悤�ȃL�����A�`�������邩�͌X�l�����߂邱�ƂƂ��Ă��邪�C�L�����A�A�b�v�����邽�߂ɕK�v�Ȕ\�͗v���͂��Ƃ��C���̔\�͎擾�ɕK�v�ȓ������ɂ��Ă��������C�{�l����̓I�ɃL�����A�Ƃ���ɕK�v�ȓ�������I�����Ă���B
�y162 �Łz
�i�U�j��c��o���ɂ���
���{�ł́C�Z���ԋΖ��҂��s�݂̎��ԑт���ɊJ�Â�����c��ł����킹�ɂ��ẮC���̏�i�⓯�����o�Ȃ��C�c�����e��\�����肷��̂���ʓI�ł���B�܂��C�o���ɂ��ẮC�Z���ԋΖ��҂͌����h����v����o���ւ͎Q�����Ȃ��X����������i�����i2012b�j�C���i2013�j�j�B
�@����C�C���^�r���[�Ώۊ�Ƃɂ����ẮC��c���e����Q���̕K�v����Z���ԋΖ��҂ɔ��f�����Ă���B�܂��C�K�v�ȉ�c�ɂ��ẮC��i���Q���𖽂��邱�Ƃ�����B�c�Ђł́C���T���܂����j���̌��܂������ԂɁC�Ǘ��E���m����L���邽�߂̉�c���J�Â��Ă��邪�C�E�ꃁ���o�[�̂X���ȏオ�Z���ԋΖ��҂ł��邽�߁C�S�����Q���ł���j���⎞�ԑтɉ�c���Z�b�e�B���O���邱�Ƃ͓���B���������āC�����̋Ζ����ԊO�ɉ�c���J�Â���C����ɏo�Ȃ���K�v������Ɩ{�l�����f�����ꍇ�́C�e�����p�[�g�i�[��Ƒ��̋��́C�܂��͊O���̃T�[�r�X�����p���ĉ�c�ɏo�Ȃ��邱�Ƃ𑣂��Ă���B
�@�܂��C�o���ɂ��Ă��C���f��{�l�ɔC���邱�ƂƂ��Ă���B���ɏo���́C���O�ɑ���̓����̒��������邱�Ƃ��ł��邽�߁C�����̒����o�������ɒE�����C�o���֍s���P�[�X�����Ȃ��Ȃ��B�T�R���Ζ��̂`�Ђ̃V�j�A�}�l�W���[�i�j���j�́C���g���Z���ԋΖ����x�𗘗p���Ă��邱�Ƃ��ڋq�ɘb���������ŁC�݂��̓��������C�o���ɏo�����悤�ɂ��Ă���B�܂��C�a�Ђł́C�Г��̑��k�����ŏo�����̎q�ǂ��̗a����ȂǂɊւ���{�ݏ��������C�x�r�[�V�b�^�\���Љ��ق��C�����̔�p����Ђ����S���C�o���Ȃǂɂ��C���˂Ȃ��Q���ł���悤�x�����Ă���B
�@�ȏ�̂悤�ɁC�Z���ԋΖ��҂ɉ�c�C�o���̎Q���̗L������̓I�ɔ��f�����C�����̃L����
�A��Ɩ��ɑ���ӔC�����������Ă���B
�i�V�j�Z���ԋΖ��҂֔z������d���̎��E�ʂɂ���
�{�����ł́C�C���^�r���[�Ώۂ̂�����̊Ǘ��E���T32���ԁi�T�S���Ζ��j�ł���t���^�C���Ζ����Ǝd�����e��ς���K�v�͂Ȃ����C�Ζ����Ԃ��Z���Ȃ镪�C�Ɩ��ʂ����炷�K�v�����邩������Ȃ��Ƃ��Ă���B���������w�i�ɂ́C�����̖@���Ńp�[�g�^�C���J���҂̋Ɩ��ɂ��ẮC�t���^�C���Ζ����Ɠ����̎d����^���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ���߂��Ă��邱�Ƃ��N�����Ă���B�������C�@�������łȂ��C�Z���ԋΖ��҂̏�i�́C�����I���_�ɗ����C�Z���ԋΖ��҂̃��`�x�[�V�����Ɣ\�͂��ێ��E���W�����邱�Ƃ��d�v���Ƃ��Ă���B���Ƃ��C�`�Ђł́C�T�R���Ζ��̃V�j�A�}�l�W���[�i�ے��N���X�j�̋Ɩ��ɂ��āC�t���^�C���Ζ����Ɠ����Č���S�������Ă��邪�C�Č��������炵�Ă���B���Ђł́C�Z���ԋΖ��҂�����L�����A�A�b�v���Ă������߂ɕK�v�Ȕ\�͂�X�L�����ێ��E�m�ۂ��Ă������߂ɂ́C�d���̎���ς���ׂ��ł͂Ȃ��ƍl���Ă���B
�@�������C�d���̎��͓��ނł��C�ڋq�Ή��̓���Ȃǂ��t���^�C���Ζ��҂ƒZ���ԋΖ��҂ňقȂ邱�Ƃ�����Ǝw�E���鐺������B�c�Ђł́C��ʐE�ɂȂ�قǍ����m���ƃX�L�����K�v�ɂȂ蕡�G�Ȍڋq��S�����邱�Ƃ������Ȃ邪�C�Ζ����ԁi�����j�ɂ���ẮC��ʐE�ɂ���҂ł���Փx�̒Ⴂ�Č���S�������邱�Ƃ�����Ƃ��Ă���B
�@�킪���ł��C�Z���ԋΖ��҂̒S���Ɩ��͈ꌩ�d���̎��������悤�Ɍ����邪�C��Ԃ���r�I�y���Č��Ȃǃt���^�C���Ζ��҂̋Ɩ��̎��ƈقȂ�ꍇ������i�����i2012b�j�j�B�h�C�c�E�I�����_�ɂ����Ă��C�t���^�C���Ζ��҂̎d���̎��́C�Z���ԋΖ��҂̂���ɔ�ׂĕ��ՂɂȂ�
�y163
�Łz
�\��������Ƃ�����B���̓_�Ɍ����Č����Γ��{�Ƒ傫�ȈႢ������Ƃ͂����Ȃ��B
�i�W�j�E��̗v���Ǘ��ɂ���
���{�ł͒Z���ԋΖ��҂�v���P�����Ƃ��ăJ�E���g���邱�Ƃ��������߁C�E��S�̂̋Ɩ��ʂ����邱�Ƃ͂Ȃ��B���������āC�Z���ԋΖ��҂����ԓ��ɏ����ł��Ȃ��Ɩ��ʂ́C�E��̑��̗v���őΉ�����̂���ʓI�ł���B
�@�C���^�r���[�Ώۊ�Ƃɂ����Ă��C�Z���ԋΖ��҂��o�Ă��E��̋Ɩ��ʂ̑��ʂ͑傫���ω������C�Z���ԋΖ��҂��S������Ɩ��œ˔��I�ȑΉ����K�v�ƂȂ�C�\�Ȍ���{�l���Ή�����B����ł��Ή�������Ȃ��ꍇ�͐E��̓����ŃJ�o�[���C�h���Ȃǂ��O������m�ۂ��邱�Ƃ͏��Ȃ��B
�@�������C�`�Ђł́C�ً}�ȑΉ����K�v�ȏꍇ�́C�h�C�c�̑��̒n�悩�瓯���̔\�͂�o�������l�ނ��Ăъ邱�Ƃ�����Ƃ��Ă���B�܂��C�a�Ђł��C�x�Ɗ��Ԃ�x���p�҂̕s�ݎ��ԑтɂ�����}�̑Ή��Ƃ��āC�C�O�i���Ƃ��Γ��{�j�ɒ��݂��Ă��铯���̔\�͂�E�ʂ̎҂��Ɩ��w���҂Ƃ��ď[�Ă邱�Ƃ�����Ƃ��Ă���B�E��̊Ǘ��E�ɁC���͈̔͂ɂ�����l�i���Ј��j�̈ٓ���F�߁C�l����������ɈϏ�����Ă���ƍl������B
�S�D�v��ƃC���v���P�[�V����
�{�e�́CWLB���i�ރh�C�c��I�����_�ɂ����铭�����̓����������Ƌ��ɁC�킪����WLB�����Ɍ��������͉����𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ����B���炩�ɂȂ����͈̂ȉ��̂T�_�ł���B
�@���ɁC�I�����_�E�h�C�c�ł́C�����͂��Ƃ��C�j���ɂ��WLB�֘A���x�̗��p�����Ȃ��炸����ق��C�E�ʂɊւ�炸�_��ȓ��������\�ł���_�ł���B�ߋ��ɏ_��ȓ������ɌW�鐧�x�𗘗p�����o�����Ȃ��Ǘ��E�̐E��ł́C���݂̋Ζ��`�Ԃ��]���ʂ�̓������ɂȂ�\���͍����B���{�ł́C�ߋ����܂߁C��E�ҁC���E�҂̓������͉��I�ł��邽�߁C�V���ɏ_��ȓ�������E��Ő��i���Ă������Ƃւ̒�R���͏������Ȃ��Ǝv����B�܂��C�����̓��������I�����_��h�C�c�ɔ�ׂĉ��I�ł��邱�Ƃ���C������WLB�̎������킪���ł͓�����Ƃ��f����B����C�E���WLB��蒅�����邽�߂ɂ́C�o�c�҂͂��Ƃ��C�E��̃}�l�W�����g�҂ւ̋�������������x�����s���ƂȂ낤�B
�@���ɁC�h�C�c��I�����_�ł͌o�c�҂�WLB�̐��i�ɋ����R�~�b�g�����g�������Ă���_�ł���B�����̗D�G�Ȑl�ނ̊l���ɌW���@���͋����C���̂��߂�WLB���K�v�Ȏ{��ł���Ƃ������F���ɗ����Ă���B���������āC�o�c�҂��x�ɂ�ϋɓI�Ɏ擾����ȂǁCWLB�����Ɍ�������͂��������Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�o�ώY�ƏȂ��i�߂�u�_�C�o�[�V�e�B�o�c���100�I�v�́C�_�C�o�[�V�e�B�̐��i�ɂ͌o�c�w�̃R�~�b�g�����g���d�v�ł��邱�Ƃ��w�E���Ă���B�܂��C�����i2011�j�́C�A�Ǝ��ԓ��ŋƖ����I����悤�}�l�W�����g������CWLB�ɌW��ӎ��������Ǘ��E�̉��ł́C������WLB�����x���������E�ꐶ�Y�����������Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B�o�c�҂�WLB�ɑ���R�~�b�g�����g�͏]�ƈ���WLB�����ɋ����e���͂����ƍl������B���������o�c�҂̎p����s�����_��ȓ�����������҂̑��l���ɂ��e�����Ă���Ǝv����B
�@��O�ɁC�h�C�c��I�����_�ł̓L�����A�v���Z�X���u�����鉻�v����Ă���_�ł���B����
�y164
�Łz
�ł̓L�����A�`���̂����ŒZ���ԋΖ����x�̗��p�����̉e�����y�ڂ��\��������ꍇ�́C���O�ɂ��̎|���֓`���C�L�����A�A�b�v��}��Ȃ���WLB���������邽�߂̃}�l�W�����g���s���Ă����B���{�ł͎Ј��̃L�����A�`���ɑ��C�Ǘ��E��l�����傪�������X���������C�������g���L�����A�`���Ɏ�̓I�Ɋւ��X���͏��Ȃ��B����C�h�C�c��I�����_�ł́C�L�����A�`���͌X�l�̔��f�ɔC����C��i�͂�����x����������ƂƂ炦�Ă���B�X�l�̃L�����A���x�����Ă������߂ɂ́C�Ǘ��E�ɂȂ邽�߂ɕK�v�Ȕ\�́E�o������������炩�ɂ���K�v������B����܂��C�l��WLB�Ɋւ��鐧�x�����p���C�L�����A�������Ɍ`�����邩���l����K�v������B�܂��C�Ǘ��E�ƕ����ŃL�����A�ɂ��Ęb�������@�������Ă����˂Ȃ�Ȃ��B
�@��l�ɁC��L�O�Ƃ��֘A���邪�C�Ǘ��E�փL�����A�A�b�v���邽�߂ɕK�v�ȏA�J���ԂƂ��āC�t���^�C���Ζ�����80�`90���i�T�S���`4.5�����x�j�ŏ\�����Ƃ��Ă���_�ł���B�܂��C�Ǘ��E���t���^�C���Ζ���80�`90���ŐE�����ʂ����Ă���P�[�X�������BKato, Kawaguchi and Owan�i2013�j�́C�킪���̏��i�V�X�e���͒j���ɂ̓��b�g���[�X�ύt�������Ă��邱�Ƃ��w�E���Ă���B�܂�C�\�͈ȏ�ɃR�~�b�g�����g���d�������L�����A�J�����s���Ă���\��������B�]���ĐE��̃}�l�W�����g���Ɩ������������R�~�b�g�����g���ɋ��߁C��������ɂ߂邽�߁C�Ǘ��E���g�������ԘJ����������Ȃ��Ɋׂ��Ă���ƍl������B
�@��܂ɁC�L�����A�����łȂ���c��o���ɂ��Ă��C�I�����_�E�h�C�c�ł͂��̏o�ȂɌW�锻�f�͏]�ƈ��ɔC����Ă���_�ł���B�����i2012b�j�́C���{�ł͉�c��o���̈Ӌ`��ړI�����m�ɂ���邱�Ƃ͏��Ȃ����C���Ȃ��Ƃ��Ǘ��E�͂��̈Ӌ`��m���Ă���C�����ɎQ�����Ȃ����Ƃ��L�����A���X�ɂȂ���\��������_���w�E�����B�h�C�c��I�����_�ɂ����ẮC��c�ɏo�邱�Ƃ𑣂��Ȃ��炻�̏o���ɂ����锻�f��{�l�ɔC���Ă��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ������B��c��o���ւ̎Q���͋Ɩ��ւ̐ӔC�����������C�v���Ȕ��f�͂�{����ʂł�����B����������g���L�����A�ӎ��������ێ����邱�ƂɊ�^���Ă���\��������B
�@��Z�ɁC�h�C�c��I�����_�ł́C�}���ȋƖ��ʂ̕ω��ɑ��ĊO������l�ނ��m�ۂł���Ȃǐl�������E��̕��咷�ɈϏ�����Ă���_�ł���B���{�ł͔h���Ј��̗̍p�͂��Ƃ��C����Ԃ̐l�ނ̂��J��ɂ͐l�����傪�傫�Ȑl������L���Ă���B���ꓯ�m�̂��J����~�����v���ɂł���d�g�݂�WLB�̎����ɑ傫���e�����Ă���\��������B
�@�ȏ�̂��Ƃ܂��C�킪���̂���Ȃ�WLB���i�ɂ͉����K�v�����l�@�������B
�@�܂��C�o�c�҂̃R�~�b�g�����g�ł���B����ɂ��ẮC�킪���ł����������Ă��Ă��邪�C���{��Ƃ̌o�c�w��WLB�ɑ���F�����Ⴂ�Ǝv����B���Ȃ��Ƃ������Ώۂ̃h�C�c��I�����_�̊�Ƃł́C���q������i�ق̉ۑ�ƂƂ炦�C����ɑΉ����ׂ��o�c�w�����悵��WLB�Ɋւ���͂������C�]�ƈ��ɂ��WLB�֘A���x�̗��p�𑣂��Ă���B�o�c�w������_��ȓ��������s���C����ɕK�v�ȑ���u���Ă������Ƃ��C����̊Ǘ��E��WLB�������ł���o�c���v��Ɩ����s���v�ɂȂ���ƍl����B
�@���ɁC����̊Ǘ��E�ւ̐l�����̈Ϗ��ł���B����i2006�j�́C���{��Ƃ̐l�����̔S�������l�����̒����W���I�Ȑl������W��ɉe�����Ă���\�����w�E���Ă���B�_��ȓ������̐i�W�ɔ����C�E��̋@���͂𗎂Ƃ��Ȃ��l�����̂�������Č�������K�v�����邾�낤�B������wWLB�v���W�F�N�g�i2009�j�́C�E���WLB�̎����ɂ́C�����̎d���̐i�ߕ��̍ٗʓx�������邱�Ƃ��d�v���Ƃ��Ă���B�l�����ɂ��Ă��E��̍ٗʓx�����߂錟�������ׂ��ł��낤�B
�y165 �Łz
��O�ɁC�Ǘ��E�ɂ��_��ȓ������̎����ł���B����C���{�͒�����Љ�Ɉڍs���C�d���Ɖ��̗�������ԉ�����\��������B�d���Ɖ��̗����́C40��ȍ~�̊Ǘ��E���܂ޏA�J�҂ɂƂ��đ傫�ȉۑ�ɂȂ�B�o�c�҂ɂ��WLB�̐��i���d�v�ł���悤�ɁC�Ǘ��E���g�����l�ȓ����������Ă������Ƃ�������WLB�����Ɋ�^����B�d���Ɖ��̗������\�ɂ��邽�߂̃V�~�����[�V�����Ƃ��āC�Ǘ��E���ݑ�Ζ������p����ȂǁC�_��ő��l�ȓ����������H���Ă������Ƃ��K�v�ł���B���ʓI�ɁC�Ɩ����s�̂�����̌������ȂǂɂȂ���\��������B
�@��l�ɁC�}�l�W�����g�͂̌���ł���B����̊Ǘ��E�̌����ڏ����s�����Ƃ́C����}�l�W�����g�҂̃}�l�W�����g�͂�����邱�ƂɂȂ�B���{�ł́C����܂ŊǗ��E���Ɩ����s�\�͂��������̂�]�������i�����Ă����B�������C����}�l�W�����g�͂������Ȃ���Ύ������g�╔����WLB�̎�����}��Ȃ���E����~���ɉ^�c���Ă������Ƃ͓���B�Ǘ��E�̑I���ɂ��āC����͋Ɩ����s�\�͂����łȂ��C�}�l�W�����g�͂����d�����Ă������Ƃ����҂����B
�@��܂ɁC�J�����ԊǗ��̕��@��]����̌������ł���B�I�����_��h�C�c�ł͒Z���ԋΖ������łȂ��ݑ�Ζ������p����Ă����B�����������������\�ɂ���w�i�ɂ́C�ڕW�ݒ�m�ɂ��C���̎����x�ɉ����ĕ]������d�g�݂�����B�䂦�ɁC�~�b�V�����̒B���ɓ����鎞�Ԃ���@�͖{�l�ɂ䂾�˂邱�Ƃ��ł���B����C���{��Ƃł́C�Z���ԋΖ��҂͋Ζ����ԊO�͋Ɩ����s��Ȃ����Ƃ������Ƃ��Ă���P�[�X�������B���������Ɩ��Ǘ����@��]�����@���]�ƈ���WLB�̎�����j�Q���Ă���\��������B�h�C�c��I�����_���������̏_��x�����߂��w�i�ɂ́C�O���[�o�����ɂ�鋣�������ɔ����J�����Ԃ̉��������߂��钆�C���������_��ɂ��邱�Ƃŏ]�ƈ��̎d���Ɛ����̗������m�ۂ������Ƃ�����B�Ɠ����ɁC�J�����Ԃ̒Z�k�̐��i������Ȃ������߂ɁCEU�����͍��킹�Č��N�̊m�ۂ�}�邽�߂ɋΖ��ԃC���^�[�o���K���������B�V���Ȍo�ς̒����ɉ����Ȃ��瓭�����̊Ǘ��E�K���C����ɂ͂�����~���ɉ^�p���Ă������߂̕]��������߂��Ă���B
�Q�l����
����p�q�i2012�j�u�I�����_�ɂ����郏�[�N�E���C�t�E�o�����X�v �w���۔�r�̎��_������{�̃��[�N�E���C�t�E�o�����X���l����x �~�l�����@���[
���Όb���q�i2012�j�u���[�N�E���C�t�E�o�����X�����̉ۑ�ƌ����̎����v �w���۔�r�̎��_������{�̃��[�N�E���C�t�E�o�����X���l����x �~�l�����@���[
���Όb���q�i2013�j�u�Z���ԋΖ����x�̌���Ɖۑ�v�C�w�@����w�L�����A�f�U�C���w��x �@����w�L�����A�f�U�C���w��C2013�N�Q��
������v�i2001�j�u��O�́@�I�����_�v �w�o�ς̔��W�E���ށE�Đ��Ɋւ��錤������x�C�����ȍ�������������
�����R���i2009�j�u���[�N�E���C�t�E�o�����X�x�����x�E��Ր��x�̑g�ݍ��킹�����߂�o�c�p�t�H�[�}���X�v �w���{�J�������G���x�CNo.583�Cpp.60-67
������r�i2006�j�w���{�^�l���Ǘ��x �����o�ώ�
��������i2011�j�u�Ј��̃��[�N�E���C�t�E�o�����X�̎����ƊǗ��E�̖����v�C���������E���Όb���q�� �w���[�N�E���C�t�E�o�����X�Ɠ��������v�x �������[
��������i2012a�j�u���[�N�E���C�t�E�o�����X�{���ʓI�ɋ@�\����l���Ǘ��v ���Όb���q�� �w���۔�r�̎��_������{�̃��[�N�E���C�t�E�o�����X���l����x �~�l�����@���[
�y166 �Łz
��������i2012b�j�u�Z���Ԑ��Ј����x�̒������p���L�����A�ɋy�ڂ��e���v�C�w���{�J�������G���x�CNo.627�Cpp.22-33
������w�Љ�Ȋw���������[�N�E���C�t�E�o�����X���i�E�����v���W�F�N�g�i2009�j �w�������ƃ��[�N�E���C�t�E�o�����X�̌���Ɋւ��钲���x
���t�{�o�ώЉ���������i2009�j�w����20�N�x�@���[�N�E���C�t�E�o�����X�Љ�̎����Ɛ��Y���̊W�Ɋւ��錤���x
�i�Ɓj�J�������E���C�@�\�i2008�j�w���B�ɂ����铭�����̑��l���ƘJ�����ԂɊւ��钲���x JILPT �����V���[�YNo. 41
�i�Ɓj�J�������E���C�@�\�i2009�j�w���[���b�p�ɂ����郏�[�N�E���C�t�E�o�����X�@�J�����ԂɊւ��鐧�x�̎���x �����V���[�YNo. 59
�i�Ɓj�J�������E���C�@�\�i2012�j�w���[�N�E���C�t�E�o�����X��r�@�����i�ŏI���j�x �J��������No. 151
KATO Takao, KAWAGUCHI Daiji, and OWAN Hideo,�i 2013�j�gDynamics of the Gender Gap in the Workplace: An econometric case study of a large Japanese firm�h, RIETI Discussion Paper Series 13-E-038