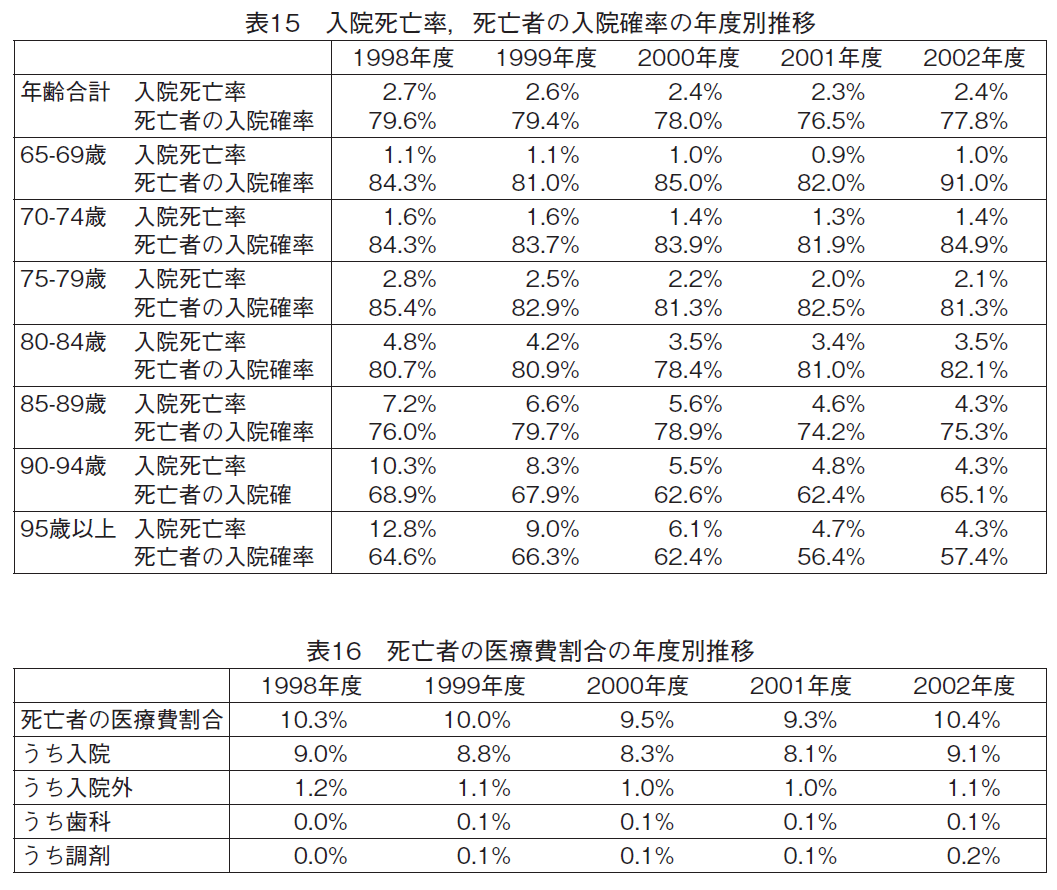�y15 �Łz
���Z�v�g�f�[�^�ɂ��I������Ô�̍팸�\���Ɋւ��铝�v�I�l�@
��@�@�j
�v�|
�{�e�́C�x�R���ɂ�����65�Έȏ�̍������N�ی������҂�1998�N�S������2003�N�R���̂T�N�ڑ����Z�v�g�f�[�^��p���ďI������Ô�̌�����m�F���C���̏�ŁC�I������Ô�̍팸�\�����l�����Ŋ�b�I�Ȓm���ƂȂ镪�͂��s�����B��̓I�ɂ́C�@�I������Ô�ɂ��āC���ґ������Ë@�֑��̓������l��������ŕ��z�̕������߂��B���̌��ʁC�I������Ô�̕��ϒl��95�������̍��̊����͂T���`�W���Ə������C�W�����E�n��i���k���ɂ��팸�\���͈ӊO�ɒႢ���Ƃ��킩�����B�A���ɁC�g�̓I�ȍ��ق����������̂́C���ȕ��S�����傫���قȂ�69��70�̐l�X�ɑ��āC�V���ڍs�O��ŏI������Ô�ǂ̂悤�ɕω����������r�����B���̌��ʁC���S�O12��������R�����܂ł̓��@�̍��ق�����Ƃ��āC�V���ڍs��ɏI������Ô20�`40�����x�傫���Ȃ邱�Ƃ����������B�B�Ō�ɁC���ی��J�n�O��ŏI������Ô���r�����Ƃ���C���ی��J�n��ɓ��@���S���C���S�҂̓��@���͉������Ă���C�N�Ԉ�Ô�ɐ�߂鎀�S�҂̈�Ô���͌����������Ƃ����������B�������C��l������̎��S�O��Ô�͂R�`10���قlj��ی��J�n��̕����������Ă���C�ݑ��ÁE��쐄�i�ɂ���Ĉ�Â�����ɃV�t�g�������̏I������Ô�́C��l������I������Ô�̒Ⴂ�l�X�̂��̂ł������Ƒz�������B
�P�D�͂��߂�
�I������Ô�Ɋւ��錤���́C�č��ł�Lubits and Prihoda�i1984�j�� Scitovsky�i1984�j����Ƃ��āC���҃��Z�v�g�f�[�^�𗘗p�����c��Ȍ����_����80�N�㔼����90�N��ɂ����Ď��X�Ɣ��\���ꂽ�B�ŋ߂ł́C�ꎞ�قǂ̐����͂Ȃ����̂́C����ł��������̘_�������\���ꑱ���Ă���C���@�_��̐������iFelder et al.�i2001�j�CHoover et al�i2002�j�j�C���ƈ�Â̊֘A���iLiu et al�i2006�j�C�e���̏iStooker et al�i2001�j�CPolder et al�i2006�j�j�C�I������Ô�̗\���\���iGarber et al�i1999�j�j���C�l�X�ȃe�[�}�ɕ����E�[�����Đ��͓I�Ȍ�����
�y16
�Łz
�������Ă���B����ɑ��āC�킪���ł͑O�c�i1987�j��Ƃ��C90�N�㏉�߂̃��Z�v�g�f�[�^�𗘗p�����{�i�I�Ȍ������{��E�S�i�i1994�j�C�{��i1998�j�C�{��E���ʁE��i1994�j�Ȃǂɂ���čs�Ȃ�ꂽ���̂́C���̌�͂����ɕC�G������M�����̍����������قƂ�Ǔr�₦�Ă��܂��Ă���ł���1�j�B
�@����ŁC�킪���̏I������Ô���߂��鐭���_�c�ł́C��Ô�}����̈�Ƃ��ď�ɂ��̍팸�\���ɕ����c�_���s�Ȃ��Ă���C�ߔN�̊�b�I�����s�݂̒��ŁC�������ǂɂ���G�c�Ȏ��Z�E��_�Ȑ������j�����e����Ă����Ԃł���B�Ⴆ�C2005�N�V���̑�17��Љ�ۏ�R�c���Õی�����ɂ����āC�����J���Ȃ́C���݂̎��S�O�P�����̏I������Ô��9000���~�Ǝ��Z������ŁC�ݑ��ÁE���̑��i�ɂ����2025�N�x�̏I������Ë��t�5000���~�팸�����Ƃ�������_�Ȑ��v�\���Ă��邪�C���̑O��⍪���͋ɂ߂Ċł���Ǝv����B�����Ƃ��C�����������ʂ��Ă��C2006�N�̈�Ð��x��������C�ݑ��Ð��i�ɂ��I������Â̍��R�X�g�����Ƃ������j�́C�o�ύ��������c�ɂ�����u��ÁE���T�[�r�X�̎�����E�������v���O�����v�ɂ��p����Ă���B
�@�������Ȃ���C�I������Ô�̍팸�\���ɂ��ẮC�Ȋw�I�Ȍ����ΏۂƂ��Ă͂قƂ�lj����𖾂���Ă��Ȃ��̈�ł���C�����ҊԂł��팸�\���E���s�\���ɂ��Ă͊m����m���͂Ȃ����肩�C�q�ϓI�G�r�f���X�̂Ȃ����ŁC�������ӌ��̑Η����N���Ă���B���ɁC�u�����̃^�[�~�i���P�A���v�i�����Љ�J���Z���^�[�i1997�j�j���Ìo�ό����@�\�ɂ�铯��̕��i��Ìo�ό����@�\�i2000�j�j�������āC��ɎЉ�ی��{��ɂ��āC�������_�����J��L����ꂽ���Ƃ͋L���ɐV�����i�Έ�i1998a�j�C�Έ�i1998b�j�C�����i1998�j�C�L��i1998�j�C�����i1998�j�C�Έ�i2001�j�C�Љ��i2001�j�C���E�r��E�Έ�i2002a, b�j�j�B�팸�\���ɔ�����Έ䎁��̎咣�i�Έ�i1998a�C2001�j�́C��Ìo�ϊw�҂��s�Ȃ����g���X�y�N�e�B�u�ȏI������Â̒�`�́C��Ì���̈ӎu����ɂ͖��ɗ����Ȃ����̂ł���C�v���X�y�N�e�B�u�Ȏ��_���K�v�ł���Ƃ������Ƃł���B���̎w�E�͊m���ɐ��������̂ł��邪�C��ÊW�҂��]���̌��ʂ��̍��m�Ƃ����`�ł�����x�̗\�z���s���Ă��邱�Ƃ��܂������ł���C�S���I������Â̒�`���ł��Ȃ��Ƃ����̂��ɒ[�Șb�ł���Ǝv����B���������ɑ��āC�č��ł�Garber et al�i1999�j�����I������Â��v���X�y�N�e�B�u�ɗ\�����C�팸�\����T���Ă��邪�C�܂��܂��\���̐��x�͔��ɒႢ�B�����I�ȃ��x���ł́C���N�C���{�~�}��w�������J���Ȃ��C�I������Â̌���⒆�~�Ɋւ���K�C�h���C�������Ŕ��\�������C����̈ӎv����ɖ𗧂ɂ͂܂��܂��ۑ肪�����B���������āC����Ƃ��C�v���X�y�N�e�B�u�Ȋϓ_����l�X�ȗl���̏I������Â𑨂��C�ǂ��܂ł��팸�\�Ȃ̂��Ƃ������ɂ߂��s���������n���ɑ������Ă䂭�ׂ��ł��낤�B
�@�����������C�{�e�ł́C�ȉ��̂Q�̖ړI�������ďI������Ô�͂����B�ЂƂ́C�{�쎁��ɂ���A�̌����ȍ~�r�₦�Ă��������Ԃ̐ڑ����Z�v�g�f�[�^�ɂ��I������Â̎�
�y17
�Łz
�Ԃɂ��āC�ŋߎ��_�̃f�[�^��p���čĔc�����s�Ȃ����Ƃł���B
�@�����ЂƂ̖ړI�́C�I������Ô�̍팸�\�����c�_���邤���ŁC����C��b�I�m���E�o���_�ƂȂ��ʓI�������W���邱�Ƃł���B��̓I�ɂ́C����܂Ō�������Ă����u�v���X�y�N�e�B�u�ȗ\���\���̖͍��v�Ƃ����������Ƃ͑S���ʂ̃A�v���[�`�����C�@��Ô�z�C�A���ȕ��S���ω��C�B���ی��J�n�Ƃ������R�̊ϓ_����̕��͂��s�����B���Ȃ킿�C��Ô�z�ɂ��ẮC�n�捷������W�����ɂ���ĉ����ł���]�n�����݂���Ǝv���邪�C��X�̗v�����R���g���[��������ł̏I������Ô�z�̕����v�Z�����B���ɁC�I������Ô�̎��ȕ��S�������E�I�ɒႷ���C�������n�U�[�h��������\�����w�E����Ă��邪�i��i2004�j�C�����i1998�j�j�C���ȕ��S���㏸�����ꍇ�ɂǂ̒��x�I������Ô���������̂����C�V���ڍs�O��̏I������Ô�̔�r�ɂ���ĕ��͂����B�Ō�ɁC�ݑ��ÁE��쑣�i�ɂ���ďI������Ô��������Ƃ̐������ǂ̌����ɑ��āC���ꂪ������������ݑ���}���ɐi���ی��J�n�O��ɂ����ɕω����������͂��Ȃ̂ŁC����������镪�͂��s�Ȃ����B
�Q�D�f�[�^
2.1�@�f�[�^�̍\��
�{�e�ŗp����f�[�^�́C�M�҂��卸�Ƃ��錤����i�������N�ی���Ô�Z�v�g�f�[�^��͎��Ɓj�ɑ��āC�x�R���̍������N�ی��c�̘A��������ꂽ��Ô�Z�v�g�f�[�^�ł���B���̃f�[�^�́C1998�N�S�����_�ŁC���ۑg���������ĕx�R���̍������N�ی������҂ł������ґS�Ăɂ��āC�Œ��łT�N�ԁi1998�N�S������2003�N�R���j�̖����̃��Z�v�g��܂܂�Ă���C����͂��̂�����65�Έȏ�̉����҂̃f�[�^���g�p����2�j�B���̌����f�[�^�iA�f�[�^�j�Ɋ܂܂�Ă�����́C�l�R�[�h�C�s�����R�[�h�C���ʁC�N��i���N�T���P�����_�j�C�f�Ë敪�i���@�C�O���C���ȁC���ܕʁj�C�����C�����C��Ô�i���t��Ɏ��ȕ��S�����������́C�_���~10�j�C���t��i�ی��ҕ��S���j�C�H���×{��C�H���×{��W�����S�z�C�ꕔ���S���i�ꕔ���S���͖�܈ꕔ���S�������������z�j�C��܈ꕔ���S���C���z�×{��i�������̂݁j�C����S�z�i��Ô�z�̂�������i���܂��͎����́j�Ŏx�������z�j�C���i�r�����R�C���i�r���N���C�ی��̋敪�i��ʁC�ސE�ҁC�V���j�ł���B�Љ�f�Ís�וʒ����̂悤�ȋ�̓I�Ȉ�Ís�ׂɂ��Ă̏��͑��݂��Ȃ��B
�@�l�ԍ��R�[�h�́C�����Ҕԍ��Ȃnjl�����ł�����̂ł͂Ȃ��C���ۘA����ɂ���ĐV���ɐU��ꂽID��p�����B����ID��p���āC��ɐ������銳�ґ����f�[�^�Ƃ̐ڍ����s�Ȃ����Ƃ��ł��邪�C�l���̕ی�̊ϓ_����C�����ґ���ID�Ɖ����Ҕԍ����Ƃ炵���킹�邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���B���i�r�����R�́C�O�F��Y���C�P�F�]�o�@�Q�F���S�@�R�F���̑��̎��R�Ŏ��i�r���Ƃ����ԍ������ĂĂ���C���i�r���N���ƍ��킹�āC�I������Ô�����ʂɓ��肷�邱�Ƃ��\�ł���B�܂��C�l�ʂɖ����̃f�[�^�ɁC�ی��敪�i��ʁC�ސE�ҁC�V���j���L�^���Ă��邱�Ƃ���C�V���Ɉڍs������������ł���悤�ɂȂ��Ă���B
�@��L��A�f�[�^�́C�厾�a���Ë@�ւȂǂɊւ��鑮����S�����݂��Ă��Ȃ��B����
�y18
�Łz
�ŁC���̓_��₤���߂ɁC���N�T�����_�̂ݔc���\�ȑ������f�[�^�iB�f�[�^�j���C�T�N���ʓr�쐬���Ă���B�������ɂ́CID�C���ʁC���N�C�s�����R�[�h�C�f�Ë敪�i���@�C�O���C���ȁC���ܕʁj�C�f�Ó����C��Ô�C�ی��̋敪�i��ʁC�ސE�ҁC�V���j�Ȃǂ̓��ꍀ�ڂ̂ق��C�f�Éȋ敪3�j�C��Ë@�֎��4�j�C��Ë@�֔ԍ��C�f�ÊJ�n���C���a���R�[�h�i���a119���ށj���L�^����Ă���B
2.2�@�f�[�^�̉��H�ɂ���
�{�e�̕��͑Ώۂł���I������Ô�ɂ��ẮC���i�r�����R���u���S�v�̐l�X�ɑ��āC�����i�r�������O�C���̑O�����P�C���̑O�X�����Q�c�Ƃ��Ă䂭�t���b�O�𗧂āC���S�O���Ԃ��ƂɎ��ʂ��Ă���B�e���ɂ́C���@�C�O���C���ȁC���ܕʂ̂S��ނ̃��Z�v�g�����݂��Ă��邪�C����f���ɂ͊e��Ô�͌����l�ƂȂ��Ă���̂ŁC������O�Ŗ��߁C�S��ނ����v�������̂𑍈�Ô�Ƃ����B�܂��C���S�O���Ԃ̗ݐψ�Ô��p����ꍇ�ɂ́C���S���i�O�j�C���S������R�����i�O-�Q�j�C�U�����i�O-�T�j�C12�������i�O-11�j�̈�Ô���C�l���ƂɎ��n��ō��v�����f�[�^���쐬�����B���S���̈�Ô�́C���ϓI�ɂ�0.5�������������݂��Ȃ����߂ɁC�S�ĂQ�{���ĉ��z�I�Ȏ��S���̈�Ô���쐬���Ă���5�j�B�ꐔ���\���ɑ傫���ꍇ�ɂ́C���ϒl��0.5�������Ɏ��ʂ��邽�߂ɁC���ϒl���݂镪�͂ɂ̓o�C�A�X�͂����炳��Ȃ��ƍl������B����͉�A���͂��s���ꍇ�ɂ����l�ł���B�܂��C���S�O�����Ƃ̕��ϒl�����ɓ������ẮC����f���������Ď�f�������̃x�[�X�ŏW�v���Ă���B
�@���āCA�f�[�^�ɂ݂̂ŕ��͂���ꍇ�ɂ́C�p���鎀�S�O���ԕʂɏI������Ô�̑S�T���v����p���Ă��邪�CB�f�[�^�Əd�ˍ��킹�ėp����ꍇ�ɂ́CID�ɂ����B�f�[�^�ƃ}�b�`
���O�ł���T���v���݂̂ƂȂ�BB�f�[�^�͖��N�̂T���������ł��邩��C���̂܂܃}�b�`���O�����ꍇ�ɂ́C�T���v���͑啝�Ɍ������邱�ƂɂȂ�B�����ŁC���S������k���čł��߂��T���̑����������S���̏��Ƃ��Ė��߂��Ƃ��s�Ȃ����BB�f�[�^�������Őf�Ë敪�i���@�C�O���C���ȁC���ܕʁj���Ƃɕ�������ꍇ�ɂ́C���̒��ōł����z�̃��Z�v�g�f�[�^�ƂȂ�
�y19
�Łz
�Ă�����̂�I��ŁC�}�b�`���O�����邱�Ƃɂ���6�j�B�����Ƃ��CB �f�[�^���́C�T���Ɏ�f���Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ͑��݂��Ȃ��̂ŁCA�f�[�^�i679,868���j�ɑ��ă}�b�`���O�ł���m����76.0���i516,379���j�ł���B�厾�a���Ȃǂ̑������ɂ��ẮC���܂݂̂̏ꍇ�ȂǁCB�f�[�^���̂ɂ��L�ڂ���Ă��Ȃ��P�[�X������̂ŁC�}�b�`���O�m���͍X�ɒႭ69.0���i468,898���j�ł���B
2.3�@�x�R���̓���
�Ō�ɕx�R���̈�Ô�̓����ɂ��Ă݂Ă������B2002�N�x�̘V�l��Ô�̒n�捷�w����0.981�Ƃ��Ⴍ�C�s���{���ʏ��ʂ�23�ʂƂقڒ��ԂɈʒu����B�������C���@�̒n�捷�w����1.114�i����13�Ԗځj�Ƃ��Ȃ荂���C������ۗ����ĒႢ���@�O0.854�i45�ʁj�⎕��0.773�i41�ʁj�����E���đS�̂����ϒl�ƂȂ��Ă���i�D�ł���B2000�N�x�́u�a�@�v�ɂ��ƁC�×{�a���ł̍݉@�����́C�S������171.6���ł���̂ɑ��C�x�R����360.4���ƒ������@�̌X��������B�܂��C�������2000�N�̍���������20.7���ƁC�S����17.4���ɔ�ׂč����Ȃ��Ă���B���������āC���̈Ӗ��ł͏I������Â͂����{�e�̌��_�����̂܂ܑS���x�[�X�ɕ��Չ����邱�Ƃ͓�����낤�B���ɁC��q�̉��ی��O��̕��͂Ɋ֘A������ی��T�[�r�X�̗��p�\���ɂ��Ă݂Ă݂悤�B2000�N�x�̌����J���ȁw���T�[�r�X�{�݁E���Ə������x���݂�ƁC�x�R���̉��V�l�����{�݂̒�����́C�S������1,358.4�l�ɑ�1,394.3�l�C���V�l�ی��{�݂͑S������1,061.3�l�ɑ��ĕx�R��1,392.2�l�C�×{�a���i��Ì^�E���^���܂ށj�́C�S������1,080.5���ɑ�1,848.9���C���^�݂̗̂×{�a�����ł��C�S������527.6���ɑ��C�x�R����1,088.8���ƂȂ��Ă���C���{�݂ŊŎ����s�Ȃ��\���͑S�����������Ǝv����B
�R�D�I������Ô�̌���
3.1�@���S��Ô�̃V�F�A
�\�P�́C2002�N�x���̈�Ô���C�N�x���̎��S�҂̈�Ô�Ɛ����҂̈�Ô�ɕ��ނ��āC�e�V�F�A���݂����̂ł���B�܂��C�N��v�ɂ��Ă݂�ƁC���S�҂̑���Ô�v���S�̂̑���Ô�ɐ�߂銄����10.4���ł���B���̊����́C1991�N�x��11�����̃f�[�^�͂����{��E�S�i�i1994�j��11.2���C1992�N�x�ɂT�����̃f�[�^�͂����{��i1998�j��11.7�������Ⴂ���قړ������ł���Ƃ�����B�܂��C���̊����́C�N������Ȃ�Ȃ�قǑ傫���Ȃ��čs�����C���̓_���ނ�̓����m���ƈ�v���Ă���B���S�҈�Ô�ɐ�߂���@��Ô�̊����͍��v��87.0���ł���C89.4���Ƃ����{��E�S�i�i1994�j�Ƃقړ������ł���B����ɁC���S�҂̓��@��Ô�C�V�l�̓��@��Ô�ɐ�߂銄���͔N��v��17.5���ƂȂ��Ă���C�����Љ�J���Z���^�[�i1994�j�̎�����19.2���������Ⴂ���x�ł���B
3.2�@���S�҈�l�����茎�ʈ�Ô�
���ɁC�}�P�́C���S�O�P�N�Ԃ̎��S�҈�l�����茎�ʈ�Ô�ɂ��ăO���t���������̂ł���B���S���Ɍ����Ď��S�O�U���������肩��}�����C���ɂR�����O����̏㏸�����������Ƃ�
�y20
�Łz
�킩��B�}�Q�̂悤�ɂ��������������S�O���ԁi�R�N�j���Ƃ�ƁC���S�O�̈�Ô�����Ă���̂͂��������U�����O�����肩��ł���Ƃ����{��i1998�j�̌������K�ł���悤�Ɏv����B�}���ɂ́C�{��E�S�i�i1994�j�C�{��i1998�j���̐�s�����ŗp�����Ă������@�{���@�O�̑���Ô���`����Ă��邪�C���܁C���Ȃ��܂{�e�̃x�[�X�ƂقƂ�Ǎ��ق͂Ȃ��B���Ȃ݂ɁC���S�O�P�N�Ԃ̈�Ô�ɐ�߂鎀�S���̈�Ô�̊�����28.2���ł���B
�@�\�Q�́C���S�O���Ԃ��ƂɎ��S�҂P�l������̗ݐϑ���Ô���v�Z���Ă��邪�C���S�O�P�����i�����j��66.0���~�C���S�O�R������135.2���~�C���S�O�U������200.2���~�C���S�O12������288.5���~�ƂȂ��Ă���B�\�R�͂�����X�ɓ��ƂɌ������̂ł��邪�C�W���ȏオ���@��Ô�Ő�߂��邱�Ƃ����̏ꍇ�ɂ��m�F�����B
�@�}�R�͔N��K���ʂɁC���S�҂P�l�����茎�ʈ�Ô�̐��ڂ��������̂ł��邪�C������{��E�S�i�i1994�j�C�{��i1998�j�������C�N��K���������Ȃ�قǏI������Ô�Ⴍ�Ȃ�Ƃ����m���ƈ�v���Ă���B�O���t���C65-69�̊K���͐�s�����ł͎�����Ă��Ȃ����̂ł��邪�C�ЂƂ�̊K���ł���70-74�̊K���Ɣ��ɋ߂��C���K���̍��ق́C���̊K���ԂŌ����鍷�ق������Ȃ菬�������Ƃ������[���B
3.3�@���a���ޕʈ�Ô�
B�f�[�^�ƃ}�b�`���O�����T���v���ɂ��āC���S���̎厾�a�̎��a�啪�ށi19���ށj�ʂɁC���S�҂P�l�����茎�ʈ�Ô�̐��ڂ��݂����̂��}�S�C�}�T�ł���B��q�̕\�S�ɂ݂�悤�ɁC���ނ����݂��Ȃ����̂�C���݂��Ă��Ă��V�F�A�����������́i�P���ȉ��j�͏ȗ����Ă���B�������݂�ƁC���S���O�̈�Ô���͊T�˂قƂ�ǂ̎����ɑ��Ċώ@����邱�Ƃ��킩��B���Ɏ��S�O�R�����ȓ��̍��������������̂́C�V�����C�����Njy�ъ��C������C�h�{�y�ё�ӎ����C�ċz��n�̎����C�؍��i�n�y�ь����g�D�̎����Ȃǂł���B����C�_�o�n�̎����͎��S�O�̍������ł��ɂ₩�ł���B�V�����C�A�H����n�̎����́C���S�O�P�N�Ԃ̂ǂ̌����قڈ�т��đ��̎��a���ނ������z�̈�Ô�ƂȂ��Ă���B
�@�}�U�́C���a119���ނ̃x�[�X�ŁC���S���̎厾�a���̊����������������̂ɂ��Ď��S�҂P�l������̌��ʈ�Ô�̐��ڂ��������̂ł���B�����ł��C���ʃp�^�[���ɂ��Ă������̃o���G�[�V������������B���S���O�̈�Ô�����傫�����̂́C�������S�����C�������������C���A�a�Ȃǂł���B�݂̈����V�����C�튯�E�C�ǎx�y�єx�̈����V�����ɂ��ẮC���O�̈�Ô���͂��قǑ傫���Ȃ����C�U�������x�O���獂���������Ɏn�܂��Ă���B�]�[�ǂ́C���S�O�P�N�Ԃ̈�Ô�����ƍ����C���O�̍����͑��ΓI�Ɋɂ₩�ł���B�������������͎��S���������C���̕��ނ������Ȃ�Ⴂ��Ô�Ɏ~�܂��Ă���B
�@�\�S�́C���a���ޕʂ̎��S�҂P�l������v����Ô�Ǝ��a���ޕʂ̃V�F�A���܂Ƃ߂����̂ł���B�V�F�A�ɂ��ẮC���S�O�U�����̗v��Ô�̃x�[�X�Ŏ���Ă��邪�C���a�啪�ނł����Ƃ��V�F�A���傫�����̂́C�z��n�̎�����38.6���C�����ŐV������18.8���ł���C���̑��͐��p�[�Z���g��ł���B���̓_���C�{��E���ʁE��i1994�j�Ƃ��������ގ����Ă���Ƃ�����B���S�O12�����ōł��ݐϑ���Ô�������̂́C�A�H����n�̎���529.4���~�ł���C�V������420.7���~������Ɏ����ł���B�t�Ɉ�Ô�Ⴂ���̂́C�T���v���V�F�A���P�����Ă�����̂̒��ł́C�畆�y�є牺�g�D�̎���258.2���~�C���Ί�n�̎���268.2���~�C�z��n����288.1���~�Ȃǂł���B119���ނɂ��ẮC���S�O12�����̗ݐϑ���Ô�������̂͊튯�E�C�ǎx�y�єx�̈����V����393.6���~�C�݂̈����V����345.7���~�ł���C�t�ɋ�
�y21
�Łz
�[�ɒႢ���͍̂�������������213.5���~�ł������B
3.4�@���@�J�e�S���[�ʈ�Ô�C��Ë@�֎�ʈ�Ô�
�{��i1998�j�ł́C���S�O�̓��@�ɂ���Ď��S�҈�l�����茎�ʈ�Ô�̃p�^�[�����傫���قȂ邱�Ƃ����Ă���B�����ŁC�{��i1998�j���s�Ȃ������S�O�U�����̃J�e�S���[��12�����ɒ����āCa�F���S�O12�����Ɉ�x�����@�����Ȃ��Cb�F���S���̂ݓ��@���Ă�����́ib1�j�{���S���ƑO���̂ݓ��@���Ă�����́ib2�j�̍��v�Cc�F���S�O��12���������Ɠ��@���Ă���C�Ƃ����R�̃J�e�S���[�ɕ��ނ����B�}�V�́C��������ʈ�Ô�̐��ڂŎ��������̂ł��邪�C�{��i1998�j���w�E�����Ƃ���C�p�^�[���ɑ傫�ȍ��ق�����C���@�̎�f��������Ô���ɉe�����Ă��邱�Ƃ��킩��B
�@����CB�f�[�^�ƃ}�b�`���O�ł������̂ɂ��ẮC��Ë@�֎�ʂɏI������Ô�̑傫�����݂邱�Ƃ��o����i�\�U�j�B���S�O12�����̗ݐψ�Ô�ˏo���č����Ȃ��Ă���̂͑�w�a�@��473.6���~�ł���B�a�@�͊T��350���~�ߕӂł��邪�C���̑��@�l�a�@�C���̑��̌����a�@�C�������a�@�C��Ö@�l�a�@�C�l�a�@�̏��Ɉ�Ô�����B�f�Ï��͈�Ö@�l�ɂ���l�f�Ï��ɂ���Ⴍ�C250���~���x�ł���B���������́C�O�c�i1987�j���m�F�������a57�N�̎��S�҂P����������@��Ô�̏Ɨގ����Ă���B
�S�D�팸�\���Ɋւ���l�@�P�F��Ô�z����̃A�v���[�`
4.1�@���͂̐헪
�ߔN�C��ʂ̈�Ô�Ɋւ��āC�����R���g���[��������ł̔�p�}���ɗL���Ȏ�i�Ƃ��āCEBM�C��Â̕W���������ڂ���Ă���B���Ȃ킿�C�������a�C���l�̃X�e�[�W�C���l�̊��ғ����̏ꍇ�ɂ́C���Ís�ׂ⎡�Ó��e�̕W������}��C��Ô�z�̍��ʂɂ�����̂��ʂɕW�������邱�Ƃň�Ô�̏k�����\�ƂȂ�B�ŋ߂ł́C�����悤�Ȗ��ӎ������Ô�̒n�捷�̌������i��ł���i�n�捷������C2001�j�C2006�N�̈�Õی����x�����ŁC�݉@�����Ȃǂɂ��ċc�_���ꂽ�悤�ɁC�n�捷���Œ�x���̒n��ɂ��킹�邱�Ƃɂ���Ĉ�Ô�팸���s�Ȃ��Ƃ����l����������ɂ����f����Ă��Ă���B����ł́C�I������Ô�Ɋւ��Ă��C���l�̔��z�ł��̍팸�\�����l���邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂ł��낤���B
�@�}�W�͑O�q�̎��S�҂ɐ�߂�V�F�A�̍������a�ɂ��āC���̑���Ô�z���J�[�l������ɂ���Č������̂ł���7�j�B�e���a�Ƃ����z�̌`��͗l�X�ȃo���G�[�V���������邪�C�@�E�������ɒ����Ȃ��Ă��邱�ƁC�A���z�̃o���c�L�����ɑ傫�����Ƃ������Ƃ��Ďw�E�ł���B���̕��z�̃o���c�L�̑傫���ɂ́C���ґ����̍���X�e�[�W�̍��C��Ë@�ւ�f�ÉȂ̍��ȂǗl�X�Ȃ��̂��܂܂�Ă���͂��ł��邪�C���������������ɂ�鍷�ق���菜���Ă�������̕��z�̕����v�Z���邱�Ƃɂ��C�I������Ô�̕W�����\����T�邱�Ƃɂ���B���̂��߂ɁC���̂悤�Ȓ莮���̐�����s�Ȃ��B
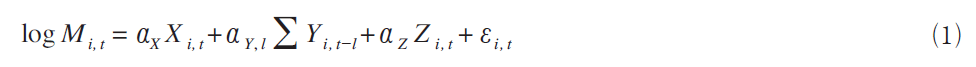
�y22 �Łz
������ϐ� log Mi,t �͎��S�O�P�N�Ԃ̈�l�����茎�ʑ���Ô�ł���C��Ô�z���E���̒����������z�ƂȂ��Ă��邽�߂ɑΐ����Ƃ��Đ��K�������݂Ă���BXi,t �͊��ґ����ł���C���ʁC�N��K���C119���ނ̎��a�ʃ_�~�[�ϐ��C�����ɓ��@���Ă��邩�ۂ��̃_�~�[�ϐ�������Ă���B���@�_�~�[�͎��a�̃X�e�[�W�̑㗝�ϐ��ƍl���Ă��邪�C�ǂ̎����ɓ��@���J�n���邩�Ƃ����I�����́C�팸�\���̂���ϐ��ł���\��������B�����ŁC���@�_�~�[�ɂ��Ă͐����ϐ��Ɋ܂ޒ莮���Ɗ܂܂Ȃ��莮���̂Q�𐄒肷�邱�Ƃɂ����BZi,t �͈�Ë@�֑��̑����ŁC19�̈�Ë@�֎�ނɊւ���_�~�[�C36�̐f�ÉȂɊւ���_�~�[���R���g���[������B���̏�ŁC���S�O���̊e�_�~�[�ϐ�Yi,t-l �̌W���𐄒肵�Cexponential���Ƃ��Ċe���̑���Ô��95���M����Ԃ��Z�o���邱�Ƃɂ��C�l�X�ȑ������R���g���[��������ł̏I������Ô�̕��z�̕����m�F����B���S�O���_�~�[�ɂ��ẮC12�������S�Ă�p���邽�߂ɒ萔�������̃��f���Ƃ��Ă���B
4.2�@���͌���
�\�V�͓��@�_�~�[�����̒莮���ɂ����鐄�茋�ʂł���B119���ނ̎��a�ʃ_�~�[�ϐ��C��Ë@�֎�_�~�[�C�f�Éȃ_�~�[�̌W���͕\�����ȗ����Ă���B���ʁC�N��K���C���S�O�e�����S�ėL�ӂƂȂ��Ă���B���茋�ʂ����ɁC���S�O���̐M����Ԃ��Z�o�������̂��\�W�ł���B�Ⴆ�C���S�����̈�Ô�͐���l��78.3���~�ł���̂ɑ��āC95������71.8���~�C95�����85.4���~�ł���C���z�̕��͂��Ȃ菬�������Ƃ��킩��B����l��95�������̍��͍��X6.5���~���x�ł���C���̕������팸�ł���Ƃ��Ă��|��������Ô��8.3�����x�ɉ߂��Ȃ��B�܂��C���S�O�̊e���Ƃ����̊����͂��������ꏏ�ł���B���S�O�U�����C12�����̒�`�ŏI������Ô���v�Z����ƁC�팸�\���̂����Ô�͂��ꂼ��17.1���~�C22.6���~���x�ŁC����Ô�̂�͂�W�����ɉ߂��Ȃ��B
�@����C���@�_�~�[�L��̒莮���ɂ����鐄�茋�ʂ��\�X�ł���B�M����Ԃ�\�������\10�ł́C�e�W���̐���l��95�������Ƃ̍��̊����͂T���䔼�܂ŏk�����Ă��邱�Ƃ��킩��B�����̌��ʂ�����߂���ƁC�������R���g���[��������ł̏I������Ô�̕��z�̕��͈ӊO�ȂقǏ������C�I������Ô�̃K�C�h���C��������Ȃǂ��āC�Ⴆ95�������ɕW�������s�Ȃ����Ƃ��Ă��C����ɂ���ē������Ô�팸���ʂ͂T�`�W�����x�ƂP���ɂ������Ȃ����Ƃ��킩�����B
�T�D�팸�\���Ɋւ���l�@�Q�F���ȕ��S���̍��ق���̃A�v���[�`
5.1�@���͂̒���_
�I������Â̍팸�ɂ��ẮC��Ò҂��u�݂Ȃ��v���s���ׂ����ǂ����C�I������Âւ̃A�N�Z�X�𐧓x�I�ɐ���₽�Ȃ����C�Ƃ����������T�C�h�̋c�_�ł͂Ȃ��C���Ҏ��g�̎��ȑI���d����Ƃ������v�T�C�h�̎��_���l������B�ނ���C�o�ϊw�I�ɂ͂��̕����{���_�ł���C��O�҂��I������Â��邩�ǂ��������߂���́C�{�l�����߂��������Ҏ匠�̗��ꂩ��͖]�܂����B�������Ȃ���C��i2004�j���ڂ������͂��Ă���悤�ɁC�킪���̏I������Âɂ����銳�Ҏ��ȑI���́C���m�C�C���t�H�[���h�R���Z���g�C���r���O�E�B���Ȃǂ̕��y�C�z�X�s�X�C���y���⑸�����Ɋւ���@���x�ȂǁC�ǂ̓_���Ƃ��Ă���肪�����C���҂��I�����̎��ȑI�����ł�����������Ă���Ƃ͌����������B����ɁC�V�l�̎��ȕ��S����
�y23
�Łz
�P���ƒႭ�C�܂��C���z��Ô�x�̑��݂ɂ��C�I������Ô�̎��ȕ��S���͏���ɒB������͌��E�I�ɂO�ƂȂ��Ă��܂��Ƃ����_���C���҂̎��ȑI�����Â��Ȃ�C�������n�U�[�h�������Ă���Ƃ���C���̔w�i�ƂȂ��Ă���Ǝv����B�����ŁC�����i1998�j���咣����悤�ɁC���҂̎��ȕ��S�������グ�āC���҂�Ƒ��̎��ȑI���𑣂��Ƃ������@�������i�Ƃ��čl������B���ɁC�����K���̉�����Â̂悤�ɁCQOL�����܂�Ƃ͎v���Ȃ��̂ɖc��Ȕ�p�������鎡�ÂɊւ��ẮC�����I������ȏ�́C������x�̎��ȕ��S�����߂邱�Ƃ��Ó��ł���Ǝv����B
�@�����ŁC���ȕ��S���������グ���ꍇ�ɂǂ̒��x�I������Ô�������邩���C���ȕ��S�����ω�����V���ڍs�O��̃f�[�^���琄�����邱�Ƃɂ���B��̓I�ɁC69��70�̔N��ł́C���a�Ȃǂ��R���g���[��������ł́C����قǑ傫�Ȑg�̓I���ق͖����Ǝv���邪�C���ȕ��S�����V���ڍs�O�̂R���ƈڍs��̂P���Ƒ傫���قȂ邱�Ƃɒ��ڂ��C���҂̏I������Ô�̏��r����8�j�B
5.2�@�I������Ô�̏�
�}�X�́C�T���v���̂���69��70�̃f�[�^�����o���C�V���ڍs�O�ƈڍs����Ď��S�O�̌��z��Ô�̏��������̂ł���B�f�[�^�̔N��͖��N�T���P�����_�Ŕc������Ă���N��Ȃ̂Ő��m�ł͂Ȃ����C��ɏq�ׂ��悤�ɁC�V���ւ̈ȍ~���͕ی��敪�i��ʁC�ސE�ҁC�V���j���L�^���Ă��邽�߂ɁC���Ȃ萳�m�ɔc���ł���9�j�B�}���݂�ƁC���S�����ɂ��Ă͘V���ڍs�O�̕�����������̂́C���S�O�P�N�̂ق��̌��ł͘V���ڍs��̕�����т��č������Ƃ��킩��B
�@���ɁC�}10�͎��S�O���ԕʂɈ�l�����葍��Ô�̕��z���C�J�[�l������ɂ���āC�V���ڍs�O�ƈڍs��Ŕ�r�������̂ł���B�܂��C�ŏ�i�̍���̎��S���̑���Ô�z���݂�ƁC�V���ڍs��irouken�j�ƘV���ڍs�O�inon-rouken�j�ł͎�̕��z�̃Y���������Ă��邪�C���z�̒����͂قړ����l�ł���C���ق͔��ɏ��������Ƃ��킩��B���ɁC���̉��̎��S�O�R�����̑���Ô�̕��z���݂�ƁC�傫�ȍ��ق������Ă���B�V���ڍs�O�̕��z�͑o��̕��z�ł���C�ڍs��ɂ͍����̎R������C�E���̎R�������Ȃ��Ă���B���S�O�U�����ł͘V���ڍs�O�C�ڍs��Ƃ��ɑo��ł���C�ڍs��̕����E���̕��z�̎R�������B���S�O12�����ł��V���ڍs�O�ƈڍs��̍��ق͉E���̎R�̑傫���ł���C�V���ڍs��ɉE�̎R�������Ȃ��Ă���B�܂��C���̉E���̎R�ƍ����̎R����ʂ��Ă���̂͂ǂ̂悤�ȗv���Ȃ̂ł��낤���B�E��ł͂��ꂼ��̊��Ԃ��Ƃ̓��@��Ô�݂̂����o���C���z�𐄒肵�����̂ł���B������݂�ƁC���̕��z�̎R�͍���̑���Ô�z�̉E���̎R�Ɉ�v���Ă��邱�Ƃ��킩��B�܂�C����Ô�ɂ�����o��̕��z�͓��@��Ô�Ƃ���ȊO�̈�Ô�ɑΉ����Ă���C�V���ڍs�O�ƈڍs��̑���Ô�̍��ق́C���@�̍��قɂ���Đ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƒz���ł���B���S���͂������ɓ��@���قƂ�ǔ������Ȃ����Ƃ��番�z�͔��ɗގ����Ă��邪�C���S�����炠����x�͂Ȃꂽ���Ԃ̓��@�̏ɂ́C���@�̍��ق������Ă���C���炭����ɂ͎��ȕ��S����
�y24
�Łz
���ق��e�����Ă���Ǝv����B
5.3�@���͂̐헪
�����ŁC���S�����Ƃ̗v����Ô�ɂ��āC���̂悤�Ȓ莮���Ő�����s���C��ʓI�ɘV���ڍs�ɂ��I������Ô�̑������ʂ��v������B
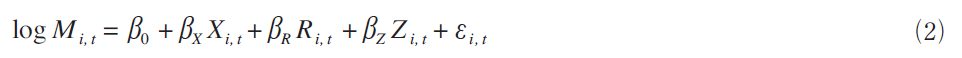
�T���v����69-70�̔N��ŁC�@���S���̂݁C�A���S�O�R�����܂Łi�O-�Q�j�C�B���S�O�U�����i�O-�T�j�܂ŁC�C���S�O12�����܂Łi�O-11�j�̂S���Ԃ̃f�[�^�Z�b�g���쐬�����B������ϐ� log Mi,t �͖����̑���Ô�̑ΐ�������Ă��邪�C���̊��Ԃ͇@�`�C���ƂɌ��肳��Ă���BXi,t �͊��ґ����ł���C���ʁC119���ނ̎��a�ʃ_�~�[�ϐ��C�����ɓ��@���Ă��邩�ۂ��̃_�~�[�ϐ�������Ă���B���@�_�~�[�͎��a�̃X�e�[�W�̑㗝�ϐ��Ƃ��C�팸�\�����܂ޕϐ��Ƃ��l�����邽�߂ɁC�O�߂̕��͓��l�C���@�_�~�[�L��C�����̂Q�̒莮���Ő��肷�邱�Ƃɂ����BZi,t �͈�Ë@�֑��̑����ŁC19�̈�Ë@�֎�ނɊւ���_�~�[�C36�̐f�ÉȂɊւ���_�~�[���R���g���[������B���̏�ŁC�V���ڍs��̃_�~�[�ϐ�Ri,t �̌W���𐄒肵�C�ǂ̒��x�C�V���ڍs�Ŏ��S���ԕʂ̗v����Ô���܂��Ă��邩��]������B�f�[�^�̒P�ʂƂ��ẮC�u�����v�̑���Ô�ł͂Ȃ��C�l���Ƃɗv����Ô������āu�l�ʂɁv���v����Ƃ������@���l����ꂽ���C�V���ڍs��_�~�[Ri,t �������P�ʂ̂��̂ł���C���������ăT���v���ɂ���ẮC����l�̎��S�O���Ԃ̓r���ŘV���Ɉڍs����T���v�����������Ă��邽�߁C�����P�ʂ̃f�[�^�Ő��v���s�Ȃ����Ƃɂ����B�����P�ʂł����Ă��C�f�[�^�Z�b�g�̊��Ԃ��C�ݐψ�Ô�����x�[�X�̊��Ԃŋ���Ă��邽�߁C���v���ʂ͊e���ԕʂ̗ݐψ�Ô��]�����Ă��邱�ƂƓ������ƂɂȂ�B
5.4�@���v����
�\11�͂܂��C���@�_�~�[�����̒莮���̐��茋�ʂł���B119���ނ̎��a�ʃ_�~�[�ϐ��C��Ë@�֎�_�~�[�C�f�Éȃ_�~�[�̌W���͕\�����ȗ����Ă���B�V���ڍs�_�~�[�̌W���́C���S���̃T���v���ŗL�ӂł͂Ȃ����̂́C���S�O�R�����C�U�����C12�����ł͂��ꂼ��L�ӂȌ��ʂƂȂ��Ă���B�W���̑傫�����݂�ƁC���S�O�R�����̗ݐϑ���Ô�͘V���ڍs�O�ɔ�ׂ�43.0���������Ȃ��Ă���C�U�����̏ꍇ�ɂ�35.4���C12�����̏ꍇ�ɂ�30.2�����܂��Ă��邱�Ƃ��킩��B�������Ȃ���C���S�O�̓��@�ɂ��ẮC���ȕ��S���̍��قɂ�郂�����n�U�[�h�̕\��Ƃ��č팸�ΏۂƂ݂�̂��C�a��̃X�e�[�W��K�v���̍�����Ís�ׂƂ��Ĕ������������̂Ƃ��č팸�s�\�Ȃ��̂ƌ��邩�ɂ���āC���_�͑傫���ς��B�����ŁC���@�_�~�[������ϐ��ɉ����č팸�s�\�Ȃ��̂Ƃ��C���S�O�̓��@�m���̍����R���g���[��������ŁC����ł��V���ڍs�ɂ���ďI������Ô�ǂ�قǕς�肤��̂��������̂��C���@�L��̃��f���ł���B�\12�̌��ʂ��݂�ƁC�V���ڍs�_�~�[�̌W���́C���S���̃T���v���ł����L�ӂł͂Ȃ����̂́C���S�O�R�����C�U�����C12�����ł͂��ꂼ��L�ӂȌ��ʂƂȂ��Ă���C�W�����画�f����ƁC���̏ꍇ�ɂ����Ă��C���ꂼ��V���ڍs�O�ɔ�ׂ�17.2���C20.1���C24.7���ݐψ�Ô�����Ȃ��Ă��邱�Ƃ�������B�������C�����l�ɂ�69��70�̐g�̓I�ȍ��ق̉e�����킸���Ɋ܂܂�Ă���\�������邪�C������l��������ł����Ȃ茰���� �y25 �Łz �����l���Ǝv����B
�U�D�팸�\���Ɋւ���l�@�R�F���ی��J�n�ɂ�鍷�ق���̃A�v���[�`
6.1�@���ӎ��Ɖ��ی��J�n�O��̏�
�����J���Ȃ����Z���Ă���悤�ɁC�����C�ݑ��Â�ݑ���̐��i�ɂ���ďI������Ô�啝�Ɍ�������̂ł���C���ɉ��ی��J�n���ɏI������Ô�̕ω�������ꂽ�͂��ł���B���Ȃ킿�C���ی��J�n�ɂ���čݑ������{�݂ł̎���Ԑ��̐������i���Ƃ���C��r�I��Â̕K�v���̏��Ȃ���ԂŎ��S���}����l�X�ɂ��ẮC���@�m�����邢�͓��@���Ԃ����Ȃ��Ȃ��āC���ی���͏I������Ô���������Ǝv����B
�@�����ł܂��C�O�߂Ɠ��l�ɁC���S�O���Ԃɂ����鎀�S�҈�l������̌��ʈ�Ô��m�F���邱�Ƃɂ���B�}11�͉��ی��O��1998�N�S������1999�N�R���ƁC�������2000�N�S������2003�N�R���܂ł̌��ʈ�Ô���r�������̂ł���B���҂͂قƂ�Ǔ����`������Ă���C���҂̍��ق͔��ɏ��������Ƃ��킩��B�悭����ƁC���S�����玀�S�O�R�����ł͎�Ȃ�����ی��J�n��̑���Ô�����C���S�O�R�����ȑO�ł͉��ی��O�̕�������Ô�����悤�Ɍ�����B���ɁC���S�O�����Ƃ̑���Ô�̕��z�y�ѓ��@��Ô�̕��z���݂����̂��}12�ł���B�O�߂̐}10�Ɠ��l�̏����ŕ���ł���B���ی��J�n��ikaigo�j�ƊJ�n�O�inon-kaigo�j�ŕ����Ă���B���S���̑���Ô���݂�ƁC��Ȃ��璆���l�͉��ی��J�n��̕��������Ȃ��Ă��邱�Ƃ��킩��B����C���S�O�R�����C�U�����C12�����̑���Ô�̕��z���݂�ƁC��͂�C�O�߂ł݂�ꂽ�悤�ȑo��̕��z�����Ă��邪�C���@��Ô�̉E�̎R�͉��ی��J�n��ɑS�ĒႭ�Ȃ��Ă��邱�Ƃ��킩��B�������Ȃ���C�E�̓��@�̎R�̒����l�͖��炩�ɉE�ɂ���Ă���i�E��̓��@��Ô�j�C���������ē��@�m���������������ƂƁC���@��Ô�̕��z���E�ɂ��ꂽ���Ƃ����E�������āC���S�O���̉��ی��O��̕ω����قƂ�Ǒ��݂��Ȃ��悤�Ɍ�����̂��Ǝv����B
6.2�@����ɂ���l�����莀�S�O��Ô�̕ω�
�������Ȃ���C���ی��O��̔�r�͎��n��Ԃ̔�r�ƂȂ邽�߂ɁC�O�߂Ƃ͈قȂ�C���̊Ԃ̔N��̏㏸�Ȃǂ̑����̕ω����R���g���[�����Ĕ�r���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ŁC���ی��J�n�O��̌��ʂ��ʓI�ɕ߂炦�邽�߂ɁC���̂悤�Ȓ莮���Ő��v���s�Ȃ��B
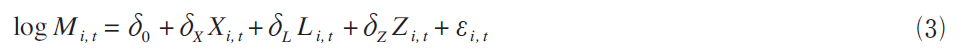
�㎮��(2)���Ƃ��Ȃ�ގ����Ă���B�T���v����65�Έȏ�̑S�N��ŁC�@���S���̂݁C�A���S�O�R�����܂Łi�O-�Q�j�C�B���S�O�U�����i�O-�T�j�܂ŁC�C���S�O12�����܂Łi�O-11�j�̂S���Ԃ̃f�[�^�Z�b�g���쐬�����B������ϐ� log Mi,t �́C�f�[�^�Z�b�g���ƂɁC�����̑���Ô�̑ΐ�������Ă���BXi,t ��(3)���l�̊��ґ����ł���C���ʁC�N��K���C119���ނ̎��a�ʃ_�~�[�ϐ��C�����ɓ��@���Ă��邩�ۂ��̃_�~�[�ϐ��ł���B���@�_�~�[��(1)(2)���l�C�L�薳���̂Q�̒莮���Ő��肵���BZi,t �͈�Ë@�֑��̑����ŁC19�̈�Ë@�֎�ނɊւ���_�~�[�C36�̐f�ÉȂɊւ���_�~�[���R���g���[������B���̏�ŁC���ی��J�n��̃_�~�[�ϐ� Li,t �̌W���𐄒肵�]�����s���B�f�[�^�̒P�ʂ́C(2)���l�C�����P�ʂ̑���Ô�ł���C�T���v���Ŋ�
�y26
�Łz
�Ԃ��@�`�C�̂悤�ɋ���Ă��邱�Ƃɂ��C�ݐϑ���Ô�̃x�[�X�Ő��v���邱�ƂƊ�{�I�ɂ͕ς��Ȃ��B
�@�\13�́C���@�_�~�[�����̒莮���ɂ��āC�T���v�����ԕʂɐ��v���s�Ȃ������ʂł���B119���ނ̎��a�ʃ_�~�[�ϐ��C��Ë@�֎�_�~�[�C�f�Éȃ_�~�[�̌W���͕\�����ȗ����Ă���B���ی��_�~�[�̌W���́C���S���̃T���v���ŗL�ӂł͂Ȃ����̂́C���S�O�R�����C�U�����C12�����ł͂��ꂼ��L�ӂȌ��ʂƂȂ��Ă���B�W���̑傫�����݂�ƁC���S�O�R�����̗ݐϑ���Ô�͉��ی��J�n�ɂ����3.5�������Ȃ��Ă���C���S�O�U������7.8���C���S�O12������10.4�������Ȃ��Ă���B���ɓ��@�_�~�[���l�����ē��@�m���̍��ق��R���g���[�������ꍇ�ɂ��Ă̐��茋�ʂ��݂�Ɓi�\13�j�C���S�O�R�����ł�͂�3.5���C���S�O�U������5.4���C���S�O12������8.0�������Ȃ��Ă���B���̎����C�f�Õ�V��2000�N����Ŏ���0.2���̈��グ�C2002�N����|2.7���̈������ł��������C����ҕ����w���i�ی���Áj��1998�N��99.1����C99�N98.4�C2000�N97.6�C2001�N98.2�C2002�N97.1�Ƃނ��뉺�����Ă���̂ŁC���ی��J�n�ɂ���Ď��S�҈�l������̏I������Ô�́C��͂�����オ�����Ƃ����邾�낤�B
6.3�@���@���S���C���@�m���C���S�҂̈�Ô���̕ω�
�������Ȃ���C�g�[�^���̏I������Ô�ǂ��ω������������邽�߂ɂ́C���ی��J�n�ɂ���āC���@���S���⎀�S�҂̓��@�m�����ǂ̂悤�ɕω������̂������킹�Ă݂�K�v������B�\14�́C���@���S���i���@���o�R���Ď��S���闦�j�Ǝ��S�҂̓��@���i���S�҂̂������@�����Ă����l�̔䗦�j�̐��ڂ�1998�N�x����2002�N�x�ɂ��Đ��ڂ��݂����̂ł���B���S�҂̒�`�͕\�P�Ɠ��l�C���̔N�x���Ɏ��S�����҂Ƃ�����`�ł���B�\14���݂�ƁC���ی��O�̓��@���S����2.7���i1998�N�x�j�C2.6���i1999�N�x�j�ł��������̂��C���ی���J�n��ɂ�2.4���i2000�N�x�j�C2.3���i2001�N�x�j�C2.4���i2002�N�x�j�Ǝ�������Ă���B���S�҂̓��@�m���͊��ɐ}12�̊e�O���t�ɂ����Ă��m�F�ł��Ă��邪�C�������m�F����ƁC���ی��O��79.6���i1998�N�x�j�C79.4���i1999�N�x�j�ɑ��āC���ی��J�n��ɂ�78.0���i2000�N�x�j�C76.5���i2001�N�x�j�C77.8���i2002�N�x�j�Ƃ�⌸�����Ă���B�N�������Ă���e�����R���g���[�����邽�߂ɁC�N��K���ʂɂ݂Ă��C�S�Ă̔N��K���œ��l�̌X����������B���ɍ����N��K�w�قǁC���@�m����������x�������傫���C���@���o���ɉ��̕���Ŏ��S���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƒz�������B���̌��ʂƂ��āC�\�P�Ōv�Z�������̂Ɠ��l�ɁC���S�҈�Ô�̑���Ô�ɐ�߂銄�����e�N�x�Ōv�Z����ƁC���̎���������i�W���Ă���ɂ��ւ�炸�C���ی��O��10.3���i1998�N�x�j�C10.0���i1999�N�x�j����C���ی��J�n���9.5���i2000�N�x�j�C9.3���i2001�N�x�j�Ɖ������Ă���C2002�N�x�ɂȂ��Ă悤�₭10.4���ɂȂ������Ƃ����������B�܂�C���ی��J�n�ɂ���āC���{�݂�ݑ���̎M�����������Ƃ��C��Ȃœ��@���Ď��S����l�X�̊��������������C���S�҂̈�Ô�̐�߂銄�����̂������������ƍl������ł��낤�B���{�݂�ݑ���ŊŎ���ꍇ�ɂ͑��ΓI�ɏd�ĂȎ����ł͂Ȃ��ƍl������̂ŁC���ʂƂ��āC��Õی��̃��Z�v�g�f�[�^�ɔ��f������l������̏I������Ô�́C��Ô�̏��Ȃ��Ώێ҂�������邱�Ƃɂ���āC���ی���Ɏ�̏㏸���݂����̂ł͂Ȃ����Ƒz�������B
�y27 �Łz
�V�D����
�{�e�́C�x�R���ɂ�����65�Έȏ�̍������N�ی������҂�1998�N�S������2003�N�R���̂T�N�Ԃ̐ڑ����Z�v�g�f�[�^��p���āC�I������Ô�̌���ɂ��Ċm�F���C���̏�ŁC�@�I������Ô�̒n��i���Ȃǂɂ�镪�z�̕��C�A�V���ڍs�O��̎��ȕ��S���ω��ƏI������Â̊W�C�B���ی��J�n�ɂ��ݑ��ÁE��쑣�i�̎��R�����iNatural Experiment�j�̌��ʂ���C�I������Â̍팸�\�����c�_���邤���ŕK�v�ƂȂ��b�I�������W�����B�܂��C�I������Â̌���ɂ��ẮC�x�R���Ƃ����n�����̌��ʂł͂��邪�C2002�N�x�̎��S�҂̈�Ô�i���@�C���@�O�̂ق��C���܁C���Ȃ��܂ށj�́C10.4���ł���C���̓���̂قƂ�ǂ́C���@��Ô�ł������i87.0���j�B�܂��C���S�҂̓��@��Ô�S�̂̓��@��Ô�ɐ�߂銄���́C17.5���ł������B���S�҈�l������̎��S�O�P�N�Ԃ̌��ʈ�Ô�̐��ڂ��݂�ƁC�{��E�S�i�i1994�j�C�{��i1998�j��1990�N�㏉�߂̃f�[�^�Ŋm�F�����悤�ɁC�@���S���ɋ߂Â��قlj����I�ɍ������Ă䂫�C���Ɏ��S�O�U�������猰���ł���C�A�N��K���ʂɂ͍���ɂȂ�قǍ������ɂ₩�ł���C�S�̗̂ݐψ�Ô�����Ȃ��C�B���@�̃J�e�S���[�ʂŃp�^�[�����傫���ς�鎖�Ȃǂ��m�F���ꂽ�B�܂��C����V���ɁC���a�ʂ̃p�^�[�����Ë@�֕ʂ̃p�^�[���Ȃǂɂ��Ă����s�Ȃ����B
�@�I������Ô�̕��z�̕��ɂ��ẮC���ґ������Ë@�֑��̓������l��������ł���95����Ԃ����߂�ƁC���ϒl�Ɖ����̍��͂T���`�W���ƈӊO�ɏ��������Ƃ��킩�����B���ɁC�g�̓I�ȍ��ق����������̂̎��ȕ��S�����傫���قȂ�69��70�̐l�X�ɑ��āC�V���ڍs�O��̏I������Ô���r����ƁC���S�O12��������R�����܂ł̓��@�̍��ق�����Ƃ��āC�V���ڍs��ɏI������Ô20�`40�����x�傫���Ȃ邱�Ƃ����������B�Ō�ɁC���ی��J�n�O��ŏI������Ô���r�����Ƃ���C���ی���ɁC���@���S���⎀�S�҂̓��@�m���������������߂ɁC���S�҂̈�Ô���͌������Ă��邱�Ƃ����������B�������C��l������̎��S�O��Ô�͂R�`10���قlj��ی��J�n��ɑ������Ă���C���{�݂�ݑ�ɃV�t�g�����l�X�͔�r�I��z�̏I������Ô�ł��������Ƃ��z�������B
�@�{�e�̌��ʂ���܂������邱�Ƃ́C�������R���g���[�������I������Ô�̕��z�̕��͈ӊO�ɏ������C���������ĕW�����ɂ��팸�]�n�͈ȊO�ɏ������Ƃ������Ƃł���B
�@���ɂ����邱�Ƃ́C�I������Ô�ɑ��鎩�ȕ��S�������グ�邱�Ƃ́C��Ô�팸�Ƃ����Ӗ��ł͂�����x���ʓI�ł���\��������Ƃ������Ƃł���B�������C���̏ꍇ�ɂ͂����܂ň�ẪA�E�g�J���i�������C�������C�������ԁCQOL�̉j���ς��Ȃ��Ƃ������Ƃ��O��ł���B�����C���ȕ��S��������������C��Ô�}������邱�ƂŃA�E�g�J���̃��x����������Ƃ������Ƃł���C�P���Ɉ�Ô�팸�̂��߂Ɏ��ȕ��S���グ��ׂ��Ƃ����c�_�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��낤�B�{�e�̕��͂ł́C���S�҂݂̂����o���Ă݂Ă��邽�߂ɁC�����҂��܂߂Ă��̎����̈�Ís�ׂ��ǂ̂悤�ȃA�E�g�J���ݏo���Ă��邩��K�ɕ]���ł��Ȃ��B���̓_��T�邽�߂ɂ́C�ʂ̊p�x����̕��͂��K�v�ł���B
�@�Ō�ɉ��ی��J�n�O��̕��͂���́C�ݑ��ÁE�ݑ���̐��i�ɂ��I������Ô�̌����́C���̌��ʂ�������Ƃ������Ƃ��z�������B�������C����͔�r�I��z�̈�Ô�̂Ƃ���ŃV�t�g���N����̂ł���C���z�̈�Ô�|���镔���ł͈ˑR�Ƃ��Ĉ�Ë@�ււ̓��@���K�v�ł���B���̏ꍇ�C��l������̎��S�O��Ô���㏸����Ƃ������ۂ������邱
�y28
�Łz
�Ƃ���C�ݑ��ÁE��쐄�i�ɂ��I������Ô�팸���ʂɂ��Ă��܂�ߑ�Ȋ��҂͋֕��ł���Ƃ����邾�낤�B
�Q�l����
���g�J�q�p�i2004�j�u���S�O��N�Ԃ̈�Â���щ���p�̌����v �w�G���Љ�ۏጤ���x Vol.40�CNo.3�Cpp.236-243
�Έ���U�i1998a�j�u�V�l�ւ̈�Â͖��Ӗ��� �� �s��V�l�̐�������ے肷�� �u�|���E�L����v�v �w�Љ�ی��{��x 1973���Cpp.6-14
�Έ���U�i1998b�j�u�݂Ȃ������Ƃ������� �� �L�䎁�ւ̉v �w�Љ�ی��{��x 1983���Cpp.14-18�C1984���Cpp.36-39�C1985���Cpp.32-35
�Έ���U�i2001�j�u�I������Ô�͈�Ô��@�������炷�� �u�I�����ɂ�����P�A�ɌW��鐧�x�y�ѐ���Ɋւ��錤�����v �̐������ǂݕ��v �w�Љ�ی��{��x 2086���Cpp.6-14
��Ìo�ό����@�\�i2000�j�u�I�����ɂ�����P�A�ɌW��鐧�x�y�ѐ���Ɋւ��錤�����v
����N�j�i2002�j�u����̈�Ô�ւ̉e���y�ѓ��@���Ԃ̕��́v �w�G���Љ�ۏጤ���x 38�i�P�j�F52-66
���������E��ؗ�q�i1998�j�u���{�̘V�l��Ô�̕��z��̏����ɂ��āv �w���{�o�ό����x No.36�Cpp.154-183
�Љ����a�i2001�j�u�I�����ɂ�����P�A�ɌW��鐧�x�y�ѐ���ɂ��āv �w�Љ�ی��{��x 2095���Cpp.12-15
�����J���ȁE�I������ÂɊւ��钲����������i2004�j�u�I������ÂɊւ��钲�����������������̏I������Â݂̍���ɂ��Ą��v
���؍��T�E�r���E�Έ���U�i2002a�j�u���S����҂̈�Ô�͖{���ɍ����̂������@��Ô�̔N��K�w�ʕ��́E�P�v �w�a�@�x 61�i�U�j�F482-486
���؍��T�E�r���E�Έ���U�i2002a�j�u���S����҂̈�Ô�͖{���ɍ����̂������@��Ô�̔N��K�w�ʕ��́E�Q�v �w�a�@�x 61�i�V�j�F578-582
��ؘj�i2002�j�u�I������Â̎��Ȍ���Ɋւ���o�ϊw�I�l�@�v �wGerontology New Horizon�x 14�i�R�j�F��245-249
��ؘj�E��ؗ�q�i2003�j�u�����̒������͘V�l��Ô���̗v�����H�v �w���ی��������x �i����w�j��W����Q���Cpp.1-14
��ؘj�i2004�j�u�I������Â̊��Ҏ��ȑI���Ɋւ�����ؕ��́v �w��ÂƎЉ�x �i���c�@�l�E��ÉȊw�������j��14���R���Cpp.175-189
���؈��Y�i2001�j�u����҂̃^�[�~�i���P�A�Ɛ����I���FQOL �̌���Ǝ��Ȍ���̉ۑ�ƓW�]�v �w��ÂƎЉ�x 10�i�S�j�F25-40
�����Љ�J���Z���^�[�i1994�j �w�V�l��ÂƏI������ÂɊւ�����Ĕ�r�������x
�����Љ�J���Z���^�[�i1997�j �w �u�����̃^�[�~�i���P�A�v �Ɋւ��钲���������ƕ��x
���c���F�i2001b�j�u�G�R�m�~�X�g�̏I������Íl�i�����W���I���̈�Â��������j�v �w�O�c�]�_�x 1036���Cpp.24-29
����L�I�i2005�j�u���U��Ô�̐��v������I���S�҂̎��S�O��Ô���ɂ�鐄�v���v �w��Ìo�ό����x vol.16
�������O�i1998�j�u21���I��Õی����v�̉ۑ�v �w�Љ�ی��{��x No.2001�Cpp.6-10
�L��ǓT�i1998�j�u�^�[�~�i���P�A�_�c�ɂ����Đ^�ɋ��߂��鎋�_�͉������u���̈�É��v�ւ̐[�� �y29 �Łz �^��ɂ��ā\�v �w�Љ�ی��{��x No.1975�Cpp.13-17
�{��N�v�i1998�j�u�V�l���S�҂̈�Ô�v �S�i�čW�Ғ� �w�V�l��Ô�̌����x �ۑP�v���l�b�g�������
�{��N�v�E�S�i�čW�i1994�j�u�V�l���S�҂̈�Ô�v �w��Ìo�ό����x Vol.1�Cpp.107-118
�{��N�v�E���ʖM�q�E��z�q�i1994�j�u�V�l��Âɂ����鎀�S���̐f�Ís�ׂ̓����v �w���{���O�q���G���x Vol.42�i11�j�Cpp.942-949
�O�c�M�Y�i1987�j�u���@��Ô�̍����Ǝ��S�O��Ô�v �w�V�l�̕ی��ƈ�Áx ���{�]�_��
���������i1998�j�u����҂̏I�����Ƃ��̎��Ӂ\�݂Ȃ������͍����Ɏ�����邩�\�v �w�Љ�ی��{��x No.1976�Cpp.13-19
Felder S., Meier M. and Schmitt H. �i2000�j, �gHealth Care Expenditure in the Last Months of Life�h, Journal of Health Economics, vol.19:pp.679-695.
Garber, A. M., T. E. MaCurdy, and M. C. McClellan �i1999�j, �gMedical Care at the End of Life: Diseases, Treatment Patterns, and Costs�h Frontiers in Health Policy Research. Garber, Alan M., ed., Cambridge: MIT Press, pp. 77-98.
Hoover DR, et al �i2002�j, �gMedical expenditures during the last year of life�h Health Serveses Research 37, pp.1625-1642
Liu K, et al �i2006�j, �gEnd of life Medicare and Medicaid expenditures for dually eligible beneficiaries�h Health Care Financing Review 27�i4�j, pp.95-110
Lubits, J. and Prihoda, T. �i1984�j, �gUse and costs of medicare services in the last two years of life�h Health Care Financing Review 5�i3�j, pp.117-131
Lubits, J., J. Beebe and C. Baker �i1995�j, �gLongevity and Medicare Expenditure,�h The New England Journal of Medicine Vol.332, pp.999-1003
Polder JJ, et al �i2006�j, �gHealth care costs in the last year of life -The Dutch experience�h Social Science and Medicine 63, pp.1720-1731
Scitovsky A. A. �i1984�j �gThe High Cost of Dying: What do the Data Show?�h, The Milbank Quarterly, vol.62�i4�j, pp.591-608.
Stooker T, et al �i2001�j, �gCosts in the last year of life in the Netherlands�h Inquiry 38, pp.73-80
�y30 �Łz
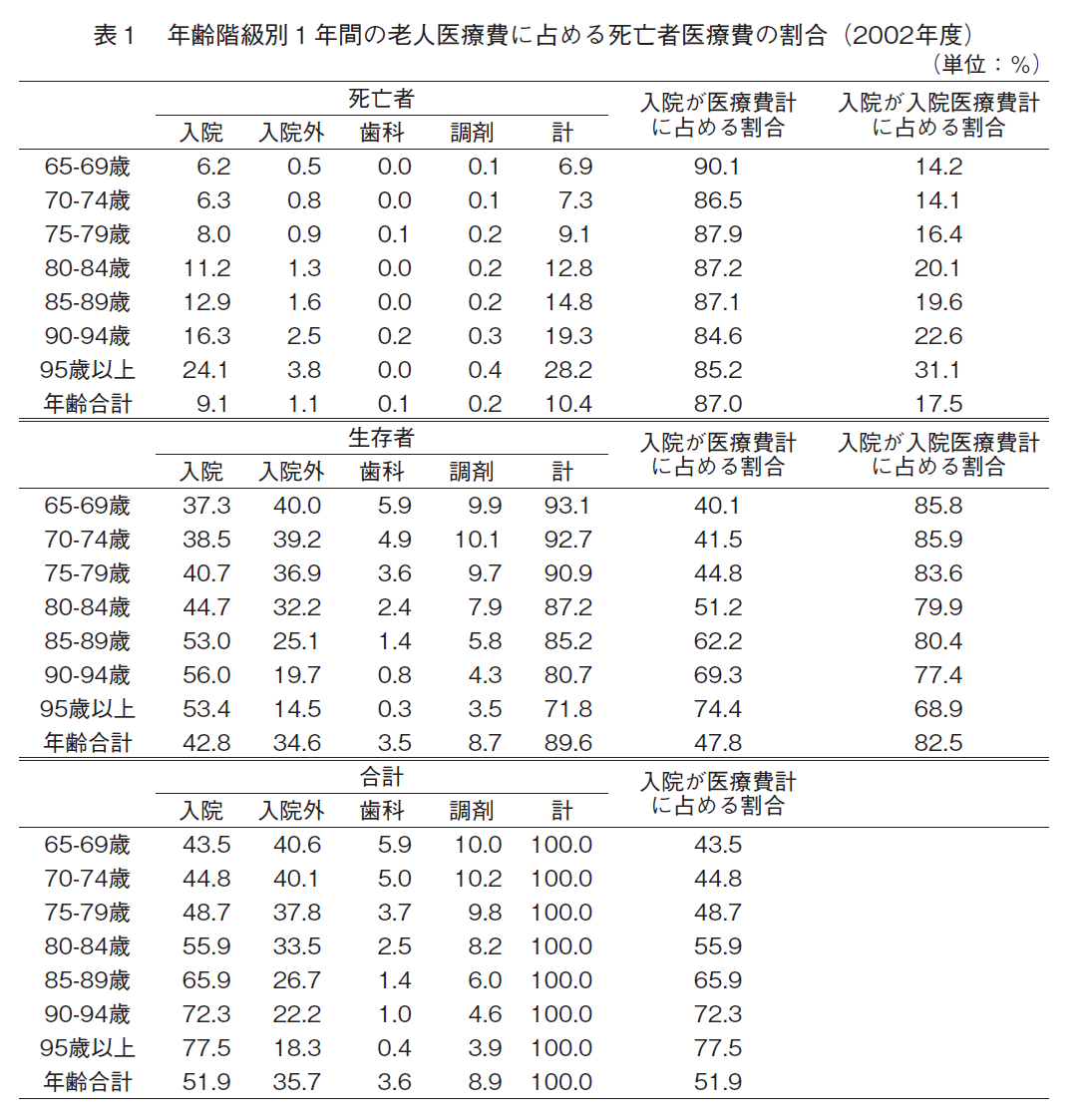
�y31 �Łz
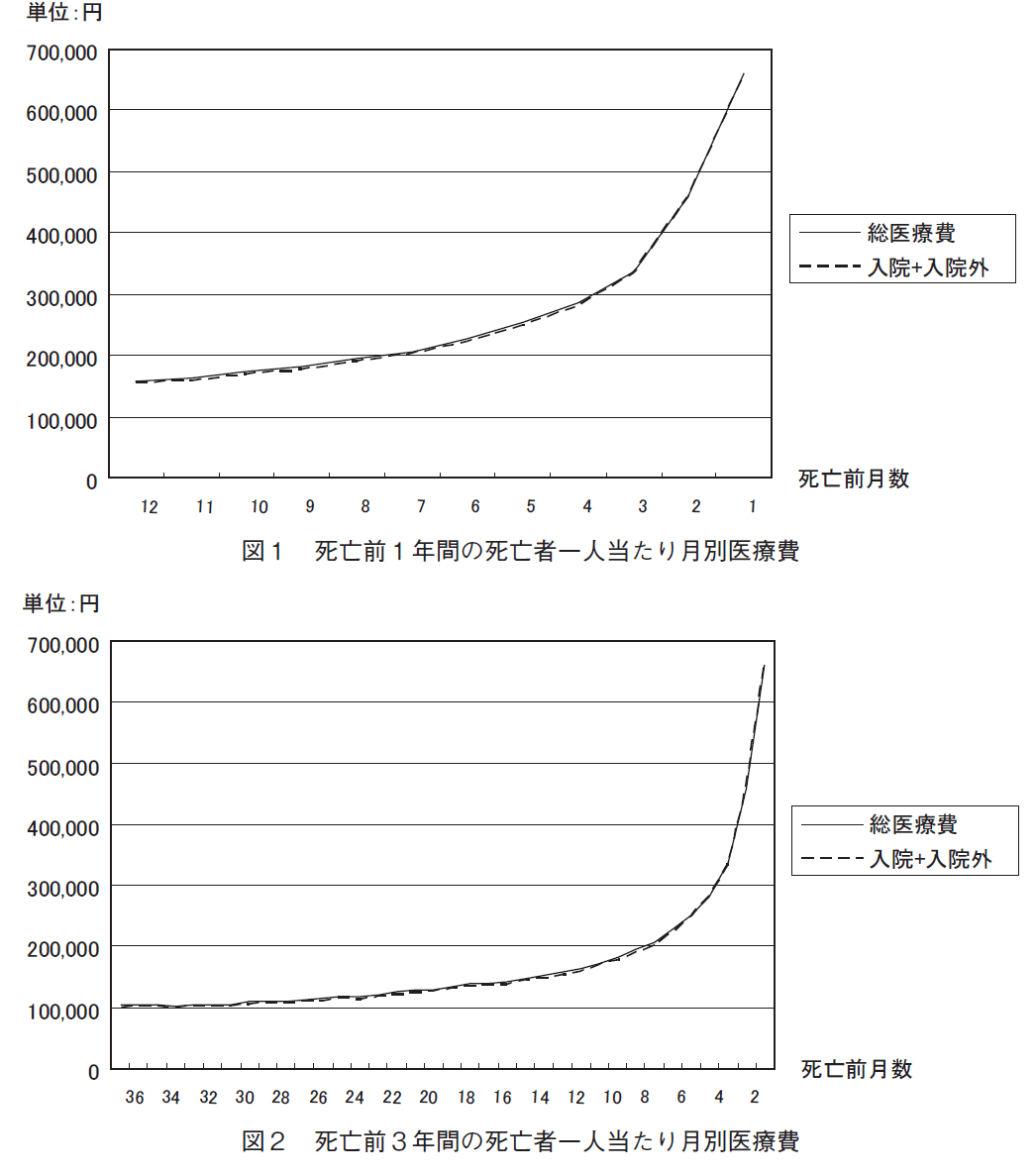
�y32 �Łz
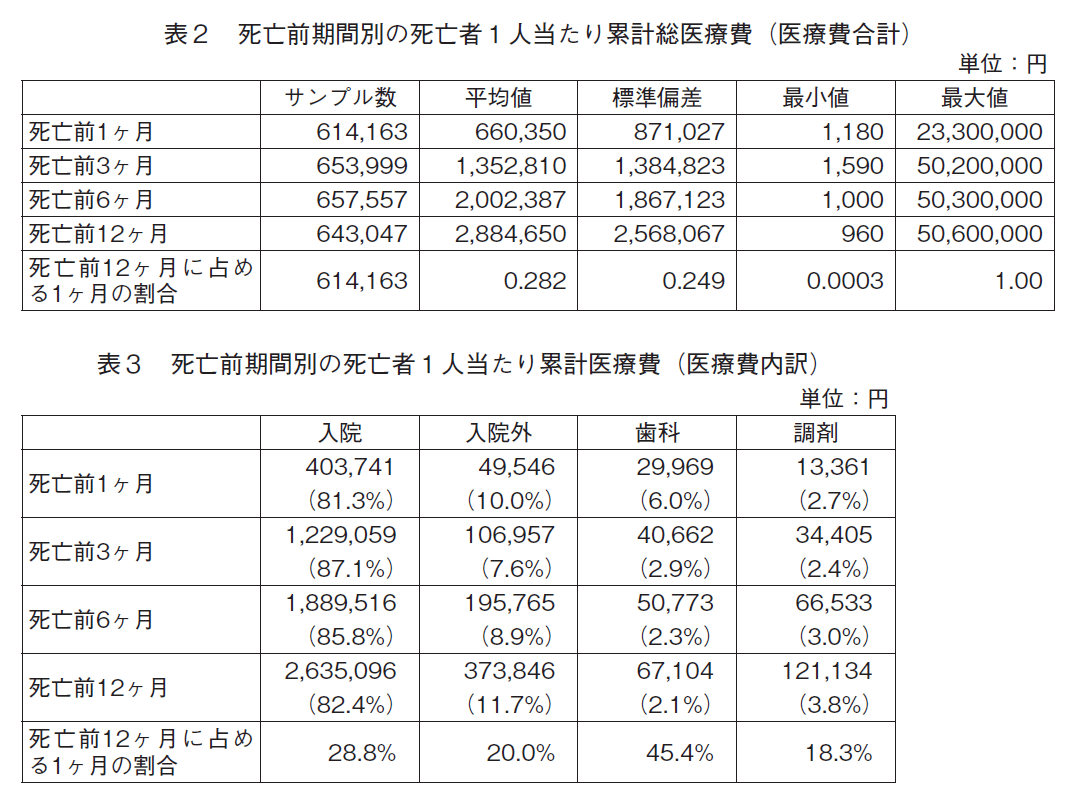
�y33 �Łz
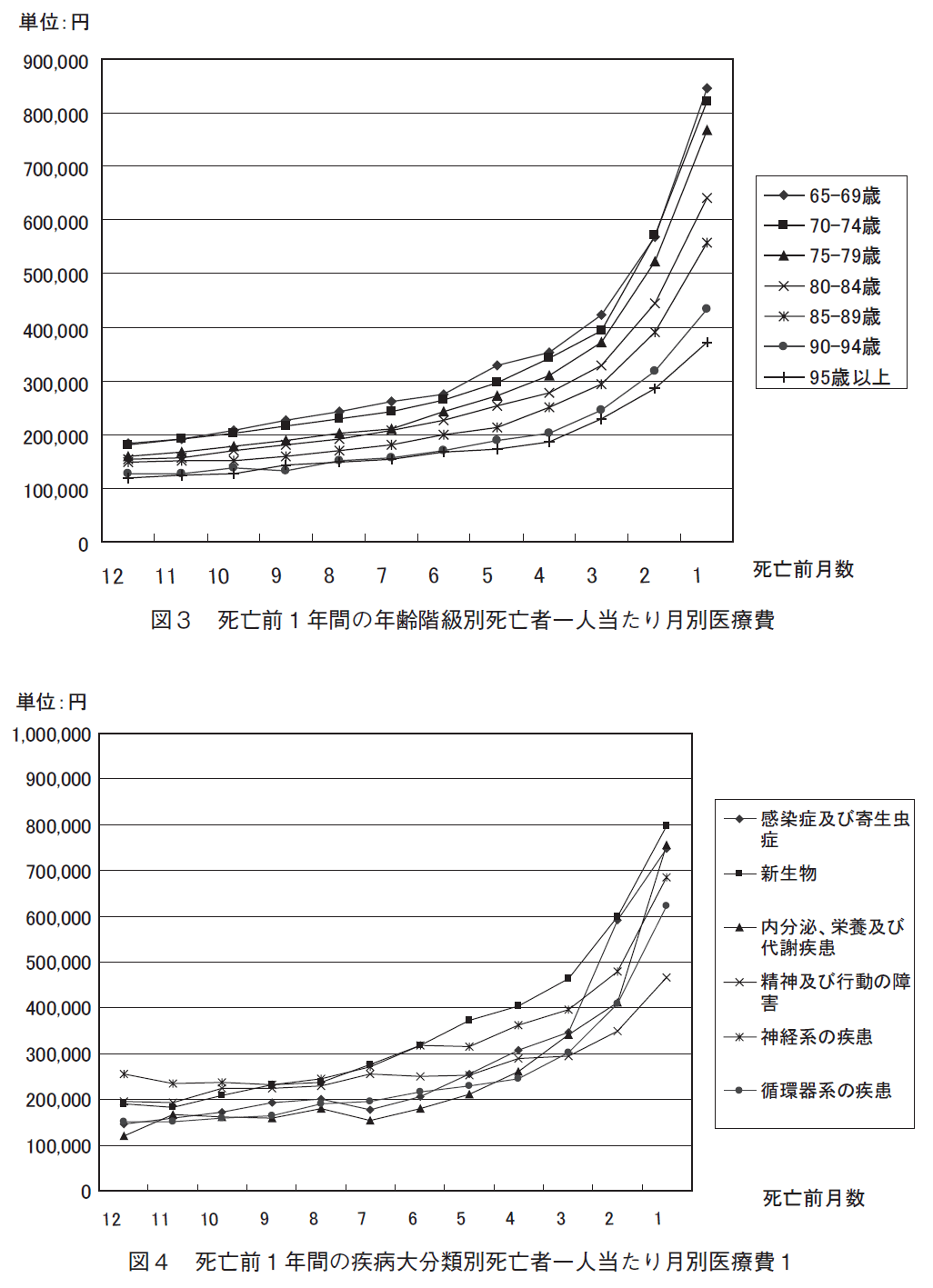
�y34 �Łz
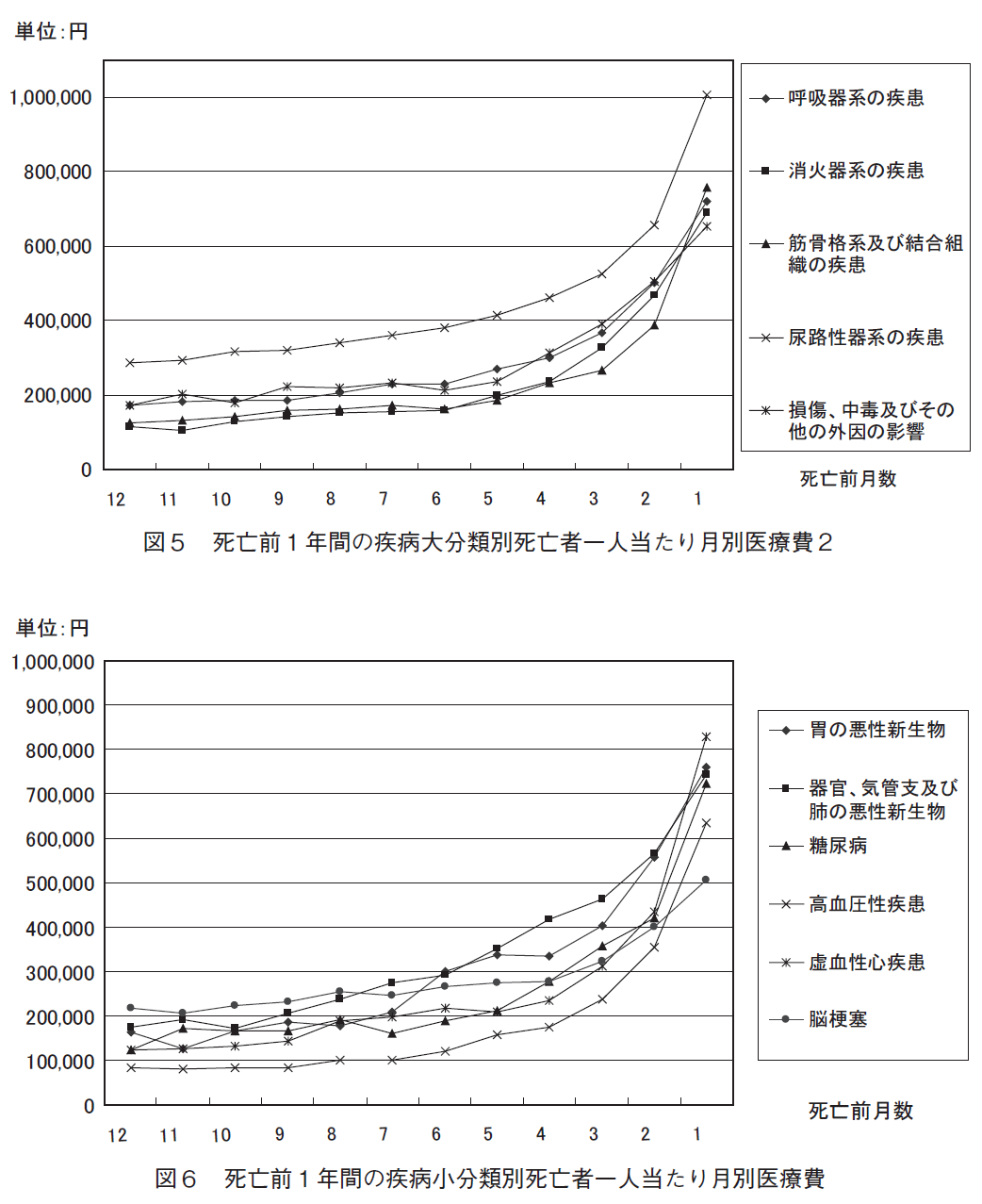
�y35 �Łz
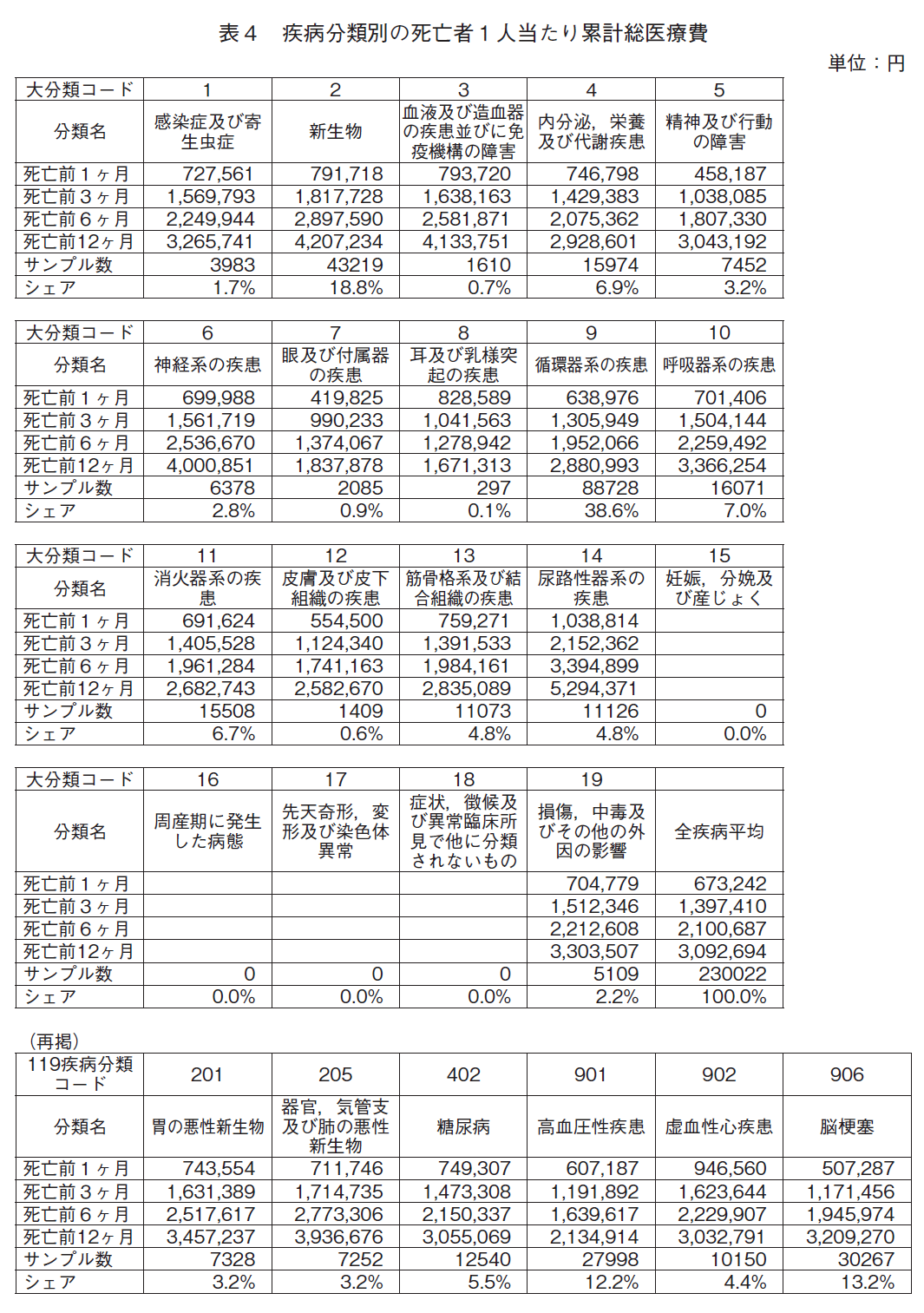
�y36 �Łz
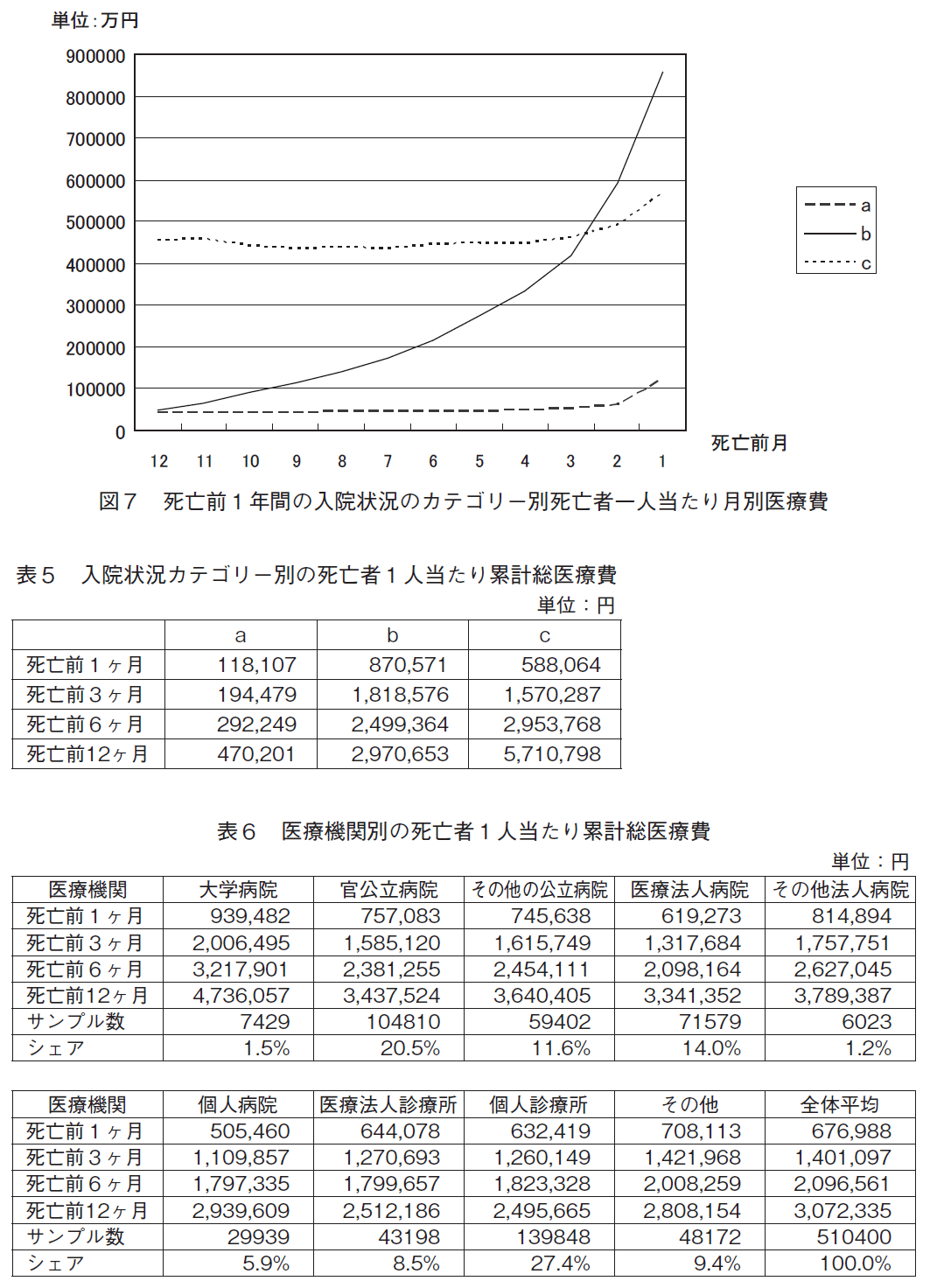
�y37 �Łz
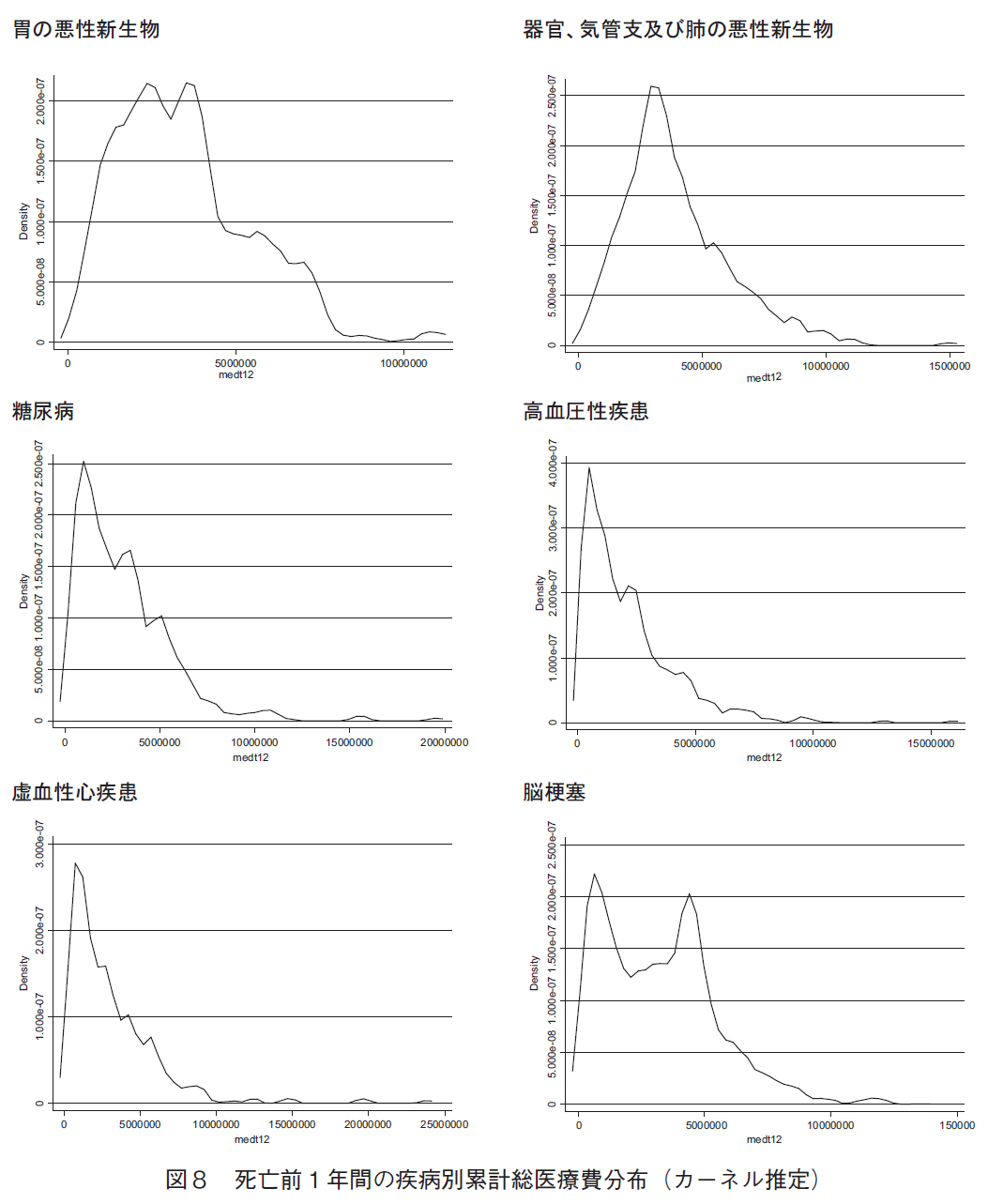
�y38 �Łz
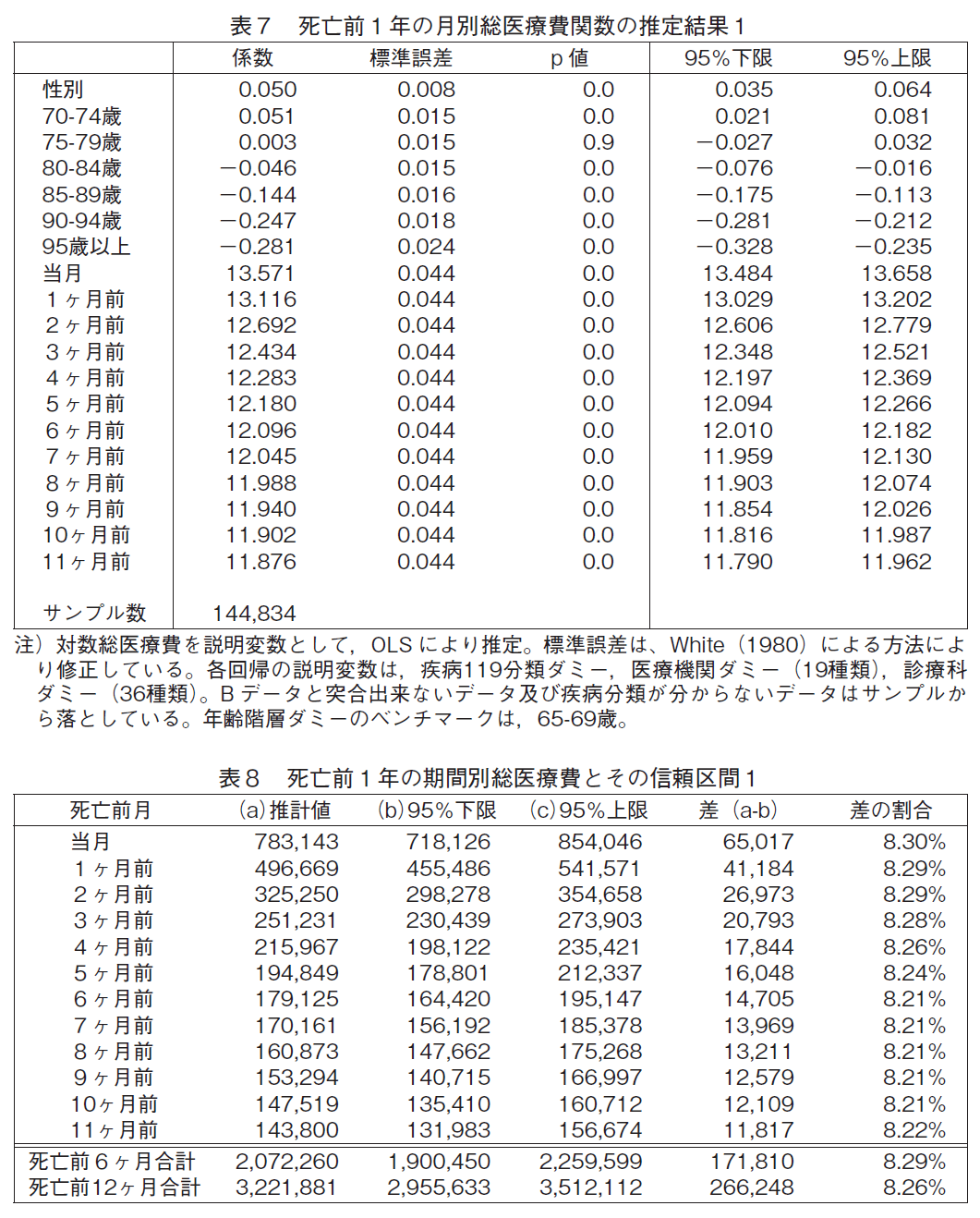
�y39 �Łz
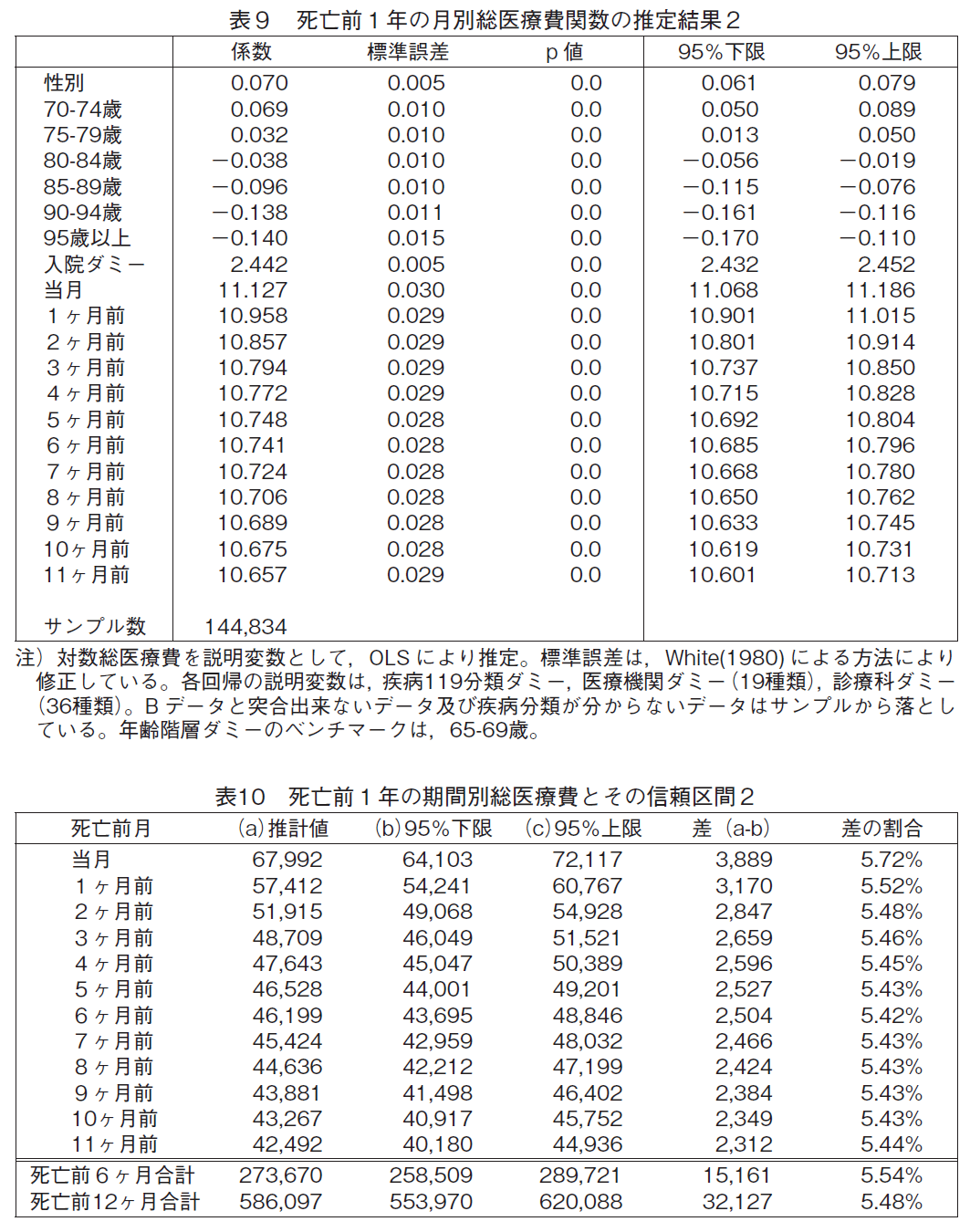
�y40 �Łz
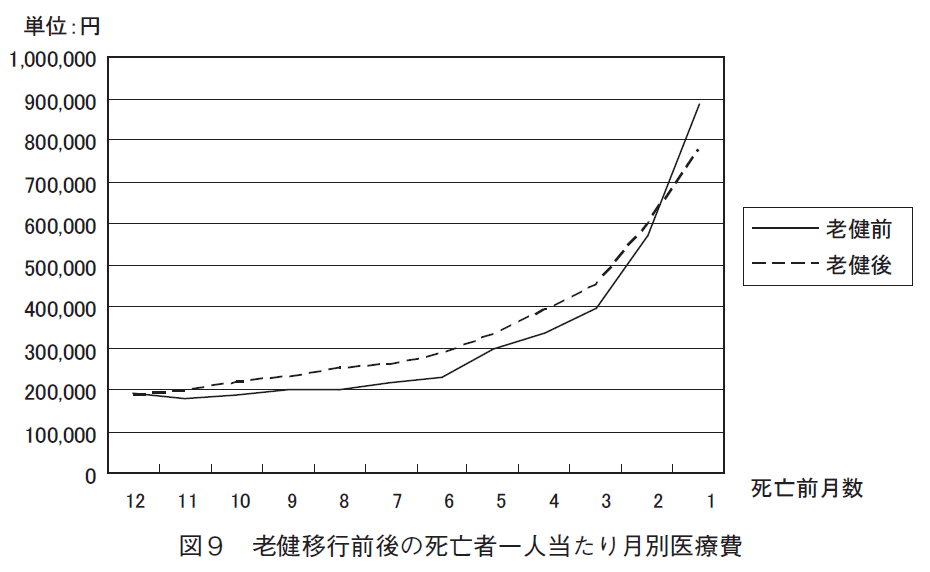
�y41 �Łz
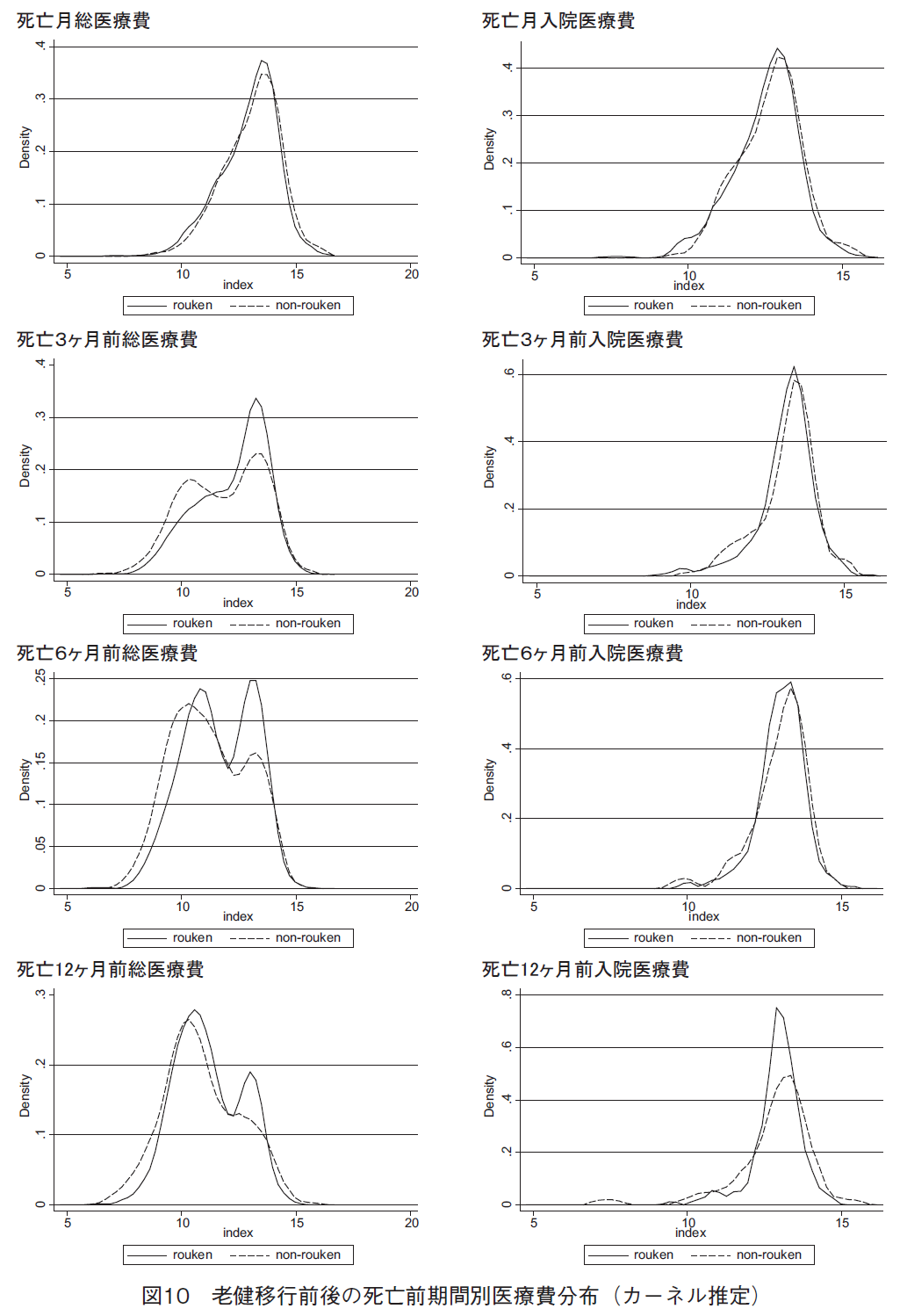
�y42 �Łz
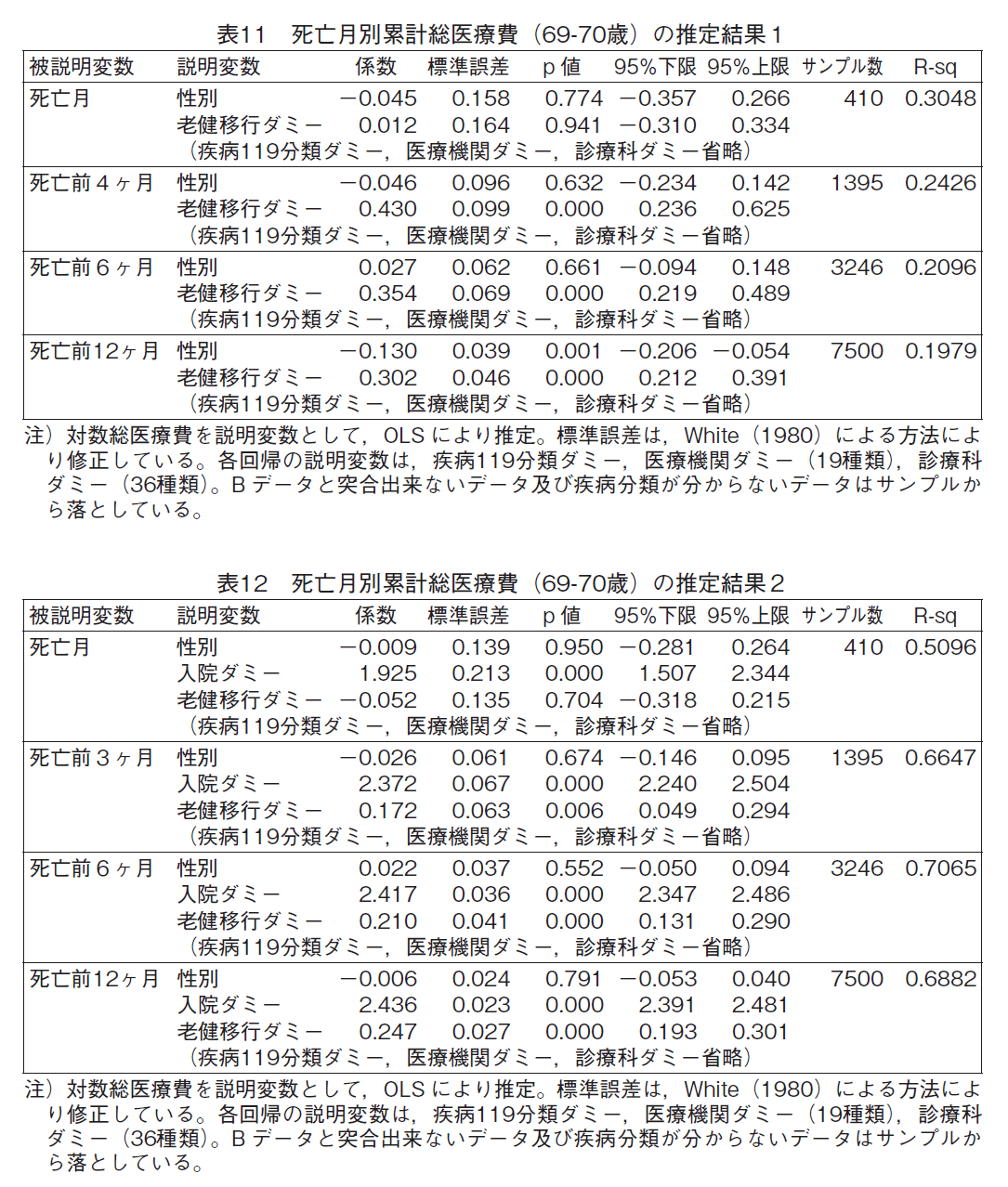
�y43 �Łz
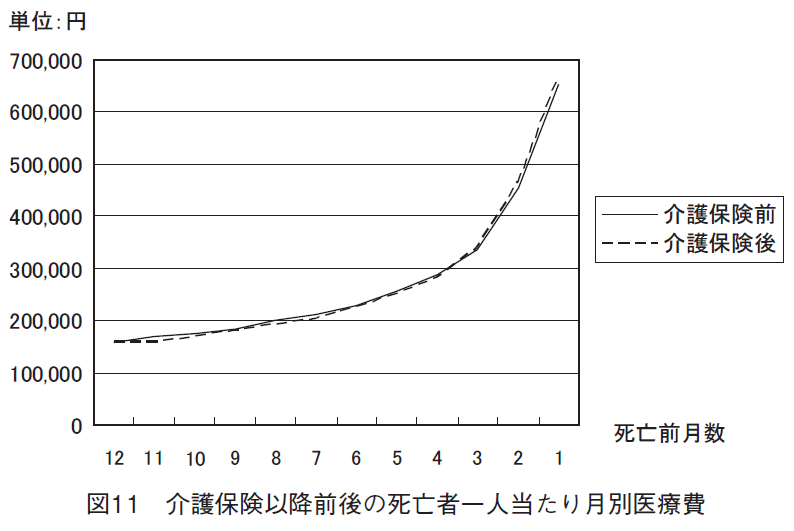
�y44 �Łz
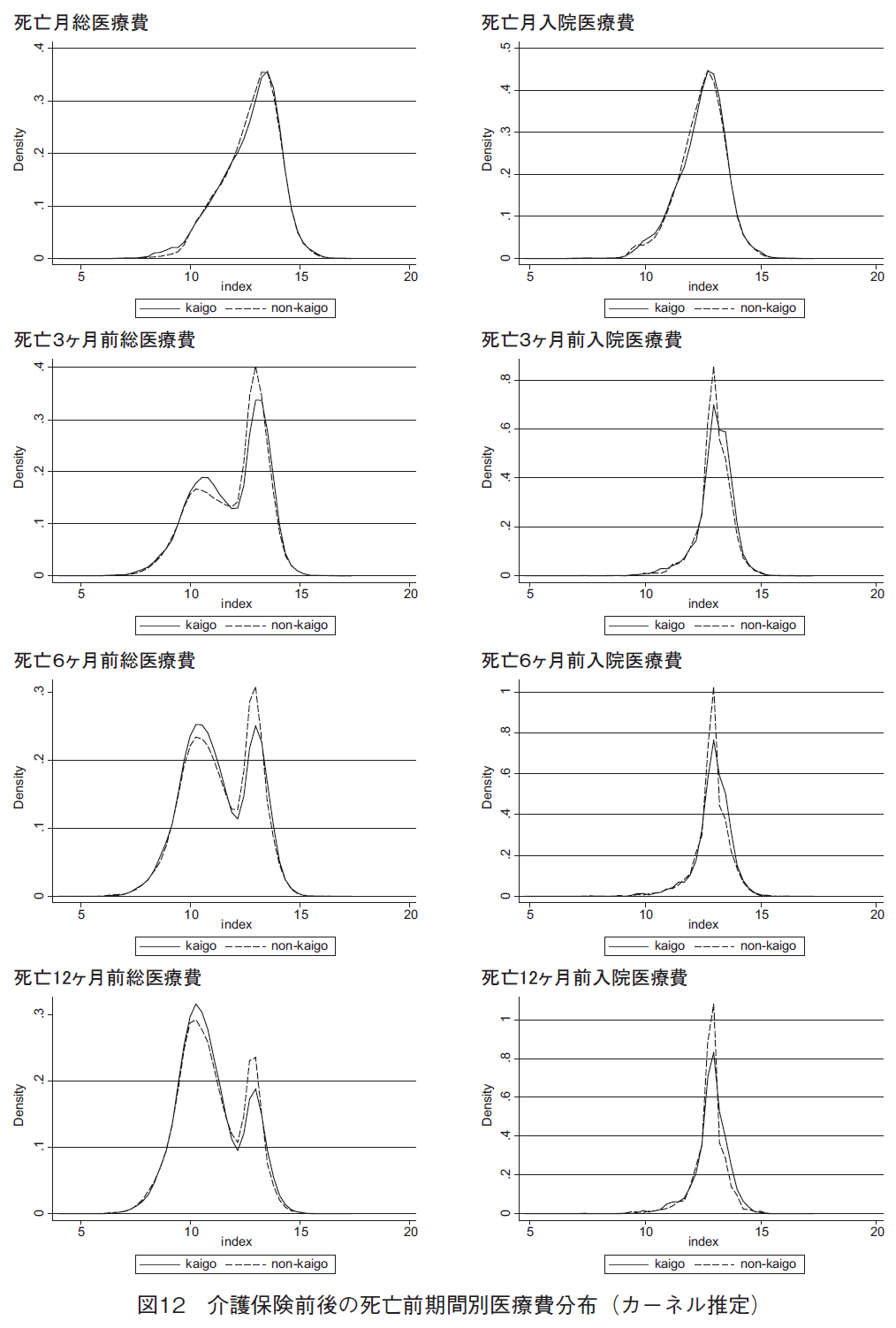
�y45 �Łz
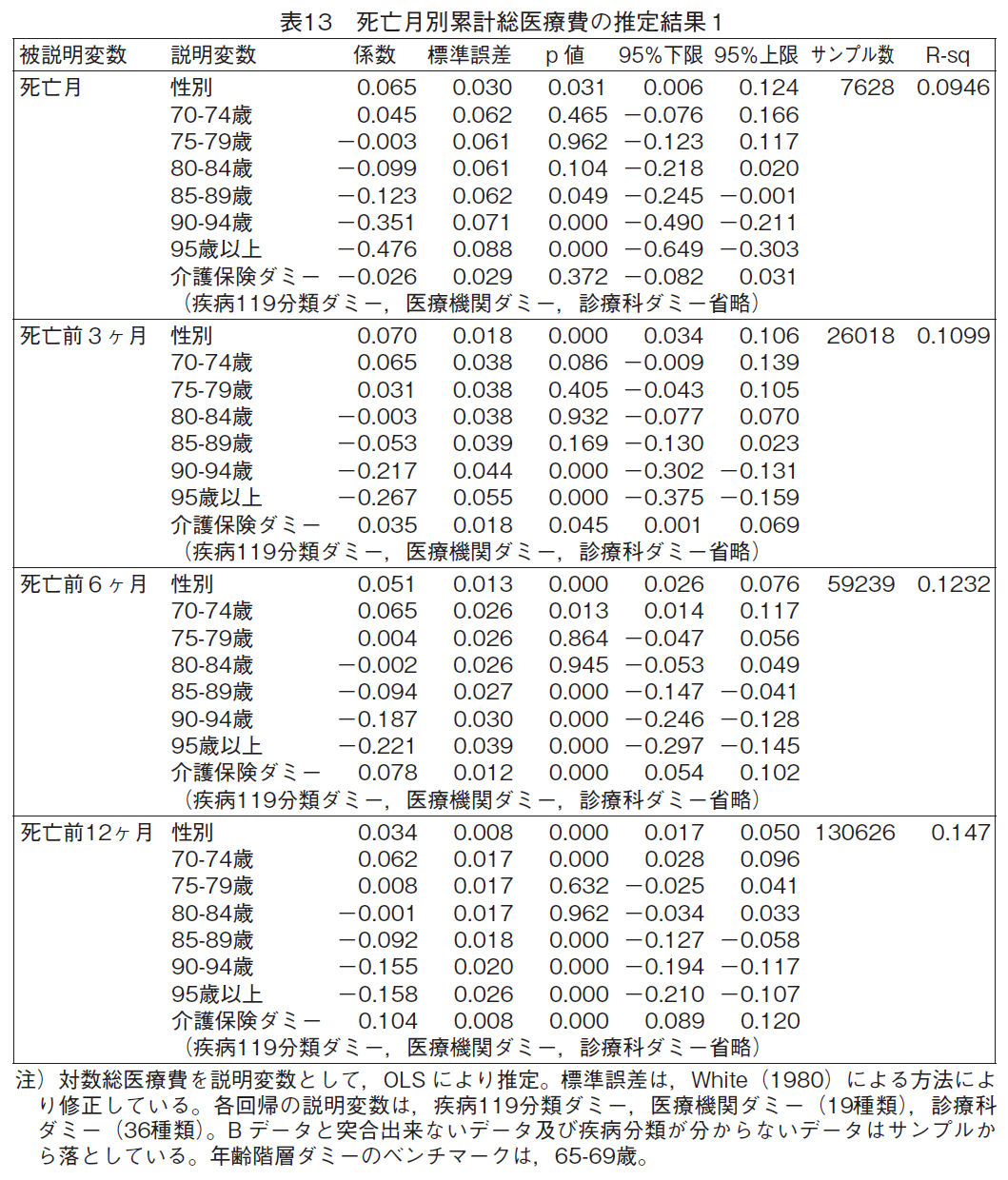
�y46 �Łz
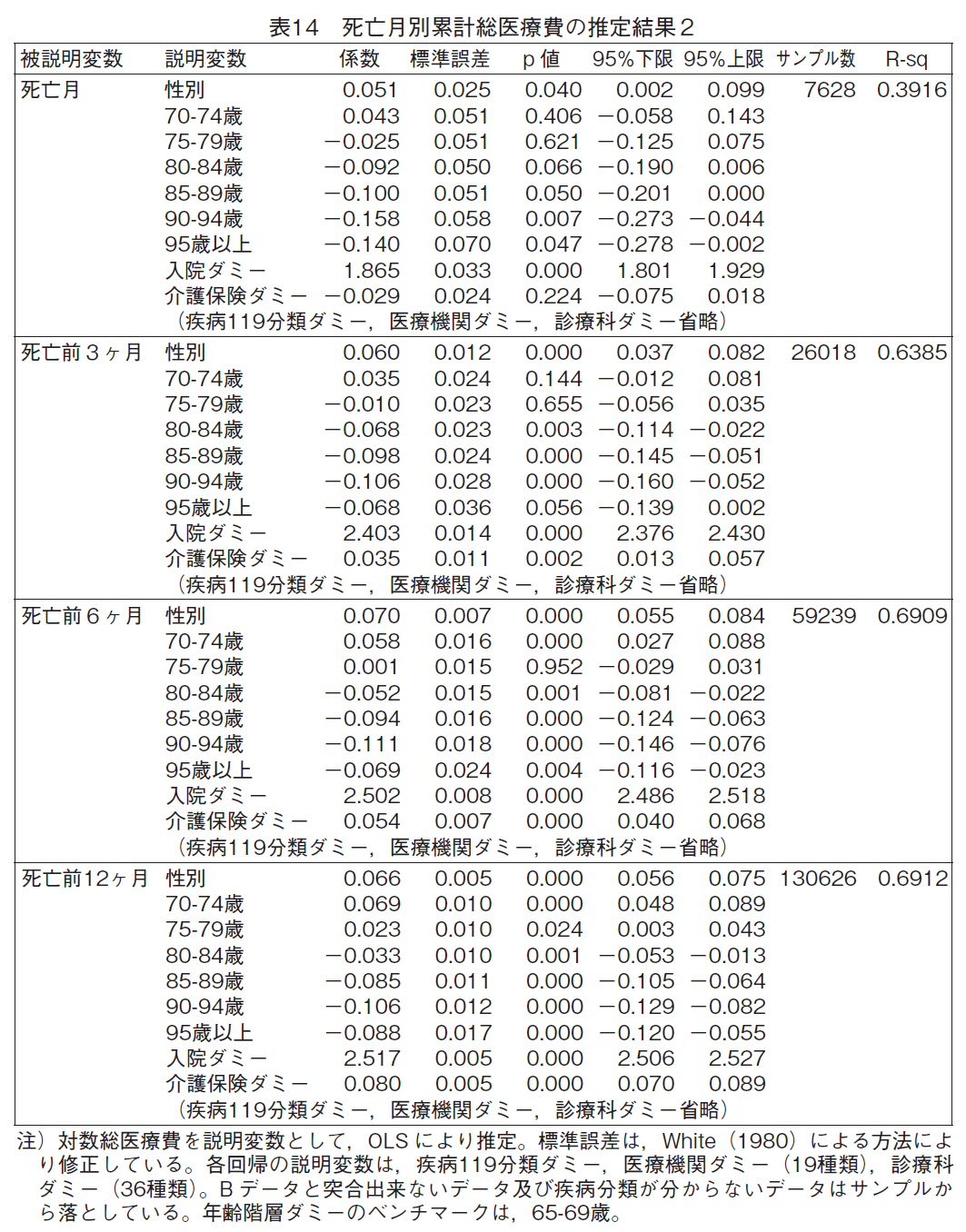
�y47 �Łz