�y87�Łz
�Ǘ��E�̒j���Ԓ����i���͑��݂���̂�
����߂��݁E����͎q�E�e�▾
�T�@�͂��߂�
2014�N�R���P���̓��{�o�ϐV�������̃g�b�v�L���́C�����1150�Ђ̊Ǘ��E�ɐ�߂鏗���̊������C�ی��E��^�Ȃǔ��Ƃł�10�������̂́C33�Ǝ�S�̂̕��ς�4.9���C�Ƃ������̂ł������B�����āC���{�͎w���I�n�ʂ̏����̊�����2020�N�܂ł�30���ɑ��₷�ڕW���f���Ă��邪�C�܂��܂��ۑ肪�������Ƃ���������Ă���B
�@�����J���� �w����28�N�����\����{���v�����x �ɂ��ƁC�]�ƈ�100�l�ȏ��Ɓi�Z���ԘJ���҂�������p�J���ҁj�ł��C�����Ǘ��E�䗦�i2016�N�j�͉ے�10.33���C����6.55���ŁC�����E�ے����v�ł�9.26���ŁC�����Ǘ��E�䗦��30�`40����1�j�̉��ď����Ɣ�דo�p�͐i��ł��Ȃ��B�m���ɏ����̊Ǘ��E�䗦���グ�邱�Ƃ͏d�v�Ȑ���ۑ�ł���B�������C�����Ǘ��E�Œj���ɏ����̍�������Ƃ�����C�P�ɏ����̊Ǘ��E�䗦���グ������킯�ł͂Ȃ����ƂɂȂ�B
�@���{�ł́C�j���Ԓ����i�������݂��邱�Ƃ��m���Ă���C���ؕ��͂ɂ��C�ώ@�����v�����R���g���[������C���̊i���͏k������Ƃ���Ă���B�����āC���̊i�������I�Ȃ��̂������I���ʂɂ����̂��̌����s���Ă���i����i2008�j�CAbe�i2005�j�j�B�������C���������j���Ԓ����i���̗v�����͂́C���E�҂̃f�[�^�𗘗p�������̂����S�ł���B�Ǘ��E�̓�����E���ł̒j�������i���ɂ��ẮC���{�ł͏����Ǘ��E�f�[�^���s�\���ł��邱�Ƃ���C���ؕ��͂����܂�s���Ă��Ȃ��̂�����ł���B
�@���̐����Ȃ��v�����͂� �w�j�������Q�攒���@����22�N�Łx �Ɍf�ڂ��ꂽ���̂ł���B����ɂ��ƁC�����̊e�v���̘J���ҍ\�����j���Ɠ����Ɖ��肵���ꍇ�̒��������́C�����E�K�ŁC�j����100�ɑ��āC������81.1�ƂȂ�C������E�ł����Ă��C�����i�������݂��邱�Ƃ�������Ă���2�j�B
�@���ɓ����Ǘ��E�ł����Ă��C�j���ԂŒ����i�������݂���C�����ɏ��������i�����邩�Ƃ������Ƃ����łȂ��C������E���ł̒j���Ԓ����i���̏k�����厖�Ȑ���ۑ�ƂȂ�B������E���ŁC���l�̋Α��N���C�E��o�������j���ł͒����i�������݂���̂��B���ꂪ�{�����̖���N�ł���B
�@�����ŁC�{�����ł́C�Ǘ��E���܂ޏ]�ƈ��̖L�x�Ȍ[�f�[�^�𗘗p���āC�������͂��邱�ƂŁC������E���ł̒j���Ԓ����i���ɂ��ďڍׂɒ��ׂ邱�Ƃɂ������B���ɁC����
�y88
�Łz
�̏ꍇ�́C�Ǘ��E�ɏ��i���邩�ۂ��Ɋ�Ƃ̔��f�����łȂ��C���Ȃ̑I�����e����^���Ă���ƍl������B���̂悤�ȃo�C�A�X�̉e�����l���������͂��s���B
�U�@�j���Ԓ����i���̐��v���s���������Ɩ{�����̖���N
�P�D�ˑR�Ƃ��Ďc��j���Ԓ����i��
�u�킪���ɂ�����j���̒����i���ɂ��Ă̌����͖c��i�R���i2008�j�j�v�ł���C�Â��͔���i1980�j���C�j���Ԓ����i���͊�Ɠ��ɂ�����Ɩ���̌P�������@��̍��Ɋ�Â����Y���̊i���ɂ��ʂ��傫�����Ƃ������Ă���B���Ȃ킿�C�j���Ԓ����i���̏k���ɂ́C�����̌P���@��𑝂₷���Ƃ��K�v�ɂȂ�B����́C���̂��Ə����̏��i�@��𑝂₷���Ƃɂ��Ȃ���B
�@�ߔN�ł́C�j���Ԓ����i���̏k�����݂�����̂́C�ˑR�Ƃ��Ēj���Ԓ����i���͑��݂���B�x�i1998�j�́C1986�N�C1994�N�̒����Z���T�X�̌[��p���āC���̂Q���_�ԂŒ����i�����k�����C���̂قƂ�ǂ̓M���b�v���ʁC���Ȃ킿���v�I�Ɋώ@����Ȃ������̒n�ʌ���Ő��������Ƃ��Ă���BAbe�i2009�j�́C�����Z���T�X�̏W�v�f�[�^�𗘗p���C�j���ٗp�@��ϓ��@�ȍ~�C���w�����������Ј��Ƃ��ē����悤�ɂȂ������ƂŁC�j���Ԓ����i�����k�������Ƃ�����̂́C���������̒j���Ɣ�ׂ�Ƃ܂������̒����͒Ⴂ���Ƃ������Ă���B
�@Miyoshi�i2007�j�́C�l�̒����ɓn��l�I���{�~�ς̏������f�[�^�𗘗p���āC���ɏ����̋Α��N���𐳊m�ɔc��������ł́C�����ƒj���Ƃ̒����i���ɂ��ĕ��͂��s�����B���̌��ʁC�����͒j���ɔ�ׂĐ��Ј��̎d���o����Α��N���������ɗ^����e�������������Ƃ�C���Ј��̌o���̕]���ɑ��Ēj���ŗL�ӂȍ��������邱�Ƃ������Ă���B
�@���̂悤�ɈˑR�Ƃ��āC�j���Ԃł̒����i�������݂��Ă��邱�ƁC�����d����̌o���������Ă��C�����͒j�������Ⴍ�]������Ă���B����CKato, Kawaguchi and Owan�i2013�j�́C��萻���Ƃ̌[�f�[�^��p���āC�ʏ�̒������͂���ƁC�����҂ł�16���C�����҂ł�31���̒j���Ԓ����i�������݂�����̂́C������job level�Cskill grade�C�J�����ԂȂǂŐ����ł��邱�Ƃ������Ă���BMiyoshi�̌������ʂƏƂ炵���킹��ƁC�����d���o�����o�Ă��C�j���Ŏd���̃��x���ɈႢ�����邱�Ƃ�C�J�����Ԃ̈Ⴂ���C�j���Ԃ̒����i���̌����ł���Ƃ����������B
�Q�D���v�I���ʂ������s�\�ȍ��ʂ�
�����ŁC���{�̒j���Ԓ����i���̌������o�ϊw�I�������ɂ����̂��C���I�ȍ��ʂȂ̂��Ƃ����_�ɒ��ڂ����������Љ��B�����i2005�j�́C���w�������̊�ƒ蒅�����Ⴂ���ƁC��ƒ蒅���̍��͌�����o�Y�ɂ�鏗���̗��E�p�^�[���ƁC�Y�Ƃɂ���ĈقȂ�j���̒蒅���ɂ���Đ����邱�Ƃ��������B�������C���Ə����c������j���̕��ϓI�Ȑ��Y���i�����R���g���[�����Ă����C�����i���������Ă��邱�Ƃ���C�o�ύ������ł͐����ł��Ȃ��i�������݂���Ƃ��Ă���B
�@�o�ύ������Ő����ł��Ȃ��i���� �u�n�D�ɂ�鍷�ʁv �ƌ�����BBecker�i1971�j�ɂ��ƁC�n�D�ɂ�鍷�ʂ����݂���ƁC���ʂ����J���҂̎��v�����邱�Ƃ��瓯�����Y���ł����Ă����̘J���҂̒����͉�����C�u�n�D�ɂ�鍷�ʁv �������Ȃ��o�c�҂������̘J���҂��ٗp���邱�ƂŔ�p�������ė��v���グ�邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ���C�₪�āC���ʚn�D�̂���o�c�҂͓��������Ƃ��Ă���B
�y89 �Łz
����i2005�j�CKawaguchi�i2007�j�́C���ꂼ���ƃp�l���f�[�^�𗘗p���C�u�s��e�X�g�v �̎�@�Ō����邱�ƂŁC�����䗦����Ɨ����ɗ^����e������C���{�ł͎g�p�҂̚n�D�Ɋ�Â����ʂɂ�鏗���̉ߏ��ٗp�����݂��邱�Ƃ��������B
�@����i2008�j���C�ٗp�ɂ����鏗�����ʂݏo���o�ϓI�ȃ��J�j�Y�����𖾂����A�̌����̒��ŁC�u���I���ʁv �� �u���v�I���ʁv �̌����s���i��S�́j�C2006�N�� �u�d���Ɖƒ�̗����x���ɂ�����钲���v �̊�ƒ����ƎЈ������Ƃ�g�ݍ��킹�邱�Ƃŕ��͂����݂��B�j���ϓ���������Ƃ̋Ɛюw�W�ɗ^����e���͈���I�ł͂Ȃ����߁C���I���ʂ̑��݂ɂ��Ă͖��m�ɂ���Ȃ��������C�j���̗��E�m���i�����傫����ƂقǁC�Ј��̐��ʂ���ɂ��ď��������肵�Ă��邱�Ƃ���C���v�I���ʂ̑��݂������Ă���B�܂��C��Ƃ̋ϓ������CWLB�ւ̎��g�݂��i��ł����Ƃł́C�����̏A�ƈӗ~�����߁C�j���̒��������������Ȃ邱�Ƃ��������i���W�́j�B���̌��ʂ́C���v�I���ʂ₻�̑����ʂ��痈�邱��܂ł̓��{��Ƃ̏����J���҂ւ̏����̈����������̐��Y�����߂āC���ʂ��J��Ԃ����Ƃ������̘A����f����\���������Ă���B
�R�D�����E���̒j���Ԓ����i���Ɋւ��錤��
�{�����ł́C�����E���Œj���Ԓ����i���͑��݂���̂��ɒ��ڂ���B�u����15�N�œ��������̎���v�i�����J���ȁi2003�j�j�ł̓R�[�z�[�g�ʂɌW���C�ے��̒j���Ԓ����i�����r���Ă���C�ϓ��@�ȑO�́C�����ے��ł����Ă������͒j�����������Q�����x�Ⴂ���ƁC�ϓ��@����ł͒j���Ԋi�����k�����Ă�����̂́C�ϓ��@��10�N����ł͒���Ă��邱�Ƃ��������B�����C�����ł̊i���͏W�v�l�ł���C��ƋK�͂Ȃǂ̑������R���g���[������Ă��Ȃ��B
�@�R���i2008�j�́C�C�O�̎��،����ł́C���ؕ��͂ɂ�蓯�l�̊Ǘ��E�ł���Βj���Ԓ����i���͖����Ƃ������ʂ������Ă���Ǝw�E����BPetersen and Morgan�i1995�j�́C�A�����J��1974�N����1983�N�܂ł̖L�x�Ȍ[�f�[�^�𗘗p���C�������Ə������E��ɂ���������i���͂����B���̌��ʁC���ꎖ�Ə��̓���E����ł͒j���Ԓ����i���͔��ɏ������C���ςŏ����͒j���̒�����98.3���Ă���BBerrtrand and Hallock�i2001�j���C�A�����J��high-level executive�ŏ����͒j������45�������͒Ⴂ���C����͂قƂ�ǂ��C�K�͊Ԋi���⏗����CEO�����Ȃ����Ƃ�����������Ƃ��Ă���B
�@�Ƃ���ŁC���{�ɂ́C�R�[�X�ʌٗp�Ǘ����x��݂����Ƃ�����B�R�[�X�ʌٗp�Ǘ����x�������Ƃł́C�̗p���ɁC�����E�C��ʐE�Ƃ������R�[�X�����߂Ă����C�����R�[�X�̒��ł́C���i���̏����ɍ���݂��Ȃ��B�R�[�X�ʌٗp�Ǘ����x��݂��Ă��Ȃ���Ƃł́C�j���ٗp�@��ϓ��@�ɏ]���C���ׂĂ̘J���҂ŏ��i���̏����ɂ͍���݂��Ȃ����ƂɂȂ�B���̂��߁C�R�[�X�ʌٗp�Ǘ����x�������Ƃł́C�����E�ƈ�ʐE�Ƃ����݂��C�����̑����͈�ʐE�̗p�ł��邱�Ƃ���C�j���Ԓ����i�����傫���Ȃ�B
�@�����i2005�j�́C�R�[�X�ʌٗp�Ǘ����x�����邱�ƂŊ�Ƃ͒����I�ɓ����ӎv�������������ʂł��C�V�O�i�����O���������ł���Ƃ����\���̂��ƁC�R�[�X�ʌٗp���x�̗L���Œj���Ԓ����i�����قȂ邩�͂����B���̌��ʁC�R�[�X�ʌٗp�Ǘ����x�������Ƃł́C�j���Ԓ����i�����傫���C����͒j���� �u�����E�v ��I�Ԃ̂ɑ��C�����̑����� �u��ʐE�v ��I�Ԃ��߂��Ƃ��Ă���B�J�������E���C�@�\�i2010�j�����l�̕��͂�2006�N��2000�N�̃f�[�^�ōs���Ă��邪�C�R�[�X������Ƃł��C�W���̐�Βl�͏��������̂́C�����_�~�[�ϐ��̌W���͕��ŗL�ӂł��邱�Ƃ�������Ă���B����ȊO�͈����Ɠ��l�̌��ʂĂ���B���̂悤
�y90
�Łz
�ɁC�R�[�X�ʌٗp�Ǘ����x�̓V�O�i�����O������������Ƃ������_������C���������E�ł���Βj���Ƃ̒����i�����k�����邱�Ƃ����҂����B
�@����C�R���i2008�j�́C�R�[�X�ʌٗp�Ǘ����x����ʐE�̂��C�������C����Ɉ�ʐE�����̐��Y���������邱�ƂŒj���Ԓ����i�����g�傷��Ƃ������z�ɂ��Ďw�E���Ă���B�܂��C��̈����i2005�j�̕��͂ł́C�R�[�X�ʌٗp�Ǘ����x�̂����ƂŋΖ����鏗���� �u�����E�v �� �u��ʐE�v ���̏���p���Ă��Ȃ����߁C�j���Ԓ����i���������E�E��ʐE�Ƃ����R�[�X�̍��ɂ����̂Ȃ̂��ۂ����킩��Ȃ��B�����̂��Ƃ���C�R�[�X�ʌٗp�Ǘ����x�̗L���⓯���x���ł̑����E����ʐE�̈Ⴂ���l���������������߂���B
�@�{�����ŗ��p�����f�[�^�ł́C�e���̋Ζ���ɃR�[�X�ʌٗp�Ǘ����x�����邩�C�R�[�X�ʌٗp�Ǘ����x������ꍇ�ɂ́C�{�l�������E����ʐE���ɂ��Ẳ�������B���̂��߁C�����ł������E�ł���Β����i�����k�����邩�ǂ������m�F���邱�Ƃ��\�ł���B�{�������������O��Ƃ���Ă���R�[�X�ʌٗp�Ǘ����x�̂����Ƃ̑����E�̒��Œj���Ԓ����i�������݂��Ă���̂��ǂ����C�����E�ʂ̊Ǘ��E�̒j���ԂŒ����i�������݂��Ă���̂��𖾂炩�ɂ������B���͂ł́C�����Ǘ��E�̃T���v�����L�x�ŁC���Α��N����z�u�]���̌o���Ƃ������C��Ɠ��ł̋���P���̋@��ɂ��Ă̏���������f�[�^�𗘗p���C�����̗v�����R���g���[�����Ă��Ȃ��C�j���ԂŊi�����c�����̂��ׂ�B
�V�@���p�f�[�^
���p�����̂́C�Ɨ��s���@�l�J�������E���C�@�\�i2014�j���s���� �w�j�����Ј��̃L�����A�Ɨ����x���Ɋւ��钲���x �̊Ǘ��E�����ƈ�ʏ]�ƈ������̌[�f�[�^�Ɗ�ƒ����[�̊�ƃf�[�^�Ƃ�˂����킹���f�[�^�ł���B�ȉ��C���������C�������@�ɂ��Ă܂Ƃ߂�B
�@ �w�j�����Ј��̃L�����A�Ɨ����x���Ɋւ��钲���x �́C�S���̏]�ƈ�300�l�ȏ�̊��6,000�ЂƏ]�ƈ�100�`299�l�̊��6,000�Ђ̌v12,000�Ђ�ΏۂƂ��C����25�N10���P�����݂̏ōs���������ŁC��ƒ����Ə]�ƈ������̗������s���Ă���B
�@�]�ƈ������́C�Ώۊ�Ƃœ����ے��E�����E�ȏ�̊Ǘ��E48,000�l�y�ш�ʏ]�ƈ�96,000�l��ΏۂƂ��Ă���B���̂����C�Ǘ��E�́C�����Ώۊ�Ƃ�ʂ��āC�]�ƈ���100�`299�l�̊�Ƃ͂R���i�ł���Ώ����R����D��j�C�]�ƈ���100�`299�l�̊�Ƃ͂R���i�ł���Ώ����Q����D��j�ɔz�z����悤�Ɏw��������Ă���B��ʏ]�ƈ��́C������Ƃ�ʂ��āC�]�ƈ���300�l�ȏ�̊�Ƃ͒j���T���C�����T���C�]�ƈ���100�`299�l�̊�Ƃ͒j���R���C�����R���ɔz�z����悤�Ɏw��������Ă���B�Ȃ��C�z�z���̒j���U�蕪���́C�w�肵���j���z���Ŕz�z�ł��Ȃ��ꍇ�C�j���̔z���͒������͊�Ƃ̎���ɍ��킹�Ĕz�z����悤�ɋ��͂��˗����Ă���B���̒����̓����́C�����̔z�z���@�̊W�ŏ����Ǘ��E�̃T���v��������������_�C�]�ƈ��̋Ζ��o�����E�C���i��]�Ȃǂ̑����̏������_�C��ƒ����Ƃ̓˂����킹�ɂ��C�Ζ���̑������m�邱�Ƃ��ł���_����������B�����ŗ��p�\�ȏ]�ƈ��f�[�^�́C��ʎЈ���10,109�T���v���C�Ǘ��E��5,567�T���v���̍��v15,676�T���v���ł���B�{�����ł͕��͑Ώۂ�呲���Ј��̂����Ƃ̃T���v���Ɍ������B���̌��ʃT���v���T�C�Y�́C��ʏ]�ƈ���7,660�T���v���C�Ǘ��E��4,234�T���v���C���v11,894�T���v���ƂȂ�B��������C����Ɏ��߂ŏq�ׂ镪�͂ɕK�v�ȕϐ�����T���v���Ɍ���ƁC���v8,333�T���v���ƂȂ�B
�@�{�����ł́C�]�ƈ������Ɗ�ƒ�����˂����킹�����̂𗘗p�����B��ƒ����ł́C��Ƃ�
�y91
�Łz
�Ǝ�C��p�J���Ґ��̑��C�����Ǘ��E�̗L���Ƃ����������ł���B
�W�@�ϐ��̐ݒ�
�����ł́C�������̐��v�̂��߂ɗp�����ϐ��̍쐬�ɂ��Ď����B
�@�������̔�����ϐ��ɂ́C�O�N�i2011�N�j�̌l�N���i�ŁE�ܗ^���܂ށj�̑ΐ���p�����B�{���C�������̔�����ϐ��ɂ́C�����ΐ���p����ׂ��ł��邪�C���p�����f�[�^�ł́C���̗��R����C������ϐ��͔N���ΐ��Ƃ��C�����ϐ��ɏT�J�����Ԃ̑ΐ����������B�����ł́C��N�x�̔N���ƌ��݂̏T������J�����Ԃɂ��Ă̏��͓����邪�C���̏���p���Ď������v�Z����ƁC�P�j�N�Ԃ̘J�����Ԃ����߂�ɂ́C�N�ԘJ�������̏�K�v�ł��邪�C�f�[�^����͂��̏�����Ȃ��̂ŁC�J���҂̕��ϓI�ȔN�ԘJ������3�j���ꗥ�ɗp����Ȃǂ��鑼�Ȃ����ƁC�Q�j�N���̏��͍�N�̂��́C�J�����Ԃ̏��͌��݂̂��̂�p���Ă��āC���_�ɂ��ꂪ���邱�Ƃ���C���߂������ɂ͌덷���������Ă��܂��Ƃ�����肪����B�Q�j�ɂ��ẮC�m���ɍ�N�̔N���������l�͍��N�̔N���������Ɨ\�z����邪�C�K��������v����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B
�@�O�̂��߁C������ϐ��ɁC��N�x�̔N�����C���݂̏T������J�����Ԃ��畽�ϓI�ȘJ���������l�����ĎZ�o�����N�J�����ԂŊ������������Ƃ������͂��s�������C�����_�~�[�ϐ��̌W���Ɛ�Βl�ɑ傫�ȈႢ�������Ȃ�����4�j�B�N�ԘJ�����Ԃ𑪒肷�邱�Ƃ̓���ɂ��ẮC���r�i2009�j�Ɏ������B
�@�l�N���̓A���P�[�g�����ł͊K���l�Őq�˂Ă���B���̂��߁C�K���̒����l���l�N���Ƃ���5�j�B���C�O�N�̔N���Ȃ̂ŁC�O�N�C�x�E�△�E���������Ԃ�����҂ł���C�N�������ɒႢ�Ǘ��E�̃T���v�������݂���B�����ŁC�N���ɂ��ẮC300���~��ȏ�C1,300���~����1,400���~��܂ł̃T���v���݂̂𗘗p���邱�ƂƂ����B�r�������C�N��300���~�䖢���̃T���v���́C�S�̂�16.08���ł���C�N��1,500���~�ȏ�̃T���v���́C�S�̂�0.71���ł���B���C2011�N�̒����\����{�����ɂ��ƁC�N��C�Y�ƌv�̊�ƋK��100�l�ȏ�ɂ�����j���̔��E�҂̔N��6�j���ϒl�͂��ꂼ��C525���~�C399���~�ł���C�j���̕����N���X�̔N�����ϒl�͂��ꂼ��C1,024���~�C867���~�ł���B���݂̉�Ђɓ��Ђ��������́C��������2012�N�̂Q�N�O�C2010�N�ȑO�̃T���v���Ɍ��邱�ƂŁC�O�N���璲���N�ɂ����ē]�E�o���̂���T���v����r�������B
�@�����ϐ��ɂ́C�l�̑����Ƃ��āC�T�J�����ԑΐ��C�N��E�Α��N���Ƃ����̂Q�捀�C�����_�~�[�ϐ��C�w���_�~�[�ϐ��C���������_�~�[�ϐ��C��E�_�~�[�ϐ��C�z�u�]���_�~�[�ϐ��C�R�[�X�ʌٗp�Ǘ����x�L���Ƃ̑����E�̏ꍇ�͂P�C����ȊO�͂O���Ƃ�ϐ���p�����B
�y92 �Łz
�T�J�����Ԃ̐��l�́C�ŏ��l�͂P�C�ő�l��70�ł��邪�C���Ј��ł���ΒZ���ԋΖ����x�𗘗p���Ȃ�����C�T40���Ԉȏ�̘J������ʓI�ł��邱�Ƃ��l�����C40���Ԗ����̃T���v���͔r�������B�J�����Ԃ��T40���Ԗ����̃T���v���͑S�̂�8.76���i15,621��1,368�T���v���j�ł������B�܂��C�J�����Ԃ̏���P���̒l��70���Ԃł��邱�Ƃ���C70���Ԃ���T���v�����r�������B
�@�Ζ���̑����Ƃ��ẮC�Y�ƃ_�~�[�ϐ��C��p�J���Ґ��̑ΐ��C�Ζ��悪�����Ǘ��E�̂����Ƃ̏ꍇ�͂P�C����ȊO�͂O���Ƃ�ϐ����������B�e�����ϐ��ɂ��Ă��ڂ�����������B�w���́C��w�E��w�@���C�Z��E���ꑲ�C���w�Z���C���Z���C���w�Z���C���̑��̂U�敪�ł���C��w�E��w�@�����x�[�X�Ƃ����B���������́C�l���E�����E�o���C���E�����E�L��C�����E�J���E�v�C����C�c�ƁC�̔��E�T�[�r�X�C���Y�i���݁C�^�A�C���ʕ���܂ށj�C���̑��̂W�敪�ł���C�l���E�����E�o�����x�[�X�Ƃ����B��E�́C��ʎЈ��C�W���E��C�S���E�C�ے��E�ے������E�C�����E���������E�C���̑��̊Ǘ��E�̂T�敪�ŁC��ʎЈ����x�[�X�Ƃ����B�����ϐ��ɂ́C��E�ƔN��E�Α��N���Ƃ̌������C����ɂ͂����Ə����_�~�[�ϐ��Ƃ̌��������p�����B�z�u�]���_�~�[�ϐ��́C���ݓ����Ă����Ђł̎��̔z�u�]���̌o��������ꍇ�ɂP�C�����ꍇ�ɂO���Ƃ�ϐ��ł���B�z�u�]���́C�@�������Ə����ł̔z�u�]���C�A�]����Ȃ����Ə��Ԃ̔z�u�]���C�B�]���������]�C�C�����̊֘A��Ђւ̏o���C�D�C�O�Ζ��̂T��ނł���B����́C�����I���Ȃ̂ŁC�����̔z�u�]�����o�����Ă���ꍇ������B�������C�z�u�]���̌o���̗L��������₤�Ă���C������ނ̔z�u�]������o�����Ă����� ��o���L�� �ƂȂ�C�z�u�]���̉܂ł͂킩��Ȃ��B�z�u�]���̌o���������ꍇ�́C���ׂĂ̔z�u�]���_�~�[�ϐ����O�ƂȂ�B
�@�����E�_�~�[�ϐ��Ə����_�~�[�ϐ��Ƃ̌��������������͎̂��̗��R�ɂ��B�R�[�X�ʌٗp�Ǘ����x�������Ƃł́C�����E��I�Ԃ��ۂ��������I�ɓ����ӎv�����邩�ǂ����̃V�O�i���ƂȂ邱�ƂŁC�����͑�������ʐE��I�Ԃ��Ƃ���j���Ԓ����i�����g�傷��C�Ƃ��������i2005�j�̌�������C�����ő����E��I�ԏꍇ�͒j���Ƃ̒����i�����k������͂�������ł���B
�@�Ζ���̑����ł���Y�Ƃ́C�@�z�ƁC�̐ƁC�����̎�ƁC�A���ƁC�B�����ƁC�C�d�C�E�K�X�E�M�����E�����ƁC�D���ʐM�ƁC�E�^�A�ƁC�X�ƁC�F�����ƁC�G�����ƁC�H���Z�ƁC�ی��ƁC�I�s���Y�ƁC���i���ƁC�J�h���ƁC�K���H�T�[�r�X�ƁC�L����C�w�K�x���ƁC�M��ÁC�����C�N���̑��T�[�r�X�ƁC�O���̑��C��16�敪�ł���C�����Ƃ��x�[�X�Ƃ����B��p�]�ƈ����́C��ƋK�͂̕ϐ��Ƃ��ėp�����B����ɁC��Y�߂̕��͂ł́C�T���v���Z���N�V�����E�o�C�A�X�̖��ɑΉ����邽�߂ɁCTreatment Regression�ɂ�镪�͂��s���Ă���B���̎��C�Ǘ��E�_�~�[�ϐ��Ƃ͑��ւ������C�덷���Ƃ͑��ւ������Ȃ�����ϐ��𗘗p����B����́C����ϐ��Ƃ��āC���ɏ����ł͎d���Ɖƒ�̗��������i�ɑ傫�ȉe����^����ƍl���C�q�ǂ��̐��i���Ȃ��ꍇ�͂O�j�C�����Ƒ�������ꍇ�ɂP�C����ȊO�ɂO���Ƃ�ϐ��C���i��]�܂Ȃ��ꍇ�C���̗��R�� �u�d���Ɖƒ�̗���������ɂȂ�v �Ɖ���ꍇ�ɂP�C����ȊO�ɂO���Ƃ�ϐ���p�����B
�@�Ζ���ɏ����Ǘ��E�̂���_�~�[�ϐ��ƁC���̕ϐ��Ə����_�~�[�ϐ��Ƃ̌��������������̂́C���̗��R�ɂ��B�Ζ���ɏ����Ǘ��E�������Ƃł́C���v�I���ʁC�n�D�ɂ�鍷�ʂ̂����ꂩ�̍��ʂ��s���Ă���m�����Ⴂ�Ƃ���B�����C�����Ǘ��E�̂����Ƃł͚n�D�ɂ�鍷�ʂ��Ȃ��Ƃ���CBecker�i1971�j�̗��_���炱�̂悤�Ȋ�Ƃ̗��v�͏㏸���邽�߁C�J����
�y93
�Łz
�̒������㏸����B���̂��߁C�����Ǘ��E�L��_�~�[�ϐ��͗L�ӂɃv���X�ɂȂ�Ɨ\�z�����B�܂��C�����Ǘ��E�̂����Ƃł͓��v�I���ʂ��Ȃ��Ƃ���C���Ԃ������Ă�����j���Ԓ����i�����Ȃ��Ȃ�͂��ł���C�����_�~�[�ϐ��Ƃ̌������͗L�ӂɃv���X�ɂȂ�Ɨ\�z�����B���Ȃ킿�C�����̕ϐ��́C���ʖ����̑㗝�ϐ��ƂȂ��Ă���B
�X�@�ϐ��̊�{���v��
���͂ɐ旧���C�ϐ��̊�{���v�ʂ�T���v���̍\����������B�܂��C��ȕϐ��̊�{���v�ʂ�\�P�Ɏ���7�j�B
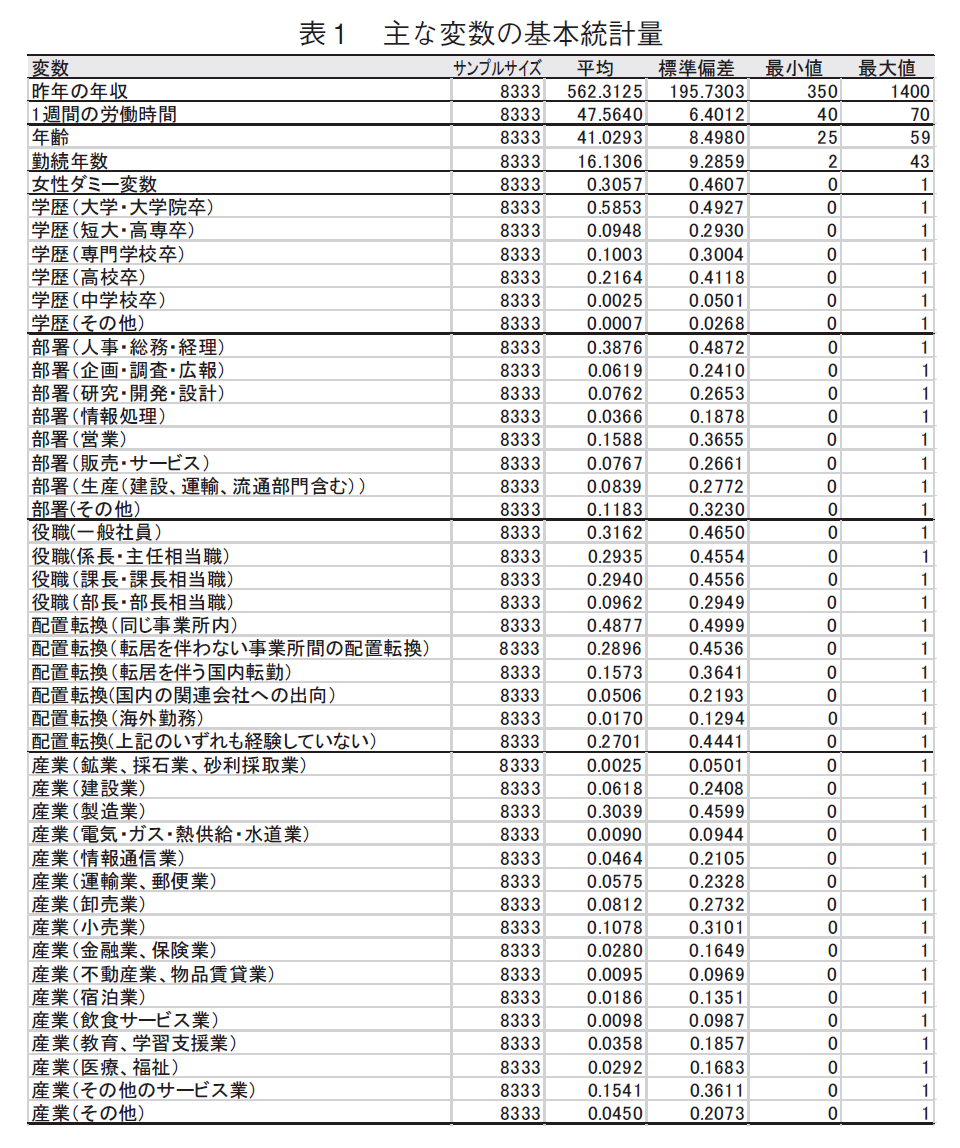
�y94 �Łz
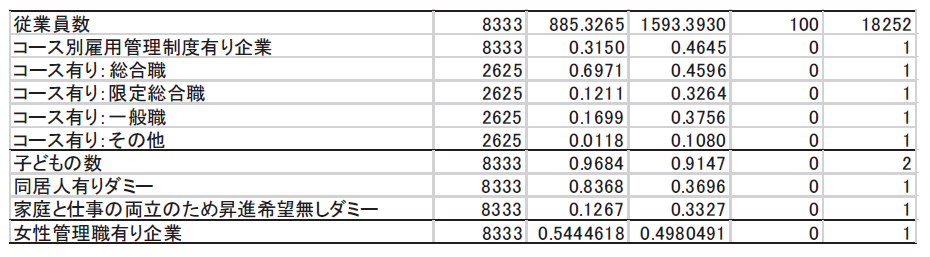
���ɁC�j���ʖ�E�\���������i�\�Q�j�B
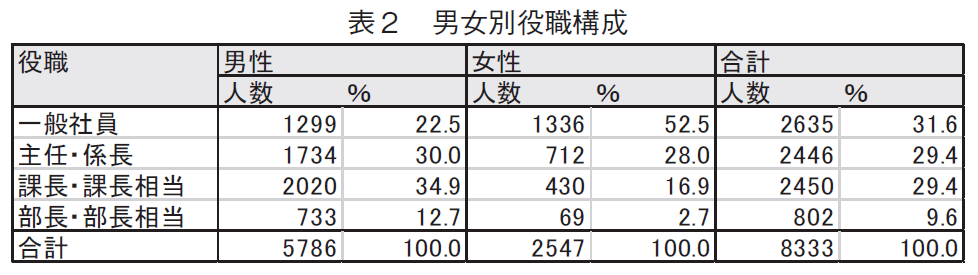
�\�Q���C��E����ɂȂ�ɂ�C�j���T���v���̔䗦�������Ȃ邱�Ƃ��킩��B����ł��C�{�����ŗ��p�����A���P�[�g�����ł́C�����Ǘ��E�̃T���v����D�悵�ďW�߂�悤�ɂƂ̈˗������������Ƃ�����C�����̕����E���������̃T���v����69�C�����Ă���B
�@�\�R�ɂ́C�z�u�]���̌o���҂̔䗦���E�ʁC�j���ʂɎ����B
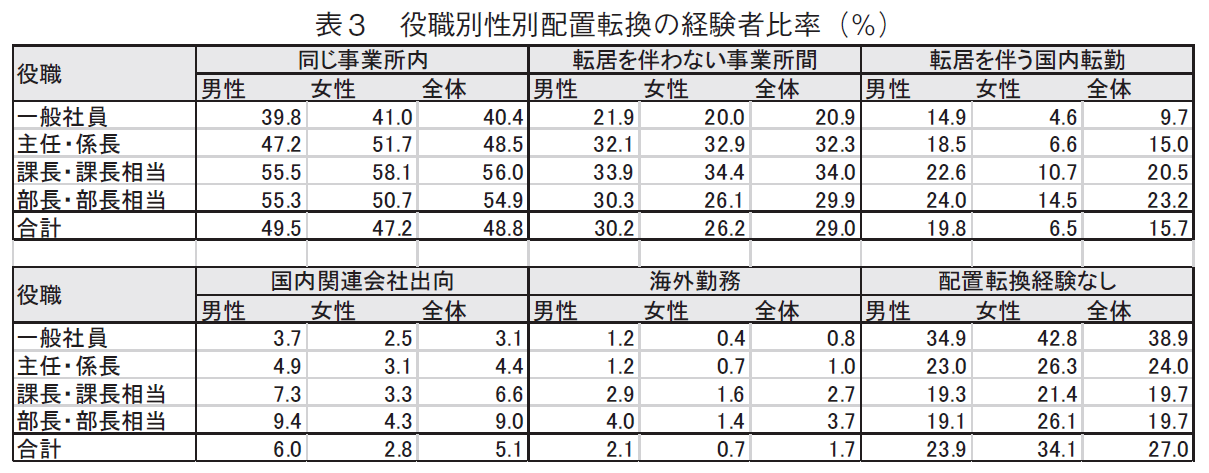
�\�R���C�u�]���������]�v �̌o���҂̔䗦�́C�j��19.8���C����6.5���ƒj���ő傫���قȂ�B���ɁC��ʎЈ��C��C�E�W���Œj�������傫�����C�����ɂȂ�ƍ����k�����Ă���B�u�����֘A��Џo���v �́C�j����6.0���C������2.8���ƁC�����͒j���̔�����ł���B�u�C�O�Ζ��v �͒j���Ƃ��o���҂����Ȃ��B�t�ɁC��z�u�]���o���Ȃ�� �͒j��23.9���C����34.1���ŁC�����̕��������B�u�������Ə����v �u�]��Ȃ����Ə��ԁv �̔z�u�]���o���҂̊����͏��������Ⴂ���̂̑傫�ȍ��͂Ȃ��B
�@�\�S�ɂ́C���ʖ�E�ʂ̎����C�N���C�N��ɂ��ĕ��ϒl�C�W�����C�T���v���T�C�Y��j
�y95
�Łz
���ʂɎ����B
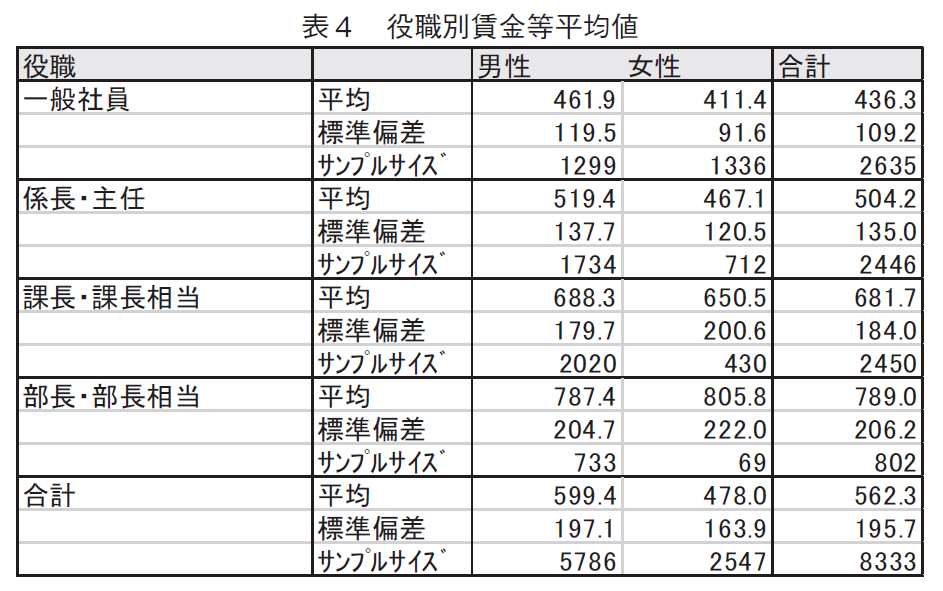
��ʎЈ��ł͒j���ŕ��ϔN����10% ���x�̊i�������邪�i�i461.9-411.4�j�^461.9�~100��10.9�j�C��E���オ��ɂ�Ă��̊i���͏k�����Ă���B�����ł͏����̕������ϔN���������B
�Y�@���͌���
�P�D���͂̎菇
���͂́C�ȉ��̎菇�ōs���B�܂��C���������C�ŏ��Q��@�ƁC��Ƃ̌ʌ��ʂ���菜�����Œ���ʃ��f���iFE���f���j�ƂŁC���v���邱�Ƃɂ��C�j���Ԓ����i������Ƃ̌ʌ��ʂ���菜����������݂��邩�ׂ�B
�@���ɁC���������i���邩�ۂ������肷��ꍇ�ɂ́C���ȑI�������������ƍl�����邱�Ƃ���C�T���v���Z���N�V�����E�o�C�A�X���l���������͂��s���B���Ȃ킿�C�����͎d���Ɖƒ�̗����̂��߂ɁC�����ď��i����]���Ȃ��ꍇ���\�z��������ŁC���i���鏗���́C���Ƃ��Ƃ��C������������ݓI�ɔ\�͂��������ߒ����������X���ɂ���Ƃ���B�����ł���C�������̊Ǘ��E�̌W���ɂ́C�����ɊǗ��E�ɂȂ邱�Ƃɂ���ē���������㏸�������łȂ��C�\�͂��������ƂŒ������㏸���镪���܂܂�āC�Ǘ��E�̒����㏸���ʂ��ߑ�]������邱�ƂɂȂ�B���̖����������邽�߂ɁCTreatment Effect Model��p���ĕ��͂��s���B
�@Treatment Effect Model�̘g�g�݂͎��̒ʂ�ł���iMaddala�i1983�jpp.117-122���Q�Ɓj�B�������́C���̂悤�Ȃ��̂ł���Byj �͒������̔�����ϐ��ł��鎞���ΐ��Cj �� j �Ԗڂ̃T���v�����Ӗ�����B
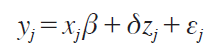
�����ŁCzj �́C�Ǘ��E�̏ꍇ�ɂP�C����ȊO�ɂO�����ϐ��ŁC�ȉ��̎��Ŏ������悤�Ɋώ@����Ȃ��B�ꂽ�ϐ� z*j �Ɋ�Â��Č��܂�B
�y96 �Łz
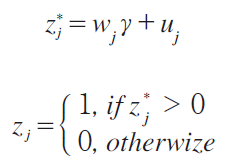
���̎��C�Â� u �́C���ς��O�ŁC���̂悤�ȋ����U�s������Q�ϗʕW�����K���z�ɏ]���B
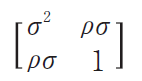
Maddala�i1983�j��two-step����ʂ́C�P�i�K�ڂŊǗ��E�_�~�[�ϐ��������ϐ��Ƃ��鎟�̃v���r�b�g���͂̐���ʂ�B
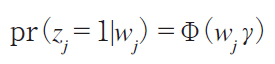
���̌��ʂ𗘗p���C�e�T���v���̃n�U�[�h�Chj �C���Ȃ킿�ߑ�i���邢�͉ߏ��j�ɕ]������Ă��镔���͎��̂悤�Ɍv�Z�����B
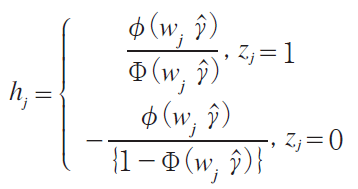
�ӂ͕W�����K���z�̖��x���ł���B
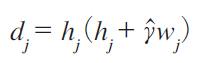
�Ƃ���ƁC
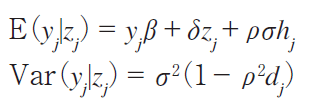
�ƂȂ�Ctwo-step����ʂ����C���C�σ������܂�B
�Q�D�������̐��v����
�������̐��v���ʂ�\�T�Ɏ����B�i�P�j�́C�ŏ��Q��@�ɂ���A���͌���8�j�ŁC�i�Q�j��
�y97
�Łz
�i�R�j�́C��ƌʂ̉e������菜�����Œ���ʃ��f���ɂ�镪�͌��ʂł���B�i�R�j�́C�i�Q�j�̐����ϐ�����C��Ƃł̔z�u�╔���Ɋւ���ϐ�����菜���ĕ��͂��邱�ƂŁC��Ɠ��ł̌o�����j���Ԓ����i���ɉe������̂��ׂ��B
�@�Œ���ʃ��f���ɂ�镪�͂��s�����̂́C���̗��R����ł���B���p�f�[�^�ł́C�����Ǘ��E�ւ̃A���P�[�g���������x�ɍs���悤�ɂƂ�������͂��Ă��邪�C��E�ɂ��Ă͌��肪�Ȃ��B�������Ƃ��ƒ��������̍�����Ƃŏ����̉ے����������̕����E���A���P�[�g�̑ΏۂƂ���X��������C���ۂ������������E�̒������������߂ɏo��Ƃ������e�����l������B�܂��C�f�[�^����͓����Ȃ�������Ɠ����������Ŋ�Ƃ̒��������ɍ�������ƁC�ʌ��ʂ��l���ɓ��ꂸ�ɉ�A���͂��s�����ꍇ�ɁC���ۂ��������v���t�@�C���̌X�����}�ɐ��v����\��������i�}�P�j�B
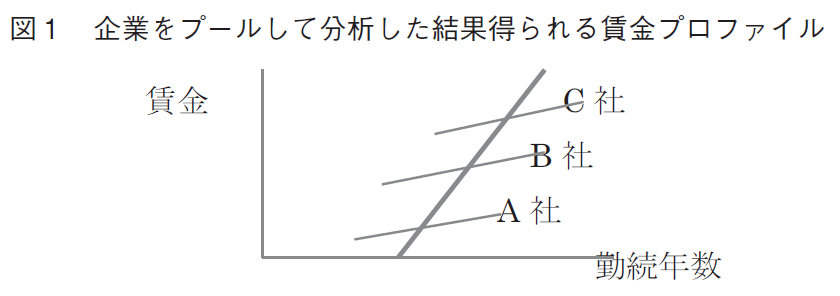
Bronars and Famulari�i1997�j�́C354�̎��Ǝ҂��瓾��ꂽ1,740�l�̌[�f�[�^�𗘗p���Ē������𐄌v���C��Ƃɂ���Ē����v���t�@�C�����قȂ�_�������Ă���B�ނ�̃f�[�^�ł́C���ς��āC�P���Ə�������6.98�l�̃T���v�������݂���B�{�����ŗ��p�����f�[�^���C���ς���ƂP��Ɠ�����̃T���v����12�l�ł���C��ƊԂ̊i�����l���ɓ��ꂽ���͂��]�܂����B
�@�Œ���ʃ��f���ƕ����ă����_���G�t�F�N�g���f���ɂ�鐄�v���s�������C�n�E�X�}���e�X�g���L�Ӑ����P���ŗ����f���̌W���̒l�͈قȂ邱�Ƃ������ꂽ���߁C�Œ���ʃ��f�����̗p����B
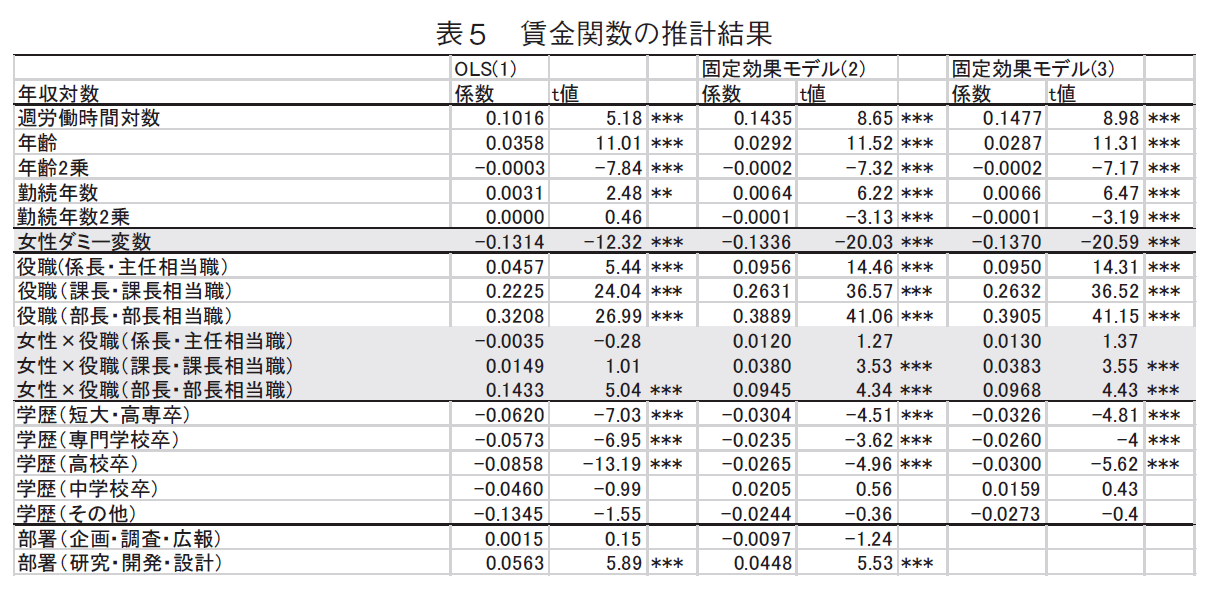
�y98 �Łz
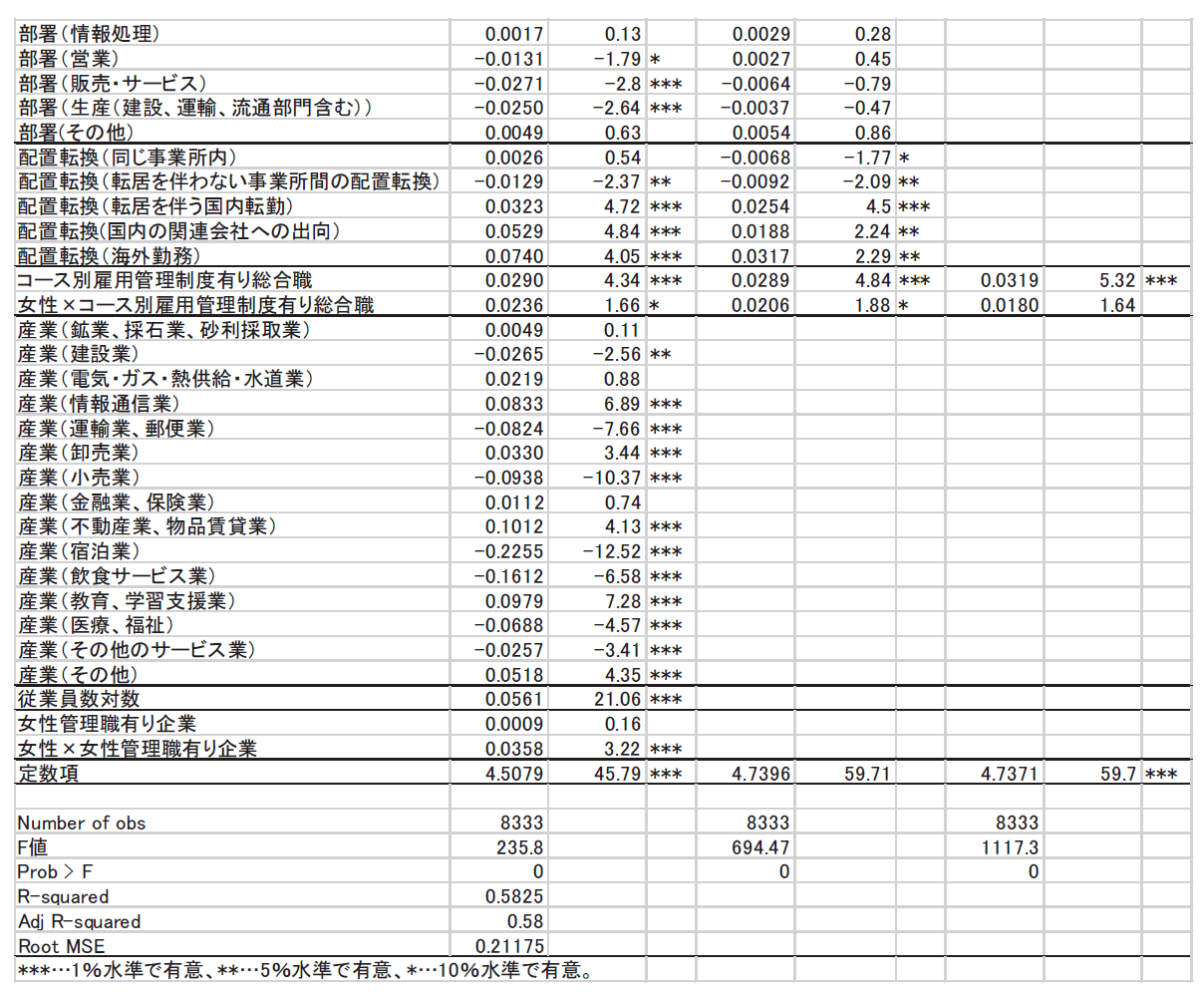
�܂��C�����_�~�[�ϐ��ɂ��Ċm�F����B�i�P�j�C�i�Q�j�C�i�R�j������̕��͌��ʂł��C�����_�~�[�ϐ��͗L�ӂɃ}�C�i�X�ł��邪�C�W���̒l�́C�ŏ��Q��@�ł́|0.1314�������̂��C�Œ���ʃ��f���i�Q�j�ł́|0.1336�Ɛ�Βl�͂قƂ�Ǖς��Ȃ��B���Ȃ킿�C��Ƃ̌ʌ��ʂ���菜���Ă��j���Ԓ����i���͏k�����Ȃ��Ƃ�����B
�@��E�_�~�[�ϐ��Ə����_�~�[�ϐ��Ƃ̌������́C�ŏ��Q��@�̕��͌��ʂł͕����E���������݂̂ŗL�ӂɃv���X�ł���B���̌W���̒l�͏����_�~�[�ϐ��̌W���ł���j���Ԓ����i����ł������傫���ł���B�Œ���ʃ��f���ɂȂ�Ƃ��̌������̌W���̒l�͌������C�ے��E�ے������E�Ə����_�~�[�ϐ��Ƃ̌��������L�ӂ̃v���X�ƂȂ�B�j���Ԓ����i���͑��݂�����̂́C��Ƃ̌ʌ��ʂ��R���g���[������ƁC��E���オ��ɂ�āC���̊i�����k�����Ă����Ƃ�����B�����̕����ł́C�i�Q�j�̌��ʂ��C�j���Ԓ����i���͂S�����x�ł���i�|0.1336�{0.0945�j�B�����_�~�[�ϐ��ƃR�[�X�ʌٗp�Ǘ����x�L�葍���E�_�~�[�ϐ��Ƃ̌������̌W�����C�����E�̏����ł���C����ɂQ���i�����k�����邱�Ƃ��킩��B
�@�i�Q�j�i�R�j�̔�r����́C��Ɠ��ł̔z�u�]���̍��╔���̈Ⴂ�Ƃ������C��Ɠ��o���̉e�����܂߂��ꍇ���܂߂Ȃ��ꍇ���C�����_�~�[�ϐ��̌W����L�Ӑ��ɑ傫�ȕω����Ȃ����Ƃ���C�j���Ԓ����i���́C�\�R�Ŏ������悤�Ȓj���̔z�u�]���̍��ł͐����ł��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B
�y99 �Łz
���̑��̕ϐ��ɂ��Ċm�F����B�T�J�����ԑΐ��͗L�ӂɃv���X�ł���B�Œ���ʃ��f���̌��ʂ��C��ƌʌ��ʂ���菜������̕����C�W���̒l�͑傫���B���݂̘J�����Ԃ������J���҂́C�P�N�O���J�����Ԃ������\�����������߁C�P�N�O�̔N���������Ȃ��Ă���Ƃ�����B
�@�N��C�Α��N��9�j�Ƃ����̂Q�捀�́C�قڗL�ӂł���C�N���Α��N���������Ȃ�قǒ����͏㏸���邪�C���̒l�͒������邱�Ƃ��킩��B��E�C�w���͍����قǒ����������Ȃ�B�R�[�X�ʌٗp�Ǘ����x�L�葍���E�_�~�[�ϐ��͗L�ӂɃv���X�C���̕ϐ��Ə����_�~�[�ϐ��Ƃ̌��������L�ӂɃv���X�ł���C�����i2005�j���w�E����悤�ɁC�R�[�X�ʌٗp�Ǘ����x�ŃV�O�i�����O��肪�������C�u�����E�v�ɂ͍����������^�����C���ɏ����ł��̌X�������܂�Ƃ�����B�Œ���ʃ��f���̕��͌��ʂł́C�����_�~�[�ϐ��Ƒ����E�_�~�[�ϐ��Ƃ̌��������C�����E�̒j���Ԓ����i���͂Q�����x�k�����邱�ƂɂȂ�B�Ƃ͂����C����ł�11���̒j���Ԓ����i�����c�邱�ƂɂȂ�B
�@��Ƒ����ɂ��ẮC�]�ƈ����ΐ����L�ӂɃv���X�ł���C�K�͊Ԓ����i���̑��݂��������B�܂��C�����Ǘ��E�L���ƃ_�~�[�ϐ��Ə����_�~�[�ϐ��Ƃ̌��������L�ӂɃv���X�ł���B
�@�����Ǘ��E�����݂����Ƃł́C�j���Ԓ����i�����킸���ł͂��邪�k�����邱�Ƃ��������B
�@�ȏ�C��Ƃ̌ʌ��ʂ���菜���Ă��C�j���Ԓ����i���͑��݂��邪�C��E���オ��ɂ�Ă��̍��͏k�����C�ے��E�N���X�ł�9.5���C�����E�N���X�ł͖�S���̊i���ƂȂ邱�Ƃ��킩��B�܂��C�����E�̏����ł́C����Ɋi�����Q���k������B
�R�DTreatment Effect Model
�����āCTreatment Effect Model�̕��͌��ʂ��C�j���ʂɎ����BTreatment Effect Model�͒j���ʂɕ��͂��s���C�Ǘ��E�i�ے��E�ے������C�����E���������j�ł���ꍇ�ɂP�C����ȊO�͂O���Ƃ�_�~�[�ϐ�������ϐ��Ƃ����B�P�i�K�ڂ̃v���r�b�g���f���ɂ���������ϐ��ɂ́C�q�ǂ��̐��C�����l�L���_�~�[�ϐ��C�ƒ�Ǝd���̗����̂��߂ɏ��i��]�܂Ȃ��ꍇ�ɂP���Ƃ�_�~�[�ϐ��̂R�𗘗p�����B�ʏ�̍ŏ��Q��@�ɂ�镪�͂������čs�����B
�@���͌��ʂ�\�U�|�P�C�U�|�Q�Ɏ����B
�@�\�U�|�P�C�U�|�Q���CTreatment Effect Model�ɂ�蕪�͂��邱�ƂŁC�ʏ�̍ŏ��Q��@�̕��͂ɔ�ׁC�Ǘ��E�̌W�����C�����ł�0.2381����0.2755�ɑ����C�j���ł�0.1969����0.3823�ɑ������Ă���B�������C�����̌덷���̑��ւ�\���������~���́C�����ł̓}�C�i�X�����L�ӂł͂Ȃ��C�j���Ń}�C�i�X�ɗL�ӂł������B�����ł́COLS�i�ŏ��Q��@�j�Ő��v���ꂽ�������̊Ǘ��E�̌W���́C�Ǘ��E�ɂȂ鏗���́C���ݓI�ɔ\�͂�������荂����������҂ɕ��Ă���Ȃǂ̗��R�ŁC�v���X�Ƀo�C�A�X������Ɨ\�z���ꂽ���C�덷���̑��ւ��L�ӂłȂ����Ƃ��炻�̉e���͖����ł���Ƃ�����B
�@����C�j���ł́COLS�Ő��v���ꂽ�Ǘ��E�̌W���́C���ۂ����ߏ��]������Ă��邱�Ƃ������ꂽ�B����́C���������̒j���Ǘ��E�̒����͒Ⴂ���C�\�͓��C�ώ@����Ȃ��v�����R���g���[������ƁC���ۂ͊Ǘ��E�͂�荂�������Ă��邱�ƂɂȂ�B���̗��R�Ƃ��āC��
�y100
�Łz
�̂��Ƃ��l������B��́C�����ł̕��͂͊�Ɠ������R���g���[������Ă��Ȃ��̂ŁC�Ǘ��E���C�ƐтȂǂɂ��������Ⴂ��Əo�g�҂ɕ��Ă��邱�Ƃł���B����Ɋւ��āC�p�l�����͂̌Œ���ʃ��f���ł����l�̐��莮�̉�A���͂��s�����Ƃ���C�����̊Ǘ��E�W���́C0.2524�C�j���̊Ǘ��E�W���́C0.2006�ƂȂ�COLS����W���l���������傫�ȍ��͐����Ȃ��������߁C���̂悤�ȕ�͖��������Ƃ�����B
�@��ڂ́C�J�����ԂƔN���̃^�C�~���O���قȂ��Ă��邱�Ƃł���B�Ǘ��E�ƂȂ��č�N���獡�N�ɂ����ĔN�����傫���ω������ꍇ����N�̒Ⴂ�N���Œ����������v����Ă���ƁC�Ǘ��E�̒����͒Ⴍ�Ȃ�o�C�A�X���������Ă��邱�Ƃ��l������B�c�O�Ȃ���C���p�f�[�^�ł͏��i���������ɂ��Ă̏�����Ȃ����߁C���̓_�͊m�F�ł��Ȃ��B������ɂ��Ă��C���ݓI�ɔ\�͂̒Ⴂ�j�����Ǘ��E�ɏ��i���Ă��錋�ʂƂ͍l���ɂ����B
�@�����ł́C�ے��E�ے������ƕ����E�������������킹�� �u�Ǘ��E�v �Ƃ��Ă���B�����ŁC�����E���������̃T���v���𗎂Ƃ��C�ے��E�ے������܂ł̃T���v���Ɍ����ē��l�̕��͂��s���āC�Ǘ��E�_�~�[�ϐ��̐��v���ʂɕω������邩�ׂ��B���̏ꍇ�̕��͌��ʂł́C�j���Ƃ��ɂ͗L�ӂłȂ��Ȃ����B
�@�ȏ�CTreatment Effect Model���C�����ł͊Ǘ��E�ɂȂ邱�Ƃɂ������㏸�́C���Ƃ��Ɛ��Y���̍����������Ǘ��E�ɂȂ��Ă���Ƃ����肪�e�����Ă���Ɨ\�z���ꂽ���C���̂悤�ȕ�͂قƂ�NJώ@����Ȃ����Ƃ������ꂽ�B
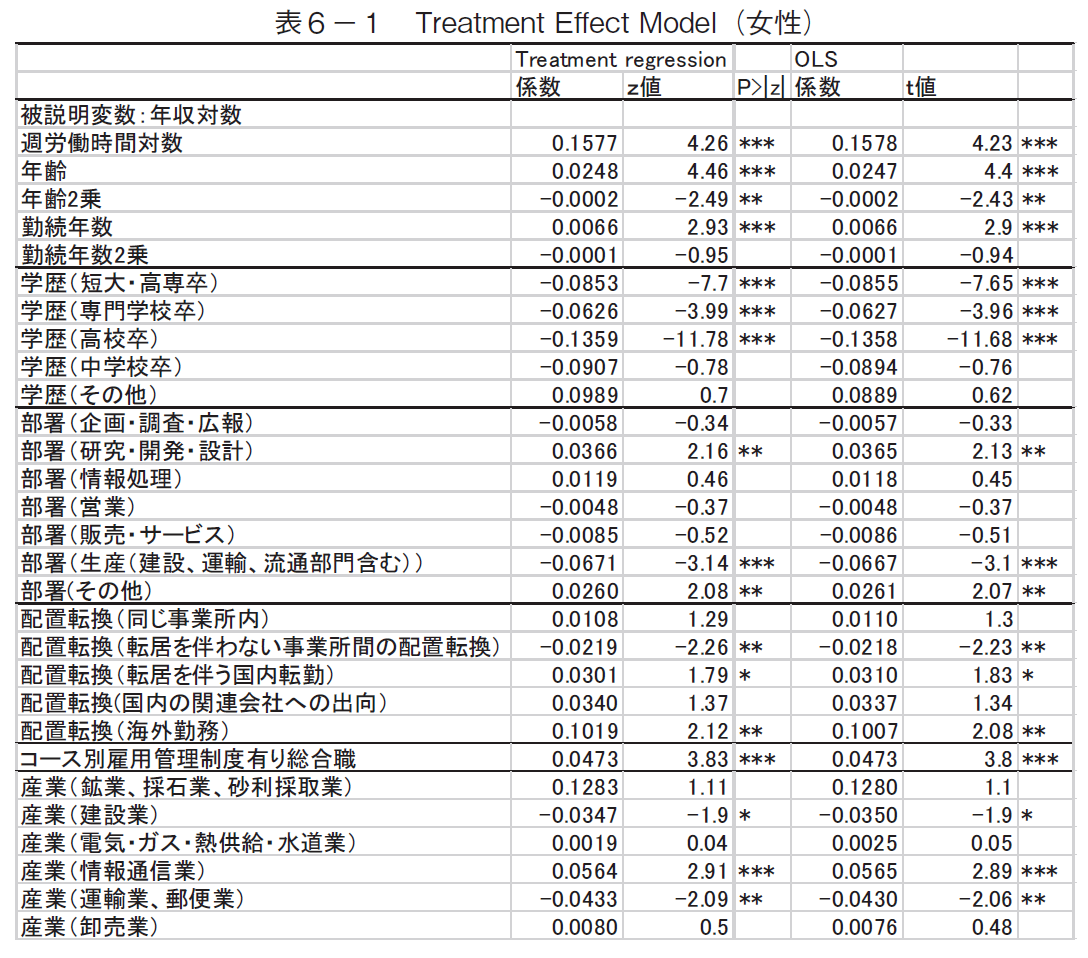
�y101 �Łz

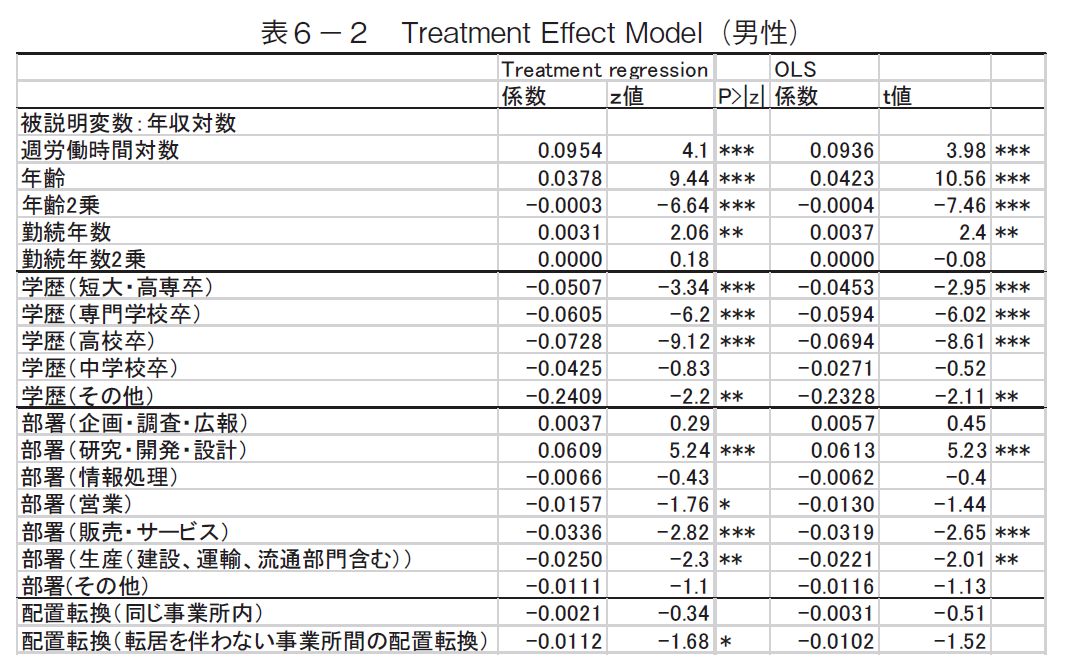
�y102 �Łz
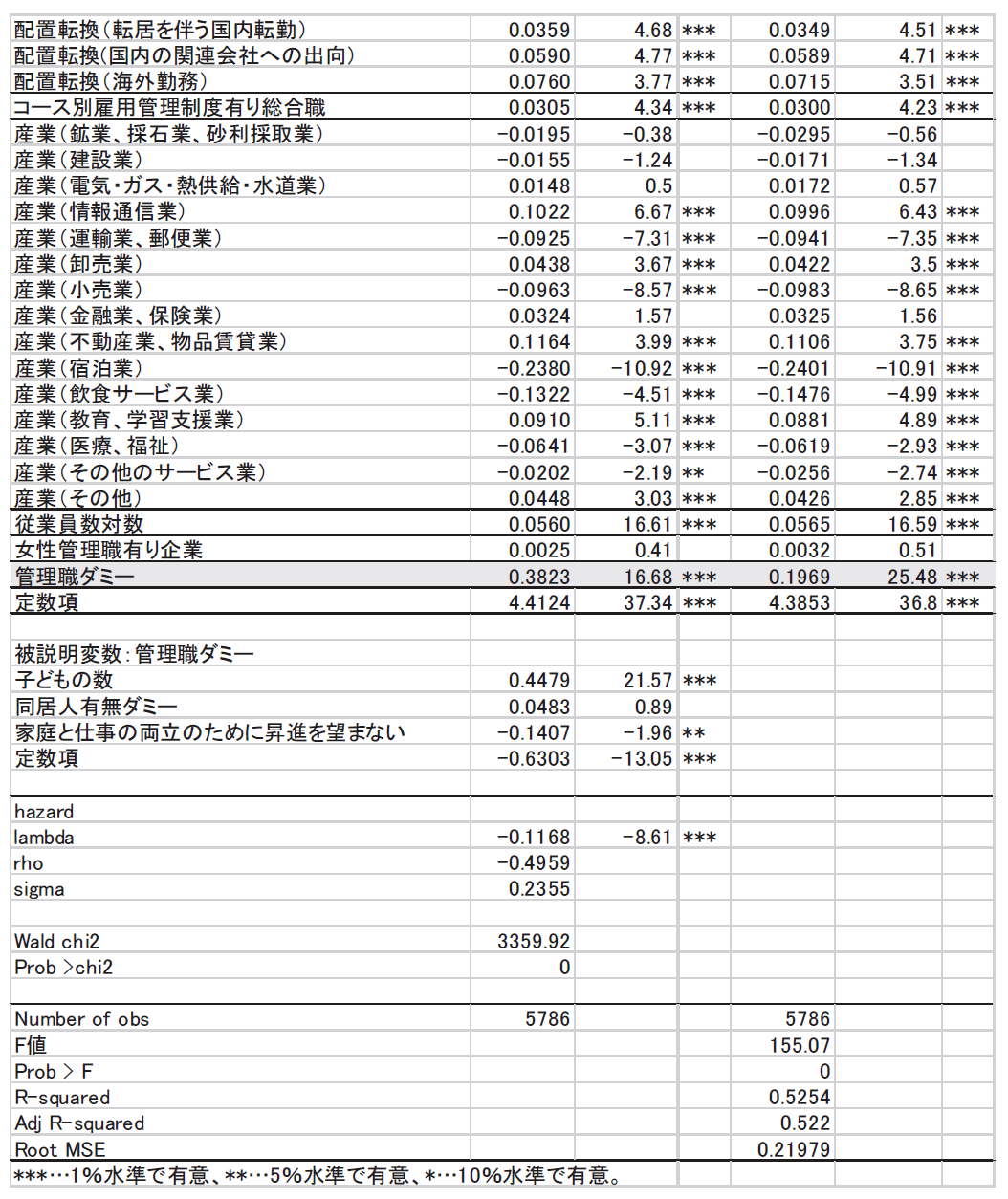
�Z�@�ނ���
�{�����ł́C�����Ǘ��E�𑽂��܂ޖL�x�ȏ]�ƈ��f�[�^�𗘗p���C�����������߂邱�ƂŒj���Ԓ����i���͂����B��Ȍ��ʂƂ��ẮC�P�j�Œ���ʃ��f���ɂ���ƌʂ̑�������菜���Ă��C�j���Ԓ����i���͏k�����邱�ƂȂ��C13% ���x���݂��邱�ƁC�Q�j��E���オ��ɂ�Ēj���Ԓ����i���͏k�����C�����E�ł͂S����ɂȂ邱�ƁC����ɑ����E�ł͒����i���͂Q���k�����邱�ƁC�R�jTreatment Effect Model�ɂ�菗���Ǘ��E�ɂ̓T���v���Z���N�V�����E�o�C�A�X�͊ώ@����Ȃ��������Ƃ������ꂽ�B
�@����C�Œ���ʃ��f���ɂ���ƌʂ̓�������菜���Ă��C13���̒j���Ԓ����i�����c�邪�C��E���オ��ɂ�Ċi�����k�����邱�ƁC�����E�ł���C����Ɋi�����k�����邱��
�y103
�Łz
�������ꂽ�B�����E��I�ԏ����Ј��ł���C��ƂɂƂ��Ă̏��̔�Ώ̐�����������邱�Ƃ��瓝�v�I���ʂ������Ȃ�C�j���Ԓ����i���͏k������Ɨ\�z���ꂽ���C���̒ʂ�̌��ʂ�����ꂽ�B�������C�����E�ł��Q�������i�����k�����Ȃ����Ƃ���C�����E��I�ԂƂ��������J���҂̃V�O�i������Ƒ��ɂ���قǐM�p����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ�����̂�������Ȃ��B
�@�R�[�X�ʌٗp�Ǘ����x�L���Ƃ̑����E�Œ����i�����k�����邱�Ƃɂ��ẮC���̔�Ώ̐����k�����邱�Ƃ̑��ɁC�R�[�X�Ȃ���Ƃł͓�����E�ł����Ă��j���Ԓ����i�����傫���Ƃ������Ƃ̗��Ԃ��Ȃ̂�������Ȃ��B���ɁC�R�[�X�Ȃ���Ƃł́C���ԂƂ��đ����E�ƈ�ʐE�ɕ����Čٗp�Ǘ����Ă����Ƃ�����i���1999�j�C�{�����Ɠ����f�[�^��p���Ĕz�u�]���̒j����r����������E����E�e��i2014�j�͓��ɃR�[�X�Ȃ���ƂŔz�u�]���̒j���������o���Ă���B����������Ƃ��ǂꂩ�̓f�[�^�ł͔c���ł��Ȃ����C�j���̒����i���������炵�Ă���\��������B���ɁC�W���E��C�����E�C�ے������E�Ȃǂ̂悤�� ������E� ���t���E�ʂ́C���C���̊Ǘ��E�ƃ��C���łȂ��Ǘ��E���܂�ł���B����i2012�j�� ������p�̖�E�v�C�e��i2014�j�� ����b�I�W���v �ƕ\�����Ă���悤�ɁC���� ��Ǘ��E�v �Ƃ������̂ł������̑��������C���łȂ��Ǘ��E�ɏA���Ă��邱�Ƃ��l�����C���ꂪ���� ��Ǘ��E� �ł��j���̒����i���������炵�Ă���\��������B��L�̑��̓_�̎��ԂƂ��đ����E�E��ʐE�ɕ����Čٗp�Ǘ����Ă��邩�ۂ��C�܂����̓_�̃��C���̊Ǘ��E���ۂ��́C��ʒ����œ��肷�邱�Ƃ͍���ł���B���ɂ��f�[�^����͓���ł��Ȃ����炩�̒j���Ԃ̐��Y���̍������邩������Ȃ��B�Ǘ��E�̒j�������i�������ɋN������̂��́C����C���^�r���[�Ȃǂ̒萫�������܂߂ĕ����I�ɃA�v���[�`���Ė��炩�ɂ��ׂ��ۑ�ł��낤�B
�@�z�u�]���̌o�����R���g���[�����Ă����C�j���Ԓ����i���������Ă��邱�Ƃ���C����̓R���g���[���ł��Ȃ��������CKato, Kawaguchi and Owan�i2013�j�̎w�E����悤�� �u�d���̃��x���v �������i���ƂȂ��Ă���\��������B����̗��p�f�[�^�ł́C�E���z�u�]���̌o���ɂ��Ă̏��܂ł�������ꂸ�C�z�u�]���̉�^�����Ă���d���̓��e�̓R���g���[���ł��Ȃ������̂��c�O�ł���B�����C��E���オ��ɂ�āC�j���Ԓ����i���͋}���ɏk������B�c��i���̌����͉𖾂���K�v�͂�����̂́C��E�҂ł� �u�d���̃��x���v �ɍ��������Ȃ��Ă������Ƃ��������錋�ʂł͂Ȃ����낤���B
�ӎ�
���̘_���̎��M�ɂ�����C�i�Ɓj�J�������E���C�@�\���M�d�ȃf�[�^�̒��܂����B�܂��C�������_�����C���{�I�ȉ���Ɋւ����ɋM�d�ȃR�����g�����������܂����B�L���Ċ��ӂ̈ӂ�\���܂��B
�Q�l����
�������_�i2005�j�u�j���̌ٗp�i���ƒ����i���v �w���{�J�������G���x No.538, pp.15-31.
����͎q�i1999�j�u�呲�����z���C�g�J���[�̊�Ɠ��L�����A�`���|���������E���E�̎��Ԓ������v �w���{�J�������G���x No.471, pp.15-28�B
����͎q�i2012�j�u���������E�E��E�̃L�����A�`���|�ϓ��@����Ƒ��Ƃł͈Ⴄ�̂��|�v �w�r�W�l�X���A�J�E���e�B���O���r���[�x ��X���Cpp.107-127�B
����͎q�E����߂��݁E�e�▾�i2014�j�u�j���̏��i�i���͂Ȃ��ǂ̂悤�ɐ�����̂��|��ƒ����ƊǗ��E�E��ʏ]�ƈ������̎��ؕ��͂��|�v�C���{�J���w���44��S����� �w�����_�W�x �y104 �Łz pp.197-204
����́i2008�j �w�W�F���_�[�o�ϊi���x �C�������[�B
���r�a�j�i2009�j �w���{�Y�ƎЉ�́u�_�b�v�x �C���{�o�ϐV���o�ŎЁB
����W���i2005�j�u�j���Ԓ����i���͚n�D�ɂ�鍷�ʂ��������v�C �w���{�J�������G���x�CNo.540�Cpp.55-67.
�x�t�F�i1998�j�u�j���Ԓ����i���̏k���X���Ƃ��̗v���v�C �w���{�J�������G���x�CNo.456�Cpp.41-51.
���㏮�G�i1980�j�u�j�����ʂƓ��{�̘J���s��v �w������{�̕a���𖾁x ��Q�́C���m�o�ϐV��ЁB
�R����j�i2008�j�u�j���̒����i�������ւ̓��\���v�I���ʂ̌o�ϓI�s�����̗��_�I�E���ؓI�����v�C �w���{�J�������G���x �CNo.574�Cpp.40-68.
�J�������E���C�@�\�i2010�j�u��Ɠ��ɂ�����R�[�X�ʌٗp�Ǘ��C�|�W�e�B�u�A�N�V�����C�玙�x����ƒj���Ԓ����i���ɂ��āv�C �w�j���Ԓ����i���̌o�ϕ��́x ��R�́CJILPT�����V���[�YNo.75 �B
�Ɨ��s���@�l�J�������E���C�@�\�i2014�j �w�j�����Ј��̃L�����A�Ɨ����x���Ɋւ��钲�����ʁi�Q�j�|���͕ҁx JILPT�����V���[�YNo.119
�e�▾�i2014�j�u�u�x���I���v�͏����ɕs���ɓ����Ă��邩�\���۔�r���߂�������ƃf�[�^�ƊǗ��E�f�[�^�̕��́v �w�j�����Ј��̃L�����A�Ɨ����x���Ɋւ��钲�����ʁi�Q�j�|���͕ҁx ��V�́CJILPT�����V���[�YNo.119 �Cpp.187-212�B
�����J���ȁi2003�j �w����15�N�œ��������̎���x
�����J���ȁi2010�j �w����22�N�Œj�������Q�攒���x
�����J���ȁi2011�j �w����23�N�����\����{���v�����x
Abe,Yukiko�i2009�j �gEqual Employment Law and the Gender Wage Gap in Japan: A Cohort Analysis�h, Journal of Asian Economics, 21�i2�j, pp.142-155.
Becker, G. S.�i1971�j The Economics of Disctimination, Chicago University Press.
Bertrand, Marianne and Kevin F. Hallock�i2001�j �gThe Gender Gap in Top Corporate Jobs�h, Industrial and Labor Relations Review, 55, pp.3-21.
Bronars, Stephen G. and Melissa Famulari �i1997�j�gWage, Tenure, and Wage Growth Variation Within and Across Establishments�h, Journal of Labor Economics, Vol.15, No.2, pp.285-317.
Kawaguchi, Daiji�i2007�j �gA Market Test for Sex Disctimination: Evidence from Japanese Firm-Level Data�h, International Journal of Industrial Organization, Vol.25, Issue 3, pp.441-460.
Kato Takao, Kawaguchi Daiji and Owan Hideo�i2013�j �gDynamics of the Gender Gap in the Workplace: An econometric case study of a large Japanese firm�h, REITI Discussion Paper Series, 13-E-038.
Maddala, G. S.�i1983�j Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press.
Miyoshi, Koyo�i2008�j �gMale-female wage differentials in Japan�h, Japan and the World Economy, 20, pp.479-496.
Petersen, Trond and Laurie A. Morgan�i1995�j �gSeparate and Unequal: Occupation-Establishment Sex Segregation and the Gender Wage Gap�h, American Journal of Socioligy, 101, pp.109-148.