�y1 �Łz
�u��Ɖƃl�b�g���[�N�v����{�o�c�j�����Ɉʒu�Â��邽�߂̎��_
��@�P�v
�͂��߂�
�{�e�́C����܂ŕ��͂��Ă����u��Ɖƃl�b�g���[�N�v�̌���1�j���C�o�c�j�����̒��Ɉʒu�Â��C���̓����ƈӋ`�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B���������珺�a��O���Ɏ��鎞�������グ���u��Ɖƃl�b�g���[�N�v���C�������猩�������ꂽ��������邾���ł͂Ȃ��C�o�c�j�����S�ʂ̒��Ɉʒu�Â���ɂ́C�ǂ̂悤�Ȏ葱�����K�v�Ȃ̂ł��낤���B������l�@������ŁC�{�����̂܂Ƃ߂Ƃ������B
�@�K�v�Ȏ葱���́C�傫�������ĂQ����B��́C�o�c�j�����ɒ��ڊւ��P�[�X�X�^�f�B�Ƃ������@��̖��ł���C��́C����܂ł̓��{�o�c�j�����S�̂ɂǂ̂悤�ɂ��ĊW������̂��C�Ƃ������ł���B�o�c�w�ł́C�o�ϊw�Ƃ͈���āC�~�N���I��̂ł����Ƃ̍s���K�́E�����I�s�������C�}�N���I�Ȏ��_�ł���Y�Ƃ⍑�̖��Ɋւ�镪�͂͏\���ɂ͈����Ă��Ȃ������B���̂��߁C���ʂȗ��_�I��Ղ��琶�ݏo����鑊�݂Ɋ֘A���������Ƃ͌������C�X�̌����͑��݂ɊW�������ƂȂ��C���������C�ߋ��̌����̊Ԍ���D���āC���ꂼ�ꋤ�ʂ̕����ΏۂƂ��āC�����ł̍v�������S�ƂȂ��Ă����B�o�c�j�����ɂ����Ă����l�ɁC��ՂƂȂ��Ƃ̍����I�ȍs��������X�̌����̊��ɂ���ׂ����ʂ̎����C�����Ă܂��X�̌���������ׂ��鎋�_�������Ă���ƌ��킴��Ȃ��B���̌��ʁC�X�̌��������邱�Ƃ��o�����ɁC���ꂼ��̕���͓Ɨ��������݂̂悤�Ȋς�悵�Ă����B
�@�����Ŗ{�e�́C�P�[�X�X�^�f�B�ň������Ώۂ̈�ʐ��ɂ��čl�@����ƂƂ��ɁC���̈�ʐ����x���Ă�����{�ŗL�̉��l���O�C�s���K�͂����l�@���Ă��������B��ʐ��ɂ��ẮC��ԓI�ȕ��Ր��⎞�ԓI�Ȍp�����̑��ɁC���O���C���Ƃɐ�i�H�ƍ��Ƃ̔�r�Ƃ������_������l�@���Ă��������B���l���O�ɂ��ẮC���{�o�c�j�͂���ɓ������ĕs���Ȏ��_�ł���C������㔭���Ƃ��������ɉ����āC���{�ŗL�̉��l�ςɊ�Â��s���K�͂̂Q�̎��_����l���Ă�������
�y2 �Łz
�P�D�u��Ɖƃl�b�g���[�N�v�̈�ʐ��ɂ���
�P�[�X�X�^�f�B�Ƃ����������@�܂��āC������o�c�j�S�̂ɓ������鎋�_����l���Ȃ�������Ȃ��B�܂��C���{�o�c�j�����ɂ����ẮC�����̐��͖c��ł͂�����̂́C���グ��e�[�}�͋����܂܂̏̒��ŁC�������C���{�̌����X�^�C���̓����ł������B�̌����ᔻ��������Ă������ʁC���J��ȕ����T���������Ă������߂ɁC�����̌����͎��Ԃ��o�ɂ�ď����ȃe�[�}�ɌQ���邱�ƂƂȂ����B���ꂼ��̃e�[�}�������ʂȎ����́C���ɂ�����Ȃ��ł����B��������������O���ɒu���āC�u��Ɖƃl�b�g���[�N�v�̌�������{�o�c�j�����̓������ӎ����āC�Z�߂Ă��������B
�@�P�[�X�X�^�f�B�Ƃ��������X�^�C���̌��E����ɂ́C�ΏۂƂ���P�[�X���C���{�o�c�j�̑S�̂̒��Łu��ʐ��v��ттĂ���K�v�����낤�B�u��ʐ��v�Ƃ́C���鎞��ŕ����̃P�[�X��������Ƃ��������ƂƂ��ɁC����̕ω��̒��Ōp�����Ă���Ƃ����������厖�ł���B���ꂾ���ł͂Ȃ��B���̃P�[�X�ݏo���Ă�����v���ɂ��ڂ�z��K�v�����낤�B�u��ʐ��v��S�ۂ���̂́C���v���ł���B�]���āC���E���ʂ̊��v���ł͂Ȃ��C���{�ŗL�̊��C���鎞��ɌŗL�̊��łȂ���Ȃ�Ȃ��B���̊��v���ɂ��ẮC�X�̌o�c��̂ɋy�ڂ������l���O��s���K�͂�ʂ��āC���{�o�c�j�̒��Ɉʒu�Â���K�v������B
�@�����ł܂��u��Ɖƃl�b�g���[�N�v�̓�����ʂ��āC���̈�ʓI�ȑ��ʂ���C��i���Ɣ�r���Ă݂����B�ŏ��ɋ�ԓI�����ԓI�Ȉ�ʐ����l���Ă������B����31�N�ɂ������Ɖƃl�b�g���[�N�́C���{�S����1,130����C�k�C�����玭�����܂ő��݂��Ă����B����40�N�ɂ͓��{�S����1,517����C���l�ɖk�C�����玭�����Ɏ���܂ő��݂��Ă����B�X�ɑ吳10�N�ɂ�5,148�������B���̐����́C�����C���N�C���B�Ȃǂł̊�Ɖƃl�b�g���[�N�����������̂ł���B�����A���n�Ȃǂł̊�Ɖƃl�b�g���[�N���܂߂�ƁC�吳10�N�ł�5,710�C���a11�N�ł�4,325������2�j�B��������C����31�N���珺�a11�N�Ɏ���܂ŁC�k�C�����玭�����܂ł��ׂĂ̕{���ɑ��݂��C�X�ɂ́C�����C���N�C���B�ɂ�����ꂽ���Ƃ�������B�]���āC��ԓI�ɂ����ԓI�ɂ����ՓI�ɑ��݂��Ă�����Ɖƃl�b�g���[�N�����グ�C���̕��Ր��C��ʐ����x���Ă����v�����l���Ȃ�������Ȃ��B
�@���ɁC��Ɖƃl�b�g���[�N���l�@����ۂɌ���ꂽ���ۂ͓��{�ŗL�̂��̂Ȃ̂��C����Ƃ���i�H�ƍ��ł�����ꂽ�̂��C�l���Ă��������B���ׂĂ̌��ۂł̔�r�͏o���Ȃ��̂ŁC�����̌��C�����l���Ă��������B�Ƃ����̂��C��Ɖƃl�b�g���[�N�̕��͂��s���ɂ́C���C���������o���ƂȂ邽�߁C�N�����Ђ̉�Ж����ł�����������ȏ��ł������B�����ŁC����31�N�C����40�N�C�吳10�N�C����я��a11�N�� �w���{�S������Ж����^�x ��p���āC��ʂ̐l���ƌ��C���������L���Ă������B�\�P�C�\�Q�C�\�R�C�\�S������ł���B
�y3 �Łz
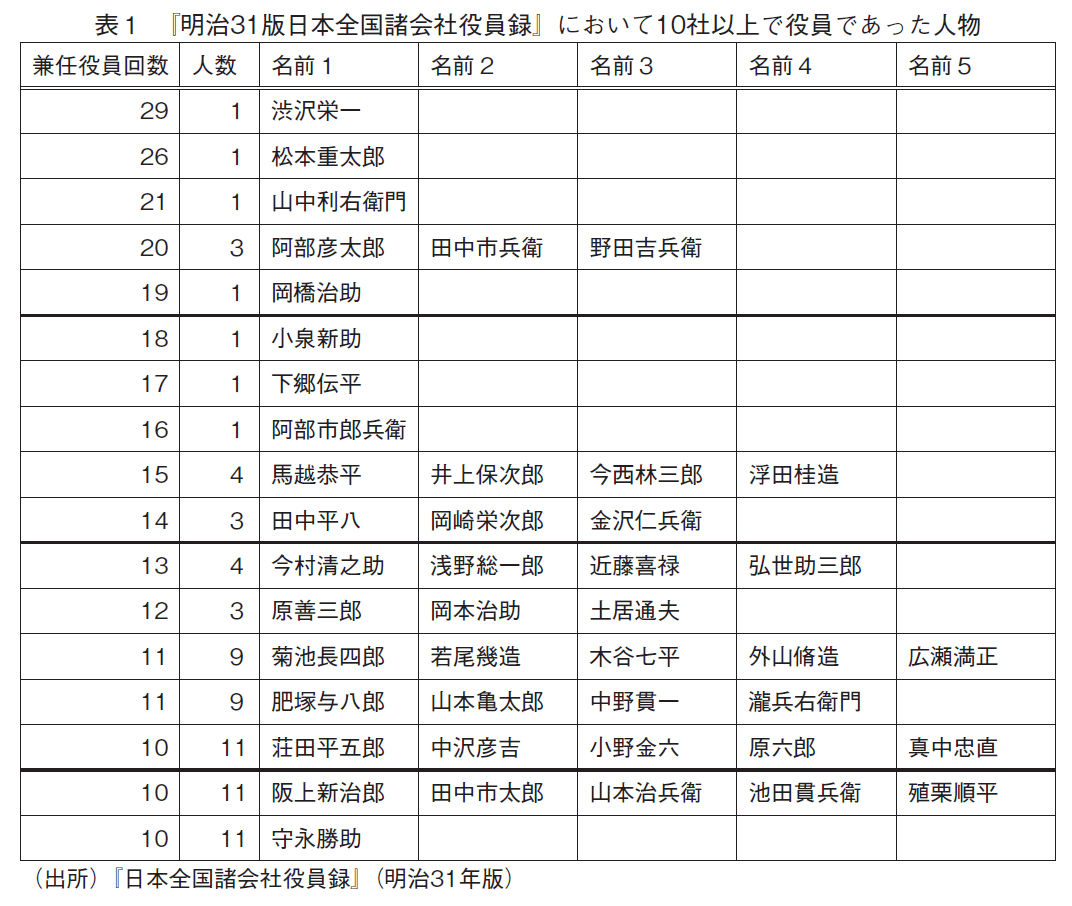
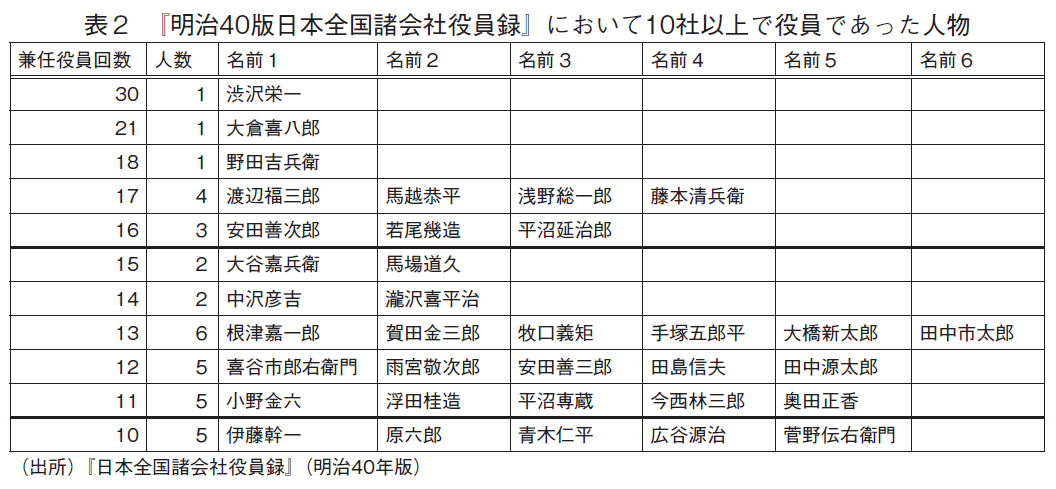
�y4 �Łz
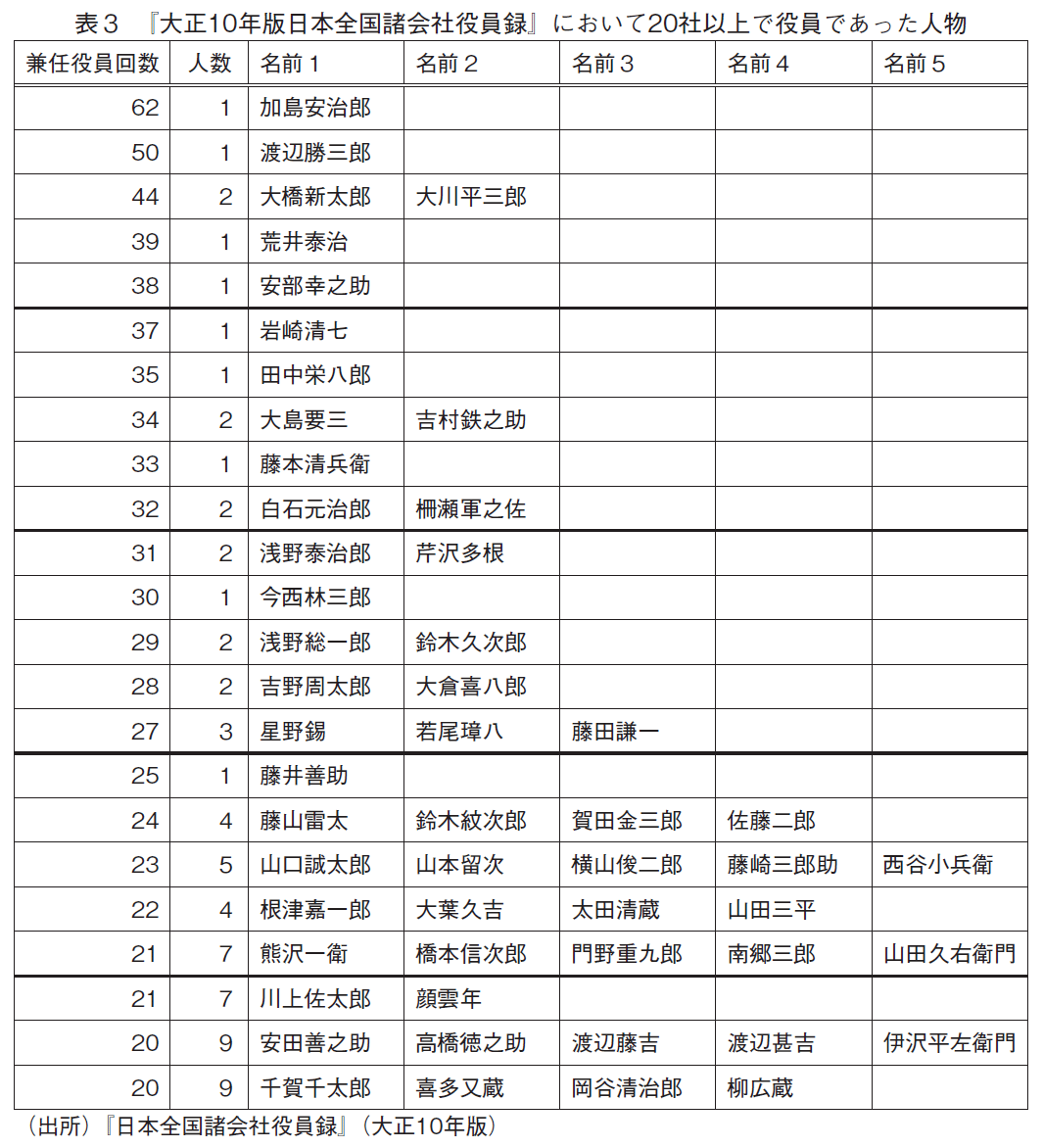
����31�N���珺�a��O���C�펞�o�ς��n�܂钼�O�̏��a11�N�܂ŁC30����60�Јȏ�ɂ��킽���ĉ�Ж����ł������҂���R�����̂ł���B�a��h��ɑ�\�����悤�Ȍo�c�҂Ƃ��ėL���Ȑl���������̉�Ђɖ����ł����������́C����܂Ŏw�E����Ă����B�X��p�� �w���{�o�c�j�x 3�j�ɋL����Ă���悤�ɁC�u������v�����ɂ���āC�����̉�Ђɖ����ƂȂ����l���C�������w�E����Ă����B�������C30�Ђ���60�Ђ��̉�Ђɖ����ƂȂ��Ă���҂́C��́C�������Ă����̂ł��낤���B�����������ۂ́C���{�����̂��ƂȂ̂ł��낤���B����Ƃ��C���{�ȊO��
�y5 �Łz
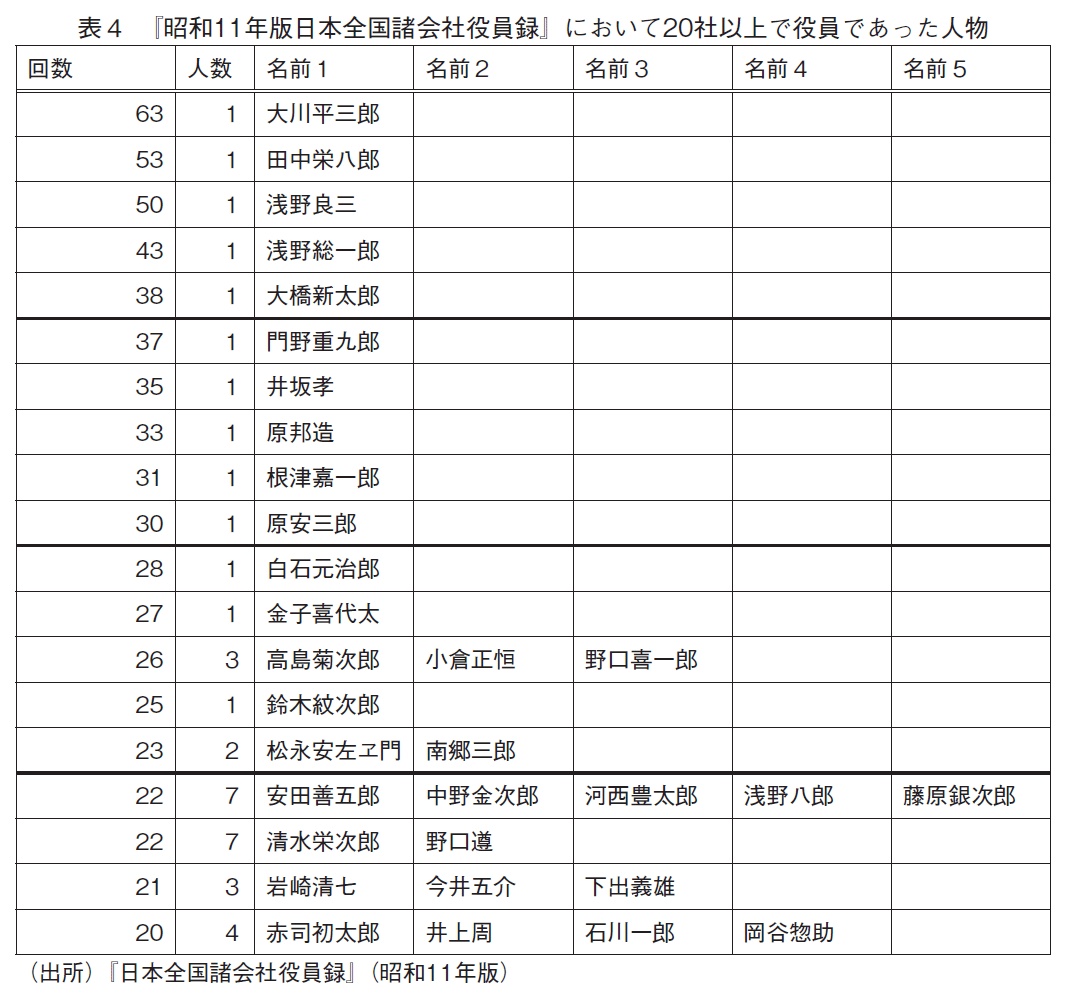
���ł�����ꂽ���ۂȂ̂ł��낤���B���������^�₪���X�ƕ�����ł���B�����ŁC���{�ȊO�̍��ł����l�̌��ۂ�����ꂽ���ǂ����C�m���߂Ă������B
�@�����Q���E�R�b�J�́CThe Rise of the Modern Industrial Enterprise in Germany �̒��ŁC���{�Ɠ��l�ɁC�����̉�Ж����ł������������w�E���Ă���4�j�B�h�C�c�ł́C1870�N�ȍ~�C��Ђ̓����@�\�͂Q�d�̍\���ł������Ƃ����B��Ƃ̃g�b�v�ɂ͎��������������C���̋@�\�́C�č�����iSupervisory Board, Aufsichtsrat�j�Ǝ��s�������iExecutive Board, Vorstand�j�̓�d�\���ł������B�č�����̃����o�[�́C���傩����̑�\�҂���I�o���ꂽ�B�č�����́C����̑�\�ɉ����ĘJ���g���̑�\���܂܂�Ă���B���̏�ŁC��Ђ̏d�v�Ȉӎv����C�Ⴆ�Γ�����g�b�v���x���̐l�������肳�ꂽ�B�č�������o�[�́C�P�N�Ő����������Ƃ͂Ȃ��C
�y6
�Łz
�����̃����o�[�͑��̊�Ƃł������E�ɏA���Ă����̂ł���B����C���s������͓��X�̌�����s���C���ۂɉ�Ђ��^�c���Ă����̂ł���B�ނ�́C�t���^�C���̏d���Ŏ��ƕ���̃g�b�v���߂Ă���C����Ђ̎�����ł��������B1914�N�ȑO�C��s�̎�������͈��O���[�v���`�����C�h�C�c�̊�����Ђ�20�p�[�Z���g���߂���ł������B�h�C�`�F�o���N�̖����͑S�̂�186�Ђ��̉�ЂŖ��������C���Ă������C��v�ȋ�s������44�Ђ��̉�Ж��������˂Ă����Ƃ���5�j�B������1930�N�܂łɁC���������100�Ђ��̖����ł������Ƃ����B���{�̎�������鎖�Ԃł������B�܂��C�t�����X�̎���ł́C���[���X�E�����B�����{���C�G�́C�L���[���}��������T�[�r�X���ƕ���ł́C��ƃO���[�v���`�����C�O���[�v�����o�[�̖����������O���[�v���̊�Ƃ̖����ɏA�C���Ă����Ƃ����B���ς���19�ЁC�͂��ł��邪�C����҂�50�Ђ���60�Ђ̖����ł������Ƃ���6�j�B
�@���Ȃ��Ƃ��h�C�c�ƃt�����X�̎��Ⴉ����M����悤�ɁC30�Ђ���60�Ђ̖��������C���Ă������{�̎���͌����ē���Ȃ��̂ł͂Ȃ��C�C�M���X�ɂ͒x��Ă������̂̓��{���͐�i���ł��鍑�X�ł�����ꂽ���ۂł������B�����Q���E�R�b�J���w�E���Ă���悤�ɁC�ނ�͊�����\���C�l���Ⓤ���Č��Ƃ�����v�Ȉӎv������s���Ă����B�����ăh�C�c�̎��Ⴉ���������悤�ɁC����̋Ɩ��̓t���^�C���̎��s�������S���Ă����̂ł���B���{�̏ꍇ�ł��C�����ł͂Ȃ��C�]���Ċ���̑�\�҂ł͂Ȃ��C�x�z�l�ɑ�\�����l��������̋Ɩ������Ȃ��Ă������͒m���Ă���B���ɁC���{�a�т̋e�r���O����\�I�ł���B�H����w�Z�o�g�̋e�r�́C�H���x�z�l�Ƃ��ĕ���a�сC���a�сC�ےÖa�т̋Z�t���H���x�z�l�Ƃ��ċZ�p�����Ă������C���̌㊔��ƂȂ��ĕ��{�В��̌�p�҂Ƃ��ē��a�т̎В��ɏA�C�������Ƃ͗L���ł���B���������������悤�ɁC����̑�\�҂Ƃ��Ẳ�Ж����Ǝ��Ƃ̐ӔC�҂ł���Z�t�E�H���x�z�l�Ƃ́C�S���ʂȎ����̑��݂ł������B�h�C�c��t�����X�����ē��{�ł��C��Ж����͊���̑�\�҂Ƃ��āC��Ђ̎�v�Ȉӎv������s���Ă͂������C����̋Ɩ����s���Ă͂��Ȃ������̂ł���B
�@����́C���傪��Ђ����Ă������Ƃ��Ӗ�����B��������C�h�C�c�C�t�����X�C���{�ł́C���a��O���܂ł́C���傪��Ђ����Ă����ƌ����Ă悢�B���a��O���܂Ō���ꂽ�����̉�Ђɖ������߂Ă����Ƃ������ۂ́C��i���O���ł�����ꂽ�̂ł���B����C��ɔ��\���������̍Ō�ɋL�����悤��7�j�C�����ɓo�ꂷ��l���́C���{�S���Ŋ���^�C�v�̋ߑ�I�Ȏ��ƂɊւ���Ă����l���ł������B�Ƃ��낪�C����ȊO�ɁC���C�������͑����͂Ȃ����̂́C�S��s�Ƃ����n���ԂŊ��Ă�����ƉƂ��������݂��Ă����B�ނ�́C�S��s�Ƃ�����ԂŁC�����̊�ƉƒB�Ɗ�Ɖƃl�b�g���[�N���`����āC��s��d���C�q�ɁC��ʋ@�ւȂǂ��ꂼ��̒n��̃C���t���Y�Ƃ������C�n��o�ςɍv�����Ă����̂ł���B�������C����31�N���珺�a11�N�܂Ōp�����đ��݂��Ă����̂ł���B�����ł������������̉�ЂɊւ��������́C��́C�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��s���Ă����̂��낤���B��������C����������Ɖƃl�b�g���[�N�̒��S�ɂ����劔��́C�ݗ����N�l�Ƃ��Ăǂ̂悤�Ȏ��Ɗ������s���Ă����̂��𖾂�
�y7
�Łz
���ɂ������B�Ƃ����̂��C���{�S�����҂ɂ������厖�ƉƂƂ��������C�����n���̎��Y�Əo�g�҂ŁC���ꂼ��̒n��ɍ��������������s���Ă����l���𒆐S�Ƃ�����Ɖƃl�b�g���[�N�ɂ��ẮC����܂ŏ\���Ȍ������Ȃ���Ă��Ȃ���������ł�����B����䂦�C���������珺�a��O���ɂ�������{�S���ł̕��͂�i�߂��ł́C�n���ɂ������Ɖƃl�b�g���[�N���͂����d�v�ł���ƍl������B
�@�ȏォ��C��Ɖƃl�b�g���[�N�����ԓI�ɂ��C��ԓI�ɂ���ʓI�ȑ��݂ł��������Ƃ����������B�܂��C�����̉�Ж����ɏA�C���Ă��邱�Ƃ��C���{�����Ɍ���ꂽ��ł͂Ȃ������B����ł́C����������ʓI�Ȍ��ۂݏo�����v���Ƃ́C��́C���ł��낤���B�����ŁC���̗v���ɂ��čl���Ă��������B���̗v���́C��Ɖƃl�b�g���[�N�̕��͂����ł͂Ȃ��C���{�o�c�j�̌����ɂ����Ă��s���Ȏ��_�ł��낤�B
�Q�D���{�o�c�j�̕��͂ɕK�v�ȂQ�̎��_
���{�o�c�j������i�߂�ۂɕs���Ȏ��_���l���Ă��������B���{�o�c�j�S�̂ɉe�����y�ڂ����v���Ƃ��āC�Q�̗v�������グ�C�l�@�����������B��P�̗v���́C�㔭���Ƃ��Ă̓����ł���C��Q�̗v���́C���{�ŗL�̉��l���O�Ɋ֘A������ł���B�O�҂́C��ʓI�ɁC�O�I�ȁC�`�ԓI�ȓ����Ƃ��Č���邪�C��҂́C�s���K�͂ɉe����^���C���ʓI�����I�ȖʂŌ����B�����ŁC�Q�̓������L���Ă��������B��P�̎��_�́C�K�[�V�F���N�����̌����ɑ�\�����悤�ɁC�o�ς̐��i��̖̂����n�߁C���[�h����Y�Ƃ̑��������ȂǁC�O�I�Ȗ��ɏW�����Ă����B�K�[�V�F���N�����̌����ɂ��ẮC�������i�C�������j�u��P�́@���{�̎Y�Ɗv���Ɗ�ƌo�c�v�́C�S�̓������L���Ă���8�j�B�܂��C�A���N�T���_�[�E�K�[�V�F���N�����i�r�c���q�q��j �w�o�ό�i���̎j�I�W�]�x �ł́C�u��҂͂������v�̒��ɂU�̓������L����Ă���9�j�B�����͂�������C�O�I�ȓ����ł���B�Ⴆ�C�}�����ł���C�d�H�Ƃ̔��W�������C�J���e���Ȃǂ̓Ɛ肪�i�ށC����̋��Z�@�ւ�{�̖������傫���C�����̏�����̋]���̏�ɐ�������C�_�H����̃A���o�����X�ɂ��L�����v���s�\���ł���ȂǁC���ʓI�Ɏ��؉\�ȑ��ʂɏW�����Ă����B
�@�������玟�̂悤�ȓ������w�E�o���悤�B��P�́C�攭���̃��f���̑��݁i�o�ϑS�̂̐��x��V�X�e���̓����C�X�̎��Ƃ�Z�p�̖͕�j�ł���C��Q�́C�o�ώ�̂̐l�דI�n�o�i�u���W���A�W�[�̌��@�Ɗ����̑䓪�j�ł���C���̑��ɍ����s��̑��ΓI�s���ƊC�O�s��ˑ��C���X����������B�������C�H�Ɖ��̏����ɍ��ꂽ�Ԑ���x�́C���̌㒷���������ɂȂ邱�ƂɂȂ邩��C��i�����f���̓�����Ƃ��Ă��C�����ɂ́C�㔭�����L�̓���������ꂽ�B�Ⴆ�C��s�C�d�H�ƁC�S�|�C�S���C�C�^�Ȃǂ̋ߑ�I�ȏ��Y�ƂƉ�Ќ`�Ԃ̓������Ȗa�т��琻���ƂƂ������y�H�Ƃɂ܂ōL���y�̂ł���B�܂��C������Ќ`�ԂȂǂ̐��x���������ꂽ�B�X�̎Y�Ƃł͊C�O����̋Z�p������ہC�A�W�A�Ŋ������Ă����Ƃ�Z�p�ҁE�E�l���ٗp������C�C�O�ɗL�\�Ȑl����h��������C�C�O������Ƃ����ق����肵�āC�����ɂƂ߂��B�܂��o�ώ�̖̂��ł́C���Ǝ��{������̑��݁C�A�o�Y�ƈ琬�̂��߂̎Y�Ɛ���
�y8
�Łz
�Ȃǂ��l������B�����̖��́C���ӎ��Ɏ��グ���Ă����B
�@�������Ȃ���C�}���ȍH�Ɖ��Ƒ��l�Ȏ��Ƃ���ĂɃX�^�[�g������̒��ŁC���������ł͂Ȃ��C���{�S���ɂ������Ɖƃl�b�g���[�N���r�W�l�X�`�����X��O�Ɂu���p���v���u�������̂ł���B�����ł̑��p���́C��ɁC�V���������W�J�������p���Ƃ͈قȂ�C���݂ɋZ�p�I�Ȋ֘A�̂��鑽�p���Ƃ������́C�}���Ȑ����ɂ��r�W�l�X�`�����X�̋}���ȓW�J�ɔ������p���ł���C���ԂƂ��Ă͍����̑��p���Ɠ������e�ł������B���̂Q�̌o�ώ�̂́C����܂łɎw�E����Ă������̂́C���҂̊W�́C�\���ɂ͖��炩�ɂ���Ă��Ȃ������B�Ⴆ�C���p���Ƃ����Ă��C�O���O�H�Ȃǂ̍����̑��p���́C���Ƃ��ӎ��������Ƃł���C�����s��͂��Ƃ��C�O�s��܂ł�����ɓ��ꂽ�����ł������B�������C�n��ɍ���������ƉƂ̂Ƃ������p���́C�����I�Ȑ���̒��Ő��i�������߂ɁC������Ќ`�Ԃ��Ƃ�C�����o���Ƃ����`���Ƃ��čs��ꂽ�B�܂��C�ނ�̖ڎw���������͈̔͂́C���ɔނ炪�������Ă����n��ɍ����������̂ł������B�O�҂̍����ɂ��ẮC����܂ő����̌����͒~�ς���Ă������C��҂̊�ƉƂ���̂Ƃ��������ł́C�܂Ƃ܂����������w�ǂȂ������B�������C�Ȗa�сC�����ƁC�n����s�C�d�͎Y�ƂȂǂ̂悤�ɌX�̋Ǝ�Ƃ����t���[�����[�N�̒��Ŏ��グ��ꂽ���ʁC�ނ��ƉƂ��ւ�������Ƃ̑S�̂𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��o���Ȃ������ƌ����悤�B
�@�����ŁC�n��ɍ����������l�ɑ�\������ƉƂ��C�n��o�ς̔��W��ړI�Ƃ��āC�ߑ�I�Ȏ��ƂɊւ���Ă������Ԃ𖾂炩�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����𖾂炩�ɂ���ɂ͑�Q�̎��_���s���ł���B��P�̎��_�́C�㔭���ɋ��ʂɌ�������̂ł��邪�C��Q�̎��_�́C���ꂼ��̌㔭���ňقȂ���̂ł���B����́C�K�[�V�F���N�����Ȃǂ̌������ʂ�������ł́C�K�v�Ȗ���T�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���{�ŗL�̉��l���O�C�s���K�̖͂����l���Ă������B�������C����܂łɂ����{�ŗL�̉��l���O�ɂ��Ă̌����C����ƌ��т������͂��s���Ă����B�ȉ��C�ȒP�ɐG��Ă������B
�@���{�o�c�́C���邢�͓��{�̊�ƉƂ̉��l���O�ɂ��ẮC�q���V���}�C���[�C�R���F�̌������v���o����邪�C���t�J�f�B�I�E�n�[�� �w�_�����{�x 10�j���܂������ĎQ�Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ƃ����̂��C���{��Ƃ̊����́C�K�������l�܂��̓O���[�v�̎���I�Ȉӎv����ɂ���ĂȂ�����ł͂Ȃ�����ł���B���{�l���������ɐV�������Ƃɒ��肷��C�ނ����藧�Ă��͈͂�̉��������̂��낤���B���v���F�߂���Ƃ��C���������҂��Ċւ�����Ƃ��������C��������́u�O���v�C�ނ炪��炵�Ă���n��C�ނ炪�������Ă���W�c����̈��͂ɂ���āC�u���͓I�v�Ɋւ�����悤�Ɏv����B���͓I�Ɋւ�����Ƃ͌����C�ւ��ȏ�C�����Ŕނ炪�閳���́u���ҁv�ɂ���āC���s�͋�����Ȃ������B�����ł́C���������W�c�܂��āC���̏W�c�ɑ�����l�ɂ܂ł��y�ڂ��́C�l�̍s�������S������Љ�I�ȗ͂��l�@����K�v�����邩��ł���B
�@�{�e�ł́C���̒�����C���{�l�ŗL�̍s���K�͂ݏo���O�I�Ȉ��͂Ɋւ�镔�����������p���邱�ƂƂ������B�Ƃ����̂��C��ɋL���u�������ҁv�ݏo���Љ�I�ȊO���͂��Ă��邩��ł���B���t�J�f�B�I�E�n�[���́C�l�̍s����̂���K�����Ă�������ɂ��ċ�̓I�ɘ_���Ă���B
�u�s���������������鑤�ɂ��Č����C���ʐl�͎O��ނ̊O���������Ă���B�܂��ォ��̈����ŁC�����Ώ㒷�̈ӎu�ɂ��ꍇ�Ȃǂł���B���̎��͂���̈����ŁC
�y9
�Łz
����͒��Ԃ⓯���ɋ��ʂ���ӎu���炭��ꍇ�ł���B������̈����ł����āC���̖ډ��̂��̂̈�ʊ���ɂ���đ�\�����̂ł���B�����Ă��̍Ō�̋����͂Ȃ��Ȃ������ĕ��肪�������̂Ȃ̂ł���B
�@����̈����|���Ђɂ���đ�\����Ă���|�́C�l������ɒ�R����ȂǂƂ������Ƃ́C�Ƃ��Ă��l�����Ȃ��B�܂�㒷�͎����C�K�����Ȃ킿�����̔��ɑ����̗͂��\�������̂�����ł���B�����̐���ł́C������l�̌l����̌����̂ɐn�������Ȃǂ́C�ƂĂ��ł��Ȃ����Ƃł���B�s���ɑR���邽�߂ɂ́C�\���Ȏx���Ȃ���Ȃ�Ȃ����C�����Ȃ�Όl�̒�R�������l�̍s����\���Ă͂��Ȃ��̂ł���B
�@����̈����|�n��Љ�̋����ł���|�ɑ����R�́C���̐g�̔j�ŁC���Ȃ킿���g�����̎Љ�S�̂̈���ƂȂ��Ă��錠���̑r�����Ӗ����邱�ƂɂȂ�B
�@��O��̈����́C�ډ��̋��ʊ���ɋ����Ă�����̂ł��邪�C���̈����ւ̒�R�́C���̎��̎����ŁC�قƂ�Lj�̌��ʂ��䂫�N�������ƂɂȂ�B�|�ꎞ�I�ȋꂵ�݂����߂邱�Ƃ���͂��܂��āC�����܂��������������Ƃɂ����Ȃ�̂ł���B
�@��O��̈����́C������`���Ƃ��Ă���Љ�̂Ȃ��ŁC������x�݂͂ȍs���Ă���̂ł���B�������C���{�̎Љ�ł́C��X���ł����X���Ɠ`���I�Ȋ���̂��߂ɁC�����̈��͂̌�����͂͂��̂��������̂ł���B�v11�j
���̂悤�ȊO���ɂ���āC�n���̎��Y�Ƃ́u�������ҁv��w���킳��Ă����̂ł���B�����ŁC���������u�������ҁv��w���킳�ꂽ���Y�Ƃ́C��́C�ǂ̂悤�ȍs����������̂ł��낤���B��������Ă��������B
�R�D��Ɖƃl�b�g���[�N�̊���͉��������̂�
��s��A���@�ցC�Ȗa�юY�Ƃɑ�\�����悤�ɁC���{�S���ő����̃l�b�g���[�N���֗^�����Y�Ɣ��W���ǂ��l����ׂ����Ƃ�����肪�c���ꂽ�B���ꂼ��n��o�ς̔��W��ڎw���ċ����ŋ�s���ʂȂǂ̃C���t���Y�ƁC�Ȗa�т���Y�ƂȂǂ̎�v�ȎY�Ƃ̐ݗ��Ɋւ��C���Ɖ^�c���s���Ă����l�b�g���[�N�̊������C��ɏq�ׂ��Q�̎��_����ǂ̂悤�ɍl���邩�Ƃ������Ƃł���B
�@��̓I�ɋL���Ă������B�@���Ǝ哱�C�����哱�Ői�߂�ꂽ���Ƃ́C�l�b�g���[�N�̊����ɉ��炩�̉e����^�����̂��낤���B�A��i�����f���̓����́C�l�b�g���[�N�̃��x���łǂ̂悤�ȓ�����^�����̂��낤���B�B��ĂɍH�Ɖ����J�n�����Ƃ����㔭�����L�̓����̓l�b�g���[�N�̊����ɂ����āC�ǂ̂悤�ȓ�����t�^�����̂��낤���B�C�C�O�f�ՂŎ�v�ȓ������s�����������Ёi���Ёj�́C�l�b�g���[�N�̊����ɂǂ̂悤�ȉe����^�����̂��낤���C�Ƃ��������l����K�v�����낤�B
�@�ȏォ��C�@�̍��Ǝ哱�Ƃ������ʂ���́C������s�̑n�݂ƒn��̊֗^���������悤���C�A�̐�i�����f���̓����́C�����Ƃł��a�ыƂł����ꂼ��t�����X��C�^���A�C���邢�̓C�M���X����̋@�B�E�Z�p�̓����ƂƂ��ɁC�Z�p�҂̏��ق��s��ꂽ�B������А��x�̓���������ɉ�����ׂ��ł��낤�B��ĂɍH�Ɖ����J�n�������ʁC�r�W�l�X�`�����X���ꋓ�ɊJ�Ԃ����̂ł���B����f���āC�����ł͑��p�����i�݁C�n���̊�ƉƂł͗l�X�Ȏ��ƂɊ֗^����
�y10
�Łz
���Ԃ����炩�ɂȂ����B�ߑ�I�ȉ�Аݗ��ɔ����������B�ɉ����đ����̊�ƂɊ֗^�����n���̊�ƉƒB�́C������А��x�ɂ���čL���O�����玑���B���������ł͂Ȃ��C�����o���Ƃ����`�Ԃɂ���đ���̎��Ƃւ̎Q�������������B�������̓��{�S���̕x�E���Y�̕����́C�{���Ԃɂ�����i���͔�r�I�������������̂́C�Ǝ�Ԃł̈Ⴂ�͌����ł������B���D���C�������������������≮��M���ɁC�����Ƃ���Ղɏ]�����Ă������l�B�͕x�̒~�ς�i�߂čs�����B���������n����ɁC���ꂼ��̒n��ł́C�L�͂ȏ��l�B���n��Љ��̊��҂�w�����āC�ߑ�I�Ȏ��Ƃ�A���������Ȃǂ̃C���t���Y�Ƃ̐�����i�߂Ă������̂ł���B
�@����31�N���珺�a11�N�Ɏ���܂ŁC���{�S���ɑ��݂��Ă����l�b�g���[�N�Ƃ����ʼnc�܂���Ɗ������l����ɓ������āC�l�b�g���[�N�ɓo�ꂷ���Ж�����˂����������u���l���O�v�́C��́C�ǂ̂悤�Ȃ��̂������̂��낤���B��������C�K�[�V�F���N�������w�E�����悤�ɁC�㔭���ł͊�ƎҐ��_�̌`�����s�\���ŁC�������͂��ߍ���������ʂ��Ă����Ƃ���C�l�b�g���[�N������Ċ������Ă����l���̍s�����ǂ�����������ǂ��̂ł��낤���C�Ƃ������ł���B��ƎҐ��_�ł͐����o���Ȃ��C���{�ŗL�́u���O�v����p���Ă����̂ł��낤���B������ɂ���C���{�S���ŁC�����ɘj���Ċ�Ɗ��������܂ꂽ�ꗬ�ɂ���C���{�I�ȁu��ƎҐ��_�v�ɂ��āC�l�@���Ȃ�������Ȃ��ł��낤�B
�@��X�����͂����őI������ �w���{�S������Ж����^�x �Ə�����Ă���Ƃ���C��Ж�����ΏۂƂ������߂ɁC�{�����������̕��͂ł���Ƃ������ʂ�������������Ă����B�������C����܂łɔ��\���������̒��ŋL�����Ƃ���C�������珺�a��O���܂ŁC����������ł���������C�����̂�����̊�ł��銔��̑��ʂ��w�E���Ă����K�v������B����Ƃ��Ă̋@�\���l�@�������B
�@��ɋL�����C�����Q���E�R�b�J�̃h�C�c�̎����[���X�E�����B�����{���C�G�̃t�����X�̎���ł́C��Ђ̑n���ł͂Ȃ��āC�n����̉�Ђ�O���ɒu���āC����Ɩ����c�ތo�c�w�̔C���𒆐S�ɁC��������Ɛт̊Ď��Ȃǂ̋Ɩ����w�E���Ă���B���������́C�n�����ɂ�����劔��Ƃ��ċ@�\�ł���B��Ђ̐ݗ��ɓ������āC�@�I�Ȏ葱���ł���N�Ɩژ_�����̔��s�⊔�����s�C���呍��̏���������s�̌���C�X�ɂ͒芼�̍쐬�C�����ɍۂ��Ă̐V���БI�тȂǁC��Ƃ̐ݗ��Ɋւ�鏔���́C�ɖ��c�q�[���̌����ɂ��L����Ă���B�������C�H��̗��n���n�߁C���@�B�̔����C�������B��Z�p�҂̗̍p�ȂǁC�����I�Ȑ����ɂ��ẮC�\���Ɍ��y����Ă��Ȃ������B�劔��Ƃ��Ẳ�Ж����C�ݗ����N�l�Ƃ��Ă̑劔��́C�������B��@�I�Ȗ��Ƃ͕ʂɁC�H�ꌚ�݂̍ۂɁC�ǂ̂悤�Ȗ������ʂ������̂��낤���B����𖾂炩�ɂ��Ă��������B
�@���m���m�������ɂ������Ɖƃl�b�g���[�N�����グ�āC�n��Ƃ̊W�����Ă������B����31�N�ɂ����鈤�m���m���S���c���ɋ��_��u������Ɖƃl�b�g���[�N�̒�����C���I�O�Y���֗^�������̂𒊏o����ƂQ����B��́C���I�����ƒ��W�����q��C�c�������ƒm���a�сC�ێO�����C�i���j���c�č����i�������������Ȃ���̂ŁC���̈�́C���W�����q��ƁC�ێO�����C����������Ђ���Ȃ�B��������́C���W�ƂƐ[���W��������B�܂��C���c�������_�Ƃ����}�g���b�N�X���쐬����ƁC�\�T�̂悤�ɂȂ�B�������番����悤�ɁC���̎��{�����猩��ƒm���a�т�100���~�C�ێO������60���~���ۗ����Ă���B�ߑ�I�ȉ�Ђł���a�ыƂƃr�[���Y�Ƃł̎��{�����傫���C�n��ɂ����ẮC�ݗ��̎Y�Ƃ������Ȃǂ̌��̎��{����10���~����30���~�ł���������C�ߑ�I�Ȏ��Ƃ�i�߂�ɂ́C���z�̋N�Ǝ������K�v�ł������B
�y11 �Łz
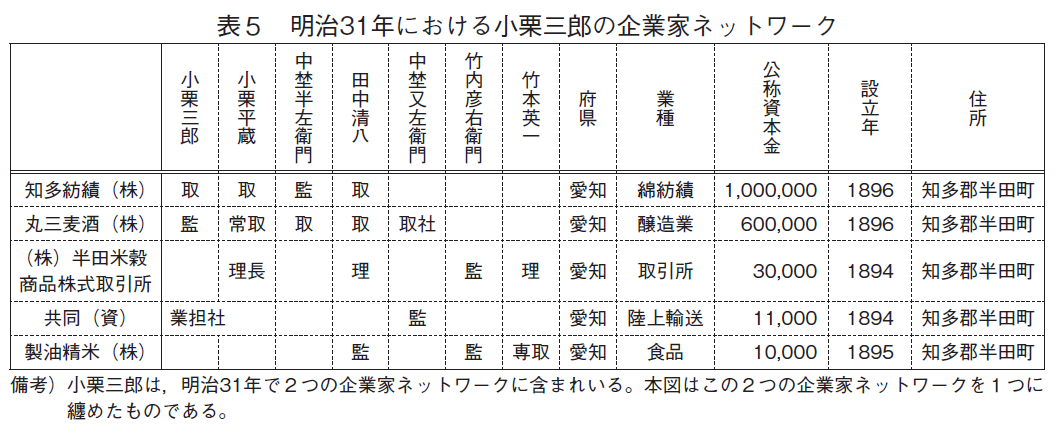
���ꂾ���ł͂Ȃ��B�ߑ�I�Ȏ��Ƃ�i�߂�ɓ������ẮC�Z�p��Ǘ��C�̔���J���C���n�⌴������ȂǁC�l�X�Ȗ����������Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł���B�P�Ɋ���Ƃ��ĐV���Ƃɏo�����邾���ł͂Ȃ��C����Ɠ����ɖ����Ƃ��ĉ�Ђ̐ݗ����玖�Ƃ̊J�n�Ɏ���܂ŁC�ǂ̂悤�Ȋ������s�����������Ă������B�����ŁC���쑾�� �w�{�M���N�a�юj�x 12�j�C�������E�䉜���F�Ғ� �w�ߑ���{�̒n�����ƉƁ|�ݎO���X���I�Ƃƒn��̍H�Ɖ��|�x 13�j���肪����ɁC����ł�������ł����������I�y���Y�C���I�O�Y�̍s����ǂ��Ă݂悤�B
�@�m���a�т́C1886�i����29�j�N�W��16���C�m���S���c���ɑn�����ꂽ�B������В��͏��I�y���Y�ŁC������ɂ͏��I�O�Y�C���I�����C�c�������C���I�����q��C���W�������C�܂��č����ɂ͒|�������C���I�����Y�C���W�����q�傪�C���ꂼ��A�C�����B���m���̒m�������ɂ������ƉƂ͂����C�������E�䉜���F�Ғ��ł́C���I�O�Y�Ƃ����グ�C�T��S�ł̋T���s�ւ̊ւ��C�m���S�ł̒m���a�т̐ݗ����瑀�ƂɎ���܂ŏڍׂȕ��͂��Ȃ���Ă���̂ŁC������Q�l�ɂ��đ劔��C��Ɣ��N�l�̉ʂ��������������Ă������B���I�O�Y�́C�T���s�̐ݗ��Ɋւ��ẮC����ł͂��������̖̂����ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�܂��T���s���ݗ�������́C���Ǝ����̒��B�Ƃ��ċT���s��ϋɓI�ɗ��p���Ă����B���̈Ӗ��ŁC�T���s�̐ݗ��ɐϋɓI�Ȗ������ʂ��������I�y���Y�Ƃ͋����������āC�n��ւ̍v���Ƃ������ʂ�������̎��Ǝ����̒��B�Ƃ��āC���p�҂Ƃ��Ċւ���Ă����̂ł���B����C�m���a�т͈Ⴄ�B
�@�u���I�O�Y�͔��N�l�ƂȂ�C���ɒm���a�тɑ��ẮC�A���������ɒʂ��ƂƂ��ɁC��v����Ƃ��Đݗ����Ɏ�����ƂȂ����B�v14�j �H��̗��n�Ɋւ��Ắu�H�w���m�̒J�����������Ĉӌ��v15�j���C�u�ŏI�I�ɁC�m���a�щ�Џd���̂Ȃ��ŏ��I�y���Y�E���I�����E���I�O�Y���N���ɏ㋞���āC�d�v�Č������߂Ă����v16�j�Ƃ����B�܂��C�a�щ�Ђ��J�Ƃ�����́C�u�������̈ړ]������s�̌��ȂǁC�d�v�ȈČ����������ۂɂ͖a�ю������֏o�����Ă����v17�j�Ƃ����B�܂�
�y12
�Łz
�m���a�т��O�d�a�тɍ��������ۂɂ��C���Ȃ��炸�~���ɐi�߂邽�߂̓w�͂�s�������̂ł���B
�@�������甭�N�l�Ƃ��āC���I�O�Y���s���������������ł����B�����Ŏ��Ɏ��ۂ̌o�c�Ǘ��C�����̖����l���Ă������B��ƑS�̂��������Ă������o�c�҂Ƃ͈���āC�a�ы@�B�̒m����ߑ�I�ȘJ���Ǘ���g�ɂ��Ă����Ƃ͌����Ȃ��劔��́C���������S�����Ƃ͂Ȃ��C���̐l���������Ĉς˂Ă����̂ł���B��������Ă������B�m���a�т̎�����S���Ă����̂́C�[�R�����q��ł������B�В��̏��I�y���Y�́C�u�ˋC�����̐V�l���W�ƂŁv����C�u���É��ɏ��I��s��ݗ����e�n�Ɏx�X��݂��C��p�ɓ��m���Ɖ�Ђ�݂����É��ŊJ�������I���X�����Ĉ��̔������߂��B��s����ׂߓe�p���Z���݂̎��C�q�C�Ƃ��c�ݓ��I�푈�̎��ɂ͌�p�D����đ傢�ɗ��v���鏊���������B���ꂪ�ׂߎ��Ƃ��g�������ɍ��x�͎��s�ɏI��v18�j
��C���I��s�͔j�Y���邱�ƂƂȂ����B�������C�m���a�тł��C���I�y���Y�́C�u�d����̎��ł��疺�����I��������㗝�v19�j�ɏo�Ȃ����Ă����B����C�ꖱ�̒[�R�����q��́C�В��̏��I�y���Y�Ƃ͑ΏƓI�Ȑl���ł������B�u�В��͕S�ݒ��Ґꖱ�͐��n���@���C�В��͋��h�̐V�l�ꖱ�͖͌؊����C�В��͗���ǂАꖱ�͎{�^���D�ށv20�j�ƌ�������ł������B
�@������̏��I�O�Y�ɂ��ẮC���쑾��̖{�ł͏ڍׂ�������Ȃ��̂ŁC��ɒ����E�䉜���ɂ���āC���炩�ɂ��Ă��������B���̑O�ɁC�m���a�т̌o�c��S�����l���Ƃ��̓������L���Ă����K�v������B�m���a�т̍H�ꌚ�݂ɓ������ẮC�v�Ɛ��t�̊ēɂ́C�u�������ʂ̑��̏��a�ѓ��l������a�ѕ����r�ꎁ���ږ�Ƃ��ĔV�ɓ��������v21�j���C���ڂ̊ē҂͏����ߕF�ƍ��؏C��ł������B�����ߕF���̎��Ƃ́C�O��̔��B�ˎm����ƂŁC�{�Ə����Ƃ͓��˂̌�a��Ƃ����ƕ��ł������B�����ߕF���g�͑��O�H�ƍ��Z���o�Ă��珬���ؐ�ȕz��ЂɋΖ����Ă����Ƃ���C�m���a�тɐ����ē��Ђ����̂ł���B�����o�g�҂ł������B�܂��C���؏C�ꎁ�͎O�d�a�я����爤�m�a�я��Ɍ��K���ɍs���C��ɖ��É��a�щ�ЂɋΖ�������C�m���a�тɈڂ����C���n�Ŋw�l�ł���B�����C���ؗ����͒����ւŊēɓ��������B�������C���҂̒��͗ǂ��Ȃ������B�u���؎��͑S�R���n�Ƃŏ������͋��炠���҂ɉ߂��Ȃ������B���̒����ւ̗��ēҊԂɂ͏�Ɉӌ��̑��Ⴊ�N����Ղ������B��������Ɋē҂Ȃ��肵�ׂ߁C���C�͎��R�₦�Ȃ������v22�j�Ƃ����B
�@����C�̔��ɂ����Ă����c�o�g�̐l���������Đi�߂Ă����B�u�̔��͎x�z�l��ϓБ��Y���w���̉��Ɏ�C���ؕF���Y���V��ɓ��������v23�j�B���؎��͍����o�̔��c�l�ł���C��ώ��͌c��`�m�𑲋Ƃ������c�l�ł������B
�@�������玟�̎����킩��B�m���S���c���ɐݗ����ꂽ�m���a�тɂ́C�n���o�g�̋Z�p�ҁC���������O���H�o�g�Ƃ����w����L�����l���������Ă��邱�Ƃł���B�܂��C���ۂɖa�эH��Ōo����ςl�����ē҂Ƃ��ď����Ă������Ƃ��d�v�ł���B�������C�̔��ɓ������Ă��c��`�m�C�����o�̔��c�o�g�̐l���̗p���Ă����̂ł���B�������C������㐧�Ő��Y���Ă����W�ŁC�ē҂͂Q�l�K�v�ł��������C���̓�l�̔w�i�͑S���قȂ��Ă������߂ɁC�a瀂�
�y13
�Łz
�����Ă����B���̏�C�g�D�̏�ő傫�Ȗ��́C�����̊ē҂��Ǘ����ׂ��l�������Ȃ��������Ƃł���B����͌�ɘ_����_�Əd�Ȃ邪�C�ߑ�I�ȊǗ��g�D�̕K�v���C�d�v�����\���ɗ������Ă��Ȃ��������ʂł��낤�B
�@���̂悤�Ȏ��Ԃ́C���{�����Ō���ꂽ��ł͂Ȃ��B�O���S���[�E�N���[�N�́C�A�����J�C�C�M���X�C���{�C�C���h�̘J�����Y���̔�r�������C�J�����Y���̑���́C�J���K���̖�肩�琶�܂ꂽ�ƌ��_�Â��Ă���24�j�B�Ⴆ�C�C���h�ł́C�Ȗa�эH��̒��ŁC�H�����Ƃ�����C�U����Ԃ�V��A��ė���҂��������B�X�ɂЂǂ���Ƃ��āC�u�T�^�I�ȘJ���҂́C�����̐e�ʂɈ͂܂�ē����C���́C�X�ɂ͈ߕ���������C�������z������C�Ђ���������C�Q����H�������Ă����v25�j�Ƃ����B����ɑ��āC�C�M���X�ł͘J���҂ւ̊Ǘ��͌������C�x���ɂ͌�����������Ă����B���{�B�F�́C �w�x���̒a���x �̒��ŁC���N�������߂́u�˒@���v�Ƃ����E�Ƃ����������Ƃ��Љ�Ă���26�j�B
�@�����āC�J���Ǘ��C�i���Ǘ��C���Y�Ǘ��C�����Ǘ��C�l���Ǘ��ȂǁC�ߑ�I�ȍH��̉^�c�ɕs���ȊǗ��̐����s�\���ł������B���ꂪ�C�i���C���Y�C�����ɉe����^���C���Ȃ��炸��Ǝ��v�̍��ݏo���Ă������Ǝv����B�����ŁC�o�c�Ǘ��̖��ɐG��Ă��������B
�S�D�ߑ�I�H��̐ݗ��ƌo�c�Ǘ��̖��
�����̍H�ꌻ��ɐG��Ȃ���C�J���Ǘ��̎��Ԃ��m�F���Ă������B �w�x�m�a�ь\�N�j�x �ɂ��ƁC�n�Ɠ����̍H��͎��̂悤�Ȃ��̂ł������B�x�m�a�т́C����31�N�̏H�ɑ��Ƃ��J�n�������̂́C�J�Ɠ�������Ɛт͕s�U�ł������B����́C�u�n�������ɂ�����x�m�a�щ�Ђ̏d���̊�G�́C���Â�����E���B�X���閼�m���Ђł��������������x�c�������͂��߁C��Ђ̓��ǂɂ́C�a�ю��Ƃ̌o�c�ɁC���n�̌o����L������Ƃ͖w���
�@����C����19�N�ɑn�����ꂽ�����ؐ�ȕz��Ђ́C�u�m���̏��@�ŁC�ЋƂ͂������������炸�C�H����C���͌��ꓹ�f�C�����̗��ʂ͑��āv29�j�C40���~���̕�����Ɏ������B���̂��߁C�X���s���q��͓������z�a�щ�Ђ̌o�c�ɑS�g�S�������Ă�������J�����q��ɏ����ؐ�ȕz��Ђ̐��������������̂ł���B������������u����J���̊�ɉf�������Ђ̕a���́C���ɍH����ɂ킾���܂閞�X�̑ċC�ł������B�j�H�͉Δ����H����Ɏ�������ʼn���
�y14
�Łz
���z�ЁC���H�͏���ɋ@�B���~�߁C�H�����⥂�~���ĐH�������Ă����B�ʘH�ɂ͗��Ȃ�����U�����āC���̓��ނƂ�����Ȃ��B��Ƃ̐l�l�́C�˒I�̂Ȃ��ɕz�c��~���ĐQ���݁C�q�ɌW�͑q�ɂ̂Ȃ��œq���ɒ^���Ă��v30�j��悤�ȏ��ł������B
�@���̌��ʁC�x�m�a�тł́C�ꐎ������̐��Y���́C���А��D�ɔ�ׂ�20�������Ȃ��C�����ؐ�ȕz�ł́C���Y�̔\�����オ�炸�C�a�o���ꂽ���̎��������C�ɂ͓V��ɂ܂ŒB������ł������B���������������悤�ɁC�C�M���X���̋@�B�����Ă��C�H����̐��Y�Ǘ��C�i���Ǘ��C�J���Ǘ��Ƃ��������ʂł́C�ߑ�I�ȍH��̑̂��Ȃ��Ă͂��Ȃ������̂ł���B�ԍG �w���{�J���Ǘ��j�����x �ł��C �w�x�m�a�ь\�N�j�x ���𗘗p���Ȃ���C���l�̖����w�E���Ă���31�j�B�ߑ�I�ȍH��Ǘ��̖�肪�N���[�Y�A�b�v�����ׂ����Ȃł���B
�@�Ǘ��̖��́C���Y�ʂ�i���̍�����ł͂Ȃ������ɂ��e����^���C���v�̊i���ݏo�����ƂɂȂ����B���̓_�����Ă������B����20�N�U���Ɉ��m���M�c���őn�����ꂽ�����a�т̎В��͉��c�����ł������B�땺�E�q���X�{�P����������ɏA�C����ȂǁC�����a�т͂܂��ɉ��c���������[�_�[�Ƃ����Ɖƃl�b�g���[�N�̑�\�i�ł������B�X�ɁC���c�a�я��ł��������m�a�т̏����ł��������c�ߍ��������ď����x�z�l�Ƃ��C�H���x�z�l�ɂ͕����r�ꂪ�A�C�����B�������C���c�������g�̌o�c���j�́C��Ǝ��v�̌���ɂ͔�������̂ł������B���̈����w�E���Ă������B�u�č�������������㓡�����Y�����C�\�ĉ��c�������ɒ���������������B�����a�т��O�l�\���~�̐ϗ�����L���Ȃ���������Ȃ��������Ȏ�����ւ�䂯�̏�����p���ʂ̂͋����łȂ����ƁC�O�d�a�тׂ̖��������ׂĔV������ӂׂ����߂��B�R��ɉ��c���͍H�ƉƂ̐����Ƃ��Ċ댯�ނ��̂łȂ��C�����ɉc�Ƃ������H�Ƃ̐i���Ɉ˂ė��v���ׂ��ł���C���@�Ŗׂ���Ȃlj��������Ə̂��E������˂����v32�j�̂ł���B���̂��ߗ��v�ɂƂ��đ傫�ȗv���ł���R�X�g�팸���s�\���ŁC���v�ɂ��\�ꂽ�B
�@����܂Ř_���Ă������Ƃ��番���鎖�́C���{�S���ɐ��܂ꂽ�a�щ�Ђ́C���ꂼ��̒n��̎��Y�Ƃ����S�ƂȂ��Ċ���ƂȂ��ĉ�Аݗ��ɍv�����ďo�������Ƃł���B���̏�C������e�n����Z�p�҂�o���ҁC���ɂ��̒n��o�g�҂̋Z�p�҂⍂�w���̎҂������āC���Ƃ��n�߂��̂ł���B�Ƃ��낪�C��Ŏw�E�����悤�ɁC�S���I�ȋ����ɂ��炳���ɏ]���āC�i����Y���̍��������āC���ꂪ�̔����i�ɔ��f���Ă������B�����Ă܂��C�J���Ǘ��̕s�O���R�X�g�팸�̓w�͂��s�\���Ȃ��߂ɁC���v�̒ቺ���������ƂɂȂ����B�H��Ǘ��̖��̏d�v�����Ċm�F����K�v�����낤�B���̌��ʁC�Ȑ��i�̎s�ꂪ�S���I�Ɋg�傷��ɂ�āC�����͌������āC����̓˂��グ�������č����ւ̓����I�����ꂽ�Ƃ����悤�B
�@���̌��ʁC�o�c�Ǘ��̖�肪�d�v�ȉۑ�ƂȂ�C�w���҂̐��o�c�҂����߂���悤�ɂȂ����B�X��p�����̐����C���o�c�҂̐��e�́C���������o�c�Ǘ��̖��܂��Ę_���邱�Ƃ��K�v�ł��낤�B
�y15 �Łz
�T�D�n���̊�Ɖƃl�b�g���[�N�ɂ����钆�S�l���̍s���K��
���{�S���Ő�������Ɖƃl�b�g���[�N�C���ɁC�a��h�����c�P���Y�C��쑍��Y�̂悤�ɓ��{�S���Ŋ�����Ɖƃl�b�g���[�N�ȂǂƂ͈���āC���ꂼ��̒n��Ŋ��Ă����l���̓��@�ɂ��čl���Ă��������B�ނ�́C��s���ʁC�G�l���M�[�C�X�ɂ͋ߑ�I�Ȗa�ю��ƂȂǁC���ꂼ��̒n��̃C���t���Y�ƂƂ��������Ƃ̐ݗ��Ɋ֗^���Ă������B�������������ɑ���ނ�̓��@�́C��́C���ł������̂��낤���C�Ƃ������ł���B���{�S���Ő�������Ɩu���u�[���ɑ��āC�ϋɓI�Ɋ�ƎҐ��_�����C�֘A���鎖�Ƃ̐ݗ����哱�����Ƃ͎v���Ȃ��B
�@���̓_�Ɋւ��ẮC��ɋL�������t�J�f�B�I�E�n�[���Ƃ͕ʂɁC�R���F�E�q���V���}�C���[�̌��������炩�ɂ��Ă���B������ �w�o�c�j�w�x �ɔ��\�����_�����肪����ɂ��čl���Ă��������B�u�]�ˎ���̉��l�̌n�ƃr�W�l�X�|�������̍H�Ɖ��Ƃ̊֘A�ɂ����ā|�v33�j�́C���{�l�̉��l���C�����I�E�����I�E���ԓI�Ƃ����R�̑��ʂ���l�@���C�@�\�I�ȁu�������ҁv�̗ϗ��Ƃ������ׂ��C���{�l���x�z�����ϗ��K�͂�������悤�Ƃ������̂ł���B
�@����ɂ��ƁC�]�ˎ���ɂ́C�u�K����W�c�̋@�\�̍��ق��āC���������ꂽ���l�ƋK�͂Ƃ��C�l��W�c�̈ӎ��ɓ��ʉ�����Ă����v�Ƃ����B�Љ�S�̂��C�ォ��l�X�ȏ���l�⏬�W�c�Ƃ����d�g�݂�ʂ��āC�������l���O�������I�ɐZ�������Ă���������ł���B����䂦�C�u�O�I�ȕ��a�Ɠ��I�Ȓ��a�̈ێ����ō��̎Љ�ڕW�Ƃ���v���̂ł���B���������Љ�ł́C���Έӌ��͂��Ƃ��C�C���ӌ��ł����Ă��C�g���������Ȃ��悤�ɁC�S��������ƋC�Â��悤�ɂ��肰�Ȃ��\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���������Љ�œ����͂̌��ł��鉿�l�̌n�́C�S�̎�ނ��������Ƃ����B��P�̉��l�́C�u�����I�ȏ���̉��l�v�ł���B����ɂ́C�m�_�H���ɂ��K���ɂ���āC���ׂĂ̐l�͕����ł���l����ے肵�C�㉺�̊K�����ɂ���Ċ�b�Â��Ă��������łȂ��C�V�������{���ˁi����j���ꑰ���i���邢�͏��l�̏ꍇ�͊����ԁj���Ɓ��l�Ƃ����悤�Ɍl�[�Ɉʒu�Â��鉿�l�̌n�ł������B��Q�̉��l�́C�u�����I�ȏW�c�I�g�D�̉��l�v�ł���B�]�ˎ���C�ܐl�g���n�ߗl�X�ȏW�c��ʂ����x�z���s���C�l�̍s���K�͂ɂ��傫�ȉe����^�����B�Ⴆ�C�u�W�c�I�K���ւ̕��]�͍����]������C�l�̋`���͏W�c�̋K���ɕ��]����ƂƂ��ɁC�W�c�ɉh�_�������炷���Ƃł������v�Ƃ����B�Ɨ������l�̗��g�o���́C�u�W�c�u���I�ȉ��l�̌n�v�ɑ������������Ă����B��R�̉��l�́C�u���Ԃ̘A�����̉��l�v�ł���C�ꑰ�����c��𐒔q���C�ƎY�̈ێ���ڎw�����Ƃł���B�����ł́C�o�c�I�����̂Ƃ��ẲƂɌ�����悤�ɁC�ƎY�̈ێ��E�g���ڎw�����̂ŁC���̂��ߌ������w�͂ƕ��]���v�����ꂽ�B��������C���������@�\�I�ȁu�Ɓv���d�����ꂽ�̂ł���B��S�̉��l�́C�u�@�\�I�������҂̗ϗ��v�ł���B�]�ˎ���C�u�l�̋K�͂́C�����̐S�̓��������C�O������̕]���Ɉˑ��v���Ă���C�l�̕]���ɓ������ẮC�l�̓��@��Ӑ}�����ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��C�u�����ς炻�̖����ƊO������݂����ʂ̂݁v����]�����ꂽ�B���̖������҂ɔw�����ꍇ�C���l�́u�p�v��������̂ł���B�p�Ƃ́C�O������^����ꂽ�������҂ɉ������Ȃ������ꍇ�ɐ����銴��ł���C�l�̍s����ϗ��K�͂ł���
�y16
�Łz
��34�j�B
�@���̌��ʁC���������O�����̉��l�ς�������炳�ꂽ�ϗ��́C�����ɂ��C�u���{�l�̎O������human nexus�Ɋ�Â��ϗ��́C �w�p�̗ϗ��x �Ƃ��̂��꓾�邪�C�ނ���C �w�������҂̗ϗ��x �Ƃ�Ԃق����ӂ��킵���悤�Ɏv����v�ƌ��_����B�����C���{�l�̍s���̍���ɂ������R�����̉��l�ς́C�u�������҂̗ϗ��v�Ƃ��ċK������悤�ɂȂ����ƌ����B�]���āC�u�������҂̗ϗ��v�́C���{�l���K�肵�Ă����K�����ׂĂ��܂�ł������Ƃɒ��ӂ��Ȃ�������Ȃ��B
�@���̍s���K�͂��n��Љ�ɂ܂ŋy�сC�܂��C�n����ł̏���C�Ɗi�⏊���Ȃǂɉ���������C�l��ƋƂ����n��o�ς�D�悷�邱�Ƃ����߂��鈳�͂Ȃǂ��l���鎞�C�n��̎��Y�ƁC���ɂ͖��]�Ƃƌ���ꂽ�l���́C���������u�������ҁv��w�����Ȃ���C�ߑ�I�Ȏ��Ƃɒ��肵���̂ł͂Ȃ��낤���B
������
�ȏ�̕��͂܂��āC�`���Ɍf��������N����{�o�c�j�����̒��Ɉʒu�Â��āC�܂Ƃ߂Ă��������B�P�[�X�X�^�f�B�Ƃ����������@���Ƃ�o�c�j�ɂ����ẮC�ΏۂƂ��鎖�Ⴊ����Ȃ��̂Ȃ̂��C����Ƃ��L�͂Ɍ�������̂Ȃ̂����l����K�v������B�܂��C���̎��Ⴊ���{�ŗL�̂��̂��ۂ��Ƃ����_�����l�ł���B���̂��߂ɂ́C��i���O���ł̎���C�������ʂ݂̂Ȃ炸�A�W�A�⒆��ĂȂnjo�ϔ��W�̌㔭���ł̎�����l���ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������Ȃ���C����܂œ��{�o�c�j�̌����ł́C�����������E�I�Ȏ��삩��_����p���ɂ�⌇���Ă����ƌ��킴������Ȃ��B�����������_���猤����i�߂邱�Ƃɂ���āC����܂łƂ͈�������۔�r���\�ƂȂ낤�B������ɂ���C��ʉ��ւ̓������߂邱�Ƃ��s���ł���B
�@�{�e�ł́C��Ɖƃl�b�g���[�N�̑��݂Ɠ������C���{�S���Ō���ꂽ�Ƃ�����ԓI�ȕ��Ր��C����31�N���珺�a11�N�܂Ō���ꂽ�Ƃ������ԓI�p�����C�X�ɂ́C�����̉�Ж������߂Ă���Ƃ��������̓h�C�c��t�����X�ł�����ꂽ�Ƃ������ʐ��ɂ��āC���炩�ɂ����B����C�h�C�c�C�t�����X�C���{�Ō���ꂽ���C�����Ƃ������Ԃ̕��͂����߂��悤�B����̉ۑ�Ƃ������B
�@���{�o�c�j�����ɂ́C�����Ȃ鎞���ł���C�ǂ̂悤�ȑΏۂł���C���{���u���ꂽ�������N�_�Ƃ��ĕ��͂���K�v�����낤�B�����łȂ��ƁC�����I�i�A���W�b�q�j�ɁC���ۂ������L�q���邾���̂��̂ŏI����Ă��܂��B��Ƃ�o�c�ҁC�X�ɂ͓o�ꂷ���̂̍��������C�ނ炪���ʂɎ����Ă��鉿�l���O��������o���Ȃ���C�ꍑ�̌o�c�j�����Ƃ͌����Ȃ��ł��낤�B����܂ŁC�u���{�I�o�c�v�ɑ�\�����悤�ɁC���{�o�c�j�̌����ł́C�u���{�I�v�Ɗ����ē��{�ŗL�̉��l�ρC�s���l���C��ƌ`�ԂȂǂ̌������i�߂��Ă����B���������������ʂɊ�Â��āC����܂ł̍����j��������ʂ̎Y�ƁC��ƕ��͂Ɏ���܂ŁC�čl����K�v�����낤�B���̍ہC�u���{�I�v�Ƃ����������q�ϓI�ɖ��炩�ɂ��Ă����̂́C�O���̌����҂ł��������Ƃɒ��ӂ��ׂ��ł���B�{�e�ŋL�����C���t�J�f�B�I�E�n�[���C���C�V�����[�C���[�X�E�x�l�f�B
�y17
�Łz
�N�g�C�ŋ߂ł́C�h�[�A�C�A�x�O�����Ȃǂł���B����͋��R�ł͂Ȃ��B�ނ�ɂ́C���{�̌������n�߂�O�Ɋ��Ɏ����̌�����ʂ��āC���{�𗝉��������o���Ă��邩��ł��낤�B����䂦�C�ǂ������{�I�Ȃ̂��C�ǂ������قȕ���Ȃ̂��𖾂炩�ɂ������Ǝv����B�Ⴆ�C�M���V�����܂�̕�e�������C������M���V���Ő��܂ꂽ���t�J�f�B�I�E�n�[���́C �w�_�����{�x �̒��ŁC���{�̐_�b���M���V���_�b�Ɣ�r���Ă���B�u�_���̏ꍇ�C�Â��M���V�A�̐M�Ɠ��l�ŁC���ʂ��Ƃ͒��l�I�͂������ƂɂȂ��Ă���|�܂蒴���R�I���@�ōK������������C�s�K��^�����肷��͂����悤�ɂȂ�̂ł���v35�j�Ƃ��C���҂̎x�z��_����B�������āC���{�Љ�̑O�ߑ�I�ȓ������L���Ă���B�u���͂��̍��̎Љ��Ԃ͂��܂��ɁC�L���X�g�ȑO�����I�O�̃M���V�A��e���̎Љ�̏�ԂɎ��ʂ����i�K�ɂ���̂ł���B�Ȃ�قǓS���C�d�M�C���I�ȋߑ�I����C�܂��������ނ̋ߑ�I�Ȋw�͓�������Ă͂��邯��ǂ��C���͂��܂��Ɏ����̍��{�I�����̕ϊv�Ƃ����Ƃ���܂łɂ͋y��ł��Ȃ��B�\�ʓI����́C�}���ɐi��ł���B�V�����@�\�͂ǂ��ǂ������Ă���B���������̎Љ�I����C�새�[���b�p�ŃL���X�g�������������͂邩�ȑO�̏�ԂɂЂǂ��ގ����Ă���܂܂ł���v36�j�ƒf�����Ă���B�����ł���C�\�ʓI�Ȑ��ʁC�o�ϓI�ȒB�������ł͂Ȃ��C���̍���ɂ�����{�I���l���O�C�s���K�͂𖾂炩�ɂ���K�v�����낤�B�����āC����Ɋւ�点�āC�u���{�I�v�Ɩ��t�����镪��i�ޕK�v�����낤�B
�@�{�e�ł́C�ォ��C������C������̂Ƃ����R�̈��͂�ʂ��Ĕ�������u�������ҁv����v�ȍs���K�͂ł���Ƃ��C���́u�������ҁv�ɂ��n��ւ̌o�ϊ������u��Ɖƃl�b�g���[�N�v�𗝉������ł̎w�j�Ƃ��Ă����B����C���������C���{�I���l���O�C�s���K�͂܂������{�o�c�j�������[�����邱�Ƃ𖧂��Ɋ���Ă���B