�y105�Łz
�u�K�v����u���K�v�ւ̈ڍs
���r�a�j���̒�����f�ނƂ���
�e��@�@��
���������v�̐��i���邢�͓���J����������̎����Ƃ��������{�𒆐S�Ƃ�����������C������u�K�v�J���҂̑����w�i�Ƃ��āu�K�v����u���K�v�ւ̈ڍs���邢�͓]�����d�v�ۑ�ƂȂ��Ă���B�u�K�v�Ƃ����p��́C���܂�ɑ��푽�l�Ȍٗp�`�Ԃ��܂�̂ŁC�p����ׂ��łȂ��ƕM�҂͎咣���Ă����i�e�� 2011�j�B���Ƃ��p�[�g�Ɣh���ł͊�Ƃɂ����đS���قȂ�@�\�������C�J���҂̔N��w���قȂ�B�������Ȃ���C�����̌������u�K�v���g�p���Ă���̂ŁC���ꂼ��C�ǂ̘J���҂���ɑΏۂɂ��Ă��邩�ɗ��ӂ��Ȃ���C���̘_�_���@�艺�������B��Ƃ��Ď��グ�钘��́C���r�a�j�i2016�j�C�u�K�J���v���l����i���É���w�o�ʼn�j�ł���B���r���̘_�_�ɂ͋Z�\��OJT�iOn-the-Job Training�j�Ɋւ�����̂������܂܂�Ă��邩��ł���B
�@�O�J�i2019�j�́C��i���ɂ����鐳�K�ւ̓]���Ɋւ���O���̌��������r���[���Ă���B�܂�PIACC �f�[�^�iSurvey of Adult Skills�j�������������۔�r�����Ă���B����ɂ��ƁC�䂪���̓����́C����҂Ə����Ɂu�K�v�������i�����́C��N�ƒ�w���j�B�����ł�OECD�́u�K�v�̒�`�́C�u�L���ٗp�{�h���v�ƂȂ��Ă���i�č��͔h���݂̂̃f�[�^�j�B���I�v�l�͂Ɗ�Ɠ��P����u���ɂ�����C���K�ƔK�̊i�����݂�Ɓi�}�P�C�}�Q�j�C�䂪���͊�Ɠ��P����u���̊i�����傫�����ɑ�����B��҂̎w�W�͂���肪����̂����i�e��2019�j�C�t�H�[�}����OJT �Ŋi�������邱�Ƃ͋M�d�Ȕ����ł���B�Ƃ��낪���I�v�l�͂ł͍��͂قƂ�ǂȂ��B�����ɂ������Ă݂�ƁC�K�̂ق����������炢�ł���i�}�R�C�}�S�j�B�䂦�ɔ�����Ă���i���݁j�\�͂́C�K�ł����Ȃ荂���̂ɁC�K�ɑ���E��ł̔\�͊J���@��R�������Ƃ����K�]���������Ă���C�Ɛ��������B�킪���ŋZ�\��OJT�̎��p����C���̖����l���邱�Ƃ��d�v�ł���B
�@����ł͏��r�i2016�j�ɉ����`�ŁC���̘_�_���@�艺�������B
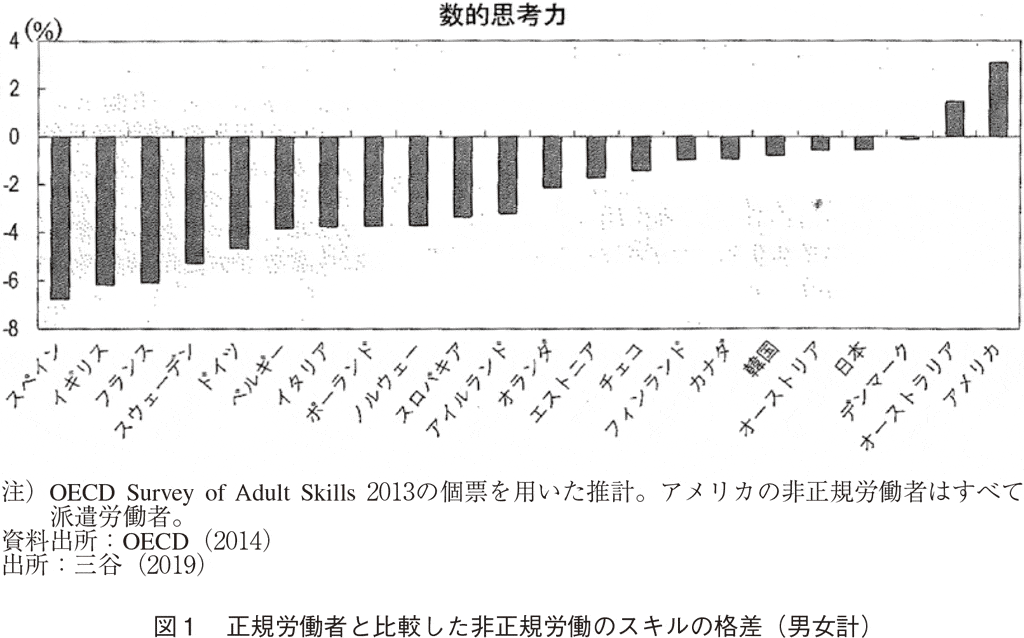

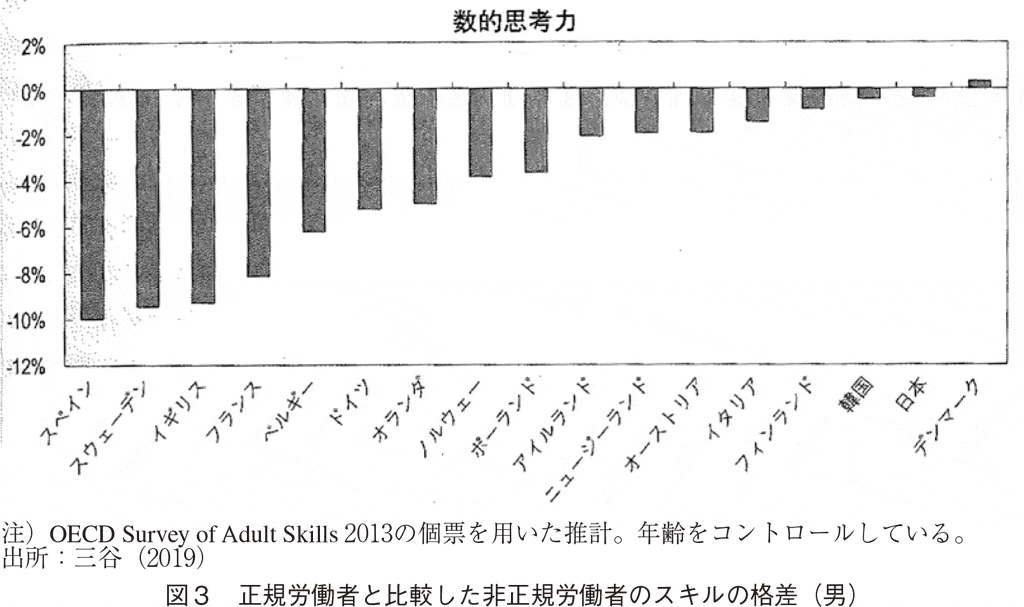
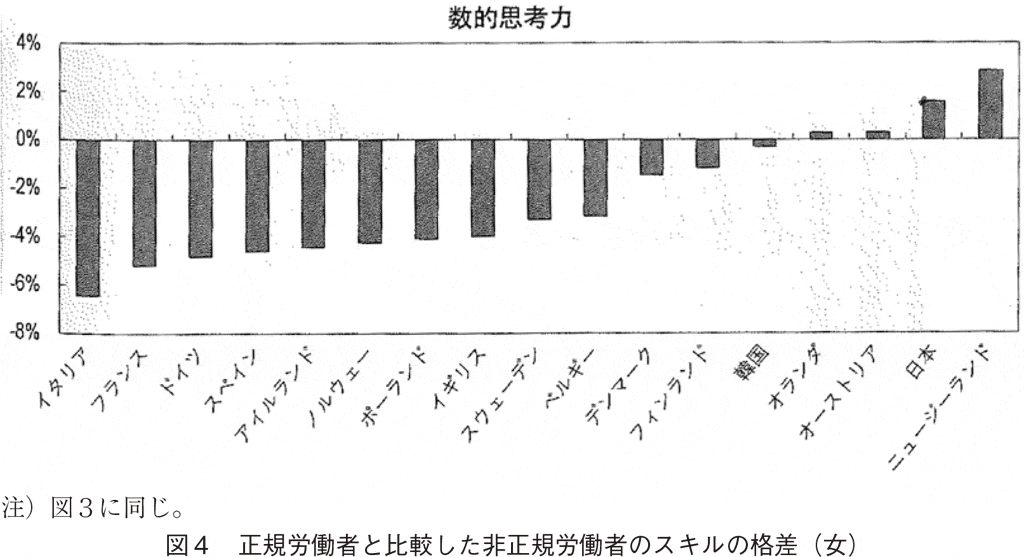
�P�@���r�ɂ�錻��F���i���_�j�̍��i
���r�i2016�j�ł́C��Ƃ��K�������i�R�X�g�j�ŗ��p���Ă���Ƃ����C���̋@�\�֍��{�I�^��������Ă���B���̗��R�͒P���ŁC�������K�Ƃقړ��l�Ȏd�������Ȃ��̂ł���C�y108�Łz��Ƃ͂��ׂāu�K�v�ɕς���悢�C���ƂɂȂ�B������100���ǂ��납���������Q�|�R���̊�Ƃ������B�ǂ̊�Ƃł������x�C�u���K�v�Ј������݂���Ƃ������Ƃ́C���̋c�_�����������ƂɂȂ�B
�P�D�P�@���r�̋c�_�ւ̃R�����g
���ʂ̌o�ϗ��_
���̋c�_�́C���ʂ̌o�ϗ��_�̑n�n�҂ł���Gary Becker �ɂ�����Ό������ɑ���ᔻ�Ƒ��ʂ���B�Ό������ł́C���Ƃ����l�E���l���ƁC�o�c�҂͍��l�ɕΌ��������Ă���Ƃ������̂ł���i�����E�j���Ȃ珗���ɑ��āj�B�܂�C�������l�Ɣ��l�������J�������Ă��āC�o�c�҂��Ό��������Ă����Ƃ���ƁC�Ό��������Ă��Ȃ��o�c�҂̂����Ƃ������ŏ����ƂɂȂ�B���̋c�_�Ə��r�i2016�j�̋c�_�͑��ʂ��Ă���B
�@�䂦�Ɍ����̍��ʂ̌��ۂ��������ɂ́C�Z�\�̎��_��u���̔�Ώ̐��v�̎��_�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B��������u���v�I���ʁv�̋c�_�C�܂�C�X�L������ݔ\�͂ɕ��z������C�ǂ̍��l���D�G�ŁC�ǂ̍��l�������łȂ����ʂł��Ȃ��B���l���l�ʂɎ��ʂł����C���ς��Ĕ��l���D�G�ł���Ɓu���v�v�ɂ���̂ŁC���̌��ʁC�u���ʁv�I���ۂ�������Ƃ������̂ł���B������u�K�v�ɂ��Ă͂߂�C�l�X�Ȑ��ݔ\�͂����u�K�v�̂����C���ꂪ�D�G�����ʂł��Ȃ����ߐ����邱�ƂɂȂ�i�������C���r�i2016�j�ł͓��v�I���ʂ̋c�_�͂Ȃ���Ă��Ȃ��j�B
�@���̋c�_�͂��������ƁC�u���̔�Ώ̐��v�̍l���������Ȃ��Ă���t���I�ȓ`���I�o�ϗ��_�ʼn��߂ł��Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B����͒�����p�Ƃ����T�O�����C�u���Ј��̎d����Ј��̎d���Ɉڂ����ԁv�Ƃ��u���Ј������فi�ސE�s��[�j����̂ɕK�v�Ȕ�p�⎞�Ԃ�������v�Ƃ����c�_�ł���B������g���X�L�����g��Ȃ��Ƃ������ł���B�����������c�_�̓T�^���C�䂪���͍��ۓI�ɂ����Ƃ����Ј������ق��Â炢�Ƃ����@�I������������߂ɁC�u�K�v�����p�����Ƃ���c�_�ł���B�����܂ł��Ȃ��C�ꕔ�́i�J���j�K���ɘa�_�҂̋c�_�ł���B�������C��b�ƂȂ��Ă���F���͐������Ȃ��COECD �̌ٗp�ی�w���̍��۔�r�ɂ����ق̂��₷�����݂�ƁC�䂪����OECD �����̐^���炢�ŁC�䂪�������ق��ɂ������̓t�����X�͂��ߑ������݂���B�������C�����Ƃ����ق��₷���͕̂č��ł���B
�@������ɂ���u�K�v�͂��߁C��Ɠ��ɕ����̌ٗp�敪�����݂�������������т��Đ�������̂͗e�Ղł͂Ȃ��B�M�҂��C���ăR�[�X�ʐl�����x�̑��݁C�܂肢����u�����E�v�Ɓu��ʐE�v�̋敪�ɂ��Ă���Ȃ�ɘ_�������i�e�� 1996, 1997�j�C���S�ɖ������Ă���킯�ł͂Ȃ��B
�@�Ȃ��C���ė��s�����}���N�X��`�I���f�_�́C�J���҂ǂ����̒c���������Ȃ����߂ɁC�敪�i���ʁj�����ق�����ƂɂƂ��ēs�����悢�C�Ƃ����c�_�ł���B����ɂ��Ă��C���̂��������Ȃ���Ɓi���Ƃ��ΑS���C������ŕ����Ȃǁj�Ƃǂ��炪���v�������邩���l����ƊȒP�ł͂Ȃ��C�����͂���c�_�Ƃ͂����Ȃ��B��͂�E��Ō`�������X�L���C���������Ƃ��Ă�OJT �̋c�_������Ȃ��ƌ������������B
�l����R�ɂ�銈�p
���r�����C����Ӗ��C��̂Ă�������@�\�ɂ��Ă����C�e���ƒ�������C��Ƃ̃p�[�g�ٗp���R�ɂ����āC�u�l����̊����i���j�v���������Ƃ̑������ǂ��݂邩�ł���B�����̒����ŁC���ꂪ��P�ʂɂȂ�B���Ƃ���JILPT2010�N�����u���l�ȏA�ƌ`�ԂɊւ�����Ԓ����v�y109�Łz�̌��ʂ��݂�ƒf�R�g�b�v�ɂȂ�B
�@�u�����E�L���p�[�g�v�̊��p���R
�@�J���R�X�g�̐ߌ��̂��߁@53.6���i�����Ƃ��������R�@31.5���j
�@�u�L���Ј��v�̊��p���R
�@�J���R�X�g�̐ߌ��̂��߁@36.3���i�����Ƃ��������R�@19.5���j
�@�����ł́u�L���Ј��v�̒�`�̓t���^�C���ł���B
�@���̎������C�ǂ��Ƃ炦�邩�C�ł���B�o�c�҂��邢�͐l���S���҂ɂ���ϓI�H���Ⴂ�Ƃ��Ė������邱�Ƃ́C��͂�ł��Ȃ��ł��낤�B�M�҂́C���ăp�[�g�^�C�}�[�ɂ��āC�u�o�b�t�@�[�@�\�v�Ɓu �i���Ј��j��@�\�v����ʂ��C��҂͊�p�[�g���S���Ă��邱�Ƃ��c�_�����i�e�� 1998�j�B
�@�ȒP�ȃp�[�g�����j���݂�ƁC�����b�i1989�j�ɂ��u��p�[�g�v�̔�������C�e��i1998�j�ɂ��u��ցv�Ɓu�o�b�t�@�[�v�@�\�̂��ƁC�{�c�i2007�j�ɂ��u���I����v�Ɓu�ʓI����v�̋c�_�Ɍ����͂Ȃ����Ă������B�{�c�̗ʓI����ɂ��ẮC�[�����Â炢�Ƃ�������邪�C�ꕔ�̃p�[�g�����ł͂Ȃ��C���Ƃ������ɂ͕K�v��������Ȃ��B�M�҂ɂ��u �i���Ј��j��@�\�v�́C�p�[�g�ɏ\����OJT �̋@�����X�L�����㏸����C���Ј��ɂƂ��Ă�����Ă����Ƃ����V�i���I�ł���B�����C��������S�ɗ��_�I�Ȑ����ɂȂ��Ă��邩�ǂ����͎��M���Ȃ��B
�l�ޑI�ʋ@�\
���r�i2016�j�́C�u������ɂ���ցv�@�\��ᔻ���Ă���̂ŁC�c��́u�ٗp�����@�\�v���u�l�ޑI�ʋ@�\�v�ƂȂ�B�����ł́C�Ƃ��Ƀt���^�C���_��Ј��i���ԍH�j�̐l�ޑI�ʋ@�\�ɐ����͂���c�_���W�J����Ă���B��̓I�ɂ͎����łӂ��B���������r���͌ٗp�����i�o�b�t�@�[�j�@�\�ɑ���������ϋɓI�ɂ���ĂȂ��悤�ɂ݂���B�����܂ł��Ȃ����ԍH���ٗp�����̋@�\��L���Ă��邱�Ƃ́C���Y�ʂ̑����ɉ����Đl�����ϓ����邱�Ƃ��疾�炩�ł���B�����Ă����C���̂��Ƃ�O��Ƃ��āu�K�i���ԍH�j�v�́u�l�ޑI�ʋ@�\�v�����L���邱�Ƃ��_�����Ă���̂�������Ȃ��B
���̐߂̍ŏ��ɏq�ׂ��悤�ɁC�u�K�v�̂ǂ̌ٗp�`�Ԃ̂��̂�O���ɂ������ŁC�����Ԃ�c�_������Ă���̂ŁC���R�̂��Ƃ����^�C�v�ɕ�����ׂ��ł���B������ӎ����Ă��C���r�i2016�j�ł́C���̂Q�̃^�C�v�̋c�_���Ȃ���Ă���B�u�K�v�������炭�J�����Ԃ̒��Z�ɂ��C�����Ă���B
�i�`�j�u�_��Ј��v�u���ԍH�i�h���j�v
�i�a�j������u�p�[�g�v�u�A���o�C�g�v
�i�`�j���玩���ԎY�ƃu���[�J���[�̊��ԍH�C�i�a�j����R���r�j�i�X�[�p�[�j�ɂ�����p�[�g�E�A���o�C�g���Ꭶ����Ă���B�����ł́C�ق��̘_�҂̋c�_�Ɣ�r���Ę_���Ă݂����B
�Q�@��r�_���ɂ݂������ԋƊE�ƃR���r�j�ƊE�ɂ�����J���̒ʐ��C���[�W
���̍��ł́C�����ԎY�Ƃ̃u���[�J���[�ƃR���r�j�i�X�[�p�[�j�̘J���ɂ��āC�����C���[�W�I�ɘ_���Ă݂����B
���c�d�̐��E
�܂������ԎY�Ƃ̃u���[�J���[�ƌ����C���Ă͂�������̂ŁC�w�����Ԑ�]�H��\����G�ߍH�̓��L�x�i����j�o�ʼn�C1973�N�j�Ƃ����x�X�g�Z���[������B����͊��c�d�Ƃ����W���[�i���X�g���g���^�����Ԃ̍H��ɋG�ߍH�Ƃ��Đ������āC�������������������ɌJ��Ԃ��P���J���ł���������`�������̂ł���B����͋G�ߍH�̘J���Ƃ��Ă����������C�E��̓������`����Ă���B�����C�]�����Ă̂́C�E��̂��Ƃ����ƒ��J�ɏ�����Ă��āC�����ԍH��Ƃ����̂͑�ςȂ��Ƃ��킩�����B����܂ł͍����n�̊w�҂Ȃǂ����낢�뒲�ׂč�悪�s���Ă���ƌ����Ă��C�E�ꎩ�̂ɂ��Ă��܂肫����Ə�����Ă��Ȃ������B������C���������W���[�i���X�g���������Ă�����������ŏo���オ�����̂���̎����ԃu���[�J���[�̃C���[�W�ł���B
�F�̐��E
���ɁC�O�b���w�����̌F���ɂ��C�u�J���͒P�����_�v�ł���B�F�͂ǂ�ǂ�J���͂͒P�������Ă����̂��Ƃ������Ƃ��c�_���ꂽ�l�ł���B�����Ԃ̗�������������Ă������C���̂Ƃ��ɂ��傤�ǃW���u�E���[�e�[�V�����̋c�_���œ_�ƂȂ��Ă����B���{�̓u���[�J���[�ł����Ă����낢��Ȏd�������Ȃ��Ă���Ă��邩��C�P�������Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����c�_���������B���̂Ƃ��ɌF�́C�W���u�E���[�e�[�V�����������Ƃ��Ă��C���̎d���͔��ɒP���ȘJ���ł����Ȃ��C�P�Ɋ�Ƃɓs�����ǂ��ړ��������Ă��邾�����Ƃ����_�w��ꂽ�B�F�͏��r���Ɓu�J���͒P�����_���v�������Ȃ��C���̂Ƃ��͏��r�����C������u�m�I�n���v�T�O���܂��o��O�ł��������C���OJT �̃��R�C�܂蕝�̂���X�L���̗D�ʐ����c�_���ꂽ�B�����猩��Δ��ɗǂ��_���������Ǝv���Ă��邪�C�K���������ׂĂ����ݍ����Ă��Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
���r�a�j�̐��E
���r���̎����Ԃ̃u���[�J���[�J���҂̐��E�Ƃ����̂́C2005�N�̋��ȏ��̂Ȃ��ɒ[�I�ɂ�����Ă���i���r 2015�j�B���̂���Ƀg���^�����Ԃ𑊓����J�ɒ�������āC�����Ԃ̃u���[�J���[�̋Z�\���P�C�Q�C�R�C�S�ƂS�̃��x���ɕ����Ă���B���x���P�͊��ԍH������d���ŁC�P�̎d����x�ꂸ�ɍ�Ƃł���Ƃ����ӂ��ɑ������Ă���B���x���S�Ƃ����͎̂����Ԃ̃u���[�J���[�ł���Ȃ���p�C���b�g�`�[���ɎQ�����C���i�v�ɂ������ł���悤�Ȑl�����ł���B�u���[�J���[�J���҂̃X�L�����S�ɕ������Ă���̂����r���̐��E�ł���B���x���P�͊��ԍH�ŁC���Ј��̓��x���Q��������ă��x���R�C���x���S�Ƃ����`�ŋZ�\�����߂Ă����B�Z�\�̌���̂��߂ɂ́C���ւ̍L����C��قnj������W���u�E���[�e�[�V�����ɂ�肢�낢��Ȏd�������Ă������Ƃ��K�v�ł���B����Ɓu�m�I�n���v�C����������Z�\�́u�[���v�ŁC
�ω��ƈُ킪�������Ƃ��ɂ�����ƑΉ��ł���Ƃ������Ƃ��_����ꂽ�B���ꂪ�C�O�ł͂Ȃ��Ȃ��ł��Ă��炸�C���{�̐����Ƃ̃u���[�J���[�̋��݂ł͂Ȃ����ƌ���ꂽ�B
�@�y111�Łz
�@���̎�����[�I�ɕ\�����̂��u�d���\�v�̂Ȃ��ɂ���1�j�B���r�i2016�j�ɂ����Ă����Ȃ�̃y�[�W��������Ďd���\�ɂ��Ę_���Ă���B��Ђɂ���Ė��͈̂Ⴄ���C�p��Ō�����skill map�i���邢��skill matrice�j�ł���B����͈ꖇ�̎d���\�ɁC�\���ɂ͎����������C�\���ɂ��낢��Ȏd���C�Ⴆ�v���X�H��ł���v���X�H��̂��낢��Ȏd�������邩��C�}�g���b�N�X��������\�ɂ���B�Z���̒��Ɋۂ������C�ۂ��S�ɕ����āC�ł���Ƃ��C�w���ł���Ƃ������`�Ŋۂ�h��Ԃ��Ă����Ƃ����̂��d���\�ł���i�\�P�Q�Ɓj�B���r�i2016�j�̍Ō�̒�Ăɂ��邪�C�ꖇ�̎d���\�̒��ɁC���K�̘J���҂����łȂ��C�K�C���̏ꍇ�͎����Ԃł��邩��C��������ԍH�ł��邪�C���ԍH��������悢�C���邢�͍ŋߑ����Ă���h���������邱�Ƃ̏d�v��������B
�@�����ҍH��ł͔h����Ђ���h������Ă���J���҂��ĊO�����C���������b��M�҂����������Ƃ�����B�܂��M�҂́C�g���^�֘A�̍H���2014�N����ɉ���āC���܂��d���\��ڂɂ����Ƃ��ɁC���l���̖��O�ɂ��āC���ԍH���h�����܂܂�Ă��邩�������B���Ȃ�̃P�[�X�Ŕh���̐l�����ԍH�̐l�������Ă������B���̗��R���ƁC�u����͓�����O�ł���C�����łȂ��Ǝd�������Ȃ��v�Ƃ��������������B������C�K���������Ј��������d���\�̎����ɓ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B���r���̒�Ă��G�ł͂Ȃ��B���r�i2016�j�ɂ������������������Ă��Ę_�����Ă���B���ꂪ���r���́C�`�^�C�v�̔K�J���҂́C�K���琳�K�֕ς��_�_�ł���B���ꂪ�����ԃu���[�J���[�̗�ł���B
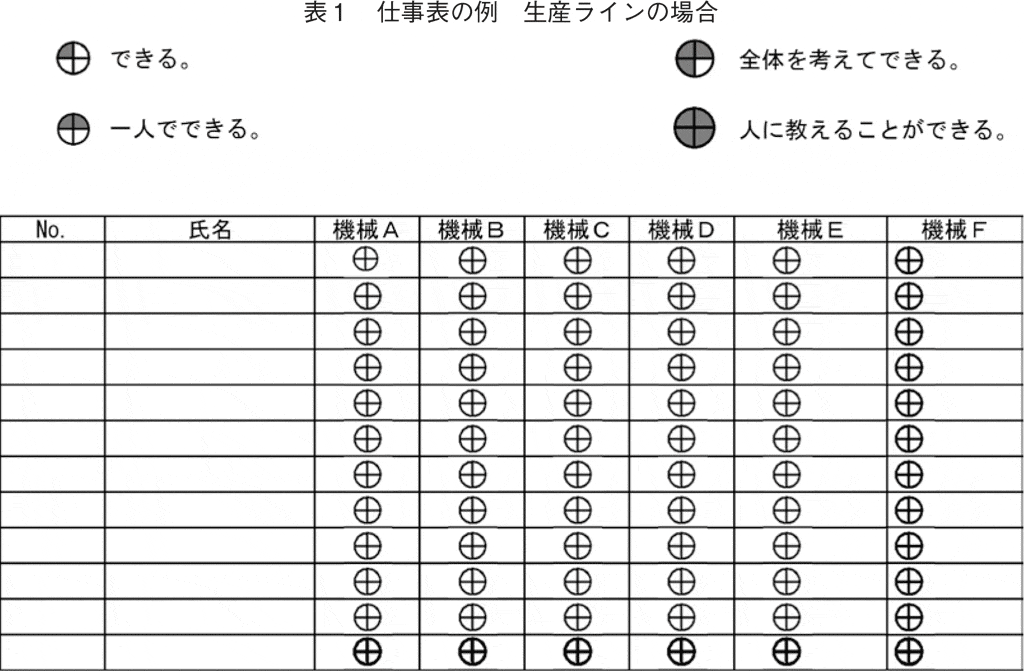
���Ɂi�a�j�̃R���r�j�ɂ��Ă݂悤�B
�y112�Łz
���c���덁�̐��E
�H���܍�w�R���r�j�l�ԁx�́C���w�Ƃ��Ă͕]���̕�����鏬�����Ǝv�����C�M�҂̓R���r�j�̎d�����e�̂Ƃ���ɋ������������B��҂̑��c���덁�Ƃ����l�́C���ۂɂ����ƍ��ł��R���r�j�̃A���o�C�g�Ƃ��ē����Ă���悤�ł���B�u�R���r�j���Ȃ肽�����Ă���`�C���X�ɕK�v�Ȃ��ƁC����炪���̒��ɗ��ꍞ��ł���v�ƁB�R���r�j�X���Ƃ��Đ���ȕ��i�ɂȂ�邱�Ƃ����̈�Ԃ̗��z�ł���C�Ə����Ă���B�d�����e������ƁC�������Ɉ��������[������C�A�C�X�̔z���������C�V���i�̕��ו��C�����C�����������Ƃ�����Ƃ������Ƃ�������Ă���B���̎�l���͏����̒��ŁC�x�e�����ł���C�V�l�ɕ��ו�����������C�����̎d���Ȃǂ��C�Ⴂ�A���o�C�g�ɂ��������肵�Ă���B�T�S���`�T���Ζ��͂��ꂪ�����ɂƂ��Ă��傤�ǂ悢�ƁB�����C�q���̂悤�Ȓj��������āC�����҂�}�{�������ƌ��ӂ����Ƃ��ɂ͏T�U���`�V���S�������Ƃ����`�œW�J����Ă���B
�@���̍�i��ǂƂ��f���Ȋ��z�́C�����b�̊�p�[�g�̋ɒv�ł���Ǝv�����B�M�҂̎��I�ȑ̌�������C�R���r�j�̃A���o�C�g�͂��ɑ����̂��Ƃ����Ȃ��Ă���C�ŋ��̎x��������g�������o�����Ƃ܂ŁC��ۂ悭���Ȃ��B�������S���̃A���o�C�g�������܂ł��Ȃ��Ă���킯�ł͂Ȃ����낤���C���Ȃ荂�x�ɂ݂����Ƃ��s���Ă���B������x�g�i���o�g�̃A���o�C�g�ł����Ă��C�S�����Ȃ��B
�u���b�N��ƁC�u���b�N�o�C�g�̐��E
���ɏЉ��̂́C�u�u���b�N�o�C�g�v�Ƃ��u�u���b�N��Ɓv�Ƃ����p����͂�点���l�ł���C����i����́j�ƌ����l�̐��E�ł���B����i2016�j�w�u���b�N�o�C�g�x�̒��ŃR���r�j�̂��Ƃ��o�Ă���Ƃ��낪����C�u�P�����E�莮���E�}�j���A�����v�ip.97�j�̓������̂��̂��Ƙ_���Ă���B�Ƃɂ����S�̂𗬂��g�[���́C���c�d��F���������g�[���Ɠ����ł���B
�@�킸�����������甼�N�Ԃ̌��C�ŁC�I�[�i�[�͓X�܉^�c���s���B�c�̔����鏤�i�͂��ׂĖ{�����J�����C���i������B�c�u�����C�R���s���[�^�[�ɔ������鏤�i�C���C���t���Ȃǂ���͂���悢�v�c�I�[�i�[�X���ւ̃q�A�����O����H�v��v����̂́u���̓��̏����ɂ����������v�����ٓ��₨�ɂ���ȂǁC�ۑ��̂����Ȃ����i�ɑ�����̂ŁC���̓��̓V�C��j�����l�����C�ߗׂōÂ����s���Ȃǂ��`�F�b�N���āu�o���ɂ��������čs���v�c���ꂳ�����I�[�i�[�ɕK�{�́u���x�ȘJ���v�Ƃ͌�����C�Ƃ����B�u���ۂɋΑ��̒����u��w�p�[�g�v�Ɉꕔ�C����Ă��鎖����m�F�ł����B�����炭�C�X���̍ő�̐E���͎���̘J���ł͂Ȃ��C�A���o�C�g���[�����C���߂Ȃ��悤�ɊǗ����邱�Ƃł��낤�v�ipp.98-99�j
�@���̖{���ǂ��̂́C��������ꂽ�߂�����C�R���r�j�ł܂��I�[�i�[���ǂ̂悤�Ȏd���C�X�܉^�c�����Ă��邩��������Ă���B�R���s���[�^�[�ɔ������鏤�i�C���C���t�Ȃǂ��������͂�������悢�̂��ƁC���ɒP���J���ŁC�X���̂���d������ςł͂Ȃ��B�H�v��v����̂́C���̓��̏����ɍ����������C�ٓ��₨�ɂ����ۑ��̂����Ȃ����i�ɑ�����́i����͏��r�������ɒ��ڂ����Ƃ���ł��邪�j�C���̓��̓V�C��j�����l�����C�`�F�b�N
���āC�o���ɏ]���Ĕ����ʂ�ς��Ă������肵�Ă����B
�@�������C���̘J�����������쎁�͍��x�ȘJ���Ƃ͌����Ȃ��Ƃ����B���x�ȘJ���Ƃ͌����Ȃ����R���C���ۂɋΑ��̒�����w�p�[�g�Ɉꕔ�C����Ă��邱�Ƃł���B�Ƃ炦���̖��ł��邪�C��قnj������悤�Ɂu�R���r�j�l�ԁv�̏����̒��ɏo�Ă���A���o�C�g��������肵�Ă���Ƃ������ƂŁC�X���̍ő�̐E���̓A���o�C�g���[�����C���߂Ȃ��悤�ɊǗ����邱�Ƃ����y113�Łz�����B�R���r�j�̐��E�̒��ł��C�X���ƃA���o�C�g��p�[�g�͊��S�ɐ�Ă��邪�C���̗��R�͑S�̂Ƃ��ĒP�������ꂽ�J���ł���Ƃ����悤�Ș_���ɂȂ��Ă���B
�@�����[���̂́C�����ƂƂ̔�r���Ȃ���Ă���i100-102�Łj�B�u�ꕔ�̒P���H���͕ʂɂ��āC���{�̐����Ƃ́C�命���̘J���҂�K�ٗp���S�ɒu�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������v�Ə�����Ă���B�u���G�Ȏd���ƒP���Ȏd���ɘJ�����C���Ƃ��@�B�Ƀg���u�����N�������ꍇ�ɂ́C�K�ٗp�͂��������̑Ώ����ւ�����B�v����͂���Ӗ��������킯�����C���ԍH�́C�@�B�Ƀg���u�����N�����Ƃ��ɂ͂�͂����o���Ă͑ʖڂł���B���̂悤�ȃg���u�����N�����Ƃ��ɂ́C�I�y���[�^�[�ł͂Ȃ��ێ烁���e�i���X�̐l���ĂԂ킯�ł���2�j�B���ۃg���^�֘A�̂Ƃ���֍s�����Ƃ��ɂ����������������C���{�ł͑S������̐l�������������Ƃ����ƁC�ێ�̐l���Ă�ł���P�[�X�������������B�����C��͂葽���̃g���u���̃P�[�X�̓x�e�����̍�ƈ��i�I�y���[�^�[�j���Ώ�����Ƃ����̂����{�̋��݂Ȃ킯�ł���B���Ј��ȊO���g���u���Ώ������Ȃ��Ƃ����������ɁC�R���r�j�Ŏ�w�p�[�g�����낢��Ȃ��Ƃɔz�����Ĕ����ʂ�ς����肷��Ƃ��������Ƃ������āC�����Ƃɂ�����K�ٗp�J���҂͋Z�p�ƕi���ɂ���Đ���Ă���Ƃ������߂��Ȃ���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@���̕����ɃR�����g������ƁC�u�P�����E�莮���E�}�j���A�����v�Ə����o���ɏ�����Ă��邪�C���Ȃ��Ƃ��R���r�j�̗�́C���e��������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv����B��قǂ̍��x�ȘJ���Ƃ͌����Ȃ����Ƃ͂�����Ə����Ă��邪�C�}�j���A�����E�莮���E�P���������܂菑����Ă��Ȃ��B
�@�Ƃɂ����C�Ȃ��J���҂f����̂��̘_�_���Ȃ��ƁC�K�ٗp���琳�K�ٗp�ւ̓]���ւ̏������o�Ă��Ȃ��B����ŁC�����Ƃ��̐S�ȂƂ���ł��邪�C�u���b�N��ƂƂ��u���b�N�o�C�g�ʼn^���Ȃ������Ă���l�����́C�K�ٗp�C���K�ٗp�̕��f�̍��{�̗��R���C�������Ă��Ȃ����C������Ă��Ȃ��Ǝv���B
���r�a�j�ɂ��R���r�j�i�X�[�p�[�j�̐��E
�Ō�ɃR���r�j�C�X�[�p�[�Ɋւ��鏬�r���̐��E�ł���B���r�i2016�j�ł͂Ȃ��C���r�i2015�j�ɁC�Z�u���C���u���̎��Ⴊ���Ȃ�ڂ���������Ă���B�܂��ǂ̂悤�ɂ��ăR���r�j�Ƃ������̂����W���Ă����̂���������Ă���B�C�g�[���[�J�h�[�̎Ўj���͂��߁C�C�g�[���[�J�h�[�ɂ��ď����ꂽ����𒆐S�ɏ�����Ă���B
�@�C�g�[���[�J�h�[����X�s���I�t�����Z�u���C���u���́C�u�������p�x�C�Z���[�h�^�C���̔z���C�����i�C�l�����Ȃ��v�œW�J���Ă������C���r���́C�u�����v�ɒ��ڂ���B�����ł́C�u�p�ɂɁC�i�ڕʂ̔�����������čs���B�v�u�X���������s���B���̂Ƃ��ɖ{�������i�ڂ���i�ڂ̑I���C�i�ڂ��Ƃ̔����ʂf����B�v�u�X��S������X�[�p�[�o�C�U�[�����k�ɂ̂�B�v
�@�l�ތ`���ɂ��ẮC1990�N����̏Ƃ��āC�S���T��Off-JT ����C���c�X�ł�OJT�A�V�X�^���g�Ƃ��ĂP�N�ȏ�C���c�X�̓X���o���P�N�ȏと�X�[�p�[�o�C�U�[�̃A�V�X�^���g���X�[�p�[�o�C�U�[���n��}�l�[�W���[�C�{���X�^�b�t�@�̃L�����A���[�g���L�q����Ă���B
�@�܂��{�c�ꐬ�̃X�[�p�[�̎�����Љ��āC�I����̌����N������̂��C�l�����̌����N������̂��C�����������Ƃ��낪������Ă��āC���������ߋ��̐�s��������ɁC������O���Y�ƁC���Ј������J�����Ԃ̒Z���p�[�g�E�A���o�C�g�̏��L����Ă���B
���r���́C������K���琳�K�ւ̓]���ŁC�Q�̃��f�����Ă��Ă���B�ia�j��������J�����Ԃ̒Z���ق��ŁC�u�P�v�I�Z���ԏ��Ј��v���f���ƌĂ�ł���B�ib�j�́C��قǂ̐����Ƃ̊��ԍH�̗�ł���B���i�\���C�܂��ʓI�ɔK���琳�K�Ɉڂ�ɂ́ia�j�Ɓib�j�̃��f��������Ƃ������Ƃł���B
�@�ia�j�̃X�[�p�[�C�R���r�j�ɂ��čP�v�I�Z���ԏ��Ј����f���Ƃ����̂́C����͂ǂ����Ă���͂菀�Ј��ƌ��킴��Ȃ��ƁC�Z���Ԑ��Ј��ł͂Ȃ��Ə��r���͋�������B���炭���r�����O���ɒu���Ă���Z���Ԑ��Ј��͍P�v�I�Ƃ������ƂŁC�����������]���ɂȂ����Ǝv����B
�@�Ƃ��낪�����J���Ȃ̃��f���ł͒Z���Ԑ��Ј��ɂ͂R�̃^�C�v������C���̂Ȃ��̃^�C�v�U������ɂ�����i�e�� 2011�j�B���̃��f���̍쐬���b�ƂȂ钲���ɕM�҂͑傫���v�������B�^�C�v�U�́C�����Ƃ��̂܂ܒZ���ԂŁC�ꎞ�I�ł͂Ȃ����̂������B����ɑ��ėႦ�Έ玙�̎��������Ƃ��C�����������Ƃ������Z���ԓ����Ƃ����^�C�v�T�Ƃ����̂�����B�^�C�v�T�����ۂɂ͑����̂����C�Ⴆ�Έ玙�Z���ԋΖ��������ł���B�����t���̒Z���Ԑ��Ј��ɂ��āC���r���͂�����ӎ������C�^�C�v�U��O���ɒu���C�Ȃ��Ȃ����y���Ȃ��Ƃ����\�������Ă���B�P�v�I�Z���Ԃ������Ј��ɂȂ肫��Ȃ��̂Łu���Ј��v�Ƃ������t���g���Ă���Ǝv���B
�@�p�[�g�̒������C���ɖ{�c���̌����ȂǂŁC�E�\�������Ă��鎖�Ⴊ���邱�Ƃ��܂��m�F����B�p�[�g�̒������P�Ȃ�u���Ȃ��͊��v�Ƃ����E�����ł͂Ȃ��C�܂�ꗥ��900�~�Ƃ�1,000�~�Ƃ����`�ł͂Ȃ��C������Ɣ\�́C�����E���i�ɂ��Ē��������߂��Ђ�����B���ꂪ�d�v���낤�Ƃ������ƂŁC�����̕��y�̓x�����v�Œ��ׂ����ʁC�p�[�g�̒������S�̂Ƃ��ĐE�\���������Ƃ͌����������B�ꕔ�̃x�e�����p�[�g�̒����݂̂ɂȂ��Ă���B���ꂪ�Z���ԏ��Ј��ƌĂԂ䂦��ł��낤�B
�@�M�҂̃R�����g�́C������������ɂȂ�B�{�����ڂ��Ă���OJT �ɂ��X�L���`���Ƃ͏�������ď����̋c�_���̂��̂ɂȂ邽�߂ł���B�E�������ƍ��肪�ł��Ȃ�����C900�~�̐l�͂�����900�~�C1,000�~�̐l��1,000�~�ɂȂ�B�m���ɐE�\�������C�p�[�g�����p���Ă���Ƃ���ł݂���B�����E�\�������Đ��Ј��Ɠ����悤�Ȓ����̌n�ɂȂ�C������p�[�g�̐l���Z���Ԑ��Ј��ɂȂ�C���邢�̓t���^�C���̐��Ј��ɂȂ�Ƃ��������̌�����@���Ɠ]���o�p�����₷���̂�������Ȃ��B
�@�������{���Ɍ��ߕ���ɂ��Ȃ��Ɠ]���͖����Ȃ̂��Ƃ����^��������Ă���B���Ȃ݂ɃC�I���́C���Ȃ葁�������Ƀp�[�g��E�\�������āC����܂ł͎Ј����E�\���I���������C�Ј��͖������ɂȂ��Ă��܂����݂͓������ߕ��ł͂Ȃ��B�����̌��ߕ����C���낦�Ă���Ɠ]�����₷����������Ȃ����C����قnj���I�ȗ��R�ł��邾�낤���B���r���̊S�́C�E�\���i�̂悤�Ȃ��́j�������z�I�Ǝv���Ă��邩��C�p�[�g�̒��ŐE�\�������i�߂ΒZ���Ԃ̂܂܂ł��]�����₷���C�Ƃ����j���A���X�ł�����̂́C���ׂĂ݂�ƐE�\�������i��ł��Ȃ��̂ŁC�����Ɋւ��ẮC���Ј��ł͂Ȃ��Ă����������Ј��ł͂Ȃ����Ƃ���������������Ă���Ǝv����B
�@�܂����Ȃ�Â������ł��邪�̍������������ꂽ�X�[�p�[�̒����ɂ����āC�����v�������y115�Łz�̂���Ƃ̑��ł͂Ȃ��p�[�g�W�c�̒�����ł��邱�Ƃ�������Ă���B�p�[�g�ŋΑ��������Ȃ��Ă���ƁC���̐l�Ǝ��̂���Ă���d���͈Ⴄ�̂��ƁC������ƍ�������Ăق����Ƃ����`�ŐE�\���I�Ȃ��̂���ꂽ�Ⴊ������Ă��āC�M�҂��C���ĉ�����X�[�p�[�̒��ł���ɋ߂��b�������Ƃ�����B������C��͂�E�\���I�Ȃ��̂́C���X����Ă���d���̐l�������C���̐l�Ǝ��͈�����d�������Ă���C�\�͂��Ⴄ�Ƃ����Ƃ��납��o�Ă��Ă���Ǝv����B
�@�ȏオ�C��{�I�Ɉ�ԏd�v�Ș_�_�ŁC���r�i2016�j�ւ̃R�����g����C�K���琳�K�ւ̊̂ɂȂ�_�_�̈ꕔ��ł����Ǝv���B
�S�@�W���u�E���[�e�[�V�����ƔK
�J���҂̃L�����A�𑪂�Ƃ��ɂR�̎����K�v�ł��邱�Ƃ����r���͋������ꂽ�B�^�e�E���R�E�[���ł���B�^�e�����i�C�[�����u�m�I�n���v�ŁC���R���������x���̎d���o���̑����ł���B�������R�̌o���̑���Ȃ����K�ɂ݂���Ƃ���C�_��Ј���p�[�g�͑��\�H���ł��Ȃ��̂ł��낤���B�Z�\�n�ɂ����炸�C�����炭���\�H�͒P�\�H��萶�Y���������B���Ȃ��v�����łł���悤�ɂȂ邾���łȂ��C��̃W���u������̂ɁC�S�̂�[���m���������łł��邩��ł���B�܂�i���̈ێ��E����ɂȂ���B���\�H���́C�傫�Ȑ��Y������̈�̃J�M�ł���B
�@���\�H���𑪒肷��Ƃ��C����ɃW���u�E���[�e�[�V�����iJob Rotation�j�̕p�x�����d�����e�ɓ��ݍ��u�d���̕��v�i���r�j�Ƃ����\���Ɋ�Â����w�W���Ƃ����ق����K�ł���B�����uJob�v�iJob Description�G��Ɨv�̏��j���C���̐��������K�肳��Ă���C���炩��Job Rotation ���s���Ă��Ȃ��ƑS�̂Ƃ��Ă̍�Ƃ��̂��̂��������Ȃ��B
�@�t�ɁC�������L���i�����܂��ɁH�j�K�肳��Ă���C�W���u�̂Ȃ��ł̍�Ɓi�^�X�N�j�̃V�t�g�ɂȂ�C���[�e�[�V�����̕K�v�͂Ȃ��B���̃P�[�X�ł́C��V���u�E�����v�Ƃ����Ă��C������u�E�\���v�ɂȂ��Ă�����������Ȃ��B�����̃^�X�N�����Ȃ��l�ƈ�̃^�X�N�������Ȃ��Ȃ��l�̕�V���ɂ��邱�Ƃ́C�ł��Ȃ��ł��낤�i�����Ƃ��P���ȐE�����ł͂����Ȃ��Ă��邪�B�j���x�Ȏd���̕�V��P���ȐE�����Ŏx�����ƌ����E�����ǂ��炩������������Ȃ��B
�@���̂悤�Ɏd�����e���邢�̓X�L�����Ƃ炦�Ă����ƁC�u�W���u�^�vvs�u�����o�[�V�b�v�^�v�Ƃ����}���͖��Ӗ��ł���B���{�̐E��Łu�W���u�v��������肠���܂����Ǝ����؋��́C���Ȃ��Ƃ��z���C�g�J���[�ɂ͂Ȃ��B�����~�ς̂���u���[�J���[�ȊO�̘J���҂̎d�����e���x�[�X�ɂ������۔�r�̏؋����Ȃ����߂ł���B
�@��V�����S�Ɂu���ʁv�x�[�X�ɂ���̂ł���C���\�H����W���u�E���[�e�[�V�����̋c�_�̑����͏�����B�Ƃ�����芮�S�Ɂu���ʁv�Ɋ�Â��Ďx�����Ă���C���K�E�K�̋敪�̈Ӗ��͂قƂ�ǂȂ��Ȃ�ł��낤�B
�������ɁC������u�K�v�̂Ȃ��ő����Ă�������҂ɂ��ď��������G�ꂽ���B�������Čٗp�ҁi�p���Α��ҁj�ɂ��čl����ƁC�قƂ�Ǐ������琳�K�ւ̈ڍs�͍l���Ă��Ȃ��B��Ƃ��{�l���ł���B
�@�Čٗp�҂́C�����_��Ј��ƃA���o�C�g�E�p�[�g�iJILPT 2015�N�����j�ł́C60��O���w�őO�҂�60.7���C��҂�21.7���C���Ј���34.2���i�����j���݂���B
�@����i���܂́j�_��Y���ɂ��u�ꍑ�x�v�_�i���� 2012�C���� 2014�j���l���悤�B��̊�Ƃ̂Ȃ��ɐ��Ј��Ə����i�Čٗp�ҁj�̂Q�̌ٗp�敪�����邱�Ƃ��g�I�ɘ_���Ă���B�������Ɂu�ꍑ�x�v����u�ꍑ�ꐧ�x�v�ւ̋c�_�͌@�艺����ׂ������C�c�_�̎��������ނ��Ƃ͍���̂悤�ɂ݂���B���������u�ꍑ�������x�v���������Ă��闝�_�I�����͉����������ł͂Ȃ��B���쎁�̂����u�����I�ٗp�v�̃P�[�X�́C��͉����Ă��Ȃ��킯������C���ʂ��ƒm��Ȃ����������ł���Ƃ������ƂŐ����ł��邪�C��͉������̂����u�ꍑ�������x�v�܂�قȂ�ٗp�敪�ŏ������鍪���C���Ȃ��Ƃ��������K�v�Ƃ����B
�@�{�_���̖`���ɂ����āC�O�J�i2019�j�ɂ�鍑�۔�r����C�����͎�N�҂ƒ�w���҂ɔK�������̂ɑ��C�킪���́C�����ƍ���҂ɁC�Ƃтʂ��đ������Ƃ��݂��B���������p�[�g�ɑ��Ă͑����̌��������Ē�����B�������C����҂ɂ��Ắu�K�v����u���K�v�ւ̓]���i�u���j�Ƃ͈�������p����OJT ���Ƃ炦��K�v�����邾�낤�B���ꂩ��܂��܂��d�v�ɂȂ�Ǝv����d���\�ɂ����āC����������҂̎��������R�����C��y�Ɂu������v���Ƃɏd�_���������d���̕��S�������Ȃ��̂������I�ł���B�u������v���Ƃ��ł���͍̂��x�ȃX�L���䂦�C�ӂ��ɂ����Ε�V�͍������ׂ��ł���B�����������͑S���t�ɂȂ��Ă���i���������j����C�X�L���ƑS���قȂ鏈������i�K�I�ɃX�L���ɋ߂Â��Ă������ƂɂȂ�̂��낤���B
�@�J��Ԃ��ɂȂ邪�C������ɂ���K���琳�K�ւ̓]����_����ꍇ�C�ǂ́u�K�v�̌ٗp�`�Ԃ̘b�Ȃ̂��C�����đΏۂƂ���J���҂̑����̈Ⴂ�ɗ��ӂ���K�v������B
�Γc���j�E��������i2009�j�w�l�����x�̓��Ĕ�r�\���ʎ�`�ƃA�����J�̌����x�~�l�����@���[
����_��Y�i2012�j�w���Ј����Ŏ���̐l�����v�x���{�o�ϐV����
����_��Y�i2014�j�w����Ј��̐l���Ǘ��x�����o�ώ�
���r�a�j�i1977�j�w�E��̘J���g���ƎQ���x���m�o�ϐV���
���r�a�j�i2005�j�w�d���̌o�ϊw�i��O�Łj�x���m�o�ϐV���
���r�a�j�i2015�j�w�Ȃ����{��Ƃ͋��݂��̂Ă�̂��\�����̋���vs �Z���̋����x���{�o�ϐV���o�Ŏ�
���r�a�j�i2016�j�w�u�K�J���v���l����x���É���w�o�ʼn�
���r�a�j�E���ؕ����ҁi1987�j�w�l�ތ`���̍��۔�r�\����A�W�A�Ɠ��{�x���m�o�ϐV���
���쐰�M�i2016�j�w�u���b�N�o�C�g�\�w������Ȃ��x��g�V��
���ђq�s�i2017�j�w�h���J���Ƃ����������x�L��t
�y117�Łz
�d�@�A������������掺�i�d�@�����j�i2007�j�w��������ē҂��Ƃ�܂����ω��ƌ���p�t�H�[�}���X�Ɋւ��錤���x���V���[�Y�@No.11�i�d�@�����C2007�N�j
�����b�i1989�j�C�u�Z�\�Ƃ������_����݂��p�[�g�^�C���J�����v���w�l���N���i�w�_�ˊw�@�o�ϊw�_�W�x37���i2006�j�Ɏ��^�B�j
���Ђ�݁i2014�j�w�E�Ɣ\�͊J���̌o�ϕ��́x�������[
���{�^�i2014�j�w���{��Ƃɂ�����\�͊J���E�L�����A�`���\�������������̃T�[�x�C�Ǝ��s�I���͂ɂ�錤���ۑ�̌����x�J�����|�[�g Vol.11
�{�c�ꐬ�i2002�j�w�`�F�[���X�g�A�̐l�ފJ���\���{�Ɛ����x��q���[
�{�c�ꐬ�i2007�j�w�`�F�[���X�g�A�̃p�[�g�^�C�}�[�\����ƐV�����J�g�W�x�������[
�O�J���I�i1997�j�w��Ɠ������\���ƘJ���s��x�������[
�O�J���I�i1999�j�u�t�����X�̒������萧�x�ɂ��āv�w�����o�ώG���x179���U���ipp.61-75�j
�O�J���I�i2019�j�u�K�J���҂̍��۔�r�v���{�o�ϒ������c��w���{�̋��݂������u���������v�v���l����x���{�o�ϒ������c��
�����v�nj��i1996�j�u�ʎY�E��ɂ�����m�I�n���Ɠ����E�����̌X���\���Ƃƒ�����Ƃ̎��Ⴉ��v�w���{�J�������G���x434��
�J�������E���C�@�\�iJILPT�j�i2015�j�u�o�c�헪�Ɛl�ވ琬�Ɋւ��钲���v2014�N�����i�J�������E���C�@�\�C2015�N�j
�J�������E���C�@�\�iJILPT�j�i2017�j�u���̂Â���Y�Ƃ��x�����Ƃ̘J�����Y������Ɍ������l�ފm�ہC�琬�Ɋւ��钲���v2016�N�����i�J�������E���C�@�\�C2017�N�j
�e�▾�i1996�j�u�R�[�X�ʐl���Ǘ��̈Ӌ`�Ɩ��_�v�w���{�J�������G���x433���i14�23�j
�e�▾�i1997�j�u�R�[�X�ʐl�����x�Ə����J���v���n�G�V�E�x�͋P�a�ҁw�ٗp���s�̕ω��Ə����J���x������w�o�ʼn�i 243-278�j
�e�▾�i1998�j�w�E��ތ^�Ə����̃L�����A�`���E����Łx�䒃�̐����[
�e�▾�i2011�j�w�J���o�ϊw����\�V�����������̎�����ڎw���āx���{�]�_��
�e�▾�i2018�j�w�����J���Ɋւ����b�I�����@�\�����̓��������������{��Ƃ̌���Ə����x ���{�]�_��
�e�▾�i2019�j�uOJT �čl�v�w�w�K�@�o�όo�c�������N��x�i�������j