【1頁】
仮想市場評価法による東京都の潜在的待機児童数の推計*
鈴木 亘**
本稿は,東京都が2017年に実施した子育て世帯への大規模アンケート調査を用い,仮想市場評価法(CVM)を使って,東京都の保育サービス需要を分析した。主な結果は以下の通りで ある。
第1に,潜在的待機児童率は19.5%と,待機児童率(1.3%)の14倍を超える大きさである。
第2に,現在の保育サービス供給量のもとで,総待機児童率をゼロにする均衡保育料(月額)は,全年齢合計で45,400円である。
第3に,中高所得者への月額5千円の保育料引き上げで総待機児童率は元の大きさの約3分の2,月額1万円引き上げで約3分の1となる。また,認可保育所の0歳児定員を廃止して,育休促進を図ることにより,総待機児童率はほぼ半減する。
待機児童,潜在的待機児童,超過需要,割当,仮想市場評価法
D45,I22,J13
待機児童が深刻な社会問題となってから,既に四半世紀ほどの月日が経過しているが,未だに捗捗しい改善が見られていない。この間,政府は単に手をこまねいていた訳ではない。図1【2頁】 に見るように,近年,待機児童数を大幅に上回る保育の受け皿(利用児童数)を毎年作り続けているが,それでも待機児童数はなかなか減少しないのである。
度重なる対策にもかかわらず,まるで「逃げ水」のように待機児童数が減らない背景には,八代(2000)が早くから指摘しているように,待機児童を大幅に上回る「潜在的待機児童」の存在がある。実は,政府によって統計的に把握されている「待機児童数」とはかなり限定的な概念である。すなわち,①自治体に認可保育の申請を行い,入所選考に漏れた児童のうち,②自治体の独自事業の認可外保育施設に入所したり,③入所をあきらめて求職活動を中止したり,④他に利用可能な認可保育があるのに,特定の認可保育所を希望して待機している児童を除いた数として定義される(①−(② + ③ + ④))1)。このうち,②に該当する児童は保育施設に入所しているが,③④に該当する児童は実質的に待機しているにもかかわらず,待機児童の統計に現れない。
また,待機児童問題が深刻な都市部では,⑤はじめから認可保育の利用をあきらめ,自治体に入所申請すら行っていない場合も多い。さらに,⑥現在は就労していないが,近隣に入所可能な保育所ができれば就労しようと考えている人々もいる。
これら③〜⑥に該当する児童数の総計を「潜在的待機児童」と呼ぶ。このいわば待機児童予備群たちは,対策によって保育の受け皿が増えると,次々に顕在化して,その一部が新たに待機児童数としてカウントされるようになる。待機児童問題を根本的に解決するためには,統計上把握されている待機児童数だけではなく,この潜在的待機児童数にも着目し,対策を講じる必要がある。
しかしながら,この潜在的待機児童数を把握しようとする調査・研究は,決して多いとは言えない。もちろん,自治体や民間調査機関が実施している住民アンケートの中には,「保育サービスの利用を希望するものの,現在,利用できていない」という意味で,一種の潜在的待機児童数を算出しているものもある。しかし,こうして把握される数は,あくまで「希望」あるいは「必要(ニーズ)」ベースのものであり,「需要」とは異なる。経済学で言う需要とは,物やサービスの対価である価格が提示され,その価格を支払う意志を伴った概念である。政策的に重要なのは,実際に顕在化する需要である。
この価格(保育料)を伴った保育サービス需要を初めて計測し,潜在的待機児童数を推計した記念碑的な研究が,周・大石(2003)である。彼女らは,マーケティングや環境経済学等の分野で用いられている仮想市場評価法(CVM: Contingent Valuation Method)を使って,首都圏(1都3県)における保育サービス需要の推定を行い,その後の同種の研究(内閣府(2003),清水谷・野口(2004),八代・白石・鈴木(2006),鈴木(2008, 2009, 2012))が踏襲する標準的手法を提示した。
こうした中,本稿では東京都における潜在的待機児童数を新たに推計する。東京都の2017年4月における待機児童数は8,586人と,全国の待機児童数(26,081人)の約3分の1を占める。東京都においても,近年,待機児童数を大きく上回る保育の受け皿を新たに作り続けているにもかかわらず,顕著な成果が表れていない(図2)。この背景には,やはり大量の潜在的待機児童の存在があるものと考えられ,その量的な把握を行うことが政策的に極めて重要である。
【3頁】ところで,本稿の分析は,手法面における新規性は特に無いが,用いているデータが優れていることが特徴である。既に挙げた先行研究は全て,無作為抽出という面で問題があるデータ(社会調査会社のモニター・サンプル等)を用いているか,サンプル数が少ないと言う問題を抱えていた2)。これに対して,本稿が用いているデータは,東京都内40区市の協力を得て,東京都福祉保健局が実施した大規模アンケート調査であり,住民基本台帳から子育て世帯を無作為に抽出し,有効回答数13,114を得ている。また,先行研究が用いているデータの多くは2000年代前半,最も新しいものでも2008年に調査されたものである。これに対して,本稿が用いた調査は2017年に実施されており,現在の待機児童問題を分析したり,今後行うべき対策のシミュレーションを行う上で,よりふさわしいデータと言えよう。
本稿の構成は以下の通りである。2章ではデータについて解説を行う。3章では,仮想市場評価法や推定モデルについて説明し,4章で推定結果と潜在的待機児童数等の推計値を報告する。以上の分析をもとに,5章において若干の政策シミュレーションを行い,6章において結論をまとめる。
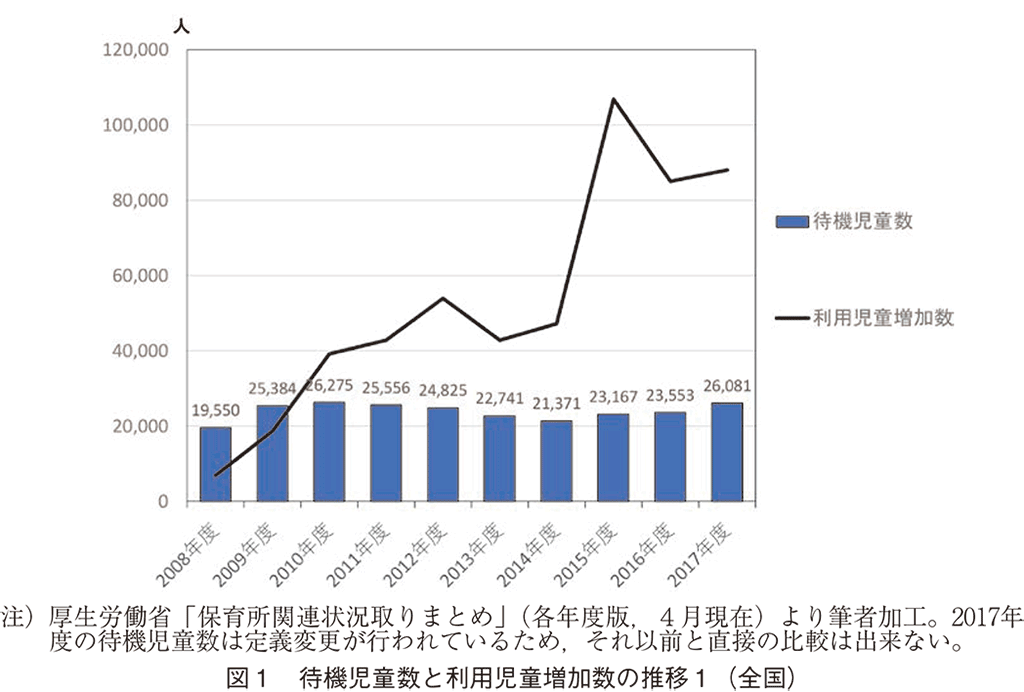
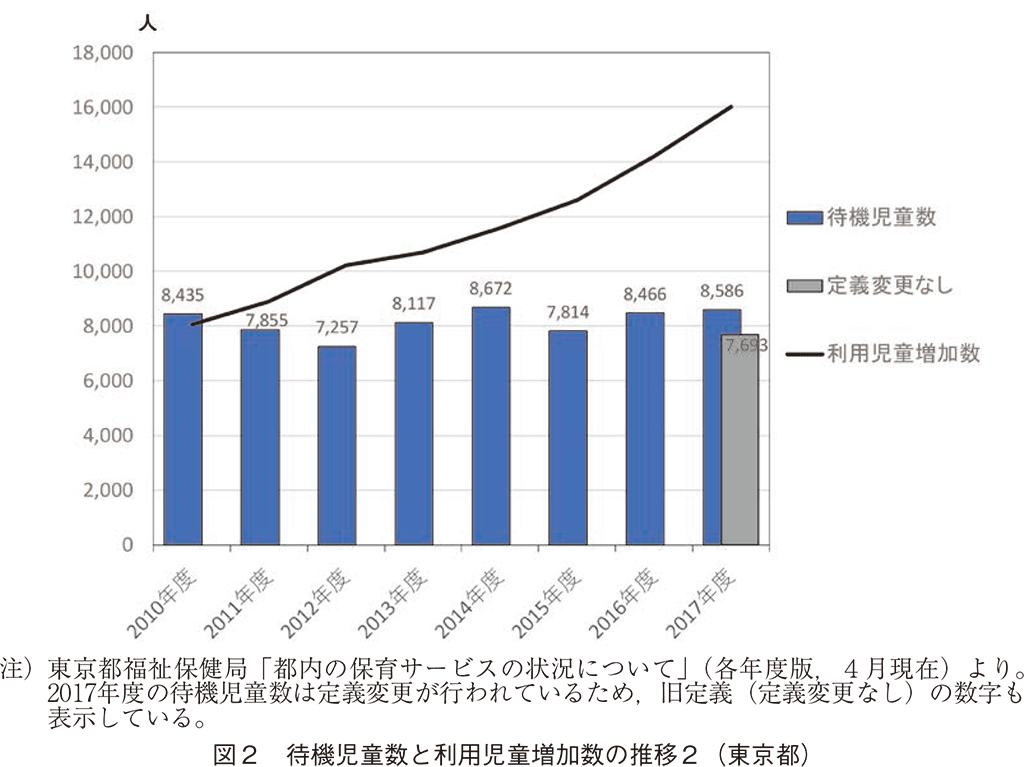
本稿が用いているデータは,東京都福祉保健局が2017年8月から9月にかけて実施した「教育・保育サービスの利用実態と利用ニーズに関するアンケート」である。調査対象地域は,23区および待機児童数が50人以上の17市である3)。区市の協力により,住民基本台帳から,0歳から5歳の子どもがいる世帯を,無作為に38,170サンプル抽出し,児童の親に対して協力依頼を郵送した。その後,協力者にはインターネットのウェッブ・サイト上に作られた調査票に回答してもらっている4)。有効回答数は13,114,有効回答率は34.36%であり,先に挙げた先行研究と比較しても,やや高い回答率と言える。
【5頁】調査項目は,親の状況,子どもの状況,教育・保育サービスの利用実態等,多岐にわたる5)。以下の分析には用いていないが,サンプル特性を示す代表的変数の記述統計を表1に示した。もっとも,比較対象として適切な大規模調査(東京都に限定された大規模子育て世帯調査等)が存在しないため,その代表性を確認することは難しい。認可保育,認可外保育施設,幼稚園の入所割合については,表5の母数の割合と極めて近い値になっている。
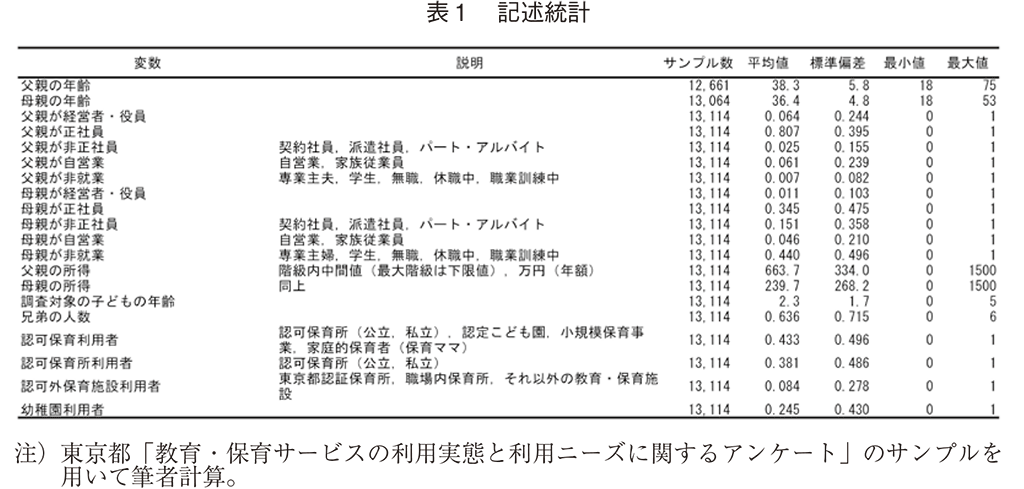
2.2 WTP の質問
調査項目のうち,本稿が分析に用いているのは,以下に示された一連の質問である。仮想市場評価法とは,こうした質問を用いて,仮想上の財やサービスに対する支払意思額(WTP)等を表明させる手法の一つである。この調査では,認可保育所の保育サービスを受けることに対する保育料(月額)のWTP を表明してもらっている。周・大石(2003)と同様,回答バイアスが少ないとされる二肢選択方式の質問形式を用いた。
下記の文章をお読みの上,質問にお答えください。
仮の話ですが,あなたの家の近くに認可保育所(定員が100人から200人程度で,園庭があり,スタッフのほぼ全員が保育士資格を持っている通常の認可保育所)があり,定員の空きが十分にあるとします(待機にはならないとします)。このとき,下記の条件でお子さまをこの認可保育所に入れるかどうか,お答えください。既に認可保育所を利用されている場合には,「引き続き利用しつづけるかどうか」についてお答えください)。
- Q1:
- この認可保育所の保育料は,あなたの世帯の所得にかかわらず月額4万円だとします。その場合,あなたは認可保育所を利用しますか(既に,認可保育所を利用されている方は,保育料が月額4万円になった場合,利用を続けるかどうかをお答えください)。
- 1
- 利用する
- 2
- 利用しない
- Q2:
- それでは,保育料月額8万円ならこの認可保育所を利用したいと考えますか。
- (母数:Q1保育料月額4万円で利用する回答者)
- 1
- 利用する
- 2
- 利用しない
- Q3:
- それでは,最高で月額いくらまでなら払っても良いと思いますか。
最も近いものをお答えください。 - (母数:Q2保育料月額8万円で利用する回答者)
- 1
- 8万円
- 2
- 10万円
- 3
- 12万円
- 4
- 14万円
- 5
- 16万円
- 6
- 18万円
- 7
- 20万円以上
- Q4:
- それでは,保育料月額6万円ならこの認可保育所を利用したいと考えますか。
- (母数:Q3保育料月額8万円で利用しない回答者)
- 1
- 利用する
- 2
- 利用しない
- Q5:
- それでは,保育料月額2万円なら,この認可保育所を利用しますか。
- (母数:Q1 保育料月額4万円で利用しない回答者)
- 1
- 利用する
- 2
- 利用しない
- Q6:
- それでは,保育料月額3万円なら,この認可保育所を利用しますか。
- (母数:Q5保育料月額2万円で利用する回答者)
- 1
- 利用する
- 2
- 利用しない
- Q7:
- それでは,最高で月額いくらまでなら支払ってもよいと思いますか。
最も近いものをお答えください。 - (母数:Q5保育料月額2万円で利用しない回答者)
- 1
- 1万5千円
- 2
- 1万円以下
- 3
- どんなに安くても認可保育所を利用しない
図3に示されているように,回答者は一連の質問に導かれて,WTP の範囲(カテゴリー)を表明する。周・大石(2003)では,Q7の回答は分析に用いず,2万円以下をWTP の最少カテゴリーとしたが,本稿ではQ7に対しても該当者全員の回答が得られるようにウェッブ上の調査設計を行っているため,1万円以下(2および3の回答者)とそれ以外に,カテゴリーを分けた。カテゴリー別のWTP の分布は表2の通りである。
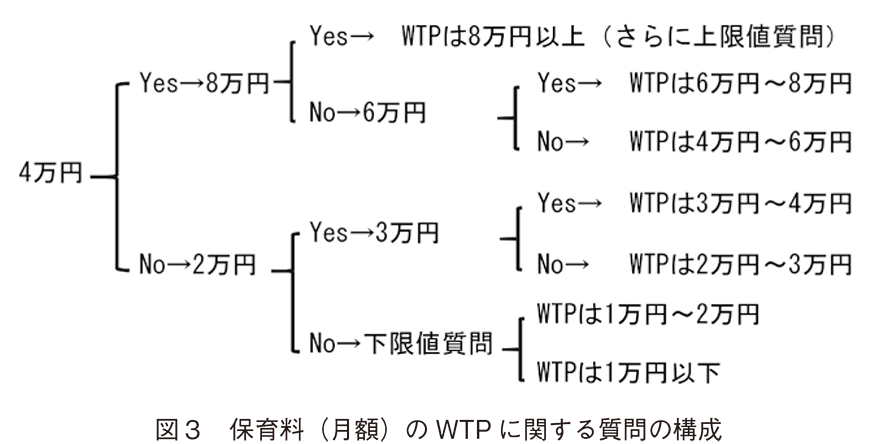
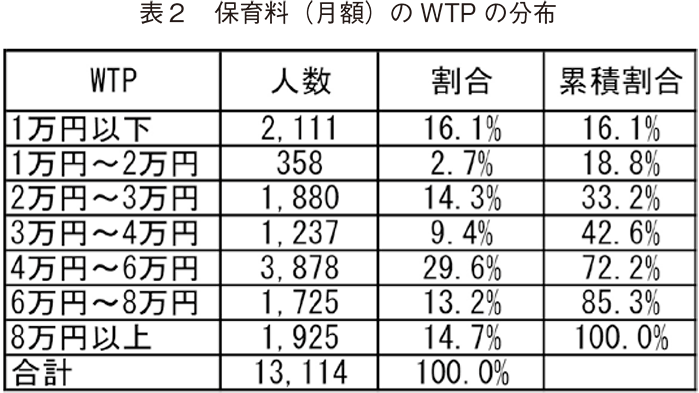
3.推定モデル6)
二肢選択方式では,WTP の値そのものではなく,提示金額に対する選択が回答される。このため,需要曲線の推定に当たっては,WTP をイベントが起きるまでの時間(duration),選択をイベントの発生(failure)に見立てた生存分析(survival analysis)の推定方法を用いることが一般的である。
今,需要関数の逆関数を生存関数S(t)とする。t は保育料(月額)のWTP であり,需要の単位は,その保育料のもとで保育サービスを受諾する割合(受諾確率)である。生存関数の形状はロジスティック分布を仮定する。
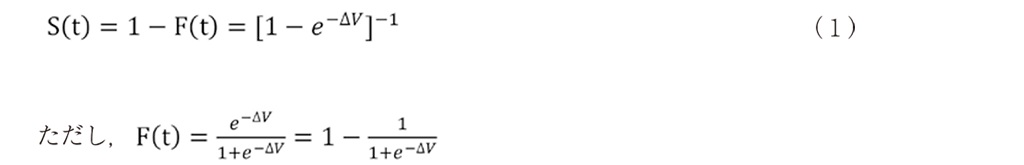
 は保育サービスをその保育料で受諾する場合の効用と,受諾しない場合の効用の差分を
示し,次のように定式化する7)。α,βは推定されるパラメータである。
は保育サービスをその保育料で受諾する場合の効用と,受諾しない場合の効用の差分を
示し,次のように定式化する7)。α,βは推定されるパラメータである。

図3に示された各カテゴリーに回答者が該当する確率は下記の通りである。
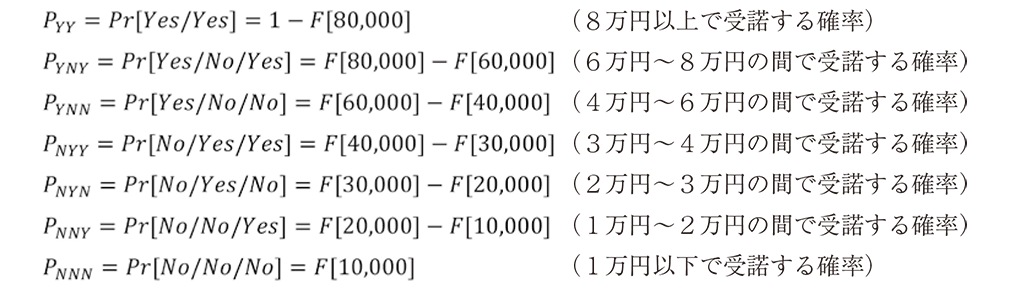
ここで, や
や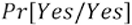 と表示されているのは,最初の質問(提示された保育料4万円)
で保育所利用を受諾し(Yes),次の質問(提示された保育料8万円)でも利用を受諾したこと
を示す。それ以外の表記も解釈は同様である。これらの各カテゴリー別の確率を用いて,(2)【9頁】式のαおよびβを推定するための尤度関数は,以下の通りである。
と表示されているのは,最初の質問(提示された保育料4万円)
で保育所利用を受諾し(Yes),次の質問(提示された保育料8万円)でも利用を受諾したこと
を示す。それ以外の表記も解釈は同様である。これらの各カテゴリー別の確率を用いて,(2)【9頁】式のαおよびβを推定するための尤度関数は,以下の通りである。
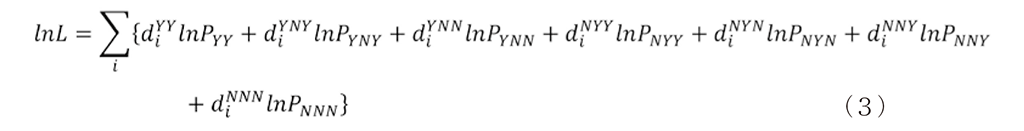
ここで, は,最初の質問(提示された保育料4万円)で保育所利用を受諾し(Yes),次の質問(提示された保育料8万円)でも利用を受諾した人が1,それ以外の人が0をとるダミー変数であり,以下,解釈は同様である。最尤法を用いて,(3)式が最大になるように各パラメータを推定する。
は,最初の質問(提示された保育料4万円)で保育所利用を受諾し(Yes),次の質問(提示された保育料8万円)でも利用を受諾した人が1,それ以外の人が0をとるダミー変数であり,以下,解釈は同様である。最尤法を用いて,(3)式が最大になるように各パラメータを推定する。
4.推定結果8)
4.1 推定結果と需要曲線
推定結果は,表3の通りである。全年齢合計と,各年齢別のサンプルに分けて7つの推定を行っており,全パラメータが1%基準で有意である。図4は,全年齢合計の推定結果をもとに,保育サービス市場の需要曲線を描いたものである。(2)式の各パラメータに推定結果を代入し,(1)式に戻した上で,t を横軸,S(t)を縦軸とする。通常の需要曲線と異なり,横軸が価格(保育料),縦軸が需要(受諾確率)であることに注意されたい。この需要曲線と実際の平均保育料との交点(E)で定まる需要が,現行の保育料のもとで生じている需要量である(D1)。これと,実際の保育サービス利用率(D0)との差(D1− D0)が,潜在的待機児童を含む「総待機児童率」ということになる。
経済学の観点から見ると,待機児童とは保育サービスに対する「超過需要」が発生している状態と考えられる。すなわち,認可保育所の平均保育料が,本来,市場で決まるべき価格水準(A 点)よりも低い水準に価格規制されていることから,保育サービスの供給量を上回る需要量が発生するのである。このため,過大な需要量を供給量の範囲に収めるために,自治体は入所選考という形で割当を行わざるを得ない。
全年齢合計と同様に,各年齢別についても,推定結果から需要曲線を描き,平均保育料との交点を求めることができる(図5)。年齢が低いほど旺盛な需要(厚みがある曲線)が存在していることがわかる。
図4,5の中に示されている現行の平均保育料(縦の実線)は,表4の一番左の列に金額が 掲載されている。認可保育所の保育料は世帯所得によって変わる応能負担であるが,その平均額をみると,全年齢合計で月額28,300円である9)。0歳児の34,300円から5歳児の22,200円まで,【10頁】年齢が高くなるほど金額が低くなる。
一方,やはり図4,5に示されている実際の保育サービス利用率(横の点線)は,東京都が把握している2017年4月現在の保育サービス利用児童数を,同年1月現在の就学前児童人口で除した値である。保育サービスの定義には,認可保育(認可保育所,認定こども園,家庭的保育事業(保育ママ),小規模保育事業,事業所内保育事業,居宅訪問型保育事業(ベビーシッター),定期利用保育事業)の他に,自治体の独自事業の認可外保育施設(東京都認証保育所,区市町村単独施策等(うち家庭的保育等),区市町村単独施策等(うち保育室等))が含まれている(表5)。これらは確かに認可外保育施設ではあるが,自治体によって一定以上の保育の質が保証されており,ベビーホテル等とは明らかに異なることから,政府の待機児童の定義には含まれない。つまり,待機児童の統計上は,認可保育と同じ扱いになっていため,供給量の中にそのまま含めることにした10)。
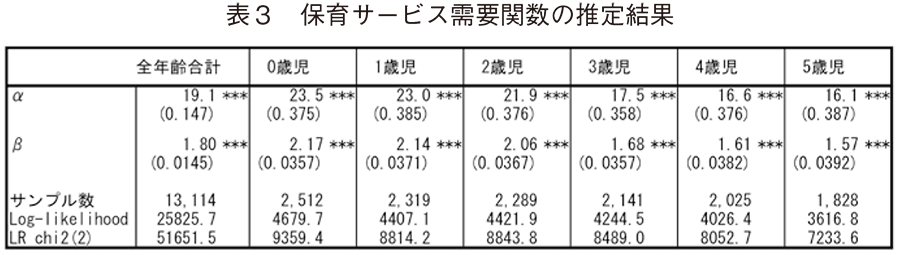
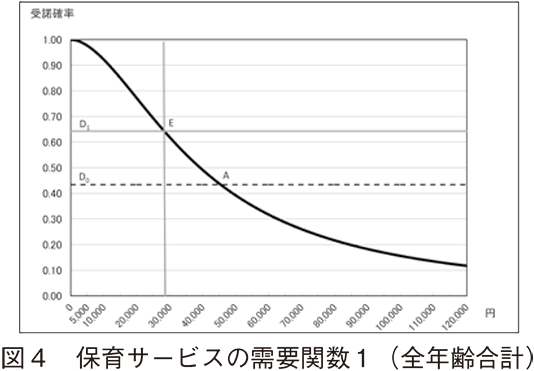
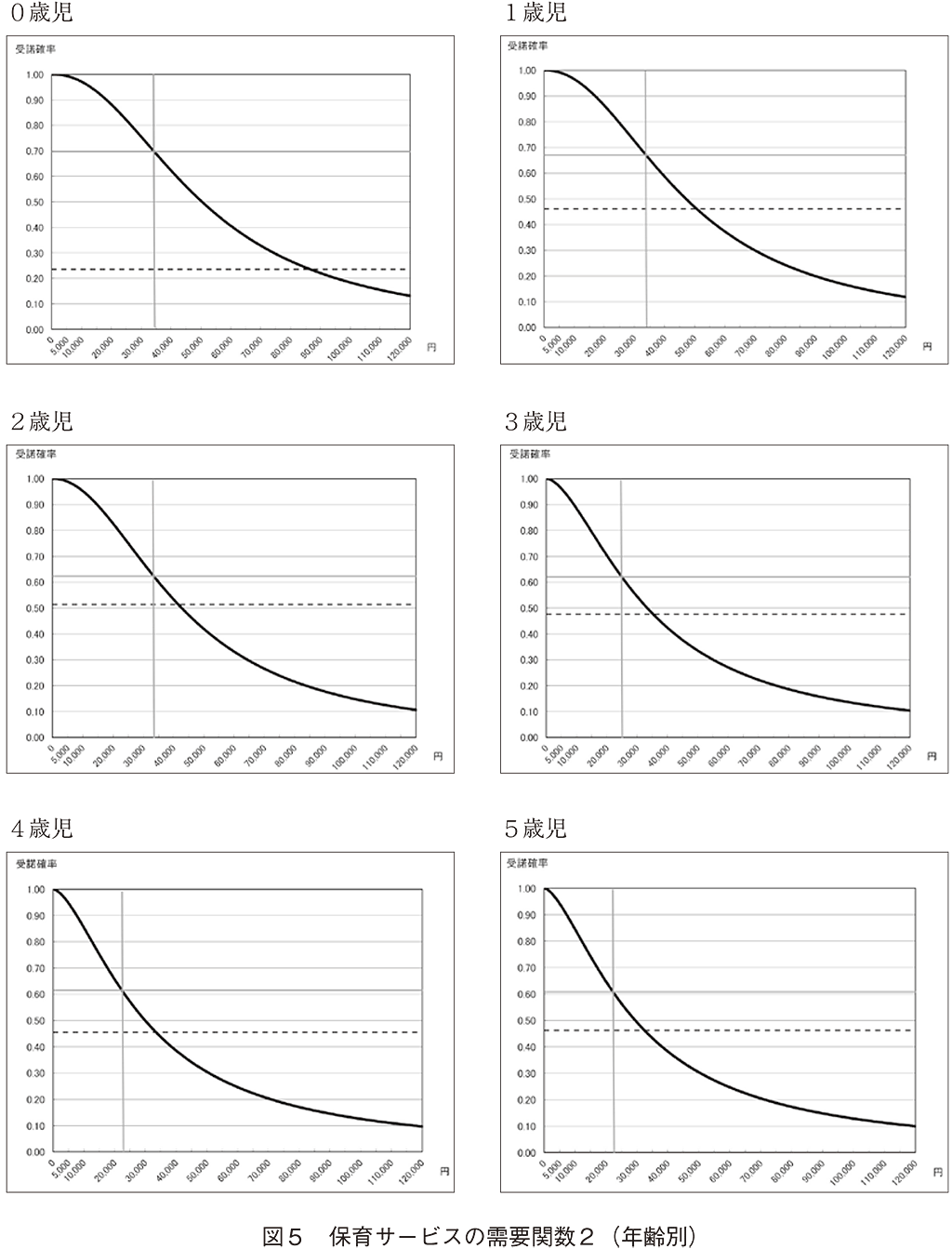
4.2 潜在的待機児童と均衡保育料の推計
潜在的待機児童等の推計値は,表6に示す通りである。一番上の行の全年齢合計でみると,月額28,300円の平均保育料と需要曲線の交点にあたる(a)受諾確率は64.3%であり,この数字と(b)保育サービス利用率43.4%との差(20.9%)が,潜在的待機児童を含む(c)総待機児童率である。このうち,(d)実際の待機児童率(待機児童数/ 就学前児童数)1.3%を差し引いた19.5%が(e)潜在的待機児童率となる。人数に換算すると125,101人であり,2017年4月現在の待機児童数8,586人の約14.6倍もの潜在的待機児童数が存在することになる。周・大石(2003)における東京都の潜在的待機児童率が5.0倍,内閣府(2003)における東京分の潜在的待機児童率が10.1倍であったことから考えると,もちろん単純な比較は難しいが,現在の状況の方がより深刻になっている可能性がある。
年齢別にみると,潜在的待機児童率が突出して高いのが0歳児である(44.0%)。0歳児は需要が最も旺盛であるにもかかわらず(受諾確率69.7%),保育サービスの供給量が少ない(保育サービス利用率23.6%)ことが影響している。0歳児の潜在的待機児童率が突出して高いという傾向は,上記の先行研究も同様である。また,2歳児の潜在的待機児童率は9.6%と,3歳児以上の高年齢児に比べても低くなっている。これは,保育サービス利用率が51.4%と高いことが影響していると思われる11)。
さて,図4の需要曲線を用いると,現在の保育サービス利用率のもとで,待機児童を全て解消するための「均衡保育料(月額)」を算出できる(図4のA 点)。具体的に,その均衡保育料を示したものが表4の一番右の列である。全年齢合計の均衡保育料は45,400円であり,現行平均保育料の28,300円よりも17,100円も高くなる。ただし,45,400円という均衡保育料は需要曲線から算出したWTP の中央値(39,200円)よりは高いものの,WTP の平均値(56,300円)を下回る金額であり,利用希望者たちの「支払い意志額」という意味では,それほど非現実的な数字とは思われない12)。実際,認可保育所と比肩し得るサービスの質が求められている東京都認証保育所の場合,その平均保育料(月額)は約6万5千円である(鈴木(2018))。さらに,東京都の各自治体における認可保育所の児童1人当たりの運営費は,月額15万円から20万円程度に上っている( 鈴木(2018))。
各年齢別に見ると,総待機児童率の高さを反映し,やはり0歳児の均衡保育料が86,400円と際だって高い13)。これは現行の平均保育料(34,300円)の約2.5倍の高さであり,もちろん,WTP(中央値,平均値)をはるかに上回る水準である。ただし,鈴木(2018)によれば,東京都の各自治体における認可保育所の0歳児1人当たりの運営費(月額)は,約40万円にも上っている。もし,その水準と比較をするならば,86,400円という均衡保育料も高すぎるとは【13頁】言えないかもしれない。また,2歳児の均衡保育料が41,500円とWTP(中央値)を下回るほ ど低い理由は,既に述べたように,保育サービス利用率が他の年齢よりも高いからであろう。
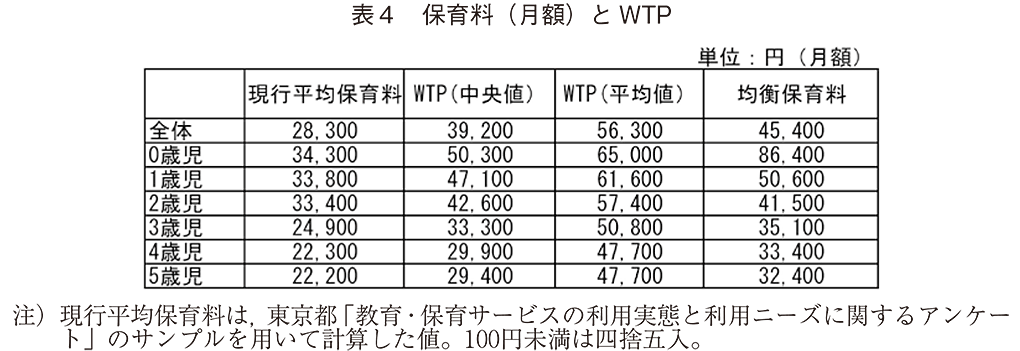
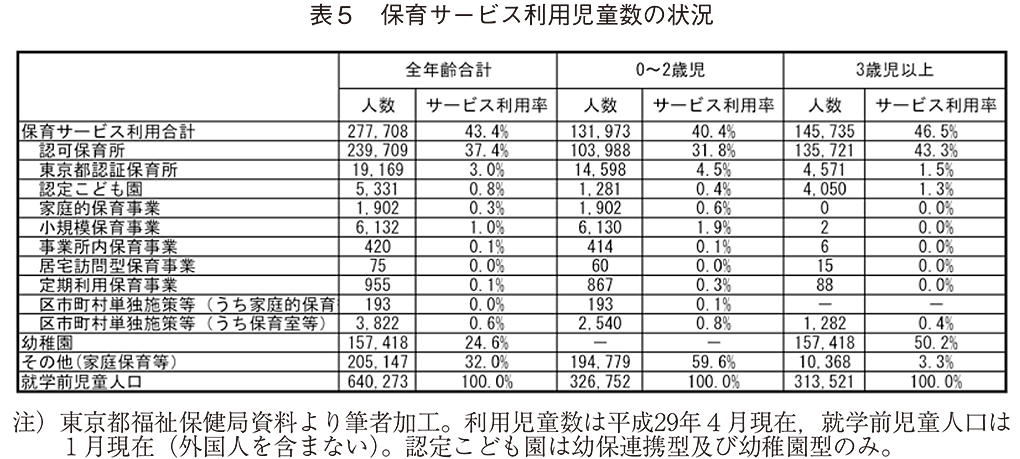
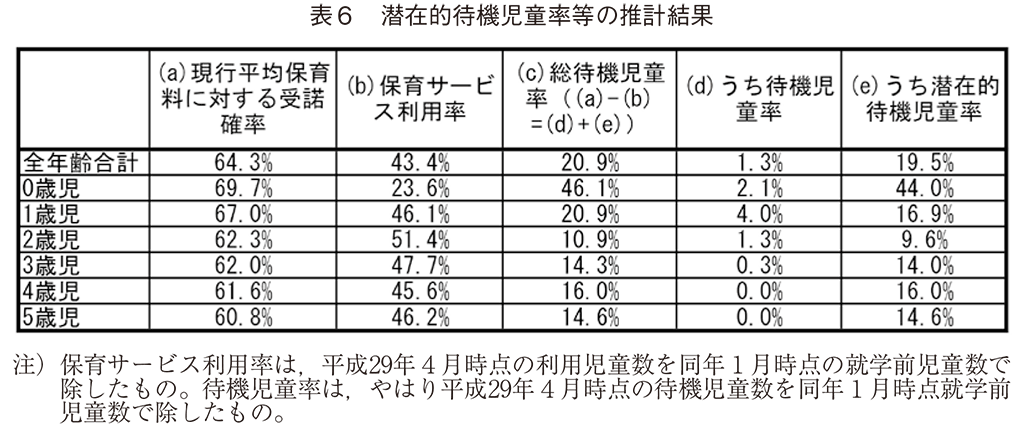
5.1 保育料の引き上げ
推定した需要曲線を用いて,具体的な待機児童対策についてのシミュレーション分析を行おう。本稿は供給曲線を明示的に分析していないので,検討できる待機児童対策も需要面に限られる。具体的には,①保育料の引き上げ,②希望通りの育休期間を取得できる環境整備,③認可保育所の0歳児定員を無くし,育休を取得できる人には1歳まで育休を取るように促す,という3つの対策の効果を分析した。
既に述べたように,認可保育所の保育料は,均衡保育料やWTP と比較しても,あるいは認可保育所の運営費や東京都認証保育所の保育料と比較しても,かなり低い水準に設定されている。したがって,保育料引き上げを正当化できる余地は大きいものと思われる。表7は,本稿で用いているデータから東京都の所得階層別保育料を計算し,国基準の保育料と比較したものである14)。低所得層では両者にさほど大きな違いはみられないが,所得層が高くなるにしたがって,国基準と東京都の保育料との差が大きくなって行くことがわかる。鈴木(2018)が詳しく論じているように,総じて見て,東京都の保育料設定額はかなり低い。
一般に,低所得層の保育料引き上げは政治的に非常に困難であることから,ここでは中高所得層の保育料引き上げについて検討する。具体的には,住民税所得割課税額が57,700円未満を低所得層と見なし,それ以上の所得階層の保育料(月額)を(a)5000円,(b)1万円引き上げた場合を考える。具体的には,それぞれのケースについて,該当サンプルの保育料を引き上げ,年齢別の平均保育料を改めて計算する。その平均保育料と各年齢別の需要曲線との交点から,総待機児童率を求めた。
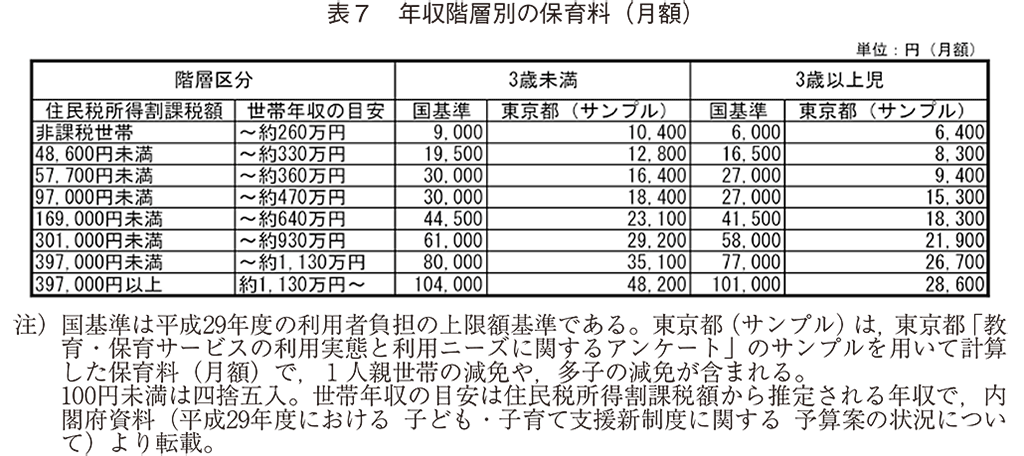
表8の左から二つの列((a),(b))がその結果であるが,月額5000円引き上げで全年齢合計の総待機児童率は6.9%ポイント,月額1万円引き上げで13.0%ポイントも減少する15)。総待機児童率はそれぞれ,元の大きさの約3分の2(5000円引き上げ)と約3分の1(1万円引き上げ)まで減少する。年齢別にみると,もともと需要が旺盛であった0歳児の潜在的待機児童率は依然として高いものの,1万円引き上げの場合には,2歳児以上の潜在的待機児童率はゼロに近い水準まで減少する。
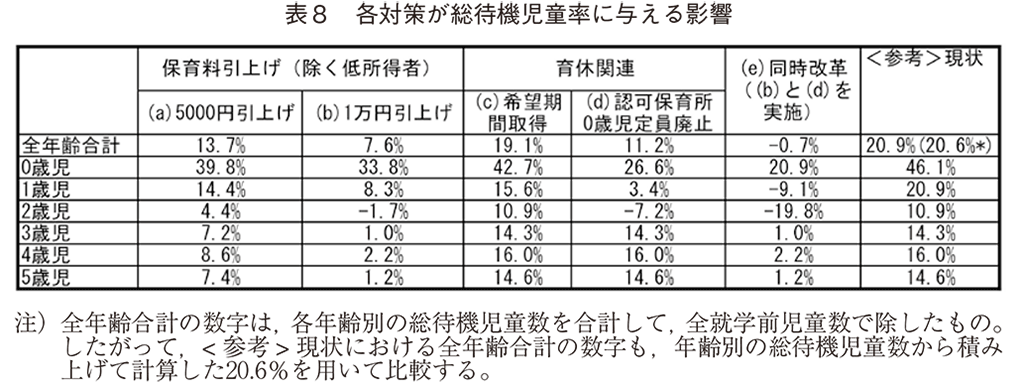
5.2 育休関連の対策
次に,育休に関連した待機児童対策について検討を行う。まず,表9はこのアンケート調査で尋ねている育休期間について,希望期間と実際の取得期間を比較したものである。希望よりも実際の方が,取得期間が短くなっていることがわかる。この調査票では,育休期間が希望よりも短くなった理由についても尋ねているが,「育休を希望期間分取得すると,取得後に保育所に入れなくなると思ったため」という理由が最も多く(64.9%),2位の「育休を取得すると収入が減るため」(25.9%)という理由を大きく引き離している。
実際,育休を早めに切り上げて,0歳児のうちに認可保育の申請を行うことは,待機児童問題が深刻な都市部では,もはや保活の常識である。新年度の入所申請において,空き定員が一番多いのは0歳児クラスであり,育休明けに1歳児クラスに申請するのでは空きが残っていない可能性がある。また,認可保育所の0歳児クラスに入所出来なかった場合でも,認可外保育施設に0歳児のうちに預けることにより,認可保育の選考時におけるポイント(選考指数)が上がる自治体も多い。
このため,身体的に無理をしても育休を早めに切り上げ,0歳児クラスに申請することが合理的な行動になってしまう。もし,育休明けにも空き定員がきちんと確保され,望み通りの育休期間を安心して取得できる環境整備が行われれば,0歳児の定員を1,2歳児に振り向けて大幅な定員増を図ることができる。東京都では2018年度から,1歳児までの育休取得を促進す【16頁】るために,新設の認可保育所の空き定員や余裕スペースを有効に活用して1歳児を緊急的に受 け入れる一方(緊急1歳児受入れ事業),もし育休明けに待機児童になった場合でもベビーシッ ター代を月額最大28万円まで補助することにして(ベビーシッター利用支援事業),安心して 育休を取得するための環境を整備しつつある。
そこで,希望通りに育休期間が取得できた場合の効果を試算してみよう。表9には希望育休取得期間と実際の取得期間が表示されているが,その差のうち,①1年から1年7ヶ月未満と,②1年7ヶ月から2年未満の合計である6.3%が0歳児の需要減少に寄与し,③2年以上の9.8%が1歳児の需要減に寄与するとした。それぞれの数字に,サンプルから計算した育休取得割合の53.8%を乗じて,各年齢の需要(受諾確率)から差し引いた。その結果が表8(c)であるが,総待機児童率の減少は約1.5%ポイントにすぎない(全年齢合計)。抜本的な効果を期待するには,東京都江戸川区が公立認可保育所で実施しているように,0歳児定員自体を全て廃止し,保育ママ等の利用に誘導するような大胆な施策が必要なのかもしれない。
そこで,表8(d)では,認可保育所の0歳児定員をすべて廃止し,その分の定員増を1・2歳児に同数ずつ振り分けた場合の効果を試算した。保育士配置基準の違いにより,0歳児から1・2歳児に認可保育所の定員を振り替えた場合には,定員数は2倍に増えると想定し,各年齢の保育サービス利用率に同数ずつ割り振った。また,0歳児定員を廃止した場合に,育休を取得可能な人々は0歳の間は育休を取得すると想定し(もしくは,そのような誘導策を講じると想定し),0歳児の受諾確率をその分少なく見積もった。すなわち,0歳児の受諾確率を従前の受諾確率×(100%−育休取得割合の53.8%)として計算した。0歳児だけではなく,1・2歳児にも大きな効果があるため,全年齢合計の総待機児童率をほぼ半減させることができる(11.2%)。
最後に,表8(e)には(b)中高所得者の1万円の保育料引き上げと,(d)認可保育所の0歳児定員廃止を同時に実施した場合の効果が試算されている。各年齢別の総待機児童率にはばらつきが見られるものの,全年齢合計の総待機児童率は-0.7%と,トータルでみれば待機児童が解消された状態と言える16)。
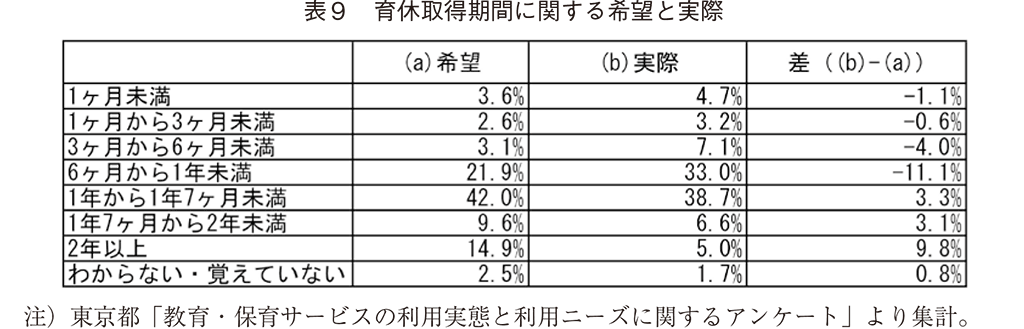
本稿は,東京都が2017年に実施した子育て世帯への大規模アンケート調査を用い,仮想市場評価法を使って,東京都の保育サービス需要を分析した。主な結果は以下の通りである。
第1に,潜在的待機児童率は19.5%と,待機児童率(1.3%)の14倍を超える大きさである。
第2に,現在の保育サービス供給量のもとで,総待機児童率をゼロにする均衡保育料(月額)は,全年齢合計で45,400円である。
第3に,中高所得者への月額5千円の保育料引き上げで総待機児童率は元の大きさの約3分の2,月額1万円引き上げで約3分の1となる。また,認可保育所の0歳児定員を廃止して,育休促進を図ることにより,総待機児童率はほぼ半減する。
現在,東京都をはじめ,全国で実施されている待機児童対策は,供給量を増やすための施策が中心である(鈴木(2018))。しかしながら,多額の公費を投じるこうした「物量作戦」は,国や自治体の苦しい財政事情を考えると,維持可能性に懸念がある。また,運営費用に比してあまりにも低い現在の保育料水準を維持し,もっぱら供給量拡大で待機児童問題に対処することは,効率性の観点からも問題が大きい。将来的には,本稿で検討した需要側に働きかける施策も,待機児童対策の重要な選択肢となるだろう。
栗山浩一(1997)『公共事業と環境の価値− CVM ガイドブック−』築地書館
清水谷諭・野口晴子(2004) 『介護・保育サービス市場の経済分析−ミクロデータによる実態解明と政策提言』東洋経済新報社
周燕飛・大石亜希子(2003)「保育サービスの潜在需要と均衡価格」『季刊家計経済研究』No.60, pp.57-68
周燕飛・大石亜希子(2005)「待機児童問題の経済分析」国立社会保障・人口問題研究所編『子育て世帯の社会保障』東京大学出版会
鈴木亘(2008)「保育制度への市場原理導入に関する厚生分析」『季刊社会保障研究』Vol.44 No.1, pp.41-58
鈴木亘(2009)「保育サービス準市場の現実的な制度設計」宮島洋・西村周三・京極騠宣編『社会保障と経済』東京大学出版会,第10章
鈴木亘(2012)「財源不足下でも待機児童解消と弱者支援が両立可能な保育制度改革〜制度設計とマイクロ・シミュレーション」『経済論集(学習院大学)』第48巻第4号, pp.239-267
鈴木亘(2018)『 経済学者,待機児童ゼロに挑む』新潮社
東京都(2018)「東京都保育ニーズ実態調査結果報告書」(東京都福祉保健局)
内閣府(2003)「保育サービス市場の現状と課題−「保育サービス価格に関する研究会」報告書−」(内閣府国民生活局)
八田達夫(2008)『 ミクロ経済学Ⅰ−市場の失敗と政府の失敗への対策』東洋経済新報社
肥田野登(1999)『 環境と行政の経済評価 −CVM<仮想市場評価法>マニュアル−』頸草書房
八代尚宏(2000)「福祉の規制改革」八代尚宏編『社会的規制の経済分析』日本経済新聞社
八代尚宏・鈴木亘・白石小百合(2006)「保育所の規制改革と育児保険〜少子化対策の視点から」『日【18頁】本経済研究』第53巻, pp.194-220
Zhou,Yanfei and Akiko Oish(i 2005)“Underlying Demand for Licensed Childcare Services in Urban Japan,”Asian Economic Journal, vol.19(1), pp.103-119