【41頁】
美味しさを生み出す情報に関する研究枠組みの検討
〜ガストロフィジックスの視点から〜
A research framework of the information which makes people feel tasting better for foods
〜 A perspective of gastro-physics 〜
学習院大学 上田 隆穂
本稿は味の評価を行う研究枠組みを検討している。この味の評価は,単に舌で味わう味覚のみならず,香り,見た目,雰囲気,テクスチャーも味の評価に重大な影響を及ぼしており,さらに本人の食文化や食べ物に付随する情報も大きな影響を与えているのである。それらが,脳で一体化し,味の評価を行う。このように多くの感覚を通じることをマルチセンサリングと呼び,味の評価は,このマルチセンサリングにより評価される脳の活動の結果から生み出される。しかしながら,食文化や情報が上記の仕組みで取り込まれたことはなく,従来全別個に取り扱われている。本稿では,過去の文献より,味覚の構造を整理・統合し,特に情報という点にフォーカスし,いかに情報が味の評価の決め手になっていくかの枠組みを検討している。
ガストロフィジックス,マルチセンサリング,感覚移転(Sensation Transference),生理,報酬効果,食文化,情報,ドーパミン,β - エンドルフィン,認知,感情,消費者情報消化モデル(CID モデル: Consumer Information Digestion Model)
『「食」という字は,「人」を「良」くすると書く。空腹でイライラした気分も,食べればおおらかになる。ヒトにとって「食」とは,精神と密接に結びついたものである。・・・「食」がエネルギーの補充のためではなく「よりおいしいものを」という報酬の側面を強めたとき,そしてリスクなく食べ物を食べられるようになったとき,食欲は制御することが難しい魔物になってしまったのかもしれない1)。』
以上のように人にとって,人生の基本である食であるが,このうち美味しさの研究は,食の分野において独自の展開を遂げている。ガストロフィジックスとも呼ばれる分野が近年注目さ【42頁】れ2),レストランでの実験も広く行われている。これらの研究によると単なる舌で味わう味覚のみならず,香り,見た目,雰囲気,テクスチャーも味の評価に重大な影響を及ぼしており,さらに本人の食文化や食べ物に付随する情報も大きな影響を与えているのである。それらが,脳で一体化され,味の評価が行われる。このように多くの感覚を通じることをマルチセンサリングと呼び,味の評価は,このマルチセンサリングにより評価される脳の活動の結果から生み出される3)。
本稿では,過去の文献より,味覚の構造を整理し,特に情報という点にフォーカスし,いかに情報が味覚の決め手になっていくかの枠組みを検討していく。
美味しさ評価の物理的属性には,食糧成分,鮮度,香り,食感(歯ごたえ,舌触り,喉ごし)等が挙げられる4)。しかしながら,「はじめに」で述べたように,他の多様な要素が関係してくる。図表1-1を見られたい。この図は,伏木亨(2008),中野久美子,伏木亨(2011)において「美味しさ」の構成要素を説明したものである5)。これらの研究の記述に従って,図の構成要素の説明を行う。
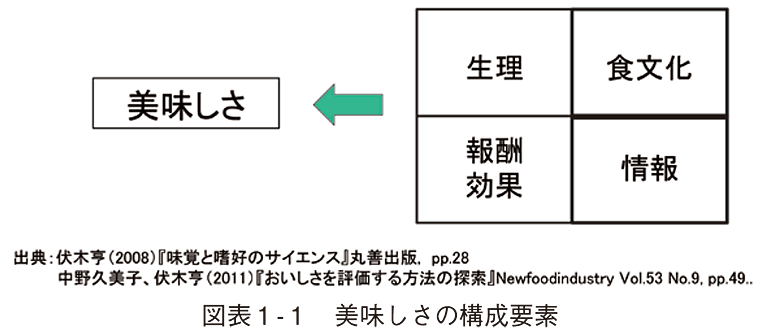
まず「生理」の項目であるが,人間には生理的な状態に基づく欲求があり,それに合致する食品はおいしく感じる。つまり,お腹が空けば,重要なものは美味しく感じるのである。たとえば,山の上で飲むビールは喉の渇きを癒すゆえに美味しく,逆に栄養のないサッカリンは飽きがはやいという現象がある。
次に「報酬効果」であるが,これは簡単に言うと,「やみつきになるおいしさ」である。原因は,脳の報酬効果であり,食べる直前に脳内では,ドーパミン増加し興奮状態を生み出し,期待を高めていく。そして食べてからβ - エンドルフィンが増加して,快感中枢を刺激するの【43頁】である。この事象をひき起こすのが,高度の嗜好性食品という言い方もできる。つまり特定の食材には人間をやみつきにさせる魅力があり,無条件に本能を揺さぶる美味しさとして他と区別する。高油脂化食品・砂糖などがその例である。いわゆる「やめられない,止まらない」という食品である。
3番目は,「食文化」である。人間や民族の文化において発展してきた酒や食などの歴史と嗜好的に合致する慣れたものは,安心感が感じられる。つまり子供の時から慣れ親しんで,食べ続けているものは美味しく感じるものである。反対に,民族や集団の文化では理解できない味や風味は違和感が残る。たとえば,くさや,鮒ずしはその食文化のない所では,美味しくは感じにくい。ましてや虫食などは論外であることが多い。
4番目は,「情報」である。この情報による先入観がリードする美味しさというものがある。これは他の動物にはない,人間だけがもつ特有の美味しさであり,安全や美味などの外来情報が,脳内での味覚の処理に強い影響を及ぼすことがある。たとえば,希少性や重要な伝統があることや,作り手の大変な苦労により作られることなどの情報が付加すると,当該食材は実際以上の価値を持つことがある。いわゆる物語マーケティングが作用すると考えてよい。
この情報がマーケティング上,活用可能で非常に重要であり,注目に値する。つまり,視覚的な情報,知名度,健康情報,安全性,価格価値などが考えられる。この情報には食文化情報も考えうるため,この2つを融合させて考えることも必要であろう。ここで図表1-2を見られたい。
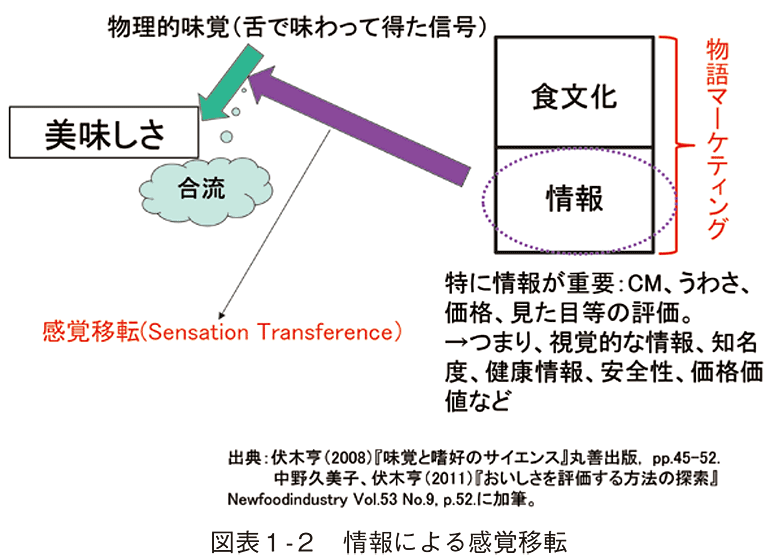
この図表では,食文化も含む情報が,舌で評価した味覚(物理的な味覚と定義)に合流し,ここで実際に感じる1つの「美味しさ」が脳内で統合される。この情報群が合流し,味そのものに影響を与えることを感覚移転(Sensation Transference)と呼ぶ。物語マーケティングによる「感情移入・共感」という表現はこのプロセスを表したものである。
【44頁】この感覚移転を少し説明しておく。Smith(2015)によると,視覚情報に関してではあるが,その定義は以下の通りである6)。
『対象そのものではなく,その対象がどう見えるかに基づいて,人々が創り出す無意識の評価』
Smith(2015)による事例も挙げておこう。
- 例1:
- 青い容器に入っている食べものは塩辛く感じ,赤い容器に入っているものはより甘く感じる。
- 例2:
- 高いスーツを着ている魅力的な人は実際よりも知的に見え,ボロのジーズやパーカーを着ている,もじゃもじゃ頭の人は,実際よりも知的には見えない。
- 例3:
- コカ・コーラ社
- コカ・コーラ社が,絶滅危惧種の白熊を救うキャンペーンとして,赤い缶から白い缶に変えた時,缶の色が変わっただけなのに,ロイヤル顧客はコークの成分が変わったと断言した。パッケージの色の変化が人々に味の変化を感じさせたのである。
- 例4:
- マーガリン
- ミスター「感覚移転」と呼ばれるLouis Cheskinは,マーガリンの色が黄色くて,アルミフォイルに包まれている原因を作った。1940年代,マーガリンは日常的に買われるほどポピュラーではなかった。便宜サンプルで実験を行ったところ,白いマーガリンを,バターのように黄色くしたら,人々はマーガリンとバターの味を見分けることができなかった。またマーガリンをアルミフォイルで包んだら,この傾向は強化され,マーガリンの売り上げは急上昇した。
- 例5:
- 7Up
- これもCheskinの事例だが,彼は,7Upの缶の色を多様に試してみた。その結果,缶 の黄色を強化したら,人々は急にその飲料にレモンの味を感じだすことを発見した。
しかし,見た目という視覚情報だけでなく,食感や重さなど多様な要素がこの『感覚移転』に含まれる。とすれば「美味しさ」を決める重要な要素である,食文化や情報も感覚移転で考えても間違いはないだろう。
「感覚移転」別の定義も見ておこう。Johnsによると感覚移転とは,『モノ自体だけでなく,関連する2次的な感覚inputにもとづいて,製品,サービス,人,またはイベントの無意識の評価が行われること』となる7)。ここで用いられている事例も視覚情報であるが,以下の通りである。
- 事例:
- ビジネスミーティングに行って,ショートパンツとサンダルで誰かが現れる。その人についてどのような判断がなされるだろうか?この人は,プロフェッショナルではない?備えのない人?などである。このミーティングがサーフショップのオーナーとのものでない限り,おそらく人々は,その服のためだけに,この人の能力に疑問を抱く【45頁】のではないだろうか。現実には,この人の能力が高いこともありうるが,その外見は,会議の雰囲気とは相反している。つまり,第一印象に二度目のチャンスはないということである。
感覚移転は,潜在意識下で毎日起こっている。多様な情報の中で,印象的な情報が1つの一般的な印象を構成する。その印象が正確かどうかはわからない。Johnsによると,たとえば商品の購入,店舗への訪問,友人との付き合い,テレビの視聴時などの中に含まれる印象的な情報から発生するのである。彼は,会社のウェブサイトが多くの場合,見込み客がブランドとやり取りする最初の場所であるため,この概念はマーケティング上,重要だと指摘している。
繰り返しとなるが,重要なのは製品やサービスそれ自体だけではない。印象的な情報も重要であり,それが製品の全体的な印象を構成する。これは「美味しさ」においても同様である。さらに「美味しさ」を構成する枠組みを検討してみる。
次に図表2-1を見られたい。これは今田(2005)による,味を評価する構造図である。この考え方によると,感覚→知覚→味という連鎖があり,ここから美味しさ・まずさへの評価に感情と認知が介在している。味評価に関する物理的属性以外に多くの感覚が加えられており,マルチセンサリングの考え方を導入している点で評価ができる。問題点としては,この図には前述の食文化や情報の記述がない。これらをどう扱うかがマーケティング視点からは重要となる。
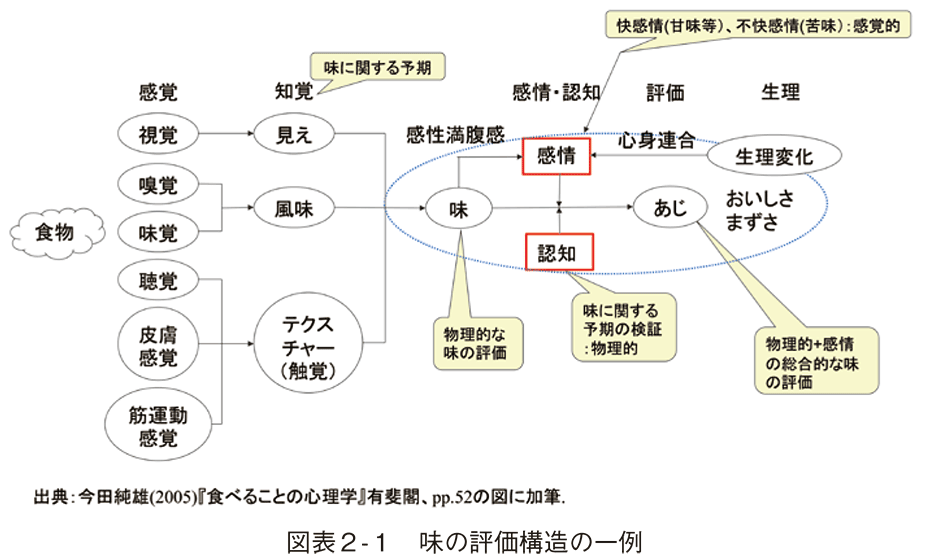
食文化や情報は,おそらく『認知』と『感情』のところで影響するものと考えうる。味の『予期』も含めて考える必要があり,この図表2-1においては,主に点線部分に注目したい。こ【46頁】 の点線部分に食文化と情報を加えると図表2-2のようになろう。食文化とは,食に関する過去の経験により,蓄積されたものであり,感情的な要素も認知的な要素も含まれる。たとえば感情的なものとしては,ふるさとを思い出させることであり,認知的なものとしては,ふるさとでとれた野菜・魚に関する客観的情報などが含まれよう。また情報においても,感情的な情報と認知的な情報が含まれる。たとえば感情的な情報としては,作り手が込めて育てた物語が呼び起こす感動などがあり,認知的な情報としてはオーガニック野菜やオンリーワンである野菜などの客観的情報があろう。
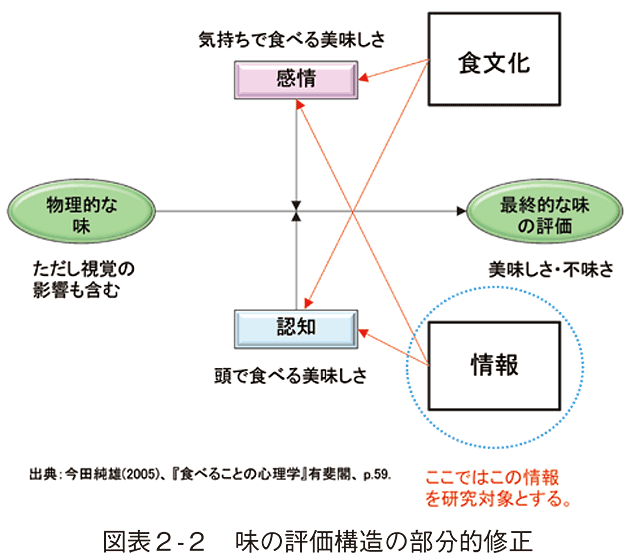
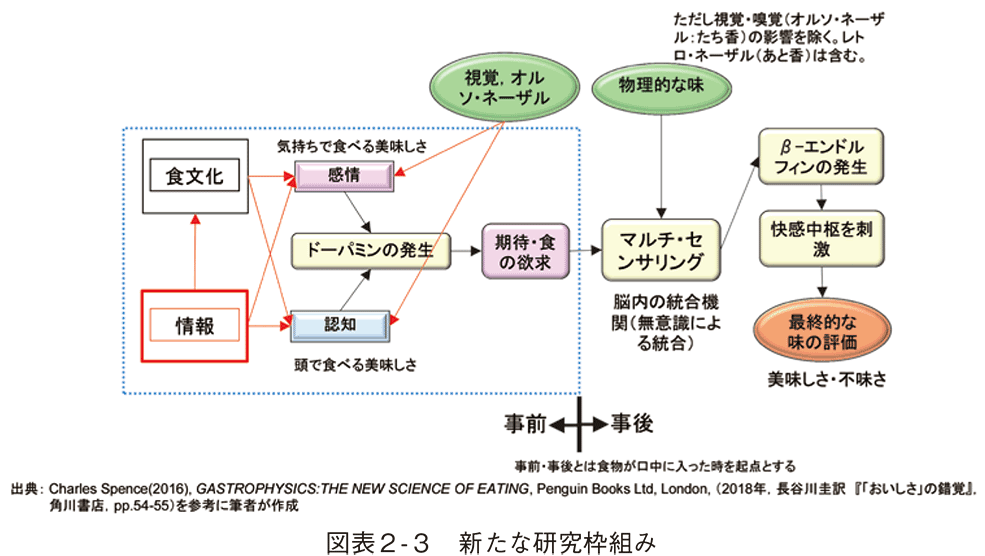
以上の図表に記された枠組みを合成し,新たに発展させたのが図表2-3である。マーケティ【47頁】 ング視点では,起点は情報となり,ここから感情・認知に影響を与えつつ,また食文化を刺激する場合には,食文化の項目を経由し,感情・認知に影響を与える。この感情と認知はドーパミンの発生を脳に促し,ここから美味しさへの期待や食への欲求を強化する。また情報以外にも食の見た目(視覚)やオルソ・ネーザル(たち香:嗅覚)が感情や認知に影響を与える。そしてこの美味しさへの期待や食への欲求と物理的な食の味(味覚)が合わさって統一され(マルチセンサリング),脳内にβエンドルフィンを発生させ,快感中枢を刺激して最終的な味の評価につながると考えられる。図中にある事前・事後は,事前側,つまり食物が口に入る前の段階に,美味しさへの期待や食への欲求までが入り,そして事後の,口に入って以降がマルチセンサリングから最終的な味の評価の部分となる。この図表に登場するドーパミンについて言及しておくと,このドーパミンは,期待によって美味しさを感じさせる脳内に出現する物質である。伏木(2005)には次のような記述がみられる8)。
『やみつき行動の原動力となっているのはおいしさの期待によって脳内に出現するドーパミンです。ドーパミンがたくさん出るほどやみつきは深刻だということになります。』
このやみつき感を与える食材は,『今までのところダシのうま味,砂糖水,油以外に執着をもたらす食素材は見あたりません。』となっている9)。そしてドーパミンによるやみつき感の作用しては,『もっと食べたいという欲求はドーパミンが担当しています。・・・舌がとろけるほどおいしいものを口に入れたら,「おいしい」という感激と同時に「早く次の一口を食べたい」という切ない欲求が高まります。これがドーパミンの作用であろうと思います。』と述べられている10)。つまり,このドーパミンは,食欲をたかめ,味への期待を高める作用をなすのである。同時に味に関するセンサーが研ぎ澄まされ,「美味しいであろう」という構えが対象者にできると思われる。つまり,「情報→ドーパミン→期待・食べたい欲求→美味しさの知覚」という流れがあると想定される。
本研究で対象とするのは,図表2-3の事前側であり,図表でいえば,点線で囲んだ部分である。ただし,ドーパミンに関してはその発生に筆者がアプローチできないため,『ドーパミンの発生』部分は割愛することになる。その他の部分で,アンケートおよび,可能であるならば,実験による実証研究を行う予定である。
この図表2-3における情報に関しても多様な切り口があり,その構造も的確に仮説的に構成しなければうまく分析はできない。この情報に関して,少々事例を挙げて考察してみる。
●情報の事例1
『人間は,不思議な動物で,口に入れる筒の味覚のほかに,とんでもない暦のひき出しがあいて,その思い出を同時に噛みしめる。土にうまれたものを喰うことの楽しみ,といってしま【48頁】えばそのとおりだろうが,口に入れるものが土から出た以上,心ふかく,暦をくって,地の絆が味覚にまぶれつくのである。』11)
この文章は,水上勉(1982)『土を喰らう日々』に出てくるものであるが,ここでは,すでに広く知られているが,季節における旬の情報が重要だということを意味している。感情が入り混じる感じがするが,旬が美味しいという感情を刺激しているわけで,認知に分類すべきだろう。
●情報の事例2
同様に同文献からの引用であるが,
『大の大人が,なぜ,祭礼の夜に太鼓がなれば腰がうくのだろう。小さいころ親に肩車されて,神社の人だかりをみた記憶がなつかしいからである。露店で売られていたカルメ焼き,綿菓子,一銭洋食。あのソースの焼ける匂いが鼻に迫ると,泣きたいような気持になる人がいる。男にしても,女にしても,味覚はその人の生にひそんだ精神史だといったのはこの謂(いい)であって,私たちは,その美味だった昔の味を忘れて生きているにすぎない。太鼓の音が,それをよびおこしたまでのことだ。料理もまたこの例にもれぬ。』12)
ここから読みとれることは,個人個人に食文化があり,それを刺激する情報を与えれば,それが美味しいという評価感情を刺激するのであろう。したがって,これは情報が食文化を介在して味の評価に影響を与える例だと考えられる。
●情報の事例3
青山謙二郎・武藤崇(2017)には,以下のような例がある13)。
『アメリカのコーネル大学のワンシンク(Wansink.B.)のグループによる研究(Wansink.VanIttersum.&Painter,2005)である。彼らの研究では,料理の名前をそっけない通常の名前にするか,凝ったおいしそうな名前にするかで期待を操作した。例えば,赤インゲン豆にライスを添えた料理を,単に「赤インゲン豆ライス添え」とメニューなどで表示するか「トラディショナル・ケイジャン風味の赤インゲン豆ライス添え」と凝った名前で表示するか,あるいはズッキーニのクッキーをそのまま「ズッキーニ・クッキー」と表示するか「お祖母ちゃんお手製ズッキーニ・クッキー」と表示するか,といった操作である。凝った名前の方がおいしそうな期待を高めるが,それによって実際に食べた後の評価も上がるのだろうか。実験は,主に教職員が利用する大学内のカフェテリアでのフィールド実験として実施された。対象となった料理は6種類で,それぞれがある日には凝った名前で表示され,別の日には通常の名前で表示された。カフェテリア形式のレストランなので,来店した人は,自分で好きな料理をとって,最後に精算のためにレジの列に並ぶ。その列に並んだ時に,対象となる食品を選んだ人に対して,アンケートへの回答を依頼した。このようにして,140名から回答を得ることができた。
・・・味の評価(9点満点)は, 通常の名前では平均値が6.8点,凝った名前の条件では7.3点であり,凝った名前の方が同じ食品を食べてもおいしいと感じていたことがわかった。・・・
【49頁】さらに,アンケートの裏面には,自由に感想を書いてもらった。それらのコメントを分析したところ,ポジティブな内容のコメント数は,凝った名前の料理を食べた場合に平均1.9個であったのに対し,通常の料理を食べた場合には平均0.9個で,凝った名前の方が有意に多かった。一方,ネガティブな内容のコメント数は,凝った名前で0.8個,通常の名前で0.7個となり有意な差はなかった。このように,凝った名前で料理を表示すると,実際には同じ料理であっても,料理の味の評価が高くなるだけでなく,見た目の印象など,さまざまな側面に影響を与えるのである。』
この例では,ポジティブと思われる説明がつくと,食物の味の評価は高くなることを示している。ただ味評価を高める情報の種類への言及はない。
●情報の事例4
同じく青山謙二郎・武藤崇(2017)に記載されているブランド情報に関する例である14)。
『アメリカのスタンフォード大学のロビンソン(Robinson.T. N.)らは,マクドナルドのプランドが付けられることで子どもの食物の好みが増加するかどうかを検討した(Robinsonel etal., 2007)。
研究に参加したのは,経済的に豊かではない家庭のための保育所に通う3歳から5歳の子ども63名であった。対象となった食物はハンパーガー,チキンナゲットなど・・・5種類であった。いずれの食物も,一方はマクドナルドのロゴが付けられており,他方はそれが省かれていた。ハンパーガー,チキンナゲット,フライドポテト,ミルクは実際にはすべてマクドナルドのものを使用した。ベビーキャロットはマクドナルドで扱っていなかったので,マクドナルドのものではなかった。
研究者がロゴ有りとロゴ無しの食物のペアを1種類ずつ子どものところに運んだ。その後,どちらがマクドナルドのものかを聞いて,子どもが理解できていることを確認した。その上でペアの食べ物を1つずつ味見してもらい,どちらの味が良いかもしくは同じかを答えてもらった。
結果は・・・ハンパーガーだけは.ロゴ有りとロゴ無しの間に有意な差はなかったが他の4種類のすべてにおいて,ロゴ有りの方が,味が良いと答えた子どもが多かった。つまり,子どもはマクドナルドのロゴによって味の評価が変わったのである。そして,その効果は,実際にはマクドナルドで売っていない食べ物(キャロット)にまで及んだのである。
アメリカの子どもはマクドナルドを好んでおり,したがって,マクドナルドのロゴにより食べ物に良い期待を抱くと考えられる。そのことがプランドのロゴによっておいしさの評価を変えたのだと考えることができる。』
この事例もポジティブな情報が付加すれば,味の評価は向上するということを示している。特にこのケースの場合,情報はブランドであり,そのブランド力に応じて,効果は高くなると考えられる。また同じくこの研究では,ワインに関する実験にも言及しており,産地の知名度によって同様の結果が得られたことを示している15)。
以上,この種の情報は,効果があるのは当然だと考えられている事が多く,枚挙にいとまが【50頁】ないほどに存在する。しかしながら,この情報の構成にメスを入れたものはいままでになく,情報の分析枠組みを図表2-3に取り入れて,実証研究,実験へと駒を進めるのが正しいプロセスだと考えられる。この情報部分の枠組みに有用と考えられるのが,「消費者情報消化モデル」(CID モデル: Consumer Information Digestion Model)である可能性が高い。
これを図表2-4に挙げておく。これを図表2-3に融合させるのは,次の課題となる。
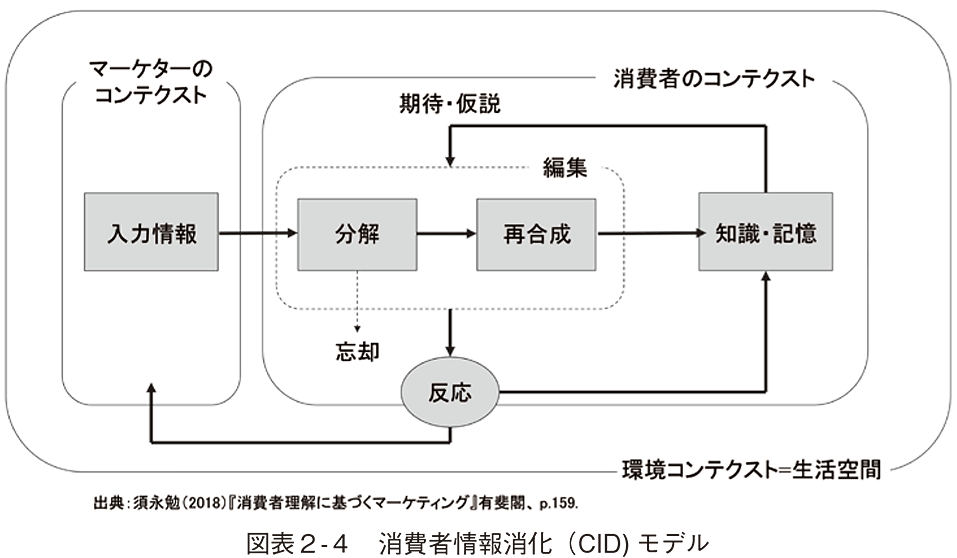
この研究においては,従来のマーケティング研究には,ほぼ見られなかった味に関する評価を扱っている。それは美味しさを生み出す情報がいったい何であるのかの研究枠組みを定めることである。まだまだ不完全さは否めないが,美味しさ評価に影響を与える情報構成を図表2-4から形成し,これを図表2-3に入れ込むことによって枠組みは完成に近づくと思われる。この研究が実証研究にすすみ,かつ実験に進めば,いかなる情報をどのような順序で組み合わせ,提示すれば消費者の感じる美味しさが増すのかに大きなヒントを与えることとなり,地域の食材をブランド力を強化でき,販売拡大につながり,地域活性化に有用となろう。そして食品メーカー,小売,外食産業にも大きな影響を及ぼすのではないかと考えられる。
(注)本研究は科研費基盤研究B(19H01540)(代表:上田隆穂)によるものである。
【51頁】Johns, Robert ACCOUNT SUPERVISOR
https://blog.unincorporated.pro/sensation-transference
Smith, Nyla (2015),“The Secret Life of Sensations: How Design Affects Perception ”,Tuesday, December 22,
http://nvision-that.com/design-from-all-angles/the-secret-life-of-sensations-how-design-affects-perception
Spence, Charles(2016), GASTROPHYSICS:THE NEW SCIENCE OF EATING, Penguin Books Ltd, London,(長谷川圭翻訳(2018),『「おいしさ」の錯覚』角川書店).
青山謙二郎・武藤崇(2017)『心理学からみた食べる行動』北大路書房
今田純雄(2005)『食べることの心理学』有斐閣
櫻井武( 2012)『食欲の科学』講談社
須永勉(2018)『消費者理解に基づくマーケティング』有斐閣
中野久美子,伏木亨(2011)『おいしさを評価する方法の探索』Newfoodindustry Vol.53 No.9, pp.49-56.
中村卓(2017)「食感による美味しさのデザイン」 『特集4 おいしさの評価技術 食品と開発』, Vol. 52 No. 4 ,pp.1-4.
伏木亨(2005)『コクと旨味の秘密』新潮社
伏木亨(2008)『味覚と嗜好のサイエンス』丸善出版
水上勉(1982)『土を喰らう日々』新潮社