消費者の購買特性によるセグメントとジョイント・スペースを持つブランド選択モデル
杉田 善弘
近年,消費者の購買行動を分析する際に有益なモデルとして,ジョイント・スペースを持ったブランド選択モデルが提案されて来た(杉田(2015,2011),長谷川(2011),里村(2004)など)。これらのモデルは,一般的なブランド選択モデルにジョイント・スペースを導入し,ブランドの競合状況と家計の選好を把握するためのものである。ジョイント・スペースは,それぞれの次元が消費者のブランド選択の基準である多次元(軸)上での代替ブランドの位置(プロダクト・マップ)に,それらの次元での消費者にとっての理想の位置であるアイデアル・ポイント(理想点)あるいは理想とする方向であるアイデアル・ベクトルを加えたものである。最近の研究は,杉田(2015,2011)や長谷川(2011)のモデルに見られるように,ジョイント・スペースを持ったブランド選択モデルに消費者の過去の購買による影響や消費者の異質性を追加してモデル化する提案をして来た。例えば,杉田(2015)のモデルでは,アイデアル・ポイントが過去の複数の購買(購買履歴)に依存して,家計毎にダイナミックに変化することとアイデアル・ポイント以外にも存在する家計のパラメター異質性がモデル化されている。
本研究の目的は,この杉田モデル(2015)をさらに改良し,消費者間に存在するパラメター異質性を消費者毎の製品カテゴリーの購買特性などの独立変数によって説明することである。製品カテゴリーの購買特性とは,例えば,それぞれの消費者のその製品カテゴリーに属するブランド全体の購買量や商品棚の端に陳列スペースを作ったエンド陳列への反応などを指す。製品カテゴリーの購買量が多い消費者はたまにしか商品を買わない購買量の少ない消費者とは異なり,商品の価格に敏感であろうと考えることができるし,商品を計画的に買わず,店舗内で意思決定する消費者は,店舗内で行われるエンド陳列のようなプロモーション活動によって製品を認知し,その場で意思決定する可能性が高いので,自ずと購買を計画的に行っている消費者とは重視する軸も異なる可能性が高い。
本論文のこれからの構成は次のようである。まず,実際の購買データからジョイント・スペースを構築することによって,ブランドの競合状況と消費者の選好を明らかにしようとするモデルの展開をレビューする。なお,このレビューは,本論文で提案するモデルの位置づけを明確にするために,杉田(2015)のレビューに手を加えたものである。そして,本研究で提案されるモデルを紹介し,モデルをスキャンパネル・データに適用した結果を報告する。最後に,今後の課題について議論する。
【116頁】
2.1 ジョイント・スペース・マップ
ひとつの製品カテゴリーで競合しているブランドの位置(ポジショニング)を多次元上でデータから統計的に再現したものはプロダクト・マップあるいは知覚マップと呼ばれる。通常は,マップを理解しやすくするために,次元は2次元で,ブランドはマップ上の点として表され,それぞれの軸は消費者がブランドを知覚(イメージ)するための基準と考えられている。プロダクト・マップ上で,どの製品が消費者に好かれるか(消費者の選好)は製品の位置からだけではわからない。知覚と選好は必ずしも一致しないからである。ある商品を高級品と知覚することと高級品にニーズがあることとは同じではない。マップ上で消費者の選好を特定できれば,消費者に好かれる良い位置を知ることができる。選好をデータから特定することは選好分析と呼ばれ,そのためにはふたつの方法が用いられる。ひとつは,マップ上で消費者にとっての理想の位置を特定することである。もうひとつは,マップ上で消費者にとって製品の価値が増す方向をマップの軸の重要度から特定することである。この方向は矢印としてあらわすので,アイデアル・ベクトルと呼ばれる。また,理想の位置はアイデアル・ポイントと呼ばれる。知覚マップと選好分析は,段階的にまずマップを作り,そのあと選好分析を行う場合もあれば,同時に行われる場合もある。段階的に行われる場合の選好分析は選好の外的分析と呼ばれ,同時に行われる場合は選好の内的分析と呼ばれる。消費者の選好(アイデアル・ベクトルあるいはアイデアル・ポイント)と知覚を併せたものがジョイント・スペースである。
実際にマップを作るためのデータとして多く用いられるのが,アンケートからのデータである。しかし,このデータは,消費者の記憶にある知識や考えを基にしたもので,実際の購買行動から得られたものではない。消費者の記憶や考えと実際の行動が一致しないことはマーケティングでは良く知られている。そこで,近年,家計毎の実際の購買データであるスキャンパネル・データから,選好の内的分析によるジョイント・スペースと価格などのマーケティング・ミックス変数への反応を同時に推定しようとする本研究で扱うブランド選択モデルが提案されてきた。家計毎のブランド選択と店舗でのマーケティング変数が観測されたスキャンパネル・データを用いて,これらのマーケティング変数の効果を織り込んでマップを作れば,マーケティング変数の影響を排除し,しかも消費者の実際の行動を基にしたジョイント・スペースを作ることができる。
ジョイント・スペースからのマップを作る際の大きな問題は,消費者のイメージにも選好にも個人差があり,本来ならジョイント・スペース・マップは消費者の数だけあるはずだということである。しかし,それではマップが多数になりすぎて,マップから戦略的示唆を得るのが逆に難しくなる。そこで,消費者間の知覚の差は無視できるほどだが,選好の差は大きいと考えて,ブランドの布置は消費者間で変わらないということにして,選好の異質性を何らかの形でモデル化することが多い。つまり,高級な車は誰が見ても高級だが,高級な車が好きかどうかは大きく違うと考えるということである。さらにスキャンパネル・データは,通常一度しか行われないアンケート調査と異なり,家計の購買を経時的に把握しているという特徴があり,消費者の知覚と選好は時間が経過しても安定しているわけではないということも考慮すること 【117頁】 ができる。ここでも,知覚は,データの期間が1〜2年と比較的短いこともあり,安定していると仮定するのが通常である。選好は,過去の購買経験による家計の好みの変化を反映するブランド・ロイヤルティー変数がモデルのフィットを大きく改善することからも,消費者の好みは変化していると考えられ,そのことをジョイント・スペースに反映させるのである。
2.2 ジョイント・スペースとマーケティング変数を組み込んだブランド選択モデル
本研究で扱うモデルは,製品カテゴリーの購買が起きたとして,どのブランドが選ばれるかをモデル化するブランド選択モデルである。その中でもジョイント・スペースとマーケティング変数を組み込んだブランド選択モデルの基本となるモデルを紹介しよう。このモデルでは,家計が各ブランドに対して感じる効用は,ブランドの布置とアイデアル・ベクトルあるいはアイデアル・ポイントとマーケティング変数によって定まる確定的効用と誤差項に依存すると仮定する。誤差項は消費者の心の揺れなどのランダムに変化する部分で,確率的に変化すると考える。ブランドの布置とアイデアル・ベクトルまたはアイデアル・ポイントによるジョイント・スペースとマーケティング変数の部分は消費者毎に確定するので確定的効用と呼ばれる。誤差項の確率分布が第2種の極値分布であらわされる場合は,以下のようなマーケティング・サイエンスで人気が高いロジット・モデルによって定式化され,ブランド選択確率は確定的効用に比例する。
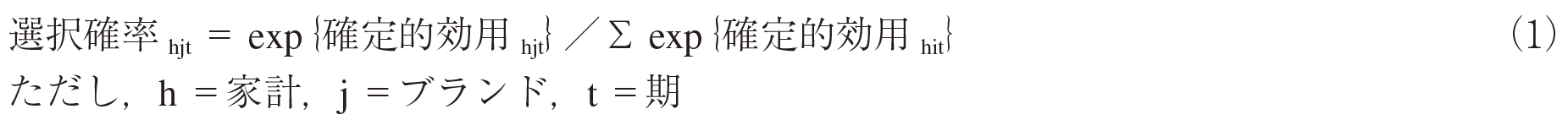
確定的効用をジョイント・スペースからの効用とマーケティング変数からの効用に分けて表すとブランドの効用は次のようになる。
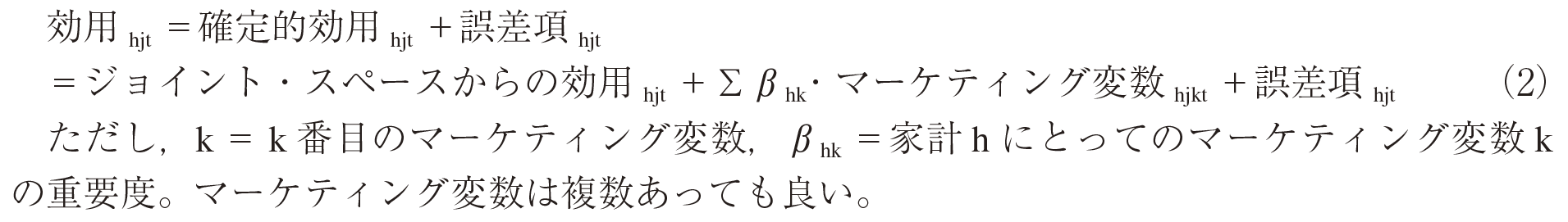
ここで,ジョイント・スペースからの効用はアイデアル・ベクトル・モデルの場合,
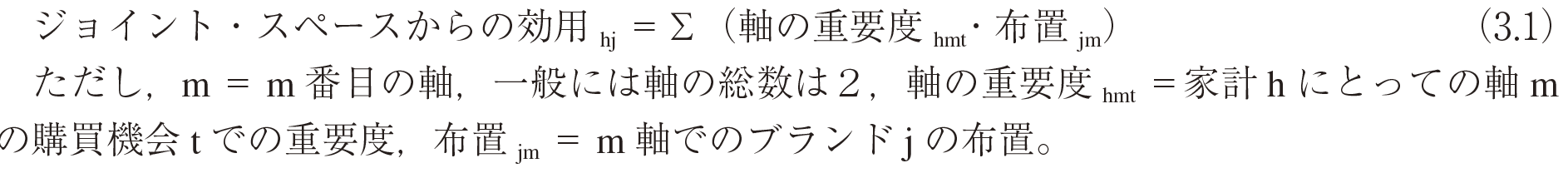
となり,アイデアル・ポイント・モデルで表すと,
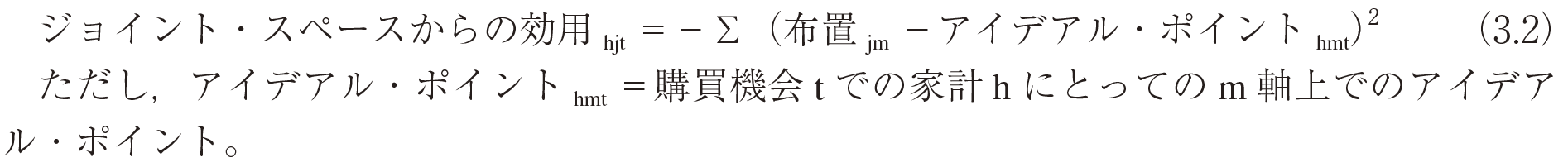
【118頁】
アイデアル・ベクトル・モデルでは,それぞれの軸の重要度(負の符号を持つこともある)と各軸でのブランドの布置の積の和でジョイント・スペースからの効用が決定されるので,重要度と布置の積が正で大きいブランドほどブランドの価値が高くなり,選択される確率が大きくなるということである。ここで,注意を要するのは,軸の重要度には家計を示す添え字がついていることとブランドの布置には家計の添え字がないことである。つまり,軸の重要度は家計に固有であるが,布置は全家計共通であることを示している。軸の数が2になっているのは,3次元以上ではマップが見にくいという理由である。このモデルにはマーケティング変数の効果も組み入れられており,例えば,商品が選択される可能性が高いのは安売りによるものかジョイント・スペースによるものかを知ることができる。そしてマーケティング変数k の重要度を示す,βhk にも家計を示す添え字h がついていて,マーケティング変数の重要度は家計ごとに違うことを示している。
アイデアル・ポイント・モデルでは,ブランドの布置とアイデアル・ポイントとの距離が少ないほうが効用を大きいと考えるので,ブランドの布置とアイデアル・ポイントとの距離であるΣ(布置jm −アイデアル・ポイントhmt)2には負の符号がついている。さらに,アイデアル・ポイントには,家計を示す添え字がついている。つまり,アイデアル・ポイントは家計に固有であるが,布置は全家計共通であることを示している。
このふたつの基本モデルからは,マーケティング変数の効果を除去したブランド価値の構造を理解することができるジョイント・スペースによるマップが得られ,ブランド価値を形作る基準とその重要度あるいはアイデアル・ポイント,マーケティング・ミックスへの反応とこれらの家計間での異質性を理解することが出来る。
これまでに提案された多くのモデルの違いは,基本モデルの長所をどう生かし,問題点をどのように扱うかである。特に,最近の多くのモデルが工夫しているのが,状況依存性と家計の異質性の取り扱いである。表1は,スキャンパネル・データとブランド選択モデルを用いて,選好の内的分析を行うモデルを五つの視点からレビューしたものである。五つの視点とは,アイデアル・ベクトル・モデルかアイデアル・ポイント・モデルかということ(モデル),消費者ニーズを前回購買ブランドというような状況に依存させているかということ(状況依存性),軸の重要度を考慮しているかということ(軸の重要度),マーケティング変数への反応を測定しているかということ(マーケティング変数),家計の観測された変数についての異質性以外のパラメター異質性をどう取り扱っているか(パラメター異質性)である。
表1からも分かるようにアイデアル・ベクトルとアイデアル・ポイントの人気は拮抗しており,ふたつのモデルを比べたElrod(1991)や筆者の研究でもアイデアル・ポイントを用いた方がデータへの適合度は少し優れているが大きな差はない。このふたつのモデルの大きな違いは,アイデアル・ベクトル・モデルでは軸の重要度が用いられ,消費者がどの軸にも同じ重みを与えているとは限らないということが認識されているが,アイデアル・ポイント・モデルでは,杉田(2015)のモデルを除けば,軸の重要度が用いられたモデルはないということである。
状況依存性というのは,同じブランド選択といっても消費者が直面している状況によってニーズが変化すると考えるもので,表1からも新しいモデルほど状況依存性をモデル化しているのが分かる。ブランド選択に関するデータを時系列でみることができるスキャンパネル・データを分析するモデル群なので,状況依存性と言うと,購買経験をモデル化することが多い。Erdem(1996)とInman et. al.(2008)は前回購買されたブランドの影響を前回購買ブランド・
【119頁】
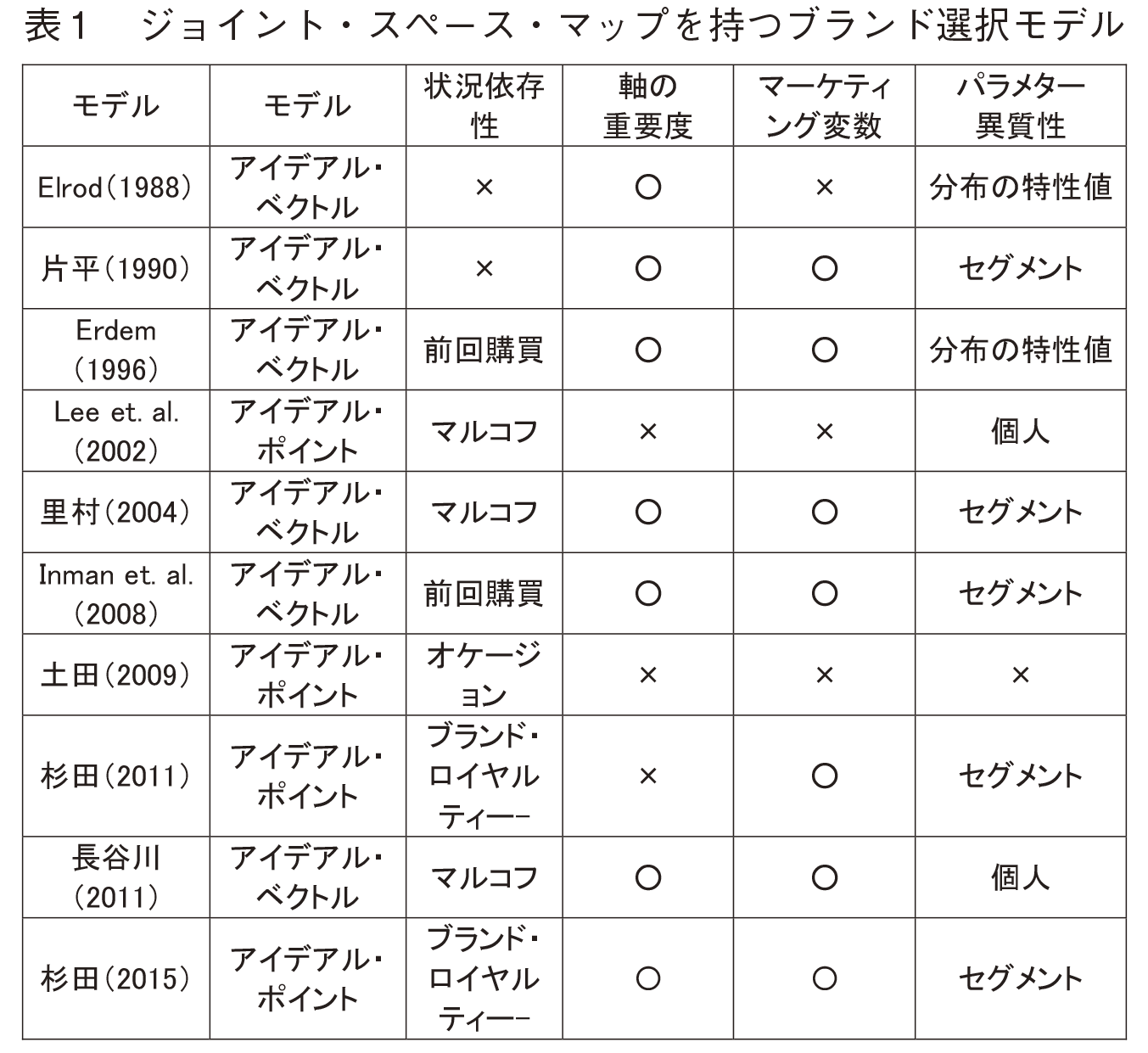 ダミー変数を用いてモデル化している。Lee et. al.(2002),里村(2004)そして長谷川(2011)は前回購買機会から一定の確率で変化,つまりマルコフ過程にしたがうニーズをモデル化している。杉田(2011, 2015)は前回購買だけではなく,過去の多くの購買経験に依存して変化するアイデアル・ポイント・モデルを構築した。土田(2009)は購買経験より一般的な購入オケージョン(時間帯と場所)によって,状況依存性を捕らえた。
ダミー変数を用いてモデル化している。Lee et. al.(2002),里村(2004)そして長谷川(2011)は前回購買機会から一定の確率で変化,つまりマルコフ過程にしたがうニーズをモデル化している。杉田(2011, 2015)は前回購買だけではなく,過去の多くの購買経験に依存して変化するアイデアル・ポイント・モデルを構築した。土田(2009)は購買経験より一般的な購入オケージョン(時間帯と場所)によって,状況依存性を捕らえた。
これらの実際の購買履歴からブランド選択モデルを用いて作ったマップの特徴のひとつは,マーケティング変数の効果を取り除いたマップを作ることであるが,Lee et. al.(2002)と土田(2009)のモデル以外はマーケティング変数をモデルに含包している。ここでパラメターの異質性というのは,家計の購買履歴のように変数として観測できるばらつきではなく,マーケティング変数への反応度のように推定しなくてはならないパラメターの家計間でのばらつきをいう。家計間のパラメター異質性の存在をモデル化しないと分析結果に偏りがおきるし,パラメター異質性はセグメンテーションや個々の家計への対応というように実際マーケティングを行う上でも非常に重要である。
この異質性に対処するためには,個々の家計ごとに推定をすれば良いのだが,問題は家計の購買データのサンプル数の少なさである。いくらスキャンパネル・データといってもそれぞれの家計について,ひとつの製品の購買データが100もあるわけではない。製品にもよるが,1週間に一度買われる製品でも100のデータが揃うには2年間かかる。この問題の一般的な解決策としては,パラメターの家計間でのばらつきに関して特定の分布を仮定するという方法が取られてきた。つまり,パラメターのばらつきが正規分布に従うなどと仮定する。こうすれば,パラメターの分布を用いて家計をプールすることができ,個々の家計のデータ不足を補うことができるからである。と言っても,1990年代初めまでは,仮定された分布の特性値(期待値と 【120頁】 分散)を求めるだけであったが,それ以降は連続的に値が分布する正規分布を仮定して,ベイズ統計の手法によって家計別パラメターを推定する方法とパラメターがいくつかの離れた値(この値をクラスという)に集まる離散分布を仮定して潜在クラス分析によって家計のそれぞれのクラスへの所属確率を推定するふたつのやり方が主流となった。潜在クラス分析でのクラスがマーケティングでのセグメントと考えられる。
異質性への対処から見ていくと,初期のモデルであるElrod(1989)とErdem(1996)のモデルは,連続分布を仮定して,分布の特性値を求めた。片平(1990)のモデルは潜在クラス分析を用いない方法でマーケット・セグメントへの所属確率を計算する独自の方法を提案した。Inman et. al.(2008)と杉田(2011 2015)は潜在クラス分析を用い,各家計のセグメントへの所属確率を推定した。里村(2004)と長谷川(2011)はどちらもベイズ統計の手法を用いて,前回購買機会に依存してアイデアル・ベクトルがマルコフ過程にしたがうとしたモデルを推定した。
パラメターの異質性に対処するための方法として,連続分布を仮定したベイズ統計と離散分布を仮定した潜在クラス分析のどちらがデータへの当てはまりがすぐれているかは判断が難しい。ベイズ統計のほうが良いとする研究(Allenby and Rossi 1999)もあれば,ベイズ統計はパラメターの推定に使われたデータにはより良く当てはまるが,家計毎のサンプル数が小さい場合,予測と推定値の誤差では潜在クラス分析に劣るとする論文(Andrews et. al. 2002)もあるからである。ベイズ統計の方が潜在クラス分析より優れているといわれる大きな理由は,ベイズ統計では各家計のパラメターを推定できるのに対し,潜在クラス分析ではパラメターは家計ごとには推定できず,各家計は一定の確率でそれぞれのセグメントに所属することになるからである。つまり,購買量など家計の特性はいろいろ異なるのにセグメントへの所属確率はすべての家計で一定というのは物足りないということである。次節では,家計の特性によってセグメントへの所属確率が異なる本論文の提案モデルを紹介しよう。
3. ダイナミックに変化するアイデアル・ポイントと軸の重要度のセグメント間の異質性を考慮したブランド選択モデル
3.1 モデルの構造
本論文の提案モデルは,家計の持つアイデアル・ポイントは過去の多くの購買経験に影響されうると考えたジョイント・スペース,マーケティング変数の効果,マーケット・セグメントごとに異なる軸の重要度を持つ杉田モデル(2015)に,家計の特性によって異なるセグメント所属確率を加えたブランド選択モデルである。このモデルの選択確率に関する式は基本モデルと同じであり,選択確率はロジット・モデル(式1)で与えられ,効用はアイデアル・ポイント・モデルを持つ式(3)に軸の重要度を付け加えた式(4)で表される。
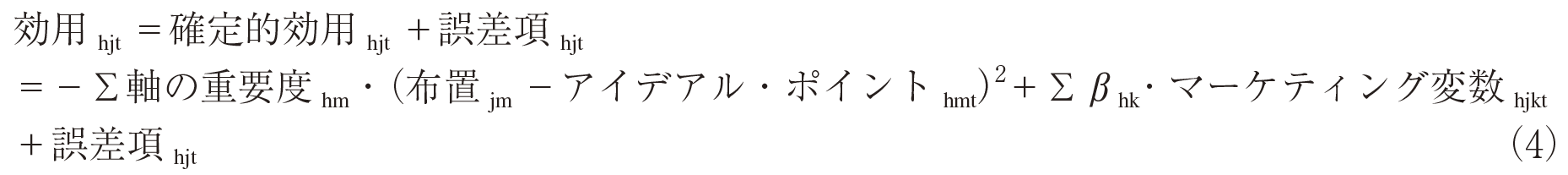
ただし,アイデアル・ポイントhmt =購買機会t での家計h にとってのm 軸上でのアイデア 【121頁】 ル・ポイント,軸の重要度hm =家計h にとってのm 軸の重要度 > 0。
式(4)は次のようにスケールを変えた,重要度を考慮しないアイデアル・ポイント・モデルとして書き換えることが出来る。
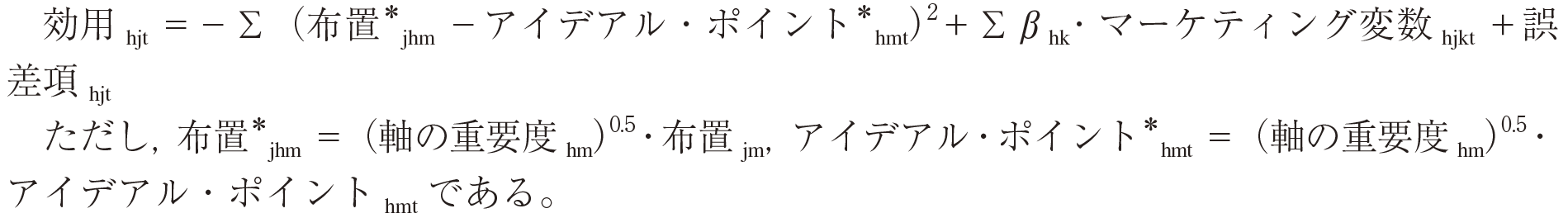
ここから分かるように,軸の重要度が全家計で同一の場合は,軸の重要度をひとつのパラメターとして扱うことの意味はない。軸の重要度を持ったアイデアル・ポイント・モデルは,家計の異質性を推定することが出来るベイズ統計や潜在クラス・モデルなどによって始めて推定可能となるモデルである。式(4)からも分かるように,このモデルでは,各軸からもたらされる効用は,その軸でのブランドの布置とアイデアル・ポイントの距離と比例して大きくなる不効用(嫌いさの度合=ペナルティー)という形でモデル化されるので,ブランドの布置とアイデアル・ポイントの距離が同じでも,軸の重要度が高ければ,その軸からもたらされる不効用は高くなる。逆に,重要度が低ければ,ペナルティーは小さい。したがって,相対的に重要度が高い軸が不効用に占める比率は高くなり,重要度が高い軸での優劣が選択確率に大きく影響する。相対的にどちらの軸が重要かという軸間の相対的重要度に加えて,それぞれの軸の重要度をマーケティング変数の係数(重要度)に比較しての相対的重要度も大切である。各軸の重要度がマーケティング変数の重要度に比べてより低くなると,ジョイント・スペースからの不効用は相対的に小さくなり,選択確率はジョイント・スペース以外のマーケティング変数に影響される度合いが大きくなるからである。
また,このモデルは,杉田(2015)モデルと同様に多くの購買経験を反映したアイデアル・ポイントを持っている。つまり,家計は,前回のみではなくそれより以前の購買による経験にも影響されていて,ニーズに多くの購買経験が反映されている可能性があるということである。表2は,ふたつの家計A,B どちらもが,ふたつのブランドを購買していると仮定した購買機会毎の架空のブランド選択を表にしたものである。
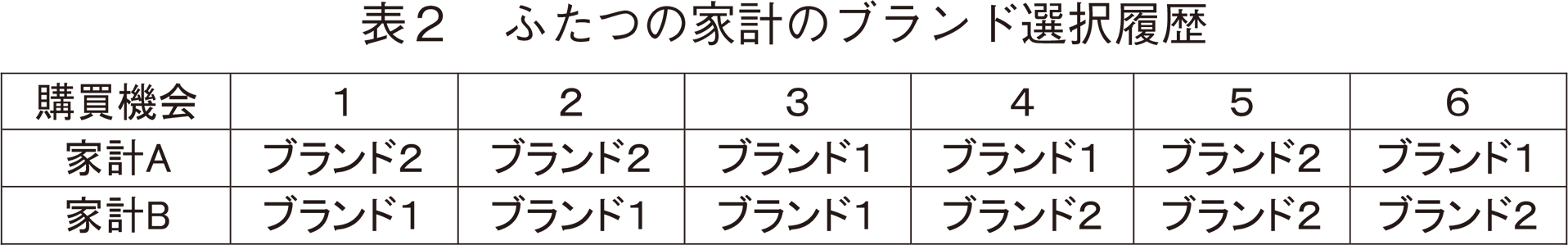
どちらの家計もふたつのブランドを半分ずつ購買し,ブランド・シェアは各ブランド50%で同一であるが,家計A はふたつのブランドを交互に購買し,複数ブランドに対するロイヤルティーを示し,家計B は最近3回ブランド2を購買している。この場合,家計A のアイデアル・ポイントはふたつのブランドの中間にあり,家計B のアイデアル・ポイントの方は,最近ブランド2を続けて購買しているので,ブランド2の位置にぐっと近づいている可能性が高いと 【122頁】 考えるのが自然であろう。つまり,家計内ブランド・シェアが同じ値(ここでは,50%)でも 購買履歴によって,アイデアル・ポイントの位置は異なると考えるのがより自然であり,このために本提案モデルで用いられるのは,Guadagni and Little(1983)のブランド・ロイヤルティー変数として知られる,購買履歴を単純なブランド・シェアより良く表現できる加重平均である。
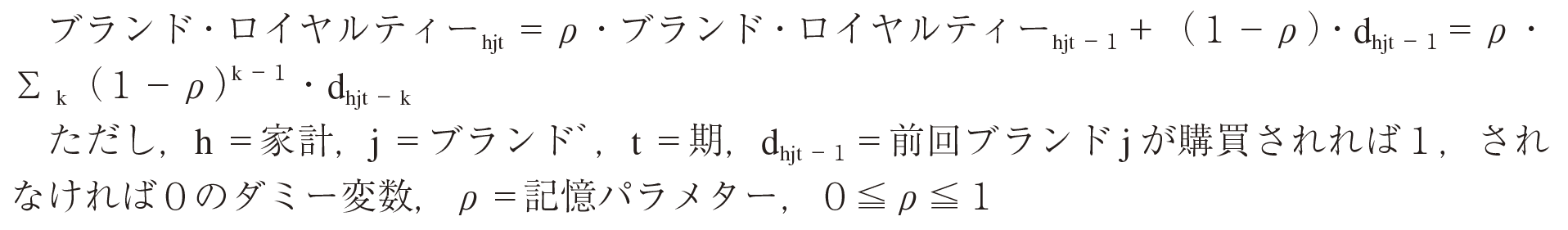
ブランド・ロイヤルティーは過去すべての購買の加重和であり,重みは前回購買が一番高くρで,一回遡るにつれ忘却のため,(1−ρ)ずつ減っていくのである。そしてアイデアル・ポイントをこの変数によって重み付けられたブランドの布置の加重平均と考える。

表2の場合,家計A の購買は,記憶パラメターであるρを大きくすれば,過去の多くの購買に重みをつけることになるので,アイデアル・ポイントは直前に買ったブランドの位置へ大きく近づくことはなく,過去買ったいろいろなブランドに関するロイヤルティーが少しずつ残り,長期的なロイヤルティーのため購買したブランドの布置の中間的な位置をとる。逆に,家計B の購買は,ρが小さくなると直近の購買により多く重みがつくので,アイデアル・ポイントは直近に購買したブランドの方向へ大きく動き,短期的なロイヤルティーをうまく表現することができる。また,記憶パラメター(ρ)は軸毎に異なると考える。つまり,家計は軸毎にブランドに対して,長期記憶であったり,短期記憶であったりする可能性を持つ。
今回のモデルの大きな特徴は,家計が持つパラメターの異質性に対処するために,ブランドの布置以外のパラメターである軸の重要度,記憶パラメター(ρ)そしてマーケティング変数の重要度の異質性を潜在クラス・モデルによってモデル化するだけではなく,家計の特性によって潜在クラス(セグメント)への所属確率が変化するということである。そのために,市場には,S 個のそれぞれの軸の重要度,記憶パラメター(ρ)とマーケティング変数の重要度を持つセグメントが存在し,家計はこれらのセグメントに家計の特性に応じた確率で所属すると仮定する。軸の重要度とρは軸毎に異なるので,それぞれS ×次元数だけある。また,ρが異なるので,結果として,アイデアル・ポイントもセグメントごとに異なる。まず,セグメントs に所属する家計h のブランド選択確率は次のようになる。
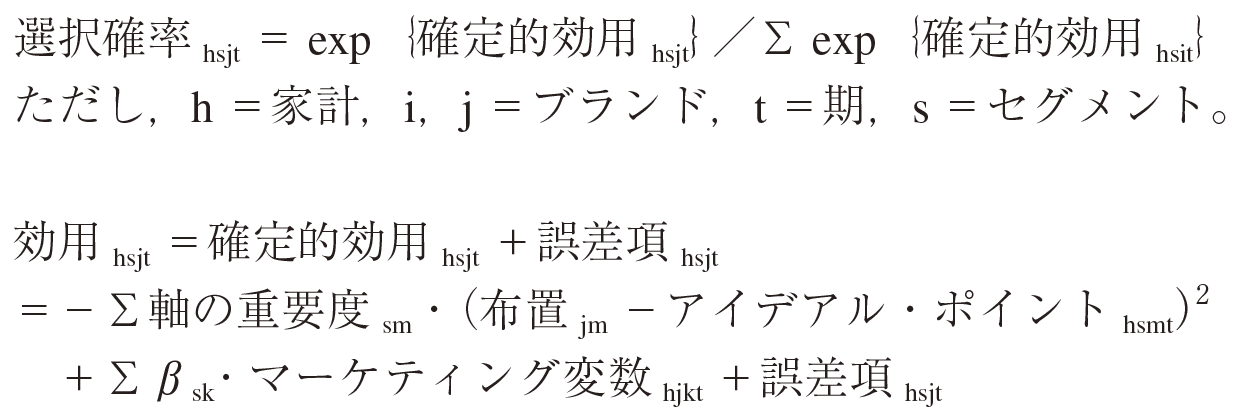
【123頁】
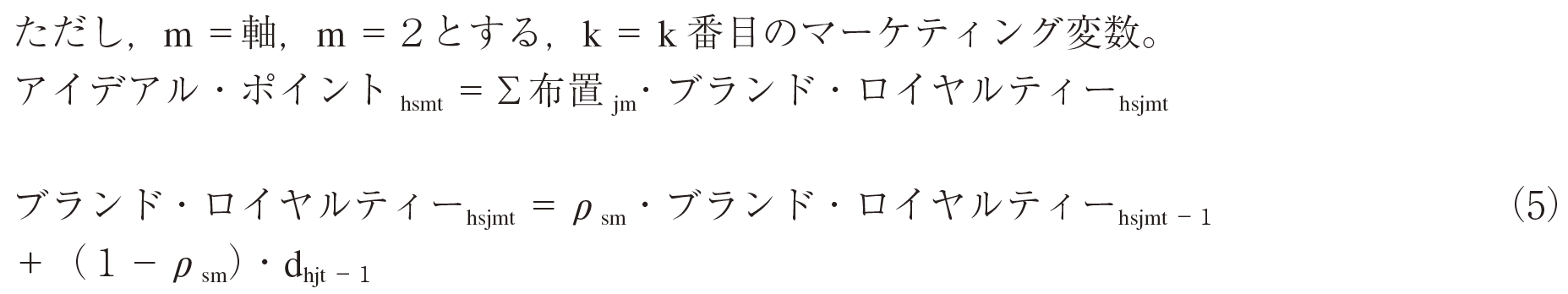
ブランドの布置は,他のモデルと同様に,状況の如何やセグメントにかかわらず一定であると仮定する。家計はセグメントs に次のような確率で所属する。
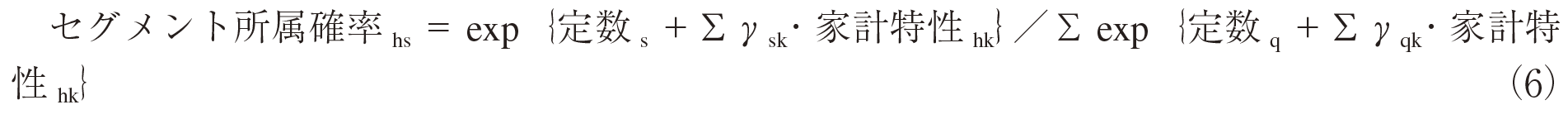
ただし,定数S =セグメントs に固有の定数,家計特性hk =家計h のk 番目の特性,γsk = セグメントs でのk 番目の特性の係数であり,セグメント所属確率は一定の特性を持つ家計hがセグメントs に全期間を通じて所属する確率を表している。
個々の家計の特性を入れることで,特性の値に応じて家計がセグメントに所属する確率が変化し,より良くセグメントへの所属を予測することができる。また,どのセグメントがどのような家計から構成されているかも明らかになるので,セグメントに適したマーケティング戦略も立てやすくなる。家計の特性としてどのような変数を用いるかも重要になる。年齢など,入手は簡単であるが,ひとつの製品の売り上げの予測には一般的過ぎて,それほど有効ではないデモグラフィック特性より,個々の製品カテゴリーでの家計の購買特性であるカテゴリー購買回数(全ブランドの購買回数の合計)や特別(エンド)陳列でのカテゴリー購買回数(エンドでの全ブランドの購買回数の合計)など,そのカテゴリーでの家計の特性の方が優れていると考えられる。
3.2 データ
分析に用いたデータは,これまでも用いてきた食料品のパッケージ財1カテゴリーに関するスキャンパネル・データで,70家計の5ブランドの購入に関するもので,全購買回数は742回である。ブランドの詳細は,表3の通りである1),2)。
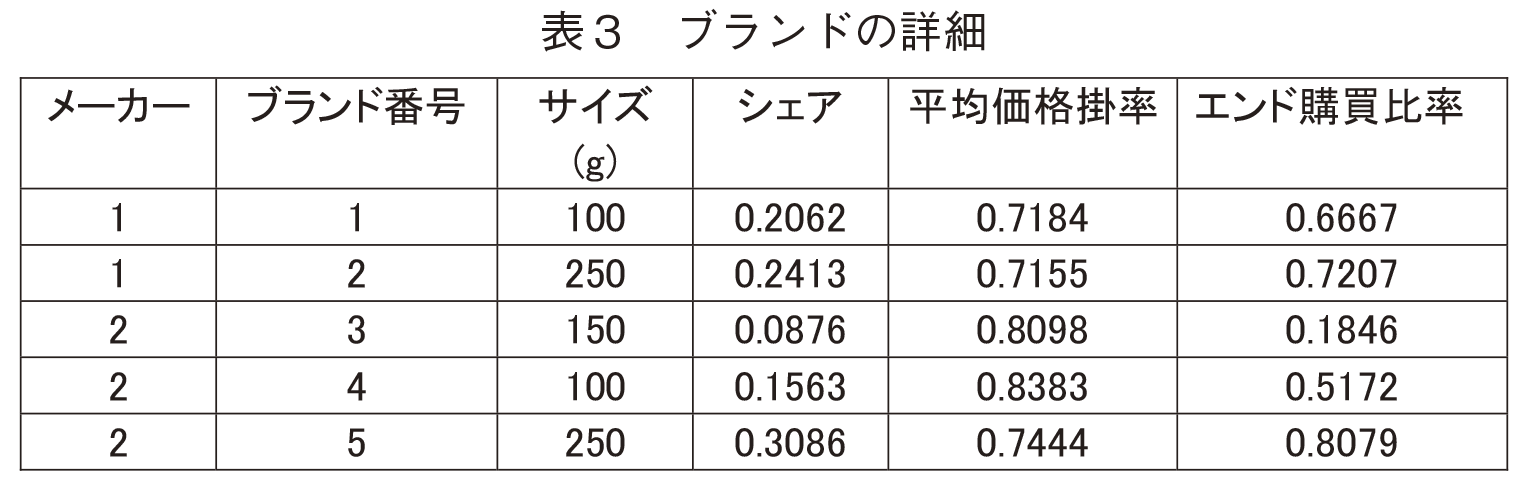
【124頁】
この製品カテゴリーには,他にも多くのブランドが存在するが,この2メーカーの5ブランドで市場全体の売上の多くを占めている。表3のシェアは,これらの5ブランドの中でのシェアを示している。表中で最もシェアが高いのが番号5のブランド(以下ブランド5と呼ぶ,その他のブランドも同様)で,シェアは約30%である。次に,シェアが高いのはブランド2であり,約24%のシェアを持っている。しかし,ブランド3とブランド4の違いはサイズだけであり3),この両者を合わせると,こちらも24%ほどのシェアを持っている。一番シェアが低いブランド1でも,シェアは20%以上あるので,シェアから見れば,この5ブランドはかなり拮抗した競争をしている。
ブランド2とブランド5は,同じ製法で作られていて,メーカーによって普及ブランドと位置づけられている。これに対して,ブランド1,3,4は,ブランド2,5とは違う同一の製法で作られ,プレミアム・ブランドとして位置づけられている。実際売価の標準価格に対する比率である価格掛率4)を見ると,メーカー1のブランド1とブランド2そしてメーカー2の普及ブランドであるブランド5の価格掛率が低い。それぞれのブランドがエンド陳列時に購買された比率であるブランド毎のエンド購買比率を見ても,これらの3ブランド(ブランド1,2,5)の比率が高い。これに比べると,ブランド3と4は,価格掛率は高く,エンド購買比率は低く,価格やプロモーションにあまり頼らないマーケティング戦略をとっているようである。
3.3 結果
このデータに対して価格掛率をブランド選択時のマーケティング変数とし,セグメントへの所属を説明する家計の特性としては,それぞれの家計がどのブランドかにかかわらずエンド陳列されているときに購買した回数の全購買回数に対する比率(以下エンドと呼ぶ)と全購買回数(以下購買回数と呼ぶ)を変数として持った本研究の提案モデルを適用して最尤推定し,杉田(2015)モデルと比較した。
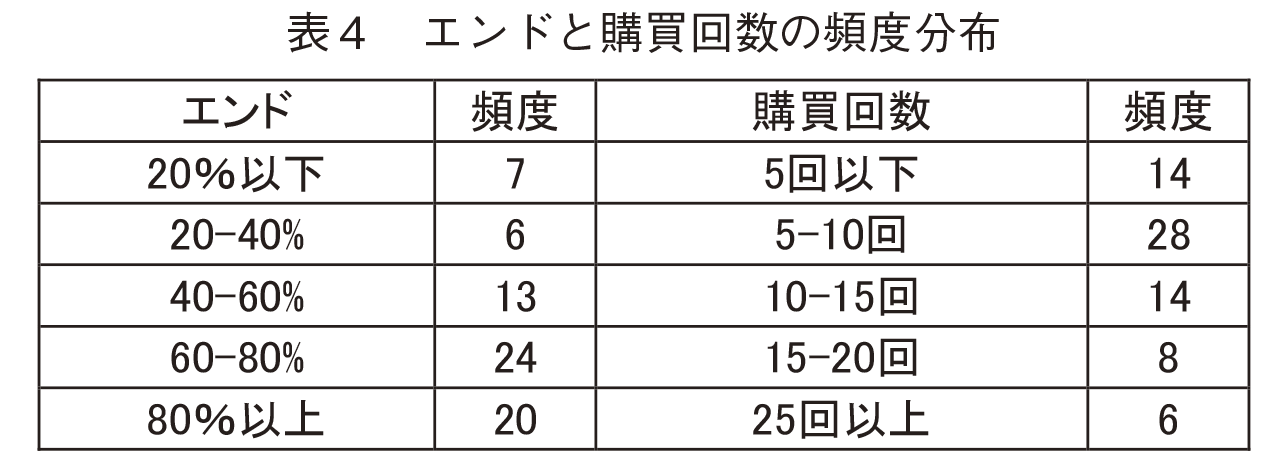
表4は全70家計のエンドと購買回数の頻度分布である。エンドの値は高く,全家計の平均で約64%に達し,購買回数の平均はおよそ10.5回であった。表4から分かるようにエンドと購買回数のデータはどちらもひとつの値に集中することはなく家計間で適度に散らばっていてセグメント所属確率の推定に支障はないと考えられる。
【125頁】
推定には,購買回数が極端に少ない4家計は除き,66家計のデータを用いた。まず,提案モデルについて,セグメント数が2から始めて,複数のセグメントを持つモデルを推定し,結果を比較して最良のセグメント数を決定した。今回の提案モデルは,セグメント所属確率を消費者の特性により説明することが大きな目的なので,セグメント数が1のモデルは除外した。推定されたモデルのデータへの適合度をAIC(赤池情報量基準)とBIC(ベイジアン情報量基準)で比較したのが表5である5)。
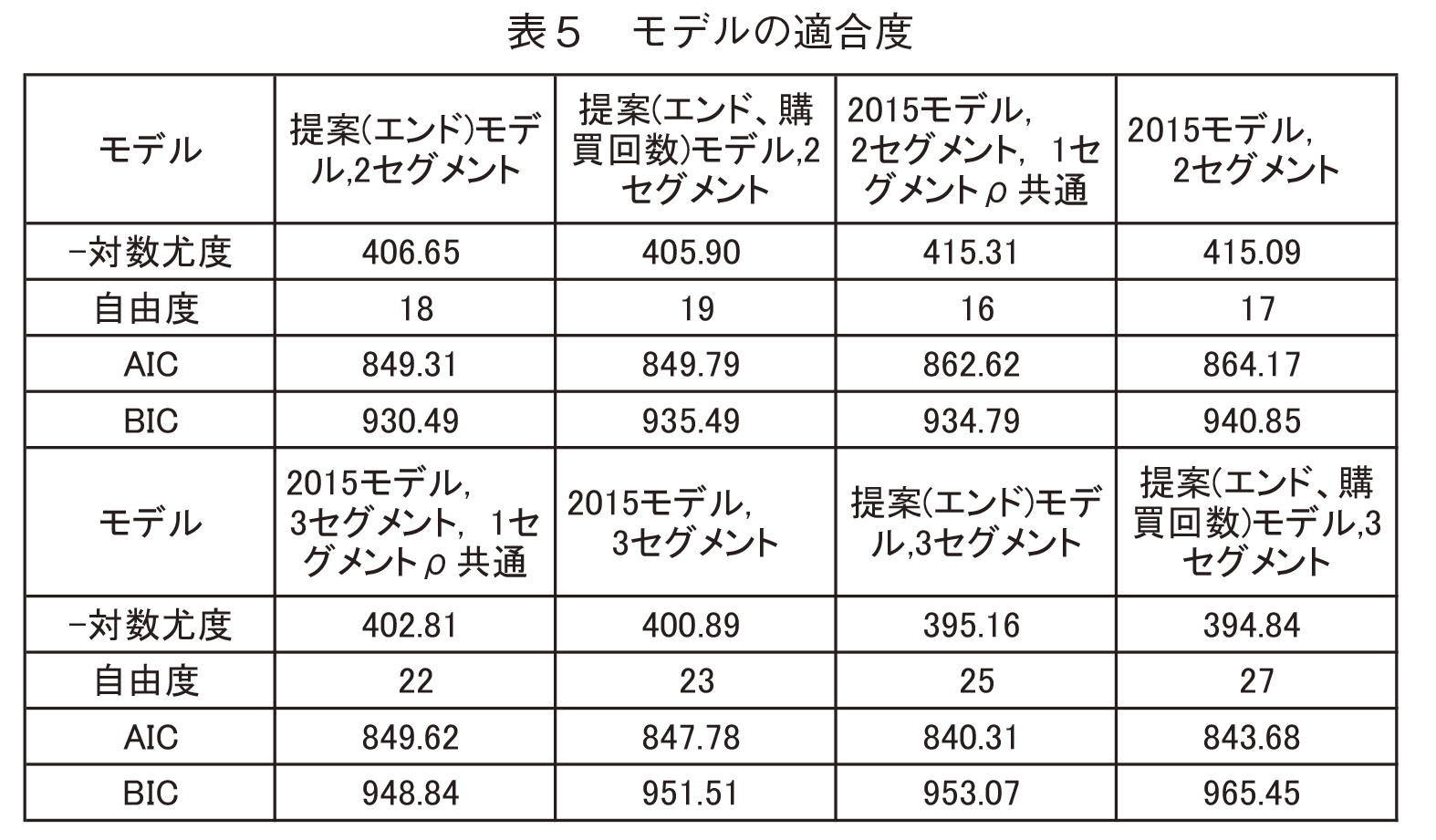
表5からAIC の適合度が最も良いのが,3セグメントで家計の特性としてエンドのみを持った提案モデルである。AIC よりパラメター数が多く,複雑なモデルに対するペナルティーが大きいBIC を見ると,エンドを家計の特性とした2セグメントの提案モデルが最も適合度が良い。AIC とBIC どちらをとっても,提案モデルの適合度は杉田(2015)モデルの適合度を上回っているが,ここでは複雑なモデルにより厳しいBIC の結果を採用して,エンドを家計の特性とした2セグメントの提案モデルを採用する。このデータでは,3セグメントを持つモデルの適合度(BIC)が2セグメントを持つモデルより劣っているので,4セグメント以上のセグメント数を考える必要はなかった。ここで,興味深いのは,家計の特性として考えたふたつの変数のうち,BIC で見ると,購買回数は統計的に有意ではなく,エンドが有意だったということである。通常,エンドや広告などのプロモーション変数の有効性は,データ分析の結果からは確認されにくいとされているにもかかわらず,エンド比率の有効性が確認されたからである。
この後は,採用された提案モデルの推定結果の解釈について見て行こう。モデルから得られたパラメターの推定値は表6の通りである6)。
【126頁】
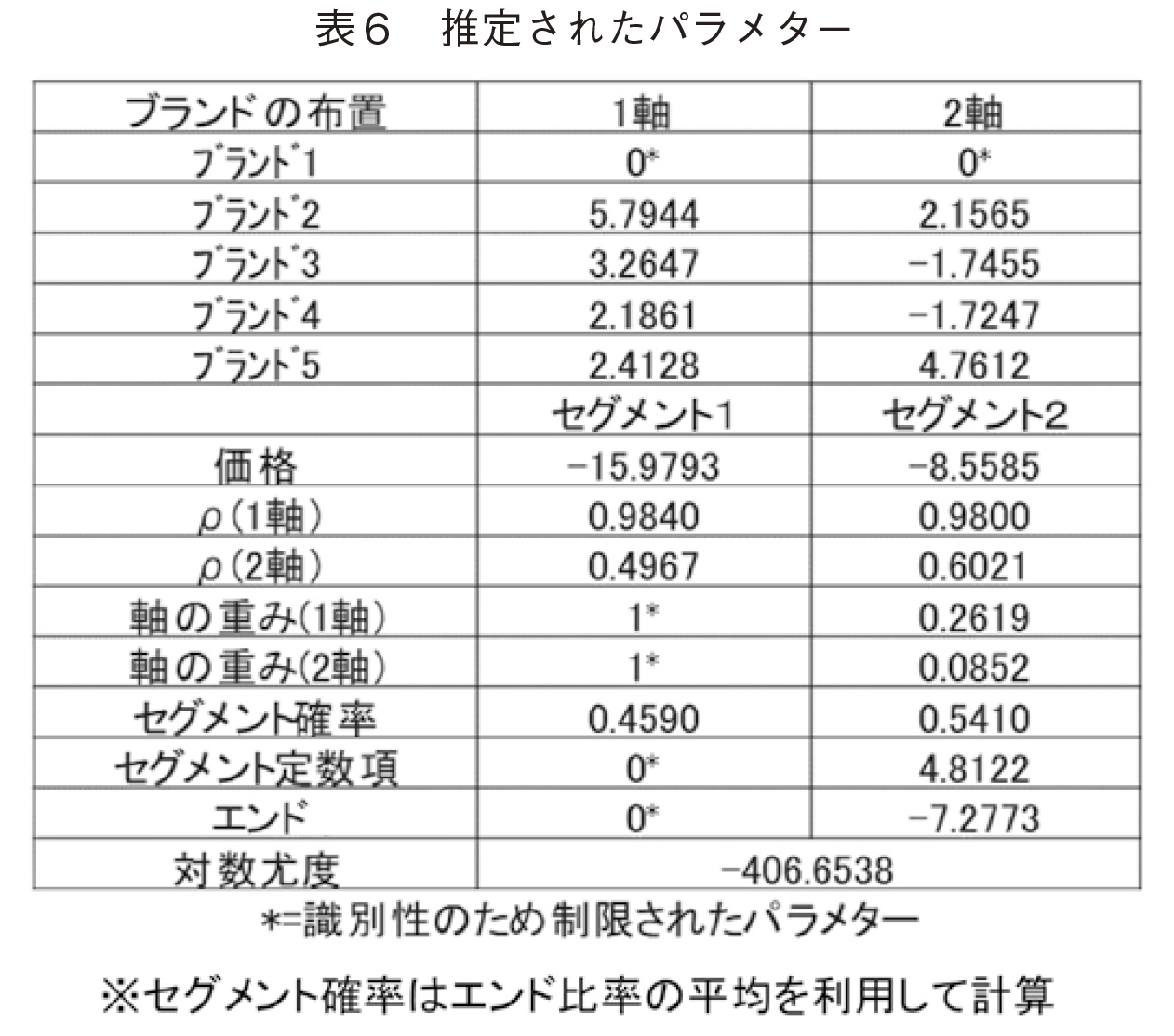
エンド比率を全家計の平均として,セグメント所属確率を式(6)と表6のパラメター推定値を用いて計算すると,表6にあるようにセグメント1が少し小さい(0.459対0.541)ことが分かる。しかし,セグメント所属確率はエンド比率の高低に大きく影響されている。
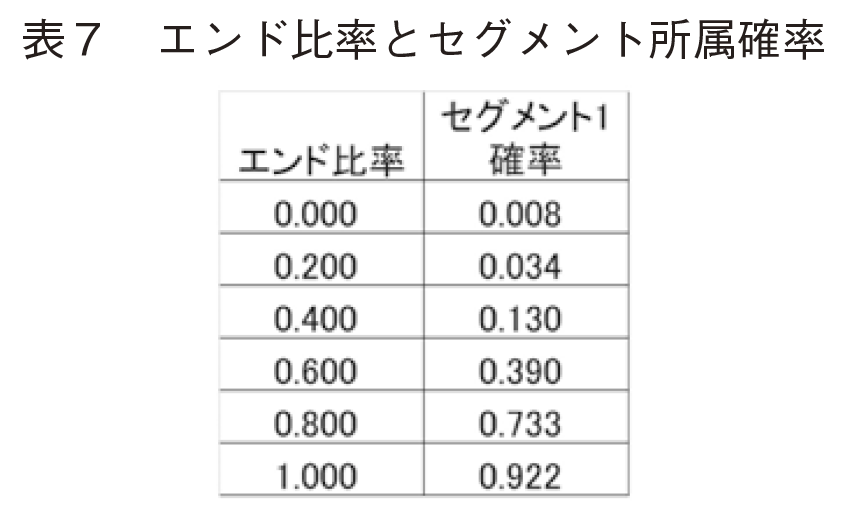
表7は,様々なエンド比率とそれに対応したセグメント所属確率を式(6)と表6のパラメター推定値を用いて計算したものである。ここから,エンド比率とセグメント1への所属確率は強く比例しており,このカテゴリーの製品をエンド陳列時に購買する比率が高い消費者ほどセグメント1に所属する確率が高いということが分かる。
【127頁】
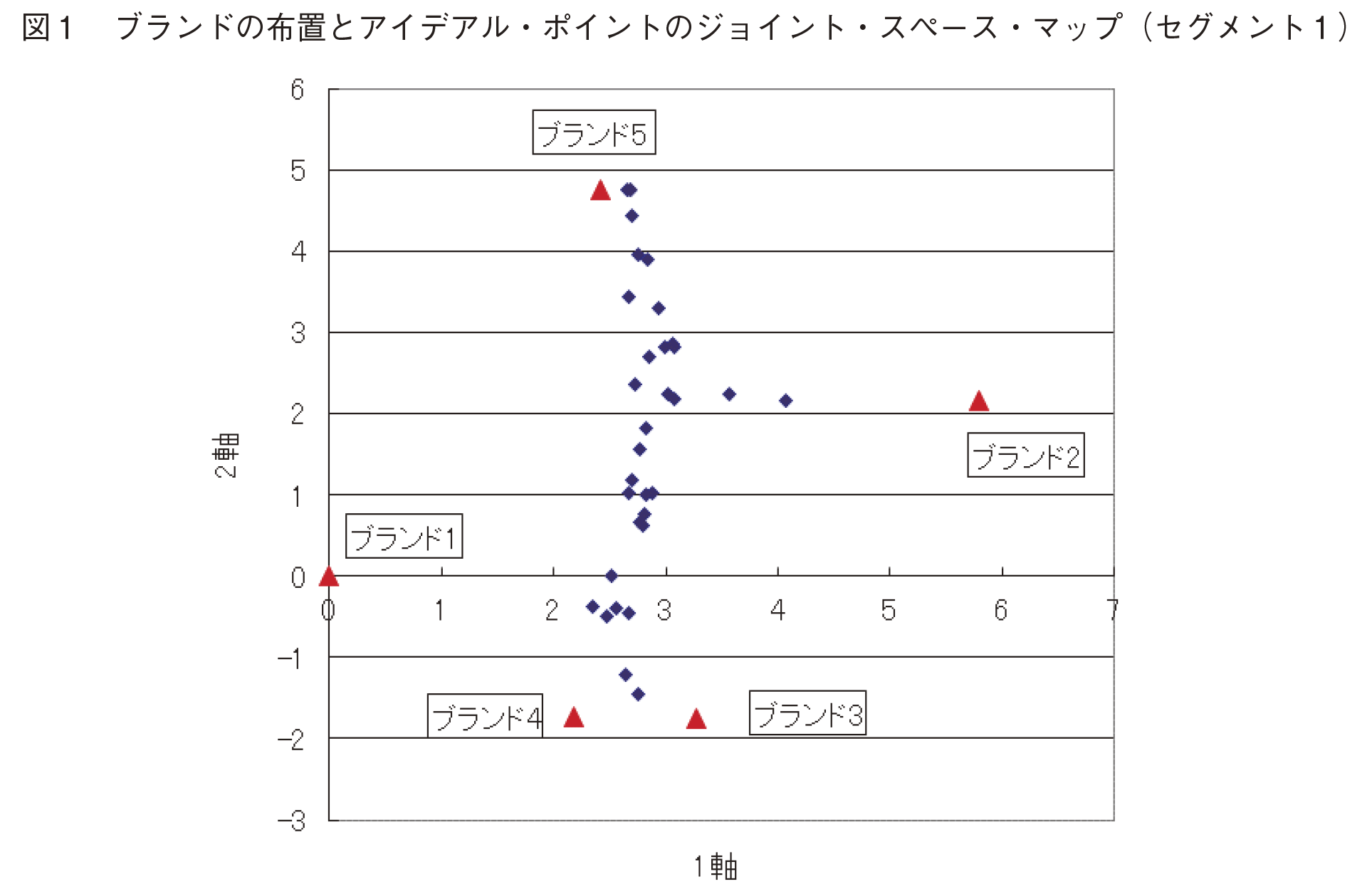
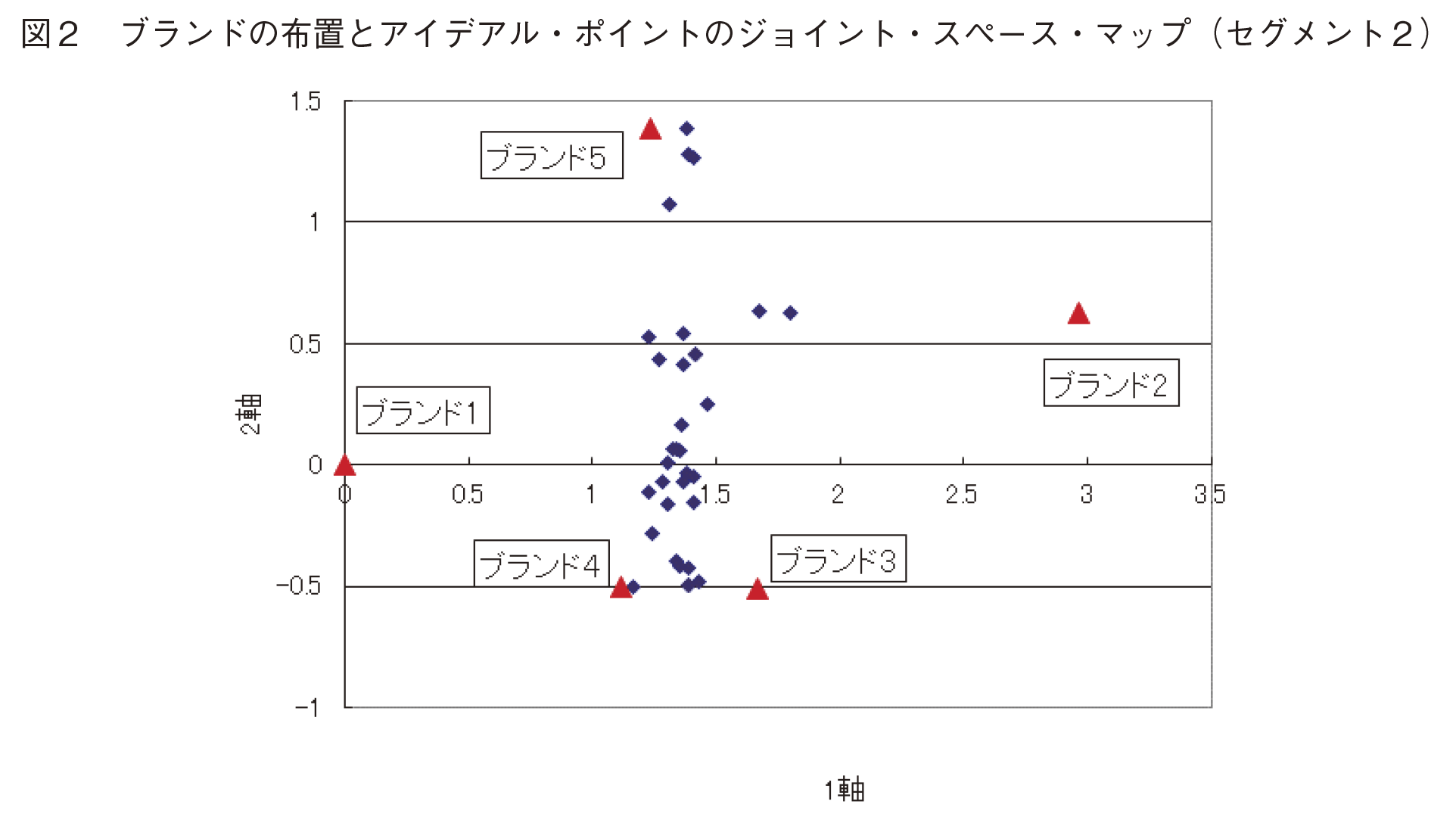
図1と2は推定の結果から得られたジョイント・スペース・マップである。これらのマップでは,ブランドの布置は▲で表し,家計のアイデアル・ポイントは◆で表した。各家計はセグメントへの事後所属確率が最大(2セグメントなので,確率が0.5以上)のセグメントに所属【128頁】するとして割り振った7)。また,図2のセグメント2については,各軸の重要度(の平方根)とブランドの布置あるいは家計のアイデアル・ポイントの積を求めて,軸の重要度を加味したセグメント2にとっての各ブランドの布置と家計のアイデアル・ポイントとした。
それでは,これらのマップからはどのようなことが読み取れるのだろうか。どちらのマップでも,ブランド5と2はマップの右上側に位置し,ブランド1,3,4は左下側に位置している。3.2節でも書いたように,ブランド2とブランド5は,同じ製法で作られていて,それぞれのメーカーによって普及ブランドと位置づけられている。これに対して,ブランド1,3,4は,ブランド2,5とは違う同一の製法で作られ,プレミアム・ブランドとして位置づけられている。製法の違いとメーカーのマーケティング戦略が功を奏して,消費者からも普及ブランドとプレミアム・ブランドは違うと認識されているようである。ところが,重要度を加味したセグメント2のブランドの布置は,セグメント1のブランドの布置と比べて,1軸(横軸)より2軸の重要度が低いことを反映してブランド3,4,5の布置が大きく近づいている。つまり,セグメント2ではメーカー2の3ブランドの位置が近づいて,メーカー内での3ブランドの競争が激しくなる可能性を示唆している。
家計のアイデアル・ポイントを見ると,ブランド間の競合状況がより鮮明に見えてくる。このモデルでは,家計のアイデアル・ポイントは購買したブランドの布置の加重平均なので,ブランドの布置を結ぶ直線付近にアイデアル・ポイントが多くあれば,その2ブランド間での競争が激しいことが分かる。どちらのセグメントでも,ブランド1と3,4を結ぶ直線の近くにアイデアル・ポイントが多いので,これらのプレミアム・ブランド間で競争が激しく,逆に,ブランド2と3,4の間にアイデアル・ポイントが少なく,ブランド1と5の間も同様にアイデアル・ポイントは少ないので,これらのプレミアム・ブランドと普及ブランドの間では競争が激しくないことが分かる。マップの中央部にあるアイデアル・ポイントはどのブランドからも購買する可能性があるが,厳密に距離を計算すれば,ブランド1,2よりもブランド3,4,5から購買する可能性が高い。また,メーカー2の3ブランド(ブランド3,4,5)を結ぶ直線の付近にも多くのアイデアル・ポイントがあり,プレミアム・ブランドと普及ブランドの中でブランド・スイッチが起きるのは主にメーカー2のブランド間であることが分かる。
セグメント2では,メーカー2の3ブランド間で競争が激しくなっただけでなく,セグメント1に比べ,ブランド3と4の近くにアイデアル・ポイントが多くなり,ブランド5は苦戦を強いられていることが分かる。つまり,ブランドの布置からはメーカー2の3ブランドの競争が激しくなるかのように見えるが,アイデアル・ポイントも考慮すると,プレミアム・ブランドであるブランド3と4の優勢が理解できるようになる。ρの値も1軸では高く,アイデアル・ポイントの動きが鈍くなることを反映して,1軸上でのアイデアル・ポイントのばらつきは2軸でのばらつきに比較するとかなり小さく,しかも軸の中央に集まっているので,1軸の両端に位置するメーカー1のふたつのブランドにとっては価格によって消費者を引き付けても,アイデアル・ポイントの動きが鈍いので,リピートを期待するのが難しい不利な状態である。
【129頁】
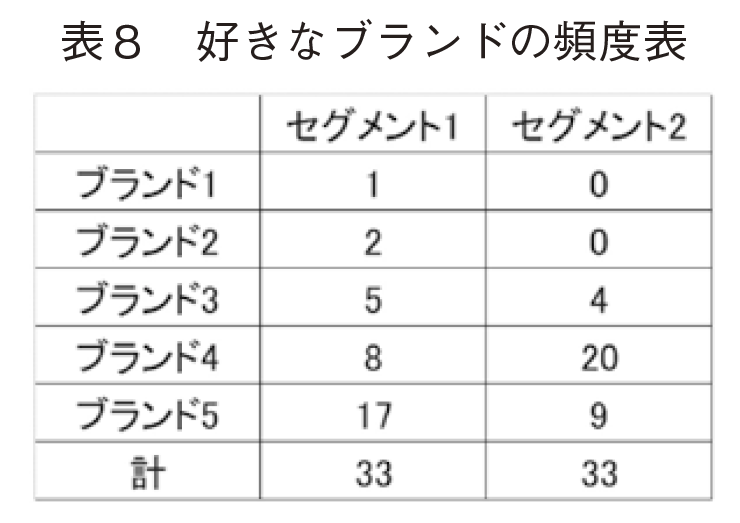
表8は,事後確率を用いてセグメント1と2それぞれに属すると判定された家計について,ブランドの布置と家計のアイデアル・ポイントとの距離から,それぞれの家計のアイデアル・ポイントに最も近いブランドをその家計が好きなブランドとして,ブランド毎にそのブランドが好きな家計の頻度を表にしたものである。この表から,どちらのセグメントでも,家計の選好はブランド3,4,5に偏っているが,セグメント1では普及ブランドであるブランド5が最も人気が高く,セグメント2では,ブランド4が高い人気を誇っていることが分かる。つまり,ジョイント・スペースからは,どちらのセグメントでもメーカー2が有利に競争を進め,セグメント2がよりプレミアム・ブランド志向であるという事が分かる。
セグメント1とセグメント2では,どちらがより価格の影響が大きいのだろうか。表6からは,セグメント1の方が軸の重要度が大きく,マップの影響が大きく見えるが,価格係数を見ると,セグメント1の係数がセグメント2の係数よりもかなり大きいことが分かる(−15.9793と−8.5585)。係数だけを見ると,セグメント1が軸の重要度も価格の重要度も高く,商品志向であるのに価格にも敏感という結果になる。セグメントごとのジョイント・スペースとマーケティング変数の相対的重要度を比較するための指標として価格弾力性をブランドとセグメントごとに計算したのが表9である。
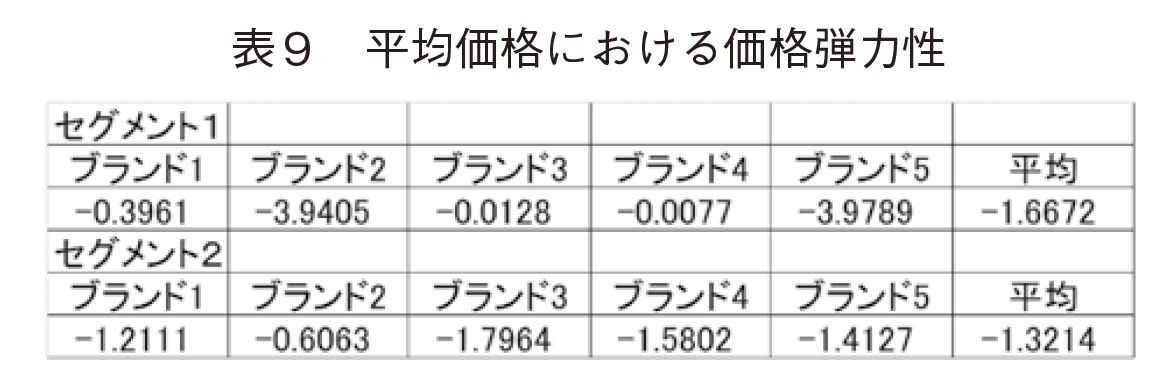
価格弾力性は,各家計がセグメントへの事後所属確率が最大のセグメントに所属すると仮定し,セグメントに所属する家計の平均アイデアル・ポイントを用いてブランドごとに平均価格を用いて計算した7)。表9から,セグメント1がセグメント2よりブランド毎の価格弾力性の平均値が高く,平均するとより価格に対しての反応が強いことが分かるが,特にメーカーによって普及ブランドと位置づけられたブランド2と5のふたつのブランドの価格弾力性が飛びぬけて高く,このセグメントでは価格によってこのふたつのブランドの売上が大きく変わることを示している。セグメント2では,差は小さいが逆にメーカー2のプレミアム・ブランドふたつの価格弾力性が最も高くなっている。このデータでは,価格弾力性による分析は,ジョイント・スペースから得た結論である低価格の普及ブランド志向のセグメント1と高級品志向の【130頁】セグメント2を補強する結果となった。恩蔵と守口(1994)によれば,エンド購買をする可能性が高い消費者は価格感度が高い消費者であるというが,今回のデータ分析の結果はそれとも一致する。
本論文では,スキャンパネル・データからジョイント・スペース・マップを選好の内的分析によってつくるブランド選択モデルの中で,軸の重要度とマーケティング変数への反応が異なる消費者セグメントと家計毎にダイナミックに変化するアイデアル・ポイントを持ったブランド選択モデルに家計特性に依存した消費者セグメントを加えたモデルを提案しデータに適用した。提案モデルのフィットは家計特性によるセグメンテーションを考慮しないモデルより良好であった。
データ分析の結果から,家計はほぼサイズが等しい二つのセグメントに分かれ,セグメント1は,エンド陳列で製品を購買する消費者が多く所属するセグメントで,普及ブランド志向で特に普及ブランドの価格に敏感であることが分かった。セグメント2では,メーカー2の3ブランドに人気が集中し,価格への敏感さはセグメント1ほどではなく,特にメーカー2のプレミアム・ブランドの人気が高いことが示された。このデータ分析から,アイデアル・ポイント・モデルに家計特性によるセグメントを加えることは有益で,セグメントごとに消費者のブランドの評価法が異なることが示唆されたことは興味深い。ただし,今回の結果はひとつの製品カテゴリーの結果に過ぎず今後多くのカテゴリーで検証を続ける必要がある。
1. Allenby, G. M. and P. E. Rossi (1999), ”Marketing Models of Consumer Heterogeneity,” Journal of Econometrics, 89, 57-78.
2. Andrews, R. L., A. Ainslie and I. Currim (2002), “An Empirical Comparison of Logit Choice Models with Discrete Versus Continuous Representation of Heterogeneity,” Journal of Marketing Research, 39, 4, 479-487.
3. Elrod, T. (1989), ”Choice Map: Inferring a Product-Market Map from Panel Data,” Marketing Science, 7, 1, 21-40.
4. Elrod, T. (1989), ”Internal Analysis of Market Structure: Recent Developments and Future Prospects,” Marketing Letters, 2, 3, 253-266.
5. Erdem, T. (1996), “A Dynamic Analysis of Market Structure Based on Panel Data,” Marketing Science, 15, 4, 359-378.
6. Guadagni, P. M. and J. D. C. Little (1983), “A Logit Model of Brand Choice Calibrated on Scanner Data,” Marketing Science, 5, 2, 203-238.
7. Inman, J. J., J. Park and A. Sinha (2008), “A Dynamic Choice Map Approach to Modeling Attribute-Level Varied Behavior Among Stockkeeping Units,” Jounal of Marketing Research, 45, 1, 94-103.
8. Lee, J. K. H.,K. Sudhir and J. H. Steckel (2002), ”A Multiple Ideal Point Model: Capturing Multiple Preference Effects from Within an Ideal Point Framework,” Journal of Marketing Research, 39, 1, 73-86.
【131頁】
9. 恩蔵直人,守口剛(1994),『セールス・プロモーション―その理論,分析手法, 戦略―』(同文館).
10. 片平秀貴(1990),「マッピングを伴う市場反応モデル」,『マーケティング・サイエンス』,36,13-27頁.
11. 里村卓也(2004),「マッピングを利用した市場反応の動的分析」,『マーケティング・サイエンス』,Vol.12,NO.1・2,1-23頁.
12. 杉田善弘(1998),「文脈効果とジョイント・スペースを組み込んだブランド選択モデル」,『消費者行動研究』,Vol.5,No.2,13-26頁.
13. 杉田善弘(2011),「消費者セグメントと次元毎に変化するアイデアル・ポイントを持つブランド選択モデルによるジョイント・スペース分析」,『経済論集』(学習院大学経済学会),Vol.47,No.4,355-371頁.
14. 杉田善弘(2015),「消費者セグメント毎に軸の重要度が変化するジョイント・スペースを持つブランド選択モデル」,『経済論集』(学習院大学経済学会),Vol.52,No.2,85-100頁.
15. 高根芳雄(1980),『多次元尺度法』(東京大学出版会).
16. 土田尚弘(2009),「オケージョン効果を考慮した清涼飲料水カテゴリーのジョイント・スペース・マップ」,『経営と制度』(首都大学東京),Vol.7,1-15頁.
17. 長谷川翔平(2011),「動的ジョイント・スペース・マップ」,日本マーケティング・サイエンス学会第89回研究大会研究報告.