����́u���{�I�o�c�v�_�i�R�j
��ˁ@���o�E���R�@���G
3.2�@���R�[�|���[�g�K�o�i���X�E�R�[�h�̖��_
3.2.3�@�����̎��������ɂ���
�u�����̎��������v�́C���X�́u�����̑��ݎ��������v�ƌĂ�Ă��āC1980�N�ォ�炱�̗p��ō̂肠�����Ă����B�M�҂̈�l������ɂ��āC�ߋ����y�������Ƃ�����B����͏��R�i2011�C2016�j�ɂ����āC���̂悤�ɍ̂肠�����Ă���1�j�B
�i�O�߂ō̂�グ���悤�ɁC�j�o�u���o�ϔj���O�̓��{�I�o�c�̍����I���ʂ�����t������̂Ƃ��ĂS���������Ă����B
�@�O���[�v���������B
�A�����̑��ݎ�����
�B��s�ɂ�銔���ۗL
�C�d���I�Ȕz������
�i���̂����̇C�́C�W−�S�ŏq�ׂĂ���̂ŁC��������Q�Ƃ��ꂽ���B�j�܂��C�@�ƇB�́C�u���łȃ��C���o���N�W�v�Ƃ��ĂЂƂ�����ɂł���ł��낤�B
�o�u���o�ς̔j��ȍ~�C���{��Ƃ̌o�c�����͖����𑱂��Ă����B����N�����̂����Ă���C���^�[�l�b�g�L����C�V�������Ă����炩�Ȃ悤�ɁC�s�����f�t�����s�����f�t���Ƃ����z�ŁC�킪���̎Y�Ƃ͂��Ƃ��Ƃ��k���X���ɂ���B�Y�Ɠ��ł̗L�͊�Ƃ̌o�c�������������C���́C���Ƃ��邲�ƂɁu���̂����ɂP�E�Y�ƂɂP�E���Ƃ̂݁C�Ƃ����ɂȂ�I�v�Ƃ��������I���Ă���B�f�p�[�g��r�[���Y�ƂȂǂł́C�Ђ���Ƃ�����C�߂������ɂ��ꂪ�N���邩������Ȃ��B
���̒��ŁC�O�q�́C�@�O���[�v���������B�C�A�����̑��ݎ����C�B��s�ɂ�銔���ۗL�C�C�d���I�Ȕz������C���ϖe���Ă���B���ɇ@�`�B�́C�]���̓��{�I�o�c�̏d�v�Ȍ�돂�ł�������ƌn��i��ƏW�c�j��������������Ƃɂ��C�`��ς�����B���Ȃ킿�C�O��O���[�v�̃��C���o���N�ł������O���s�i�������s�j�ƏZ�F�O���[�v�̃��C���o���N�ł������Z�F��s���������āC�O��Z�F��s���ł������炢�ł��邩��C���͂⋷���O���[�v��`���ʗp���Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ͂킩��B�������C�A�ɂ��ẮC�ꎞ�e�𔖂����Ă����̂��C�܂��ڗ����Ă��Ă���B���̗��R�͓����C
�@�@�����t�@���h�ɂ�銔���̌��J�����t���Ȃǂ̊�ƍ����E�����iM&A�j���N����C�Ăш��芔����ڂ���Ă��邱��
�A�@�o�c�헪�̎�l�܂�C���Ȃ킿�}�[�P�b�g���̂̊g�傪���܂�]�߂Ȃ��Ȃ��Ă��錻 �y316�Łz �݁C�P�ƂŗL���Ȑ헪���݂��Ď��s���邱�Ƃ�����ł��邱�Ƃ���C���݂ɗL�v�ȃp�[�g�i�[���݂��Đ헪�I��g���s�����Ƃ����X�������܂��Ă��邱��
����������B
�킪���̏���Ɩ�3900�Ђ́C2006�N�x�̊����������䗦��5.9���ŁC2005�N�x��5.5������㏸���Ă���B1991�N�x�͂��ꂪ23.6���������̂ł��邩��C���̒ቺ�͎����ł���B���ہC1991�N�ȗ������������͓����Ƃ��đ����Ă������C2006�N�ɏ��߂ď㏸�i�����j�ɓ]�����̂ł���B����́C��Ɠ��m�̎��{��g�i�헪�I��g�j�┃���h�q�ւ̈ӎ������܂��Ă��邱�Ƃɂ��Ƃ����B����2006�N�x�ɂ́C���ۓI�Ɏ��ƓW�J������Ɠ��m�̊��̎擾���ڗ������ƌ�����B���Z�ɂ��ƁC���̔N�C�g���^�����Ԃ͏����d��Y�Ƃ̊����490���~���C�t�ɏ����d��Y�Ƃ̓g���^�����Ԃ̊���440���~�������������Ƃ����B2006�N�x�ɐV���ɔ����������������̎擾���z�́C�S�|�Ƃ�1425���~���ƍł������C�d�@��1417���~���C�A���@�킪1030���~���ƂȂ��Ă���B�����āC����ɓ����I�Ȃ̂��C���������́u�L����v�ŁC��Ƃ��ۗL���鑼�Њ��̖������������Ă���B2004�N�x�͂P�Е��ς�2.8�Ђ̊��������Ă����̂��C2005�N�x��3.2�ЁC2006�N�x��3.5�Ђɑ������̂ł���i�f�[�^�͂��ׂđ�a�����̒������ʂɂ��j�B
�����̎������f�[�^���琄�@�ł���̂́C�ƊE���Ƃ̎���C���Ɍ���������Ђƒ��B��ЂƂ́C�T�^�I�Ȑ헪�I�Ȏ������ł��낤�B�����ԋƊE�͂��̓T�^�ŁC�������B��ł���S�|�ƊE�Ǝ��������s�����Ƃɂ��C�ޗ����B�̈��艻��}��C�Ƃ������Ƃł���B�܂��C�S�|�ƊE�̏ꍇ�C�O����Ƃɂ�锃���̃��X�N�������Ȃ����Ƃ���C�O�q���@�C���Ȃ킿�����h�q��Ƃ��Ċ����̎��������s����C�Ƃ������ƂɂȂ�B���̌��ʁC�ȑO�͈قȂ�����ƏW�c�ɏ������Ă������Ɠ��m�i�Ɨ��n�̐V���c�C�Z�F�n�̏Z�F�����C��ꊩ��n�̐_�ː��|�j���C����ƏW�c�̊_�����z���āC���ݎ��������s�����ƂƂȂ��Ă���B
�i�ȏ�C���R�i2011�j�ɂ��B����ȉ��͏��R�i2016�j�Œlj����ꂽ���́j
�Ƃ��낪�C���{�o�ϐV��2014�N�V��16���t�̒����P�ʂɂ��ƁC������������ۗL����281�Ђ̂���168�Ђ�2014�N�x���ɕۗL�����̐������炵�Ă����Ƃ����B�Z�F�������ۗL���Ă����V���S�Z����8000������242���~�Ŕ��p�����ق��C�݂��ً�s���x�m�d�H�Ɗ�830������331���~�Ŏ藣���C�O��Z�F�M����s���O��s���Y��632������223���~�ŏ����������ƂȂǂ���Ƃ��ċ������Ă����B�����́u�������������͍ŏI�i�K�ɓ����ė����v�ƕ��͂��Ă���B
�����o�L�҂̕]�_�Ƃɂ��ƁC�������������̓A�x�m�~�N�X�̐����헪�̉B�ꂽ�^�[�Q�b�g�ŁC2014�N�U���Ɋt�c���肵�������헪�u���{�ċ��헪�@����2014�v�ł́C�u���{��Ƃ̉҂��͂����߂��v�Ƃ��āC�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�̋������u���̈�ԁv�Ɍf����ꂽ�Ƃ����B�����ł͒��Ƃ��āC�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�E�R�[�h�̓������ł��o����C���{��ƂɃK�o�i���X���������悤�Ƃ����ꍇ�C���N�ɂ킽���čő�̏�Q�ł���Ǝw�E����Ă����̂��������������������Ƃ����B��Ƃ��s�����݂Ɋ�����ۗL���邱�ƂŁC�o�c�҂����݂Ɂu�����ϔC��v����ɂ���ɓ������C�O���̊���Ⓤ���Ƃ̐����r������邱�ƂɂȂ����Ă����͎̂����Ƃ����ʂ����邩������Ȃ��B�����ŁC�o�c�ɋK��������ɂ͎�����������������̂��挈���C�Ƃ����킯�ŁC�������C�������������Ɍo�c�҂̏W�܂�ł���o�c�A�Ȃǂ͋�����R���Ă����Ƃ����B
�����C�o�ϊE�̔����悻�ɁC��������������͒��X�Ɛ����I�ɐ��荞�܂�Ă������B2015�N�R���ɋ��Z���Ɠ����،�����������������ǂ߂�L���҉�c�Łu�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�E�R�[�h�v�����܂������C�����ɂ����������ɂ��ď������܂�Ă���B�R�[�|���[�g�E �y317�Łz �K�o�i���X�E�R�[�h�͏���Ƃ̂���ׂ��p�����������̂ŁC�����ł͉��B�ȂǂōL���g���Ă���u�R���v���C�E�I�A�E�G�N�X�v���C���v�Ƃ������[���̌n�C���Ȃ킿����i�R���v���C�j����̂͋`���ł͂Ȃ����C�������炵�Ȃ��ꍇ�ɂ͂��̗��R������i�G�N�X�v���C���j���邱�Ƃ����߂��Ă���B
�����ɂ́y�����P−�S�D�����鐭���ۗL�����z�Ȃ���̂�����C����Ђ������鐭���ۗL�����Ƃ��ď�ꊔ����ۗL����ꍇ�ɂ́C�����ۗL�Ɋւ�����j���J�����ׂ��ł���Ƃ���B�܂��C���N�C�������Ŏ�v�Ȑ����ۗL�ɂ��Ă��̃��^�[���ƃ��X�N�Ȃǂ܂����������I�Ȍo�ύ������⏫���̌��ʂ��������C����f�����ۗL�̂˂炢�E�������ɂ��ċ�̓I�Ȑ������s���ׂ��ł���Ƃ��Ă���B����Ђ́C�����ۗL�����ɌW��c�����̍s�g�ɂ��āC�K�ȑΉ����m�ۂ��邽�߂̊������E�J�����ׂ��ł���Ƃ����̂ł���B
�u�������C�o�c�W�ٖ̋����Ƃ������������\�����C����������O�̋@�֓����Ƃ�l���傪�[�����邩�ǂ����͕�����Ȃ��B�����C�ۗL�ړI�����m�ł͂Ȃ������������͔��p��������ɌX���Ă���̂��B�v�Ƃ��̕]�_�Ƃ͏q�ׂĂ���B�������C����͉ʂ����Đ��_���낤���B�O�q�́u�헪�I�������v�ɔ����銔��́C���ۂ͂��܂葽���Ȃ����낤�B�����āC���{�I�����̓����Ƃ��āC���̂悤�ȁu�헪�v�͂������҂�ɐ����ɂ��ăA�i�E���X������̂łȂ����Ƃ́C������{�̌o�ςɊW������̂Ȃ炷�ׂĂ����ӂ��Ă�����̂ł���B�������Č���ƁC�����炭�A�����J�̋��ȏ��Ȃǂ����č��肵���Ƃ݂��铌�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�E�R�[�h�C�����ĕM�҂́u�ʼn_�Ȍo�ϑO�i����v�ƂƂ炦�Ă���u�A�x�m�~�N�X�v�Ȃ�㕨�́C�����������C���͑O��������炯�̋��ȏ����@�B�I�ɐ^���Đ����i�߂悤�Ƃ����C�g���f���i�C�s���ł���C�Ǝv����̂ł���B�܂�C�u�������𐧌�����Ή䂪����Ƃ̃R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�����P�����v�ȂǂƂ����C�͂����茾���āu�n���ȁv�c�_�́C�܂��Ɂu���s���v�̋A���ł���C�����������|�W�e�B�u�Ȍ��ʂɂ����C�����̔��W�̂��߂ɂ͖ڂ�������ׂ����ƁC�S����o�ϐl�͍l���Ă���ƁC���͎v���Ă���B
��ˁE���R�C����́u���{�I�o�c�v�_�i�Q�j�ŕM�҂�͎��̂悤�ɏq�ׂ��B
���{�̊�ƌo�c�̓��F���ŏ��Ɏw�E����C�L�����ɒm��n�邫�������ƂȂ����̂́C�O�e�̎�ˁE���R�i2021�j�ŐG�ꂽ�悤�ɁC�A�x�O�����́w���{�̌o�c�x�i1958�j�̏o�łł������B�����ł́C���Ɍٗp���x���邢�͌ٗp���s�ɂ��āC�p�Ċ�ƂƂ͑傫���قȂ��Ă��邱�Ƃ��C�킪���̐������Ƃ𒆐S�Ƃ�������ώ@�Ɋ�Â��āC���炩�ɂ��ꂽ�B�[�I�ɂ����ƁC�킪���̊�Ƃ̑傫�ȓ����́C�I�g�ٗp�C�N������C��Ɠ��g���̂�����R��̐_��Ƃ������ׂ��ٗp�V�X�e���ɋ��߂�ꂽ�B
�������C�����ғI�ȗ��ꂩ��̌��������łȂ��C�����Ƃ́u���{�I�o�c�v���ǂ̂悤�ɍl���Ă��邩���C�����ɂ悭�m�F���Ă����ׂ��ł��낤�B�����ŁC�����m��ׂ����Ă݂����ʁC���̋L���ɂ��ǂ�����B���Ȃ킿�C
THE OWNER �ҏW���u���{�I�o�c�Ƃ́H��������b�g�E�f�����b�g���ڂ�������I�v2021/09/092�j�ɂ��ƁC
�y318�Łz�P�D���{�I�o�c�Ƃ́H
�Q�D���{�I�o�c�̓����u�O��̐_��E���C���o���N���E�������������v
�P�D��ƕʘJ���g���i�O��̐_��j
�Q�D�N�����i�O��̐_��j
�R�D�I�g�ٗp�i�O��̐_��j
�S�D���C���o���N��
�T�D������������
�R�D���{�I�o�c�̂S�̃����b�g
�P�D�P�D�o�c�̈��艻
�Q�D�Q�D�l�ވ琬
�R�D�R�D�Ј��̃��C�����e�B�i�����S�j
�S�D�S�D�g���Ƃ̒c�̌���
�S�D���{�I�o�c�̂R�̃f�����b�g
�P�D�P�D�g�D�̍d�����E�ƊE�̕NJ�
�Q�D�Q�D�N���҂̍��R�X�g��
�R�D�R�D�o�c�̔�������ɂ�鋣���͒ቺ
�T�D���{�I�o�c�̑�\�R��
�P�D�P�D�p�i�\�j�b�N
�Q�D�Q�D�g���^
�R�D�R�D�L���m��
�U�D�V����́u���{�I�o�c�v
���{�I�o�c�̖{���I���l�����������I
�Ƃ����ڎ����ݒ肳��C�u��ƕʘJ���g���i�O��̐_��j�C�N�����i�O��̐_��j�C�I�g�ٗp�i�O��̐_��j�v�Ƃ����A�x�O�����̎O��̐_��ɑ����āC���C���o���N���Ɗ��������������̂肠�����Ă���B�����ł́C
������������
�������������Ƃ́C�Q�ȏ�̊�Ƃ����ݔF���̏�C���݂��̊�����ۗL���Ă����Ԃ������B�������������́C���芔��̌`���i�G�ΓI�����̖h�~�j�C��Ƃ̃O���[�v���C��ƊԎ���ɂ��o�c�̈��艻�Ȃǂ�ړI�Ƃ��čs���Ă����B
�������������̃����b�g�́C���C���o���N���̂悤�Ɍo�c�Ɋ֗^�i����j���邱�Ƃ�ߓx�ȗ��v�v���Ȃǂ��N����ɂ����C����I�Ɋ�ƊԂ̊W�ێ����ł��邱�Ƃɂ���B�܂��������������ɂ���ƃO���[�v�̌`���́C���ނ̒��B�ȂǂɃX�P�[�������b�g�������炷���Ƃɂ��Ȃ�C���Ђ̎��v����Ɋ�^����_�������b�g�Ƃ����邾�낤�B
�ƋL����Ă���B
�O���ł��q�ׂ��ʂ�C�ߔN�̃R�[�|���[�g�K�o�i���X���v�ɂ��ċɂ߂Ĕᔻ�I�Ș_�҂̈�l�Ƃ��ĉ���삪����B�����i2014�j��1990�N��㔼����n�܂���������p�ė��̊������`���f���C�����ڕW�Ƃ���R�[�|���[�g�K�o�i���X���v�́C�`���I�ȉ䂪���̊�Ƃ̌o�c�̗ǂ���ے肷��Ԉ�������̂ł���ƒf���Ă���B
�y319�Łz�Čf�ƂȂ邪�C�������������ɂ��Ă��C�Z���I�Ȏ��_�ŁC�z���◘�v�Ҍ���v�����銔��̊��҂ɉ����邱�Ƃ́C�����Ē����I�ȉ�Ђ̔��W��헪�̐��s�ɂƂ��ď�ɍD�܂������̂ł͂Ȃ��C�Ɖ����͏q�ׂ�B���ɉ�Ђ͊���̂��̂ł������Ƃ��Ă��C�Z���I�Ȏ���ɂƂ���Ă��銔��̈ӌ��Ɍo�c�҂��������E����邱�Ƃ́C�]�ƈ����͂��߂Ƃ��鑼�̗��Q�W�҂ɂƂ��Ă͖]�܂����Ȃ��B�����������e��������邽�߂̕��@���F�D�W�ɂ����Ɠ��m�������𑊌݂Ɏ����������Ƃł������B�����C���ݎ�������1960�N��ɊO�����{�̔���������{��Ƃ�h�q�����i�Ƃ��č̗p���ꂽ���̂ł��������C���{��Ƃ̒����I�Ȏ��_����̌o�c�ɍv���������̂Ƃ��ĕ]���ł���Ƃ��Ă���B����ɂ��ւ�炸�C�����̃R�[�|���[�g�K�o�i���X���v�͂��̗ǂ��������������邱�ƂɂȂ����Ă���Ƃ����B�������C�]���i2011�j�́C�������������͕s�����ŕs�����ȕ��@�ł���C��ފ����̔��s��@�֓����ƂƂ̘A�g�ɂ���āC�K�v�ł���Όo�c���̈�����m�ۂ��ׂ����Ǝ咣���Ă���̂͑O���̒ʂ�ł���B
�܂��C���̎咣�ɑ��ẮC�Ⴆ�C�������������́C�����I�Ȏ��{�̑����ɂȂ��炸�C�܂���Ɗԋ�����j�Q���邷��\��������C�Ɛ�֎~�@��̖�������Ă���Ƃ����咣������C��Ж@��́C�������ɂ���Ĉ�ʊ���̌������C���ɏ�������̌������������ꂪ���ł���Ƃ��������w�E�������������B
�����͉���삪�咣�E��Ă���C����ׂ��C���邢�͖]�܂����u�����̒����A�ъ���v�̊T�O�ɂЂƂ��ɏ]�����c�_�ł���B
�����ɂ���3�j�C2010�N���͂�����̎��������͋�s�𒆐S�Ƃ������̂ł͂Ȃ��C�������C�헪�I�A�g�W�ɂ����ƊԁC�o�c�ғ��m�̐M���W�̂����ƊԂł��݂��̊������������Ƃ����`�Ői�߂��Ă���4�j�B���������̖ړI�͂͂����肵�Ȃ����C���������́C�O�q�̂悤�Ɍo�c�ғ��m�̈Öق̗����̂����ɐ��藧���Ă���B���̈Öق̗����Ƃ́C�܂��C�傫�Ȏ���̕ω����Ȃ����葊����Ƃ̊�����ۗL��������Ƃ��������ł���B�܂��C���̊������C������Ƃ̗����Ȃ����邱�Ƃ͂��Ȃ��Ƃ�������������B���ꂾ���ł͂Ȃ��C�c�����s�g�Ɋւ��Ă��C�o�c�w���x������悤�ɍs�g����Ƃ�������������B�����̗����͖������Ɏ����̂ł͂Ȃ��C����̌o�c�Ɍ�肪����ƌ��Ȃ����C�����ɔ������s�����Ƃ��邱�Ƃ����肤��B���̏��������O�ɓ���ł��Ȃ�����_�͎����킹�Ȃ��̂ł���B���{�̎Y�ƎЉ�ɂ͂��̂悤�ȏ����ꂴ��_��W�������B�I�g�ٗp���C�����I�Ȏ���W���C��������̗��E�͂��肤�邪�C���̏��������O�ɓ���ł��Ȃ����珑�ʂ̌_�ɂ͂ł��Ȃ��̂ł���B
���������̃����b�g�ƃf�����b�g�Ɋւ��Č����C�������ɁC���������͊���̗��v�ɂ�����Ȃ��Ǝv���鑤�ʂ�����B
�܂��C���������́C����̕K�{�̌����ł���c�������`�[�������鋰�ꂪ����B�����́C���̏��L�҂ɁC���v���z���錠���C���Z��̎c�]���Y�̕��z���錠���ƕ���ŁC���呍��ŋc�������s�g���錠���Ƃ����R�̌�����^����،��ł���B���̂����̑�O�̌������`�[������C����̌������N�Q����邱�ƂɂȂ�B�Ƃ��ɁC�������������̔䗦�����܂�C���������ɎQ�����Ă��Ȃ�����̌����͐N�Q����Ă��܂��B�����������̔䗦���ߔ����� �y320�Łz �Ă���ꍇ�ɂ́C��ʊ���̋c�����͂Ȃ��ƍl���Ă��悢�قǂ��B
���ɁC���������́C�s��ɂ����鉿�i�`�����䂪�߂�\��������B�s��ł́C���ꂼ��̎Q���҂����Ȃ̗��v�������l���čs������ꍇ�ɁC�����Ƃ����������i���`�������B����ȊO�̖ړI�����Q���҂������Ă���Ɖ��i���䂪�߂���\��������B��O�ɁC���Ďw�E���ꂽ���Ƃ����C���������͔z���̉ߏ�x�����������炷�\��������B���ꂪ����ɂƂ��ăf�����b�g���ǂ����͋c�_�̗]�n�����邪�C�z��������䂪�߂�\���͔ے�ł��Ȃ��B
�������C�ȏ�̂悤�Ȍ��_����łȂ��C���������́C����Ƀ����b�g��^���邱�Ƃ�����B
���ɁC���������́C�o�c�҂̑��݊Ď��@�\�Ƃ��Ă̐����������Ă���B���������W�ɓ���ɐ悾���āC�o�c�҂́C���葤��Ƃ̕]�����s���B����܂łɗǂ��o�c���s���Ă���C������ǂ��o�c���s���邩�ǂ�����]�����C�M���ł����ƂƎ��������W�����ڂ��Ƃ���B�ǂ��o�c���s���Ȃ���ƂƎ��������W�����ĂC���������W�͎����ł��Ȃ�����ł���B���̂悤�ȑ��ݕ]���́C���������W���`������Ă�����p���I�ɍs���Ă���B��ʂ̊���Ƃ͈���āC����W���邢�͔�r�I�߂��W�ɂ����Ƃ̌o�c�҂̊Ԃł̑��݊Ď��́C�����ʓI�ł���B�݂��ɂ��ǂ����������Ă��邵�C�]�����鑤������鑤���o�c�̃v���ł��邩����̌����͌��ʓI�����C��������Ƃɍs����]���͐��m�ł���B�����̏ꍇ�C�s��ł̕]�����Q�Ƃ����B��ʂ̊���́C���̂悤�Ȍo�c�̃v���ɊĎ��ƕ]�����ς˂邱�Ƃɂ���ė��v�邱�Ƃ��ł���B���ꂾ���ł͂Ȃ��C���̕]���̌��ʂ��Q�Ƃ��邱�Ƃɂ���āC���I�m�Ȕ��f�����邱�Ƃ��ł���B���������W���ێ��ł��Ȃ��Ȃ����Ƃ������Ƃ́C��ʊ���ɂ��d�v�ȏ��ƂȂ邩��ł���B
���̃����b�g�͎s��ł̗��ʊ������炷�Ƃ������ʂł���B����ɂƂ��Ď��������͎��Њ������Ɠ������ʂ����̂ł���B
��O�̃����b�g�́C��Ђ̒����I�ȗ��v�Ƃ͂Ȃ���Ȃ��o�c���s���\�������G�ΓI���������Ђ����Ƃ������ʂ������Ă���B���̂悤�Ȕ����h�q�́C��Ƃ���芪�����l�ȃX�e�[�N�z�[���_�[�̗��v�ɂȂ�C�ŏI�I�ɂ́C����S�̗̂��v�ɂ��Ȃ���B���̓_�ɂ��Ă͂Ƃ݂ɋ����������C������M&A�ɂ����Ă���荹������Ă���Ƃ���ł��邱�Ƃ͒m���Ă���B
��l�Ɏ��������́C����̃������n�U�[�h��}������ʂ����B����́C�L���ӔC�̏��L�҂ł���B�L���ӔC�Ƃ́C�o�����ȏ�ɉ�Ђ̕��x�����ɑ��Ă͐ӔC��Ȃ��Ƃ����ӔC�̌���ł���B���̗L���ӔC�́C����̃������n�U�[�h�މ\��������B��Ђ̗��v�̉ߏ�Ȕz����v�����Ă��܂��\�������邱�Ƃł���B��Ђɗ��v�𗯕ۂ��Ă����C����͕��̎x�����Ɏg���邪�C���v������̎茳�ɔz���Ƃ��Ďx�����Ă��܂��C����͕��̕ԍςɎg���邱�Ƃ͂Ȃ��B���̃������n�U�[�h�������N�����T�^�́C�O���[�����[���[�ł���B�ۗL���������̉e���͂����ƂɁC���̔��s��Ђ�W�҂ɑ��č��l�ł̈�����v������҂��O���[�����[���[�Ƃ������C�����Ŏg����u�O���[�����[���v�́C�d��̈��Ƃ��āC�_�����߂���Ƃ̊����𑽐��ۗL������C���̊����̋c�����s�g�ɂ����āC�o�c�҂Ɉ��͂���������C���Y�������o�c�w���D�܂����Ɗ����Ȃ����҂ɓ]�����邱�Ƃ�I�����Ƃ��Ē����肷�邱�Ƃɂ��C��Ƃ��u�����v���C�ۗL���������l�Ŕ�����点�đ傫�ȗ��v���������@�ł���B��̑O�́u����v�������čs����s�ׂŁC�������I�ɂ́u�o�ϔƍ߁v�ƌĂԎ҂������B
���̂悤�Ȏ��������́u�����b�g�v�������o�����߂ɂ́C���������W�͐������C���邢�� �y321�Łz �������Ɏ�舵���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�݂��̌o�c��Ԃɂ��Ă̌p���I�Ȋw�K���K�v�����C�����������̔䗦���u�ߑ�v�ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��K�v�ł���B�o�u���o�ς̎���C��s�𒆐S�Ƃ��鎝�����������܂��@�\���Ȃ��Ȃ��āC��s���K���Â��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����̂́C�������������̔䗦�����܂�ɂ����܂肷��������ł���C�Ƃ����B
���̂悤�ȉ����̎咣�́C����ɂ����āC�܂��ɂ���ɂ���C�Ƃ������Ƃ��ł���B�Čf�ɂȂ邪�C�O�q�́u�헪�I�������v�ɔ����銔��́C���ۂ͂��܂葽���Ȃ����낤�C�ƕM�҂�͍����l���Ă���B�����āC���������ɏd�v�Ȃ̂����C���{�I�����̓����Ƃ��āC���̂悤�ȁu�헪�v�͂������҂�ɐ����ɂ��Ď���ɁC���邢�͋�������̂���}�[�P�b�g�֒��ڃA�i�E���X������̂łȂ����Ƃ́C������{�̌o�ςɊW����҂Ȃ炷�ׂĂ����ӂ��Ă�����̂ł���B���Ȃ킿�C�R���y�e�B�^�[�������Q�Y�������Ă��鐢�E�ŁC���ׂĂ̎�̓����y���y���ƌ��\�����Ђ́C���ʂ͂Ȃ��B
�������Č���ƁC�����炭�A�����J�̋��ȏ��Ȃǂ����Ă���Ӗ��C�[�W�[�ɍ��肵���Ƃ݂��铌�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�E�R�[�h�C�����ĕM�҂́u�ʼn_�Ȍo�ϑO�i����v�ƂƂ炦�Ă���u�A�x�m�~�N�X�v�Ȃ�㕨�́C�����������C���͑O��������炯�̋��ȏ����@�B�I�ɐ^���Đ����i�߂悤�Ƃ����C�Ƃ�ł��Ȃ��s���ł���C�Ǝv����̂ł���B�܂�C�u�������𐧌�����Ή䂪����Ƃ̃R�[�|���[�g�K�o�i���X�����P�����v�ȂǂƂ����C�͂����茾���Ċ��S�ɗ���s���̋c�_�́C�܂��Ɂu���s���v�̋A���ł���C�����������|�W�e�B�u�Ȍ��ʂɂ����C�����̔��W�̂��߂ɂ͖ڂ�������ׂ����ƁC�S����o�ϐl�͍l���Ă���ƁC�M�҂�͎v���Ă���B
�l ��q���ɂ��u�A�z�m�~�N�X�v�_�ł́C�A�x�m�~�N�X�Ə̂���l�X�Ȑ���ɂ��ďڍׂɔᔻ��W�J���Ă���B�O�m�̒ʂ肱�̎�̋c�_�͈�T�ɐ��ہE�����f���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����C�C�O���玝���A�����u���_�v�����̂܂܉䂪���Ɏ������ނ��Ƃ̊댯���ɂ��ẮC�����ƔF������K�v�����邾�낤�C�Ƃ������Ƃ́C�ԈႢ�Ȃ�������ƁC�M�҂�͍l���Ă���B
3.2.4�@���{�I�o�c�̃����b�g�ĕ]���Ɗ�����������
�������Č��Ă���ƁC���̂悤�Ȍ��_�֓������ł��낤�B
�܂��C���{�I�o�c�̖{���I���l�����������C�Ƃ������Ƃł���B���{�I�o�c�́C�����I�Ȏ��_�ɗ����u�l�v���ɂ���Ƃ����C���{�Љ�̉��l�ςf�����o�c�̍l�����ł���C�����Ƃ��āC��ƕʘJ���g���E�N�����E�I�g�ٗp���������Ă��āC�܂��u�l�{��`�v�Ƃ������t���C���ɓI�ɂ͂���܂������̂ƌ�����ł��낤�B
�����̊��K���������b�g�́C�����܂ł̓��{�o�ς̔��W���x���Ă�����ƌo�c�̏d�v�ȃx�[�X�ł���C���ՓI�ȉ��l�����Ƃ�����ƍl���Ă���B�Ƃ�킯�������⍇�����i�����j���������߂��錻��ɂ����āC���{�I�o�c�̖{���I�ȉ��l�����������Ƃ��L���i�߂���ׂ��ł���ƕM�҂�͍l���Ă���B����͂܂��ɃO���[�o�����Ƃ��A�����J�I�s��o�ςȂǂ́u��i�I�i���邢�͒P���ȁu���ȏ��I�v�j�v�Ȕ��z�����ɂ�錻���ւ̎��g�݂Ɉ�𓊂�����́C�ƌ������Ƃ��ł���Ǝv����C���ɋM�d�Ȏw�E�ł���ƍl����B
�������������́C��ƊԂ̌��������߂�d�v�ȕ��@�̂ЂƂł���C�Ɛтւ̃��X�N�����L���C�����ɂ킽�������łȊW��z������������B�������������̍����I�ȗ��R�����߂���悤�ɂȂ�C�����������������������Ƃ������Ă��邪�C����͂܂��Ɉ�ʓI�ȁu�O���[�o�����v�C�����Ĉ��Ղȋ��ȏ��I�u�o�ύ������v�̊T�O�Ɋ�Â��v���t�����甭�����鋭���ɂ� �y322�Łz ����̂ł���ƍl����B���Ɍ�ҁi���Ղȋ��ȏ��I�u�o�ύ������v�̊T�O�j�͗l�X�ȑO������Ɋ�Â��C���邢�͂����̐����̉��Ɏ����\�ȋc�_�ł��邱�Ƃ́C���͂��܂藝���E�F������Ă��Ȃ��悤�ŁC���Ɉ⊶�����߂�ׂ����̂ł���ƌ�����B
�S�D���{�I������s�Ƃ͉����[���j�ƕ]���̕ϑJ
�O�߂Ō��������悤�ɁC���Z���{�s��ɂ������ƊԂ̊����̑��ݎ����������{�I�o�c�̓����̈�ł���Ƃ��āC���̃����b�g��f�����b�g���w�E����Ă������C�����i�╔�i�̎s��ł̎���̂�����ɂ����ĂƂ͈قȂ���{�I�ȓ������w�E����Ă����B��ƊԂ̎���́C�����i���[�J�[�����i�⎑�ނB����T�v���C���[�V�X�e���Ɗ����i���[�J�[�������Ǝ҂⏬���Ǝ҂Ǝ�������闬�ʃV�X�e���̗��ʂ���\������邪�C�ȉ��ł͑O�҂̃T�v���C���[�V�X�e���𒆐S�ɓ��{�̎�����s�ɂ��āC�ǂ�Ȗ�肪�w�E����C�ǂ̂悤�ȕ]�����Ă����̂��C�����ď����W�]�ɂ��čl�@�������Ă��������B
4.1�@���č\�����c
1980�N��㔼�C�킪���̗��j�I�Ȗf�Ս����C����ɂ�����A�����J�̖c��ȑΓ��f�ՐԎ���O�ɂ��āC�A�����J�͂킪���̌o�σV�X�e���݂̍����{�Ɗ�ƂƂ̊W�C�ʂ̊�ƍs�����ƊԊW�ɂ��āC�p�ė��̎��R�ȋ����s��o�ςƂ͈قȂ�̂ł͂Ȃ����C�Ƃ̋^�O��[�߂��B80�N��͎����ԎY�Ƃ��͂��߂Ƃ��āC�d�C�E�d�q�@��Y�Ƃ��}�������C�S�|�Ƃ��������ɂ߁C���{�̂��̂Â���o�c�����E�����|�����B���̂��߁C���ɃA�����J�Ƃ̊ԂŖf�Ֆ��C�������C���̌���1985�N�̃v���U���ӂ����������ɉ~�h������̐����̒������i�݁C���j�I�ȉ~�������ɂȂ���5�j�B�~���͗A�o�Y�Ƃ̌��Տ��������������C���{��Ƃ͍���ɒ��ʂ������C����ɂ�������炸�C���{��Ƃ͌o�c�̗l�X�ȋǖʂɂ�����H�v�Ɠw�͂ɂ���āC���̓�ǂ����������B
�������Ȃ���C���{��Ƃ̌o�c�w�͂̕\��̈�ł�����{�s��ɂ������ƊԂ̎�����s��d�g�݂Ȃǂ́C�O����Ƃ̎Q����j�ޏ�ǂƂ݂�ꂽ�B���{�����炷��C�Ⴆ�C���Ƃƒ�����Ƃ̂�����n�����W�����i�̉��i��i���C�T�[�r�X�̖ʂł̋����͂̌����}��K���̌o�c��̍H�v�ł���C���i�̖�肪�Ȃ��Ƃ̔F�������������C�C�O����͕K�������������������ł͌����Ȃ������B
1989�N�ɊJ�Â��ꂽ���č\�����c�ł́C���{�̌o�ς��Ɗ����݂̍���ɂ��āC�����̖��_���w�E����C���P���v�����ꂽ�B�}�N���o�ϖʂł͒��~�Ɠ����̃A���o�����X����莋����C���������̊g�傪���߂�ꂽ�B�Y�Ɛ���ł́C��K�͏����X�ܖ@�̌��������v������C�~�N���̊�ƍs���ł́C�r���I������s�����Čn���肪�����ΏۂƂ��ꂽ�B��Ƃ̐��Y�E���ʉߒ��ɂ����鐂���I�Ȃ��̂�T�[�r�X�̗���̒��ɂ�������I�Ȋ�ƊԂ̒����p���I�ȊW�����Ƃ��ꂽ�B���������W���C�O��Ƃ̎Q����j�݁C�A�����J�̖f�ՐԎ��̈���Ƃ��ꂽ�̂ł���B
1970�N��ȍ~�̓��{�o�ς̐����͙��ڂ��ׂ����̂ł��������C���R�̈�ɁC�u���{�I�o�c�v �y323�Łz �̗ǂ��ɂ���Ƃ��錩�����������B������R��̐_��i�I�g�ٗp�C�N������C��ƕʑg���j���j�Ƃ���Ɠ��̌o�c��@�ł��邪�C����͎s��ɂ����鎩�R�ȋ����ƎQ���E�ޏo����{�Ƃ���V�ÓT�h�I�Ȍo�ϊw���炷��C�ْ[�ł������Ƃ�������B�O�e�̎�ˁE���R�i2021b�j�Ō��������悤�ɁC���̌o�c�݂̍���́C��Ƃ̍\�����Ԃ̒����I�W�C�A�сC��L�Ȃǂ��d�v�ȗv�f�Ƃ��Đ��藧�̂ŁC�ۉ��Ȃ����I�ȃV�X�e���ƂȂ炴��Ȃ��ʂ�����B���{�I�o�c�͓T�^�I�ɂ́C��Ɠ��̌ٗp��J�g�W�ɂ�����邪�C���͊�ƂƊ�Ƃ̊W�C�܂�s��Ƒg�D�̋��E���Ƃ��[���W���Ă���B�ٗp�W�Ɗ�ƊԊW�͓��{�̊�ƌo�c�̓�����\�����Ȃ����ۂȂ̂ł���B
�܂��ɂ��̓��{�I�o�c�̓������C���č\�����c�Ŗf�Վ��x�Ƃ����}�N���o�ϖ��ƌ��т����Ĕ��ꂽ�B���̔ᔻ���Ó��Ȃ��̂ł��������ǂ����͋c�_�̗]�n�����邪�C���̐߂ł́C���{��Ƃ̊�ƊԊW�������s�̓����Ƃ͉����C���߂Č������Ă��������v���B�p�ė��̊�ƊԊW�����Ɣ�r���Ăǂ�ȓ���������Ƃ��ꂽ�̂��C����͍����I�E�����I�Ȃ��̂ł������̂��C�ǂ�Ȗ��_���w�E����Ă����̂��C�����_�łǂ̂悤�ɕ]�������̂��B�V���x�h�o�ϊw�C�Ƃ�킯����R�X�g���_�̒m���܂��Ȃ���C�c�_��W�J���Ă��������B
4.2�@���{�̊�ƊԎ���̓����\�n�����W�𒆐S��
4.2.1�@���{�̊�ƊԊW�̕���
�s��@�\����ՂƂ��Čo�ϊ������Ɗ�����W�J���鎑�{��`�����ɂ����ẮC��ƊԂ̎���́C��{�I�ɂ͉��i�������N�}�[���Ƃ��Ďs���ʂ��ĂȂ����B��ƂƊ�Ƃ̎���W�́C�A�[���Y�����X�̋����������āC����������Ƃ̈ӎv����Ɋ�Â��Č`�������B��ƊԂ̋��d��k���͎����z����c�߁C������Ȍ��ʂ����炷�̂ŔF�߂��Ȃ��̂������ł���B����͈�Ƃɐ��Z����C�������͏�ɐ��������݂��邱�Ƃ���{�I�ɂ͖]�܂����B���̂��߂ɁC�s��ւ̐V�K�Q���͗e�Ղł��邱�Ƃ��K�v�ł���B���ꂪ���ȏ��I�Ȏs��o�ς̐��E�ł��낤�B�A�����J�o�ς͂��̗��O�^�ɋ߂��`�ʼn^�c����Ă����B
����ɑ��āC���{�̏͂��Ȃ�قȂ��Ă����B�킪���̌o�ϊ����ɂ�����1960�N��ɒ��ڂ𗁂тĂ����̂��C�U���ƏW�c�ƌĂ�鋐���ƃO���[�v�ł������B�O�H�O���[�v��O��O���[�v�Ȃǐ�O�̍����̗�������ޑ��ƊԂ̌��т������{�o�ςɑ傫�Ȕ�d���߁C����͓Ɛ�I�n�ʂ��߁C�o�ϓI�e���͂��r�傠��Ƃ̋c�_���W�J����Ă���6�j�B�����ł͑��݂Ɋ��������������C�W�c�Ƃ��Ă̌������ւ��Ă����ƌ�����B���̊�ƏW�c�ɂ͓����̓s�s��s�𒆊j�ɑ��p�I�E�����I�ȗl�X�ȋƎ�Ɍׂ��Ƃ��Q�����C���{�̑�\�I�Ȋ�Ƃ�����I�ɎВ�����J�Â��C���܂��܂ȏ��̌������s���Ă����B���̊�ƏW�c�����{�o�ςɂ����Ăǂ̂悤�Ȗ������C�ǂ̒��x�ʂ����Ă����̂��ɂ��ẮC�{��i1976�j�̌������͂��߂Ƃ��āC��ʓI�ɂ͂��̌o�ϓI�e���͂��邢�͎x�z�͂͋���ł������Ƃ��錩�����L�͂ł������B�������C�O�ց������U�C���[�i2001�j�͂��������ʔO�ɉs���^�����Ă���B�����ΏۂƂȂ��Ă����ƏW�c���ꎩ�̂̒�`�̞B������C�����ɏ������邱�Ƃ��瓾���闘�v�Ȃǂɋ^����Ȃ������Ă���B
���ɁC�����������p�I�Ȋ�ƏW�c�Ƃ͕ʂɁC������g���^�Ȃǂ̋��僁�[�J�[�_�ɑ����̕��i�E���H�T�[�r�X������ƌQ���K�w�I�Ɏ�����s���Ă���n�����W�ƌĂ� �y324�Łz ��C��A�̐��Y�i�K�����Ԋ�ƊԂ̐����I�ȊW���킪���̌o�ύ\��������Â�����̂Ƃ݂��Ă����B
�Ƃ�킯�C�킪���o�ς��}�����𐋂��������ɂ́C���̌n�����Ƃ̌p���I�������I�Ȋ�ƊԎ���̉ʂ����������傫�������ƌ�����B���̓_�ɂ��ẮC���߂ŏڍׂɋc�_����Ƃ��āC��ƊԂ̐����I�W�Ƃ��Ă͗��ʋ@�\�ɂ����郁�[�J�[�Ə��Ђ⏬���X�Ƃ̊W�����邪�C���̊W�ɂ������p���I�ȐF�Z���Ǝ���ώ@���ꂽ�B���̈Ӗ��ŁC���{�̌o�ϊ����ɂ����ẮC���R�ŋ����I�Ȏs��o�ςƂ����Ȃ���C���ď����ɔ䂵�Ă�����u���������v�ɂ�钲���Ɉς˂��Ă��镔���ɔ�ׂāC�u�������v�ɂ�钲���̐�߂銄�����ڗ����Ă����̂ł���B
��ƏW�c���܂߂āC��ƊԂ̊W���L�`�Ōn��ƌĂׂC����i1992�j�ɂ��ƁC��ʂ��āC���̂悤�ɕ��ނł���B
�P�D�����^��ƃO���[�v�@�ɂ����p�I�Ɍ��т�����ƊԊW�ł���C�L�͋�s�����C�o���N�̋@�\���ʂ����Ă���C��Ƃ̏W�c�B
�Q�D�Ɨ��^��ƃO���[�v�@�����C�g���^�̂悤�ȗL�͂ȑ��Ƃ��j�Ƃ��Č`�������֘A��Ƃ̃O���[�v
�Q�̓Ɨ��^�̃O���[�v�͂��̔��W�ߒ��ɒ��ڂ��āC����ɂ������̏��O���[�v�ɕ�������B����ɂ��ƁC�Q�̃^�C�v�͂ǂ��̍��ɂ��݂�����̂ł��邪�C�P�̃O���[�v�͂킪���ɓƓ��ȑ��݂ł���B�P�̍����^�̊�ƃO���[�v�́C��O�̓��{�̗��j�ƌ��т��āC���̉e���͂����`����Ă������C��q�̎O�ցE�����U�C���[�i2001�j���w�E����悤�ɁC���̎����I�ȋ@�\�͂��܂�Ȃ������Ǝv����B��ƏW�c�O�̊�ƂƂ̎�����s���Ă������C���������o�ύ������������ďW�c�������D������悤�ȊW�����v����������炷�Ƃ͍l���ɂ����̂ł���B
���č\�����c�ł͗��҂Ƃ��n��ikeiretsu�j�ƌĂ�C�킪���̕�����������ے�����o�ς̍\�����Ƃ��Ĕᔻ�𗁂т��B���������]�����I�m�ł��������ǂ����́C�X�̃O���[�v�̋@�\������ɗ��������Č�������K�v�����邪�C�����ł͂Q�ɑ�����O���[�v�̐����I�Ȑ��Y�n������グ���Ƃɂ������B���̊�ƃO���[�v�͂ǂ��̍��ɂ��݂���ƌ����邪�C���̍L�����ʂ����������̑傫���Ƃ������ʂł͉䂪���͔�����łĂ����Ǝv����̂ł���B
4.2.2�@�����I����W�\�n�������
�P�j�`���I�c�_�Ƃ���ւ̔ᔻ
���������_�܂���C�킪���̊�ƊԊW�̓����̈�ɁC�n��W��ʂ��Ď���������I�ɂȂ���C�p���I�ɍs���Ă��邱�Ƃ������Ă悢�ł��낤�B��\�I�ȎY�Ƃ��g���^����Y�Ƃ��������Ƃ_�Ƃ��鎩���ԎY�Ƃł���B�����ԎY�Ƃ́C�ŏI���i�̑g�ݗ��Ă�S�����Ƃ̎P���Ɉꎟ�C�C�O���E�E�E�Ƃ������`�Ōn������Ƃ��s���~�b�h��ɊK�w���Ȃ��Ă���C���i�̋����C���H�T�[�r�X�̒��A���I�ɍs���Ă���B
���_�ɗ���Ƃ́C�e��ƂƌĂ�C��������Ƃ͐e��Ƃ��璍�����āC���Y���H�����āC���i��T�[�r�X������Ƃ��ď��K�͂̊�Ƃ��w���̂ł��邪�C���Ă͂����ɂ����Đe��Ƃ���̎��D����ɂ���āC���̗͂�鉺����������Ƃ͔̏ߎS�ł��邱�Ƃ��w�E����Ă����B
���ꂪ�킪����Ƃ�o�ς̋}���W�̉A�ɑ��݂�����d�\�����ł���B���̖��̓}���N�X �y325�Łz �o�ϊw�̉e������������ƌ����҂��������Ė��Ƃ��Ă����Ƃ���ł���B�܂�C������������Ƃ̋]���̏�ɁC�e��Ƃ̐����C����ɂ͓��{�o�ς̔��W�����藧���Ă���Ƃ������̂ł���B�����������C����̈���I��~�C�s���Ȓl�����v���C����C�Ȃǂ����s���Ă����Ƃ����킯�ł���B���̋c�_�́C�}���N�X�o�ϊw�I���_����W�J����Ă���C���̗��_�I�}������Ɛ�I���Ƃƒ�����Ƃ̎x�z�]���W������Ӗ��C���R�̂��ƂƂ��Ă����B
�������C�����������Ƃ̐ꉡ���ǂ̒��x������Ă������C���邢�͂��������\�ł��������C����ɋ^����悳���悤�ɂȂ����B�`���I�ȋc�_�́C�n�������ꊇ���Ď�҂Ƃ��Ĉʒu�Â��C�Z�p�͂����C�J���������ŁC��Ɨ������Ⴂ�Ƃ��Ă������C���Y������ώ@���������҂ɂ���āC���Ԃ͕K�����������ł͂Ȃ��C�������钆����ƁC�Z�p�͂̊m���Ȓ�����Ƃ��������݂��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă����B�O�ցi1989�j�́C1970�N��ȍ~�̑��Ƃƒ�����Ƃ̗��������r���C��҂̗���������т��č��������f�[�^�Ɋ�Â��āC���ƌĂ��悤�Ȍ��ۂ͂����������݂��Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝ咣�����B����ɑ��ẮC�ʂ����ė������������݂āC������Ƃ̒u���ꂽ�f���Ă悢���ǂ����Ƃ̔��_�͉\�ł��낤���C��҂Ƃ��Ă���������Ƃ𑨂��錩���ɂ͌��E�����邱�Ƃ������Ă���ƌ����悤�B
�܂��C����i1997a,b�j�͌n�����W�ɂ��āC���j���7�j�Ƃ��̃T�v���C���[�Ƃ̊W�Ƒ����Ȃ����C�n�����Ƃ������t�Ɋ܂܂��]���I�ϔO��r�����āC���̎��ԂJ�Ȍ��꒲���Ŗ��炩�ɂ��C�����ԎY�Ƃɂ����镔�i����\���ɐV���Ȍ��Ă��B
�ނ̕��͂́C���j��Ƃƈꎟ�n�[�J�[�Ƃ̊W���z�肳��Ă���C�n�����W�S�ʂɑÓ�����킯�ł͂Ȃ����C�`���I�c�_�ł͌����Ȃ������n�����̑��ʂ����炩�ɂ��ꂽ�B
�����ԎY�ƂŎ������镔�i�́C��ʂɂR��ނɕ��ނ����B��́C�s�̕i�ƌĂ����̂ŁC�w���s��ɂ����Ďs�ꉿ�i�œ���ł��镔�i�ł���C�Ƃ肽�ĂāC����̃��[�J�[�����ɂ��炦��K�v���̂Ȃ��ėp�i�ł���B��������������Ђɂ́C�K�͂̑傫����Ђ�����C�������Ƃ͌Ă�Ȃ��̂��ʗ�ł���B
���ɁC����̃��[�J�[�̐��i�C���邢�̓��f�������ɂ��炦��K�v�̂��镔�i�C�����i������B�����������������Ƃ��āC�Q��ނ���Ƃ����i�}�\�P�Q�Ɓj�B��͑ݗ^�}��Ƃ�ʂ��������ŁC������͏��F�}��Ƃ�ʂ��������ł���B�O�҂͒��j��Ƃ��v�}��^���C����ɉ����āC���i�삷��B�ݔ���H����^�����邱�Ƃ������C�����I�ɒ��j��Ƃ̎w���ɂ��̂܂]���B���̈Ӗ��ŁC�������Ɍ������ƂƂ������悤�B����ɑ��āC��҂͒��j��Ƃ̗v���ɉ����āC�T�v���C���[�����i�̐v���s���C���i�̐���������B���j��Ƃ̓���̐��i��f���ɂ����g����ݔ��ɓ������C���Y���邱�Ƃ��v�������B���̍ہC���j��ƂƂ͕��i�̐v�i�K���狦�͂��C�w���C���������肵�Ȃ�����C����ɋZ�p�\�͂�~�ς��C�������Ă����P�[�X������B������ɂ���C���j��ƂƃT�v���C���[�̊W�͒����p���I�Ȏ���ƂȂ邱�Ƃ���ʓI�ł���B
�y326�Łz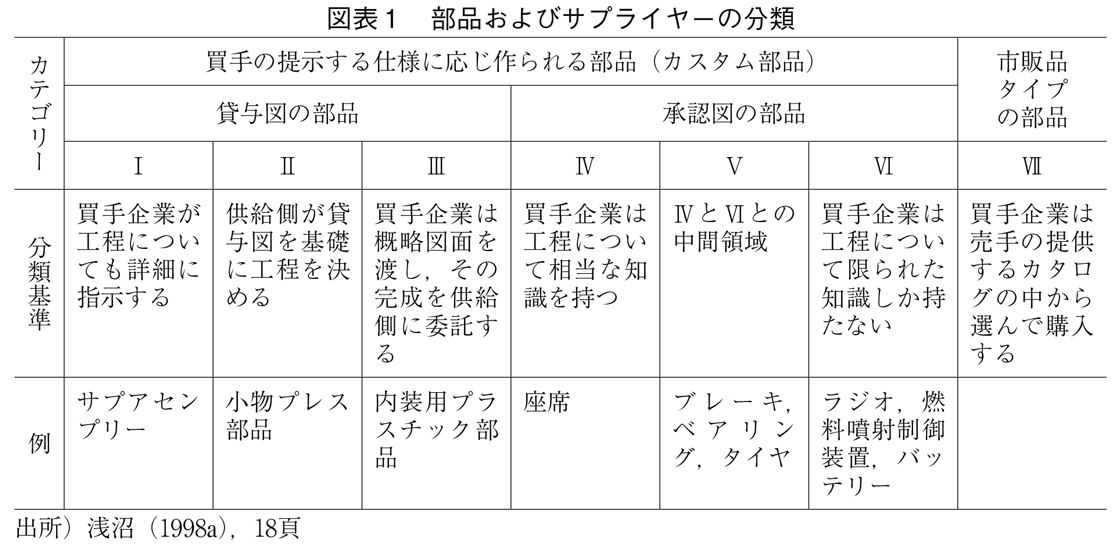
���������W��ʂ��āC���j��ƂƃT�v���C���[�͂Ƃ��ɐ������Ă����B����I�ɍ�悪�s��ꂽ�Ƃ��C�s�����ɂ����ăT�v���C���[���o�b�t�@�Ƃ��Ĉʒu�Â��Ă����Ƃ��C�x�z�]���W�ɂ��������Ƃ������_����͑������Ȃ��������������̂ł���B�p���I����Ƃ����Ă��������Ɍp�������킯�ł͂Ȃ��C���R�̂��ƂȂ���C���������̎d�g�݂�D������Ȃ���C�T�v���C���[�Ԃ̋����𑣂��C��������o�ύ��������ѓO�����Ă����̂ł���B����ł́C�������������p���I����͂ǂ�ȏ����̂��ƂŁA�L���ł��肦���̂��낤���B
����R�X�g���_�ɂ���āC���̗��_�I������T���Ă݂悤�B
�Q�j����R�X�g���_�ɂ�����
��ƂƊ�ƂƂ̊W���ǂ̂悤�ɐv����̂��Ƃ������́C�s��Ƒg�D�̋��E���ƌ��������邱�Ƃ��ł���B�V�ÓT�h�I�Ȍo�ϊw�̎s��ςɂ��C���i�������N�}�[���Ƃ���X�|�b�g�s��ɂ�鎑���z���ɂ���āC���������B�������B�ɒ[�ɗ��z�I�ȃP�[�X�C���S�����̏��������������ꍇ�ɂ́C�s��ł��ׂĂ̎����z�����s�����Ƃ��\�ł���͂��ł���B�������C�R�[�X�i1937�j�����Ę_�����悤�Ɍ����̎s��𗘗p����ɂ́C���܂��܂ȃR�X�g��������B�s��͕s���S�ł���C�l�Ԃ̍������ɂ͌��E������B�����ŁC�s��ɑ���q�G�����L�[���o�ꂷ��B�E�B���A���\���i1975�C1985�j���w�E����悤�ɁC����R�X�g�̑��݂��K�w�g�D��a�������邱�ƂɂȂ�B
�o�σV�X�e�����\�����鑽�l�Ȑ��x�̗D����K�肷��L�͂ȗv��������R�X�g�Ƃ����킯�ł���B����R�X�g���_���邢�͐V���x�h�o�ϊw��1970�N��ɓo�ꂵ�C�o�ϊw��o�c�w�ɑ���̉e����^���Ă����B�����́C��ƂƂ����g�D�͂Ȃ����݂���̂��Ƃ����C����Ӗ��ɂ߂đf�p�ȋ^��ɑ��铚���������悤�Ƃ�����̂ł������B���̓����́C�����P���Ɍ����Ύ���R�X�g�̑��݂ł���C�s��̋@�\�s�S�ɑR���Đ������鐧�x���g�D�ł������B�]���āC�s�ꂩ�g�D���Ƃ����Q���@�Ɋ�Â��C�s�ꂪ�����I�łȂ���C�����������s���Ċ�Ɠ����Ɏ������荞�ނ��ƂɂȂ�B�����́C�s��ɂ����Ē����p���I�Ȋ�ƊԂ̊W�������Ƃ������Ƃ́C��{�I�ɂ͑z�肳��Ă��Ȃ������B���邢�͂��������W�͖]�܂����Ȃ����̂Ƃ݂Ȃ���Ă����B
�y327�Łz�Ƃ��낪�C���{�o�ς��Ƃ��}��������ߒ��ŁC���Y�ʂɂ����Ă��C���ʖʂɂ����Ă��܂����Z���{�ʂɂ����Ă��C��ƊԂ̊W���A�����J�ɔ�ׂĔZ���ŁC�p���I�ŁC�����I�ł��邱�Ƃ��ώ@����C�F������Ă����B������������݂̍���́C�X�|�b�g�I�s������C���Ƃ��C�X�|�b�g�I�Ȏs�ꂪ�@�\���Ȃ��ꍇ�ɂ́C�����I�����ɂ��K�w�g�D������ɂƂ��đ���̂��W���ł��鉢�Ă���َ͈��Ƃ݂��Ă����B�������킪���ł́C�����ԎY�Ƃ�d�@�C���D�ƂȂǂɂ݂�ꂽ�悤�ɁC��d�ɂ��킽��n������Ƃ����i�C���H�T�[�r�X�����Ƃ����̐����ł��Ă����B����͏����Ȏs��Ƃ��C�����Ƃ��قȂ��ƊԂ̎���ł������B�Ȃ����̂悤�ȊW���p������̂��C�����Ă���͌����I�ł���̂��B
����ɂ��āC�ɓ��i1989�j���̂悤�ɐ������Ă���B�P���Ȏs�����ł��ׂĂ��܂������̂ł���C�����p���I�W�͕K�v�Ȃ��B�����������ɂ͂����͂����Ȃ��B�Ȃ����B��ɂ͎������镔�i���W���I�łȂ��ꍇ�ł���B���̂Ƃ����G�ȍ��ɂ��āC���̐����E�d�l�m�Ɍ_��ɗ��Ƃ�����ŁC���Ԃ̂�����Ȃ�B�܂����ɒ����ł��Ă��C�_���Ɏ�����~�����Ȃǂ́C����s�ׂ�����C���������T�v���C���[�͑�������B����s�ׂłȂ��Ƃ��C�����ς�������Ƃɂ���āC�����҂����c����K�v�������邱�Ƃ�����B�l�Ԃ̍������Ɍ��E������C����͔������Ȃ����Ƃł���B���������ꍇ�C�Z���I�ȊW�ł���C���̓����҂͗��ȓI�Ɉꎞ�I�ȗ��v�̊l���ɑ��邪�C�Q�[�����_�̐��ʂ������悤�ɁC�p���I�W�ł���C�����I�ȗ����̍ő剻���l���āC�s�����邱�ƂɂȂ낤�B
�܂��C��Ɠ���I�ȓ������K�v�ȏꍇ�C�����ԎY�Ƃł����C�s�̕i�ȊO�̕��i�ɂ��ẮC�����������z�̉���ɂ͈����Ԃ̎��Ԃ��K�v�ł���C���̊Ԃ̌_���炳���K�v������B���̌_��͕K�R�I�ɂ��ׂĂ̌_��������K��ł��Ȃ��s�����Ȃ��̂ɂȂ炴��Ȃ����C���̂��ߒ����I�W���v�������B����͖@���̐��E�ł͊W�I�_��ƌĂ����̂ł���C�_��̒�������߈Ӗ��Â��͎Љ�I�Ȕw�i�╶���̒��ōs����K�v���o�Ă���B�����ł́C�����i1997�j�̌����M��8�j�C���ɑP�ӂɂ��M�����傫�Ȗ������ʂ������ƂɂȂ낤�B���{�́C�����I�Ȗ����ō\������C�����ł���Ƃ����n���w�I����������āC�M���������N���������Ē~�ς���Ă���C���̂��߂������Čp���I�W�����ɗL���ɋ@�\���Ă����Ƃ�����̂ł͂Ȃ����낤���B�������C����͂�����S�ɋ@���`�I�s����j�~������̂ł͂Ȃ��C��E�̗U���͏�ɂ���Ƃ�������B�����ŁC���Q�̋��ʐ������߂邽�ߊ����̑��ݎ������⋦�͉�`�����ꂽ�ƍl������̂ł���B
����R�X�g���K�肷��̂́C������Ɛl�Ԃ̍������̌��E�ɂ��̂ł��邪�C�ǂ̂悤�ȓ����\���������I�ł��邩�����E����v���Ƃ��ăE�B���A���\�������ɋ��������̂́C�����̔�t���⎑�Y���ꐫ�ł���B���Y�̓��ꐫ���Ȃ���C�s����g���R�X�g�͈������̂ŁC���ׂĎs��ɔC����悢�B���Y�̓��ꐫ�����܂�ɂ�āC��蕡�G�ȓ���@�\���K�v�Ƃ����̂ł���B�O���ŋL�q�������F�}�̕��i�ɂ���C�ݗ^�}�̕��i�ɂ���C�n������Ƃ��S���Ă���̂́C�����x�̎��Y���ꐫ��L���镔�i�ł���C�s��ƃq�G�����L�[�̒��ԓI�����\���ɓK���I�Ȃ̂ł���B
���̋c�_�͊�{�I�ɂ͎���R�X�g���_�Ɋ�Â����̂ł���C���䑼�i1982�j�̓����g�D�̌o �y328�Łz �ϊw�œW�J���ꂽ�c�_�ƒʒꂵ�Ă���B�s��ɂ��K�w�g�D�ɂ����ꂼ�ꃁ���b�g�C�f�����b�g������C����������������̓����ɂ���ẮC���҂̒��ԓI�Ȍ`�ԁC�����\���������I�ł��蓾��̂ł���B���{�I�Ȍn�����W�Ƃ͂܂��ɂ��̒��Ԍ`�ԁC�n�C�u���b�h�`�Ԃ��邢�̓l�b�g���[�N�ɊY������ƍl������B
�R�j�n��W�̕]��
���������������炷��C���̏����̉��Œ��ԓI�ȑg�D�C���邢�̓l�b�g���[�N�͌����I�ł���C�m����Z�\�̒~�ςɂ��v�����Ă����B�]���āC�ǂ̍��������Ă���ƊԂ̒����p���I�W�͌o�ύ�����������ƍl������B���ꂪ�Ȃ����{�ɂ����Č����ɂ݂���̂��Ƃ����_�Ɋւ��Ă͂����炭���j�I�ȗv���C�����I�v�����傫���̂ł��낤�B���̉�œI�ɂ����āC�����I�ɂ��l�ޖʂł����Ƃ����ׂĂ̕��i�̐��Y�C���H�H�������Ђōs�����Ƃ͔\�͓I�ɂł��Ȃ������B�����Œ����̒n���Ƃ��w���琬���C�^�������̓I�ɎY�Ƃ̔��W��S�����ƂɂȂ����B�����ԎY�Ƃɂ��Ă݂�ƁC�A�����J�ł͂ނ���t�ɂ��̏����ɂ����ė��p�\�ȕ��i��Ƃ����݂����C�g�ݗ��ă��[�J�[������������Ȃ������Ƃ������j�I����������B
�ٖ��Ȋ�ƊԊW���ǂ̂悤�Ȏ����ɁC�ǂ̂悤�ȎY�ƂŌ`������邩�́C�o�ϓI�v�������邪�C���j�I�v��������C���R�̗v�f���傫���Ǝv����B��U�C�`�����ꂽ�W���������߂ɂ͍������E���������Ȃ���Ȃ�Ȃ����C���ꂪ�m�ۂ���Ă���C��قǂ̋Z�p�I�ω����Ȃ���Α����Ă����ƂɂȂ낤�B���̉䂪���ɂ�����n��W�C�����p���I������s�͂��̏��������Ă����Ɛ��F�����B
4.3�@�ߔN�̓W�J
1980�N�ォ��1990�N��ɂ����āC���{�I�n�����C���������L�������Γ��{�I�Ȋ�ƊԊW�������đ傢�Ɍ����̒~�ς��i��ł����B����͊T�ˁC���_�͂�����̂́C���{�I��ƊԊW�̌������C�o�ϓI���������咣�����B������x���鍪���͗l�X���邪�C���Y�ʂ���̋Z�p�I�����́C�����ԎY�ƂɓT�^�I�ł��邪�C����ΏۂƂȂ鐻�i�����荇�킹�^�i�C���e�O�����^�j�̓�����L����Ƃ������Ƃł������B�������i���v�C�H���Ǘ��C�[�������̊Ǘ��������ԎY�Ƃ̋����ɏ����������߂̕K�{�����ł���C������ō��x�ɐ����i�߂��g���^�̃J���o�������͂��̑�\�I�Ȑ��Y���@�ł������B����̓��[�����Y�����Ƃ��ăA�����J�ł��C�O��I�Ȍ������Ȃ���C1990�N���ʂ��āC�Z�����Ă������B
�������C�܂��ɁC���̎��ɁC����ɂ��n��Ȃ��������p���I����̌��������o�c�s�U�Ɋׂ��Ă������Y�����Ԃɂ���Đi�߂�ꂽ9�j�B���I�Ȏ���W���ʂ�ܓ��I�ȑ��݈ˑ��������炵�C�o�c�̌������˂Ă���Ƃ̌�������C�S�[���В��̉��Ōn��̌������C�ĕҐ����s��ꂽ�B�n��O������Ђ�����������C�S���E��ΏۂƂ��čœK�w���̃X���[�K���̉��Ɍ��������B�헪���W�J���ꂽ10�j�B���������������́C�����ԎY�Ƃ����łȂ��C�d�C�E�d�q���i �y329�Łz �Y�Ƃɂ����Ă��i�߂��C�Œ�I�E�p���I�Ȏ�������ΏۂƂ���w���s���͏��X�ɕς��n�߂��B���̔w�i�ɂ́C���i�̃��W���[����11�j�Ƃ������ꂪ�������B���W���[�����Ƃ͕����̍\�����i���犮���i������C���i�Ԃ̐ڍ��̓C���^�[�t�F�C�X��ʂ��čs����悤�Ȑv�v�z�ł���B���̂��߁C���i��g�ݗ��Ă�̂ɔ����ȁC�����ĕ��G�Ȓ������K�v�Ƃ���Ȃ��Ȃ����̂ł���B���̋Z�p�I�ȕϊv�́C���j��ƂƃT�v���C���[�̊Ԃł̖Ȗ��Ȓ������������s�v�Ƃ�����̂ł������B�����������Ԃ��n��W���ǂ̂悤�ɕς��Ă������ƂɂȂ����̂��B�ŋ߂̒��������Ă݂悤�B
2017�N���s�́w�����@���x�ɓ��{���@�w��V���|�W�E���u�u���{�I������s�v�̎��Ԃƕϗe�v�ɒ�o���ꂽ�������̘_�����f�ڂ���Ă���B�����ł́C�����ԎY�ƁC�d�@�Y�ƁC�V�X�e���E�C���e�O���[�V�����Y�Ƃɍi���āC���⎆�����ƃC���^�r���[���������݂Ă���B
���ӎ��͂����̎Y�Ƃɂ����āC���{�I������s�ƌ����钷���p���I����W�����������ǂ����̊m�F�C����͌��݂��F�߂��邩�C�ߔN�ǂ̂悤�ɕω��������C�ω������Ƃ����炻�̗��R�͉����C�܂�����ɂƂ��Ȃ��Č_��݂̍���͕ϗe�������C�Ƃ������_�ł���B���ˁi2017�j�́C�W����I�����̏d�v���Ǝ�������҂̓������Ƃ����ϓ_������{�I������s�ƃA�����J�I������s�𒊏o���Ă���i�}�\�Q�Q�Ɓj�B���{�I������s�͊W����I�������d�v�ȎY�ƂŊώ@����C�_��͂��܂�ڍׂɂ͂Ȃ���Ȃ��Ƃ������F��L���Ă���B����ɑ��ăA�����J�I������s�́C�W�I���ꎑ�Y�̏d�v�������Ȃ��Y�ƂŁC��������҂������̏ŁC�_��̓t�H�[�}���Ȍ`�ŏڍׂɂȂ����Ƃ������F�������Ă���C�Ƙ_���Ă���B
���̒����ɂ��C�Y�Ƃɂ���ĈقȂ邪�C���{�I������s�͊m���ɑ��݂����̂ł���C�_��̎d���ɂ����Ă����Ă̍�������B����������͌Œ�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��C�Z�p�v�V�C���Ƀ��W���[�����Ƃ������ۂ��C��ƊԊW�ɂ��Ȃ�̉e�����y�ڂ��Ă���悤�ł���B���W���[�����͎�����s�ɉe����^���Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��C�����ԎY�Ƃł͂܂����荇�킹���d�v�ł��邪�C���̎Y�Ƃł͎���͏����قȂ��Ă���C�s�����I�v�f�������Ȃ��Ă���B�������C����ɂ�������炸�C�_��̏ڍׂ��ȂǁC�_��̂�����͑傫�ȕω��͌����Ă��Ȃ��̂����Ԃł���C���ꂪ���{�̓����Ƃ����邩������Ȃ��B
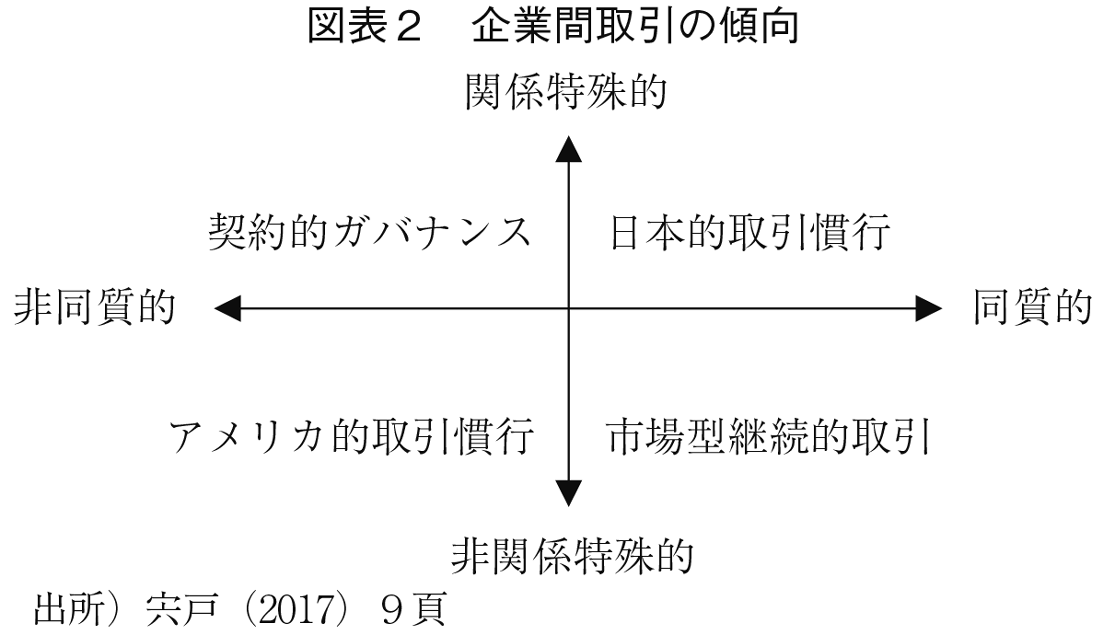 �y330�Łz
�y330�Łz
���ɁC���i2021�j�́C�}�\�R�Ɏ�����Ă���悤�Ȏs�ꐫ�Ƒg�D���̗��ݍ����Ƃ������_����䂪���̊�ƊԎ���������ԁC�H��@�B�C�S�|�ƂȂǂɂ��Đ�O����̒����X�p���̒����ŁC���̓����𖾂炩�ɂ��Ă���B���ꂼ��̎Y�Ƃ͑f�ށC���i�C���{���Ƃ��������i���قȂ�C�܂�������\�������Ƃ����Ƃƒ�����Ƃ����ł͂Ȃ��C���ƊԂ̊W���܂܂�Ă���C��ƊԊW�̕��͂Ƃ��ď]���̌����Ƃ��قȂ����C�L���p�x���番�͂������Ă���B����ɁC�����ԎY�Ƃ̗��j�܂������ė����̔�r���͂��Ȃ���Ă���B
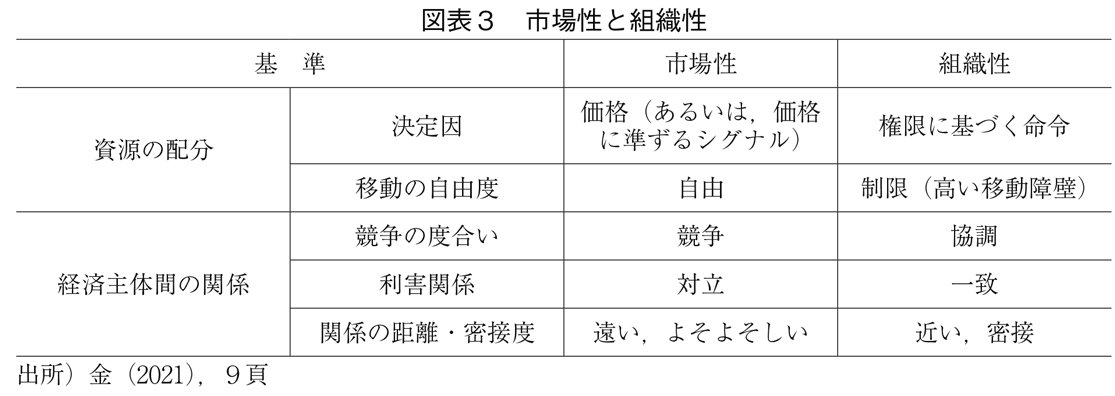
�����ł̌��_�������P�������Ă����C��ƊԊW�ɂ�������{�I�ȓ����͒ʏ�C���i2021�j�̕\�����g���C�g�D���ɋ��߂��邱�Ƃ��������C�K����������͓��{��Ƃ�Y�Ƃɓ��L�Ȃ��̂��Ƃ͌����Ȃ��B�A�����J�ł��g�D�I����͂��Ȃ�L�͈͂Ɋώ@�����̂ł���C���{�Ǝ��̌��ۂł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B��ƊԎ���ɂ����āC�s��ɋ߂��Z���I�ȊW����C�g�D�ɐڋ߂��������p���I�ȊW�܂ŁC�����X�y�N�^�N�����Ȃ��ĕ���ł���̂ł���C�ǂ̍��ɂ����Ă��C�܂��ǂ̎���ɂ����Ă��C�s��̃P�C�p�r���e�B�̕����◘�p�\���܂��Ȃ���C�����I�ɑI�����Ȃ���Ă���Ǝ咣���Ă���B
��ʂɓ��{��Ƃ̊�ƊԊW�̓����ɂ��āC�n��C��ƏW�c�Ƃ������g�D�I�ȕR�т���������c�_�������C���ꂪ�o�ύ����I�ł������Ƃ���B�������C��O�ɂ����ẮC���{�ɂ����Ă��s��I�ȒZ���I�W���嗬�ł������Y�Ƃ�����B���̊ϓ_���猩��C���̓��{�I�o�c�Ȃ������{�I������s���`���I�ł���Ƃ������Ȃ���������Ȃ��B�ɓ��i1989�j�������悤�ɁC����͐��̌o�ς̍��x�����Ƃ����������x���Ă����Ƃ�������B
���{�I������s�̎�_�́C���̕����ɂ���̂ł���C�ߔN�ł͂��̕����̂ɁC�Z�p�ω��ɑΉ��ł��Ȃ��C�O���[�o�����̖W���ɂȂ�f�����b�g�Ƃ��Ĕᔻ����邱�Ƃ������Ă���B�������C���ۂɂ͉ߋ��ɂ����Ă����݂ɂ����Ă��C�g�D�I�Ɋ�ƊԊW��Ґ����邾���łȂ��C����ɂ����Ďs��I����̑��ʂ������݂�ꂽ�̂ł���B����������Ƃ͂��̗��҂̗ǂ����I�݂Ɏ�����C���W�ł����̂ł���C���̓_�ɂ����Ă͓��Ċ�Ƃ̍��͈�ʂɌ����Ă���قǑ傫���͂Ȃ��C���i2021�j�͗ގ����������Ǝ咣���Ă���B
4.4�@���@��
�����p���I��ƊԊW�́C�����ԎY�Ƃ�T�^�ɍ��x�g�ݗ��ĎY�Ƃ��x�������{��Ƃ̋��݂ł������B����ɑ��āC���̕��ƍ\�������I�ł���Ƃ���ᔻ�I�c�_���������B�������C�� �y331�Łz �{�I�Ȋ�ƊԊW�͌o�ύ������E�������ɗ��ł����ꂽ�d�g�݂ŁC���Ƃ����ɗL���ł������̂ł͂Ȃ��C���X�N���S�݂̍�����݂�Ǝ��͌n�[�J�[�ɂ������b�g�͂������̂ł���C�m��I�ȕ]�����������Ƃ��ł���ƕM�҂�͍l����B����͈��̋Z�p�I������o�ϊ��C�J�����Ɏx����ꂽ���̂������ƌ����悤�B
�C���e�O�����^�̐v�v�z�ō���鐻�i�́C���i����H�T�[�r�X�ȂǃT�v���C���[�Ƃ̂��߂ׂ̍����A�g����ł���B���̍ہC��Ɠ���I�ȓ����ɔ����@���`�I�s����j�~���邱�Ƃ́C���ڂȊ�ƊԊW�̍\�z�̏d�v�ȗ��R�ł������B�������Ȃ���C�����W�]�Ƃ��ẮC���i��ŏI���i�̃��W���[�������i�ނƁC����܂ł̂悤�Ȓ����p���I�Ȏ���W�̃����b�g�͔���Ă�������������Ȃ��B�������C���ɂ��̂悤�Ȑ�����L���Ȃ����̂ł����Ă��C�s�m�����̍������̒��ł̎���ł���C�����p���I�ȊW�̗L�p���́C��������݂����ʂ͑��X����Ǝv����B�f�W�^���E�g�����X�t�H�[���[�V�����ւ̑Ή����ۑ�ƂȂ�C�v���b�g�t�H�[����G�R�V�X�e���̌`�����������ɂ߂钆�C�T�v���C���[�Ƃ̊J���ꂽ��ƊԂ̃l�b�g���[�N�W�C�s��I�W�Ƒg�D�I�W�̗Z����헪�I�g�������C�����ċZ�p�~�ς⑊�݊w�K���\�Ƃ���_�C�i�~�b�N�Ȋ�ƊԊW�̍\�z���v������邱�ƂɂȂ邾�낤�B
�؏��F�E�������F�Ғ��i2002�j�C�w���W���[����—�V�����Y�ƃA�[�L�e�N�`���̖{���x���m�o�ϐV���
����ݗ��i1997a�j�C�u���{�ɂ����郁�[�J�[�ƃT�v���C���[�Ƃ̊W—�u�W����I�Z�\�v�̊T�O�̒��o�ƒ莮���v�i���{���G�E�����q�G�E�ɓ��G�j�ҁw���[�f�B���O�X�@�T�v���C���[�E�V�X�e���x�L��t�C1-39�j
����ݗ��i1997b�j�C�w���{�̊�Ƒg�D�@�v�V�I�K���̃��J�j�Y���x���m�o�ϐV���
����ݗ��E�e�J�B��i1997�j�C�u���i����ɂ����郊�X�N���S�ƃ������E�n�U�[�h�[�����ԎY�Ƃɂ�����_��̃~�N���v�ʕ��́v���{���G�E�����q�G�E�ɓ��G�j�ҁw���[�f�B���O�X�@�T�v���C���[�E�V�X�e���x�L��t�C249-282�j
�ɓ����d�i1989�j�C�u��ƊԊW�ƌp���I����v�i���䌫��E���{�����Y�ҁw���{�̊�Ɓx������w�o�ʼn�C109-130�j
���䌫��i1992�j�C�w���{��`�̃V�X�e���ԋ����x�}�����[
���䌫��E�ɒO�h�V�E���r�a�j�i1982�j�C�w�����g�D�̌o�ϊw�x�C���m�o�ϐV���
�E�F�X�g�j�[�E�N�X�}�m�i2010�j�C�u�u��Ձv�Ɓu�I���v�̐�ɉ����݂���̂��F���Ă̘_���ɂ݂���{�̋����͕]���v�i�����E���Ώ��E�}�C�P��A.�N�X�}�m�w���C�h�E�C���E�W���p���͏I���̂��x���m�o�ϐV��ЁC24-65�j
���c�M�i1990�j�C�w�_��̍Đ��x�O����
THE OWNER �ҏW���i2021�j�C���{�I�o�c�Ƃ́H��������b�g�E�f�����b�g���ڂ�������I�@2021/09/09�@ https:// the-owner.jp/archives/2802
����쒉�j�i2010�j�C���u�������������v�͑P�Ȃ̂����Ȃ̂��@PRESIDENT 2010�N�W���Q����
���e�x�i2021�j�C�w���{�̊�ƊԎ��-�s�ꐫ�Ƒg�D���̗��j�\��—�x�L��t
���R���G�i2011�C2016�C2018�j�C�o�c�����_�C�n����
�����^���i1997�j�C�u���{�̃T�v���C���[�W�ɂ�����M���̖����v�i���{���G�E�����q�G�E�ɓ��G�j�ҁw���[�f�B���O�X�@�T�v���C���[�E�V�X�e���x�L��t�C91-118�j�B
�y332�Łz���ˑP��i2017�j�C�u�u���{�I������s�v�̎��Ԃƕϗe�v�i�w�����@���x�C2142�C4-16�j
�����^��q�i2017�j�C�u���W���[�����Ɓu���{�I������s�v�v�i�w�����@���x�C2142�C17-29�j
���Ώ��E��C�`�v�i2017�j�C�u���{�̎����ԎY�Ƃɂ�����n�����W�̕����F�V���Ȍ����ۑ�v�i�֓��w�@��w�w�o�όn�x�C13-28�j
��ˌ��o�i2002�j�C�u�M���Ɗ�Ɗԃl�b�g���[�N�v�w�o�ό����x��158���C267-284
��ˌ��o�E���R���G�i2021a�j�C�u����́u���{�I�o�c�v�_�i�P�j�v�w�K�@��w�w�o�Ϙ_�W�x�C58�C2�C175-186
��ˌ��o�E���R���G�i2021b�j�C�u����́u���{�I�o�c�v�_�i�Q�j�v�w�K�@��w�w�o�Ϙ_�W�x�C58�C3�C227-252
�q�c���r�iSubaru-inc�j�i2021�j�C�������������͉������ׂ��H�����b�g�E�f�����b�g�C��̓I�Ȏ菇���Љ� �쐬���F2021�N�S��26���@�ŏI�X�V���F 2021�N�X��27���@ https://subaru-inc.co.jp/manda_souzoku_daigaku/manda_gakubu/stock-cross-holding/
�{��`��i1976�j�C�w�����{�̊�ƏW�c�x���{�o�ϐV����
�O�֖F�N�i1989�j�C�u���{�̒�����Ƃ́u�C���[�W�v�C�u���ԁv�Ɓu����v�v�i�y����́E�O�֖F�N�ҁw���{�̒�����Ɓx������w�o�ʼn�C39-59�j
�O�֖F�N�EJ.�}�[�N�E�����U�C���[�i2001�j�C�w���{�o�Ϙ_�̌��—�u�n��v�̎�������̉���x���m�o�ϐV��ЁB
�a�c�k���i2003�j�C�u��萫�ƌ��������߂��鉺�����Ɋւ��闝�_�̓W�J�ƍl�@�F1980�N��㔼����90�N�㏉���̋c�_�𒆐S�Ɂv�i�Éx��w�w�����_�W�x46�C1�C69-83�j
Williamson, O.E.�i1975�j, Markets and Hierarchies: Analysis and Anti-Trust Implications, New York: Free Press�i��������E���W��w�s��Ɗ�Ƒg�D�x���{�]�_�ЁC1980�j
Williamson, O.E.�i1985�j, The Economic Institutions of Capitalism, New York: Free Press