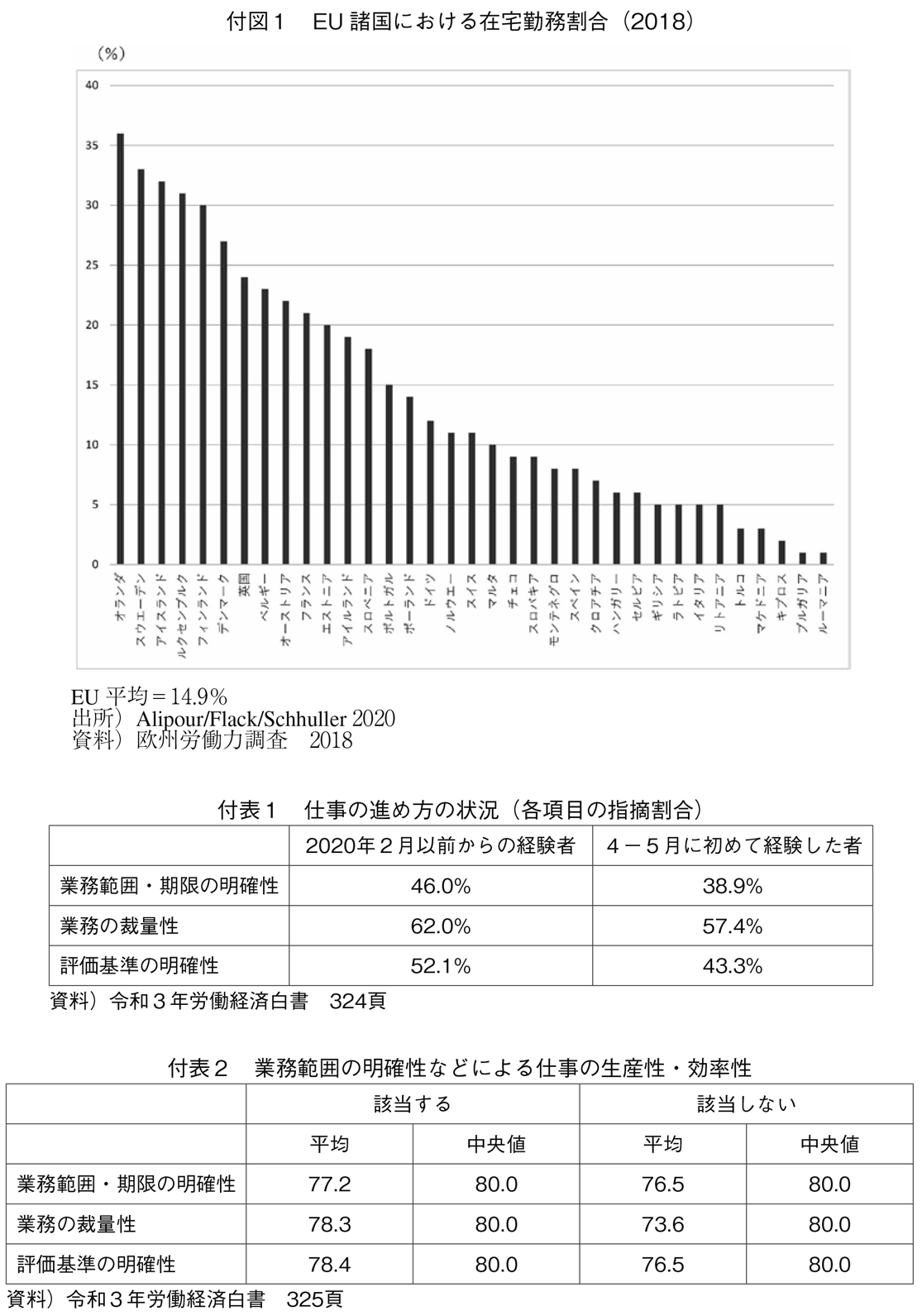テレワークに関する各種調査
脇坂 明
2020年3月からのCovit19も感染の広がりをうけ,少なくない企業でテレワークが実施され,各種機関で多くの調査がなされた。本稿は,感染下のテレワークに関する,2021年半ばぐらいの時点までに行われた各種調査からわかったことをまとめるものである。
本格的なテレワーク研究をはじめるための覚書ふうなものであるため,あえて初歩的な事実だけを書き留めた箇所もある。筆者の関心の強い項目については,論点を提示したい。この作業を今後の調査や本格的分析の出発点としたい。
なお本稿では在宅勤務と「テレワーク」をほぼ同義に用いる。厳密には,1−2で述べるようにテレワークのほうが広い概念だが,まぎらわしいケースはその都度注意する。また,企業によっては,リモートワークや遠隔勤務などの名称で導入しているケースもあるが,テレワークに統一する。
1-1 企業の導入割合
企業における導入割合は,「通信利用動向調査」(総務省,H29)によると2017年で13.9%であった。2018,2019年とそれぞれ,19.1%,20.2%となったので,この2割という数値が基礎となる。そして2020年(令和2年)の,この数値は,47.5%まで上昇した。導入予定の企業を加えると,58.2%である。
労働政策研究研修機構(JILPT)が行った企業調査(2021年2月「第3回新型コロナウイルスの感染拡大等が企業経営に及ぼす影響に関する調査」)によると,テレワークを活用した経験のある企業の割合は全体の40.4%である(注1)。そのうち「導入後,2021年2月現在でも実施している企業」23.4%,「過去に実際し,いったん停止し,現在再実施の企業」が,6.8%,すなわち30.2%の企業が導入している。通信利用動向調査の結果よりも少ないが,非常事態宣言の発出や解除が繰り返された2021年2月の時点でも,少なくとも3割もの企業が導入している。ちなみに2020年1月以前から活用経験のある企業は10.8%である。
業種では,情報通信,学術研究,専門・技術サービス,金融業,保険業で高く,宿泊業,飲食業,生活関連サービス,娯楽,医療,福祉業,運輸業,郵便 で少ない。また企業規模が大きいほど活用経験のある企業が多い。2021年5月時点では(パネルデータ),300人以上 60.0%,100−299人 45.1%,100人未満 25.7%である。
JILPT企業調査を利用して,2020年の月ごとの導入率の推移をみた「令和3年労働経済白書」 【254頁】 によると,2月は6.4%であったが,3月から増えはじめ,2020年4−5月に54%台とピ−クを迎える。その後減少し,2020年7−12月は30%台となっていた。第4回調査(2021年5月までの調査)では,2021年にはいって40%台まで上昇し2021年5月では40.7%である(数値は異なるが,パネルデータでも同じ傾向である)。
テレワークの企業による経費負担についての調査(人事院 2020年11−12月)では,テレワークを導入している33.3%の企業のうち,34.7%の企業が負担している。負担金額は,毎月定額支給している企業の平均で,4101円である。
1-2 労働者の利用割合
つぎに企業側からみたテレワークでなく,労働者の側からみたテレワークについて,コロナ以前の状況をみよう。「国土交通省テレワーク人口実態調査(平成30年)」によると,雇用型テレワークは就業者の16.6%を占める。外回りの営業や出張先のモバイルワークも含まれるので,決して多いとはいえない。
日本生産性本部(以下,JPCと略)が2020年5月から7回にわたって個人調査を行っている。企業などに雇われている雇用者1100名に対する調査で,最新のものは,2021年10月11−12日調査である。この調査結果を本稿でよく利用するので,JPC調査と呼ぶ。2021年10月の調査によると,「自宅での勤務」(在宅勤務)を行っているのは19.8%とやや少ない。サテライトオフィス勤務 3.8%,モバイルワーク 2.5%である。ほかに時差出勤15.1%,短時間勤務13.5%,一時帰休が2.6%と柔軟な働き方がみられる。JPC調査では,在宅勤務に,サテライトオフィス勤務,モバイルワークを加えて「テレワーク」と呼んでおり,この広義の「テレワーク」では22.7%になる。在宅勤務の割合は,2020年5月では29.0%であったが,2020年7月に18.4%に減少し,その後は2割前後でほぼ一定である(図表1)。広義のテレワークは,従業員1000人以上で37.1%,100人以下で14.3%と,規模が大きいほど利用者が多い。
JPC調査は,感染拡大後3か月に1度,1年半にもわたり,継続的に同じ設問で行われている貴重な調査であり,感染拡大後の状況を,時系列的にみるにはもっともよい調査である。
JILPT労働者調査(2020年12月「新型コロナウイルスの感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査(JILPT第3回)」)によると,テレワーク経験のある労働者は28.2%であり,2020年12月調査時点では,16.7%がテレワークをしている。
企業調査と同じように労働者の利用割合の推移をみると(令和3年労働経済白書),感染拡大前の通常月が,5.1%であったのに対し,2020年5月第2週の18.3%と上昇する。そこがピークで,6月以降減少し,11月まで10%をやや超える程度である。なお,これは,パネルの回答者をもとに算出されたものである。
三菱UFJリサーチ&コンサルテイング(MURC)2020年11月調査①(注3)によると,オフィスワーカー2000人調査から推定したテレワーカーは,901万人(男性599万人,女性302万人)である。該当の雇用者に対する割合は,男性22.8%,女性13.3%である。
調査によって利用割合の違いはあるが,いずれにしろ,企業の導入割合よりも,実際に利用している労働者の割合は低くなる。企業のなかの全ての労働者が利用しているわけではなく,業務の性格上などから,無理だと思われている労働者が多いためである。5節でみるが,テレワーク導入企業のうち,従業員の平均3割ぐらいが利用している。
【255頁】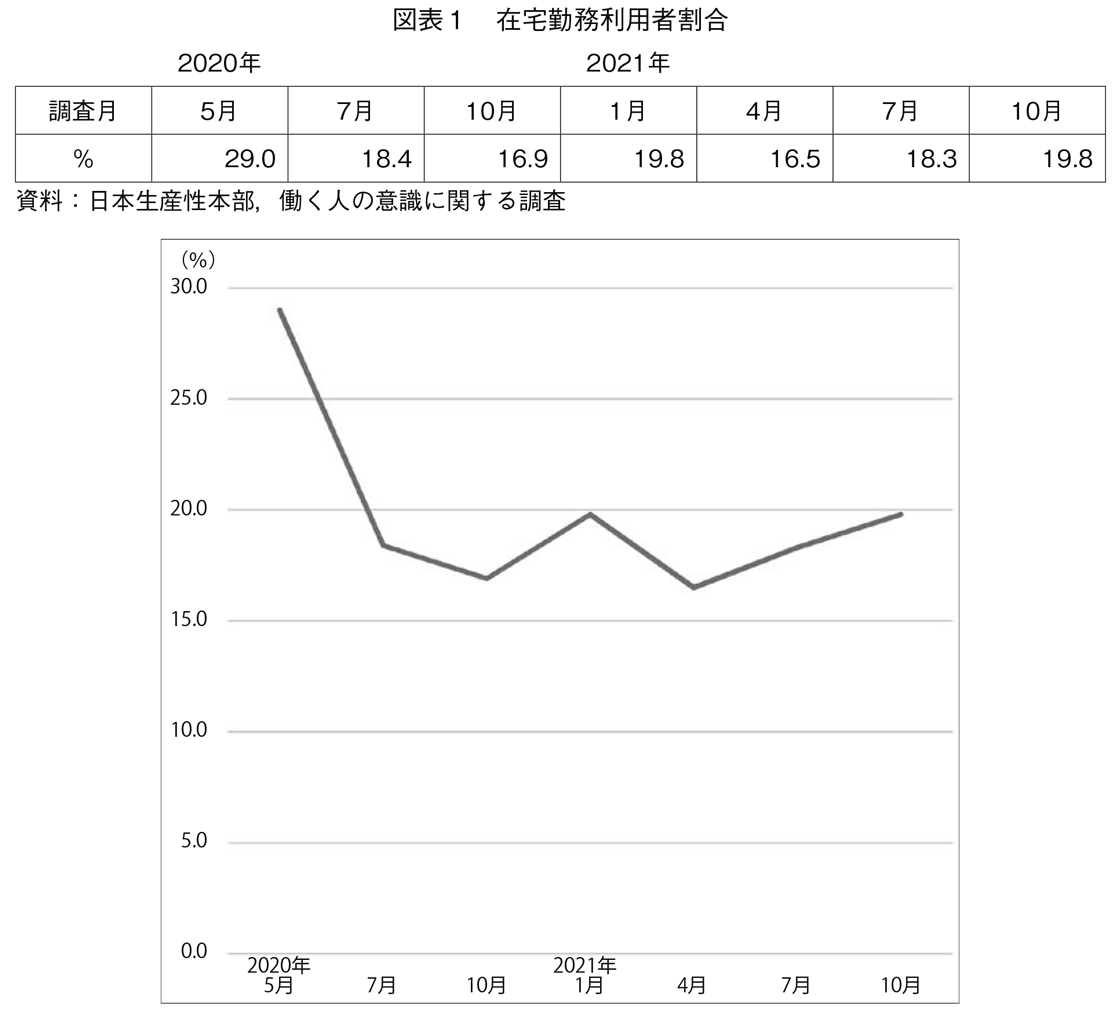
1-2-1 職種別
JILPT労働者調査を利用して分析した「令和3年労働経済白書」(以下,白書とよぶこともある)によると(298頁),テレワークの経験のある職種で多いのは,管理職(課長以上)56.1%,専門・技術職 37.7%,事務職 33.0%,営業・販売職28.4%である。少ない職種は,サービス職 9.7%,輸送・機械運転 9.6%,建設作業,採掘 7.7%,生産技能職 5.0%,運搬・清掃・包装 4.4%,保安・警備 0.0% である。
白書では(299-300頁),職種や業種そして仕事の性質の違いから,対面でのコミュニケーションや現場での業務が主となる仕事において,テレワークが定着しにくかったことを分析している。もっともな結果で良い分析である。
なおJPC調査では,職種の設問はあるがクロス集計はない。
森川(2020c)によると,米国の仕事内容情報を用いた推計では,34%が「自宅での仕事が不可能でない」としている。またこれを欧州に適用した試算では「潜在的に在宅勤務が可能な仕事」は,イタリアの24%から英国の31%である。
【256頁】石井・中山・山本(2020)は,アンケート調査を用いて在宅勤務可能性指標と実際の在宅勤務実施率を試算している。管理的職業が0.946(つまり95%),事務従事者 0.707,専門的・技術的職業従事者 0.468,販売従事者 0.366であるが,それ以外は0.1を下回っている。
EU諸国の2018年労働力調査によると,在宅勤務の利用割合は,平均14.9%だが,国によって違いがあり,オランダ36%,スウェーデン33%から,イタリアやギリシアの5%まで大きな開きがある(付図1)(Alipour/Flack/Schhuller 2020)。ドイツは12%である。
Alipour/Flack/Schhuller(2020)は,ドイツのサーベイに基づく試算を行い,ドイツでは上限が56%であるとしている。「しばしば在宅勤務」10%,「時々在宅勤務」16%に対して「未活用 untapped」30%である。つまりすでに26%は在宅勤務を利用している(経験者が含まれると思われるので,労働力調査の12%より多くなる)。この上限56%は職種,地域,業種などで調整している。2016年の労働者調査(17160名)を用いて,「事業者が認めたとしても,在宅勤務が不可能」だとしなかった労働者の割合から求めたものである。WfH(Working from Home Capacity)と呼んでいる。同じ製造業のなかでも,被服製造 65.42% から食料品製造 41.83%の開きがある。注目すべきは職種別である。職業別2桁分類で,コンピュータ科学情報通信技術や広告マーケテイング,商業・制作メデイア企画など90%を超える職業から,自動車輸送機械の運転手・オペレータや原材料,ガラス・セラミック製造加工労働者の10%台のものもある。
我が国での今後の研究は,サーベイデータに基づくほうがよいように思われる。ドイツのように平時のときだけでなく,感染以後の調査に対する反応を含めて可能な割合を属性別にとらえるべきであろう。いずれにしろ,これらの数値は,「在宅勤務の難しさを考慮しない最大値」(森川 2020c;289頁)と理解しなければならない。
1-2-2 性別
男女別のテレワーク利用は,調査によって異なるが必ずしも男女別の集計はされていない。そのなかで,山口・大沢(2021)は,男女のテレワーク機会の違いを分析しており貴重である。利用した調査は,連合の「第39回仕事と暮らしに関する調査」(2020年4月1−3日)で有効回答者4307名(有効回答率 13.6%)の調査である。コロナ下の職場で「在宅勤務・テレワーク」推進の取組みがあったかどうか尋ねている。実際にしているかではなく,その機会の有無である。また第一派のときの状況をみたものである。
テレワーク推進割合は,男性 22.9%,女性 12.9%と大きな差がある。正規雇用者に限っても,男性 25.3%,女性 18.8%の差である。ちなみに非正規雇用者は8.7%と正規の23.2%に比べかなり低い。分析の結果,正規/非正規をコントロールすると,職種の男女差は関係せず,規模や業種の男女差が関係していることを見出している。そしてテレワーク機会の男女差の70%を,女性に非正規が多いことと,女性の勤め先の規模が小さいことで説明できるとしている。
繰り返しになるが,MURC2020年調査でも,テレワーカーの雇用者に対する割合は,男性22.8%,女性13.3%と,男性のほうが多い。
1-2-3 職階(社内資格)別
職種の分析のところの管理職(課長以上)において,テレワークの経験ある割合が圧倒的に 【257頁】 高かった。その理由を知りたいところである。管理職の役割は,多様な働き方に対応するための研究は増えてきているが(たとえば,坂爪・高村 2020),部下のマネジメントだけでなく,管理職本人の働き方を含めた検討の余地があろう。
また管理職より下位の職階のランクの高低によって,どちらがテレワークをやりやすいも知りたいところである。責任の重い業務を担う労働者のほうが,テレワークをしやすいのか,しにくいのかを見るためである。
1-2-4 テレワークの頻度
JPC調査では, 直近1週間の出勤日数を調べている。
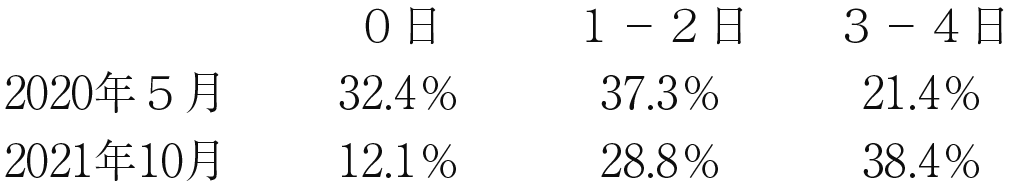
初期のころにくらべ,「2日以下」が69.7%から40.9%へ減少し,テレワークの頻度が少なくなっていることがわかる。完全在宅(0日)も32.4%から12.1%へと減少している。
JILPT労働者調査を利用した白書の分析によると,週当たりテレワーク実施日数は,日数分布が2020年5月第2週と11月最終週で大きく異なっている。「1−4日」の割合はそれほどの差はないが,「実施していない(0日)」が大きく上昇し,「5日以上」が大きく減少している。完全在宅だった労働者が,日数を短縮したことなど,の対応がみられたことが考えられる。
感染拡大期(2020年3−5月)と直近1か月(2020年12月調査)を比較したテレワークの日数の変化をみると,3−5月に初めて導入した企業では,減少が38.8%,増加が10.0%である。また2月以前から導入していた企業では,減少26.6%,増加17.5%である。テレワークの経験が長い企業ほど,テレワークを実施する日数の減少が少ない。すなわち経験が長くなるとテレワークの定着度合いが高まる。
またJILPT労働者調査(JILPT第5回)」では,テレワーク経験者について,2020年4月から2021年3月のテレワーク実施日数の変化をみている(プレスリリース速報 図表19)。2020年5月第2週では,「0日」が5.7%なので,ほとんどの対象労働者が在宅勤務を経験しており,在宅勤務の37.2%が「5日(以上)」であった。ところが,全面的解除の5月の最終週では,「0日」が23.7%,7月最終週 45.3%となる。その後,「1日以上」の実施割合は2021年にはいって上昇し(2021年6月17−23日で64.1%),実施日数もやや増えている。感染状況により変化していることが伺える。
2-1 導入目的
JILPT企業調査によると,導入目的でもっとも多いのは,「感染拡大対応」80.3%である。つぎに多いのは通勤がらみで,「通勤負担の削減」33.8%,「通勤者のゆとりと健康生活」16.8%である。それにつづく目的は15%未満となり,「自宅待機代わり」14.5%,「ワーク・ライフ・バランス(WLB)向上」12.4%,「災害等の非常時の対応(BCP対策)」9.4%である。より少 【258頁】 なくなるが,生産性やパフォーマンス向上に関連するものとして,「生産性向上」8.4%,「人材確保・流出阻止」8.1%,「オフィスコスト削減」4.6%,「企業の業績向上」2.7%となっている。必ずしも無視できない割合だが,これを目的に導入している企業は少数派である。
また,各項目について,実際に効果を感じた割合をみると(白書305頁),どの項目も5~8割の企業が効果を感じている。
2-2 実施(導入)しない理由
他の調査では,あまり見られない,導入しない理由について,JILPT企業調査で尋ねている(白書298頁)。「1−2−1」でみた「テレワーク可能性割合」の議論につながる。
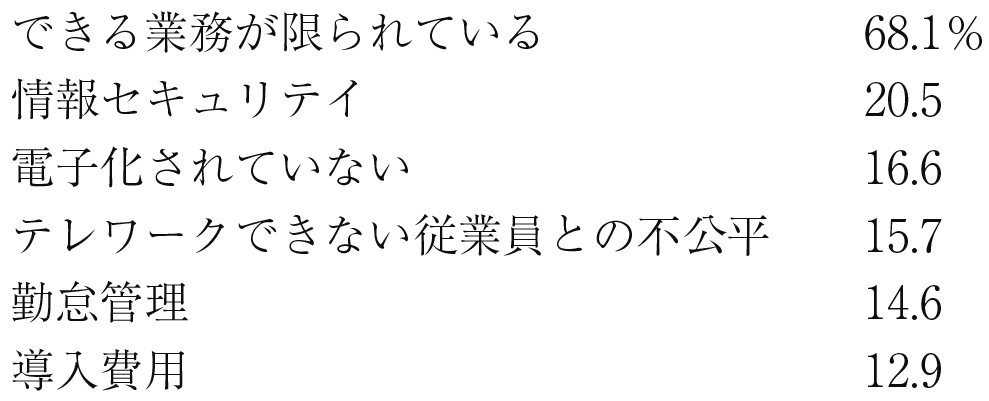
「できる業務が限られている」が圧倒的に多いが,選択肢の文言は,「在宅勤務・テレワークでできる仕事が,限られているから(顧客対応や紙ベースの仕事など)」となっており,理由として「顧客対応など難しいなど」が例示されている。紙ベースの仕事はデジタル化で解消されるかもしれないが,顧客対応は営業スタイルの抜本的改革を必要とし,時間がかかるであろう。
またJILPT労働者調査により,テレワーク開始時期で比較すると,下記のように経験が長いほど,この理由をあげる労働者が断然少なくなる。この事実も時間をかければ,「できる業務が限られている」が必ずしも決定的な理由とはならないことにつながる。
テレワークの経験あるが現在実施しなくなった労働者(白書311頁)
2020年2月以前から経験し,調査時点で実施していない労働者
できる業務が限られている 18.2%
2020年3−5月に初めて経験し,調査時点で実施していない労働者
できる業務が限られている 53.8%
ただし,回答をした労働者も調査時点でテレワークをしていないわけだから,非常事態宣言などが解除されて,(企業の要請かもしれないが)職場での勤務のほうが効率的だ(やりやすい)とされたことになる。
三菱UFJリサーチ&コンサルテイング(MURC)2020年調査(注3)を使用した白書(302頁)から,労働者が感じるテレワークのメリットをみよう。
【259頁】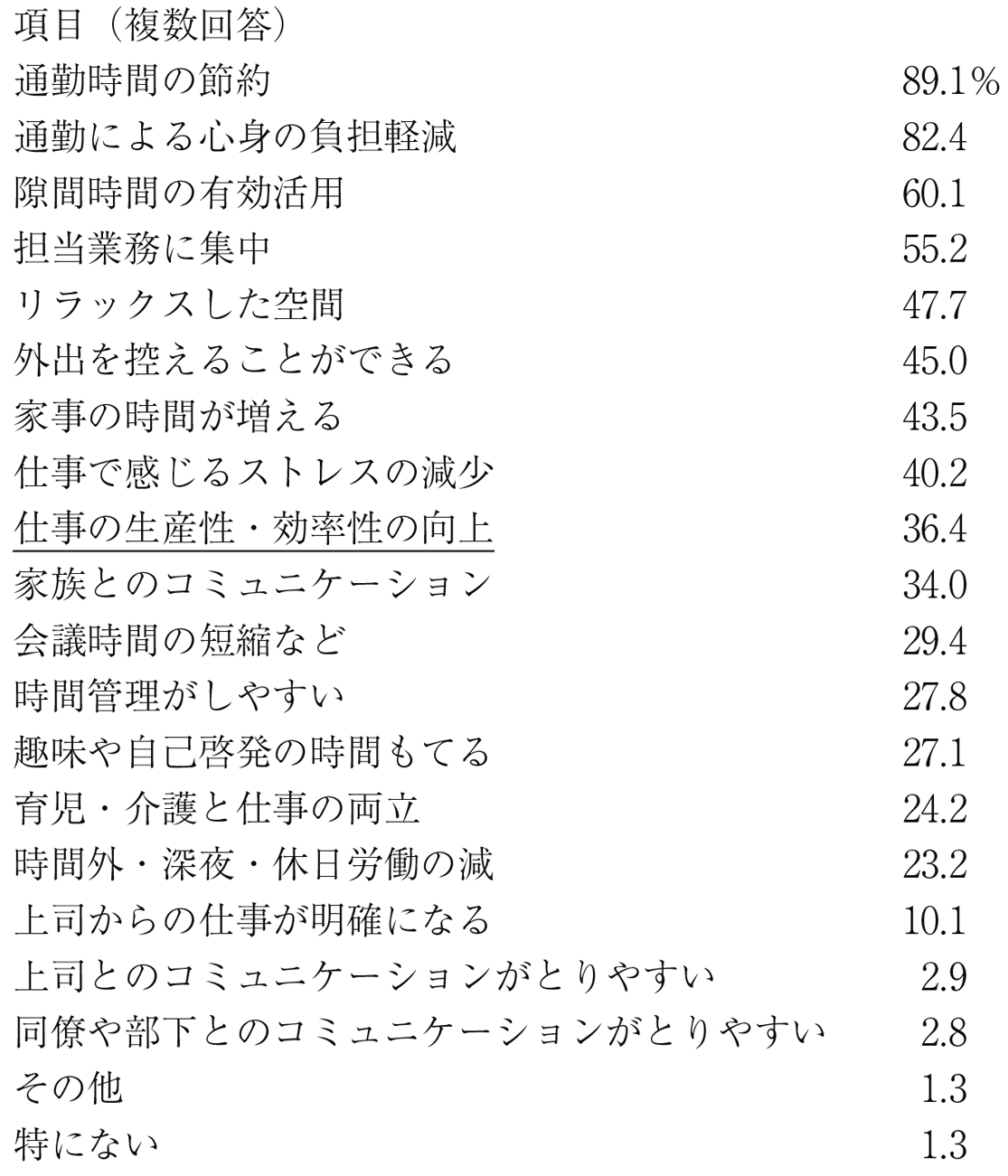
企業調査の結果と同じく通勤がらみのメリットをあげるものが8割以上と多い。他方,5節でみる生産性向上にかかわるメリットを,少なくない労働者が感じている。
メリットとは逆に,テレワークのデメリット(課題)をみよう。仕事面と人事管理面に分かれる。
4―1 仕事面
JPC調査(2021年10月)における広義のテレワークについての課題は以下。
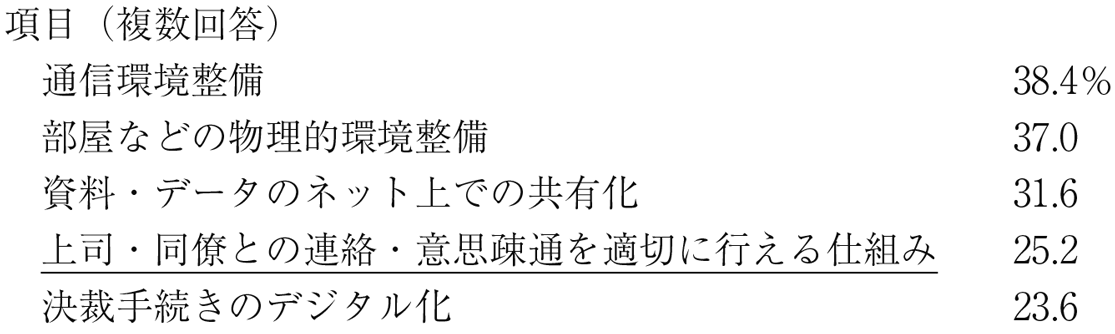 【260頁】
【260頁】
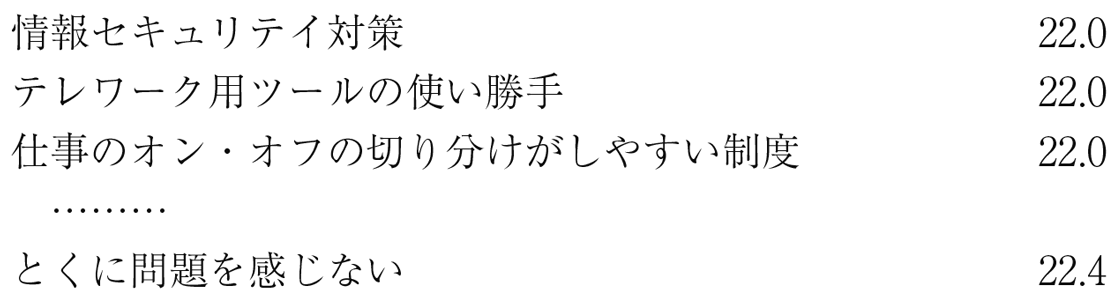
通信などの作業環境をあげるものが3分の1ほどいるが,これらの課題は解決できそうなものである。
4-2 人事(労務)管理面の課題
JPC調査(2021年10月)の最新の状況をみよう。
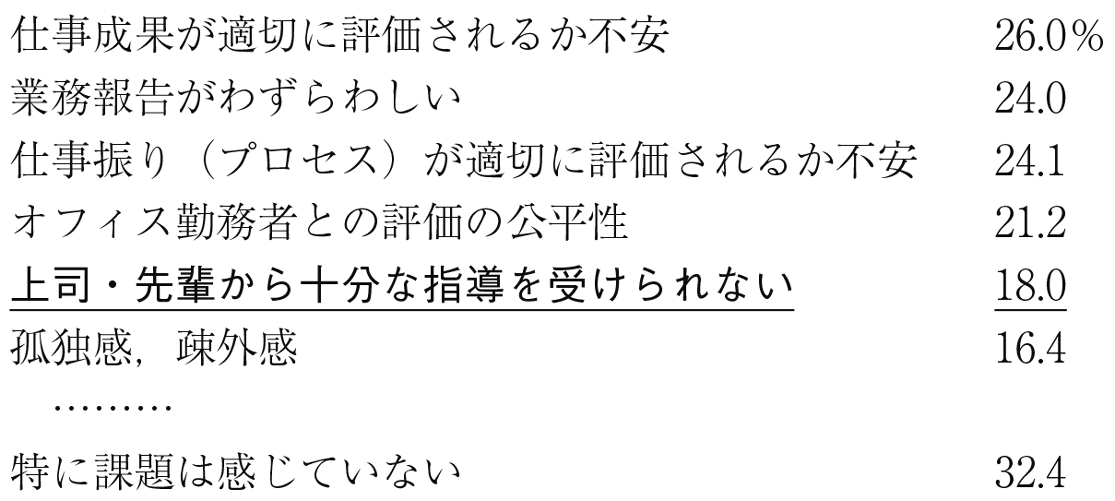
人事労務管理のうえで,「課題なし」とするものが,2021年10月で3割に達した。それまでは20−25%であったので,少しずつ課題がクリアーされているのかもしれない。
指摘割合は必ずしも多くはないが,注目すべきは,下線部の人材育成に関連するものである。詳細は次の「4−3」で触れるが,テレワーク中の労働者における,技能や能力の向上をどうやって行っているかである。上司や同僚(あるいは顧客)から仕事を通じて学ぶ,いわゆるOJTがうまく機能するかどうかである。アンケート調査では,どうしても日々困っていることに目が向きがちだが,自分あるいは部下の成長がないと長期的には大きな課題となる。
またMURC2020年調査(白書,302頁)による労働者が感じるデメリットは以下。
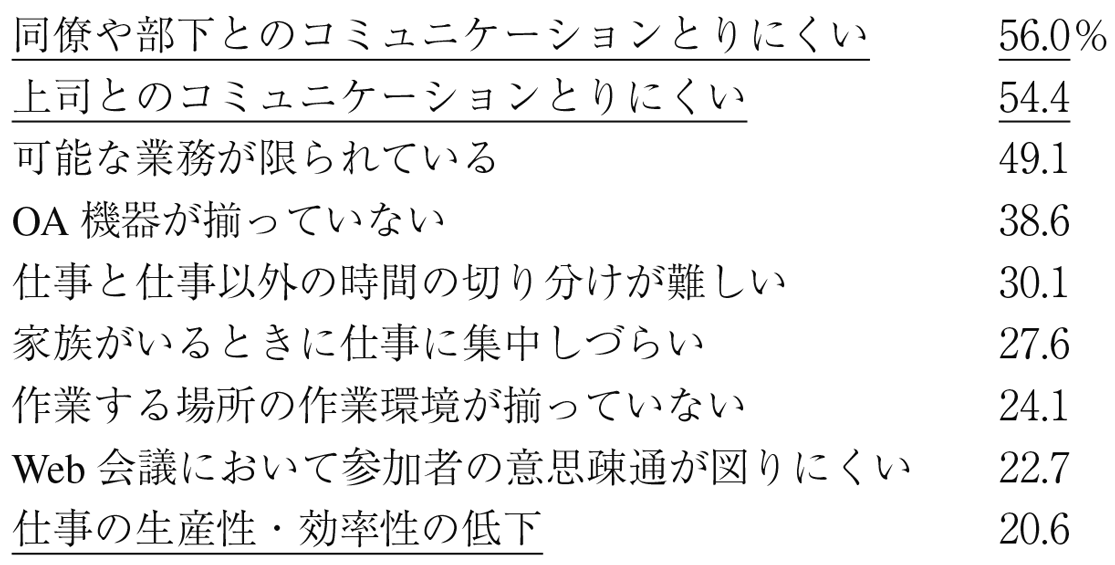 【261頁】
【261頁】
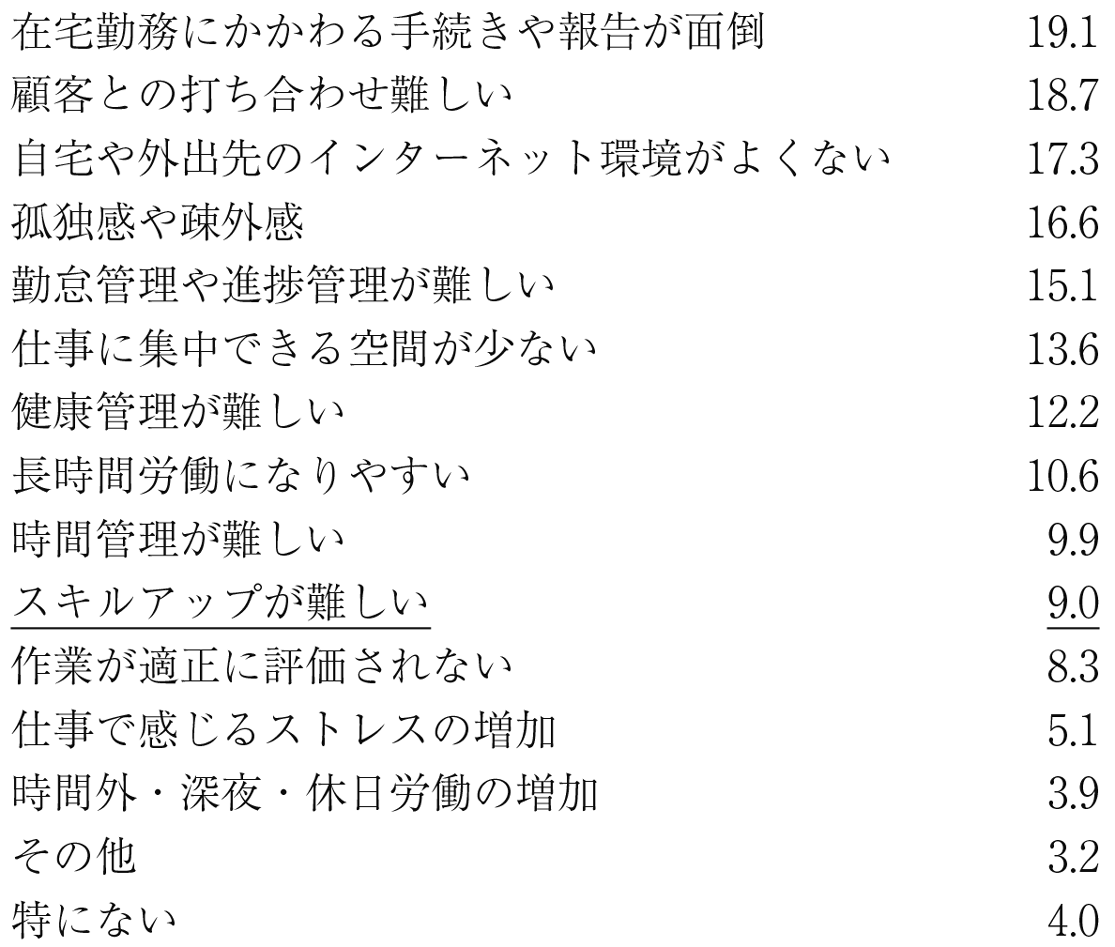
上司や同僚とのコミュニケーションの問題を指摘するものが多い。これはOJT不足からきている可能性が大きいと考えられるが,ここでも直接,「スキルアップが難しい」とキャリアを意識しているものは少数派である。
二つの調査から,自宅での通信環境などの物理的側面以外では,コミュニケーションをあげる回答が多い。しかし,より長期にテレワークの持続可能性につながる,生産性の低下やキャリア形成につながるOJTの課題が今後,重要になってくると思われる。
守島(2021)も,職場のOJTが危機的だとし,「これまでわが国の企業が培ってきた組織のルーテイン(例えば職場のOJTや頻繁なコミュニケーション)を困難にし,企業の競争力の基盤となる組織力(人材を育成する力や調整する力)を毀損する可能性がある」(216頁)としている。
4-3 OJTとテレワーク
テレワーク利用者の2割弱が「上司・先輩から十分な指導を受けられない」と指摘しているが,この事実を,指摘率の多少とは別に,より深刻に考えたほうがいいであろう。上司や同僚とのコミュニケーションがテレワーカーで少なくなることをみた。これもOJTが減ったことの帰結かもしれない。また孤独感が生じるのも,OJT不足が原因かもしれない。
日本生産性本部の報告書には,「わが国の企業内教育は,伝統的に欧米企業に比べて,Off-JTよりOJTの占める割合が大きいといわれている」と通説通りの説明がある。これは,OECD調査などからやや怪しいのであるが(脇坂 2019),この一連のJPC調査には,OJTやOff-JTについて設問があるところが素晴らしい。
OJTについての定義もしっかりしており,「最近3か月の間に,仕事を通じて,あなたが職場の人たちに指導,アドバイス,説明(OJT)を行う機会はありましたか。」という設問になっている。もう一つの設問,「最近3か月の間に,仕事を通じて,あなたが職場の人たちに指導,アドバイス,説明(OJT)を受ける機会はありましたか。」とあわさって,OJTは,与える側 【262頁】 も受ける側のふたつの側面から見ることができる。これと在宅勤務利用者/非利用者のクロス集計があれば,意味あることがわかるだろう。
非テレワーク利用者を含んだ全体の結果をみよう。2021年10月調査で,「行う機会」があったのが16.7%,「受ける機会」があったのが17.6%にすぎない(図表2−1,2−2)。8割以上が,受ける機会も行う機会もなかったのである。テレワーク利用者は2割ぐらいなので,利用していない労働者の多くがOJTに関与していない。とてもOJT中心の国とはいえない。似たような調査でも,しばしば,このような結果になる。
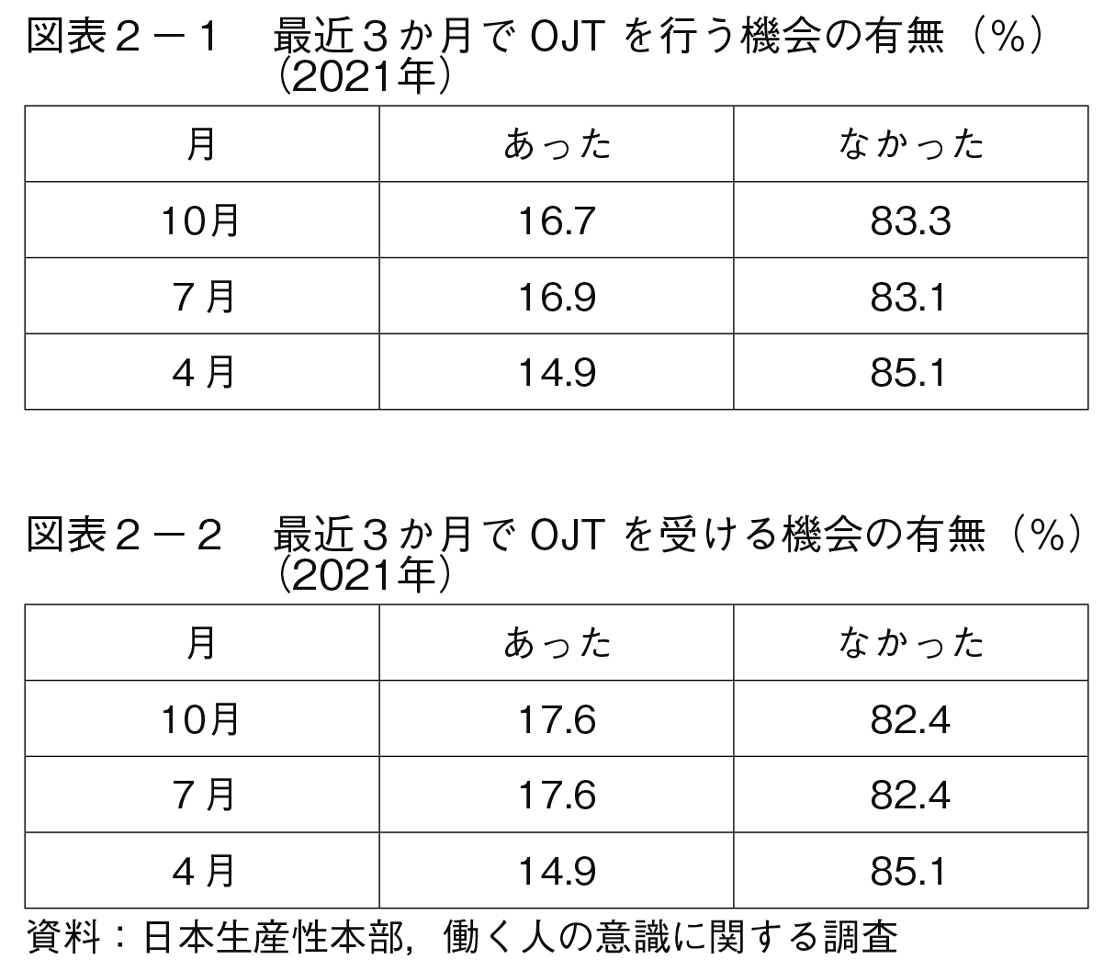
新卒入社をはじめ人事異動が4月に行われるので,そこからの期間において指導・アドバイス(OJT)を意識した回答が多くなるとすれば,7月調査(最近3か月は,4−6月になる)の回答で多くなるはずである。しかしながら2021年7月の結果は,「行う機会」16.9%,「受ける機会」17.6%と変わらない。どの月でも少ない。
テレワーク利用者でOJTがどのようになされているかを具体的に知りたい。対面でない(あるいは少なくなる)場において充分なOJTは困難であると思われる。「5−4」で生産性について事例を少し紹介するが,OJTにおいてどのような工夫がなされているのか,これが重要なテーマだと思われる。
5 生産性への影響
JPC調査に,「自宅での勤務により,仕事の効率性は上がりましたか」という設問がある。結果は,在宅勤務により効率が上がったものは53.7%と,下がったものは46.3%である(2021年10月)。ちなみに,2020年5月では,33.8%が上がっただけだった。2020年7月以降,おおよそ5割に上昇し,その後一定である。図表3では,感染拡大初期と最新の時期だけ掲載している。図表3にあるような四択の設問にして生産性が上ったか下ったかと尋ねると,2020年5 【263頁】 月を除き,同等か上った者の方が多い。すぐ後で見る生産性の程度をスコア化した設問にすると,おおむね下がるケースが多い。
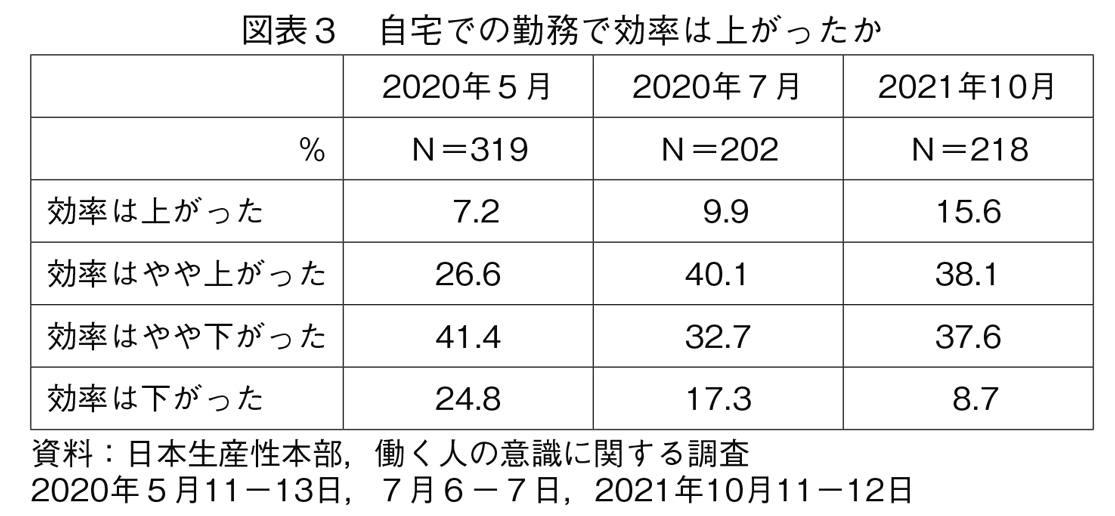
「仕事の生産性」について,回答者がなにをイメージするかは,人によって違いがあるだろう。もし通勤時間の節約のみを念頭においているとすれば,本当の意味での効率性向上ではない。急いで限定すれば,通勤による心身の負担が軽減することで,仕事に集中した結果,生産性が上がったケースは該当する。初歩的ながら,「仕事の効率」とは何かが,ここでもポイントとなる。
経済産業研究所(RIETI)も精力的に在宅勤務の生産性に関する調査を行っている。就労者への調査を行った森川(2020a)は,オフィス勤務に比べ,平均的な生産性は60~70%であるとしている。2020年6月に行われたインターネット調査によるもので,5105名の回答のうち就労者3324人について分析している。在宅勤務実施者は約32%,週労働時間と在宅勤務頻度を考慮した,労働投入時間の平均シェアは約19%である。コロナを契機に開始した人は,その前からしている人に比べ,かなり生産性は低くなっている<(注4)
つぎに,ほかでは見られない企業調査をもとにした生産性の研究が森川(2020b)である。「経済政策と企業経営に関するアンケート調査」(2020年8−9月)で,1579社の回答を得ている。調査対象は,従業者50人以上かつ資本金または出資3000万円以上の企業である。製造業が53.5%と半数以上をしめ,卸売,小売,サービス業,情報通信業とつづく。資本金1億円超/以下で区分した規模気分では,大企業 34.8%,中小企業 65.2%のサンプルである。在宅勤務は49.6%が導入しており,感染拡大以前から導入していた企業(A)4.1%,コロナを契機に導入した企業(B)が45.5%である。
導入企業のすべての従業員が利用しているわけではない。この調査では,テレワーク利用者がもっとも多いときの割合を尋ねているが,平均は30.7%で,(A)企業 49.1%,(B)企業で29.0%である。テレワーク導入企業では,3割ぐらいが利用しているとみてよい。もちろん製造業のサンプル数が多いので,実態はもう少し多いかもしれない。
さて,問題の企業調査からみた生産性はどうであったであろうか。結果は,平均 60.0 となり,(A)拡大以前から導入 76.8,(B)拡大以降導入 58.1 である。この数値は,つぎの設問に対する回答による。「ふだんの職場で行う仕事を100としたときの在宅勤務の生産性」を「平均的な数字」で記入させている。職場より高い可能性を考慮し100を超える数字も許容して 【264頁】 いる。
貴重な発見であるが,これをもって労働者調査の主観的結果と優劣を競うのは,すこし危ないであろう。上記の設問は,多くのテレワーク利用者のいる企業ほど回答しづらいようにみえる。各部署の生産性は把握できていても,そのなかの在宅勤務利用者の生産性を,個別の指標で保有していないかぎり,客観的データからの判断というのは難しい。まして平均的な数字の回答は,かなりイメージ的なもの,すなわちアンケート回答者(おそらく人事・総務)の主観的なものになるだろう。ただ,先の就労者サーベイの結果とほぼ同じなので,信頼性は高い。
つぎにJILPT労働者調査(2020年12月調査)を利用した白書(要約45頁)における,「仕事の生産性・効率性」について,オフィス勤務を100としたときのスコア(0−200で回答)をみよう(図表4−1)。
結果は2割前後は減少している。JPC調査では2020年10月時点において生産性が上った労働者が多かったので,大きく異なる結果である。またテレワークの経験が長いほど,減少幅は小さい。ちなみにWLBの実現度はどれも100前後である。また仕事を通じた充実感・満足感は1~2割減少する(図表4−2,4−3)。いずれにしろオフィスワークあるいは通常勤務と比べた生産性について,ざっくり尋ねるかスコア化して回答させるかによって結果は大きく異なる。
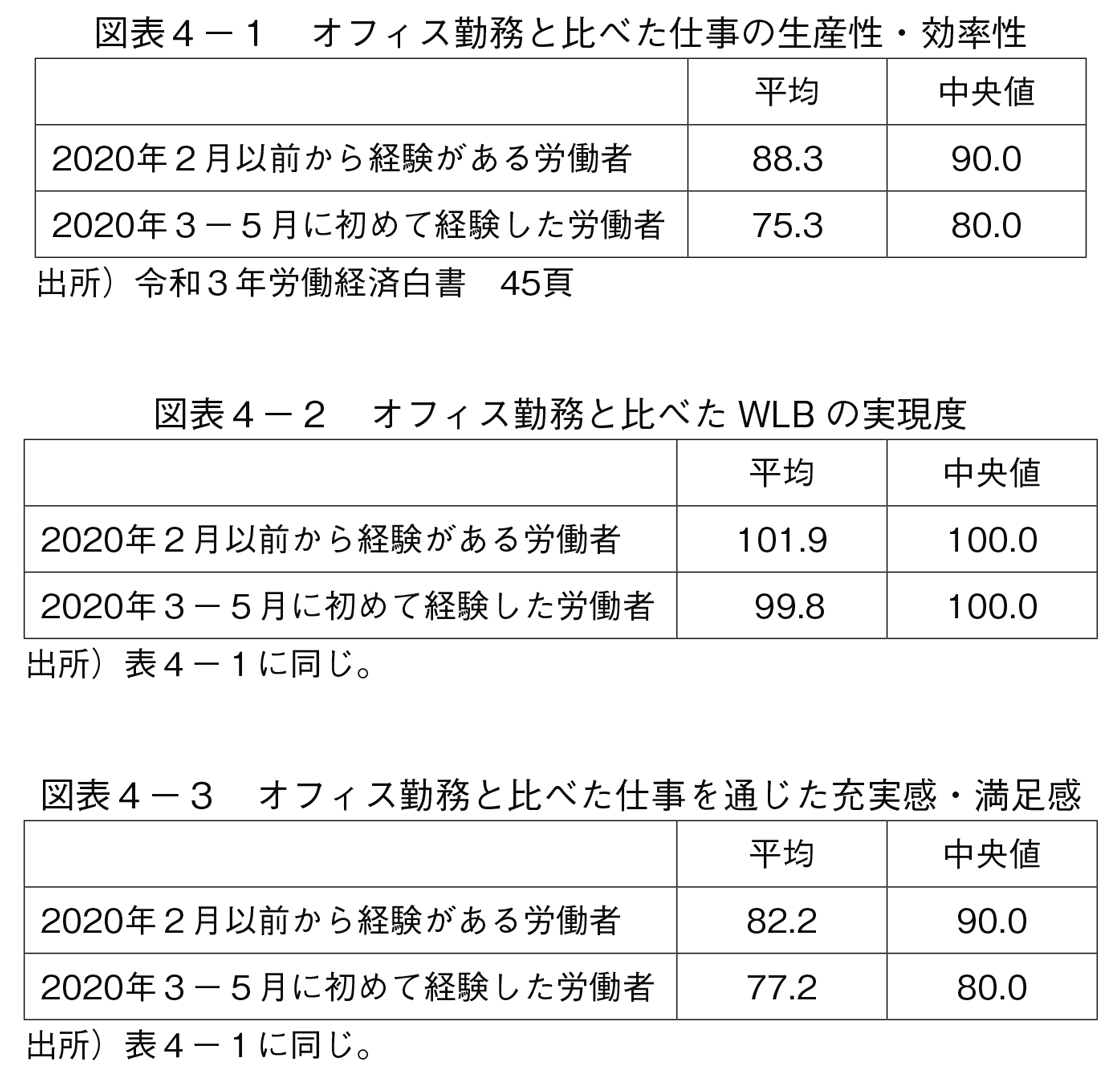
つぎに個別企業のデータを使用して行われた興味深い研究がある。Kitagawa et al(2021)は,一部上場の製造業4社に所属する従業員22815名に対して,2020年4−6月に在宅勤務調査を行い,生産性についても分析している。結果は,テレワーク実施者と非実施者を比較して,テ 【265頁】 レワークが生産性を低下させていることを見出している。生産性の尺度として,WHOが開発した主観的生産性の尺度(WHO-HPQ)を主に用いている。それをpresenteeism と呼んでおり,0−10のスケールで回答させている。それも,コロナが生じる(emergency)以前とその後の変化について聞いている。結果は,C社の5日在宅勤務者を除き,コロナ以後,在宅勤務をして生産性が落ちている。その原因も分析しており,初期における通信などの設備の準備不足とコミュウニケーション不足を挙げている。部門別(職種別ではない)の分析から,部門により,その原因が異なることも見出している。企業ごとに分析できる優位性がかなり生かされた研究である。
コロナとともに活動していく点で生産性の向上あるいは維持は欠かせない。生産性低下がつづくのであれば,ビジネスとしては維持可能ではない。テレワークは可能性のある働き方ではあるが,しばらく時間がかかるであろう。この生産性低下の課題をクリアーしないと,テレワークは定着しない。
5-1 平時における生産性
今回の感染対応のテレワーク利用における生産性を考える前提として,「平時」の生産性をみておく必要がある。森川(2020c)によれば,中国企業のコールセンターでは,在宅勤務がTFRを30%高めたことなどを紹介したうえで,コロナ感染のもとでの生産性を,「平時」の情報から類推するのはバイアスがあることに注意を促している。
テレワークの生産性を明示的に考慮した感染症シミュレーションモデルでは,職場の生産性にくらべ,50%とか70%低いという仮定した試算が行われているらしい。「テレワークが可能な仕事割合」とともに,平時とは異なる「テレワークの生産性」を明らかにすることが,基礎的な情報となろう。
5-2 仕事の進め方と生産性
コミュニケーションの程度や環境整備だけでなく,ある意味,そこからの帰結である「仕事の進め方」が重要である。生産性に直結するからである。
白書では,調査時点でテレワークを実施しているものの方が,実施していない者よりも,「仕事の進め方について上司や部下とのコミュニケーションがうまくとれていると思う割合が,4.7%ポイント高い(48.9%vs 44.2%)。また表4−1でみた生産性の低下幅について,コミュニケーションが取れている労働者のほうが小さい(平均 78.1 vs 72.3;中央値 80.0 vs 70.0)。平均,中央値ともに,コミュニケーションが取れている方が低下幅が小さいが,それでも2割ほど生産性が低下している。
そのほか「業務範囲・期限の明確性」「業務の裁量性」「評価基準の明確性」との関係もみている(付表1)(白書318-328頁)。「業務範囲・期限の明確性」とは「あなたが日々業務を進める上で,担当する業務の範囲や期限は上司などから明確に伝えられている」という設問に「当てはまる」「どちらかというと当てはまる」とした回答割合である。「業務の裁量性」は,「業務内容について上司が逐一細かく指示するのではなく,仕事を進める上での裁量がある」,「評価基準の明確性」は,「達成すべき目標の水準など仕事(成果)の評価基準が明確に定められている」という設問である。この3種類の回答割合すべてにおいて,テレワークの経験が長い職場のほうが高い。付表2に生産性のスコアがある。
【266頁】このように,かなり具体的な項目を分析しているところが参考になる。
5-3 生産性を引き下げる要因
森川(2020c)では,RIETI職員への定性分析から,つぎの4つを課題となる要因としてあげている。ある意味,上記で指摘した課題と同じであるが,生産性を意識した調査からの指摘なので列挙する(294頁)。
1)在宅勤務時のハードウエアやソフトウエアの問題
2)オフィスでしかできない業務の存在
3)フェース・ツー・フェースのコミュニケーションの欠如
4)自宅の仕事環境の制約
単なるアンケートによる定量調査だけでなく,しっかり聞き取りしたデータは貴重である。
5-4 生産性の課題に対する取り組み事例
労働政策研究・研修機構(2021c)では,2020年11−12月に大手企業14社(2労働組合含む)にテレワークについてのヒアリングを行っている。調査対象すべての企業において,育児・介護のためのテレワーク制度は存在し,2011年東日本震災以後は,自然災害の備えの防ためのBCPの一環としての制度があったが,利用者は数パーセントであった。それが今回のコロナにより「もうコロナ前の働き方に戻らない」という共通の姿勢になっている。その表れが,それまであったテレワークの回数制限やコアタイムの廃止,感染拡大時は「原則在宅勤務」で出社を申告制にするなど,社員による「時間管理の自律性」をめざしていった。多くのテレワークの内容について調べているが,生産性に関して注目されるものを取り出そう。
14社のうち,生産性の面で効果があったとするものが8社,効果が表れていないとするものが6社であった(37-41頁)。
J社(住宅設備機器・建材)では,コロナ以前から営業のオンライン化を進めてきたが,コロナ問題発生以後,加速化した。顧客ニーズにスピード感をもって対応できるようになった。トップクラスの専門家や事業責任者,場合によってはCEOを登場させることができるというような付加価値化が進んだ。また在宅勤務普及によりオフィスのあり方も変え,都内20を超える拠点の本社への集約化が段階的に進んでいる。
H労組(自動車関連製造)では,プログラマーなど技術系の仕事の一部について,各人の進捗状況を一覧できるよう,仕事の「見える化」を進めてきたが,それが加速された。課題は,通常勤務と変わらないコミュニケーションがとれるか,である。
M社(食品製造)は効果がまだない事例だが,多くの検討をしている。労働時間以外の何で生産性をみるかという困難な課題に取り組んでいる。巣ごもり消費で残業時間が増え,2020年年間1800時間の実現は一時休止状態となった。平常に戻ってもテレワーク定着だけでなくフレックス制度の掛け算で労働時間短縮をめざすが,それには個々の社員の目標への習熟が重要だとしている。たとえばメリハリある日々の業務計画など,働き方のあり方についての学びである。それについては,会社と個人のルールとして,アウトルックのスケジューラーに業務計画を記入するよう要請している。これもコロナ以前からおこなってきたことだが,コロナ以後加速化し,会社と個人の信頼関係を構築しようとしている。
【267頁】5-5 短期と長期の区別
世界に通用する人材あるいは競争力のある人材を育成するには,「競争」そのものを短期の競争と長期の競争を区別する必要があることを,ずっと主張されてきたのが小池和男氏である(小池(2015))。生産性の問題を考える場合も,この視点を忘れてはならない。たとえば,テレワークで短期的な仕事の効率性を達成しても,それが長期の生産性に寄与しない,あるいは低下させるものであれば,意味ある施策にはならない。
このように,短期と長期の違いを十分意識した,生産性の議論が必要である。
JPC調査(2021年10月)において,在宅勤務者に「コロナ収束後もテレワークを行いたいか」どうかを尋ねると,71.6%と多数が希望している。2020年5月では62.7%が希望していたので,希望者は増えている(図表5)。この希望者増の解釈としては,(1)テレワークを継続するにつれて,その有用性を認識し平時でも希望する労働者が増えた,(2)この期間,テレワーク利用者が減っているので,テレワークを(あきらめて)やめた労働者がサンプルから消えている,の2つが考えられる。
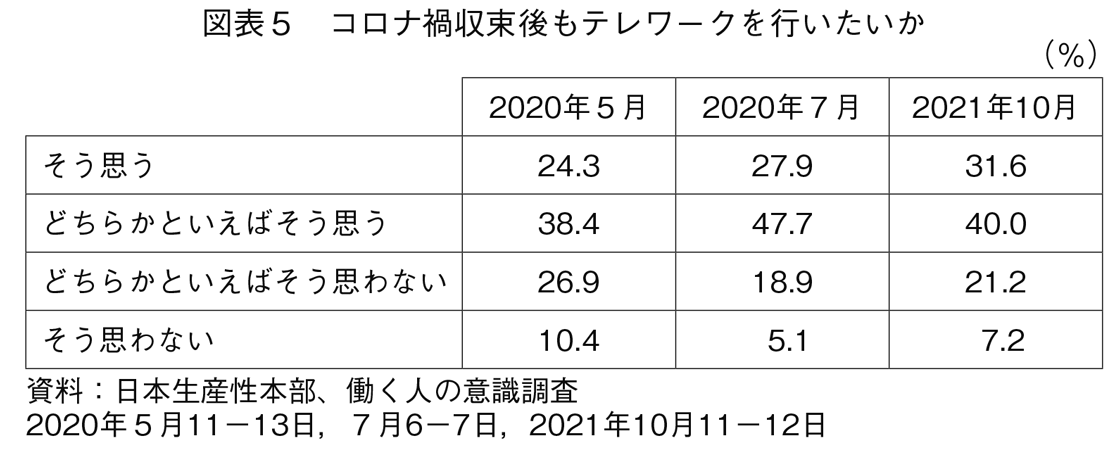
これについては,基本的にパネルデータでない限り確定的なことはいえない。
MURC調査を利用した労働経済白書によると,テレワーク経験者のなかで,調査時点でテレワークをしているものの87.2%,調査時点ではしていないものの43.0%が,希望している。なお,これは「収束後」という設問ではなく「今後」の希望をきいている。
各種調査から,テレワークしているものの多くが,収束後のテレワークを希望している。
JPC調査の在宅勤務利用者の満足度をみると,66.1%が満足,33.9%が不満である。2020年5月調査から,満足割合は上昇していったが,2021年以降,下降気味である。
職場満足度にかぎらないが,ある指標の状況をみるときに比較すべきは,まずテレワーク利用者と非テレワーク利用者の状況である。職場から在宅になって満足度がどう変化したかを個 【268頁】 別にみることができれば最適だが,それができないときが多い。そうすると,テレワークをしていない労働者との比較にたよらざるをえない。できるだけ同じ職種や属性の労働者の比較が意味をもつ。9節で紹介する江夏(2021)は,それを行っている。そのうえで,在宅勤務の利用者における,満足者と不満足者の違いをみるべきである。
5節でみたように,テレワークにより生産性が2~4割落ちる,今後OJTによる技能向上を阻害していることが生産性にマイナスの効果をもたらすとすれば,キャリア形成に悪い影響を与える。
短期的な生産性の低下(不慣れなど)や向上(通勤時間,通勤疲労軽減)のことよりも,長期的な影響のほうが重要である。それが企業の競争力につながり,労働者にとってもキャリア形成のカナメになるからである。
このキャリア形成のために,労働者が日々,いかなる行動をとっているか否かが重要な情報である。また背景となる事実として,現在の企業における昇進が早いほうか遅いほうかも関係しよう。
あまり論点としてあげられることはないが,テレワークと高年者のキャリアの関係も重要である。
いずれにしろテレワークについて,キャリア形成への影響をとりあげたものは少ない。
企業レベルでの在宅勤務の制度運用の有無だけでなく,職場レベルにおけるテレワーク労働者の心理や行動が注目される。とくに上司との関係が重要で,どのような上司のマネジメントでテレワークがうまくいくかが具体的にわかると,有益である。理想的には上司—部下のマッチングデータで職場マネジメントに関わる項目のある調査がよい。それは困難だとしても,従業員調査のなかに,上司からうけているマネジメントに関わる項目があるとよい。それは,たとえテレワークが生産性を向上させる,あるいは低下幅を抑えることがわかっても,具体的にどのようなプロセスで実現するかがわかる基礎情報を提供するからである。この問題を直接あきらかにしているわけではないが,江夏(2021)は,テレワークの実施者と非実施者を比較しているので参考になる。
江夏(2021)は組織心理学の視点から分析している。2020年7月に,インテージ登録モニターのうち就労者から得られた3073名について分析している。いくつかのことを明らかにしているが,たとえば職場における孤立感について,テレワーク実施者(この論文ではリモートワークと呼んでいる)では,職務プロセスの他者依存性が高いほど孤立感が高まっている。日常的に周囲と緊密な連携をとっていると,調査時点ではテレワークに慣れていないので孤立感が高まるとしている。一方,非実施者では,成果の他者依存性が高まるほど孤立感が増えている。周囲との連携がテレワークの実施・非実施によって異なるメカニズムで孤立感に影響することを示唆している。そのほか,ワーク・エンゲイジメントや変化の創出についても知見を得ている。このように,テレワーク利用者だけでなく実施していない労働者と比較することによって,有 【269頁】 益な情報が得られる。
うえでみた生産性やキャリア形成についても,同様の比較が重要であろう。
JPC調査では3か月前と比較した労働時間の長さを尋ねている。
2021年7月では,増加 13.3%,増減なし 72.0%,減少 14.7%となっている。DI(増加 - 減少)でみるとマイナスである。つまり減少したものの方が多い。2020年10月もマイナスであったが,その幅は小さくなっている。ちなみに業務量のDIは1.4(16.1−14.7)でプラスである。すなわち業務量は増えているのに,労働時間は減っている。
10−2でみるMURC調査では,増加 18.0%,減少 38.9%で,DIは,マイナス20.9である。
2020年9~10月に行った労働政策研究・研修機構(2021b)による10000人調査によれば,テレワークの経験ある者(N=3507)のうち,労働時間が長くなりがちな者は,男性26.1%,女性31.9%で,そうは思わない者が男性29.3%,女性30.1%である。二極分解している。
10-1 通勤時間
テレワークのメリットとして通勤時間がゼロ,あるいは短くなったことを挙げる労働者が多かったが,どれほど減少したのであろうか。
MURC調査②(注3)によると,2020年以降在宅勤務をおこなった労働者(n=789)のうち,51.6%が減少している。その時間の分布をみると,5時間以上 10.7%,3~4時間 10.6%,1~2時間 29.3% である。
10-2 家事時間などの変化
減少した労働時間のぶんがどこに増えているのか。家事時間や余暇時間の変化をみる。
JPC調査では,15.1%が増加 14.2%が減少である。家事時間や余暇時間の増減をDIでみると,プラスだが,女性のほうが男性よりプラス幅大きい。
MURC2020年調査による通勤時間が短くなった在宅勤務者の変化(2020年1月と10月の比較)は以下。
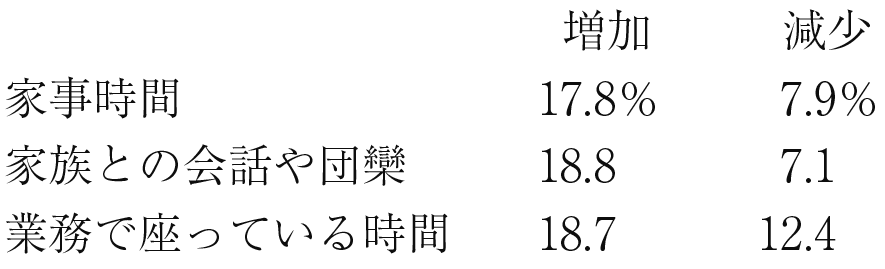
男女別に家事・育児時間の変化を,テレワーク/非テレワーク者で比較した池田(2021)は分りやすい。高見(2021)をもとに2020年4~5月では,テレワーク/非テレワークともに女性の方が家事・育児時間が増えたが,2020年12月では,テレワーク利用者で男性の増加が多く,非テレワークで女性の方が多かった。また高見・山本(2021)は,家事・育児時間増加の規定要因をロジスティック回帰したところ,テレワーク勤務継続者において有意に増加している。労働時間の変化をコントロールしたうえの結果なので貴重である。テレワークを通じて性別役割分業が変化する可能性を秘めている。
【270頁】10-3 配偶者との関係
テレワークにともなう家庭と仕事の関係も重要である。とりわけ配偶者との関係に注目したい。新たな生活様式は職場だけでなく,配偶者を含めた家族における生活のあり方も変えるかもしれないからである。
MURC調査①では,テレワーク利用者のなかで,同居で主に仕事している配偶者がいるのは,332万人(36.9%),同居で主に仕事していない配偶者がいるのは153万人(17.0%)推定としている。
同居で主に仕事している配偶者がいる332万人のうち,配偶者の在宅勤務日数の状況は,以下である。
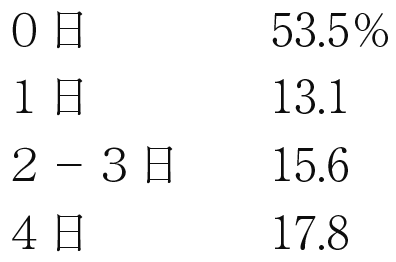
共働きの片方の半数強が在宅勤務でないが,46.5%もが在宅勤務を行っている。それも2日以上が3分の1もいる。
また子供の存在も大きい。同居の子供がいる世帯は360万人(39.9%)と推定しているが,子どもの学校段階をみると,
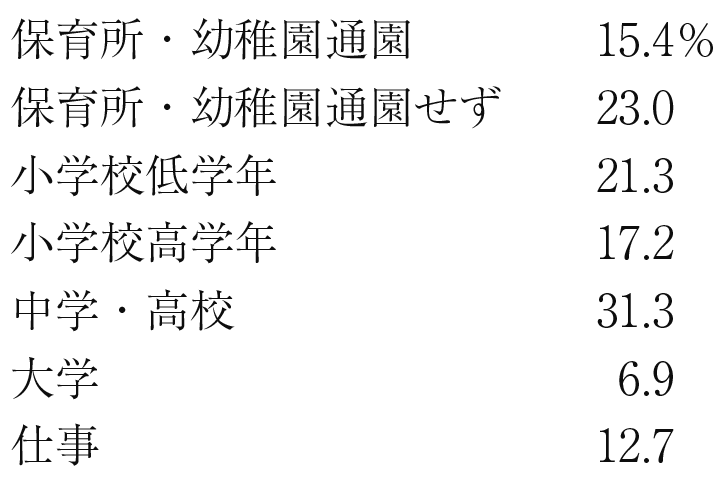
通勤時間が減少した共働き子どもありの世帯にかぎると(MUFI③),家事時間は男性が1.4時間増加,女性が1.3時間増加している。
10−2で示唆した性別役割分業の変化とまでいかなくとも,それぞれの家庭において,子どもも含めて時間配分や行動の変化をテレワークが促している。「新しい生活様式」と抽象的に語るのではなく,できるだけ具体的なことの分かる調査が必要である。
JPC調査では,「収束」後の変化が「おこりうるか」とその変化を「希望するか」について,11項目のそれぞれについて尋ねている。11項目は,「業務の要不要の見直し」「時間管理の柔軟化」からはじまって「ワーケーションの普及」「出張の削減」などである。
「収束」という言葉が,アフターコロナのニュアンスに近い「終息」を念頭におくか,ウイ 【271頁】 ズコロナに近い「収束」を念頭におくかで,回答がちがってこよう。いずれにしろ,JPC調査は細かく未来像を探っているところがよい。11項目のなかに「テレワークの普及」があり,2021年10月で,「起こり得る」13.7%,「どちらかといえば起こり得る」28.9%と,42.6%が変化を感じている。ただその変化を希望するかといえば,「希望」18.2%,「どちらかといえば希望」27.5%と,テレワークが普及した社会を望むものは,45.7%である。
2020年9~10月に行われた企業調査(N=7624)では,コロナ流行が落ち着いた後の「仕事のやり方」や「働き方の変化」があるとする企業が27.0%存在する(労働政策研究・研修機構2021a)。300人以上企業では56.3%である。能力開発への影響を尋ねると,「よりOJTを重視する」は19.6%である。労働者調査では,管理職の59.0%が変化があると思っている(労働政策研究・研修機構2021b)。
企業職場では,Covid-19の影響で在宅勤務が,感染対策の面から広がった。在宅勤務が今後普及するとすれば,働き方は今後どのように変化していくのであろうか。
コロナ以前の在宅勤務は「働き方改革」などを背景におおむね労働者のWLB(ワーク・ライフ・バランス)の推進や裁量労働的に生産性向上をめざすためのものであった。今回のCovid-19関連による在宅勤務は,「2−1」で見たように,これらの目的と異なっていた。それは感染防止のため,労働者が望もうが望まなかろうが,可能な業務はすべて在宅で行おうとしたところに特徴がある。感染拡大の状況により,テレワーク実施割合や頻度が増減したことが,それを裏付ける。
そのうえで今後を展望すると,もし在宅勤務の経験から,在宅でもできる業務がこれほどあるのか,と多くの人が気づくと,平時でも広がるというシナリオが考えられる。この経験が働き方改革の在宅勤務につながっていけば,その職場での新しい経験となる。そのなかで当初は生産性をあまり考えず行わざるをえなかったが,このピンチがチャンスにつながっていく可能性がないわけではない。
自粛行動により,1日仕事を自宅でこなす,ということで,事務的な仕事はかなり集中できるが,4節でみたように,やはり調整業務(社外含めて)ではかなりの時間を無駄に要したであろう。ゆえに,このシナリオが可能か否かは,ひとえに生産性のいかんによる。これまでの調査では2~4割減少していた。ただし「5−5」でも述べたように,問題は短期の生産性ではなく,長期の生産性である。
この問題意識の背景にあるのは,各種機関の提言に必ず出てくる「テレワークによる生産性の向上やイノベーションの促進」にあるのではない。筆者は生産性の維持で十分だと思っている。生産性が変わらなければ,通勤を嫌う労働者に在宅という選択肢が増えるし,企業も交通費用(場合によってはオフィスコスト)の削減もできよう。
長期の生産性向上には,テレワークがOJTによる能力開発が阻害されないことが重要である。この視点から,より深くテレワークを考察していく必要がある。
統計・白書など
日本生産性本部「働く人の意識調査」第1回−第6回
厚生労働省(2021)「令和3年労働経済白書」
労働政策研究・研修機構 様々な報告書やプレスリリース
労働政策研究・研修機構(2021a)『人材育成と能力開発の現状と課題に関する調査(企業調査)』JILPT資料シリーズ No.216
労働政策研究・研修機構(2021b)『人材育成と能力開発の現状と課題に関する調査(労働者調査)』JILPT資料シリーズ No.217
労働政策研究・研修機構(2021c)『ウイズコロナ・ポストコロナの働き方−テレワークを中心としたヒアリング調査』JILPT資料シリーズ No.242
学術文献
Alipour,Jean-Victor,Oliver Flack,Simone Schhuller(2020),”German’s Capacities to Work from Home”, IZA Discussion Paper N0.13152
Kitagawa,Ritsu, Kuroda Sachiko, Okudaira Hiroko and Owan Hideo(2021),”Working from Home:Its Effects on Productivity and Mental Health”, 『RIETI Discussion Paper Series』21-E-024
池田心豪(2021)「コロナ禍での在宅勤務は男性の家事・育児を促進しているか」『電機連合NAVI』No.80
石井加代子・中山真緒・山本勲(2020)「コロナ禍における在宅勤務の実施要因と所得や不安に対する影響」JILPT Discusion Paper 20-SJ-01
江夏幾多郎(2021)「リモートワークの背景と効果」江夏幾多郎ほか(2021)『コロナショックと就労:流行初期の心理と行動についての実証分析』ミネルヴァ書房
坂爪洋美・高村静(2020)『管理職の役割』中央経済社
小池和男(2015)『なぜ日本企業は強みを捨てるのか:長期の競争 vs 短期の競争』日本経済新聞出版社
高見具広(2021)「在宅勤務によるワークライフバランスの新しい形」『JILPTリサーチアイ』No.57
高見具広・山本雄三(2021)「コロナ禍の在宅勤務による生活時間の変化−新しい日常生活」樋口美雄/労働政策研究・研修機構編『コロナ禍における個人と企業の変容−働き方・生活・格差と支援策』慶應義塾大学出版会
森川正之(2020a)「コロナ危機下の在宅勤務の生産性:就労者へのサーベイによる分析」『RIETI Discussion Paper Series』20-J-041
森川正之(2020b)「新型コロナと在宅勤務の生産性:企業サーベイに基づく概観」『RIETI Discussion Paper Series』20-J-041
森川正之(2020c)「コロナと在宅勤務の生産性」小林慶一郎・森川正之編『コロナ危機の経済学』日本経済新聞出版社
守島基博(2021)『全員戦力化—戦略人材不足と組織力開発』日本経済新聞出版社
山口一男,大沢真知子(2021)「新型コロナの影響下での在宅勤務の推進と男女の機会の不平等」『RIETI Discussion Paper Series』21-J-002
脇坂明(2019)「OJT再考」『学習院大学経済経営研究所年報』33巻(59−89)
【273頁】1)インターネット調査会社のモニター登録企業の全数11070社へのWeb調査。有効回収 3265社(回収率 29.6%)。2021年2月1−9日調査。なおJILPTは,その後も調査をしているが,「令和3年労働経済白書」が,この調査を使った分析しているので,これを中心に記述する。より最近の調査結果は本文や注で触れている。
2)インターネット調査会社のモニター登録会員へのWeb調査で2020年12月12−17日実施。20-64歳の民間企業で働く雇用者の有効回収。4307人の分析。なおJILPTは,その後も同じ対象者に調査をしているが,「令和3年労働経済白書」が,この調査を使った分析しているので,これを中心に記述する。より最近の調査結果は本文や注で触れる。
3)インターネットモニターを対象としたアンケート調査(2020年11月12−15日)。対象は15-59歳のオフィスでの仕事(デスクワーク)をしているテレワーカーで,2020年10月に週当たり在宅勤務(サテラート含む)を1日以上行っているもの,2000サンプル。マル数字は,MURCが2021年2月から6回にわたって「政策研究レポート」を出しており,その番号。例えば①のタイトルは,「在宅勤務者の人数規模と属性:在宅勤務は何をもたらすか」。
4)RIETIに所属するおよそ80名の役職員を対象にした,2020年3−4月の調査によれば,管理職・事務スタッフでは 67.2,研究員では86.7の生産性であった(森川 2020c).