����́u���{�I�o�c�v�_�i�S�j
��ˁ@���o�E���R�@���G
�P.�@�C�m�x�[�V�����Ɠ��{�I�o�c
1990�N��ȍ~�C�䂪���̌o�ς͒ᐬ���ɒ��ʂ��C��ƋƐт��傫��������邱�ƂɂȂ����B�}�\�P�ɂ���悤�ɁC��l���������GDP�̐��ڂ��݂�ƁC2000�N��ɓ���ƁC�̓������݂�ꂽ���̂́COECD�����̕��ςɔ�ׂđ傫��������Ă���B1980�N���ʂ��ẮC���{�o�ς���ѓ��{��Ƃ̗����́C���E������������̂ł������̂ŁC�����\�����g���ΔߎS�Ƃ�������Ɋׂ����B���̗��R���ǂ��ɋ��߂邩�C���q�����Y�N��l���̌����Ƃ������Љ�\����肩�C���̌o�ρE���Z�����Y�Ɛ��C��Ƃ̓����s����o�c�헪���C���邢�͂��L�������肩�C�l�X�ȋc�_�����蓾�悤�B�����炭���l�ȗv���̕����������ʂ�����ꂽ10�N�C���邢��20�N�C����ɂ�30�N�ƌĂ��C���ɑ����䂪���̒���ݏo�����̂ł��낤�B

���̂悤�ȓ��{�̐������̒ቺ�̔w�i�ɂ́C���{����јJ���Ƃ��������Y�����̐L�тƂ��ꂪ�����Ɍ����I�ɐ��Y�����ɗp����ꂽ�����������Y���̐L�т��݉��������Ƃ�����B���Y���̐L�т͊�Ƃ̌����J���ւ̓�����C�m�x�[�V���������Ɛ[����������Ă���ƍl������B
�y4�Łz�����Ŗ{�e�̑O���ł́C���̊Ԃ̓��{��Ƃ̌����J����C�m�x�[�V�����ւ̎��g�ݕ��Ɋւ��Ăǂ̂悤�Ȗ�肪�������̂��C�V�����Y�Ƃ⎖�Ƃݏo���������Ȃ��s�\���ł������̂��C���Z�p�̐i�W��f�W�^�����Ȃǂ̋Z�p���̕ω��ɂǂ����ēK���ł��Ȃ������̂��C�������Ă��������B�܂��C��ƌo�c�ɑ傫�ȉe��������ڂ��Z�p�����ɂǂ̂悤�ȕω����������̂���_���C���������ω��ɓK���ł��Ȃ����������Ƃ��āC����܂ŕM�҂炪�_���Ă������{�I�o�c�̓����͂ǂ̂悤�ɊW����̂��C����͓��Ɉӎv��������Ƃ̊֘A�����܂��čl�@���Ă��������B
1.1�@�Z�p���̕ω�
�P�j�A�[�L�e�N�`���ւ̒���
1990�N��ɂ����āC��Ƃ̐��Y�����ɑ���ȉe����^�������Y�Z�p�ʂɂ�����ω��Ƃ��ẮC���i�̐v�v�z�i�A�[�L�e�N�`���[�j��̕ϊv�����ڂɒl����B���̕ϊv�́C���{��Ƃ̓ƒd��ł������G���N�g���j�N�X�Y�ƂŗD�ʐ��������Ă������ƂɂȂ����ƂȂ����Ƃ�����傫�ȓ����ł������B�A�[�L�e�N�`���ɂ͑�ʂ��āC���W���[���^�ƃC���e�O�����^������B���W���[���^�Ƃ́C���i�V�X�e�����\������v�f��Ɨ������C���ꂼ��̗v�f���C���^�[�t�F�C�X��ʂ��Č��������邱�ƂŁC���i���������邱�Ƃ��ł���悤�ɂ������Y�����ł���B�T�u�V�X�e���Ԃׂ̍��Ȓ�����K�v�Ƃ����C���O�ɌX�̕����̌��т��������߁C�e�Ղɑg�ݗ��Ă��\�ƂȂ�����ł���B���̕����́C�X�̕����̐ڍ��̒�����g�ݗ��Ă̌���ōs���C���e�O�����^�Ƃ͈قȂ�C���Y�H���Ԃł̔����Ȓ����⓯�����͕s�v�Ƃ���C���{��Ƃ����ӂƂ��Ă�������ł̏n���Z�\��ׂ��ȃR�~���j�P�[�V������v�����Ȃ��Ȃ����B
�A�[�L�e�N�`�������W���[���^�Ƃ��邩�C����Ƃ��C���e�O�����^�Ƃ��邩�C�܂����W���[���^�Ƃ���ꍇ�C���̃C���^�[�t�F�C�X���I�[�v���i���J�j�ɂ���̂��ۂ��C�Ƃ������I���͒P�ɐ��i�̊�{�v�̍l���ɂƂǂ܂炸�C�g�D�Ɛ헪�̊�{�v�̍l���Ƃ��W���Ă���i����i2006�j�j�B���W���[���^���i�̏ꍇ�C�p�\�R���Y�ƂŌ���ꂽ�悤�ɁC�L�[�ƂȂ镔�i���f�t�@�N�g�E�X�^���_�[�h�ɂ��邱�ƂŁC��l���������߂邱�Ƃ��\�ł���1�j�B�g�ݗ��Ď��̂́C�C���^�[�t�F�C�X��ʂ��ĊȒP�ɂł���̂ŁC�����\�͕͂K�v�Ƃ���Ȃ��B�]���āC�����ԎY�ƂœT�^�I�ɂ݂���悤�ȁC����ɂ����郂�m�Â���\�͂����ʉ��v���Ƃ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
���W���[���^�̃P�[�X�ł́C���i���Ƃɋ@�\��\�̉��P���Ɨ��I�ɒNj�����āC���̌��ʂƂ��Đ��i�S�̂̐��\�͍��x�����Ă����B�e��Ƃ�����ƂƂ̘A�g�⒲�����l�����邱�ƂȂ��C�����J����Y�������s���B�H���Ԃ̖Ȗ��Ȓ����͕s�v�ł���̂ŁC��ƊԂ̎���͎s����o�R���čs���C���Y�Y�Ƃւ̎Q�����ޏo�����R�ł���Ƃ���������L����B
80�N��ɐ��E�𐧔e�����C�G���N�g���j�N�X�Y�Ƃ┼���̎Y�Ƃɂ�����90�N��ȍ~�C���{��Ƃ��D�ʐ����������v���̈�ɂ́C���i�J����Y�������K�肷��v�v�z�̕ω��ɂ������ƍl������̂ł���B�������C�o�u������ɔ����Ɛт̈����ɂ���āC���z�̐ݔ�������K�ȃ^�C�~���O�ł̎v���������f���ł��Ȃ��������Ƃ�C���{�̘J���҂̒��������̖��C���Z�Ƃ̕s�U�Ȃǂ��܂��܂ȗ��R���W���Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��낤���C���Y�Z�p �y5�Łz �ʂɂ�����ω��Ƃ���ւ̑Ή������܂��ł��Ȃ��������Ƃ��傫�������ƍl������B
�����ԎY�Ƃɂ��ẮC�����������W���[�����̉e���͂��܂�傫���͂Ȃ��C���\��i�����m�ۂ��邤���ŁC���Y�H���ɂ����钲���Ɠ������d�v�ł��葱�����Ƃ����Ӗ��ŁC�C���e�O�����^�̐��Y�����̗D�ʐ��������̂Ƃ���ňێ�����Ă����B���{��Ƃ̐v�E�J���E���Y�̐��̋��݂͕ς�炸�C�����͂�ۂ������Ă���B�n������ƂƂٖ̋��ȁC�����I�������ՂƂ��鐶�Y�����̎d�g�݂̗D�ʐ��͈ˑR�Ƃ��Ĉێ�����C����͌����_�܂ő����Ă���ƌ����悤�B�������C�����ԎY�Ƃ͂���O�ł���CIT�v���Ƃ���ɔ������i�A�[�L�e�N�`���̕ω��Ɍ�����ꂽ�����̎Y�Ƃł́C�����������Ă���̂ł���B
�Q�j�I�[�v�����̗���
�C�m�x�[�V�����Ƃ́C�����Ӗ��ł͋Z�p�v�V�Ɩ�邱�Ƃ������C�킪���ł͓`���I�ɂ��̈Ӗ��ɂƂ��Ă������C���������C�m�x�[�V��������I�ɘ_�����V�����y�[�^�[�̋c�_�ɂ́C�V�g�D�̎����Ƃ��������_���܂܂�Ă���C�����Ӗ��ł̐��i��Z�p�̊v�V�Ɍ��肳�����̂ł͂Ȃ������B���݂ł͍L���u�Љ�ɉ��l�������炷�v�V�v�i�ꋴ��w�C�m�x�[�V���������Z���^�[�ҁi2017�j�C�R�Łj�Ƃ����`������C�����ł��Z�p�I�ȑ��ʂɂƂǂ܂炸�C�o�ϓI�ȉ��l�������炷�C�V�����g�D�Ԃ̋����̎d�g�݂̗̍p�Ȃǂ��C�m�x�[�V�����ƍl���悤�B
���������ϓ_����C�C�m�x�[�V�����ɂ�����I�[�v�����̗���́C���l�̑n�o�ɂƂ��ďd�v�Ȗ������ʂ����悤�ɂȂ��Ă������Ƃ́C���ڂ��ׂ��_�_�ƂȂ�B�I�[�v���E�C�m�x�[�V�����̏d�v���ɂ��Ă̎w�E�́C�`�F�X�u���[�i2003�C2006�j�Ő挩���������ĂȂ���Ă���B�]���̌����J���́C���Ƃ̓����Ŋ������邱�Ƃ����R������Ă����B�V�������i����悵�C�J�����C���Y���C�̔�����Ƃ����C���̂��ׂĂ̒i�K�����Ђł�萋���邱�Ƃ��ł��C���v���ő���l���ł���Ȃ�C����͗��z�I�ł���B���̉�ЂƂ̋�����A�g�́C�Z�p�Ɋւ�����R�o�������Ƃ����ϓ_������C�܂�����ꂽ���v�̕��z���߂��镴���������Ƃ����Ӗ��ł��C�K�������ǂ����@�Ƃ͂����Ȃ��B��������̋@���`�I�s���ɒ��ʂ��鋰�ꂪ����C�܂��s��I�Ȏ���_��̒����E���s�ɂ͑���ȃR�X�g��������\��������B����́C���Ђ̒��ŁC�N���[�Y�h�ȑ̐����\�z���邱�Ƃ̃A�h���@���e�[�W�͑傫���B�����I�����ɂ���āC���C�J���C���Y�C�̔��Ƃ�������A�̒i�K���Г��ɕ������ނ��ƂɗD�ʐ����F�߂�ꂽ�̂��C20���I�^�̎Y�Ƒ̐��ł������B
�������Ȃ���CICT�Z�p�̊i�i�̐i���C�Y�Ƃ������G�Ȑ��i�E�T�[�r�X�̏o���C�o�ς̃\�t�g���E�f�W�^�����̐i�W�́C�����I�����Ƃ����r�W�l�X���f���̗D�ʐ������������ƂɂȂ����B�P���ȋZ�p�C���邢�͌��肳�ꂽ�̈�ł̌����J���ł���C�N���[�Y�h�ȑ̐��������I�ł��������C�ߔN�ɂ�����Z�p���̕ω��̑����╡���I�ȋZ�p�̑g�ݍ��킹�̗v���C�ƊE�̊_���������i�J���̕K�v���Ȃǂɂ��C�P�ВP�ƂŐV�������i�E�T�[�r�X�ݏo���̂ɕK�v�Ȃ��ׂĂ̒m������C�o�c������ۗL���邱�Ƃ͍���ƂȂ��Ă����B�s�ꋣ���ŏ����c�邽�߂ɂ́C��������Ǝ��Ԃ������Čo�c������~�ς��邱�Ƃ�������Ȃ������܂�Ă����̂ł���B
�����J����p���啝�ɏ㏸���C���i�̃��C�t�T�C�N�����Z�k����X���������Ă���C�N���[�Y�h�Ȍ����̐���O��Ƃ����r�W�l�X���f���ł͑Ώ��ł��Ȃ����o�����Ă����ƍl������i�}�\�Q�Q�Ɓj�B���Ў����̈ꕔ�𑼎Ђ֔��p��������C���ЂƂ̘A�g�ɂ��C�R�X�g�̍팸��}�����肷�邱�Ƃ��d�v�Ȍo�c��̌����ΏۂƂȂ�̂ł���B
�y6�Łz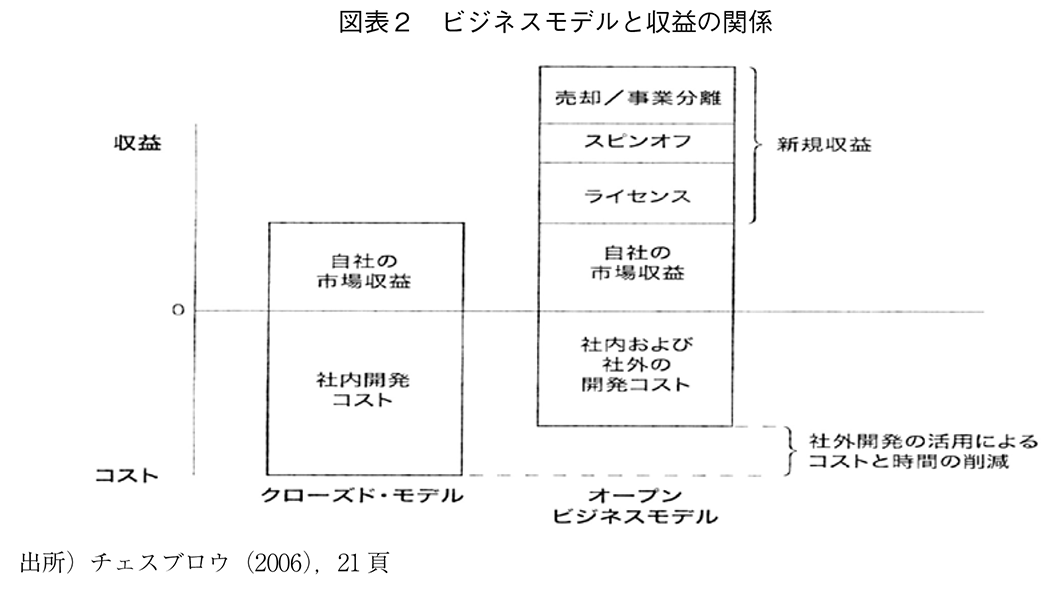
�`�F�X�u���E�i2006�j�ł́C�C�m�x�[�V�����̃I�[�v�����̓T�^�Ƃ��Ĉ��i�Y�Ƃ┼���̋ƊE�����グ���Ă���B�O�҂ɂ����ẮC�������x�ɂ��m�I���Y���͈����Ԏ���邪�C����ł��W�F�l�b���b�N��Ƃ̋����Ȃnj������������Ă���C�o�C�I���2�j�̏o���ɂ���Ĕ���Ȍ����������s���ƂȂ��Ă���B
��҂͎��m�̂Ƃ���C�����̉�H�̏W�ϖ��x�̌��㑬�x�͂����܂����C���Y�ɕK�v�Ȑݔ������z�͔����I�ɑ����Ă���B�����������ŁC�������{�Ɍ��������v���グ�邽�߂ɁC�I�[�v���E�C�m�x�[�V�������C�헪�I�Ɍ�������C���s����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă���B
�����ŁC���߂āC�I�[�v���E�C�m�x�[�V�����Ƃ́C�u�m���̗����Ɨ��o�����Ђ̖ړI�ɂ��Ȃ��悤�ɗ��p���ĎГ��C�m�x�[�V��������������ƂƂ��ɁC�C�m�x�[�V�����̎ЊO���p�𑣐i���邱�Ɓv�ƒ�`�ł���i�`�F�X�u���E�i2006�j�j�B���̒�`�͂��Ȃ�L�����̂ł��邪�C��Ɠ����ƊO���̃A�C�f�A��L�@�I�Ɍ��������C���l��n�����邱�Ƃ�ڎw�����̂ł���C�ЊO�̒m�����Ӑ}�I�Ɏ�����C�Г��̒m�����Ӑ}�I�ɗ��o����Ƃ����Q�̑��ʂ�L����i�đq�E�����i2015�j�j�B�܂�C�C���o�E���h�^�ƃA�E�g�o�E���h�^�̂Q�̃^�C�v������̂����C������̃^�C�v�ł���C����������I�ɍs���C���������邽�߂ɂ́C�g�D�\����g�D���s�C�Ǘ��҂Ə]�ƈ��̈ӎ��E�����̕ϊv���K�v�ƂȂ낤�B�I�[�v���E�C�m�x�[�V�����ւ̒�R�́C�����J������ɍ���������NIH�inot invented here�j���ہC���O��`�ɂ���Ƃ����B�A�����J��Ƃł����������v�l�l�����I�[�v���E�C�m�x�[�V�����̖W���ɂȂ��Ă���Ƃ̎w�E�����邪�C����`�I�ŏc����ӎ��̋������{��Ƃł̓C�m�x�[�V�����̃I�[�v�����̐��i�ɂ͈�w�̍���҂��邱�Ƃ��\�z�����̂ł���B
�y7�Łz�R�j�f�W�^�����ƃf�W�^���E�g�����X�t�H�[���[�V����
�ŋ߁CDX�i�f�W�^���E�g�����X�t�H�[���[�V�����j�ւ̑Ή������{��Ƃ̉ۑ�Ƃ��Ď��グ���邱�Ƃ������B�ꋴ�r�W�l�X�������[�i2020�j�œ��W�����g�܂�C���{�E����i2020�j�́CDX���u�f�W�^���Z�p�̐Z����������Y�ƂȂǂ̂����镪������悢�����ɕω�������v�Ƃ����Ӗ��̊T�O�ł���Əq�ׂĂ���B�����āCDX�͒P�ɋƖ����P���Ӗ����Ă���̂ł͂Ȃ��C�f�W�^���Z�p�ŎY�Ƃ��ς��Ƃ����C�d�v�Ȏ��_���܂܂�Ă���C�Ƙ_���Ă���B��̓I�ɂ́C�R���s���[�^�Y�Ƃ��Ƃ��āC�}�\�R�Ɏ�����Ă���悤�ɁC�Y�ƍ\����1990�N��
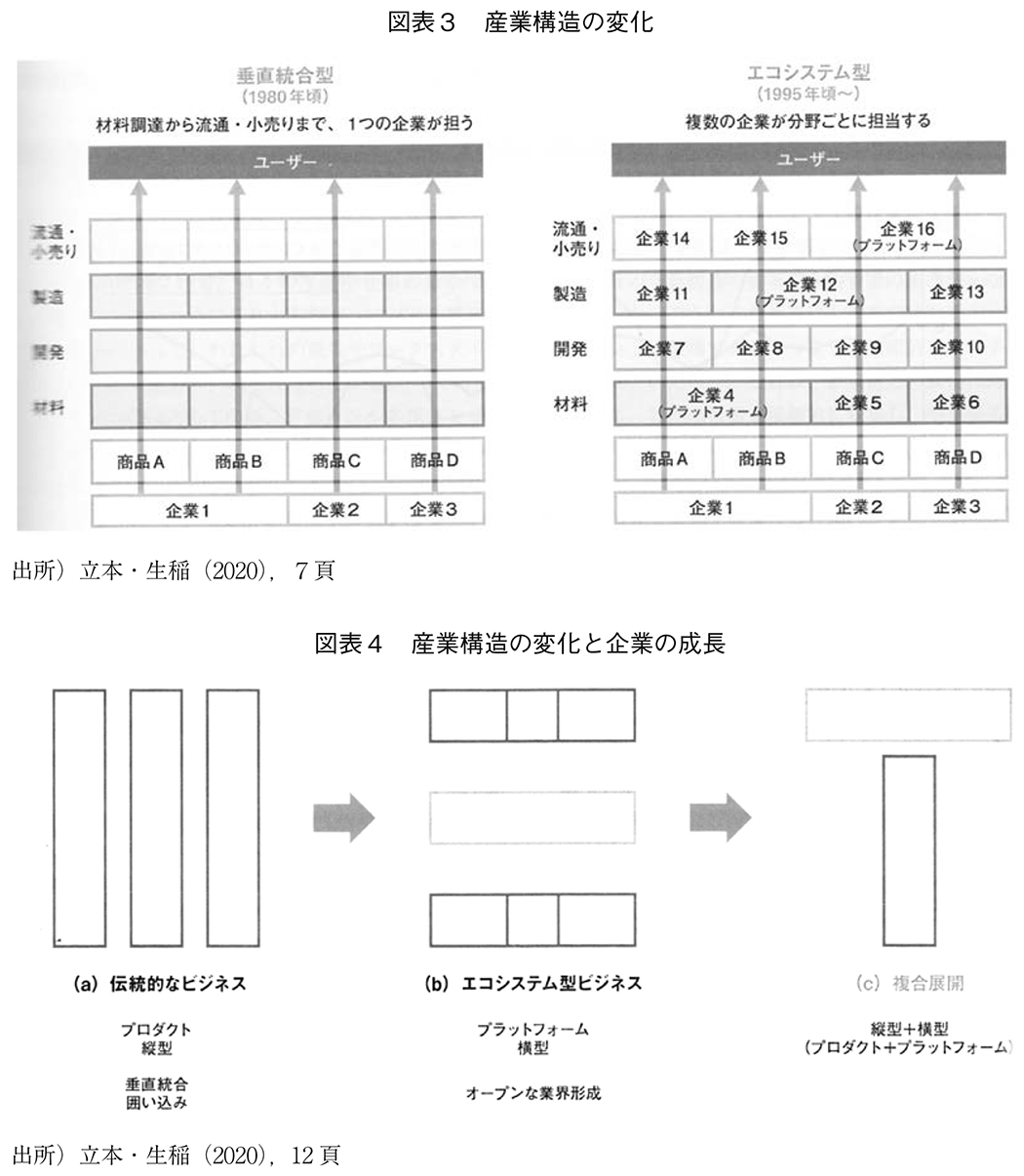 �y8�Łz
�y8�Łz
�ɑ傫���ω����C�c���牡�ɕω������Ƃ��Ă���B
�����I�����^�̃r�W�l�X���f���͎Y�Ƃɂ���Ă͌��E���}���C�G�R�V�X�e���^3�j�ƌĂ��Y�ƍ\�����嗬�ƂȂ����B�����ł́C���j�ƂȂ��Ƃ��`������v���b�g�t�H�[���ɑ����̊�Ƃ��Q�����C�����E�A�g���邱�Ƃɂ���āC�`���I�Ȓ�����ł��j��j��I�Ȃ��邢�́C����I�Ȕ��z�ɂ���ď]���̐��i�E�T�[�r�X�ɂƂ��đ���V���ȉ��l�ݏo���C�m�x�[�V�������n������₷���ƌ�����B
�`���I�Ȑ�����Ƃ��]���̗̈�ɗ��܂�̂ł͂Ȃ��C�ϋɓI�Ƀf�W�^���Z�p��L�����ƂƐڐG���C�V���Ȑ��i�E�T�[�r�X����Ă����p��������Ă���̂��CDX�̖{���ł���i�}�\�S�Q�Ɓj�B���̍ہC�f�[�^�̉ʂ����������傫���ƌ����Ă���B���{�E����i2020�j�́C�f�[�^�̃o�����[�`�F�[���Ƃ����T�O����C�f�[�^�Ƃ����������o�����[�`�F���̂ǂ��ŕt�����l�ɕϊ����C���[�U�[�ɒ��邩�̑S�̑����\�z�����邱�Ƃ��厖�ł���C�g�b�v�}�l�W�����g�̊֗^�ƌ��ꃌ�x���̎��s����̑g�ݍ��킹���C�ϊv�ɂ͕K�v�ł���Ƃ��Ă���B
1.2�@���{��Ƃ̈ӎv��������̓����Ɩ��_
��q�����悤��ICT�Z�p�̊i�i�̐i���𒆊j�Ƃ����C�I�[�v�����C�f�W�^�����C�̔g�́C��S���Y�Ɗv���Ƃ��̂����C���{�o�ς����{��Ƃ����ĂȂ������ɒ��ʂ��Ă���B���������̒��ŁC��Ƃ͂ǂ̂悤�ɑΏ�����̂������Ȃ̂��C���R�̂��ƂȂ���ȒP�ɂ��̉��͌����炸�C�ꓬ���Ă���̂������ł���B�����ł́C���{��Ƃ̕�����ۑ���ӎv��������̓����Ɨ��߂Ę_���Ă݂����B
���{�I�o�c�̂R��̐_��i�I�g�ٗp�C�N������C��ƕʑg���j�ɂ��ẮC���̘A�ڂ̒��Ŋ��x���w�E���Ă������C���͈ӎv����݂̍���ɂ����{�Ɠ��̂��̂��݂���B���̏ے����g�c���x�ł���B�g�c���x�́C�g�D���̑����̐l���ӎv����ɎQ�悳���C�������L�����i�Ƃ��ėD�ꂽ�����ł���Ɨ��������ʂ�����B�����i1996�j�́u�킪���̑����̑g�D�̂ɂ����ẮC�ʏ�C�e�팈��̖���N�E�����Ă̍쐬�́C�傫�Ȍ����������Ȃ������̒S���ҁi�ʏ�͒��ԊǗ��ґw�j���N�Ă��C������W�e�����ɉ�c�C���c���C������e�̎��{���C���ނɂ���ď�ʂ̌����҂ɏ�\���C���̌��ق����B��ʎ҂͂���ɂ���ĉ��ʎ҂̑��ӂ��m�F�������Ƃɂ��C���̐ӔC�̂��Ƃɓ��e��F�߂ē���ق���C���ꂪ���ɂ��낳��邱�Ƃɂ���Ď��s�Ɉڂ����Ƃ����������̗p���Ă���v�Əq�ׁC������g�c���x�ł���Ƃ��Ă���B�R�鑼�i1979�j�⏬��i1980�j�̌����́C�g�c�����������{�I�o�c���̂��̂ł���Ǝw�E���C���ė��̌o�c�Ǘ��̕����ƈقȂ�Ǝ��̓��F��L����Ƃ��Ă���B
�g�b�v�_�E�������ł͂Ȃ��C�ے��N���X����̔��Ă���������g�c���x�́C�쒆�i1995�j���m���n����ƂŎ咣����~�h���E�A�b�v�_�E�������̃}�l�W�����g�X�^�C���Ƃ����ʂ���Ƃ��낪����悤�ɂ��v����B�킪���ł́C�g�b�v�̊K�w�����̌�����w�i�ɁC���莖�������ʊK�w�̏]�ƈ��ɖ��ߓ`�B����Ƃ��������C�~�h���̎����I�Ȓ�Ăd���镗�y������C����ɂ���ĉ~���ŁC����̑n�ӂ��ӂꂽ���z�����g�D�^�c���s���Ă���B����܂łɎ��Ԃ�v���Ă��C���s����i�K�ł́C�����S�̂ŗ����������Ă���̂ŁC�x�Ȃ��������i�� �y9�Łz �Ƃ�������������B�������C�g�b�v�̃��[�_�[�V�b�v���������Ȃ��ۑ������C�g�b�v�ƃ~�h�����邢�̓��[���[�o������̃_�C�i�~�b�N�ȏ��̗���ƈӎv�a�ʂ͂ǂ�ȑg�D�ɂ����Ă�����邪�C�ӎv����̍ۂɂǂ���ɏd�_��u���������Ċ�ƂƓ��{��Ƃ͈قȂ��Ă���̂ł���B
80�N��܂ł́C���{��Ƃ̏W�c�I�Ȉӎv��������͋��݂����Ă������C��q�̂悤�ȋZ�p����s����̕ω��̑��x�������ƁC���̑����ɂ��Ă����Ȃ��Ȃ�Ƃ������_�����B�W�c�I���c���ɂ��܂Ƃ��ω��ւ̒�R��r�����邽�߂ɂ́C�g�b�v�_�E�������ɂ��v���Ȍ���̕����C�~�h���E�A�b�v�_�E���������]�܂�����������Ȃ��B��Ђ̋��E���z���đ��ЂƂ̘A�g�⋦����}�낤�Ƃ���ۂɂ́C�W�c�I�ӎv����́C���ӂ̌`���Ɏ��Ԃ�v���C�c�_��f�����܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��Ȃ����������C���ꂪ�v���I�ȃf�����b�g�ɂȂ邩������Ȃ��B���̓_�͓��ɁC�n���I�ɉ����C����݂̂Ȃ��C�܂��������m��Ȃ���ƂƂ̐ڐG��W�̍\�z�����݂悤�Ƃ���ۂɂ͑傫�ȏ�Q�ƂȂ낤�B
�헪�ʂł݂�ƁC���{��Ƃ͑��p���ɂ���āC���L�����i�E���Ƃ�����Ă����X�����������i���{�E�^��i2017�j�j�B���ɁC�d�@�Y�ƂœT�^�I�ɂ݂�ꂽ�悤�ɁC�����̉�Ђ�������Ɠd���i������C���̂��ߌ������������W�J����C���ʓI�ɎY�ƑS�̂Ƃ��ĕi����\�����サ�C����҂ɂƂ��Ė]�܂�����Ԃ������炳�ꂽ�B�������Ȃ���C����ɂ����āC����͎��Г��Ō����J������C���Y�C�̔��܂Ŋ��������C���ꂼ��̊�Ƃ������I�����^�̌o�c�̐���z���グ�邱�ƂɂȂ����̂ł���B
���{��Ƃ͌�������Ɗԋ������J��L���钆�ŁC�ǂ̂悤�ȐV�K���Ƃɐi�o���邩�̌���́C�K�������S�ГI�Ȋϓ_����g�b�v�_�E���I�ɂȂ����̂ł͂Ȃ��C�e���ƕ��ɂ����ă~�h�����������݂Ȃ���s���Ă����B���̂��ߎG���ŁC�d���������ƕҐ��ƂȂ�C��БS�̂ł݂�ƁC�����I�Ƃ͌����Ȃ����i�\���E���ƃ|�[�g�t�H���I�Ɋׂ�����Ƃ��������B����͖{�Ђɂ����ăg�b�v�_�E���^�̐헪�I���肪������Ȃ����̂̔ߌ��Ƃ����鎖�Ԃ������]���ł��邩������Ȃ��B
���{��Ƃ̑g�D�́@�c����ŁC����Ԃ̕ǂ������C�Г��ł̍��⒲���Ɏ��Ԃ��Ƃ��C���݂̒x�������̂悤�ɂȂ��Ă����\��������B�ӎv����ɂ������āC�R���Z���T�X���ߓx�ɏd���������ʁC�C�m�x�[�V�����̃I�[�v�������K�{�ƂȂ�������ɓ����āC���܂��K���ł��Ă��Ȃ��ƕ]����Ă��d���Ȃ��ʂ��������̂ł���B
1.3�@�䂪���̊�ƊԊW�ƃC�m�x�[�V����
�I�[�v���E�C�m�x�[�V�����ɑ��āC���{��Ƃ̎��g�݂��x��Ă���C���ꂪ�A�����J��Ƃɗ�シ�錴���ƂȂ��Ă���Ƃ̋c�_�����邪�C����ɂ����Ċ�Ƃ̋��E���z������ƊԂ̋����J���⌻��̉��P�����ɂ�鐶�Y���̌���Ȃǂ�ʂ����C�m�x�[�V�����̒Nj��͂킪���ł������ԎY�Ƃ�T�^�Ƃ��āC��ƃO���[�v�̒��Ő���ɍs���C����Ȃ�̐��ʂ��o���Ă����B�����ɂ��C���{��Ƃ̓I�[�v���E�C�m�x�[�V�������Â�������H���Ă����Ƃ������邩������Ȃ��B�������Ȃ���C����͍������`����Ă���C�I�[�v���E�C�m�x�[�V�����Ƃ͂��قȂ�B�ŋ߂̃I�[�v���E�C�m�x�[�V�����Ŋ��҂���Ă���̂́C�ٖ��Ȋ�ƊԊW���x�[�X�Ƃ���`���I�ɂ͕\���ł��Ȃ��Öْm�̈ړ]�₻��Ɋ�Â����݊w�K�ł͂Ȃ��C�����Č����C�s��W���x�[�X�ɏ]���C�ڐG�����̂Ȃ�������ƂƋ������C�َ��ȃA�C�f�A���Ԃ������C�V�������l��n�����邱�Ƃł���B�\�������o�[�����Ȃ�Œ肵�����{�̌n��W�ł͂����� �y10�Łz �����l�̑n���͊��҂ł��Ȃ��Ǝv����B
��ƊԂ̒�������W�����{�I�o�c�̈�̓����ł��邱�Ƃ́C��ˑ��i2021b�j�Ř_�������C���̍��i�͌��݂ł��ێ�����Ă���B����ɂ̓����b�g���f�����b�g������C���P�̗]�n�����邱�Ƃ��w�E�����B���̍ۂ̘_�_�Ƃ��āC�n��W�ɂǂ����Ă����܂Ƃ������̖��_���������B���̓_�͂��āC���č\�����c�ɂ����Čn��͎Q����ǂƂ��ċ@�\���Ă���Ƌ����ᔻ���ꂽ�Ƃ���ł��������C��Ř_�����C�m�x�[�V�����̒������ӂ݂�ƁC�O������̔ᔻ��҂����Ƃ����̌��_�����Ă����w�͂����߂��悤�B
��ʂɑg�D�Ԃ̊W�ɂ́C�^�C�g�Ȍ��т��i�����R�сj�ƃ��[�X�Ȍ��т��i�ア�R�сj������B���ꂼ��̌��т��ɂ́C�m�̋��L��m�̒T���Ɋւ��āC�꒷��Z������C��T�ɂǂ��炪�D��Ă���Ƃ͌����Ȃ��i��сi2017�j�j�B
�����R�т́C�Öْm�̋��L�����₷���C��Ƒ��݂̐M������������C�R�~���j�P�[�V�������~���ɂȂ���C���L���ꂽ�ړI��B������ɂ͗D��Ă���B�Z�p�I�ȃC�m�x�[�V�����ł����C�]���̐��i�̕i���̉��ǂ�\�̌���Ȃǂ̎����I�C�m�x�[�V�����ɓK���I�ł���B�m�̒T���Ɗ��p�Ƃ����ϓ_���炷��C��҂Ɍ����Ă���4�j�B�������Ȃ���C�َ��ȃA�C�f�A�┭�z���������āC����I�ȃC�m�x�[�V�����ݏo���ɂ͓K���Ă���Ƃ͌�����B�m�̒T������������ɂ́C�ނ���ア�R�т̕����D��Ă��邾�낤�B�ア�R�т��_�@�Ƃ����ƊԂ̌��т��́C�n���I�ɗ��ꂽ��Ƃ��C�܂����푽�l�ȋƊE�̑g�D���Q���ł��C�v��ʏo�������C�Z�����f�s�e�B�������炷�\��������B���̈Ӗ��ŁC�ŋ߂̃I�[�v���E�C�m�x�[�V�����ƓK���I�ȃl�b�g���[�N�W�ł���B���{�̌n����\�Ƃ����ƊԊW�͋����R�т̐F�ʂ������C��̌�����l�b�g���[�N�ƌ����悤�B����́C�K�����������I�ɕ\������Ȃ��ÖٓI�ȏ��̖Ȗ��Ȏn���ɂ̓A�h���@���e�[�W�������Ă���B
�������C����܂ł̉�������ɂ͂Ȃ��j��I�C�m�x�[�V�������邢�͔���I�ȃC�m�x�[�V���������s����ɂ́C�������т��ł͓���C�ނ��낻�������C�m�x�[�V�������N�����Ȃ����X�N���傫���Ȃ�B�����ɂ��āC��ƃO���[�v�̋��E��Ⴍ���C���ߐ������߂邩��������Ă���B�Ⴆ�C�m�̐[���ƒm�̒T���𗼗������邽�߂ɁC�ٖ��ȘA�g�Ɗɂ₩�ȃl�b�g���[�N��S�����镔����蕪����Ƃ������`�ł̑g�D�̍ĕҐ����L����������Ȃ��B����C�g�D�̃C�m�x�[�V�������v������Ă���̂ł���B
1.4�@�ϊv�Ɍ�����
���{�o�ς̒�����������C���Y�����オ��Ȃ��v���Ƃ��āC�u���Ƃ��l�ނ�ݔ��Ƃ��������ւ̓��������Ȃ��Ȃ����v�ƁC���{�f�ՐU���@�\�A�W�A�o�ό������̐[�����i�����͘b���C���v�����傲�Ƃ̏c�����l���N�p�̔N����`�Ƃ������ǂɑj�܂�C�f�W�^�����ȂǍ\���ω��ւ̓K���͖͂�����Ȃ������Ƃ����i���{�o�ϐV��2020�N�P��10���t�j�B
�y11�Łz�����������{��Ƃ̕�������́C�ٗp���x�⊵�s5�j�̍��{�ɂ������̂ŁC�꒩��[�ɉ������邱�Ƃ͖����ł��邪�C���{�I���v��O��Ƃ��Ȃ��Ƃ��C�����_�ʼn\�ȉ��v�Ɉ���ł����ݏo�����Ƃ͏d�v�ł��낤�B
�A�����J��GAFAM�̂悤�ȓˏo�������Z�p�n�̊�Ƃ��o�����Ȃ����ƁC���邢��90�N��ɂ�����R���s���[�^�Y�Ƃ┼���̎Y�Ƃ̐��ނɂ���āC�R��̐_����\�Ƃ���ٗp���x�̎d�g�݂⊔����d�����Ȃ��R�[�|���[�g�K�o�i���X�̐��C�ȂǓ��{��Ƃ̌o�c�݂̍���������ᔻ���ꂽ�B�܂��x���`���[��Ƃ�x���`���[�L���s�^���̏��Ȃ����Ƃ��C�V��ӂ̋N���Ȃ������Ƃ���C��莋���ꂽ�B�g�D�̕����C���X�N���I�Ȍo�c�p���C���̍����ɂ���a�ԓ`���I�v�l�l���ւ̋����^�������Ă����B�A�����J��Ƃ�͂Ƃ���g�b�v�_�E���I�Ȑv���Ȍ���̕K�v���C�R�[�|���[�g�K�o�i���X���͂��߂Ƃ��āC�l�����x�⊵�s�C����ɂ͋��琧�x�܂ŁC���{�I�Ȑ��x���v�C�����Ċ�ƕ�����]�ƈ��̈ӎ��̕ω���v������c�_���V����o�ώG���Ő���ɘ_����ꂽ�B
�đq�E�����i2015�j�́C�I�[�v���E�C�m�x�[�V�����𐄐i���邽�߂ɁC�g�b�v�̋����R�~�b�g�����g�Ƌ���ȃg�b�v�_�E����@�Ɛ�啔���̗����グ����C��̓I�ȑg�D�Ґ���_���Ă���B�m���ɕϊv�ɒx�ꂽ���Ɍ�������{��Ƃ̏��l������C����������ł��낤���C�������C�������������Ɉꋓ�Ɍ������ׂ��Ȃ̂��C���邢�͌��������Ƃ��ł���̂��C���^��Ȃ��Ƃ��Ȃ��B�`���I�ȓ��{��Ƃ̃~�h����[���[���������݁C�O�m���W�߂�o�c�̗ǂ��́C�����Ď̂ċ���ׂ��ł͂Ȃ��Ǝv����B�ӎv����̃X�s�[�h���������ׂĂł͂Ȃ��C���{��Ƃ̋��݂�����悤�Ȑ��i�E�T�[�r�X�⎖�Ƃ̊J���E�͍��C�g�D�\���̕Ґ��C��ƊԊW�̎d�g�݂��\�z���ׂ��ł��낤�B���̂��߂ɂ́C���ω��̑�������Ƃ���قNj}���ȕω��ւ̑Ή������߂��Ȃ������藣���ȂǁC�n�C�u���b�h�ȑg�D�\�����\�z���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ邩������Ȃ��B�܂��CDX���ɂ��Ă��C�ɒO�i2020�j���w�E����悤�ɃA�i���O�^�̗ǂ��ƃf�W�^���^�̗��_�̗Z��������ɓ���āC���{��Ƃ̓����C���{�l�̊������ő�������ł���悤�ȁC�헪�W�J��g�D���v��}��̂���̕����ł��낤�B
�M�҂炪����܂Łu����́u���{�I�o�c�v�_�i�P�j�i�Q�j�i�R�j�v�ŏq�ׂĂ����C�����_�ł́u���{�I�o�c�v�_�́u�����v�ł́C�܂��Ɂu������v���{�I�o�c�_���̂�グ�Ă��Ă���B
����ɑ��Ė{�e�ł́C���{�I�o�c�́u�����I���ʁv�ɂ��āC��������B
�y12�Łz2.1�@�o�u���o�ϕ���O�̓��{�I�o�c�̍����I����
���R�i1992�j�ł́C��������̂悤�ɊT�ς��Ă���6�j�B
�i�P�j�O���[�v���������B
�킪���ɂ͑����̊�ƃO���[�v����ъ�ƌn�������B�L���ȂƂ���ł́u��ƏW�c�v�ƌĂ����̂�����C�O�H�O���[�v�C�O��O���[�v�C�Z�F�O���[�v�C���u�O���[�v�C��ꊩ��O���[�v�C�O�a�O���[�v�̂U���u�Z���ƏW�c�v�ƌĂԂ��Ƃ�����B������ƏW�c�̒��S�ɂ͋�s���ʒu���āC���Z���^�[�̖������ʂ����Ă����B�����Ēʏ킱�̋�s�́C�O���[�v����ƂɎ����̑ݕt���s���C�܂������ɃO���[�v����Ƃ̊���ɂ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ������B�����ɂ�����Ƃ̏]�ƈ��̋��^�U�荞��s�ƂȂ��Ă���̂��ʏ�ł���B
���̂悤�ȑ̐��́C������u���C���E�o���N�v���x�Ƃ��Ė��������C�d�v�Ȃ��Ƃ́C�����̊�ƃO���[�v���C�����I�ɂ͂ЂƂ́u�~�j���{�s��v���`�����Ă������Ƃł���B���́u�~�j���{�s��v�́C���{�s��S�̂ɑ��āC�ЂƂ̕��f���ꂽ�C���邢�͊u�����ꂽ�}�[�P�b�g���`�����Ă����B���̂悤�ȃ}�[�P�b�g�̑��݂̈Ӌ`�́C���̏��_�Ɍ��o����ƌ����Ă����B
�@�O���[�v����Ƃ̎ؓ������͎s���ʂɂ���ׁC�ϓ������Ȃ����Ă��炦��B
���C���E�o���N�ƃO���[�v����Ƃ̌_������́C�����ɂ킽���r�I�ɌŒ肵�Đݒ肳��邱�Ƃɂ��C�o���ɂƂ��ėL���ƂȂ�B���Ȃ킿�C���Z�ɘa���ɂ́C��ʂɎs������͒ቺ���邪�C�O���[�v����Ƃ͂���ɂ�������炸�C��荂�����������C���E�o���N�Ɏx�����C����C�s������̏㏸������Z�N�����ɂ͋t�Ƀ��C���E�o���N�͂��Ƃ̂܂܂́C�s���ʂ����Ⴂ������K�p���C���݂��̈���I�Ȏ��Ɗ����C����𑣐i�������邱�Ƃ��ł���B
�܂��C�O���[�v����Ɠ��m�̎���ɂ������Ă͔������]���Ԃ��O���[�v�O��Ƃ��������ݒ肵�C���݂��Ɏ����̗Z�ʂ����₷���Ȃ�悤�ɂ��Ă������Ƃ��m���Ă���B
�A�O���[�v�ɑ����Ă���Ƃ������Ƃ��C���Y��ƂɂƂ��Ă���u�S�ہv�����ƂɂȂ�B
���炩�̊�ƃO���[�v�ɏ�������Ƃ������Ƃ́C�����ł̃��C���E�o���N�����Y��Ƃ́u�ʓ|���݂�v���Ƃ�������Ƃ��C������Ӗ����Ă���Ƃ���C���ɁC�o�c�s�U�⎑���J�舫���ɂ��������Ă��C�Ō�ɂ͕K�����C���E�o���N���o�c�̃e�R����C�lj��Z�����s�����Ƃ̕ۏ����ƂɂȂ�B
����ɂ��C���Y��Ƃ͑��̎��������҂�����C���L���ȏ����Ŏ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B
�i�Q�j�����̑��ݎ�������
�킪���̊�Ƃɂ����銔���̑��ݎ��������́C���M���ׂ����̂�����B���Ȃ킿�C���̓��{�̌o�c�Ҏx�z�ƌĂ�錻�ۂ́C�I�n��т��āC�u��Ђɂ���Ђ̏��L�v�Ƃ������̂��y��ɂȂ��Ă��邱�ƁC����������́C��Ђ̊����̑��݂̎��������ɂ��u���݂̎����ꍇ���v�̑̌n�������Ƃ������Ƃł���B�������C���̂悤�ȉ�Б��݂̊������L�Ƃ����`�́C��ɒ����ɁC�i�s���Ă��Ă����̂ł���C�l����̗ʓI�Ȕ䗦�̉����C����ю��I�ȕϖe�C���Ȃ킿�������L�̕��U�x�̉����Ƃ������ہC�����đ�@�l�ۗ̕L���銔���̔䗦�̑���Ƃ����C�� �y13�Łz ���錻�ۂ��C�Œ艻���������B
���P���̏ꍇ�C1991�N���_�ł̖@�l����̎����䗦��75���Ƃ����Ă��āC�����͎s��Ŏ���������邱�Ƃ͂Ȃ������B�Ȃ��Ȃ�C�u������艻����v�Ƃ����ړI����C���p����邱�Ƃ͂Ȃ�����ł���B���̏ꍇ�C�o�c�Ҏ��g�ɂƂ��ẮC���Њ����̂�L�ӂȔ䗦�C���Ȃ킿�C�x�z�\�Ȃقǂɂ͏��L���Ă���킯�ł͂Ȃ����C�ނ���\���Ă����Ƃ́C���������̑��肽���Ƃ̑劔��ɂȂ��Ă���C����䂦�C�ގ��g���@�l�劔��̂���u��\�ҁv�Ƃ��āC����̊�ƂɑΉ����邱�ƂƂȂ�B����ɁC ���̂悤�Ȍo�c�҂������ꓯ�ɎQ���u�В���v�́C�����I�ɂ͍����劔���ł���C�����ɁC���ɁC�u���ݏ��L�ɂ��x�z�v���I��I�ȃ��[�g���o�ċ�������Ƃ��ꂽ�i���{�I��ƏW�c�̔����j�B�������Čo�c�҂́C����̉�Ђ��u���L�v�ɂ���Ďx�z����̂ł͂Ȃ��C�����ƂƑ��݂ɏ��L���������Ƃɂ��C����̉�Ђ��I��I�Ɂu���ݎx�z�v���邱�ƂɂȂ��Ă���ƌ����Ă����B���̂悤�ɁC ���{�̊�ƏW�c�ɂ�����u�В���v�́C���݂ɑ劔��Ƃ��āC����u�M�F�v�������C�x�z���s�������u���ݐM�F�v�̑̌n�ł������Ƃ�����B���̂悤�Ȏ��������́C�A�����J�̋@�֓����Ƃ̂悤�ɁC��Ƃ����Y�̌����I�ȉ^�p��}�낤�Ƃ����ړI�ŁC����Ƃ̊�����ۗL�������ʂƂ��Đ��������̂ł͂Ȃ��B���̉�ЂɎ����̉�Ђ̊������擾���������Ƃ��C��������芔��H��C��̓I�ɂ����Ώ�����̖h�~�C���邢�́C�u�������͂ߍ����v�Ƃ���������������Ă������Ƃ�������炩�ȂƂ���C ���̂悤�ȑ��ݎ��������́C�u�͂ߍ��ݍ����v�Ƃ����̂����̎���Ƃ���Ă����B���Ȃ킿�C ���Ƃ��Ƃ́u���傪��Ђ�I�ԁv�̂����ʂł���Ƃ�����C�킪���ɂ����Ă͋t�Ɂu��Ђ�����̊����I�ԁv���ƂɂȂ��Ă����Ƃ����B�������C���̂悤�Ȗ@�l����́C�A�����J�̋@�֓����Ƃ̂悤�Ɏ�����𑗂荞�ނ��Ƃ����邪�C���̂悤�ȏꍇ���唼�����C������ł����āC�o�c��ᔻ�I�ɊĎ������肷�邱�Ƃ͂��܂肵�Ȃ��ƌ����Ă����B�������̂悤�Ȃ��Ƃ����݂Ă��C����̉�Ђ�������̉�Ђɓ����悤�Ɏ�����𑗂荞��ł��Ă���i�Ƃ����Ă���͂茓�C������j������̉�Ђ̌o�c�ɁC ����u�R�I�v�Ɋ����邱�Ƃ��ł��邩��C�������L�Ɋ�Â��e���͂́C������͑��E����Ă���Ƃ����B�������C���݂��̎���W�̓r�ⓙ�ɂ���āC���݂Ɏ��������̊W�����������肷��悤�ȁC�܂�ȏꍇ�������C����̉�Ђ��K�v�Ƃ������C���̖@�l����͂��̑����Ƃ̊���ł��葱����̂����ʂł���B
�i�R�j��s�ɂ�銔���ۗL
�����C������Ђ̗e�F���߂����ĉX�����c�_���N���Ă����u�Ɛ�֎~�@�v�ł́C���Z�@�ւ͍����̉�Ђ̊��������̔��s�ϊ��������̂T�����z���Ď擾���C �܂��͏��L���Ă͂Ȃ�Ȃ��i��11���P���j�Ƃ��������݂��Ă���B��O�̍����ɂ��C���̋��Z�͂����������Y�Ǝ��{�̎x�z�Ƃ������Ԃɑ��锽�Ȃ��琷�荞�܂ꂽ�K���ł���Ƃ����B���̂悤�ȋ��Z�@�ւ𒆊j�Ƃ�����ƌn��̌`���ƁC����ɂ��o�ϗ͂̏W���́C �������Ȃ����㒅���ɐi�s���ė������̂ł���C���a40�N��̂킪���̍��x�o�ϐ������x����d�v�Ȗ������ʂ����Ă������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����ł͊�Ƃ��K�v�Ƃ��钷�Z�����̋��n�����C���邢�͈���������s�������Ă����킯�ł���C����W�ɂ����Ƃ̊�������s���ۗL���Ă��邱�Ƃ́C����ɂ�銔�����v�Ăɂ��Ă���̂ł͂Ȃ��C���݂��́u�W�̕\���v�������ƌ�����B�܂�C���Z�W�i�������邱�Ƃ̏Ƃ��Ď��Ɖ�Ђ̑������s�Ɋ�����ۗL���Ă��炤�C�Ƃ����`������Ă����Ƃ������Ƃł���B�����ł̋�s�̖ڕW�͌����܂ł��Ȃ��C�Z�� �y14�Łz �̑��i�ł���B
����C�G�[�W�F���V�[���_�̗��ꂩ�猾���C��s�������Ɋ���ƍ��҂̑o�������˂邱�Ƃ̓v�����V�p���ƃG�[�W�F���g�̊Ԃ̏��I��Ώ̖̂�����������̂ɑ傢�ɍv��������B���̌��ʁC���j�^�����O�E�R�X�g�C�{���f�B���O�E�R�X�g�͔���I�ɐߖꂽ�ł��낤�B�����āC���̊W�������I�Ȃ��̂ɂȂ�Ȃ�قǁC�_��W�̉����ɔ������X�g���N�`�������O�E�R�X�g�͐ߖ�C���ʂƂ��ăG�[�W�F���V�[�E�R�X�g�̑��z�͌����I�ɗ}����ꂽ�ł��낤�Ǝv����B
�܂����R�i1992�j�ŋ������Ă����u�i�S�j�d���I�Ȕz������v�ɂ��Ă͂��̌�C���̂悤�ȏ��q�ƂȂ��Ă���B
�i�S�j�d���I�Ȕz������
�����ԁC�z������ɂ́u����z����`�v�Ɓu�z��������`�v�̂Q������ƌ����Ă��Ă���B�O�҂́C�����̂P������z���������ɕۂ��Ƃ�}��z������ł���C��҂́C���v�������o���ꍇ�͑��z�̔z�����C���Ȃ��ꍇ�ɂ͔z���͏��z�ɗ}����C�Ƃ����l�����ŁC���ʂƂ��Ĕz���������������肵���l�ɂȂ�C�Ƃ�������ł���B��ʓI�ɂ͉��Ċ�Ƃ͌�҂ɏ]���C ���{��Ƃ͑O�҂ɏ]���C�ƌ���ꑱ���Ă����B
���_���q�ׂ�C���̂悤�Ȏ咣�͊��S�ɊO��ł͂Ȃ����C����ȑO�قnj����ł͂Ȃ��C�Ƃ������ƂɂȂ낤�B���Ȃ݂Ɏ����ԎY�Ƃɂ��āC�ŋ߂̂��̔z�����r����ƁC���̂悤�ɂȂ�B
���������Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁC���ۊ�Ƃł���g���^���C�܂��z��������`�Ƃ����Ȃ����Ȃ����C����ƂĂ͂�����Ƃ������̂Ƃ͂����ɂ����B���̎����C�e�ЂƂ����̎Y�Ƃ̍D���ɏ���ċƐт�L���C�z�������₵�Ă������Ƃ��킩��B�������C 2008�N�Ĉȍ~�ɐ��E���P�����C�قƂ�njo�ϋ��Q�ƌĂ�ł������x���Ȃ����Ԃ̌��ʁC2008�N�x�́C�P������z���z�̓g���^��100�~�C���Y��11�~�C�z���_��63�~�Ƒ傫�����炵�Ă���B�z�������ɂ������ẮC�g���^��554.4���i!�j�C���̂Q�Ђ͑������o�������ߔz�������͌v�Z����Ȃ��B
���̂悤�ɋƐт̋ɒ[�Ȉ����Ɋׂ��Ă��z�������Ƃ��s�������Ƃ͋����Č����Έ���z������Ƃ����Ȃ����Ȃ����C ���͂�ȑO�Ƃ͈���āC�ЂƂ�����Ɂu���{��Ƃ̔z������́E�E�E �v�ȂǂƏq�ׂ邱�Ƃ͂ނ��������Ǝv����B
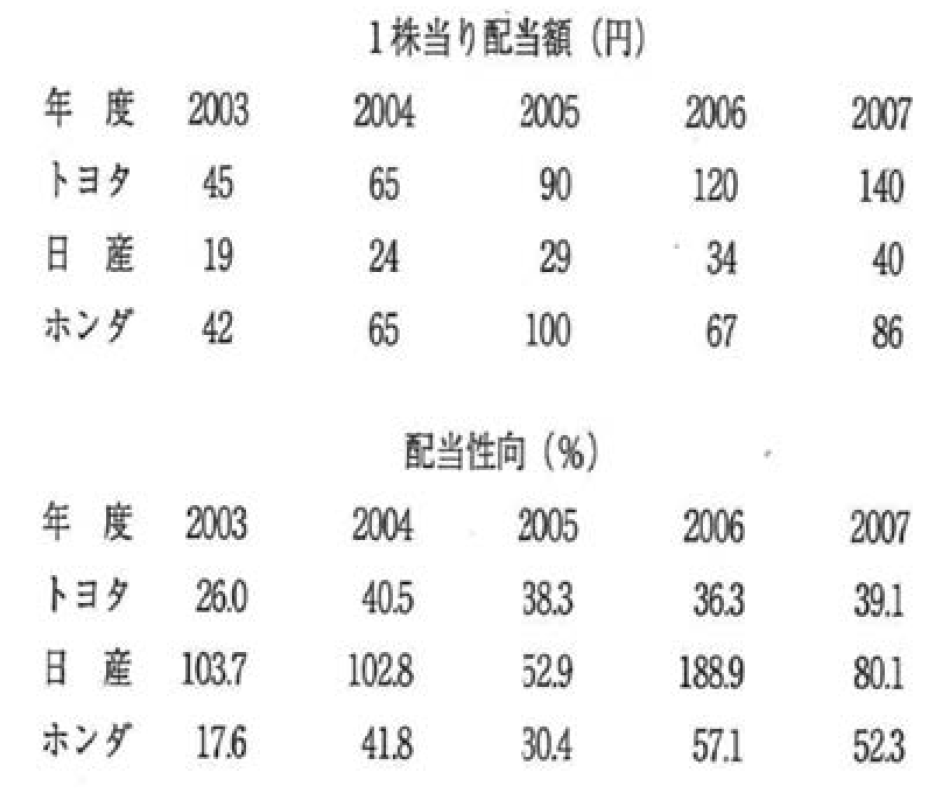 �y15�Łz
�y15�Łz
�������Č��Ă���ƁC�u�i�Q�j �����̑��ݎ��������v�������ē��{�I�o�c�̍����I���ʂ͂��܂�h���X�e�B�b�N�ȕω��͖ڗ����Ă��Ȃ��C�Ƃ������Ƃ��ł���悤�ł���B�i�Q�j�ɂ��Ă͑O���C����́u���{�I�o�c�v�_�i�R�j�ō̂肠�����B
2.2�@���{��Ƃ̎������B�̕ϑJ
��Ƃ̎������B�Ƃ������ꍇ�C�܂��͎��Ȏ��{�䗦��_���邱�ƂɂȂ�B���Ȏ��{�䗦�́C�Ǝ�ɂ���đ傫���قȂ�B������ƒ��u����30�N������Ǝ��Ԋ�{�����v�ɂ��Ǝ�ʂ̍�����Ƃ̕��ςɂ��C���̒ʂ�ł���B
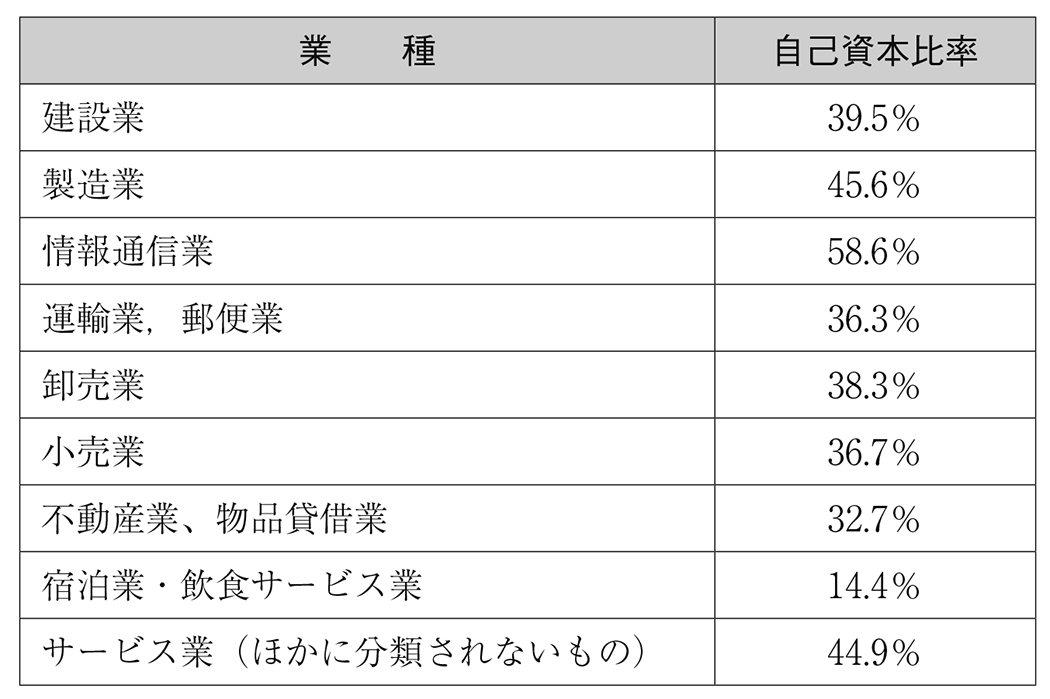
�܂��C���������������ɂ��u�@�l��Ɠ��v��������݂���{��Ƃ̓����v�͎��̒ʂ�ł���
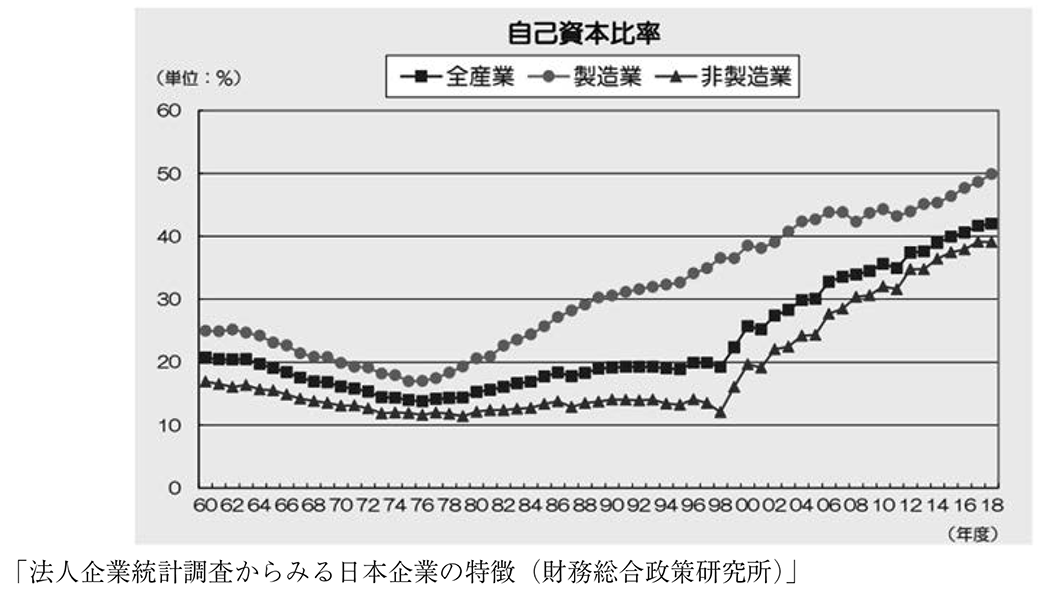 �y16�Łz
�y16�Łz
�M�҂̈�l�́C1970�N��ɉ䂪���̑��Ƃ̎��{�\���ɂ��ăf�[�^�����ăt�H���[�������C���a40�N��̔������S�̎��Ȏ��{�䗦�̂W���i�I�j�Ƃ������l�����āC���ɋ������L�����Y����Ȃ��B������̃f�[�^�����Č��͂ł����C���̐��������ؖ����邱�Ƃ͓�����C�����̂��̏�Ԃ̐����Ƃ��āC�䂪���̎��{�s��i���Ȏ��{�C���l���{���Ɂj�̖����B�C�����n�ƁC���Ƃ��āC���ꂩ��n�܂鍂�x�������ɂ�����C�������������Ƃ��ċ��͂ɐ��i���Ă����ɂ������āC���Ƃ��Ί���ɂ��o�c����ւ̉e���ɂ���āi���ɓ����C������u���{���R���v���n�܂����������������Ƃ�����j�C���Ӑ}�ʂ�ɐi�߂��Ȃ��Ȃ�\���Ɋӂ݁C���l���{�C���ɊԐڋ��Z��i�߂邱�Ƃ��Ӑ}���Ă����̂ł͂Ȃ����C�Ƃ������ɔ[�����Ă����L��������B�o�ϐ���Ƃ��Ă̋�s�ւ̎w���́C����Ƃ��Ă������I�ɍs����̂łȂ����C�e���͂��s�g���₷���̂ł͂Ȃ����C�Ƃ����咣�ŁC�ꉞ�̐����͂͂���Ǝv�������̂ł������B
���̃O���t������Ɠ��{��Ƃ̎��Ȏ��{�䗦��1974�N�����Œ�ɁC���₩�ɏオ���Ă���悤�Ɍ�����B���݂܂ł̕ϑJ�ɂ��ẮC�����悻���̂悤�ɂ܂Ƃ߂���ł��낤7�j�B
���{��Ƃ̎��Ȏ��{�䗦�͍��x�������ɂ�20����30���قǂŁC�����̃A�����J�̊�ƂȂǂɔ�ׂ�Ɛ�������肵�Ă����B�悭�������Ă������R�́C���C���E�o���N���������āC�����Ƃ������͋�s���ʓ|�����Ă���邩��Ƃ��C�n�����l�オ�肵�Ċ܂ݎ��Y���傫������Ƃ���������Ă����B�����������s���ɂȂ��āC�n���͉�������C��s�݂͑�������������C�ȂǂƂ������ɂȂ��āC������Ǝ��O�̎�����p�ӂ��Ȃ��ƌo�c����Ȃ��ƌ�����悤�ɂȂ����̂ł���B
�����ĕ����s���ɂȂ��Ă���C�s���̒��ł���Ƃ͓w�͂��C���Ȏ��{��ςݑ�������C�^�p�����Y�����k�����肵�āC���Ȏ��{�䗦�����߂Ă����B2013�N�ɂȂ��ē���َ̈������Z�ɘa����ʼn~���[�g�����퉻���C�����s������悤�₭�E�o�C�����Ƃ̗A�o�֘A��Ƃł͉~�����v�Ȃǂ������āC���Ȏ��{�䗦�͂���ɏ㏸���Ă����̂ł���B
������O���t�Ō���Ɖ��̂悤�ɂȂ�
�ԁF���{��10���~�ȏ�E���ƁC���F�P�`10���~�E������ƁC���F�P�疜�`�P���~�E������ƁC�F�P�疜�~�����E���ƂƂȂ�ł��낤�i�S�K�͕��ς͍��j�B
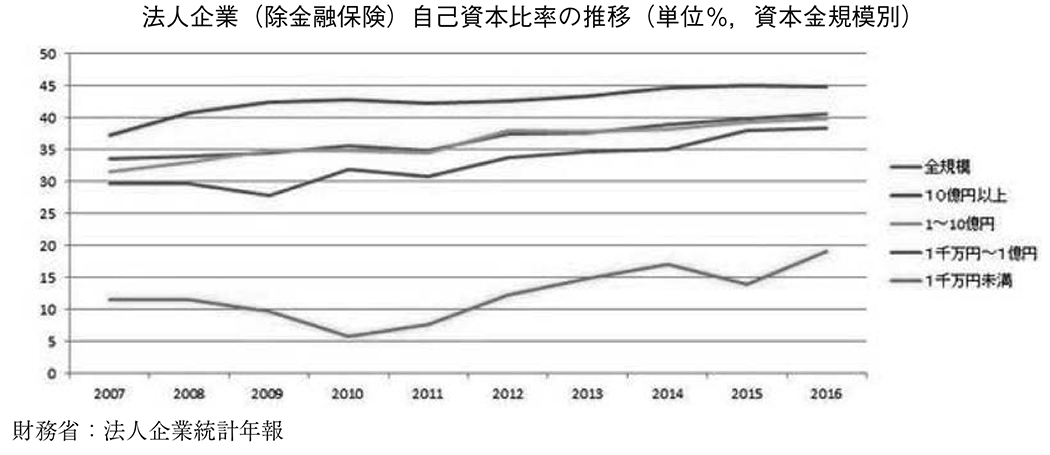 �y17�Łz
�y17�Łz
������ƂƑS�K�͕��ς͂قƂ�Ǐd�Ȃ��Ă��邪�C���Ƃ͂��낻��50���ɒB����Ƃ���܂ŗ��Ă���̂��킩��B2008�N����2010�N�ɂ����āC���[�}���V���b�N������C���Z�@�ւ��͂��߁C���{��Ƃ���Ō��������C���ƁC������Ƃ͎��Ȏ��{�䗦�����コ���Ă���B���ɑ��Ƃł͌����ŁC����͎��v���グ�Ď��Ȏ��{��ςݑ������Ƃ������C���X�g���ŁC���^�p���{�����炵�C��������������Ď��Ȏ��{�䗦�����߂��Ƃ����������傫���̂ł��낤�B
������ɂ��Ă����{��Ƃ̎��Ȏ��{�䗦�͌���C��Ƃ̍����ʂł̈��萫�͂���10�N�Ō��Ă������ɍ��܂��Ă���B
2012�`2014�N�̉~���ǖʂł͍X�Ȃ钅���ȉ��P��ςݏd�˂ė��Ă���悤�ŁC�����Ƃ̉��P�����Ɍ����Ƃ����B
����ɓ��e�ł́C�ŋ߂͍����o�ς̐L�єY�݂���C�]�T�����͊C�O�����C�C�O��Ɣ����ȂǂɌ������P�[�X�������悤���C�Əq�ׁC���Ȏ��{�䗦�̌���Ɍ���悤�ɁC����������Ƒ̎��̐������C�V���ȃt�����e�B�A���L���邱�Ƃ͊m�����C�Ƃ��Ă���B�����āC��Ƃ����̎��Ȏ��{�䗦�̌�����C�ǂꂾ���I�݂Ɋ��p�ł��邩������̓��{�o�ς̍s�����S���Ă���Ƃ�������̂ł͂Ȃ����C�ƌ���ł���B
�������C1964�N�i���a39�N�j�̓����I�����s�b�N��̎����C���a40�N��ɂ��Ă͂��ᔻ�I�Ȍ������L�͂Ǝv����B���̑�\�I�Ȃ��̂����̎咣�ł���8�j�B
�܂��C�o�ϔ����ɂ����ꂽ��Ƃ̎��{�\�������̌����Ƃ��āC����͎��̂悤�ɏq�ׂ�B
���a40�N�x�̔N���o�ϕ��o�ϔ������́C�u���萬���̉ۑ�v�Ƒ肵�āC�����ʂ�C���x����������萬���ւ̓]���Ƃ��̏������ɂ��ĕ��͂��Ă���B�����́C���a30�N��͌o�ϐ����̎���ł��������C40�N��̌o�ς����ʂ���d�v�ȉۑ�́C�����ƈ���Ƃ��ǂ̂悤�ɂ��ė��������Ă䂭���Ƃ������Ƃł���Ƃ��āC���낢��Ȋp�x������萬���̓����������Ă���B���̒��ŁC�Ƃ��Ɋ�ƌo�c�ɂ��āC�o�ς̑��̓I�Ȑ����̔��ʁC�������̒ቺ�⎑�{�\���̈����� �ڗ����C�������ĕs���萫�����܂����_���݂Ƃ߁C���̌������������Ă���B�������̒ቺ�͂��Ă����C�킪���̊�Ƃ��ǂ̂悤�Ȑ��ڂ��ւĎ��{�\�����������������C�����ɂ��������悤�B�܂����{�̎�v��Ƃɂ��Ă݂�ƁC��O�i���a�X�\11�N�j�͑����{�̂U���ȏ�͎��Ȏ��{�ł������B���������Ȏ��{�䗦�́C���a30�N�ɂ�40���ɉ�����C39�N����ɂ�30���������悤�ɂȂ����B�܂��C�A�����J�C�C�M���X�ɂ���ׂĂ��C���l���{�ւ̈ˑ��x�����������ɁC���l���{�̒��ł����|����Z���̎ؓ����ȂǗ������̊������傫���C���萫���R�����B���̂悤�ɁC���݂̓��{�̊�Ƃ́C��O�Ƃ���ׂĂ��C�܂����ď����Ƃ���ׂĂ��C���l���{�ւ̈ˑ����傫���B�������w�E���鎩�Ȏ��{�䗦�ቺ�̌����́C��P�ɁC�푈���̏������̂܂����z����Ă��邱�Ƃł���B�푈���C�R���Y�Ƃł͐��{�������s�݂̑��o���ɂ���Đ��Y���s�Ȃ�ꂽ�̂ŁC�I�펞�ɂ͎��Ȏ��{�䗦��30���ȉ��ɂȂ��Ă������ƁB�܂��푈�̔�Q��s��ɂ��C�O���Y�̕����Ȃǂ����{�\���������������Ƃ���B���̂��Ƃ́C�A�����J��C�M���X�ɂ���ׂ�Ɛ��h�C�c�̎��{�\�����C���{�Ɠ������������Ƃɂ���Ă����@�����B��Q�́C��Ƃ̓����̑������ɂ߂đ����������Ƃł���B�Z�p�v�V�̃e���|�������C�܂��S�ʓI�Ɏ��{�s���̏�Ԃɂ������̂ŁC�V�����ɂ���ė������l������`�����X���傫���� �y18�Łz ������C�����͌Œ�I�ŗ��q���͊��җ�������������Ă�������C��Ƃ͗��q���ċ�s����؋����ӂ₵�Ă��[�������������B�����Ŋ�Ƃ͎��Ȓ~�ς��z���ē������g�債�悤�Ƃ����B���Ƃ��C��Ƃ̑������ɑ��鑍���~�̕s�����́C34�N�`36�N�x�̂R�͔N���ς�46���C37�N�`38�N�x���ς�36���ɒB�����B��R�́C���I�ȓ����������łȂ��C������̑����Ⓤ�Z������ȂǁC���Z���Y���邢�͌o�c�O���Y�������������Ƃł���B��S�́C���{�s��̔��B�������ꂽ���Ƃł���B���̂킪���ł́C�������{�s��C�Ƃ�킯�������s�s���V�K�N�s��̔��B���C�����o�ς̋K�͂���݂Ă�����Ă������߂ɁC���������r�ɂ�鎑���̋����͏��Ȃ��C�����������ԂȂ�тɐ��{���Z�@�ւ݂̑��o���ɗ��炴��Ȃ������B��T�ɁC��ƂɂƂ��Ďؓ���̕������������L���ł������Ƃ����������B���Ƃ��C�����z���ɂ͉ېł���邪�C�ؓ����q�͔�p�Ƃ��Đŋ���������Ȃ�����C��Ƃ͎؋������Ď����B�������������������������R�X�g���Ⴍ�Ă��ށB�����͑O�L�T�̌����ɂ���Ƃ̎��{�\���͈��������Ƃ��Ď��̔@���ׂ̂Ă���B
�u��Ƃ̎��Ȏ��{�䗦�̒ቺ�ɂ́C���̂悤�ɂ��낢��Ȍ���������B���� ���ቺ��������Ƃ����āC�����ɐ����̂䂫�������Ƃ��邱�Ƃ͐������Ȃ��B���Ƃ��Ɗ�Ƃ����������ɕK�v�Ȏ�����S�����Ȓ~�ςł܂��Ȃ����Ƃ͕s�\�Ȃ��Ƃł���B�e����Ƃ̎������B���@������ׂĂ݂�ƁC�����������Ƃ������{�Ɛ��h�C�c�́C�A�����J��C�M���X�ɂ���ׂāC�ؓ��ˑ��x���͂邩�ɑ傫���B�܂���Ƃ̎��Ȏ��{�䗦���ቺ���Ă��C�����Ɍo�c�̌��S�������Ȃ�ꂽ�Ƃ݂邱�Ƃ����v�ł���B�v
����ɔ����͂��Ƃ𑱂��āC
�u��Ƃ̎��{�\������O�≢�ď����ɂ���ׂĈ�������Ƃ����āC������Ɋ�Ƃ̕����Ȍo�c�ɂ����̂��Ƃ��邱�Ƃ͂�����Ȃ��B����́C�}���Ȍo �ς̕����Ɛ������������邽�߂ɁC�ݔ����{���g�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������̓I�ȕK�v���C���l���{�ˑ���L���Ƃ���悤�ȍ������Z���x�C��Ƃ��s �̍s���l���Ȃǂ��낢��Ȍ������W���ċN�������̂ł���B����C�ݔ������̐� �������ꎞ���łȂ��Ȃ�C����͎��{�\�������P����P�̏����ɂ͂Ȃ�ƍl �����邪�C�ؓ��ˑ��x�̑���ɂ́C�O�q�̂悤�ɁC���̂ق������̌���������C�����̊g��e���|���������Ŏ��R�Ɏ��{�\�����悭�Ȃ�킯�ł͂Ȃ��v �Ƃׁ̂C�u���{�\�����P�̏����Ƃ��āC��Ƃ��s�����T�d�ɍs�����邱�Ƃ���Ȃ��Ƃ͂������ł��邪�C����ƕ���Ŋ�Ƃɑ��Ē����̈��肵���� �{����������̐������肠���邱�Ƃ��d�v�ł���B���̂��߂ɂ́C�،����s �`�Ԃ̑��l���C�����̎��R���C�Ő��̉��v�ȂǁC�Ђ낭�����C���Z�����S�ʂɌ������ׂ��_�������v�ƌ���ł���B
�ȏオ�����̎����킪����Ƃ̎��{�\�������̌����ƍ���̓W�]�ł��邪�C�����ɂ͎��Ȏ��{�䗦�̒ቺ�������Ɋ�ƌo�c�̕s����������炵�C�����̕s���̑傫�Ȍ����ƂȂ��Ă��邩�C�܂��i�C�����g���Ȃ������⎑�{�\���̒������ቺ�ɑ��锽�ȂƁC���������������̓I�Ȓ�Ă����ЂƂ������킹�Ă��Ȃ����Ƃ͂܂��ƂɈ⊶�ł���B�Ƃ��ɁC�u���Ȏ��{�䗦���ቺ��������Ƃ����āC�����ɐ����̍s���߂����Ƃ��邱�Ƃ͐������Ȃ��v�Ƃׂ̂�Ɏ����ẮC���̌������܂��ƂɊÂ��Ǝv���B�����Ƃ����ƁC�����������Ƃɑ��锽�ȂƑ� �K�v�ł͂Ȃ����낤���B���{�\�������������������́C���{���Ő��̉��v ���s�Ȃ킸���āC���R�����̂܂܂ɖ@�l�Ŏ������ߓ��Ɏ��グ�����ʂł���C���ʂ����������x�����������߂邽�߂ɂ́C���炩���ߐ��Ƃ�A�����J�����Ƃ����悤�Ȏ��ȋ��Z�̓��i�������p��̊g��Ȃ�тɎГ����ۂ̊g��j���� �u���ׂ��ł������Ƃ������Ȃ̂Ȃ����Ƃ͎c�O�ł���B
�y19�Łz�ȏオ����̈ӌ��ł��邪�C�����50�N�ȏ�O�̘_�e�Ƃ��Ĕ��ɋM�d�Ȉӌ��ł��낤�B�������̃t�@�C�i���X�̗��_�Ƃ����ϓ_�C�����Ă��̂��Ƃ̉䂪���̊�Ƃ̃t�@�C�i���X�̗��j���l����ƁC�܂��Ɂu�o���_�̍l�@�v�Ƃ������ƂɂȂ�B�Ƃ�킯�u���Ȏ��{�䗦�̒ቺ�������Ɋ�ƌo�c�̕s����������炵�C�����̕s���̑傫�Ȍ����ƂȂ��Ă��邩�C�܂��i�C�����g���Ȃ������⎑�{�\���̒������ቺ�ɑ��锽�ȂƁC���������������̓I�Ȓ�Ă����ЂƂ������킹�Ă��Ȃ����Ƃ͂܂��ƂɈ⊶�ł���B�Ƃ��ɁC�u���Ȏ��{�䗦���ቺ��������Ƃ����āC�����ɐ����̍s���߂����Ƃ��邱�Ƃ͐������Ȃ��v�Ƃׂ̂�Ɏ����ẮC���̌������܂��ƂɊÂ��Ǝv���B�v�Ƃ��������́C�A�����J���́u���ȏ��I�咣�v���̂܂܂ŁC���̌�̓��{��Ƃ����Ȏ��{�䗦�̒ቺ�ɂ���Ċ�ƌo�c�̕s����Ɍ������C���ꂪ�s���̑傫�Ȍ����ƂȂ�����C�i�C�����g���Ȃ������⎑�{�\���̒������ቺ�ɑ��锽�Ȃ�v���ꂽ��͂��Ȃ��������Ƃ��C����̎������͒m���Ă���B�����Ƃ̎��Ȏ��{�䗦�͂܂��Ƀr�W�l�X�ɂ�����C��{�I�ɕK�v���{�̎��v�Ƌ����ɂ��ύt�I�Ȓl�ł���C���x�������C���̌�̃o�u�����C�����Ă��̃o�u���j���̉ߓn���ƁC�������v�̎��Ԃɍ��킹�Đi��ł��Ă���̂ł���C���ꂪ�������Ⴂ���͂܂��ɂ��̂Ƃ��ǂ��̎�������Ȃ���_���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��킯�ŁC�����Ă��܂��Ύ��Ȏ��{�䗦�ƕs���E�i�C�͊�{�I�ɂ͊W�͂Ȃ��C�Ƃ����̂��C����̎������̒m���ł���B
���Ȃ킿�C�����Ɋւ��āu���{�I�v�Ȃ̂͂ǂ����C�����I�Ƃ������Ƃ��Ɓu���{�I�v�ƌĂׂ�����͔���Ă�������C�Ƃ������ƂɂȂ�B�������C���Ȏ��{�䗦�͏オ���Ă���B���̗��R�́H�ƌ����C�u�������s�����v�̋����́C���̈���ł��邱�Ƃ͊m���ł��낤�B����������́C���x���ς��������ł���B���ꂪ�������s�����ł���9�j�B
�킪���́C1968�N�Ɏ������s���x���A�����J���瓱�������B���̎������s���x���������ꂽ�̂́C��Ƃ̎��Ȏ��{�����₭�[�����č��ۋ����͂��������邽�߂ł������Ƃ����B�����C�킪���̊O�ݏ�������30���h���O��ƒᐅ���ɂ���C�A�o�ŊO�݂��҂����Ƃ��傫�ȉۑ�ƂȂ��Ă����Ƃ��āC���ׂ̈ɂ͊�Ƃ̍��ۋ����͂���������K�v������C��Ƃ̍����͂̋������K�v�ł������Ƃ����B���Ȏ��{�䗦�́C��Ƃ̍����͂�������̎w�W�ł��邪�C�킪���̊�Ƃ͂��̓_�Ŕ��ɗ���Ă����Ƃ����B1960�N�㏉���ɂ����鎩�Ȏ��{�䗦�́C�킪����20�`30���ł������̂ɑ��C�A�����J��60�`70���ƁC�i�i�̍����������B�����ŁC�،��ƊE�̒�ĂɊ�Â��Č������ꂽ�̂��C�������s���x�̓����ł�����10�j�B1980�N��C�����̏㏸���玞�����s�������}�������B�������C�o�u���j����1990�N�C�����̌����Ƃ��đ呠�ȁi�����j�ɂ���āC��ʂ̏���Ƃ̎������s�����͋K������C�V�K���J���ȂǂɌ���ꂽ�B���̌�C�K���ɘa����C1996�N�ɋK���͓P�p���ꂽ�B�����2001�N�̏��@�����Ŋz�ʊ������p�~���ꂽ���߁C���݂́C������C�������s���������ɂȂ�C������z�ʔ��s�����C���Ԕ��s�����͂Ȃ��Ȃ��Ă���B
�������s������1986�N�ɊJ�n����Ĉȍ~�C1990�N�ɕ����o�u�����j��܂ŁC��Ƃ̎������B��i�Ƃ��đ傢�Ɋ��p���ꂽ�B�����1986�N�ɑ�|����ɊJ�n����Ĉȍ~�C1990�N�ɕ����o�u�����j��܂ŁC��Ƃ̎������B��i�Ƃ��đ傢�ɗp����ꂽ�̂ł���B
�y20�Łz�������Ɏ������s�����́C���s��Ђ́u��y�ȁv���{�[���ɂ͌��ʓI�ŁC�����̊�Ƃ����؋���ЂɂȂ����Ƃ���邪�C���̂Ƃ��̎������s�����́C����E�����ƂɂƂ��Ă͐V�������z�ʂŊ��蓖�Ă��錠����D���ق��C�^�p�̂�������ł͕��Q�������炷���Ƃ̂���u�Ȏҁv�ł���C�Ƃ����ӌ����������̂ł���B
�܂��C1980�`90�N��ɁC�킪���̊����s��́u�R���s��v�ƌĂ�Ă����B����́C����Ƃ̊����s�����̂V�����@�֓����Ƃ�@�l�ɕۗL����Ă��āC�s��Ŏ������Ă���̂͂R���ɉ߂��Ȃ����Ƃ��Ӗ�����11�j�B��ʂ̖@�l�����X�N�̑傫���������ʂɕۗL����͈̂ٗ�̂��Ƃł��邪�C���̎����ɑ�ʂ̊����������s�Ȃ�ꂽ�w�i�ɂ͂��̂悤�Ȏ���������̂ł���B
�@�l�Ԃ̊����̎�����������K�͂ɍs��ꂽ���Ƃ͎��̂悤�Ȏ����ɕ\��Ă���B�܂��C�@�l�ۗ̕L�䗦���C�������s���x�̓��������1970�N�x��55.5������90�N�x��73.1���ւƋ}�����C���̂����C�����������o��Ɩ��Ƃ��鐶���ی���Ђ������������́C15.6���i45.5����61.1���j�Ƃ����ُ�ɑ傫�����̂ł������B���ɁC�S�̂̎������z���}�����钆�ɂ����āC�@�l�ۗ̕L�䗦���ُ�ɑ傫�������������Ƃł���B��O���o�u�����i1986�`90�N�j������246���X�牭�~���������C1989�N�x���̎c����446���ł������B�Ō�ɁC�����o�u�����ɂ�����@�l�ɂ�銔���̔����z���z���ُ�ɑ傫���������Ƃ���������B1986�`89�N�̂S�N�ԂɁC���Z�@�ւƎ��Ɩ@�l�̍��v��24���~�̔����z���ƂȂ�C�������ԂɎ������s�Œ��B���ꂽ�����ʂ�62���~�ł������̂ŁC��40�������������Ɍ�����ꂽ���ƂɂȂ�B
���̂悤�ȁC�@�l�ɂ�銔���ۗL���̑���́C�����s��̎����W��N�������C�����H��ɂ���Ď������㏸������̂�e�Ղɂ����Ƃ����B�܂��C���̌�̕����o�u���̔j��Ŋ����s�ꂪ���C�@�l�i���ɋ��Z�@�ցj�����z�̑������������Ƃ͂悭�m���Ă��邱�Ƃł���B�����āC���Y���e�̌��S���̂��߂ɕۗL�����̕��o��]�V�Ȃ�����C���ꂪ�傫�Ȋ��������v���ƂȂ�C�����o�u���j��20�N�ȏオ�o�������݂ł������s�����̗v���ƂȂ��Ă���Ƃ����̂ł���B
���{��Ɠ��L�̍����I�ӎv����Ƃ����ƁC�����łǂ����Ă��G��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂́u�������ۂ̒��ߍ��݁i�����I���_�j�v�ł��낤�B
�������ۂƂ́u���v��]���v�̂��ƂŁC�������ۂ͊�Ƃ���鑤�ʂ�����Ƃ���邱�Ƃ�����ɏd�v�Ȏw�W�ɂȂ�B�������ۂƂ��Čv�コ��闘�v��]���́C�{�Ƃ������ł���C�N�X����������͂��ŁC�o�c�̎����̂��̂��ǂ���Ԃ̊�Ƃ��Ƃ����邾�낤�B���̗��v��]���i�������ہj�́C�{���͌����̂܂��̂ł͂Ȃ��C��Ђ̐����̂��߂ɍH��ݔ���X�܂Ȃǂɓ����������̂ł���B���v��]����������C��@�̎��Ɋ�Ƃ����C�����Đ����̂��߂ɍs�������Ɍ�������̂��X�W�ł���B���̓������ۂ����{��Ƃ͂Ƃ�킯�����Ƃ����咣������B�������C�����i2021�j�ɂ��ƁC��v���Ɣ�r����ƁC���{��Ƃ̓������ۂ͓��ɑ����킯�ł͂Ȃ��Ƃ����B����ɂ��Γ��{��Ƃ̐l����䗦�i�ٗp�ҕ�V�̕t�����l�ɑ��銄���j�́C2008�N�x�ɕč��͏㏸���Ă��Ȃ��̂ɁC���{�ł͑啝�ɏ㏸���Ă���Ƃ����B���̗��R�́C���v�����ɉ����Čٗp���팸�����č���Ƃɑ��C���{��Ƃ͗��v�������قǂɂ͌ٗp���팸�����C���ΓI�Ɍٗp����������߂Ƃ��Ă���B�܂��C������J�����z���Ō��Ă��C �y21�Łz ���{�ł͑��̐�i�����ɔ�ׂč������ڂ������Ă��āC���{��Ƃ͐��ݏo�������v�𑼂̐�i������Ƃ��������ٗp�҂ɊҌ����Ă���Ƃ���B���Ƀ��[�}���V���b�N��́C���{�͑��������J�����z���̏㏸����ԑ傫���Ƃ���āC�J�����z���̐��ڂ���͓��{��Ƃ͑��̐�i����Ƃ������ΓI�Ɍٗp���ێ�������������Ă���Ƃ����B���̂��Ƃ���C��Ƃ̗��v�̌ٗp�����ւ̊Ҍ����w�W�Ō���C���{��Ƃ����v�����ߍ��݂����Ă���Ƃ͎v���Ȃ��C�Ƃ����B�����ł͂ނ���C��Ƃ���芪���������������C���{��Ƃł͏]�ƈ��d���̌o�c�������Ă���ƌ��_���Ă���B�悭�����邱�Ƃ́C���{��Ƃ̌o�c����͒����I���_�ɂ����̂ŁC�܂��Ɂu��Ђ̂��߁v�C���Ȃ킿����w���C���ꂪ�]�ƈ��̂��߁C�Ƃ������ƂȂ̂��C�Ƃ������Ƃł���B�������C����ł̓��{��Ƃ̒��グ�̎���C���{�̖ڎw���ƌv�x�o�̑����C�i�C�̕��g�ɏ\���Ȃ��̂ł��邩�C���Ƃ��Ηǂ��R�[�|���[�g�K�o�i���X�E�V�X�e���̗v���ł���C��Ƃ̗��v�����̎����ɍv�������X�e�[�N�z���_�[�Ɂu�t�F�A�Ɂv�z��������̂ƂȂ��Ă��邩�C�Ƃ�����������C�m�肳�����̂ɂȂ��Ă��邩�́C�܂��ʂ̌����ۑ�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����B
�Q�l����
�؏��F�E�������F�Ғ��i2002�j�C�w���W���[�������V�����Y�ƃA�[�L�e�N�`���̖{���x�C���m�o�ϐV���
�ɒO�h�V�i2020�j�C�w���{��Ƃ̕����́x�C���Y�t�H
���R�͉h�i2019�j�C�w���E�W���̌o�c���_�x�C�_�C�������h��
����L���i1980�j�C�w�،��E���{�̌o�c���ߑ㉻�͂��̂悤�ɍs��ꂽ���x�C�}�l�W�����g��
Doda�C�wVol.10 ��Џ��iIR�E�����j�̓ǂݕ�����u���x
���R���G�i2019�j�C�w�o�c�����_�m�V����T�Łn���s�m�����C�G�[�W�F���V�[�E�R�X�g����ѓ��{�I�o�c���x�C�n����
���������������i2019�j�C�w�@�l��Ɠ��v��������݂���{��Ƃ̓����x
���{�����E����j�F�i2020�j�C�uDX�̉ߋ��C���݁C�����v�i�w�ꋴ�r�W�l�X�������[�x2020�CAUT. , 6-18�j
������ƒ��i2018�j�C����30�N������Ǝ��Ԋ�{����
tnlabo�fs blog�i2018�j�C�w���{��Ƃ̎��Ȏ��{�䗦�̐��ڂ�����x�C2018�N�W��10��
��ˌ��o�E���R���G�i2021a�j�C�u����́u���{�I�o�c�v�_�i�P�j�v�i�w�K�@��w�w�o�Ϙ_�W�x58�C2�Cpp.175-186�j
��ˌ��o�E���R���G�i2021b�j�C�u����́u���{�I�o�c�v�_�i�Q�j�v�i�w�K�@��w�w�o�Ϙ_�W�x58�C3�Cpp.227-252�j
�������u�i2021�j�C�w���{��Ƃ͗��v�����ߍ��݂����Ă���̂��x�C�݂��ّ���������
��������i1996�j�C�u�I�t�B�X���̕ω����g�c���x�Ɋւ����l�@�v�i�É�������w�Z����w���w�����I�v�x10�Cpp.107-118�j
����È�Y�i1965�j�C�w��Ƃ̎��{�\���̈����Ƃ��̑�:���Ō����s�̒x�C���w�����C��16����Q��1965-12-20�Cpp.51-71
���㊲�i2006�j�C�u1990�N��̌o�c�헪�_�v�i�ɒO�h�V�E���{���G�E����N��E�ɓ��G�j�E���㊲�ҁi2006�j�C�w���{�̊�ƃV�X�e����U���@��R���@�헪�ƃC�m�x�[�V�����x�C�L��t�Cpp.1-17�j
���_�O�i2011�j�C�w�������s�����Ƃ����Ȏҁi�P�C�Q�j�x�C���OB�y���N���u�@2011.10
�_���j��Y�i2021�j�C�w�W���u�^�ٗp�Љ�Ƃ͉��������Ј��̐��̖����Ɠ]�@�x�C��g���X
�ꋴ��w�C�m�x�[�V���������Z���^�[�ҁi2017�j�C�w�C�m�x�[�V�����E�}�l�W�����g�����Q�Łx�C���{�y22�Łz�o�ϐV����
���{���T�E�^�琽�i�i2017�j�C�w�I�[�v�����헪�F���E���z����C�m�x�[�V�����x�C�L��t
�R��́E���R���p�E�����O�i1979�j�C�w���{�I�o�c�̍\�z�x�C�r�W�l�X����o�Ŏ�
�đq����Y�E�����m�i2015�j�C�w�I�[�v���E�C�m�x�[�V�����̃}�l�W�����g�x�C�L��t
��ђ����i2017�j�C�w��Ɗԃl�b�g���[�N�̃}�l�W�����g�x�i���{���T�E�^�琽�i�i2017�j�w�I�[�v�����헪�F���E���z����C�m�x�[�V�����x�L��t�C��V�́Cpp.153-168�j
Chesbrough, Henry�i2003�j�COpen Innovation, Harvard Business School Press�i��O�b��N��wOPEN�@INNOVATION�x�i2004�j�Y�Ɣ\����w�o�ŕ��j
Chesbrough, Henry�i2006�j�COpen Business Models, Harvard Business School Press�i �`�F�X�u���E�C�w�����[�i2007�j�w�I�[�v���r�W�l�X���f���x�i�I�����E�z�K���F��j�ĉj�Ёj
Iansiti, Macro, and Levin, Roy�i2004�j�CThe Keystone Advantage, Harvard Business School Press�i�C�A���V�e�B�C�}���R�E���r�[���C���C�i2007�j�w�L�[�X�g�[���헪�x�i���{�K���Y��j�ĉj�Ёj
Nonaka, I. and Takeuchi H. �i1995�j�CThe Knowledge-Creating Company: How Japanese companies create the dynamics of Innovation, New York: Oxford University Press�i�~�{������i1996�j�w�m���n����Ɓx���m�o�ϐV��Ёj