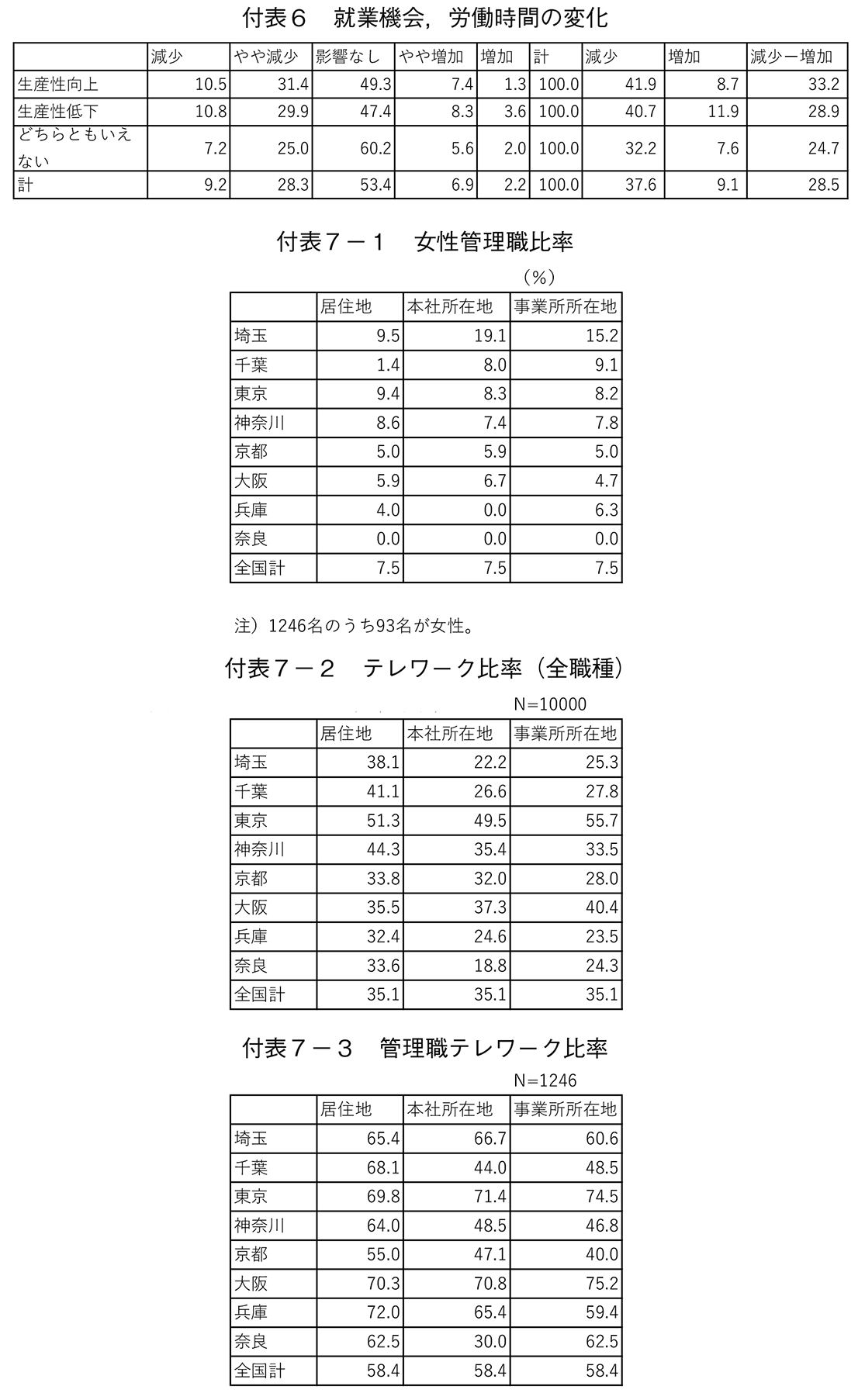�y161�Łz
�Ǘ��E�̃e�����[�N�́C���܂��@�\����̂�
�e��@��
1.�@���ݒ�
�e�����[�N�́C�]�ƈ��ɂƂ��Ă͖]�܂����Ǝv���邪�C���̌ł���i���o�ЋΖ��ɂ��Ǘ����D�ނ̂ŁC�Ȃ��Ȃ��e�����[�N�����y���Ȃ��Ƃ�����B
�Ƃ��낪�C�e�����[�N�Ɋւ���ǂ̒������݂Ă��C�E��ʂɂ݂�ƁC�����Ƃ��e�����[�N���p�����̑����̂́C�Ǘ��E�ł������i�e�� 2022�j�B
�����ނ˂T���ȏ�̊Ǘ��E�ɗ��p�o��������C���Z�p�E���������E���������B2022�N�P���̓��{���Y���{���iJPC�j�����ł́C�Ǘ��E�e�����[�N���������̂����C�E��ʃe�����[�N���{���́C�Ǘ��E38.1���C���Z�p�E34.2���C�����E18.8���ł���i���̏ꍇ�͍ݑ�Ζ������łȂ��C�T�e���C�g�I�t�B�X�Ζ��C���o�C���Ζ����܂ށC��������҂Q�͏��Ȃ��j�B�{�e�ɂ�����g�p�f�[�^�̒������_�ł���C2020�N10����JPC�����ł́C�Ǘ��E41.5���C���Z�p�E22.8���C�����E24.9���ł������B
���ꂾ���e�����[�N�Ǘ��E�������̂ł���C�Ǘ��E���_��łȂ��C�Ƃ��e�����[�N�̂��Ƃł̃}�l�W�����g�\�͂Ɍ�����C���Ƃ�_���̂łȂ��C�e�����[�N�ɂ�������ł���Ǘ��E�ɏœ_�����āC���̏����܂������Ă��邩�ǂ����������ق������Y�I�ł���B
�Ǘ��E�̃e�����[�N��T��Ӌ`�́C���ꂾ���ɂƂǂ܂�Ȃ��B�Γc���j����ɂ�钚�J�ȍ��۔�r�̌����ɂ��C�䂪���̊�Ɠ��ɂ�����ӎv����̓����́C�o�c�w���烏�[�J�[�ɂ�����܂ŁCPDCA���ѓO���Ă��邱�Ƃɂ���B�i���j�Ċ�Ƃł́CPDCA���͂��炢�Ă���̂͌o�c�w�݂̂ł���i�Γc 2022�j�B���̊K�w�I�g�D�ɂ�����PDCA�́u���{���f���v�Ń|�C���g�ƂȂ�̂́C�o�c�w�ƈ�ʎЈ����Ȃ��Ǘ��E�ɂ�����PDCA�����܂��܂���Ă��邩�ǂ����ł��낤�B���Ẵg���^�ɂ����錻���`�̊Ǘ��E ���ψ�̖��O�Ɠ`����������Ύ������ł��낤�B
���̗���Łu�V�����d���l���v�Ƃ�����e�����[�N���l����C�e�����[�N�Ǘ��E����e�����[�N�Ǘ��E�C�܂�]���̊Ǘ��E�ɔ�ׂāC�Œ����PDCA���܂킹�Ă��邩�ǂ������C����̑g�D�̕ϖe������Ȃ������ƂȂ낤�B
�{�e�ŗp����f�[�^�ɂ́C�\�͊J���Ɋւ��鑽���̐ݖ₪����B���[�J�[�w�ɂ����鑽�\�H��J�C�[���������Ƃ肠���Ȃ��Ƃ��C�z���C�g�J���[���܂߂�PDCA���@�\����ɂ́C�\�͊J����w��ɂ������E��̐l���Ǘ����K�ɍs���Ă��邩�ǂ������d�v�ł��낤�B�e�����[�N�ɂ�萶�Y�����㏸�����Ǘ��E�����Ȃ��炸�݂��C���̏����Q�l�ɂȂ�B����C�E����БS�̂Ƃ��ăe�����[�N�����y�E�蒅���邩�ǂ����́C�Γc�̂���PDCA���C�e�����[�N���s���Ă��C�o�c�w�����łȂ��C�Ǘ��E�w�����Ĉ�ʎЈ��ɂ����Ă��C��邩�ǂ����ɂ������Ă���B
�y162�Łz
�{�e�̃f�[�^�́C���̑傫�ȃe�[�}�̑S�e�ɒ��ڔ������̂ł͂Ȃ����C���Ȃ��Ƃ��c�_�̎�������Ă����Ǝv���Ă���B
�Q�D�g�p�f�[�^
�J�������E���C�@�\�iJILPT�j���s�������L��2020�N�����ɁC�Ǘ��E�̃T���v������1246�����蕪�͂ɒl����B�ǂ̂悤�ȊǗ��E���e�����[�N�������Ȃ��Ă��邩�C���ꂪ���܂������Ă��邩�ǂ�����T��B
�J�������E���C�@�\�u�l�ވ琬�Ɣ\�͊J���̌���Ɖۑ�Ɋւ��钲���i�J���Ғ����j�v2020�N9-10������
���Ԓ�����Ђ��ۗL����o�^���j�^�[10000�l
2016�N�o�σZ���T�X���������Ɋ�Â��C�ΏۋƎ�ʁC��ƋK�͕ʂ̏�p�J���Ґ��̍\�����10000�l�ɂ��Ă͂߁C���ׂẴZ���̉���������܂ʼn�����p�������B
�]�ƈ��T�l�ȏ�̉�Ђɂ�����18-65�̐��Ј�����ђ��ڌٗp�̔Ј��i�_��Ј��C�����C�p�[�g�^�C�}�[�E�A���o�C�g�j
�i���́C�����V���[�Y No.217 2021�N11���B�����̏ڍׂ͕��Q�Łj
�Ǘ��E1246���̂����C727���i58.3���j�ɂ����āC�e�����[�N���p�Ɋւ���Ă����Ƃ݂���B���m�ɂ́C�R���i�����g�傪�C���Ȃ����߂��Ђ̌o�c�₠�Ȃ����g�̏A�Ƃɂǂ̂悤�ȉe����^�������C�Ƃ����傫�Ȑݖ�̂Ȃ��ɁC�u���Ȃ��̃����[�g���[�N�̊��p�v�ɂ��ĂS�̑I������������Ă���B�Ȃ��C���̏ꍇ�̃����[�g���[�N�́C����Ζ����܂߂ĕ��i�̐E��ȊO�ŋΖ����邱�ƁC���w���Ă���B�I�����́C1�j�ȑO����i��ł���C2�j����傫���i�C3�j������i�C4�j�i��ł��Ȃ��^����������������Ă��Ȃ��C�̂S�ŁC�{�e�ł�1�j�`3�j�̍��v���e�����[�N���p�Ƃ����B
�E��v�ł̓���́C1�j2.1���C2�j16.0���C3�j17.0���@�v35.1���ł���̂ɑ��C�Ǘ��E�ł́C1�j4.3���C2�j27.7���C3�j26.4���@�v58.3���ƐE��ʂł͍ł����������ł���i�\�P�j�B���̓���̕��͂͌�ŏ����s�����C�u�ȑO����i��ł���v���Ǘ��E�ł�4.3���Ə��Ȃ��C�e�����[�N�o���̒����̈Ⴂ�ɂ�镪�͂͂ł��Ȃ��B
�Ƃɂ����C���̒����ɂ����Ă�58.3���Ɣ����ȏ�̊Ǘ��E���C�e�����[�N�Ɋւ���Ă���B�ݖ₩�炷��C�Ǘ��E�{�l�������[�g���[�N�i�e�����[�N�j�͂��Ă��Ȃ����C�E��S�̂Ńe�����[�N���s���Ă���ꍇ���H�ɂ��邩������Ȃ��B�������Ȃ���C���̏ꍇ���C�Ǘ��E�̓e�����[�N�Ɋւ���E��}�l�W�����g�ȂǂɊ֗^���Ă���̂ŁC���ݒ肩��́C�傫���͂���Ȃ��B
�Ȃ���ɏq�ׂ�ׂ��ł�������������Ȃ����C�Ǘ��E�̒�`�ł���B�E�핪�ނŁu�Ǘ��I�Ȏd���v�ɉ���1246�����Ƃ��Ă���B�����[�̗p������Ɂu�ہi�ۑ������܂ށj�ȏ�̑g�D�ł̊Ǘ��I�Ȏd���������v�Ƃ���̂ŁC������u�ے������E�ȏ�v�ł���B�Ƃ��낪�C�E�ʂɊւ���ݖ�ւ̉ł́C���������E�ȏ� 717�C�ے������E 977�C�v1694����1246����傫������i���Ȃ݂ɌW�������E��1827���j�B�ق��̐E��C���Ƃ��ΐ��E�Z�p�E�̂Ȃ��ɁC�E �y163�Łz �ʂƂ��ĕ����C�ے��ɉ������̂������B�E�ʂ̉ɂ��ے��ȏ�1694�̓T���v�����ł͑����Ȃ邪�C�E�핪�ނɂ�����̊Ǘ��E�ŕ��͂���B�Ȃ��C�E�ʉɂ��E�ʕʂ̃e�����[�N�����́C�����ȏ� 60.3���C�ے� 56.7���C�W�� 57.5���ł���B
����C�u�Ǘ��I�Ȏd���v�Ƃ�����1246�̐E�ʂɑ���́C�����ȏ�E 529�C�ے� 543�C�W�� 174���ł���B�u�W���v�ɉ���174���͐��������J�ɂ�܂Ȃ������̂ł��낤�B�����ɂ͌W���ւ̉��͂������Ƃ��l�����邪�C�E�ʂ̌��ʂ��݂����̂ŁC�܂߂ĕ��͂���B
������ɂ���58.3���Ƃ������l�́C�Ǘ��E�e�����[�N���p�Ɋւ��鑼�̒����̐��l�Ƃ��傫���قȂ�Ȃ��̂ŁC��q�̒�`�ŕ��͂��č����x���Ȃ��Ǝv����i�e�� 2022�j�B
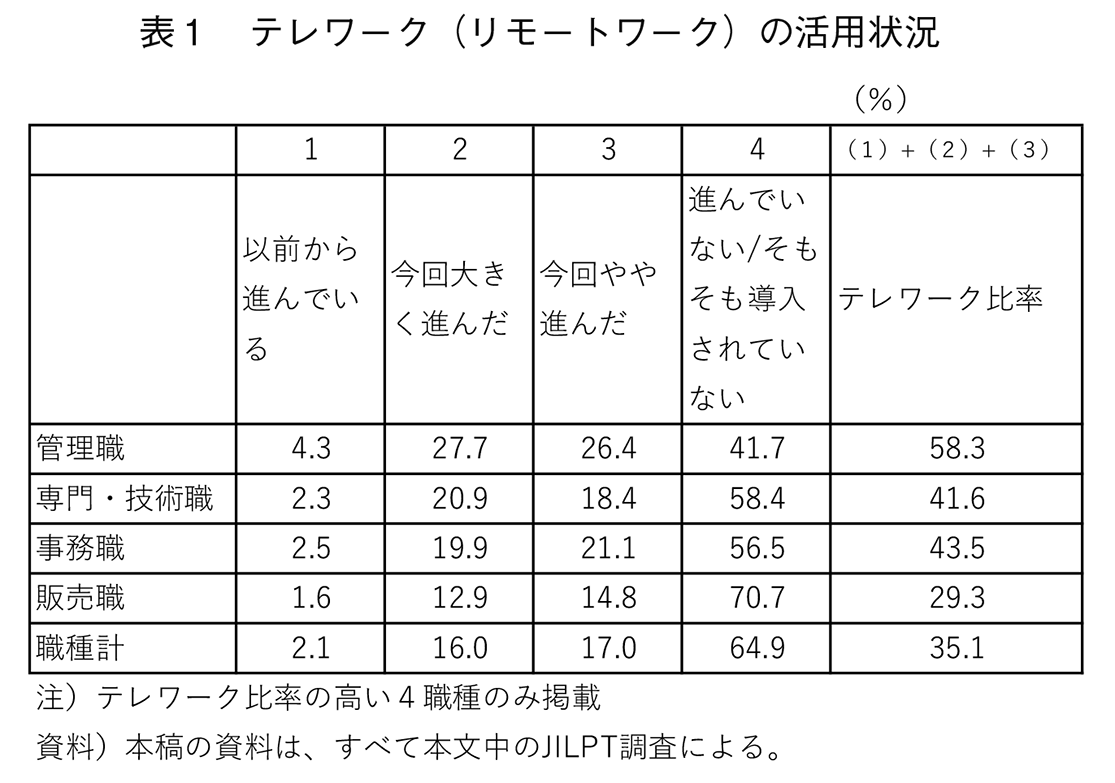
�R�D�ǂ��ɊǗ��E�e�����[�N��������
�ȒP�ȃv���r�b�g���͂ɂ��C�ǂ��Ƀe�����[�N�Ǘ��E�����������݂��i���P�j�B���̌��ʁi�L�ӂȂ��́j�C���̌��ʂ������B�i�@�j���̓e�����[�N�������L���B
�i�P�j300�l�ȏ�̊�Ɓi68.3���j�ɑ����B
�i�Q�j��ʁi65.4���j�C��t�i68.1���j�C�����i69.8���j�C�_�ސ�i64.0���j�C���i70.3���j�C���Ɂi72.0���j�C�R���i90.1���j�ɑ����B
�i�R�j���������E�ȏ�i60.3���j�ɑ���
�i�S�j�����i64.5���j�ɑ���
�i�T�j�Ǝ�ł́C�u���ʐM�Ɓv�i86.0���j�C�u�w�p�����C���E�Z�p�T�[�r�X�Ɓv�i77.8���j�C�u�����Ɓv�i67.0���j�ɑ����C�u�d�C�E�K�X�E�M�����E�����Ɓv�i16.7���j�C�u��ÁE�����v�i31.3���j�C�u�^�A�ƁE�X�Ɓv�i34.6���j�ɏ��Ȃ��B���Ȃ݂Ɋ�Ƃ����u���Ɓv�́C42.7���ł����i���Q�j�B
�y164�Łz
�����ɑ������Ƃ��܂����ڂ����B��s�����ł́C�R���i�g���C�����Ƀe�����[�N�̋@����Ȃ��������C�Ǘ��E�ɍi��C�����̂ق����������p���Ă���B������64.5���ɑ��C�j���ł�57.8���ł���B�S�̂ł́C�j�� 40.3���C���� 26.9���ƒj���̌o���������B�e�����[�N�̑����ق��̂R�E��̐��ʃe�����[�N�䗦���݂�ƁC���Z�p �j��49.2���@����26.8���C���� �j��52.1���@����38.0���C�̔� �j��38.9���@����18.9���ł���B�Ǘ��E���L�̌X���ł��邱�낪�킩��B
�u�ȑO���烊���[�g���[�N���i��ł����v�����Ǘ��E��8.6���ŁC�j���i3.9���j��葽�����C�����̓R���i�Ή������������Ƃ��ď����Ǘ��E�̗��p���L�܂������Ƃ��킩��B
�����̂��Ȃ��Ǘ��E������������Ǝv���邪�C�ށE�ޏ���̓e�����[�N���₷���ł��낤�B�����ĕ����Ȃ��Ǘ��E�͏����ɑ����Ƃ����Ă���B�����ł���C�����Ƀe�����[�N�Ǘ��E���j����葽�����Ƃ��������ׂ��łȂ���������Ȃ��i���R�j�B
�����`�����Ǘ��E�ł͂Ȃ��C�W�������E���܂ސ��Ј��ɂ�����j������݂�ƁC�����䗦�́C�����ȏ� 4.5���@�ے� 8.4���@�W�� 24.0���C��� 44.3�� �Ƃ�����u�K���X�̓V��v�̍\���ł���i�\�Q�j�B�܂��\�P�̐E�ʕʂ̒j���ʃe�����[�N�䗦���݂�ƁC�ے��ȏ�ł͏����������C�W���ȉ��ł͒j���������C�S�̂Œj���������B
���̂ق��C�K�͂̑傫����ƁC�s�S�C���ʐM�ƂȂǁC��E�������Ƃ���ŁC�e�����[�N�������Ƃ������ʂ́C��s�����̐E��v�̌��ʂƂ��Ȃ��ł���B
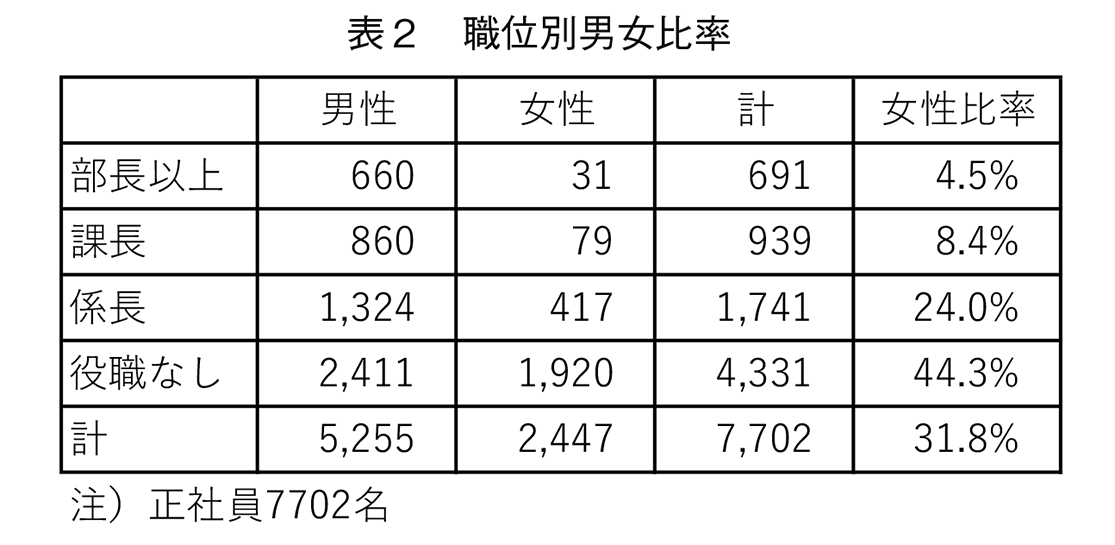
�R�|�P�@�Ǘ��E�̐E��Ƒ���
�E��i���Ə��ƍl������j�̐l���ł݂�ƁC�e�����[�N���p���Ă���̂͑�K�͐E��ł���B��ƋK�͂̌��ʂƓ����ł���B�E��̏����䗦�́C�e�����[�N�̗L���ő傫�ȍ��͂Ȃ��B�E��̔Ј��䗦�����݂͂��Ȃ��B�Ǘ��E�̔N��C�Α��N��������ׂĂ��C�傫�ȍ��͂Ȃ��i���S�j�B�]�E�o���̗L���ł݂�ƁC�e�����[�N�Ǘ��E 55.3���C��e�����[�N�Ǘ��E 65.1���̓]�E�o��������C���������̊Ǘ��E�̂ق����e�����[�N�͏��Ȃ��B
�R�|�Q�@�e�����[�N�Ǘ��E�̐E��ɂ������g��
�e�����[�N�̗L���ʂɁC�ӂ���́i����܂ł́H�j�E��ɂ�����19���ڂ̎�g�݂������Ȃ��Ă��邩�ǂ������݂悤�i�\�R�j�B�u�E��̐l�ԊW���悭����v�������C�u�����ԘJ���̗}���v��u�]�����ʂƂ��̐����v�Ȃǂ̎�g�݂��s���Ă���E��قǁC�Ǘ��E���e�����[�N�𑽂��s���Ă���B�Ƃ��Ɂu�����^���w���X�x���v�ł́C��20��pt�̍�������B
�y165�Łz
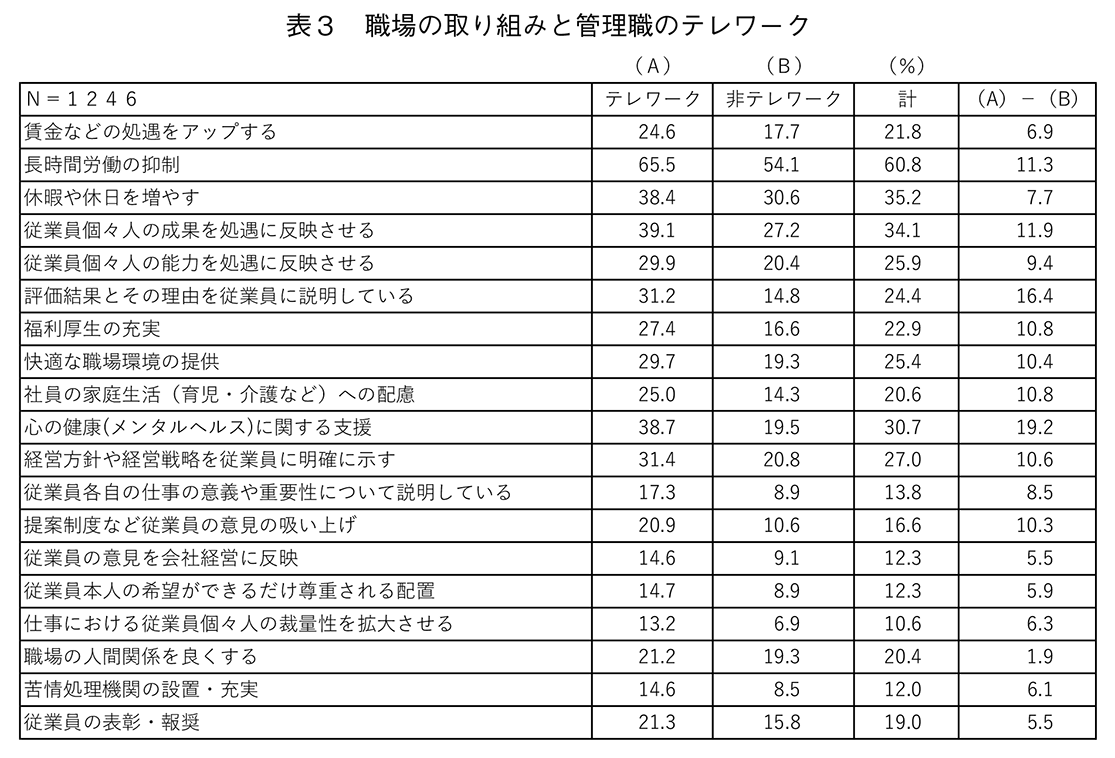
�]�����ʂ��J�����C���̗��R��������Ă����Ƃ̊Ǘ��E�ɂ����āC31.2�����e�����[�N���Ă���C���Ă��Ȃ�14.8����傫������B����́C�����炭�ڕW�ʐڐ��x�̌`�ōs���Ă���Ǝv����B����i2004�j�ɂ��C�䂪���̖ڕW�Ǘ����x�iMBO�j�́C
�m���}�I�ڕW�Ǘ��i1960�N��㔼�j�@���@�Q���I�Ǘ��Ƃ��Ă�MBO�i1970�N��j�@���@MBO�̒蒅�i1980�N��j���@�l���d�u��MBO�i1990�N��㔼�̈ꎞ���j���@�l���]�����x�Ƃ��Ă�MBO�i1990�N�㒆���ȍ~�j
�̂悤�ɓW�J���Ă����B���݂��C�\�͎�`�Ǘ��ł���C���ʎ�`�Ǘ��ł���l���Ǘ����x�Ƃ���MBO���Ȃ���Ă���ƍl������̂ŁC�Ǘ��E�ɂƂ��āC���Ȃ�̕��S�ƂȂ�^�X�N���Ǝv����B�������C�ڕW�ʐڂ��s���l���]�����s�����Ƃ��C�e�����[�N�ł��\���\�ł��邱�Ƃ��������Ă���B
�Ǘ��E�ɂ����������̂ł͂Ȃ����C���N���[�g���[�N�X�������̃p�l���f�[�^�ɂ��ƁCMBO���x�������Ƃ̂ق����C�ً}���Ԑ錾���i2020�N�S�E�T���j�ɂ����ăe�����[�N�Ɉڍs���Ă���i36.5�� vs 2.0���j�B�܂��C���̃f�[�^�ł͎�ϓI���Y���́C�e�����[�N�ɂ��ቺ�������CMBO����������Ă��邱�Ƃɂ��C�ቺ���}������Ă���B�錾���ł̃e�����[�N���{�ɂ��}�C�i�X0.145�̂����CMBO�ɂ���āC�v���X0.107�̌��ʂł����āC�ቺ��}�����Ă���i���� 2022�j�B
�\�R����C�ӂ���l�X�Ȏ��g�݂������Ȃ��Ă����E��ɂ����āC�Ǘ��E���e�����[�N�ł��邱�Ƃ��C�킩��B
�Ȃ��\�̏ォ��S�ԖڂƂT�Ԗڂ̍��ڂ́C�e�����[�N�����ʎ�`�Ɣ\�͎�`�̂ǂ���ɂȂ��݂₷�������l���邤���Œ��ڂ������̂ł���B�����E��v�̉��݂邩����C�ǂ���� �y165�Łz ���ڂɂ����Ă���]�ƈ������Ȃ葶�݂���i���L�̕\�j�B�܂��ǂ�������f���Ȃ����S���̂R������B���̋�������傫�ȃe�[�}�́C���̃f�[�^�ł͕��͂��Â炢�B
���Ј��݂̂Ɍ���iN��7702�j
�ǂ�������f���Ȃ� 5788 75.2 ��
���ʂ̂݁@�@�@�@�@�@�@�@ 778 10.1
�\�͂̂݁@�@�@�@�@�@�@�@ 403�@�@ 5.6
���ʂ��\�͂��@�@�@�@�@�@703�@�@ 9.1
�R�|�R�@�d�������ʓI�Ɋo���邽�߂̋�̓I�o���̗L��
�e�����[�N�̗L���ʂɎd�������ʓI�Ɋo���邽�߂̋�̓I�o��16���ڂ̗L�����݂�B�u�Ƃɂ������H�o��������ꂽ�v��u�}�j���A���z�z�v�Ȃǂ��܂荷���Ȃ����̂����邪�C���ׂĂ̍��ڂɂ����āC�e�����[�N�Ǘ��E�̂���E��ɂ����āCOJT�Ȃǂɂ������o�����������̂������i�\�S�j�B�e�����[�N�̗L���ō����傫���̂́C�u��Ђ̗��O��n�Ǝ҂̍l������������ꂽ�v�Ɓu��Ђ̐l�ވ琬���j�ɂ��Đ������������v�ŁC���ꂼ��13.9��pt�C15.1��pt�̍�������B
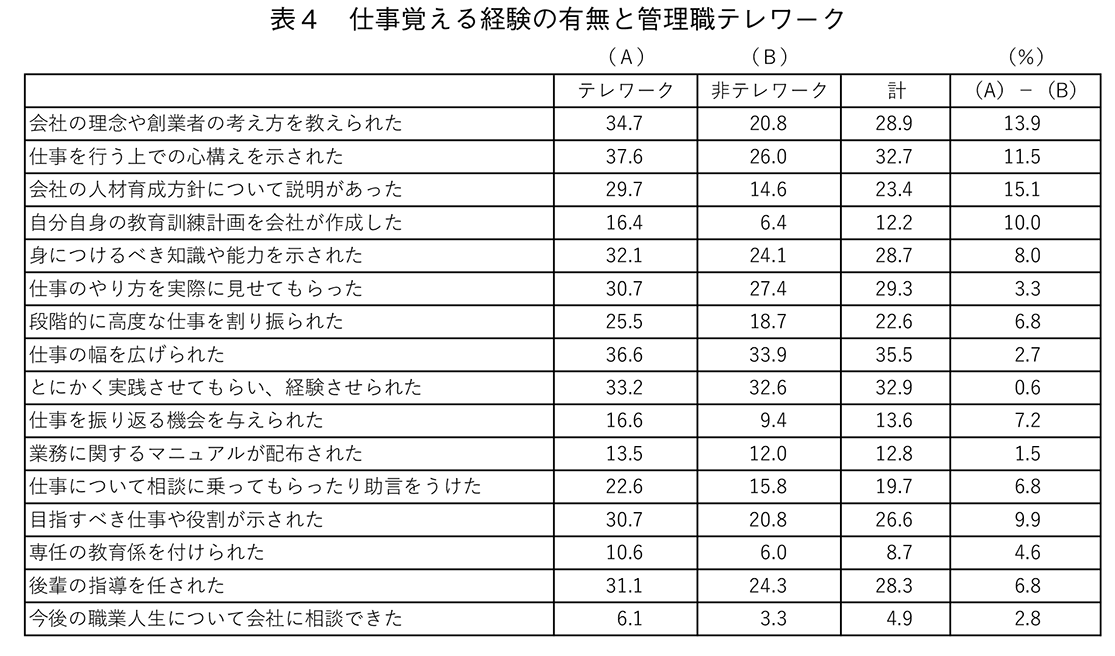
�u��Ђ̗��O��n�Ǝ҂̍l�����v�́C����N��ȏ�̐l�ɂ͓`���I���{�I�o�c�́u�o�c�Ƒ���`�v�̓T�^�I�ȕ\��̂悤�ɂ݂��邩������Ȃ��B21���I��20�N���������ł́C�����ł͂Ȃ��C�_�C�o�[�V�e�C�o�c�̗v�ƍl�����ق����悢�B���������i2020�j�ɂ��C�_�C�o�[�V�e�C�o�c�̂T�{�̒��̈�ɁC�u���O���L�o�c�v������B���l�ς�l�����������I�Ȑl�ނ݂̂ł́C�g�D�̒��ɐV�������l�n���͐��܂�Ȃ��B�_�C�o�[�V�e�C�o�c���v�������䂦��ł���B�������Ȃ���C���l�ȉ��l�ς����l�ނ������ƁC���S�͂̈ێ��ǂ��납�C���S�͂��� �y167�Łz ���炭�B�����h����̕��@���C��Ƃ��f����u�o�c���O�v�ł���B���l�ȉ��l�ς����l�ނ��ꂼ��ɐZ��������u���O���L�o�c�v���߂����B�e�����[�N�ɂ��Ă����l�Ȉӌ������]�ƈ����邢�͊Ǘ��E������ł��낤�B���������Ȃ��Ƃ��Ǘ��E�́C���́u�o�c���O�v�����L���邱�Ƃ��C�_�C�o�[�V�e�C�o�c�𐄐i���邱�ƂɂȂ��낤�B���̃f�[�^�ɂ����āC�o�c���O��������ꂽ�o�����e�����[�N�Ǘ��E�ɑ����������Ƃ͐ϋɓI�ɂƂ炦�邱�Ƃ��ł���B�u��Ђ̐l�ވ琬���j�ɂ��Đ����v�����l�̂��Ƃ�������ł��낤�B
�\�R�C�\�S�̌��ʂ���C�ӂ���OJT�C������PDCA �����܂��@�\���Ă���Ǝv����E��ɂ����āC�Ǘ��E���e�����[�N�ł��Ă���ƁC�ꉞ�������Ƃ��ł���B
JPC�����ɂ����āCOJT�i��C�s���j�̎��{�́C15-17���Ƒ����͂Ȃ����C2021�N���Ƃ����Č����X���݂͂��Ȃ��B�������R���i�g��ȑO�̃f�[�^���Ȃ��̂ŁC�R���i�������_�@��OJT�������������������͂킩��Ȃ��B���ꂪ�킩��f�[�^�����N���[�N�̃p�l�������ł���B�Ζi2022�j�ɂ��COJT��2019�N��24.4������2020�N��21.9���ƌ������Ă���i�}�C�i�X2.5pt�����B�K�͂��킸�������Ă���C5000�l�ȏ�̑��Ƃł��}�C�i�X3.0pt�̌����ł���B�����ł�OJT�̒�`�́C�u��i���y������w���������Ƃ�����v�ł���BJPC�����̒�`�Ƃقړ����ŁC�{�e�g�p�f�[�^�ق�OJT�̑����̑��ʂ��݂Ă�����̂ł͂Ȃ����C�ԈႢ�̂Ȃ����ʂł��낤�B
��������ƁC�e�����[�N�����y���Ă����Ƃ́COJT����������ƂȂ���Ă����E��ł���B����C�e�����[�N�̏ƂȂ��āC�Ǘ��E�͂��ߏ�i���y����w�����邱�Ƃ�����Ȃ��Ă��邱�Ƃ��������ɗ\�z�����B�S�߂ł݂邪�C�e�����[�N�Ǘ��E�����Y�������コ������������B������OJT�̂悤�ȃ{�f�C�u���[�̂悤�ɒ������ɂ����Ă�����ʂɂ��ẮC�Z���̐��Y���̋c�_�����ɂ������̂͂悭�Ȃ��B�e�����[�N�̂Ȃ��ŁC�V���Ј��͂��ߘJ���҂��C�ǂ̂悤��OJT����̓I�ɐ��s����Ă��邩��T�邱�Ƃ��K�v�ł���B
�R�|�S�@�R���i�Ȍ�̊Ǘ��E�̘J�����Ԃ̕ω�
�R���i�Ȍ�̊Ǘ��E�̘J�����Ԃ̕ω����݂�Ɓi�T���G�t�\�P�j�C ��e�����[�N�Ǘ��E�Ɣ�r����ƁC�e�����[�N���s���Ă���Ǘ��E�̂ق����u�����v�������̂������i37.6�� vs 20.8���j�B�R���i���ɂ����āC�e�����[�N�փX���[�Y�Ɉڍs�����P�[�X�����Ȃ��Ȃ����Ƃ��킩��B
�e�����[�N�̐i��𑪂�ݖ���ďq���邪�C�Ǘ��E�̉́C1�j�ȑO����i��ł���4.3���C2�j����傫���i��27.7���C3�j������i��26.4���@�ł������B�J�����Ԃ̕ω��͂ǂ��ł��������B�i�t�\�P�̉������j1�j2�j���قړ����ŁC�ʼn��s�́u������i�v�Ǘ��E�̐E��ł́C�u�����v��30.3���Ƒ��ΓI�ɏ��Ȃ��B�u�����v��11.3���ƁC��e�����[�N�Ǘ��E�́u�����v9.6����葽�����炢�ł���B
�u����傫���i�v�E��ł́C�u�ȑO����i��ł���v�E��Ɠ������炢�J�����Ԃ������������C�u���i�v�E��ł́C�������Ă���Ƃ��������B�X���[�Y�Ɉڍs�����C�������ĘJ�����Ԃ��������\��������B
������ɂ���C�e�����[�N���̊Ǘ��E�ɂ����āC�J�����Ԃ������������̂͏��Ȃ��C�S���قǂ��������Ă���B
�e�����[�N�ɂ��ʋΎ��Ԃ��ߖꂽ�i�������j���Ƃ͊m���ł���B�t�Ɍ����ΒʋΎ��Ԃ̒����J���҂قǃe�����[�N�ɓ��ݐ����\���������B�{�e�f�[�^�ɂ͒ʋΎ��Ԃ̐ݖ�͂� �y168�Łz �����C���Z�n�Ɩ{�Ђ���яA�Ǝ��Ə��̓s���{���ʃf�[�^������B�����ŁC���Z�n�ƏA�ƒn���������̘J���҂ƈقȂ錧�̘J���ҁi�u���܂����v�j���r�ł���B��������҂̂ق����e�����[�N������\�����傫���Ƃ݂�B
�T���v����16.6�����u���܂����v�����Ă���C���Ј��ɂ��ڂ�ƁC18.1���ł���B�����ĊǗ��E�ɂ��ڂ�ƁC26.1���i325���j�ɂ��Ȃ�B���́u���܂����v�Ǘ��E�̂����C���悻�S�l�ɂR�l��73.5�����e�����[�N�����Ă���i���ꌧ�ł�53.0���j�B
�R�|�S�|�P�@�n��ɂ��Ⴂ
�n��ɂ��Ⴂ���d�v���Ǝv����B�e�����[�N�Ǘ��E�̑������Ə��́C��͂蓌������Ȃǂɑ����B�����ł͊ȒP�ȏW�v�����č���̖{�i�I���͂ɂ��Ȃ������B
�t�\�V�|�P�́C�����Ǘ��E�̊����Łu��������v�̎p��������B
�e�����[�N�i�S���Ј��C�Ǘ��E�j�������݂�Ɓi�t�\�V�|�Q�C�V�|�R�j�C�֓����̈Ⴂ�����C�����E���Ƃ���ȊO�̌��̍����ڗ��B
�R�|�T�@�e�����[�N�����Ă���Ǘ��E���g���C�������Ă��邩
�����x�@�i�S���j�ɂ��ẮC�����̖��������łȂ��C�W���ڂɂ��Đq�˂Ă���i�\�T�j
�S�̓I�ɁC�e�����[�N�Ǘ��E���C��e�����[�N�Ǘ��E���������x�������B�����̖����x�ɑ傫�ȍ����݂��邾���łȂ��iDI�w����33.0pt�̍��j�C�u�\�͂�m����g�ɂ���@��v�̖����x���e�����[�N�Ǘ��E�̂ق������Ȃ荂���i27.1pt�̍��j�B���ꂾ���łȂ��C���ׂĂ̍��ڂɂ����āC�����������݂Ă�DI�w�����݂Ă��C�e�����[�N�Ǘ��E�������x�������B
�d����̒n�ʂ⌠���ɂ����Ă��e�����[�N�Ǘ��E�̖����x�������Ƃ��������́C�e�����[�N�ڍs�ɂ���āC���̊Ǘ��E�̌������������Ȃ������Ƃ͂Ȃ��\�����傫���B
�����x�͐T�d�ɉ��߂��ׂ��ϐ��ł��邪�C�Ǘ��E���e�����[�N���邱�Ƃɂ���āC���Ȃ��Ƃ��傫�ȕs���������Ȃ������Ƃ͂����邾�낤�B������C���������Ɏ������߂ɁC�K�́C�Ǝ�ȂǂŒ��������C��A���͂������Ȃ����B
���̏��ʃv���r�b�g�ł́C����̌W�����u���v�ł���u�����v�C�u���v�ł���u�s���v�����߂��B�e�����x�����̕ϐ��ʼn�A�����B
�e�����[�N�E�_�~�[�C��ƋK�́C�E�ʃ_�~�[�C�j���_�~�[�C�N��C�N���C�Α��N���C�Α�����C�w��
���茋�ʂ́C�e�����[�N�E�_�~�[���C���ׂĂ̖����x�ŗL�ӂł������i�قƂ��0.1�������j�B���Ȃ킿�����悤�ȊǗ��E�ł����Ă��C�e�����[�N�����Ă���Ǘ��E�ɂ����Ė����x�������B�ԐړI�ɂł͂��邪�C�e�����[�N�����܂������Ă���؋��ł��낤�B
�t�\�Q�������̖����x�Ɋւ��鐄�茋�ʂł���B�����Ǘ��E�̂ق��������C�N������قǕs���C�E�ʂ��Ⴂ�قǕs���C�Ǝ�ł͓d�C�K�X�M�����̂ݖ����i���Ɗ�j�Ƃ������ʂł������B�i���T�j
�����ȊO�̖����x�C���Ȃ킿���������C�����₷���C�d�����e�C�E�ʁC�ٗp����x�C�\�́E�m����g�ɂ���@��C�L�����A�̌��ʂ��C�ɂ��Ă��C���ʂ͓����ł���B
�y169�Łz
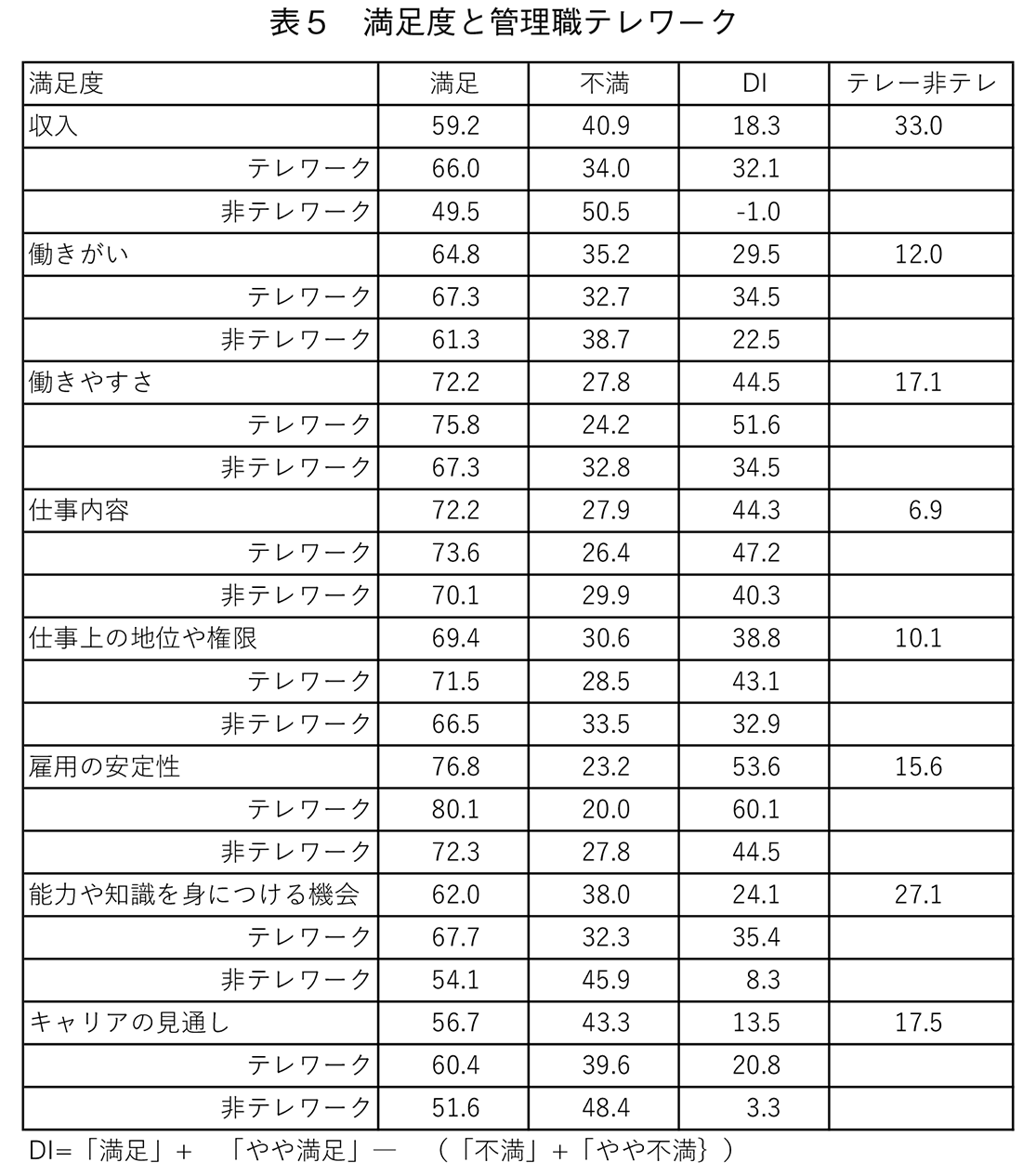
�S�D���Y���Ƃ̊W
��s�����ɂ����鐶�Y���̌����CRIETI�̐X�쎁�̈�A�̌����CJILPT������p�����ߘa�R�N�J���o�ϔ����CJPC�����Ȃǂ�����BJPC�������番�������̂́C�e�����[�N�i�ݑ�Ζ��j�����Č��������������������������Ɛq�˂�ƁC�������̂����C�オ�����ق��������B�Ƃ��낪�ق��̒����ŁC�ӂ���́i�I�t�B�X�j�Ζ���100�Ƃ����X�R�A�Ő��Y����q�˂�ƁC���ςR�`�S���Ă��nj������Ă���B�����Ɍ��y���������i2022�j�ł���ϓI���Y���������������Ƃ͂��Ă���B
�{�e�Ŏg�p����JILPT�����f�[�^�ɂ́C���Y���ɊW����ݖ₪�����B�e�����[�N���p�҂ɑ��āC�u�����[�g���[�N�œ������Ƃɑ��āC�ǂ̂悤�ȔF���������Ă��܂����v�Ƃ����ݖ�̈�ɁC�u���i�̐E��œ��������d�����͂��ǂ�v�Ƃ������ڂ�����B�u�͂��ǂ�v�́C�ǂ��݂Ă����Y����\���Ă���ł��낤�B����ɑ��āC1�j�����v���C2�j�ǂ��炩�Ƃ��������v���C3�j�ǂ���Ƃ������Ȃ��C4�j�ǂ��炩�Ƃ��������v��Ȃ��C5�j�����v��Ȃ��C �y170�Łz ��������Ă���B1�j2�j��I���������̂��u���Y������v�C4�j5�j���u���Y���ቺ�v�Ƃ݂Ȃ��B�e��i2022�j�ŋ��������悤�ɁC����͂����܂ŒZ���̐��Y���ł����āC�����͂ɂȂ��钷���̐��Y���ł͂Ȃ��B����ǂ���������e�����[�N�����y���邩�ۂ��́C�Z���̐��Y���ł����Ă��l�@�ɒl����B�u�����ł́C�݂Ȏ���ł��܂��v�i�P�C���Y�j
���Y���ɂ��Ă̌��ʂ́C
�E��v�iN��3507�j �u���Y������v�@32.3���C�u���Y���ቺ�v�@27.1��
�Ǘ��E�iN��727�j �@�@�@�@�u���Y������v�@31.5���C�u���Y���ቺ�v�@26.7��
���E�Z�p�iN��1005�j �@�u���Y������v�@36.7���C�u���Y���ቺ�v�@25.0��
�S�̂Ƃ��āC�u���Y������v�������̂��C�u���Y���ቺ�v�������̂������������BJPC�����̌��ʂɋ߂��B�Ǘ��E�̏ꍇ���E��v�Ƃقړ����ł���B���Z�p�E�ł́u����v�������̂�10��pt�����B
�S�|�P�@�e�����[�N�S�E��̐��Y���̌���E�ቺ�̗v��
OJT�𒆐S�Ƃ����E��ɂ�����l�ވ琬��\�͊J���ɂ��āi�d�������ʓI�Ɋo���邽�߂̌o���j�C�����̐ݖ₪����̂ŁC����𒆐S�ɔ�r����B
A ����CB �ቺ�CC �ǂ���Ƃ������Ȃ��@���r�����B
�e�����[�N�o���҂̂Ȃ��ŁC�u����v�����������̂́C�u��Ђ̗��O�Ȃǂ��w�ԁv��u�l�ވ琬���j�̐����v�������̂����������B����ȊO�ɂ��u����P���v��쐬�v��u�E�Ɛl�����k�v�������̂��C�Ƃ��Ɂu����v�����������B���̂ق��C�قƂ�ǂ̎�g�݂ɂ����āC�o���������̂́u����v���������������B�i�t�\�R�j
�S�|�Q�@�e�����[�N�Ǘ��E�ɂ����鐶�Y���̌���E�ቺ�̗v��
�e�����[�N�������Ǘ��E�̂Ȃ��ŁC���サ�����̂ƒቺ�������̂��悤�ɔ�r�����B�i�\�U�j
�u����P���v��쐬�v�u��C�̋���W��t����ꂽ�v�u�E�Ɛl�����k�v�������̂ɂ����āC�u����v�������Ƃ��ɍ��������i���ꂼ��C41.2���C42.9���C43.2���j�B�܂��C�قƂ�ǂ̎�g�݂ŁC�o���������̂̂ق����C�u����v���������������B
��C�̋���W��t�����Ĉ�����Ǘ��E���C�e�����[�N�Ɉڍs���Đ��Y�����サ�Ă���B�����}�l�W�����g�̌o���ŏd�v�ȁu��y�̎w����C���ꂽ�v�Ǘ��E�́C���Y�����オ��⑽�����炢�ł���B
�e�����[�N�̑����S�̐E��ʂɃv���r�b�g��p���āu����v�������̗̂v����T��B���̂S�̐E��̃e�����[�N�����́C�Ǘ��E58.3���C���Z�p41.6���C����43.5���C�̔�29.3���ł���B�u����v�������̂��u�P�v�C����ȊO�̃e�����[�N�Ǘ��E���u�O�v�Ƃ���_�~�[�ϐ����쐬���C�v���r�b�g���͂����B
�܂��E��������ϐ��ɂ����Ɓi�t�\�S�j�C
�Ǘ��E����Ƃ��āC�����E������C�A���E�@�B�^�]�E�����サ�Ă��Ȃ��B�E�ʂł͕��������サ�Ă���B
���Ƀe�����[�N�̑����S�̐E��i�Ǘ��E�C���E�Z�p�E�C�����E�C�̔��E�j�ʂɍs�����B
�y171�Łz
probit�@�u����v�@���@�Ǝ�@�K�́@�E�ʁ@���_�~�[�C�N��C�N���C�Α��C�Α�����C�w��
�Ǘ��E�ɂ����Ắi�t�\�T�j�C�Ǝ�ł́C�u�s���Y���݁v�C�u�h���C���H�T�[�r�X�Ɓv�ɏ��Ȃ��B�E�ʂł͕���������C����ȊO�̕ϐ��͂قƂ�NJW�Ȃ��B�ق��̂R�̐E����قړ������ʁB
�S�|�R�@����P���v��
�e�����[�N�Ǘ��E�ŁC����P���v�����Ђō쐬���ꂽ���̂̂����C41.2�������Y�����サ�Ă���i�\�U�j�B�S�E����Ƃ��Ă�42.5�������サ�Ă���B�쐬����Ă��Ȃ��Ǘ��E���10��pt�ȏ�C���サ�����̂������B��Ɠ��L�����A�ɂ����āC���ɉ����Ȃ��ׂ����̓����͂����肵�Ă�����̂��C�e�����[�N�Ɉڍs���ĒZ���̐��Y�������コ���Ă���B���̃L�����A���݂��Ă���C�E��𗣂�Ă���ق����C�e�L�p�L�d�������Ȃ���̂�������Ȃ��B
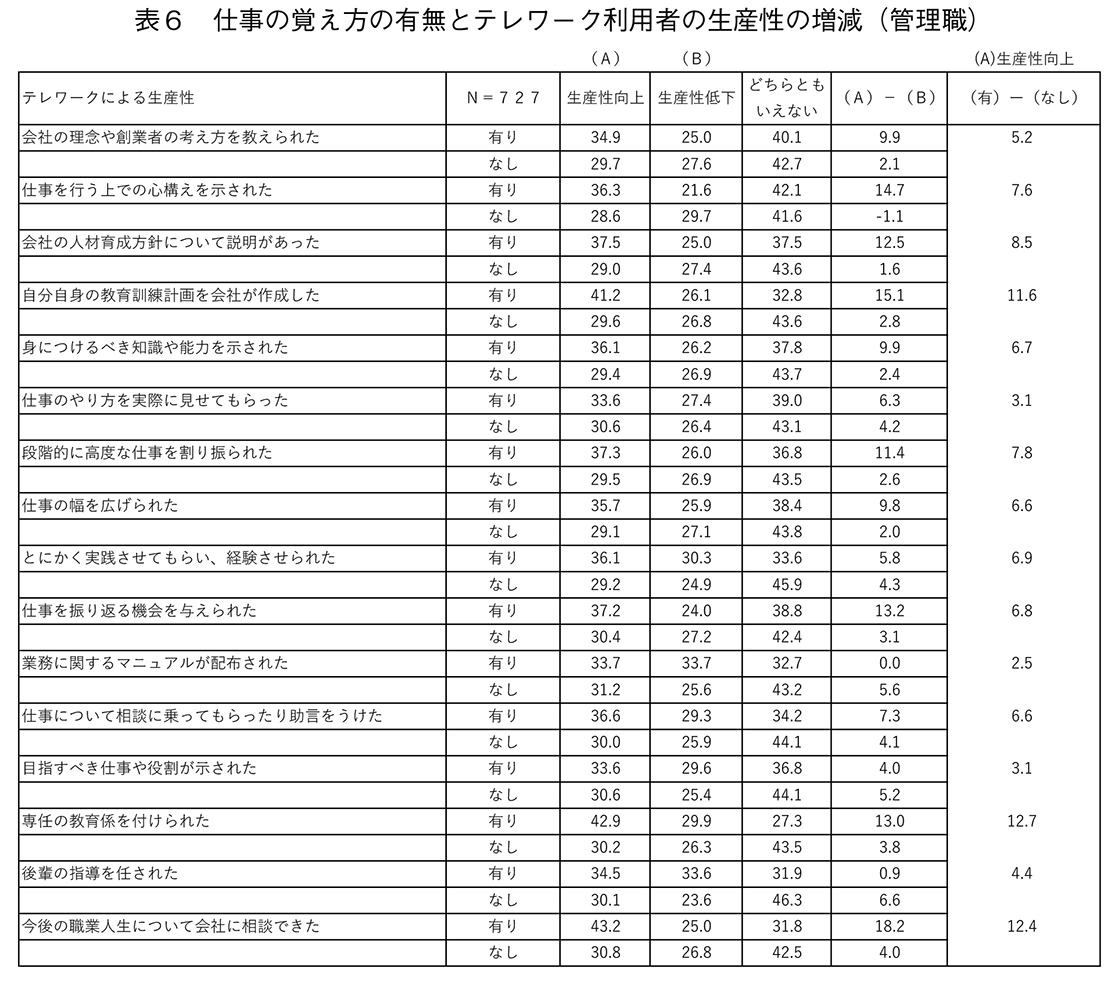
�y172�Łz
�S�|�S�@�e�����[�N�̌���
�e�����[�N���s�������ʂ�q�˂Ă���ݖ������B���ʂP���ځC�ۑ�V���ڂ�����B�e�����[�N�̑����S�̐E��ɂ��ďW�v�����B�i�\�V�j
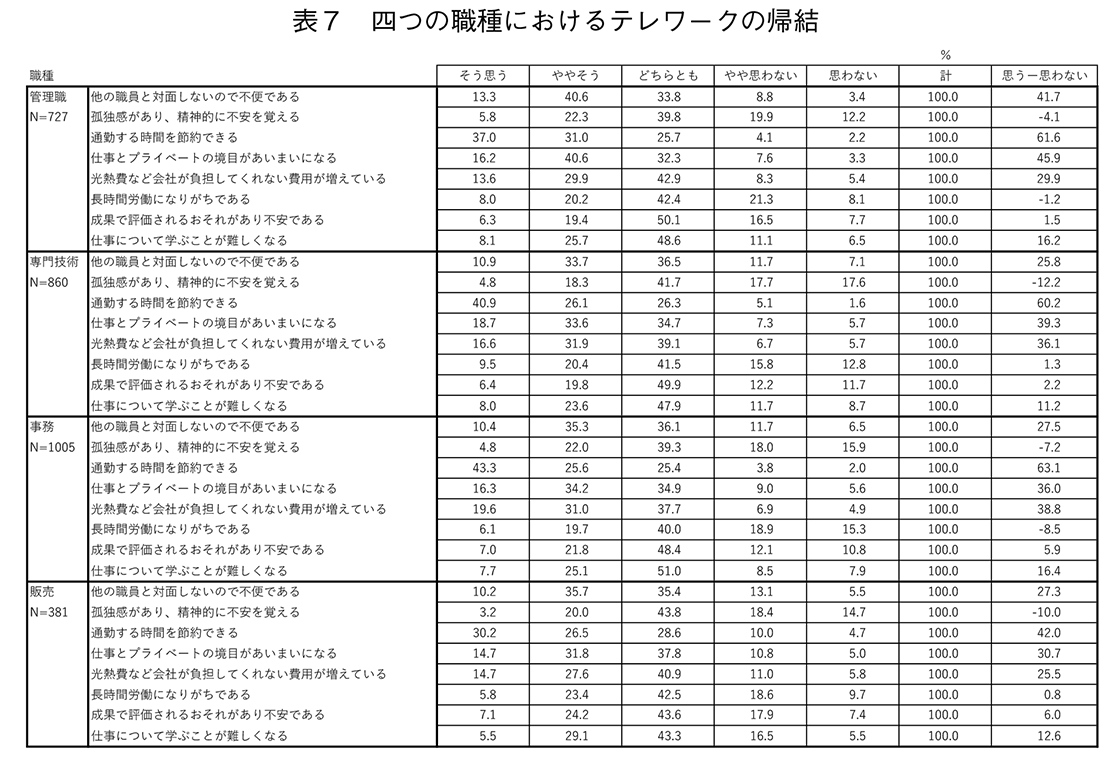
�����b�g�́u�ʋΎ��Ԃ̐ߖ�v�́C�ǂ̐E������悻�R���̂Q�����ʂ������Ă���B�ۑ�́C�Ǘ��E�Łu���̐E���ƑΖʂ��Ȃ��̂ŕs�ցv53.9���C�u�d���E�v���C�x�[�g�������܂��v57.2���Ȃǂ������B����C�u�ǓƊ������萸�_�I�ɕs���v��28.1���Ə��Ȃ��C�u�����v��Ȃ��v�ق��������B�u�����ԘJ���ɂȂ肪���v�����Ȃ��B�܂��E��ɂ�鍷�͂��܂�Ȃ��B
���Y���̑����ʂɁu�ʋΎ��Ԑߖ�v���݂�ƁC�u����v��77.7���C�u�ቺ�v��72.7���Ƒ傫�ȍ��͂Ȃ��B�i�\�W�j�����Ă����u�ǂ���ł��Ȃ��v��57.5���Ƒ��ΓI�ɏ��Ȃ��B�ށE�ޏ���́C�ʋΎ��Ԑߖ�ɂ��Ă�38.2�����u�ǂ���ł��Ȃ��v�Ɖ��Ă���B�T�d�ȉ�����X���̂���҂Ȃ̂�������Ȃ��B
����C�ۑ�ɂ��ẮC�u�ቺ�v�����Ǘ��E�ő��ΓI�ɑ����̂́C�܂��u�Ζʂ��Ȃ��̂ŕs�ցv���C71.1���i�u����v�ł�62.9���j�C�u�d��/�v���C�x�[�g�������܂��v69.0���i�u����v�ł�62.9���j�ł���B
���Y���u����v�����Ǘ��E��������ۑ�ő����̂́C�u�ǓƊ��v41.5���i�u�ቺ�v25.3���j�C�u���M��Ȃǂ̉�Е��S�Ȃ��v58.9���i�u�ቺ�v45.9���j�C�u�����ԘJ���ɂȂ肪���v42.8���i�u�ቺ�v25.2���j�C�u���ʂŕ]������邨����v43.7���i�u�ቺ�v22.2���j�u�d���ɂ��Ċw�Ԃ��Ƃ�����v45.5���i�u�ቺ�v38.1���j�ł���B���Y�����u����v���Ă������C�ǓƊ��ɔY�܂���Ă���B�����E�����Ƃ̐ڐG�����Ȃ����C�Ǘ��E�{�l�͎d�����e�L�p�L�Ƃł��Ă��āC�ǓƂ������Ă�
�y173�Łz
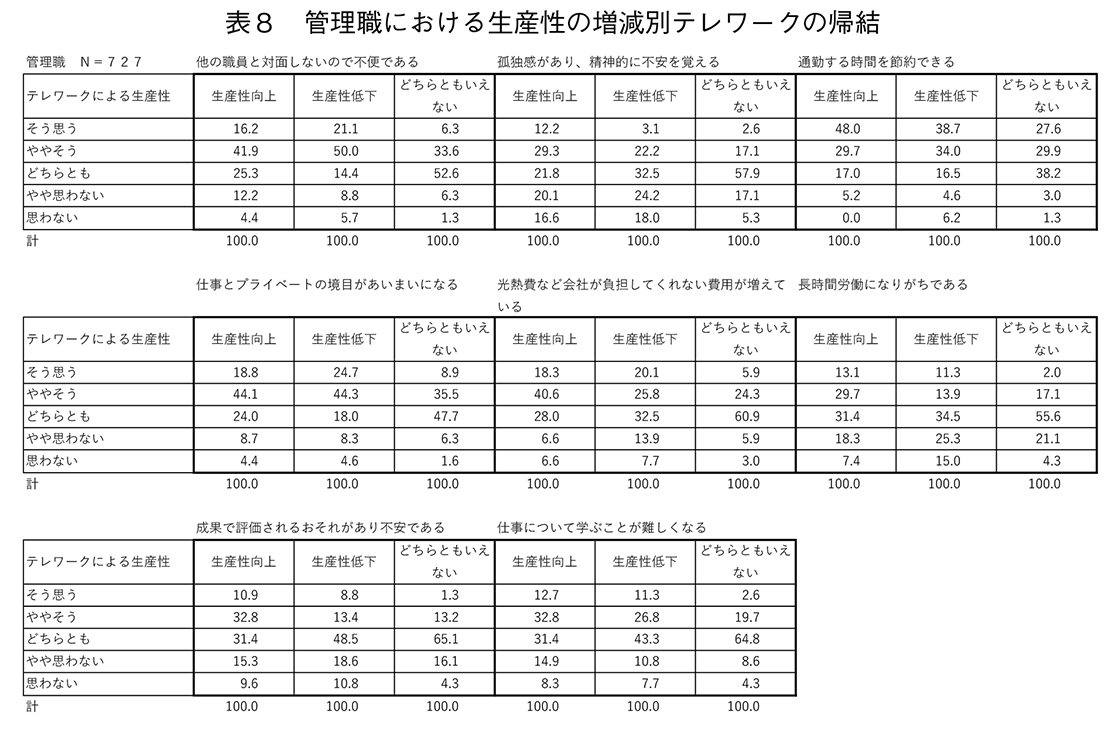
��̂ł��낤�B�S�̂Ƃ��ẮC�ǓƊ��ɔY�܂���Ă�����̂͏��Ȃ��B
�u�ǓƊ��v�ɂ��ẮC�]�āi2021�j���C�e�����[�N�̎��{�҂Ɣ���{�҂��r���Ă���̂ŎQ�l�ɂȂ�B2020�N�V���ɁC�C���e�[�W�o�^���j�^�[�̂����A�J�҂��瓾��ꂽ3073���ɂ��ĕ��͂��Ă���C���Ƃ��ΐE��ɂ�����Ǘ����ɂ��āC�e�����[�N���{�҂ł́C�E���v���Z�X�̑��҈ˑ����������قnjǗ��������܂��Ă���B����I�Ɏ��͂Ƌٖ��ȘA�g���Ƃ��Ă���ƁC�������_�ɂ����ăe�����[�N�Ɋ���Ă��Ȃ��̂ŌǗ��������܂�Ƃ��Ă���B����C����{�҂ł́C���ʂ̑��҈ˑ��������܂�قnjǗ����������Ă���B���͂Ƃ̘A�g���e�����[�N�̎��{�E����{�ɂ���ĈقȂ郁�J�j�Y���ŌǗ����ɉe�����邱�Ƃ��������Ă���B�Ǘ��E�͖��炩�ɑ��҈ˑ����̍����E��Ȃ̂ŁC�{�e�̌��ʂ͍]�āi2021�j�̌��ʂƈقȂ�̂�������Ȃ��B
�u�J�����ԁv�ɂ��ẮC���Y���u����v�ł͘J�����Ԃ́u�����v�����������B�ۑ�ł��C�u�����ԘJ���ɂȂ肪���v�͏��Ȃ��B ���ۂ̘J�����Ԃ̕ω����݂�Ɓi�t�\�U�j�C���Y���̌���E�ቺ�ɂ��C���������̍��͂Ȃ��B�e�����[�N�ƘJ�����Ԃ͂��܂�W�Ȃ��Ƃ�����B
�T�D������̓W�]
�R���i������́u�������v�Ȃǂɂ��āC�u�ω�����v�u�ω��Ȃ��v�̂Q���Őq�˂Ă���B��e�� 38.0���C�e�� 74.1���ƁC�e�����[�N�Ǘ��E�̂S�l�̂����R�l���u�������v���ω�����Ɨ\�����Ă���B����C�e�����[�N�����Ă��Ȃ��Ǘ��E�͂R���̂P���ɂ����Ȃ��i�\�X�j�B�傫�ȈႢ�ł���B�g�̉��̏��݂āC�l�͖�����\������B��s�����ɂ����Ă��C�ݑ�Ζ��i�o���j���������̂قǁC�������ݑ�Ζ���]��ł���B
�y174�Łz
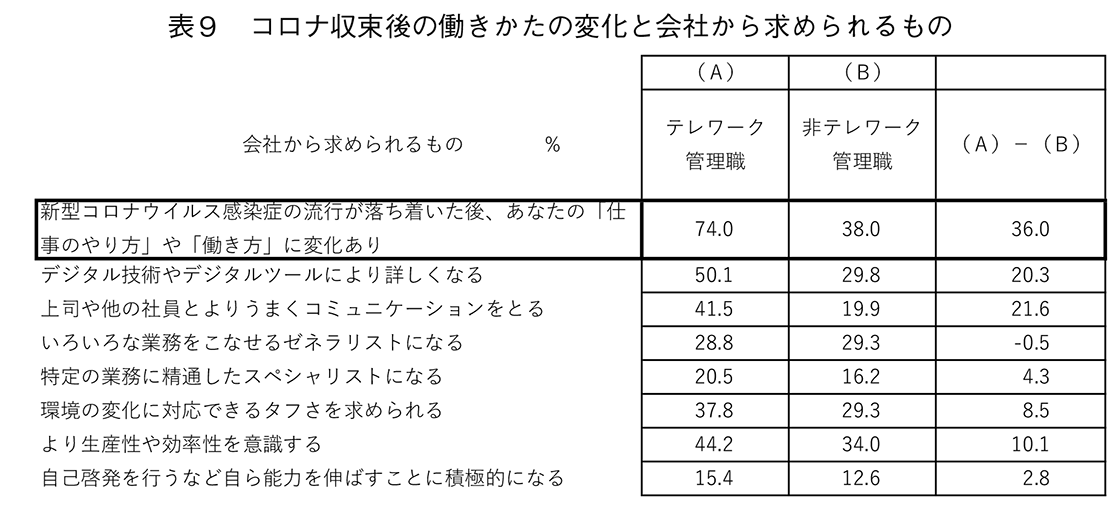
�ω��́u�L��v�̓��e���݂�Ɓi�V���ځj�C�ω��u�L��v�̊������قȂ�̂œ��R�ł��邪�C�e�����[�N�Ǘ��E���قƂ�ǂ̍��ڂő����w�E���Ă���B�Ƃ��Ɂu�f�W�^�����ɏڂ����v�C�u�R�~���j�P�[�V�����v�Ȃǂ���Ђ��狁�߂���ƍl���Ă���e�����[�N�Ǘ��E�������B�f�W�^�����ɐ��ʂ��Ȃ��ƃe�����[�N���ł��Ȃ��͓̂��R�ł��낤�B�܂��u���Y���E�������ӎ��v�́C�e�� 44.1���C��e�� 34.0���ł���������B
�u�[�l�����X�g�v�u���ł͍��͂Ȃ����C�u�X�y�V�����X�g�v�u���ł́C���e�����[�N�Ǘ��E�̂ق��������B�������C���̓@�ɂ��āC�ϋɓI�ɉ��߂���킯�ɂ͂����Ȃ��B�i���U�j
������̕ω��̍��ڂ̂Ȃ��ɁCOJT��\�͊J���Ɋւ�铭�����̕ω��̍��ڂ��c�O�Ȃ���Ȃ��B�ߋ��ƌ��݂ł́C�������ɂ݂��Ȃ������̍��ڂ����������C�����ɂ��Ă������ł�����Ƃ悢�ł��낤�B
�U�D�܂Ƃ߂Ɨ��ӓ_
�e�����[�N�Ɋւ��錤���͋}�����Ă��邪�C�Ǘ��E�Ƀt�H�[�J�X�����Ă����̂͂Ȃ��C�l�ވ琬�Ƃ����ϓ_�Ɨ��߂����͂��قƂ�ǂȂ��B
�{�e�̏d�v�Ȍ��ʂƂ��āC
�@�T���ĊǗ��E�͌��ʂ������Ă���C���ʁi���Y���j���������Ǘ��E���ǓƊ����ۑ�Ƃ��Ă����Ă���
�A�ʉ���������E�琬���s���Ă����Ƃ̊Ǘ��E�����Y�������サ�Ă���
�B���̃L�����A�������Ă��邱�Ƃ��e�����[�N���ł��d���������I�ɐi�߂�
�Ȃǂ�����B
���͌��ʂ���́C�R���i�Г��Ńe�����[�N�Ɉڍs�ł�����Ƃ́C���������l�ރ}�l�W�����g���K���\���ɂȂ���Ă����\�����傫���B�\�R�E�\�S���݂Ă��C�S�Ă̍��ڂɂ����ā@�e�����[�N�Ǘ��E����e�����[�N�Ǘ��E�@�Ƃ������Ƃ���������ł���B�Ǘ��E�i�����炭��ʏ]�ƈ����j�ɑ���琬�Ɏ��g��ł�����Ƃł́C�Ǘ��E�ɗ͂����邾���łȂ��C���̕� �y175�Łz ���ɂ��琬��ʂ��ė͂����邱�ƂŁC���Y�������シ�铙�ǂ����ʂ������C�����e�����}�����Ă���悤�Ɋ�������B
�������ɁC���̘_�e�̌��E���q�ׂ����B�{�e�ŗp�����f�[�^�́C�����J���Ȃ̗v���ɂ��CJILPT�̌������������[���쐬�������̂ł���B�M�҂ɂƂ��ċ����[�����ڂ������C�w�i�ɂ����Ɖ������e�Ղɑz�������̂������B�������Ȃ���C�����܂ł��Ȃ��C���̒����[�쐬�v���Z�X�Ɋ֗^���Ă��炸�C�����܂ŁC�M�҂Ȃ�ɁC���̃f�[�^����܂Ƃ߂����̂ɂ����Ȃ��B
�Q�l����
�Γc���j�i2022�j�u�w�ѓ������Ɓv�Γc���j�^��c���m�ҁw�p�i�\�j�b�N�̃O���[�o���o�c �|�d���ƕ�V�̃K�o�i���X�x�~�l�����@���[
���ؕ����i2021�j�w�o�ώЉ�̊w�ѕ� �|���S�ȉ��^�̖ڂ�{���x�����V��
�]�Ċ����Y�i2021�j�u�����[�g���[�N�̔w�i�ƌ��ʁv�]�Ċ����Y�ق��i2021�j�w�R���i�V���b�N�ƏA�J�F���s�����̐S���ƍs���ɂ��Ă̎��ؕ��́x�~�l�����@���[
���얾�q�i2004�j�w�ڕW�Ǘ��̃R���e�C���W�F���V�[�E�A�v���[�`�x�������[
���c�L�j�E�����q�q�ҁi2022�j�w�d�����猩���u2020�N�v �|���ǁC�������͕ς��Ȃ������̂��H�x�c��`�m��w�o�ʼn�
�����J���ȁi2021�j�u�ߘa�R�N�J���o�ϔ����v
���r�a�j�i2015�j�w�Ȃ����{��Ƃ͋��݂��̂Ă�̂��F�����̋��� vs �Z���̋����x���{�o�ϐV���o�Ŏ�
��ܗm���E�����Ái2020�j�w�Ǘ��E�̖����x�����o�ώ�
���������i2022�j�u�_�C�o�[�V�e�C�o�c���x����T�̒��v���������E���Όb���q�E��ܗm���w���l�Ȑl�ނ̃}�l�W�����g�x�����o�ώ�
�����q�q�i2022�j�u�e�����[�N�ւ̈ڍs�ƒ蒅�C�����Č��ʁv���c�L�j�E�����q�q�ҁi2022�j�w�d�����猩���u2020�N�v �|���ǁC�������͕ς��Ȃ������̂��H�x�c��`�m��w�o�ʼn�
�Ζؗm�V�i2022�j�u�����g�傪�����N��������ƋK�͊Ԋi���v���c�L�j�E�����q�q�ҁi2022�j�w�d�����猩���u2020�N�v �|���ǁC�������͕ς��Ȃ������̂��H�x�c��`�m��w�o�ʼn�
�X�쐳�V�i2020a�j�u�R���i��@���̍ݑ�Ζ��̐��Y���F�A�J�҂ւ̃T�[�x�C�ɂ�镪�́v�wRIETI Discussion Paper Series�x20-J-041
�X�쐳�V�i2020b�j�u�V�^�R���i�ƍݑ�Ζ��̐��Y���F��ƃT�[�x�C�Ɋ�Â��T�ρv�wRIETI Discussion Paper Series�x20-J-041
�X�쐳�V�i2020c�j�u�R���i�ƍݑ�Ζ��̐��Y���v���ьc��Y�E�X�쐳�V�ҁw�R���i��@�̌o�ϊw�x���{�o�ϐV���o�Ŏ�
�J�������E���C�@�\�i2021�j�w�E�C�Y�R���i�E�|�X�g�R���i�̓������|�e�����[�N�𒆐S�Ƃ����q�A�����O�����xJILPT�����V���[�Y No.242
�e�▾�i2019�j�uOJT�čl�v�w�w�K�@��w�o�όo�c�������N��x33���i59-89�j
�e�▾�i2022�j�u�e�����[�N�Ɋւ���e�풲���v�w�w�K�@��w�o�Ϙ_�W�x58���S���i253-274�j
�y176�Łz
������
�P�j�Ǘ��E�ɂ��āCJILPT�����̃����[�g���[�N�ɂ��Ẳ��C�u1�j�ȑO����i��ł���C2�j����傫���i�C3�j������i�v�Ƃ�����̂��C�e�����[�N���p�Ƃ��āu�P�v�Ƃ��C�u4�j�i��ł��Ȃ��^����������������Ă��Ȃ��v�̉҂��e�����[�N�p�҂Ƃ��āu�O�v�Ƃ����B���̂����Ŏ��̂S�̐����ϐ��ŁC���p���ǂ��ɑ��������݂��B�Ǝ�C��ƋK�́C���Z�s���{���C�E�ʁi�����C�ے��C�W���j�C����
�Q�j�����s��2020�N����s���Ă���uTOKYO�e�����[�N�A���[�h�v�ő�P��̑�܂́C���Ƃł́i���j�D��i�T�[�r�X�ƁG�����f�U�C���C�{�H�G414���j�C������Ƃł́C�i���j�V���[�P�[�X�i���ʐM�ƁG87���j�C��Q���܂́C�i���j�g���i�i���C�H�i���ޕ���[�J�[�j�ł���B�g���́C225���̊�Ƃł��邪�C�H�ꌻ����܂ޑS�Ј����Q������I�����C����c���J�Â��C�c�ƎЈ��̃����[�g���k�ȂǑ��l�ȐE��Łu�T�R��Ј��V���ȏ�e�����[�N�v���s���Ă���B�����̊�Ƃɂ�����Ǘ��E�̏͂킩��Ȃ����C�l�X�ȋƎ�ł��s���Ă��邱�Ƃ��킩��B
�R�j���ƍ\�z��w�@�̐��_�����̎w�E�ɂ��B
�S�j�N��́C�e�����[�N�Ǘ��E�@���� 49.9�C�����l 51�C��e�����[�N�Ǘ��E 50.8�C52�C�Α��N���́@�e�����[�N�Ǘ��E 19.8�N�C20�N�C��e�����[�N�Ǘ��E 18.6�N�C18�N�ł���B
�T�j�����ɂ͓������̖�肪����B�e�����[�N�_�~�[�̌W���|0.366�͉ߑ各�肩������Ȃ��B�e�����[�N�́i���j�����I�ɓ������ꂽ�O���ϐ��ɂ݂��邪�C�`���I�ɂ͖{�l���u�����I�Ɂv�I�����Ă���B���Ƃ��Ɩ����x�̍����J���҂��e�����[�N�I�����₷���C�Ƃ���Ήߑ�ɂȂ�̂ŏC������K�v������B�K�ȑ���ϐ���������K�v�����荡��̌����ۑ�ł���B
�U�j���Ȃ��Ƃ��呲�z���C�g�J���[�̃L�����A�ɂ����ẮC��̐E�\���ɂ����܂�B�E�\�̂Ȃ��̕����L����݂̂̈ٓ������肤��i���r�j�B�������ɑΏۂ��Ǘ��E�̏ꍇ�́C�ʂ̐E�\�̊Ǘ��E�Ɉڂ�P�[�X���o�Ă��悤�B�������C������u�[�l�����X�g�v�Ƃ��C��̐E�\�������u�X�y�V�����X�g�v�ƌĂԂ̂́C���������B�����J���s��ƊO���J���s��̋�ʂ��ӎ����C�u�X�y�V�����X�g�v�̕����]�E�\���������Ȃ�Ƃ����u�_�b�v������̂�������Ȃ��B�Ǘ��E�ɂ������Ă����C�ނ��땝�̍L���d����E�\���o�������ق����C�]�E�ɂ͗L���ł��낤�B
�u�I�g�ٗp�v�u�N�������v���C�䂪�����L�łȂ��C��i�����ʂɂ݂��邱�ƁC�䂪���ł�����ɂ���ẮC�]�E���������������ƂȂǂ́C�w��I���L���Y�����C�ʔO�̓��{�I�����́u�v�����݁v�͍������B�ꐶ�C���Ƃɋ߂�J���҂͂܂�ł��邱�Ƃ��i���S�ł́j�킩���Ă��Ă��C�J�g�o���̌���ɂ��ƂÂ��u�蒅���v�����߂���J��Ԃ���Ă����̂�������Ȃ��B���i2021�j�ɂ��C�u�Α��������Ȃ�C�J�g�o���ɂƂ��Ē����I�Ȑ��Y�������߂邱�Ƃ́C����̏�m����̂ɂƂ��Ă����炩�ł���i175�Łj�B�����m��Ȃ������ҁC�܂��͊�ƌo�c�҂������Ǝv����̂ŁC�u����v���ǂ̂悤�ȃv���Z�X���o�āC���s�����Čٗp�V�X�e���Ƃ��Ē蒅���Ă������̌��������߂��Ă���̂�������Ȃ��B�E���Љ�ɂ�����u�K�́v�Ř_����̂́C���`�����ɂȂ�₷���B
�[�l�����X�g�ƃX�y�V�����X�g�̃P�[�X�́C�u�I�g�ٗp�v�u�N������v�قǁC��ʂɂ́u�_�b�v�͍L�����Ă��Ȃ����C�\�͊J����OJT�Ɋւ���Ă���̂ŁC�u�_�b�v�u�v�����݁v����������Ȃ�̈Ӌ`�����邩������Ȃ��B
�y177�Łz

�y178�Łz
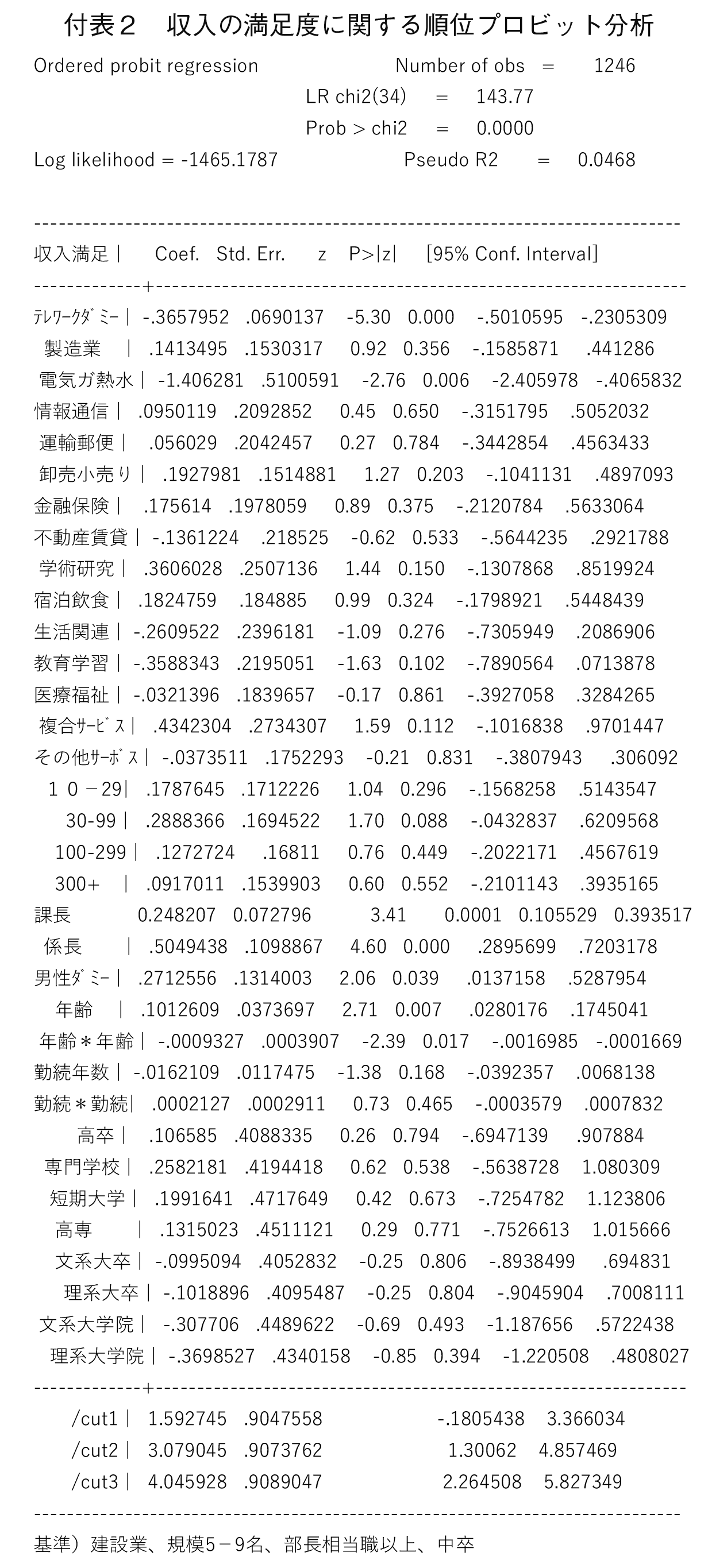
�y179�Łz
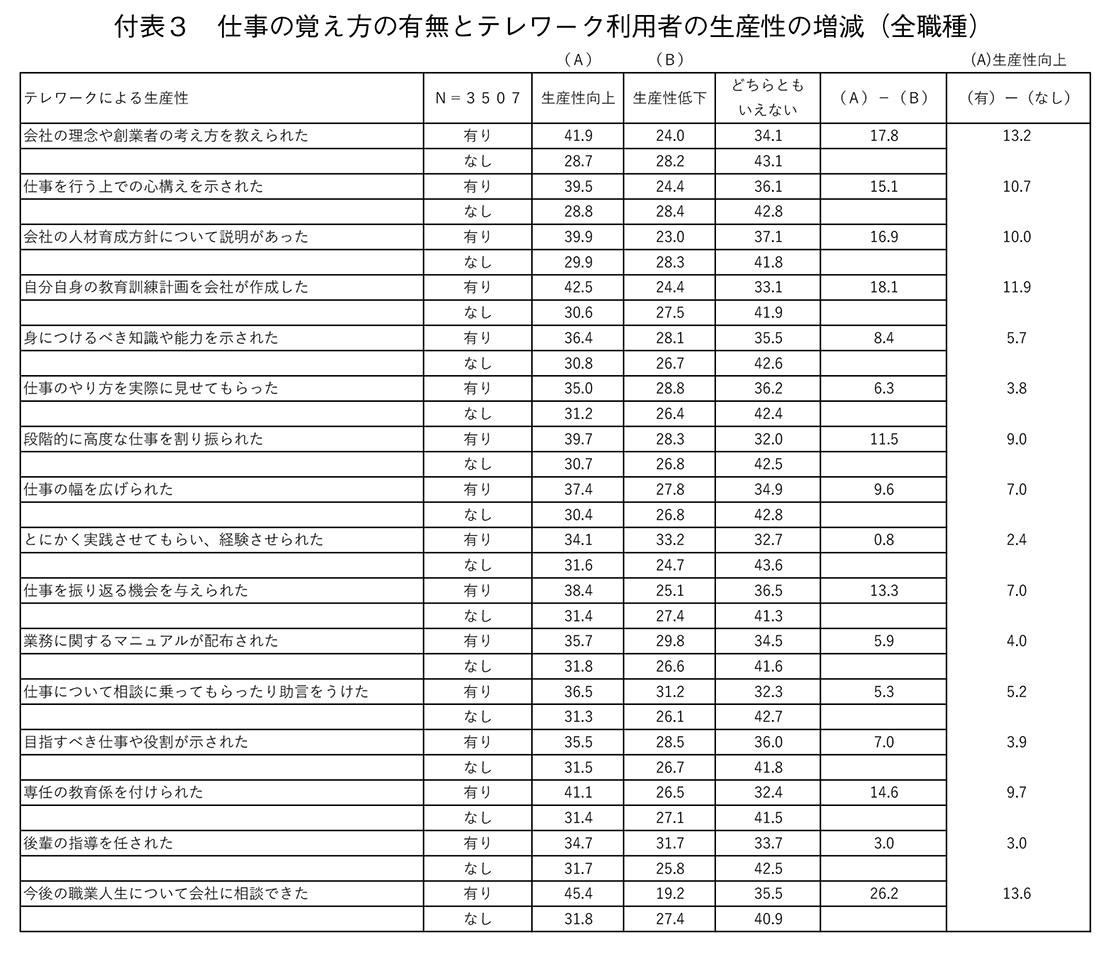
�y180�Łz
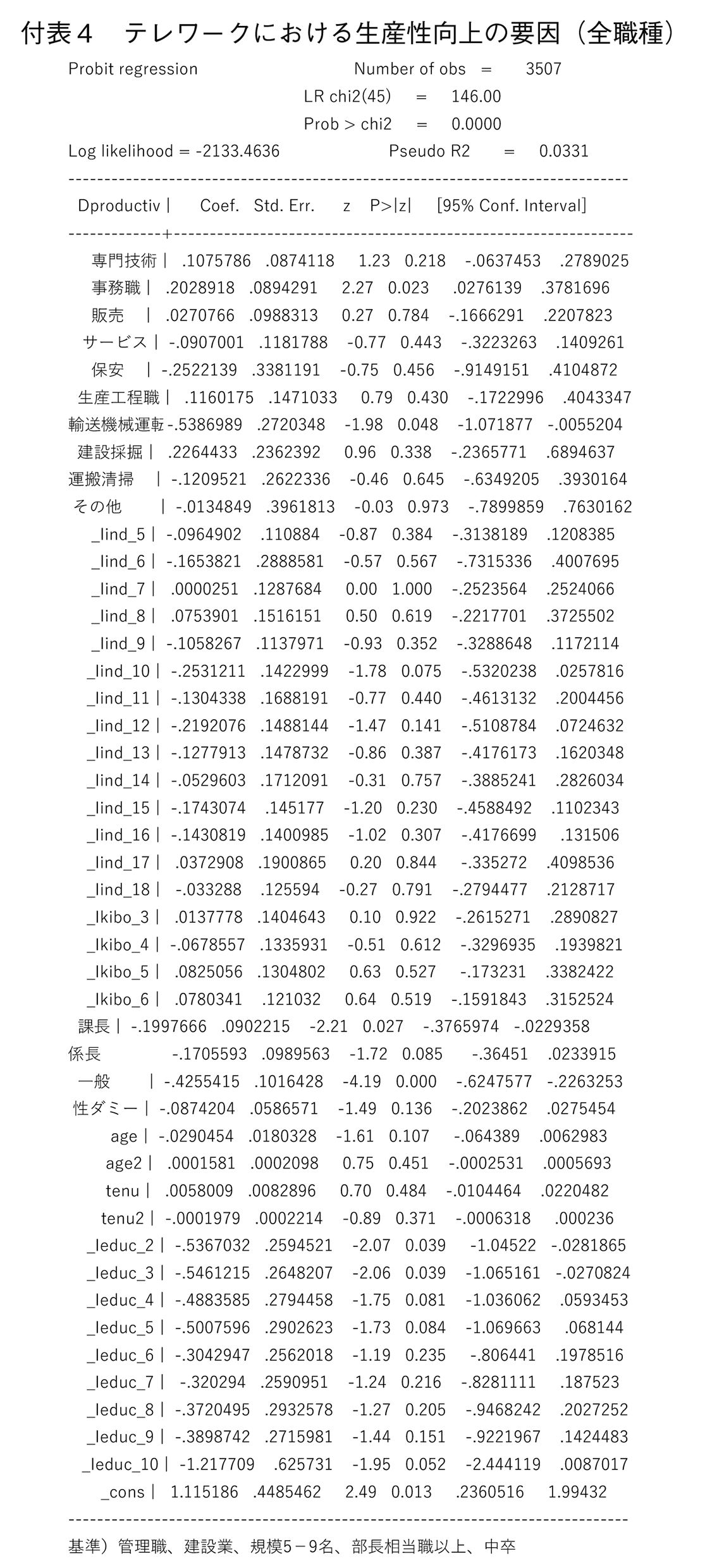
�y181�Łz
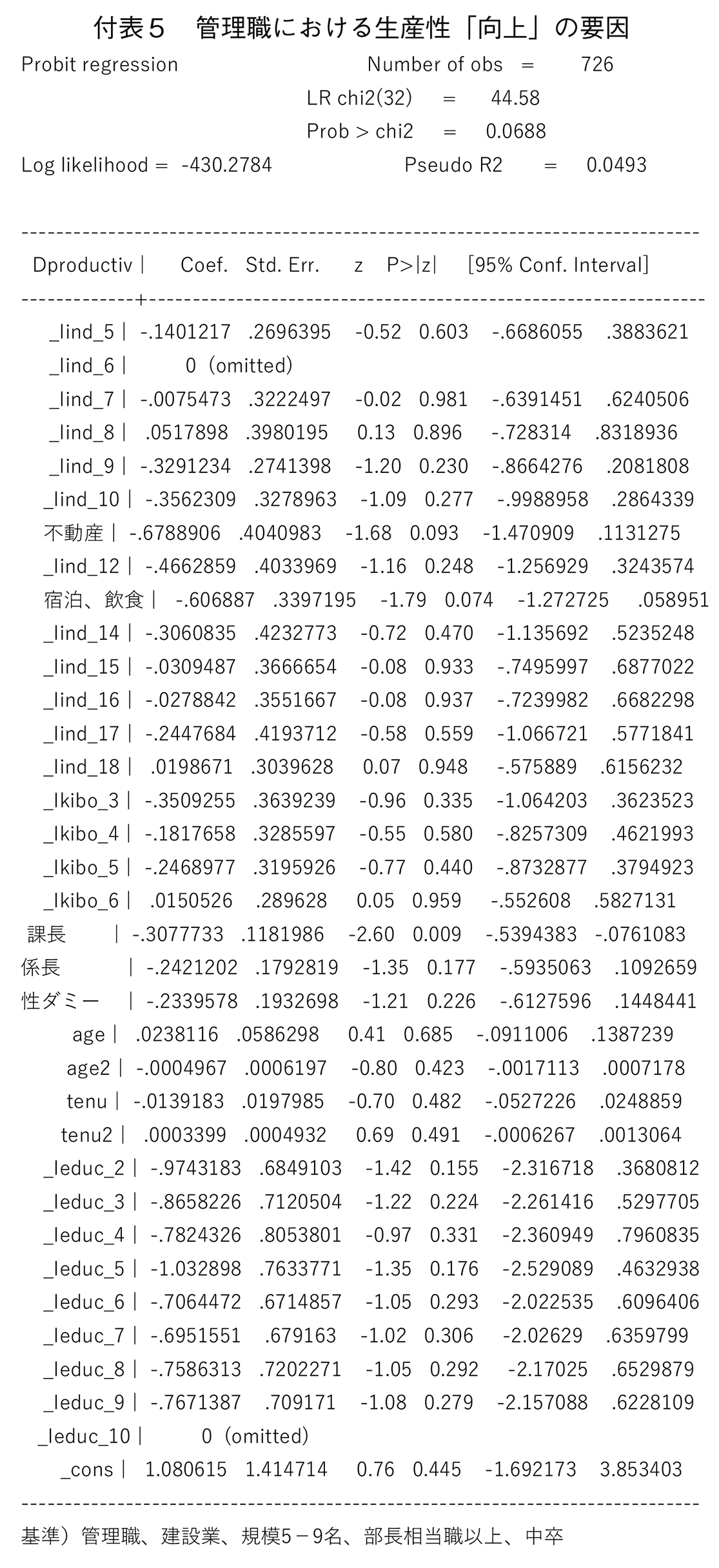
�y182�Łz