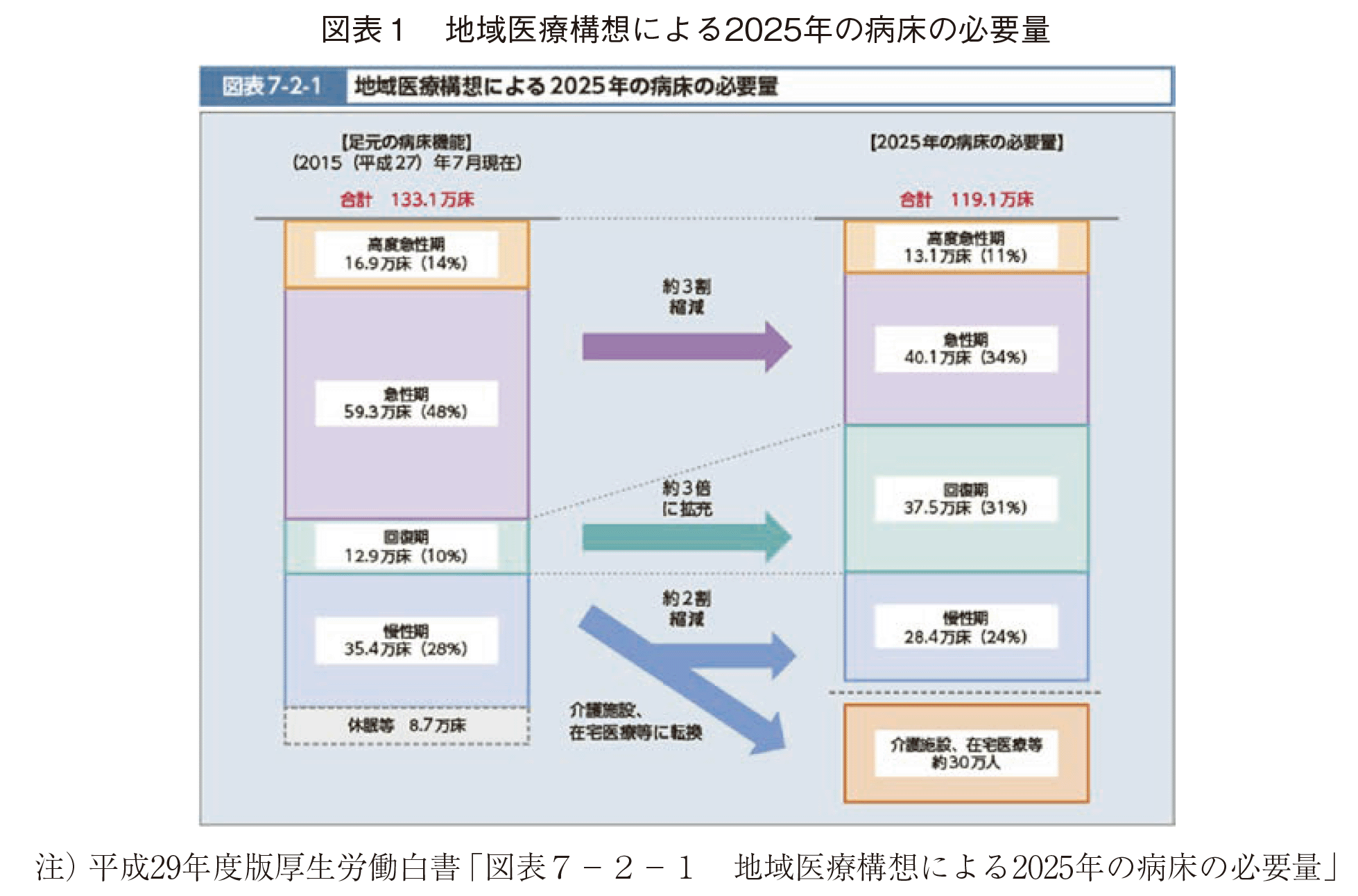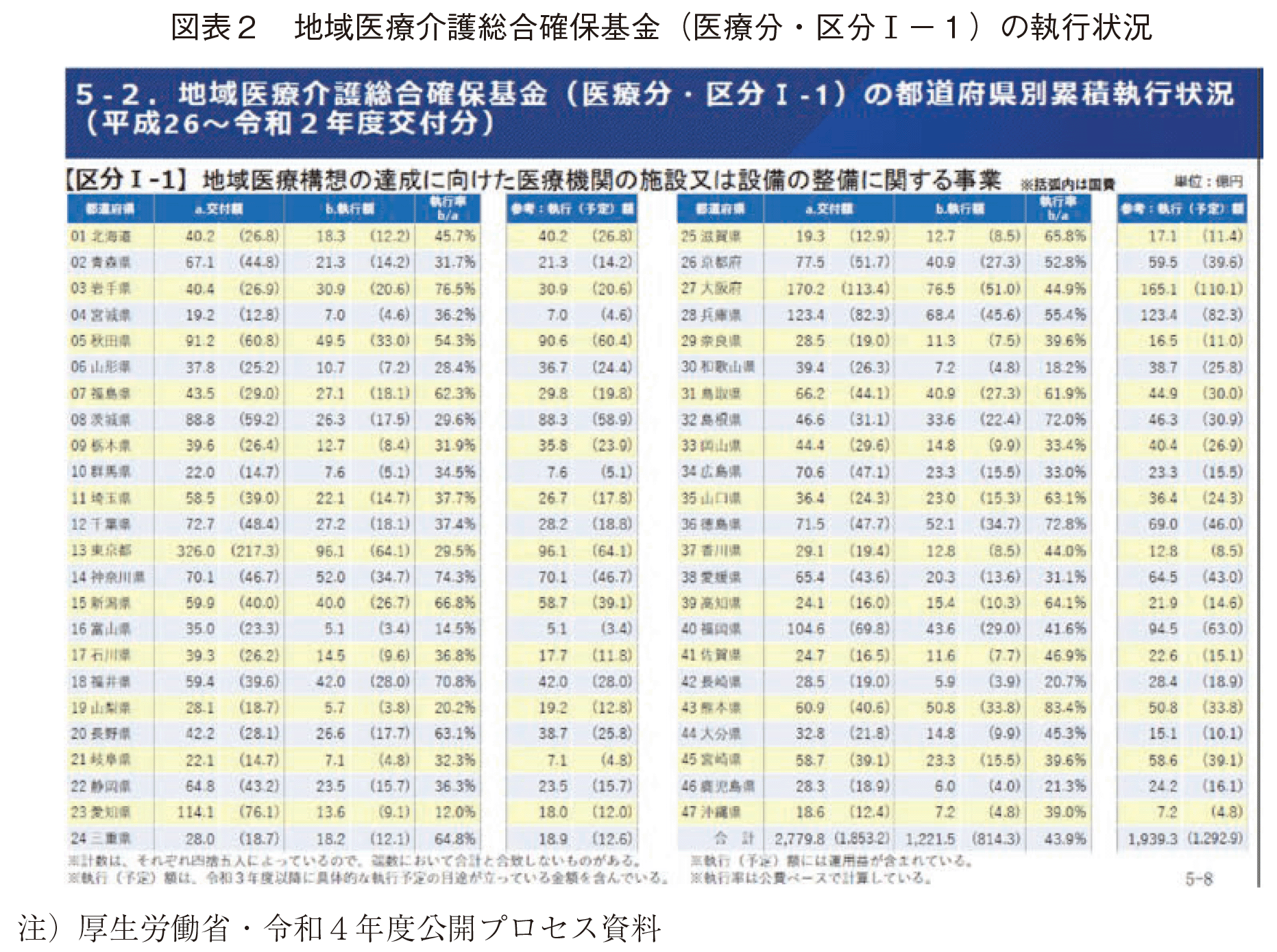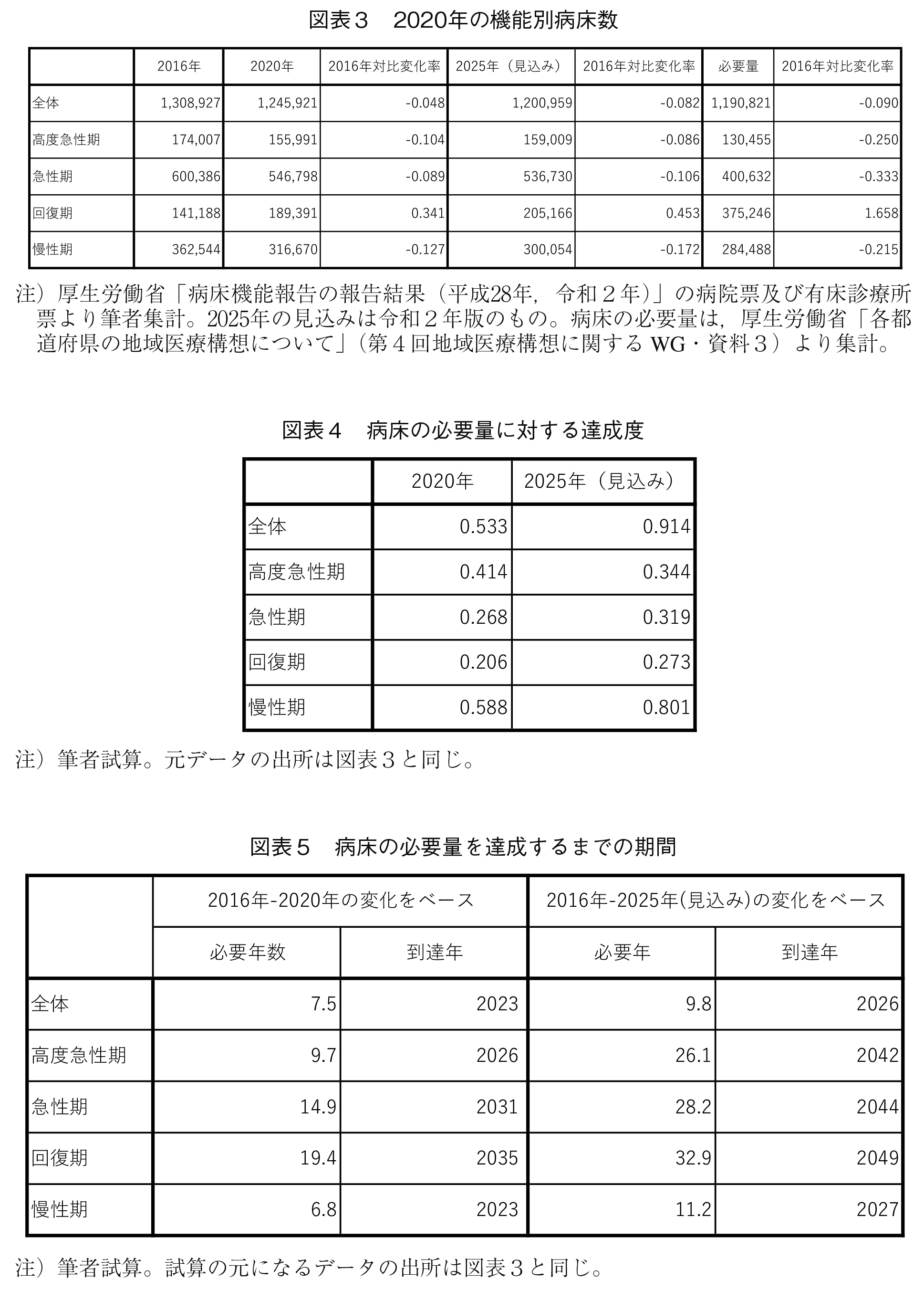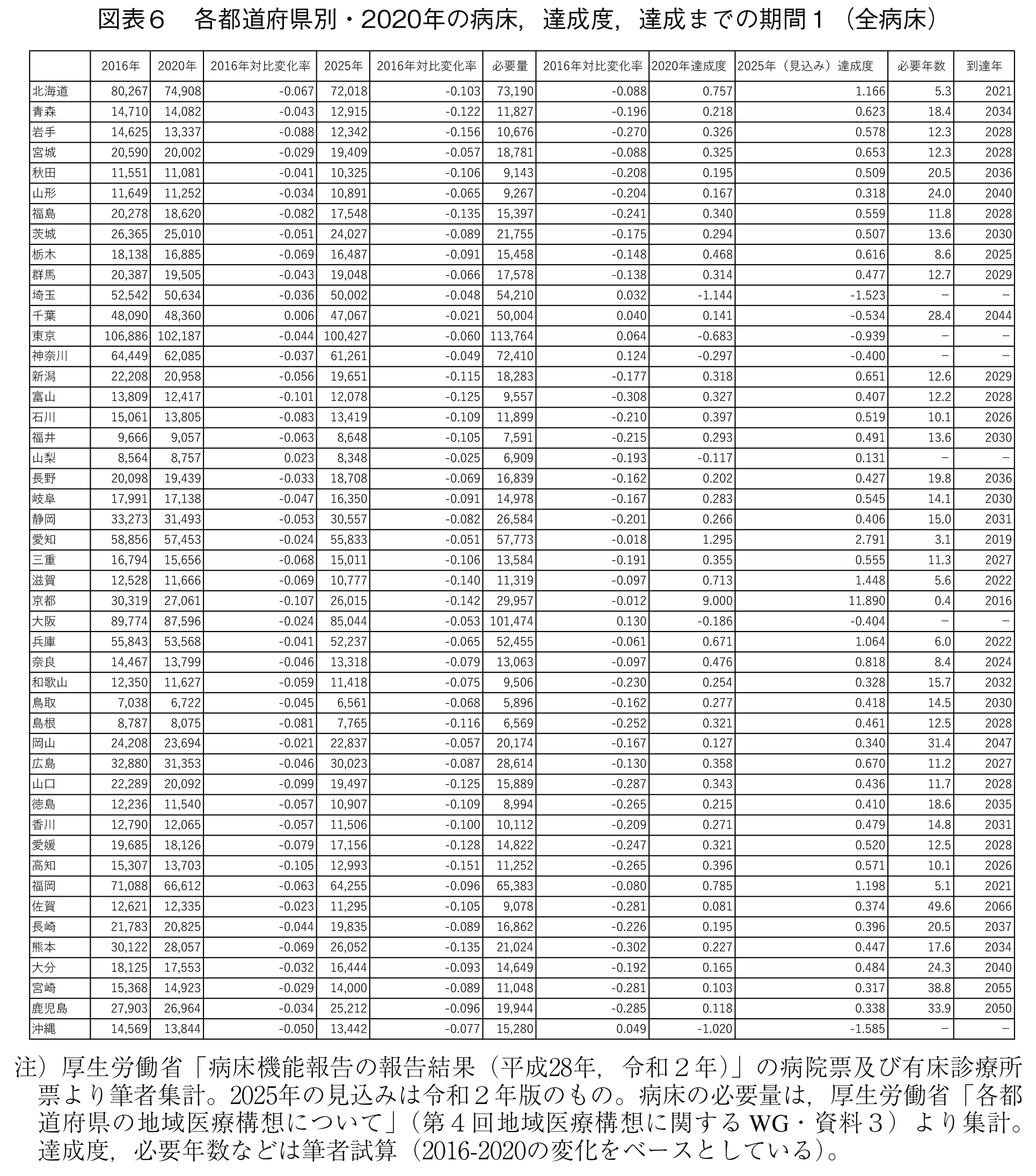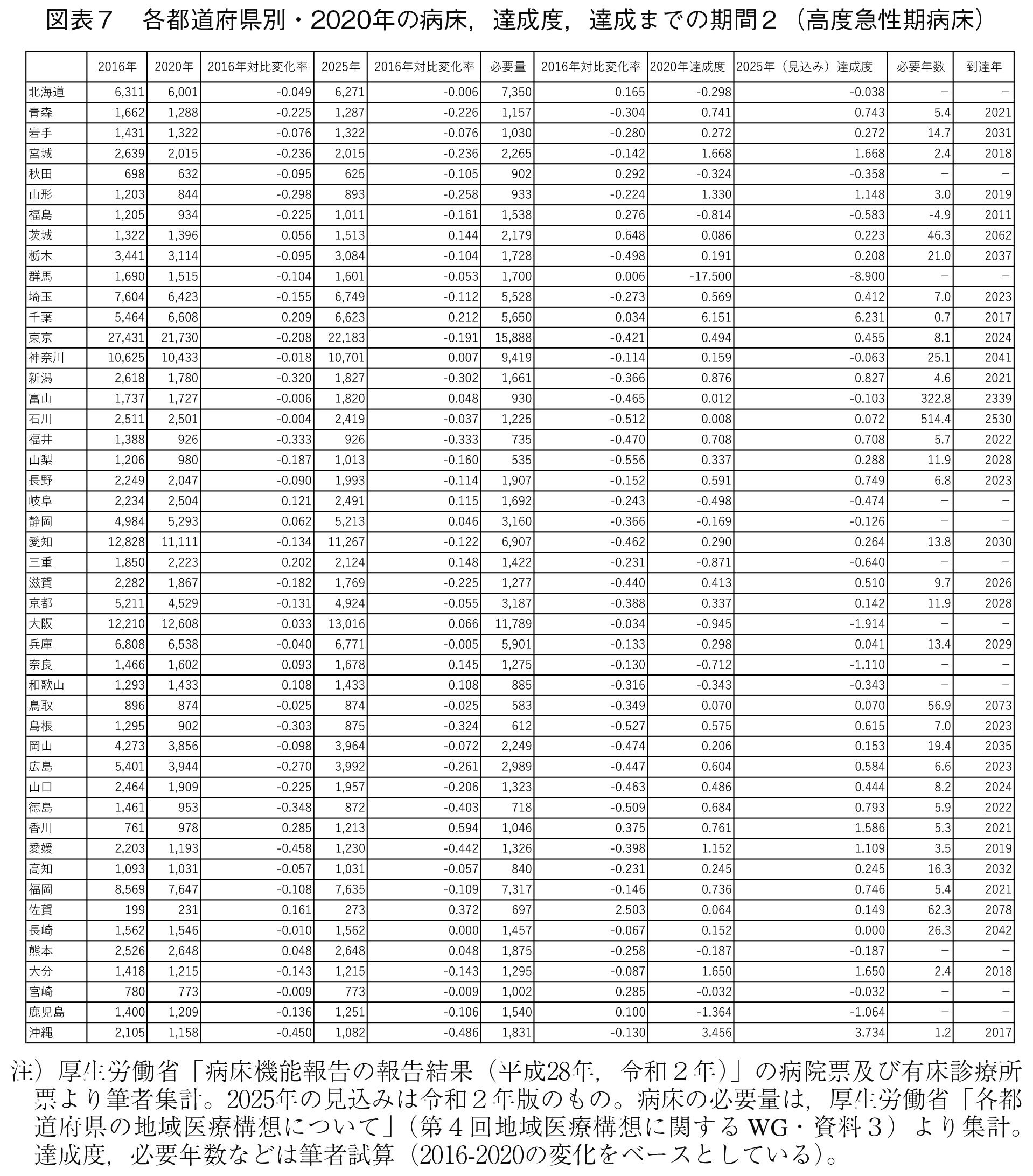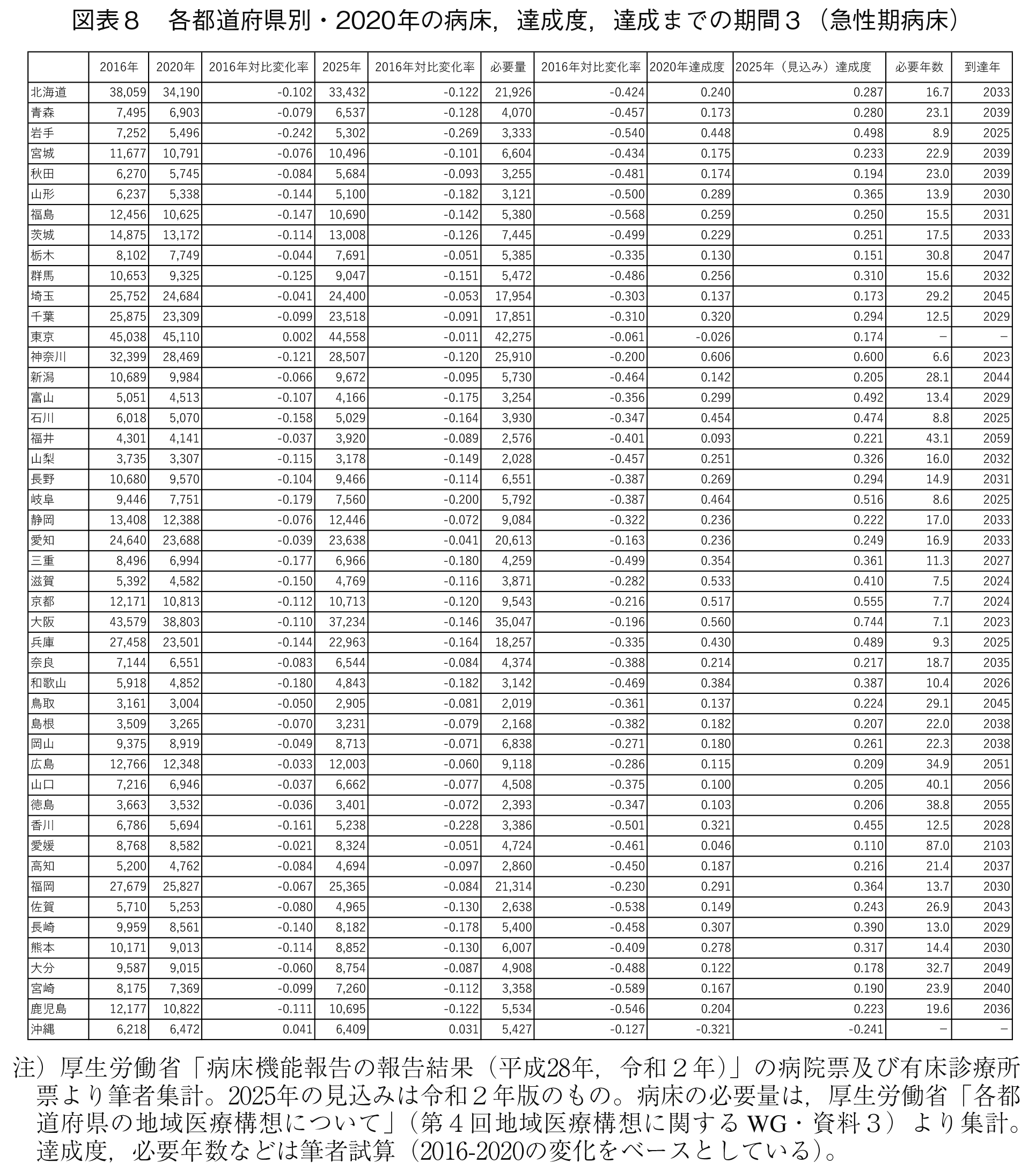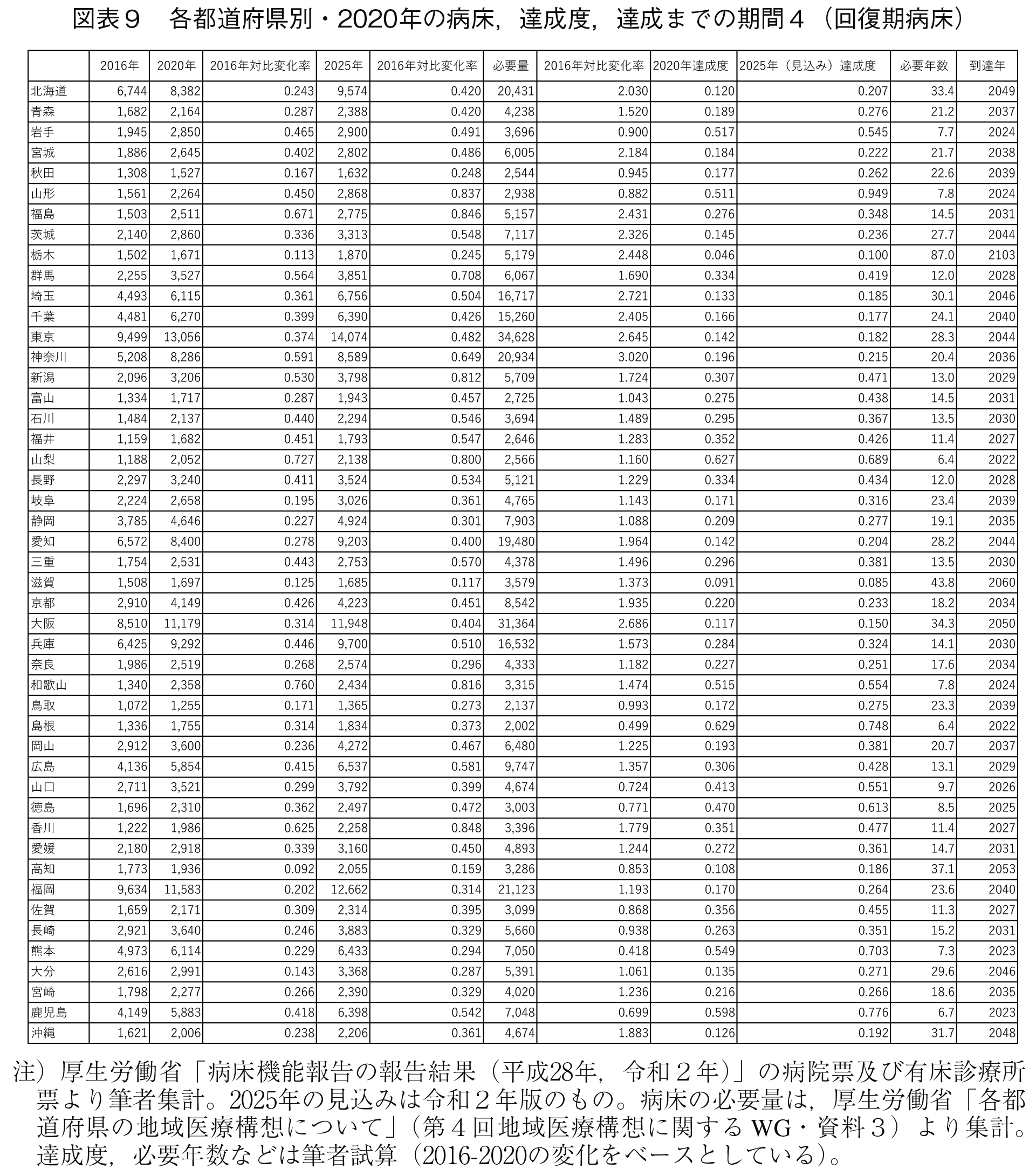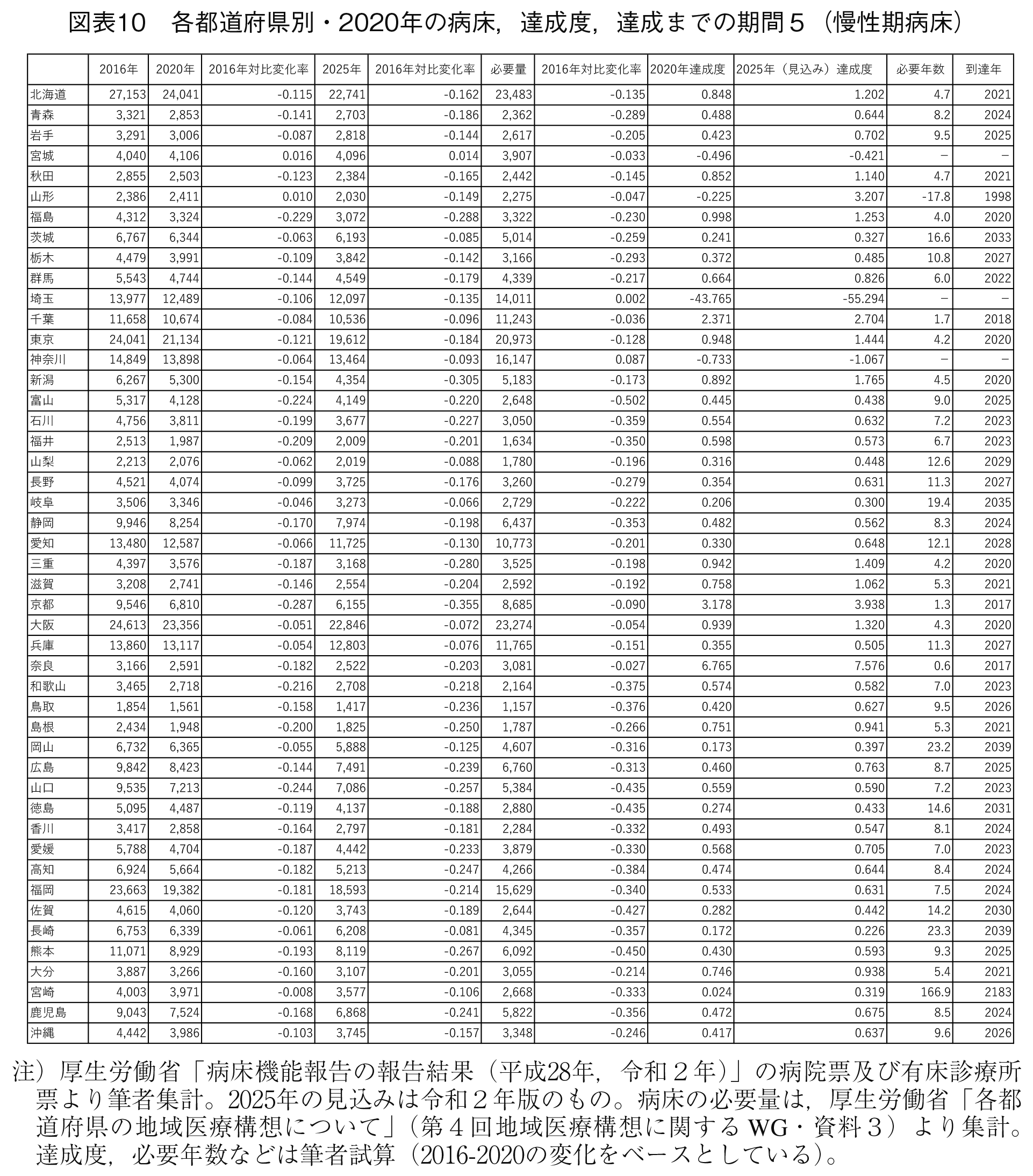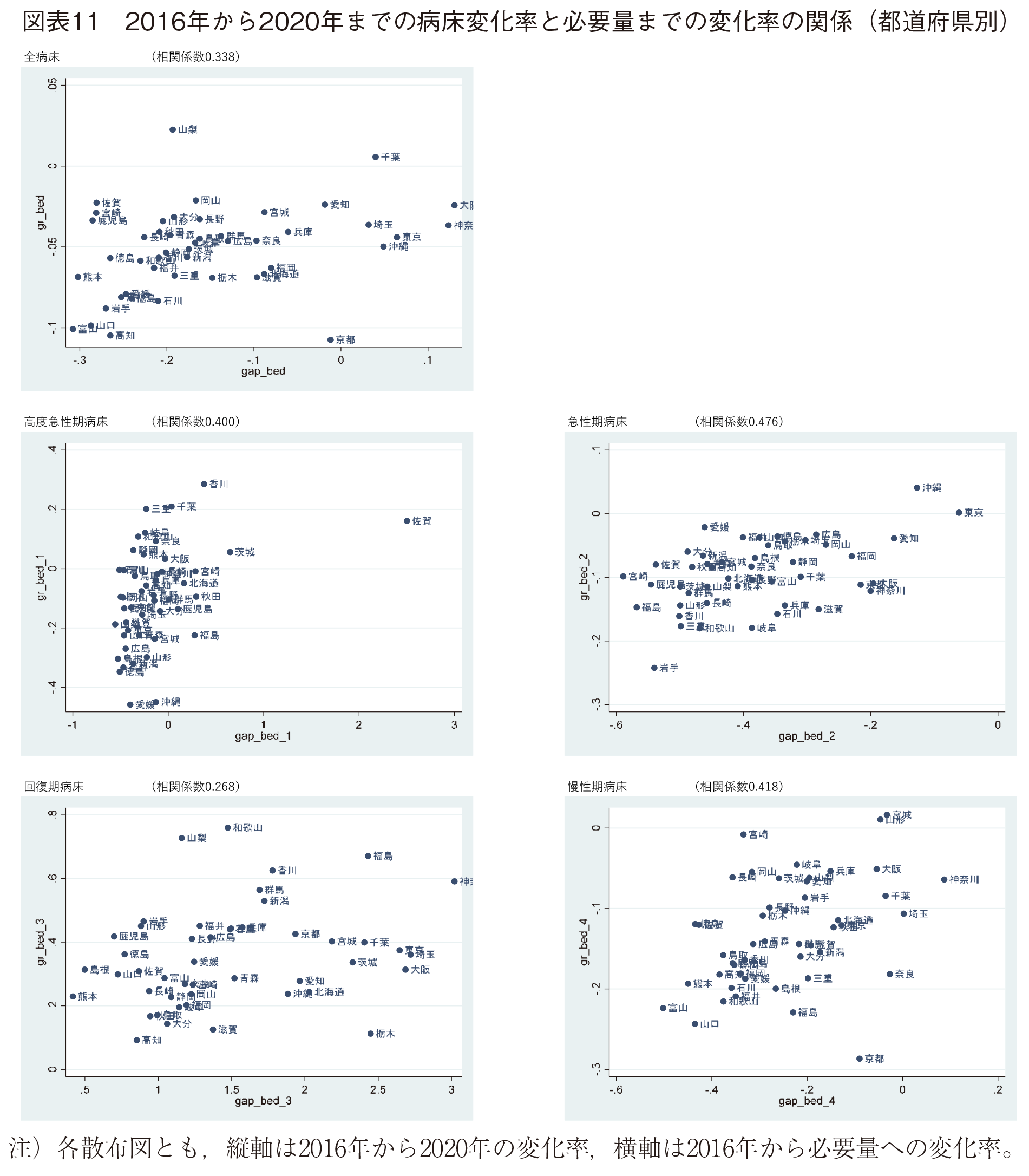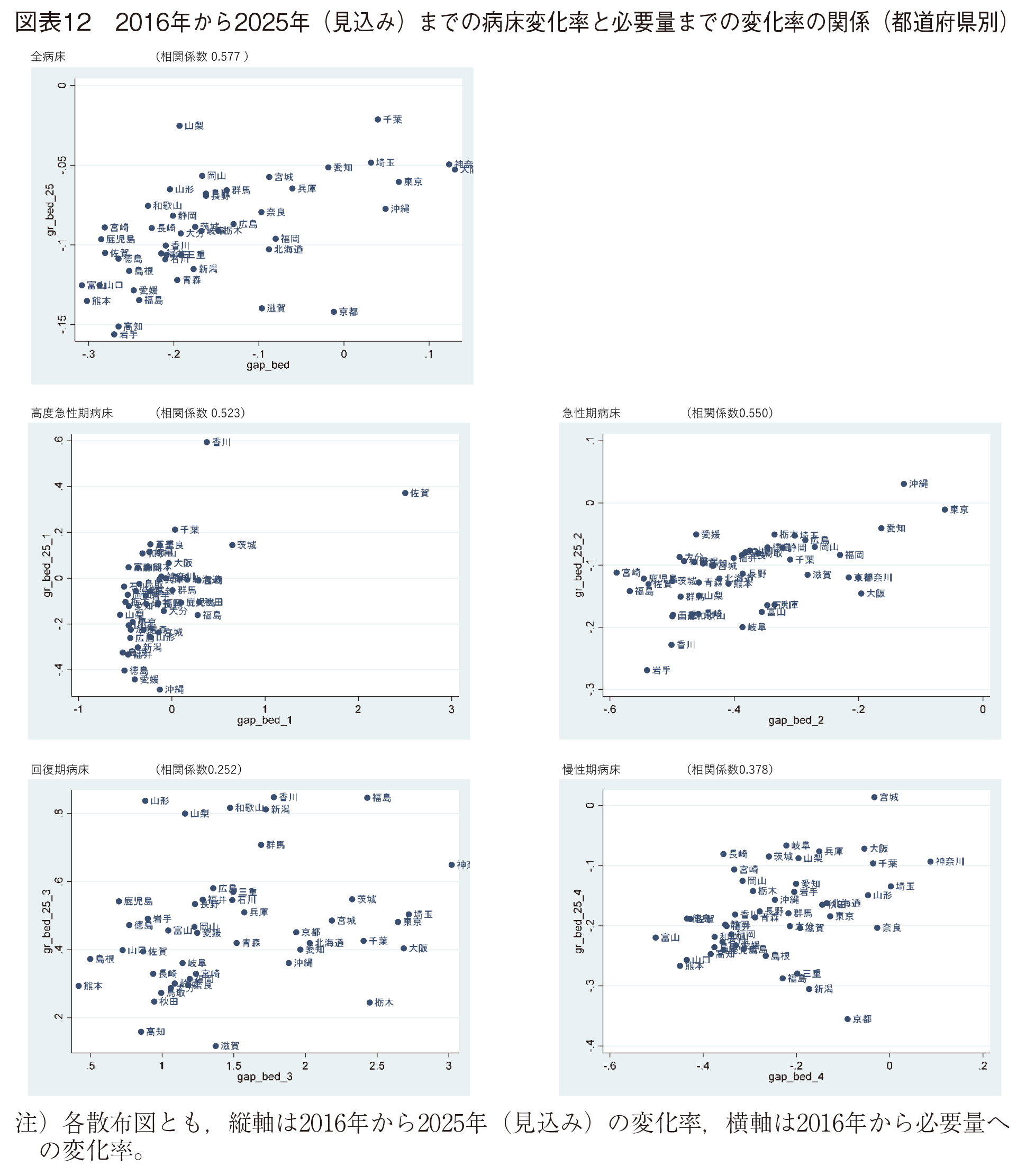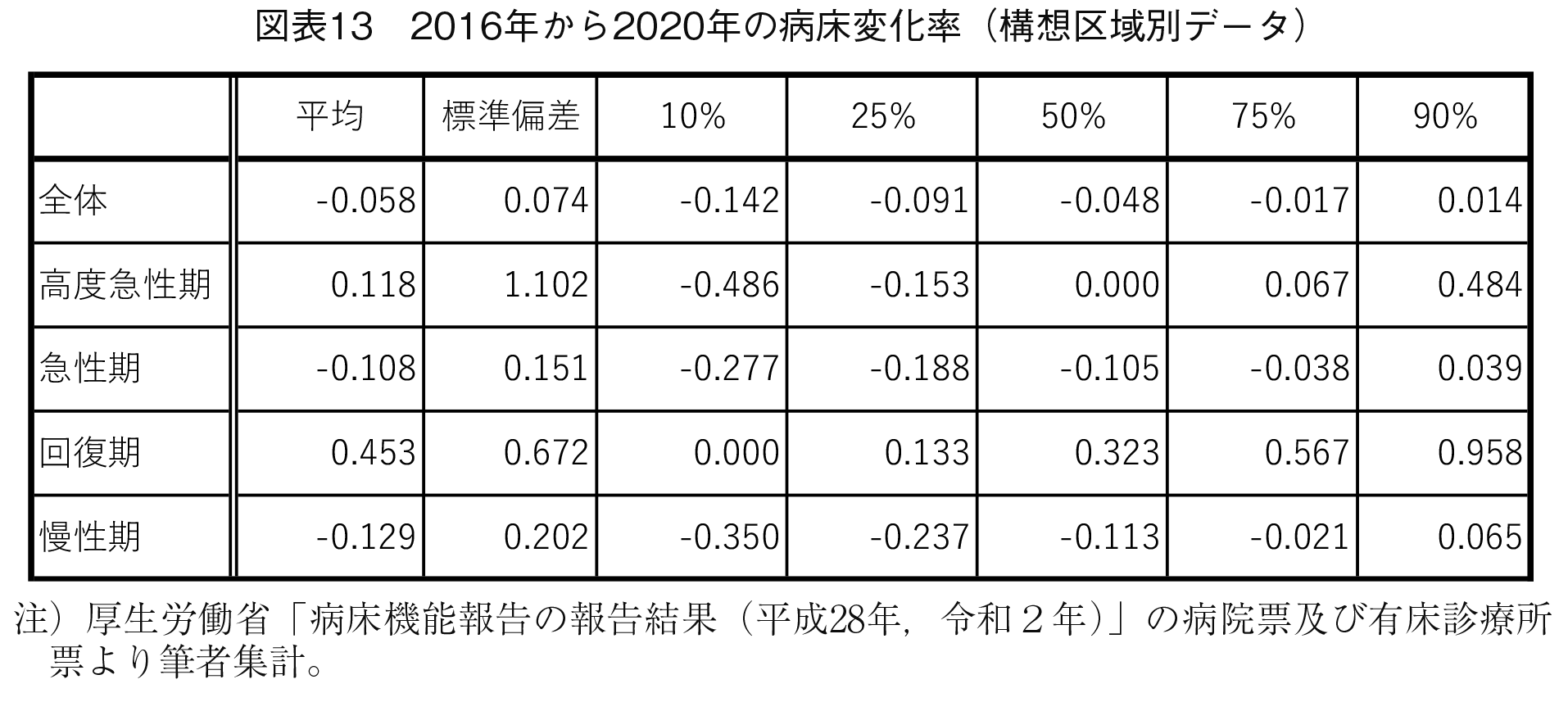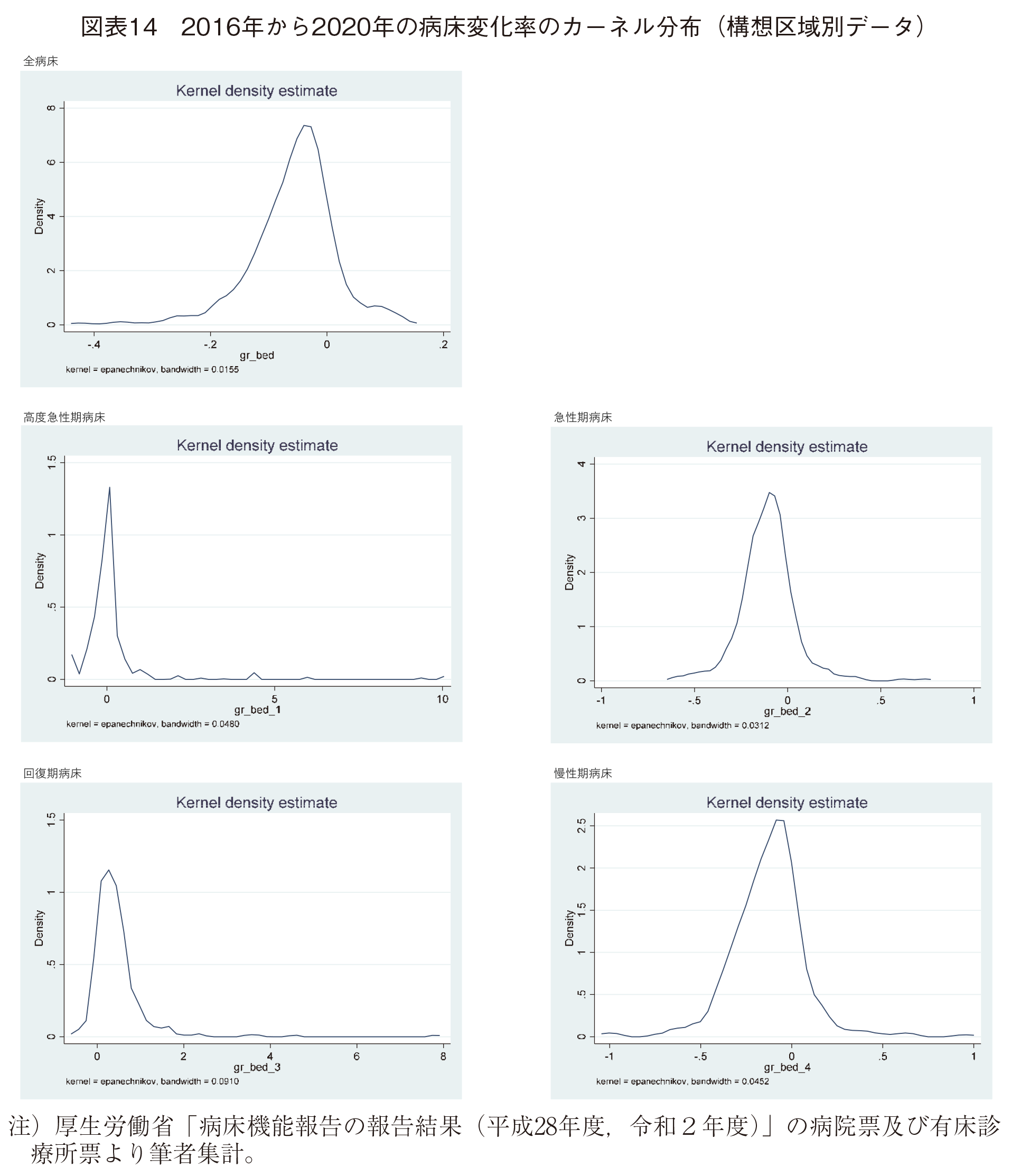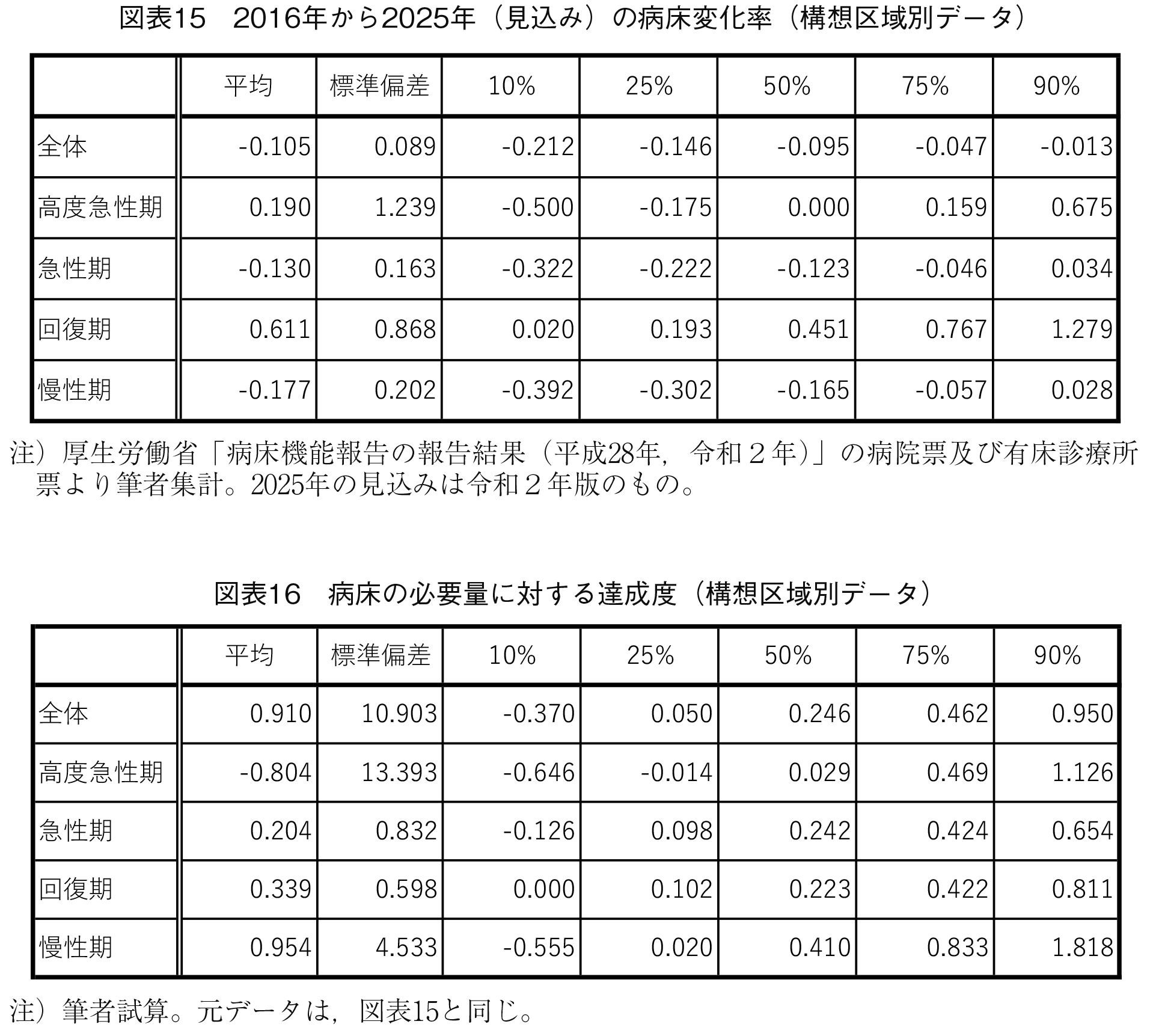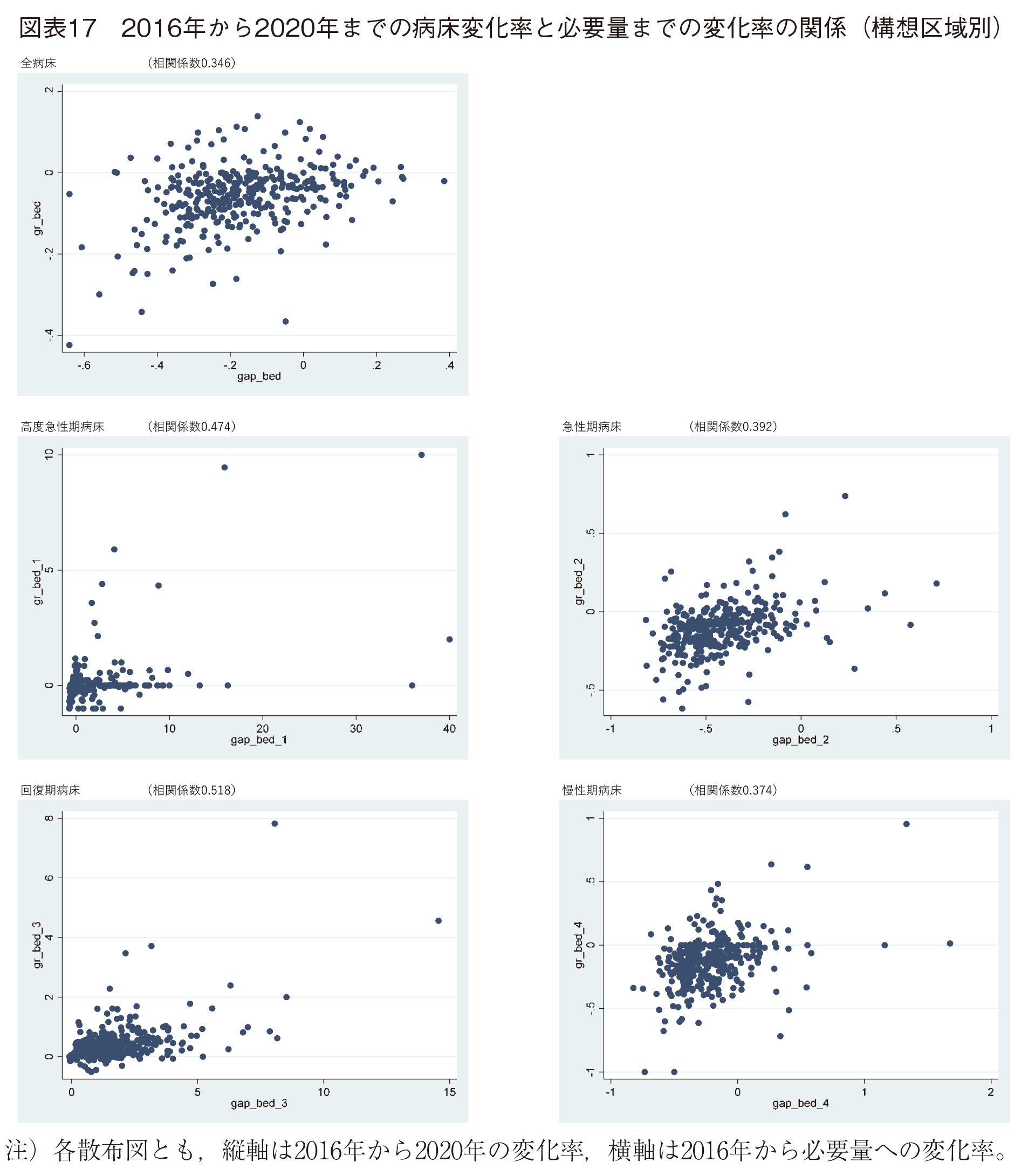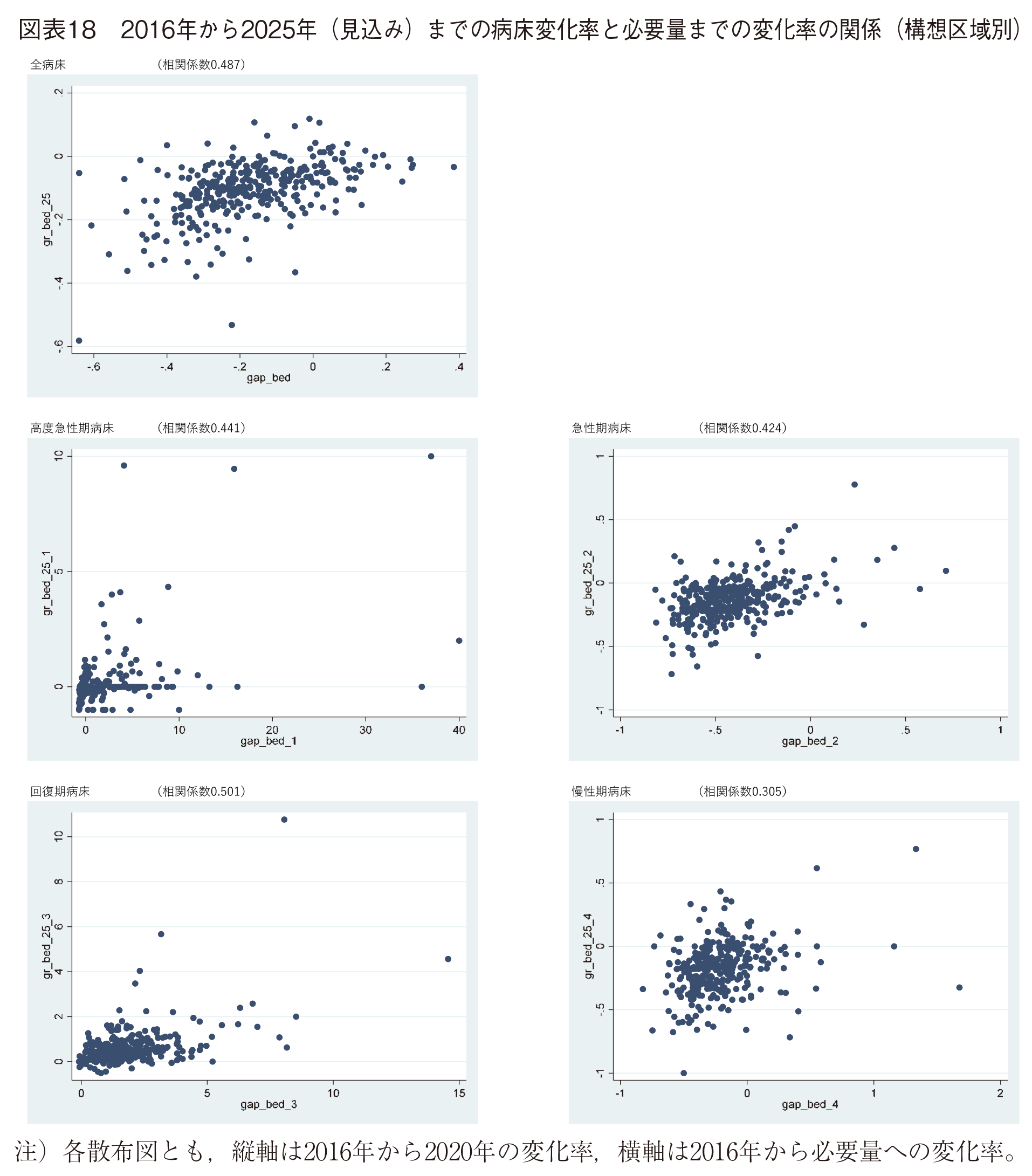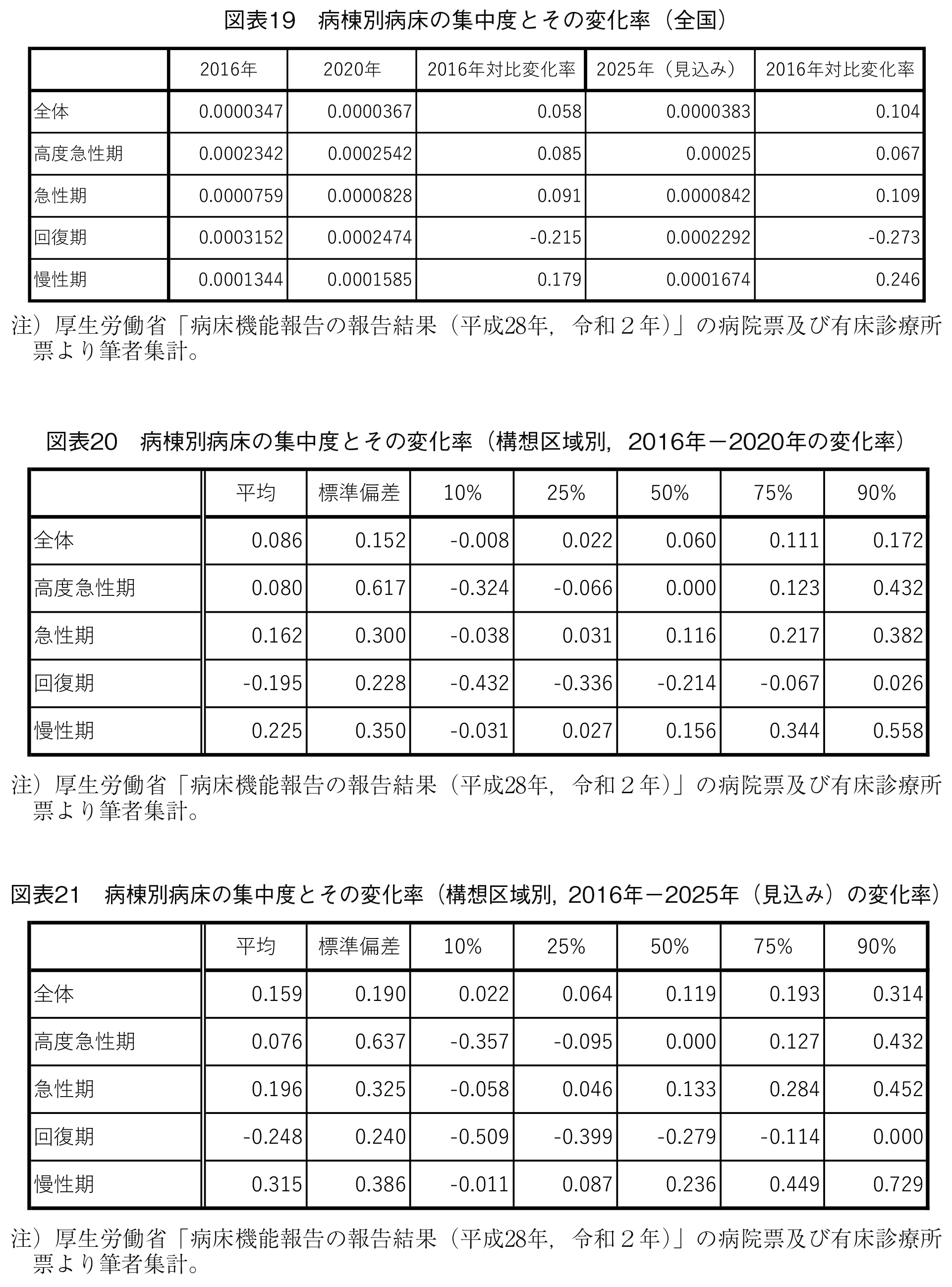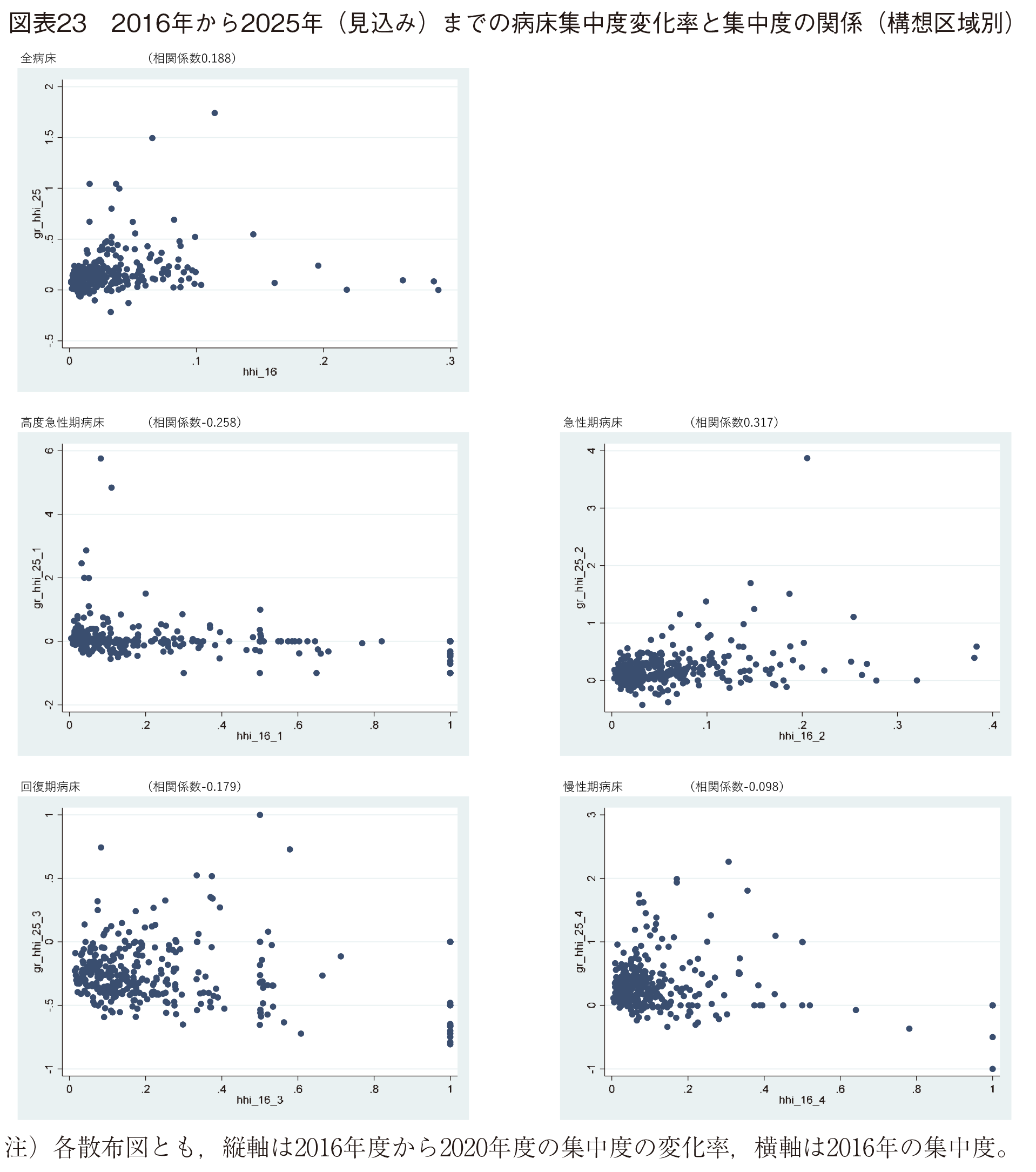�n���Í\�z�ɂ�����@�\�ʕa�����̕ω�
�\2016�N����2020�N�̕a���@�\�f�[�^�ɂ�錻�́\
��@�j
�{�e�́C�n���Í\�z�ɂ�����S�a��������ы@�\�ʕa�����̕ω��ɂ��āC2016�N��2020�N�̕a���@�\�̌[�f�[�^��p���Č��͂��s�����B��̓I�ɂ́C�\�z�n�悲�Ƃɐ��v���ꂽ�a���̕K�v�ʁi�K�v�a�����j�ɁC�ǂ̒��x�C2020�N�̕a������2025�N�i�����݁j�̕a�������߂Â��Ă��邩�Ƃ����ϓ_����]�����s�����B�܂��C�e�\�z�n��̕a���̏W���x�i�a���a�����̃n�[�V���}���E�n�[�t�B���_�[���w���j��p���āC�a���̏W���i��ł��邩�ǂ����������B
�܂��C�S���ɂ�����2020�N�̊e�@�\�ʕa������2016�N�Δ�ł݂�ƁC�S�a����4.8���̌����C���x�}�����a����10.4�������C�}�����a����8.9�������C���a����34.1�������C�������a����12.7�������ƂȂ��Ă���C���ꂼ��̕a���̕K�v�ʂɌ����Ă���ׂ������ɐi�����Ă��邱�Ƃ��킩��B2025�N�i�����݁j�ɂ́C���x�}�����a���������C����ɐi��������\��ł���B�������Ȃ���C�a���̕K�v�ʂƂ̊Ԃɂ͂܂��傫�Ȋu���肪����B2020�N�ɂ�����S�a���̖ڕW�B���x��53.3���Ɣ��������x�ł���C���x�}�����a���C�}�����a���C���a���C�������a���́C���ꂼ��41.4���C26.8���C20.6���C58.8���̒B���x�Ɏ~�܂�B2025�N�i�����݁j�ɂ��ẮC�S�a���̒B���x��91.4���܂Ŕ�����̂́C���x�}�����a���C�}�����a���C���a���̒B���x��34.4���C31.9���C27.3���ƁC�ˑR�C�a���̕K�v�ʂ���傫�����������܂܂ł���B
���l�̕��͂�s���{���ʁC����ɍ\�z�n��ʂɃu���[�N�_�E�����čs���Ă݂�ƁC���R�̂��ƂȂ���C�e�n��̕ω�����B���x�ɂ͑傫�ȃo���c�L�������Ă��邱�Ƃ��킩��B�����C2016�N���_�ŕa���̕K�v�ʂƂ̘������傫���n��قǁC���̌�̕ω����傫���Ȃ�Ƃ����X�����C�ア���ւȂ�����m�F�ł��C�����I�ɂ͖ڕW�Ɏ��ʂ��Ă䂭�X��������������B
�܂��C�a���̏W���x�Ɋւ��ẮC2016�N����2020�N�ɂ����āC�S�a���C���x�}�����a���C�}�����a���C�������a�������܂��Ă������C���a���̏W���x�͒Ⴍ�Ȃ��Ă��邱�Ƃ��킩�����B����́C�n���Í\�z����}���Ă���������ƁC�T�ː����I�ȓ����Ɖ��߂ł���B
�n���Í\�z�C�@�\�ʕa���C�a���K���C��É�쑍���m�ې��i�@
�R���i�Ђɂ����Ă������Ζ��ƂȂ����悤�ɁC�䂪���̈�Ò̐��͗l�X�ȍ\���I��������Ă���B��P�ɁC�l��������̕a������OECD�����̒��ōł��������̂́C���ΓI�Ɉ�t��Ō�t�̔z�u�����Ȃ����߁C�S�̂Ƃ��Ēᖧ�x��ÂɊׂ��Ă���ƌ�����B��Q�ɁC��Ë@�ւ̋@�\�ʕa���̓�����݂�ƁC�}�����a���̊��������Ȃ荂���C���̒��ɂ́C�����a�@�𒆐S�ɁC���ۂɂ͋}�����̊��҂������邱�Ƃ�����u�Ȃ���ċ}�����a��1�j�v�ƌ�������̂����Ȃ��Ȃ��Ƃ����B��R�ɁC�䂪���Ɠ��̃t���[�A�N�Z�X�Ƃ������x�Ƒ��܂��āC���O���ɔ�ׂāC��Ë@�֊Ԃ̋@�\������������S�C�A�g�W�����m�Ŗ����C�a�@�E�a���̏W�����܂�i��ł��Ȃ��B��S�ɁC�n��ʂ̈�t���Ë@�ւ݂̕��������C���ɒn���ɂ����Ă͈�t�s���C�a�@�s�����[�������Ă���n�悪����B����C�n��Ԃ̐l�������⍂��ɔ�����Â̎���ʂ̕ω��ɔ����āC���������\�����͂܂��܂��[�������邱�Ƃ��\�z�����B���̂��߁C���{�́C2014�N�Ɉ�É�쑍���m�ې��i�@�𐧒肵�C�e�n��̒���2025�N�x�܂łɓK�Ȉ�Ò̐��̍\�z��ڎw���u�n���Í\�z�v�ɒ��肵�Ă����̂ł���B
�������Ȃ���C�n���Í\�z�̐i�W�́C�ꕔ�̒n��������āC�S�̓I�ɂ��܂�F�������̂Ƃ͌����Ȃ��B�܂��C2020�N�͂��߂���́C�V�^�R���i�E�B���X�iCOVID-19�j�̃p���f�~�b�N���n�܂�C����Ɏ{���i�߂邱�Ƃ�����ƂȂ��Ă���B�����Ƃ��C�n���Í\�z�̖ڕW�ł���2025�N�x�͂��͂�ڑO�ɔ����Ă���C2024�N�x����͒n���Í\�z��O��Ƃ�����W����Ìv����n�܂邱�Ƃ���C�n���Í\�z�̐��i�̂��߂Ɏc���ꂽ���Ԃ͂��܂�ɏ��Ȃ��B�܂��́C�������������Ɣc���E�]�����C�n���Í\�z�����ԓ��ɏ����ł��{���i�������邽�߁C���{�I�ɐ헪����蒼���K�v�����邾�낤�B
�����ŁC�{�e�́C���̒n���Í\�z�̌���c���Ɏ����邽�߁C�[�f�[�^������\��2016�N����2020�N�܂ł̋@�\�ʕa�����̕ω��͂��C���̎��_�܂ł̐i���̕]�������݂�B�������C�n���Í\�z�̐����ړI�͋@�\�ʕa�����̕ω������ł͂Ȃ��C��ڂ̂Ȃ���Ò̐��̍\�z�Ȃǂɂ�����̂Łi�������c�i2017�j�C�O���i2020�j�j�C�{�e�̕��͂����Œn���Í\�z�̑����I�]�����s�����ƌ�������͂Ȃ��B�{�e�ł́C�@�e�n��Œ�߂�2025�N�̕a���̕K�v�ʁi�K�v�a�����j�ɑ��āC�e�n�悪�߂Â��Ă���̂��C�߂Â��Ă���Ƃ���ǂ̒��x�i�����Ă���̂��C�A��Ë@�֊Ԃ̋@�\������������S�ƊW����@�\�ʕa���̏W���ǂ̒��x�i��ł���̂��C�Ƃ����Q�_�ɍi���Č���]�������݂�B
�ȉ��C�Q�߂ł́C�n���Í\�z�ɂ��ĊT������B�R�߂ł́C�{�e�ŗp����@�\�ʕa���̌[�f�[�^�ɂ��Đ�������B�S�߂ł́C2016�N�x����2020�N�x�C���邢��2025�N�x�i�����݁j�܂ł̕a�����ω��ɂ��ĕ��͂�i�߂�B�T�߂ł́C�����Ԃɂ��ĕa���̏W���x�̕ω��͂���B�U�߂͑S�̂̂܂Ƃ߂ł���B
���ɏq�ׂ��悤�ɁC�n���Í\�z�́C2014�N�U���ɐ���������É�쑍���m�ې��i�@�ɂ���Đ��x�����ꂽ�{��ł���B�����l�����v�����Ƃ�2025�N�ɕK�v�ƂȂ�a�����i�a���̕K�v�ʁj���S�̈�Ë@�\���Ƃɐ��v������ŁC�e�n��̈�ÊW�ғ��̋��c��ʂ��ĕa���̋@�\�����ƘA�g��i�߁C�����I�Ȉ�Ò̐����������邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B��É�쑍���m�ې��i�@�̐������C�����J���Ȃ�2015�N�R���Ɂu�n���Í\�z����K�C�h���C���v���߂Ă���C����ɏ]���āC2016�N�x���ɑS�Ă̓s���{���ŁC�e�n���Í\�z�����肳�ꂽ�B�܂��C�����͊e�s���{���ɂ���āC2018�N�S������n�܂�����V����Ìv��̒��Ɉʒu�Â����Ă���2�j�B
��̓I�ɁC�n���Í\�z�ł́C��Ì�����{�ɑS����3393�j�̍\�z����ݒ肵�C�\�z��悲�Ƃɍ��x�}�����C�}�����C���C�������̂S�̈�Ë@�\���Ƃ̕a���̕K�v�ʂ𐄌v���Ă���B�}�\�P�́C�e�\�z���Ő��v���ꂽ�a���̕K�v�ʁi�K�v�a�����j��S���̃x�[�X�ɏW�v���C2015�N�̋@�\�ʕa�����̏W�v�l�Ɣ�r�������̂ŁC����29�N�x�����J����������]�ڂ��Ă���B�S���x�[�X�ł݂āC���x�}�����Ƌ}���������킹���a�������R�����x�k���������C���a���͖�R�{�Ɋg�[����K�v�����邱�Ƃ��L����Ă���B�܂��C�������a������Q�����x�k�����C�S�̂̕a�������P�������x�k������K�v����������Ă���B
���̖ڕW���������邽�߂̎d�g�݂��C�n���Í\�z������c�ł���C�e�n����̈�ÊW�҂�s���W�ҁC�L���ғ�����\�������B������c�ł́C�e��Ë@�ւ�����I�ɑI������a���@�\���x�Ɋ�Â��C�e�N�̌���a������2025�N�̕a���̕K�v�ʁC��Ìv��ł̊�a���������Q�l�ɁC�a���̒n��݂�C�]��܂��͕s���������܂��@�\�𖾂炩�ɂ��C�W�ҊԂŒn��̎����L�����B�����āC�����̃G�r�f���X�����ɁC�W�ҊԂ̋��c�ɂ���č\�z���ɂ�����ۑ���������C2025�N�̂���ׂ���Ò̐��̍\�z��ڎw���̂ł���B
�������Ȃ���C�����ɂ͒n���Í\�z�̐i�W�͂͂��������Ȃ��B���̗��R�́C������c���\�z��悲�Ƃ̖ڕW�ɋ߂Â��Ă䂭���߂̎�i���C�����ς�W�ғ��m�̘b�������ɂ䂾�˂Ă��邩��ł���B�p�C���g�債�Ă䂭����ł���Ƃ������C�k�݂䂭����̍��ӌ`���E���Q������b�����������ōs�����Ƃ����̂́C�����������܂茻���I�Ƃ͌����Ȃ��i��i2017�C2020�C2021�j�j�B�������C�}�����a�������a���ɓ]������ۂɂ́C���z����x�̕⏕�����o��d�g�݁i�n���É�쑍���m�ۊ���̈�Õ��E�敪�T�|�P�̎��Ɓj�����邪�C�o�ϓI���@�Â��Ƃ��Ă͎キ�C�\���Ƃ͌����Ȃ�4�j�B���ۂɁC����̗\�Z�ɑ��鎷�s�͖����ɂ��Ȃ�Ⴂ�ł���i�}�\�Q�j�B�܂��C��Ë@�ւ̐V�K�J�݂���Ɋւ���s���{���m���̌���������������C���ɂ�鏕����W���I�����x��������d�_�x�����̐ݒ�C�����a�@�̓����ĕ҂̓������s������Ȃǂ̏��{����s���Ă������C�Ȃ��Ȃ���ؓ�ɂ͐i�܂Ȃ��y294�Łz �̂�����ł���B
���āC�{�e�ł͒n���Í\�z�̐i���̕]���ɂ������āC��ɁC�a���̕K�v�ʁi�@�\�ʕa���̕K�v�ʂ���ёS�a���̕K�v�ʁj�ƌ���i2020�N�����2025�N�����݁j�̔�r���s�����Ƃɂ���B�������C�a���̕K�v�ʂ𐭍��ڕW�Ƃ��Č��ėǂ����ǂ����ɂ��Ă͈٘_�̂���Ƃ��낾�낤�B�a���̕K�v�ʂɒB���邽�߂ɂ́C�����̓s���{����\�z�n��ɂ����đS�a������}�����a���������팸����K�v�����邪�C�����J���Ȃ͕a���팸�������ڕW�ł��邩�ǂ����ɂ��āC�ԓx��B���ɂ��Ă���5�j�B�܂��C�e�s���{���̒n���Í\�z�̕��͂͂����������c�i2017�j�C�O���i2020�j�ɂ��C47�s���{���̂�������29�̓��{�����C�a���팸�Ƃ��������ړI�ɂ��āC�u�����I�ɍ팸���Ȃ��v�C�u�@�B�I�ɓ��Ă͂߂Ȃ��v�Ȃǂ̕\���ŁC�B���Ȃ܂܂ɂ��Ă���Ƃ̂��Ƃł���B
�������Ȃ���C����Ȃ�C�����������̂��߂̕a���̕K�v�ʂ̐��v�Ȃ̂��Ƃ������ƂɂȂ�B�������c�i2017�j�C�O���i2020�j���ڂ����_���Ă���悤�ɁC�n���Í\�z�̍�����c�_���Ă������{�̉�c�i�Љ�ۏፑ����c�C���S�Љ������c�C�Љ�ۏᐧ�x���v������c�j�ł́C�a���팸���܂߁C�@�\�ʕa������K�������Ă䂭���Ƃ����S�ۑ�Ƃ���Ă���C���ہC�n���Í\�z�̐��x�v����C���ꂪ�ړI�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�����J���Ȃ�29���{���̞B���ȑԓx�́C���{��t����͂��߂Ƃ���W�҂̔���������C�n���Í\�z�̖ړI�m�ɂł��Ȃ��C���邢�͂������Ȃ��Ƃ��������I�ȈӖ��������傫�����̂Ǝv����B
������ɂ���C�{�e�́C�@�\�ʕa���̕K�v�ʂ������ɐ����ڕW�Ȃ̂��ǂ����Ƃ����c�_�ɐ[���肷�����͂Ȃ��B�n���Í\�z�̋@�\�ʕa���̕ω�������]�������̊�Ƃ��āC�a���̕K�v�ʂ�p���邱�Ƃɂ���B�܂��C�a�@�E�a���̋@�\�����̓O��ƏW�Ƃ������Ƃ��C�n���Í\�z�̒��Ő����ړI�Ƃ��ċc�_����Ă����d�v�e�[�}�ł��邱�Ƃ���C�a���̏W��x�̕ω���p���āC���̌���]�����s�����Ƃɂ���B
�{�e�̕��͂ɗp����f�[�^�́C�e�s���{��������̈�Ë@�ցi�S�a�@�C�S�L���f�Ï��j���������Ă���a���@�\�̌��\�f�[�^�ł���B�����J���Ȃ̃E�F�u�T�C�g6�j����C����28�N�i2016�N�j����ߘa�Q�N�i2020�N�j�܂ł̑S�[�f�[�^������\�ł���B�{�e�ł͂��̂����C����28�N�Ɨߘa�Q�N�̃f�[�^��p���邱�Ƃɂ���7�j�B�a�@�f�[�^�́C�{�ݕ[�ƕa���[�ɕ�����Ă��邪�C�a���[�̕���p����B�a���[�́C�e�a�@�̕a�����Ƃ̕a�����i��ʕa������ї×{�y295�Łz �a���C���ꂼ�ꋖ�a���Ɖғ��a���C�×{�a���ɂ��Ă͈�××{�����×{���̕ʁj������Ă���C�����N�̂V���P�����݂ɂ�����a���̈�Ë@�\�����L����Ă���B�{�e�ł́C��ʕa���Ɨ×{�a���̍��v�ɁC�S�̈�Ë@�\�̃��x����t���C�e�@�\�ʂ̕a�������Z�o�����B�L���f�Ï��f�[�^�ɂ��Ă����l�̏������s���C�a�@�f�[�^�ƗL���f�Ï��f�[�^�����킹�āC�\�z�n�悲�ƂɏW�v�����B�ߘa�Q�N�̃f�[�^�ɂ��ẮC2025�N�V���P�����_�̈�Ë@�\�̗\�������Ă��邽�߁C�����2025�N�̋@�\�ʕa�����i�����݁j�Ƃ��č\�z�n�悲�ƂɏW�v���Ă���B
�Ȃ��C�{�e�̏W�v���ʂƊe�s���{���̕a���@�\�ł܂Ƃ߂��Ă���a�������r����ƁC�����ɒl���قȂ�\�z�n����ꕔ�C���݂��Ă����B����́C�����J���Ȏ��g�����\�f�[�^�̗��ӎ����ɖ��L���Ă���Ƃ���C�����J���Ȃ��f�[�^�����W������ɁC�e�s���{���ɏC�����s������C�V���ɉ�����Ë@�ւ����݂��邱�Ƃ������Ǝv����B�������C�{�e�ł́C�a���W��x�ȂǁC�[�f�[�^��p���Ȃ���Ε��͂ł��Ȃ����e�����邽�߁C�����J���Ȃ̌��\�f�[�^�̕������̂܂ܗp���邱�Ƃɂ����B����C�e�s���{�������v�����\�z�n�悲�Ƃ̋@�\�ʕa���̕K�v�ʂɂ��ẮC�����J���ȁi2017�j�Ɉꗗ�\���f�ڂ���Ă���̂ŁC���̒l��p�����B
���āC�a���̏W��x��\���w�W�Ƃ��ẮC�n�[�V���}���E�n�[�t�B���_�[���w���iHHI�j��p���邱�Ƃɂ����BHHI�͖{���C�Y�Ƒg�D�_�ȂǂŎs��̋�������\���ϐ��Ƃ��Ă悭�p������w�W�ł���B�܂��C�\�z�n����ɂ�����e�a���̕a���̃V�F�A���v�Z���C���̂Q��l�����C������\�z�n����ŏW�v���Ďw�W�Ƃ����BHHI�͂O����P�̊Ԃ̒l���Ƃ�C�V�F�A�̑傫�ȕa��������قǁC�傫�Ȓl���Ƃ�B�n����̕a���W���i�߂CHHI�͂��傫�Ȓl���Ƃ�ƍl������B�\�z�n��������ł͂Ȃ��C�S���x�[�X��HHI���v�Z���Ă���B
4.1�@�S��
�܂��C�}�\�R����}�\�T�́C�S���̃x�[�X�ŁC�@2016�N����2020�N�܂ł̊e�@�\�ʕa���̕ω����C�A2016�N����2025�N�i2020�N�ɂ����錩���݁j�̊e�@�\�ʕa���̕ω����C�����āC�B2016�N����a���̕K�v�ʂ܂ł̕ω������݂����̂ł���B�@��2020�N�ɂ�����e�a������2016�N�Δ�̕ω������݂�ƁC�S�a���Ƃ��Ă�4.8���̌����C���x�}�����a����10.4���̌����C�}�����a����8.9���̌����C���a����34.1���̑����C�������a����12.7���̌����ƂȂ��Ă���B���Ȃ킿�C�S�a������ъe�@�\�ʕa���Ƃ��C���̕K�v�ʂɌ������āC����ׂ������ɐi�����Ă��邱�Ƃ��킩��B�A��2025�N�̕a���������݂ɂ��ẮC�S�a����8.2���̌����C���x�}�����a����8.6���̌����C�}�����a����10.6���̌����C���a����45.3���̑����C�������a����17.2���̌����ł��邩��C���x�}�����������āC����ɖڕW�Ɍ����Đi������\��ƂȂ��Ă���B
�����C�S�̂Ƃ��Ă͊T�ˁC�ڕW�̕����ɐi��ł���Ƃ͌����C�e�a���̕K�v�ʂƂ̊Ԃɂ͂܂��傫�Ȋu���肪����B�}�\�S�́C2016�N�̊e�a�����ƕa���̕K�v�ʂƂ̍����P�Ƃ����ꍇ�C2020�N�̕a���������2025�N�i�����݁j�̕a�������ǂ��܂ł���ɔ����Ă��邩��B���x�Ƃ��Č������̂ł���B2020�N�ɂ��Ă͑S�a����0.533�Ɣ��������x�̒B���x�ł��邪�C���x�}�y296�Łz �����a���C�}�����a���C���a���ɂ��ẮC���ꂼ��0.414�C0.268�C0.206�ƒB���x�͂��Ȃ�Ⴂ�B�������a���̂݁C0.588�Ƃ��B���x�������Ȃ��Ă���B����C2025�N�̌����݂ł́C�S�a���̒B���x��0.914�C�������a���̒B���x��0.801�ɂȂ邪�C���x�}�����a���C�}�����a���C���a���̒B���x�͂��ꂼ��0.344�C0.319�C0.273�Ƒ傫�����������܂܂ł���B�a���̕K�v�ʂ͌����Ȑ����ڕW�ł͂Ȃ����Ƃ͊��ɏq�ׂ��ʂ�ł��邪�C���ɁC�}�����a������a���ő傫�Ș����������Ă��邱�Ƃ́C��͂�傫�ȉۑ�ƌ����邾�낤�B
���Ȃ݂ɁC���̃y�[�X�Ői�������ꍇ�C�a���̕K�v�ʂ̖ڕW�l�ɒB����܂ʼn��N������̂��C���B�N�͂��ɂȂ�̂����v�Z�������̂��}�\�T�ł���B2016�N����2020�N�̕ω����x�[�X�Ƃ����ꍇ�ɂ́C�S�a����2023�N�ɖڕW�ɒB���邱�ƂɂȂ邪�C���x�}�����a����2026�N�C�}�����a����2031�N�C���a����2035�N�ƁC�n���Í\�z�̌v����Ԃ�傫�������邱�ƂɂȂ�B�܂��C2016�N����2025�N�i�����݁j�܂ł̃y�[�X�Ő��ڂ����ꍇ�ɂ́C���x�}�����a���C�}�����a���C���a���͂���ɒx��C2040�N��ɂȂ�Ȃ��ƖڕW�l�ɒB���Ȃ����Ƃ��킩��B
4.2�@�s���{����
��L�̑S���x�[�X�Ɠ������͂��C�s���{���ʏW�v�l�ɑ��čs�������̂��C�}�\�U����}�\10�ł���B�܂��C�}�\�U�̑S�a�����̕ω����݂�ƁC2016�N����2020�N�܂ł̕ω����́C�قڑS���Ō������Ă��邱�Ƃ��킩��B�����C���̕ω����̕��͕x�R����10.1��������R������2.3�������܂ł��Ȃ�̃o���c�L������B�����[���̂́C�S�a���̕K�v�ʂ�2016�N�Δ�ő������Ă����s�O���i�����s�C�_�ސ쌧�C��t���C��ʌ��j����{�C���ꌧ�܂ł����S�a���������������Ă��邱�Ƃł���8�j�B�܂��C����ȊO�ɁC�a���팸�ڕW�̒B���x�������͖̂k�C���C���m���C���ꌧ�C���s�{�C���Ɍ��C�ޗnj��C�������Ȃǂł���C��ɓs�s���ŖڕW�Δ�̕a���팸�����傫���i�ꕔ�͖ڕW������j�悤�ł���B����C����ȊO�̌��ɂ��Ă͑S���Ɠ��l�C�B���x�͒Ⴂ�܂܂ł���B�e�s���{���ԂŐi���ɑ傫�ȍ�������ƌ�����B
�}�\�V�̍��x�}�����a���ɂ��ẮC���������a���̕K�v�ʂ�2016�N�Δ�ő������Ă��錧���W��������C�܂��܂����x�}�����a�����s�����Ă���n�悪�������C2016�N�Δ�Ŕ������x�܂Ō���������ׂ��n������������Ƃ������ł���B�܂��C2020�N�ɂ�2016�N�Δ�ŕa�����팸�����n��ł��C2025�N�i�\��j�ł͍Ăё���������\��ɂȂ��Ă���Ƃ��낪��ϑ����ȂǁC���������������ƂȂ��Ă���B���̂��߁C�s���{���ʂ̃o���c�L�����Ȃ�傫���B
�}�\�W�͋}�����a���̕ω��������݂����̂ł���B2016�N����2020�N�̕ω����́C�قƂ�ǂ̒n��Ō������Ă��邪�C18.0���������������a�̎R������4.1���̑��������Ă��鉫�ꌧ�܂ŁC���̃o���c�L�͂�͂�傫���B�܂��C�a���̕K�v�ʂɑ���B���x�͊e�s���{���Ƃ��Ⴍ�C�����s�Ɖ��ꌧ�͍팸���ׂ��Ƃ�����t�ɑ��₵�Ă��邱�Ƃ���C�B���x�̓}�C�i�X�̒l�ƂȂ��Ă���B
����C�}�\�X�̉��a���ɂ�����2016�N����2020�N�̕ω����ɂ��ẮC�S�s���{���ł��ꂢ�ɂ�����đ������Ă���B�����Ƃ��C�a���̕K�v�ʂɑ���B���x�́C�k�C���≫��̑��C�y297�Łz ��s��������C���m���C�������Ȃǂ̓s�s���ő����ĒႢ�B�}�\10�̖������a���ɂ�����2016�N����2020�N�̕ω��ɂ��Ă��C�قƂ�ǂ̒n��Ō������Ă�����̂́C���̃o���c�L�͑傫���B��ʌ��Ɛ_�ސ쌧�̕a���̕K�v�ʂ�2016�N���������Ȃ��Ă�����̂́C2020�N�C2025�N�i�����݁j�܂ł̕ω��͌����𑱂��Ă���B�����C�ڕW�̒B���x�͑��̋@�\�ʕa�����͑����č����C���s�{��ޗnj����͂��߂Ƃ��ĂP���Ă���n�悪�U�������B
���āC�s���{���ʂɂ݂�ƃo���c�L���傫���Ȃ邱�Ƃ͓��R�ƌ����邪�C�����I�ɋ���������̂́C2016�N�̋@�\�ʕa�������a���̕K�v�ʂ���傫���������Ă����s���{���قǁC���̌�̕ω������傫���Ȃ��Ă��邩�ǂ����ł���B�܂�C�L���b�`�A�b�v���郁�J�j�Y���������C�ڕW�ւ̎��ʌX���������邩�ǂ������d�v�ł���B�}�\11�́C�@�\�ʕa�����ƂɁC�c����2016�N����2020�N�̕ω����C������2016�N����a���̕K�v�ʂւ̕ω������U�z�}�Ƃ��ăv���b�g�������̂ł���B�����C���ʌX��������Ȃ�C�E�߂Ɋe�s���{�������Ԃ͂��ł���B�}�\11���݂�ƁC�S�a���ƍ��x�}�����C�}�����a���C�������a���ɂ��ẮC�ア�Ȃ�������ʌX��������悤�Ɍ�����B�������C�o���c�L�͑傫���C���W���͂��ꂼ��0.338�C0.400�C0.476�C0.418�Ƃ��܂荂���Ƃ͌����Ȃ��B���l�ɐ}�\12�́C�c����2016�N����2025�N�i�����݁j�̕ω����C������2016�N����a���̕K�v�ʂւ̕ω������Ƃ����U�z�}�ł���B�S�a���ƍ��x�}�����C�}�����a���ɂ��Ă͂�⑊�ւ����܂�C���ꂼ��0.577�C0.523�C0.550�ƂȂ����B
4.3�@�\�z�n���
�s���{���ʂ̕��͂���C�����339�̍\�z�n��ʂ̕��͂Ƀu���[�N�_�E�����Ă䂭���Ƃɂ��悤�B�}�\13��2016�N����2020�N�܂ł̋@�\�ʕa���̕ω����̕��z���敪���Ƃɂ݂����̂ł��邪�C��͂�C���Ȃ�ω����̃o���c�L�͊g�債�Ă���9�j�B�J�[�l�����x������g���Ă��ꂼ��̋@�\�ʕa���ω����̕��z�����o�����Ă��C��͂肩�Ȃ�傫�ȃo���c�L�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��킩��i�}�\14�j�B���̃o���c�L���傫���Ƃ��������́C2016�N����2025�N�i�����݁j�̕ω��������Ă����l�ł���i�}�\15�j�B�܂��C�}�\16�̕a���̕K�v�ʂɑ���B���x�����Ă��C�͂��\�z�n��Ԃő傫�ȃo���c�L�����邱�Ƃ��킩��B
�s���{���ʂ̕��͂ł��_�����悤�ɁC�\�z�n��ʂ̑傫�ȃo���c�L�Ɋւ��āC�����I�ɏd�v�Ȃ��Ƃ͖ڕW�Ɍ������Ă̎��ʌX���������邩�ǂ����Ƃ������Ƃł���B�}�\17�C18�͂��̓_���m�F���Ă���B�܂��C�}�\17�͋@�\�ʕa�����ƂɁC�c����2016�N����2020�N�̕ω����C������2016�N����K�v�ʂւ̕ω������U�z�}�Ƃ��ăv���b�g�������̂ł���B�s���{���ʃf�[�^��������ɔ��R�Ƃ��Ă͂�����̂́C��������ア���̑��ւ��m�F�ł���B���W���͍��x�}�����a���Ɖ��a������⍂���C���ꂼ��0.474�C0.518�ł���B�}�\18�ɂ݂�悤�ɁC�c����2016�N����2025�N�i�����݁j�̕ω����ɂ���ƁC�S�a���Ƌ}�����a���ɂ��Ă͐��̑��ւ���⍂�܂�C���W���͂��ꂼ��0.487�C0.424�ƂȂ�B
�Ō�ɁC�a���̏W���x�̕ω��ɂ��Č��邱�Ƃɂ��悤�B�}�\19�́C���ɐ�������HHI�ɂ��āC�@2016�N����2020�N�̕ω����C�A2016�N����2025�N�i�����݁j�̕ω������C�S�a���Ɗe�@�\�ʕa���ɂ��Ă݂����̂ł���B�܂��S�a����HHI�́C�@2016�N����2020�N�C�A2016�N����2025�N�i�����݁j�̕ω��Ƃ��C�W���x�����܂��Ă��邱�Ƃ��킩��B�@�\�ʂɂ݂Ă��C���x�}�����C�}�����͇@�A�̊��ԂƂ��W���x�����܂��Ă���C�a���̏W�Ƃ����ϓ_����́C�n���Í\�z�̊�}�Ɛ����I�ȓ����ł���Ɖ��߂ł���B�����C�����ł݂Ă���W���x�́C�����܂ŕa���ʂ̏W���x�ɂ����Ȃ�����C���̔w�i�Ƃ��ĕa���K�͂̑傫���a�@�ɕa�����W����Ă���̂��C�ǂ̂悤�ȕa�@�ɏW����Ă���̂��ȂǁC�ڂ������Ƃ͂悭�킩��Ȃ��B
���a���Ɋւ��ẮC�ω����͇@�A�̊��ԂƂ����ł���C�W���x���������Ă��邱�Ƃ��킩��B�����C�����a�@�ɂ����ċ}�����a��������a���ւ̓]�����i��ł���̂ł���C�}�����a���̏W���x�����܂����ŁC���a���̏W���x�͒Ⴍ�Ȃ�͂��ł��邩��C������n���Í\�z�ɂƂ��Ė]�܂��������Ɖ��߂ł���B�������a���ɂ��ẮC�@�A�̊��ԂƂ��W���x���オ���Ă���B�������a���̋K�̗͂��v��Nj�����Ȃ�ΏW���x���オ������]�܂������Ƃ���C������n���Í\�z�̊�}����O��Ă͂��Ȃ����낤�B
�}�\20�C21�́C�\�z�n��ʂɁC�@�A�̊��Ԃ̕ω������݂����̂ł��邪�C��͂�e�@�\�ʕa���Ƃ��n�悲�Ƃ̕ω����̃o���c�L���傫�����Ƃ��m�F�ł���B���́C�W���x���Ⴂ�n��قǁC���̌�̏W���x�������悤�ȃL���b�`�A�b�v�������Ă��邩�ǂ����ł���B�����ŁC�}�\22�́C�@�\�ʕa�����ƂɁC�c����2016�N����2020�N�̕ω����C������2016�N�̏W���x���Ƃ��ĎU�z�}���݂����̂ł���B�S�a���C�@�\�ʕa���Ƃ��ɖ��m�ȊW���ώ@����Ȃ��B���Ȃ킿�C���W�������ƂȂ�����C���ł����Ă����W���͔��ɒႢ�B���̓_�́C�}�\23��2016�N����2025�N�i�����݁j�̕ω������Ƃ����O���t�ł��قړ��l�̓����ƂȂ��Ă���B
�{�e�́C�n���Í\�z�ɂ�����S�a��������ы@�\�ʕa�����̕ω��ɂ��āC2016�N����2020�N�̕a���@�\�̌[�f�[�^��p�������͂��s�����B�����]�����邽�߂ɂ́C���炩�̐����ڕW���K�v�ł���B�����ŁC�����ɂ͐����ڕW�ƔF�߂��Ă��Ȃ����̂́C�\�z�n�悲�Ƃɐ��v���ꂽ�a���̕K�v�ʁi�K�v�a�����j�ɁC�ǂ̒��x�C2020�N�̕a������2025�N�i�����݁j�̕a����������Ă��邩�Ƃ����ϓ_����]�����s�����B�܂��C�e�\�z�n��̕a���̏W���x�i�a���̃n�[�V���}���E�n�[�t�B���_�[���w���j��p���āC�a���̏W���i��ł��邩�ǂ����������B
�܂��C�S���ɂ�����2020�N�̊e�@�\�ʕa������2016�N�Δ�ł݂�ƁC�S�̂Ƃ���4.8���̌����C���x�}�����a����10.4�������C�}�����a����8.9�������C���a����34.1�������C�������a����12.7�������ƂȂ��Ă���C�a���̕K�v�ʂɌ����đS�a���C�e�@�\�ʕa���Ƃ��C����ׂ������ɐi�����Ă��邱�Ƃ��킩�����B2025�N�i�����݁j�̊e�@�\�ʕa�����ɂ��ẮC���x�}�����a���������āC����ɐi��������\��ł���B�������Ȃ���C�a���̕K�v�ʂƂ̊Ԃɂ͂��y299�Łz ���傫�Ȋu���肪����B2020�N�ɂ�����S�a���̒B���x��0.533�Ɣ��������x�ł���C���x�}�����a���C�}�����a���C���a���C�������a���́C���ꂼ��0.414�C0.268�C0.206�C0.588�Ƃ����B���x�ł���B�}�����a���C���a���̒B���x�����ɒႢ�ƌ�����B2025�N�i�����݁j�ɂ��ẮC�S�a���̒B���x��0.914�܂Ŕ�����̂́C���x�}�����a���C�}�����a���C���a���̒B���x��0.344�C0.319�C0.273�ƁC�ˑR�C�a���̕K�v�ʂ���傫�����������܂܂ł���B���̓_�C����ɂ͑傫�ȉۑ肪�c��B
���l�̕��͂�s���{���ʁC����ɍ\�z�n��ʂɃu���[�N�_�E�����Ă݂�ƁC���R�̂��ƂȂ���C�e�n��̕ω�����B���x�̃o���c�L�͂��Ȃ�傫���Ȃ�B���̏ꍇ�C�����I�ɂ́C�a���̕K�v�ʂƘ������傫���n��قǁC���̌�̕ω����������C�L���b�`�A�b�v��������ɓ����Ă���̂��ǂ����������[���Ƃ���ł���B�U�z�}��p���Ă��̃L���b�`�A�b�v�̏��m�F�����Ƃ���C�o���c�L�͑傫�����̂́C�ア�Ȃ�������̑��ւ��m�F�ł��C�L���b�`�A�b�v���Ă䂭�X��������������B
�܂��C�a�@�E�a���̋@�\�����̓O��ƏW�ɂ��Ă��C�n���Í\�z�ɂ�����d�v�e�[�}�̈�ł��邱�Ƃ���C����Ɋ֘A����w�W�ł���a���̏W���x�ɂ��āC��̕��͂��s�����B���̌��ʁC�S�a���C���x�}�����C�}�����C�������̊e�a���̏W���x�����܂��Ă���C���̕a���̏W���x���Ⴍ�Ȃ��Ă��邱�Ƃ��킩�����B�����̓����́C�n���Í\�z����}���Ă���������ƊT�ː����I�ȓ����Ɖ��߂ł���B
�r�㒼�ȁi2017�j�u���{�̈�ÂƉ��@���j�ƍ\���C�����ĉ��v�̕������v���{�o�ϐV���o�Ŏ�
�����J���ȁi2017�j�u�e�s���{���̒n���Í\�z�ɂ��āv��S��n���Í\�z�Ɋւ���WG�E�����R
�@�ihttps://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000164337.pdf�j
�������F���i2017�j�u����27�N�x�a���@�\�f�[�^�i�S���Łj�̌��J�v Monthly IHEP 267: 26-28
�@�ihttps://www.ihep.jp/publications/other/?y=2017�j
��ؘj�i2017�j�u��Ô�}���ɐV���Ȏ��_�i���j�}�����a���팸�֗U���� �a������s����I�����Ɂv���{�o�ϐV�������E�o�ϋ����i����29�N�T��11���j
��ؘj�i2020�j�u�Љ�ۏ�ƍ����̊�@�v PHP������
��ؘj�i2021�j�u��Õ���@�^�Ɛl�͒N���v�u�k��
�������F�i2017�j�u��Ë�������̐���ߒ��@�n���Ìv��̌`���E����E���{�ߒ��Ɛ���̕ϗe�v���F��
�O���x�i2020�j�u�n���Â͍Đ����邩�@�R���i�Ђɂ�����̐����v�v���o�ώ�
�������c�i2017�j�u�n���Í\�z�̐��ʂƉۑ�`���ӌ`�������Ƃ�����ڂ̂Ȃ��̐����`�v
�@�ihttps://www.tkfd.or.jp/files/research/heathcare/files/2017-01.pdf�j