����́u���{�I�o�c�v�_�i�U�j
��ˁ@���o�E���R�@���G
�P.�@�u���{�I�v�R�[�|���[�g�K�o�i���X
1.1�@�o�u���o�ϔj��܂ł̓��{��Ƃ̃R�[�|���[�g�K�o�i���X
���̃g�s�b�N�̌����ɂ́C�`���I�ȓ��ƕẴR�[�|���[�g�K�o�i���X�E�V�X�e���̔�r���L�p�ł���B���̐}�͂�����ے��I�ɕ\�����̂ł���B
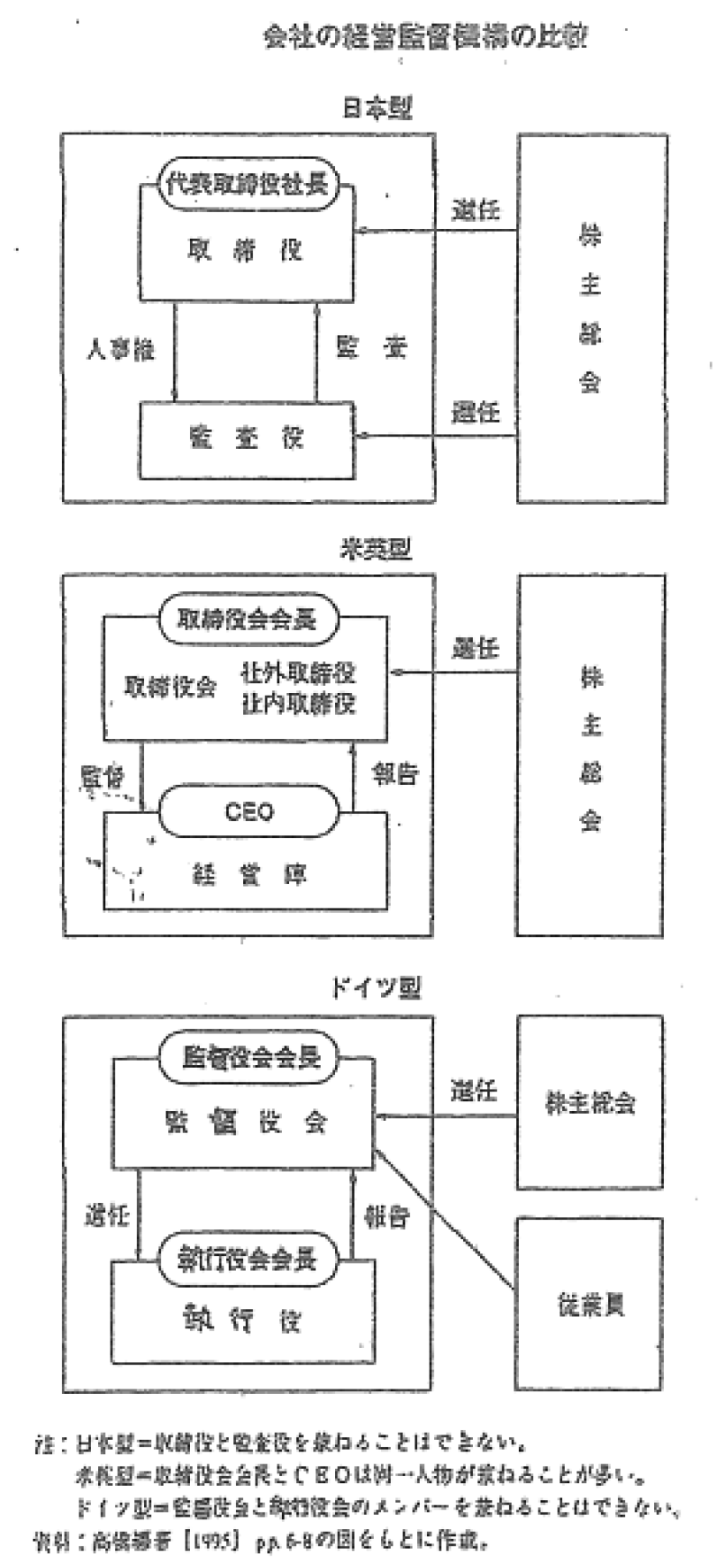
�u��Ђ̌o�c�ē@�\�̔�r�v�Ə̂��邱�̐}�́C�܂��ψ���i���j�ݒu��Ђ����z�����O�́i�Â��j���{��Ƃ�O���ɒu�������̂ł���B�����ł������{�^�͂�����u��w�^�v�C�h�C�c�^�́u��w�^�v�C���̒��Ԃ́u�ĉp�^�v�͐l�ɂ��u��w�^�v�Ƃ��u��w�^�v�Ƃ��Ă����̂ł���B���ė��̉��߂ł́C�g�b�v�}�l�W�����g�g�D�́u�@ �d��������l�v�Ɓu�A �@�̐l�������ē���l�v�Ƃ����Q�O���[�v����Ȃ�Ƃ���Ă��āC���̂Q�O���[�v�̊W�͂ǂ��Ȃ��Ă��邩�C�Ƃ��������ɂȂ�B
�����ł́u���{�^�v�ł͎�������Ɩ����s�Ƃ���monitoring�Ƃ����O�q�̇@�A��̋@�\�������C���̂��߁u��w�^�v�ƌĂꂽ���̂ł���B�`���I�ɂ͎������̒��́C��\��������������Ɩ����s��S���i�@�j�C����ȊO�̎������������ē���i�A�j�C�Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ��Ă������C�����g�D���ł����S�����Ă����̂ŁC�܂��Ɂu��w�^�v�Ƃ������ƂɂȂ�B�����Ă��̂��߂킪���ł́u������v�Ƃ����ƋƖ����s���s���l�����C�Ƃ�����������ʉ����Ă��āC�{�����������l�������u�����܂�v�̂��d���Ȃ̂���ʑ�O�ɂ͐�������������Ă��Ȃ������B�l�ɂ���Ă͂��̏�Ԃ��u�D�_�ƌx�@�������v�Ȃǂƕ\�����Ă������Ƃ�����B�ꉞ�č����Ƃ������̂����邪�C���̂���̊č����́C�����͌`���I�ȑ��݂ŁC�g�b�v�}�l�W�����g�g�D�́u�Ӓ��v�ȂǂƂ����`�e���Ȃ���Ă����B�Г��ł̎�������i�����ɔs��C�u�ՐE�v�Ƃ��Ă��Ă����Ă����i���_�j�E�C�Ƃ������߂���荹������Ă����L��������B
�ĉp�^�ł́C�}�̏�ł͇@�ƇA�͌䗗�̒ʂ蕪�����Ă��邪�C���ꂼ��̃g�b�v�����C����Ă���i���Ƃ������j���Ƃ���C������w�^�Ƃ݂͂Ȃ����C��w�^�Ƃ݂錤���҂��C���Ƀh�C�c�ɑ����B�h�C�c�^�͂��ꂪ���S�ɕ�������Ă��āC���^�����̓�w�^�Ƃ݂Ȃ���Ă���B
���{��Ƃɂ����邱�̂悤�ȁu��w�^�V�X�e���v�ł́C���̑S�̂��Ď�����̂͒N�Ȃ̂��C�Ƃ����^��͕M�҂̈�l���h�C�c�l�����҂����ɖ���Ă������Ƃ����C�����̓��{�ł́C�����I�ɂ̓��C���o���N���ŏI�I�Ď��҂������C�Ƃ����̂����̉ł�����1�j�B����͐i1995�j�Łu��Ԉˑ��I�K�o�i���X�v�ƌĂ����̂ł���B
�u��Ԉˑ��I�K�o�i���X�Ƃ́C��Ƃ̍�����Ԃ����S�ł��邩����C��Ƃ̃R���g���[�����͏]�ƈ��̓����q�G�����L�[���ւď��i�E�I�����ꂽ�o�c�ҁi�C���T�C�_�[�j�Ɋ��S�Ɉς˂��Ă��邪�C��Ƃ̍�����Ԃ����������ꍇ�C�����Ă��������ꍇ�ɂ̂݁C�����҂���u����v�̊O���ҁC���Ȃ킿���C���o���N�ցC�R���g���[�����������I�Ɉڍs����C�����������Ƃ������҂̂������őO�����ė�������Ă���悤�ȃK�o�i���X�\��������B2�j�v
���̂ق��CSheard�i1988�j��Aoki�i1991�j�́C��ƌo�c���̎x�z�Ƃ����ϓ_���烁�C���o���N�W���Ƃ炦�C���{�ɂ����Ă̓��C���o���N���e�C�N�I�[�o�[�s����ւ�������������Ă����Ƃ��Ă���B�����ł̓��C���o���N�͈��芔��Ƃ��Ċ�ƌo�c���̈��艻�ɋ��͂��Ă��邪�C���o�c�w�ɂ��o�c��������I�Ɣ��f���ꂽ�ꍇ�ɂ́C�o�c�҂̍��V���Ƃ̍ĕҐ������߂�ȂǁC�o�c�ɉ������Ƃ������ʂ��������ꂽ�B����͏d�v�Ș_�_�ł���C���C���o���N�W�̈Ӌ`��_����ɂ������ẮC���̂悤�ȋ�s�ɂ���ƌo�c�ւ̉�����\���l�����鉿�l������Ƃ����B
�h�C�c�ł̌�����ł��h�C�c�l�����҂��ŏI�I�ɖ��Ƃ���̂́C����ł͒N���ŏI�I�ɋ�s���Ď�����̂��H�C�Ƃ����^��ł������B�����Ă��ꂪ�܂��ɁC�o�u���o�ϔj���̓��{�y319�Łz �o�ς̑�j�]�̌����ƂȂ������Ƃ́C���ł͏O�q�̂��ƂƂȂ��Ă���B���Ȃ킿�C���O�Ƃ��Ă͍�����s���Ď�����͂��������C�Ƃ������Ƃł���B���́u�Ď��v���s���ŁC��s�܂ł��o�u���ɔ�э���ł��܂������Ƃ���C���̈Í��̎������������C�����Ă��܂����̂ł������B
1.2�@�ψ���u���v�ݒu��Ђɂ���
�ψ���u���v�ݒu��Ђ́C2002�N�̏��@�����ɂ���ē������ꂽ��Ƃ̊č��`�ԂŁC����́C�o�c�̊Ď��@�\�Ƃ��āC����܂ł̊č����ɑウ�ĎЊO������𒆐S�ɍ\�������w���ψ���C�č��ψ���C��V�ψ���̎O�̈ψ����ݒu���C����܂Ŏ�������s���Ă����Ɩ����s�@�\�����s���ɑウ�鐧�x���̗p������Ђł���B��̓I�ɂ͎�����������߂�u�w���ψ���v�C�č����̖�����S���u�č��ψ���v�C�����̕�V�����߂�u��V�ψ���v��ݒu���C����܂ŎГ���������s�Ȃ��Ă����Ɩ����s�@�\�������̈ψ����s����B�e�ψ���͎�����R���ȏオ�K�v�ŁC���̂����ߔ����͎ЊO������ō\������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ɂ��C��Ɗ����̓����������߁C�s��̐M�������m�ۂ���̂��_���ł������B���@����@��̑��ЂȂ����݂Ȃ����Ђ��C���@�̈ψ���ݒu��ЂɊւ������̓K�p����|�̒芼�̒�߂�݂��ē�������B2002�N���@�����ɂ���ē������ꂽ���C2006�N��Ж@�{�s�ɂ��C�ψ���ݒu��Ђƌď̂��ύX���ꂽ�B
1.3�@����̓��{�̂R�̃^�C�v�̃R�[�|���[�g�K�o�i���X�E�V�X�e��
������{�ɂ�����R�[�|���[�g�K�o�i���X�E�V�X�e���͎��̂悤�ɗv���3�j�B�䂪���̉�Ж@�́C����17�N�ȗ��C�Ƃ�킯26�N����30�N�܂Ŗ��N�C������ɂ킽������̗��j�����B�����āC���{��Ƃ̃R�[�|���[�g�K�o�i���X�̗��j�������ꏭ�Ȃ��ꂱ�̉����ƕ��s���Đi��ł��Ă���B����26�N�̉����̊T�v�͈ȉ��̂Ƃ���ł���i�����������@���������ɂ��j�B
�P�D�V���ȃL���b�V���A�E�g���x
�`������90���ȏ�����L���銔��́C���̊���Ɋ�����n���悤���ڐ����ł���`�i����26�N�W���S���j
�Q�D�x�z����̈ٓ����V�����s���Ɋ��傪�֗^�ł���
�`�c������10���̂P�ȏ�̊���̔�������ΐV�����s���Ɋ��呍��̌��c���K�v�`�i����26�N11���T���j
�R�D�č����ψ���ݒu���
�`�č�����ݒu��Ђł��ψ���ݒu��Ђł��Ȃ��V������Г����̎d�g�݂��n��ꂽ�`�i����26�N11���T���j
�S�D�ЊO������E�ЊO�č����̗v�����i���C�ЊO�����ݒ萄�i�[�u�i����26�N11���T���j
�T�D���d��\�i��
�`�e��Ђ̊��傪�q��Ђ̖����Ɋ����\�i�ׂ��N������悤�ɂȂ�`�i����26�N11���T���j
�U�D�q��Ђ̊������n�Ɛe��Ђ̊��呍����ʌ��c
�`�q��Ђ̊������n�����Ə��n�Ɠ����Ӌ`��L����悤�ȏꍇ�C�e��Ђ̊��呍��̓��ʌ��c���K�v�Ƃ����`�i����26�N11���T���j
�y320�Łz�V�D���~�������ł���g�D�ĕ҂͈̔͂̊g��
�W�D���҂��Q�����Е����ɂ�������ҕی�
�`���҂͏��p��Ђɑ��Ă������ł���`�i����27�N�P���V���j
�X�D���̑�
���Ȃ킿�C����26�N�����ł́C�č����ψ���ݒu��Ђ̑n�݁C�ЊO����̗v���̌��i���C���d��\�i�א��x�̑n�݂Ȃǂ��s��ꂽ�B�����Ƃ��C�����̉ߒ��ŋc�_����Ă����ЊO������̋`�����͌������C���̏]���^�̊č�����ݒu��Ђɂ��āC�u�ЊO�������u�����Ƃ������łȂ����R�v��莞���呍��Ő������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƂ����ƂƂ��Ɂi��Ж@��327���̂Q�j�C����������Ő݂���ꂽ�B
���{�I�ɓ��{�̉�Ђ͓��������C�č��V�X�e���ɑ傫�Ȗ�������Ă��āC�o�u���o�ςƂ��̔j��œ��{�̊�����Ђ̊č��V�X�e���̎コ�����ۓI�ɂ����𗁂т�悤�ɂȂ����B
�����ŕ���17�N�ɉ�Ж@���������C���ĂɂȂ�����u�ψ���ݒu��Ёv���K�肵���B�Ƃ��낪���܂�Ɏێq��K�߂��č̗p�����Ђ����܂�Ȃ������i�t�ɍ̗p������Ђ͎��ԂƂ��ċƐт����������j����C�s�ˎ��͂��̃I�����p�X�������������ׁC�Ăѕ���28�N����u�č����ψ���ݒu��Ёv���K�肷��Ɏ������̂ł���B
�������]���̈ψ���ݒu��Ђ������Ȃ���̗p�����Ђ����������߂ɁC���܂���p�~���鎖���ł����u�w���ψ���ݒu��Ёv�Ƃ������̂Ŏc�����Ƃ������Ƃł���B
�č����ψ���ݒu��Ђ́C�č�����ɑ����ĉߔ����̎ЊO��������܂ގ�����R���ȏ�ō\�������č����ψ���C������̐E�����s�̑g�D�I�č����s���Ƃ�����Ђł���B�]���^�̊č�����ݒu��ЂƎw���ψ���ݒu��Ђ̒��ԓI���i��тт���O�̉�Ќ`�Ԃł��邪�C�����ɂ͎����Ă��Ȃ��B
������{�̂R�̉�Ќ`�Ԃ͐}�Ō���Ǝ��̂悤�ɂȂ�i�����V���Ёu�@�ƌo�ς̃W���[�i���v�ɂ��j�B
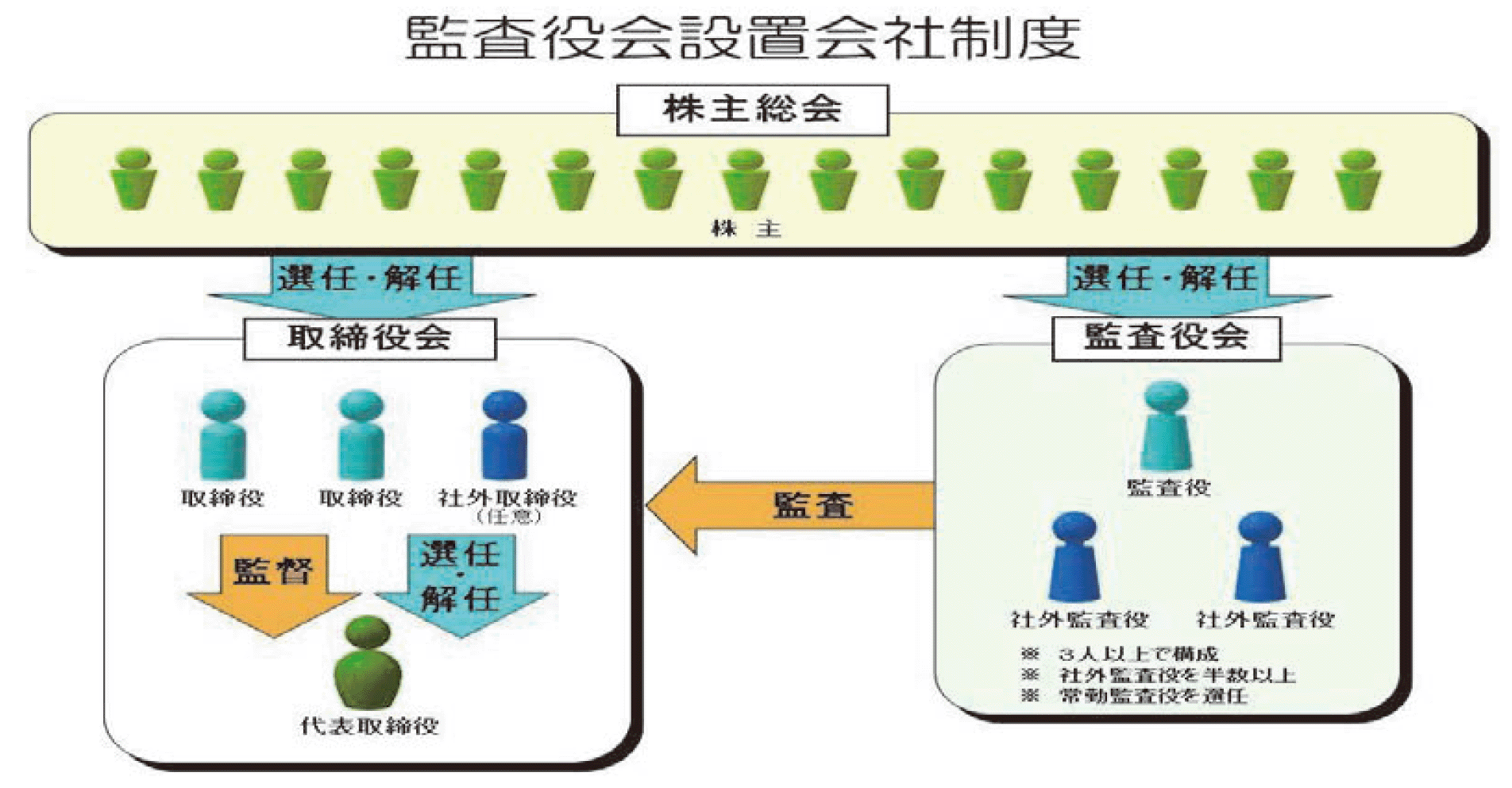
�u�]���^�v�Ƃ�������̂ŁC���ݓ��{�ł͍ł������^�C�v�ł���B2017�N���_�œ��P������Ƃ�75�����߂Ă���B
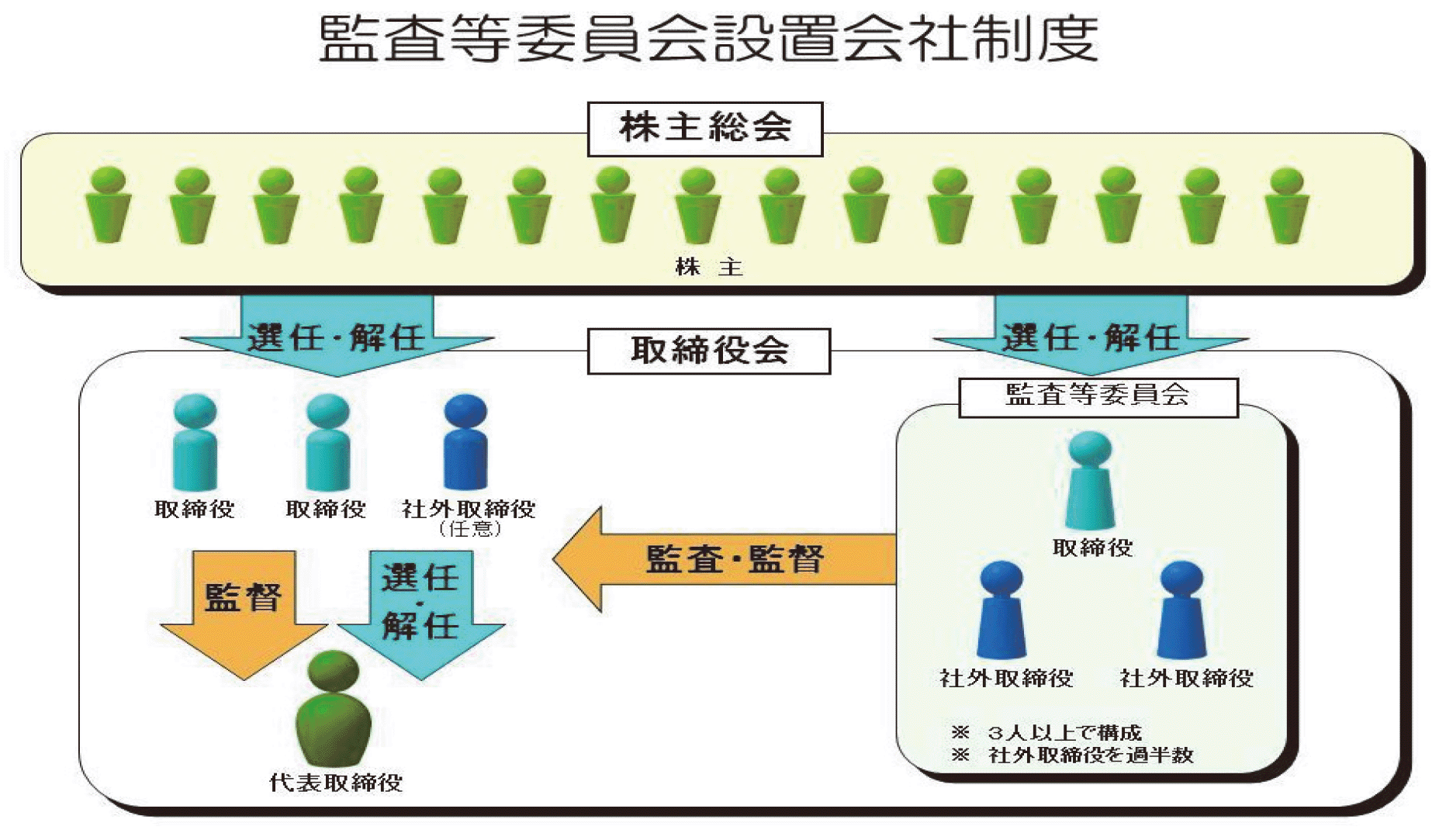
�č����ψ���ݒu��Ђ͑O�q�̒ʂ�̐G�ꍞ�݂ōl�Ă��ꂽ���̂ŁC2015�N�͂U���C2016�N��18���C������2017�N�ɂ�22���܂ő����Ă���Ƃ���邪�C��͂�]���^�̊č�����ݒu��Ђ���ڍs���邱�Ƃɂ�郁���b�g���C������炩�ł͂Ȃ��Ƃ����]���������Ɉ�ʓI�̂悤�ł���B
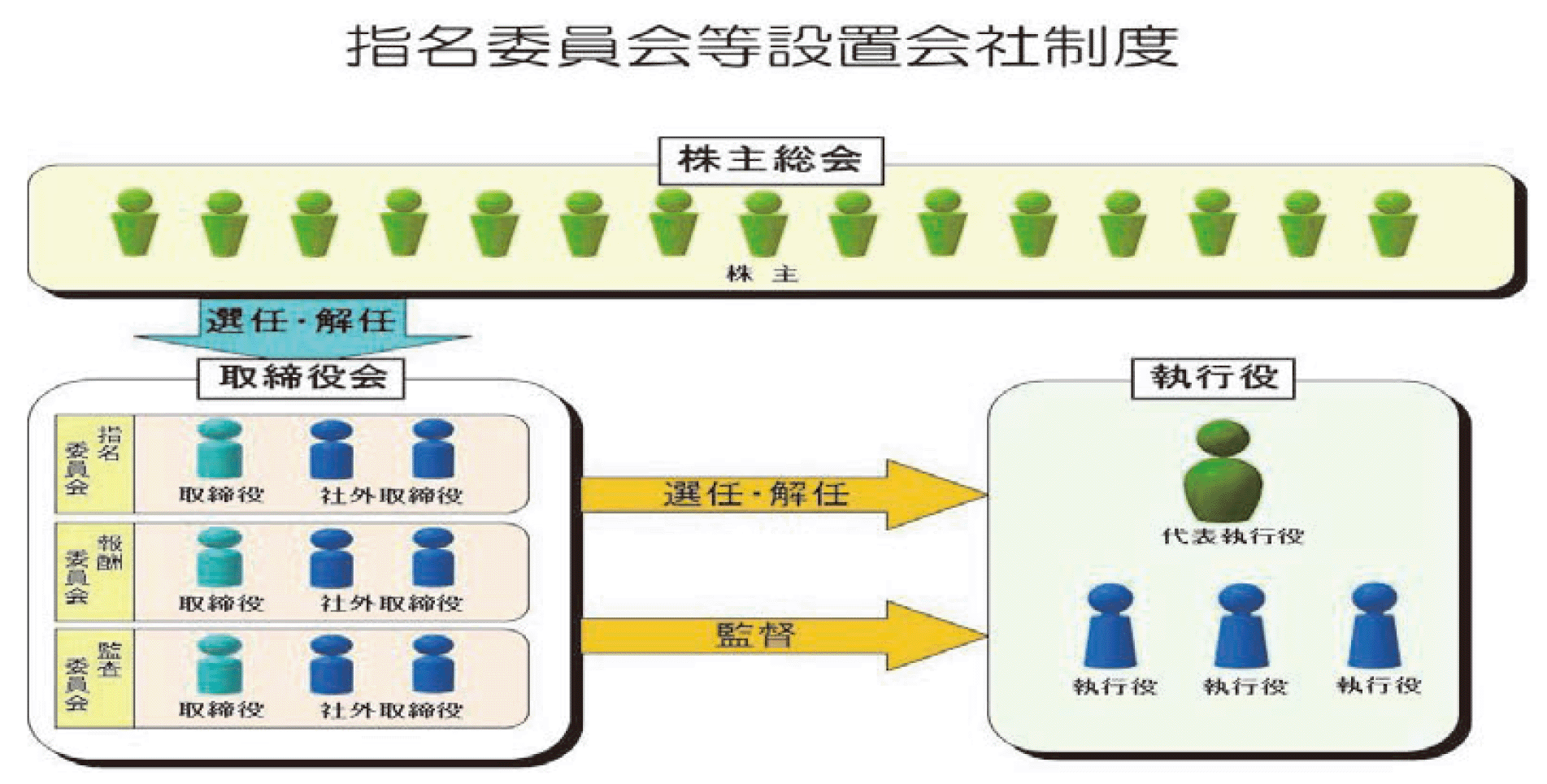
10�N�ȏ�O�ɖ蕨����ōl�Ă��ꂽ�u�ψ���u���v�ݒu��Ёv�̖��c�̎w���ψ���ݒu��Ђ́C2015�N�ȗ�2017�N�܂őS�̂̂R���ɂƂǂ܂��Ă���C�l�I�ɂ͂���ȏ㑝���邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ�����ۂ������Ă���B�������C������ςȘb��ɂȂ��Ă�����Y�����Ԃ��C�S�[����ւ̂��܂�̌��͏W���̌��ʁC���̂悤�Ȏ��ԂɊׂ������ƂȂ��āC�]���̊č�����ݒu��Ђ���}篁C�w���ψ���ݒu��Ђւ̈ڍs���v�悵�Ă���Ƃ����������āC�Ȃ��Ȃ��̒��ڂ��W�߂邱�ƂɂȂ��Ă���B����������ɂ͒芼�̕ύX�₨���炭�ꕔ�͊��呍��ł̏��F���K�v�ȉ\�������邵�C���������m�[������̎�����̎^�����Ȃ��Ǝ����ł��Ȃ����Ƃɂ��ڂ������Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���̃e�[�}�́C�킪���̊�����Ђ̃R�[�|���[�g�K�o�i���X���P�̂��߂ɂ́C�ЊO������������č����������C�ǂ��炪�L�����C�Ƃ����^��ł���B
�������C���̓_�ɂ��Ă͂͂�����ƁC�č������������ЊO����������̕����C�ǂ��R�[�|���[�g�K�o�i���X��Ԃ̎����ɂ͗L�����C�ƍl����l�������̂�����ł���B
���̗��R�͂�������������ł��낤���C�ő�̂��̂́C��Ж@�����Ŋč������������ɏo�Ȃ��C�ӌ����q�ׂ邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ������̂́C�c�����͕t�^����Ă��Ȃ����Ƃ��������Ă���B�����C�ЊO������Ɠ��l�ɁC�ЊO�č����Ƃ������̂��ȑO��蒍�ڂ���Ă��Ă���C����ɗL�\�Ȑl�ނ����낦�邱�Ƃ��ł���C�ЊO������Ƌ��ɁC����ɕ։v��^����R�[�|���[�g�K�o�i���X�E�V�X�e�����ێ��ł���悤�ɂȂ�ł��낤�B
2020�N�̓��P���S���2172�Ђ̂����C�č�����ݒu��ЁE�w���ψ���ݒu��ЁE�č����ψ���ݒu��Ђ̑I���́C
�E�č�����ݒu��Ђ�1448�Ё@�@�@ 67��
�E�č����ψ���ݒu��Ђ�661�Ё@�@30��
�E�w���ψ���ݒu��Ђ�63�Ё@�@ �R��
�ƂȂ��Ă���B
�č�����ݒu��Ђ������Ƃ��������C�ߔN�č����ψ���ݒu��Ђ������X���ɂ��邱�Ƃ��|�C���g�ł���B�������C�Ȃ����̂悤�Ɋč����ψ���ݒu��Ђ��������Ă��邩�C���̗��R�͒肩�ł͂Ȃ��B�ߔN�ł͎O�H�d�H��������̗p���Ă��邪�C���́u����v���H�ȂǂƂ���������������B
2.1�@�ЊO������E�ЊO�č���I�C�̓���
2.1.1�@�ЊO�č����̓����ƒn�ʂ̋���
�o�u������ȍ~�C���{�o�ς͒�����ɂ߁C���̈�̌����Ƃ��ē��{�I�o�c���ᔻ�𗁂т��B���{�I�o�c�ɑ���ᔻ�ɂ͏I�g�ٗp����N������Ƃ������ٗp���s���͂��߂Ƃ��Ă������̘_�_�����邪�C������Ђ̋@�v�Ɋւ��R�[�|���[�g�K�o�i���X�̌��ׂ��������w�E���ꂽ�B1990�N���ʂ��ē��{��Ƃ͌o�c�s�U�ɔY�݁C���X�̕s�ˎ��������N�����Ă����B�����ŁC���ꂽ��̎�i�������@�\�̉��v�Ƃ��Ă̊č����̒n�ʂ̋����ł������B�č����́C��\������������̐E�����s���č�����@�ւł��邪�C1974�N�ȍ~�̐����ɂ킽�鏤�@�����ɂ��C�č����̌����ƓƗ������L�͈͂ɋ������ꂽ�B���̒��ł��u�ЊO�č��𐧓x�v�́C�o�y323�Łz �u��������1991�N�ɏ،��s�ˎ��i������U���j���\�ʉ����C�������ւ̊Ď����x�����d�v�������悤�ɂȂ������Ƃ���C1993�N�̏��@�����ŋK��ɉ�����ꂽ�B
�č����̒n�ʂ���������C����4�j�ɂ����Ă͂P���ȏ���ЊO�č����Ƃ��邱�Ƃ��`���Â���ꂽ�B����́C������̋Ɩ����s�ɑ��āC�ЊO����Ɨ������č��������邱�ƂŁC��Ƃ̃K�o�i���X�̐����������悤�Ƃ���ړI�������Ă����B���{�̊�Ƃ͓`���I�ɎГ��̐l�ނɂ���Ď������\������C�����I�ɑ�\������������̍s����K���ɊĎ����C�������邱�Ƃ͓�������B�����ŊO���̋q�ϓI�Ȏ��_�������ꂽ�K�o�i���X���x���������悤�Ƃ����̂ł���B
�����2005�N�̉������@�̎{�s�ɂ��C�ēx�C�č����̒n�ʋ������}��ꂽ�B���@�����̑��Ђ́C�č����̍Œ�K�v�l�����P������R���ɑ����C���̂����̔����ȏ���ЊO�č����Ƃ��邱�Ƃ��`���Â���ꂽ�B�܂��C�ЊO�č����ɋ��߂���������ύX�ɂȂ�C�A�C�O�̂T�N�Ԃɂ��̉�Ёi�܂��͂��̎q��Ёj�̎�����E�x�z�l�E���̑��̎g�p�l�ɂȂ������Ƃ��Ȃ��҂Ƃ���Ă������C�����ł��̂T�N�̗P�\���Ԃ��Ȃ��Ȃ�C�u�S���̎ЊO�̐l�v�ł��邱�Ƃ��v�����ꂽ�B�����O�́C��Ђ̏]�ƈ��Ȃǂ��č����ɏA�C����P�[�X�������C�q�ϓI�Ō����Ȋč������҂ł��Ȃ���������ł���
�����������@�̉����ɔ����C���ۂɎЊO�č����̐l�����ǂ̂悤�ɕω����������݂��̂��C�}�\�P�ł���B�S����Ђ̊č���ݒu��Ђɂ����镽�ϐl����2.5�l�O��ň��肵�Ă���C�ߔN������X���ɂ���B�ЊO�č����͊č���S�̂̊T�˂U���ȏ���߂Ă���悤�ł���B
�܂��C�ЊO�č����̑������݂�ƁC2021�N�̃R�[�|���[�g�K�o�i���X�����ł͑��̉�Џo�g�҂�47.4�����߁C�ٌ�m�i21.0���j�C���F��v�m�i18.8���j�C�ŗ��m�i6.9���j�C�w�ҁi2.1���j�C�ƂȂ��Ă���B2005�N�̓������ł́C���̉�Џo�g�҂�61.8���ł������B�}�\�Q��2012�N�ȍ~�̐��ڂ������Ă��邪�C����ɂ��̔䗦�͌����āC�ٌ�m��ŗ��m�Ȃǂ��Ɨ����̍����Ǝv����l�ނ̔䗦�������Ă��邱�Ƃ��킩��B
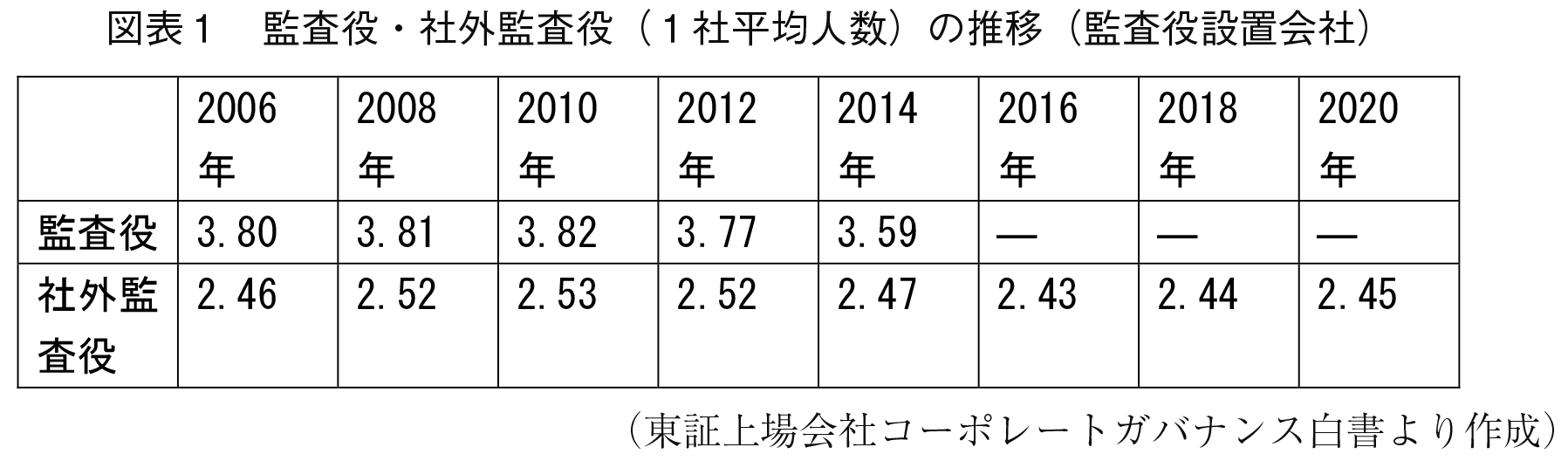
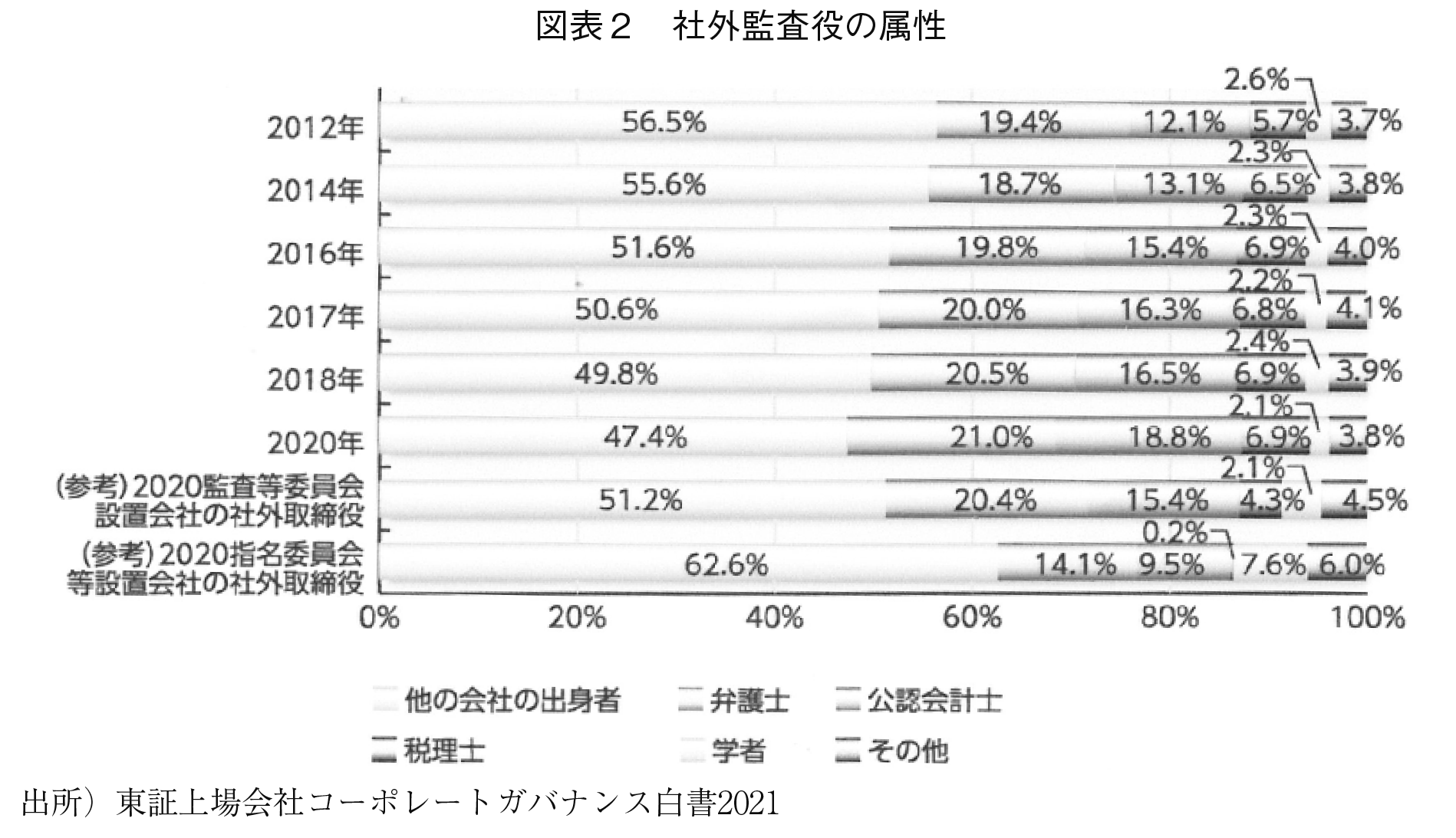
2.1.2�@�V���ȋ@�v�̓���
�������������ƕ��s���āC�A�����J�^�̃K�o�i���X�\�������悤�Ƃ���@�^�����܂����B���̖ړI�́C�[�I�Ɍ����C�ēƎ��s�@�\�̕����ł���B���{��Ƃ͏]���C��������Ɩ����s�@�\���S���C�ē@�\���\���ɔ�������Ă��Ȃ������B�Ɩ����s�@�\�Ɗē@�\�̖��������o�u�������C���[�J�[�C��s�C���ЁC�s���Y��Ђ��킸�C�����̑��Ƃŕs�ˎ���������������Ƃ݂Ȃ��ꂽ�̂ł���B�܂��C90�N��̓��{��Ƃ̋Ɛт̒���Ƒ����ɂ�����A�����J��Ƃ̋����ɂ��C�A�����J�^�̓����@�\���^������_�����}�X�R�~��w�E�ȂǂōL�܂����B������������̒��ŁC�w���ψ���C��V�ψ���C�č��ψ����u���A�����J�^�̈ψ���ݒu��А��x���������ꂽ�̂�2003�N�S���ł�����5�j�B
���̐��x�����������ȑO�ɁC�\�j�[�́C1997�N�ɓ��{�ŏ��߂āC���I�Ɋē@�\�Ǝ��s�@�\�������C���s���������̗p���C�������̊ȑf�����͂���ƂƂ��ɁC�ē@�\�̏[���Ǝ������Ɏ��g�B���̌�C�ǐ������Ƃ͋}���ɑ��������C�{���i2011�j�ɂ��ƁC����ɂ�2003�N�ɉ�Ж@����������C�`���I�Ȋč���ݒu��Ђƈψ���ݒu��Ђ̂����ꂩ��I���ł���悤�ɂȂ������߁C���{�̃��[�f�B���O�J���p�j�[�̑����́C�č���ݒu��Ђ̉��ŁC���s���������̗p���邱�ƂɂȂ����B�ψ���ݒu��Ђ̋@�v�̓����̈�́C�ЊO����̐l�ނ�o�p���C��Ƃ̌o�c�������Ď�������ƂƂ��ɁC��{�I�Ȍo�c���j�Ȃǂɂ��Ă��c�_���C�ӌ�������݂��邱�Ƃł������B�]���āC�ψ���ݒu��Ђɂ͈�萔�̎ЊO������̗̍p���`���Â���ꂽ�B
�������C���̎d�g�݂͓����o�g�҂ɂ���Ď��������\�����C���ւł̒����⍪��W�J���Ă������{��ƂɂƂ��āC�̗p�̃n�[�h�����������̂ł������B���̂��߁C�V�����ψ���ݒu��Ђ��̗p������Ƃ͂��������ɂƂǂ܂����B�����Č��݂Ɏ�����O�߂ŏq�ׂ��悤�ȗ��y325�Łz �R�ɂ��C�ψ���ݒu��Ђ̗̍p�䗦�͒Ⴂ���C�ЊO������̐l���́C���X�ɑ������Ă����̂͊ԈႢ�Ȃ��B���ɂ��̓��������Ă������B
2.1.3�@�ЊO�����I�C�̓���
�}�\�R�́C2006�N�ȍ~�̓��؏���БS�Ђ̎�����ƎЊO������̂P�Е��ϑI�C���̐��ڂ����������̂ł���B������݂�ƁC������̐l���́C2014�N�܂Ōp���I�Ɍ������C�������̃X���������}���Ă������Ƃ��킩��B����ɑ��āC�ЊO������̐l���͏��X�ɑ������Ă����B�\�̊��ʓ��̐����́C�ЊO�����I�C���`���Â����Ă��Ȃ������č���ݒu��Ђɂ�����ЊO������̐��ڂł��邪�C���̐����K�オ��ɑ����Ă���B
���ɁC2016�N�����ɂQ�{�ɑ����Ă��邪�C����́C�O�N��2015�N�ɃR�[�|���[�g�K�o�i���X�E�R�[�h�̓K�p���J�n���ꂽ�e���ł���ƍl������6�j�B�ЊO�������u���Ȃ��ꍇ�ɂ́C���̗��R�̐��������߂��邱�ƂɂȂ����̂ł���i�R���v���C�E�I�A�E�G�N�X�v���C���j�B�Ȃ�2021�N�̉�Ж@�̉����ɂ��C�č���ݒu��Ђɂ����Ă��ЊO������̑I�C���`���Â���ꂽ�B
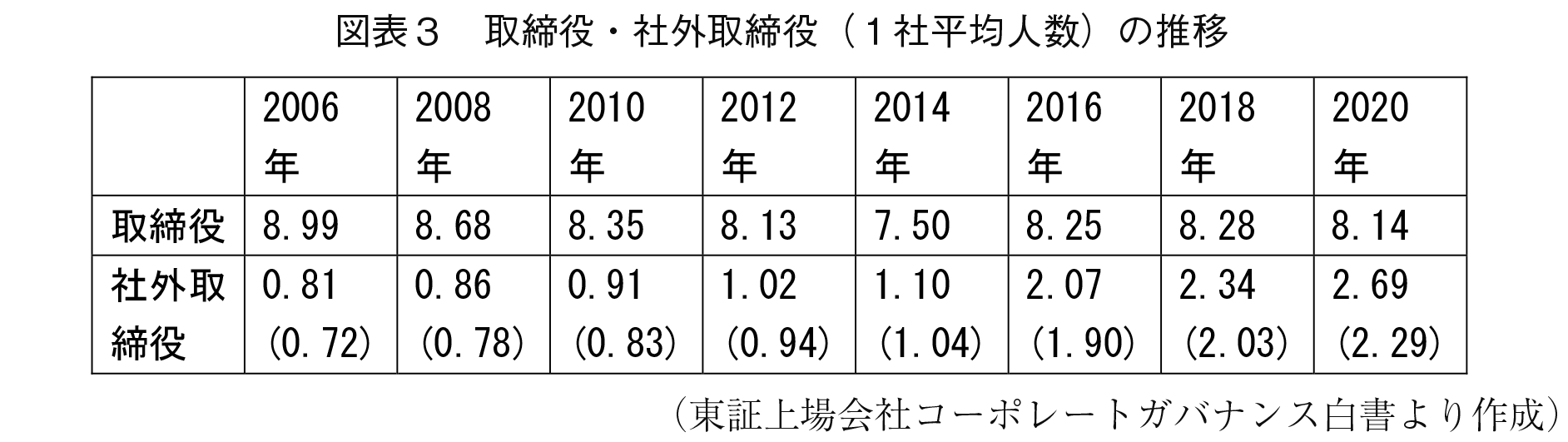
����ɋߔN�ł͎ЊO������̒��ł��C�Ɨ����̍���������̔䗦���d�v�ƂȂ��Ă���B�Ƃ����̂́C�ЊO������Ƃ����Ă��C���Y��ЂƊW�̐[���e��Ђ�֘A��Џo�g�҂̏ꍇ�ɂ́C�K�o�i���X���v�̖ڎw���ړI���\���ʂ������Ƃ��ł��Ȃ�����ł���B�������C�Ɨ��ЊO������̑������݂�ƁC2021�N�̔����ł͑��̉�Џo�g�҂�58.5�����߁C�ٌ�m�i16.3���j�C���F��v�m�i10.5���j�C�ŗ��m�i2.7���j�C�w�ҁi6.6���j�C�ƂȂ��Ă���B���̉�Џo�g�҂̔䗦�͔N�X�������Ă��邪�C�ЊO�č����ɔ�ׂđ����B����͈ψ���ݒu��Ђ̎ЊO������́C������̋Ɩ��̎��s�̊č������łȂ��C�Ɩ����s�̌���ɂ��]�����邽�߁C�o�c�ɐ��ʂ��Ă���l�ނ����߂��邩�炾�ƌ����Ă���B
�}�\�S���݂�ƁC2004�N�ɂ�30���ɉ߂��Ȃ������ЊO������̗p��Ƃ̔䗦�͔N�X�㏸���C2015�N�ɂ͂ق�100���߂��ɓ��B���Ă��邱�Ƃ�������B�ŋ߂ł͂��̂قƂ�ǂ��Ɨ��ЊO�������I�C���Ă���B�}�\�T�͎ЊO������ƓƗ��ЊO������̑��������������̂ł��邪�C���o225�����TOPIX100�̂�������Ƃ肠���Ă��C�l�������������Ă���l�q���݂ĂƂ��B�܂��C�}�\�U�C�V�͓Ɨ��ЊO�����I�C��Ƃ̔䗦�������Ă��邪�C��������o�N�I�ɑ������y326�Łz �Ă���B
�]���āC�ЊO�������I�C���邱�ƂŁC�킪���̓����\�������v���悤�Ƃ��鎎�݂́C����ƂɊւ��ẮC�����̏�ł͒B������Ă���ƌ����悤�B�������C���ԓI�ɎЊO����������҂���Ă���������͂����Ă��邩�ǂ����́C�����̗]�n������7�j�B���P�����i2021�j���w�E����悤�ɁC�������̏ꂪ�u�������v��������I�ȐR�c�̏�ɐ��܂�ς��K�v������B���̂��߂ɂ́C�ЊO������Ƃ��ēK�Ȏ�����L���Ă���l�ނ�I�C���邱�Ƃ����߂��邵�C�o�c�Ɋւ���l�X�ȏ���������Ɠ`�B���C�܂����s�����ӌ����p���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv����B
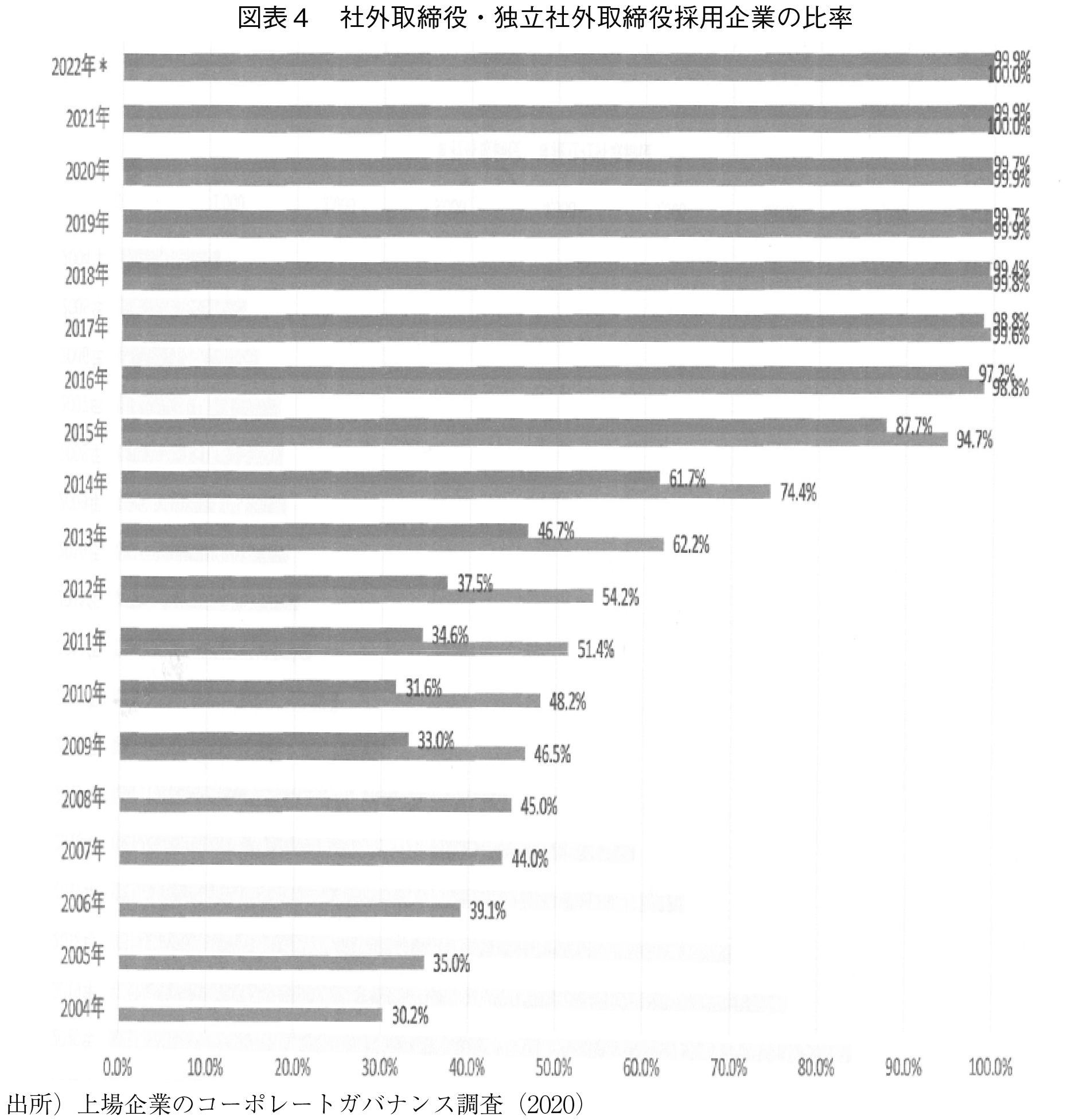
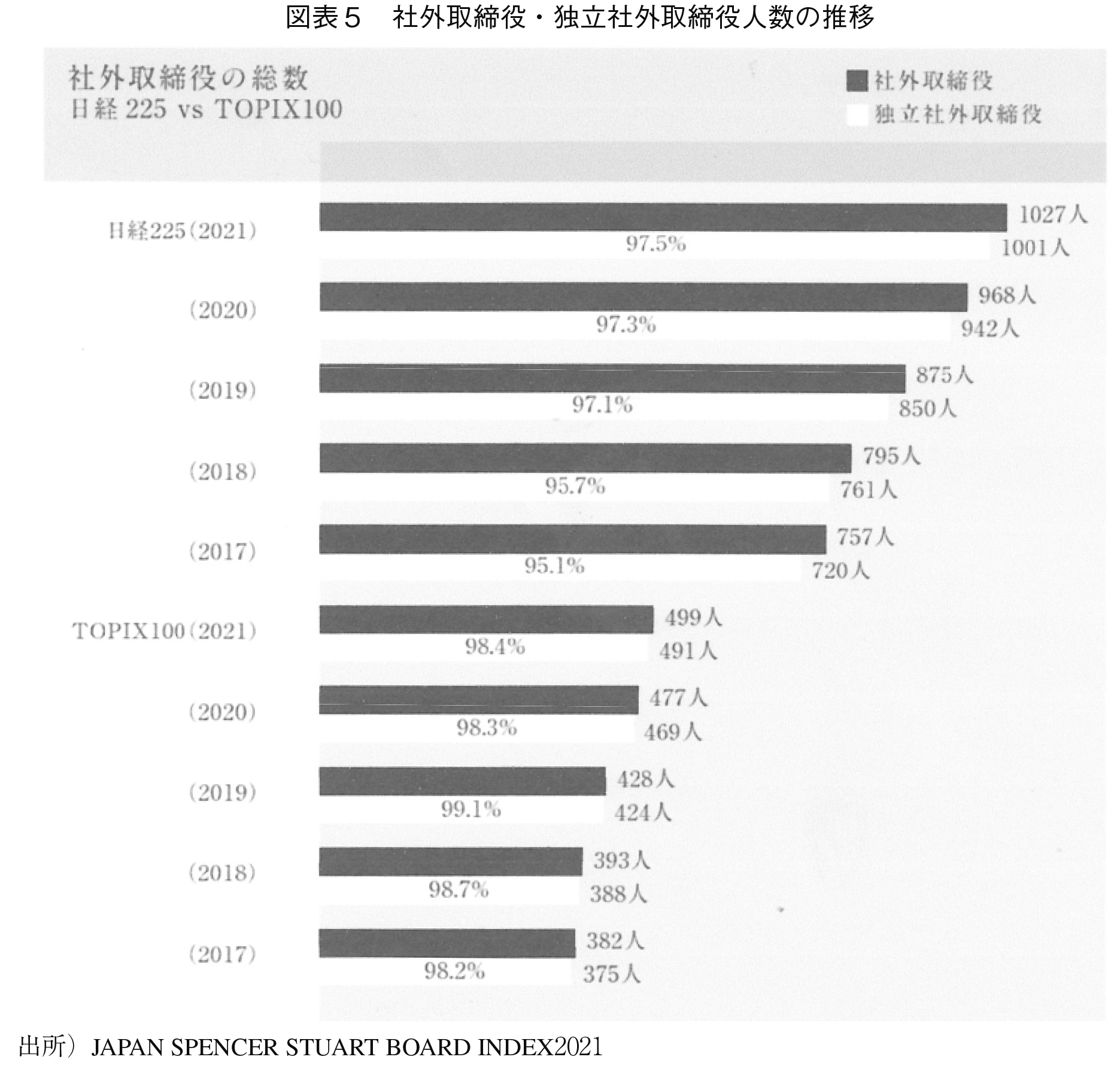
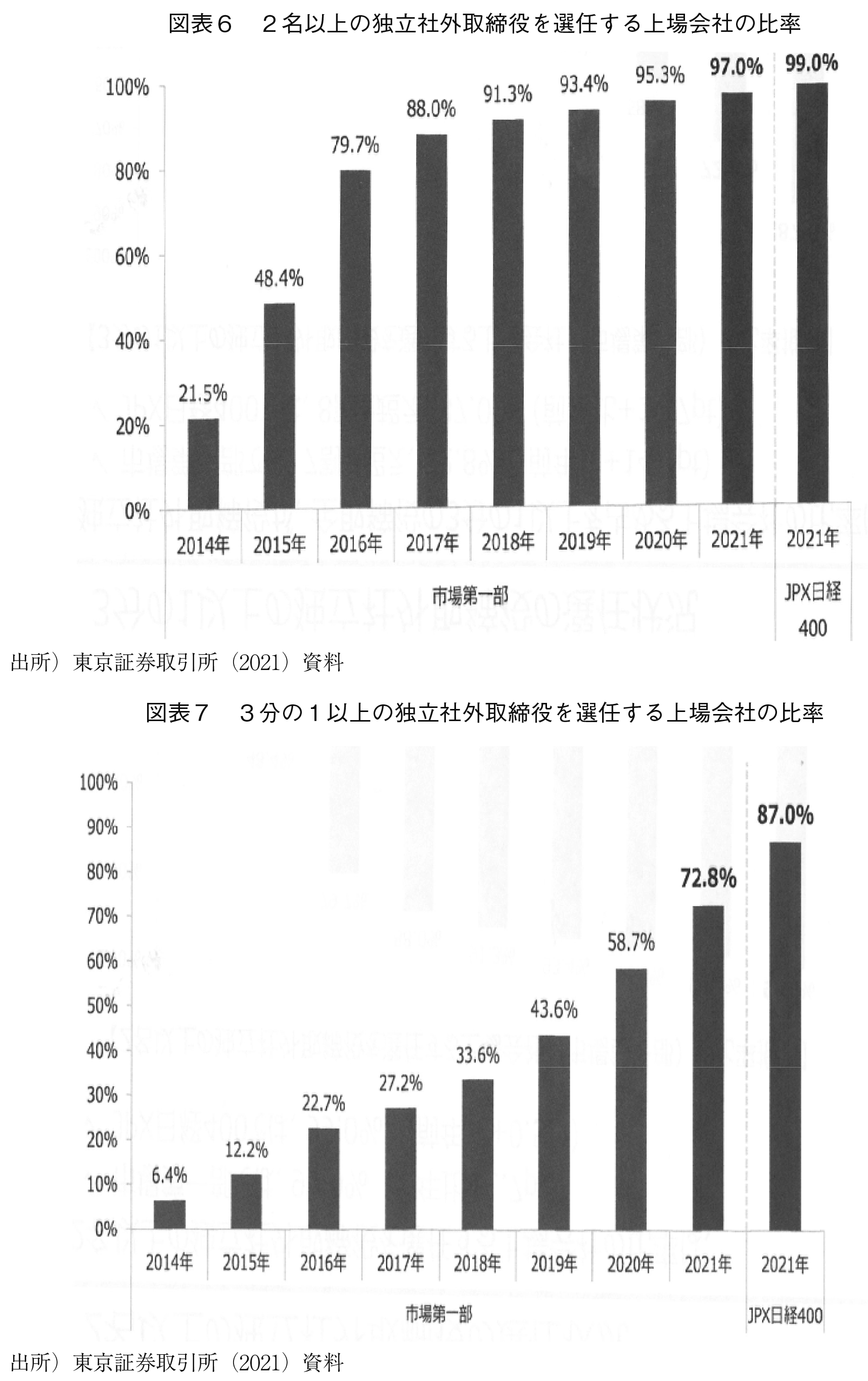
2.2�@���������C�O���l�����̓o�p
�u��㋭���Ȃ����̂͏��ƌC���v�ȂǂƂ����R�g�o���Ȋ����Ă������a30�N��C����͍m��I�������̂��ے�I�������̂��͖����ɒ肩�ł͂Ȃ����C���Ȃ��Ƃ����̍��܂ł́C����̈ӌ������鏗���ɑ��āu�����C���̂����ɁI�v�ȂǂƔ��_����j�����������������̂͊m���ł������B���̂悤�ɓ��{�ł͉��ĂƔ�r���Ă�������j���������낷�C���Ō����u�ォ��ڐ��v�Őڂ��Ă����͕̂�����Ȃ������ł��������C��������邱�Ƃ��K�v�������͖̂��炩�ł͂������B�����Ă����ڎw���Ċ����N��������
����ɂ����āu���������䗦�v�����Ӗ��C�u�����v�̖����C���邢�͊O���l�����䗦�C�u�O���l�v�̖����C�Ƃ������̂����Ӗ��͉��ł��낤���B�����̖ړI�́H
����́C�^�Ɂu�\�́E�ӗ~�v�̂���l���I�C�j���W�Ȃ��\�͎�`�ʼn�Ђ��^�c����̂���Ԃ��C�Ƃ������Ƃł���B�����ŏn�����ׂ��́C�����_�ŏ����̔䗦�����߂邱�Ƃ́C����Ώ��Ȃ��Ƃ��C�f�I���M�[�I�ɕK�v�ł���C���R�ɔC���Ă����Ă͐i�W���Ȃ����낤�ƁC���Ȃ薾�m�ɗ\�z�ł��邱�Ƃ���C�u�܂��͎��i�߂悤�v�Ƃ����p�����������Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃł��낤�B
���Ȃ킿�C���������䗦�����߂邱�Ƃ̖ڕW�́C�܂��́u���߂邱�Ǝ��́v�ł���C�ƔF������K�v������ƕM�҂�͍l���Ă���B����͌���������C������o�p���邱�ƂŎ��v�͂����߂悤�Ƃ���Ɖ��l�傳���悤�C�ȂǂƂ������Ƃł͂Ȃ��C�Ƃ����Ӗ��ł���B���̓_������i���邢�͈Ӑ}�I�ȗ��p�H�j���āC�����䗦�������Ǝ��v���������Ƃ����u���v�v���f������i���t�{�j�������Q��ǁu���O���ɂ������Ɩ����̏����o�p�ɂ��āv�ߘa�S�N4��21���Ȃǁj�C����CMeier���i2022�j�̂悤�ɏ��������䗦�̍�����Ƃ͊�Ɖ��l���Ⴂ�ȂǂƁC�����_�Ō��������Ă����܂�Ӗ��͂Ȃ��悤�Ɏv����̂ł���B
2.3�@�h�C�c�ł̌���i���ʁj
�h�C�c�ł́C2016�N�P�����珗���䗦�@�i���邢�͏��������@�CGesetz zur Frauenquote�C�ʏ́u�����N�H�[�^�@�v�j���{�s����C���݂Ɏ����Ă���B�Ɨ��s���@�l�E�J�������E���C�@�\�ɂ��Ǝ��̒ʂ�ł���i���ʘJ���g�s�b�N�F2015�N�U���j�B
�A�M�Q�c�@�͂R��27���C�����N�H�[�^�@�����F�����B���@�̐����ɔ����C�����108�Ђ́C2016�N�P������ē���̏����䗦��30���ȏ�Ƃ��邱�Ƃ��`���t������B����ɑ����3500�Ђɂ́C������Ǘ��E�̏����䗦�����߂邽�߂̎���ڕW�̐ݒ�C��̓I�[�u�C�B���Ɋւ���`�����ۂ����B�����N�H�[�^���́C�����Ɍ��I����ɂ��K�p�����B
���������u�����N�H�[�^�@�iGesetz zur Frauenquote�j�v�̐������̂́C�u���Ԋ�Ƌy�ь��I���y330�Łz ��̎w���I�n�ʂɂ�����j�������Q���̂��߂̖@���iGesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst�j�v�ŁC�E��̈ӎv����Ɋ֗^�����w���̒j�������Q��𐄐i���邱�ƂŁC��ʘJ���҂ɂ����̌��ʂ�g�y�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B
����̌��ő傫���N���[�Y�A�b�v���ꂽ�u�ē���iAufsichtsrat�j�v�́C���s���̔C�ƁC�����v��C�l���v��C�����̌��蓙�ɂ��ċ���������L���Ă���B����́C�]�ƈ�����ƌo�c�̈ӎv����ɎQ��ł���u��������v�Ƃ����h�C�c���L�̐��x�ɗR��������̂ŁC�Ⴆ�Ώ]�ƈ�2000�l���̏���Ƃł́C��������@�iMitbestimmungsgesetz�j�Ɋ�Â��C�u�ē���v���ݒu�����B�ē���́u�����\�v�Ɓu�J���ґ�\�v�ō\������C���̊������P��1�̏ꍇ�C������u���S�ȋ�������v�Ƃ����B����C�����N�H�[�^�������������̂́C���S�ȋ�������`���̂�������108�ЂŁC2016�N�ȍ~�C�V���Ɋē��̈ψ���I�o����ꍇ�C�����䗦�i�j���䗦���j���Œ�ł�30���ȏ�ɂ���`�����ۂ����B�Ȃ��C�ŏI�I�ɐ��������@���ł́C�����\�ƘJ���ґ�\�̑����ɑ���30���ȏ�̔䗦�ł���Ηǂ��Ƃ��ꂽ�B�������C�ψ��I�o�O�ɁC�ǂ��炩���ً`��\�����Ă��ꍇ�́C�ʌ�30���K�肪�K�p�����B�Ȃ��C�������\���ɑI�o����Ȃ������ꍇ�ɂ́C��Ȃ��ێ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��i��Ȑ��فFSanktion leerer Stuhl�j�B
�Ώۊ�Ƃ̂����C�w���P���i���[�J�[�j�C�~�����w���ĕی��i�ی��j�C�����N�i���w�E���i���[�J�[�j�ł͂��łɁC�ē��̏����䗦�����ꂼ��43.8���C40.0���C37.5���ɒB���Ă���B���̈���ŁC�����̊ē����P�l�����Ȃ��Ƃ�����Ƃ�����C��҂͍���̖@�Đ����ő傫�ȉe������ƌ����Ă���B
�O�q��108�ЈȊO�ɂ��C�u����Ƃ��C�]�ƈ�500�l���̋�������`���̂����3500�Ёv��ΏۂɁC�ē���C���s����C�Ǘ��E�i�㋉�E�����̓�w�j�ɂ����鏗���䗦�����߂邽�߂̖ڕW�l���̓I�Ȏ��g�ݓ��e��2015�N�X�����܂łɐݒ肷��悤���@�ł͋��߂Ă���B�ڕW�l�̉����͋K�肳��Ă��Ȃ����C����ŏ����䗦��30�������̏ꍇ�C���������ڕW��ݒ肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ŏ��̖ڕW�B��������2017�N�U�����ŁC���̖ڕW�ݒ�ƒB�������͂T�N�ȓ��Ƃ���Ă���B�������C����ڕW��B���ł��Ȃ�������Ƃւ̖@�I���ق͓��ɐ݂����Ă��Ȃ��B
���@�́C�����������I�W�@�ւ̏����N�H�[�^���ɂ��Ă��K�肵�Ă���B
�h�C�c�ł͏]������C��������ɂ�����j�������𐄐i���邽�߂ɂQ�̖@�������肳��Ă���B�u�A�M�����@�iBundesgleichstellungsgesetz�j�v�́C�A�M�̊e�@�ւɑ��āC�j�������v��̍�����`���t���Ă���C�����䗦��50�������̕���ɂ�����̗p�⏸�i�̍ۂɁC����̓K���C�\�́C���I�Ɛт�����ꍇ�ɂ́C������D��I�ɍl�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��C�u�A�M�ψ���\���@�iBundesgremienbesetzungsgesetz�j�v�́C�A�M�̊����ɉe�������ψ��I�o�̍ۂɂ́C�\�Ȍ���j���Ə����̐����ϓ��ɂȂ�悤�ɒ�߂Ă���B�����N�H�[�^�@�́C��q�̂Q�̖@�����������邱�ƂŁC����w�̒j�������̑��i��}��B��̓I�ɂ́C�A�M�����@�̉����ɂ���āC�s���@�ցC�ٔ����C�A�M�����̌��I�@�ցi��:�A�M�ٗp�G�[�W�F���V�[�j�C���I����y331�Łz �i��:�Љ�ی��g�D��A�M��s�j�ɑ��āC�]���̒j�������v��̒��ŁC�����Ǘ��E�̊����Ɋւ����̓I�ȖڕW�l���K�w���Ƃɒ�߁C�ڕW��B�����邽�߂̋�̓I�ȑ[�u���Ƃ邱�Ƃ��`���t����ꂽ�B����ɘA�M�ψ���\���@�̉����ɂ���āC�A�M���R�l�ȏ�̈ψ����w������ē���i��:�h�C�c�S��������Ёj�ɂ����ẮC2016�N�P���ȍ~�C�A�M���w������ψ����j���Ƃ���30���ȏ�ƂȂ�悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����2018�N�ȍ~�́C���̔䗦��50���Ɉ����グ����i��̏ꍇ�̂P�l�̍��͋��e�j�B
����C��Ƃɂ����鏗���N�H�[�^����@���ŋ`���������w�i�ɂ́C2001�N�ɐ��{�Ǝg�p�Ғc�̂������������g���肪�W���Ă���B���̋���ł́C�w���I����̏����䗦�̈����グ�C�j���̋@��ϓ��C�]�ƈ��̃��[�N���C�t�o�����X�x���ȂǂɊ�Ƃ�����I�Ɏ��g�ނ��Ƃ��K�肳�ꂽ�B�������C���̌�10�N�ȏ�C�w���I����̏����䗦�͂قƂ�Ǐ㏸�����C�u��Ƃ̎��含�ɔC���Ă��������Ȃ��Ƃ����������ǂ̔��f���������v�ƁC�h�C�c�o�ό������iDIW�j�̃G���N�E�z���X�g���m�͌��Ă���B�����m�́u����̖@��N�H�[�^���̓����ɂ���ĘJ���҂̓��������ƕ����̕ϊv�C�o�ϑS�̂̊������C�Љ�ۏᐧ�x�̈ێ��ȂǁC�L�͈͂ɂ킽��g�y���ʂ����҂ł���v�Ƃ��Ă���B
DIW�̏����Ǘ��E�o�����[�^�[�����iManagerinnen-Barometer�j�ɂ��ƁC2014�N���_�̏��200�Ђ̎��s����C�ē���ɂ����鏗���̊����́C���ꂼ��5.4���C18.4���ɗ��܂��Ă���B
�����N�H�[�^�@�́C�i�@�E����ҕی�ȂƉƑ��E����ҁE�����E���N�Ȃɂ�苤���Œ�o���ꂽ�B�n�C�R�E�}�[�X�i�@�E����ҕی쑊�́u�����N�H�[�^���̓����́C�����̎Q���������ȗ��́C�����ւ̍ő�̍v���ƂȂ邾�낤�B�\���Ȏ��i��L�������������Ȃ��Ƃ��������͎t���Ȃ��B�������ɍ������x���̋����P�������������吨����C�ǂ̊ē���ł���ȂƂ������Ԃ͋N���Ȃ��Ɗm�M���Ă���v�Əq�ׂ���ŁC�u�����N�H�[�^���́C�\���I�ɗl�X�ȃ��x���̏����̎Q���𑣂��C�����Ȍ����ւ̃}�C���X�g�[���ƂȂ邾�낤�v�ƌ�����B�}�k�G���E�V�����F�[�Y�B�q�Ƒ��E����ҁE�����E���N���́C�u���@�́C������ς��邽�߂̎n�܂�ł���B�P�Ȃ�N�H�[�^�ȏ�̈Ӗ��������C�����̎w���I����̏����������邱�Ƃ́C�ˑR�Ƃ��đ傫���j���̒����i���̉��P�ɂ��Ȃ���B���̈Ӗ��Œ����̕����ɂƂ��Ă����j�I�ȂP���ƌ����邾�낤�v�Əq�ׂāC���@�̐��������}�����B
����ŁC�o�ϊE�̔��͍������B�h�C�c�g�p�ҘA���iBDA�j�́u�����I�ɏ����䗦���߂Ă��C���{�I�Ȗ������ɂ͂Ȃ���Ȃ��v�Ɣ������Ă���B
�h�C�`�F�E���F���i���ی��������j�̃E�e�E���@���^�[�L�҂͘_���L���ŁC�u�����N�H�[�^�@�́C��Ƃ�Љ�̕�����ς��邩������Ȃ����C�ē���͎��s������ӎv����͂��������C�䗦�ɖ����Ȃ��ꍇ�͋�Ȃ̂܂܂ɂȂ邽�߁C���ʂ̒��x�͋^�₾�v�Ƃ��Ă���B���̏�ŁC�u���i���[���̂���Ȃ铧�����C�_��ȘJ�����Ԃ̎��{�C�玙����x���̋����C�ӎv����̒����ł����Ƃ̎��s����ɂ����鏗���̐i�o���d�v���v�Ƃ��Ă���B
���̂悤�ȃh�C�c�ł̓����ɂ��ẮC�܂��Ƀh�C�c��Ō����uJa und Nein�v�Ƃ����]�������Ă͂܂�Ǝv���B���Ȃ킿�C�U�X�q�ׂĂ����ʂ�C�j���ɔ�ׂĈ�ʓI�ɏ��������ɗL�\�C�Ȃǂƍl���Ă���l�́C�����͂Ȃ����낤�B�������C�������L�\�ł͂Ȃ��C�ȂǂƎv���l�����y332�Łz ���͂Ȃ����낤�B�d�v�Ȃ̂́C�܂��͌����ς��邱�ƂŁC���̂����Ő��ʂ��l���邱�ƂɂȂ�B
�����ŕM�҂炪�x������ׂ��ƍl���Ă���̂́C�����̎Q���́u���l���𑝂��v�Ƃ��u�����炵����ʂ����҂���v���X�̂������I�����ʔ����ł���B���������u���l���v�ȂǂƂ����͉̂����B�u�����炵����ʁv�Ƃ����̂͋�̓I�ɂǂ��������Ƃ��B�����ɑ���^��E����ɑ��āC�ʂ��Ղ̈Ӗ��s���̐������Ȃ��ꑱ���Ă��Ă��āC��̓I�ɔ[���ł�����C�M�҂�͉Ǖ��ɂ��Ēm��Ȃ��B�܂�Ƃ���C�����Ă����炭�����Ƃ��d�v�Ȃ̂́C��ƌo�c�ɂ�����ӎv����ɂ������ẮC�L�\�Ȑl�ł���C�j���ł������ł����ق͂Ȃ����낤�C�Ƃ������Ƃł���B
�����ŁC�h�C�c�ɂ����鏗���䗦�Ǝ��v���E��Ɖ��l�̊W�̌����Ɍ��y���Ă���8�j�B
2016�N�P���{�s�̊Ǘ��E�ʖ@�iFührungspositionen-Gesetz�CFüPoG�j�ł́C�ē�����o�[��30���������ł��邱�Ƃ��C����̊�Ƃɂ��ėv�]���Ă���B���̌����ł́C�ē���ɂ����鏗���̊����̑�������Ɖ��l�̒ቺ�Ɗ֘A���Ă���Ƃ������_�ɒB���Ă��邪�C���v�ւ̉e���͓���ł��Ă��Ȃ��B����͊m���ɐ����I�ɕ��c���������ʂł��邪�C�ē���ŏ��Ȃ��Ƃ��R�l�̏����Ƃ����u�K���v�ɓ��B����ƁC��Ђ̉��l���ቺ����Ƃ��������ɂ����f����Ă���Ƃ���B�Ǘ��E�ʖ@�̓������C�������ꂽ�p�t�H�[�}���X�ϐ��̃��^�[���Ɗ�Ɖ��l�ɗ^����e�����}�C�i�X�ł���Ƃ��Ă���B
�M�҂�̊ώ@�ł́C���̌����ł̓��v�I�Ȍ��ؕ��@���C���l���F�߂���̂ł��邩�ǂ����C�^��̗]�n�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ����C�ꉞ�����������_�ɒB���Ă���̂́C�����ł��낤�B
���{��Ƃɂ����鏗���̗���i����j�ɂ��ẮC���Ɂu�q�ϓI�f�[�^�v�Ə̂�����̂��������咣�ł����Ă��C���́u�q�ϓI�f�[�^�v�̔w�i�y�т����ւ̕��́E�����̕��@���^�ɂ݂�ȂɂƂ��Ĕ[���ł�����̂����m�F�ł�����̂łȂ���C�����͂͊��҂ł����C�\�����������咣�ł͂Ȃ����C�Ƌ^���邱�Ƃ͔������Ȃ��C��������邵���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��ƍl���Ă���i�O�q�̓��t�{�j�������Q��ǁu���O���ɂ������Ɩ����̏����o�p�ɂ��āv�ߘa�S�N4��21���Ȃǁj�B
�I���R�b�g�i2010�j�́CConflict and Change --- Foreign Ownership and the Japanese Firm, Cambridge University Press�i2009�j�̖�ŁC�O���l�̖ڂ��猩�����{��Ɓi���{�I�o�c�j�ւ̋����[���ώ@�ł���ƕM�҂�͍l���Ă���B�����ł͑�U�͂Łu�����Ј��v�Ƃ����L�q������C��ǂɒl����ƍl������B
���_�͎��̂悤�ɂȂ��Ă���9�j�B
�S�̓I�Ɍ��āC�����ł̒�����Ƃ̕�����ʊ�Ƃ�菗���]�ƈ��̏��i�@��͌b�܂�Ă���悤���B��ʐE�C�����E�̂悤�ȋ�ʂ�C�����̂悤�ȏے��͔p�~���ꂽ�B�V����s�͓��ɊǗ��E�ɂ����鏗���]�ƈ����������B�������Ȃ���C�j�������̏]�ƈ��̊Ԃŕω��̔F���͒�����Ƃɂ����ė\�z�����قNj����Ȃ��C����̒������ڂ̒��ł͍Œ�ł������B���̂����y333�Łz �́C�ēx�C���傪�ς�邾���ł͐[�����ߍ��܂ꂽ�W�F���_�[�ɑ���p����ς���ɂ͏\���ł͂Ȃ����Ƃ��������Ă���10�j�B
���̏͂ł̏��q���\������̂Ƃ��āC�V����s�ł̏��������E���̑����ɂ��Ă̂��̂�����B
�V����s�ł́C�����i�ے��ȏ�j�ɐ�߂鏗���̔䗦��1998�N��1.0������2003�N�ɂ�10.0���܂Ŕ���I�ɑ����Ă���B���̗��R�Ƃ��ċ������Ă���̂́C�V�o�c�w�ɂ�钼�ړI�ȃg�b�v�_�E���̉���ł���C�V����s�ł�2003�N�X���ɖ{�Ђɑ��������J�݂��C���̂R�N�Ԃŏo�Y�E�玙�x�ɂ�����������̂���94�����E��ɕ��A�����B�������̊J�݈ȗ��C�呲���q�̉����20������30�����������C�Ƃ��Ă���B
�܂��C�u���Z�T�[�r�X�Q�v�̉�Ђł́C�����Ǘ��E���ӎ��I�ɑ��₳�Ȃ��Ă��C���r�̗p�𑝂₷���ƂŎ��R�ɏ����Ǘ��E�����������Ƃ����B���̗��R�̈�Ƃ��āC�������j�������p����K�����Ă��邱�Ƃ��������Ƃ����B���̉�Ђ̊Ǘ��E�ɂ��C�ȑO�͑����E�̏����𑽂��̗p���Ȃ������̂ŁC���i������ׂ����������������͂Ȃ������B�ŋߍ̗p�������������̑唼�̓o�C�����K���ł���B�������r�̗p���s���ꍇ�C�o�C�����K���ł��邱�Ƃ������Ƃ���Ȃ�C�K�������̕����������傷��ł��낤�C�Ƃ��Ă���B
�V����s�̃P�[�X�œ��Ɍ����Ǝv���邪�C�������Ǝ��̃v���b�V���[�Ɛ킢�Ȃ���L�����A�`�����ł���悤�ȐE��Â���̏d�v���C���[�L���O�}�U�[���x�����邽�߂Ɋ�Ƃ����ʂȓw�͂��邩�C�Ƃ������Ƃ��傫�ȗv���ł��낤�B
�W�F���_�[�ɂ��@��ϓ��Ƃ����̂́C�����̎p���͓��ɕێ�I�ŁC�����̏��i�ɂƂ��đ������ƂȂ��Ă����Ƃ����B���ߍ��܂ꂽ�u�Љ�K�́v�ɂ���Ēj�������ւ̐i�W�͊ɖ��Ȃ��̂ɂȂ炴��Ȃ������B���Ƃ��Βj���]�ƈ��������̏�i�������Ƃ�����邱�Ƃɂ́C������������t���܂Ƃ��Ă���B
����ɂ��ẮC����̒j���Ǘ��E�ɂ��ƁC�u�����͂����ꌋ���E�o�Y���邩��吨�ق��Ȃ��v�Ƃ����Â��N�w�����݂���B�P�ɗǂ��l�ނ��K�v�Ȃ̂ł���C���̂悤�Ȑ�����Î邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������Ȃ���C�������܂߂Ēj���������̏�i����������ǂ��v�����낤���Ƃ������Ƃɕ\���悤�ɁC�F�X�ȂƂ���ɌÂ��l�������c���Ă���B�قƂ�ǂ̐l���C�j���̏�i���������Ƃ��Ɠ����悤�ɂ͂��܂������Ȃ����낤�ƍl���邾�낤�B����͓��{�S�̖̂��ł���B
�O���l�̖ڂ��猩���ЂƂ̓��{�I�o�c�_�C���{��Ƙ_�Ƃ������ƂɂȂ�ƁC���̂悤�Ȉӌ��ƂȂ�B���{�ł́C�u�Â��������Ă���C���݂��Ă�����̂́C�w�����Ƃ����x���R��������̂ŁC��������̂��킴�킴�ے肷�邱�Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ����v�z������ɂ�����̂ŁC���̂悤�ȁu�����v���{�v�z�ɑ����Ȃ����̂悤�ȏ��q�́C��͂�ڂ𗯂߂�K�v�����邾�낤�B�������C���łɑO�ŏq�ׂĂ���悤�ɁC�����������Ј��E�����ɂȂ邱�Ƃ�����傫�ȗ��R�̈���C�ނ�̑傫�Ȏ咣�ł���u�����E�v�Ɓu��ʐE�v�̕��ނ̑��݂��C�Ƃ������Ƃ́C�N���ڂ���炷���Ƃ��ł��Ȃ����̂ł���B
�O���l�����̓o�p�ɂ��ẮC�܂��Ɉ�ؓ�ł͂����Ȃ��g�s�b�N�ł���B���������ނ���y334�Łz �p��ňӌ����\���邱�ƂɂȂ邪�C���{�l�����Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����̂��߂Ɂu�����ʖ�v��o�p���邱�ƂɂȂ�B�������Q���ґS�̗̂����̂��߂ɂ͂��ꂪ��ԂƂȂ邩��ł���B�������C�����ł͂����炭�Q�̓�_���������邱�ƂɂȂ�B
�@�@�����ł̊�ƌo�c�̂��܂��܂ȍׂ������́C�͂����Đ������`��邩�B
�A�@�u���{�I�o�c�v�̗ǂ��ʂɂ��āC�ނ�͐������������Ă��邩�B
�O�҂ɂ��ẮC�����炭�v���̐l�X���S�������̂ŁC�����M�����邵���Ȃ����낤���C���Ƃ����Ă���ƌo�c�̘b�ł��邩��C�T�d�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ł��낤�B��҂͍ł��d�v������g�s�b�N�ŁC����́C�Ȃ��Ȃ��ۏ͂���Ȃ��̂ł͂Ȃ����C�Ƃ����̂��M�҂�̈�ۂł���B�O���l������ɂ����_�̎w�E�͂������ɏd�v�Ȃ��Ƃł��邪�C���X�ɂ��ċN����u�ᔻ�v�́C���ꂪ���{��Ƃ̌o�c�ւ̗������s�\���ł��邱�ƂɋN�����Ă͂��Ȃ����C�Ƃ������Ƃ́C��ɓ��̋��ɓ���Ă����K�v�����邾�낤�Ǝv����̂ł���B
3.1�@SDGs/ESG�����Ƃ�
�����\���i�T�X�e�i�r���e�B�j�����㐢�E�����L�[���[�h�ƂȂ��Ă���B���̔w�i�ɂ͒n���K�͂ł̊����̐[����������B���ɍ����ُ̈�C�ۂ̑����́CCO2�r�o�ʂ̋}�㏸�ɔ����~�܂�Ȃ��C���㏸�Ɍ���������Ƃ���C���̖��̔����ɂ́C�Љ���\������l�X�̂����銈�����ւ��ƍl�����邪�C�����Ă���Ƃ̌o�ρE�Y�Ɗ����ɋN������ʂ͑傫���B
����������@�I�̒��ŁC2000�N��ɓ����āC���A�͊�ƂⓊ���ƂɌ����Ă������̒����Ă���B2006�N�ɂ͓����ƂɌ����ĐӔC���������iPRI�j������B����ȍ~�C�����\�����d������ESG�������}�g�債�Ă���BESG�����Ƃ́CE�o�ρCS�Љ�CG�K�o�i���X���l�����āC�����Ƃ͍s�����ׂ��ł��邱�Ƃ�����Ă���B��Ɗ����̐��ʂ���������ӓ|�ł͂Ȃ��C�Љ�ۑ�ւ̌������������Ɠ����̑̐���������ɓ���ĕ]�����ׂ��ł���Ƃ̍l�����Ɋ�Â��B
����1960�N��Ɏ����Ԃ̔r�C�K�X��H�ꂩ�牘�������̔r�o�ɂ���āC���Q��肪��i���Ő[���Ȗ��ƂȂ�C��Ƃ̎Љ�I�ӔC�iCSR�j������ɘ_����ꂽ����������B���Ƃɑ���ᔻ�����E���Ŋ����N�������B��Ƃ͗�����Nj����邾���łȂ��C���Q��n�����C�i�����Ȃǂɂ��z�����āC�s�����ׂ��ł���Ƃ̋c�_���W�J���ꂽ�B
����ɑ��āC�t���[�h�}����̐V�ÓT�h�o�ϊw�҂́C��Ƃ͑��`�I�Ɋ���̂��߂ɗ����ő剻��Nj����ׂ��ł����āC���ꂪ�o�ς̌����������߂�̂ł���C�@����K���ɑ����Đ��Y�������s������C���ɒS���ׂ��ӔC�͂Ȃ��Ǝ咣�����B���Q����������Ƃ���C�@����[�������Ȃ̂ł����āC�ǂ̂悤�ȃ��[�����쐬���C�K�p���邩�͐��{�̐ӔC�ł����āC��Ƃ��ӔC���ׂ����ł͂Ȃ��Ƃ����B����́C�p�Ăɂ�����V�F�A�z���_�[�E�A�v���[�`�ƌĂ��l�����ł���C���݂ł����̎x���Ă���B
�������C��ƁC���ɑ��Ƃ̊����������炷�Љ�ւ̃v���X�E�}�C�i�X�̉e���i�O���o�ρE�O���s�o�ρj�́C�ɂ߂đ傫�����̂�����C���{�̋K���Ŏ�����Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�B�o�c�w�̕���ł́C�Ƃ�킯���������ϓ_�����ƂƎЉ�̖�肪���グ���C��ƂƎЉ�Ƃ̂���ׂ��W��L���Ӗ��ł̊�Ƃ̎Љ�I�ӔC���_�����Ă����B��Ɗ����Ɗւ��y335�Łz ��C�����Ă�������e�����鑽�l�ȗ��Q�W�҂��l�������o�c�������]�܂����Ƃ�����̂ł���C����̓X�e�[�N�z���_�[�E�A�v���[�`�Ƃ�����B���Ƃ̗L���Ă���Z�p����C���Y�ȂǂɊւ��Ă̈��|�I�D�ʐ����l����C�o�c�҂͎���̈ӎv���肪�Љ�y�ڂ��e���܂��čs�����邱�Ƃ��v������悤�B
���̓_�͌o�c�҂̎��o�����ł͂Ȃ��C��ƂɎ�������铊���Ƃɂ��������Ȃ��ӎ��ł���Ƃ����̂��C���A��ESG�����̒Ɍq�������Ƃ����悤�B��Ƃɓ�������ۂɁC���Y��Ƃ̌o�ϊ����̑��ʂ����łȂ��C�Љ���ɑ��Ăǂ����g��ł��邩�C�����Ċ�Ƃ��^�c����K�ȃK�o�i���X�̐����m�����Ă��邩��]�����C�����������邱�Ƃ����߂��̂ł���B
���̌�C���A��2015�N�ɃO���[�o���ȎЉ�ۑ���������C�����\�Ȑ��E���������邽�߂̍��ۖڕW�ł���SDGs�i�����\�ȊJ���ڕW�FSustainable Development Goals�j���̑������B����́C�����\�Ȑ��E���������邽�߂�17�̃S�[���i�ڕW�j�E169�̃^�[�Q�b�g����\������C�n����̒N��l�Ƃ��Ďc���Ȃ��ileave no one behind�j���ƂȂǂ�搂��Ă���11�j�BSDGs���т������Ƃ��Ĉȉ��̂T�̓�������������B
���Ր��@��i�����܂߁C���ׂĂ̍����s��
��ې��@�l�Ԃ̈��S�ۏ�̗��O�f���u�N��l���c���Ȃ��v
�Q��^�@�S�ẴX�e�[�N�z���_�[��������
�������@�Љ�E�o�ρE���ɓ����I�Ɏ��g��
�������@����I�Ƀt���[�A�b�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�O���ȃz�[���y�[�W���j
���̂悤�ɁC2010�N��ɓ����āC�����\�Ȓn�����̈ێ��C�n����l���ւ̖ڔz�肪�S���E�I�Ɉӎ������悤�ɂȂ�C��Ƃɂ�������������o�ϐ��������O�����߂��C�����������O������܂łƂ͈قȂ����������x���Ŏ��ۂ̊�Ɗ����ɔ��f�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ����ƂȂ����̂ł���B
3.2�@���{�I�o�c�Ƃ̊W
SDGs���邢��ESG��搂��Ă��邱�Ƃ́C���{��ƂɂƂ��ẮC���̂Ƃ���K�������ڐV�������̂ł͂Ȃ��B���Q�W�҂�厖�ɂ���o�c�́C���Ă̋ߍ]���l�́u�O���悵�v�̌o�c���O�ɕ\��Ă���B���Ђ̗��v���������܂�悢�Ƃ͍l�����C�����I�Ȋ�Ƃ̑����E�������������邽�߂ɂ́C�u�����ɂ����Ĕ����Ɣ����肪��������͓̂��R�̂��ƁC�Љ�ɍv���ł��Ă����悢�����Ƃ�����v�Ƃ����o�c�N�w�ł���12�j�B���������o�c�N�w�̐Z�������{�ɒ�����Ƃ��������Ƃ̈���ł͂Ȃ����ƌ����Ă���13�j�B���̓N�w�͉p�ė��̊��咆�S��`�Ƃ͑��y336�Łz ���ɈقȂ�B�Љ�ۑ������ɓ��ꂽ�o�c�́C���{�ł͍]�ˎ��ォ����I�Ɏ��H���Ă����Ƃ��]���ł��邩������Ȃ��B
�������C���{�ł����Q��肪�������Ă���C�Â��͖�������̑������R�̌��Q�C�܂��S����Q�i�ׂɑ�\�����C���x�������̐[���Ȋ����������Ƃɂ���Ĉ����N�����ꂽ�����Ƃ͔F�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�{���ɗ��Q�W�ґS�ʂɖڔz��̂������o�c�������Ȃ��Ă����̂������B�������Ȃ���C�����������̗��j��������C�������`�������{�̊�Ƃ̌o�c�ڕW�ł������킯�ł͂Ȃ��B�p�Ċ�Ƃɔ�r����C���ΓI�ɂ͊���ȊO�̊W�҂ɂ��z�����Ȃ���o�c���Ă����ƍl������̂ł���B�o�c�҂�90�N��܂ł́C���������Ƃ̎Љ�I�ӔC�������ӎ����Ă���14�j�B
�Ƃ��낪�C���oESG���i2018�j�ɂ��ƁC���E�I�Ɍ��ē��{��Ƃ�ESG�]���͒Ⴂ�B���̗��R�Ƃ��āC�O���[�o���ȕ��ՓI�ۑ�ł��鏗���E�l�����ւ̎��g�݂̒x��Ə�M�̖͂�肪�������Ă���BESG�ւ̎��g�݂̉��P�̗]�n�͑傢�ɂ���悤�ł���B�]�ƈ��┄���C������C���Ԃɔz�������`���I�ȓ��{��Ƃ̌o�c�N�w�ɂ́C�@����K���ݒ�ɂǂ��ւ��̂��C���邢�͂��L��������T�v���C�`�F�[����ł̐l�����C���邢�̓W�F���_�[���ɂ܂łɂ́C���삪�y��ł��Ȃ���݂͂���Ǝv����B
�܂��C���{��Ƃ͋����̈ӎ����������C�t�ɂ��̂��Ƃ͋����̂̊O���ɂ͖ڂ��͂��ɂ����Ƃ������_�����悤�Ɍ�����B���ԁC���ԓ��ł̕]�����C�ɂ��āC���͈̔͂ł͈������Ƃ������C�������h��ڎw�����C���͈̔͂��Ă̖ڔz��ɂ����邤��݂�����B�����������ŁC���A�ɂ��SDGs�̒́C���{��Ƃɑ��āC�S�n���I�Ȃ����Đ�������C�Љ�ۑ�Ɏ��g�ޕK�v���𔗂��Ă���ƌ����悤�B
3.3�@���{��Ƃ̎��g��
���{�̗L�͂ȏ���Ƃ́C���݃T�X�e�i�r���e�B���|�[�g���쐬���C�n������l�����C�n���C�ȂǃO���[�o���ȉۑ�ɐϋɓI�Ɏ��g��ł���CSDGs�̐��i�⌟�ؑ̐����܂߂ĕ��L������ɂ킽���ďڍׂȕ����Ă���B����͂S�C�T�N�O�܂ł͊������Ƃ��������̂ł��������C�o�����i2022�j���ƁC���߂ł̓T�X�e�i�r���e�B���|�[�g�Ƃ��Ă����Ƃ������悤�ł���B�z�[���y�[�W������{���\���邢�����̊�Ƃ̃T�X�e�i�r���e�B���|�[�g2021�̊�{�I�ȕ��j�̕������݂Ă݂悤�B
�u�N���G�C�e�B�r�e�B�ƃe�N�m���W�[�̗͂ŁC���E�������Ŗ������v�Ƃ���Purpose�i���݈Ӌ`�j�ƁC�u�l�ɋ߂Â��v�Ƃ����o�c�̕������̂��ƁC�u�l�v�����ɑ��l�Ȏ��Ƃ�W�J���C���̑��l�������݂Ƃ��������I�ȉ��l�n���ƒ������_�ł̊�Ɖ��l�̌����ڎw���Ă��܂��B
�l�X�������Ōq���邽�߂ɂ́C�����������S���ĕ�点��Љ�⌒�S�Ȓn���������邱�Ƃ��O��ł���C�\�j�[�́C���̎��Ɗ���������C�ڋq�C�Ј��C���B��C�r�W�l�X�p�[�g�i�[�C�n��Љ�C���̑��@�ւȂǂ̃\�j�[�O���[�v�̃X�e�[�N�z���_�[��n�����ɗ^����e���ɏ\���z�����čs������ƂƂ��ɁC�Θb��ʂ��ăX�e�[�N�z���_�[�Ƃ̐M����z���悤�w�߂܂��B
�����āC�C�m�x�[�V�����ƌ��S�Ȏ��Ɗ�����ʂ��āC��Ɖ��l�̌����Nj����C�����\���y337�Łz �Љ�̔��W�ɍv�����邱�Ƃ�ڎw���܂��B
�����́C�T�X�e�i�r���e�B�����Ɛ헪�̒��j�ɑg�ݓ��ꂽ�T�X�e�i�u���o�c�����H���Ă���C2021�N�x���ŏI�N�x�Ƃ���u2021�����o�c�v��v�ɂ����Ă��C�Љ�C�m�x�[�V�������Ƃ̃O���[�o�����[�_�[�Ƃ��Ď����\�Ȑ��E���������邱�Ƃ�ڕW�Ɍf���܂����B���̖ڕW�̎����Ɍ����C�u���v�u���W���G���X�v�u���S�E���S�v�̂R�̗̈�ɒ��͂��邱�ƂŎЉ�Ɗ�ƌo�c�̉ۑ�̉����ɍv�����C�l�X��Quality of Life�iQoL�j�Ȃ�тɌڋq��Ƃ̉��l�̌����}���Ă����܂��B�܂��C�T�C�o�[�t�B�W�J���V�X�e���Ƃ��ăf�W�^���C�m�x�[�V��������������\�����[�V�����uLumada�i���}�[�_�j�v����C�f�W�^���ƃ��A���̋�Ԃ�A�g�����C���Ɨ̈�m���Ɛ��E���̃p�[�g�i�[�Ƃ̋��n�̂��ƎЉ�C�m�x�[�V�������Ƃ��g�債�Ă����܂��B�����́C�T�X�e�i�r���e�B�Ǝ��Ƃ̗Z��������ɐi�߂Ă������ƂŁCSociety 5.0��SDGs�Ɏ����ꂽ�Љ�ۑ�̉����ɍv�����Ă����܂��B
�iSDGs�ւ̍v���j�@SDGs�̓O���[�o���ȎЉ�E���ۑ���������邱�ƂŎ����\�ȎЉ���������C�l�X��Quality of Life�iQoL�j�̌�����߂������ۖڕW�ł��B����������܂Ő��i���Ă����Љ�C�m�x�[�V�������Ƃ́C�܂���SDGs�̒B���ɍv��������̂ł���C�����̎����I�����̌���ł���ƍl���Ă��܂��B���̂��߁C�����͎Љ�C�m�x�[�V�������Ƃɂ�����v�V�I�ȃ\�����[�V������i�̒�ʂ��ĐV���ȎЉ�E���E�o�ω��l��n�o���邱�Ƃ��o�c�헪�ɐ�����ƂƂ��ɁC�����̎��Ƃ��Љ�E���ɂ����炷�l�K�e�B�u�C���p�N�g��ጸ���C�Љ�E���̕ω��ɂ�鎖�Ƃւ̃��X�N��c�����邱�ƂŃl�K�e�B�u�C���p�N�g�ɑ��鋭�x���̌���ɓw�߂܂��B
�������i�g���^�����Ԋ�����Ђ���т��̎q��Ёj�́C�n�ƈȗ��C�u�L�c�j�́v�̐��_���p���C�u�g���^��{���O�v�Ɋ�Â��Ď��Ɗ�����ʂ����L���ȎЉ�Â����ڎw���Ă܂���܂����B2020�N�ɂ́C���̎v����b�Ɂu�g���^�t�B���\�t�B�[�v�����Z�߁C�u�K���̗ʎY�v���~�b�V�����Ɍf���āC�n��̊F�l���爤���ꗊ��ɂ����C���̒�������̉�Ђ�ڎw���Ă��܂��B
���̃g���^�t�B���\�t�B�[�̂��ƁC�T�X�e�i�r���e�B��{���j��ʕ��j�Ɋ�Â��C�T�X�e�i�r���e�B���i�ɓw�߁C����܂ł��C�����Ă��ꂩ����C�������́w�Љ�E�n���̎����\�Ȕ��W�ւ̍v���x�Ɏ��g��ł܂���܂��B
���̂悤�ɁC������̉�Ђɂ����Ă��CSDGs��ESG�܂��āC�T�X�e�i�r���e�B���ӎ�������{���j����Ă���B�X�e�[�N�z���_�[��n�����Ƃ̊ւ����ɂ��C�����\�ȎЉ�̔��W�ւ̍v����ڎw���Ă���B�e����ɂ������̓I�Ȏ��g�݂̏ڍׂ́C�e�Ђ̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ���Ă���B�������C���ۂ̂Ƃ���C���ꂪ��БS�̂ɐZ�����C���s����Ă���̂��C�^��Ȃ��Ƃ��Ȃ��B�c��ȕ��ʂ̕����P�Ȃ�앶�Â���C���邢��SDGs�Ɏ��g��ł��邩�̂悤�ȃ|�[�Y�ł���C���邢�͐�i�I�Ȏ��g�݂����Ă��邱�Ƃ𐢊ԂɁu��`�v���铹��ƂȂ��Ă��鋰������邱�Ƃɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��C�Ǝv����̂ł���B
3.4�@����̉ۑ�
�ȏ�Ō������Ă����悤�ɁC���{�̑��Ƃ��Љ�ۑ�̉����Ɍ����āCSDGs�̗��O�ɑ������o�c�w�͂����Ă���B�܂���ƂɂƂǂ܂炸�C�o�ώY�ƏȂ���ȁC�O���ȂȂǂ̏Ȓ��ɂ����Ă�SDGs�Ɋւ��R�c����J�Â��C�������������s���C�ŋ߂ł͐V����G���ɂ����Ă��p�ɂɎ��グ���Ă���B����������ESG��SDGs�Ɏ��g��ł���B�������C���݂��x�X��������i���s��15�j��n���X�����g���Ă��݂Ă���ƁC�e�Ђ̃T�X�e�i�r���e�B���|�[�g�ɐ���ꂽ�g�������h���C�ʂ����Ė{���Ɏ������悤�Ƃ���ӎu������̂��C�^�킵���Ƃ��낪����悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B��Ƃ̃u�����h�����߂邽�߂̍L���̖�����S���Ă���C�z������B�K�J�i2020�j�ɂ��ƁC����܂ł�SDGs�EESG�ւ̓�������Ƃ̃p�t�H�[�}���X�ɐ��̉e����^����̂��C�^�O���������Ƃ����B�����ł���Ƃ���C��Ƒ��ł��^���Ɏ��g�ރC���Z���e�B�u�������̂��v�����Ȃ���������Ȃ��B�������C���_����2020�N�ȍ~�C�͕ς�����Ƙ_���Ă���BESG�ƃp�t�H�[�}���X�͕��ї��Ƃ̌������ʂ��݂���B���Ƃ���C���͂��`�ɗ��߂�ׂ����R�͂Ȃ����낤�B
���ɃO���[�o���W�J�����ƂɂƂ��ĎЉ�ۑ����ɖڂ��������C�����I�Ȏ���ɗ������o�c���C��Ƃ̑����Ɣ��W�ɂƂ��ĕs���ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B��Ɖ��l�̑���̂��߂ɁC�X�e�[�N�z���_�[�ƂƂ��ɉ��l��n��o���C�|�[�^�[�̒���u���l���n�v�̎��_�̈Ӌ`�͋ɂ߂đ傫���B�����I�����Ɣ��W������Ƃ̑��݈Ӌ`�ł���C�����������o�c�݂̍����d�g�݂́C���{��Ƃ̓`���I�ȗ��O�Ƃ͖������Ȃ����C�O�q�����悤�ɂނ���e�a�����傫���B���E�I�����L���O�œ��{��Ƃ�ESG�ւ̎��g�݂��]������Ȃ��͓̂��{��Ƃ̏��J�����s�\���ł���Ƃ������ʂ����邪�C����I�ȉۑ�ւ̎��g�݂��s�����Ă���Ƃ������Ƃ����낤�B���{�I�o�c�̗ǂ��ł��鑽�l�ȃX�e�[�N�z���_�[��厖�ɂ��鎋�_�ɕt�������āC����ɂ��̎�����g�債�Ď��Ђ�SDGs�ECSR�ɑ�����g�݂�P�Ȃ�L���Ƃ��Ĉʒu�Â����C���^���ɑS�ГI�Ɍ��������Ă������Ƃ����߂��悤�B
Aoki, M., Patrick, H. and Sheard, P.�i1993�j, The Japanese Main Bank System: An Introductory Overview, April 1993
�� ���F�i1995�j�C�u�o�σV�X�e���̐i���Ƒ������\��r���x���͏����v�C���m�o�ϐV���
�ɓ��M�Y�i2017�j�C�u�R�[�|���[�g�K�o�i���X���v��PDCA�v�i�w�ꋴ�r�W�l�X���r���[�x�Cwinter, 65, 3�Cpp.8-31�j
�ɓ��M�Y�E����J�N�V�E��ؒq��E�͓��R�i2017�j�C�u���{�ɂ�����K�o�i���X���v�́u�����I�v�e�����߂�����ؕ��́v�i�w�ꋴ�r�W�l�X���r���[�x�Cwinter, 65, 3, pp.77-92�j
���P���E��{�T�q�E�a�J���L�i2021�j�u�T�X�e�i�r���e�B�E�K�o�i���X���v�v���{�o�ϐV���o��
�I���R�b�g�CG�i2010�j�C�u�O�����ς�����{�I�o�c�\�\�n�C�u���b�h�o�c�̑g�D�_�v�C�������i�E�{�{�����E�R��������C���{�o�ϐV���o�ŎЁC����Conflict and Change --- Foreign Ownership and the Japanese Firm, Cambridge University Press�i2009�j
�y339�Łz�o�Y�ȕ��i2018�j�C�u���l���n�K�C�_���X�v
�@https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/kigyoukaikei/Guidance_Supplement_Japanese.pdf�i2022�N�W��20���ŏI�A�N�Z�X�j
�o�Y�ȁi2019�j�C�uSDGs�o�c�K�C�h�v
�@https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190531003/20190531003-1.pdf�i2022�N�W��20���ŏI�A�N�Z�X�j
�����́i2022�j�C�u�@�\���v���琸�_�̉��v�ց\�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�̐V�����\�v�w�o�c�N�w�x�P���C18, 2, pp.69-74�B
���R���G�i2019�j�C�u�o�c�����_�v�C�V����T�Ł@�n����
Sheard., P. �i1989�j, The Main Bank System and Corporate Monitoring and Control in Japan, Journal of Economic Behavior and Organization, Vol.11. No.3.
JAPAN SPENCER STUART BOARD INDEX2021
�@https://www.spencerstuart.jp/research-and-insight/japan-board-index�i2022�N�W��24���ŏI�A�N�Z�X�j
�K�J���K�i2020�j�C�u���߂�ESG�����������猩��u���߂���v��Ёv�i�w�ꋴ�r�W�l�X���r���[�x�Cwinter, 68, 3, pp.40-53�j
�����r�v�i�ҁj�i1995�j�C�u�R�[�|���[�g�K�o�i���X���{�ƃh�C�c�̊�ƃV�X�e���v�C�����o�ώ�
��ˌ��o�E���R���G�i2021�j�C�u����́u���{�I�o�c�v�_�i�Q�j�v�i�w�K�@��w�w�o�Ϙ_�W�x58, 3, pp.227-252�j
��ˌ��o�E���R���G�i2022�j�C�u����́u���{�I�o�c�v�_�i�R�j�v�i�w�K�@��w�w�o�Ϙ_�W�x58, 4, pp.315-332�j
�o�����M�V�i2022�j�C�u�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X���v�ƃT�X�e�i�r���e�B�̓��{��Ƃւ̉e���v�w�o�c�N�w�x1, 18, 2, pp.90-99�B
�����،�������i2021�j�C�u���؏���Ђɂ�����Ɨ��ЊO������̑I�C�y�юw���ψ���E��V����̐ݒu�v
�@https://www.jpx.co.jp/news/1020/nlsgeu000005poi8-att/nlsgeu000005polb.pdf�i2022�N�W��20���ŏI�A�N�Z�X�j
���؏���ЃR�[�|���[�g�E�K�o�i���X�����u�N��
�Ɨ��s���@�l�E�J�������E���C�@�\�i2015�j�C�u�����N�I�[�^�@�C�����v�i���ʘJ���g�s�b�N�F2015�N�U���j
���t�{�j�������Q��ǁi2022�j�C�u���O���ɂ������Ɩ����̏����o�p�ɂ��āv�C�ߘa�S�N�S��21��
���oESG�i2018�j�C�u���{�I�o�c�͒ʗp���Ȃ��\���E���]�����Ⴂ�̂͂Ȃ����v�T����pp.20-22.
���{���������i2022�j�C�u����Ƃ̃R�[�|���[�g�K�o�i���X�����v
�@https://www.jacd.jp/news/opinion/cgreport.pdf�i2022�N�W��20���ŏI�A�N�Z�X�j
Meier J.H., Kobs K., Ratjen N., & Teßmann J.�i2022�j, Frauenquote und Unternehmensperformance --- Eine Analyse der Gleichstellung aus Kostenperspektive, Zeitschrift für Corporate Governance, pp.30-37.
���Y���ȁi1993�j�C�u���C���o���N�̑I���ƍs���v�C�،��o��186���C1993�D12
�{���p���i2011�j�C�u���{�̊�Ɠ����̐i���������ɂƂ炦�邩�\��@��̍Đv�Ɍ����āv�i�{���p���Ғ��w���{�̊�Ɠ����x���m�o�ϐV��ЁC����pp.1-70�j
�{�{�����i2014�j�C�u���{�̊�Ɠ����ƌٗp���x�̂䂭���\�n�C�u���b�h�g�D�̉\���\�v�C�i�J�j�V���o��