日本における電機産業の発展史
⑸1950-60年代における半導体事業の展開
石井 晋
日本の電機産業の長期的な発展史を描くことを目ざし,石井晋[2022]および石井晋[2023]において,戦後・高度経済成長期における日本の主な電機メーカー11社(日立製作所,東京芝浦電気,三菱電機,日本電気,富士通信機製造,沖電気工業,日本無線,松下電器産業,早川電機工業(シャープ),三洋電機,東京通信工業(ソニー))を対象として,各メーカーの事業展開と海外からの技術導入を中心に分析した。戦後の各企業は多岐にわたる技術導入を行ったが,そのなかでも各メーカーが共通して重要視し,多方面にわたる事業展開の基礎となったのが半導体技術であった。そこで,本稿では,前記の11社のうちから日立製作所(以下,日立),東京芝浦電気(以下,東芝),三菱電機,日本電気,東京通信工業(ソニー)を取り上げ,1950-60年代の半導体事業の展開の歴史について,既存資料をもとに主要な事実を整理すること課題とする。また,同時に,近年に至るまでの長期的な半導体産業史を見すえながら,日本の電機メーカーの半導体事業の発展史を分析するための視角を提示することを目ざす。半導体の歴史でいえば,ゲルマニウム・トランジスタに始まり,その後素材の中心がシリコンへと転換し,ディスクリート半導体から集積回路(IC,LSI)化が進展し始める時期までが対象となる。本稿で取り上げる5つのメーカーは,当時の日本の半導体メーカーのすべてではないが,主要なメーカーの大半を占める。
高度経済成長期における日本の半導体産業の歴史に関しては,各メーカーの動向を網羅した半導体産業新聞編・垂井康夫監修[2000],ICの共同開発に着目した金容度[2006],技術の展開を簡潔に描いた久保脩治[1989],本稿と同時期を対象とした河村徳士[2022]など少なくない文献が存在する。それらは各企業における半導体産業に特化して注目する志向性が強い1)。これらの文献に対して,本稿においては,各メーカーの半導体事業が,電機メーカーとしてそれぞれに特色を持った複合的な経営体の一部門であったことを重視する。各メーカーの半導体部門は,海外からの技術導入コストがかなり高いものであったという共通の条件に置かれていただけでなく,各メーカーが重視する他の事業部門向けの半導体開発を求められるというそれぞれに固有の制約条件にも直面した。このような日本における半導体産業の独特な発展のあり方を各電機メーカーの事業戦略と関連づけてシステマティックにとらえることが本稿の【14頁】 目標となる。このような見方により,日本における半導体産業の発展から停滞(ないし衰退)までを包括的にとらえるための一貫した視角が得られるものと考える。
石井晋[2022]で強調したように,高度経済成長期の電機産業においては,重電機・通信機・家電メーカーのそれぞれが多様な経営戦略を展開しつつも,電子・情報関連機器により注力していく傾向が見られた。また,石井晋[2023]では,11社の電機メーカーの技術導入の内容について分析し,その結果,かなりの多様性が見られたが,電子・情報関連機器に関わる技術が競って導入されたことが確認された。
電子・情報関連機器が発展するための技術的な基盤となったのは,当初は電子管であったが,1950年代半ば以降においては,半導体(トランジスタ,ダイオード,集積回路等)の役割が急速に重要性を増した2)。半導体は,ラジオ等の製品に利用されてから急速に普及し,その後,高周波特性が改良された結果,テレビなど民生用製品に大量に用いられていった。半導体の最初の需要ドライバーとして,ラジオ,テレビなどの民生用製品の果たした役割は大きく,こうした民生用製品をめぐる競争の中で,各メーカーにおいて半導体事業が重要視され,発展していったのである。
そこでまず,テレビの技術導入に関する動向を確認しておこう。
1950年代のテレビに関するすべての技術導入メーカーについては,表1に示した。1951-54年に,日本のメーカーとRCA社との契約が続々と結ばれた。また,1957年にはこの時期に成立したPhilips社の特許許諾契約が各社と結ばれた。先行研究でよく指摘されているように,1950年代のテレビ受像機市場においては,非常に活発な参入が生じ,その後淘汰されていったのである3)。淘汰のダイナミクスには,販売網の整備と基幹部品の生産・開発能力が大きな影響を及ぼしたものと考えられる。基幹部品となる受信管・ブラウン管等の電子管に関しては,技術導入を行ったメーカーは限られていた。特にブラウン管からの一貫生産体制の成立は,テレビ・メーカーの競争力にかなりの影響力を与え,1960年代には松下電器,ソニー,東芝,日立などのメーカーがテレビ受像機市場で優位を占めるに至った4)。その後,ブラウン管の改良に加え,電子回路のトランジスタ化,半導体化もまた,テレビ受像機としての性能を作用する重要な要因となった。1950年代末から1960年代初めにかけて,ソニー,松下電器(松下電子),三洋電機,東芝,日立三菱電機とも,テレビ用トランジスタの開発に競って取り組んでおり,各社のテレビ事業の発展に大きく貢献した5)。本稿で取り上げた11社のうち,富士通,沖電気,【15頁】 日本無線を除く8社は,テレビ受像機市場で激しい競争を展開し,高度経済成長期を通じて一定の地位を占めたのである。さしあたりは,ラジオ,テレビなどの家電製品市場の急拡大が,次に述べる半導体事業の発展のあり方にきわめて大きな影響を与えたことを強調しておきたい。
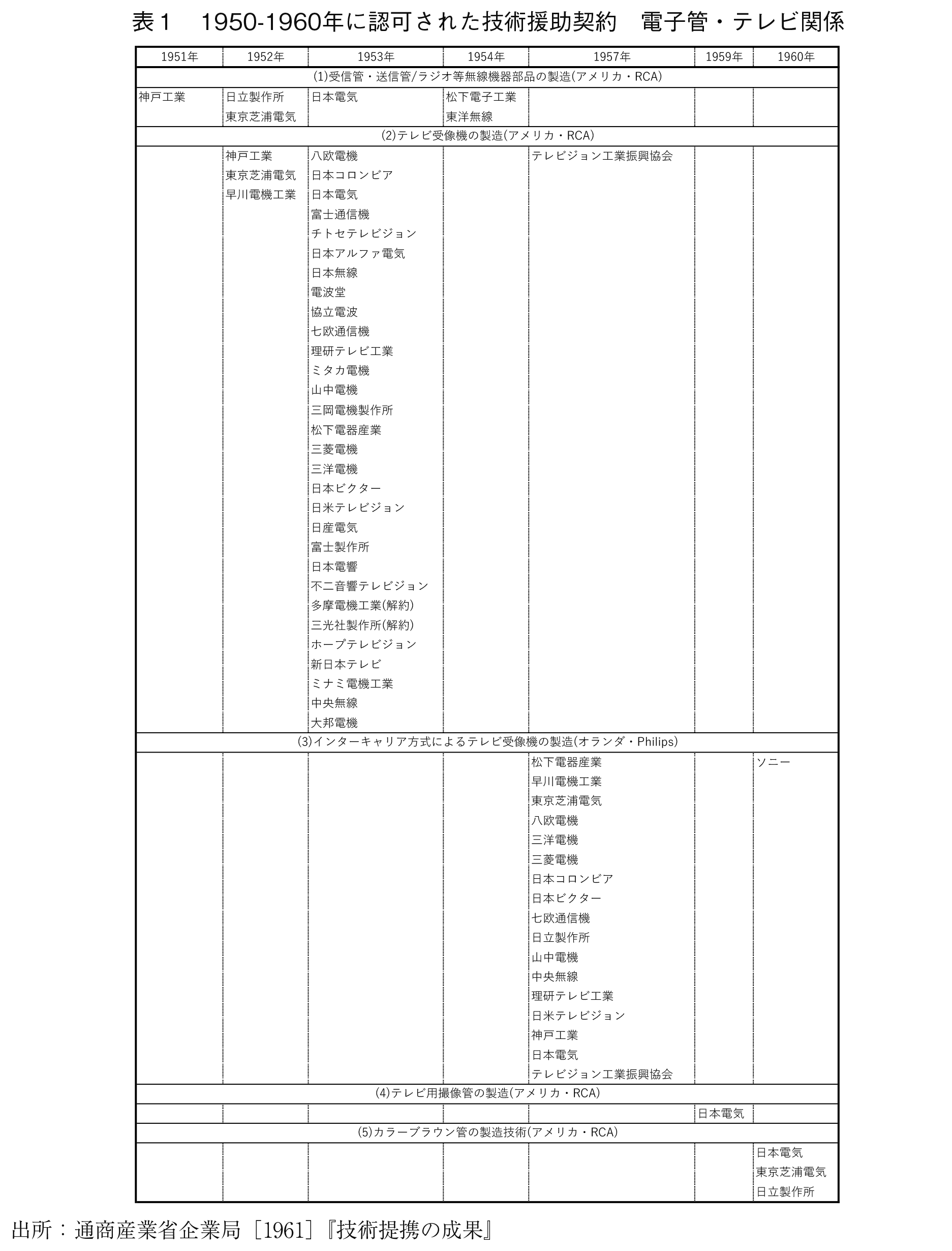
【16頁】
表2には,1950年代における半導体関係のすべての技術導入メーカーを掲げた。電子管同様,テレビに比すれば導入メーカーは限られており,1960年の3社(東邦産研電気,新電元工業,オリジン電気)を除けばすべて,石井晋[2022]および石井晋[2023]で取り上げた12社6)の中に含まれている。少なくとも1950年代においては,半導体に関しては,テレビほどの激しい参入が生じたわけではなかった。
大規模な軍需が存在した米国と異なり,日本においては,1950年代から1960年代後半にかけては,ラジオに次いでテレビが主な半導体の需要先であった。一方,より高機能な半導体については,量的には少なかったがコンピュータや通信機器(電子交換機など)に利用された。その後,電卓向けに大きな需要が表れ,1970年代初めにマイコンと半導体メモリーが開発されて以後は,パソコン向けMPUやメモリー,各種家電製品の制御装置,自動車の車載品等へと需要が拡大していくことになる。したがって,国内の半導体メーカーの数は比較的限られていたとはいえ,時代ごとに異なる新たな分野における集中的な需要の盛り上がりが断続的に生じ,短期間のうちにきわめて激しい「同質的な競争」が展開するという状況が繰り返し現れた。
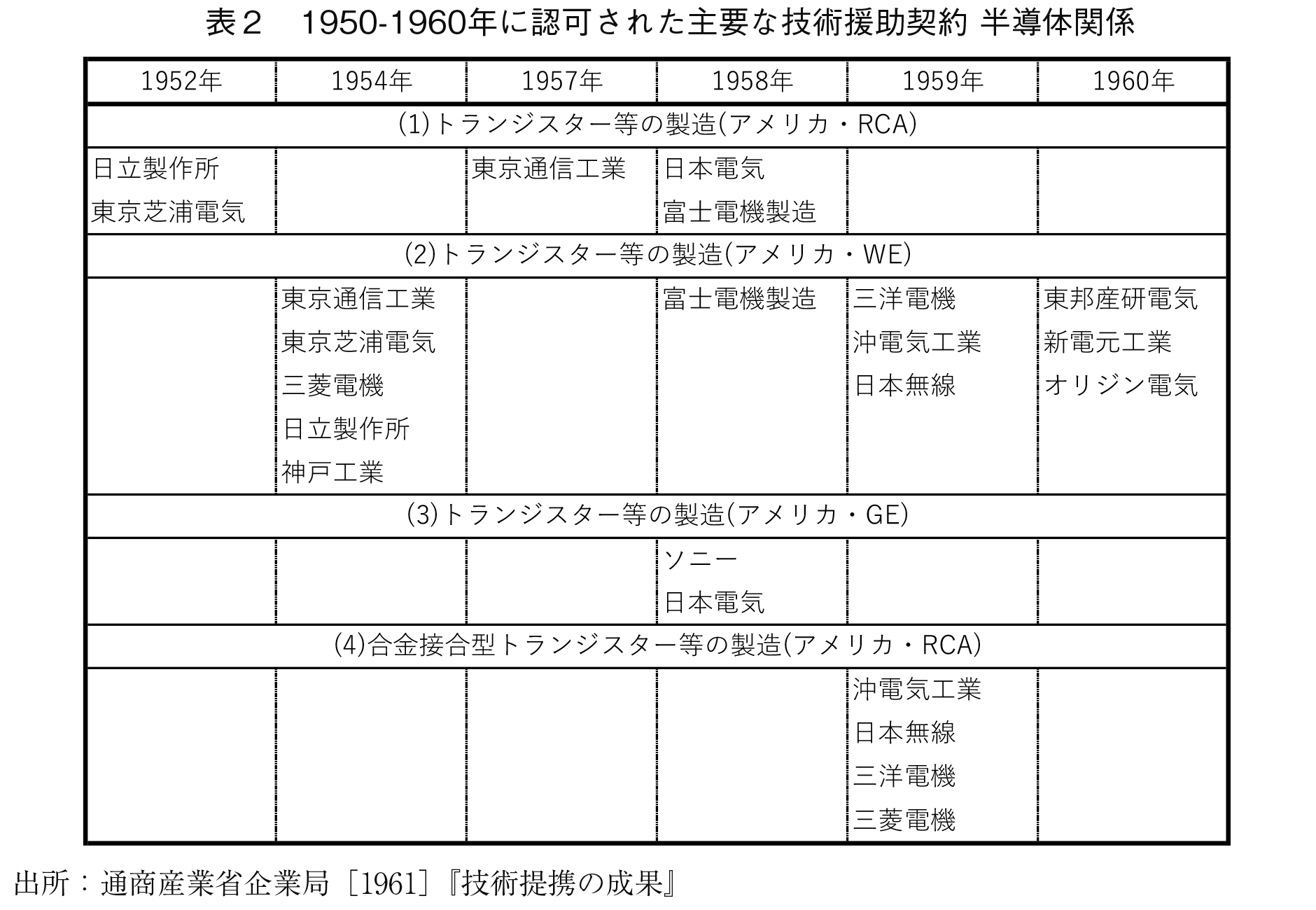
ただし,「同質的な競争」が生じやすかったとはいえ,各メーカーの半導体事業に対する取り組み方には,それぞれ固有の事情が見られることにも留意しておきたい。そこで,以下では,本稿で取り上げた11社(12社)のうち,比較的早くから半導体事業に取り組んだ日立,東芝,三菱電機,日本電気,ソニーを取り上げ7),関連資料および先行研究をもとに,1950-60年代半ばまでの,各メーカーの半導体事業展開の概要について整理し,それぞれの特徴を明らかにすることを目ざす。特に新しい事実を提示するわけではないが,この時期の日本の電機メーカーにおける半導体事業をめぐる制約条件や課題に注目し,適切な分析視角を得るために,主要メーカーの展開の歴史を整理することがその目的である。
⑴ 日立の半導体事業8)
日立においては,戦時期から日立研究所および中央研究所においてセレン半導体の研究が採り上げられていた。戦時期には,軍需の増大を受け,戸塚工場および中央研究所において電波・通信用途の電子機器研究が急速に拡大したことから,社内においても次第に電子材料への関心は高まりつつあった。しかし,重電機や産業機械などの大物製品が事業の中核を占めていたことから,1950年代初めまでは,日立の社内における半導体の位置づけはきわめて小さなものであり,競合メーカーに比して率先して重視していたわけではない。
1947-48年の,ベル研究所におけるバーティーン,ブラッテン,ショックレーによるトランジスタの発明は電子技術者に衝撃を与え,電気試験所などにおいて関心を持つ技術者による勉強会が開催された。日立中央研究所の伴野正美は,そうした勉強会の常連であった。伴野は,そこで得た情報をもとに,日立内における初期の半導体研究において,中心的な役割を果たすこととなった。伴野の働きかけにより,1950年,日立中央研究所では,「特殊半導体」の研究という名称で,トランジスタの研究を正式に採り上げることが認められた。なお,伴野は,戦後の中央研究所において,セレン整流器や蛍光体の研究に取り組んでおり9),半導体研究については,以前からなじみやすい位置にいたと見てよいであろう。日立は,研究レベルでは,後述する東芝や三菱に比して,比較的早くから,半導体に興味を示したのである。
1952年4月,ベル研究所を傘下に置くアメリカのAT&T社がトランジスタ特許の有料公開を行い,トランジスタに関するセミナーを開催したことが,日本の電機メーカー各社が半導体事業に参入する,最初の大きな契機となった。日立は,1952年5月,RCA社との間に,トランジスタなどの技術援助契約を締結した。契約の詳細は次の通りである10)。技術援助の対象となる品目は,①受信管・トランジスタ,②ブラウン管・送信管,③テレビ受像機・電子管であり,売上に対するロイヤルティー(特許使用料および技術援助料)は,①3%,②5%,③2% 【18頁】 (ただし,最低保証料年6万ドル),期間は10年と定められた。当時の日立にとっては,技術援助の対価はかなりの高額であり,また,トランジスタについては,ノウハウを習得するために,技術者をアメリカに派遣して学ぶ必要があったことから,かなりの負担となった。また,当時のトランジスタはまだ不安定な製品であり,真空管の代替となり得るほどの品質とコストを達成していなかった。このため,日立においては技術導入をしたものの,製品化への動きは鈍かった。
トランジスタの製品化に先んじたのは,よく知られているように,東京通信工業や神戸工業である。これに対して,日立は,中央研究所において,当初,点接触型トランジスタの試作に取り組んだが,1953年から合金型トランジスタに取り組み,1954年8月,初めてトランジスタの試作に成功した(低周波用PNPトランジスタHJ15/HJ17)。金属製のカン封止の合金型ゲルマニウムであり,日立における実用的な最初のトランジスタとなった。ただし,この合金型トランジスタの遮断周波数は1MHz以下であり,ラジオを作ることができず,補聴器向けを想定して補聴器メーカーに見本を配るにとどまった。その後,RCAで開発されたドリルド・ホール型,ドリフトベース型などに取り組み,高周波化を実現していった。1955年4月,日立の中央研究所では,ラジオ用高周波トランジスタ(HJ22/HJ23)の試作に成功,ようやくラジオ受信機への工業的基礎を確立した。
なお,1954年1月には,すでにトランジスタの試作に成功していた神戸工業が,自社製トランジスタを使用したラジオの製作に成功し,発表した。さらに,同1954年秋には,東京通信工業がトランジスタの販売を開始し,翌1955年8月には自社製作のトランジスタを組み込んだトランジスタ・ラジオTR-55を日本で初めて市販している。東京通信工業によるトランジスタ・ラジオのヒットを受けて,翌1956年,日本の電機メーカーのトランジスタ事業化への取り組みが一気に加速することとなった。
日立は,小型ラジオ用トランジスタ需要の急増に対応するため,量産体制の構築への取り組みを開始し,1956年9月,中央研究所にトランジスタ部を新設した。トランジスタ部では70名あまりの部員を結集して,試作,量産化をハイスピードで進めた。1956年10月には,通産省電気試験所よりトランジスタ品質優秀の認定を受け,またラジオメーカーであった白砂電気より日立製トランジスタを使用したポータブル・ラジオが発売された。翌1957年1月には,日立の戸塚工場においてトランジスタ・ラジオの製作が始まり,自社内のトランジスタ需要も拡大していった。日立のトランジスタ事業は急激な立ち上がりを見せたのである。
トランジスタ需要の急増を受け,1957年9月,日立は,中央研究所建屋に新たに3階の丸屋根部分を増築して緊急対応したが,本格量産への取り組みが必須となった。中央研究所内での増産は困難と判断されたことから,日立は,1957年10月に隣接の小平町の畑地を買収し,翌1958年7月,新工場を竣工させた。なお,地目変更が追いつかなかったため,当初はこの新工場に「工場」の名称を冠することができず,「トランジスタ研究所」と名付けられた。「トランジスタ研究所」は,翌1959年8月,「武蔵工場」へと改称された。武蔵工場におけるトランジスタ生産量は急速に伸び,1959年度の生産量は1956年度の40倍を超えたという。1960年6月には工場建屋の増築が完成し,武蔵工場の建坪は33,000㎡,従業員3000名へと拡大した。
以上のように,日立において,トランジスタの事業化に向けた動きが一気に加速化した背景として,東京通信工業によるトランジスタ・ラジオ市場の創出が外的な契機となったことは間違いない。これに加えて,本稿では,もう一つの内的な契機として,石井晋[2021]で指摘し【19頁】 た技術導入コストの高さを強調しておきたい。日立におけるトランジスタについての技術導入コストのデータは得られないが,1950年代半ばにおける真空管に関するRCAへの技術料支払い負担の高さから十分に推測し得るだろう。また,一般的にいって,1950年代後半における半導体素子の技術支払料が売上高に占める割合は比較的高いものであった(後掲,表3)。日立の社内において,テレビ等と同様,トランジスタについても,技術導入コストの早期の回収が重要な課題とされていたものと考えられる。
この間,トランジスタの品質,性能の強化に向けた研究開発も進展した。1958年4月には,日立中央研究所において,ドリフト・トランジスタ,パワー・トランジスタを発表し,真空管より優れた性能を持つトランジスタ製品を続々と発売した。また,1959年には,電子交換機用ワイヤスプリングリレー駆動用の高出力トランジスタを開発,戸塚工場の電子交換装置に組み込まれて,電電公社に納入された。このほか,FMラジオ,補聴器,コンピュータなどにも使用されるようになり,1959年8月に完成した国鉄初の座席予約用コンピュータMARS-Ⅰには,日立製トランジスタ2,000個,ダイオード10,000個が使用された。
日立では,中央研究所のほか,日立研究所,日立工場においても,電力機器に関わる半導体の研究開発および生産に乗り出した。1939年にはすでに日立研究所においてセレン整流器の研究を開始,軍関係の研究が増加し,1944年には量産化に入った。戦後,1947年9月には国分工場内にセレン研究分室で研究を再開し,長時間使用後の出力低下がほとんどない高性能な長寿命セレン整流器の製造法を確立,1953年以降,量産研究を開始し,製造販売が拡大していった。一方,ゲルマニウム整流器については,1955年に研究を開始し,1957年,日立工場内にゲルマニウム整流器素子工場を完成し,生産を開始した。さらに,シリコン整流器についても試作研究が進められ,1958年から59年にかけて製品化の目途が立ち,量産に入った11)。
以上のように,1950年代末において,日立は,東芝,三菱などに先駆けて,高性能・高品質のトランジスタ開発に成功し,それまで主に真空管を利用していた多くの分野において採用されるに至った。このことについて,日立製作所中央研究所[1972]は,RCAと技術提携し,見習うところが多かったものの,日立による「独自の構造や特性をもつトランジスタの研究開発にも多くの努力がなされた」こと,「ゲルマニウム-インジウムの合金,再結晶の過程」について「再結晶成長機構,欠陥,電気的特性にわたる極めて広範な研究が展開され,学界のこの分野の主導的役割を果たした」こと,「物理的意味を深く考えながら物を作る」という「半導体研究の運営方針」をもとに「開発の中に基礎研究の題目を見出し,その成果が再たび開発に生かされた」ことが,大きな事業成果につながったことを指摘しており,基礎研究にまで及ぶ研究開発能力の効果を強調している12)。
この時期における,日立トランジスタ技術開発の代表的な成果が,1959年に試作に成功したドットメサ型トランジスタである。ドットメサ型トランジスタは,150MHz程度の高周波に対応した製品であり,主にFMラジオ受信機やテレビ受像機に使用された13)。当時,高周波トラ【20頁】 ンジスタについては,欧米先進国においても量産技術が確立されていない状況であった。日立は,精度の高い合金技術を開発することにより,1960年10月からドットメサ型トランジスタの量産を開始し,翌年には生産が軌道に乗った14)。技術導入から8年を経て,1960年代初めには,日立のゲルマニウム・トランジスタの生産技術は,欧米と肩を並べるに至ったと見ることができるであろう。
なお,1950年後半の日立の半導体事業部門においては,ゲルマニウム・トランジスタの新製品および量産技術の開発に注力していたが,中央研究所においてシリコン・トランジスタの研究開発も少しずつ進展していた。また,1960年頃になると,日立内では,中央研究所の単体ゲルマニウム・トランジスタの開発者はほとんどが武蔵工場に転出し,中央研究所は,超高周波デバイス,IC構造,素子特性の研究に移行したという。もっとも,1960年前後のアメリカにおいて生じていた,ゲルマニウムからシリコンへの移行,プレーナー技術やエピタキシャル技術(シリコン単結晶の基板上に,単結晶の薄膜を成長させる技術)の開発,IC(集積回路)の発明などの急速な変化の重要性が認識されていたとはいいがたい。中央研究所において,半導体研究者と回路研究者が合体してICの本格的研究が開始されたのは,1964年2月である。また,武蔵工場においては,大野稔がシリコン100面を使用したMOSトランジスタの可能性を追求する研究を続けていたが,日立の社内では必ずしも評価されず,のちにRCAなど海外企業からの指摘でその重要性が認識されるに至ったという著名なエピソードもある15)。事業戦略としては,導入技術を洗練して,より高性能・高品質のゲルマニウム・トランジスタを開発し,その量産技術を高めることにより,急増する国内の家電製品需要に対応して,生産を拡大することが主要方針であったから,研究開発と事業展開との間において,必ずしもシステマティックな連繋がなされているわけではなかったものといえるだろう。
もっとも,前述のように基礎研究が重視され,独自の技術開発や画期的な発見も生まれたことは強調しておきたい。また,のちに「日本電気」を取り上げる時に触れるプレーナー特許を回避するために,日立は新たにLTPトランジスタを開発した。LTPトランジスタが,シリコン化,IC化時代における日立の半導体事業に一定の貢献をしたことはよく指摘される16)。1960年代の日立は,導入技術に強く依存しつつも,「模倣的性格」からの脱却過程にあり,自社技術の事業化に向けた体制を構築する過程にあった。
⑵ 東芝の半導体事業17)
東芝では,1951年初めから,マツダ研究所の砂町分室において,犬塚英夫が中心となって,ゲルマニウムの結晶とデバイスの特性の評価・研究を行っていた。翌1952年8月には,日立に次いで,RCA社との間で技術導入契約を締結した。技術導入を受けて,東芝では,犬塚を中【21頁】 心とするマツダ研究所の少数のメンバーで,合金トランジスタの試作研究に着手した。当時の東芝は,真空管日本一であったことから,トランジスタ事業の展開には消極的であった。また,1954年ごろまでは,マツダ研究所における研究は,限られた予算のもとで,砂町工場の一角において乏しい設備によってトランジスタの試作が繰り返される程度であった。東芝の経営陣は,半導体をそれほど重要視していなかったのである。
1954年に神戸工業と東京通信工業がトランジスタの試作に成功し,ラジオ向けの製品化の実現可能性を証明したことを受けて,日立と同様に,東芝でも半導体の事業化に向けての動きが始まった。その体制整備のため,基礎研究以外をマツダ研究所から管球事業部に移し,当初は,砂町工場で半導体材料生産,堀川町で部品生産,横須賀工場で組み立てを行う形で,分散体制で生産することが決まった。1955年には,東芝は,すでにラジオ用の接合型トランジスタの試作に成功していたが,経営陣がトランジスタの量産に難色を示していた。そうした中で,1956年12月,石坂泰三社長の決断によるトップダウンで,ようやく東芝はトランジスタの量産化を決定し,1957年6月に合金型トランジスタの量産を開始した。1958年1月,東芝横須賀工場のトランジスタが初出荷されたが,300個のうち当初は歩留まり率1%だったという。日立に若干遅れた量産開始となり,その後,歩留まり向上に向けた取り組みが進められた。
1956年頃から,日本のトランジスタ需要が急増したことを受けて,1957年8月,東芝はトランジスタの一貫生産を行うための専用工場を川崎市小向に建設することを決断,同工場は翌1958年4月に稼働を開始した。この間,東芝では,合金型のドリフト・トランジスタの量産化開発研究を進め,1958年2月頃から生産を開始し,当初の歩留まりは2%だったが,同年9月頃には30%程度にまで高められたという。量産体制は徐々に整備されていったが,東芝のトランジスタは特性が不安定で,他社製品に比べて性能も見劣りすると言われ,社内使用が進まなかった。そこで,東芝は外部ユーザーへの売り込みを進め,三洋電機のラジオ用の大量受注に成功,これが契機となり,社内でも評価されるようになったという。日立には若干遅れたものの,1950年代末には,東芝のゲルマニウム・トランジスタ事業は軌道に乗った。トランジスタについては,東芝においても,日立と同様にRCAからの技術導入に大きく依存していたから,日立と同様に契機により(トランジスタ・ラジオ市場の急拡大と技術導入コストの早期回収),トランジスタ事業が急速に立ち上がったものと見ることができるだろう。
さらに,東芝では,日立と同様に電力機器関連の半導体の開発も進めた。特に注目されるのが,国鉄から要請のあった鉄道の交流電化に必要な整流素子(当初はゲルマニウム,のちシリコン)の開発,自動車交流発電機向けの整流素子の開発である。なお,自動車交流発電機向け整流素子が米国フォード社の要請に応えて,1962年以降,低価格で安定供給を実現したものである。また,1960年2月には,東芝は,米国モトローラへのドリフト型トランジスタ大量納入に成功(カーラジオ向け),日本の電子部品輸出第1号といわれた。フォードやモトローラからすれば,比較的高品質の半導体素子を低価格で調達することができるという点で,東芝の半導体は魅力的であったものと考えられる。
1950年代後半から1960年代初めにかけて,東芝のトランジスタ事業もまた,ラジオ向けの需要が多かったという点で,日立など競合メーカーと類似している。ただし,日立の場合には,半導体の基礎研究に踏み込み,独自技術開発を重視しながら,半導体の性能・品質を高めることで,適用範囲を広げていく傾向が見られた。これに対し,東芝の場合は,基礎的な研究開発への関心はあまり見られず,独自技術への強いこだわりも感じられない。東芝は,競合メー【22頁】 カーからの遅れを認識しながら,半導体を使用した電子機器市場への新規参入企業の需要や,新たに半導体を活用しつつあった電子機器に関わる需要を見出し,高品質の半導体を低価格で供給することで,この事業分野における活路を切り開いていったものということができるだろう。
また,東芝は,1960年代初頭から始まるプレーナ・トランジスタ,エピタキシャル技術の登場,ゲルマニウムからシリコンへの転換,単体トランジスタからICへの展開といった変化への対応についても,日立と同様に決して速い反応を示したわけではなかった。東芝においては,経営陣がゲルマニウム・トランジスタで十分であると考えていた。さらには1961年からの景気後退への対応が遅れ,東芝全体の経営業績が大きく悪化したことなどから,半導体の事業展開においてもシリコン,ICへの進出に遅れをとることとなったのである。1960年代前半の東芝においては,すでに半導体利用が一定規模に達していたラジオ,テレビ向けを中心とした市場の拡大を超えるような,新たな半導体市場の出現への展望は乏しかったように思える。
東芝が,シリコン化,IC化に向けた半導体事業への取り組みを本格化させたのは,1965年4月に社長が岩下文雄から土光敏夫に交代した後のことである。もっとも,土光時代になってから,東芝の半導体事業展開は積極性が高まる。のちに1970年代初めにいち早くCMOSを事業戦略の中心に据えるなど,他社からの遅れを取り戻すために,開発の方向性を絞って重点化を進めるという特徴的な戦略が採用されることとなったのである。
⑶ 三菱電機の半導体事業18)
三菱電機では,1952年に,同社の研究所(1944年設立)において,ゲルマニウムの材料面から半導体の研究を開始した。その後,1956年頃までは,研究開発レベルの試作にとどまっており,日立,東芝に比すれば,かなり遅いスタートとなった。1955年になって,三菱電機はようやく,初めての実用的なデバイスとなる合金型PNPトランジスタを完成させた。トランジスタ・ラジオ・ブームを背景に,翌1956年には,ラジオ等に使用可能な高周波トランジスタ(遮断周波数4MHz程度)を完成し,同年6月末に試作工場が建設された。
翌1957年,三菱電機は,ラジオ用のトランジスタを開発し,量産を開始した。また,同年には,電力用のゲルマニウム整流素子を開発し,整流機器を完成させるとともに,シリコン整流素子の開発も開始した。三菱電機においては,日立,東芝に比すれば,ラジオなどの民生用トランジスタよりも,電力向け半導体素子(パワー半導体)の開発が常に優先されたといわれる。このことは,石井晋[2022]で指摘したように,三菱電機の事業展開においては,総合電機(重電機)メーカーの中でも,重電機・重機械を重視する傾向が強かったことと関連するであろう。1959年,三菱電機は,シリコン単結晶の試作に成功し,100-200A/500Vのシリコン電力用整流器を完成させた。これは,国産で初めて電力用に実用化されたシリコン整流器であり,国鉄の電気機関車,化学プラントの電解用電源などに用いられた。
三菱電機が半導体の重要性を認識し,専用の量産工場の建設を決めたのは,1958年のことである。半導体専用の工場は北伊丹工場(のち北伊丹製作所)と呼ばれ,1960年4月に竣工,操【23頁】 業を開始した。当初の生産は,ウェスティングハウスの技術によるシリコン整流素子と,三菱電機の研究所の技術によるゲルマニウム・トランジスタが中心であった。三菱電機における専用のトランジスタ量産工場の建設は,日立,東芝から2年程度遅れたのである。
トランジスタの量産化には遅れたものの,三菱電機は,1960年頃に始まる半導体のIC化という歴史的転換に際して,それまでの遅れを取り戻すように,かなり迅速に対応した。1961年,北伊丹製作所の構内の新研究棟において,研究所の半導体関連部門が統合され,以後,三菱電機の半導体開発拠点となった。同じく1961年には,三菱電機研究所では,シリコン・トランジスタの試作を進め,二重拡散法により,高周波用メサ型シリコン・トランジスタ(遮断周波数200MHz)を完成させた。
その前年の1960年夏,三菱電機は,ウェスティングハウス社が開発した,一種の集積回路のサンプルを入手していた。これをもとに三菱電機研究所で研究開発を進め,1961年2月,シリコン片中にトランジスタ,抵抗,コンデンサを一体化した製品「モレクトロン」を発表した。これは,国産初のICとされる画期的な出来事であった。「モレクトロン」については,高集積化は困難であり,その後のIC事業の発展に直接つながるものではなかったが,三菱電機では,1962年3月に集積回路開発部門を中央研究所から北伊丹製作所に移管してIC開発を開始させるなど,国内メーカーの中はICへの取り組みは比較的早かったものといえる。1966年には,のちにICの最初の大きな市場となる電卓に関して,三菱電機は他のライバル社を抑えて,いち早く早川電機との提携を実現した19)。それまでの三菱電機においては,重電機・産業機械中心とした事業構造の影響を強く受け,電力向けパワー半導体が重視される傾向にあったが,電卓等の新たな半導体市場の急拡大への対応が強化されていったのである。
⑷ 日本電気の半導体事業20)
日本電気は,包括提携先のISE(International Standard Electric)社を通じてベル研究所と密接な関係にあったことから,トランジスタ発明の情報に接したのは早く,研究への着手は,日本企業のなかではもっとも早かったものといわれる。開発にあたっては,当初から通信機器向けの部品という明確な位置づけが与えられていたことが特徴である。ただし,それまでの基幹部品であり,社内で製造していた真空管との競合部品となるため,その事業化には他社に比して慎重な姿勢がとられた。
日本電気における半導体の開発は,戦後,新たな通信方式として注目されており,日本電気も力を入れようとしたマイクロウェーブ多重通信の実用化のプロセスから始まった。日本電気は,戦前から無線通信に関する研究を進めていたものの,マイクロウェーブ技術に関しては,東芝や日本無線に対して後発であり,遅れていた。同時期,日本無線は,戦時期のレーダー技術の実績をもとにマグネトロンを開発し,神戸工業と組んで,1949年にはマイクロウェーブ多重通信の実験に取り組もうとしていた。しかし,日本無線の送受信機の信頼性が不十分であったことから十分な成果を挙げることができなかった。このため,1950年,電気通信省の電気通信研究所は,マイクロウェーブ多重通信の実用研究において,電信電話事業に関して総合的技【24頁】 術を持っている日本電気に強く協力を依頼した。これを受けて,日本電気では,玉川事業所の長船広衛が中心となって,マイクロウェーブの増幅用にミキシング・ダイオードの研究を進めた。このミキシング・ダイオードは,シリコン単結晶を使用した21)もので,翌1950年5月に試作を完成,きわめて低ノイズで性能も高く,電気通信研究所主催のマイクロウェーブ協議会において第1位の成績を収め,優位に立った。
日本電気の長船らは,トランジスタに関しても1950年に研究を開始し,1953年にはゲルマニウムの点接触型トランジスタ,翌1954年には合金接合型(アロイ型)トランジスタの試作を実現したが,工業化には遅れた22)。1950年代前半においては,電気通信省・電電公社が注力していたマイクロウェーブ多重通信への協力によって始まったミキシング・ダイオードが,日本電気の半導体事業の主力であった。1954-55年頃の日本国内のダイオード生産は,ほぼ日本電気の独占であったという。
1954年,東京通信工業によるトランジスタ・ラジオ開発の情報を受けて,日本電気もゲルマニウム・トランジスタの工業化に着手し,電子管工業部の製造技術課に半導体係を設置,研究所の設備が電子管工場に移されて,トランジスタの生産が始まった。その後,1955年頃からトランジスタ・ラジオのブームにより,トランジスタ需要が爆発的に増大すると,日本電気はトランジスタ事業への進出の遅れへの懸念を強める。そこで,1956年8月,電子工業部半導体係を半導体開発部に強化し,本格的にトランジスタ生産に乗り出した。もっとも,当初は製造技術が遅れていたことから歩留率がきわめて低かった。これを解消するため,海外から生産技術のノウハウを導入する必要に迫られ,1958年2月に米国RCA社とトランジスタに関する基本特許の許諾契約を結び,同年11月に米国GE社と間で技術資料の提供,技術指導および特許許諾契約を結んだ23)。同時に,トランジスタ量産工場の建設が進められ,1958年4月に,玉川事業所内に日本初のトランジスタ専門工場が竣工した。これにより,日本電気のトランジスタ生産は急速に拡大,1960年4月には電子管工業部から半導体工業部が独立した。
この時期の日本におけるトランジスタは,主にラジオなど民生品に使用されていたのに対し,日本電気は伝送機器・無線機器・放送装置などの通信機器用,および計測制御機器・産業交通機器などを半導体応用分野として重点を置いた。また,ゲルマニウムを材料とするトランジスタでは他社に遅れていると判断し,1958年という比較的早い時期に,日本電気は「シリコン素子に重点を置くべきである」との基本方針を確立している。さらに,1954年頃から高周波特性を求めることが困難で歩留まりも低い合金型に見切りをつけ,グロン型に開発の重点をシフトした。1956年にはメサ型トランジスタに注目して開発に取り組み,1960年2月にメサ型のゲルマニウムおよびシリコン・トランジスタの試作を相次いで完成させるなど,遅れを取り戻すべく,他社に先駆けた開発への取り組みが目立った。
1960年2月,日本電気は,電子管工業部の半導体技術部材料技術課内に開発班を編制し,シリコン・プレーナー・トランジスタおよび集積回路(IC)の開発に着手した。同時期,日本電気では,自社開発のコンピュータや自動交換機の半導体化に向けた構想が進展しており,半導【25頁】 体開発の主な目標はこれらの電子応用機器,通信機器にあったものと思われる。
IC時代の到来に際して,日本電気は半導体事業への積極性を強め,他社に先駆けた動きが目立つ。ただし,ICの自社開発に関しては,前述の三菱電機など他の日本メーカーの事例と同様に,日本電気においても,直接実を結ぶことはなかった。ICの開発・生産にあたっては,先行する米国Fairchild Camera and Instrument (FC)社のプレーナー特許および米国Texas Instruments (TI)社のIC構造に関するキルビー特許との特許許諾契約が必須であることが明確となってきた24)。このうち,FC社は,1961年頃から,日本の各半導体メーカーに対し,プレーナー特許の売り込みをかけてきた。しかし,FC社の提示した当初の条件は,特許料として一時金5万ドルに加え,売上の7%,地域を日本だけに限るとした厳しいものであり,日本電気以外の各社は契約に消極的であった。当時,各社とも,民生用のゲルマニウム・トランジスタ事業が拡大して,大きな収益を上げていたことも,プレーナー特許に対する消極姿勢の背景にある。そうした中で,日本電気はプレーナー特許の重要性を強く認識し,特許料を4.5%にまで引き下げる交渉を経たすえ,1963年9月,FC社との間で日本における独占的実施権を獲得した25)。
ただし,軍需の大きい米国に比して,当時の日本においてはICの需要開拓が困難であり,日本電気においても電子応用製品や通信機器向けの社内需要のみでは不十分とみられた。一方,同時期の半導体の主な需要先であったテレビ・ラジオ等の家電製品メーカーが有望であったが,これらのメーカーは単体トランジスタに比して単価の高いICの採用には消極的であった26)。
1964-65年頃になると,IBMが大型コンピュータにおいてICを採用する意向を示したことや電卓向けIC需要が出始めたことから,ICの将来的な需要の拡大が見込まれた。世界的にIC化の流れが進展しつつあったことへの焦りもあり,1965年7月,日本電気は,社長の小林宏治が率先して,集積回路(IC)事業の比重を高める決断をした。当初,IC生産の中心もオペアンプ用のバイポーラ・リニアICであり,日本電気もその開発に注力し,国内市場では高いシェアを獲得したが,あまり大きな需要の伸びは見られなかった27)。その後,電卓向けICが立ち上がり始めたことが,日本電気のIC事業の飛躍につながった。翌1966年11月,日本電気は,電子部品事業グループに集積回路設計本部,半導体集積回路製造本部,混成集積回路製造本部を設置し,半導体事業を強化する体制を整備した。同じ1966年,日本電気は電卓向けMOS ICを開発して早川電機に納入を開始した。
⑸ ソニー(東京通信工業)の半導体事業28)
ソニー(東京通信工業)のトランジスタ技術導入とトランジスタ・ラジオの生産については,かなりポピュラーなストーリーとしてよく知られているが,その主要な経緯を改めて確認しておきたい。
戦後1946年5月に設立された東京通信工業は,1951年に民生用テープレコーダーを発売し,その好調な売れ行きによって企業基盤を確立した。もっとも,販路が学校など教育関係需要などに限られていたことから,社長の井深大は,テープレコーダーの市場調査を主な目的として海外視察を行うこととし,1952年3月に渡米した。この時,井深は,たまたまWE社のトランジスタ特許公開の話しを聞き,興味を抱いた。当時,東京通信工業では,大卒や専門学校卒の技術者が社員の1/3を占めており,そうした技術者の活用との観点から,井深はトランジスタ事業に取り組むことをひらめいたという。
1952年には,日立,東芝が,RCAとの間に,トランジスタを含む電子部品に関してノウハウを含む技術導入契約を結び,高額な技術支払いを行っていた。一方,資金的な制約の厳しかった東京通信工業は,WE社からの特許許諾契約のみを締結することを目ざし,他の日本メーカーに先駆けて動き,1953年中にWE社との間に特許契約の仮調印を行った(特許料2.5万ドル=900万円)。東京通信工業をWE社との特許契約に関しては,当初,東京通信工業の技術力に懸念を抱いていた通産省が難色を示したことで一時棚上げとされたが,1954年2月に認可された。
特許契約の交渉が行われていた時期にはすでに,井深は,トランジスタ・ラジオの開発を決断していたとされる。この時期のゲルマニウム・トランジスタは高周波特性に難があり,せいぜい補聴器程度にしか使えないと考えられていたが,井深はより大きな需要が必要であるとの判断から,ラジオの開発を決めたのである。もっとも,WE社との特許契約は,ノウハウ供与を含まないものであったから,トランジスタ製造のプロセスについては,東京通信工業は自力で確立しなければならなかった。このため,特許契約の認可と相前後して,1954年初めに,トランジスタ開発の担当を自ら申し出た岩間和夫が渡米した。その後,約3ヶ月にわたって,岩間は,WE社のトランジスタ工場を見学して,トランジスタ製造法をつぶさに観察し,著名となる80枚強の「岩間レポート」(その後4期にわたって計256枚)を送り,東京通信工業の技術陣はこれをもとにトランジスタ製造に取り組むこととなった。なお,前述のように,当時のトランジスタは合金型トランジスタが主流であり,「岩間レポート」においても,成長(グロン)型トランジスタの可能性に否定的であった。しかし,東京通信工業は,ラジオを作るためには高周波特性に優れるグロン型トランジスタが必須であると判断し,その開発に取り組んだ。
自社で開発したグロン型ゲルマニウム・トランジスタを使用した東京通信工業のトランジスタ・ラジオの試作品は,1955年1月,「TR-52」として完成した。ただし,「TR-52」にはキャビネット強度に不備があったために改良が必要となり,1955年8月,「TR-55」として発表したトランジスタ・ラジオが日本初の製品として,18,900円(大卒初任給の2倍強)で発売された。これを契機に,トランジスタ・ラジオ・ブームが巻き起こったことは既述の通りである。その際,東京通信工業は,トランジスタを普及させるために,松下電器,三洋電機,早川電機,東芝,ビクターなどの技術陣に集まってもらい,自社のトランジスタを公開して,外販を行った。【27頁】 これを契機に,三洋電機は当時生産体制に入ろうとしていたラジオの計画をストップさせ,新たにトランジスタ・ラジオを開発して参入したという。
トランジスタ・ラジオで他社に先駆けた東京通信工業は,1955-56年にはすでに,テレビの半導体化を見据えて,より高周波特性が優れ,耐熱性の高いトランジスタを求めて,シリコン・トランジスタの開発に関心を向けていた。社名をソニーに変更した1958年1月には,テレビ用のシリコン・トランジスタの開発を開始した。1958年中に高周波トランジスタの試作が行われ,同年12月,トランジスタ・テレビの試作研究を開始,1959年12月に,ソニーは8インチのコンパクトなトランジスタ・テレビ「TV8-301」を発売した。当時,テレビは普及期にあり,据え置き型が主流であり,コンパクトなテレビへの関心が乏しかったこと,また故障しやすかったことから,「TV8-301」は中途半端な商品と目され,あまり売れなかった。そこで,ソニーは,さらに小型の5インチのマイクロ・テレビの開発を目ざし,そのために必要な高性能なシリコン・トランジスタの開発を進めた。その際,ソニーは,この時期に高品質の半導体を製造する最先端の技術として開発されていた,エピタキシャル技術に取り組み,1960年8月に製造技術を完成,同年10月にはマイクロ・テレビ用高周波高出力のシリコン・トランジスタの開発に成功した。1962年5月,ソニーは当時世界最小・最軽量の5インチ・マイクロ・テレビ「TV5-303」を発表した。この製品はアメリカで好調な売れ行きを記録,新たなブームを引き起こした。
なお,マイクロ・テレビ開発においては,トランジスタ以外の困難も多かったことに留意しておきたい。また,ソニーのテレビが大きく脚光を浴びるのは,1968年に発表したトリニトロン・カラーテレビの誕生時である。トランジスタ・ラジオでは,半導体開発・製造とラジオ製造が比較的ストレートに結びつくことによって,ソニーは成功を収めた。しかし,テレビ以降の家電情報機器では,半導体開発と半導体を利用した製品開発の間には乖離が生じ,半導体開発の優位性が必ずしも最終製品の成功に結びついたわけではなかった。
そうした乖離は1960年代に明らかとなる。1960年代初めまでは,ソニーは半導体技術の開発にきわめて積極的であった。その際に重要視されたのは,ラジオ,テレビといった大衆商品市場に向けて,画期的な新たな製品を創るという発想であり,半導体開発はそのための一つの手段であった。1960年代半ばの集積回路(IC)時代になると,井深社長の考え方の影響もあり,特許使用料が高額であること,開発競争が激しくコスト削減をめぐる「同質的競争」に巻き込まれることが懸念されたことなどから,ソニーは半導体開発に消極的になっていった。同時期には,電卓開発競争が始まり,ソニーにおいても,電卓「SOBAX」と電卓に必要なIC,LSIの開発が続けられたものの,激しい価格競争の中で1972年に電卓市場から撤退した。前述のように,LSI開発について,米国で軍需等に向けて先端的な半導体を開発していたRockwell社に委ねた早川電機が電卓市場において優位に立ったことに示されるように,この時期には,高集積の半導体を基幹部品とする量産品においては,半導体から最終製品までの一貫開発は容易ではなくなっていたのである29)。
以上検討してきたように,1950-60年代における各電機メーカーの半導体技術導入のあり方と事業展開について,強調すべき点をまとめておきたい。
第一に,半導体の需要ドライバーは,最初がラジオ,それに次いでテレビ,オーディオ等の家電製品であり,1960年代末に新たに電卓が加わった。この需要ドライバーを最初に自らの企画で設定し,トランジスタからラジオまでの一貫生産を先駆的に行うことにより,半導体事業発展の契機を作ったのは,東京通信工業(ソニー)であった。東京通信工業のトランジスタ・ラジオでの成功は,日本の電機メーカーにきわめて大きな影響を与え,それ以前から半導体研究に取り組んでいた日立,東芝,三菱電機,日本電気,松下電器(松下電子)等の先発大手メーカーを刺激し,その事業化を早め,急速に事業を拡大させる要因となった。
第二に,先行するソニーに追随してトランジスタの生産を本格化させたこれらのメーカーは,ほぼ同種の技術導入を行っており,半導体素子に関する技術支払い料率は比較的高いものであった(表3)。このことは,技術導入コストを早期に回収するため,ラジオ向けトランジスタ事業を急速に立ち上げるという類似した戦略を導く要因となったものと考えられる。また,早期にトランジスタ生産体制を確立することが可能となった要因として,各メーカーにおいて比較的早くからトランジスタに関心を示し,開発に取り組む一定の技術者層が存在していたことも忘れてはならないであろう。さらに,トランジスタ・ラジオの大ヒットは,同時に,
 【29頁】
【29頁】
三洋電機や日本無線などのメーカーが新たに半導体事業に参入する契機ともなった。1950年代後半から1960年代にかけて,多くの電機メーカーが,類似した海外技術導入をもとにラジオ・テレビ向けトランジスタ事業に参入することにより,激しい「同質的な競争」が展開したのである。
第三に,断続的に現れた半導体の需要ドライバーに導かれて集中的に特定分野の半導体開発にほぼ同時期になだれ込むという意味では,各電機メーカーの動きは「同質的」ではあったが,前節で見たように各メーカーの半導体事業のあり方はそれぞれに固有の動きも示した。日立は,重電・通信機器・コンピュータ等に関連した製品のほか,基礎研究にも取り組みながら,先端的な新製品開発を重視した。東芝は,重電,鉄道など産業需要など多方面にわたる応用を重視し,三菱電機もまた産業向けパワー半導体に注力した。NECは,通信機・コンピュータ向けの半導体開発を重視し,迅速で大量の情報処理のために必要な高集積化をめざし,比較的早くからIC事業に本格的に取り組んだ。東京通信工業(ソニー)は,トランジスタの先駆者であり当初は外販も大きかったが,民生用電気製品の開発が経営の中核であり,魅力的な新製品に必要な半導体の開発には注力したものの,巨額の投資を必要とするIC開発には消極的になっていった30)。以上の事実は,これらのメーカーにおいて,それぞれ固有の経営方針のもとに,半導体事業のあり方が方向づけられたことを意味するであろう31)。各メーカーの半導体事業部門からすれば,その事業戦略は,半導体市場の動向だけでなく,各メーカーの経営方針によって大きく左右されたのである。
このことは,日本メーカーによる半導体開発が,のちに通信・コンピュータ向け,民生用製品向け,産業機器向けなど多岐にわたる分野に広がっていくことに大きく貢献したものと思われる。この結果,1970年代から90年代の日本において,きわめて多品種の半導体開発がなされ,さまざまな分野におけるエレクトロニクス化の進展が世界に先駆けて進んでいくことになった32)。
しかし,同時に,各メーカーの半導体事業部門はメーカー全体の経営方針に左右されたがゆえに,半導体の技術発展や需要動向を見すえながら長期的な戦略を樹立し,半導体それ自体に関する独自のマーケティング能力の強化や自律的な開発を目ざす動きを妨げる要因ともなり得るものであった。高度経済成長期以来,日本においては,半導体事業が発展する要因は豊富に存在し,各メーカーにおける半導体事業は実際に大きく発展したものの,半導体企業の自律的な発展には必ずしもつながるものではなかったのである。
【30頁】以上の小括と関連して,高度経済成長期における日本の半導体産業の発展史においては,以下に見るようなアンバランスな様相が見られたことが業界団体によって記録されている。
トランジスタ・ラジオ・ブームを契機とした有力電機メーカーの本格的な半導体事業への参入と激しい競争を経ることにより,1960年頃には,日本は一時的に「世界第1位のトランジスタ王国」となった。そうした意味では,日本の半導体産業は,導入技術を素早く消化し,比較的早期に「成功」を収めたものといえる。もっとも,1960年代後半の電子工業界においては,「成功」要因として,トランジスタ・ラジオという需要があったことに加え,「ゲルマニウム・トランジスタ産業がどちらかといえば人海戦術的産業であり,豊富な労働力をもったわが国には最も適した産業だった」ことが指摘されており33),それと同時に日本の技術力の弱さも強調されている。すなわち,シリコン・プレーナー・トランジスタおよびICの登場とともに,次のような認識が一般化したのである。米国で開発された「プレーナー技術は米国で着実に成長し,シリコン・トランジスタ製造の中核技術になっており,日本がそれに着目したときにはとり返しのきかないほどの技術格差を生んだ」。また,「典型的な装置産業といわれるICにおいて日本がかつてのゲルマニウム・トランジスタで築いた輝かしい地位を獲得することは,なおきわめて困難といわなければならない。(中略)問題は米国との差があまりにも大きい」34)。端的にいえば,ゲルマニウム・トランジスタにおける爆発的な需要拡大への急速な適応能力はきわめて高かったものの,その後の急速な半導体技術の発展を見すえた長期的な研究開発に向けた資源投入は乏しかった。このため,導入技術への依存度が高く,先端技術には大きく遅れたまま,家電向け半導体製品の開発と生産がアメリカを凌いで急増するという,アンバランスな発展が生じたのである。
この背景として,繰り返しになるが,以下のような事情が指摘できる。1950年代から1960年代初めにおいて,日立,東芝,三菱電機,日本電気は事業部門の多角化を進めていたものの,半導体は必ずしも中核ではない一部門であり,1950年代半ばまではあまり重視されておらず,技術導入コストの高さも課題となっていた35)。そうした中で,半導体部門の社内的な地位を確立するために,各メーカーとも急速に拡大し,事業収益が見込めそうなラジオ市場に一気になだれ込んでいった。このため,ラジオ,テレビなどの市場拡大に追随する形で半導体事業を展開したものの,高度経済成長末期に至るまで,半導体そのものの技術や事業についての長期的な展望を踏まえた事業戦略を樹立していたとはいいがたい36)。日立において見られたように,中央研究所等における先端的な半導体研究と半導体の事業展開は必ずしも円滑に連携してはいなかった。ICの重要性をいち早く認識していた日本電気においても,コンピュータや電子交換機向けの高度な半導体開発に注力する一方,事業展開としては電卓向けICや家電向けリニアICに重点を置いた37)。三菱電機においては,当初は,重電関係のパワー半導体を重視する事【31頁】 業展開を示していたが,1960年代半ばには電卓向けICの開発にいち早く乗り出すなど,その時々の市場動向に適応する傾向を強めていった。
すなわち,各メーカーの半導体事業は,企業内の経営方針の変遷と激しく変動する市場動向の双方から大きなショックを断続的に受けていた。この結果,1960年代後半において,日本の半導体産業は,アンバランスな発展という様相を示すことになったものと考えられる。
以上より,日本の半導体産業史に関して,次のような分析視角を提示したい。
高度経済成長期日本の半導体産業は,「急速に進展する技術革新」,「時代ごとに変わる需要ドライバーの登場により激しく変動しながら成長する市場」,「多角的な企業経営のもとにおける事業展開」という3つのダイナミクスに強く影響された38)。そうしたダイナミクスの中で,各メーカーが半導体事業についての最適な戦略を見つけ出すことは容易ではなく,1960年代後半においては,アンバランスな様相が顕著に生じた。各メーカーとも自社内の優れた人材を集め,研究開発を展開していたものの,研究開発と事業展開との間の連繋は必ずしも十分ではなく,マーケティングを含めた事業戦略を見すえた研究開発,ないし研究開発をベースとした事業展開といった,研究開発と事業を統合するような戦略を構築するには至らなかった。
もっとも,1950年代から1960年代初めという半導体の草創期において,日本においてラジオやテレビなど家電向けトランジスタの開発が隆盛を極めたことは,1970年代後半頃から1980年代における,家電向けの多様なリニアICの発展につながっていることは間違いないであろう。このようなリニアICの開発は,のちに日本メーカーの主導によって開発された国際商品である家庭用VTR事業の発展に大きな役割を果たした39)。さらには,ポータブル・オーディオ機器,家庭用小型ビデオカメラなど小型化・多機能化のためには新たなIC開発が必須であった40)。また,各メーカーにおけるリニアICの開発は,細かな差別化を可能とし,商品種類の多様化につながっていった。半導体の開発がエレクトロニクス家電分野を中心に新商品を続々と誕生させて新たな半導体需要を導くという形で,半導体事業が持続的に拡大するダイナミクスが内生的に生み出されたのである。このようなダイナミクスにより,1980年代から1990年代初めにか【32頁】 けての日本の半導体産業の最盛期を現出させる重要な要素となったことは特筆すべきであろう41)。ただし,そのような最盛期においても,半導体産業ないし半導体事業の顕著な発展の一方で,半導体企業の自律的な発展には乏しかったことにも留意する必要がある。
本稿においては,高度経済成長期における日本の半導体産業の展開について,各メーカーにおける半導体事業の発展の過程を整理することにより,半導体事業が大きく発展する一方で,半導体企業として発展するには,必ずしも良好な環境条件には恵まれていなかった可能性を強調した。その背景として,各メーカーの半導体事業は,「急速に進展する技術革新」,「時代ごとに変わる需要ドライバーの登場により激しく変動しながら成長する市場」,「多角的な企業経営のもとにおける事業展開」という三つのダイナミクスのもとで,最適な事業戦略を見つけ出すことがきわめて困難であったのではないかとの分析視角を提示した。
ただし,本稿では,各メーカーの周辺的な環境条件等を提示した上で,具体的な歴史過程を素描したにとどまっている。今後は,上記の分析視角を踏まえた上で,各メーカーにおける事業展開についてより深く検討したい。
これに加え,より広く,日本の電機産業の歴史を展望しつつ,以下の点を指摘しておきたい。石井晋[2023]において,終戦直後に指摘された日本の技術の「模倣的性格」とそれにともなう,技術部門間のアンバランス,各分野のセクショナリズムと連繋の不足,基礎研究から応用研究への接続の不円滑,日本で開発された技術への不当な評価などについては,かなり後の時代まで,軽視しえない課題として後々まで継続した可能性を指摘した。本稿で検討してきた半導体事業の展開については,このことが強くあてはまるように思われる。家電製品市場およびそれと密接に関連する半導体市場の拡大と展開がきわめて速かったために,研究開発とマーケティングと効率的な量産を連繋させるような,中核となる企業戦略を立て,そうした戦略のもとに組織を体系的に整備していくことが困難であったことが,その背景にあるものと考えられる。
青木洋[2014]「半導体技術の発展を支えた共同研究」平本厚『日本におけるイノベーション・システムとしての共同研究開発はいかに生まれたのか』ミネルヴァ書房
石井晋[2020]「日本における電機産業の発展史 ⑴論点の整理と課題の設定」学習院大学『経済論集』第57巻第3号
石井晋[2021]「日本における電機産業の発展史 ⑵研究開発体制の形成と技術導入の影響」学習院大学『経済論集』第57巻第4号
石井晋[2022]「日本における電機産業の発展史 ⑶高度経済成長期各メーカーの動向」学習院大学『経済論集』第59巻第3号
石井晋[2023]「日本における電機産業の発展史 ⑷高度経済成長期の技術導入と主要メーカーの事業展開」学習院大学『経済論集』第59巻第4号
泉谷渉・川名喜之[2019]『伝説 ソニーの半導体』産業タイムズ
伊丹敬之+伊丹研究室[1989]『日本のVTR産業 なぜ世界を制覇できたのか』NTT出版
岩瀬新午[1995]『半導体に賭けた40年』工業調査会
大野稔・鈴木茂・桃井敏光・大橋伸一・久保征治[1965]「MOSトランジスタの開発」『日立評論』第47巻8号
大朏博善[2006]『ソニーを創ったもうひとりの男 岩間和夫』ワック
沖電気工業株式会社[1981]『沖電気100年のあゆみ』
奥山幸祐[2009]「半導体のはなし 半導体の歴史 その9 20世紀後半 集積回路への発展⑷」SEAJ Journal No. 123
河村徳士[2022]「高度成長期日本の半導体開発」林采成・武田晴人編『企業類型と産業育成-東アジアの高成長史』京都大学学術出版会
金容度[2006]『日本IC産業の発展史』東京大学出版会
久保脩治[1989]『トランジスタ・集積回路の技術史』オーム社
工業技術庁[1949]『技術白書 わが国鉱工業技術の現状』工業新聞社
三洋電機株式会社[1980]『三洋電機三十年の歩み』
柴田昭太郎・佐藤興吾[1963]「拡散型メサトランジスタ」『日立評論』第45巻第7号
清水英治[1980]「民生用リニアICの開発動向」『電子材料』1980年12月号
ソニー株式会社広報センター[1996]『ソニー創立50周年記念誌 GENRYU 源流』
竹間茂樹[1960]『東芝コンツェルン』展望社
只野文哉・白神毅[1942]「電子超顕微鏡の試作とこれに関する二三の実験『日立評論』1942年8月
只野文哉・島史朗[1971]『研究・開発(増補第二版)』マネジメントセンター
通商産業省[1959]『電子工業年鑑(1959年度版)』電波新聞社
通商産業省[1990]『通商産業政策史 第6巻』より第5章第2節「外資導入と技術導入」(筆者は沢井実),第5章第5節「機械・電子工業の育成」(筆者は,橋本寿朗)
通商産業省企業局[1962]「外国技術導入の現状と問題点 甲種技術導入調査報告書」
通商産業省重工業局[1957]『日本の電子工業』日刊工業新聞社
電子機械工業会[1968]『電子工業20年史』電波新聞社
東京芝浦電気株式会社[1977]『東芝百年史』
「東芝 重電の歩み-技術への挑戦-」編集委員会[2007]『東芝 重電の歩み-技術への挑戦-』株【34頁】 式会社東芝
徳山巍・山本雅幸[1969]「LTPトランジスタ」『応用物理』第38巻第5号
中川靖造[1992]『自主技術で撃て 日本電気にみるエレクトロニクス発展の軌跡』ダイヤモンド社
中川靖造[1985]『日本の半導体開発』講談社(初版は,ダイヤモンド社,1981年)
中川靖造[1989]『東芝の半導体事業戦略』ダイヤモンド社
二木久夫[1954]「サーミスタ」『日立評論』1954年別冊6号(通信機器特集号)
西澤潤一・大内淳義[1993]『日本の半導体開発-劇的発展を支えたパイオニア25人の証言』工業調査会
日本能率協会[1986]『シャープの技術戦略』
日本電気[1972]『日本電気株式会社七十年史』
パナソニック株式会社百年史編纂委員会[2019]『パナソニック百年史』
早川電機工業株式会社[1962]『アイデアの50年 : 早川電機工業株式会社50年史』
半導体産業新聞編・垂井康夫監修[2000]『日本半導体50年史』
日立製作所創業100周年プロジェクト推進本部社史・記念誌編纂委員会[2011]『日立事業発達史−100年の歩み−1910-2010』日立製作所
日立製作所中央研究所[1972]『日立製作所中央研究所史Ⅰ』
日立製作所中央研究所[1951]「中央研究所8年史」
日立製作所半導体事業部・武蔵工場[1989]『日立半導体三十年史』による。
日立製作所日立工場・日立工場50年史編纂委員会[1961]『日立工場五十年史』
日立製作所武蔵工場[1978]『武蔵工場二十年の歩み』
日立製作所茂原工場三十年史編纂委員会[1974]『茂原工場三十年史』
日立製作所臨時五十周年事業部社史編纂部編[1960]『日立製作所史』(改訂版)日立製作所
平本厚[1994]『日本のテレビ産業』ミネルヴァ書房
富士通株式会社[1976]『富士通 社史Ⅱ』
降籏誠[1980]「VTR用リニアIC」『電子材料』1980年12月号
「毎日新聞」1963年12月11日朝刊
三菱電機株式会社[1951]『建業回顧』三菱電機株式会社
三菱電機株式会社社史編纂室[1982]『三菱電機社史 創立60周年』
三菱電機株式会社開発本部[1986]『三菱電機研究所50年史』
三菱半導体事業30年記念誌編集委員会[1989]『三菱半導体事業30年記念誌』
山本雅幸・佐藤和夫・渡辺寛・古賀康史・山田栄一・若島喜昭[1969]「LTPレンジモールドトランジスタの開発」『日立評論』第51巻第3号