�n��t�[�h�u�����h�̋i�H�����K��n��ւ̖K��ɂȂ��邩�i�O�ҁj
�`�T�O���f���쐬����ю��،����p�A���P�[�g�����[�쐬�̂��߂̃C���^�r���[�����`
�w�K�@��w�@�@��c�@����
�w�K�@���q��w�@�@�|���@�r�q
�n��Ő��Y����Ă���n��t�[�h�u�����h�����H���邱�Ƃɂ��C���Y�t�[�h�u�����h�����n������C���Y�����肷�関�K��n��֖K�₷�邱�ƂɎ��ۂȂ���̂��C�Ȃ���Ƃ���ǂ��������R�ɂ����̂Ȃ̂���T�邱�Ƃ������ړI�Ƃ����B���̎�̌����́C�d�v���������ɂ��ւ�炸�C�قƂ�nj������Ȃ���Ă��Ȃ����߁C�œ_�Ă����̂ł���B�{�����͑O�҂ł���C�܂������I�Ȓm���邽�߂ɁC�C���^�r���[�����{���C�l���ƂɁC�Ȃ������ɍs���̂��ɂ��Ă̍\���}��`���o���C���̌��ʂɊ�Â��āC�T�O�}��`���Ă���B�����ăC���^�r���[���ʂ���C�T�O�}�Ɋ�Â������͂̂��߂̃A���P�[�g���ڂ�T�������B�{�_���͂��̃A���P�[�g�Â�����C�v���Z�X�������Ȃ���C���J�ɍs���Ă���B
�n�抈�����C�n��t�[�h�u�����h�C�F�m�^���C����^���C�e���g�[���I�헪�C�f���O���t�B�b�N�v���C�T�C�R�O���t�B�b�N�v���C�C���^�r���[�E�t���[
�n�抈�����ɂ����Ă͒n��Y�i�u�����h�̌`���┄��g����d�v�ł��邪�C����ɂ���Č𗬐l���𑝂₵�Ă������Ƃ��d�v���ƌ�����B�Ⴆ�C�t�����X�E�{���h�[�C�u���S�[�j����J���t�H���j�A�E�i�p�̃��C���C�X�y�C���E�C�x���R��C�^���A�E�p���}�̐��n���C�Z�Ԓ��̃`���R���[�g�C�H�c�̂��肽��ہC�ɐ��̐ԕ��C�[���������C���������q�C�h�q�@���C�L���̉��y�C�����n���R�ԕ��̌ܕ��݁C��Ԃ̂܂���C���㋍�C�Ή����ق̔������l�ȂLj��H�Ɋւ���L���Ȓn��Y�i�t�[�h�u�����h�͖����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��B�������Ȃ���n�抈�������l����ۂɂ́C���������n�ȊO�Ŕ�������iEC�܂ށj�C�l���������肵�Ĉ��H�����ꍇ�C���̐��Y�n�֍s�������Ƃ����C�����ɂȂ邱�Ƃ́C�𗬐l���𑝂₷���߂ɔ��ɏd�v�ȃJ�M�ƂȂ�B�����̗L���u�����h�̒��ŁC�K�₵�Ă��Ȃ��n��̃u�����h��H�ׂ�����肵�����C���̒n��K�₵�����Ȃ���̂͂ǂ���������������̂��낤���B�܂��ǂ������l���ǂ��������������ŖK�₷��̂��낤���B
�ȑO����C�n��̂��̂��u���������v�˂��̐��Y�n���u�K�ꂽ���v�˂��̒n��̐l�X�Ɓu���y58�Łz ���������v�˂��̒n��Ɂu�Z�݂����v�Ƃ����S�̏d�v�ȃ}�l�W�����g�̈�̃X�e�[�W���w�E����Ă��邪1�j�C����́C�u���������v�ˁu�K�ꂽ���v�̃v���Z�X�ɋ߂��C�i�H���K��ɂȂ��镔���ɏœ_�Ă����B�{�_�ł́C�O���[�v�E�C���^�r���[�����{���C�l���Ƃɒn��t�[�h�u�����h�̋i�H�����n�K��ɂȂ������P�[�X�͂��C�ߋ��̕����������āC�����������邽�߂́Cweb�A���P�[�g����[���쐬����B
�Q�D����܂ł̌�������̌����ړI�̖��m��
����܂Ŋό��ƐH�Ɋւ���T�O�I�Ȍ����ɂ́C���i2019�j�C���Ɓi2015�j�C�c���E�㓡�E���v�ԁi2008�j��������C�܂��C���o�E���h�֘A�ł��ό����i2020�j�C���c�i2015�j���̕������邱�Ƃ��w�E����Ă���2�j�B�������Ȃ���C�H���ό��q�̗U�v�ړI�ƂȂ肤��Ƃ����C�{�����̃^�C�g���ɒ��ڊ֘A���������͂قƂ�Ǒ��݂��Ă��Ȃ��B�����Ȃ������Ƃ��ẮC�����i2022�j�ɂ����ď���҃A���P�[�g�����ɂ�錤��������3�j�B�����́C�A���P�[�g�ɂ����Ă��łɁu�K��o������v�̏ꍇ�Ɓu�K��o���Ȃ��v�̏ꍇ�ŁC����ю��X�܂��邢��EC�ł̍w���ʂŁC�n����Y�i���w��������̐S��ω����V���ځi�Y�n�Ɉ������������C�Y�n�ɐe�ߊ����������C�Y�n�������������Ȃ����C���Y�ҁE�����҂ɐe�ߊ����������C���Y�ҁE�����҂������������Ȃ����C���Y�E�������ꂽ�w�i���m�肽���Ȃ����C�Y�n�ŐH�ׂĂ݂����Ȃ����j�ɂ킽���Ē��ׂĂ���B���̕ω��ł́C���X�܂�EC�ł͂قڍ����Ȃ��������C�K��o������ƂȂ��ł̍��͔��ɑ傫���C�K��o������ł͔��ɓ��_�����������B�܂��K��o�����Ȃ��ꍇ�ɂ́C�S��̕ω��́u���Ă͂܂�Ȃ��v�ɋ߂��C�n��t�[�h�u�����h���w���E�i�H���Ă����K��n��ɗU�v���邱�Ƃ͓���Ƃ������ʂƂȂ��Ă���B�����̌����ł́C�u�H�i�̍w�����Y�n�ɂ��Ă̏���i�̒~�ςɂȂ����Ă���\��������ȏ�C���s�ړI�n�I���ɂ���������W��i�ƂȂ蓾��v�Ƃ��Ă��邪�C���n�ł̒n�抈�����t�[�h�u�����h�̍w���o��������Ƃ������ƂɊւ��ẮC�K��o�����̂��̂��C�P�Ƀ��s�[�g�K��ɂȂ���₷�����Ƃ��������Ă���\���������C�n��t�[�h�u�����h�w���ƒn��K��Ƃ̊֘A������������Ɏ����Ă��Ȃ��Ǝv����B����ɍw�������ł́C�y�Y�Ƃ��Ĕ���ꂽ�\���������C�i�H�o���Ɩ��K��n��K��Ƃ̊֘A����������������C�u�H���ό��q��U�v���邩�v�Ƃ�������ɉ��������̂ƌ����悤�B
�܂���c�E�|���i2020�j�ł́C���������ݏo�����̖����ɂ��ăA���P�[�g��p�����������͂��s���Ă���B���̒��ł́C���������͕����I�Ȗ��o�݂̂Ō��܂���̂ł͂Ȃ��C�]�y59�Łz ���̌������疾�炩�ɂ���Ă���C�����C�����Ɋ��o�ړ]��ʂ��ĕt�����C���������̊��o�����邩���Əq�ׂĂ���B�����ăe�L�X�g�}�C�j���O�̌��ʓ�����}�Q-�P�̂悤�ȐH�ɂ��n��n���ɂ������p�̍\�}��`���Ă���B
���̍\�}�̎�������Ƃ���́C�u�n��̐H�Ɋւ��āC�w�����邱�Ƃɂ���āC�{�ꊴ�C�n�����C�N�x���C�f�ނ̗ǎ����C�i�F���E���Y�̏W����Տꊴ�������Ƃ��Ă̔F�m�^���Ɗ��o�Ƃ��Ă̊���^����ݏo����CSNS�E�e���r���̃��f�B�A�⌻�n�ł̒n�����Ƃ̐G�ꍇ����ʂ��ē`�����C�n��K��҂��邢�͎���Œ����������҂��h�[�p�~���������C�H�ւ̊��҂�~�������߂邱�ƂŁC���������̊��o������v�Ƃ������Ƃł���B�{���������ẮC���K��n��̃t�[�h�u�����h���i�H�̌����邱�Ƃɂ��C�{�ꊴ�C�n�����C�N�x���C�f�ނ̗ǎ����C�i�F���E���Y�̏W����Տꊴ�����߂ĖK�₵�����Ȃ�Ƃ������Ƃ������ɒl���鉼���Ƃ��Č�������B
�Ȃ�B-�P�O�����v���ŗL���ɂȂ��������Ȃǂ��C�ό��q�̗U�v���n�抈�����Ɍ��ʂ�L���邱�Ƃ��_�����Ă��邪�C��ʓI�ɖ��K��̏ꍇ�ɂ́C�i�H������̏ꍇ�������C�����ł͑ΏۊO�Ƃ���4�j�B
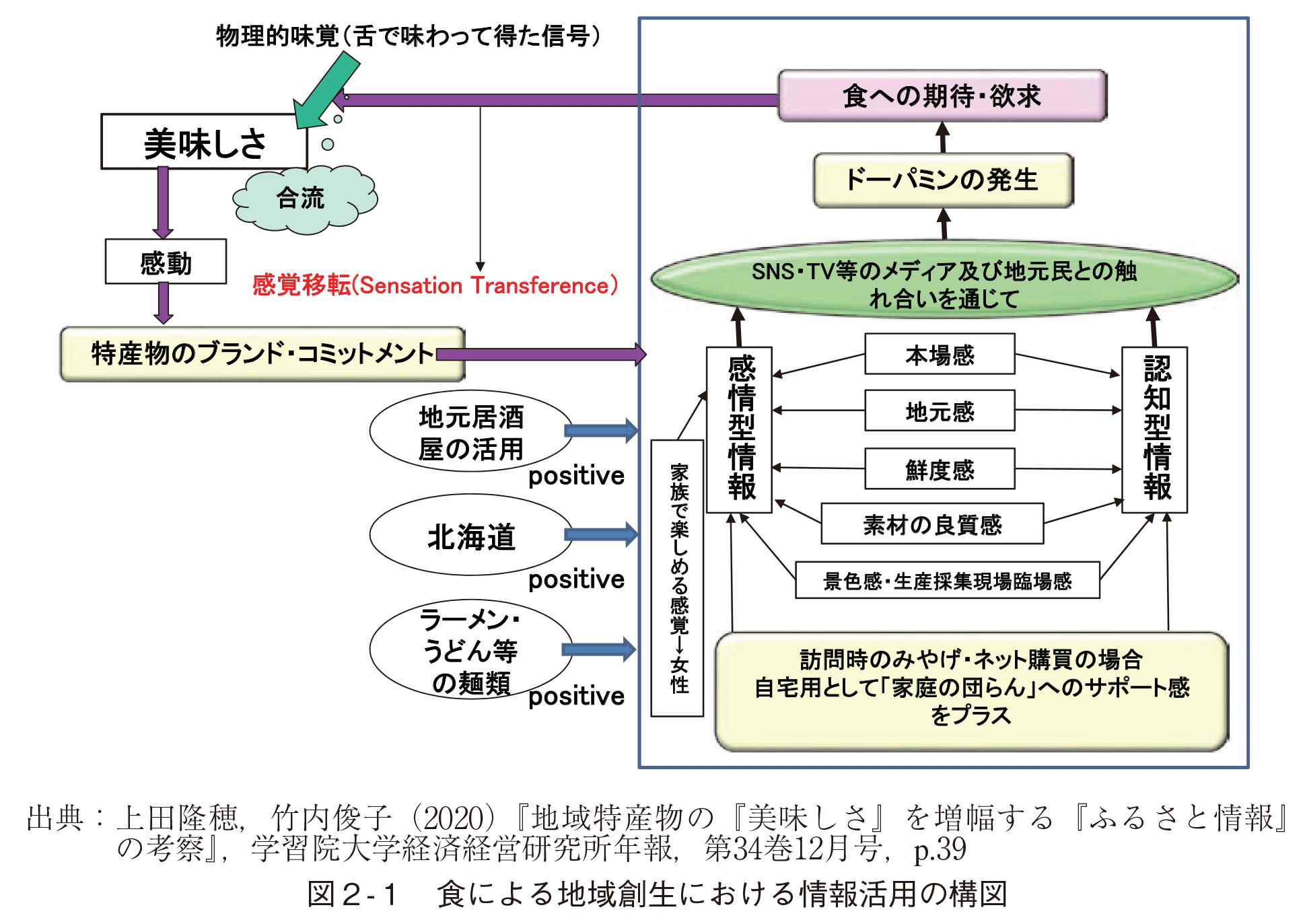
�n��u�����h�����ɂ����āC���сi2016�j�́C�n��u�����h��n���ԃu�����h�ƒn��Y�i�u�����h�ɋ�ʂ��C���҂��x���������݂ƂȂ�C���ꂪ�n��ɂ��u�����h�E�A�C�f���e�B�e�B�̑n���ɂȂ�Ƙ_���C�ڋq�̐S�Ɍ`�����������z�I�ȃu�����h�E�C���[�W�Â���𐄏����Ă���5�j�B�}������ΐ}�R-�P�̂悤�ɂȂ�C�l�X�ɂƂ��ĐS�䂩���悤�Ȓn��C���[�W�n���̂��߂ɕ��ꓙ�ł��̂Q�̒n��u�����h������K�v�����낤�B
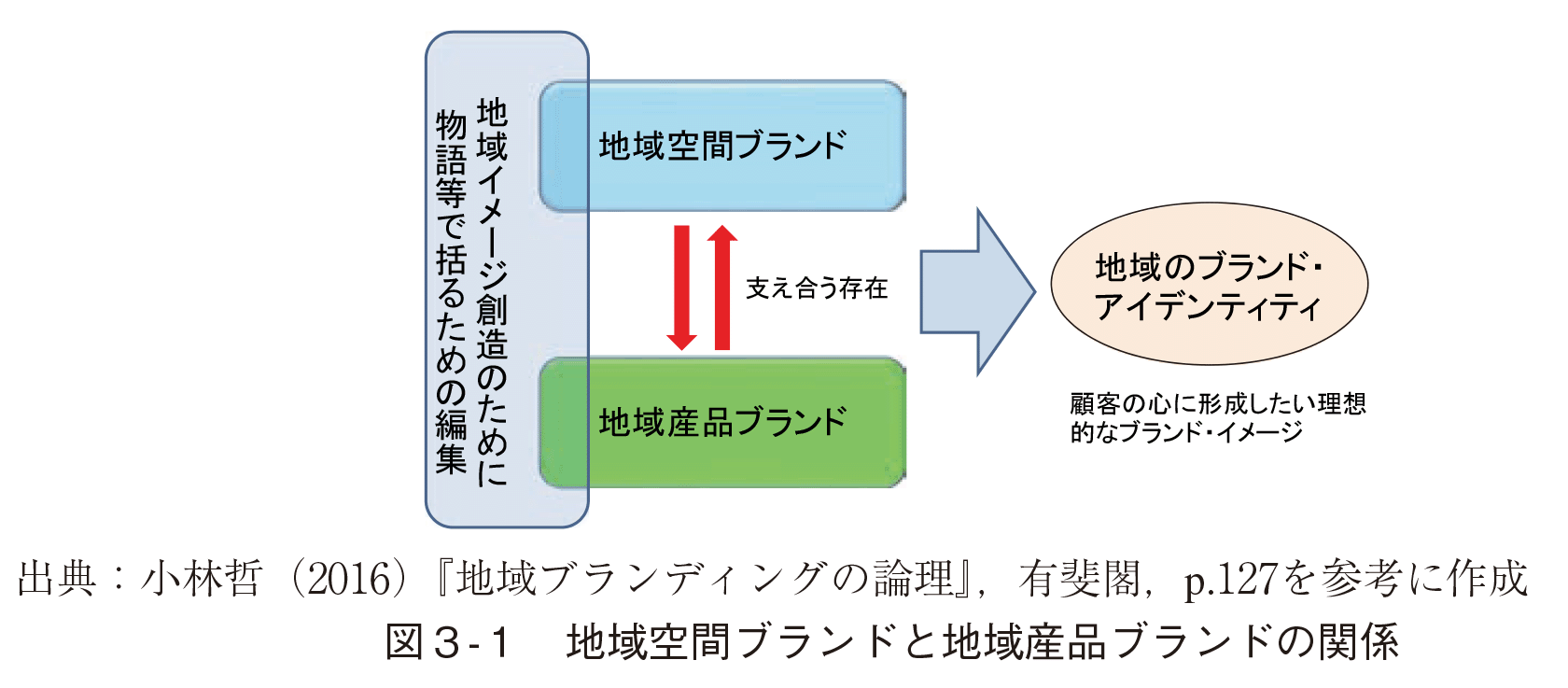
�܂����̂��߂ɂ́C�u�����h�v�f���l����K�v������C���v�f�Ԃ̑�����ʂ��o���C���ꓙ�Ŋ���C�ҏW����K�v������B�ҏW����̂́C����ȊO�ɂ��R��C�C���̑��̎��R�C�`���I�Ȍ�������������B�}������ΐ}�R-�Q�̂悤�ɂȂ�B
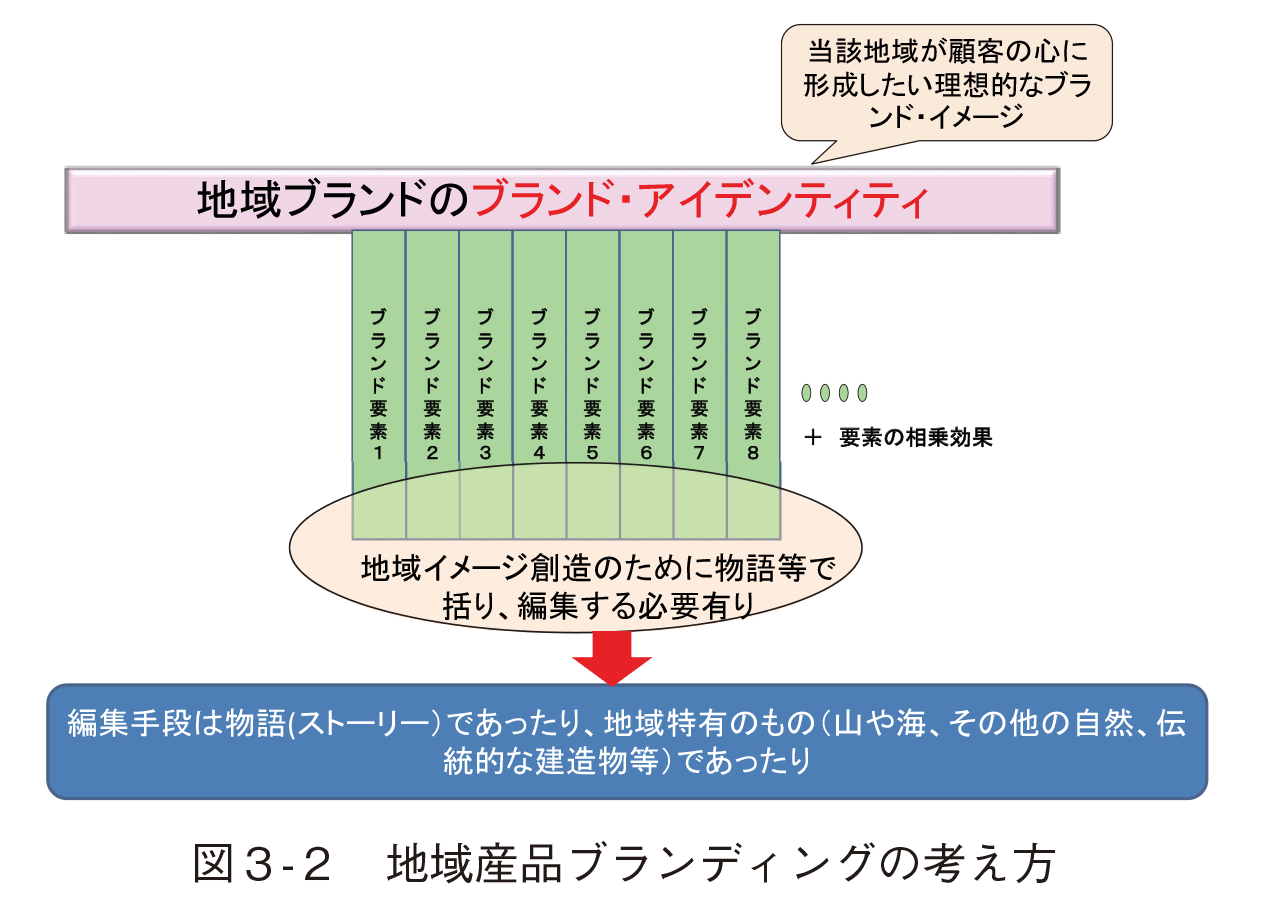
���ۂɒn�抈�����ł��̊W����̉����Ă���̂��C�C�^���A�̃e���g�[���I�헪�ł��낤�B�ؑ��E�w���i2022�j�́C�e���g�[���I�����̂悤�ɐ������Ă���B
�u�y�n��y��C�i�ρC���j�C�����C���z���C�`���i��H�|���܂ށj�C���ԓ`���C�n�拤���́C�ό��T�[�r�X�C�ڋq�̂�����C�|�p���X�̗l�X�ȑ��ʂ���������̂̂��̂ŁC�y�n�̎����R�����C���邢�͑�n�̓������������Ȃ���C������ɐl�Ԃ̑��l�ȉc�݂��W�J���Ă����B�����ł͔_�ƁC�q�{�C�ыƁC���X�̎Y�Ƃ��c�܂�C���⑺�̋��Z�n���ł��C�c���ɂ͔_��C�C���@���_�݂��C���������ԓ��̃l�b�g���[�N���ł���B�����ɗ��j��`�����~�ς���C�ŗL�̌i�ς����܂�Ă����B���������Љ�o�ϓI�C�����I�ȃA�C�f���e�B�e�B�����L�����Ԃ̍L����Ƃ��Ă̒n�悠�邢�͗̈悪�e���g�[���I�ł���6�j�B�v
���̃e���g�[���I���`������v�f�͐��������邪�C����炪��̉��E�Z�����C�n��Y�i�u�����h�ɋÏk����Ēn���I�\���iGI�j�̊�ƂȂ�m�I���L���Ƃ��Ă̑傫�ȉ��l�ݏo���Ă���̂ł���B�܂��Ƀz���X�e�b�N�ȃu�����h�E�C���[�W�ł���C�n��Ǝ��̌i�ς�����҂ɂ�苭��Ɉӎ������_�������I�ł���B���̃e���g�[���I�n���̕����Ƃ��ăe���g�[���I�E�A�v���[�`��}���������̂��}�R-�R�ł���C���ꂪ�����̊T�O���f���̌���ƂȂ�7�j�B���z�Ƃ��ẮC�n��t�[�h�u�����h�����̃e���g�[���I�̒n���̉��C���[�W���C�i�H�������ɕ����I�ɂł��i�H�҂Ɉړ]�ł��邱�Ƃ��]�܂����B�������C�n��ւ̖��K��̒i�K�ł̋i�H�̌��ʂł��邽�߁C�������ꂽ�C���[�W�ɂ͂قlj����C�e���g�[���I�̈ꕔ�����C���[�W�`�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�K�₵�ď��߂ăe���g�[���I�̃C���[�W�������ɋ߂Â��Ă������ƂɂȂ�B���̂��߁C�i�H�ɂ���āC�n��Ɋւ���F�m�I�ȗv�f��������I�ȗv�f���h������āC�K��Ӑ}�ւƂ̂Ȃ���\�����������Ƃ��l������B
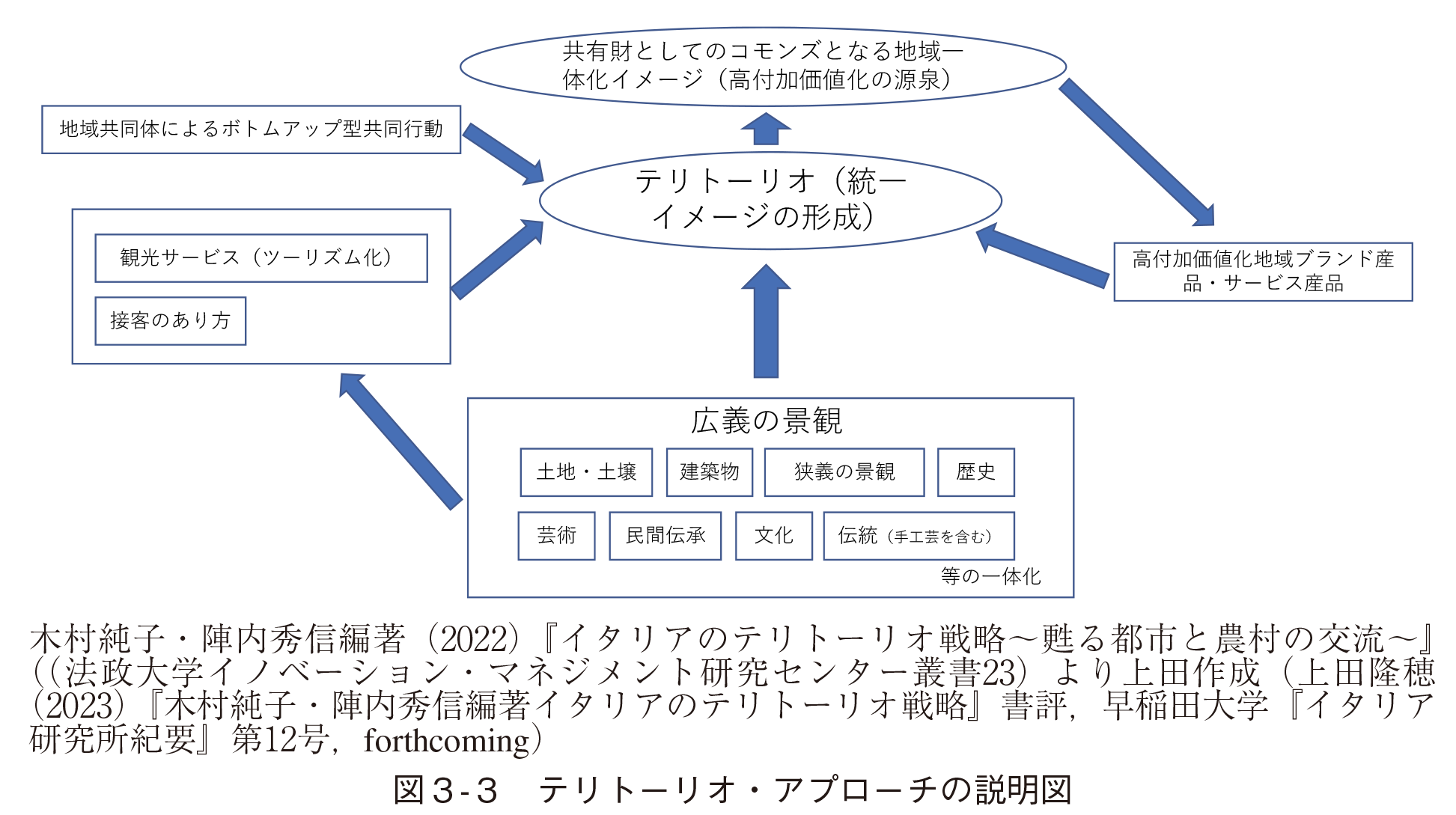
�Ȃ��K��ӗ~�̌���ƂȂ�n���̉��C���[�W�ɂ́C�i�H�҂̔N��C���ʁC�Ƒ��̗L���Ȃǂ̃f���O���t�B�b�N�v����S���I�X���ł���T�C�R�O���t�B�b�N�v�����e�����Ă��悤�B����ɑΏۖK��n��ɂ�����e���E�F�l�̂���Ȃ��ȂǕ����I�K��v�����d�v�ł��낤�B
�S�D�A���P�[�g�������ڂo���邽�߂̃O���[�v�E�C���^�r���[�̎��{
�t���[���ɉ��������⍀�ڂ��������C������ЂɈϑ����C�j���R�������ʂ��ƂɃO���[�v�E�C���^�r���[�����{����8�j�B�������C�O���[�v�E�C���^�r���[�ƌ����Ă��p�[�\�i���E�C���^�r���[�ɋ߂��`�ŃC���^�r���[�͐i�߂�ꂽ9�j�B
�@�����ۑ�́C�ȉ��̒ʂ�ɐݒ肳�ꂽ�B
⑴�n��Y�i�̐H�o�����炻�̒n���K���܂ł̌o�܂��Ƃ炦��
�@�@�ǂ̂悤�Ȍo�܂ŐH�ׂ��̂��i���������������肵���̂��j
�@�A���n�ɍs�������Ȃ�悤�ȃu�����h�̓�����T��i�s�������Ȃ�^�s�������Ȃ�Ȃ��Y�i�j
�@�B���n�ɍs���܂ł̃v���Z�X�E�X�e�b�v�𗝉�����
⑵�n��Y�i�������ɍs�������Ǝv�킹��v�f�͉�����T��
⑶�K����㉟������v�f�͉�����T��
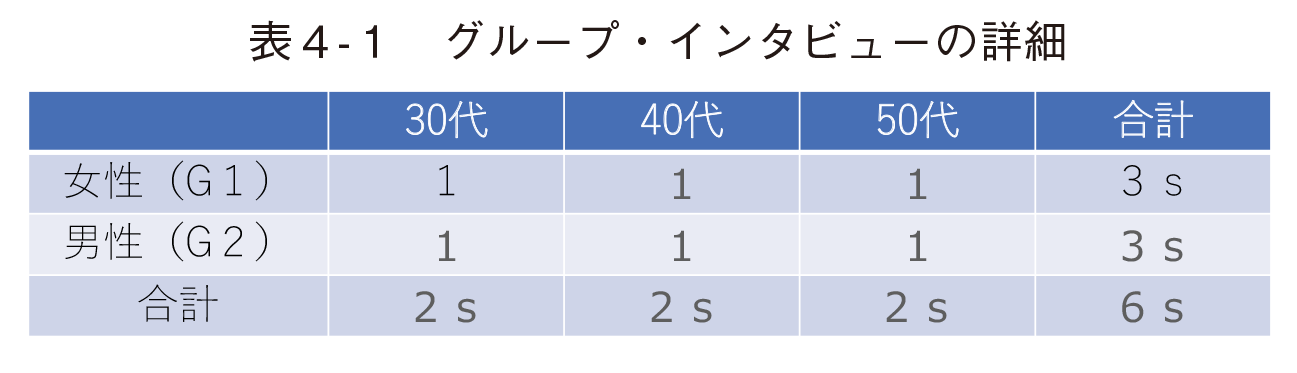
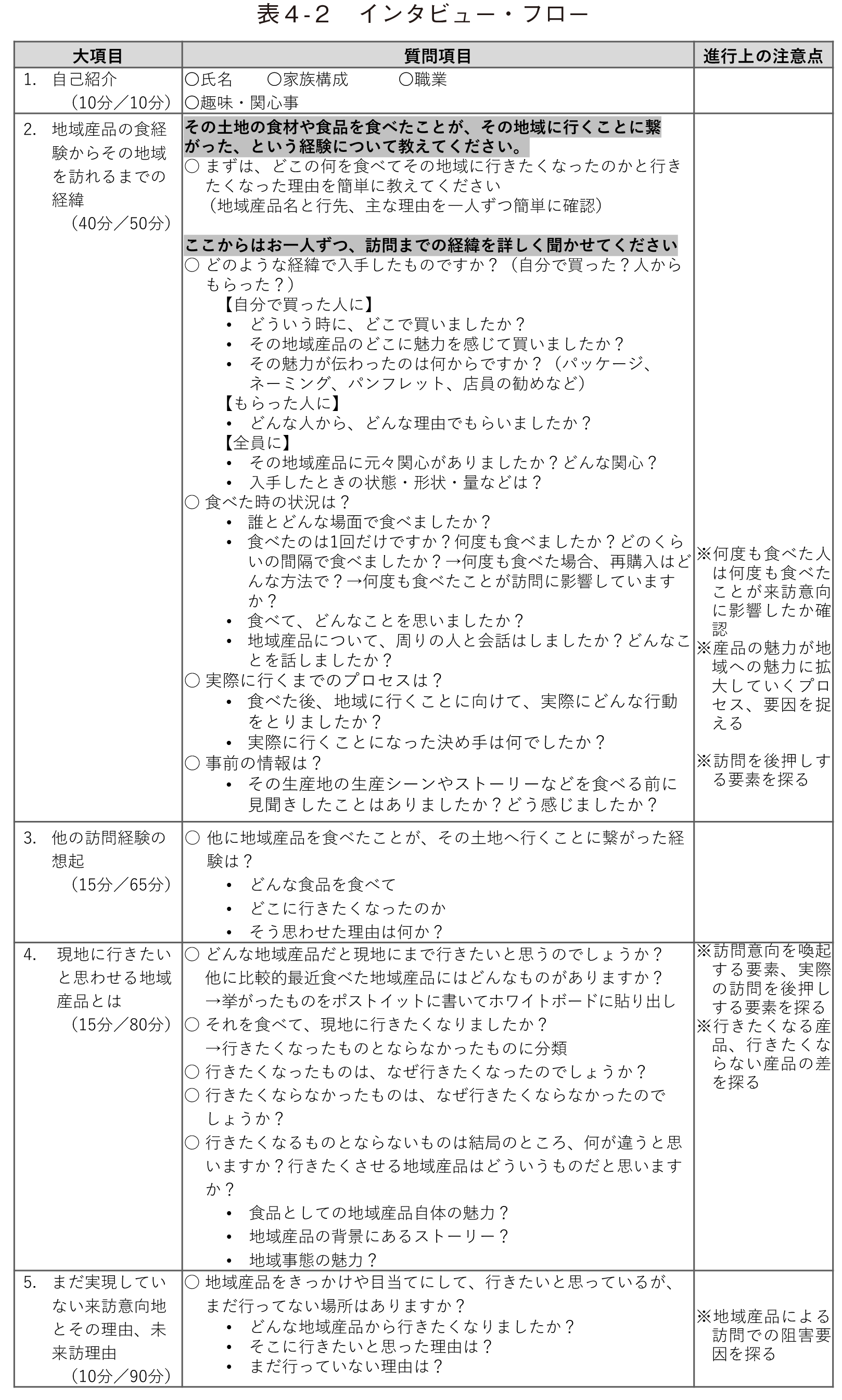
�����Ώےn��́C��s���i��s�O���j�ł���C�T���v�����͂U���i�j���R�����𐫕ʂłQ�O���[�v�ɕ����C�ʌɎ��{�j�C�C���^�r���[���Ԃ�90���Ɛݒ肵���B�n��t�[�h�Y�i�i���H�H�i���邢�͔_���{�Y���j��H�ׂ����Ƃ����������ɂ��Ă����ɋ����������Ă����֍s�����o���̂���T���v���ŁC���ꂼ��30��C40��C50������N���[�g���Ă���B�\�S-�P���ڍׂł���B�C���^�r���[�́C2022�N�X��28���ɍs�����B
�@�Q�l�Ƃ��ăC���^�r���[�E�t���[��\�S-�Q�Ƃ��Čf�ڂ��Ă����B���̃t���[�́C��X�ƒ�����ЂƂ̃~�[�e�B���O���璲����Ђ��쐬���C��X���C�����s�������̂ł���B
�܂��O���[�v�E�C���^�r���[�̎ʐ^���ȉ��Ɍf�ڂ��Ă����B�Ȃ����̔z�u�ʐ^�ȊO�̃O���[�v�E�C���^�r���[���i�́C���j�^�[���[�����猩�����̂ł���B
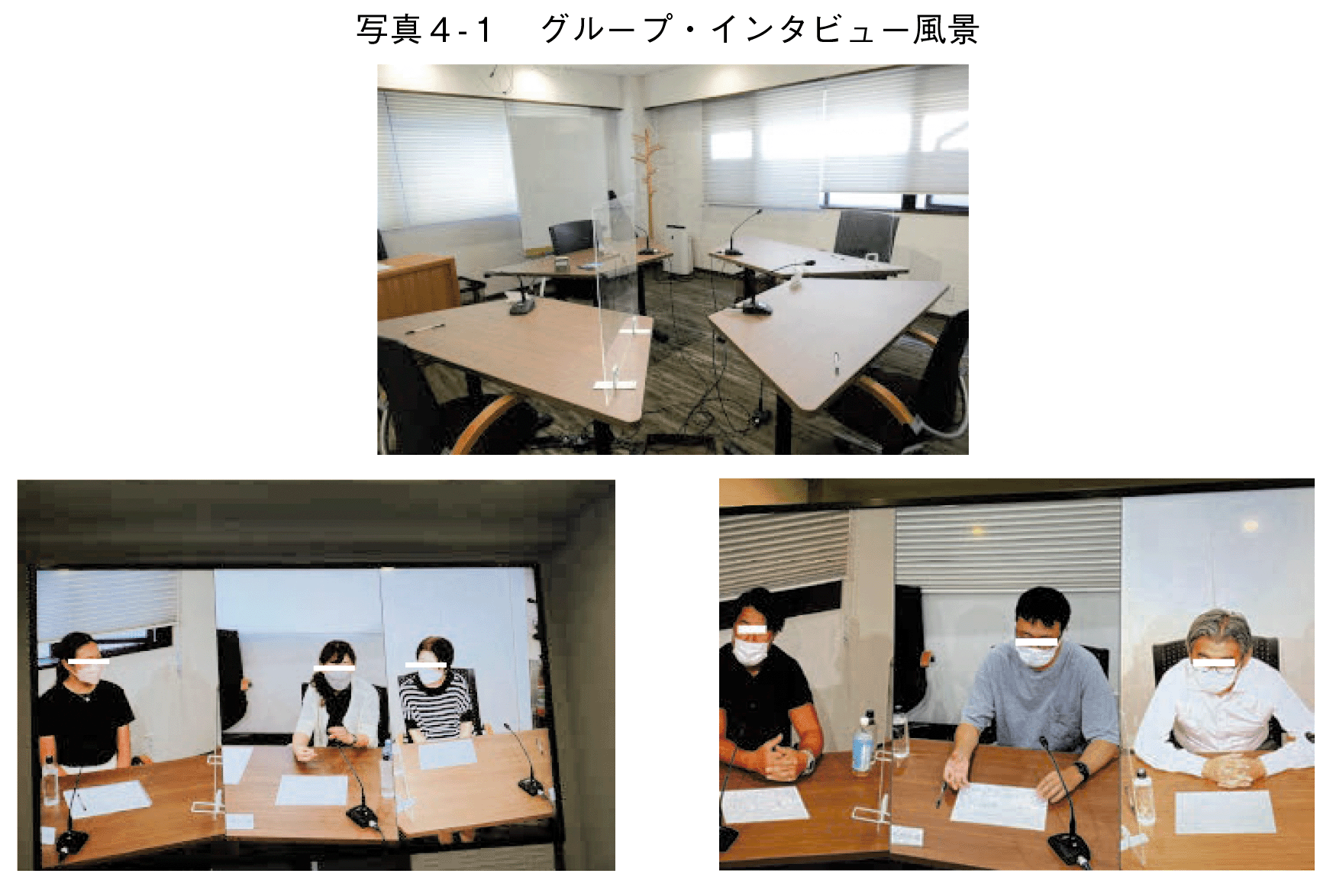
�����̃C���^�r���[���ʂ��}�C���h�}�b�v�����ɂ���Đ}���������̂��C�ȉ��̐}�S-�P�`�S-10�ł���B
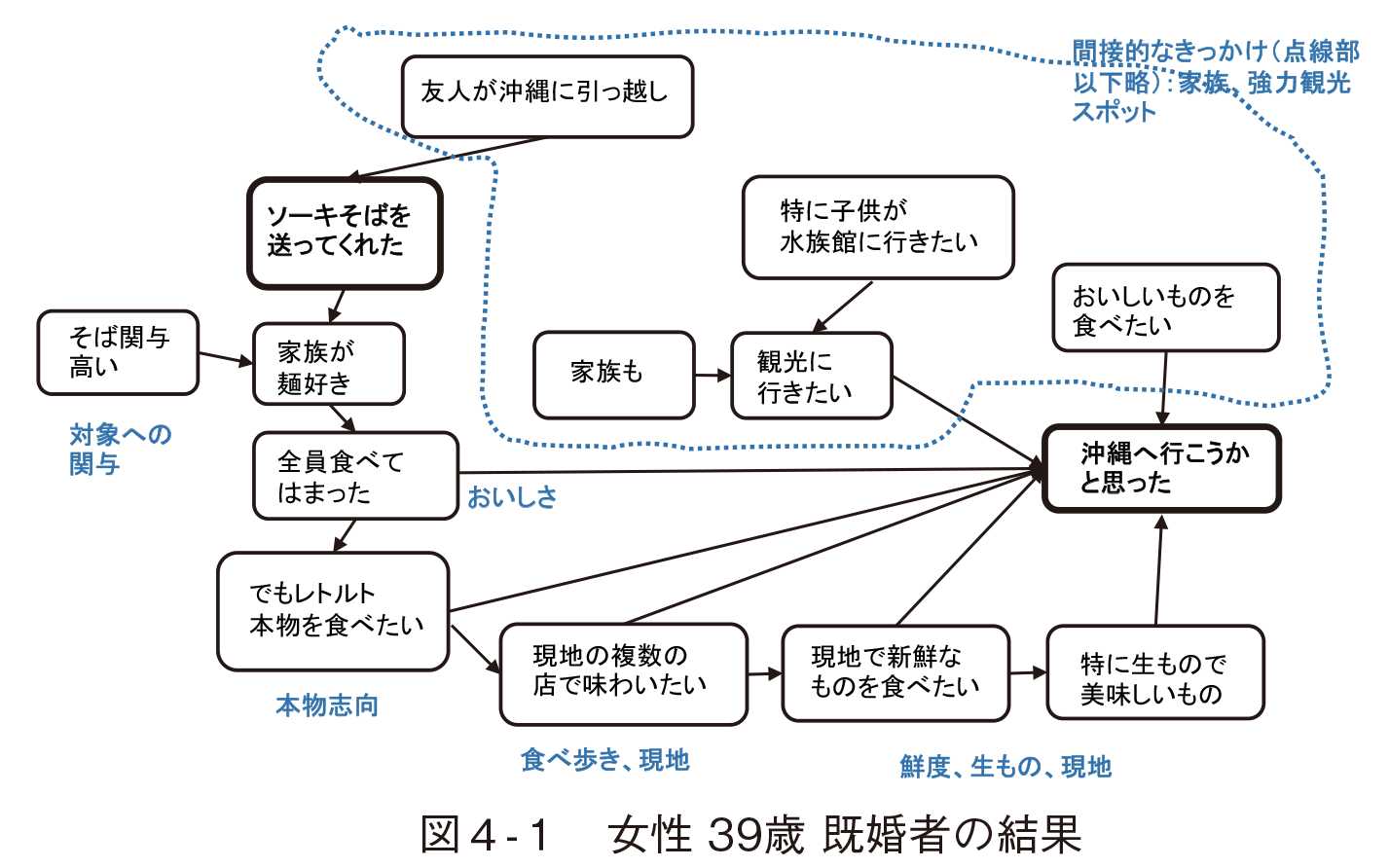
���̐}�S-�P�������39�Ί����҂́C���Ί֗^�������������C����̗F�l����u�\�[�L���v�𑗂��Ă��炢�C�Ƒ����ˍD���ŁC�H�ׂđS�����͂܂�C���������Ǝv���C����֍s�������Ǝv�������Ƃ�������B�������C�����\�[�L����H�ׂɍs���̂ł͂Ȃ��C���n�̂��낢��ȓX�ŐH�ו��������Ǝv���C���n�ŐV�N�Ȃ��̂𖡂킢�����ƍl���C���łɌ��n�ɂ͗L���Ȑ����ق�����C�q���̐����ق֍s�������v���������Ă������C�Ƒ��Ŋό��ɍs���Ƃ����ʂ̖]�݂����������Ƃ��č�p���Ă���B���������āC���̐}����́C�n��t�[�h��H�������Ƃ����̒n��ɖK�₷��v���Ƃ��ẮC�}���ɂ���C�Ώۂւ̊֗^�C���������C�{���u���C�H�ו����D���X���C�n��t�[�h�u�����h�̌��n�d���X���C�N�x�d���X��������C�܂��}���̓_���ň͂��́C���������ƂȂ�v���Ƃ��ĉƑ��⌻�n�ɋ��͂Ȋό��X�|�b�g������Ƃ������Ƃ���������B
���l�ɂ��āC�ȉ��̐}�S-�Q����}�S-10�܂Ő}���猻�n�K��̏��v�������o�����Ƃ��ł���B��ł��邪�C�����̕����j�������v���������悤�Ɋ�����ꂽ�B
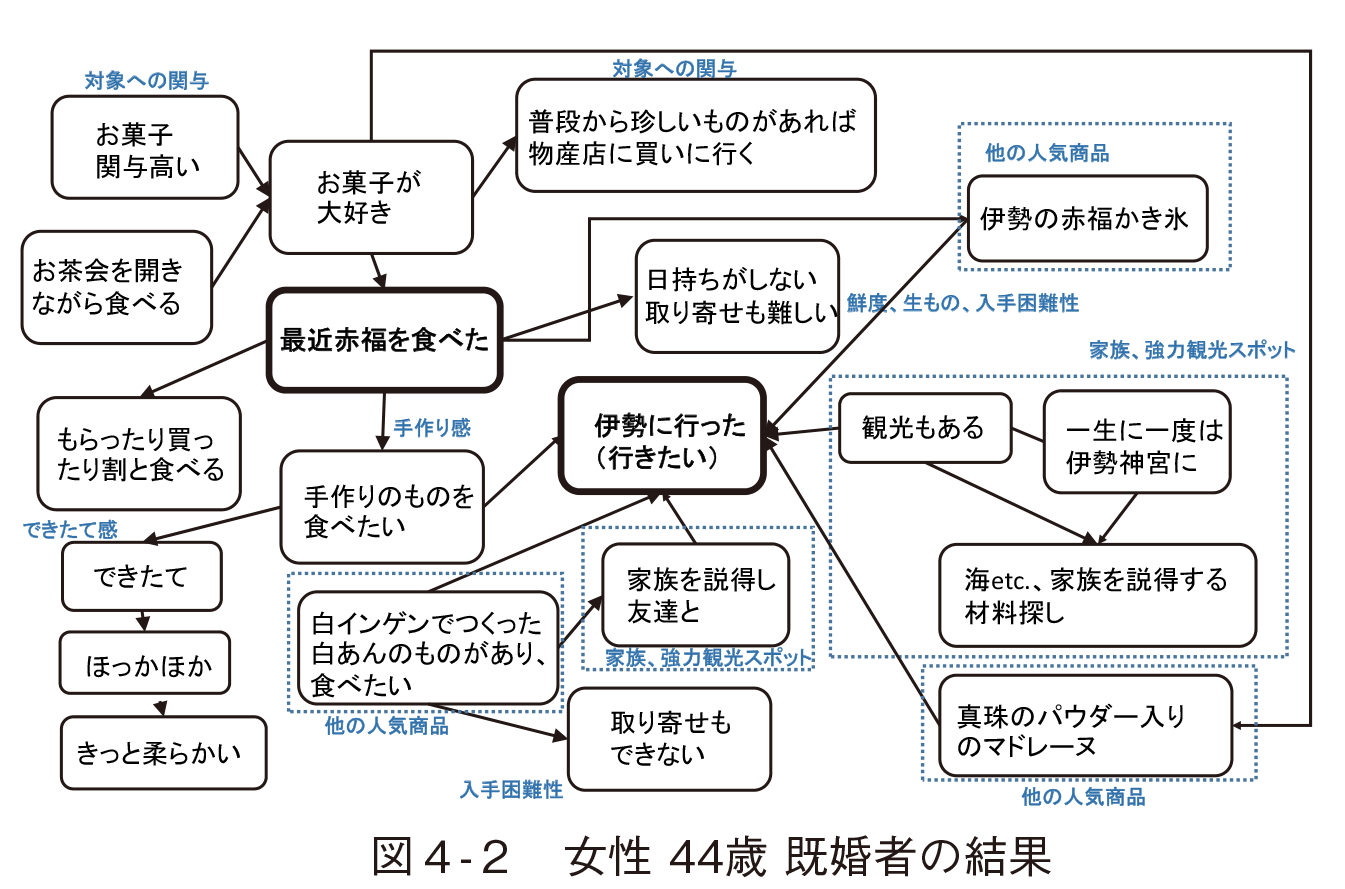
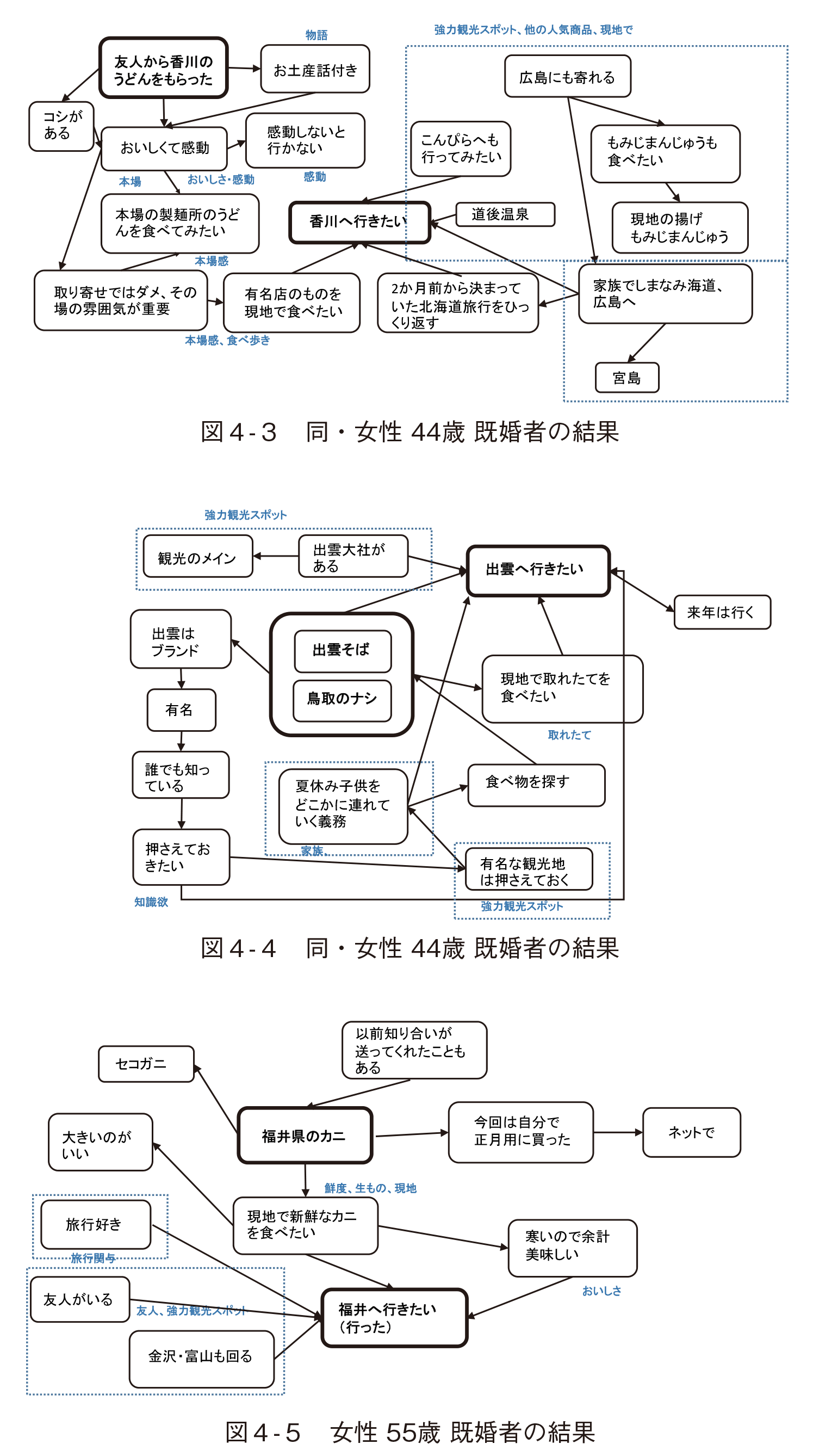
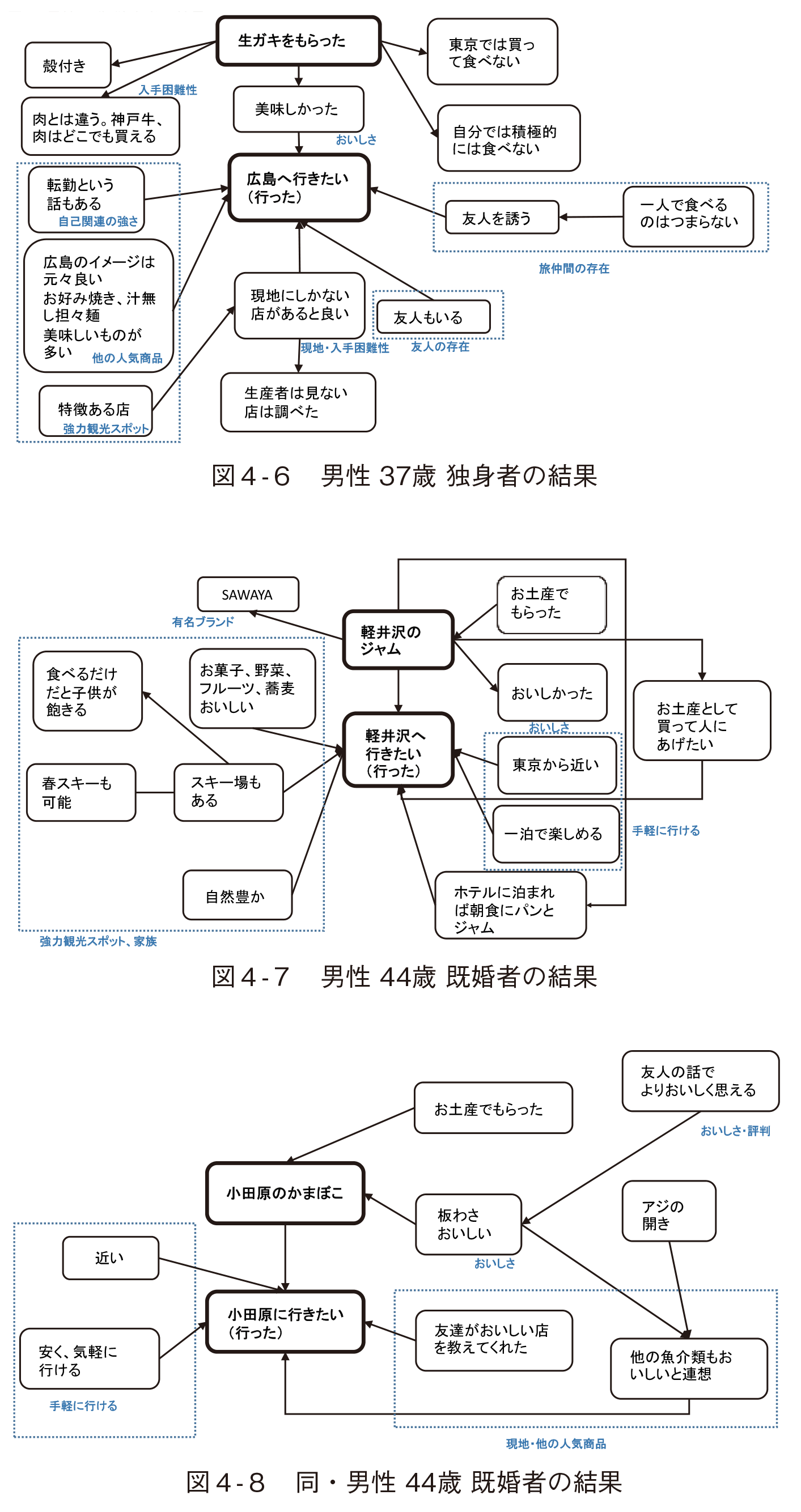
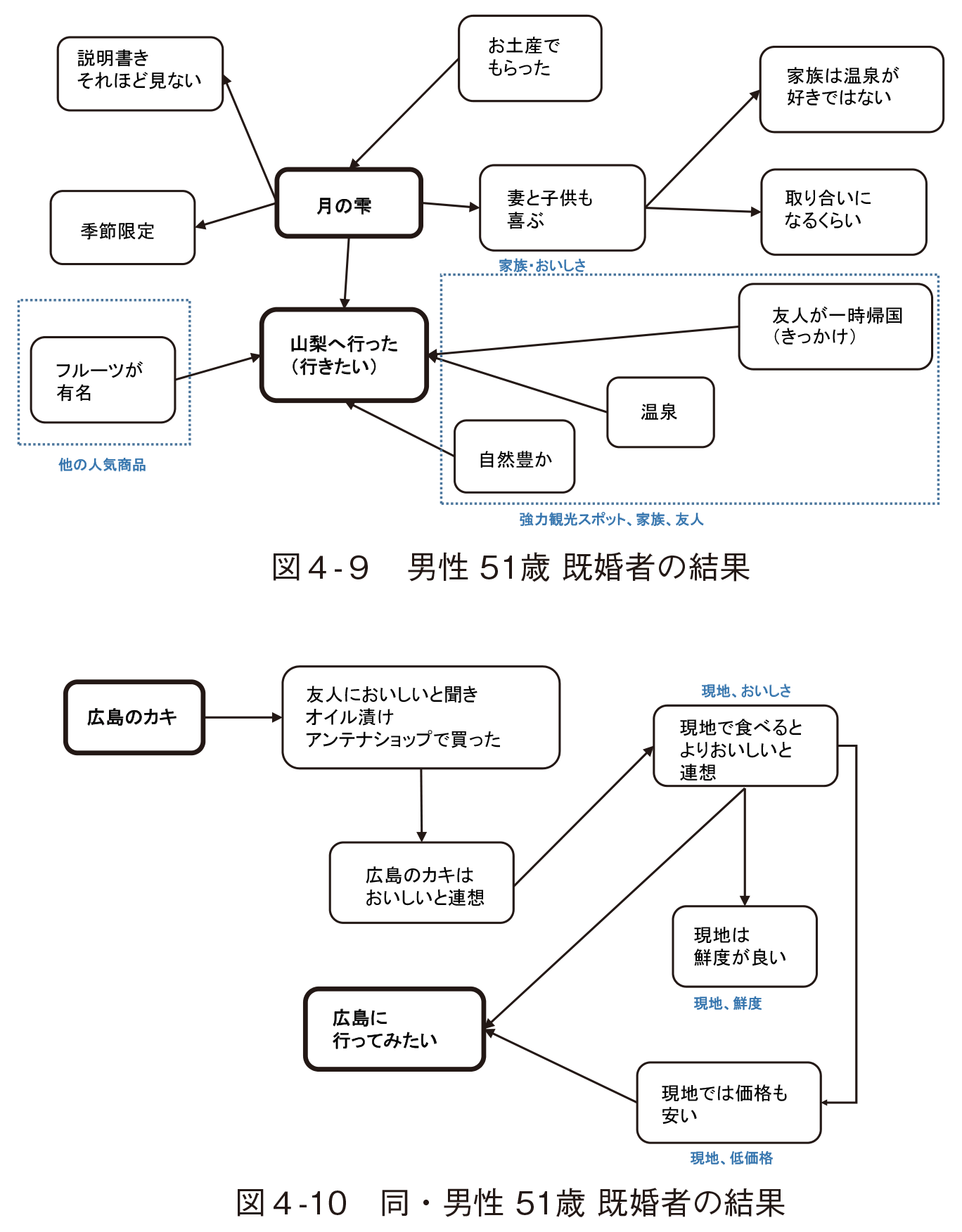
�}�S-�P���܂߂ĖK��v��������ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B
���}�S-�P
�E�{���I�v���F�@�n��t�[�h�u�����h�Ώۂւ̊֗^�C���������C�{���u���C�H�ו����D���X���C���n�t�[�h�Ɋւ��錻�n�d���X���i�{��w���ƌ���������j�C�N�x�d���X��
�E���������v���F �Ƒ��̗v�]�C���͂Ȋό��X�|�b�g�̑���
���}�S-�Q
�E�{���I�v���F�@�n��t�[�h�u�����h�Ώۂւ̊֗^�C�N�x�C���芴�C�ł����Ċ��C���n�ȊO�̓��荢�
�E���������v���F �Ƒ��̗v�]�C���͂Ȋό��X�|�b�g�̑��݁C���̐l�C���i�̑���
���}�S-�R
�E�{���I�v���F�@�{�ꊴ�C���������C�����C����C�H�ו����D���X��
�E���������v���F ���͂Ȋό��X�|�b�g�̑��݁C���̐l�C���i�̑���
�y69�Łz���}�S-4
�E�{���I�v���F�@��ꂽ�āC�m���~
�E���������v���F ���͂Ȋό��X�|�b�g�̑���
���}�S-�T
�E�{���I�v���F�@�N�x�C�{�ꊴ�C��������
�E���������v���F �F�l�̑��݁C���͂Ȋό��X�|�b�g�̑���
���}�S-�U
�E�{���I�v���F�@���n�ȊO�̓��荢��C���������C��ꂽ�āC�m���~
�E���������v���F ���͂Ȋό��X�|�b�g�̑��݁C���̐l�C���i�̑��݁C�����Ԃ̑��݁C�n��Ǝ����Ƃ̊֘A�̐[��
���}�S-�V
�E�{���I�v���F�@�L���u�����h�ł���C��������
�E���������v���F ���͂Ȋό��X�|�b�g�̑��݁C�Ƒ��̗v�]�C��y�ɍs����
���}�S-�W
�E�{���I�v���F�@�{�ꊴ�C���������C�]��
�E���������v���F ���̐l�C���i�̑��݁C��y�ɍs����
���}�S-�X
�E�{���I�v���F�@��������
�E���������v���F ���̐l�C���i�̑��݁C���͂Ȋό��X�|�b�g�̑��݁C�Ƒ��̗v�]�C�����Ԃ̑���
���}�S-10
�E�{���I�v���F�@�{�ꊴ�C�N�x�C���������C�ቿ�i
�E���������v���F �Ȃ�
����炩���x�ł��o�������v��������Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
�@�{���I�v���F
�y�n��t�[�h�u�����h���̂̓����z ���������C�ቿ�i�C�]���C�{�ꊴ�C���芴�C�ł����Ċ��C��ꂽ�Ċ��C���n�ȊO�̓��荢��C�����C����
�y�i�H�҂̌X���z �{���u���C�n��t�[�h�u�����h�Ώۂւ̊֗^�C�N�x�d���X���C�H�ו����D���X���C�m���~
�A���������v���F
�y�n��̓����z ���͂Ȋό��X�|�b�g�̑��݁C���̐l�C���i�̑���
�y�i�H�҂̗v���z �Ƒ��̗v�]�C�F�l�̑��݁C�����Ԃ̑��݁C�n��Ǝ����Ƃ̊֘A�̐[���C��y�ɍs����
���̌��ʂ��݂�ƁC��͂�n��Ɋւ��ẮC����I�ȗv�f�����傫�ȃE�F�[�g���߂Ă���悤�Ɏv����B�������O���[�v�E�C���^�r���[�̌��ʂƂ��ăA���P�[�g���ڂƂ��ē��ꍞ�ނ̂��ǂ��ƍl������B
�T�D�O���[�v�E�C���^�r���[�܂��Ă̊T�O���f���̍쐬
�}�R-�R�����ɖ{�����̕�I�ȊT�O���f�����쐬����B�}�T-�P������ꂽ���B���̐}�ɂ͕����̃��[�v������B�܂�C�n���̉��C���[�W�́C�n��t�[�h�u�����h�i�H�̂��������ƂȂ�C�i�H�̌��ʁC�n��t�[�h�u�����h�̃C���[�W���ω����C���ꂪ�n��̈�̉��C���[�W��ω�������B�܂��n���̉��C���[�W�́C�n��t�[�h�u�����h�̃C���[�W�ɕω���^���C�ēx�̋i�H�̌����Ƃ��Ȃ�B�����Ēn��t�[�h�u�����h�̃C���[�W�́C�i�H�҂̃f���O���t�B�b�N�E�T�C�R�O���t�B�b�N�v����F�l�̑��ݓ��C�i�H�҂̂��������ƂȂ�K��v���ƂƂ��ɒn��ւ̊S�����߁C����炪�K��ւƂȂ����Ă����B���̖K��̌��ʂ́C�n���̉��C���[�W�ɕω���^���C���Y�n��ւ̊S�ɕω���^����B�������C��q�̂悤�ɁC�n��t�[�h�u�����h���^����e���ɂ́C�F�m�I�Ȃ��̂Ɗ���I�Ȃ��̂�����B�������ו������āC����ɏڍׂȊT�O���f���ɂ�镪�͂��s���K�v�͓��R����Ǝv����B
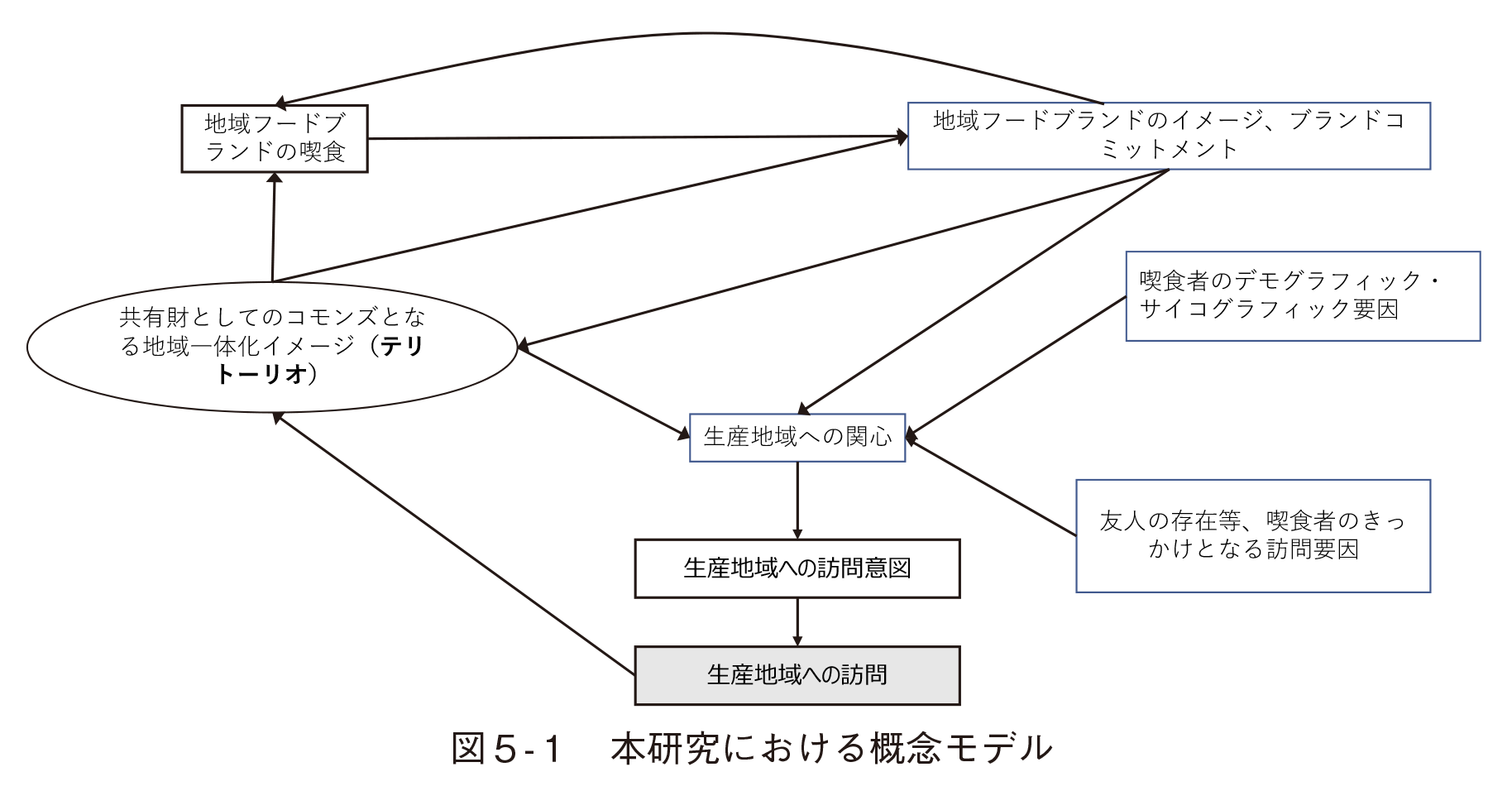
�ȏォ��A���P�[�g���쐬���Ă����B�ȉ��A���P�[�g���ڂ��f�ڂ��Ă����B
�Ώێ҂͈�s�O���i�����s�C�_�ސ쌧�C��ʌ��C��t���j��30�`60��̒j���C�n��t�[�h�u�����h�̋i�H�����n�K��ɂȂ������l�i�s�������Ƃ̂Ȃ��n��j�ł���B
���Ώێ҂��i�邽�߂̐ݖ�i�P��j
Q�@���Ȃ��́C�n��t�[�h�u�����h��H�ׂ����Ƃ����������ɁC�͂��߂Ă��̒n���K�₵�����Ƃ�����܂����B
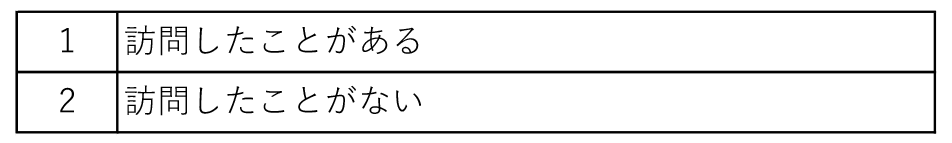
���u�n��t�[�h�u�����h�̋i�H�v�Ɋւ���ݖ�i�S��j
Q�@���Ȃ����n��t�[�h�u�����h��H�ׂ����Ƃ����������ɖK�₵���s���{���Ƌ�̓I�Ȓn��C���Ȃ����K�₷�邫�������ƂȂ����n��t�[�h�u�����h�Ɠ�����@�����������������B
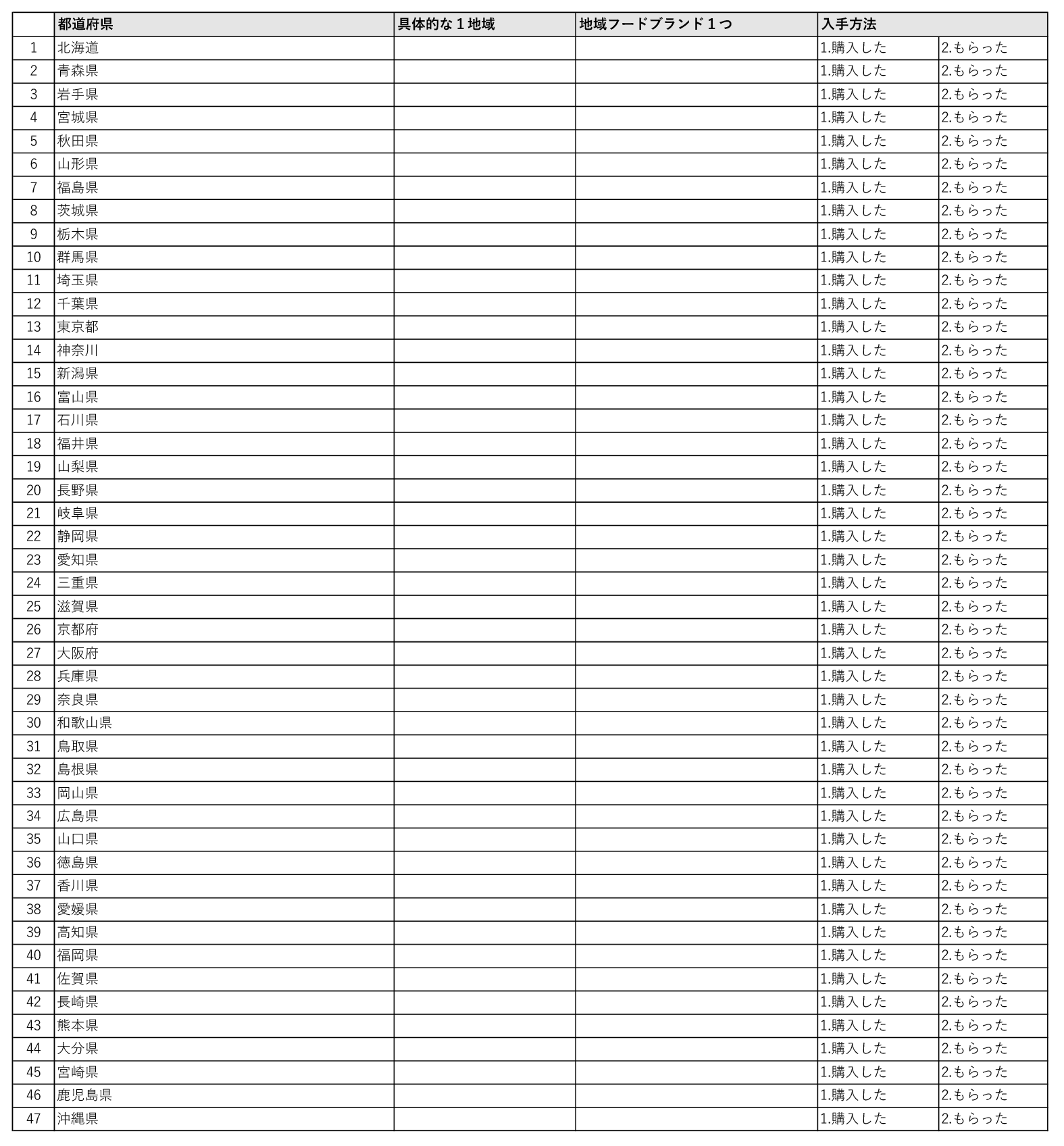
�y72�Łz
Q�@�n��t�[�h�u�����h���w���������R�ɂ��āC���Ă͂܂���̂����������������B���ꂼ��̍��ڂɂ��āC�Y������I�������P���I�т��������B
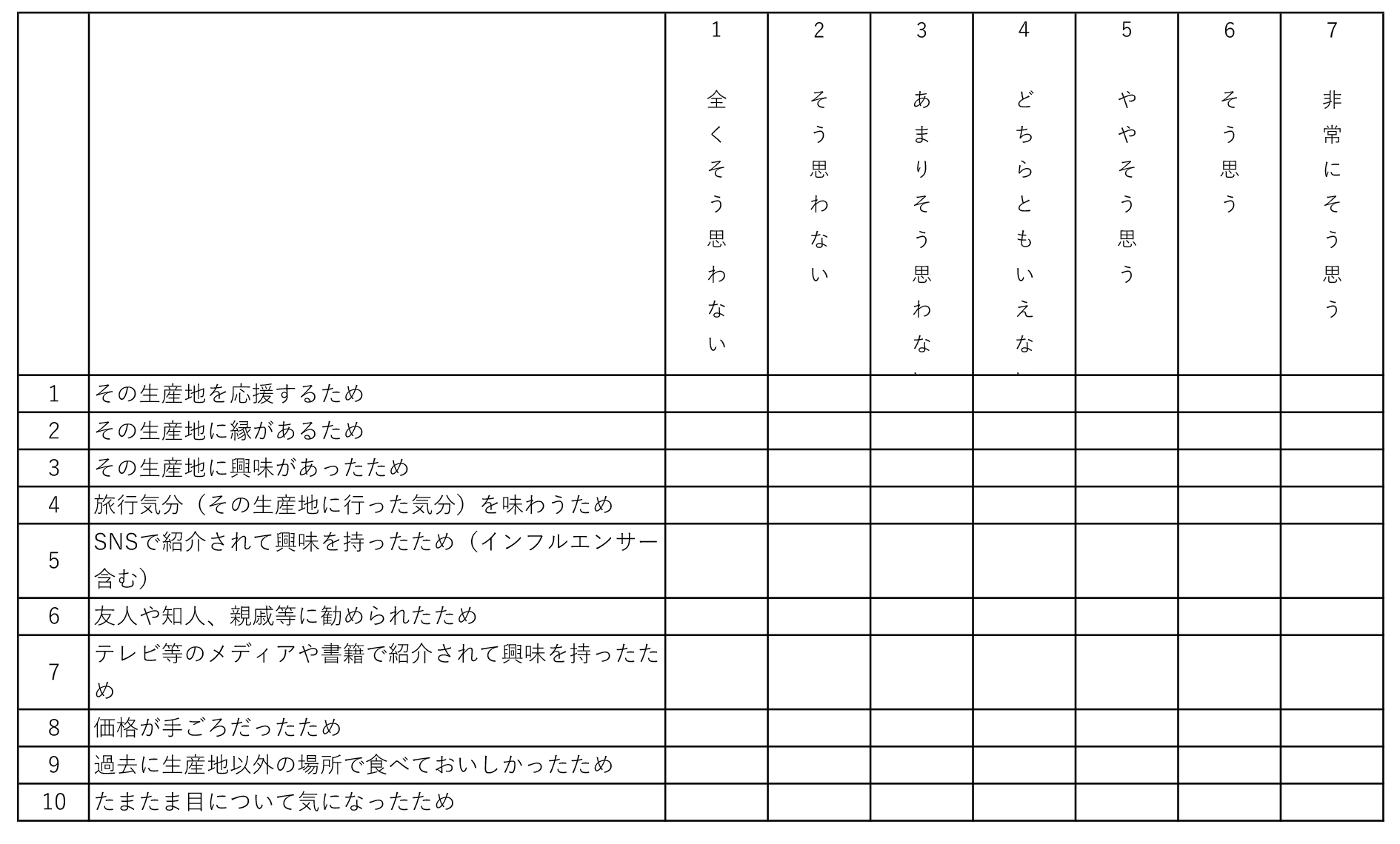
Q�@�n��t�[�h�u�����h���i�H��ɂ����C���Ă͂܂���̂����������������B���ꂼ��̍��ڂɂ��āC�Y������I�������P���I�т��������B
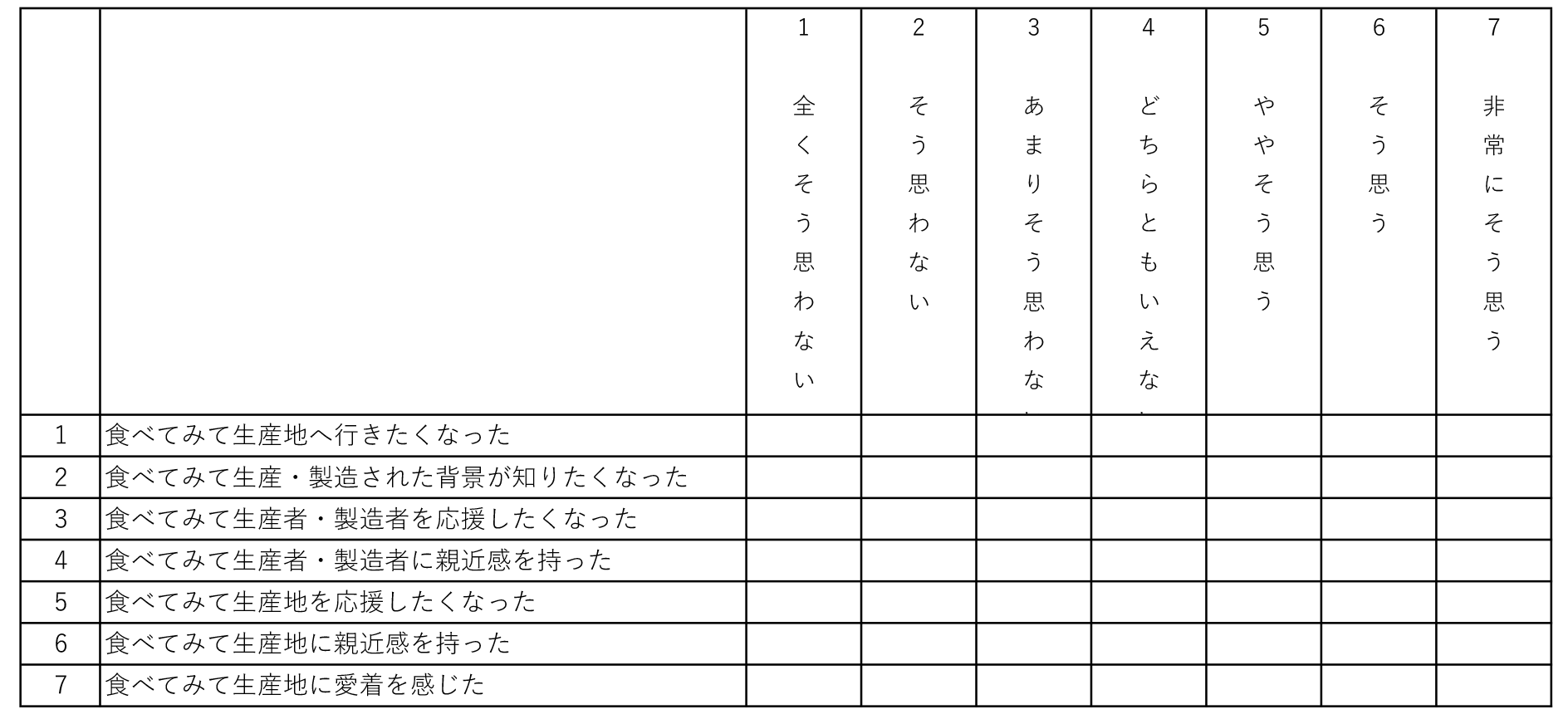
Q�@���Ȃ����w���̒n��x��K�₷��܂łɒn��t�[�h�u�����h������i�H�����������������������B
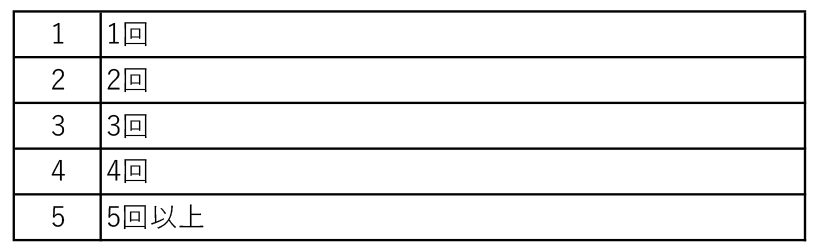
���u���L���Ƃ��ẴR�����Y�ƂȂ�n���̉��C���[�W�i�e���g�[���I�j�v�Ɓu���Y�n��ւ̊S�v�Ɋւ���ݖ�i�P��j
Q�@�i�H�O�Ƌi�H��Łw���̒n��x�Ɋւ��邠�Ȃ��̍l���ɂ��āC���Ă͂܂���̂����������������B���ꂼ��̍��ڂɂ����C�Y������I�������P���I�т��������B
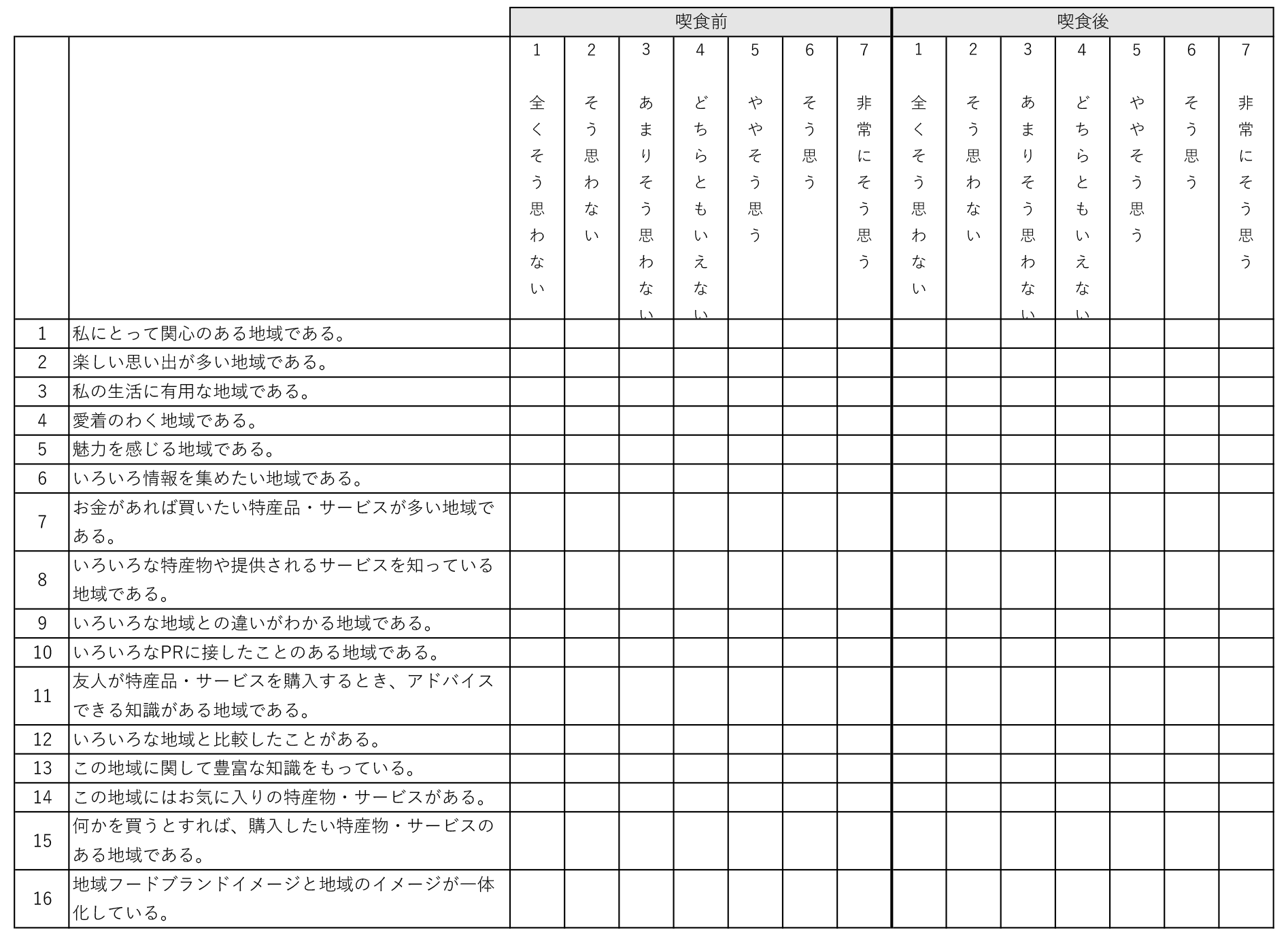
���u�n��t�[�h�u�����h�̃C���[�W�C�u�����h�R�~�b�g�����g�v�Ɋւ���ݖ�i�P��j
Q�@�w�n��t�[�h�u�����h�x�Ɋւ��邠�Ȃ��̍l���ɂ��āC���Ă͂܂���̂����������������B���ꂼ��̍��ڂɂ��āC�Y������I�������P���I�т��������B
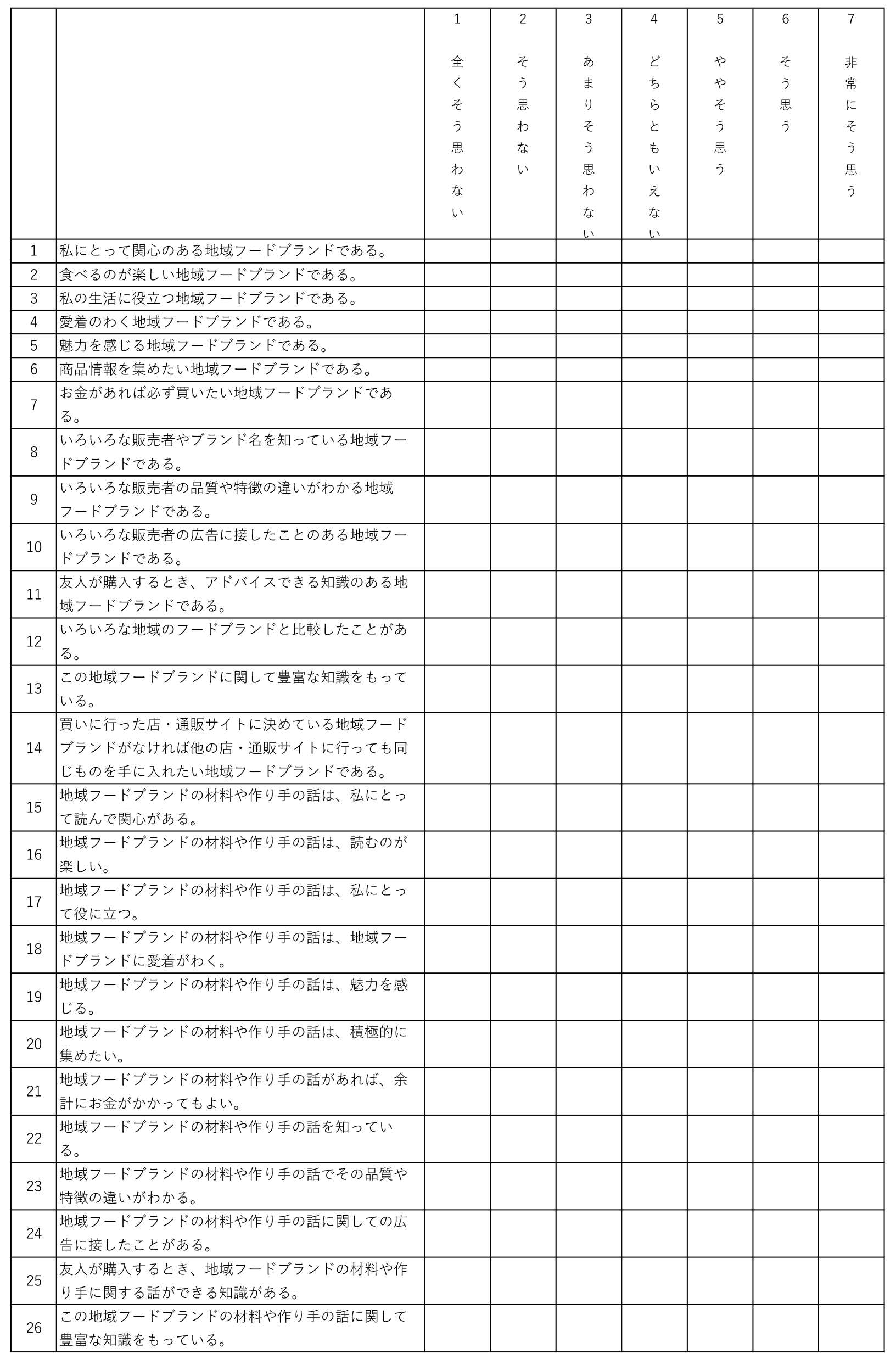
���u�i�H�҂̃f���O���t�B�b�N�E�T�C�R�O���t�B�b�N�v���v�Ɋւ���ݖ�i�S��j
Q�@���Ȃ������s�ɍs���p�x�����������������B
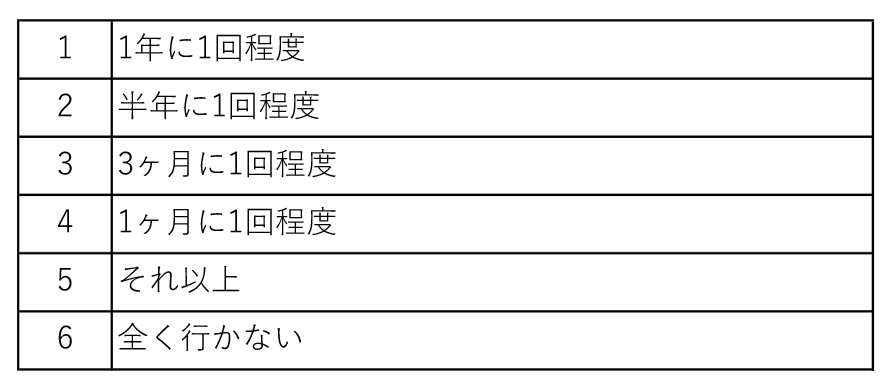
Q�@���Ȃ��̐��т̔N�Ԏ��������������������B

Q�@���Ȃ��Ɠ������Ă��邲�Ƒ��̕������ׂĂ��������������B
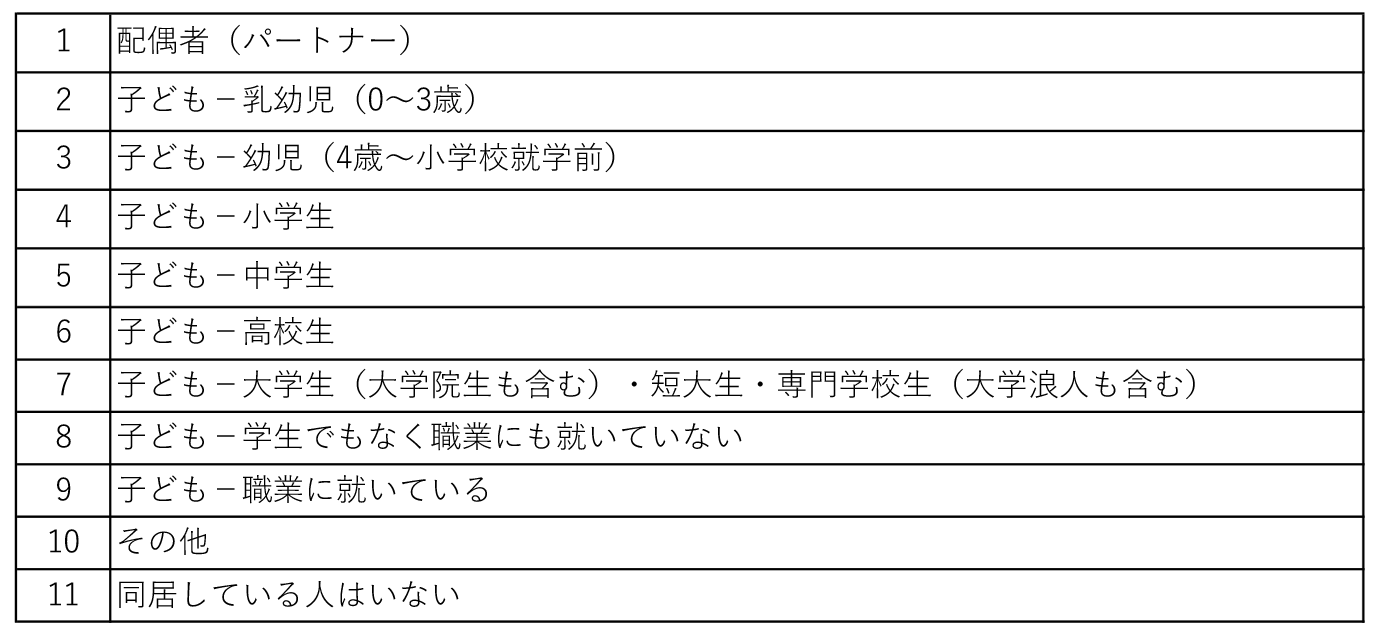
Q�@�w���s�x�Ɋւ��邠�Ȃ��̍l���ɂ��āC���Ă͂܂���̂����������������B���ꂼ��̍��ڂɂ��āC�Y������I�������P���I�т��������B
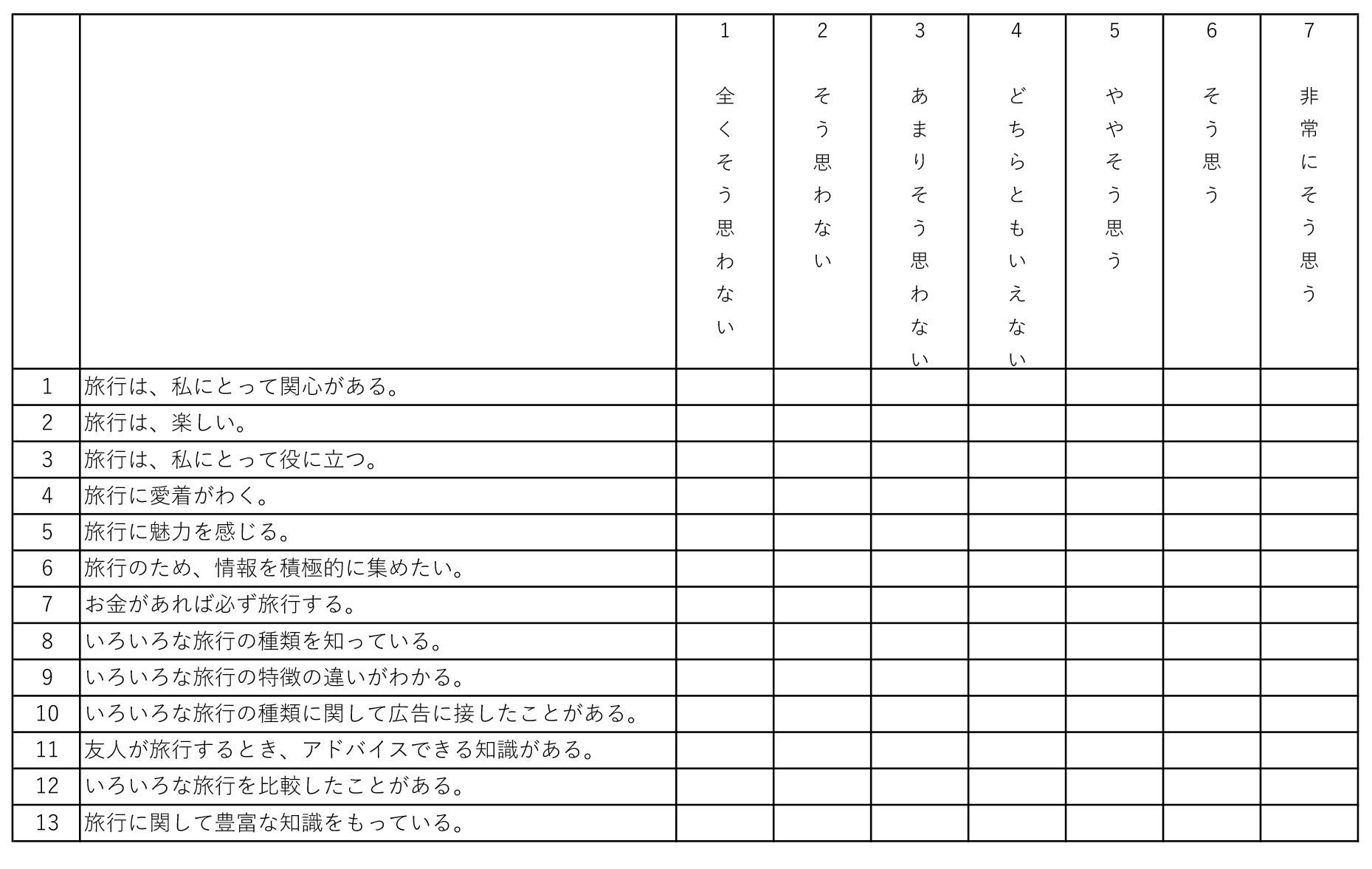
���u�F�l�̑��ݓ��C�i�H�҂̂��������ƂȂ�K��v���v�Ɓu���Y�n��ւ̖K��Ӑ}�v�Ɋւ���ݖ�i�P��j
Q�@���Ȃ����w���̒n��x��K�₵�����R�����������������B

�����͕��͖ړI�ɉ������A���P�[�g���ړ��e�ł���C���ケ���̌��ʃf�[�^�Ɋ�Â��C�_���̌�҂ɂ����đ��l�ȕ��͂��s���Ă����\��ł���B���ɔF�m�I�ȗv�f�Ɗ���I�ȗv�f�Ɋւ��Ē��ڂ��Ă��������B
�{�����͉Ȍ����Ռ���B�i19H01540�j�i��\�F��c����j�ɂ����̂ł���B�܂��O���[�v�E�C���^�r���[�̋Ɩ��ϑ����s�����i���j�g�[�N�A�C�̕��X�ɂ͏��Ȃǒ����Ă���C�ӈӂ�\�������B
1. ��c����C�|���r�q�i2020�j�w�n����Y���́w���������x������w�ӂ邳�Ə��x�̍l�@�x�C�w�K�@��w�o�όo�c������ �N��C��34��12�����Cpp.1-39
2. ��c����i2023�j�w�ؑ����q�E�w���G�M�Ғ��C�^���A�̃e���g�[���I�헪�x���]�C����c��w�w�C�^���A�������I�v�x��12���Cforthcoming
3. �ؑ��E�w���i2022�j�w�C�^���A�̃e���g�[���I�헪�x�������[
4. ���ѓN�i2016�j�w�n��u�����f�B���O�̘_���x�C�L��t
5. �d��abic project�ҁ@�a�c�[�ǐl�C���썲�D�C���R���Ìb�C������M�C��эG�ے��i2009�j�w�n��u�����h�}�l�W�����g�x�L��t
6. ��������i2022�j�u�H�i�̍w���Ƃ��̎Y�n�ւ̊ό��Ƃ̊W�Ɋւ��錤���v�C�w���ʏ��xN0.557�C�V���Cpp.36-37�D
7. ���oMJ�C2010�N�X��27�����C�}�[�P�e�B���O�����\�q�[�~