����́u���{�I�o�c�v�_�i10�j
1.1�@�A�N�e�B�r�X�g�́u���`�̖����v��
���o�ϘA����ȂǑS���̎��̌o�ϒc�̂�11���C����Ƃ̍s���K�́u�R�[�|���[�g�K�o�i���X�E�R�[�h�i��Ɠ����w�j�j�v�̑啝�ȉ��������߂��A���Ŕ��\�����B��{�I�ȍl�������C���厑�{��`����C�ڋq��]�ƈ��C�����Ƃ��������l�ȗ��Q�W�҂d����u�}���`�X�e�[�N�z���_�[���{��`�v�֓]������悤���߂��B
�ł́C�Z���Ŋ���ɕ�o�c�ł͂Ȃ��C�����������������o�c�𑣂����Ƃ��d���B�܂��C�o�c�̎���f���āC������̂R���̂P�ȏ���ЊO������ɂ��郋�[�����u�ڈ��v�Ƃ��ď_�����������悤���߂��B
�o�A��������C�k�C���⒆���C�����C��B�Ȃǂ̂U�n��̌o�ϒc�̂��^�������B����C�A���Ő��{�E�^�}�C�����،�������Ȃǂɗv�]����B
����͒����V��2023�N�X��12���̒����ɍڂ����L���ł���B�����ł̃^�C�g����
��Ɠ����u������v��NO
�Ƃ������̂ŁC����Ƃ���
�u���l�ȗ��Q�W�҂̑��d���v�o�A�Ȃǒ�
�Ƃ������͂����Ă���B
���łɌo�ϊE�ł͑傫���b��ɂȂ��Ă���e�[�}�ł��邪�C���̂Ƃ���u�A�N�e�B�r�X�g�v�ƌĂ��l�X�̊������傢�ɒ��ڂ���Ă���B�����Ă���́C�ނ炪�u����������v�ȂǂƂ����u���v�ō̂�グ���Ă��܂��Ă��邱�Ƃɂ��N�����Ă���ƍl����o�c�w�҂����Ȃ��Ȃ��̂ł���B���Ȃ킿�C
�]���̓��{��Ƃ̊���́C�قƂ�ǂ����呍��ɂ͏o�Ȃ����C����ɏo�Ȃ��Ă��o�c�������Ă��ꂽ�ĂɁu�V�����V�����v�Ǝ^�����邾���ŁC����̓Ǝ��̈ӌ��͎����Ă��Ȃ��C���邢�͎����Ă��Ă��J���Ȃ�����
�Ƃ����ӌ����悭�咣����Ă������Ƃɂ����B
�������C���̂悤�ȃA�N�e�B�r�X�g�Ƃ����l�����̏o���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��낤���B���ׂĂ���ʓI�ɏq�ׂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ����C�����̏ꍇ�C���{�I�o�c�Ƃ͈قȂ锭�z�ɂ��C�O����̗��v�l�������߂铊���Ƃ̏W�c�C�ƌ�����̂ł͂Ȃ����B�����Ă��̂悤�Ȑl�����̊����ڕW���C�^�[�Q�b�g��Ƃɂǂ̂悤�ȃ����b�g�������炷�̂��낤���B���đO�Ƃ��Ĕނ�́u���y272�Łz �Ɖ��l����v���邢�́u����̕x�̑����v��搂��Ă��邱�Ƃ��������C�����ł́u��Ɖ��l�v�̊T�O�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��B�A�����J�ɓT�^�I�ȁC���傾���̕x�̌������{��Ƃɖڎw������̂́C�͂����Đ��������낤���B���Ȃ킿���{�ł́u��Ɖ��l�v�ƌ������ꍇ�C���傾���ł͂Ȃ��]�ƈ����͂��߂Ƃ���l�X�ȃX�e�[�N�z���_�[�̕x�C���̍��v��傫�����悤�Ƃ���̂����{�I�o�c�̏d�v�ȃR���|�[�l���g�ł���C����̃����b�g��ނ�͗������Ă��邾�낤���C���Ă��Ȃ��Ɣ��f����邱�Ƃ������̂ł͂Ȃ����B
�ȑO����Ɋւ��āu�n�Q�^�J����v�Ƃ����T�O���L�܂������Ƃ�����B����i2021�j�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�A�N�e�B�r�X�g�̎p�����ς���Ă��Ă���B���{�ɂ�����]���̃A�N�e�B�r�X�g�̃C���[�W�́u�U���I�v�B�Z���Ԃō����^�p�������グ�悤�Ɠ������Ƃɑ��đ啝�ȑ��z�C���Њ������Ȃǂ̊���Ҍ���C���Ɣ��p�Ƃ�������K�͂ȃ��X�g����v���B���̂��߁C�u�n�Q�^�J�v�ȂǂƏ̂���邱�Ƃ��������B
�Ƃ��낪�C�ŋ߂́u�A�N�e�B�r�X�g����ƂƁg�E�B���E�E�B���h�̊W��ڎw���X�������܂������߁C��ʊ���Ȃǂ̎^�������₷���Ȃ����Ƃ���B�����������������瓊�����Ƃ̊����蔲���Ă��܂��̂ł͂Ȃ��C�������̃X�^���X�Ōo�c�ɎQ�悵���v�\����K�o�i���X�̕ϊv�Ȃǂɒ��͂���A�N�e�B�r�X�g�����Ȃ��Ȃ��B
���Ƃ��ƃn�Q�^�J�t�@���h�Ƃ́C�r��������n�Q�^�J�̃C���[�W���痈�����̂ŁC�j�]�����i���邢�͔j�]���O�́j��Ƃ����l�Ŕ����Č���������ɔ��p���铊���t�@���h���w���Ă����B�������ŋ߂́C�l�K�e�B�u�ȓ����s�������t�@���h���n�Q�^�J�t�@���h�ƌĂԂ悤�ɂȂ����Ƃ����B�}�X���f�B�A�̕��͂��߂ƂȂ�C��ʓI�ȃn�Q�^�J�t�@���h�̃C���[�W�́C�����������C��Ђ�H�����ɂ��Ă���C�@�������Ȃ��C�y�����Ėׂ��Ă���C�O���n�ł��邱�Ƃ������C�Ȃǂ��������邱�Ƃ������B���������ۂɂ́C�����n�Q�^�J�Ȃ̂��H�Ƃ������m�Ȓ�`�͂Ȃ��Ƃ����B�R���i2007�j�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�n�Q�^�J�t�@���h�̐��̂Ƃ͉����낤�B�[�I�ɒ�`����C�u���̗��Q�W�ҁi�Ј��C�o�c�ҁC����Ȃǁj�̋]���̏�ɁC����̗��v��n��t�@���h�v�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����B
����i2021�j�ł̓A�N�e�B�r�X�g�ƃn�Q�^�J���傪���`�Ɉ����Ă���C����͂�����Ƌ������C����ɂ����Ă͂��̂悤�ȉ��߂͓T�^�I�Ƃ͌����Ȃ����낤�Ǝv���B�����C�A�N�e�B�r�X�g�̒��ɂ͂��̂悤�Ȑl���������邩������Ȃ��B�����ŁC�����ł̓n�Q�^�J����I�A�N�e�B�r�X�g���@�A�N�e�B�r�X�gA�C��n�Q�^�J����I�A�N�e�B�r�X�g���A�A�N�e�B�r�X�gB�C�Ɖ��ɖ��t���Ă������ƂƂ���B��҂́C�����ɂ���ẮC����u���`�̖����v�𖼏���Ă��邩������Ȃ��B���̐^�U�́C�Ƃ肠�����͂킩��Ȃ��B
�����āC����͑����̃P�[�X�ł�������Ă����肾���C�]���̂悤�ȁu���{�I�ȁv����́u����Ɂv�V�����o�����Ă��銔�傪�K���������ȏ��I�ɗǂ��Ӑ}���������ҁi�A�N�e�B�r�X�gB�j�ł���ۏ͂Ȃ��B���̓_�ɂ��ẮC�ȉ��̂悤�Ȕ��ɋ��P�I�ȃP�[�X���o�����Ă���B
1.2�@�A�N�e�B�r�X�g�ւ̑R�P�[�X
����������u�n�ƉƎx�z�s�K�v�@�c���nHD�����_
�h���b�O�X�g�A���̃c���n�z�[���f�B���O�X�i�{�ЁE�D�y�s�j�ƁC�u����������v�Ƃ̍U�h���������𑝂��Ă���B�ЊO������̈�V�����߂鍁�`�̓����t�@���h�u�I�A�V�X�E�}�l�W�����g�v�ɑ��C�c���n�͂V���C�����Ăɔ�����ӌ���\�������B�h���b�O�X�g�A�ƊE�̍ĕ҂ɔ��W����\��������C�c���n�̕M������ł���C�I���̓��������ڂ���Ă���B
�I�A�V�X�͂U���Ɋ����ď��𑗂�C�u�n�ƉƎx�z�ɂ��s�K�Ȋ�Ɠ����̐��ɂȂ��Ă���v�ƌo�c�w��ᔻ�B�������n�������̋����M�Y�ٌ�m��ЊO������T�l�̑I�C��C��E�̔p�~�Ȃǂ����߂Ă���B
�c���n�̎�����͌��݂X�l�B�n�ƉƂ̒߉H����C���j�̏��В����܂ތv�S�l���{�̂��q��Бn�ƉƏo�g�҂��B�I�A�V�X�͂��̍\�}���u�l�ނ̓o�p��j��ł���v�Ɩ�莋����B
����ɑ��C�c���n�͂V���̎������Ŋ����Ăɔ�����ƂƂ��ɁC�ЊO������R�l���܂ߌ��݂̎�����̑̐����ێ����C�lj��̎ЊO������Q�l��I�C����c�Ă��W���̒莞���呍��ɏo�����Ƃ����߂��B
�c���n�̒߉H���В��͂V���C�����V���̎�ނɁu�ЊO������̑�����ւ����K�v�Ȋ�Ɠ�����̖��͂Ȃ��C�n�ƉƂ̑��݂����e�����y�ڂ��Ă��鎖�����Ȃ��v�Ɣ��_�����B
�I�A�V�X�͂T���ɒ�o������ʕۗL���Ńc���n��12.84����ۗL����劔��ɕ��サ�C��13�������C�I���Ɏ����劔��ɂȂ����B�I�A�V�X�̃Z�X�E�t�B�b�V���[�ō������ӔC�҂͂U�����C�����V���̎�ނɑ��C�u�h���b�O�X�g�A�ƊE�̓R���r�j�ƊE�̂悤�ɂR�C�S�Ђ��x�z����\�}�ɕς��v�ƌ��C�ƊE�ĕ҂Ɉӗ~���������B
�ő�̒��ڂ�1995�N�����g���Ă���M������C�I���̓������B�I�A�V�X�̓C�I���̊������ۗL���Ă���Ƃ���C�C�I���ɑ��u�c���n�Ɉ��͂�������悤�ɓ��������Ă���v�i�W�ҁj�Ƃ����B�c���n�̊��呍��͂W����{�ɎD�y�s���ŊJ�����\��B�C�I���̋c�����s�g�̍s�������ڂ����ق��C�C�I���O���[�v�̃h���b�O�X�g�A�ő��E�G���V�A�z�[���f�B���O�X�Ƃ̍ĕҘb�����シ��\�����o�Ă���B�i�ҏW�ψ��E�x�U�r�ށj
�����2023. 07. 08�t���̒����V�������̋L���ł���B�c���n�z�[���f�B���O�X�ɂ��ẮC���̒ʂ�ł���B
�c���n�z�[���f�B���O�X
1929�N�C�k�C������s�Œ߉H��t���Ƃ��đn�ƁB�S���e�n�̃h���b�O�X�g�A�����Ŕ������C�u�c���n�h���b�O�v�̂ق��C�u������̕����Y�v�u�Ǘѓ���ǁv�u�h���b�O�C���u���v�ȂǍ��N�T�����_��2589�X��W�J����B���N�T�������Z�Ŗk�C����ƂƂ��ď��߂ĂƂȂ�u���㍂�P���~�v���߂����Ă���B
�����Ă��̌�C���̂悤�ȋL�����������i2023. 08. 11�����V�������j
�����t�@���h�̊����Ă�ی��@�c���nHD����
�h���b�O�X�g�A���̃c���n�z�[���f�B���O�X�iHD�j��2023�N�W��10���C�莞���呍����D�y�s���ŊJ�����B�劔��ł��鍁�`�̓����t�@���h�u�I�A�V�X�E�}�l�W�����g�v����o�Ă����Ǝ��̖����I�C�Ȃǂ����߂銔���Ă͂��ׂĔی�����C�c���n�o�c�w���o���Ă�����В�Ă̖����I�C�c�ĂȂǂ����F���ꂽ�B
�y274�Łz����ɂ�131�l�̊���炪�o�ȁB�Q���҂ɂ��ƁC���傩��o��22�̎���̓I�A�V�X�ɂ����̂��ڗ������Ƃ����B����́C�K�o�i���X������̑I�C�ߒ��̓������ȂǂɏW�������B�u�����Ă��o���̂ŁC�ǂ�ȋc�_�ɂȂ�̂����������Ă���Ă����v�Ƒ����^��������������B
�����ɉ�����c���nHD�̒߉H���В��́u���������헪�I��M&A�i��Ƃ̍����E�����j�𐄐i���C����Ȃ鐬���������������v�ƌ�����B
���̂悤�ȃA�N�e�B�r�X�g�̊����́C�Z�u�����A�C�E�z�[���f�B���O�X��2023�N�T���ɍs�����咣�ɖ��炩�Ȃ悤�ɁC�����ł̓����t�@���h�̃A�����J�E�o�����[�A�N�g�L���s�^�����S��L����̂́C�����ȉ��l�n�����]���ɂ�����ł̒Z���I�Ȋ����㏸�����ŁC�ŏI�I�ɂ͑��̊���̗��v�ɔ�����C�Ƃ����ʂ������Ǝv����B�����ăZ�u�����i�߂�\�����v�ւ̗�������������ȂǂɌĂт����Ă���B
1.2.2�@�Z�u�����A�C�E�z�[���f�B���O�X
�Z�u�����A�C�E�z�[���f�B���O�X�̎�������2023. 5. 12�C�ċc�����s�g������Ђ�ISS�i�C���X�e�B�e���[�V���i���E�V�F�A�z���_�[�E�T�[�r�V�[�Y�j�̌����ɔ��_���鐺���������\�����B
ISS�͂X���C�ē����t�@���h�̃o�����[�A�N�g�E�L���s�^������Ă����S�l�̎��������S���I�C����悤�C�Z�u���̊���ɐ��������B�������Z�u���̎������́CISS�̐������e�Ƃ͌������قȂ�Ƃ��ē��Ђ����E�����������̑I�C�Ɏ^������悤�Ăт������B���������́CISS�̃��|�[�g���e�̓Z�u���̃K�o�i���X�̐��̕ϊv�Ȃǂ����Ă���Ă��Ȃ��Ǝw�E�����B���̏�ŁC�Z�u�����E���҂ɑ��锽�ΐ����́u����ɑ���s���S�ȗ������ߋ��̎��тɏd����u�����F���Ɋ�Â������́v�ŁC�����̕����Ńo�����[�A�N�g�̈���I�Ȏ咣���J��Ԃ��Ă���悤�Ɍ�����C�Ƃ����B�m�����@12���@���C�^�[�n
�������čs��ꂽ���呍��̌��ʂ͎��̒ʂ�ł���3�j�B
���ڂ��ꂽ�u����������v�Ƃ̑Ό��͂�������Ɩ�������B�T��25���ɊJ���ꂽ�Z�u�����A�C�E�z�[���f�B���O�X�̊��呍��́C�����t�@���h����̊����Ă�ی��C��㗲��В���̍ĔC�����܂����B����Ɍ����Ă͂R���ɃA�����J�̓����t�@���h�C�o�����[�A�N�g�E�L���s�^�����C���В���S�l�̎�����̑ޔC�������I�ɋ��߂銔���Ă��s���Ă����B�Z�u�����A�C�̎������͂S�����{�C�����Ăɑ��锽�𐳎��ɕ\���B���������o�����[�A�N�g�̊����ۗL�䗦��4.4���ɉ߂��Ȃ��B�����́u�i���̐��Ɂj���낢����͂��邯�ǁC�����͂����Ă��ō��v���������o���قǐ�D�������犔���Ă͒ʂ�Ȃ����낤�v�i�Z�u�����A�C�O���[�v�����j�Ƃ������y�ϓI�Ȍ��������������B
�������T���ɓ���A�����J�̑��c�����s�g������ЁC�C���X�e�B�e���[�V���i���E�V�F�A�z���_�[�E�T�[�r�V�[�Y�iISS�j�ƃO���X���C�X���C���В����В�Ă̎����I�C�Ăɂ��y275�Łz ����Ĕ��𐄏�����ƁC�y�Ϙ_����ށB���f�B�A��ʂ��Č݂��̎咣��W�J�������ȂǁC�U�h�������Ă����B
JR�l�J�w�߂��̃Z�u�����A�C�{�ЂŌߑO10������n�܂������呍��ɂ́C��N���187�l����436�l�̊��傪�Q�������B�`����2023�N�Q�����̋ƐъT�v�������ꂽ��C�c���߂���В�����В�ĂƊ����Ă̊T�v��W�X�Ɛ����B�u��Ă��s���Ă��銔��l�C�������Ȃ����܂����v�ƃo�����[�A�N�g���ɔ����̋@���^�������̂́C���̏�Ŏ����������̂͂��Ȃ������B
�������^�����ł́C��q����S�ݓX�̂������E�����̔��p�ɂ��āC���В����u���̒i�K�Ńv���W�F�N�g�𒆎~����l���͂Ȃ��v�Ɖ��߂ĕ\�������ȊO�ɖڗ��������e�͂Ȃ������B�S10�̎���̂����̂T�́u���h�v�Ƃ�������C�Z�u���|�C���u�����^�c����I�[�i�[����̂��́B���N�Q�����Ă���Ƃ�������́C�u��N�ƕς��Ȃ����}���������v�ƌ�����B
�ߌ�P���߂��ɍ̌�����C�����Ă͔ی��C��В�Ă������ꂽ�B��В�Ă̂����C���В��̍ĔC�ɂ��Ă̎^������76.36���������B���͎��O�̕[�ǂ݂ł́C�^�����͂����ƒႭ�Ȃ�Ƃ̌����Ă��������BISS�ƃO���X���C�X�Ƃ����Q�̏����@�ւ���В�Ăɔ������ꍇ�C�O���l�����Ƃ͂��́g�����h�ɏ]�����Ƃ��ʗ�Ȃ��߂��B
�Z�u�����A�C�̊O���l����䗦�͖�33���i�Q�����_�j�B�����̈ꕔ�̋@�֓����Ƃ���В�Ăɔ�����C�^������60�����x�܂Œቺ����Ƃ̌������������B����̎^���������āC���В��͋����Ȃʼn��낵�����Ƃ��낤�B
�u���Ɏc�O�B�s�̎Z�ȃX�[�p�[���Ƃ�藣���C�����v�ȃR���r�j�ɏW���ł��邹�������̋@����Ă��܂����v�B���В��̍ĔC�ɔ��Ε[�𓊂����l����͂������B
�Ƃ����̂��C�o�����[�A�N�g�̓Z�u�����A�C�̊���ƂȂ������̐��N�C���ЂɃX�[�p�[���Ƃ�藣���C�����h���C�o�[�ł���R���r�j�Ɍo�c�������W������悤���߂Ă������炾�B����̊����Ă͂����܂Ŏ����I�C�c�Ă��������C�w�i�ɂ������̂͑c�Ƃł���C�g�[���[�J���C�����ăX�[�p�[���Ƃ����̃Z�u�����A�C�ɕK�v���ۂ��Ƃ����₢�������Ƃ�����B
�R�N�ŃX�[�p�[���Ƃ��Č��C�ƈ��В��͐錾���Ă���悤�����C�o�����[�A�N�g�̃p�[�g�i�[�C���u�E�w�C�����͑���O�ɍs��ꂽ���m�o�ς̃C���^�r���[�ɁC�u�Z�u�����A�C�͒��v���o�����тɃ��[�J���̍\�����v��i�߂�ƌ��������Ă����B�����ɖ�100�X�W�J���郈�[�J���̌��Ē����ɗ͂𒍂������܂�C���E�ɂW���X�ȏ゠�萬���̌����͂ł�����Z�u���[�C���u���ɒ��͂�����Ă��Ȃ��v�ƕs��������Ă���B
�Z�u�����A�C�����̐��Ɉڍs���ĂV�N�B���̎��Ԃ͌����ĒZ���Ȃ��B����������Ƃ̑Ό��̖��C�ĔC���ꂽ���В��͍��x�����\�����v�������ł���̂��B�^�̎�r������邱�ƂɂȂ�B
���������A�N�e�B�r�X�g�̒�Ă��������̂��ǂ����͓��R�C�����ɂ͂킩��Ȃ��B���N����C���̐��ʂ��������Ă���ł���B���ɁC���В��̎��_�����u�c�Ƃł���C�g�[���[�J������邽�߂̌��f�ł͂Ȃ��C�R���r�j�̐����ɂ́u�H�v�̋������K�v�ł���C�X�[�p�[���Ƃ��K�v�ł���v�C�Ƃ����헪�ɂ́C�ɂ킩�ɂ͌��_�͏o�Ȃ����낤�B2007�N�����舵�����n�߂��v���C�x�[�g�u�����h�iPB�j�́u�Z�u���E�v���~�A���v�́C���⍑���Z�u���|�C���u���X�܂̔���グ�̂S���̂P���߁C����PB�J���`�[���͑�����130�l�ɂ̂ڂ邪�C����77�����X�[�p�[�ȂǃR���r�j�ȊO�̎��Ɖ�Џo�g���Ƃ����B�R���r�j����舵�����i���͖�2000�A�C�e�����x�B����ɑ��ăX�[�p�[�́C�H�i�����łP��5000�A�C�e���ȏ����舵���Ă���B�����y276�Łz ���ɂ��Δ�����ڋq�̎���ɑ���m���̍L���́C���i�J���̕���[���̌���ƂȂ�Ƃ����B
���Ƃ��Έ�̑O�܂ŁC�Z�u���|�C���u���̐H�i�Ƃ����C���ɂ����T���h�E�B�b�`����̂������B�������C�����̎Љ�i�o�␢�ѐl���̌����C����Ȃǐl�����Ԃ̉e���ŁC�H�⎞�Z�j�[�Y�����܂��Ă���B2022�N�x�̗Ⓚ�H�i�̔���グ�́C�X�[�p�[�ŗⓀ�H�i���̂�������O������2009�N�x��20�{�ɂ܂ő����Ă���Ƃ����B�����Ĉ��В��̓Ɠ��̎咣���C�u�R���r�j���ǂ��L�����v���l����ƁC�J�M�������Ă���̂́u�H�v���C�Ƃ������Ƃł���B�u�H�v�͐l�����Ԃ��ω����钆�ł��s��K�͂��ꌘ���B�O���[�o���ł��C�t���b�V���t�[�h�̔���グ�\����Ƌq���Ɋւ��ẮC���̑��ւɂ���Ƃ����B
�������C�o�����[�A�N�g�����߂�C�g�[���[�J���ȂǃX�[�p�[���Ƃ̐藣���́C���В��ɂ����́u�H�v�̃��\�[�X�������Ă��܂����Ƃɓ������B�������I�ɂ̓R���r�j�̋����͂��킢�ł��܂����낤�B
���������ω��͂��ꂩ����ԈႢ�Ȃ������Ă������C����ɑΉ����邽�߂̃��\�[�X�́C�R���r�j�������q�l�́u�H�v��ʂ�m���Ă���X�[�p�[���Ƃɂ���B�����͂����l���Ă���C�ƈ��В��͔M�����B�����C�܂��ɂ��̎咣���A�N�e�B�r�X�g�ɂ͗����ł��Ȃ��i  �j�̂ł͂Ȃ����ƕM�҂�͍l���Ă��āC�ނ�ɂ͖ڑO�̑������Ƃ��������Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B���̐��ۂ͕M�҂�ɂ͂킩��Ȃ��B
�j�̂ł͂Ȃ����ƕM�҂�͍l���Ă��āC�ނ�ɂ͖ڑO�̑������Ƃ��������Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B���̐��ۂ͕M�҂�ɂ͂킩��Ȃ��B
�����ł̃o�����[�A�N�g�������ł͂Ȃ����C�����͓��Ƀ[�l�R���ƊE�œ��ʔz���⎩�Њ�������v������P�[�X�������Ă���B����͂܂��ɒ����I�Ȑ��������ڑO�̗��v��ǂ��p�����C�Ƃ����ᔻ�̍D�ΏۂɂȂ邱�ƂɂȂ�B
1.2.3�@�u�A�N�e�B�r�X�g�v�͉�������l�X��
�ł́C���̂悤�ȁu�A�N�e�B�r�X�g�v�͈�̓łȂ̂��낤���C��Ȃ̂��낤��
���̓_�ɂ��ẮC�ڍׂȌ��y������̂ŁC�����ǂ��c�_�E�������Ă݂���4�j�B
�����ł́C�u�A�N�e�B�r�X�g�͓ł��v�Ƃ����^�C�g���ŁC�u����̌����v�ŕϊv�v���C�Ƃ������肪���Ă���B�ȉ��C���ɒǂ��Ă����B
�A�N�e�B�r�X�g�����̂��铊���t�@���h�u�X�g���e�W�b�N�L���s�^���v�iSC�j��\�̊ۖ؋����́C����܂łɂR��C����ɂ������������Ƃ�����B
�u���Ȃ��͂����C�В�������߂ɂȂ����ق����ǂ���Ȃ��̂��v
������C������̎В��Ə��߂đΖʂ������C���̊��傪���銔�呍��ł��B���v���C���s��ɏ�ꂷ����{�،����Z���C���̂ЂƂ��B���̖Ƌ��Ɋ�Â��C�،���Ђɂ����⊔��݂����Ƃ�Ɛ�I�Ɏ肪����B
�ۖ؎�����莋�����̂͂��̉�Ђ̎В���70�N�ȏ�ɂ킽��C10�㑱���ē��{��s�̏o�g�҂����߂Ă��邱�Ƃ��B�L�єY�ދƐт������C�u�V���肠�肫�̕s�����Ȑl���őI�ꂽ�o��w�ł́C��Ɖ��l����ɐ^���Ɏ��g�߂Ă��Ȃ�����ł͂Ȃ����v�Ǝw�E�����B
���{�،����Z�́u���͂Ȃ��v�Ɣ��������B
SC�́C�V����̎��Ԃ��O�҂ٌ̕�m�炪���ׂ�悤���߂Ă���B���̓~�C���̒������K�y277�Łz �v���ǂ����₤�Վ����呍��̊J�Â��C��Ж@��̊���̟D�����g���Đ��������B�Q���ɂ��J����錩�ʂ����B
�ۖ؎��́u����ɂ͖��R�ƌo�c�����Ă���В���ウ�錠�����C��O�҂̒��������߂錠��������B���傪���̗͂��ő���g�����ƂŁC��Ђ��ς��C�Љ���悭�Ȃ�Ƃ����̂���X�̑�`�����ł���C�����J�~��20�N�O�ɖڎw�����p�ł�����v�Ƙb���B
�u�����J�~�v�Ƃ͋�����t�@���h��\�̑��㐢�����̂��Ƃ��B
�Q�l�͓咆���i�_�ˎs�j�̓������ŁC�ۖ؎����쑺�،����瑺�㎁�������ʏ��Y�Əȁi���o�ώY�Əȁj�ɏo������20��㔼�ɍĉ�B��10�N���1999�N�ɂ�����l��U���ĂR�l�ő���t�@���h�𗧂��グ���B�ۖ؎��͕���\�ɂȂ����B
����t�@���h�͊�Ƃ����ߍ���ł���]�莑�Y�ɖڂ����C�z���⎩�Њ������Ȃǂ́u���������v�Ɏg�����Ƃ���Ƃɔ������B
�ʎY��OB���d�|����U�h�͒��ڂ̓I�ƂȂ����B����擯�m�⓯�������n�Ŋ������������C�݂��̌o�c�ɂ͌����o���Ȃ��W�����{��Ƃł͕��ʂ������B
�������咣�����剓����I���ɔ���p�ɁC�o���҂͓G��������������������B�������킩������Ƃ͊������������҂��������}�������B����ȗ��v���������ƂŐ��Ԃ���u���̖S�ҁv�Ƃ������ᔻ�����т��B
�������㎁�̓j�b�|��������������C���T�C�_�[��������őߕ߁C�L�ߔ�������B06�N�C����t�@���h�͉��U�����B
�u����t�@���h�v�Ƃ����ƈ�ʂɂ͂قƂ�ǁu���̌����v�̂悤�Ȋ�����������Ă���ƕM�҂�͍l���Ă���B������u�n�Q�^�J�t�@���h�v�̓T�^�Ƃ���Ă��āC�u���`�̖����v�ƍl���Ă���l������悤�ɂ͎v���Ȃ��B�������C�ŋ߂͂Ȃɂ������u�ߑւ��v��������悤���B
���������ς�����̂́C���{�W�O�������o�ϐ���A�x�m�~�N�X�őł��o�����u��R�̖�v�������B�C�O���瓊���}�l�[���Ăэ������ƁC��̎w�j���ł����B14�N�́u���{�ŃX�`�����[�h�V�b�v�E�R�[�h�v�i�u�ӔC����@�֓����Ɓv�̏������j�ƁC15�N�́u�R�[�|���[�g�K�o�i���X�E�R�[�h�v���B
�������̍����o�c�̐�����J���C����̌����̊m�ۂ���Ƃɋ��߁C����ł���@�֓����Ƃɂ͊�Ƃ̂��������p�����Ď����Ă����ӔC������ƒ�߂��B�����^�̓��{��ƂƊ���́u�Ȃ��Ȃ��v�ȊW���������C�����Ɗ���ɂ��K�o�i���X���d�v������u���Č^�v�ւ̕ω��𑣂����̂������B
��̃R�[�h�ɖ@�I�ȋ����͂͂Ȃ����C�������߂�w�j�ɑ��C�����錾�����Ƃ͈�C�ɍL�������B�u�R�[�h�ɂ�����Ȃ���Ƃ́w�K�o�i���X�����x�Ǝ咣�ł��������^���C���ʓI�ɃA�N�e�B�r�X�g�Ɋ�Ƃ����������n�����ƂɂȂ����v�B��Ɠ����ɏڂ�����������ٌ�y�͂����݂�B
�A�N�e�B�r�X�g�Ή��x���Ɩ��̍����ő��C�A�C�E�A�[���W���p���ɂ��ƁC�A�N�e�B�r�X�g�ɂ�銔���Ă͓�́u�R�[�h�v����������ォ��}���B22�N�͖�175���ʼnߋ��ő��������B��Ă̒��g���C�����^�̏�]�������ȂǂɎ����Łu�K�o�i���X�v�������Ă���C�R��������y278�Łz ��B
�ۖ؎������{�،����Z�́u�V����v���w�E���鎑���ł��C���������l�����܂���ʂ��Ђ̏��u�K�o�i���X�����Ă���v�Ɣᔻ�����B����������Ăɑ���Ŏ^�ۂ𓊂���@�֓����Ƃ̓X�`�����[�h�V�b�v�E�R�[�h�ɂ��C�^�ۂ̌��ʂ┻�f������\���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ����B
���{�،����Z�́u�V����v�ᔻ�̌��ɂ��ẮC�����铊���Ƃ͌��݂̓��{�ł͑����͂Ȃ��̂�������Ȃ��B�����Ă���́C�������Ɋ���̕x�����ł͂Ȃ���Ɖ��l�S�̂ɂƂ��ẮC���đO�Ƃ��Ă͍D�܂����Ȃ����̂ł��邩������Ȃ�����ł���B
���{�����ی��̔��c�S��E�����ے��́u�A�N�e�B�r�X�g����X���ǂ��܂łȂ�^���ł��邩���ώ@���C���͈͓̔����ꂷ��ł̒�Ă����Ă���悤�ɂȂ��Ă�����ۂ��v�Ɩ������B
�c�����d�q�s�g���Ƃ��肪����ICJ�̒��ׂł�22�N�U������ɏo���ꂽ�����Ăւ̎^���䗦�́C�����@�֓����Ƃ�6.7���C�C�O�@�֓����Ƃ�24.5���B11�N�U������̂��ꂼ��2.1���C8.3�����炢������R�{�قǂɑ����Ă���B
��̃R�[�h�ŁC�A�N�e�B�r�X�g�͊�Ƃ�˂��V���ȕ���āC����ȋc�����������@�֓����Ƃ��������ɂ�����B
���̓������m��I�ɂƂ炦��̂��C����Ή��̏����Ɩ����肪���鋍���M�ٌ�m���B�u�������I�Ȏ��_����̗ǎ��Ȓ�ĂɁC�@�֓����Ƃ͔��ł��Ȃ��Ȃ����B�A�N�e�B�r�X�g������������Ă��o���C�^�����W�߁C��Ƃ�ς��Ă�����C��������{�o�ς��~�����݂ɂ��Ȃ蓾��v
�ʂ̌���������B�����ٌ�m�́u�A�N�e�B�r�X�g�̎����̏o����ɒZ���̃��^�[�������߂铊���Ƃ������Ƃ����\�}�͐̂���ς��Ȃ��v�Ǝw�E�B�u�������I������ڎw����ƂƁC�Z���u���̃A�N�e�B�r�X�g�͊�{�I�ɂ͑�����Ȃ��v�Ƃ݂�B
�A�N�e�B�r�X�g�̒�Ăɂ́C�����I�Ȏ���Ɋ�Â��Ă���Ƃ��鐬���헪���ڗ��B�����C�u��Ƃ̐����ɂȂ��邩�ۂ��́C�o�c�w�Ɗ��傪���ɂ߂�K�v������v�ƁC�A�C�E�A�[���W���p���̖k���Y��Y�В��͌����B�u���̋��ڂ͂��܁C�{���ɂ킩��ɂ����Ȃ��Ă���v
�������Č��Ă���ƁC���n�Q�^�J�t�@���h�͉䂪���̎���ɍ��킹�đΉ��E�K���������Ă��Ă����Ƃ��������ł���B�����C�J��Ԃ��ɂȂ邪�C���{�I�o�c�̗D�ꂽ�ʂ𐳂����������C������������ł̈ӎv����𑣐i���Ă����ł��낤���B
���̓_�ɂ��ẮCTOB�ɑ��ăz���C�g�i�C�g�Ƃ��đI�����ƃO���[�v�Ƃ̃g���u���Ɋ������܂ꂽ�s���Y��Ѓ��j�]�z�[���f�B���O�̎��s�Ⴊ��荹������Ă���B���Ђ�HIS�ɂ��G�ΓI�����ɑ��邽�߂ɁC�]�ƈ��ƃA�����J�����t�@���h�̃��[���X�^�[�������ݗ������u�`�g�Z�A�����v�ɂ��TOB�Ŋ��������J�������B�����̓��[���X�^�[���炨�悻��牭�~�B�B���������̕ԍς̂��߂Ɏ���̎��Y�p������C�D�ǎ��Y�̔��p�ɂ�胍�[���X�^�[�ɂ͕ԍς͍ς��̂́C���̎ؓ����̕ԍς�Џ��҂̂��߂ɍX�Ɏ��Y���p�ɔ���ꂽ���ʁC����J������R�N���2023�N�S���ɖ����Đ��@�̓K�p�ƂȂ����̂ł���BM&A�ɂ�����C�����ő��d���ׂ������Ƃ��āC��Ɖ��l�̌���ƈ�ʊ��嗘�v�̊m�ۂ��C2019�N�U���Ɍo�Y�Ȃ����\�����u������M&A�݂̍���Ɋւ���w�j�v�ł͋����Ă������C���j�]�����y279�Łz �����ł́u��Ɖ��l�v�ɂ͏]�ƈ��̌ٗp�⓭���������܂܂��Ɖ��߂��Ă����̂ł���B���������ۂɂ̓��[���X�^�[���TOB���i�͑啝�ɍ������Ă��܂��i2600���~�Ƃ�������j�C�����J��ɋ��������ʁC���j�]�͌o�c�j�]�����̂ł������B�����ł͊�Ɖ��l�Ƃ����T�O�̒��ɁC���ʂƂ��ă��[���X�^�[���Ƃ��Ă̓��j�]�����R�ƍl���Ă����u�]�ƈ��̌ٗp�⓭�������v�Ƃ������{�I�o�c�̌���ł�����͓̂����Ă��Ȃ��������ƂɂȂ�B
���̂悤�Ɍ��Ă���ƁC��͂�A�N�e�B�r�X�g�Ƃ����l�����́C����̗��v�u����сv�]�ƈ��̗��v�C�Ƃ�����Ɖ��l�̊T�O�C����͂��Ȃ킿���{�I�o�c�̌��_�ł��邪�C����͌����Ă��Ȃ�  �C�ƍl������Ȃ��̂ł͂Ȃ����C�Ƃ������_�i��ł��������C�Ǝv����̂ł���B�O�q�̇@�A�N�e�B�r�X�gA���C�A�A�N�e�B�r�X�gB���C�Ƃ������ƂɂȂ�B
�C�ƍl������Ȃ��̂ł͂Ȃ����C�Ƃ������_�i��ł��������C�Ǝv����̂ł���B�O�q�̇@�A�N�e�B�r�X�gA���C�A�A�N�e�B�r�X�gB���C�Ƃ������ƂɂȂ�B
�����Ȃ�ƁC�u�A�N�e�B�r�X�g�v�]�X�ȑO�ɁC�o�c�҂́C�ǂ�Ȏ��_�ʼn������������Ƃ�����Ƃ��Č}����ׂ����C�Ƃ������Ƃ��l����ׂ����C�Ƃ������ƂɂȂ�B�I��������IR�S���E��_���́u��Ƃ͊����I�ԓw�͂͂ł���v�Ɛ����������ł��邪�C�����I�Ȏ��_�Ŋ�Ƃ�]�����C�o�c�ւ̏��������Ă����悤�ȃv���̓����ƂɊ���ɂȂ��Ă��炤�C���̂��߂ɂ́u�^�[�Q�e�B���O�v�ƌĂ����@�C���Ȃ킿�A�v���[�`���ׂ����������Ƃ��I�сC�ʂ��邢�͏��O���[�v�̃~�[�e�B���O���J�Â���C�Ƃ������Ƃł���B���Ȃ킿�C�O�q�́u�ǂ�Ȏ��_�ʼn������������Ƃ�����Ƃ��Č}����ׂ����C�Ƃ������Ƃ��l����v�C����͐헪�I�ȓ����ƌ����L��iIR�j�ɂ�����B��ʓI�Șb�Ƃ��Ă͎��Ђ̊���\���ɏ�ɋC��z��K�v�͂��邪�C����Ɂu�]�܂�������v�ւ̃A�v���[�`���O���K�C�Ƃ������ƂɂȂ�B
�����Ă����ł�͂�@�A�N�e�B�r�X�gA�C���A�A�N�e�B�r�X�gB���̐��m�ȔF���̏d�v���C���Ȃ킿�C�b�Ƃ��Ă͇@�ɋC��t���C�A�Ƃ̗L���ȃR�~���j�P�[�V������}��C�Ƃ������Ƃ���Ɏ��݂邱�Ƃł��낤�B
�Q�D�����p���_�̎��_�Ɠ��{�I�o�c�̕]��
1980�N��ɏ̎^���ꂽ���{�I�o�c�ɑ���]���́C90�N�ォ��2000�N���ʂ��Ă̓��{�o�ς̒�������o�āC�傫���ς�����B���Ă͓��{��Ƃ̋��݂Ƃ���Ă���������������݂ƕ]�������悤�ɂȂ����B����܂ł̂����̈�A�̘_�l�œ��{�I�o�c�̓�������_�ɂ��Č������Ă������C�����i2010�j�́C�}�\�P�̂悤��80�N��̐����v����90�N��̎��s�v������Ă���B
�y280�Łz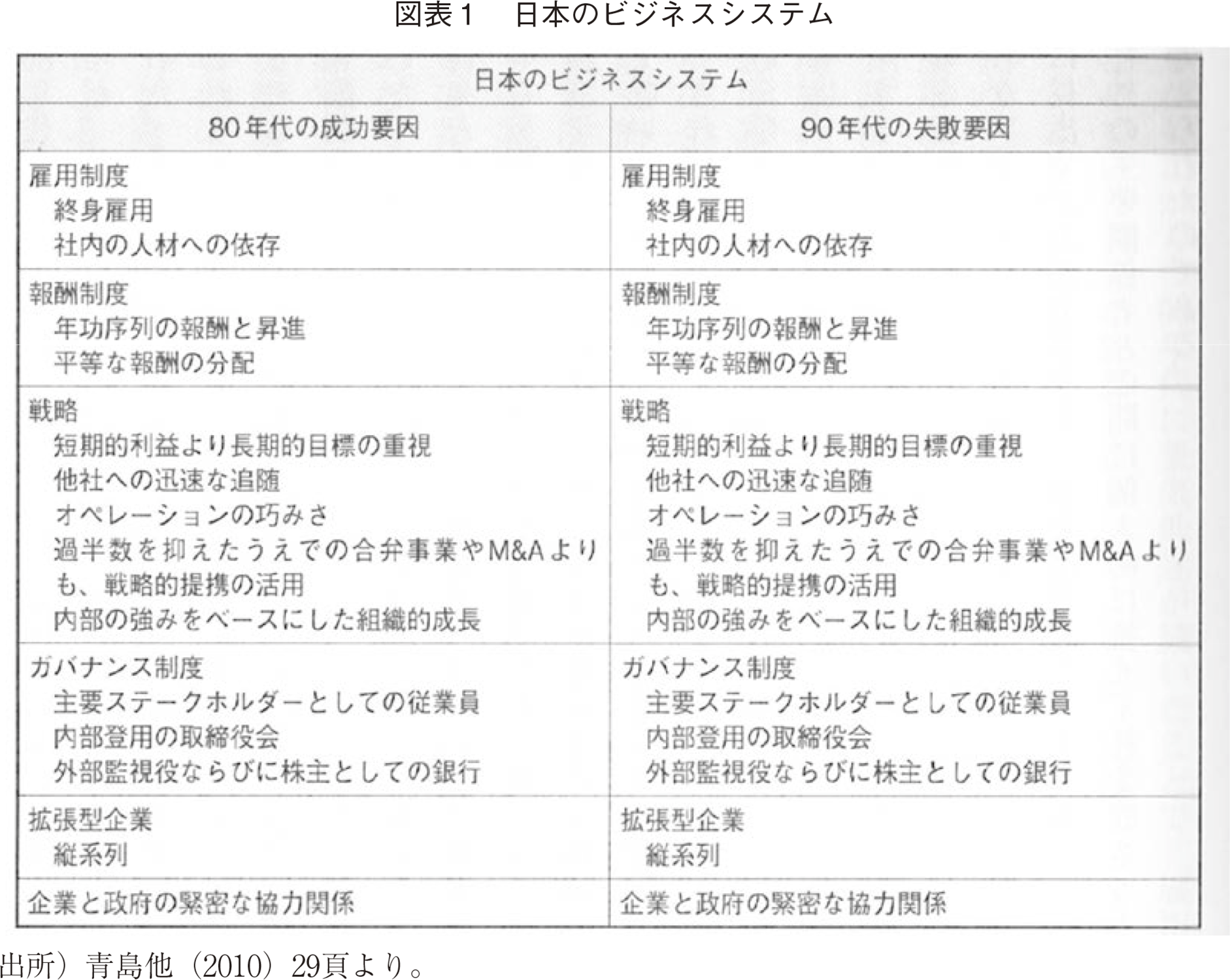
���̕\���疾�炩�Ȃ悤�ɁC�ٗp���x�C��V���x�C�헪�C�K�o�i���X���x�C�g���^��ƁC��ƂƐ��{�̊W�̂��ꂼ��ɂ��ē����v�����C80�N��ł͐����v���ł��������̂��C90�N��ł͎��s�v���ƂȂ��Ă���B�Ȃ��Ȃ̂��B���̗��R�͂��܂��܂��낤���C�����ł͐V���x�h�o�ϊw�C���̒��ł����Ɏ����p���_�̊ϓ_����l�@���Ă݂����B�s��Ƒg�D�̑��ΓI�D�ʐ��̕ω��ɏœ_�����ĂāC���{��Ƃ̌o�c�V�X�e�������܂��@�\���Ȃ��Ȃ���������V���x�h�o�ϊw�̒m���܂��ċc�_�������B
�o�u���o�ϕ�����1990�N��́C���{�o�ς��ɓx�̕s�U�Ɋׂ������߁C���{��Ƃ݂̍�����₢�����ꂽ����łȂ��C�����o�ϖʂł�����ȉۑ肪���ڂł������B���ɃA�����J�Ȃǂɔ�ׂĐ��{�ɂ��o�ϓI�E�Љ�I�K���̑�������莋���ꂽ�B90�N��ɐ�����S�����������̓��t�ŋK���ɘa�����グ���C��Ƃ̎��R�Ȋ����ɂ��V��ӂ̑��i��X�l�̑n���͂��̐���������ׂ��C�����K����V�����������i�߂�ꂽ�B�J���s��̉��v����Z�r�b�O�o���Ȃǂ��܂��܂Ȏ{���݂�ꂽ�B2010�N��ɂ͊�Ƃ̖{�i�I�ȃK�o�i���X���v���i�߂�ꂽ���C���������w�͂ɂ�������炸�C�X�C�X�̃r�W�l�X�X�N�[��IMD�̒����ɂ��ƁC1980�N��㔼���E��̋����͂��ւ��Ă������{�́C���߂�2023�N�ɂ�35�ʂ܂Œቺ�����Ƃ����B�����������ʂ������炵���ӔC�̈�[�́C���{�I�Ȍo�c�V�X�e���ɂ���̂ł͂Ȃ����Ƃ̌���������B��������{�I�o�c�͑S�ʓI�ɕ������ׂ��ł���Ƃ̎咣���o�ꂵ���B�{���ɂ������ׂ��Ȃ̂��B
�ŏ��ɁC����܂ŕM�҂炪�c�_���Ă����Ƃ���ł�����{�I�o�c�V�X�e���̓��������߂Č������Ă݂����B��̐}�\�P�ɂ�����悤�ɁC���{��Ƃ̓�����\���v���Ƃ��āC�ٗp�V�X�e�����Ƃ̖ڕW�C�s���Ƃ������헪�v���C�K�o�i���X���x���X���������邪�C�_�҂ɂ���āC�܂�����ɂ���ĉ��������ē��{�I�o�c�̓����Ƃ݂Ȃ����͈قȂ��Ă����B�ȉ��ł́C�E�B���A���\���i1996�j�̋c�_����ɁC��������B�E�B���A���\���́CAoki�i1990�j�Ɉˋ����Ȃ���C���{��Ƃ̓������ٗp�C���Z�C�����Ɋւ�鐧�x�⊵�s�𒆐S�ɂ܂Ƃ߁C�����̗v���̕⊮�I�W����{�I�Ȋ�ƃV�X�e���̓����Ƒ������B⑴�ٗp�C�������x�C��s�̎O�̎�v�������{��Ƃ̐����̍��{�����ł���C⑵���̊e�X�̎������͍ۗ��������x�I�x���Ɉˑ����Ă���C⑶�O�̗v���݂͌��ɕ⊮�I�W�ɂ���C�Ƙ_�����B
�I�g�ٗp�ƔN�����x�͎��m�̓��{�I�o�c�̓����ł��邪�C�����1990�N��Ɏ����Ă͂����ꂩ���Ă����B�ނ���E�B���A���\���͓��{��Ƃ̌ٗp�W�̓������Ј��������x5�j�ɂ���Ƃ̐̋c�_�����ꂽ�����ŁC�����I�ɏd�v�ȓ�̐��x�I�x���Ɉˋ����Ă����Ƃ����B��́C��Ɠ��̐l������̒n�ʂ̍����ł���C��͊�ƕʑg���ł���B�܂����{��Ƃ̐l������̔z�u�Ɛ�剻�����ď�i�ƕ����̏��i�L�����A�������l������ɂ���ĊǗ������Ƃ����d�g�݂́C��Ɠ����������\�o����Ƃ��������y�����Ă����B�č���Ƃɔ�ׂāC���{�̒�����i�͕����̖��^�ɗy�ɏ��Ȃ��Ǘ������y�ڂ����C�l�����傪�L�����A�`���ɑ傫�Ȗ������ʂ����Ă����B
����ɁC�u���{��Ƃ̊�ƕʑg���́C��Ƃ̖ړI�ƕK�v���ɂ���k���Ɋ֗^���C�����ɁC�l������̋@�\�����Ɏ����I�ȃ`�F�b�N�Ɣ������s���āv�i�E�B���A���\���i1996�j�C385�Łj����C��ƕʂł��邽�߁C�����ړI���������J���҂̌o�ϓI�K�v�ɏœ_�����ĂĂ���B���̂��Ƃ��J���҂Ɗ�Ƃ̒����I���v�ɓK�����ƂɂȂ邾�낤�C�Ƙ_���Ă���B��Ɠ���I�Ȑl�I�����̐[���Ƃ����ʓI�Ȋ��p�́C������̌ٗp�W�̐��x�I�x���ɂ���đ��i����Ă���Ƃ�����������Ă���B
���{�̐����Ƒ��Ƃ̓A�����J�̂�����萂���I�ɓ�������Ă��Ȃ������B���̂��Ƃ͎����ԎY�Ƃł̕��i�������̔�r���瓝�v�I�ɂ����炩�ɂ���Ă���6�j�B�E�B���A���\���́C���{��Ƃ͍����I�_��ɂ��L�͂Ɉˋ����Ă���Ƃ����B�܂�C�������x���I�݂Ɋ��p���āC�����I�ȕ��i���B���������Ă����B
���ۂɂ́C���{���č������B���s�͗ގ����Ă���C���x�ȓ���I�����͐e��Ƃɂ���ĂȂ���C����ɂ��Ă͐����I�����̉��ōs���C����ɑ��āC������ʓI�E�ėp�I�����ɂ�镔�i�͎s��Œ��B�����B���͂��̒��ԂɈʒu���镔�i�̒��B�C�������ǂ����邩�ł���B���{��Ƃ́C����i1997�j�̌����ɂ���悤�ɁC⑴��������镔�i�̐��i�C⑵�_��W�̗��j�C�y282�Łz ⑶�Y�Ƃ̐��n�x�C⑷�e�W���ꐫ�Z�\�̃T�v���C���[�̕]���C�ɉ����Č_��͑̌n�I�ɕς��C�o�ϐ�����Ƃ��āC���x�ɐ������ꂽ�����ŊǗ����Ă����B����́C�����I�����͍ŏI�I�ɑi����ׂ��g�D�`�Ԃł���Ƃ�����{��Ƃ̗����̔��f�ł���Ƃ���B
�܂�C���j��ƂƃT�v���C���[�����ڂɋ������Ȃ���C���i�����ɉ����ē������s���C�ł��������������ł���悤�Ȍ_����H�v���Ȃ��畔�i���B�����Ă����Ƃ����悤�B�����Ă��ꂪ���{�̐������Ƃ̏d�v�Ȑ헪�I�ȓ����ł�����
���{�̋�s�͑S�̂Ƃ��Ă݂�C����Ƃ̔��s�ς݊����̑傫�Ȋ������߂Ă����B�����w�i�ɋ�s�͐�����Ƃ̌o�c�s���Ɋ֗^���Ă����B���{��Ƃ̓��C���o���N�ƌĂ�钷���Z���̎�̂ƂȂ��s����L���Ă���C���C���o���N�͓��Y��Ƃ̎��Ə̌��i�Ȋč��ɐӔC�������Ă���B��Ƃ��o�c����Ɋׂ�C���C���o���N�͊e��̋~�ϑ[�u���{�̎傽��ӔC���B
���̐ӔC���ʂ������Ƃ����₷�邱�Ƃ͖������ʂ̌̂ɁC���蓾�Ȃ��B���C���o���N���ӔC���ʂ����Ȃ��ƁC��s�W�c�̃����o�[���珜�O����C����Ȕ�����������ۂ����邱�ƂɂȂ�B�܂���s�̊������L�Ɗ�ƊԂ̑��݊����̎��������ɂ���āC������̋��Ђ���u������Ă����B�܂��s�𒆐S�Ƃ�����Z�@�ւ̖��������{��Ƃ̐헪�̎��{�ɑ傫�ȉe����^���Ă����̂ł���B
�����̂킪���̏����s�͑��݂ɖ��ڂɊ֘A���Ă���C���Ɍٗp���s�͍L�͂ȉ������x�Ƌ�s�ɂ��R���g���[���Ɏx�����Ă���C�ƃE�B���A���\���͘_���Ă���B�I�g�ٗp�I�Ȋ��s�́C���{��Ƃɑ����̃����b�g���������B�������C�����p���_�̊ϓ_���炷��ƁC���ׂĂ̒����_��͕s��I�ɕs���S�ł���C�I�g�_��������_��ł��邽�߁C�s���S�Ȍ̂ɕ��Q���B��̓I�ɂ́C�o�ϓI�ɋꋫ�Ɋׂ������̑Ή��̓���C�E�����s�̑Ӗ��C�����Ƃւ̐��Y�\�͂̓��������]�ƈ�����Ɣ����Ȃǂɂ���ē��Y��ƂƂ̖��̂ɂ����댯�C������`�I�ȗv���̔۔F�̍���ɂ��I�g�̕ۏ�̕s���C�Ƃ��������Q������̂ł���B
�����������Q���y������̂��C�l�����Ɗ�ƕʑg���̋��͂ł���C���ꂪ�ӋƂ�ߓx�̕�����`���y������B�܂�������Ƃ����I�g�ٗp�łȂ����Ƃɂ���āC���v���ɔ����e��Ƃ̌o�ϓI�ꋫ�̍�����ɘa����B����ɍL�͂ȉ������x�͒��j��Ƃ̘J���͂������C�l���Ǘ��Ɗ�ƕʑg���̉^�c��P���������C������`�̕��Q���y������B���E�̌o�c�w��������ɂ���ĉ�C����邱�Ƃ��琶������̕��Q�́C���C���o���N���������������x�R���g���[�����邱�Ƃɂ���Č������Ă����̂ł���B
1980�N���ʂ��āC���{��Ƃ͏]�ƈ���������C��s�ƁC�����Ă����C�����E�p���I�W��ێ����邱�Ƃɂ���āC�����̊Ԃ̃V�X�e���I���ʂ�ʂ��Č݂��Ɏx�������Ȃ���C��Ƃ̃p�t�H�[�}���X�����߂�d�g�݂��\�z���Ă����B
����ɂ����āC��Ř_����悤��1980�N��̃q�G�����L�[�D�ʂ̎���ɂ�����C�č����Ƃ̌o�c�̃p�t�H�[�}���X�͍����Ȃ������B�g���Ƃ̑Η��⊔���s��ɂ�����Z���I���_����̌o�c���̒D�������ȂǁC���[���Ȗ��ł������B���{�I�o�c�̍I�݂����č���Ƃ̌o�c�̎d���������Ă����Ƃ�����悤�Ɏv����B1980�N��́C���{�̌o�σV�X�e���S�̂̎d�g�݂Ɠ��{�I�o�c�̉^�c�݂̍�������ݕ⊮�I�ɂ��܂��@�\���Ă����B
�Y�Ƃł����Ύ�Ƃ��āC�d�q�@��C�����ԁC�H��@�B�Ƃ������Z�N�^�[���킪����Ƃ̐����y283�Łz �ɑ傢�ɍv�������B���������Y�Ƃł͐��Y�H���ɂ������k���ȕ��ƂƓ����C���荇�킹�⋦���C���̋��L�C����̍H���ɓ��������l�I�������n�������ɏd�v�ł������B
�������C���̌�C�}���ɋZ�p�v�V���i�݁C���x��i���̎Y�Ƃ̒��Ő��v�Ȓn�ʂ��߂�悤�ɂȂ������Z�Ƃ���ʐM�Y�ƂȂǂŋ��߂���e�N�m���W�[��m���݂̍���͑傫���ω����C���{�I�o�c�̓����͎������}���邱�ƂɂȂ�̂ł���B
�ȏ�̂悤�ɁC���{��Ƃ̌o�c�݂̍���́C�ٗp�C��ƊԊW�C��s���x�Ȃǂ����ꂼ��W���I�Ȍo�ϊw�̘_���Ƃ��قȂ����`�Ԃ��Ƃ�Ȃ�����C���݂ɕ⊮����V�X�e���I���ʂ����āC�ڊo�܂������ʂ��グ�Ă����B����ł́C�Ȃ�1980�N��ɗ������ւ������{�o�ς���{��Ƃ͒���邱�ƂɂȂ����̂��B���̗��R��V���x�h�o�ϊw�C���Ɏ����p���_�̊ϓ_���番�͂��Ă݂����B
�V�ÓT�h�o�ϊw�̐��E�ł́C�s��@�\�̌��������̎^����C���������������������̉𖾂����_�I�����̒��S�ł������B�������C���_�I�ɖ��炩�ɂ��ꂽ���z�I�ȏ����͌������C�����̌o�ς̓����͂����őz�肳��Ă������̂Ƃ͒������قȂ�B�R�[�X�i1937�j�����I�ɘ_�����悤�ɁC�V�ÓT�h�o�ϊw���z�肷�銮�S���̐��E�Ƃ͈قȂ�C�������E�͏�s���S�ł���C�s�m�����ɖ����Ă���B�����Đl�Ԃ̔\�͂������Ă���B����\�͂�L���\�͂Ȃǂɂ����Č��E������C������������̒��Ō��������������ׂ��C��ƂƂ����g�D�͗l�X�Ȍ���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������s�ꂪ���S�ł���C���i���J�j�Y�������C�Ȃ��쓮�����������B������邪�C���ۂɂ͎����I�Ɍ���������������킯�ł͂Ȃ��B�����炱����ƂƂ����g�D���s��ɑ����ēo�ꂷ���ʂ����܂��̂ł���B
�s���S�ȏ���m���̂��ƂŁC�@���Ɏ���W���\�z���C�L���Ȑ헪���Ƃ邩����Ƃ͖͍����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̕s���S�Ȑ��E�ł́C�����p���s��I�ɔ�������̂ł���C���̔�p�̑召�́C���x�I���ɏd�v�ȈӖ����������B���S��Ƃ͈قȂ�C�ǂ̂悤�Ȋ�Ƒg�D��헪���]�܂����̂��C�B��̉��͂Ȃ��B���ɓK�����ׂ����l�Ȑ��x��V�X�e������������B���̂���l�́C���ɂ���Ď���ɂ���ĈقȂ邱�ƂɂȂ낤�B�ǂ̂悤�Ȑ��x���]�܂����̂��C�����I�ł���̂��Ɋւ�������l�@����̂ɗL�p�Șg�g�݂���Ă���闝�_�̈���C�����p���_�Ȃ̂ł���B
�����p���_�́C�R�[�X�i1937�j�̐��I�Ɛтł���u��Ƃ̖{���v����ɁC�E�B���A���\���i1975�C1985�j�ɂ���Ċm������C���Ȃ����W������B����͂̊�{�Ƃ���Ƃ������z�̌��_�́C�����x�o�ϊw�̋c�_�ɑk��邪�C�����x�h�͂����Ύw�E�����悤�ɗ��_�I�g�g�݂������Ă���Ƃ������_���������B����ɑ��ĐV���x�o�ϊw���m�������E�B���A���\���́C����͂̊�{�P�ʂƂ��C��ƂƂ������x���Ȃ��s��̒��Ő�������̂���������闝�_�I�g�g�݂����������B
���̊�{�I�Șg�g�݂ɑg�ݓ�����Ă����̂́C�����C�l�I�v���Ƃ��Ă̌��肳�ꂽ�������Ƌ@���`�C���v���Ƃ��Ă̕s�m�����Ǝ������̏������ł������i�E�B���A���\���@�i1975�j�j�B���v���Ɛl�I�v�������т����Ƃɂ���Ďs��ł̎����p�����܂�C���̌��ʁC�K�w�g�D�i�q�G�����L�[�j���o������B���̍ہC���̕s���S���E��Ώ̐����傫�Ȗ��������y284�Łz ����B�������̍s������Ɋւ�����̓���ɔ�p�̂����邱�Ƃ������p�̔�������傫�ȗ��R�ƂȂ�̂ł���B�V�ÓT�h�o�ϊw�ł́C�����p�̓[���ł��邱�Ƃ����肵�Ă���C�����ł͎s�ꂪ���ׂĂł���C���x�̑I���͖��ƂȂ�Ȃ����C�����p���_�ł͖����I�Ɏ��グ���邱�ƂɂȂ����B
���̌�C�������Ƃ����v�����K�肷��v���Ƃ��āC�E�B���A���\���́C���Y���ꐫ�|���Ȃ킿����ɓ��L�Ȏ��Y�ւ̓����|�����ʂƂ��Ď���҂̐��������I�ɏ��Ȃ����Ă��܂��Ƃ������Ƃ���������悤�ɂȂ����B����J�n���ɂ����Ă͑����̎�����肪���ċ�����Ԃɂ������Ƃ��Ă����Y���ꐫ�����݂��āC����I�Ɏ�����肪���������Ă��܂��ɏœ_�����Ă���悤�ɂȂ����B��������{�I�ȕϊ��ƃE�B���A���\���͌Ă�ł���B
��������肷�鑮���Ƃ��āC�s�m���������̕p�x�C���Y���ꐫ�����グ���C���̒��ł����ɁC���Y���ꐫ������̃K�o�i���X�i�����j�l���̗L���������E����ŏd�v�Ȃ��̂Ƃ��ďd�����ꂽ�B���Y���ꐫ�ɂ́C���n���ꐫ�C���I���Y���ꐫ�C�l�I���Y���ꐫ�Ȃǂ����邪�C��������������̎������̂��߂Ɋ�悳��邽�߁C�ړ]���������ϋv�I�ő��ɕς����������l�������̂������B����́C����̓����ΏۈȊO�ւ̎��P�I�g�p������ꍇ�ɂ́C���̉��l���ቺ������Ȃ����Y�ł���7�j�B
���Y���ꐫ������ꍇ�ɂ́C�Z���̎���_��W�ł͏\���ȓ������Ȃ���Ȃ����ꂪ�����C�����I�E�p���I�Ȏ�����s���邱�Ƃ��]�܂����B�����I�W���p������悤�Ȑ��x�I�g�g�݂��o�ϓI�Ȍ������̊m�ۂɂ͕K�v�Ƃ����B�����������ꐫ�̑傫���ɂ���āC�s��ɂ���������p�̑召�����肳��C�������p�̏��Ȃ����x�̗̍p�����������Ƃ����̂������p���_�̊�{�I�ȃA�C�f�B�A�ł���B�s��C�K�w�g�D�C��g�E�n�̒��ԑg�D�Ƃ������e�K�o�i���X�l���̑��������͎����p�Ɋ�Â��������̊ϓ_���牺����邱�ƂɂȂ�B
2.3.2�@�����p���_����̐����Ə����䂭�艼��
�V���x�h�o�ϊw�Ȃ��������p�_�Ɉˋ������C���{�I�Ȍo�ρE�o�c�V�X�e���̓����̐��������݂������ɂ́C�O��i2000�j�═�c�i2013�j�Ȃǂ�����B�Ⴆ�C�O��́C���{�I�Ȍٗp���s�ł���I�g�ٗp�̐����������p���_�̘g�g�݂�p���Đ������Ă���B���̕s���S���Ɛl�Ԃ̏���\�͂̌��E��O��Ƃ���ƁC�ٗp�W�ɂ����ĒZ���I�ȃX�|�b�g�_����J��Ԃ������ł͎����p���������C�����_��ł���I�g�ٗp�̕����������ꍇ������B���ɁC�l�I�ɓ���I�ȓ����ɂ��X�L����n�����傫�Ȗ������ʂ����悤�Ȑ����Ƃł́C�����_�]�܂����C�I�g�ٗp�̃����b�g���傫���Ƃ������ƂɂȂ�C�Ƙ_���Ă���B�܂����c�́C�����p�ߖ��̍l������U��Ԃ�C���̒m������{�^�o�Ϗ����x�ɓ��Ă͂߂邱�Ƃ�, ���{�^�����x���D�ʐ����������邱�Ƃ̐��������݂Ă���B
�s��̎����p�̑召���������s�ꂩ���ԑg�D���C�Ƃ�������`�Ԃ̑I�������߂�Ƃ����̂��C�R�[�X�E�E�B���A���\�����̎咣�ł���C�ǂ̓����V�X�e�����D��Ă��邩�����߂�̂́C����̊���\���ł���B���̕ω����C���Ă͗D�G�ł������V�X�e�����コ���邱�Ƃ�����B����́C���̕ω��ɓK�����Ă������Ƃ��ǂ�ȑg�D��V�X�e���̑����ɂ��s���ł���B���ꂪ�ǂ̒��x�̕ϊv��g�D��V�X�e���ɗv������̂��C�₦���ᖡ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�y285�Łz����ł́C1990�N���ʂ��āC���{�I�o�c�V�X�e���̋��݂�ł������悤�Ȃǂ�Ȋ��̕ω����������̂��낤���B���̍ő�̗v���͋��炭�C���ʐM�Z�p�̊v���I�ȕω����낤�BIT�̊i�i�̐i���ɂ��C���Y�v���Z�X���ƊԎ���ɂ����ă��W�����[����f�W�^�������i�B�ߔN�̏��Z�p�̔���I���W�܂ł̎���ɂ����ẮC�����I�ȓ�����Ƃɂ�钲�����s���������������D�ʂɂ������ƌ�����B���̓_�ɂ��ẮC�����O���A�̉����������ɒl����B�����O���A�i2003�j�́C�s��Ƒ�K�͑g�D�Ƃ̑��ΓI�ȗD�ʐ����}�N���I�Ȋϓ_����C���j�I�Ɍ��������B�ނɂ��ƁC�`�����h���[���w�o�c�҂̎���x�Ř_����19���I������20���I���ɂ����āC��Ƃ̐헪�Ƃ��Đ����I�������L���ł������B�������C����̐�i���o�ςł́C�s����x���鑽�l�Ȑ��x�̐����Ə��������̏㏸�ɂ����v�̑��l���ɂ��C�����I���������s�ꃁ�J�j�Y���ɂ�钲�����x�z�I�ƂȂ����B�ނ�20���I�㔼�ȍ~�C�o�c�҂ɂ��u�������v����s��́u�������v�֎����z���̒������J�j�Y���̎�����ڂ��Ă���Ƃ�����������Ă���B����������ƊԂ̎s����o�R����������C��K�͂ȓ�����Ƃ�������̌o�ώЉ�ɂ����Ă͌����I�ł���Ƃ������Ƃł���C�`�����h���[�̖���͔ے肳��邱�ƂɂȂ�B
�}�\�Q�������O���A�̏����䂭��̉����������Ă���B�s�ꂪ�L�����ǂ����́C�s��̌��݁C���Ȃ킿�l���⏊�������̍����C�Ȃǂ̊O���I�v�f�ɂ���č��E����C�����ǂ����ƂɌ��݂𑝂��Ƒz�肳��Ă���B����ɂ����āC�ǂ̂悤�Ȏ���̃K�o�i���X�`�Ԃ��L���ƂȂ邩�����肷��v���Ƃ��āC�ɏՂً̋}�x���������Ă���B����͕��G���C�������C���X���[�v�b�g�Ƃ������ϓ_���猩�����Y�Z�p�̒��x�̖��ł���B���Y�Z�p�����G�ō��X���[�v�b�g�ł���C�ɏՂً̋}�x�͍����Ȃ�B�}�\�Q�ŁC�s��ƊK�w�̋��ڂ�\���ߐ��̏�ł́C�K�w�g�D�ɂ�钲�����L���ł���C���̉��ł͎s��ł̒������D�ʐ������B�ǂ���̃K�o�i���X�������x�z�I�ƂȂ邩�́C���Y�Z�p��s�m�����̒��x�ɉe�������B�܂����Z�p�̐i�����傫�ȉe����^���邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�s��Ɠ����̓]���_��1880�N���1990�N��ɖK�ꂽ�Ƃ����̂��C�����O���A�̎咣�ł���B1880�N��ȑO�́C�s�ꂪ�x�z�I�ł��������C���̌�C�����I�������D�ʂƂȂ�C1990�N��ɍĂюs�ꂪ�D�ʂƂȂ������Ƃ������Ă���B����̓����O���A���g���F�߂Ă���悤�ɋɂ߂ă��t�ȋc�_�ł͂��邪�C��ƂƎs��̋��E�̕ϑJ��������̌����ł��낤�B
�Ƃ��낪����Ȃ��ƂɁC�����䂭��̋Ȑ��̒��_�ł́C�č��̓������Ƃ̌������͕K�����������Ȃ������B��Q������C�A�����J���ŋ��̌o�ϑ卑�ł���C�����ɔ䂵�Ĉ��|�I�Ȓn�ʂ��߂Ă����B���Ƃ̌o�c�͌����Č����I�Ƃ����Ȃ��������C����ɂ�������炸�C���{��h�C�c�Ȃǂ���������܂ł́C�������v���Ɛ����������ł����̂ł���B
��K�͂ȃX���[�v�b�g�́C��ʐ��Y�̐����Z�p�I�ɗv���������C�A�����J��Ƃ͂���ɂ��܂��K���ł��Ă����Ƃ͌����Ȃ������B�����^�̌������ߊW�C��������ɂ������ƈ��Ɗē̕����C�e�[���[�I�ȉȊw�I�Ǘ��@�̌��E�C�����J���g���Ȃǂɂ���āC�A�����J��Ƃ̐��Y���͍����Ȃ������B�������������Y�Ƃł́C��Ɠ���I�Ȑl�I�����������͂̌���ɂ͕K�{�ł��邪�C�J���҂̗������̍����A�����J��Ƃł͍���ł������B�����I�Ȑ��Y�̐��Ɨ����I�ȓ]�E�s��C���ꂼ��̘_���̗����͓���B����ɉ����āC���{�s��ɂ�����G�ΓI�����̉��s���o�c�҂̒����I���삩��̌o�c��j�Q���Ă����B����ɑ��āC��q�����悤�ɁC���{��Ƃ͏]�ƈ���������C��s�ƁC�����Ă����C�����E�p���I�W��ێ����邱�Ƃɂ���āC����Ώ������I�Ȍ`�ԂŁC�����̊Ԃ̃V�X�e���I���ʂ�ʂ��Č݂��Ɏx�������Ȃ���C����y286�Łz ��p��ߖC��Ƃ̃p�t�H�[�}���X�����߂�d�g�݂��\�z���Ă����̂ł���B�s��Ɠ����g�D�̒��ԓI�ȓ����\�������Ɋ��p���Ă����B
�������Ȃ���C�ŋ߂̏��Z�p�̔���I�Ȕ��W�ɔ����C�s��̌������̌���͒����E�p�������|�Ƃ�����{�I�o�c�ɂƂ��ĕs���ɓ����\��������8�j�B���{��Ƃ̋����^�C�g�ȕ����i�V�F�[�f�i2022�j�j�Ɋ�Â����W�b�h�Ȋ�ƊԂ̊W�C���邢�͌o�c�҂Ə]�ƈ��̊W�C�]�ƈ����݂̊W�́C���������Ⴂ���߂Ɏs��̎��R�Ȏ����z����j�Q���C��������W����悤�ɂȂ����Ƃ����邩������Ȃ��B�����䂭��̎���ɓK��������Ȃ������Ƃ����邩������Ȃ��B����ɑ��ĕč���Ƃ͒��ԓI�ȁC�����I����W�Ɉˑ����邱�Ƃ͏��Ȃ��C�����I�ȑg�D���s���ƂȂ�ƁC�s��𗘗p���邱�Ƃɏ�Q�͏��Ȃ������Ƃ݂���B
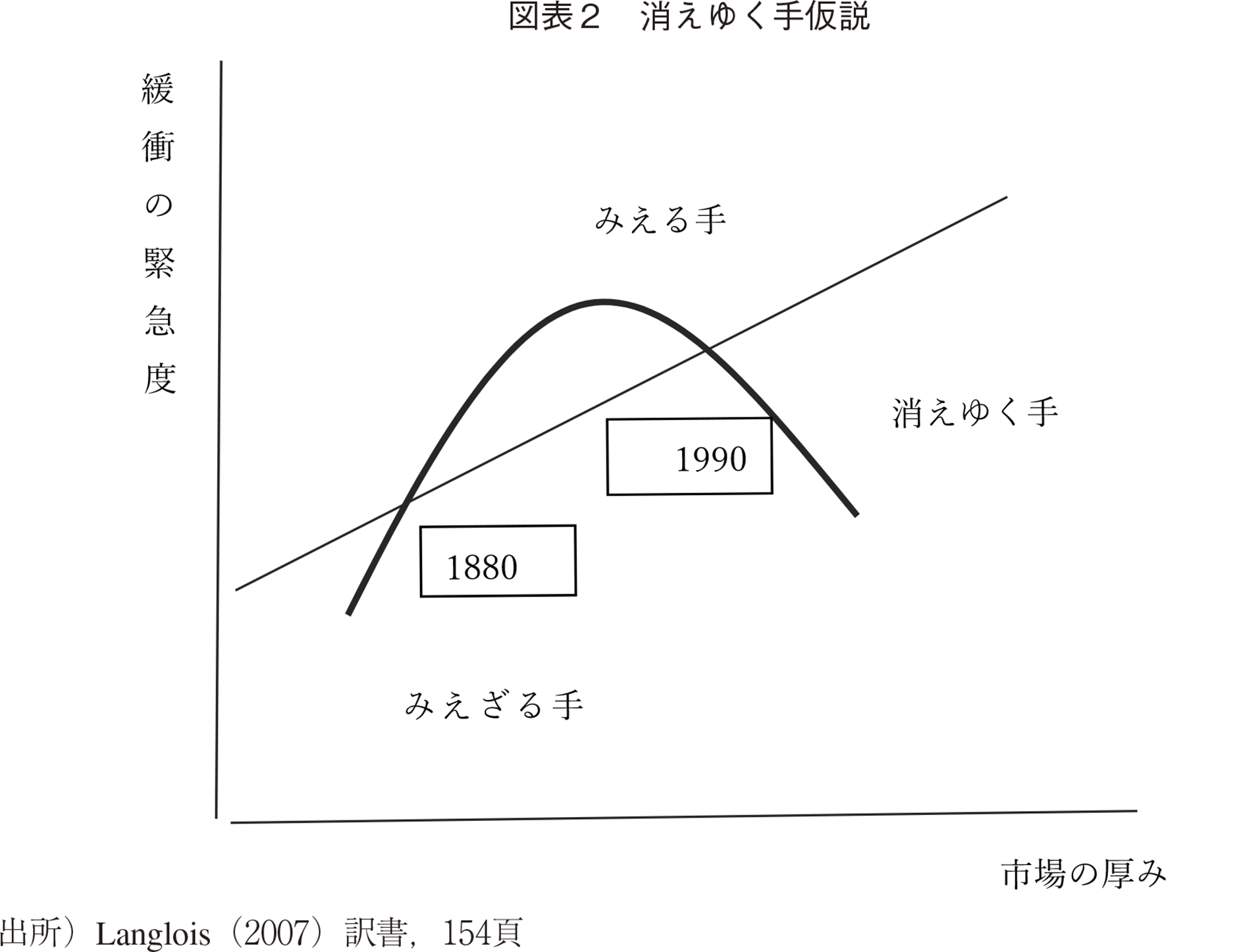
����܂ł̋c�_�܂��āC���{�I�o�c�C�L�������ē��{�^�̊�ƌo�c�V�X�e���ɂ��Č��i�K�ŁC�ǂ̂悤�ɕ]�����ׂ����B�͂��߂ɂŏq�ׂ��悤�ɁC1990�N��ɓ����ē��{�I�o�c�ɑ��錩���͑傫���ς��C�ߊϓI�]�����x�z�I�ƂȂ����ς�����B�������C�����͂��̌����ɂ͕K�������^���Ȃ��B
�ǂ̂悤�Ȋ�Ƃ�Y�Ƃœ��{�I�Ȍo�c�V�X�e�����D�ʂł��������ׂ�ƁC�����ɂ͂�����x���ʂ����������݂���悤�Ɏv����B�ɒO�i2019�j�ɂ��ƕ��G���C���݈ˑ����C���y287�Łz �ݐM�����x�[�X�Ƃ��鐶�Y�H���C�����ăC���e�O�����^�̐��i�ɂ��ċ����͂��������B�Ƃ��낪�C���i�A�[�L�e�N�`���[�̕ω���IT�̔���I�i�W���C���Y�V�X�e���S�ʂɓn���ăf�W�^�����𑣐i���C���W�����[�^�̐��Y�̐��������I�ɂ���悤�ɎY�ƁE��Ƃ̍\����ς����B���C�v�C���B�C���Y�C�̔��̊e�i�K���������Ď����I�Ȋ������\�ƂȂ�C�����I�����̋Z�p�I�����������܂����B���̌��ʁC���Y���ʂ̊e�i�K�Ԃ̎���ɂ͎��Y����I�����͂��܂�v�����ꂸ�C�������ꂽ�g�D���ł̖Ȗ��Ȓ����͕K�v�Ȃ��Ȃ����B�s����g������ƊԎ�������ΓI�Ɍ����I�ƂȂ������Ƃ����{��Ƃ̗D�ʐ���D�����ƌ����悤�B
���������ω��̉Q�̒��ɂ����Ă��C���{��Ƃ����݊��������������Y�Ƃ͂������B���G���Z�p��K�v�Ƃ���Y�Ƃł������B�n�[�h�n�̐����H���ł�������̕��i���g�ݗ��Ă��镡�G���Y�Ƃɂ����ē��{��Ƃ����������̂ł���C�����ł͓��{�I�o�c�̗ǂ������������Ă����B���G���Y�Ƃ̓T�^�����Ȃ����{�o�ς��x���鎩���ԎY�Ƃł���B
�����i2010�j�́C�Y�Ƃi�v���^�ƃf�o�C�X�v�b�V���i�@�\���W���[���j�^�ɑ�ʂ��C���{��Ƃ����ӂƂ��Ă����̂́C�O�҂ł����������B���i�v���^�Y�ƂƂ́C�ŏI�s��ɋ�������銮���i�ɗv�������ڋq���l��@�\���������ׂ��Z�p�J���E���i�J�����i�߂���Y�Ƃł���C�ڋq���l���ǂꂾ�������ɍČ��ł��邩���C�����̗v�ƂȂ�B
����ɑ��ăf�o�C�X�v�b�V���^�Ƃ́C�����I�Ȑ��i�̋��E�ɂƂ���邱�ƂȂ��C���ۓI�ȋ@�\�i�f�o�C�X�j�̋��E�̕ϊv��ʂ��ĐV���ȉ��l�����ݏo�����悤�ȎY�Ƃł���B�����ł͕ω�����ڋq�j�[�Y�ƋZ�p�̐i���ɑΉ������āC���i�C���j�b�g�C���i�Ƃ��������̂��p���I�ɍĒ�`����Ă����C���̍Ē�`�̗L�����������̗D������߂邱�ƂɂȂ�B
�����ԎY�Ƃ�1980�N��̃G���N�g���j�N�X�Y�Ƃ͐��i�v���^�Y�Ƃł���C���{��Ƃ����|�I�D�ʂɗ����Ă������C�G���N�g���j�N�X�Y�Ƃ┼���̎Y�ƂŃf�o�C�X�v�b�V���^�ֈڍs����ƗD�ʐ����D��ꂽ�B���i�v���^�Y�Ƃł́C���̐��i���������ׂ��v�������肳��Ă���C�����@���ɒ����ɖ����������d�v�ł��邪�C����ɑ��āC�f�o�C�X�v�b�V���^�ł͏�ɐ��i�̋��E���h�ꓮ���C���z�͂���́C�Ƒn������苁�߂�ꂱ�ƂɂȂ�B
���{��Ƃ̌o�c�V�X�e���|�Ⴆ�ΏI�g�ٗp��N������C�܂�����ƌ��т����Ј��������x�́C�C�m�x�[�e�B�u�Ȕ��z��v�������ꍇ�ɁC����ɉ�������l�ނ���Ă�ɂ͕s�K���ł���\���������B�Ȃ��Ȃ�C�]���Ƃ͖{���I�ɈقȂ锭�z����ɂ́C�َ��Ȑl�ނ╶���Ƃ̌𗬂���ł���C���{�I�ȕ��I�V�X�e���́C�Q�i�I�ȉ��v�ɂ͌����Ă��邪�C����I�ȉ��v�ɂ͓K���Ȃ�����ł���B�����p�̊ϓ_���猩��ƁC���i���Y�ɂ����Ă��l�ވ琬�ɂ����Ă��C���邢�͗Z���Ȃǂ̎��������Ɋւ��Ă�����̑���ɓ���I�Ȕ\�͂{���邱�Ƃ́C����W�̎��R�Ȑ�ւ����v�������s��I�W�̍\�z������ɂ���ƍl������
�܂��C�C�m�x�[�V�����Ƃ̊֘A�ł�����9�j�C���X�N�Ƃ͏�����������x�\���\�ȏł��邪�C�s�m���ȏ͗\���s�\�ł���B���{��Ƃ̓��X�N�ɑΏ�����ɂ͗D��Ă��邪�C�s�m�����ɂ͂��܂��Ώ��ł��Ȃ������̂�������Ȃ��B���̂��Ƃ�1990�N��ȍ~�̓��{��Ƃ̋��ɂȂ������̂ł���C����͓��{�I�o�c�̎d�g�݂����ݕ⊮�I�ɃV�X�e���Ƃ��ċ��łȂ��̂ł���������C�o�H�ˑ��ɔ����]�����邱�Ƃ���������Ǝv����B
�������Ȃ���C������Ƃ����āC���{��Ƃ�o�ς��A�����J�I�Ȍo�ρE�o�c��͕킷��悢���Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�Y�Ƃ̒��ł��C���{�I�o�c�̖{���I�ȗǂ����ʗp����̈��T�����C���y288�Łz �����邱�Ƃɂ���č���̐��������҂ł���Ǝv����B�V�F�[�f�i2022�j�͓��{��Ƃ̎��ׂ��헪���W���j�b�`�헪10�j�ƌĂ�ł���B���������̈�́C��E�\�t�g������i�Ɛi�W����o�ς̕K�������嗬���`�����Ȃ���������Ȃ����C���{��Ƃ�����̓��ӕ����[�k���邱�Ƃ��ł���C�ɒ[�ɔߊϓI�ɂȂ�K�v�͂Ȃ��ƕM�҂�͍l����B
���{�I�o�c�ɑ���]�������]�Ȑ܂��o�Ă��邪�C���{�I�o�c�̗ǎ��ȕ����C�����������ێ����Ȃ���C�K�ȏC���������Ă������Ƃ��]�܂����ƕM�҂�͍l����BIT�̊i�i�̐i���ɂ��C���W�����[����f�W�^�������i�݁C�s��̌������̗D�ʐ��������C�����p�_�I�ϓ_���炵�āC�k���ŕ��G�Ȓ����ɗD�ꂽ���{�I�o�c�̏��V�X�e���̋P���͔���Ă��Ă���̂����Ԃł��낤�B90�N��ȍ~�̓��{��Ƃ̒ᐬ���␢�E�o�ςɐ�߂�v���[���X�̒ቺ�������@���ɕ�����Ă���B
���{�I�Ȍo�c�V�X�e���̒��j���Ȃ��ٗp�ʂ��݂Ă݂�ƁC�I�g�ٗp���s�̑Ŕj���������C�J���s��̗�����������Ă���B��҂̈ӎ��̕ω����w�E����C�A�Ђł͂Ȃ��C�܂��ɏA�E�C�W���u�^�ٗp��ʂ����X�l�̃X�L���A�b�v���v������Ă���B�������C��N�҂����̂Ƃ��ďI�g�ٗp�I���s�������Ă���킯�ł͂Ȃ��B��Ƃ̐l�ވ琬�⋳�猤�C���肪���郉�[�j���O�G�[�W�F���V�[�����{�����u2023�N�V���Ј��̈ӎ������q�����ƕҁr�v�ɂ��ƁC�V���Ј���71.9�����u�ł�����̉�Ђœ������������v�Ɠ����C�I�g�ٗp���x����]���Ă��邱�Ƃ����������B
�����ɂ����āC�}�C�i�r�]�E�u2020�V���Ј��̈ӎ������v�ɂ��ƁC�u���̉�Ђʼn��N�����Ǝv�����v�ƕ������Ƃ���C�u�R�N�ȓ��v�Ɖ����l��28���ɏ��C�O�N�̐V���Ј����5.9�|�C���g�����������B�u10�N�ȓ��v�ɂ܂Ŋ��Ԃ������ƁC�v50.3���ɏ��B��������O�N����3.5�|�C���g�������錋�ʂƂȂ����B
�܂��C���{�\������i2023�N�����j�����{�����V���Ј��ӎ������ŁC�u��N�܂łP�̉�Ђɋ߂����v�u�@�����Γ]�E�E�Ɨ��������v�̂ǂ�����u�����邩�������Ƃ���C�u�Ɨ��E�]�E�v�u���̐l���S�̂�30.1���ɏ�����B�ЂƐ̑O�̏I�g�ٗp����Ƃ͈ӎ����ω����Ă��Ă���B�w��ʂł́C���Z���ƌQ��20.6���������̂ɑ��C�呲���i�������w�Z�C�Z��ȂNJ܂ށj��34.0���������B
���̂悤�ɁC��҂̉�Ђɑ���ӎ��ɂ��ẮC�������钲�����ʂ����邪�C�S�ʓI�ɏI�g�ٗp�I���s�����ۂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��Ǝv����B�l�ނ��Ɉ����C�����I�Ɉ琬���悤�Ƃ�����j�͊Ԉ���Ă��Ȃ����C�ߔN�̐l�I���{�o�c���d�����闬��ɑ�����ʂ�����Ǝv����B�������C�ߏ�ȓ������u���͔ے肳��Ȃ���Ȃ�Ȃ����C�X�l�̎v���d���Ȃ���l�ނ��I�ϓ_�����ĂĂ������Ƃ͈ˑR�Ƃ��đ厖�ł���C����̎�҂ɂ��������]�n�͂���B
�y289�Łz���{��Ƃ̋��݂ɂ��āC�V�F�[�f�i2022�j�́C���{�ɂ̓^�C�g�ȕ���11�j����Ղɂ���C����ɉ����ēƓ��̍s���K�͂�����Ǝw�E���Ă���B�ޏ��́C�ω��͒x�����C�F�X�ȋƎ�Œ����ɉ��v���i�߂��Ă���p���i�I�Ȋ�Ƃɏœ_�ĂāC���͂��Ă���B�^�C�g�ȕ����ɂ͂�������b�g������f�����b�g�����邱�Ƃ͔F�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��Ђ��]�ƈ��̉Ƒ��܂ł��ە�������悤�ȁC�ٗp���s�͂��͂�s�\��������Ȃ��̂ŁC�I�g�ٗp�Ƃ����Ă�����܂łƈႤ�l����悵�Ă��邾�낤�B���̂��߁C���{��Ƃ̋��^�Ɋ܂܂�Ă����������I���ʂ̎Љ�Ƃ��������Ȃ�傫�ȕϊv���K�v��������Ȃ��B
���̈Ӗ��ŋ��炭���{�I�o�c�́C���{�Љ�E�o�ς̃}�N���I�Ȏd�g�݂̕ϊv�Ɨ��ݍ����Ȃ���C�ω��Ȃ����͐i�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��낤�B���{�I�o�c�V�X�e����������Y�Ƃ␢�E�e����Ȍ����邱�Ƃ͂Ȃ����낤���C���̋��݂�ǂ���������Y�Ƃ�Z�N�^�[������̂͊ԈႢ�Ȃ��B�����p���_�̊ϓ_����݂Ă��̌o�ϐ��������ł���̈�ł́C������������Â���ׂ��ł���C�ނ��낻�̋��݂�Ƃ��āC�V�F�[�f�̌����W���j�b�`�헪��W�J���ċ����ɗՂނ̂���̗L�͂ȕ����ł���ƍl������B
�؏��F�i1993�j�C�u���{��Ƃ̌o�σ��f�������v�i�ɒO�h�V�E����쒉�j�E�ɓ����d�ҁi1993�j�w���[�f�B���O�X�@���{�̊�ƃV�X�e���@��P����ƂƂ͉����x�L��t�@��X�́C240-276�j
�����E���Ώ��E�N�X�}�m�C�}�C�P���i2010�j�C�w���C�h�E�C���E�W���p���͏I���̂����u��Ձv�Ɓu�I���v�̐�ɂ�����́x���m�o�ϐV���
����ݗ��i1997�j�C�w���{�̊�Ƒg�D�@�v�V�I�K���̃��J�j�Y���x���m�o�ϐV���
�����V���i2023�j�C�A�N�e�B�r�X�g�@�ł��C�u����̌����v�ŕϊv�v���C2023.01.05
�����V���i2023�j�C����������u�n�ƉƎx�z�s�K�v�@�c���nHD�����_�C2023.07.08
�����V���i2023�j�C�����t�@���h�̊����Ă�ی��@�c���nHD����C2023.08.11
�����V���i2023�j�C��Ɠ����u������v��NO�u���l�ȗ��Q�W�҂̑��d���v�o�A�Ȃǒ� 2023.9.12
�ɒO�h�V�i2019�j�C�w�����̌o�c�x���{�o�ϐV���o��
�ɓ��M�Y�i2023�j�C�u�l�I���{�o�c�̃p���_�C���ϊ��v�i�w�ꋴ�r�W�l�X���r���[�x2023�ċG���C8-27�j
���R���G�E��ˌ��o�i2012�j�C�u��Ƃ̌o�ϕ��͂̎��_�����_�I�l�@�v�i�w�K�@��w�w�o�Ϙ_�W�x49�C�P�C23-45�j
�V�F�[�f�C�E���P�i2022�j�C�w�ċ��@THE KAISHA ���{�̃r�W�l�X�E���C���x���V�����x�i�n���T�q��j���{�o�ϐV���o��
���c�I�i2013�j�C�u�����p�ቺ�Ɠ��{�^�o�Ϗ����x�v�i������w�w���S�_�p�x�C81�C3-4�C315-343�j
�O������i2000�j�C�w�V���x�h�o�ϊw�ɂ��g�D�����̊�b�x�������[
��ˌ��o�i2021�j�C�u�s��Ɗ�Ƃ̋��E��脟�O���[�o���o�c�Ƃ̊֘A�ń��v�i�����w�o�ό������N��C34�C5-29�j
��ˌ��o�E���R���G�i2022a�j�C�u����́u���{�I�o�c�v�_�i�R�j�v�i�w�K�@��w�w�o�Ϙ_�W�x58�C�S�C�y290�Łz 315-332�j
�y�i �]�i2023�j�C�Z�u�����A�C���̐������Ŗ����u�^�̎�r�v�X�[�p�[���R�N�ŗ��v�̎��C�J�M�͏c����Ŕj�@���m�o�ρ@2023/05/29
���{���G�E�����q�O�E�ɓ��G�j�i1998�j�C�w�T�v���C���[�E�V�X�e���|�V������ƊԊW��n��x�L��t
����O�i2021�j�C���呍��u�n�Q�^�J�v�����̑傢�Ȃ�ϖe�̂Ȃ��C�t�H�[�u�X�W���p���C2021.07.21
�{�{�����i1997�j�C�w���{�^�V�X�e���̐[�w������������v�_�x���m�o�ϐV���
�R���g���i2007�j�C�n�Q�^�J�t�@���h�́C�Ȃ��n�Q�^�J�Ȃ̂��H���������t�@���h��������킯�̎������z�C�R���g���̎������z�@2007�N07��03��
Aoki,M�i1990�j, �gToward an Economic Model of the Japanese Firm�h, Journal of Economic
Literature Vol. XXVlll �iMarch 1990�j, pp. 1-27
Aoki,M.�i2010�jCorporations in Evolving Diversity: Cognition,�@Governance,�@and Institutions, Oxford University Press�i�J���a�O��i2011�j�w�R�[�|���[�V�����̐i�����l���xNTT�o�Łj
Chandler,A.D.�i1977�j, The Visible Hand�FThe managerial Revolution in American Business .Cambrige :The Belknap Press.�i���H�ӈ�Y�E���ьU������i1979�j�w�o�c�҂̎��ㄟ�A�����J�Y�Ƃɂ�����ߑ��Ƃ̐����x���m�o�ϐV��Ёj
Coase,R.H.�i1937�j, �gThe Nature of the Firm.�h Economica, 4�i16�j
Langlois,R.N.�i2007�j, The Dynamics of Industrial Capitalism: Schmpeter,Chandler, and the New Economy, Routledge, New York�i�J���a�O��i2011�j�w�����䂭��F������ЂƎ��{��`�̃_�C�i�~�N�X�x�c����w�o�ʼn�j
Williamson, O.E.�i1975�j, Markets and Hierarchies: Analysis and Anti-Trust Implications, New York: Free Press�i��������E���W��i1980�j�w�s��Ɗ�Ƒg�D�x���{�]�_�Ёj
Williamson, O.E.�i1985�j, The Economic Institutions of Capitalism, New York: Free Pres
Williamson,O.E.�i1996�j, The Mechanisms of Governance. Oxford: Oxford University Press.�i�Γc���j�E�R�c�����i2017�j�w�K�o�i���X�̋@�\���o�ϑg�D�̊w�ۓI�����x�~�l�����@���[�j