「差別」概念の意味についての覚書
脇坂 明
いまから約40年前に人生初めての論文である修士論文を書き上げた。「労働市場における差別」というタイトルである。京都大学の紀要である『経済論叢』に掲載された(脇坂 1980)。修士論文の作成過程において指導教官の菊池光造先生(2023年4月11日逝去)から,様々な良きアドバイスをいただいた。女性労働問題をテーマにしたいと考えていた筆者に対して,まず労働市場に関する先行研究を渉猟し,そのうえで女性労働に迫ったほうがよいというものであった。結果的には,このアドバイスにより,その後の研究のとてもよいステップになった。
ただ労働市場論を無味乾燥にサーベイするのでは面白くないので,「差別」という視角から迫ることにした。修士論文の素案のなかで,「差別」にかかわる文献を読み重ねるうちに,「差別は,客観的な現象ではなく,差別されている側が『差別』されていると感じれば,それが差別である」という試論のような報告をした。今から思えば,恥ずかしい問題提起であったが,菊池先生は,そういう見方もあるかもしれないが,差別は客観的に存在する,とコメントされた。
この方向性での論文作成はよくないと思いなおし,レスター・サローの「仕事競争モデル」の著作を読んでいたので,それをベースに,「差別の経済学」の議論から,労働市場の構造をみようとした。ゆえに「差別」概念そのものにはそれほど深く切り込まず,当時の米国の「差別の経済学」の研究を基に展開した。その後,共訳を刊行したが(サロー 1984),差別研究に直接切り込むことはなかった。
本稿は,筆者が修士のときに考えていたことを,40年をへて,現時点で少しでもクリアーに説明し,今後の差別研究につなげたい。
まず経済学であるか否かを問わず,労働市場における差別の定義は,
「質量同じ“労働”(A)なのに,“何らかの基準”(B)で“賃金”に差がつく」
というものであろう。差をつけるのは,労働需要側つまり企業である。教育水準などの差は「労働市場以前の差別」で,当面,議論の対象外になる。
「賃金」のところにはいくつかの労働市場の用語が入りうる。
(1)賞与
(2)付加給付(社宅,社内ローンの優遇金利など)
(3)定年年齢
【236頁】(4)雇用機会(採用)
(5)昇進(昇格)
(4)の雇用機会が最も重要だと思われるが,この場合の「労働」には現時点における労働力だけでなく,将来の労働のポテンシャルも含まれる。いわゆる「内部労働市場」の側面も含めた,スキル向上の可能性がある労働である。より本質的には,生涯経験するOJTの機会が理不尽な理由で阻害されるか否かである。これが結果的に賃金の差にもつながるし,(5)の昇格による賃金の差にもつながる。
以下,「主観性 vs 客観性」にかかわる2つの仮説について述べる。これは,筆者の学部講義の教科書(『労働経済学入門』)に記載のものから,エッセンスを抜き出したものである。
「偏見説」は,ゲイリー・ベッカーが1957年に定式化したもので,「嗜好」モデルとも呼ばれる。人種差別を念頭においたものだが,わかりやすいケネス・アローのモデルをみよう。企業の経営者は,通常モデルでは,利潤にしか関心をもたないが,嗜好モデルでは,黒人従業員の人数にも関心がある。経営者の効用関数に,白人や黒人の従業員数がはいっている。白人の経営者は,黒人を雇うときは,同質な労働でも異なる労働とみなす。これは企業による「偏見」といってよいであろう。ベッカーは,これを「嗜好(好み)」と呼んだ。差別の種類によっては「好み」と呼んだほうが適当なものもあるかもしれないが(そのときは「差別」という認識はないかもしれない),採用のケースでは「偏見」と呼んだほうが適切である。
白人と黒人が同じ技能をもっているとしよう。これが差別の経済学の前提である。技能が異なることの背景に「差別」があるかもしれないが,それは教育などの労働市場にはいってくる以前の「差別」と考える。もちろん,それらも含めて広い視野から経済的差別とみることもあるが,分析の出発点は,同じ技能あるいは能力をもつことを前提とする。そのうえで差別が生まれるメカニズムを考える。
偏見説では,差別「嗜好」をもつ経営者は,それぞれ実際の限界生産力(MP)と異なる評価をする。それは次式であらわされる。
MPb= 黒人の賃金+Db
MPw= 白人の賃金+Dw
Db,Dwを差別係数とよびDb > 0,Dw < 0である。通常の経営者の効用関数は,U(利潤)だが,偏見のある経営者では,U(利潤,白人の人数,黒人の人数)となる。偏見がどこにはいるかというと,白人が多いと効用あがるので,白人の生産性を実際より高く評価するMPwの式になる(黒人の場合は低く評価する)。
そして,かりにすべての経営者が同じ効用関数(生産関数)をもっているとすれば,黒人,白人の人数構成比は,どの企業も同じとなる。
MPb=MPwと仮定しているので,
【237頁】白人の賃金−黒人の賃金= Db−Dw > 0
だから,均衡では(Db−Dw)だけの賃金格差が生じる。ある意味,当然であるが,経営者の「嗜好」すなわち「偏見」が人種間賃金格差を生じさせていることがわかる。
ケネス・アローやレスター・サローが指摘するように,この仮説の難点は,「すべての経営者が同じ効用関数をもっている」という非現実的な前提にある。もし同一の効用関数という仮定をはずすと,もっとも差別をしない経営者(差別係数が最小)が,利潤をあげることができ,最も成長する。なぜなら同じ技能(限界生産力)をもつ労働者を安く雇用できるからである。それゆえ均衡はくずれ,最終的に人種間の賃金差は消える。その「偏見」をもつ者が経営者でなく,在籍従業員であったとしても,同じことがいえる。
この偏見説を男女について適用した場合も同じ問題設定により,男女間賃金格差が説明できる。しかし上記と同様の論理が成り立ち,非現実的な仮定をおいているという難点がある。
偏見説に対する「統計的差別」説をみよう。企業が客観的(統計的)行動をしても,生じる差別である。
統計的差別とは,情報の非対称性のもとで,情報を有していない側が,外からみえる特徴でグループ分けをおこない,そのグループの平均的な性質を推定することから生まれるものである(神戸(2004))。自動車保険や生命保険の保険料は,年齢によって異なり,前者は若いほど,後者は年寄りほど高くなっている。若者でも安全運転する人はいるし,年配でも乱暴な運転する人はいる。しかし過去のデータに基づいて事故確率の年齢差があれば,保険会社は保険料に年齢差をつけることが合理的になる。その結果,若くて安全運転する人が,高い保険料を支払わされていることによる「統計的差別」をうけていることになる。
労働市場ではどうなるか。いま潜在能力が全く同じ2名の個人甲と乙を例にして説明しよう。甲が属するグループAには,企業にはいってから高い業績をあげる者が,乙の属するグループBよりも,確率的に多いことが「統計的」にわかっているとする。経営者は,個人の能力の識別はできないが,グループとしては「客観的に」把握している。こういった状況下では,訓練費用などを節約するために,経営者はグループAにいる甲を優先的に採用する。企業は客観的な採用行動をとっているが,乙を含むグループBに属する個人は「統計的差別」をうけている。これを「合理的差別」と呼ぶこともあるが,必ずしも正しくない。「偏見」に基づかないことが,そのまま「合理的」であるとまでは言えない。たしかに自動車保険会社の年齢による保険料の差は,一見,合理的にみえる。しかし,安全運転する若者は,明らかに個人的に「差別」されている。
統計的差別理論はE・S・フェルプスが提唱し,アイグナー=ケインなどにより発展した。労働者のもつ技能(向上)に関する,労働者と経営者の「情報の非対称性」が根底にある。より長期の観点からいうと,次のようになる。この理論のよってたつ企業行動は,採用時に関心があるのは,現在,もっている能力ではない。将来,期待する一定のレベルの技能であり,そこに到達するのに必要な期待訓練費用が企業の関心事である。訓練費用を最小化するために,有効で入手しやすいデータをもとに判断する。年齢,性,人種,(身長,体重),学歴,資格,【238頁】 出生地(国籍),宗教,以前の仕事など,つまり「労働者のパフォーマンスを予測」できる個人の背景となる特性から,総合的に判断する。企業が,この背景的特性を用いると,その特性による「統計的差別」,いわゆる格差につながる。性による格差,年齢格差,学歴格差などである。
労働市場としては,外部労働市場よりも内部労働市場(Internal Labor Markets; I LM)において生じやすい。このことは強調してもしすぎることはない。外部労働市場モデル(サローは「賃金競争モデル」とよぶ)だと,その時点でのスキルと賃金でみた差別になるので,視野が狭くなる。もちろん,この場合にも「統計的差別」は生じるが(スキルレベルの分布があるので),将来のスキルレベルまで視野にいれたILMモデルだと,より「統計的差別」が生じやすい。
その背景にある世界を描いたのが,レスター・サローの「仕事競争モデル」である(Thurow 1975,訳1984)。仕事競争モデルにおける企業は,年齢,人種,性,学歴,資格などの変数とこれまでの業績などの「統計」に信頼をおき利用する。「統計」には「誤差」(error)がつきものである。この誤差こそが,能力と意欲があるにもかかわらず,平均的生産性の低い劣位のグループに属しているというだけで「不当」に低い評価をうけている個人である。サローの文章を引用しよう。
仕事競争モデルでは,「労働市場の需給の一致は,(賃金変化ではなく)必要とされる背景的特性の上げ下げをつうじて行われるが,それによって広く観察される統計的差別という現象をもたらす。」「経営者は,もっとも好まれる背景となる特性をもつ労働者を採用する。・・・ある水準を下回っていれば採用されない。・・・多くの労働者が必要で,採用分岐点より上位の集団から採用できる人数では足りないとき,経営者は,・・採用基準を変更して,新しい集団も資格者とするだろう」(訳205頁)。「ほとんどの種類の差別(人種的・性的・宗教的など)が特定の集団に影響をおよぼすのに対し,統計的差別はだれにでも影響を与える現象である。統計的差別がおこるのは,属している集団,またはいくつかの集団の平均的な特性を基準に判断され,その人自身の個人的な特性によらないときである。その判断は,集団がその集団に帰せられる特性を実際にもっているという意味においては,正確なもので事実であり客観的である。しかし集団のなかの多くの個人に関して,その判断は不正確である。」(訳206頁)
上記以外にも,統計的差別に関する多くの論点を提示しているが(訳206-211頁),このくらいにとどめ,男女の差別について考えよう。
男女のケースでは,一部の仕事をのぞき,グループとしても潜在能力に差はないようにみえる。しかし,何割かの女性が結婚,出産で男性より早く辞めてしまう確率が高い。わが国の場合でも,出産を機会に企業を辞める女性が多い。ILMにおいても男性は辞めるが,少なくとも男性のほうが定着しやすい。その結果,平均的にみて辞めることの少ない男性を優先する。すると能力が高く辞めるつもりもない女性が,個人的に「差別」をうけることになる。これが「統計的差別」で,企業は従業員にほどこした訓練投資を確実に回収するために,リスク回避行動をとる結果,統計的差別が生じる。このリスクをとり,女性を積極的に採用・活用するのが,「イノベーション」企業である」(脇坂 1998)。
サローも統計的差別としての「性差別」も論じている。とくに「生涯における労働力への参加」という視点から「女性は,有業者ということでは,男性よりも労働力率がひくい」ことを1973年のデータで確かめている。「経営者は,事前にどの女性が生涯,年間を通してフルタイムで働く労働者になり,どの女性が労働力からしりぞき,あるいはパートの労働者になるかを【239頁】 見分けることはできない。」(訳211-215頁)
筆者が強調してきた企業への定着率(残存率)についての統計的差別(脇坂 1998)とほぼ同じ論理である。かつて企業の人事担当者と話をしていたときに,「差別」と「区別」は異なる,という論点がよく議論されていた。コース別人事制度や複線型制度の設計,運用に苦労されている人事担当者である。どの制度にも念頭においている労働者がいるので,よくよく聞いてみると,意味するところは,「区別」が客観的な「統計的差別」であり,同じ制度内での差別が偏見説に基づく議論のようであった。当然,同じ雇用区分では「差別」をしないよう運用に心がけているという議論である。筆者の議論は,特定の区分でなく,総体として,様々な労働者に「差別」があるかどうか,である。「統計的差別」も,受けている該当労働者からみれば「差別」である,と言っているにすぎない。しかし実務者(一部研究者にも)には,なかなか理解してもらえなかった。
一つだけ留意しておきたい。1節に記した(B)の何らかの基準は,サローの仕事競争モデルにおいては,(期待)訓練コストの多寡である。ひくいほうが優位に立つ。急いで限定をつければ,どの背景となる特性(background characterisics)が,訓練コストの違いとなり差が生まれるかについて企業がどのように判断しているか,の明示的な説明はない。もし,それが曖昧であったり,根拠のない基準であれば,統計的差別理論による説明も,かぎりなく「偏見説」に近づく。
偏見説の立場では,差別解消のための施策は,基本的に差別意識をなくすための啓発になる。経営者であれ従業員であれ,場合によっては,社会の構成員全体の意識が変わることによって,差別がなくなる。黒人は白人と変わらない,女性も男性と基本的に同じであるという意識をもつように,様々な機関が啓発をおこなうことに尽きる。
一方,統計的差別論の立場からすると,とるべき施策は異なる。経営者は偏見なく客観的に技能や潜在能力を評価しているから,啓発による効果は,限定的である。統計的差別の解消に有効な施策は,もし2つのグループに能力や定着度のばらつきの違いがあれば,その違いをなくす対策を施すことである。
もし黒人の能力分布が低いところに集中していれば,労働市場に入る前の能力,たとえば教育水準を上げて白人なみにするといった施策が有効になる。米国の大学入試における「アファーマテイブ・アクション」が,それにあたる。
男女間格差の場合は,人種間格差よりも論理的には差別解消策の実施は難しい。もちろん教育水準で男女差があれば,黒人の場合と同じように女性の教育水準を引き上げることが有効である。しかし,かりに学歴などが同じになっても統計的差別は生じる。女性が男性より結婚・出産で辞める確率が高いためである。とくにILMが発達している企業においては,人的資本投資が回収されるころに辞められる確率が高いと女性を劣位におく。サローのいう「仕事待ち行列」で後方のほうにランクづけられてしまう。つまり,その他の条件が同じであれば,男性より採用される人数が少なくなる。
この状況をどう突破するか。端的に言えば,女性の定着度を男性と同じにすればよい。そのためには,基本的にファミリー・フレンドリー企業への展開を促すことである。企業自身でその動きが不十分であれば,政府が女性の就業継続支援策を行う。そこで注目されるのが,「ポ【240頁】 ジテイブ・アクション」(PA)である。
PAについては,国あるいは自治体により,規制の強いものと緩やかなものがある。もっとも強いのは,たとえば採用の一定割合を女性にする,管理職の一定割合を女性にする,それをしないと罰則を科すといったものがある。米国などのアファーマテイブ・アクションである。ただ,これは「割り当て制度」(Quota System)に近いものであり,PAとは異なる。PAは基本的に,企業にアクションを起こしやすいように誘導するものである。しかしながら,女性の一定割合に達していない企業は,入札に参加できない,とか入札で不利になる,といった条件をつければ,実質上,割り当て制度に近いものになる。米国の連邦政府と契約する企業への条件として上記のようなものがあり,州によっては,より厳しいものがある。わが国は法レベルでは,先進国ではもっとも緩やかなPAとなっている。ただ調達企業の決定にさいし,女性活用やワーク・ライフ・バランス(WLB)施策の導入度合いなどを重視するPA的なやり方が,自治体レベルでは存在する。
いくつか労働市場以外で起こる「統計的差別」をみてみよう。
不動産(賃貸)市場
住居・土地を購入したり,典型的には賃貸市場で起こる「差別」である。たとえば,中国人が日本で部屋を借りる場合,日本人よりも高いという話をよく聞く。少なくとも敷金・礼金が高いという現象である
単純に国籍差別・民族差別だという見方もあるが,家主側からみると合理的側面もある。中国人のほうが平均して家賃未払いになる確率が高くなりやすいとか,部屋を汚しやすいという理由である。一見もっともそうな理屈だが,まじめで清潔好きな中国人からすれば,同じ物件なのに,なぜ日本人より高い家賃を支払わねばならないなのか釈然としない。家主が統計的証拠にしたがって行動しているのに,「個人」は「差別」をうけていると感じる。ひいては,外国人差別だと訴えるケースがあるかもしれない。
あきらめの境地で,こんなものだと納得すると,問題は生じない。かつて日本人が外国の先進国で同じ屈辱?を経験した人も多いだろう。いずれにしろ不動産市場における差別は,表面化しなくとも潜在的に大きな問題をはらんでいる。現実的には,同じ地域に様々な人種が住むよりも,一つの地域に同じ国籍のものが多く住み,問題が顕在化しないのかもしれない。いわゆる「居住分離」である。しかし,これでは共生社会とか多様性を尊重する社会という理想からは,程遠いであろう。
自動車保険
つぎに,ほとんど実際には問題となっていない「統計的差別」の例をみよう。任意の自動車保険の例である。平均的な年齢別事故確率にしたがって,年齢別に保険料が異なるのが通常である。若者は高く,中高齢者は低い。なかには安全運転を心がけ,運動能力の高い若者がいても,平均的な若者の事故確率から,高い保険商品しかない。
現実には,支払えないほどの保険料であれば任意ゆえに加入しない選択をとる若者が多いのであろう。しかし,年齢によって保険料に差があることに疑問をいだくものは少ないようにみ【241頁】 える。このケースは冒頭で述べた「差別は,当事者がどう感じるか」によって規定されるという議論につながるものである。同じ「統計的差別」の構造のもとでも,案件により,反応の仕方や意識が異なる典型的な例である。
年金
同じ保険であるが,自動車保険よりつよく生活にかかわる年金のケースをみよう。米国の男女差別の一つとして,年金保険料の差の裁判をみる。判決は男女差からの観点のものだが,被告の主張は,「統計的差別」に基づくものである。
1978年のマンハート事件で,ジリアン・トーマスの著書『雇用差別と闘うアメリカの女性たち』(中窪裕也訳)の第3章のなかで紹介されている。12000人の労働者を抱えるロサンゼルス市水道電力局(DWP)では,制度加入が義務とされており,いわゆる「企業年金」において,女性労働者に対し,男性よりも15%高い掛け金を払わせていた。支給される年金額は男性と同じである。使用者側の説明は,「集団として見れば,女性のほうがより長期にわたって受給する。そこで,女性という集団に属する労働者は,在職中に給与から,その差額分を埋め合わせるための拠出を求められる」(訳91頁)というものであった。
あまりにも稚拙な論理とはいえ,保険原理にのっとった「合理性」にもとづく論理である。いうまでもなく性別基準にもとづく「統計的差別」がおきている。背景には,先進国ほぼすべてにみられる平均余命の男女差がある。
原告のマンハートを支持する意見書が多く紹介されている。労働組合のUAWやAFL=CIOは,「今日の年金制度は,すでにほとんどが,女性により高い掛け金を支払わせるのをやめており,かつ,退職後に女性に支給される年金額をより低くもしておらず,それで問題なく運営されている。今でも男女で異なる制度をとっているのは,主に教育施設と政府機関である」という(訳110頁)。その当時の米国の状況を知るには貴重な情報である。また女性平等行動連盟と女性数学協会の共同提出した意見書によれば,「DWPが用いた保険数理は女性の平均寿命の長さを過大に考慮しており,65歳を超えて生きる男女のうち84%が同じ年齢で死亡している」「より高い掛け金を支払わされている女性労働者が,その分の恩恵を受けるまで長生きするのは16%にすぎない」。この保険数理の議論が,どれだけ確実に正しいかを判断する能力は筆者にはないが,平均と分散の違いを意識したものであろう。
また全米大学教授協会のメンバーの多くは,教職員保険年金協会・大学退職株式基金が運営する年金制度に加入していたが,その年金,生命保険のいずれにおいても男女別の死亡率表がもちいられていた。そして「男女同じ額の拠出を行っていたが,平均寿命が長いという理由から,女性のほうが支給額が低く定められていた。」この案件も当時訴訟中であったようだ。
あと双方の主張が詳細に紹介されているが,連符最高裁の判決は「2000人の労働者に対し,女性であることを理由に,他の1万人の労働者よりも高い掛け金を基金に支払うことを求める雇用上の制度は,(公民権法)第7編の文言にも政策にも真っ向から反する」と賛成の判事は述べ,多数意見となった。「第7編の基本理念は,我々は種類でなく個人に対する公正さに焦点を当てなければならない」「保険上のリスクがプールされる場合には,常にリスクの低いほうからたかいほうへと金銭的な補助がなされることになる」(訳115頁)
繰り返すが,専門の保険理論の見地から。この議論が,民間でも公共でも正しいのかどうか正確に判断することを筆者はできない。ただ個人でみる場合と集団でみる場合とで論理が大き【242頁】 く異なることが,わかる。本来の「統計的差別」の議論そのものである。
この判決の影響も記してある。最高裁判決から5年以内に,24の州の年金制度を,性中立的な保険数理表を用いる形に変更された。1978年以前から性中立であった13州から大きく増加した(訳116頁)。ただ最後に,つぎのような記述がある。
「第7編が適用されない一般の民間保険の市場には,影響を及ぼさなかった。その領域についても男女の不平等を是正する連邦の法律を制定しようという努力が,再三にわたってなされたが,保険業界の抵抗により,失敗に終わっている。」(117頁) 「保険数理の原則」により利益をあげる保険業界が抵抗するのはよくわかるし,現在の米国では,それが改善されているのかもしれない。筆者の不勉強で現在の状況や,もし変更されていたときの論理がわからないが,労働市場における「統計的差別」を考察するうえで,かなり参考になると思われる。
情報の不完全性あるいは情報の非対称性のもとで作成された理論モデルを実証するのは,一般的に非常に難しい。理論展開の推論プロセスにおいて,「観察されないもの」が多く,実証にならないケースが多いためである。
たとえば,教育経済学の分野で,高等教育の役割を考察するうえで,大きく2つの考え方がある。ベッカー流に人的資本を向上させるものと,スペンス流の「選抜装置(機能)」とみなすものである。後者は,シグナリング仮説とよばれる。どちらも労働市場とおおきく関係する。しかし,どちらの仮説にたとうと,どちらも高い教育ほど収入があがるので,実証はかなり難しい。具体的な教育内容とその教育が職場においてどれだけ仕事に役立っているかを丹念に調べるしかない。現在そのような研究もあらわれて決着がついているのかもしれないが,寡聞にして筆者は知らない。
同じことがいえるのは,差別現象をとらえるときにも起こる。原因(メカニズム)とアウトカムがわかっても実証困難な面が大きいからである。偏見と統計的差別を(あるいは差別は存在しないという議論も)区別できるような指標や実験がないかぎり,実証したことにはならない。
田中(2023)は,統計的差別についての実証?研究をサーベイしているが,少なくとも日本の研究は,偏見説と対比しての「統計的差別」を検証したものとはいえない。実証結果は,偏見や好みでも,解釈できるからである。
米国については,おもに人種おおむね黒人差別の研究を紹介している。たとえば,入職段階における差別禁止を導入したタイミングが州により異なるので,それを利用している。たしかに,州による制度導入のタイミングの違いは,その州の企業や労働者の差別意識というよりも,制度導入そのものの効果を測定しているという意味で客観的に「統計的差別」を検証しているともいえよう。いわゆる「自然実験」的な手法といえよう。
ただこれでもって,偏見説と比較した形で「統計的差別」が実証できたとまでは,いえないであろう。内在的批判でないので,これ以上はコメントしない。
ある時点での状況を分析できるかどうかよりも,差別のメカニズムを考えることこそ重要である。つまり,差別メカニズムを知ることが,差別がなくなるプロセスをも展望できる。そのためには歴史分析が必須のように思える。
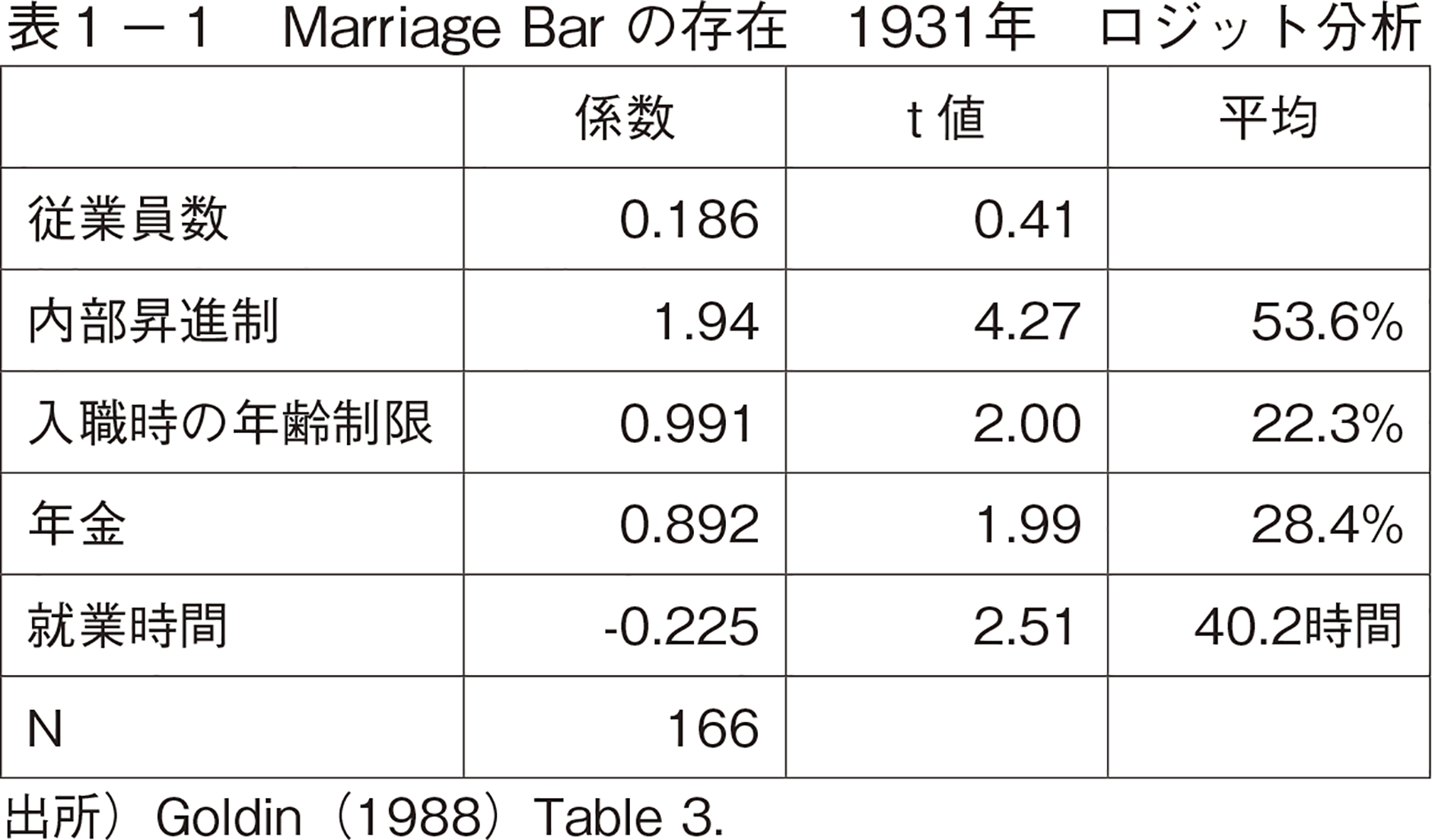
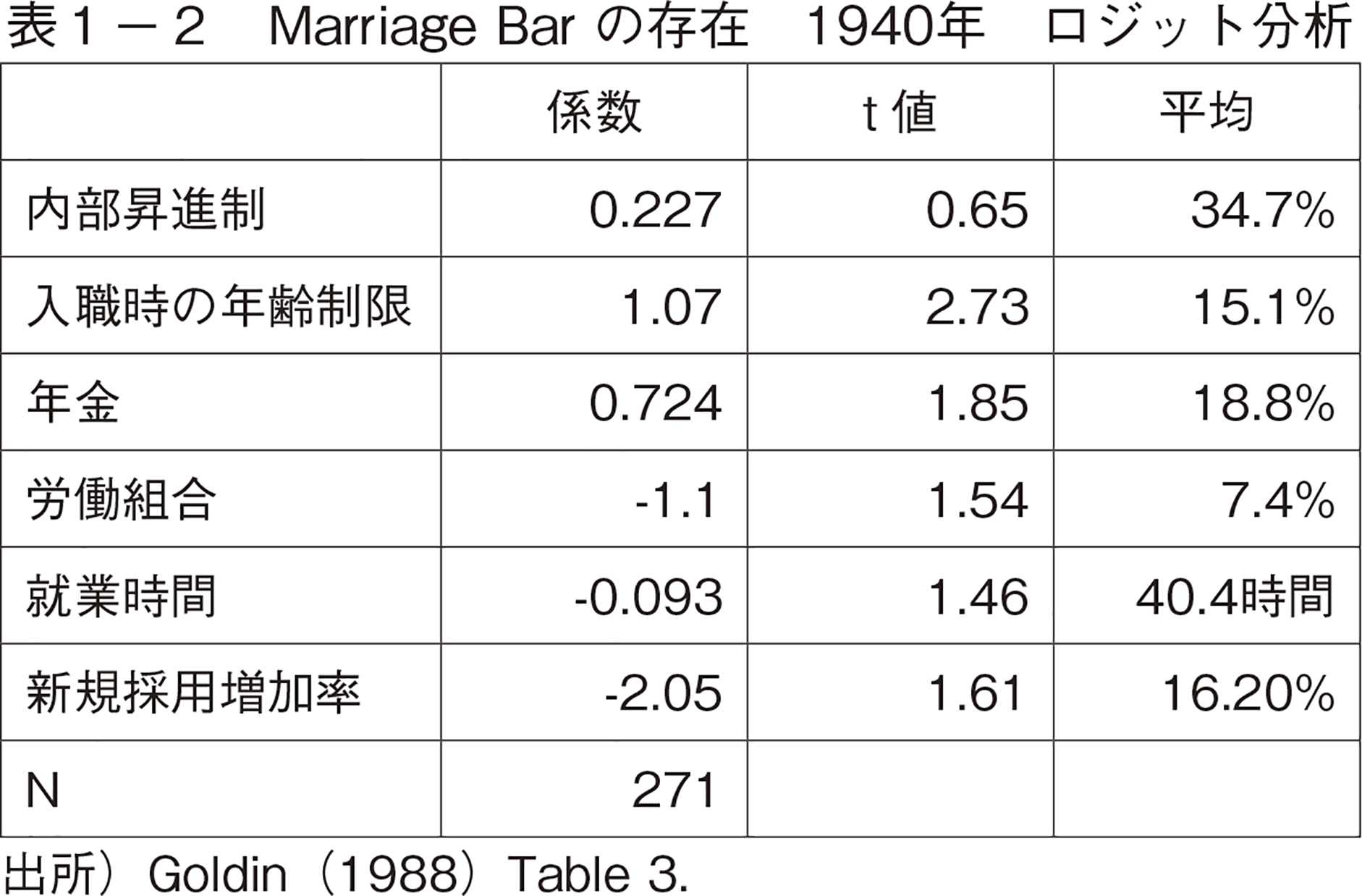
2023年のノーベル経済学賞は,経済史そして労働経済学者のクローデイア・ゴールデインが受賞した。筆者は,彼女のMarriage Barの研究(Goldin 1988)に驚いたことがある。米国にも,結婚退職制は存在し,そのデータを収集した研究者がいたことだ。Marriage Barは,日本流にいえば,結婚退職制となるが,正確に言えば,既婚女性の採用をしないケースもあるので,「結婚の壁」といったほうがいいかもしれない。
米国の1920-1950年代におけるフィラデルフィアやロサンゼルスの教員や事務職のデータを入手し,分析している。1940年代までは,結婚すれば退職する規則(慣行)が5割程度の組織に存在し,既婚女性を雇わない組織が7−8割あった。まず,1931年のデータを用いてロジット分析を行っている(表1−1)。内部昇進制のある組織ほど,入職時の年齢制限をしている【244頁】 組織ほど,就業時間が短い組織ほど,Marriage Bar が存在する。サンプル数が166と少ないとはいえ,貴重な発見である。1940年データによる分析結果が表1−2である。
その後,1950年代以降,Marriage Bar はなくなっていくが,その原因を法律や差別意識の消滅に求めていない。1950年代以降の労働力人口構成の変化にその原因を求めている。つまり女性を本格的に活用,未婚者も既婚者も継続雇用し,採用しなければなくなったマクロの労働市場の構造変化が原因である。つまり,差別がなくなったわけではない。労働力不足(labor squeeze)が起こったのである。
Goldinは,偏見(嗜好)でも統計的差別でも,理論的には,長期的に差別がなくなる方向にすすむことがありうるとしている(Goldin 1990;p.89)。偏見が消えていくプロセスはアローの論理とほぼ同じだが,統計的差別においては,「経営者が有能な者とそうでないものを区別する(discern the able from the less able)能力が高まり差別がなくなる」という道筋を考えている。
彼女の中心とする議論は,歴史資料からは,「競争」が差別を解消する方向に進んでいない,これはどちらのモデルでも同じである,という点にある。筆者は,この2つのモデルは同列に論じられないと思う。情報の非対称性にもとづく統計的差別が,競争により情報の精度が増すという議論にみえるが,筆者の考えは,本質的に,それはいくらコストをかけても難しい。ゆえに差別構造や差別の再生産は,統計的差別をベースにとらえるべきだと思っている。
差別の再生産が起こる論理やそれが消え去っていくプロセスをみるうえで歴史研究こそ重要であることを考えさせられる事例である。一時点の差別があるか否かを判定する研究でなく,差別が再生産されるプロセスを知る研究こそ望まれる。
Goldin, Claidia (1988)”Marriage Bar :Discrimination against married women workers,1920’s to 1950’s”, NBER Working Paper No.2747
Goldin, Caidia (1996), Understanding the Gerder Gap : An Economic History of American Women. NY : Oxford University Press.
Thurow, Lester (1975), Generating Inequality. NY : Basic Books.
レスター・サロー(1984)『不平等を生み出すもの』(小池和男と共訳)同文舘
ジリアン・トーマス(2020)『雇用差別と闘うアメリカの女性たち』(中窪裕也訳)日本評論社
神戸伸輔(2004)『入門ゲーム理論と情報の経済学』日本評論社
田中喜行(2023)「経済学からみた選抜と労働問題─統計的差別を中心に」『日本労働研究雑誌』756号
脇坂 明(1980)「労働市場における差別(1)(2)─レスター・サロウの「ジョブ・コンペテイション・モデル」の意義について」『京都大学経済論叢』125巻1/2号,125巻5号 1980年1月,5月
脇坂 明(1998)『職場類型と女性のキャリア形成・増補版』御茶の水書房
脇坂 明(2023)「OJT再考⑵」『学習院大学経済経営研究所年報』37巻(27-52) 2023年12月