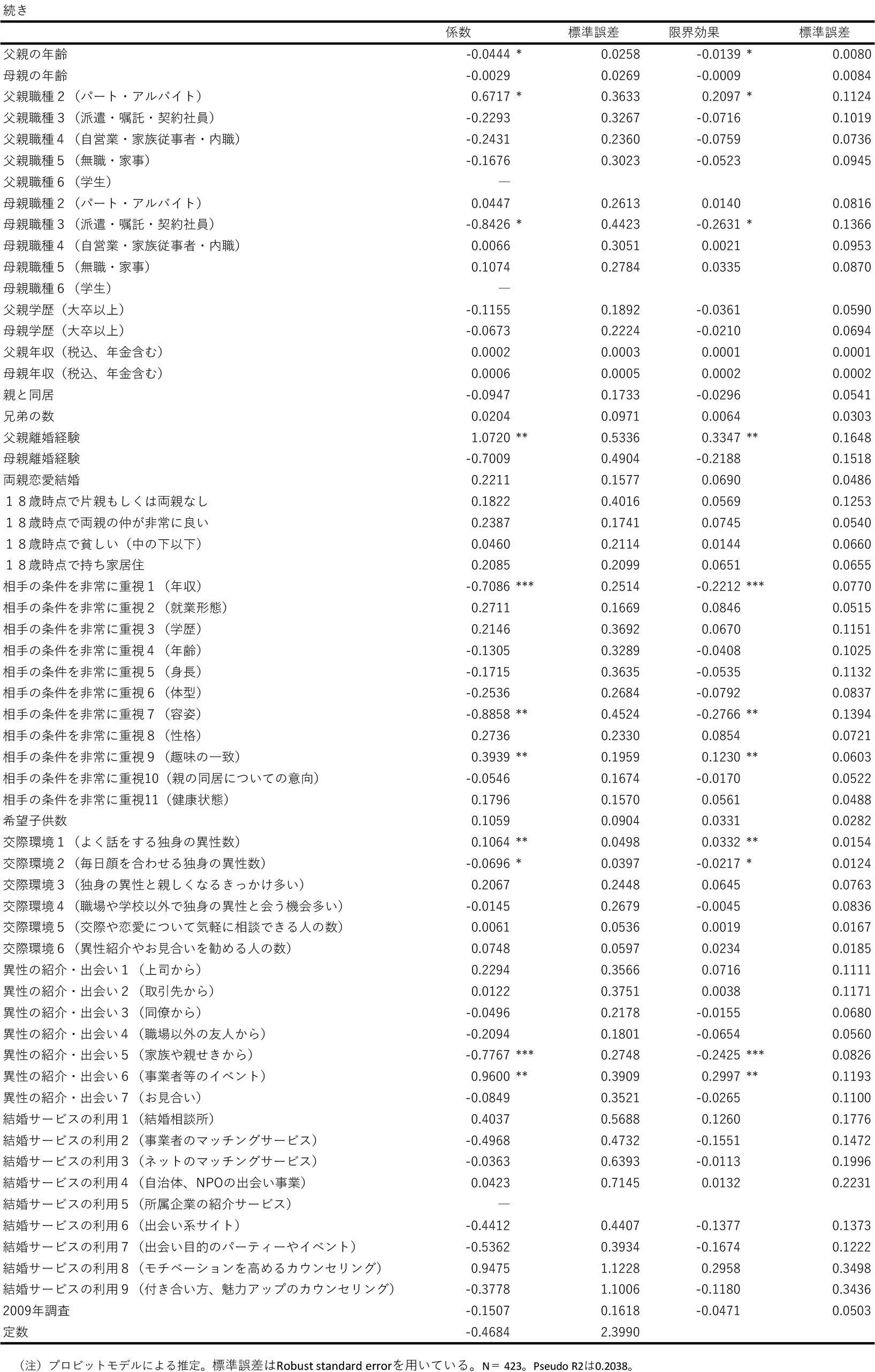���{�l�����ɂ����錋�����̌��ۑ����
�L���Ɋւ��铝�v����
��@�j
�{�e�́C�M�҂炪�Ǝ��Ɏ��{�����u�����ςɊւ���A���P�[�g�v�̌[�f�[�^��p���āC��i2024�j���s�������{�l�����̌����̌���v���Ɋւ��镪�͂Ƃقړ����t���[�����[�N���g���C�������̌��ۑ��肪���錈��v����T�����B
�L�q���v�x�[�X�Ŋe�ϐ����ώ@�����ۂɂ́C�����̌���v���ƈقȂ�����͂���قǑ����Ȃ��������C�v���r�b�g���f���ɂ�鐄����s���ƁC�L�ӂȕϐ��́C��i2024�j�ɔ�i�i�ɏ��Ȃ��C����W�����Ⴍ�Ȃ����B�����Ƃ��C���̌X���͐�s���������l�ł���B
�L�ӂƂȂ����ϐ��ɂ��āC�����I�ȓ_���������s�b�N�A�b�v����ƁC�܂��C�O���Ɋւ��ẮC�얞�̏ꍇ�ɁC�������l���Ă�����ۑ��肪����m������������B�E��Ɋւ��ẮC���K�E���ɔ�ׂāC�p�[�g�E�A���o�C�g��C���c�ƁE�Ƒ��]���ҁE���E�̏ꍇ�ɁC�������l���Ă�����ۑ��肪����m������������B�w��������C�e���Y�͗L�ӂł͂Ȃ��C�ނ���C�d���̌p���N���������قǁC�������l���Ă�����ۑ��肪����m���������Ȃ��Ă���C�����̌���v���Ƃ��ďd�v�ł������@���p�����͓��Ă͂܂�Ȃ��悤�ł���B�}�b�`���O���Ɋւ��ẮC��i����̏Љ����ꍇ�C���Ǝғ��̃C�x���g�ɎQ������ꍇ�C���`�x�[�V���������߂�J�E���Z�����O����ꍇ�ɁC�������l���Ă�����ۑ����m���������B
���߂�����ϐ������Ȃ��Ȃ����C������ɂ���C�����̌���v���ƁC�������̌��ۑ��肪���錈��v���̊Ԃɂ́C���قȂ郁�J�j�Y�������݂���\��������B
���q���C�����C�����C���ۑ���C�}�b�`���O
2022�N�̉䂪���ɂ�������{�l�̏o������77��747�l�ƁC�O�N��81��1622�l���S���l�ȏ���������C�ߋ��Œᐔ���X�V�����i�}�\�P�j�B2023�N�̏o�������C�O�N��łS���l�ȏ�̌����ƂȂ邱�Ƃ������܂�Ă���C���q���̐i�s�Ɏ��~�߂�������ʏ������Ă���B�����������C���{��2024�N�Q���ɁC�����蓖�̑Ώۊg���z�C���������̓P�p�C���e�Ƃ��Ɉ�x�擾�����ꍇ�̈�x���t���̎x���������グ�C���ǂ��N�ł��ʉ����x�̑n�݂Ȃǂ��琬��u���q����Ɋւ�������@�āv���t�c���肵�C�u�َ����̏��q����v�Ɩ��ł�^��ɒ��肵���Ƃ���ł���B
�y52�Łz�������Ȃ���C�悭�m����悤�ɁC�䂪���̏��q���̎���͍������̒ቺ�ɂ���C�u�َ����̏��q����v���C������ɑS�����ݍ���ł��Ȃ����Ƃɂ͑傫�Ȍ��O������B���ہC�䂪���̍��������C�������͋ߔN�C�ቺ�̈�r�����ǂ��Ă���C���ɃR���i�Ђ̒��ŋ}�������B�䂪���́C�`���I�ɔo�q�̊������������C�������Ȃ��Ǝq�ǂ����o�Y���Ȃ������Ȃ̂ŁC���̍��������C�������̌����͔��ɐ[���Ȗ��ł���B���q���Ɏ��~�߂�������ɂ́C�������㏸�̗v�����𖾂��C����ɑ��������s���邱�Ƃ��d�v�ł���B
���̂悤�Ȗ��ӎ�����C�M�҂͊��ɗ�i2024�j�ɂ����āC�M�҂炪�Ǝ��Ɏ��{�����u�����ςɊւ���A���P�[�g�v��p���āC���{�l�����̓Ɛg�҂���ъ����҂̃f�[�^���v�[�����C�����̌���v���͂����B���̌��ʁC�����̌���v���Ɋւ��鏔�����𗠕t����l�X�ȕϐ������v�I�ɗL�ӂƂȂ邱�Ƃ��킩�����B�܂��C���ݓI�Ȍ��ۑ��肩�猩�����Y�����̖��́i�����ʁj�ɂ��ẮC�얞�C�e�p�̈����C���a������ꍇ�ɁC�����m�����ቺ����B�܂��C�����C�p�`���R�E�p�`�X���C�P�`�ƌ������K�����������Ƀ}�C�i�X�Ɋ�^����B�E��Ɋւ��ẮC�E�������Ȃ��ꍇ�ɔ�ׁC�E������قnj������͍��܂�C���K�E���C�p�[�g�E�A���o�C�g�C�h���E�����E�_��Ј��̏��ɁC�����������܂�B����C���v�ʂɂ��ẮC�呲�ȏ�̊w���̏ꍇ��d���̌p���N�������܂�قǁC���������ቺ���錋�ʂƂȂ��Ă���C�����̋@���p�����܂�قǁC�������Ȃ��Ȃ鉼���Ɛ����I�ł������B�܂��C�����̒ʋΎ��Ԃ������قǁC��V���ȍ~�C���X���ȑO�̏A�Ǝ��Ԃ������قǁC�����m�����Ⴍ�Ȃ邱�Ƃ���C���ԓI������d�v�ȗv���ƍl������B���̂ق��C���e�������������Ă���ꍇ�Ɍ����������܂�C��e�ɗ����o��������ƌ������͒Ⴍ�Ȃ邱�Ƃ���C�������v�ɁC���e����̃f�����X�g���[�V�������ʂ����݂��邱�Ƃ��������ꂽ�B����ɁC�}�b�`���O�̊��ɂ��ẮC����������킹��Ɛg�ِ̈����������قǁC�E���w�Z�ȊO�œƐg�ِ̈��Ɖ�@������قǁC�����������܂邱�ƂȂǂ����������B
�����C��i2024�j�̃A�v���[�`�́C�����҂ɂ��ẮC���������C���邢�͌����O�̏��v���o���ĉ��邱�ƂɂȂ��Ă��邽�߁C�ߋ��̐U��Ԃ�f�[�^�ɔ�����ڃo�C�A�X�����݂��邱�Ƃ��ے�ł��Ȃ��B�����ŁC�{�e�́C�����̃G�r�f���X���C�ʂ̊ϓ_����T�|�[�g����邩�ǂ�����T�邽�߁C��ڃo�C�A�X�̂Ȃ��Ɛg�ҁi�����j�݂̂ɃT���v�������肵�C�������l���Ă�����ۑ���̗L���ɂ��āC���̌���v���͂��邱�Ƃɂ����B�������C�������l���Ă�����ۑ��肪���邩��ƌ����āC���ꂪ���̌�C�����Ƃ������ʂɂȂ��邩�ǂ����͂킩��Ȃ��B�������҂���������ƂȂ�܂łɂ͗l�X�ȃn�[�h�������邱�Ƃ͗e�Ղɑz���ł���B�������Ȃ���C���Ȃ��Ƃ����҂ɂ͋������ւ�����ƍl�����邵�C�����Ƃ������ʂɌ��т�����O�̒i�K�͂��邱�Ǝ��̂ɂ��C��������l�����ŏ\���ȈӋ`������Ǝv����B
���āC��i2024�j�ł́C�䂪���ɂ����āC�����Ɋւ���o�ϕ��͂����܂葽���Ȃ����Ƃ�����Ă��邪1�j�C���ۑ���̗L���Ɋւ��镪�͂Ƃ��Ȃ�ƁC����ɏ��Ȃ��̂�����ł���B�y53�Łz �킸���ȗ�O���C���X�i2012�j�C�����i2015�C2016�j�ł���B���X�i2012�j�́C�o�ώY�ƏȂ̌�������{�����C���^�[�l�b�g���j�^�[�̃A���P�[�g�����i�[�f�[�^�j�̂����C�j���݂̂̃T���v����p�������͂��s���Ă���B��̓I�ɂ́C���ۑ���̗L�����C�����ӗ~��o��̋@���ʂ������[�g�Ɣ��ɓ������肷���@�i���J�[�V�u�Q�ϗʃv���r�b�g���f���j��p���Ă���B���ۑ���̗L���Ɋւ��ẮC�����ӗ~��Ɛg�ِ̈��Ɛe�����Ȃ邫�������̑����̂ق��C���������̍����C�w���̍�����N��̒Ⴓ�Ȃǂ����̉e�����y�ڂ����Ƃ���Ă���B�ٗp�̕s���肳�i�K�ٗp�j�ɂ��ẮC���ڌ��ʂƊԐڌ��ʁi�����ӗ~��o��̋@���ʂ������[�g�j�ŕ������t�]����ȂǁC���܂薾�m�Ȍ��ʂ��ώ@����Ă��Ȃ��B
����C�����i2015�j�́C���҂��Ǝ��ɖ����̒j���ɑ��Ď��{�����C���^�[�l�b�g�A���P�[�g�̌[�f�[�^�͂��C�T�D���łɗ��l�܂��͍���҂�����O���[�v�i�������A�^�j�C�U�D���l���~�����Ǝv���Ă���C�o����߂ɉ��炩�̊��������Ă���O���[�v�i�����T�[�`�^�j�C�V�D���l���~�����Ǝv���Ă��邪�C�o����߂ɉ��̊��������Ă��Ȃ��O���[�v�i���������g���A���^�j�C�W�D���l��~�����Ǝv���Ă��Ȃ��O���[�v�i�������S�^�j�̂S�ɗތ^�����s������ŁC�����T�[�`�^�C���������g���A���^�̂Q�ތ^�̒j���ɑ��āC�v�ʓI�ȕ��͂��s���Ă���B���ތ^�Ƃ��C�K���ȑ���ɏ��荇��Ȃ��m���ɑ��āC�j���̔N��e���������C�����̒Ⴓ�͉e����^���Ă��Ȃ��B����C�����T�[�`�^�ɂ����āC�ِ��Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����\�͂�X�N�ɑ���I�D���e�����Ă��邱�Ƃ������[���B����C�����i2016�j�́C���ۑ���̃T�[�`�s���Ɛ摗��s���̊W���C�s���o�ϊw�̊ϓ_����C�o�ώ��������{���ĕ��͂���Ƃ��������������ł��邪�C�{�e�Ƃ͒��ڂ̊ւ�肪���������ł��邽�߁C�ڂ����͐G��Ȃ��B
�����Ɋւ���v�ʓI���͂Ƃ����Ӗ��ł́C�Љ�w�̕���ōs��ꂽ�v�ʓI��������Ϗd�v�ł���B�����E�����i2010�j�́C���X�i2012�j�Ɠ��l�C���҂̈�l�i�����������j�������߂��o�ώY�ƏȂ̌�������{�����C���^�[�l�b�g���j�^�[�̃A���P�[�g������p�������͂��s���Ă���B�j���ʂɁC���l�̗L�������W�X�e�B�b�N�E���f���ɂ�蕪�͂������ʁC�j���ɂ��Ă͔N���C��ƋK�́C�E��̓Ɛg�ِ��̐l���C�F�l�t�������̕p�x���C���ݗ��l�����邱�Ƃɐ��̉e�����y�ڂ��C�����ɂ��ẮC�p�[�g�J���Ƌx���o�̕p�x�i�̒Ⴓ�j�����̉e�����y�ڂ��Ă��邱�Ƃ�����Ă���B�j���ԂŁC���ۑ��肪����v�����傫���قȂ邱�Ƃ�������Ă���_�������[��2�j�B�܂��C���сi2023�j�́C���҂炪�Ǝ��Ɏ��{�����ߋ��̐U��Ԃ�A���P�[�g�����ɂ���āC�n���Ɖߋ��ɕt�����������l�l���Ȃǂ̊W�͂��Ă���B���͂̌��ʁC�j���̏ꍇ�ɂ͌��݂̕n�������l�l����W�l���ɕ��̉e�����y�ڂ��C�����̏ꍇ�ɂ�15�Ύ��ɐ������ꂵ���ꍇ�ɁC�t�ɗ��l�l���C���W�l�����������邱�Ƃ���Ă���B
�����C�o�ϊw���邢�͌o�ϊw�̊ϓ_������d�v�ȎЉ�w�̌v�ʓI���������Ȃ��Ƃ͂����C�Ƒ��Љ�w��l���w�̕���ł́C��������ۂ��d�v�ȕ��̓e�[�}�ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�y54�Łz ���R�̂��ƂȂ���C�䂪���ɂ����Ă��C�������̌������s���Ă���B�����͖{�e�̕��͂ƒ��ڂ̊W���Ȃ����߂ɂ����ł͏Љ�Ȃ����C��r�I�ŋ߂̏d�v�ȕ����ɂ��ẮC�i�c�E�吙�i2019�j���O�O�ȃT�[�x�C���s���Ă��邱�Ƃ�G��Ă��������B
���āC�{�e�́C���{�l�����̌����̌���v����T������i2024�j�Ɠ����f�[�^����уt���[�����[�N��p���āC�Ɛg�����ɂ����錋�����̌��ۑ���̗L���Ɋւ��錈��v���̕��͂��s���B�����̌���v���Ɣ�r���ĉ����قȂ�C�����قȂ�Ȃ�����m�邱�Ƃ��傫�ȖړI�ł���B
�ȉ��C�{�e�̍\���͎��̒ʂ�ł���B�Q�߂ł́C�{�e�ŗp����f�[�^�̐������s���B�R�߂́C�����ƕ��̓��f�������B��S�߂ł́C�܂��͕\�ɂ���āC�������l���Ă�����ۑ��肪����l�Ƃ����łȂ��l�̊ȒP�Ȕ�r���s������ŁC��A���͂��s���B�T�߂͌���ł���B
�{�e���p���Ă���f�[�^�́C�����Â����C�M�҂炪�Ǝ��Ɏ��{�����u�����ςɊւ���A���P�[�g�v�̌[�f�[�^�ł���B���̃A���P�[�g�����́C2008�N�Q���ɓƐg�҂̒j���y�ъ����҂̏�����ΏۂɗX�������@�ōs��ꂽ���̂ł���B�Ώ۔N���20����45�C�Ώےn��͑S���ł���3�j�B�T���v�����́C2008�N�̒����œƐg��1155�C������535�ł���B�܂��C���̒�����2009�N�R���ɉ��߂āC�S�����������[��p���Ēlj����������{���Ă���C�Ɛg��568�C������586�����W����Ă���B�{�����ł́C2008 �N������2009�N�����̓Ɛg�҂̏����ɃT���v���������ĕ��͂��s�����Ƃɂ���B
���̒����̓����́C�ɂ߂đ����̌l�����⌋���ɑ�����C�ӎ���q�˂Ă��邱�Ƃł���B�{�e���p���鏔�ϐ������݂Ă��C�N��C�{�l�w���C�w�̍����̎��ȕ]���C�얞�x�̎��ȕ]���C�e�p�̎��ȕ]���C���N�̎��ȕ]���C���a�̗L���C�ۗL���Z���Y�i���~�j�C�ؓ����i���~�j�C�������Y�i���~�j�C�����łł���Ǝ��i�|���C����C�H�����C�H��C�������C�������ځC�A�C���������C�玙�C�S�~���ʁC�q���̑��}�C���j�C�����K���̗L���i�i���C�����C���n�E���ւȂǂ̃M�����u���C�p�`���R�E�p�`�X���C���C�ȁC�����ȁC�؋��ȁC�Q��ȁC�P�`�j�C�{�l�̐E��i���K�E���C�p�[�g�E�A���o�C�g�C�h���E�����E�_��Ј��C���c�ƁE�Ƒ��]���ҁE���E�C���E�E�Ǝ��C�w���j�C������������i�ō��j�C���Y�̎d���̌p���N���C�T������J�����ԁC�����ʋΎ��ԁC��V���ȍ~�E���X���ȑO�̏A�Ǝ��ԁi�T������j�C��x�擾���̗ǂ��C�E��ɂ��鐧�x�i�Z���ԋΖ��C�����o�C�玙�x�E�C�Čٗp���x�C�t���b�N�X�^�C���C�ݑ�Ζ��j�C���e�̔N��C��e�̔N��C���e�E��i�{�l�Ɠ��l�̕��ށj�C��e�E��i���j�C���e�w���C��e�w���C���e�N���i�ō��C�N���܂ށj�C��e�N���i�ō��C�N���܂ށj�C�e�Ɠ����C�Z��̐��C���e�����o���C��e�����o���C���e���������C18�Ύ��_�ŕАe�������͗��e�Ȃ��C18�Ύ��_�ŗ��e�̒��̗ǂ��C18�Ύ��_�ʼnƒ�̗T�����C18�Ύ��_�ŏZ��C��������ɋ��߂�����Ƃ��̒��x�i�N���C�A�ƌ`�ԁC�w���C�N��C�g���C�̌^�C�e�p�C���i�C��̈�v�C�e�̓����ɂ��Ă̈ӌ��C���N��ԁj�C��]�q�����C���ۊ��i�悭�b������Ɛg�ِ̈����C����������킹��Ɛg�ِ̈����C�Ɛg�ِ̈��Ɛe�����Ȃ邫�������̕p�x�C�E���w�Z�ȊO�œƐg�ِ̈��Ɖ�@�y55�Łz ��̕p�x�C���ۂ�����ɂ��ċC�y�ɑ��k�ł���l�̐��C�ِ��Љ�₨��������i�߂�l�̐��j�C�ِ��̏Љ�E�o��i��i����C����悩��C��������C�E��ȊO�̗F�l����C�Ƒ���e��������C���Ǝғ��̃C�x���g�C���������j�C�����T�[�r�X�̗��p�i�������k���C���Ǝ҂̃}�b�`���O�T�[�r�X�C�l�b�g�̃}�b�`���O�T�[�r�X�C�����́ENPO�̏o����ƁC������Ƃ̏Љ�T�[�r�X�C�o��n�T�C�g�C�o��ړI�̃p�[�e�B�[��C�x���g�C���`�x�[�V���������߂�J�E���Z�����O�C�t���������C���̓A�b�v�̃J�E���Z�����O�j�Ȃǂ̖c��ȍ��ڂ�����B
�����̏��ϐ��ɂ��āC��i2024�j���s�����Ɛg�҂Ɗ����ҊԂ̔�r���͂Ɠ����t���[�����[�N�ŕ��͂��s�����Ƃɂ���B�܂��C�{�e�ŗp���鏔�ϐ��̋L�q���v�͐}�\�R�̒ʂ�ł���B���̒����ł́C���ۑ���̗L����q�˂鎿��̌�ɁC���̌��ۑ���Ƃ̌����̊�]��q�˂鎿�₪����B�����Ɍ��ѕt���\���������̂́C�y�����ہC����������ړI�Ƃ�����ۂ��܂�ł���ƍl������u���ۑ���̗L���v�ł͂Ȃ��C������O��Ƃ�����^���Ȍ��ۂł���ƍl�����邽�߁C���ۑ��肪���āC�Ȃ����C���̌��ۑ���ƌ�������]���Ă���ꍇ�ɂP�C����ȊO�ɂO���Ƃ�u�������l���Ă�����ۑ���̗L���v�Ƃ����ϐ������C��ȕ��͑ΏۂƂ���B�}�\�S�̋L�q���v�́C�������l���Ă�����ۑ���̗L���ʂɂ����̕ϐ����r���Ă���B
��i2024�j���l�C�{�e�̕��͎�@�͎����ăV���v���ł���B������ϐ��Ƃ��āu�������l���Ă�����ۑ���v������ꍇ�ɂP�C���Ȃ��ꍇ�ɂO�Ƃ���v���r�b�g���f�����C�l�X�Ȍl��������E�ӎ��ϐ�������ϐ��Ƃ��Đ��肵�C���̂悤�Ȍ��ۑ��肪����v����T��Ƃ������̂ł���B
��i2024�j�ŏڂ����q�ׂ��悤�ɁC�����̌���v���Ɋւ��ẮC�@�������̗v���C�A���v���̗v���C�B�o��̌o�H�i�}�b�`���O�E�V�X�e���j�̂R�ɑ傫�����ނ���邪�C�������l���Ă�����ۑ��肪���錈��v�����C���l�̃t���[�����[�N�ōl���邱�Ƃɂ���B
�{�e���p���鏔�ϐ��Ɉ����čl����C�@�������̗v���Ƃ́C���ݓI�Ȍ��ۑ���i�j���j���猩�����͑Ώہi�����j�̖��͂�\�������ϐ��ł���B�܂��́C�O���̎��ȕ]���ł���B�w���Ⴂ�i�T�i�K�]���̂����C������Q�j�C�얞�i�T�i�K�]���̂����C������Q�j�C�e�p�����i�T�i�K�]���̂����C������Q�j�C���N�����i�T�i�K�]���̂����C������Q�j�C���a����ƌ������ϐ������邪�C�����Ƃ��ẮC�S�ĕ��̌W�����\�z�����B�܂��C�����łł���Ǝ��i�����łł���Ǝ��P�i�|���j�C�����łł���Ǝ��Q�i����j�C�����łł���Ǝ��R�i�H���j�C�����łł���Ǝ��S�i�H��j�C�����łł���Ǝ��T�i�������j�C�����łł���Ǝ��U�i�������ځj�C�����łł���Ǝ��V�i�A�C���������j�C�����łł���Ǝ��W�i�玙�j�C�����łł���Ǝ��X�i�S�~���ʁj�C�����łł���Ǝ�10�i�q���̑��}�j�C�����łł���Ǝ�11�i���j�j�ɂ��ẮC�Ǝ����ł���قnj�������Ƃ��Ă̖��͂������ƍl�����邱�Ƃ���C���̌W�������҂ł���B
����ɁC���������K���̗L���i�K���P�i�i���j�C�K���Q�i�����j�C�K���R�i���n�E���ւȂǂ̃M�����u���j�C�K���S�i�p�`���R�E�p�`�X���j�C�K���T�i���C�ȁj�C�K���U�i�����ȁj�C�K���V�i�؋��ȁj�C�K���W�i�Q��ȁj�C�K���X�i�P�`�j�j�́C�S�Ė��͂�������ƍl�����邽�߁C���̌W�y56�Łz �����\�z�����B�{�l�̐E��i�{�l�E��P�i���K�E���j�C�{�l�E��Q�i�p�[�g�E�A���o�C�g�j�C�{�l�E��R�i�h���E�����E�_��Ј��j�C�{�l�E��S�i���c�ƁE�Ƒ��]���ҁE���E�j�C�{�l�E��T�i���E�E�Ǝ��j�C�{�l�E��U�i�w���j�j�ɂ��ẮC�{�l�E��P�i���K�E���j���x���`�}�[�N�Ƃ���_�~�[�ϐ��Ƃ��邪�C�ǂ̂悤�ȕ����ƂȂ邩�͐挱�I�ɂ͂킩��Ȃ��B�E�ɏA���Ă�������C�����l���\�͂����܂閣�͂�����ƍl����C���K�E���ɔ�ׂāC���̐E��͕��̌W�������҂ł���B����ŁC��Ǝ�w�Ƃ��ẲƎ���玙�̔\�͂ɖ��͂�����Ȃ�C�J�����Ԃ̒Z���K�̐E��E�������Ȃ��E�킪���̕����ɂȂ�\��������B
�����Ƃ��C�E��Ɋւ��ẮC�A���v���̗v���C�܂�C�{�l�̌������v�Ɋւ�������ϐ��Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B�Ⴆ�C�E�������Ă���قǁC���������⌋����̈���I�Ȑ��������҂ł��邱�Ƃ���C�������v�����܂�\��������B
���Ɏ��v���̐����ϐ��Ƃ��ďd�v�Ȃ��̂́C�@���p�Ɋւ�����̂�����BBecker�i1973�j�Ɏn�܂�o�ϊw�̕W���I���_�ł́C�����̎Љ�i�o���i�݁C������o�Y�ɑ���@���p�����܂��Ă������Ƃ��C�������ቺ��o�����ቺ�̗v���Ƃ����B�@���p��\���ϐ��Ƃ��ẮC�܂��C�w���i�呲�ȏ�j�C������������i�ō��j�C���Y�̎d���̌p���N������������B�@���p��������������C�����̐����ϐ��̌W���͕��̒l�ƂȂ邾�낤�B�����C�Ⴆ�C������������Ɋւ��ẮC��ɐE��̂Ƃ���Ő��������悤�ɁC���̒l�������قǁC���������⌋����̈���I�Ȑ��������҂ł��邱�Ƃ���C�������v�����܂�Ƃ����\��������B���̏ꍇ�́C�W�������ƂȂ邾�낤�B�{�l�̎����Z���Y�C�ؓ����C�������Y�Ƃ��������Y�Ɋւ���ϐ����C�L���Ӗ��ł̋@���p�Ɋւ���ϐ��Ƃ݂邱�Ƃ��\�ł��邪�C������������Ɠ��l�̑��ʂ����邵�C���ݓI�Ȍ������肩��݂����͂Ƃ��āC�����v���ƍl���邱�Ƃ��ł���B
����ɁC�����ԘJ����ʋɂ���āC��������T������ێ��ԂɊ����鎞�Ԃɐ�����ƁC�������l���Ă�����ۑ��肪����\�����Ⴍ�Ȃ�ƍl������B�T������J�����ԁC�����ʋΎ��ԁC��V���ȍ~�E���X���ȑO�̏A�Ǝ��ԁi�T������j���C���Ԑ���Ɋւ�������ϐ��Ƃ���ƁC���̌W���͕������҂����B���l�ɁC�������ďo�Y�������ꍇ�C��x����������擾�ł�����C�q�ǂ����ł����ꍇ�ɁC�_��ȓ��������ł���E������ǂ����Ƃ������Ƃ��C������O��Ƃ�����ۂ��s���ꍇ�ɉe������\��������B�Ȃ��Ȃ�C�䂪���̏ꍇ�́C�o�Y�ƌ������������т��Ă���C���ۂ���i�K�ł����ꂪ�e�����Ă���\�������邩��ł���B��x�擾���ǂ��C�E��̐��x�P�i�Z���ԋΖ��j�C�E��̐��x�Q�i�����o�j�C�E��̐��x�R�i�玙�x�E�j�C�E��̐��x�S�i�Čٗp���x�j�C�E��̐��x�T�i�t���b�N�X�^�C���j�C�E��̐��x�U�i�ݑ�Ζ��j�Ȃǂ̐����ϐ��́C�������l���Ă�����ۑ���������Ƃɑ��āC���̉e����^����ƍl������B
���ɁC�����̎��Ƃ̉ƒ�����C�������v�Ɠ��l�C���ۑ���̗L���ɉe������ƍl������B�Ⴆ�C���Ƃ��T���ł��邩�ǂ����C���e����E�ɂ��Ă��邩�ǂ����Ƃ������Ƃ́C����������̃T�|�[�g�����҂ł���Ƃ����Ӗ��ŁC���̉e����^����\��������B�����C�t�ɁC���ɓ������Ă�����C���e����Ɛg�����̌o�ϓI�T�|�[�g����Ȃǂ��āC�����ɑ���e���ے����f�������グ�Ă���ꍇ�ɂ́C���̉e�������邱�Ƃ��l������B���������ƒ���̐����ϐ��Ƃ��ẮC���e�̔N��C��e�̔N��C���e�E��P�i���K�E���j�C���e�E��Q�i�p�[�g�E�A���o�C�g�j�C���e�E��R�i�h���E�����E�_��Ј��j�C���e�E��S�i���c�ƁE�Ƒ��]���ҁE���E�j�C�y57�Łz ���e�E��T�i���E�E�Ǝ��j�C���e�E��U�i�w���j�C��e�E��P�i���K�E���j�C��e�E��Q�i�p�[�g�E�A���o�C�g�j�C��e�E��R�i�h���E�����E�_��Ј��j�C��e�E��S�i���c�ƁE�Ƒ��]���ҁE���E�j�C��e�E��T�i���E�E�Ǝ��j�C��e�E��U�i�w���j�C���e�w���i�呲�ȏ�j�C��e�w���i�呲�ȏ�j�C���e�N���i�ō��C�N���܂ށj�C��e�N���i�ō��C�N���܂ށj�C�e�Ɠ����C�Z��̐���p���邱�Ƃɂ���B
����ɁC�������������ĉƒ����邱�Ƃɓ��ꂪ����ꍇ�ɂ́C�����̂��߂̌��ۂւ̎��v�����܂�͂��ł���B�ƒ�ɑ��邠������́C�g�߂ȃ��[�����f���ł��闼�e�̎p���琶����\�����������߁C���e�̃f�����X�g���[�V�������ʂƂ��āC���e�����o���C��e�����o���C���e���������C18�Ύ��_�ŕАe�������͗��e�Ȃ��C18�Ύ��_�ŗ��e�̒������ɗǂ��C18�Ύ��_�ŕn�����i���̉��ȉ��j�C18�Ύ��_�Ŏ����Ƌ��Z�Ƃ��������ϐ���p���邱�Ƃɂ���B
���v�ʂƂ��ẮC��������ɋ��߂�������d�v�Ȑ����ϐ��ł���B�{�e���p����A���P�[�g�ł́C�l�X�ȃJ�e�S���[�ɂ��āC������d��������x��q�˂Ă���̂ŁC���ɏd������Ɠ������ꍇ���P�Ƃ���_�~�[�ϐ��Ƃ����B���Ȃ킿�C����̏�������ɏd���P�i�N���j�C����̏�������ɏd���Q�i�A�ƌ`�ԁj�C����̏�������ɏd���R�i�w���j�C����̏�������ɏd���S�i�N��j�C����̏�������ɏd���T�i�g���j�C����̏�������ɏd���U�i�̌^�j�C����̏�������ɏd���V�i�e�p�j�C����̏�������ɏd���W�i���i�j�C����̏�������ɏd���X�i��̈�v�j�C����̏�������ɏd��10�i�e�̓����ɂ��Ă̈ӌ��j�C����̏�������ɏd��11�i���N��ԁj�ł���B�悭������悤�ɁC����ɋ��߂�����ɂ�����肷����ƁC�����͂��납�C���ۑ���邱�Ƃ��������Ȃ邾�낤�B�܂��C��]�q�������C�q�ǂ�����������ق����l�قnj������v�������ƍl������̂ŁC�����ϐ��ɉ������B
�����ϐ��Ƃ��Ă̍Ō�̃J�e�S���[�́C�o��̌o�H�i�}�b�`���O�E�V�X�e���j�Ɋւ�鏔�ϐ��ł���B�{�e�̕��͂ɗp����f�[�^�ł́C���ۊ���ِ��̏Љ�E�o��C�����T�[�r�X�̗��p�ɂ��Đ������̎�������Ă���B��̓I�ȕϐ��́C���ۊ��P�i�悭�b������Ɛg�ِ̈����j�C���ۊ��Q�i����������킹��Ɛg�ِ̈����j�C���ۊ��R�i�Ɛg�ِ̈��Ɛe�����Ȃ邫�����������j�C���ۊ��S�i�E���w�Z�ȊO�œƐg�ِ̈��Ɖ�@����j�C���ۊ��T�i���ۂ�����ɂ��ċC�y�ɑ��k�ł���l�̐��j�C���ۊ��U�i�ِ��Љ�₨��������i�߂�l�̐��j�C�ِ��̏Љ�E�o��P�i��i����j�C�ِ��̏Љ�E�o��Q�i����悩��j�C�ِ��̏Љ�E�o��R�i��������j�C�ِ��̏Љ�E�o��S�i�E��ȊO�̗F�l����j�C�ِ��̏Љ�E�o��T�i�Ƒ���e��������j�C�ِ��̏Љ�E�o��U�i���Ǝғ��̃C�x���g�j�C�ِ��̏Љ�E�o��V�i���������j�C�����T�[�r�X�̗��p�P�i�������k���j�C�����T�[�r�X�̗��p�Q�i���Ǝ҂̃}�b�`���O�T�[�r�X�j�C�����T�[�r�X�̗��p�R�i�l�b�g�̃}�b�`���O�T�[�r�X�j�C�����T�[�r�X�̗��p�S�i�����́CNPO�̏o����Ɓj�C�����T�[�r�X�̗��p�T�i������Ƃ̏Љ�T�[�r�X�j�C�����T�[�r�X�̗��p�U�i�o��n�T�C�g�j�C�����T�[�r�X�̗��p�V�i�o��ړI�̃p�[�e�B�[��C�x���g�j�C�����T�[�r�X�̗��p�W�i���`�x�[�V���������߂�J�E���Z�����O�j�C�����T�[�r�X�̗��p�X�i�t���������C���̓A�b�v�̃J�E���Z�����O�j�ł���B���ۊ��P�C�Q�C�T�C�U�ȊO�͑S�āC���Ă͂܂�ꍇ�ɂP�C�����łȂ��ꍇ�ɂO�ƂȂ�_�~�[�ϐ��Ƃ���B���ꂼ��C���ۑ����\�������߂���̂Ȃ̂ŁC�W���͐��ƂȂ邱�Ƃ����҂����B�Ō�ɁC�N��̕ϐ��ł��邪�C�N��̑��ɁC�N��̂Q�捀�������ϐ��ɉ������B
�y58�Łz�O�߂ŏq�ׂ����̓��f���i�v���r�b�g���f���j�𐄒肷��O�ɁC��v�Ȑ����ϐ��ɂ��āC�������l���Ă�����ۑ���̗L���ʂɒP����r���Ă������B�܂��C�}�\�T�͊O���Ȃǂ̎��ȕ]�����r�������̂ł���B�������l���Ă�����ۑ���̂��Ȃ������C��͂�w���Ⴂ�C�얞�C�e�p�������C���N�����C���a����̑S�Ă̕ϐ��ɂ��āC�Y�����銄�����������Ƃ��킩��B�����܂Ŏ��ȕ]���Ȃ̂ŁC���ۂ̊O���Ȃǂ������Ƃ͌���Ȃ����C���Ȃ��Ƃ��C���ȕ]���Ƃ��ẮC�������l���Ă�����ۑ���̂��Ȃ������Ⴂ�]���ƂȂ��Ă���B
���ɁC�}�\�U�͈����K���������Ă��銄�����������̂ł��邪�C�����Ă݂āC���҂̊Ԃɑ傫�ȍ��ق�����悤�ɂ͌����Ȃ��B�K���P�i�i���j�C�K���Q�i�����j�C�K���W�i�Q��ȁj�Ȃǂ́C�ނ��댋�����l���Ă�����ۑ��肪��������C�����������B����C�K���R�i���n�E���ւȂǂ̃M�����u���j�C�K���X�i�P�`�j�Ȃǂ́C�������l���Ă�����ۑ��肪���Ȃ������C�����������B���v���I�Ȍ��_�ł���Ƃ������Ƃł��낤���B
�}�\�V�͐E��ł���B�������l���Ă�����ۑ��肪����������K�E���̊������������Ƃ��킩��B�������l���Ă�����ۑ��肪���Ȃ����́C�p�[�g�E�A���o�C�g�̊��������ς��Ȃ����̂́C����ȊO�̔K�△�E�҂̊����������B
�}�\�W�́C�@���p�Ɋւ��鏔�ϐ��̔�r�ł���B�܂��C�ӊO�ɂ��ƌ����ׂ����C�������l���Ă�����ۑ��肪��������呲�ȏ�̊w���҂������C�����������������4�j�B�����Ƃ��C���Y�̎d���̌p���N���C���Z���Y�i�l�b�g�C�O���X�Ƃ��j�C�������Y�͌������l���Ă�����ۑ��肪���Ȃ����������B�e�Ƃ̓��������C�������l���Ă�����ۑ��肪���Ȃ�������⍂���B
�}�\�X�̎��ԓI����ɊW����ϐ��ł��C���ӊO�Ȃ��ƂɁC�������l���Ă�����ۑ��肪��������J�����Ԃ��ʋΎ��Ԃ��C�����āC��V���ȍ~�C���X���ȑO�̏A�Ǝ��Ԃ�����5�j�B
�}�\10�͑���ɋ��߂�����ł���B�����Ă݂āC���҂̈Ⴂ�͂��܂�傫���Ȃ��悤�ł��邪�C�������l���Ă�����ۑ��肪���Ȃ������C�N�����d�����銄���������B����ŁC�������l���Ă�����ۑ��肪���Ȃ������C�A�ƌ`�ԁC�N��C���i�C��̈�v�Ȃǂ��d�����Ă��銄������⍂���B��]���ǂ����͗\�z�ʂ�C�������l���Ă�����ۑ��肪������������B
�}�\11�́C���e����̃f�����X�g���[�V�������ʂɊւ��鏔�ϐ��̔�r�ł���B�������l���Ă�����ۑ��肪���Ȃ������C��e�̗����o���̊����������B�܂��C���e�����������C18�Ύ��_�ŗ��e�̒����ǂ��Ƃ���䗦���C��͂�C�������l���Ă�����ۑ��肪������������B
�}�\12�́C�E����Ɋւ��鏔�ϐ��̔�r�ł���B�\�z�ʂ�C�������l���Ă�����ۑ��肪��������C�t�@�~���[�t�����h���[�Ȋ�Ƃɋ߂Ă���䗦�������B
�}�\13�́C���ۊ��Ɋւ��鏔�ϐ��ł��邪�C��͂�C�������l���Ă�����ۑ��肪��������C�����Ĉِ��Əo��@��������Ƃ��킩��B
�}�\14�́C�ِ��̏Љ�E�o��̃��[�g�ł��邪�C�����Ă݂āC���҂ɂ���قnj����ȍ����y59�Łz ����Ƃ͌����Ȃ��B�����C�Ƒ���e��������̏Љ�Ƃ��������ɂ��ẮC�������l���Ă�����ۑ��肪���Ȃ������C�����������B����́C�Ƒ��ȂǁC����̊�@���̕\��Ƃ݂�ׂ���������Ȃ��B
�}�\15�́C�����T�[�r�X�̗��p�ł��邪�C�����Ă݂āC���҂ɂ��܂茰���ȈႢ�͂Ȃ��B�������k���̗��p���́C�������l���Ă�����ۑ��肪���Ȃ�������������C���Ǝ҂̃}�b�`���O�T�[�r�X�̗��p���͌��ۑ��肪������������B
�ȏ�C�l�X�ȕϐ����C�������l���Ă�����ۑ���̗L���ʂɔ�r���Ă������C����炪�ŏI�I�Ɍ���v���ł��邩�ǂ����́C���ϐ����ɃR���g���[��������Ŕ��f����K�v������B�����ŁC�O�߂Ő��������v���r�b�g���f����p���āC�S�Ă̕ϐ����ɃR���g���[��������A���͂��s�����B���茋�ʂ́C�}�\16�̒ʂ�ł���B
�S�̂Ƃ��āC��i2024�j�ɂ�錋���̌���v���̕��͂ɔ�ׁC�L�ӂƂȂ�ϐ������Ȃ��B���_�C����W�����C��i2024�j�ɔ�ׂĊi�i�ɏ������Ȃ��Ă���B����́C�T���v���������Ȃ����Ƃ����邪�C��s�����i�����E�����i2010�j�C���X�i2012�j�C�����i2015�j�j�����l�̌X���ł���C�����̑I���ƌ������l���Ă�����ۑ���̑I���̊Ԃɂ́C���قȂ錈�胁�J�j�Y��������̂�������Ȃ��B
�܂��C�O���Ȃǂ̎��ȕ]���ł́C�얞���L�ӂł���C�얞�ł����10.1�����C�������l���Ă�����ۑ��肪����m�����Ⴍ�Ȃ�B�ӊO�Ȃ̂́C�e�p�������ꍇ�C���a������ꍇ�ɁC10����ł͂��邪�C�������l���Ă�����ۑ��肪����m���������Ă��邱�Ƃł���B
�Ǝ��ɂ��ẮC�B��C���������ł���ꍇ�ɁC�������l���Ă�����ۑ��肪����m�������܂�B�K���ɂ��ẮC�p�`���R�E�p�`�X�����s���K��������ƁC�������l���Ă�����ۑ��肪����m���������Ă���C�����߂�����Ƃ���ł���B
�E��Ɋւ��ẮC���K�E�����x���`�}�[�N�Ƃ��Ă��邪�C�p�[�g�E�A���o�C�g��C���c�ƁE�Ƒ��]���ҁE���E�ł���ꍇ�ɁC���ꂼ��16.5���C29.3���C�������l���Ă�����ۑ��肪����m�����������Ă���B���߂Ƃ��ẮC����I�ȐE�ɂ��Ă���قǁC������̐������肪�W�]�ł��邽�߂ɁC�������l���Ă�����ۑ���ɑ�����v�����܂�Ƃ������Ƃł��낤���B�����āC���ۑ���Ƃ��Ă̒j���Ƃ��Ă��C���⋤������������O�ƂȂ��Ă���ł́C����I�ȐE���������ɖ��͂������Ă���\��������B
�@���p�W�̐����ϐ��ɂ��ẮC���Y�̎d���̌p���N�������܂�قǁC�������l���Ă�����ۑ��肪����m���������Ȃ��Ă���C�@���p�����Ɣ��������ʂƂȂ��Ă���B�����C�@���p�͌���������C�o�Y�����肵����C�L�����A���������ƂŐ����邽�߁C���ۑ��肪���鎞�_�ł͂����܂ōl���Ă��Ȃ��\��������B�ނ���C�E��ɒ������Ĉ���I�ȃL�����A���������قǁC�j�������͂���������C���ۑ���̒j���ɏo��m���������Ƃ������ʂ�����̂�������Ȃ��B���ԓI�Ȑ���ɂ��Ă��C�T������J�����Ԃ������قǁC�������l���Ă�����ۑ��肪����Ƃ������ʂł���C���O�̗\�z�ɔ��������ʂƌ�����B�����C������C�J�����Ԃ�������������I�Ȏ�����E�ł���C���̖ʂł̖��͂�����Ƃ������߂��\�ł���B�E����ɂ��ẮC�t���b�N�X�^�C������������C�������l���Ă�����ۑ��肪����m���������Ă���C��͂�C���_��ȓ������ł�������C���ۂ��₷���Ƃ������ʂ�����̂�������Ȃ��B
�y60�Łz�ƒ���ɂ��ẮC���e�̐E�킪�p�[�g�E�A���o�C�g�̎��ɁC�������l���Ă�����ۑ��肪����m���������C��e���h���E�����E�_��Ј��̏ꍇ�Ɋm�����Ⴍ�Ȃ邪�C�����̗��R�͂悭�킩��Ȃ��B�܂��C18�Ύ��_�ŕn�����ꍇ�ɁC�������l���Ă�����ۑ��肪����m�����Ⴍ�Ȃ��Ă���B���̓_�́C���сi2023�j�ɗގ����Ă���B
��������ւ̏����ɂ��ẮC�N������ɏd������ꍇ�ɁC�������l���Ă�����ۑ��肪����m�����R���߂��i26.9���j��������B����������ʓI�ȎЉ�ł́C�j���݂̂̎����ʼnƌv��d�����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ���邩��C���������D�����̌��ۑ���������邱�Ƃ�����Ȃ��Ă���\��������B����ŁC��̈�v���d������ꍇ�ɂ́C���ۑ��肪����m���������Ă���C����͌��ۍs���ƌ����Ӗ��ŁC�����ɂ����R�ł���B�����[���̂́C�e�̓����ɂ��Ă̈ӌ����d������ꍇ�ɁC�������l���Ă�����ۑ��肪����m�����������邱�Ƃł���B�e�Ɠ������鐢�т��}�����Ă��錻��炵���X���ł���B�܂��C����������킹��Ɛg�ِ̈��������ꍇ�ɂ͂������āC�������l���Ă�����ۑ��肪����m�����������Ă���B�����߂̓���Ƃ���ł���B
�܂��C��i����̏Љ����ꍇ�C���Ǝғ��̃C�x���g�ɎQ������ꍇ�C���`�x�[�V���������߂�J�E���Z�����O����ꍇ�ɁC�������l���Ă�����ۑ����m������������C�Ƒ���e��������Љ����ꍇ�ɂ́C�������l���Ă�����ۑ��肪����m������������B���ʊW���t�ł��邪�C�Ƒ���e��������̏Љ�Ƃ����̂́C�ނ���C���ۑ��肪���Ȃ����Ƃւ̊�@���̕\��Ȃ̂�������Ȃ��B
�O�̂��߁C�}�\17�ɂ́C�������l���Ă�����ۑ���̗L���ł͂Ȃ��C�P�Ȃ���ۑ���̗L���ɂ��Ẵv���r�b�g���͂��s�������ʂ��ڂ��Ă���B�}�\16�ɔ�ׂĂ���ɗL�ӂȕϐ������Ȃ��Ȃ��Ă���B
�{�e�́C�M�҂炪�Ǝ��Ɏ��{�����u�����ςɊւ���A���P�[�g�v��p���āC��i2024�j���s�������{�l�����̌����̌���v���Ɋւ��镪�͂Ƃقړ����ϐ���p���āC�������l���Ă�����ۑ��肪����v����T�����B
�L�q���v�x�[�X�Ŋe�ϐ����ώ@�����ۂɂ́C�����̌���v���ƈقȂ�����͂���قǑ����Ȃ������B�v���r�b�g���f���ɂ�鐄����s���ƁC�L�ӂȕϐ��́C��i2024�j�ɔ�i�i�ɏ��Ȃ����̂ƂȂ����B�����ɁC����W�����i�i�ɒႭ�Ȃ��Ă���B
�����I�ȓ_���������s�b�N�A�b�v����ƁC�܂��C�O���Ɋւ��ẮC�얞�̏ꍇ�ɁC�������l���Ă�����ۑ��肪����m���͌�������B�E��Ɋւ��ẮC���K�E���ɔ�ׂāC�p�[�g�E�A���o�C�g��C���c�ƁE�Ƒ��]���ҁE���E�̏ꍇ�ɁC�������l���Ă�����ۑ��肪����m���͌�������B�w��������C�e���Y�͗L�ӂł͂Ȃ��C�ނ���C�d���̌p���N���������قǁC�������l���Ă�����ۑ��肪����m���������Ȃ��Ă���C�@���p�����͓��Ă͂܂�Ȃ��悤�Ɍ�����B���̂ق��C���Ԑ����ƈقȂ錋�ʂł͂��邪�C�T������J�����Ԃ͒��������������l���Ă�����ۑ��肪����m���͑����B�����C�t���b�N�X�^�C��������������Ă���قǁC���ۑ��肪����m�����������Ƃ���C���ԓI���܂������d�v�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��̂��낤�B
�y61�Łz�}�b�`���O���Ɋւ��鎖���ł́C��i����̏Љ����ꍇ�C���Ǝғ��̃C�x���g�ɎQ������ꍇ�C���`�x�[�V���������߂�J�E���Z�����O����ꍇ�ɁC�������l���Ă�����ۑ����m������������C�Ƒ���e��������Љ����ꍇ�ɂ́C�������l���Ă�����ۑ��肪����m�����������Ă���B
��i2024�j�Ƃ̍��ق������Ă��闝�R�́C���낢��Ȃ��̂��l������B�������������ƌ��ۂ͈قȂ�I���s���ł���Ƃ������Ƃ�������Ȃ����C��i2024�j�̊����҂ɉ�ڃo�C�A�X�����݂��邹���Ȃ̂�������Ȃ��B�܂��C����̓Ɛg�҂̕��͂ɂ́C�����҂�������Ă���Ƃ����T���v���Z���N�V�����o�C�A�X�����邱�Ƃ��e�����Ă���\��������B�����Ƃ��C���ꂾ���傫�Ȍ��ʂ̈Ⴂ�Ƃ��Ȃ�ƁC�����̌���v���ƁC�������l���Ă�����ۑ��肪���錈��v���̊Ԃɂ́C���قȂ郁�J�j�Y�������݂��Ă���Ɖ��߂���̂����R�̂悤�Ɏv����B�����āC���҂̃��J�j�Y���̍��قɂ����C���ۑ���̂���Ɛg�҂������܂œ������߂̐���̃J�M���B����Ă���\��������B
���V�����E�O�c�[���i2005�j�u�E�������̐����Ɩ������̐i�W�v�w���{�J�������G���x535,16-28�D
�k���s�L�E��{�a���i2007�j�u����ԊW���猩�������s���v�w�o�ό����xVol.58�i1�j�C31-46.
���я��i2023�j�u�n���Ɨ����F���l�l���Ɛ��W�l���̕s�����̌v�ʕ��́v�w������w���w���I�v�x58,45-53
���䐳�E������Y�i2005�j�u�t���[�^�[�̂��̌�F�A�ƁE�����E�����E�o�Y�v�w���{�J�������G���x535,19-41�D
���X�؏���i2012�j�u�����s��ɂ�����i�����Ɋւ�����ؕ��́F�j���̔K�A�Ƃ����ۍs����Ɛg�p���ɗ^����e���v�w���{�J�������G���x54�i2�E3�j�C93-106
���������E�i��Ŏq�E�O�֓N�i2010�j�w�����̕�-�E�Ӎ��̍\���x�������[�D
��ؘj�i2024�j�u���{�l�����̓Ɛg�҂Ɗ����҂����͉̂����H-�Ɛg�҃f�[�^�Ɗ����҂̐U��Ԃ�f�[�^�ɂ�錋���̌���v���̕���-�v�w�o�Ϙ_�W�x��60����P���i�ߊ��j
���R���V�E����_�E�g�c�_�E�L�c�x���q�E���q�\�G�E�������v�i2000�j�u�����E�玙�̌o�σR�X�g�Əo���͏��q���̌o�ϊw�I�v���Ɋւ����l�@�v�w�l����茤���x��56����S���C1-18.
�k�؏r�فE�ؑ����q�i2008�j�w�Ƒ��̌o�ϊw-�������J�̂��߂������xNTT�o��
���t�{�i2023�j�w�o�ύ��������`�����n�߂������ƒ����`�i�ߘa�T�N�Łj�x
�����^�R���E���������i2010�j�u�Ȃ����l�ɂ߂��荇���Ȃ��̂��H�@�o�ϓI�v���E�o��̌o�H�E�ΐl�W�\�͂̑��ʂ���v���������E�i��Ŏq�E�O�֓N�i2010�j�w�����̕�-�E�Ӎ��̍\���x�������[�C54-73
�i���L�q�i2002�j�u��N�w�̌ٗp�̔K���ƌ����s���v�w�l����茤���x��58 ����Q���C22-35.
�i�c�ė��E�吙����i2019�j�u��҂ɂ���������ƌ��������̓����v�w�Ƒ������N��x44, 77-88
�����q�i2015�j�u�����҂̗����s�����́@�Ȃ��K���ȑ���ɂ߂�����Ȃ��̂��v�C�w�o�ϊw�_���x��68����R���C493-515
�����q�i2016�j�u��҂̗�������Ɋւ����l�@�F���l�T���ɂ݂�摗��s���v�w�l���w�����x52�i0�j�C25-37
������Y�E�������_�i1999�j �u�o�ϕϓ��Ə����̌����E�o�Y�E�A�Ƃ̃^�C�~���O�v����Y�E��c�������y62�Łz ���w�p�l���f�[�^����݂����㏗���x���m�o�ϐV��ЁC25-65.
�X�c�z�q�i2008�j�u�����̏����m���̌���v���̕��͂ɂ���-���e�̏������v�̏�����-�v�w�I�C�R�m�~�J�x��45����Q���C25-40.
���������i2006�j�u�w������̌ٗp��Ԃ������^�C�~���O�ɗ^����e���v�w�����o�ϊw�����x22-23,167-176�D
���㏮�G�i1993�j�w�����̌o�ϊw-�����Ƃ͐l���ɂ�����ő�̓����x���[�D
�R�c���O�i1999�j�w�p���T�C�g�E�V���O���̎���x�}�����[�D
Becker, Gary �i1973�j �gA theory of marriage Part I,�h Journal of Political Economy, 81,813-846.
�y63�Łz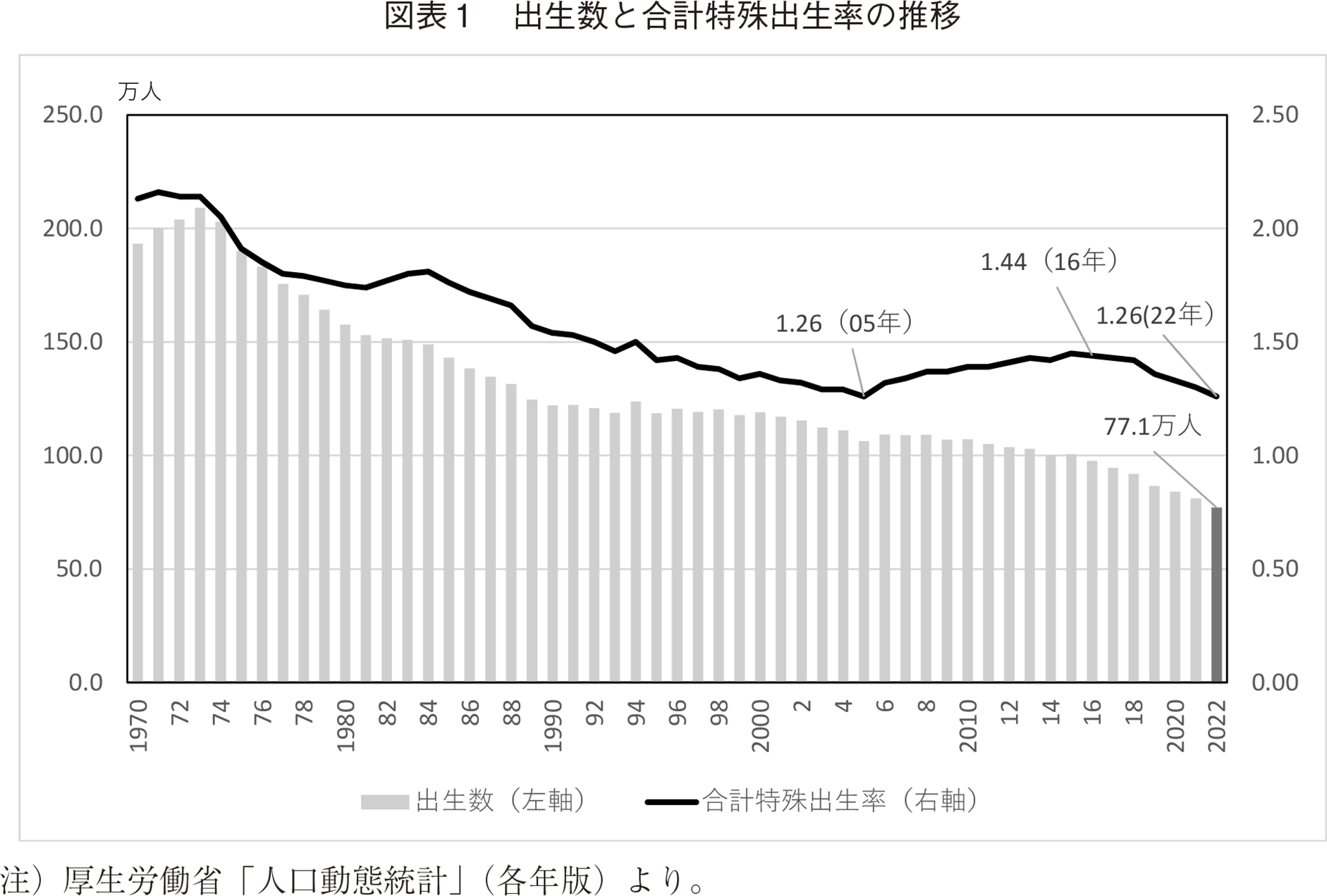
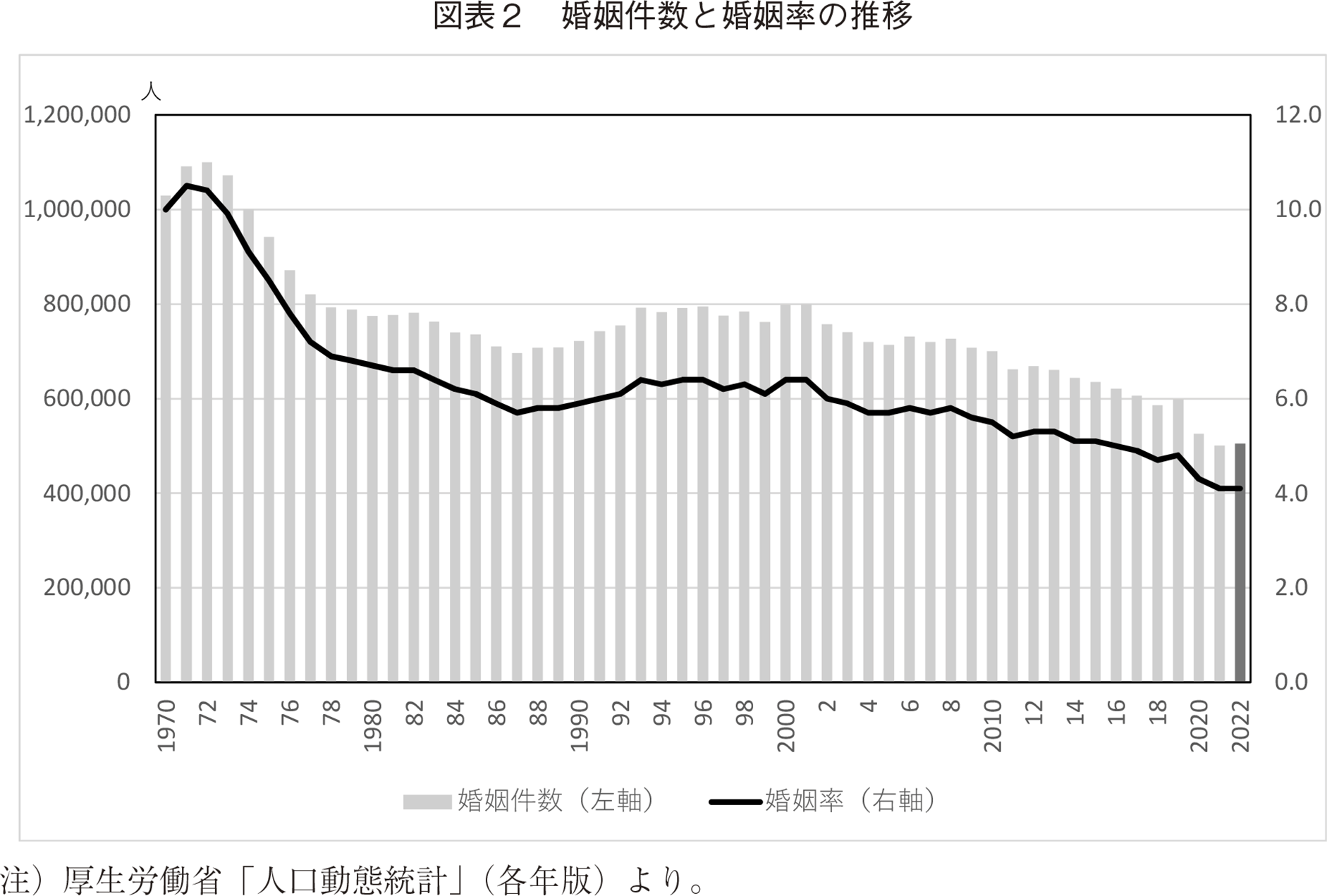 �y64�Łz
�y64�Łz
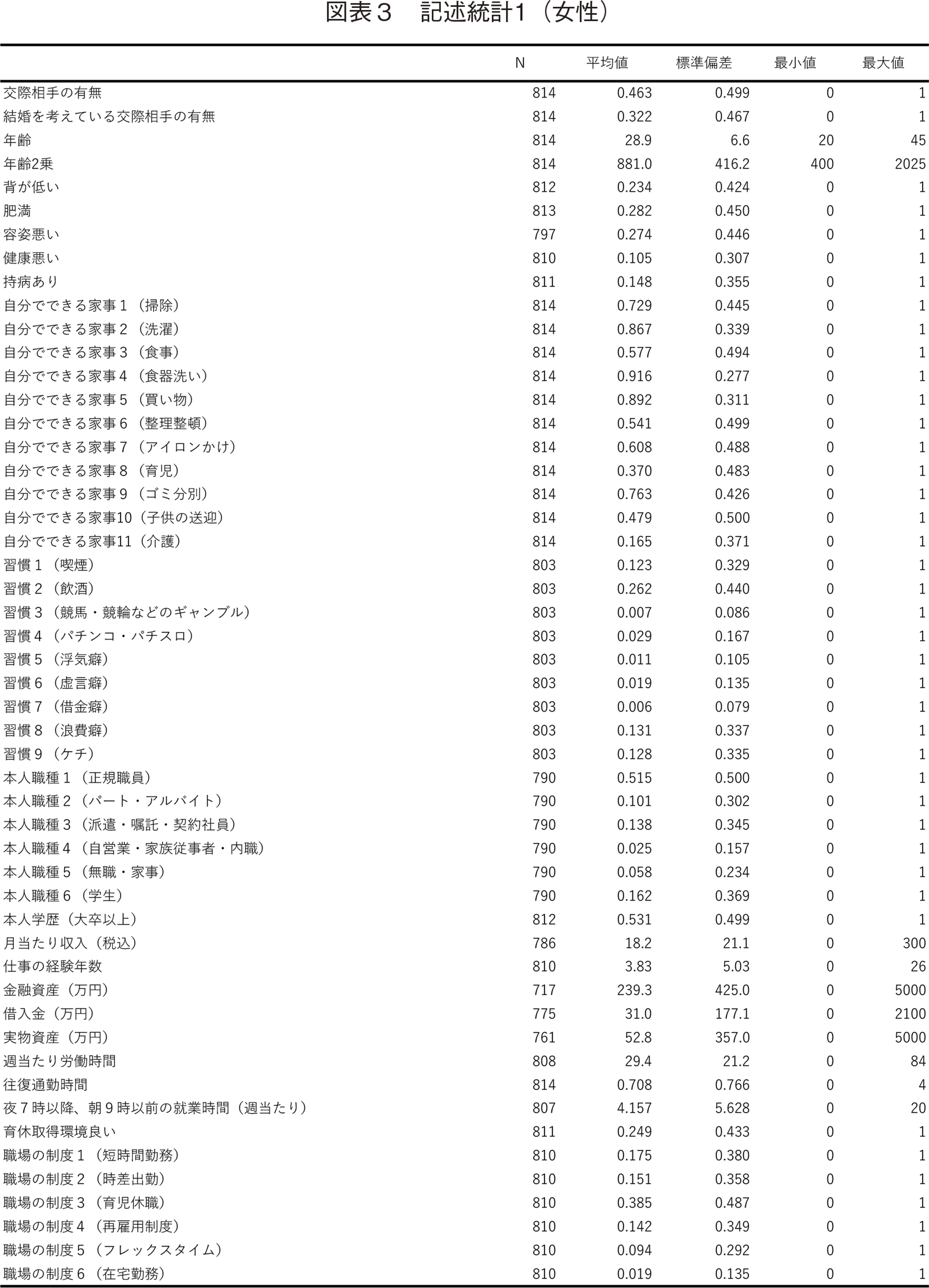 �y65�Łz
�y65�Łz
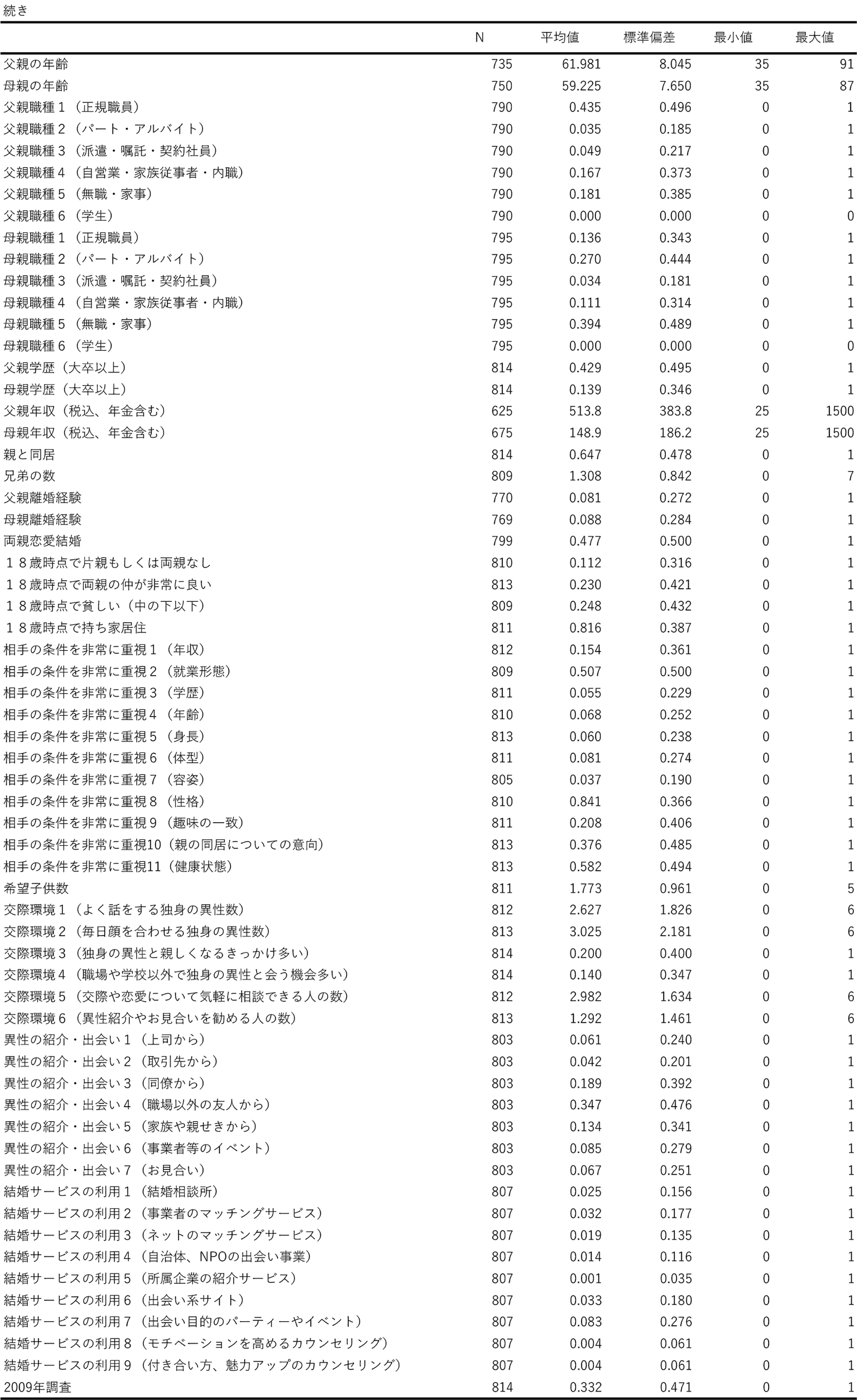 �y66�Łz
�y66�Łz
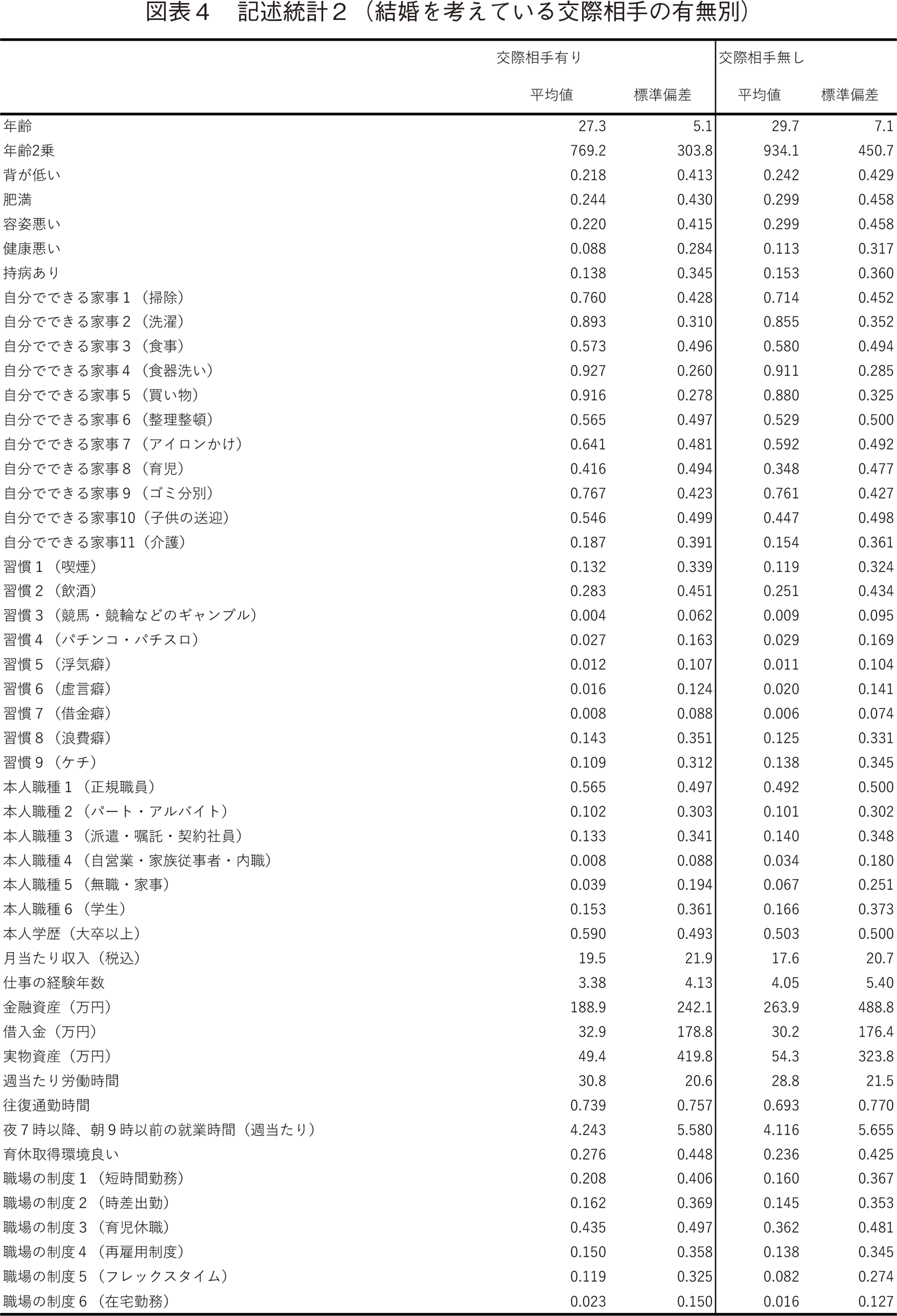 �y67�Łz
�y67�Łz
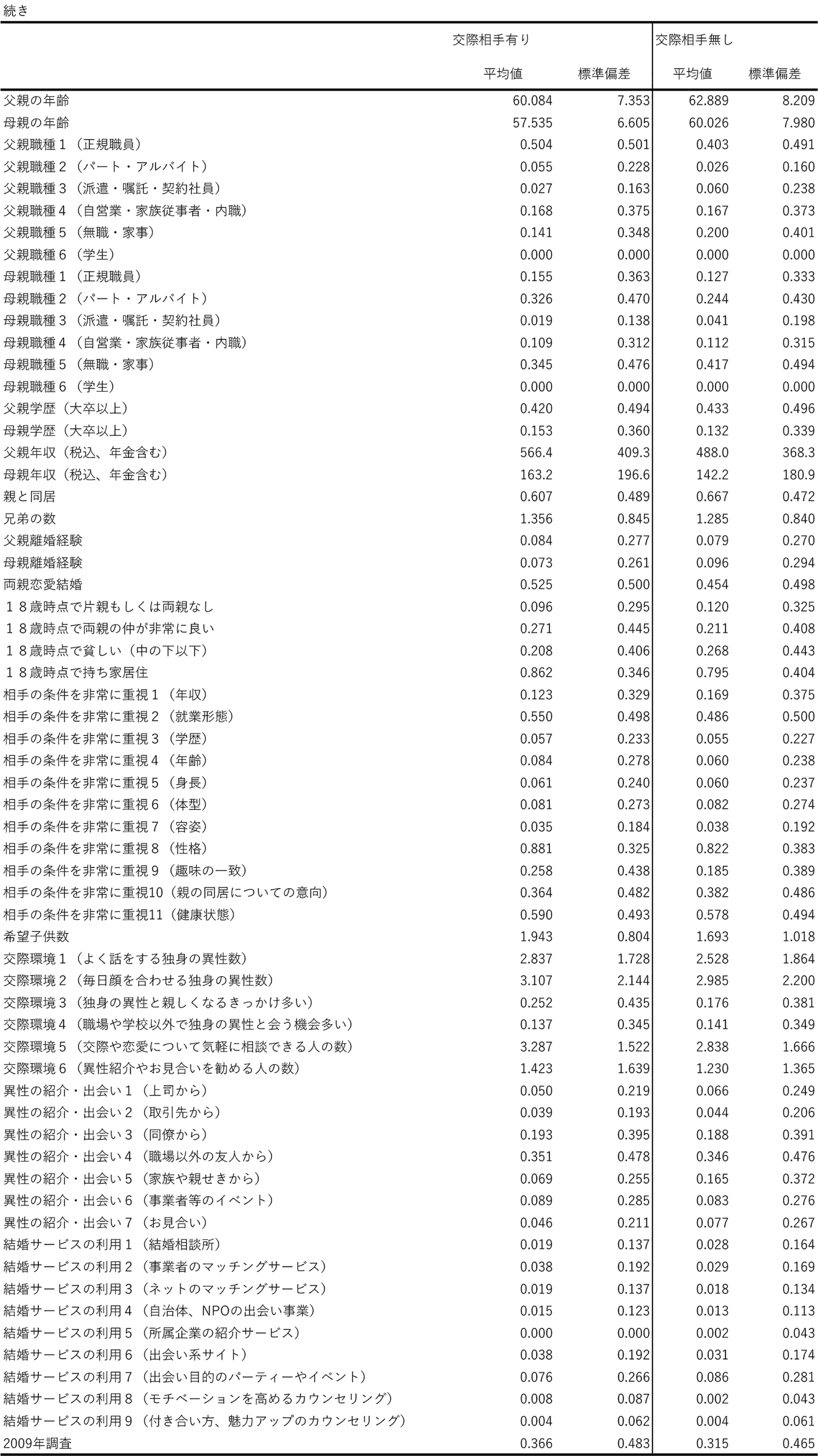 �y68�Łz
�y68�Łz
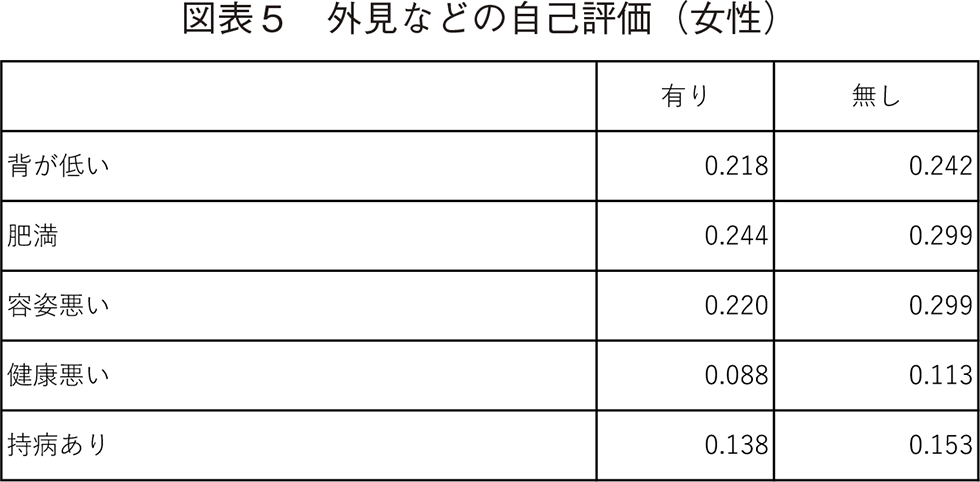
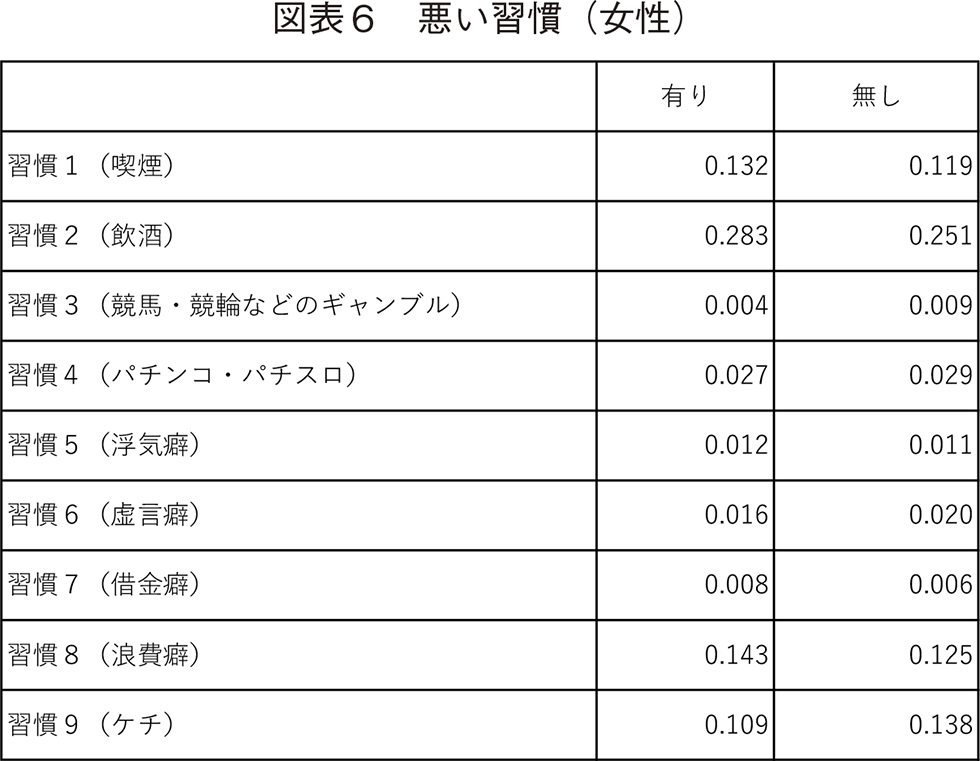
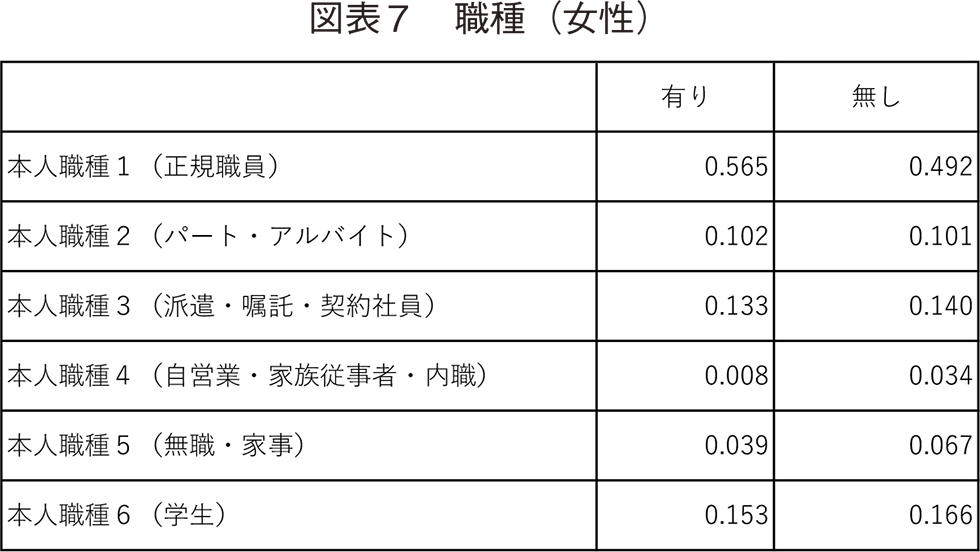 �y69�Łz
�y69�Łz
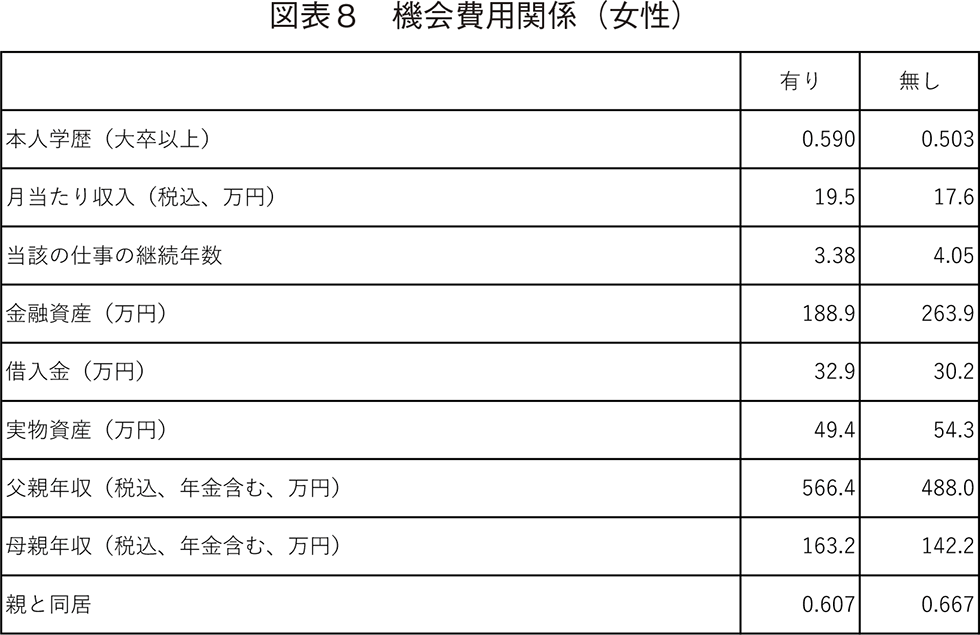
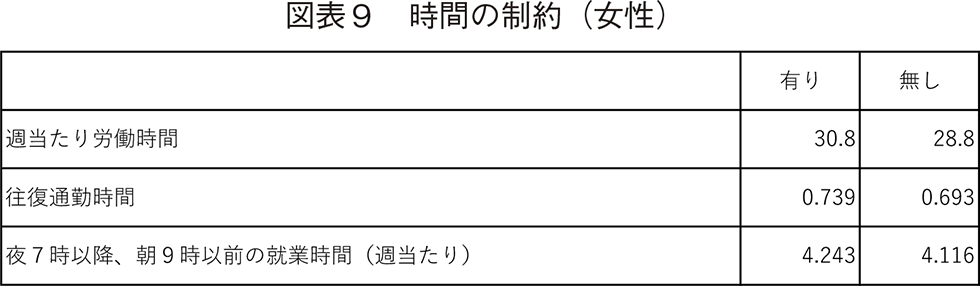 �y70�Łz
�y70�Łz
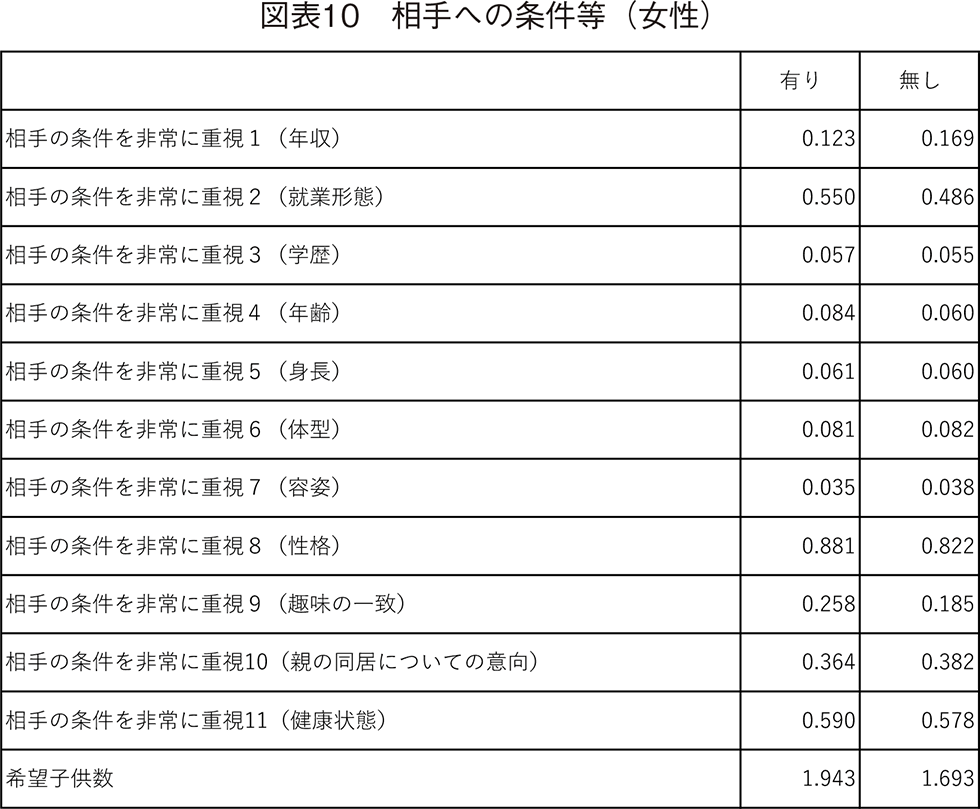
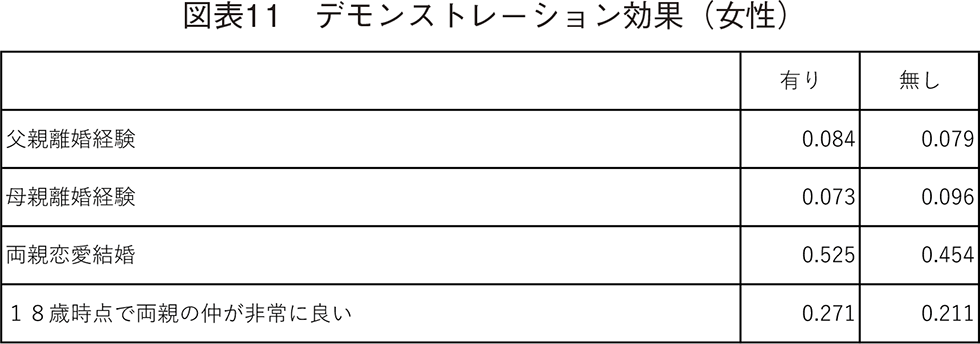
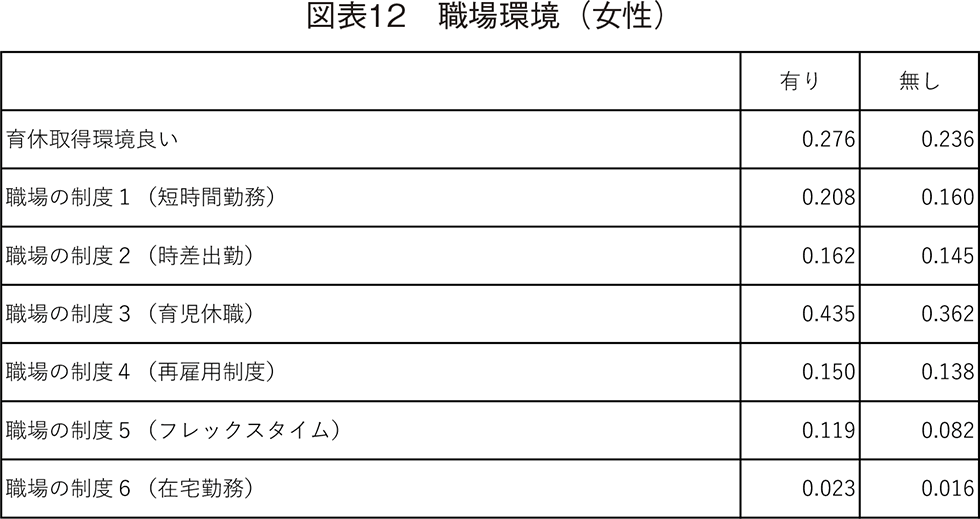 �y71�Łz
�y71�Łz
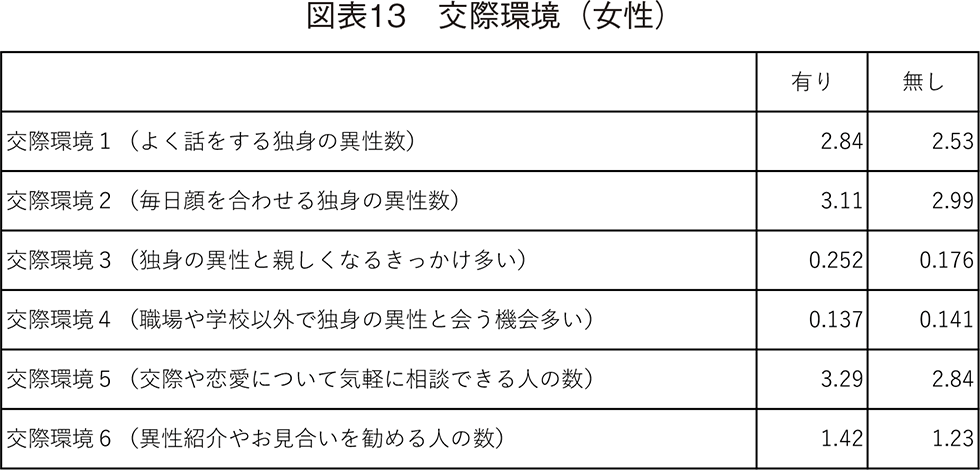
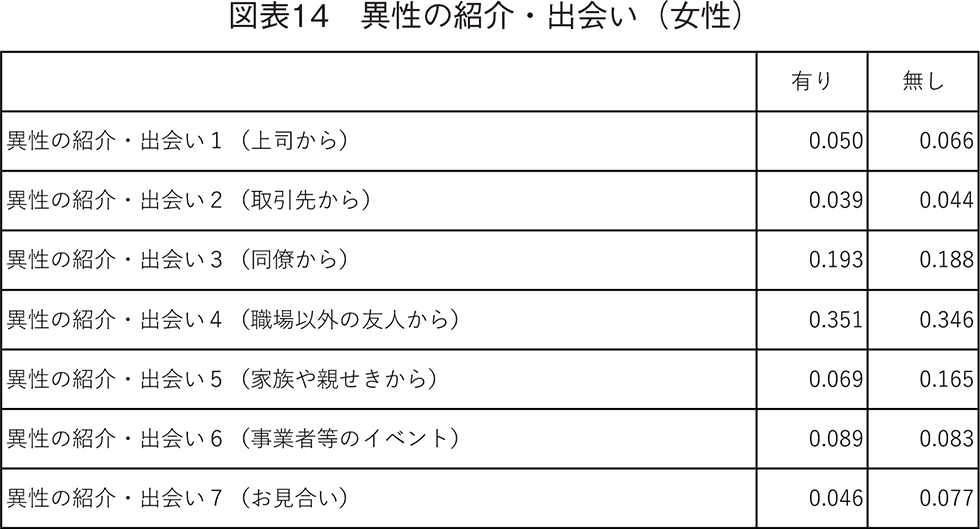
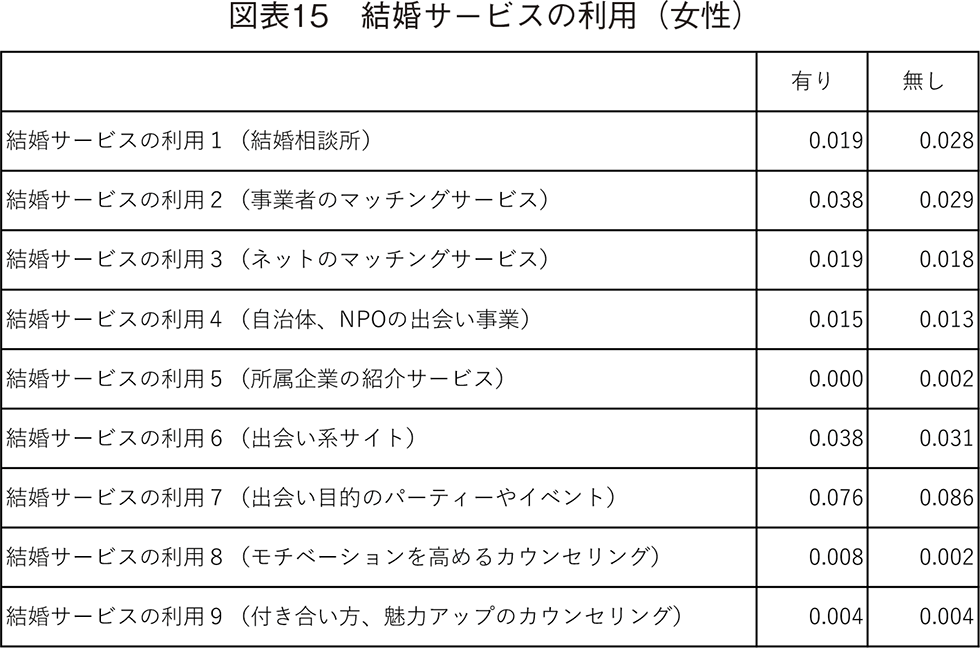 �y72�Łz
�y72�Łz
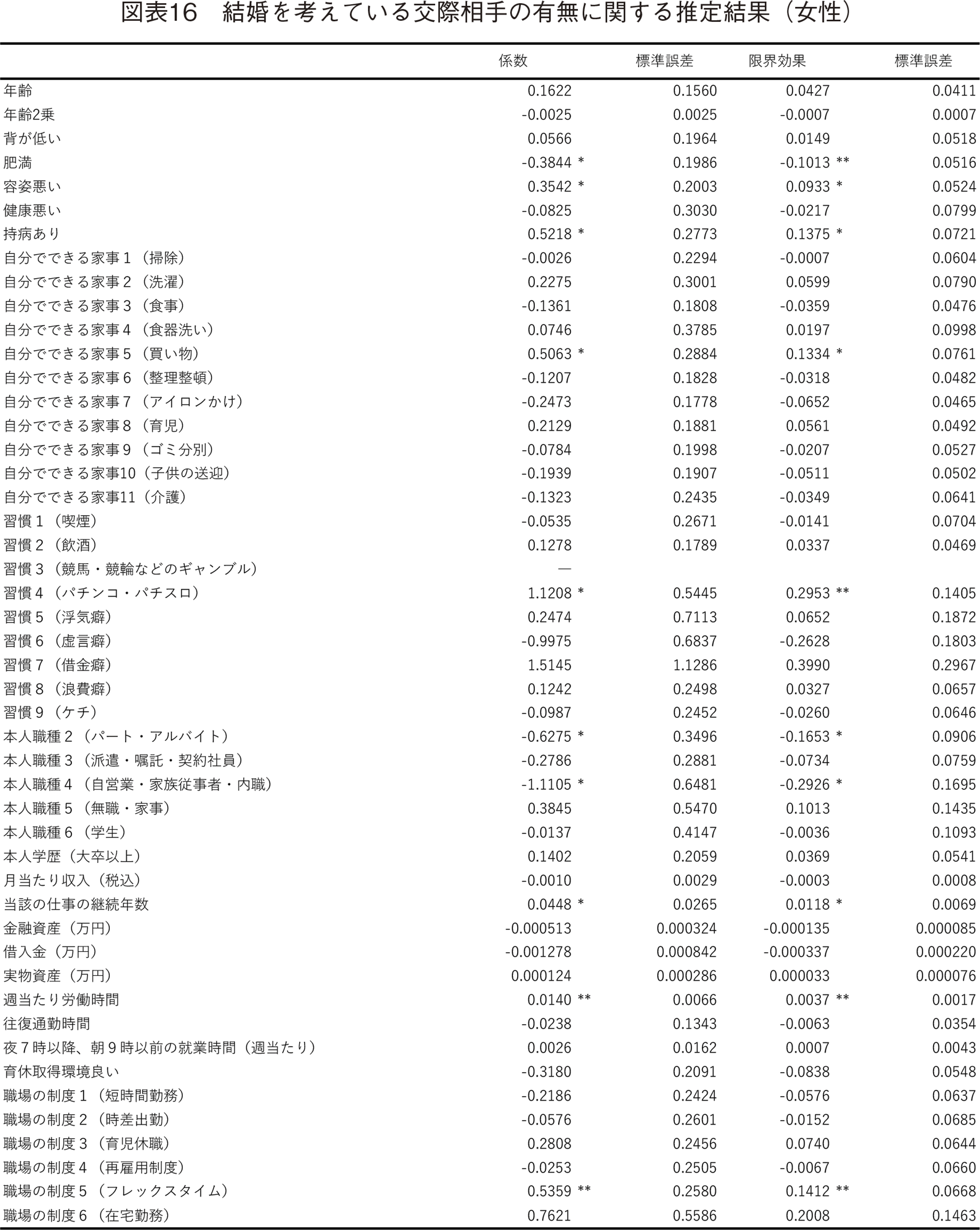 �y73�Łz
�y73�Łz
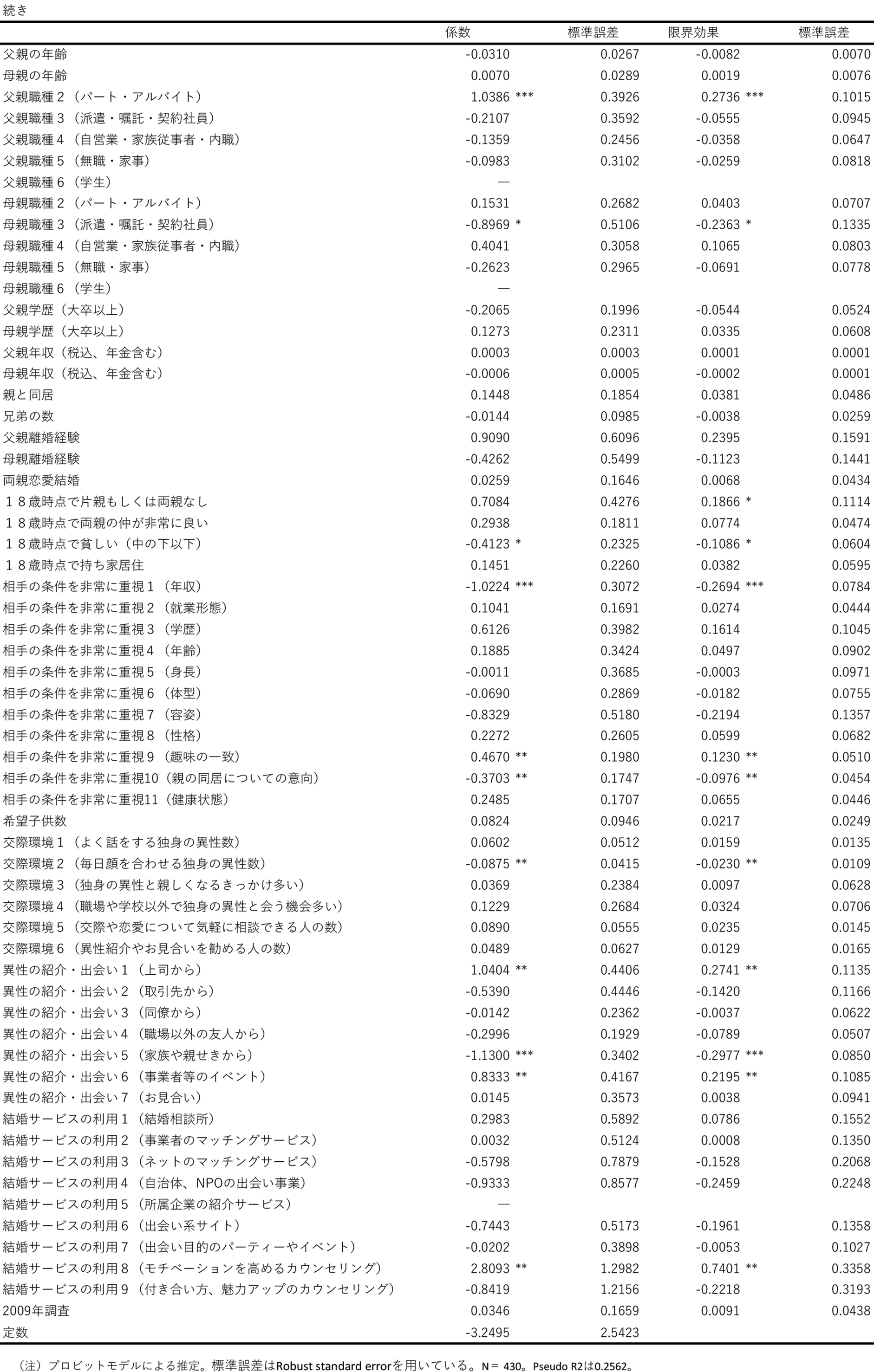 �y74�Łz
�y74�Łz
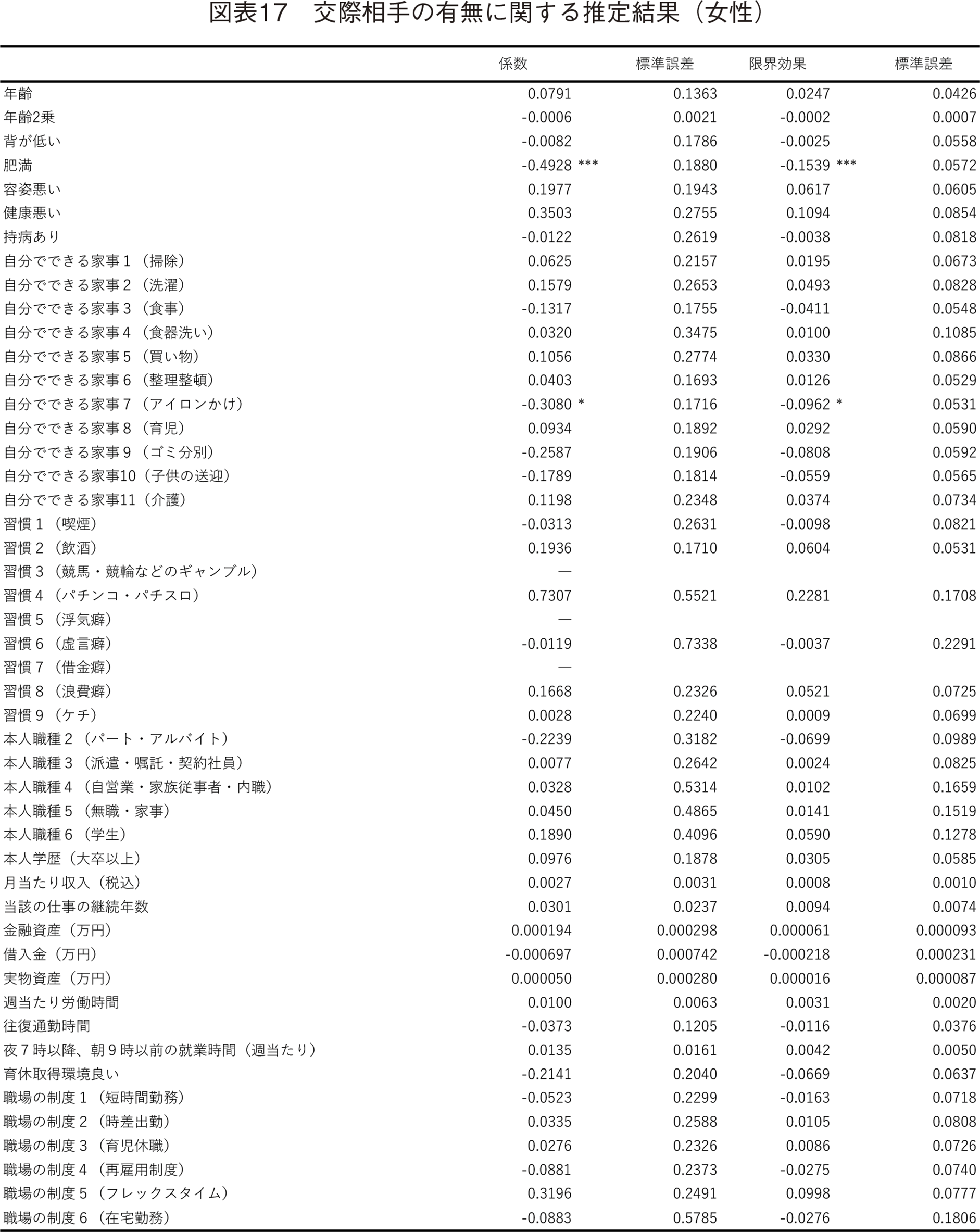 �y75�Łz
�y75�Łz