インド自動車部品産業の成長に果たしたMaruti Udyogの役割
──2014年財務データとSHAP分析による定量評価──
学習院大学経済学部経営学科教授 白田由香利
千葉商科大学商経学部教授 橋本 隆子
インド マダナパレ工科大学計算機学部学部長,岩手県立大学特命教授 バサビ・チャクラボルティ
インドにおける自動車産業の飛躍的発展は,1982年のMaruti Udyog(現Maruti Suzuki India Limited,以下,MARUTI)による生産開始を契機として加速した[1],[2],[3],[4]。以降,同社は一貫して市場シェア首位を維持し,他社を寄せ付けない競争力を示してきた。その秘訣として,本研究では「現地部品サプライヤの体系的育成」に着目する。すなわち,MARUTIはインドの部品メーカーを単なる下請け業者とみなすのではなく,長期的視点に立って教育・支援を行い,互いの発展を共に追求する「共存共栄」の理念を実践してきた点に強みがあると仮説を立て検証する。
本研究の目的は,機械学習回帰モデル(XGBoost)およびSHAP(SHapley Additive exPlanations)を活用し,企業の時価総額成長率(Market Capital Growth Rate, MCGR)に影響を与える主要因を定量的に明らかにすることである。特に,2014年前後,グローバル自動車メーカーがアジア諸国市場への進出を加速させる中,MARUTIがインド市場で優位性を維持し得た要因を多角的に検証する。本稿では,以下の構成で議論を進める。
● 第2節:世界自動車製造業の発展要因の分析
世界主要自動車メーカー65社を対象に,2014年の財務データを基にMCGRへの各種財務指標の影響・貢献を定量分析する。2014年は特にインドおよび中国市場での急成長が顕著であった[5]。そこで,これらの企業の特徴を抽出し,分析する。結果として,MCGRの高い企業は,サプライ・チェーン・マネジメント力と新製品開発力の2つが両輪となってMCGR向上の要因となっていることが分かった。
● 第3節:インド自動車製造業の発展機構の分析
前節を受け,インドに限定し既存研究をサーベイし,インド自動車部品産業の成長に対するMARUTIの影響およびMARUTIの競争優位性に関する仮説を構築する。また,インド自動車メーカーの2011年から2014年までの財務データ等を分析する。調査の結果,MARUTIが2014年前後において他社の市場参入圧力を跳ね返し続けられた背景には,部品サプライヤとの協力関係を長期的なパートナーシップとして構築する共存共栄の精【42頁】 神が存在し,これが低コスト車両の開発競争力を生んだ可能性が高いことが示唆された。
最終節第4節はまとめとする。
本節では,世界主要自動車メーカー65社を対象に,2014年の財務データを基にMCGRへの各種財務指標の影響・貢献を,回帰分析などを用いて定量分析する。
本研究では,世界の自動車製造業を対象に分析する。データはBureau van Dijk(BvD)社のORBISデータベースから業種コード「2910(Manufacture of motor vehicles)」に該当する企業データを取得した。分析対象企業の選定にあたっては,規模の極端に異なる企業を除外するため,2011年の売上高が20万千米ドル(200百万米ドル)以上に限定した。図1では,赤線で示した基準を上回る(左側に位置する)企業が選定された(図1参照)。65社にはTESLAも含まれている。なお,本稿では基準年を2011年とし,長期の時系列データ分析を視野に入れつつ分析するものであるが,特に顕著な変化が観測された2014年の財務データを用いて定量分析を行う。
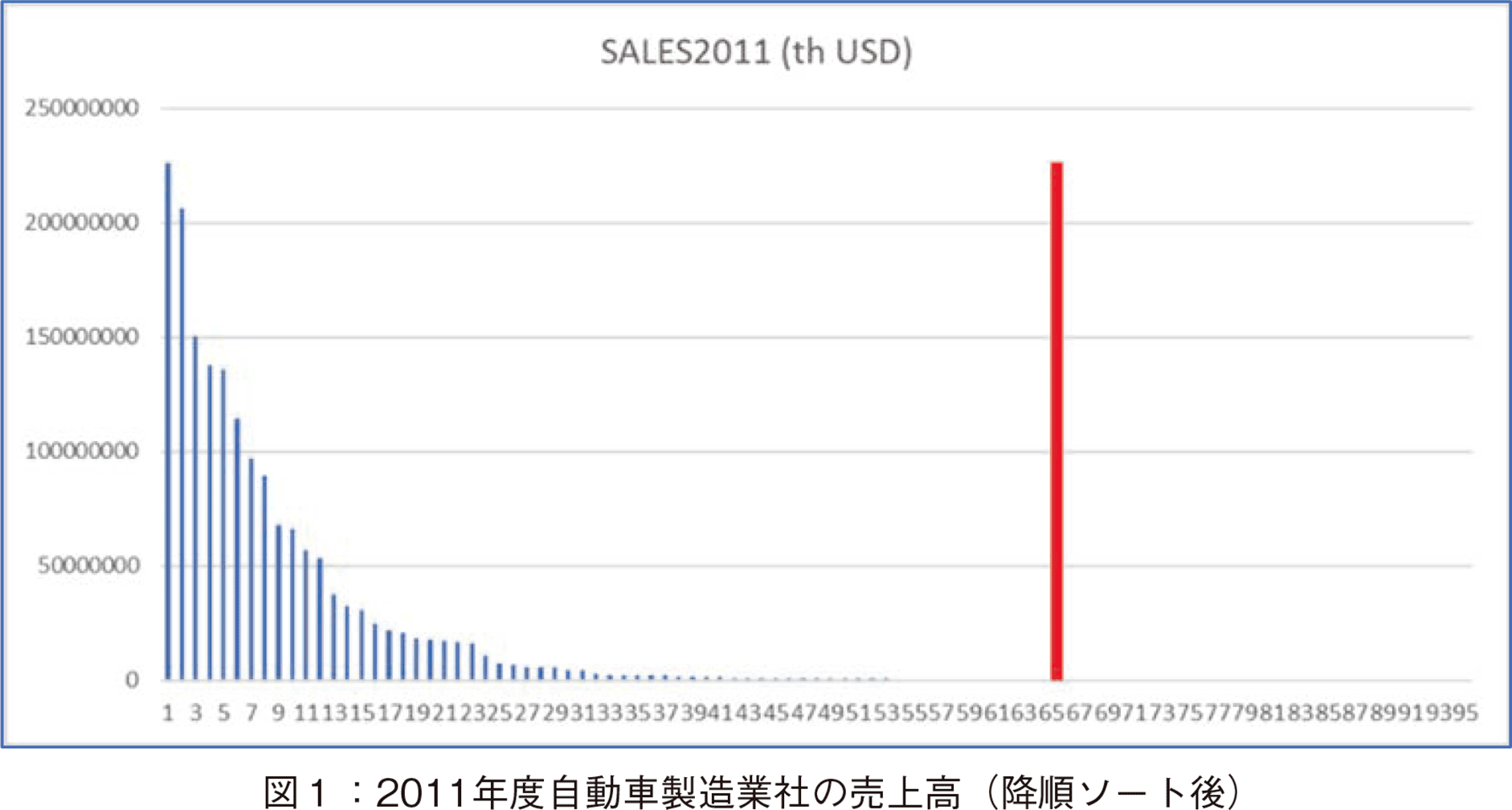
本節では,回帰に用いたデータと,回帰手法及びその解釈のSHAPアプローチを解説する。
ターゲット変数と説明変数
本稿では,手法として回帰分析を用いた。本分析のターゲット変数には,企業の市場価値拡【43頁】 大を表す指標として時価総額成長率(Market Capital Growth Rate, MCGR)を設定した。時価総額は株価に発行済株式数を乗じたものであり,MCGRが高いことは,株式市場における当該企業への期待度が上昇し,市場評価が急速に拡大していることを意味する。ただし,株価変動は経営実績のみならず投資家心理や外部環境の変化も反映するため,MCGRは経営成果の直接的指標ではなく,総合的な「期待値」指標として解釈すべきである。
説明変数として,以下の5つの財務指標を採用した。本来は労働生産性も指標に含める予定であったが,従業員数データの欠損率が高かったため,やむなく本稿では除外した。説明変数には,売上高の成長率の他,売上高の金額そのものも説明変数として入れた。
1.棚卸資産回転率(Inventory Turnover Ratio, INV)
2.売上高(Net Sales, SALES)
3.売上高成長率(Sales Growth Rate, SGR)
4.売上高利益率(Profit Ratio, PROF)
5.有形固定資産回転率(Fixed Asset Turnover Ratio, FA)
各指標は年次データを用い,以下のように定義した。
MCGR = (MC(2014) - MC(2013)) / MC(2013)
INV = Costs of Goods Sold(2014) / Inventory(2014)
SGR = (Net Sales(2014) - Net Sales(2013)) / Net Sales(2013)
PROF = PLBT(2014) / Net Sales(2014)
FA = Net Sales(2014) / Fixed Assets(2014)
回帰分析手法とSHAP値の意義
本研究では,目的変数である時価総額成長率(MCGR)を説明する回帰モデルとして,勾配ブースティング決定木に基づくXGBoost回帰器[6]を採用した。線形モデルと異なり,複雑な形状となる。まず,XGBoostを用いてモデルf(X)を構築し,次いでその予測値に対する各説明変数の寄与度をSHAP(SHapley Additive exPlanations)値として算出する。SHAPは,ゲーム理論におけるシャープレイ値(Shapley value)[7],[8],[9],[10]を基盤とし,機械学習モデルのターゲット値の予測結果を,個々の説明変数の貢献に,分解する手法である。従来の線形回帰における回帰係数解釈はモデル全体の平均的傾向を示すのみであったが,SHAP値を用いることで企業の特性が考慮され「企業ごとに,どの要因がMCGRの向上に最も大きく貢献したか」を定量的に評価できる点に大きな強みがある[11],[12],[13]。
本節では,SHAP値を用いた分析結果を報告する。図2には,2014年における主要企業のSHAP値の積み上げ棒グラフを掲げる。各企業の時価総額成長率(MCGR)の平均からの偏差(図2)は,INV_shapvalue,SALES_shapvalue,SGR_shapvalue,PROF_shapvalue,FA_shapvalueの5個のSHAP値に分解されている(図3参照)。SHAP値は平均からの偏差を表すため,負の値も取る。よって,企業ごとに5個のSHAP値を合計した値が,MCGRの偏差となる。よって図2の形状は図3の形状に近くなる。
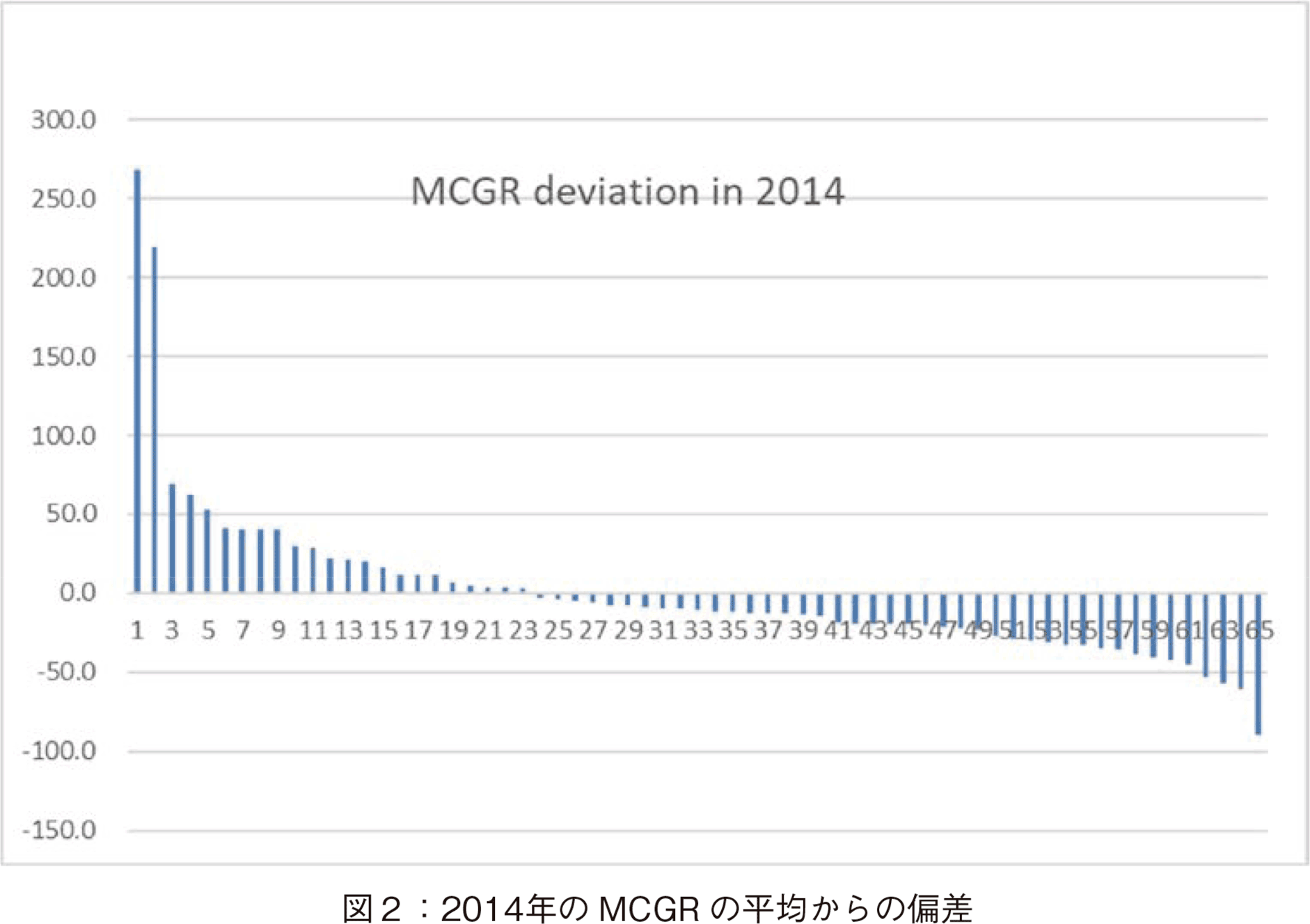
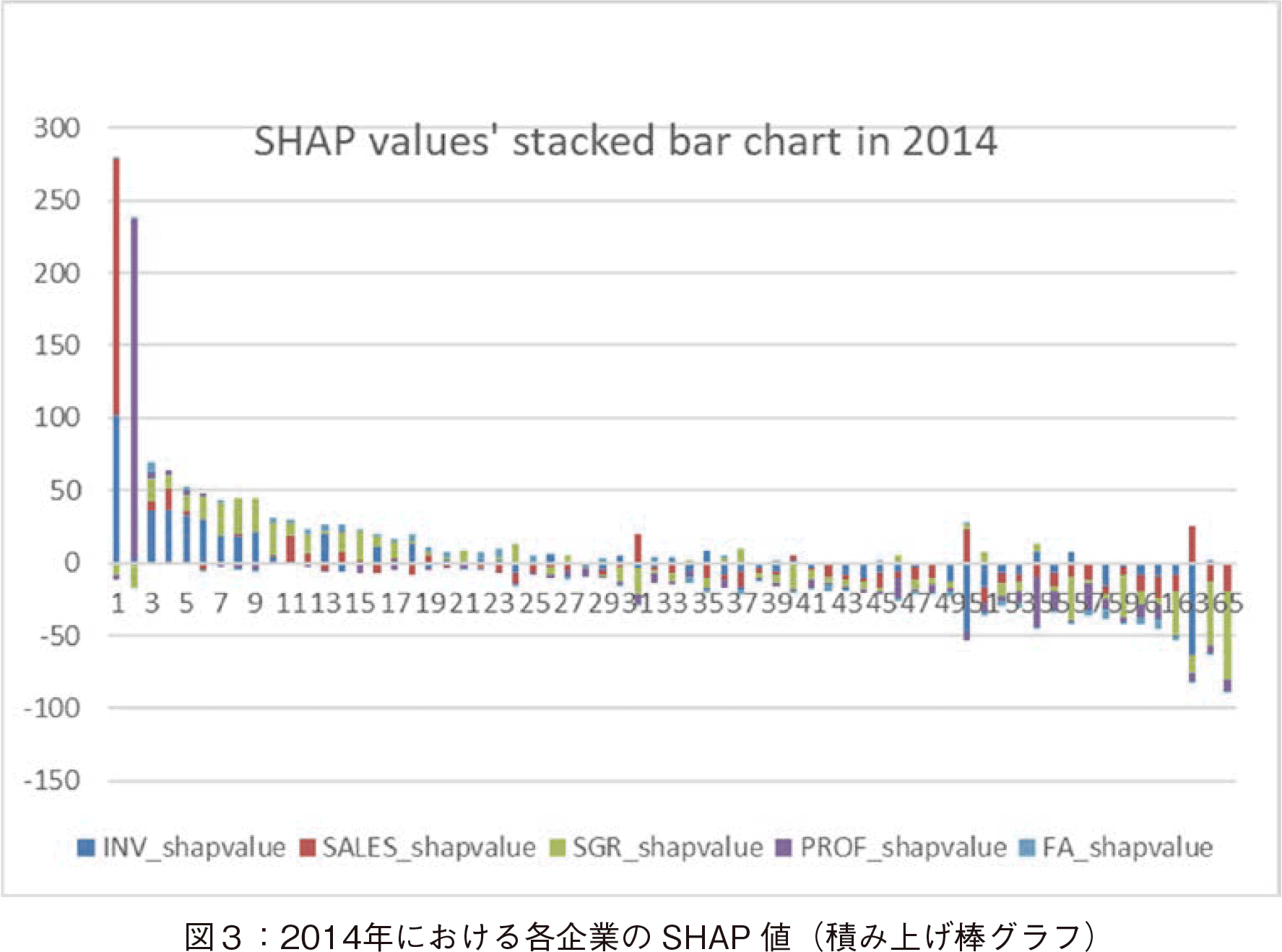
次にMCGRに貢献度が高い説明変数がどれかを,相関係数を用いて分析する。表1は,各変数間の相関係数を示したものである。表1では,生の説明変数と説明変数のSHAP値の両方の値を比較のため示した。MCGRとの相関係数において,生の説明変数値ではなく,そのSHAP値を用いることで精度が増す(表1参照)。例えば,INVでは-0.09が0.71に増加している。INV_shapvalueとMCGRとの相関係数は0.71と最も高く,MCGRに最も影響を与える説明変数はINVであることが分かった(表1)。ついで,SALES_shapvalueとMCGRとの相関係数が0.68と高く,在庫回転率および売上高がMCGRに対して強い寄与を示していることが分かる。SGR_shapvalueは0.33と弱い相関にとどまった(表1参照)。
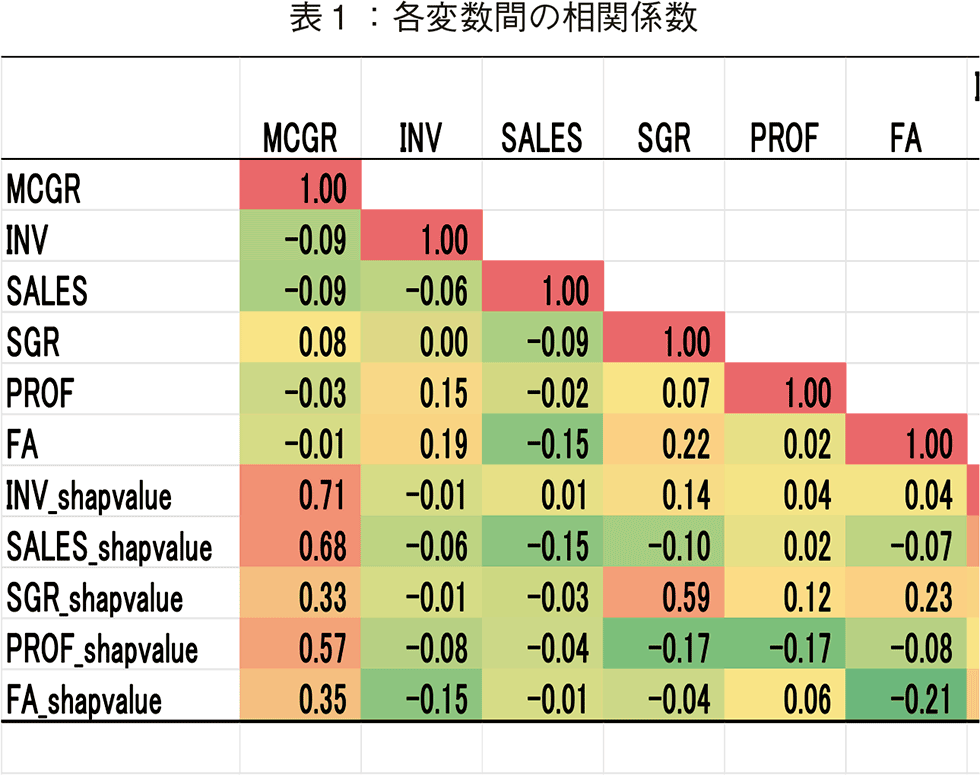
図4にINV_shapvalue(横軸)とMCGR(縦軸)の散布図を示す。青点の分布傾向から,両者に強い正の相関関係(0.71)があることが視覚的に確認できる。とりわけ,インド企業(接頭辞“IN:”),中国企業(接頭辞“CN:”)においてその傾向が顕著であった。大手自動車メーカーの多くは図4中央付近に集積しており,既に大規模資本となった企業においては,MCGRを急速に高めることは困難であり,中規模資本の企業のほうが急成長可能であることが示唆される。例えば,RICO AUTOやMARUTI(インド),INDUS(パキスタン),中国メーカーおよびTESLAは,高いINV_shapvalueに対応してMCGRを伸長させている。この時期のTESLAは,電気自動車(EV)生産台数が2.4万台(2013),3.4万台(2014)と増加して,この後,指数関数的な急上昇を見せる[14]。2014年はTESLAの急成長の黎明期と言える。
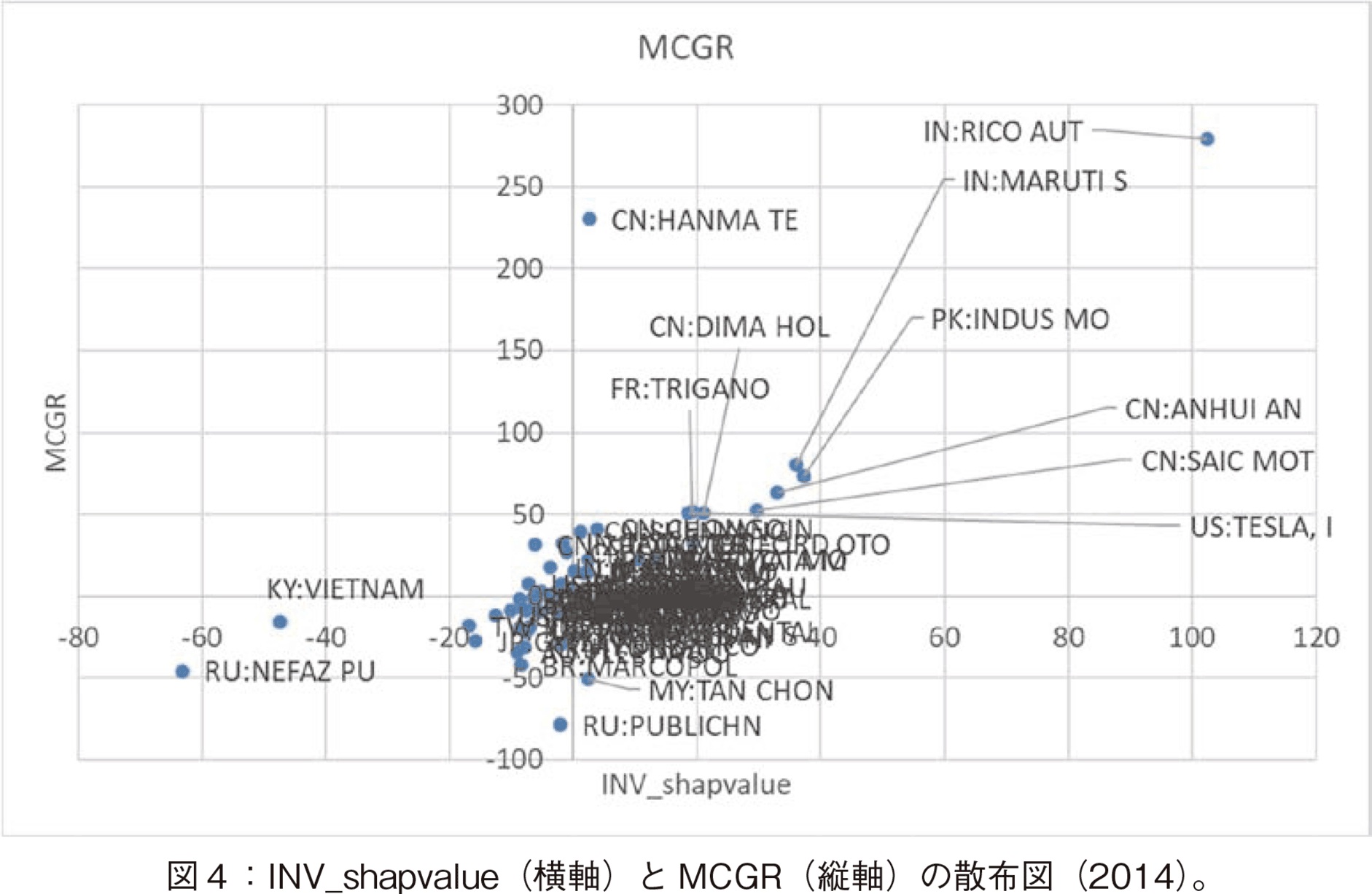
森田とMachucaは「二刀流経営(ambidextrous management)」の概念を提案し,「売上高の成長SGRとサプライチェーン(Supply Chain, SC)の強化・改善(カイゼン)を並行的に持続する企業が,持続的に高い収益パフォーマンス(Earnings Before Interest and Taxes, EBIT)を達成する」と述べている[15]。Tushmanらは,サプライ・チェーン・マネジメント力を“exploitative (operational) competence”,売上成長を“explorative (innovative) competenceと捉え,成長戦略における両者のバランスの重要性を指摘している[16],[17],[18],[19]。一方,2020年以降の自動車産業においては,新製品開発力を示すSGRが主たる成長ドライバーとなっているとの報告がある[20,[21]。他の研究では,2020年以降の自動車製造業における成長の主要因は売上高成長率(SGR)であることが示されている[22],[23]。SGRは新製品開発能力を表す指標と見ることができ,特にEVが市場シェアを拡大する局面では,そのSGRの寄与度が著しく高まる。典型的企業としては,2020年以降のTESLAが挙げられる。一方で,今回のデータの2014年急成長期におけるデータ分析では,棚卸資産回転率(INV)の方が主要因となった。この結果については,次節のクラスタリングの結果も含めて考察する。
次に,SHAP値の分布の類似度によって,64社をクラスタリングする。クラスタリングとは,ラベルのないデータを特徴の類似性に基づいて自動的にグループ分けする教師なし学習手法である[24]。その目的は,データの潜在的な構造やパターンを把握し,類似したデータをまとめることであり,本事例では,MCGRが急成長した企業群を求めることを目的とする。そのため,各社のデータとして,MCGR, INV_shapvalue, SALES_shapvalue, SGR_shapvalue, PROF_shapvalue, FA_shapvalueの6個の値を用いた。クラスタリングの手法はk-means法を用い,距【47頁】 離はユークリッド距離を用いた[24]。クラスタ数kはエルボー法から4と決めた[25],[26]。k-means法によってクラスタリングした結果を,図5に示す。インドのRICO AUTOが単独でクラスタ(クラスタ1)を作っている(図5赤点参照)。また,中国のHANMAも単独クラスタ(クラスタ2)となっている(図5黄緑の点参照)。残りの62社が,図5の黒い点のクラスタ(クラスタ3,赤線で囲った部分)と,青い点のクラスタ(クラスタ0)となった。
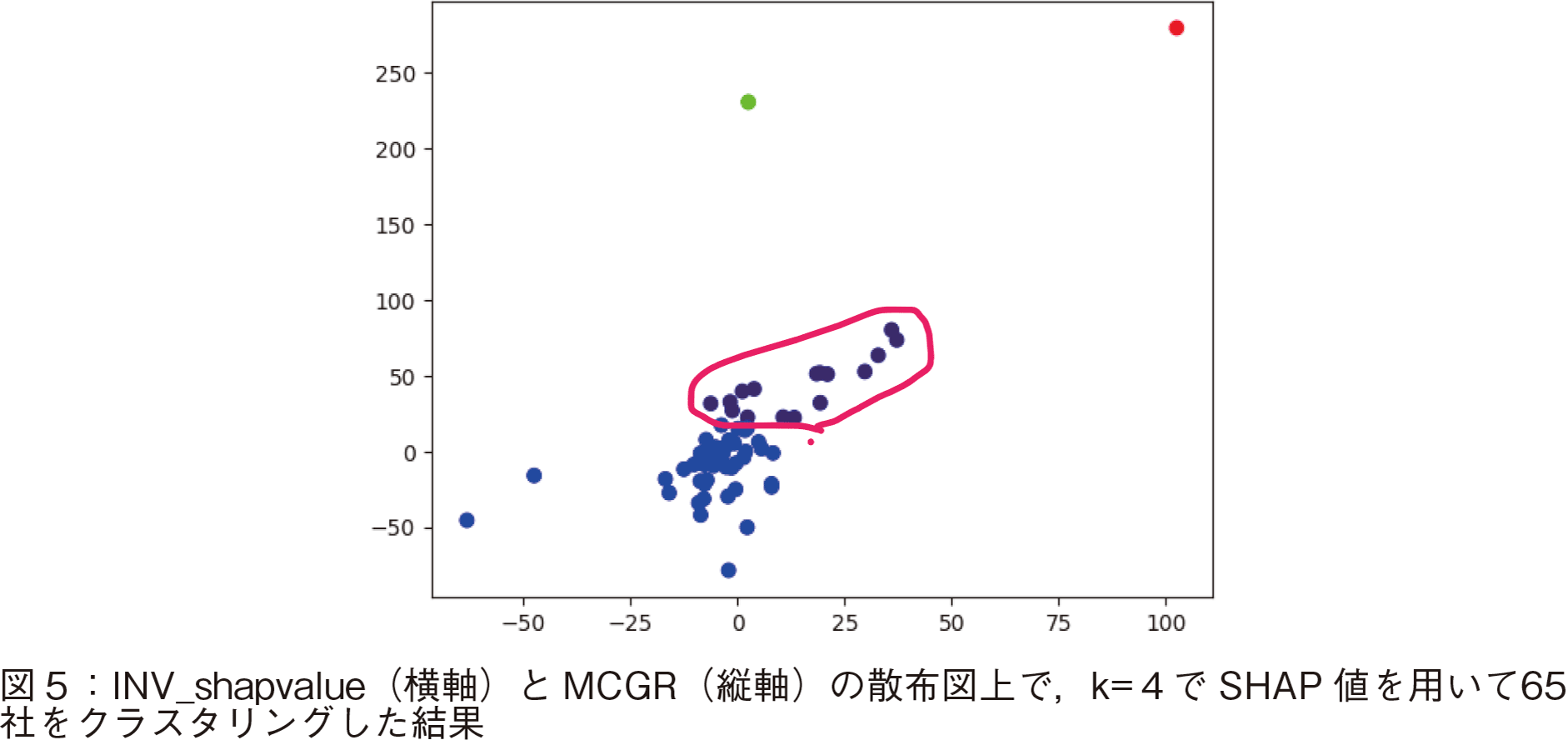
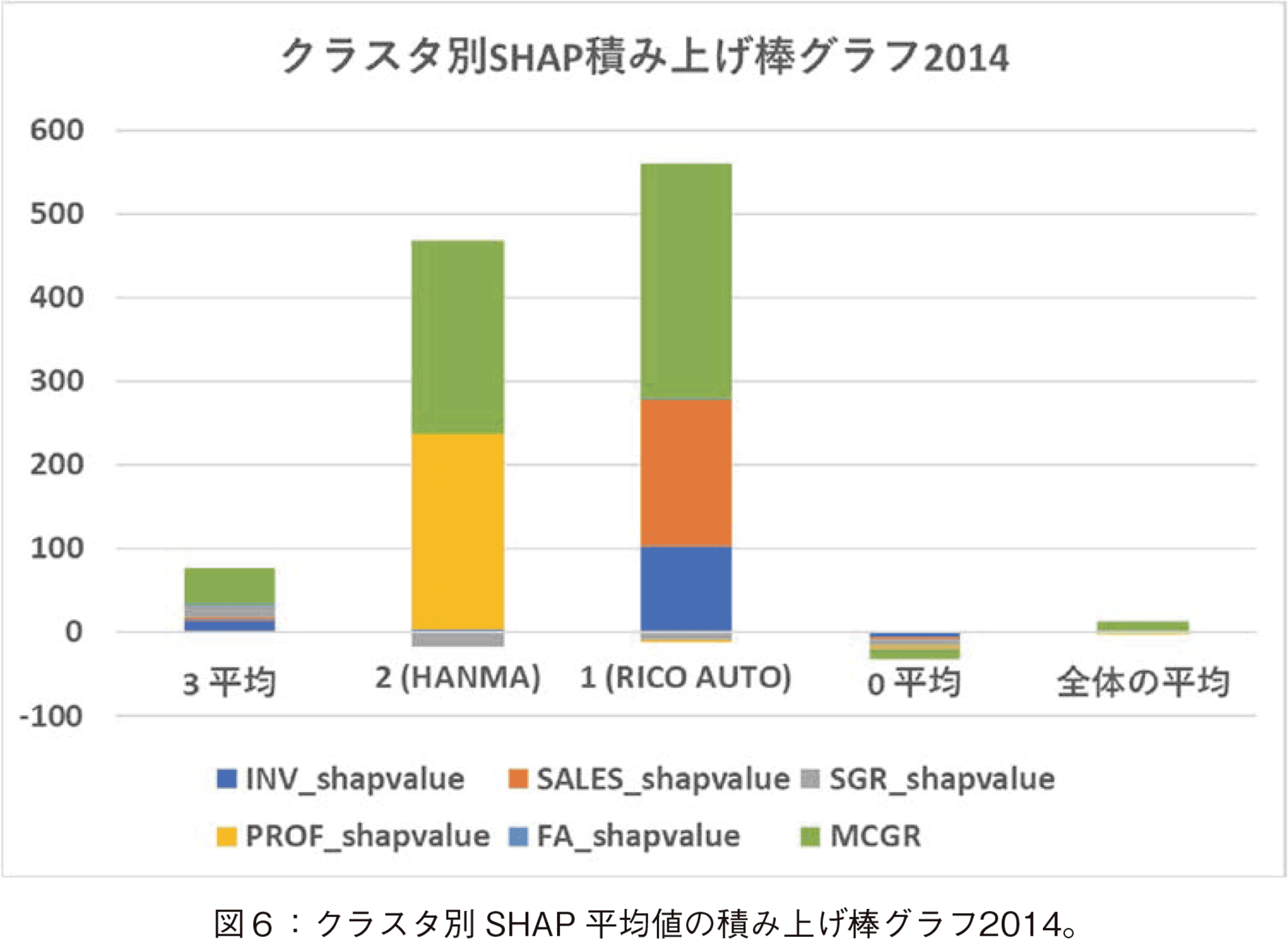
図6に,4個のクラスタの6個の変数の平均値を示した。RICO AUTOの強みは,SALES_shapvalue,ついでINV_shapvalueであり,これら2つの要素がMCGRを向上させていることが分かる。HANMAでは,PROF_shapvalueが主要因である。
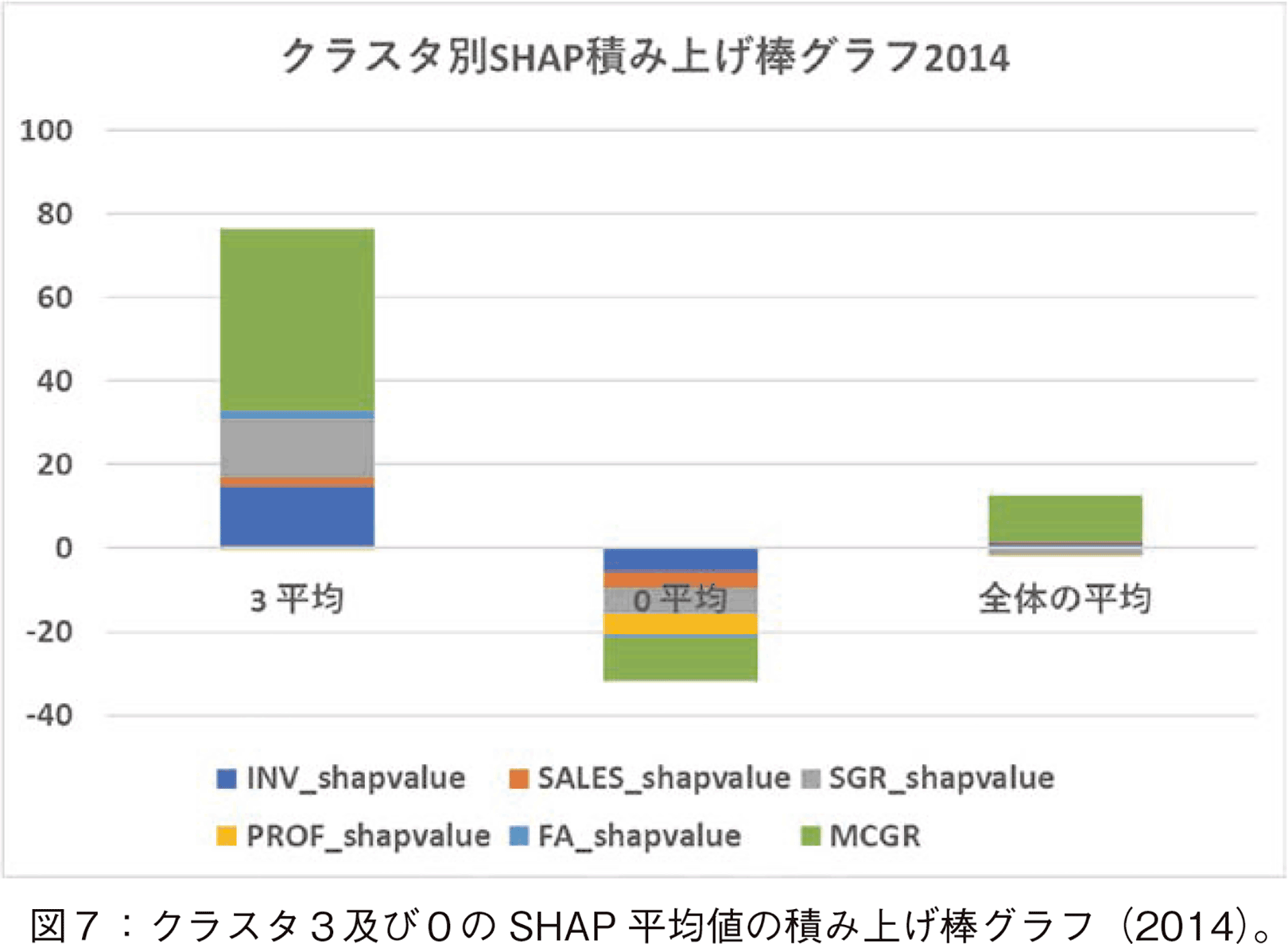
図7に,クラスタ3とクラスタ0の拡大図を示した。クラスタ0は,すべてのSHAP値が平均以下のマイナス値となっている。MCGRの高いクラスタはクラスタ3の方である。クラスタ3では,全てのSHAP値が正であり,64社の平均値よりも高い。INVとSGRのSHAP値がバランスよく大きな値となっている。SALES, PROF, FAのSHAP値は殆ど0である。クラスタ3の企業の個別SHAP値分布を図8に示した。企業別の寄与比率を見ると,MARUTI, INDUS, ANHUI, SAICではINV_shapvalueの比率がSGR_shapvalueを上回っており,棚卸資産回転率の高さがMCGR向上の主要因であることが示唆される。一方,TRIGANO, TESLA, DIMAの3社においてはINVとSGRがバランスよく寄与している。TESLAについては,2020年以降SGR_shapvalueの比重が高まるものの,この2014年時点ではINVとSGRが共に高い寄与を示していた。総括すると,企業のSHAP分布特性に違いはあるものの,上位7社(MARUTI〜DIMA)では,INV_shapvalueとSGR_shapvalueがほぼ均衡して寄与していることが確認された。これは森田らの「二刀流仮説」を如実に示しており,INVとSGRが両輪となって高いMCGRを支えていることを意味する。SHAP分析においては,このような企業ごとの特性が明確に可視化できる点が大きな利点である。
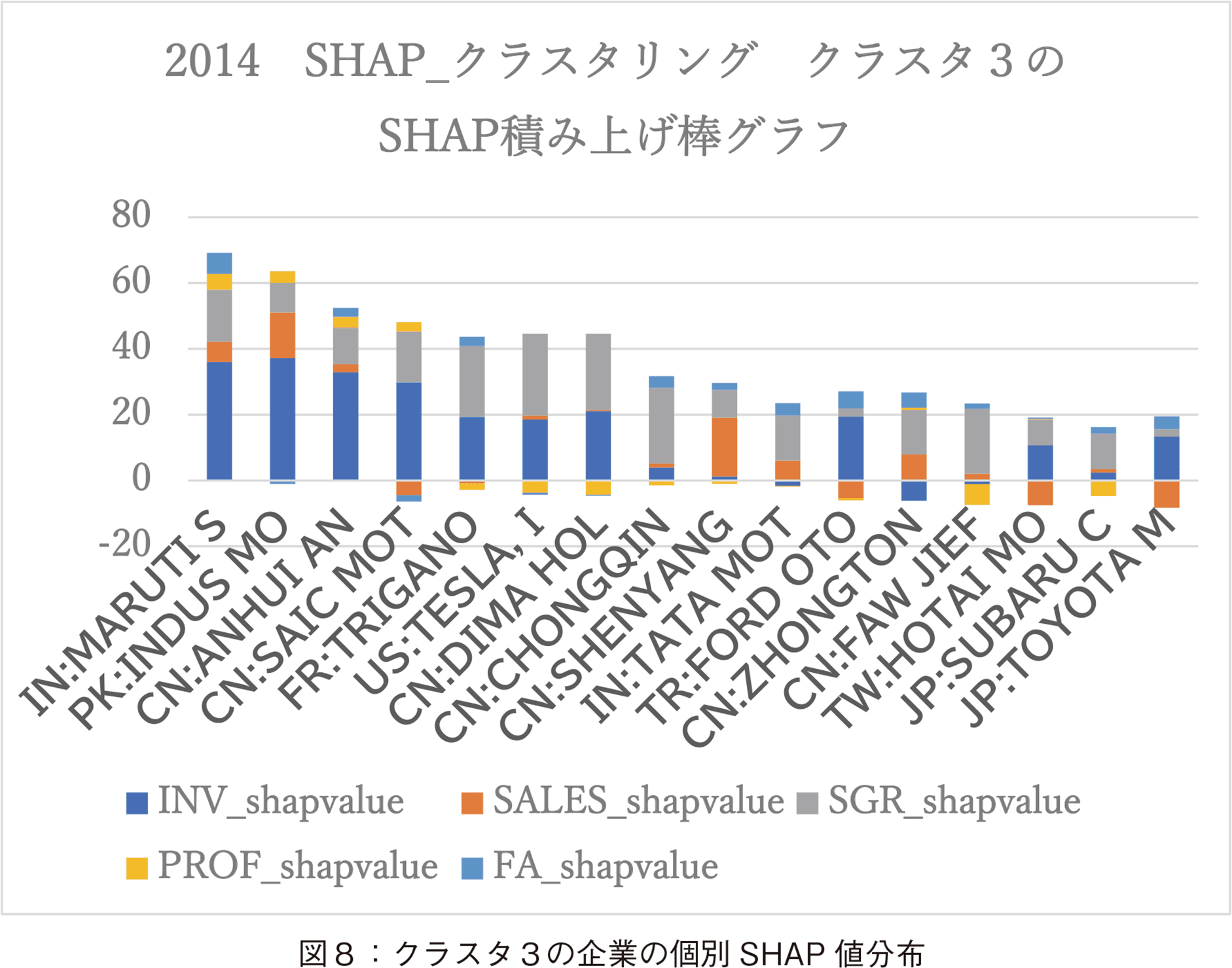
表1によると,MCGRとの相関係数は,INV_shapvalueが0.71と最も高く,SALES_shapvalueが0.68,SGR_shapvalueは0.33であった。これはクラスタリング前の結果である。SALES_shapvalueとの相関が最も高かった要因として,RICO AUTOが極めて高いMCGR及びSALES_shapvalueをもつ点が挙げられる。RICO AUTOの存在が,全体のSALES_shapvalurを引き上げた。そのため,SGR_shapvalueの寄与は全体では0.33と小さくなった。クラスタリング後,MCGR上位企業のクラスタに限定して分析すると,SGR_shapvalueが上昇することが確認された。本研究では,SHAP値に基づくクラスタリングを用いることで,全体的な傾向だけでは把握しづらい企業ごとの特性を明らかにすることができ,結果として,SGRとINVがバランスよく高い製造業ほど高いパフォーマンスを維持するセオリーが成立していることを確認できた。
本節では,MCGR値の高い企業から,この時代の世界自動車製造業の動向を分析する。
表2に,MCGRのTOP20企業を売上高(千ドル)及びMCGR(%)と共に示した。売上高が比較的小さい企業が多い中,売上高の大きな企業として,TOYOTA,ついでSAIC,TATAの順に大手メーカーも並んでいる。
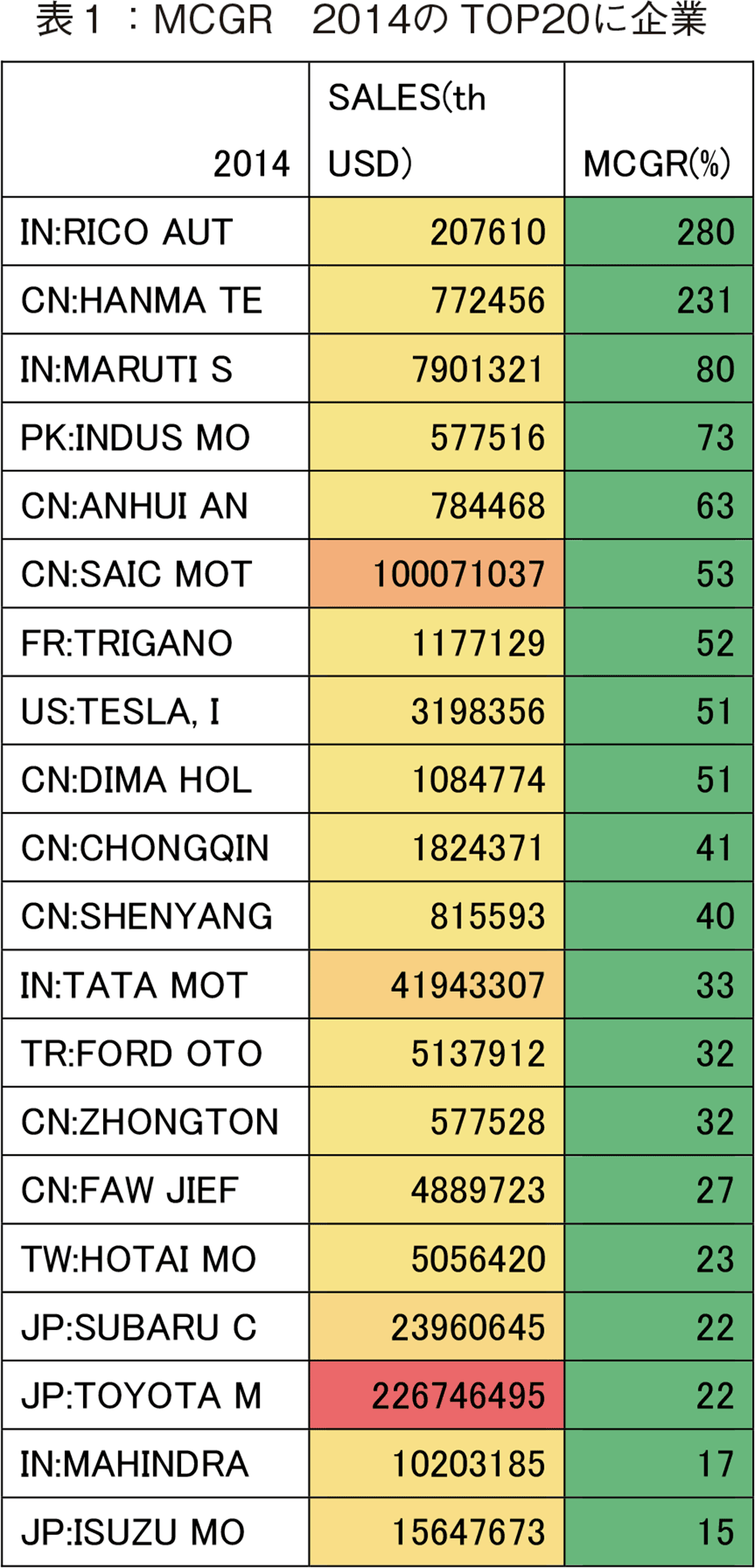
表2を見ると,最もMCGRの高い会社はインドの自動車部品サプライヤRICO AUTO(以後RICO)である。インドのMARUTIも3番目にいる。MARUTIは,インドの自動車工業化を達成した始めての企業であり,1983年に生産を開始した。始めはインド政府と日本のSUZUKIとの合弁会社であったが,SUZUKIが次第に出資比率を高め,2002年に子会社化,2007年に社名をMaruti Suzuki Indiaに変えた。RICOはMARUTIとの提携が非常に強く,MARUTIの主要な部品供給業者のひとつである。RICOの歴史を見ると,”1985-86: Focus - Hero Honda & Maruti Suzuki, 1990-92: Focus - Maruti Suzuki”とある[27],[28]。2014年時点では,取引先にTATA, NISSAN, TOYOTAなど多くの大手企業が名前を連ねるが,黎明期に最重要契約先であった企業はMARUTIであると推測される。
MARUTIが育成したインド部品メーカーは多数ある。Jay Bharat Maruti LimitedおよびKrishna Maruti Limitedの両社は,企業名に「Maruti」を冠する,Maruti Suzuki India Ltd.の出資・協業の下で自動車部品を製造する合弁会社および子会社である。また,Samvardhana Motherson 【51頁】 Sumi Systems(旧:Motherson Sumi)やSundram Fastenersなど,インドの主要部品メーカーにもMaruti Suzukiとの取引実績が豊富な企業が存在する。これらは,Maruti Udyogによる部品サプライヤ育成による成果事例といえる。表2に示す2014年のMCGR上位20社のうち,インド企業としてTATA MOTORSとMahindra & Mahindraが含まれているが,両社はいずれもインドを代表する財閥系企業である。MARUTIが同国の部品サプライヤ育成に果たした好影響は,これら企業にも大きく波及したと考えられる。高品質な部品サプライヤが育成されることで,他の自動車メーカーとの取引範囲が拡大し,優れた技術力や行動規範が業界全体に伝搬していくことが期待されるからである。MARUTIの果たした影響のエビデンスとして,インド政府が,2024年12月に逝去した鈴木修氏(スズキ株式会社元会長)に対し国家勲章「パドマ・ビブシャン」を追贈したことは,同氏の功績を高く評価した証左と言える[29]。ナレンドラ・モディ首相も追悼の辞の中で,「インドに対する深い愛情を抱き,インドの自動車市場に革命をもたらした」と述べており,その影響力の大きさがうかがえる。
インドから東南アジアに視点を広げてみる。2014年ごろに東南アジア諸国で自動車製造業が大幅に成長した。その要因として,遡った時代に日本の自動車産業が日本式経営などを東南アジア諸国に導入して現地部品メーカーを育成したことがある[30]。2014年の東南アジア諸国での日本メーカーの市場シェアは高く,インドネシア92%,タイ87%,フィリピン76%,ベトナム53%,マレーシア41%,インドではMARUTI単独で45%である[31]。MARUTIの親会社スズキにとって,インド(1983年生産開始),及びパキスタン(1975年現地生産会社)では,競争相手のいない時代が長く続いた。この理由は政情不安なため大手メーカーが参入しなかったためである[32]。その後,1995年ごろを境に,Volkswagen AG(VW)は中国へ,トヨタは東南アジアへ攻勢をかけた[33],[34]。その結果,中西によると,2012年市場シェアでは,アジア他で,トヨタグループ17%,VWグループ3%であるが,中国では反転して,トヨタグループが4%,VWグループ14%である。インドへの進出としては,HONDA CARS INDIA LIMITEDが1995年に設立され,HYUNDAI MOTOR INDIA LIMITEDが1996年設立,TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR PRIVATEが1997年に設立された[32]。東南アジア諸国における日本メーカーに共通する特徴は,(1)小型車中心の製品戦略,(2)日本式経営手法および生産管理方式の採用,である[2],[4],[35]。とりわけ生産開始初期に,現地の方々が購入しやすい小型車に注力した点が重要であり,現地のGDP向上に直結する戦略といえる。東南アジア諸国で自動車製造を立ち上げた際は,小型車や軽自動車から展開することが有効であったと言える。
中国も同時期に自動車製造業の急成長を遂げており,表2にもMCGRの高い企業としてSAIC Motor Corporation Limited(上海汽車集団)およびFAW(First Automotive Works, 中国第一汽車集団)が出てきた。この2社は海外企業との合弁事業を通じて市場競争力を強化した[36]。SAICは1984年設立の上海フォルクスワーゲン,及び,1997年設立の上海ゼネラルモーターズを中核に,欧米ブランド車の生産・販売を担った。一方FAWは1991年設立の一汽フォルクスワーゲンおよび2003年設立の一汽トヨタを通じ,フォルクスワーゲン,トヨタブランド車などを生産し,中国市場で重要な役割を果たした[36]。このように中国の場合,1970年代以降,特にドイツ企業との経済連携が強化された歴史的背景がある。次節では,このような背景の違いを踏まえつつ,インドにおいてなぜMARUTIが圧倒的シェアを維持し続けたのかを分析する。
本節では,インドにターゲットを絞り,MARUTIの成功要因を探る。
本節では,インドの企業に焦点をあててデータ分析する。
前節では回帰分析の結果をSHAP値によって解釈した。全65社中,インドの企業4社が含まれていた。MARUTI, TATA, MAHINDRA, RICO AUTOである。これらのSHAP値を図3から抽出したものが図9である。RICO AUTOのMCGRが非常に高く,SALESのSHAP値の貢献が最も大きく,ついでINVのSHAP値が高い。SGRのSHAP値が65社の平均程度である(殆ど0)である理由は,部品メーカーであるためと我々は推測する。図10に,見やすさのため,RICO AUTOを除いたインド3社のSHAP値を示した。
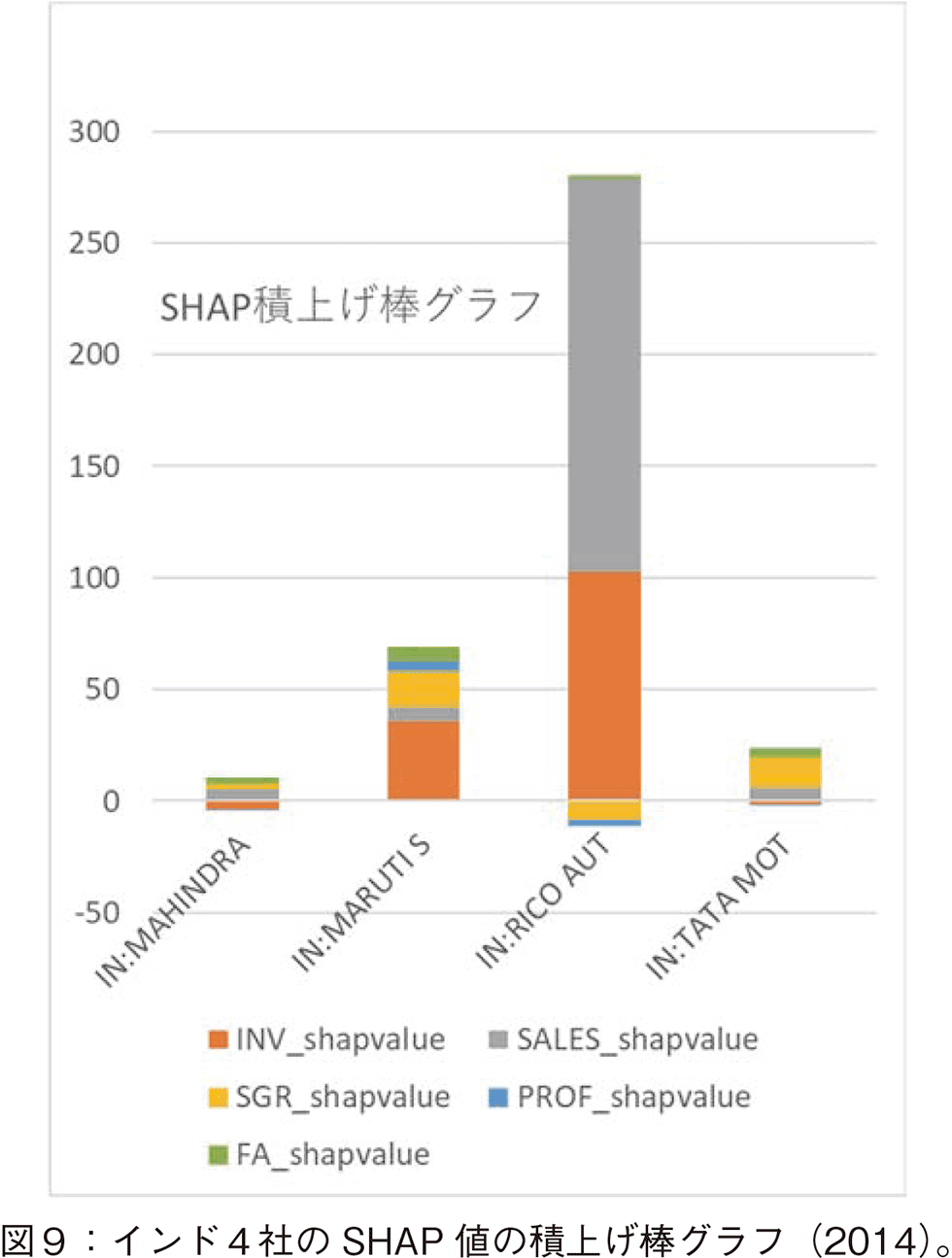
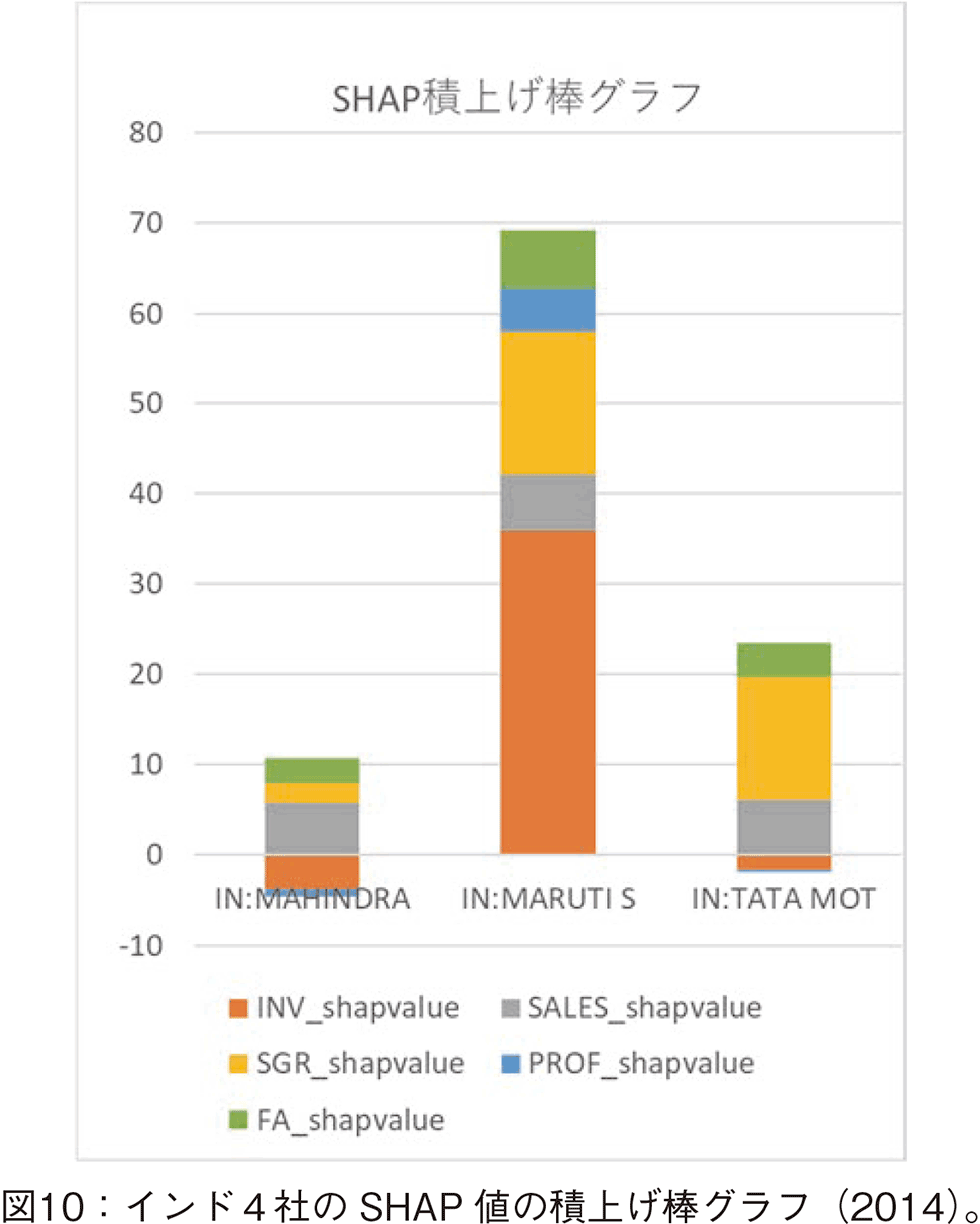
MARUTIのMCGRが最も高い。MARUTIは,INVの貢献が最も大きく,ついでSGRのSHAP値が高く,INVとSGRのバランスがよい。これはハイパフォーマンス企業の特徴である。TATAはSGR主導型であり,INVは65社平均を若干であるが下回っていることが分かる。MAHINDRAでは,SALESのSHAP値が最も高く,FAとSGRが同程度,INVは平均を下回っている。この結果をまとめると,MARUTIは3社中,INVとSGRがバランスよく貢献しているハイパフォーマンス企業型を示し,特にINVの貢献が主導的である,と言える。
次に,この3社他の経営指標を用いて,2011年から2015年のインドの自動車製造業の状況を分析していく。データはORBIS WEBから検索した。インド企業の2011年から2015年のデータでは欠損値が多いため,欠損値は補間せずそのまま空白とした。代表的な企業,MARUTI, TATA, MAHINDRAの他,多くのグローバル企業が存在するが,この時期グローバル企業でデータが取得できた指標は,税引前利益(Profit/Loss Before Tax, PLBT)のみであった。売上高などの単位はすべて千ドル(thousand USD)である。
図11のPLBTの推移をみると,TATA, MARUTI, MAHINDRAの3社の利益が圧倒的に他のグルーバル企業に対して高く,中には損失計上の企業もあることが分かる。PLBTが最大な企業はTATAであるが,MARUTIは2011年から2018年,市場シェアを41.4%から51.8%へと伸ばし,TATAは12.3%から6.4%に減少した[37]。MARUTIの2011年からの成長の様子は着実にインドの拡大需要を取り込んだMARUTIの伸びを示している[37]。
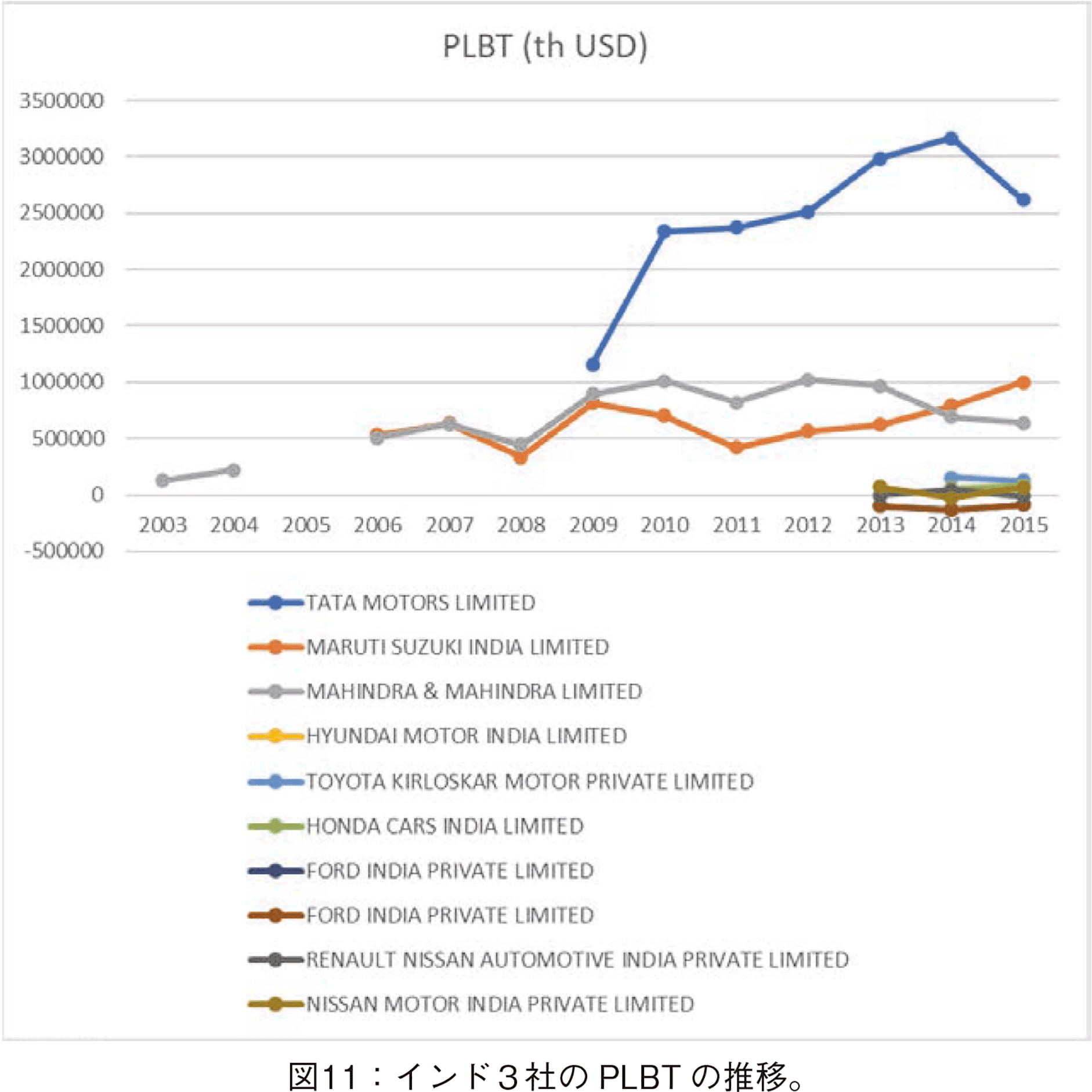
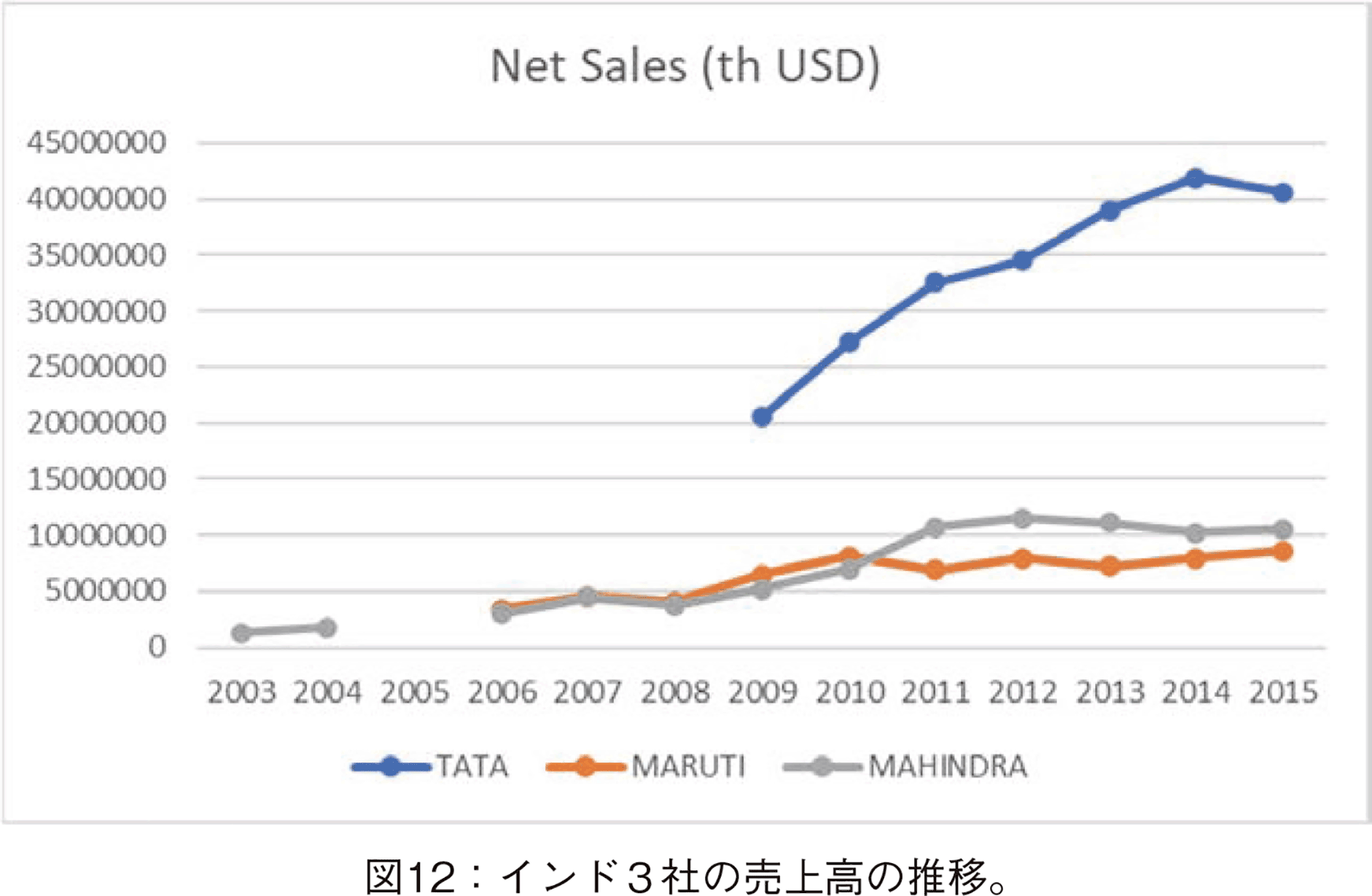
代表的3社の経営指標の特徴を見ていく(図11から14参照)。売上高(Net Sales)及びPLBTでは,TATAが最も高い値であるが,利益率(=PLBT÷売上高)では,2014年以降MARUTIが最も高く,2011年からほぼ1次的直線的に着実な増加傾向を示している。棚卸資産回転率(INV)もMARUTIが常に非常に高い(図14参照)。図10のSHAP値分布の比較では,MARUTIのINV_shapvalueが非常に高く,他の2社では平均を下回っていた。その要因として,このような棚卸資産回転率の高さがある。棚卸資産回転率の高さは日本式サプライ・チェーン・マネジメント方式の力によるものと考えられる。
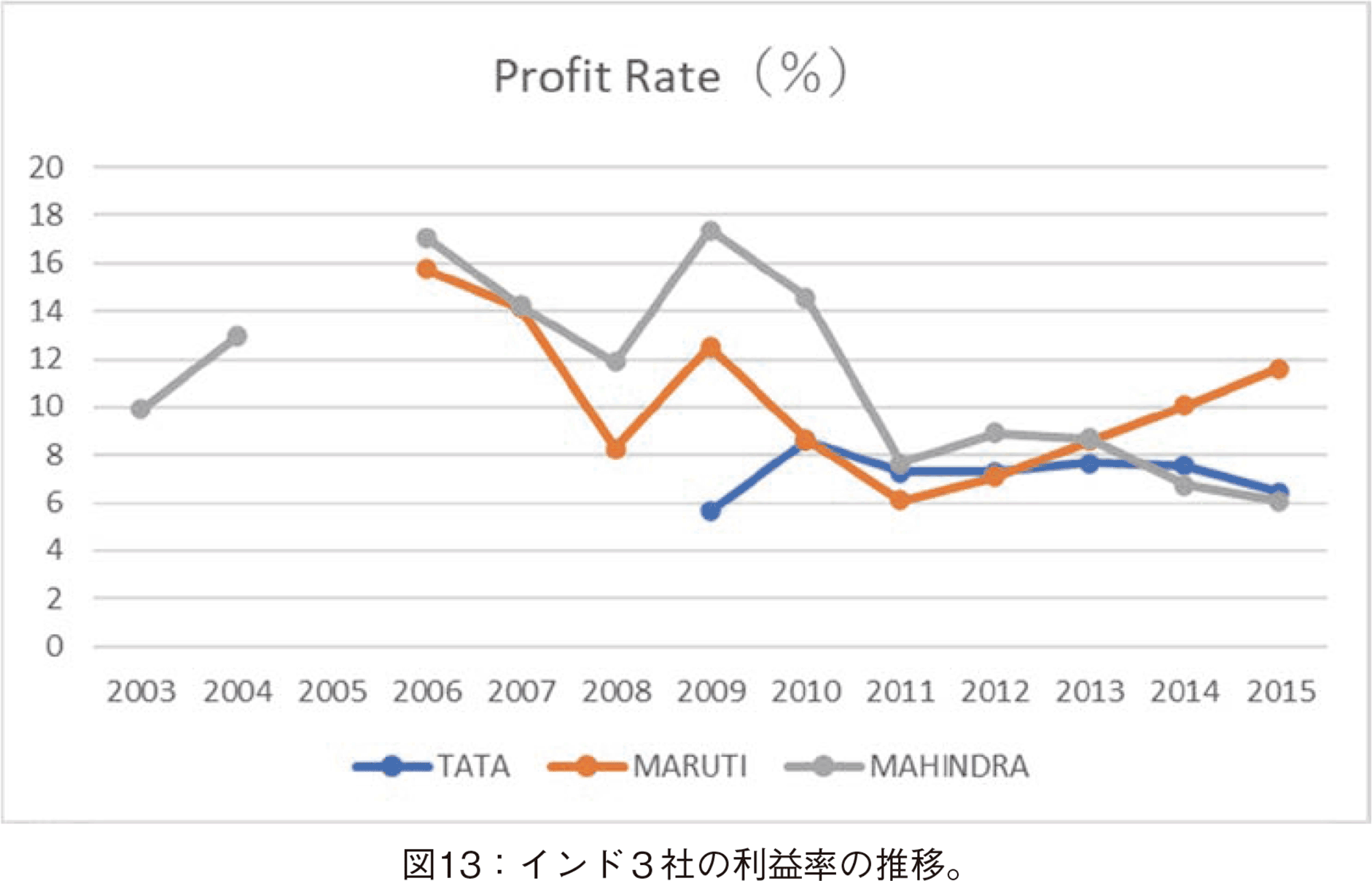
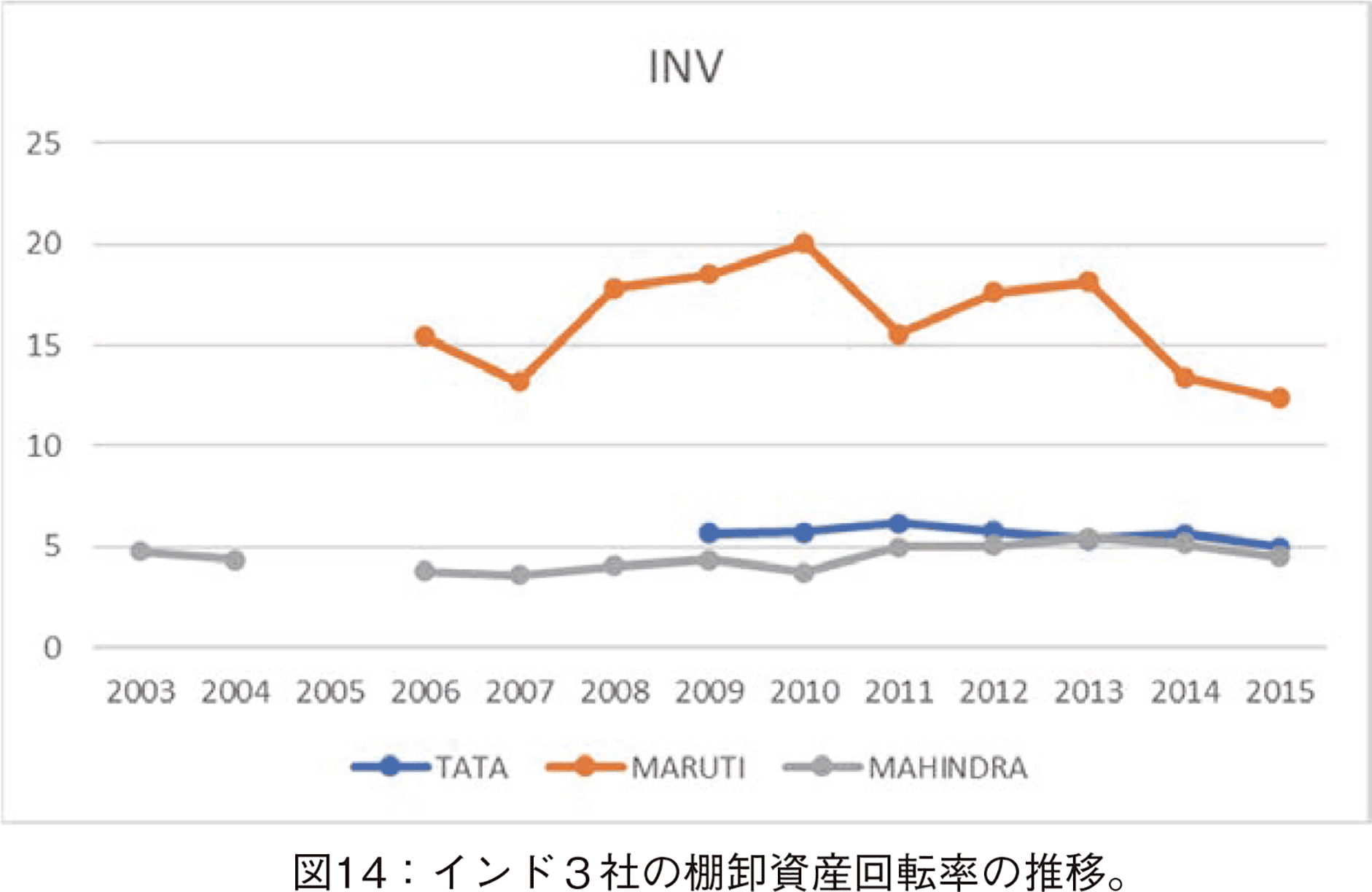
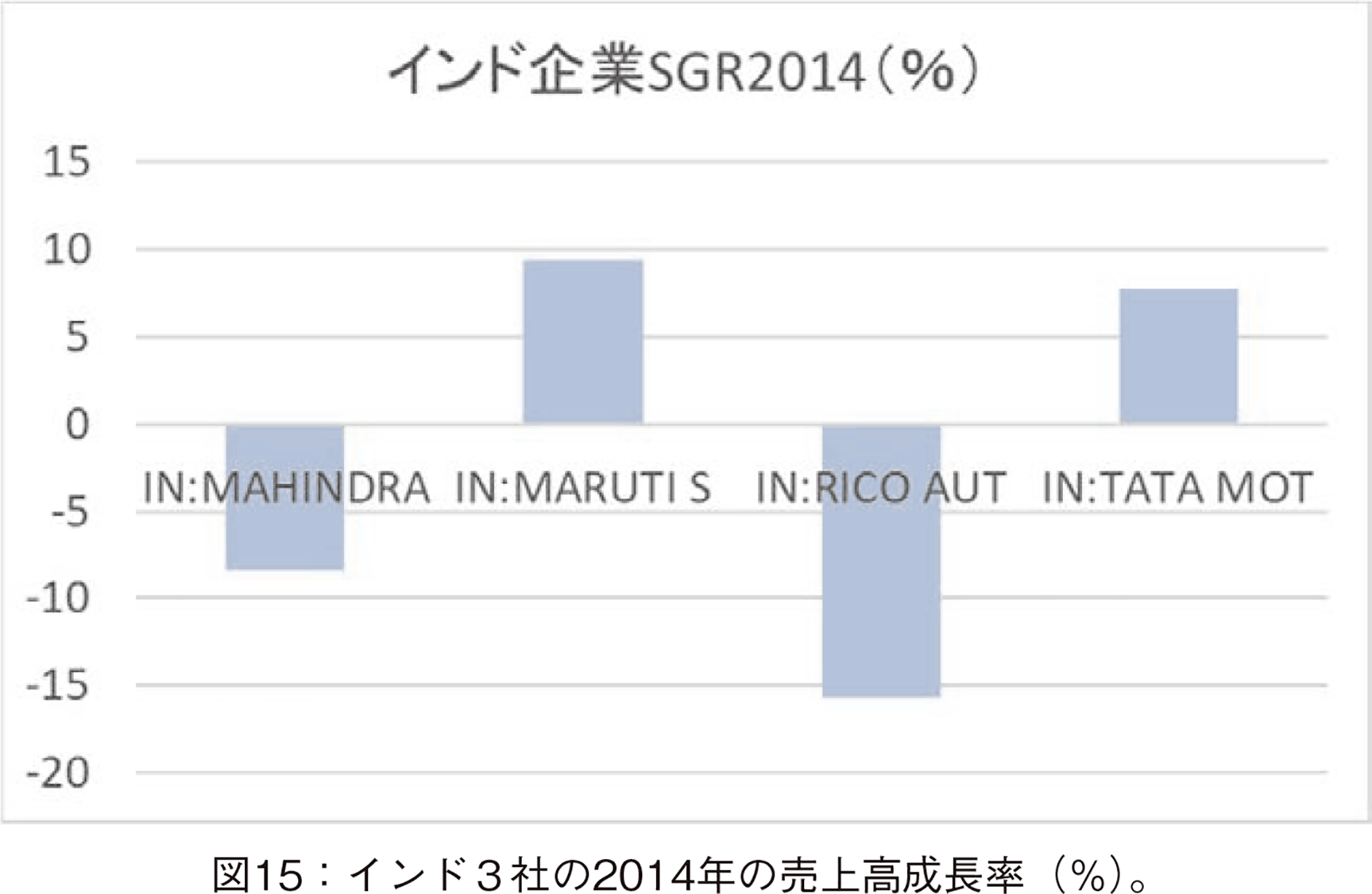
さらに,SHAP値によって明らかになった売上高成長率(SGR)の貢献について見ていく。SHAP値の優れた点は,SGRの生データを比較したのでは,図15のようにMARUTIとTATAの違いは目立たないが(MARUTIが若干高い),その企業のもつ特性(他の説明変数の値)を考慮すると,MARUTIの中では,INV_shapvalueの比率が圧倒的にSGR_shapvalueの比率よりも高くなることである(図10参照)。TATAにおいては,SGR_shapvalueの比率が最も高い値となる。生データ値で同じ位の値を取っていても,その企業の他の特性値を含めて考慮するので,そのSHAP値の比率は変わってくる。SHAP値は各企業の特性を考慮して評価可能である点が,AI結果の評価手法として優れている。今後は,2011年以降のSHAP分析を時系列に行い,SHAP値の推移について分析していきたい。
MARUTIの部品メーカー育成,教育に焦点をあて,サーベイを行う。
MARUTIがインドの部品サプライヤの育成に果たした影響は大きい。バルバガは,UDYOGの設立時「我々は既に自動車関連産業に従事している既存の現地企業を,MARUTIの部品メーカーに育てていく方針を打ち出した」と述べている[4]。これは,日本の技術を持ち込むのではなく,MARUTIがインド国内での国産化比率向上に努め,ものづくりという本業の分野で現地部品メーカーにアウトソーシングを積極的に行い[37],部品メーカーを単なる下請けではなくパートナーとして遇したところに特長がある[1]。1982年,MARUTIは部品メーカー育成計画を策定したが,その特徴はMARUTIと部品メーカーの相互の長期的なパートナーシップを基礎に置くものであり,後に国連工業開発機構(UNIDO)は,MARUTIのこの育成プログラムを発展途上国の製造業において広く応用可能なモデルであると高く評価した[4]。
芦澤は,インドの部品サプライヤ”Imperial Auto Industries Ltd.”社長に2011年2月16日にインタビューし,MARUTIが果たした役割について聞いている[38]。その社長の答えは「日本のスズキがインドへ来てからインドでの車の考えが大きく転換した。それまでは車の部品の不良【57頁】 はある程度あるのは当然と考えられてきた。それでも車として堂々と売られていた。しかしスズキがインドへ来てから車の機能と品質に対する考えが大きく転換した。不良部品があってはならず,売ってはいけないという考えがインドでも定着するようになっている」とあり[38],MARUTIが直接教育・育成に携わっていないサプライヤに対しても意識変革を及ぼしたことが分かる。このImperial Auto Industriesは,インド国内・国外の多くの組立メーカーやサプライヤと取引があるが,特段MARUTIとの強い関係はない。よって,この社長の言葉は公平なインドサプライヤの意見として信頼がおけると考える。
MARUTIの設立以来の歴史を見てみる。1984年前後,スズキ以外の日系自動車製造業社によるインド進出があった。例えば,トヨタがDCM(Delhi Cloth & General Mills Co. Limited)との合弁でDCM Toyota Ltd.を,マツダがPunjab Tractors,住友商事との合弁でSwaraj Mazdaを立ち上げ,技術提携を開始している。しかし,1985年のプラザ合意に伴う円高の流れにより,TATAなどの地場メーカーが台頭し,これら日系企業が撤退を余儀なくされた。MARUTIだけは国産化比率向上に努めていたおかげで,円高の影響を受けることなくインド国内市場のTOPシェアを守ることができた[39]。これは,MARUTIの部品国産化比率の高さによる結果と言える。
2010年前後,再度,グローバル大手企業はインドに進出を試みた。Govindarajanは,「新興国市場の攻略においてグローバル企業が先進国の資源を利用すると価格上昇につながり,また,消費者ニーズに適さない。そのため新興国専用の新製品を開発する必要がある」と述べている[37],[40]。大手企業はこのセオリー通り,インド専用の戦略的モデルを導入し,対印進出を行った。例えば,2010年のトヨタのEtiosがあり,他社では,ホンダのBrio, Amaze, Jazz,ヒュンダイのi20, Eon, 日産Goなどがある[37]。しかしこうした他社の進出にもかかわらず,MARUTIはスイフト(Swift)の大規模な売り上げによりTOPシェアを守った。スイフトはインドの小型車の価格破壊を起こした車であり,価格は39万ルピー(当時の為替レートで67万円)から中心価格帯でも45万ルピー(同77万円)であった[33]。中西は,「この低価格化の原動力は,非常に高いインド国産化率であり,その結果グローバルブランドがどうしても手が届かない低価格が実現できた」と分析している[33]。
上野・佐藤は,スズキ(MARUTIの親会社)が有する本国資源である軽量化技術と,顧客メリットである購入および維持コストの低さに関連性があることを明らかにした[37]。同氏らは,スズキの競争優位性を,本国資源の活用と,それを時間をかけてインド市場に段階的に適応させてきたインクリメンタルな戦略に求めている。確かにスズキの軽量化技術は高水準である。しかし,トヨタやホンダが最終的にMARUTIの市場シェアを奪えなかった理由を,これのみで十分に説明可能であるのか,疑問が残る。技術的な問題以外に成功要因があるのではないか,と我々は考える。
上野・佐藤の研究では販売車種の仕様の比較により原因を探している[37]。しかし果たして,車の仕様のみで十分な説明とみなされ得るのか,疑問が残る。たとえ顧客ニーズに合致するスペックが判明したとしても,その要求仕様を低コストで実現できるか否かは別問題であり,実装の障壁となる可能性が高い,と我々は考える。多くの場合,コスト競争力を維持するため,機能を削減せざるを得ない。中西の言うように,MARUTIが他社の攻勢を退けた最大の要因は,やはり部品の高い国産化率にあると考えられる[33]。
次に,MARUTIがインドで行った教育について考察する。競争力を養成するためには,バルバガ(元,MARUTI社長)が指摘するように,地道な教育が重要である[2],[4]。教育対象は,(1)工場の労働者,(2)経営者・管理職(意識改革),(3)販売店(サービス),(4)部品サプライヤなどがある。MARUTIは管理職から従業員,労組幹部までを教育のため日本に派遣し,技術だけでなく,日本文化,習慣,経営システムまでも,その教育内容に盛り込んでいた[4]。上記4種類の人たちへの教育のうち,我々は,特に部品メーカーの育成教育が最も困難であったのではないかと考える。自社社員の教育と比較して,現地サプライヤを対象とした教育は,まず信頼関係の構築から始める必要があるからである。MARUTIは部品メーカーとの物品および代金のやり取りをIT化し,透明かつ公正・迅速な支払いシステムを整備することで,サプライヤとの信頼関係を着実に築いていった[4]。この「迅速な支払い」を率先するという,中小企業経営者的な提携先への細やかな配慮は,故・鈴木修社長が自らを「中小企業のおやじ」と言うように[41],故・鈴木修社長の面倒見のよさや「パートナーシップ」の理念を体現していると言える。こうしたサプライヤ育成の長年の努力がMARUTIの高い国産化比率につながったと言える。
インドにおいて,単に,教育にコストと時間を投入すれば成功するといった単純な図式は成り立たない。突き詰めて考えていくとMARUTIの真の強みは,バルガバ及び故・鈴木修の言う「下請けでなく長期的パートナーと位置付ける」その行動規範にあったのではないかと我々は考える。インドの人はMARUTIブランドを,インドがインド人のために製造する自分たちの国民車であると思っている[33]。それは,MARUTIが着実に構築してきた消費者及び部品メーカーとのパートナーシップの結果であると考える。
そこで以下のような仮説を設定する。
仮説1:2010年代に大手自動車メーカーがインド市場へ相次いで進出したにもかかわらず,MARUTIがトップシェアを維持できた主因は,インドの部品メーカーを短期的な下請けと見なすのではなく,長期的な事業パートナーとして位置づけ,育成・教育に注力したことにある。一般化すれば,新興国市場への製造業進出においては,「進出先国家との共存共栄を重視する」行動規範が企業の長期的かつ持続的な成長にとって重要である。
故・鈴木修社長の面倒見のよさや「パートナーシップ」の理念を体現していると言える[42]。労働組合と経営者,親会社と下請けのように対立し得る関係においても,各組織は自らの利益を追求するだけでなく,相互の繁栄が結果として自身の目的達成やキャリア形成に寄与するという共通認識を持つことが重要である。この精神的規範は数値化が困難であるため,データ分析からは測れない。そこで証左となる事例を探してみる。スズキはインドにおいて,インド工科大学ハイデラバード校(IITH)と連携したスズキ・イノベーションセンター(SIC)の運営や,社会課題解決型スタートアップへのインパクト投資ファンド設立・支援などを通じ,共存共栄の文化を具現化している[43]。特にNext Bharat Ventures(NBV)を介した取り組みでは,社会起業家を発掘・育成し,そのソリューション実装に協働することで雇用創出と所得向上を同時に目指している[44]。これらの活動は地域コミュニティの持続的成長を牽引し,スズキの長期的成長基盤を支えていると言える。白田・チャクラボルティらは2025年1月にIITHのSICを訪問し,農業やサプライチェーン分野で活動する社会起業家の支援プログラムを取材した。これらの草の根的な取り組みは定量的指標では捉え難いものの,現地における自他共栄の【59頁】 文化醸成を着実に促進していることが印象的であった。
また,MARUTIは,ハリヤナ州マネサール工場において,廃棄物由来のバイオマスガス生成施設を導入し,再生可能エネルギーの活用に取り組んでいる。工場内の食堂から排出される食品廃棄物および敷地内で栽培されるナピアグラスを原料とし,日量約0.2トンのバイオガスを生成している[44]。白田は2025年1月に同工場を訪問し,バイオマスガス生成プロセスを見学した。バイオガスは,主として工場内食堂における煮炊き用燃料として使用されており,化石燃料の代替エネルギー源として機能している。またバイオガス生成後に残る副産物は有機肥料として再利用され,工場敷地内の緑化活動に活用されている。実際にこのバイトガスをタンクに詰めて自動車を走らせる。こうした取り組みを通じて,SDG的再生可能エネルギー活用と地域社会への貢献を両立させる持続可能な製造業のモデルケースを提示している。
スズキは小さな巨人と呼ばれる[33]が,本節では,MARUTIの成功要因を教育という側面から分析し,規模資本の企業が教育により,競争力を育成し大資本企業となる戦略について論じる。
経営戦略において,教育は重要である。松橋らは,サッカーチームの経営戦略において,「資本力が小規模なチームが大規模資本チームとの競争力(勝ち点,勝率など)を得るためには,アカデミーでの選手育成に投資することが有効な手段となりうる」という結論を得た[45],[46],[47]。これは一般化可能なセオリーと考える。資本的に小規模な企業であっても,教育に投資することで,優秀な人材を育成すれば,大規模資本企業との競争力が養成可能であり,こうした教育に熱心な企業はインクリメンタルに大規模資本企業へと遷移可能である。図16に,中小規模から大規模への遷移状態にいる強いサッカーチームをマークで示した[46]。この分析にも,本稿のようにSHAP値による分析手法が活用されている。松橋は,アカデミー運営費用のSHAP値をコアにして,教育成果達成度の指標を作成した。一般に,企業の経営戦略では適格なKPI(Key Performance Index)の設定が重要であるが,KPIを作成する際にSHAP値をコアとして利用することは有効である,と白田は考える[48]。
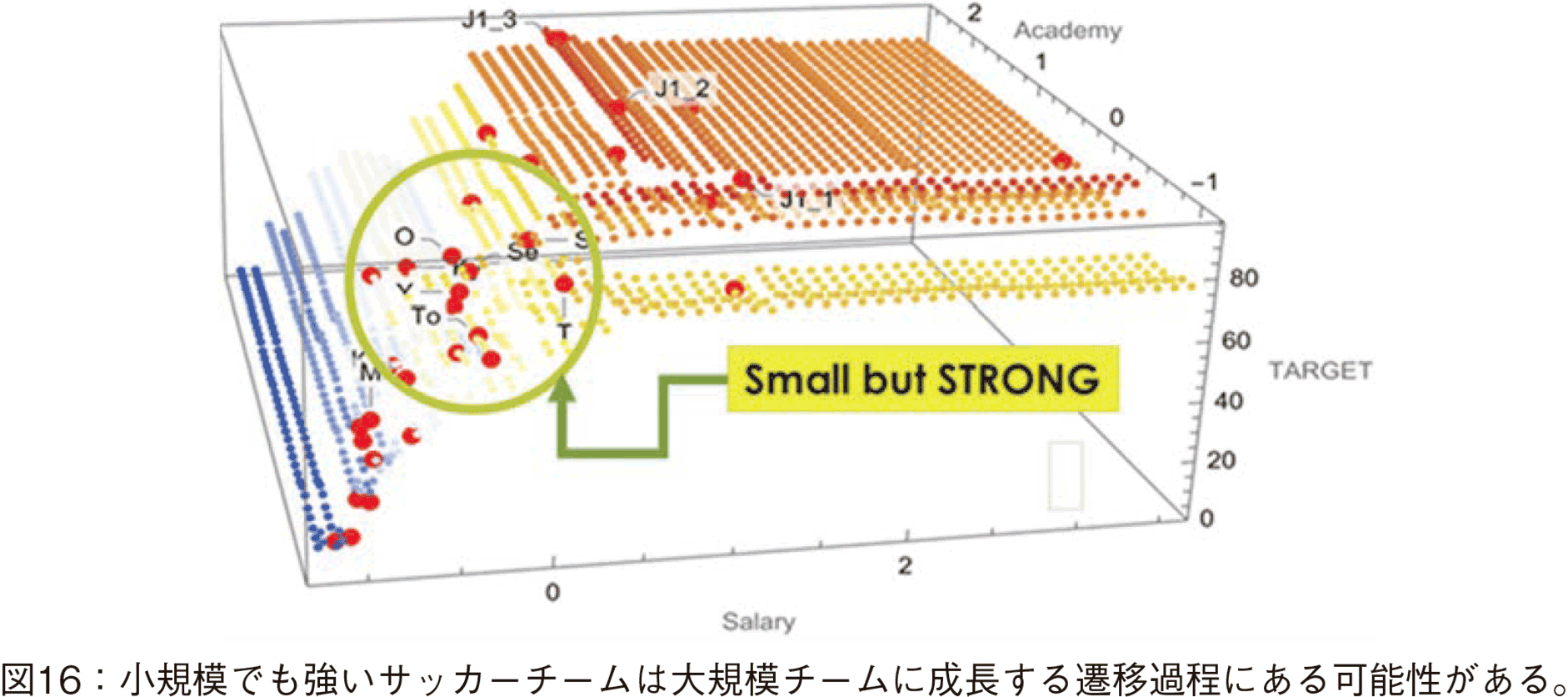
本研究では,スズキ(MARUTIの親会社)のように,売上高や従業員数ではグローバル大手に比較して小さいけれども,「小さな巨人」[33]と呼ばれ,インド市場で驚異的なトップシェアを獲得・維持している原動力を,「教育力」に求める。前節の我々の仮説を含めると,共存共栄の精神に基づく教育,となる。当時のスズキは,小型車の高効率かつ低コスト生産技術を確立していたことに加え,故・鈴木修社長の卓越した経営センスのもと,現地スタッフおよび部品サプライヤを単なる労働力や下請けとみなすのではなく,長期的な事業パートナーとして位置づけ,継続的な育成プログラムを実施したことで,生産性と品質の両面で大手に匹敵するパフォーマンスを引き出したと考えられる[33]。この成功事例は,「小規模企業であっても,人材教育への投資と熱情を徹底することで,大企業と同等以上の業績を達成し,さらなる成長機会を切り拓くことが可能である」という重要な教訓を示している。特に,新興国市場における製造業進出では,技術移転や現地化の過程で,現地人材の能力開発が持続的競争優位の鍵を握ると言えよう。以下に仮説としてまとめた。
仮説2:小規模企業は資本力では大企業と競合し得ないが,人材教育への投資及び熱意を通じて競争力を獲得し,大企業に匹敵する規模へ成長し得る。
我々も教育コスト及び時間などについてのデータ収集を試みた。しかしながら,分析において,教育プログラムへの投資額や投入時間といった定量データを入手することは容易でなく,現状では数理的に教育効果を証明することは困難である。それゆえ,本稿では,MARUTIの事例を「教育力が企業成長を牽引する顕著な成功例」と位置づけ,今後の研究で定性的データや事例分析を通じて,教育投資と企業業績の相関関係をより詳細に検証していく所存である。
本研究では,インド自動車産業の飛躍的発展におけるMaruti Udyog(現Maruti Suzuki India Limited)の役割を定量的かつ定性的に分析した。特に2014年の財務データを基に,時価総額成長率(MCGR)に影響を与える要因をXGBoost回帰モデルおよびSHAP分析を用いて評価した。その結果,MARUTIがインド市場で競争優位性を維持した主な要因として,棚卸資産回転率(INV)と売上高成長率(SGR)がバランスよく寄与していることが明らかとなった。
また,本研究ではMARUTIが長期的な視点に立ち,現地部品サプライヤを単なる下請けではなく,戦略的パートナーとして位置付け,育成したことを指摘した。この「共存共栄」の経営理念が,インド国内での高い部品国産化率を実現し,低コストで競争力のある製品開発を可能にしたと結論付けた。本研究は,以下の2つの仮説を提示した。仮説1では,MARUTIがインド市場でトップシェアを維持できた主因を,自他共栄の精神に基づくインドどの長期的パートナーシップ構築にあると位置付けた。そのエビデンスとして,MARUTIがバイオマスガス生成施設を導入し,再生可能エネルギーを活用している実践例や,社会起業家育成を通じた地域貢献活動にも言及し,持続可能な企業経営モデルとしてのMARUTIの取り組みを紹介した。
仮説2は,小規模企業に対する示唆を含むものである。具体的には,小規模企業が教育への【61頁】 投資及び熱意を通じて競争力を高め,段階的に規模を拡大し,大規模企業へと成長可能であるという可能性を示した。教育力を経営戦略の重要な要素として位置付けることにより,中小企業の成長戦略に対する理論的および実践的な示唆を提供するものである。総じて,本研究はMARUTIの成功要因を多角的に検証し,その戦略の普遍性および他の新興市場への応用可能性を示唆するものである。
このプロジェクトは部分的に学習院大学GEMプロジェクト2025年度と学習院大学東洋文化研究所の研究プロジェクト2024年度のサポートを受けて実施された。またマネサール工場の見学を許可してくださったスズキ株式会社,特に鮎川堅一エグゼクティブフェローに深く感謝する。
[1] R. C. Bhargava, The Maruti story: how a public sector company put India on wheels HarperCollins Publishers India, 2013.
[2] R. C. Bhargava, Getting Competitive: A Practitioner's Guide for India HarperBusiness, 2020.
[3] R. C. Bhargava, Impossible to Possible: Maruti's Incredible Success and How It Can Change India (English Version) Bloomsbury India, 2024.
[4] R. C. Bhargava(バルガバ),スズキのインド戦略:「日本式経営」でトップに立った奇跡のビジネス戦略 KADOKAWA(中経出版), 2006.
[5] 白田由香利,佐倉環,and B. Chakraborty, "世界自動車製造業2014年度株価成長の時系列分析," 学習院経済論集,vol. 59, no. 2, pp. 141-160, 2022.
[6] XGBoostDevelopers, "XGBoost Decumentation (Revision 534c940a.)," 2022. [Online]. Available: https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/
[7] L. S. Shapley, "A value for n-person games, Contributions to the Theory of Games, 2, 307-317," Princeton University Press, Princeton, NJ, USA, 1953.
[8] A. E. Roth, The Shapley value: essays in honor of Lloyd S. Shapley Cambridge University Press, 1988.
[9] A. E. Roth, "Introduction to the Shapley value," The Shapley value, pp. 1-27, 1988.
[10] E. Winter, "The shapley value," Handbook of game theory with economic applications, vol. 3, pp. 2025-2054, 2002.
[11] S. M. Lundberg and S.-I. Lee, "Consistent feature attribution for tree ensembles," arXiv preprint arXiv:1706.06060, 2017.
[12] S. M. Lundberg and S.-I. Lee, "A unified approach to interpreting model predictions," Advances in neural information processing systems, vol. 30, 2017.
[13] S. M. Lundberg, G. G. Erion, and S.-I. Lee, "Consistent individualized feature attribution for tree ensembles," arXiv preprint arXiv:1802.03888, 2018.
[14] 中西孝樹,CASE 革命:MaaS時代に生き残るクルマ 日経BP,東京,2020.
[15] M. Morita and J. A. Machuca, "Integration of product development capability and supply chain capability: The driver for high performance adaptation," International Journal of Production Economics, vol. 200, pp. 68-82, 2018.
【62頁】[16] M. J. Benner and M. L. Tushman, "Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited," Academy of management review, vol. 28, no. 2, pp. 238-256, 2003.
[17] C. A. O Reilly and M. L. Tushman, "The ambidextrous organization," Harvard business review, vol. 82, no. 4, pp. 74-83, 2004.
[18] C. A. O’reilly Iii and M. L. Tushman, "Ambidexterity as a dynamic capability: Resolving the innovator's dilemma," Research in organizational behavior, vol. 28, pp. 185-206, 2008.
[19] D. Lavie, U. Stettner, and M. L. Tushman, "Exploration and exploitation within and across organizations," The Academy of Management Annals, vol. 4, no. 1, pp. 109-155, 2010.
[20] Y. Shirota, K. Kuno, and H. Yoshiura, "Time Series Analysis of SHAP Values by Automobile Manufacturers Recovery Rates," IC Deep Learning Technology, China and Online, 2022.
[21] K. Kuno and Y. Shirota, "Time Series Analysis of Shapley Values in Machine-Learning Regression," IEICE Technical Report; IEICE Tech. Rep., 2022.
[22] M. Fujimaki, E. Tsujiura, and Y. Shirota, "Automobile Manufacturers Stock Price Recovery Analysis at COVID-19 Outbreak," 6th World Conference on Production and Operations Management - P&OM Nara 2022 EurOMA (European Operations Management Association), Nara, Japan, pp. Decision Science Institute Best Paper Award, 2022.
[23] Y. Shirota and B. Chakraborty, "Impact Analysis of Supply Chain Competence on Market Capital Growth in Automobile Manufacturers," 2023 14th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI) IEEE, pp. 438-441, 2023.
[24] C. M. Bishop and N. M. Nasrabadi, Pattern recognition and machine learning Springer, 2006.
[25] M. Syakur, B. Khotimah, E. Rochman, and B. D. Satoto, "Integration k-means clustering method and elbow method for identification of the best customer profile cluster," IOP conference series: materials science and engineering IOP Publishing, pp. 012017, 2018.
[26] F. Liu and Y. Deng, "Determine the number of unknown targets in open world based on elbow method," IEEE Transactions on Fuzzy Systems, vol. 29, no. 5, pp. 986-995, 2020.
[27] RicoAutoIndustories, "RICO AUTO INDUSTRIES," 2016. [Online]. Available: https://new.ricoauto.in/
[28] RicoAutoIndustories, "RICO Annual Report 2015-16, Key Milestones," 2016. [Online]. Available: https://www.ricoauto.com/files/Rico_Report_For%20Web.pdf
[29] NHK, "スズキの故 鈴木修氏にインドが国家勲章を授与すると発表," 2025年1月27日.[Online]. Available: https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250127/k10014704591000.html
[30] Y. Shirota, M. Sekine, and B. Chakraborty, "The Rise of India’s Automotive Supplier Industry and MARUTI’s Influence -A SHAP-Based Analysis Using 2014 Financial Data -," IEICE Technical Report IEICE Tech. Rep., 2025.
[31] 中西孝樹,自動車業界のいまと未来がわかる本.洋泉社,2015.
[32] 野村俊郎,"急成長するインド自動車市場-盤石の覇者スズキと追うトヨタの挑," 商経論叢,vol. 67, pp. 1-39, 2016.
[33] 中西孝樹,オサムイズム"小さな巨人"スズキの経営 日経新聞社,2015.
[34] 中西孝樹,トヨタ対VW: 2020年の覇者をめざす最強企業 日経BPマーケティング,2013.
[35] バスカー・チャタージー、インドでの日本式経営:マルチとスズキの成功 サイマル出版会,1993.
【63頁】[36] 中西孝樹,自動車(第2版)日経BPマーケティング,2010.
[37] 上野正樹 and 佐藤隆広,"インドにおけるスズキの競争力:製品特性分析による企業戦略と競争力の探索," 神戸大学経済経営研究所RIEB Discussion Paper Series, no. DP2019-J06, pp. 1-29, 2019.
[38] 芦澤成光,"インド自動車産業における部品サプライヤーの競争力:3社の事例分析,"論叢:玉川大学経営学部紀要,vol. 2012, no. 18, pp. 1-13, 2012.
[39] 太田志乃,"インド自動車市場から考える日本自動車産業の強さ," 機械情報産業カレント分析レポート 機会振興協会,2010.
[40] V. Govindarajan and J. Euchner, "Reverse innovation: an interview with Vijay Govindarajan," Research technology management, vol. 55, no. 6, pp. 13-17, 2012.
[41] 鈴木修,俺は,中小企業のおやじ 日経BPマーケティング,2009.
[42] 永井隆,軽自動車を作った男 知られざる評伝 鈴木修,プレジデント社,2025.
[43] 日本貿易振興機構(ジェトロ),"スズキ,インドに社会的インパクト投資ファンドを設立(インド,日本)," 2024. [Online]. Available: https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/07/170a774a9321fb40.html
[44] スズキ株式会社,"By Your Side スズキ新中期経営計画(2025〜2030年度)," 2025/2/20. [Online]. Available: https://www.suzuki.co.jp/ir/library/forinvestor/pdf/0220_s.pdf
[45] 松橋誠治 and 白田由香利,"Shapley値による企業成長パターンの発見 〜 Jリーグにおけるアカデミー育成事例 〜," 信学技報 no. 電子情報通信学会,情報論的学習理論と機械学習研究会 (IBISML) 2022年12月22−23日,京都,2022.
[46] S. Matsuhashi and Y. Shirota, "Football Teams Sustained Growing by Academy Training - Proposal of Shapley-based Measurement -," DBKDA 2023 IARIA XPS Press, Barcelona, pp. 13-18, 2023.
[47] S. Matsuhashi and Y. Shirota, "Critical Factors in Doubling Revenue for Soccer Teams: A Comprehensive Study," IEEE IC of Optimization Techniques for Learning (ICOTL 2023) IEEE, Madanapalle, India (Hybrid Mode), pp. 1-5, 2023.
[48] 白田由香利,"最強DB講義:機械学習回帰における Shapley 値の活用法," in 日本データベース学会,2023. [Online]. Available: https://dblectures.connpass.com/event/274198/