計画的偶発性と創造的対応の関係
大谷翔平のキャリアに着目して
脇坂 明
本稿は,異色のキャリア論である,クランボルツの「計画的偶発性」論のなかの,ある種の「偶然」が,シュンペーターの「創造的対応」いわゆるイノベーションを生み出すのではないか,という問題関心から出発する。とりあげる材料は,プロ野球選手の大谷翔平のキャリアである。かれは現在31歳で,非常に短いキャリアであるが,十分考察に値すると考え,詳しく扱う。
キャリア論は,大きく分けて二つ存在する。一つは,伝統的なキャリア論で,「目標設定」を本人あるいは指導者(コーチ)が行い,それに向かって鋭意努力し,目標を達成するプロセスを描くものである。 様々なキャリア(発達)論が存在するが,おおむねこの形をとる。実践的には,この目標を,できるだけ細かく具体的に設定することが推奨されている。「より幸せになる」とか「金持ちになる」といった抽象的な目標は,有効でないことが多いからである。
のちに述べる大谷にかかわる典型的な象徴としては,高校時代に作成した道具(方法論)がある,曼荼羅(目標達成)シートである。大谷の活躍により高校時代の曼陀羅シートが世間に流布し,「大谷翔平シート」とも呼ばれ商品化されている。また,社員研修や塾でも活用されている。マンダラ・シート活用の根底にあるキャリア論は,これにあたる。
それに対して,“計画された偶発性”(“planned” happenstance)理論は,目標を立てて計画しても,キャリアは,8割は「偶然」で決まるという現実から出発する。ここで「偶然」とは,予期しないことをあらわすが,クランボルツは,これを積極的に利用することを推奨する,あるいはキャリアをこの観点から描く。想定外の偶然を,「計画されたかのように」積極的にキャリアに利用するところが,肝である。「偶然」の内容については,項をあらためて述べよう。
心理学者大庭さよ(2018)によるクランボルツの紹介によれば,彼はスタンフォード大学名誉教授で,臨床場面における学習理論を研究し,社会的学習理論を打ち立てた。その彼が,「計画された偶発性」という概念を,1999年に提唱するようになった。キャリアカウンセリングの目標として,偶然の出来ごとを作り出し,認識し,自分のキャリア発達に組み入れるように支援することをあげる。
この理論にもとづき,キャリアカウンセリングへのアドバイスを5つあげているが,そのうちの1つは,「新しい活動を試みたり,生涯にわたる学習を続けるための機会として,想定外の出来事を利用する」というものである。
一人の選手が投手も打者もこなすという「二刀流」は,近代野球における分業体制を大きく【66頁】 変える可能性をもっている。「二刀流」のMLB(大リーグ)における厳密な定義は出場回数などの実務的なものだが,そのこととは一線を画して,二刀流は,近代野球の大きな分業化の流れのベクトルをかえるかもしれない。一人の選手がチームのなかでポジションの複合化あるいは統合がなされるからである。一方,二刀流は分業化の極致である「指名打者制度」(DH制)を活用して,分業化ではなく,脱・分業化をはかっているところも歴史的に興味深い。DH制については本文中で詳しく論じる。
大谷のキャリアのなかで,大谷が「偶然」をうまく活用したことを本文で強調する。そこでの偶然の定義は,第一義的には,キャリア計画で想定していなかった事象になるが,より偶然の内容に深くはいると,リスクと不確実性の違いをみなければならない。
酒井泰弘(2010)は,経済学者フランク・ナイトにしたがって,リスクと不確実性を区別する。通常この2つの区別は厳密になされないことが多い。不確実性やリスクの研究者である酒井によると,不確実性の経済学が流行した1970-80年代に,この区別を意識したものはほとんどなかったようだ。酒井自身も「(ナイトの文章を読むと)私はなんだか恥ずかしい気分になる。ナイトの警告にもかかわらず拙著(不確実性の経済学 1982年)においては,リスクと不確実性の分離が不十分にしかおこなわれていなかったようである。そして,両者をほぼ同一視することが当時の学界の主流であり,私自身もおおむねその考え方に従ったわけである」(酒井 2010 118-119頁)と反省している。
ナイトは,1921年に出版した著書で,リスクは「測定可能で数学的に計算可能なもの」,そして不確実性は「測定が不可能なもの」と区別している。「前者はある事例集合における結果の確率分布は知られているが,他方,不確実性の場合そうではない。その理由は一般に,扱われる状況が非常にユニークなので,事例の集合を作ることができないということである」(Knight 訳309-310頁)。この違いから,企業にとって最も重要な利潤について論じている。利潤の本質は,真の意味での不確実性に立ち向かう企業家が利潤を獲得できるとしている。
ナイトは表1のように,区分している。
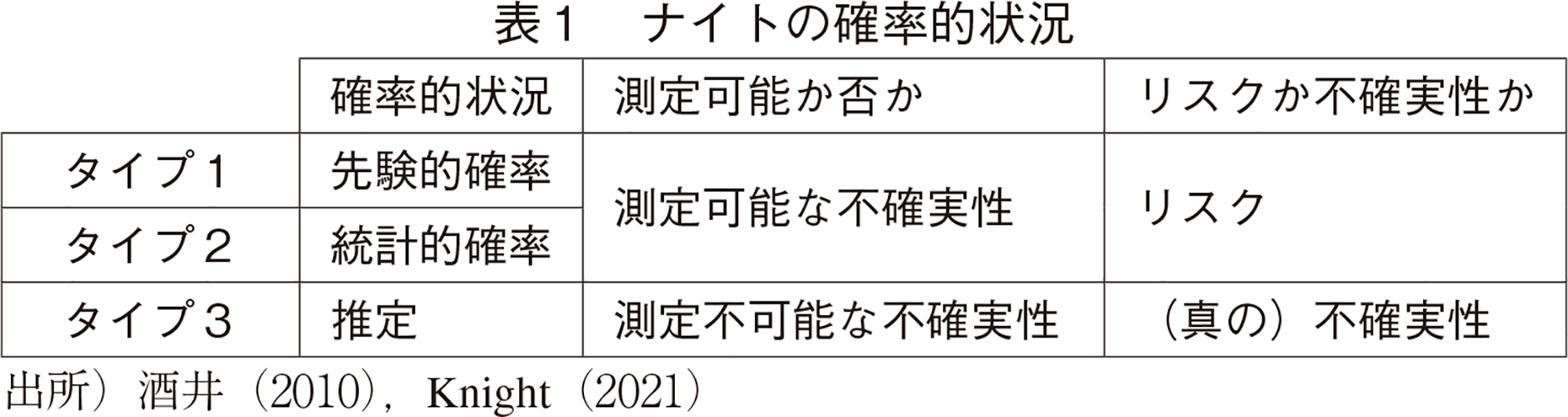
表1において,第1のタイプの先験的確率は,数学的な組み合わせ理論にもとづくものである。たとえば「二つのサイコロを同時に投げる時,目の和が7になる確率」のようなものである。第2のタイプの統計的確率は経験データに基づく確率なので,先験的確率のような数学的厳密さはない。状況や歴史が変われば確率も変わりうる。
これに対して第3のタイプは,推定(estimate)とよばれ,確率形成の基盤となるべき「状態の特定と分類」が不可能である。ある事象が生じる確率を計算しようとしても,その事象自体が確定できないから,確率計算どころではない。
この区分に基づいて,様々な保険や利潤の源泉となる企業家精神について論じている。この【67頁】 ナイトの大著(リスク,不確実性,利潤 1921)に即して,当該内容をきっちり理解するのは筆者の能力を超える。筆者の仮の理解としては,計測可能なもの(リスク)は保険で対応でき,計測不可能なもの(不確実性)は保険でカバーできない。ゆえに企業家精神は後者の状況においてより発揮される。このような解釈である。ナイトの著作には,この解釈にそぐわないような事例の説明もあるが,このように理解する。
イノベーションの概念の生みの親であるシュンペーターは,その内容の中に単なる技術革新だけでなく,多くのものを含めている。販路の革新や人事システムの大改革も含まれる。一部にイノベーションを技術だけに限定し,「技術革新」と略すものもいるが,多くはシュンペーターにならって,広く定義している。筆者も女性活用の歴史を展望するうえで,統計的差別から男女分業型職場が生まれやすい状況において,男女同等型職場がなぜ生まれるかをイノベーションで説明した(脇坂 1998 46頁, 50頁)。多くの事例調査から少なくない男女同等型職場が観察されたためである。ほかの企業とは異なり,1980-90年代で女性を多く採用そして活用する企業はイノベーターであろうし,そのイノベーションは21世紀にはいってある程度定着した。
その理屈は,レスター・サローの仕事競争モデルを前提とし(Thurow 1984),仕事待ち行列の選好順位において,「性以外の重要な要素」に「いちはやく」気づいた経営者がイノベーターとなったというものである。前者の要素としては,学歴であってもよいし,容貌や語学力であってもよいと記した。さすがに現代では学歴の要因が大きかったであろうと推測されるが,論理としては,「いちはやく」「性以外の要素」に気づいた経営者をイノベーターとしている。職場調査が中心であったので,企業の中の誰がイノベーターの主体であったかは,深く追究しなかった。
このことについて,筆者が見落としていたシュンペーターの論文のなかで,主体について論じられている。日本の近代の経済史において,高峰譲吉など多くの政財界の人物をとりあげた米倉誠一郎(2017)は,理論的枠組みをシュンペーターの1947年の論文中にある「創造的対応」(creative response)においている。
その論文のなかで,シュンペーターは,「創造的対応」をおこなう主体について,発明者(inventor)と革新実行者(entrepreneur)の区別の重要性を強調している(Schumpeter 1947 p. 152)。アイデアだけを出す前者よりも,実際にそのアイデアを実現させた後者が,革新者(entrepreneur),すなわちイノベーターにふさわしい。ギリシアの科学は,蒸気機関に必要な理論をほとんど準備したが,ギリシア人もローマ人も蒸気機関は作れなかった。このような例をかれはあげる。
さて,ナイトによるリスクと不確実性の区別をシュンペーターの議論につなげると,前もって計算できない不確実性の中で,生まれるのが「創造的」対応ではないか。前もってケガなどの予測できる確率的状況で測定可能なイベントは,イノベーションとはいえない。成功しても失敗しても,事前確率の結果としてあらわれる事象である。前もって測定不能な事象は,だれもが測定できない事象に対して,なおかつ成功すれば,社会に価値を生み出す「創造性」をもつであろう。
大谷の二刀流の取り組みの歴史は,その概念に合致すると考えてよい。
【68頁】本稿でとりあげる二刀流の実施もイノベーションだとすれば,本文で述べる経緯や歴史をみると,アイデアは,日ハム首脳かもしれないが,それをやり遂げた(get things done)のは,いうまでもなく大谷翔平自身である。
大谷のキャリア(略歴)を年表風にみよう。
1994年 岩手県(奥州市)に生まれる
中学時代「一関リトル・シニア」
コーチ 父親徹 「野球ノート」
2010−2012年 花巻東高校 エースで強打者
ドラフト指名(日ハム1球団のみ)
2013−2017年 日本ハム ここから「二刀流」はじめる
2018−2023年 大リーグ(MLB)エンゼルス
二刀流「Two-way player」として開花
2024年 MLBドジャースへ移籍 1年目は(指名)打者のみ,54本塁打,59盗塁
2025年 6月16日から二刀流として出場,14試合登板,1勝1敗,55本塁打
日米ともに「二刀流」で有名になった選手だが,二刀流とは,投手でも打撃でもチームに貢献する選手である。大谷は高校時代も二刀流であったが,卒業後は投手だけをめざしていた。
ちなみに野球は,9人の投手と野手(捕手含む)からなる点取りゲームであるが,野球の初期段階では投手は戦力としても打者であった。現在も高校以下では投手も打者として期待されているケースが多い。しかし野球の技量や作戦が高度になるにつれ,分業化・専門化されていく。投手専任,打者や野手の専任として活躍するようになる。
大谷の母校である花巻東高校の佐々木洋監督は,曼荼羅シートを各部員に,作成させて目標を決めていた。
曼荼羅シートは,真ん中に最終目標を書かせ,それを実現するためには何をすればよいかの8項目を最終目標のまわりに決める。その項目それぞれに為すべきことについて8項目を周りに記入する。全体として,大きくは3×3の目標,細かくは,9×9の目標シートとなる。佐々木監督の特徴は,たんに部員に書かせるだけでなく,どうすれば実現するかを本人に考えさせ実行させる。それだけでなく,自分もコーチも同じシートを作成し,スタッフと部員のすり合わせをはかっている。企業の現場での目標管理に近いと思われる(目標管理については,中嶋 2015,奥野 2004 がよい)。
メデイアでもよくとりあげられる大谷のシートは,まず真ん中の最終目標は「ドラ1・8球団」である。「ドラ1」はドラフト1位のことである。ドラフト制度については,特定球団だけが入団交渉権をもつ制度である。ドラフトにおいて,人気選手は複数球団が1位に指名することが多い。このケースでは抽選で決める。花巻東の3歳上の菊池雄星は甲子園のセンバツ大会で準優勝したこともあって,6球団の指名があったが,それを超えることを目標にたてた。【69頁】 また小目標の「スピード160km」は当時の高校生の最速記録である。また小項目の「運」のなかに「ごみ拾い」がある。運を拾うという格言?からたてた目標と思われるが,大リーグの試合中のグラウンドで,ゴミを拾う大谷が有名になった。
この大谷の曼荼羅シートを引用して,一般の人に対しても目標設定そして実現させる資料として論じられることが多い。注意したいのは,大谷のシートのほとんどの項目が投手を念頭に置いた目標である。当時は高校生でチームでも強打者であったが,本塁打はじめ打撃に関する項目はない。つまり「二刀流」を意識していない。次節でみるように,日ハムとの折衝ではじめて二刀流の意識が芽生えた。
また言うまでもないが,高校卒業までを念頭においた目標である。野球選手としての長期のキャリアではなく,短期の目標といえよう。
大谷のキャリアについて,父親よりも高校時代の佐々木監督の影響が強いように思われる。大谷の発言のなかに,しばしば佐々木監督と同じ言葉が現れるからである。
佐々木洋監督は,野球後進県の岩手にありながら,花巻東を強豪校にひきあげた。とりわけ大谷の3歳上の菊池雄星(西武球団から大リーグに移籍,現在はエンゼルス)や息子の佐々木麟太郎(スタンフォード大学在籍で大リーグめざす)らを指導したことで有名である。
指導における個々の部員の指導における“カスタマイズ゙“の必要性を強調している。つまり選手育成における“個”の重要性をとく。先の目標達成シートを有名にしたのは,大谷というよりも佐々木監督である。育成に重きをおくところから,「タイミングを間違えると,育つものも育たない」という。また「目標の実現に向けた組織全体の取り組み」を強調しているが,選手だけでなく,監督やコンディショニング・コーチも,各自の立場での目標達成シートを作成している。
そして,大谷もよく引用する「先入観は可能を不可能にする」という佐々木監督の名言は,後述するドラマが象徴するように,大谷本人は意識していなかったようだが,皮肉にも二刀流という「創造的対応」の基盤となった。「偶然」が先入観をこわし,イノベーションをおこした。
大谷は優れた素質をもち順風満帆のキャリアを歩んだように描かれることが多いが,多くの「偶発性」と遭遇した。
花巻東高校1年の時の目標が,日本(NPB)でのドラフト1位8球団であったが,徐々に考えを変える。ドジャース日本担当スカウト 小島圭市の努力により,監督や大谷と信頼関係を構築していた。大谷の3歳上の菊池雄星からを含めると,花巻には5年半の長きにわたる接触であった。大谷本人も3年になると,MLBをめざすようになり,監督-本人,両親で何度も相談し,その気持ちを固めていった。(佐々木亨『道ひらく海わたる -大谷翔平の素顔』2018)ドラフト4日前の2012年10月21日大リーグ挑戦を表明したので,日ハム以外の球団はそ【70頁】 れを信じた。しかし日ハムは2日前に強行指名を表明し,10月25日 ドラフト当日に指名し,日ハムのみドラフト1位指名となった。単独指名なので抽選はなく,日ハムが交渉権を得た。
交渉時に,持参した球団提出資料が「大谷翔平君 夢への道しるべ」(全26ページ)である。現物はある時期まで日ハムHPにあったが現在はなく,現物は未入手だが,よく引用される情報なので,それらをもとに記述する。
日ハムの大渕スカウトが下記の資料を作成した。
1)大谷の夢の確認 MLBがトップクラスだから行きたいのであって,米国に行きたいわけではない。
2)NPB経由と直接MLBとの道のりの比較
3)過去の日本人メジャーリーガーのキャリアの分析
活躍している9選手は即戦力として渡米(30歳前後)
4)韓国人メジャーリーガーのキャリアの分析
直接渡米いるが,全員野手で活躍期間が短い
5)NPBには「選手を引き上げる仕組み」がある
6)他競技(卓球,テニスなど)との比較
ポイントは,「実力をつけてMLB挑戦したほうが成功確率が高い」というデータを示したことである。また指名打者(DH)のあるパ・リーグの特徴を生かした起用法,トレーニング法を提案した。ちなみに大渕スカウトは,「急がば回れ」(琵琶湖の写真)の裏表紙をつけている。
当時の交渉による逆転劇を物語る逸話として,大谷後日談によれば「だまされないぞ」「何かこじつけというか,一つの説得材料」とみていた。また 栗山後日談「最初,目も合わせなかった」という。
この日ハム(栗山英樹監督・山田正雄GM編成部長)の「二刀流」提案が,大谷のキャリアの分かれ道となった。以上,野球関係者ならだれでも知っている事実を長々と記したのは,大谷にとって,思ってもみなかった二刀流の提案という「偶然」がおこり,二刀流やれるかもしれない,と積極的に考え直した点を確認するためである。
二刀流の画期性,創造性については後述していくが,先取りすれば,1)野球界の分業化の流れのベクトルの方向を転じる可能性をもつこと,2)その「創造的対応」をした主体は,栗山・山田の首脳陣ではなく,大谷自身であること,である。
大谷のキャリアにおいて,ケガの影響は大きい。アスリートゆえに当然だといえばそれまでだが,野球選手として多い部類に入ると考えている。かれのケガの歴史について,年表風にみよう。関連する実績も適宜加える。
<高校時代>
高校2年 骨端線損傷(成長期に見られる骨が成長するために必要な成長軟骨が阻害される)。
甲子園夏 帝京戦は右翼手から登板
治療に専念し,打者限定
高校3年春 大阪桐蔭と初戦で対戦し惨敗
高校3年夏 岩手大会準決勝で160キロ出すも,決勝で本塁打を打たれ敗退
<日ハム時代>
2013年 当初は右翼手として出場
4・13 オリックス戦 右足首捻挫 登録抹消
5・4 復帰 5・23 ヤクルト戦初登板
7・11 楽天戦前のランニングで打球受け,右頬骨不全骨折
2017年(5年目;最後の日本時代)
2月 WBC(ワールド・ベーシック・クラシックという野球の国際大会)に選出されるも,怪我のため出場辞退
4・8 オリックス戦一塁走塁の際,左ハムストリングス痛める。
肉離れで,6・27復帰も,満足なプレーできず
10・12 内視鏡による「右足関節有痛性三角骨除去術」を受ける
11月 ポステイング・システムを利用し,MLB挑戦表明。エンゼルスに移籍。
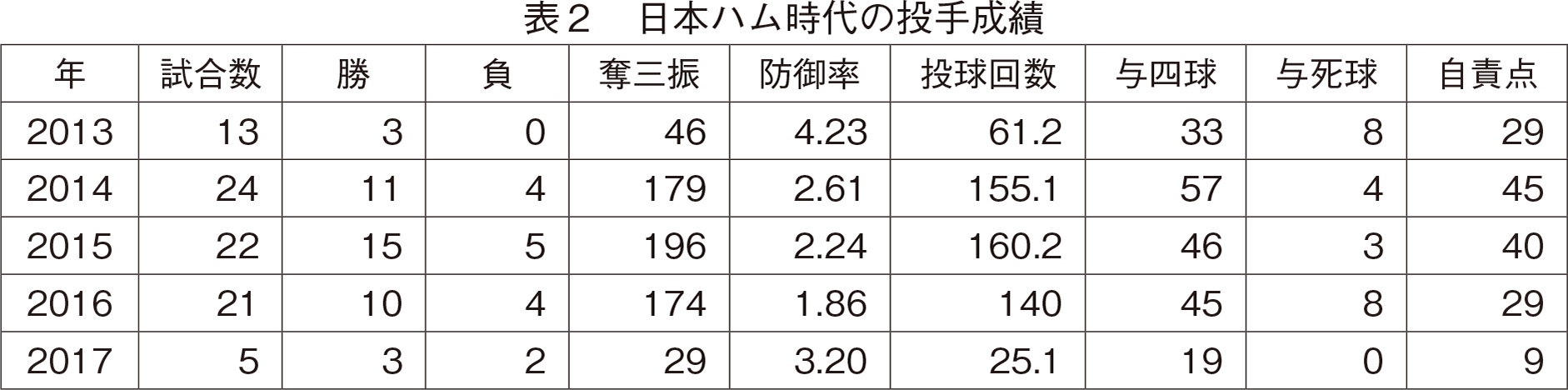
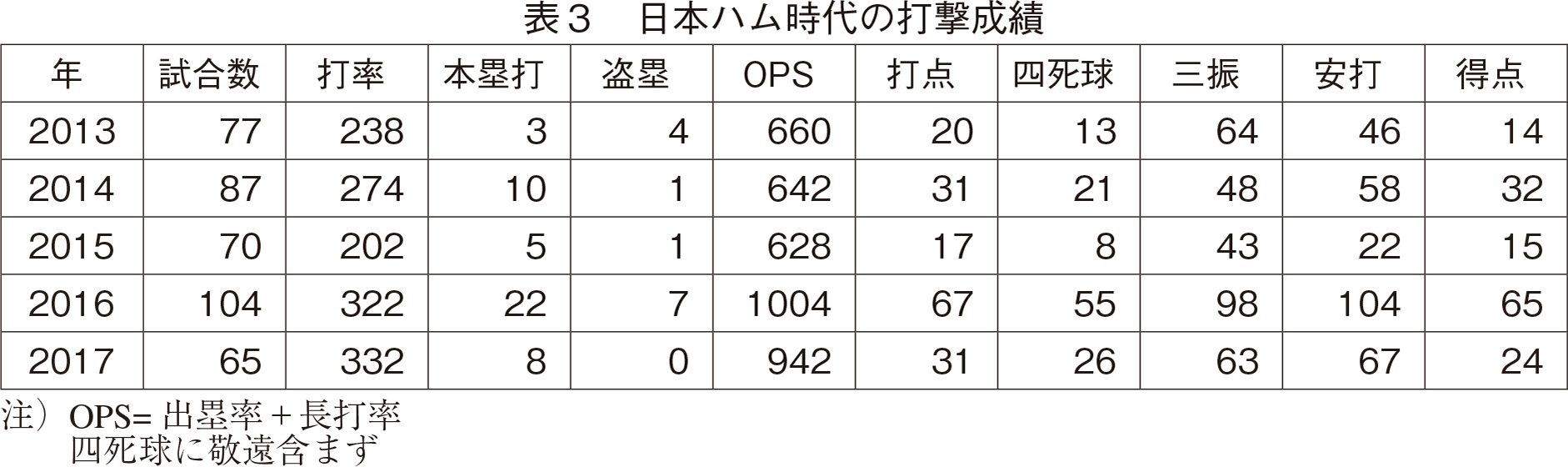
日本ハム5年間の投打の成績が表2,表3にある。表3の打撃成績には,OPS(On-base Plus Slugging)という指標が記されている。日本ではあまり記録されることはなく,打点が多い。MLBでは,OPSが公式記録にもあり,打撃指標として重要視されているので,ここでも掲載した。OPSが重要視される理由は,のちに触れるセイバーメトリクスでの研究から打撃能力をよくあらわしているからである。(鳥越 2022)
OPSの定義は,(出塁率 + 長打率) で,
出塁率 = (安打 + 四死球)/(打数 + 四死球 + 犠牲飛球)
長打率 = (単打×1 + 二塁打×2 + 三塁打×3 + 本塁打×4)/打数
OPSの値は,0.9以上が「素晴らしい」と評価されるようだ。NPBでの最高評価は,1974年【72頁】 の王貞治(巨人)の1.295で,MLBでは,2004年バリー・ボンズ(ジャイアンツ)の 1.422 である。
<エンゼルス時代>
2018年 エンゼルス1年目
3・29 8番指名打者 初打席初球初安打
4・1 アスレチック戦 初先発初勝利
4・24 アストロズ戦 100マイル(160,9キロ)超え
6・8 右肘の内側側副靱帯を損傷 10日間故障者リスト
7・21 打者として復帰
9・2 アストロズ戦復帰登板
9・5 MRI検査 右肘靱帯に新たな損傷 トミー・ジョン手術(ジョブズ博士による手術で,最初に受けた投手の名前をとっている)を勧められる
その後は打者として出場し,9・15 20号本塁打
2018・10・1 ロサンゼルス市内の病院で,トミー・ジョン手術受け成功
2019年(2年目)
開幕からリハビリ
5・6 打者として復帰
6・13 タイガース戦 3番DHでサイクル安打
9・13 左膝骸骨手術 全治8-12週間
残りシーズン欠場
2023年(6年目,エンゼルス最後の年)
3・31 二年連続二刀流として開幕投手(3番投手兼指名打者)
7・28 ダブルヘッダーで1試合目に完封後(45分後),2試合目に本塁打2本。直後に痙攣し退場。<後に再述>
8・23 ダブルヘッダー1試合目に先発登板し,初打席で本塁打放つ。投手出としては1回1/3投げた後,右ひじの痛みを訴え降板。
検査の結果,右ひじの内側側副靭帯損傷が判明し,投手としては出場不可。
9・4 フリー打撃中に右わき腹痛める
9・16 右わき腹痛で故障者リスト入りし,シーズン終了
9・19 2回目のトミー・ジョン手術を行い成功
大谷のエンゼルスでの投打の成績(ドジャース時代を含む)は,表4,表5にある。ベーブルース以来の「二桁勝利・二桁本塁打」など輝かしい成績だが,背景にはここで記したようなケガの歴史がある。けっして「超人」ではない。
<ドジャース時代>
2024年ドジャースへ移籍
手術明けなのでDH専念で,2025年に向けての投手リハビリ
2024年10月19日 ワールド・シリース第2戦で盗塁のさいに,
左肩関節亜脱臼 残り3〜5戦出場し(まったく打てず),WS終了後,手術。
2025年にむけて,右ひじと左肩の同時リハビリが必要
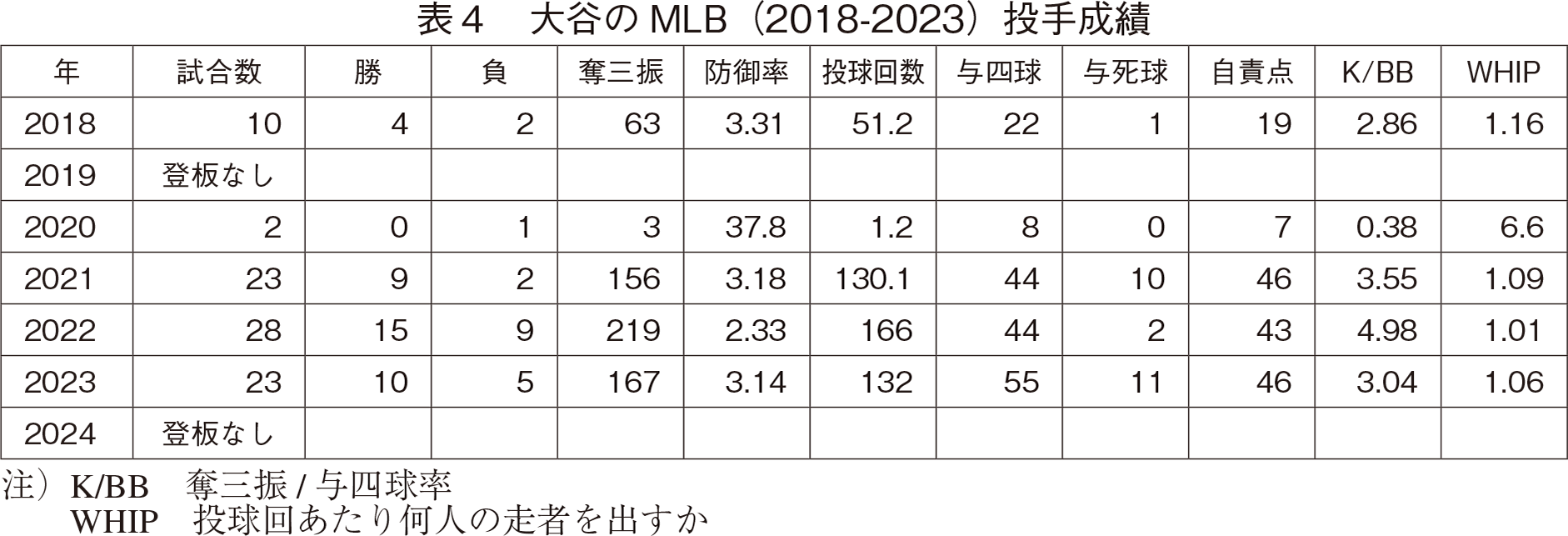

大谷のケガの歴史にたびたび登場するトミー・ジョン手術とMLBの投手について,一言ふれておきたい。トミー・ジョン手術とは投手の肘関節内側側副人靭帯損傷に対して行われた靭帯再建手術である。投球動作において肘関節内側に強い牽引力がかかるため損傷しやすい。とくに先発投手に多いといわれる。
1974年にフランク・ジョーブ医師がトミー・ジョン投手に対して初めておこなわれた手術なので,この名称が使われている。手術の成功率は高くなってきているようだが,手術後,復帰の登板までは時間を要し,1年から2年のリハビリが必要といわれている。
のちに触れる「セイバーメトリクス」の実践例としては,2001-2002年に応用し成功したアスレチックスをとりあげた『マネーボール』が有名である。映画化もされセイバーメトリクスを一気に有名にし,大リーグ野球を変えたtもいわれている。ここでは,もう一つの成功例である,2013年のパイレーツを扱った『ビッグデータベースボール』(トラヴイス・ソーチック)の著作から,トミー・ジョン手術に対する監督や球団の対応をみたい。
【74頁】2013年の開幕時点でMLBのベンチに入っていた投手のうち3分の1はトミー・ジョン手術の経験があった,2014年9月までに76人の投手が受け,・・・不詳の予防に関しては,有効な対策の兆しが見えない状態にある」,(ソーナック訳219頁)負傷の増加の要因として,「今の投手は子供の頃から年間を通じて投げ続け,十代の頃にはプロや大学のスカウトが見守るなか中で無理ぃする傾向がある」,また球速が上昇(2008年平均145,4キロから2014年147.36キロへ)するなかで増大する負荷に体が耐えられない」と推測している(220頁)。投手の体格が向上しているが,「筋肉は鍛えることはできるものの,筋や靱帯を鍛えることはできない」,「靱帯は1球投げただけで断裂するのではなく,・・・年月をかけて擦り減っていく」。
このように原因は明らかになってきているが,予防法の理解は少なく,原始的なツールとして,球数(制限を設ける)を用いることが多かった。そのような状況下で,パイレーツは修正方法を発見できたと考えた(221頁)。
それは,なんと「先発4人制」である。これは筆者が驚いた点である。2010年代終わりから日本人投手が各球団で活躍するようになり,投手の疲労保護から,通常の「先発5人制」から「先発6人制」に変えていくことの検討あるいは実践していく球団が増えてきた。しかし2013年のパイレー.ツがとった投手の肘を守る方法は真逆で,先発投手の数を減らすことであった。監督のハードルが前任の球団ロッキーズで失敗したやり方を,パイレーツで導入したのである。それだけでなく,セイバーメトリクスのデータに基づいて,投手の球種構成を変えたりする工夫もした。
トミー・ジョン手術を受け,つらいリハビリをしていたモートンなどとの話し合いなど,この方法は一応成功したようだ。つまり先発投手を減らせば,投手1日当たりの球数を減らさざるを得なくなり,それによって肘の負傷などを予防するというやり方である。投手の登板間隔は短くなるわけであるから,筆者は,本当にこれで予防効果があったかどうか確信をもてないが,怪我予防に本格的に取り組んだ首脳陣が存在したことの事実は重い。
とにかくハードル監督が1993年から「20シーズン連続負け越し」の記録に終止符をうったこと,そしてビッグデータを用いて勝利に貢献する選手起用をしたことは大きい。監督は事後の手術よりも,この損傷が起きない予防が重要であるという。もっともである。その予防法をみると,投手の登板間隔を狭める,その結果,ベンチは1日当たりの投球数を少なくするであろう,と予測するのである。筆者は違和感をもつ予防法である。
エンゼルスの番記者であったフレッチャーによると,2度のトミー・ジョン手術を受けた後は,ほとんど活躍できず,二度の手術後活躍した投手はレンジャーズのイオバルデイ投手一人である(フレッチャー 2024 189頁)。続く候補として,2度のサイヤング賞(当該シーズンの最優秀投手)をとったデグロム(レンジャーズ)が期待されるとしている。ちなみにデグロム(37歳)は,2024年の登板は3回にとどまったが2025年は30試合登板,12勝8敗と復活している。フレッチャーは,「イオバルデイは,完全な回復が可能だと証明する絶好の事例だ」とし,そしてイオバルデイの言葉として「大谷の禁欲的な労働倫理を見ると,間違いなく一流投手として復活できると信じている」(フレッチャー 2024 193頁)。フレッチャーの著作は全編大谷に好意的なトーンで書かれており,その予測は割り引いて考える必要はあるが,ポイントとなる選手や監督への取材は手堅いものがあることも事実である。
さて,これらのケガと野球選手としてのキャリアをどうとらえるかである。恩師の佐々木監督によれば,「翔平はケガさえも,何かを見つけるきっかけにする」(週刊ベースボール26頁)。【75頁】 筆者の「計画的偶発性」の議論そのものを述べているようにもみえるだが,怪我にこのキャリア論をそのまま適用することには,筆者は慎重である。フランク・ナイトの区別を借りれば,ケガは不確実性よりもリスクに近いと思えるからである。
佐々木監督の言明は,2年夏甲子園大会後,精密検査で,股関節の骨端線損傷(骨の成長に筋肉が追いつかず,関節の軟骨が傷つく)が判明したときの経験によっている。そのさい,走る際に痛みは出るが,打つことはできたことにより打撃向上?したことを指しているらしい。「ケガの功名」そのものだが,その後の大リーグでの経験も色濃く反映した言明であろう。2024年ドジャースではDH専念で打撃能力が向上したことだけではない。2024年のドジャースでの右ひじのリハビリ段階で,盗塁ができるようになり,いわゆる「50本塁打−50盗塁」をはじめて達成した事実である。
大谷の2年夏の甲子園では,監督は身体を気にして先発投手とせず右翼手に配置したが,試合展開のなかで投手として起用している。長期育成に重きをおく佐々木監督にしては,理解しにくい行動だと筆者は思っている。
さて大谷の二刀流と指名打者制度との関係をみよう。そのまえに,指名打者制度(Designated Hitter;DH)を簡単に説明する。投手はほかのポジションの選手より体力消耗するため毎日投げるわけにはいかない。そのため(ほぼ)毎日試合に出場しようとすれば,投手として投げないときには,野手として守備をする必要性がある。これは怪我をする危険などから,できるだけ避けたい選択肢である。高校強豪校は,投げない日はベンチに待機することが多い。
指名打者制のないリーグ(現在のNPBのセリーグ)で投手が打者として活躍しても「二刀流」とはよばない。打撃は期待されておらず,上位打順に組まれることはほとんどない。
ちなみに大谷については,守備は苦手でなく足も速く,日ハム,エンゼルス初期には外野手もやった。現在使用されている意味での「二刀流」(two-way player)と名付けたのは,栗山監督と山田GMの会話から生まれたらしい。
このように野球は,かつては投手も打者であったが,技量が上がるにつれ,分業化(専門化)が進んだ。近代社会の発展とともに生じた企業内分業あるいは社会的分業とおなじである。野球界の分業化の徹底が,指名打者制度といえよう。
指名打者制度は,米国では1972年 アメリカン・リーグで導入された。導入の背景には人気低迷があったようだ。日本では,1975年 パシフィック・リーグで導入された。これも人気回復のためと考えられ,エンたーテイメントとしての野球の魅力向上のためともいえる。つまり分業化することによって,専門能力をもつ多くの選手を消費者が鑑賞できるようにする施策といえよう。
DH制度のめざすところは,打者の能力向上がもっとも大きく,その理由は守備(走力)がうまくなくとも,打撃のよい選手の出場機会がふえるからである。もちろん,出場機会が減る野手も出てくるので,理論的には打撃重視を志向した施策である。
また間接的に投手能力が向上するという議論もある。とすればDH制度のあるリーグの球団において競技力(競争力)が向上するはずである。この議論を検証するには,日本であればセパ交流戦や日本シリーズの結果で判断すればよいといえるが,そう単純ではない。試合は交互に,それぞれのルールでやるので厳密な比較とはならない。
【76頁】そのうえで結果を示すと,1975年以後の日本シリーズにおける勝利球団はパリーグ29勝,セリーグ21勝である。また6球団すべてが他リーグの球団と戦うセパ交流戦については,優勝球団は,パリーグ15回,セリーグ5回である。また通算成績(2005−2025年)は。パリーグ1306勝,セリーグ1174勝,引き分け 76である。2025年の交流戦の結果は,パリーグ63勝,セリーグ43勝で,20勝の差がついた。
ちなみに高校野球は2026年春からDH制導入が決定し,その影響からかセリーグも2027年からDH制の導入が決定した。
本稿は,このDH制導入の是非の議論に直接絡むのではなく,想定していなかった効果(効率性,スターの誕生),つまり二刀流と指名打者制度との関係を強調するものである。「二刀流」をシーズン通して続けるには,指名打者制が有利であろう。いや不可欠ともいえる。大谷がエンゼルスやドジャースを選択した経緯を振り返ってみたい。
日ハムから初めて米国の球団に移るとき(2018年),大谷は両リーグのほぼすべての球団からオファーをうけた。世間の評判は,人気球団であるニューヨークのヤンキースが本命であったが,最終候補にも選ばれずなかった。7つの球団に絞り面談した。大谷は全部資料を読んだが,「7つに絞るのが最も難しかった」という。
「アリーグやナリーグなど・・それ自体は重要でなく」(佐々木亨 23頁)と言っているが,一方で「各球団への配慮もあり」(22頁)ともいう。アリーグ(エンゼルス,レンジャーズ,マリナーズ゙),ナリーグ(ドジャース,パドレス,ジャイアンチ,カブス)からエンゼルスを選択した理由は,決定的なものはいまだわからないが,筆者は指名打者制度の有無が大きいと思っている。大谷は「二刀流」へのこだわりあったと思われる。当時アメリカン・リーグのみDH制度が存在した。二刀流ゆえに体力面から気候面では西海岸の球団を上位においたであろう。
筆者の仮説を裏付けるものとして,当時,獲得競争に敗れたドジャース側からの証言をみよう(ブランケット 2024)ドジャースの番記者であるブランケットがDH制の影響力について語っている。
ドジャースは最終候補に選ばれたが,DHのないナリーグにいることが,「一つだけ重大な弱み」(28頁),大谷が投げていない日には打つ機会に制限(フリードマン編成部長)がある。あるいは面談に参加したカーショー(ドジャースの投手)によれば,「彼がDHをやりたいのは,前からわかっていたじゃないか。・・・彼の代理人に腹が立っているんだ。最初からナリーグ所属の15球団を除外しておくべきだったんだ」(30頁)。といった発言をあげている。
あるいはゲイレン・カー(ドジャース選手調整担当)によれば,我々は本気で彼が投手と打者の両方で活躍できるプランを立てた。獲得競争は,「アリーグでDHとして毎日試合に出る」 vs 「いつも代打で待機してもらう」 この2つの対決であった。ドジャースでは,年間300打席ぐらいは立てる計算であった(この算出は疑問;筆者)。でも「大谷の決断はよくわかる」(29頁)
大谷本人の弁によれば,入団会見で「縁」や強い「絆」を強調し,選択理由は「理屈でなく直感」であった,あるいは「フィーリングが合った」(佐々木亨 26頁)と言っている。
いずれにしても「お金ではなかった」ことは確かで,大谷(当時23歳)が入団する直前に作られた規定では,25歳以下の契約金上限が$54.5(6000万円)であった。この額は日ハム時代の年俸を大きく下回っている。数年待ってからなら$2億(220億円)はあったと推定されていた。
2023年のシーズン終わった後,大谷は2度目のトミー・ジョン手術を受け成功した。投手としてのリハビリがあるので,ドジャース移籍後の1年目は打者(DH)専任になることに決まった。そこでシーズンはじめに走塁練習を行った。もともと日ハム時代にはチームで2番目に足の速い選手であったが,二刀流では怪我のリスクがあるので盗塁はほとんど試みてこなかった(2016年の7個がもっとも多い)。エンゼルス2年目の打者専任のときも,「2番大谷」であったが,盗塁数は12にすぎない。
ところがドジャース1年目は,コーチなどのすすめもあり走塁を本格的に練習する。優勝することが至上命題の球団えあったので,少しでもチームに貢献する準備をしたのであろう。
シーズンにはいり「2番大谷」で,これまでよりも盗塁は少し増えた。ところが,ここでまた「偶然」が起こる。1番を打っていたベッツが死球を受け長期離脱をしいられた。ロバーツ監督はベッツが抜けたので,「1番・大谷」の打線に組み替えた。2番でも盗塁機会はあるが,1番のほうが盗塁機会が増える。1番になってから盗塁は増え,チームに貢献する。その実績のもとにベッツが復帰してからも「1番・大谷」という打順はそのままであった。その結果,シーズン59盗塁という大幅な増加を果たし,前人未到の「50本塁打-50盗塁」を達成した。
手術という偶然で打者専念が決まり,そのため走塁練習をし,同僚のケガによる打順変更が盗塁機会を増やした。「偶然」を積極的に利用した例である。背景となる「計画性」は,野球が好きでチームにどんな形でも貢献したいという姿勢にあろう。ただ,次の項で見るように,その年のワ−ルドシリーズで,(試合の流れからみて必ずしも必要ではない)盗塁を試み,左肩を怪我したことは,チームにとっても本人のキャリアにとってもマイナスになったことは皮肉である。
どんなスーパースターであっても,欠点はある。大谷翔平については,野球選手に厳しい日米のメデイアもほめちぎる論調が多い。もちろん二刀流についての実現可能性に疑問を呈する論調は,日米ともに初期段階で存在した。その点ではなく,二刀流を前提として,大谷のめざしているキャリアに即して欠点と思えるものを述べたい。まずとても些細な小さな欠点をあげる。
2024年8月28日の愛犬デコイ(デコピン)の始球式についてである。愛犬がマウンド上にあるボールをくわえ,捕手の大谷まで走って渡すという余興である。球場は大盛り上がりで,日本の放送でもなんども放映された。これについて難癖に近い指摘をしたい。
この芸当のために自宅で3週間の練習をしたという発言があった。それくらい時間を要する芸当であったろう。しかし,この3週間の成績はよくない。あまり指摘されてこなかったのは,本塁打が減ってないからであろう。
6月 打率 299 出塁率 425 HR 12 OPS 1196
7月 打率 280 出塁率 391 HR 6 OPS 982
8月 打率 230 出塁率 290 HR 11 OPS 866
9月 打率 384 出塁率 444 HR 11 OPS 1212
8月は前後の月にくらべ,本塁打数を除き有意に打撃成績が悪い。8月は暑さ?のために例年悪いかどうかみると,エンゼルス在籍時の8月の打撃成績をみると,
2018年 打率 328 HR 6 OPS 1,096
2019年 打率 281 HR 1 OPS 0.744
2020年 打率 203 HR 3 OPS 0.695
2021年 打率 202 HR 5 OPS 0.749
2022年 打率 317 HR 8 OPS 1.039
2023年 打率 316 HR 5 OPS 1.004
コロナのあった2020年と翌年は,かなり悪い成績だが,移籍直前の2022-2023年は好成績である。愛犬との練習が,打撃にマイナスの効果を与えたと,頑強に結論づけられないものの,「野球一筋」でキャリアを歩んでいる大谷にとって,少し気がかりな事実である。
さいごに,もっとも重要だと思われる欠点について,述べたい。
筆者にはもっとも本質的な事実であると考えているが,残念なことに,下記の事例はメデイアが欠点とするどころか,美談あるいは怪物として扱う材料となった。3つとも,ケガあるいは疲労をおしての試合への強行出場である。
3-5-1 エンゼルス時代の奇跡
同じ日(2023年7月28日)に,投手として完封のあと,2試合目(45分後)に,ホームラン2本を放ったが,その後,痙攣のため退場する。当時のネヴィン監督は,2試合目の出場は,本人の希望を尊重したとコメントした。
3-5-2 ドジャース時代のシーズン終了時期
2024年地区優勝決定後もレギュラーシズンに出場しつづけた。投手リハビリもあるので,休ませるべきだったのでは,と考える。三冠王記録達成の可能性もかすかにあり,それを期待したともいわれっている。
3-5-3 ドジャース時代のワールド・シリーズ
2024年ワールド・シリーズ(WS)第2戦での(無謀と思える)盗塁の際に亜脱臼による肩のケガをする。その後,WS終了まで出場した。肩をかばいながらの走塁で戦力とはならなかった。WS終了後,左肩関節唇断裂手術を行い成功する。ケガ直後に欠場し,手術をすべきだったと思われる。ロバーツ監督によれば,出場は本人の意思を尊重したという。
この3度の節目をみると,どちらの球団の監督も,本人任せである。悪く言えば,責任とらないサラリーマン気質さえ垣間見える。こういった環境にいることは,大谷も承知しているであろうから,日本にいる時以上に,自己管理(体調管理)の徹底が求められる。筆者はそう思う。
「二刀流」が最大の特徴の選手ゆえに,そのための体調やリハビリで管理することに万全を期すことが,最優先課題であろう。30歳前後になれば自ら主張すべきであって, MLBの監督・スタッフに対して,忖度やしたがう必要はない。本人が本当に大丈夫だと思っていても,【79頁】 それを制するのが,上司あるいは球団であろうが,まずは本人が自己管理しなければならない。
球団経営からみても,10年で年俸1000億円を支払う選手に対して,無理をさせる必要はない。選手の起用の権限をもつ監督は,中間管理職であり,勝利にこだわりすぎるのは致し方ないとしても,選手の状況をより観察して判断すべきあろう。先に詳しく見たように,大谷には,怪我にまみれた歴史がある。
セイバーメトリクス(Sabermetrics)という学問,手法は,選手の分業化に応じて,打撃の評価,守備の評価,投手の評価などを,ビッグ・データに基づいて行うものである。
最後にも述べるが,いまだ大谷を除いて日米とも本格的二刀流はおらず,サンプル1の状態なので,新しい指標は作成されていない。ただ打撃評価と投手評価において,チームにどれだけ貢献したかを示す指標がある。(鳥越 2022)
WAR という選手の球団への評価指標がある。Win Above Replacement という名称の通り,「当該選手がチームに上積みした勝利数」を示し,その算出は控え選手と比較して行う。
鳥越(2022)による大谷の2021年の成績のWARをみると,まず野手評価としては,5.1である。野手で1位はゲレーロJr(ブルージェイス)の6.7で大谷は10位である。指名打者で守備はしていないし,走塁評価も盗塁も少ない年なので,とびぬけて高くはない。ところが2021年の投手評価は,3.0で足し合わせると,8.1になり,図抜けて高くなる。二刀流を続ける限り,WARという指標では,大谷を超える選手は現れないとまでいわれている。
ちなみに大谷も2023年のWARは,
10.0 = 6.0(打撃)+ 4.0(投手)
であり,2024年WARは,9,2である。この年は,投手評価ゼロなのに高いのは,走塁評価が高いためである。(「教えてメジャーリーグ・データ用語編」NHK BS 2025・3・16)
ビッグ・データつまりサンプル数の多いデータが基本となっている手法なので,この学問分野では,よほどの画期的手法があみだされない限り,正確な二刀流の評価は原理的に不可能であろう。これも,大谷が生み出した学問的手法に対するインパクトである。
経済学者シュンペーターには主体を論じた論文があった。繰り返すが,
その論文のなかで,シュンペーターは,「創造的対応」をおこなう主体について,発明者(inventor)と革新実行者(entrepreneur)の区別の重要性を強調している(Schumpeter 1947 p. 152)。アイデアだけを出す前者よりも,実際にそのアイデアを実現させた後者が,革新者(entrepreneur),すなわちイノベーターにふさわしい。ギリシアの科学は,蒸気機関に必要な理論をほとんど準備したが,ギリシア人もローマ人も蒸気機関は作れなかった。このような例をかれはあげる。
本稿でとりあげた二刀流の実施が,もしイノベーションだとすれば,経緯や歴史をみると,アイデアは,日ハム首脳の栗山・山田かもしれないが,それをやり遂げた(get things done)【80頁】 のは,いうまでもなく大谷である。
もし二刀流の選手が大谷一人でおわってしまうと,歴史の一齣のエピソードで終ってしまう。イノベーションの議論からすれば,フォロワーがあらわれないと,「イノベーション」とは呼ばれない。大谷が二刀流をはじめて10年以上たつが,日米ともに本格的な二刀流の後継者があらわれていない。
たった一人のアスリート,それもせいぜい15年のキャリアから,計画的偶発性とか創造的対応といった,大きなことがいえるか,という根本的課題は存在する。
たしかに人生のキャリアをおっていくうえで,15年は短いし,一人のキャリアを論じるには時期尚早なのかもしれない。ただ筆者自身,今後,大谷をおっていくつもりなので,暫定的結論や仮説が検証されていくことになる。
内容的には「育成」についての論じ方が不十分であった。ロッテの吉井監督らのコーチング・モデルの検討を準備中だが球団の内部情報を知るには限界がある。本格的に育成を論じるには,まだまだ全般的に研究蓄積が乏しいようにみえる。
あと野球だけとっても数多くの選手が存在する。少しでも多くの選手を学術的にトレースすることが,研究全体を深めよう。ましてや他のスポーツ,人気スポーツだけとっても,サッカーやバスケットボールなど,それなりの資料などは存在する。スポーツ選手をけっして特殊なキャリアと捉えるのでなく,多くのホワイトカラー,とくに専門性をもつ労働者のキャリアを考えるうえで参考になろう。
奥野明子(2004)『目標管理のコンテインジェンシー・アプローチ』白桃書房
大庭さよ(2018)「ジョン・クランボルツ──学習理論からのアプローチ」『新版 キャリアの心理学』ナカニシヤ出版
クランボルツ,J.D ほか『その幸運は偶然ではないんです! ─夢の仕事をつかむ心の練習問題』(花田光世ほか訳)ダイヤモンド社
酒井泰弘(2010)『リスクの経済思想』ミネルヴァ書房
佐々木亨(2018)『道ひらく海わたる ─大谷翔平の素顔』扶桑社
ソーチック,トラヴイス(2016)『ビッグデータベースボール』(桑田健訳)角川書店
鳥越規央(2022)『統計学が見つけた野球の真理 ─最先端のセイバーメトリクスが明らかにしたもの』講談社
中嶋哲夫(2015)『正しい目標管理の進め方 ─成果主義人事を乗り越える職場主義のMBO』東洋経済新報社
フレッチャー,ジェフ(2023)『SHO-TIME 大谷翔平 メジャー120年の歴史を変えた男』(タカ大丸訳)徳間書店
フレッチャー,ジェフ(2024)『SHO-TIME 2.0 大谷翔平 世界一への挑戦120年の歴史を変えた男』(タカ大丸訳)徳間書店
【81頁】ブランケット,ビル(2024)『SHO-TIME 3.0 大谷翔平』(タカ大丸訳)徳間書店
ホーンストラ,J.P.(2025)『SHOHEI OHTANI:YEARS IN LA DODGERS』(田代学訳)東京書籍
米倉誠一郎(2017)『イノベーターたちの日本史 ─近代日本の創造的対応』東洋経済新報社
脇坂明(1998)『職場類型と女性のキャリア形成・増補版』御茶の水書房
Knight, Frank Hyneman(2021) 『リスク,不確実性,利潤』筑摩書房(原典は1921年出版)
Schumpeter(1947),”The Creative Response in Economic History”, Journal of Economic History Vol.7.No.2.(『起業家とは何か』(清成忠男訳)に所収 1998)
Thurow,Lester(1984)『不平等を生み出すもの』同文舘 (小池和男・脇坂明訳)原典は1974年刊行
週刊ベースボール(2025)『花巻東高校野球部』