Answer

どんなことを学ぶの?
どんな授業があるの?

- すべての教員が高い水準の教育を提供し、 在学生の満足度を高めています。
-
特定の分野に偏ることなく、バランスのとれた
オーソドックスなカリキュラムを提供します。
Answer



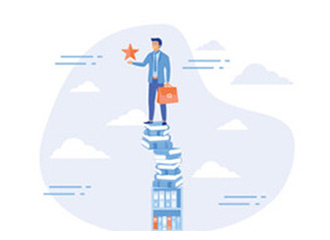

Columnコラム
前年の令和4年度では最終合格者が1,403名で、内、法科大学院未修者が218名、割合は約15.5%ですから、司法試験において未修者の最終合格は難化したと言えます。令和5年度から法科大学院の在学中受験が可能になり、そのほとんどが大学在学中から司法試験合格を目指して法律を学んでいた方だと思われます。そのような方々が法科大学院入学後、早期に司法試験受験資格を獲得し、令和5年度では637名が最終合格を掴みました。つまり、法科大学院入学以前に必死に法律を学んでいた者(=既修者)の司法試験受験者が増え、対して、最終合格者数は大幅に増えていない結果、相対的に法科大学院入学後に法律を学び出した者(=未修者)が最終合格を果たすのは難しくなったということです。そもそも法科大学院が創設されるきっかけとなった司法制度改革は、多様な人材の法曹界への参入を促進する狙いがあったはずであり、法律とは別の分野で活躍していた社会人は法科大学院への入学を契機に法律を学び始めるとすればそのほとんどが未修者であると思われるため、このような司法試験最終合格の結果は、本来の司法制度改革の狙いとは逆行しているような気がします。
私自身が20年弱、法律とは別の分野で社会人を経験し、41歳で学習院大学法務研究科に未修入学しましたので、個人的には、より多くの未修者の方々に最終合格を果たしていただきたいと応援したい気持ちでいます。司法試験の結果データに戻ると、最終合格者1,781名中、1回目の受験者が1,584名(約89%)なので、法科大学院修了後、年数が経てば経つほど合格が難しくなることは明らかです。つまり、法科大学院未修者にとっては、何が何でも法科大学院在籍中の3年間で司法試験最終合格に足りる実力を身に付ける必要があるのです。
その経験を踏まえて、未修者が司法試験に最終合格するために法科大学院在学中に行うべき学習方法について、お話しさせていただきたいと思います。まず、当たり前の話ですが、司法試験合格のために何をどのくらい学習すべきかの方法論は人によって異なります。基本書や判例百選をベタ読みした方が良いとか、予備校の〇〇講座を受講した方が良いとか、〇〇という参考書を読んだ方が良いとか、〇〇という事例問題集をやり込んだ方が良いとか、巷には色々な司法試験の学習方法が語られていますが、それが効果的かどうかは人によって異なります。前述した通り、法科大学院未修者にとって司法試験までの時間はたった3年間しかありませんから、他人やウェブサイト、予備校講師等が一般論として語っている「効率的な」学習方法を試し、失敗を積み重ねて、自分に合った学習方法を探り当てるといったトライアル&エラーを繰り返す時間的余裕はありません。そのため、自分にとって、司法試験に最終合格するための課題とはどのようなものか、その克服のためにどのような学習方法を選択すべきなのか、といった自己分析が何よりも大切です。つまり、この自己分析、そしてそれに基づく学習計画の策定方法を知っているかどうかこそが未修者が首尾よく司法試験の最終合格を掴み取ることができるかどうかの肝なのです。
逆算して考えましょう。司法試験の受験勉強の王道は本試験論文過去問演習です。これまで司法試験の受験勉強をしてこなかった未修者は本試験論文問題を解き慣れていませんから、問題文に慣れるためにも最低でも5年分、できれば10年分は過去問演習をしたいところです。本試験論文過去問を週に2問解くとして、10年分を解き終えようとすれば10か月かかります。本試験が7月にあると想定し全国模試等が同年4月5月にあることを前提として、法科大学院には前期後期の試験もありますから、本試験前の4月までに論文過去問を10年分解き終えようとすれば、その1年前、つまり法科大学院3年生の4月から論文過去問を解き始める計算になります。しかし、それまで論文過去問演習をしてこなかった方がいきなり週2問のペースで答案作成ができるようになるとは思えません。それぞれの論文過去問の出題趣旨を捉えて、合格答案をイメージした上で、答案作成の練習をしなくては意味がないのです。論文過去問の出題趣旨を捉えるには、毎年法務省のホームページで公開されている「出題趣旨」と「採点実感」を読む必要があります。これらを読みこなしながら、その年のその科目の論文試験において、合格するには何をどの程度書かなくてはならなかったのか、或いは、何をどの程度書けば足りたのか、を分析する必要があります。そのような作業を法科大学院の正規授業の予習復習の合間に行わなくてはなりませんから、少なくとも憲法・民法・刑法の論文過去問演習は、法科大学院2年生の後期、できれば前期から、週1問ないし二週間に1問のペースで行うべきだと思います。そうなると、憲法・民法・刑法の論文過去問演習を行うだけの基礎知識、基礎理解は、法科大学院1年生の1年間で身に付けておくべきことがわかります。
司法試験の受験勉強を行っていると「これは基礎知識です」などと言われることが時々あると思います。「当然知っておくべき知識」くらいの意味で使われていると思いますが、受験生としては、受験間近になって「当然知っておくべき知識」すら身に付けていなかったことを指摘され、ショックを受ける、なんていうこともあり得ます。しかし、自ら「当然知っておくべき知識」がどのようなものか知る方法があります。それは、本試験(予備試験)短答過去問です。短答知識には簡単なものもありますし難しいものもありますから、そのすべてが「当然知っておくべき知識」というわけではありません。ただ、司法試験の結果データによると、令和5年度の短答式試験の合格に必要な成績を得た者(=短答合格者)の平均点は175点満点中126点(72%)で、その平均点獲得者数は1,552人、令和5年度司法試験の最終合格者数は1,781人ですから、その大半が短答式試験で7割以上を正答したと考えることができます。つまり、短答過去問演習を行い、7割から8割を確実に正答できるだけの知識を有していれば、司法試験合格のために「当然知っておくべき知識」は有していると言えるのです。
よって、憲法・民法・刑法においては、法科大学院1年生の内に短答過去問で最低でも7割はコンスタントに正答できるようにしておかなくてはなりません。そうしないと、論文過去問演習を始めるためのスタート地点にすら立てないのです。換言すれば、短答過去問で7割以上安定して正答できるだけの知識を有していれば司法試験最終合格者が平均的に有している知識や理解を有しているということですから、その自分の知識や理解を物差しにして論文過去問の出題趣旨や採点実感を読むと、最終合格者が答案上どの程度の知識を用いてどの程度の理解を答案上示すのかがわかるようになります。つまり合格答案をイメージできるようになるのです。そのような自分の知識や理解を基準とした物差しを磨くことで、論文試験の問題を読めば、出題趣旨や採点実感を読まなくても、合格答案がイメージできるようになるのです。その上で、そのイメージした答案を作成できるように訓練します。これが論文過去問演習です。
論文過去問演習の際、合格答案のイメージが上手にできない場合やイメージした合格答案がうまく作成できない場合に、問題文の読み方が悪いのか、法的三段論法の理解が乏しいのか、判例理解が浅いのか、暗記すべきものが正確に暗記できていないのか、字を書くスピードが遅いのか…といった課題が浮き彫りになります。これこそが、その方だけの課題であり、その課題を明確にする作業が前述した自己分析です。そして、この課題を克服するために、例えば、基本書や判例百選を読み込んでみたり、〇〇という参考書で暗記すべき文言を確認したり、〇〇という事例問題集をやって法的三論法の基本的な使い方をマスターしたりといった必要な学習を行います。それをどのようなスケジュールでこなしていくのかを考えることが学習計画の策定というわけです。
本稿の冒頭でも申し上げましたが、法科大学院未修者にとって、司法試験に最終合格するための時間はたった3年間しかありません。法科大学院に入学したら、まずは正規授業の進行に伴って学習した分野の短答過去問演習を徹底的に繰り返しやり込んでください。そして、まずは憲法・民法・刑法の各科目を1周したら、できるだけ早い段階で論文過去問演習を始め、自己分析に基づく学習計画の策定を行ってください。(両訴訟法や行政法、会社法については2年生から正規授業が始まるものもあると思います。その場合も正規授業の進行に伴って学習した分野の予備試験短答過去問をやり込むことをお勧めします。)
このような学習の中で色々迷うこともあると思います。その際、法科大学院の教員や私のような修了生法曹、同級生や予備校講師などにアドバイスを求めることもあるでしょう。そのような相談に各々真剣に向き合ってくれるとは思いますが、良かれと思って、一般論的な学習方法を伝えようとする方もあります。前述した通り、一般論的な学習方法がその方の課題克服に有益かどうかはわかりません。下手をすれば、無益な学習に時間を費やし、回り道をしてしまうこともあり得ます。また、論文過去問演習を行う前に、インプットを完璧にすべきとか、簡単な事例問題を解く練習をすべきといったアドバイスをされたりもするでしょう。そのような順序で実力を培える人もいると思います。ただ、本試験の論文過去問演習をしなければ、司法試験最終合格までの距離感やその間に立ち塞がる課題は見出せません。よって、自分だけの課題分析ができません。これらのことを考えると、法科大学院未修生が司法試験の最終合格を果たす秘訣は、従うべきアドバイスを見極めて上手に選択すること、とも言えるかもしれません。


Interviewインタビュー
私は、学部4年間を政治学科で過ごし、法科大学院へ未修で入学しました。当初は授業についていくのも大変な状況でしたが、先生方に支えていただき、昨年の司法試験に合格して、今は司法修習生として過ごしています。修習生バッジを毎朝つけるたびに、司法試験に合格できたことを実感するとともに、憧れていた世界へ近づいているという嬉しさをかみしめています。
法曹になりたいという意思、最後まであきらめない意思さえあれば、いつ法曹への道を決意しようが遅いということはないのだと思います。
司法試験を目指して勉強していると、挫けそうになるタイミングが幾度となく訪れるかもしれません。そんなときは、法律家への道を選択したときの決心を思い出してみてください。勉強を続けていれば、きっと道は開けます。学習院大学法科大学院で学ぶみなさまが目標を達成できるよう陰ながら応援しています。


