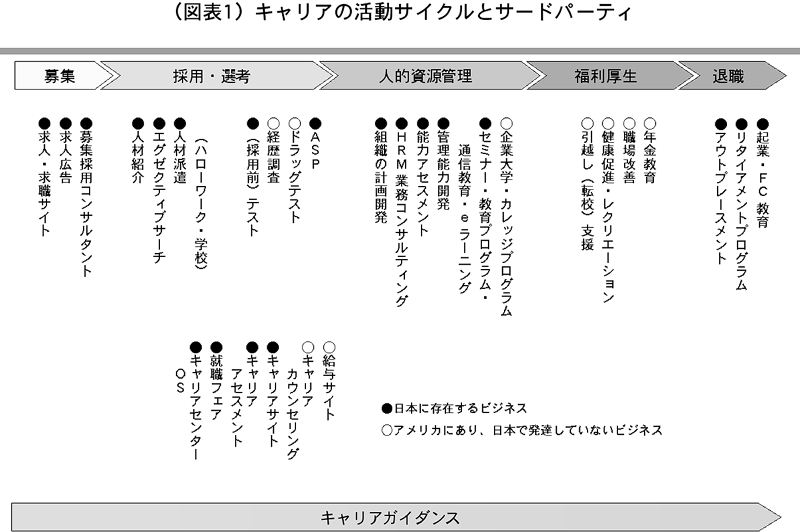
若年のキャリア支援を考える
――アメリカの取組みと日本への示唆――
株式会社リクルート ワークス研究所 主任研究員
村田 弘美
【33頁】
キャリアの語源は,フランス語で「carriere」。競馬場や競技場のトラックや車輪などを表したといわれている(他にラテン語説などもある)。以前はキャリアというと高級官僚を指す用語として使われていたが,近年では,「経歴」,「経験」,また「職業」という意で一般的に使用されるようになった。曖昧な用語ではあるが,キャリアサービスの先進国ともいえるアメリカの取組みを紹介するとともに,日本において個々のキャリアを育て生かすためにはどのような支援が有効か考察する。
目 次
Ⅰ.キャリアの領域 ~活動サイクルとサードパーティ~ 目次に戻る
キャリアとは何か。キャリアに関しては諸理論あるが,実際には人によって持つイメージやその行動も異なる。ここでは,外部労働市場や労働市場サービスの視点から包括的にアプローチし,全体像の把握を試みることとする。はじめに,募集~採用・選考~人的資源管理~福利厚生~退職・退社に至る一連の活動サイクルの中で,どのようなキャリアサービスが存在するのか描いてみた(図表1)。
募集領域では,求人・求職サイト1),求人広告,募集採用コンサルタント。採用・選考領域【34頁】 では,人材紹介,採用選考試験,経歴調査,ドラッグテスト,アプリケーションサービスプロバイダー。人的資源管理領域では,組織計画開発,HRM業務コンサルティング,能力アセスメント,管理能力開発,セミナー,教育プログラム,通信教育,eラーニング,企業大学・カレッジプログラム,人材派遣。福利厚生領域では,転職に伴う引越し支援(引っ越し会社紹介,住宅斡旋,家族の転校や転職など),健康促進,職場改善,年金教育。退職領域では,アウトプレースメント(再就職支援),リタイアメントプログラム,起業,フランチャイズ教育。ここに挙げた意外にもキャリアに関わるサービスはますます多様化しかつ複雑化している。
他にも,キャリア領域があり,アメリカではさまざまなサービスが展開されている。大学等のキャリアセンターの運営,ジョブフェア,キャリアアセスメント,キャリアポータルサイト2),キャリアカウンセリング3),サラリー(給与)サイト,レジュメ(経歴書)作成など,多くの職業に関する情報やサービスが提供されている。日本では少数だが,自分の履歴書や職務経歴をサイトに貼るいわゆる「求職」サイトが多く展開されており,付加したサービスや,キャリア入門書4)など書籍も多数ある。このようなキャリアサービスは,学業と職業の連動性から大学やコミュニティカレッジなどとも大きく関わっている。大学の選択イコール職業選択となり得る機会も多いからである。
Ⅱ.小学校からのキャリア教育支援 目次に戻る
アメリカでは,子供が親の職場を見学する「子供参観日」が浸透しているが,州によっては加えて毎年2月2日に「ジョブ・シャドウイング・デー」を実施している。これは,自分が興味を持つ企業や職業で働く社会人に,一日密着して主にマンツーマンで,さながら影のようになり就業感を養うものである。また,州によるが高校生には「スクール・トゥ・ワーク」のプログラムなどに力を入れる。主にサービス業や現場の仕事だが,数週間企業で働く機会も与えている。実際に職場を体験することで,自分はどのような職業が向いているのか職業適性をつかみ知ることができる,逆に自分は現場の仕事よりも管理職として働きたいので進学すると,【35頁】 進路を変更する者もいるという。
大学生のキャリア教育は,主に「インターンシップ」であるが,日本の職場見学的なインターンシップとは異なる。後に詳述するが,4年間のうち1000時間を超える本格的なもので単位として義務化するところもある。また,学校に併設されるキャリアセンターではキャリアカウンセラーを配置し,選択科目など学業の相談から適職診断,個別の進路相談,学内でのジョブフェアの企画運営などを行う。スタンフォード大学など,既卒者も受け入れているキャリアセンターもある。
また,アメリカは自助努力を奨励する国である。日本との一番の違いは,学費を誰が負担するかである。日本では,大学までの授業料や生活費を親が賄うケースが多いが,アメリカでは,大学の学費は学生自身が支払うことが多い。そのため若年者の就業及び職業訓練を支援する個人を対象とした社会制度として,1997年に制定された生涯学習のための税額控除や,民間を含む学費援助プログラムや奨学金制度もキャリア支援の1つとして機能している。返済義務のない奨学金制度は20万種類で,専用の検索サイトも存在する。学生ローンは返済義務があるが日本の育英会の奨学金と類似しており,すべての大学が制度を適用し連邦や銀行経由で貸し付けを行なう。18歳以下の子供がいる家庭には家計単位での教育口座が適用となり,毎年500ドルまでの預金が可能で,利子や引出し金は非課税となる。
ここに挙げたのは一例であるが,これ以外にも小学校からの学習指導要綱に合わせたキャリア教育が各所で実践され効果を上げている。
Ⅲ.公共のキャリアサービスによる職業情報サービスと職業訓練の提供 目次に戻る
1.連邦労働省によるキャリアに関する情報の提供
職業概念が確立しているアメリカでは,職業に関する情報提供にも力を入れている。連邦労働省雇用訓練局のインターネットサービスは,キャリアに関するあらゆる情報を無料で提供している。ウェブサイトは現在では主に4つのサービスで構成されている。各州とも連携し州の実状に合った情報提供を行っている。
“キャリア・ワンストップ”は,学校の紹介(国公立・私立),キャリアガイダンスサービス,アセスメント,職業訓練,職業紹介などあらゆるサービスへの接続案内で,どのサービスを何処で利用できるかを紹介するサイトである。“キャリア・インフォネット”は,職業情報を提供するサイトで,仕事内容や必要なスキル・資格,給与,昇進,職に就くためにどのような教育が必要かといった情報を文字や映像で提供している。“アメリカズ・ジョブバンク”は,連邦政府が運営する求人・求職サイトで,マイノリティを中心に利用者は多い。
“アメリカズ・サービスロケーター”は,全国に7,612カ所あるワンストップセンターの検索サイトで,若年者向けの施設を特定しての検索も可能である。アメリカのワンストップセンターは,若年者の他に高齢者向け,IT技術者向けなど専門的なセンターや,空港やショッピングモールなどに置かれる情報検索端末,大型トレーラーの中にワンストップセンターと同じオフィスを作り,カウンセラーが乗って各地を移動するモービルなど多彩であるため,このような検索サービスが有益である。
【36頁】
2.ワンストップキャリアセンターを中心とした公的なキャリアサービス
連邦政府と州政府は,数多くのルートから労働者に対して職業訓練を提供している。職業訓練は失業保険や職業紹介とともに労働者支援ネットワークの要である。代表的なプログラムは労働力投資法(WIA:Workforce Investment Act)に基づくものであるが,その特徴は,一部の州を除いて日本の労働保険特別会計のような事業主から徴収した財源を持たないこと,統一規定は最小限で州や地方に柔軟性をもたせること,公共職業訓練用の施設を持たないこと,訓練はバウチャーまたは委託方式により既存機関を利用して行われ,成果管理を導入していることなどにある。
連邦政府はワンストップキャリアセンター(公共職業紹介所:以下ワンストップセンター)を中心として労働者に多様な訓練と雇用プログラムへのアクセスを提供している。公的な職業訓練サービスを合理化し,州政府,地方及び訓練提供者の責任を強化している。州政府と民間の委員により構成される労働力投資委員会が5カ年にわたる職業訓練計画を作成する。実際には,各地域単位の労働力投資委員会が雇用主のニーズに合った地域の計画を作成し,ワンストップセンターを監督,訓練提供者を認定するなど,目標及び成果管理に至るまで一連の管理運営を行うという組織構造になっている。
若年者に関しては,ユース・ワンストップセンターと称する16歳から24歳までの若年を対象とした専用の施設を若者が行きやすいショッピングモールなどに設置している。地域により内容は異なるが,連邦や州による若年者向けの就業プログラムや職業訓練を提供している。プログラムの実施は入札などにより政府機関,教育機関,非営利団体などの事業者が受託する仕組みをとる。なかでも高い効果を上げたワンストップセンターはカリフォルニア州ロングビーチ市にあるユースオポチュニティセンターといわれ,同センターではカリフォルニア州立大学やYMCA,地元のコミュニティカレッジなどの教育機関が運営に参加し,多種多様なプログラムを提供している。内容は,夏期の8週間に行われる雇用されるための基本スキル習得コース,座学と現場の交互訓練コース,起業コース,子供を持つ父親を対象とした再就職と子育ての両立のグループコース,有給のインターンシップ,ジョブ・シャドウイング(職場体験)などで,基本サービスは無料である。センターの端末にはレジュメの書き方のソフトウェアもインストールされており,職員が丁寧に指導する。地域の産業構造に合わせたオリジナルの職業ファイルを作成するところもある。また,訓練終了後は職業紹介のプロセスへと移行する。
3.2002年に若年者を対象とした職業訓練の成果
2003年4月に公表された米国会計検査院の報告“Multiple Employment and Training Programs”によると,2002年に実施された連邦の44の雇用・訓練サービスのうち,若年を対象とした職業訓練は,各省庁のものを合わせて6つのプログラムが実施された。アメリカの公共職業訓練は主に失業者や貧困層,難民,障害者に特定したものであるが,その予算の累計額は27億ドル超(2003会計年度),参加人数の累計は約47万人(2002会計年度)に達する。このうち代表的な3つのプログラムを紹介する。
1つは連邦労働省のWIA若年プログラムで,ワンストップセンターで実施される。予算額は約10億ドル,2002年の参加者数は約37万人と最大規模である。若年労働者が知識やスキ【37頁】 ルを身に付け,生産的な市民となり,成年期にスムーズに移行し,ビジネスや経済変化に対応し,キャリアに適した仕事を維持し,昇進・昇格できるようサービスの質の向上とプログラム成果の拡大を目指すことを目的としている。対象は14歳から21歳で,家族の所得が生活標準収入の7割を超えていないことや基礎識字率に欠けること,学校中退者やホームレスであることなどで,教育の完遂や雇用の維持に支援を要する者となっている。プログラムは,雇用カウンセリング,アセスメント,英語教育,OJT,職業維持訓練,就職活動,職業紹介などで,個々人に合った適切な内容の支援をしている。
2つめは連邦労働省直轄のジョブコアプログラムである。全米最大の寄宿型の教育雇用訓練で,仕事に就くのに複数の障害を持つ若年向けのプログラムである。WIAに基づき運営され,予算は約15億ドルと前年度より増額された。2002年の参加者数は約6.8万人で,開始以来200万人以上が参加した実績を持つ。学校教育,職業訓練,生活訓練,仕事に必要な教育など,労働市場にとどまるのに必要なスキルを習得させることを目的とする。寄宿所は全米に118カ所設置され,在籍期間に制限はないが2000年度の平均在籍期間は10.6カ月,プログラムを修了することで高校卒業資格を得ることも可能となる。参加条件は16歳から24歳の学校退学者で,公的支援を必要とする低所得者,里子,障害者,ホームレスなどとなっていて,未成年者は保護者の同意が必要となる。参加費は無料。基礎訓練に加えて,生活面でのケアも重視される。医療関連,自動車,ビジネステクノロジー,建設,調理,消防などで多くの職種の訓練が可能である。また,参加者には毎月,生活手当が支給され,健康保険や歯科保険も提供される。加えて,目標達成度や在籍期間によってボーナスも支給される。プログラム修了後も,1年にわたりキャリアカウンセラーによる就職支援が行われる。プログラムの実施は都市ごとに民間事業者や労働組合に委託され,企業の従業員や組合員が指導にあたる。地元の職業訓練学校やコミュニティカレッジとも提携し,通常のプログラムにない職種の職業教育も提供している。2000年度の修了者の就職率は94%で,その平均賃金(時給)は7.97ドルと目標の7.49ドルを上回ったが,就職継続率(就業後90日)は67%と目標に満たなかった。2001年度のプログラム修了者のうち,90%が就職,就学,または入隊している。
3つめは,住宅都市開発省が実施するユースビルドプログラムで,1992年,Hope for Youthプログラムとして住宅地域開発法(Housing and Community Development Act of 1992)のもと開始された。現在は43州で180のプログラムが実施されている。予算額は6千万ドル,2002年の参加者数は3,729人の実績を持つ。財源はこの他に民間企業や財団などからの寄付による。高校を中退した者や経済的に不利な立場にある者が自立に必要な教育と雇用に必要なスキルを習得し,地域開発においてリーダーシップを発揮できるよう設計され,かつホームレスや低所得者のために住宅の供給も行う。対象は16歳から24歳の低所得者で高校を中退している者,特に女性に重点を置いている。所得要件や教育要件を満たしていなくとも教育上のニーズがあれば参加可能である(全参加者の25%以下に制限)。参加者は1年にわたり,座学と建設現場の交互訓練を受け,住宅建設や改築に参加する。講習の内容は,読解,筆記,数学,リーダーシップ,労働習慣,決断力の習得,時間管理,キャリアプランの作成など。現場訓練では組合に所属する熟練技能者のもと,大工,解体,石工,塗装,メンテナンスなど,住宅建設における一連のスキルを習得し,修了者には高校卒業資格も与えられる。プログラムの運営機関は競争入札により選ばれる。参加者一人あたりのコストは給付金を含めて2万ドルだが,前出のジョブコアよりもコストの安いプログラムといわれている。プログラムが実施された1993年以【38頁】 降,2001年までに累計で8,351人が参加,4,935件以上の住宅建設や修復をした。また,修了者の約9割が建設関連会社に就職し,平均時給7.61ドルを得ている。職業経験を持つ者を対象とした奨学金の対象となるため,大学に進学した者もいる。
いずれのプログラムも成果評価が行われ,その内容は公表されている。成果の判断基準は参加人数の他に,①就職したかどうか,②雇用が維持継続(定着)しているか,③資格認定や学位取得できたか,④昇給したか,などで,職業訓練を受けることによりどのような結果に結びついたかを精査するものである。
Ⅳ.専門職を養成する社会システム 目次に戻る
ここまで包括的なしくみについて説明したが,具体的にホテル業でのキャリア支援について見てみたい。
1.キャリア情報サイトの利用
ホテル業で働きたい場合,どのような職種があり,仕事に就くためにはどうしたらよいか。
まず,“キャリア・ワンストップ”と“オキュペーショナル・アウトルック”で検索し,職に就くために必要な知識,経験,資格,スキル,賃金,地域の企業の情報を調べることが可能である。“キャリア・ワンストップ”では平均収入,就業者数,今後の就業者数の予測と増加率,一般的な講習プログラム,必要な学歴や訓練,入職経路などの情報が容易に入手できる。また,職種の情報はサイト内のビデオでも説明される。ホテル業の職種にもさまざまあるが,代表的なフロント,コンシェルジュ,ルームサービス,ハウスキーパー,ベルボーイ,マネジャーの6職種を調べた結果が図表2である。“オキュペーショナル・アウトルック”は労働省が発行する職業ハンドブックであるがこちらでも職業に関するさまざまな情報が提供されている。ここでは,業界の特色,業界の分類,近年の傾向,労働条件,就業者数,自営業数,企業規模,就業者の年齢層と全産業の比較,職種,教育,必要なスキル,職業大分類・小分類別仕事内容,就業者の将来予測,職業訓練の内容と昇進昇格条件,職種別賃金・平均時給などといった情報が提供されている。ホテル業種の特徴は図表3にまとめた。
2.協会による支援
米国団体役員協会よると,アメリカでは6,589の職業単位での協会組織が存在するという。ホテル業ではアメリカ・ホテル・アンド・ロッジ協会や,アメリカ調理連盟などでも職業資格制度を設け,中小企業を中心にホテル業で働く者の教育訓練といったキャリア支援を実施している。
3.学業と連鎖した職業訓練 ~コミュニティカレッジと大学の取組み~
公共職業訓練は,主に失業者やマイノリティ層を対象とするが,それ以外の若年者はどのような職業訓練を行っているのか。ここでは,ホテル業の職種に就くための学業と連動した職業訓練事例を紹介する。
はじめに,学業によって得られる資格と職業の連動性であるが,高卒資格では客室係や予約係などの基礎的な職に,準学士号ではスーパーバイザーまで,学士号ではアシスタントマネジ【39頁】 ャーまで,修士号ではマネジャーまでと,学歴によって初職で配属されるポジションが決まるのが一般的である(図表4)。職業経験が最も重視され,いわゆる下からのたたき上げも可能だが,キャリアアップの早道として一旦職に就いてから学業に戻る者が多い。
また,各地域のコミュニティカレッジにも多くのホテル関連のプログラムが組まれている。コミュニティカレッジは日本の短大や専門学校にあたるもので,全米各州に1,132校ある。取得できる単位は15~60単位で,全日制で準学士相当の単位や,職業資格の取得が可能である。州の住民であれば無料で受講できる(ハワイ州を除く)ため利用が容易である。若年者に限らず,地元のホテルが従業員用に実践的な訓練プログラムを開発し提供していることもある(図表5)。
専攻分野と職業が連鎖している社会では大学選びも重要視される。ホテル経営に特化した学部を設置している大学もあり,コーネル大学やネバダ大学ラスベガス学校などが代表的である(図表6)。現在ホテルに勤務する者の多くはこうした大学の卒業生である。大学で特筆されるのはインターンシップ制度で,近年日本で行われているものとは様相が異なる。500時間から1,000時間と長期間が殆どで,現場訓練が重視されている(図表7)。低学年時に客室係などスキルの低い職務を経験し,高学年時にマネジャークラスの仕事や複数の職種を経験するなど2回に分けて実施することもある。ラスベガスでは実際のホテルを貸し切りにし,学生が実際に従業員と同じ職務を行い,大学のOBやホテル関係者が審査するなど大規模な訓練を行っている。インターンシップには地域移動を伴うことも多く,住居費を企業が負担するなど,有償もある。インターンシップ体験は実際の就職の際に職務経歴書に書くことができ,就職後の配属にも影響を与えることとなる。社会人としてのマナーや態度,ビジネスの基礎知識を習得する機会でもあり,企業も入社後に日本の新卒者のように一からOJTを行わず,即戦力として活躍の場を与える。他には,ホテルで働く卒業生とのメンター制度を取り入れる所も多く,就職の相談などが行われている。
入社後もOJTに力を入れるリッツカールトンホテルの職業教育は有名であるが,大手企業のように自社で固定の教育プログラムを持たない場合はどうか。例えばカリフォルニア州ではホテル業全体の教育制度として,キャリアラダーといった階層別教育を推奨している。特筆すべきは,成功報酬制で,プログラムに参加した者は,修了後に必ず昇給もしくは昇格を企業に義務付ける。講師はベテランのマネジャーが行い,実務ベースであることから,受講者は長期間の現場トレーニングに熱心に取り組んでいる。その教育プログラムは,地域のコミュニティカレッジやサンディエゴ州立大学のプログラムとして提供することで汎用性を高め,ホテル業の職業教育のマニュアルにする予定であるという。
Ⅴ.日本のキャリア支援への示唆 目次に戻る
アメリカの若年キャリア支援制度は多種多様である。基本的な情報提供やマイノリティに特化したキャリア教育支援は官が主導して実施する。また,民間も多彩なサービスを行っている。日本のキャリア教育や支援が目指す方向性は必ずしもアメリカに向いているとはいえないが,各所で参考にすべき点は多い。
若年に対するキャリア支援で大切なことは3つある。
1つめは,リアルな情報を知ることである。イメージやバーチャルな世界ではなく,労働の【40頁】 現場の事実を伝え,知らせる機会を持たせることが必要である。リアルな業界や職業情報,職業教育などの情報提供は結局のところキャリア選択や会社選択の近道となる。自分の選択した職業の需要や,地域の産業構造の変化,収入などの現実的な側面を知ることも必要である。いつでも誰でもがその情報にアクセスができること。多くのものがアクセスできるインターネットでの情報提供や,職業を画像で紹介することも有効である。また,職別に学校やハローワークなどの求人件数の実態を知らせることなどである。
2つめは,学業と職場の連鎖である。世の中にどのような仕事があるのか。さまざまな職業を自分の目で知ることや,自分の就業可能性に気づかせるといったキャリアガイダンスは,小中学校など早期から実施するほど有効である。次のステップは,目指す職業に就くにはどうしたらよいか,その有効策を知らせ導くことである。具体的には学校や学部の選択やスキルや資格取得とも大きく関わる。中学や高校での進路選択の機会を有効に活用したい。キャリアカウンセリングとの併用が望ましい。また,専修学校や大学時に,長期のインターンシップといった現場を知る機会を持たせ,就業可能性や職業適性に加えて,職場を自分の肌感覚で知ることは,職業選択の決め手となり,かつ,就職後の定着にも繋がる。
3つめは,実際に仕事をして修羅場を積むこと。これがキャリアへの一番の近道である。自分探しや職に固執するばかりに就職の機会を逃すこともある。キャリアを積むというのは,プランをたてることではなく,実際に仕事をすることからはじまる。時には有無を言わず飛び込んでみることも必要である。思考でなく経験から得られるものはとても大きい。日々の積み重ねなど時間の経過が自分を成長させることも実は多いということを忘れてはいけない。フランスの若年対策では,派遣会社と国家協約を結び,職業のブランクをつくらせないよう,まず派遣として企業で働かせる機会をつくっている。職業経験を積ませることで,1年後の正社員への就職率を高めたという結果がでている。
日本においても若年対策が社会的に重要な問題であると認識され,4閣僚,4省庁による人材立国プランが動きはじめたが,このような画期的な試みに注目したい。若年者のキャリア教育は,特に文部科学省や厚生労働省の狭間に位置することから立ち遅れていた領域であり,省庁の連携のもと早期に問題点と取り組むべき課題を明確化することが必要である。それに加えて,企業が取り組むべきこと,官が取り組むべきこと,学校などの教育現場で取り組むべきこと,家庭で取り組むべきことは何か,そして自分自身は何をすべきか,目標や解決策を具体的に提示し,誰にも分かるよう周知することが重要である。
アメリカやイギリスでは,地域を特定して新しい試みを「実験」し,その効果測定の結果によって全国に施策を波及させている。イギリスでは,一人ひとりを顧客にみたて,処方箋を作り,まさに治療をするように,面接用の服装のコーディネイトや,仕事に必要な資材の支給,職業訓練,オーダーメイドの就職先の開拓をするというところまで進んでいる。日本においても,新たな手法も取り入れるべきであると考える。
【41頁】
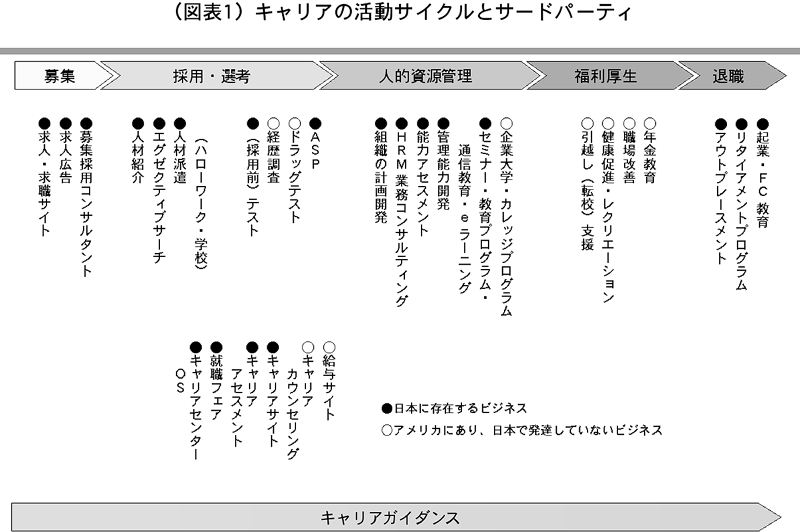
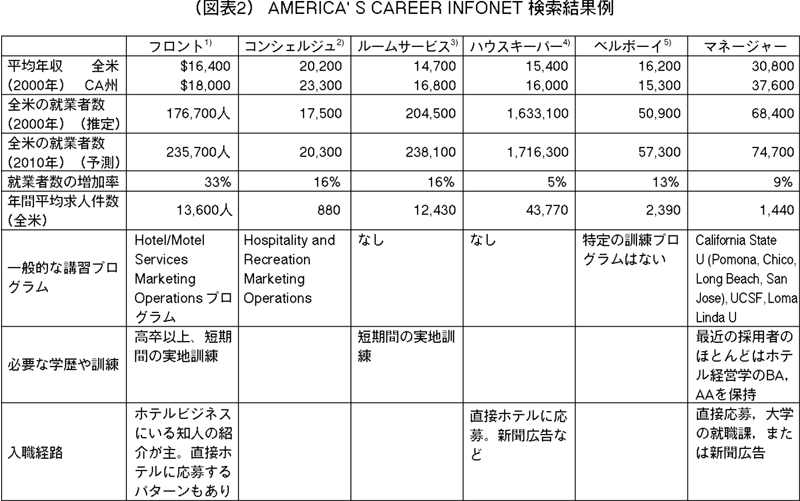
【42頁】
(図表3)職業展望ハンドブック 情報掲載例
<ホテル業のトレーニングと昇進・昇格>
○エントリーレベルでは,OJTが中心
○大手では,トレーニングセッションあり。ビデオを利用したトレーニングを行っているところもある。
○大学や短期大学,専門学校,職業学校,高校などでホテル業トレーニングを行う需要は伸びている。
○調理,ケータリング,レストラン管理部門のトレーニングは,労働組合や職業学校がトレーニングプログラムを運営していることも少なくない。これらのプログラムの期間は,数カ月から数年と異なる。
全米で約200の短期大学またはコミュニティカレッジが,ホテル・レストラン管理の準学士コースを設けている。アメリカ軍も飲食サービスのトレーニングコースを備えている。
○ホテル業のマネージャーには,通常,オフィスサポート部門の従業員で,コミュニケーション能力,学歴,ロイヤリティ,勤勉さを備えた者を昇格させることが多い。大手ホテルチェーンでは,4年制大学教養学部等の新卒者をマネージャー候補として採用することもある。
○約150の大学がホテル管理の学士号または修士号コースを設けている。
○フロントマネージャー,飲食マネージャー,営業マネージャー,ジェネラルマネージャーといった上級管理職については,通常,正式なトレーニングと職歴が要求される。コントローラーや購買マネージャー,エグゼクティブハウスキーパー,エグゼクティブシェフといった職については,特別のトレーニングと長期間のOJTが求められる。
○昇進・昇格のために,ホテルからホテルへと渡り歩く者が多い。
○オフィスサポート部門の昇進昇格システムは多様。ハウスキーパーや清掃員といった職種では,昇進の機会は限られている。規模の大きなホテルでは,清掃員からスーパーバイザーに昇格することもある
○フロントデスクは,マネージャーへの昇進昇格の道が開かれている。フロントデスクの昇進機会は他の部門の職種よりも大きい(ホテルの顔はフロントであり,ホテルの仕事のすべてがフロントに集約されているため)。フロントからPR,広告,営業,マネージメントなどへと異動することもある。
○シェフやコックは他のサービス職に比べると昇進の機会が多い。コックからシェフ,エグゼクティブシェフ,レストランマネージャー,飲食サービスマネージャーといった職へ昇進することになる。同じ業界内での転職も多いが,独立する者,料理教室の講師になる者も少なくない。
出典:CareerGuidetoIndustries2002-2003,OccupationalOutlookHandbook2002-2003
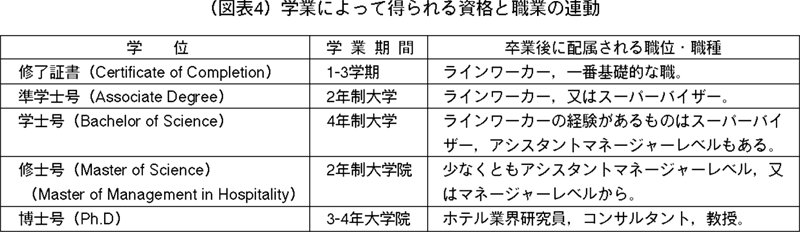
【43頁】
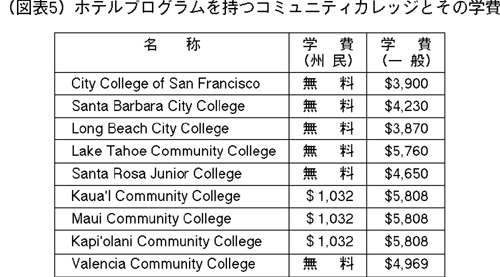
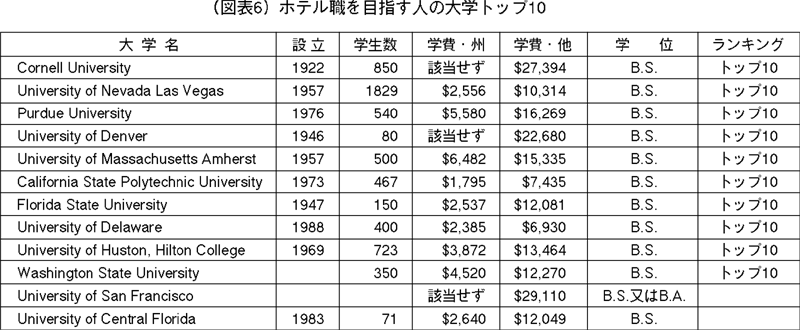
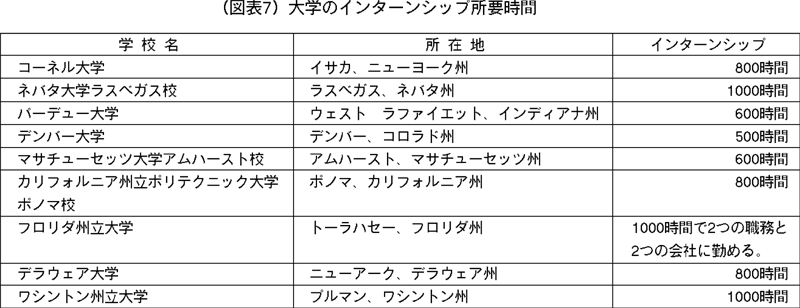
参考文献
・DOL/ETA “Notice of availability of funds and solicitation for grant applications for the national grants portion of the Senior Service Employment Program” Nov.2002
・DOL/ETA “Training and Employment Information Notice to All State Workforce No.15-00”
・DOL/ETA http://wdsc.doleta.gov/jobcorps/
・GAO“MULTIPLE EMPLOYMENT AND TRAINING PROGRAMS Funding and Performance Measures for Major Programs-” April 2003
・CWIB“California Health and Human Service Agency Employment Development 2002”
・AACC (ALL ABOUT COMMUNITY COLLAGES) http://www.aacc.nche.edu
・リクルート ワークス研究所 2002 Vol.5“アメリカ カリフォルニア州の労働市場サービス”