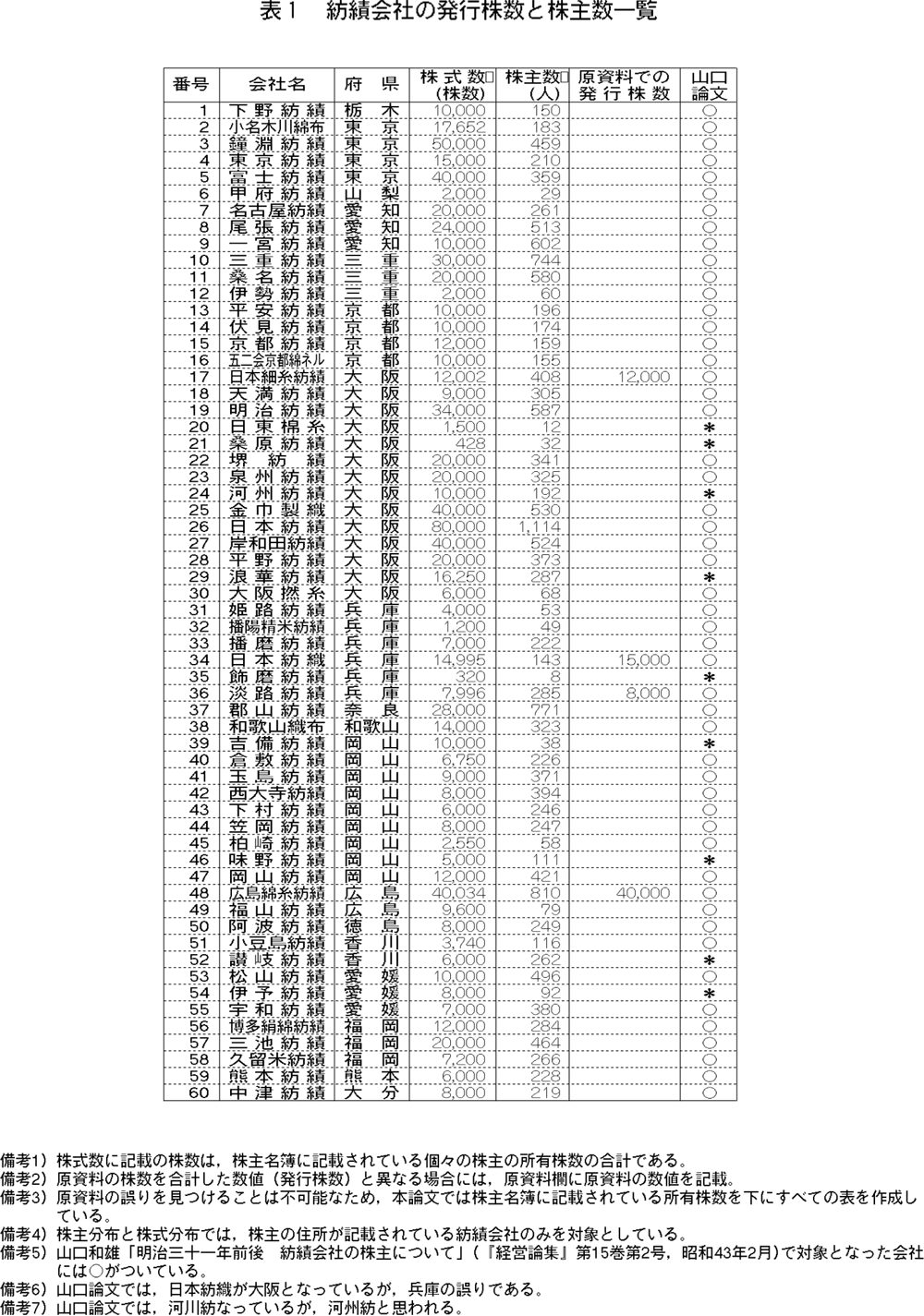
����31�N���ɂ�����Ȏ��a�щ�Њ��喼��̕���
��@�P�v�A������@�m��A�a�c�@��v
�͂��߂�
�{�e�́C����31�N���ɂ�����Ȏ��a�щ��60�Ђ̊��喼��̃f�[�^�ɂ��ƂÂ��C����E���L�������ɂ��ĕ��͂��邱�Ƃł���B��̓I�ɂ́C����犔��̏��������������炩�ɂ��悤�Ƃ�����̂ł���B���̂��Ƃɂ��C�킪���a�щ�Ђ̏����̏o���̎��Ԃւ̃A�v���[�`�����݂�B�����́C���݁C���N���ɂ�����S���̉�Ђ�ΏۂɁu�l�b�g���[�N�v�̕��͂��s�Ȃ��Ă����i��1�j�C�{�e�́C�a�щ�ЂɌ��肷����̂ł͂��邪�C���̃l�b�g���[�N���\������l���̊������L���ώ@���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B
�������ɂ�����Ȏ��a�щ�Ђ̊���ɂ��Ă̕�I�ȕ��͂Ƃ��ẮC���łɎR���a�Y����ё���i�����j�͂����ɂ�錤���������i��2�j�B�R�����́C���{�a�ы�����̖a�щ�Њ��喼��i�l�ۏ��j�����ƂɁC���㎁��̋��͂̂��ƁC��Ƃ��Ė���31�N���i����j�̕��͂��s�Ȃ����B����́C�u�������{�̑�\�I�Y�Ƃ̈�ł������a�ыƂ̎��{�\�\���ƂɌŒ莑�{�\�\���ǂ�ȐE�ƁE�K�w�E�n��̐l�X�ɂ���ċ�������Ă������𖾂炩�ɂ���v�Ƃ����ړI�̂��ƁC���N���ɑ��݂����S���̖a�щ��81�Ђ̂���65�Ђ�ΏۂɁC�e�Ђ̑劔��i�u��r�I�������̑����d�v����v�j�v1141�����Ƃ肠����ƂƂ��ɂ����̐E�ƒ������s�Ȃ������̂ł���B�܂��C���㎁�́C�R���a�Y�Ғ��́w���{�Y�Ƌ��Z�j�����@�a�ы��Z�ҁx�ɂ����āC���̖���31�N�̒����ɉ����āC��39�N����ё吳2�N�i�����������j�ɂ�����e�a�щ�Ђ̊��喼��͂����B�{�e�ƑΏێ�������������31�N���ɂ��Ă̑��㎁�̍l�@���݂�ƁC����̑劔��1141���ɂ��Ă̐E�ƒ����ɉ����āC�����̏W���E���U���ɂ��ĕ��͂��Ă���B
���̎R���E����_���Ƃ����̌����Ƃ̕��͑Ώۏ�̂������������C�ΏۂƂ����Ђ̈ٓ��ƂƂ��ɁC�������e�Ђ̑劔���ΏۂƂ����̂ɑ��C�����͊��喼���̑S�����ΏۂƂ����Ƃ����_�ɂ���B�܂��C�����́C�w����31�N�@���{�S������Ж����^�x����сw����31�N�@���{�S�����H�l���^�x�f�ڂ̐l���Ɗ��喼��f�ڂ̊���Ƃ��ƍ�����ƂƂ��ɁC����E�����̏����z���Z�o�E���͂����Ƃ����_���R���E����_���Ƃ̂������ł���B
�ȏ��3�̎�����p���C����̏�����ƋƂ̏ڍׂ𖾂炩�ɂ��C�܂��C�a�щ�Ђ̖����ɏA�C���Ă����l���ɂ��ẮC���L�����ȉ��C��E�Ȃǂ͂������B��������C����20�N��ɋ������Ă����Ȗa�ъ�Ƃ̊���w�̎��Ԃ������яオ���Ă��悤�B�Ƃ��ɁC����̏����K�w��{���ʕ��z����Ɋ����̏W���E���U�̒��x����������ƂƂ��ɁC�����̎����䗦��������C����E�����̎��Ԃ�m�蓾�悤�B
���͂ɂ�����C�ȉ���3�_���ۑ�Ƃ��Čf�������B��1�_�́C����̏Z�����L�ڂ���Ă���60�Ђ�ΏۂɊ���̒n�敪�z�Ɗ����̒n�敪�z���l�@���邱�Ƃł���B����w�̕{�����z��Ԃ�ʂ��āC�ǂ̂悤�Ȓn��̐l�X�������ɏo�������̂��𖾂炩�ɂ��邱�Ƃł���B��Ђ��ݒu���ꂽ�{���ɋ��Z����l�X������Ƃ��ĎQ�������̂��C����Ƃ����╺�ɂȂǂ̊��n��C���邢�͓����Ȃǂ̊֓��n��C�����Ĉ��m��O�d�Ȃǂ̓��C�n��̐l�X���C�L�͂ɓ������Ă����̂����C��������B
��2�_�́C����20�N��ɖu�����Ă����a�щ�Ђ̊��储��і������ǂ̒��x�̏����K�w�ɑ����Ă����̂��𖾂炩�ɂ��邱�Ƃł���B���ƂɁC�������������銔��w�Ɍ��肵�āC����w�̏��������̈�[�𖾂炩�ɂ������B�]���C�ꕔ�̕x�����m���������ĉ�Ђ�ݗ��������̂悤�ȗ������Ȃ���Ă������C����̏����𖾂炩�ɂ��邱�ƂŁC�L�͂Ȋ���w����Ղɐݗ������̂��C���邢�́C�ꕔ�̕x���������o�����Đݗ������̂����C��������B
�Ō�ɑ�3�_�́C�ǂ̂悤�Ȋ��傪�a�щ�Ђ̖����ɏA�C���Ă����̂��C�܂����̑��̉�Ђɖ����Ƃ��Ċ֗^���Ă����̂��𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��ۑ�Ƃ������B�劔�傪���̂܂܉�Ж����ɏA�C���Ă����̂��ۂ��C�Ƃ������ł���B�X�̖����̎����ɉ����āC�����S�̂łǂꂾ���̊��������L���Ă����̂��C�Ƃ����_�_���l�@�������B
�Ȃ��C����31�N�Ƃ��������́C�킪���Ȏ��a�ыƂ�23�N�̋��Q���痧������C��А��������C31�N����33�N�ɂ����ĉ�А��̃s�[�N�ɓ��B���邱��̎����ł���B�����āC���̂̂��C33�N����34�N�̋��Q���_�@�ɁC��ƏW�����i��ł������ƂɂȂ�
��1�߁@����Ɗ����̒n�敪�z
�{�_���őΏۂƂ����a�щ�БS�̂ɂ��Ă̎����̊T�v���L���Ǝ��̂悤�ɂȂ�B���吔�͑��v17,843���i���ׁj�C���������v882,217���ł���B60�Ђɂ��Ă̌X�̃f�[�^�ɂ��ẮC�\1�ɋL�����ʂ�ł���B����ɂ��C���s�����ł́C���{�a�т�8�������ő�ŁC�����a�т�5����������ɑ����B����C�����̏�������Ђł́C�����a�т�320���C�K���a�т�428��������B1�����ȏ�̉�Ђ�60�В�33�Ђ��߁C5�犔�ȏ�̉�Ђ�18�ЁC1�犔�ȏ�̉�Ђ�7�Ђł��邩��C�����a�тƌK���a�т́C�ɒ[�ɏ��Ȃ��ƌ����悤�B�����ŁC60�Ђ̕��ςƏ����C�K���a�т����������ς��L���ƁC���̂悤�ɂȂ�B�S60�Ђ̕��ςł́C1��4��700���]��ł��邪�C�����E�K���a�т������ƁC1��5��200���ł���B���悻1�Е���1��5�犔�s���Ă����ƌ����悤�B
�@
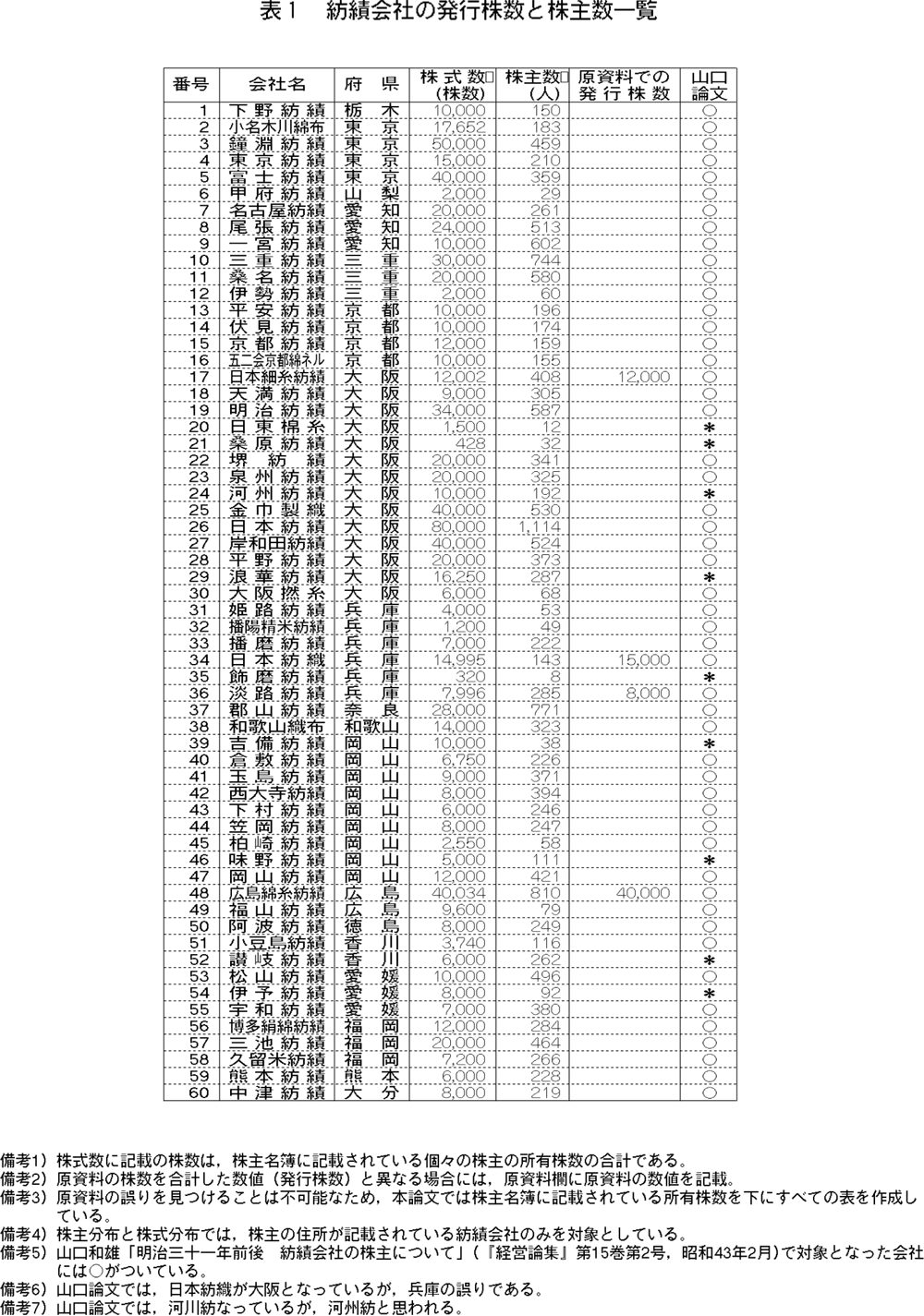
�@
���吔�ł́C���{�a�т�1114�����ő�ŁC�L���a�т�810��������ɑ����B����C����̏��Ȃ���Ђ́C�����a�т�8���C�����ǎ���12���ł���B1�疼�ȏ�̊����i�����Ђ�1�ЁC500���ȏ�̉�Ђ�9�ЁC300���ȏ�̉�Ђ�14�ЁC200���ȏオ14�ЁC100���ȏ�̉�Ђ�10�ЁC������100�������̉�Ђ�12�Ђł������B60�Е��ςł́C297���ł���B�ȏォ��C60�Ђ̕��ς��畂���яオ���Ă���p�́C���s������1��5�犔�ŁC���傪300���Ƃ������̂ł���B�Ȗa�щ�Ђ̊��吔�ɂ��ẮC�ɖ��c�q�[���̌���������B�ɖ��c�q�[�u�������ɂ����銔����Ђ̔��W�Ɗ���w�̌`���v�ɂ��C�u1�Е��ρw����x���̐��ڂ�����ƁC�w�a�сx�ł͖���26�N�܂ł͂����ނ�100�l��ŁC�W�v�͈͂����@��̉�Њ�Ƃ݂̂ƂȂ�������27�N�ȍ~��200�l�ȏ�Ȃ�i�}�}�j�C30�N�ȍ~��400�l�ȏ�ƂȂ��Ă���v�i��3�j�ƋL���Ă���B
�{�e�őΏۂƂ����a�щ�ЂƂ́C������Ώ۔͈͂��قȂ邽�߁C�ڍׂȔ�r�����͏o���Ȃ����C60�Ђ��ꂼ��̉�Ж��Ɋ��吔�Ɗ���̕{�����z���������B���̌��ʁC��O�̏�������̊�Ƃ������ƁC�ɖ��c�����f�������吔��������Ȃ��Ȃ��Ă���B
60�Ђ̕{���ʈꗗ��\2�ɋL�����B����ɂ��ƁC60�Ђ�18�{���ɂ܂������Ă���B���̒��ő��{��14�Ђ��ő�ŁC���R����9�Ђ�����ɑ����B���n��ɂ�60�В�26�Ђ��܂܂��B���R��L���̒����n��ł�11�ЁC���m��O�d�Ȃǂ̓��C�n��Ƌ�B�ł�6�ЁC�֓��Ǝl���ł͂��ꂼ��5�ЁC�b�M�n�悪1�Ђł���B
�@
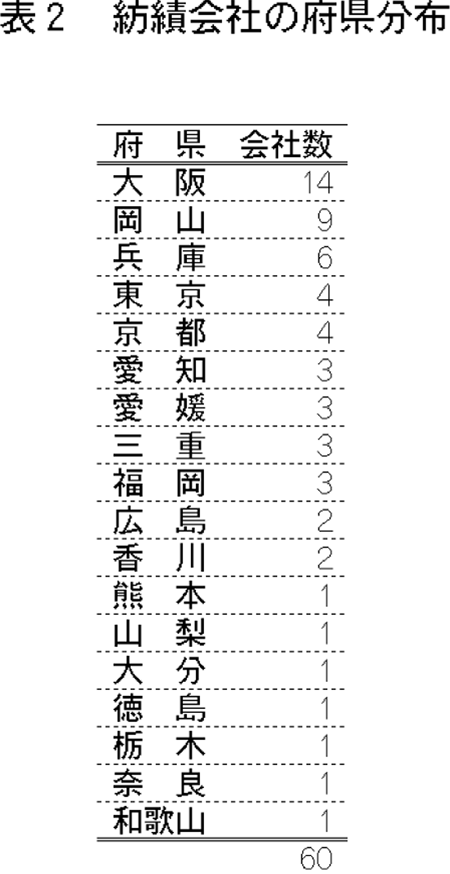
�@
�����ʼn��߂āC��1�ۑ�̈Ӌ`���L���Ă������B���傪�ǂ̂悤�Ȓn��I�ȍL����������Ă��邩�́C�������ɂ������Аݗ��̈Ӌ`�C���ɁC���ꂼ��̒n��Őݗ����ꂽ��Ƃ̓������l����ۂɏd�v�Ȗ��ł���B�ߑ��Ƃ͂ǂ̂悤�Ȓn�悩�犔����W���Ă����̂��C���邢�́C�L�����L���Ă����̂��Ƃ��������C�������ɂ�����哱�I�ȎY�Ƃ̈�ł������Ȗa�юY�Ƃ�f�ނɂ��āC��L�̉ۑ���l�@���邱�ƂƂ������B�����������傪�֗^������Ƃ̖��������͂�ʂ��āC���ꂼ��̒n��ŁC�ǂ̂悤�ȏo������������ƉƂɂ���ċߑ�Y�Ƃ��v�悳��C�����ɒn��̐l�X���o�����Đݗ����ꂽ�̂��ۂ���������ł��낤�B
�a�юY�Ƃ��ɂƂ��āC���́u�n�搫�v�������邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���啪�z�Ɗ������z�̗������\�ł��邩��C��������C����̏W���Ɗ����̏W����������C���O�̊��偁���ΓI�ɑ劔��C�����̊��偁���ΓI�ɏ�����ł��������ۂ��̊W����������B
�ȏ�̊���̕��z�̗l�q����C�n����Ƃ̊���W���E���U�̗l�q��������B���Ȃ킿�C���U���������̊��傪�o�����Đݗ����ꂽ�̂��C����Ƃ��C�����̊���ɂ��o���E�ݗ��ł������̂�����������B�ߑ�Y�Ƃ̒S���肪�C�Ƒ��E�����̏o���ɂ��C�o���҂ƌo�c�҂Ƃ����ڂȊW�������C���m�Ȍo�c�ӔC������Ă����̂��C���邢�͑����̏o���Ə�������Ƃ����W������Ƃ����Ƃł������̂���������B�R�[�|���C�g�K�o�i���X�̖��ɂ��Ȃ���ۑ�ł���B
�\3��60�Ђ̊���̕{�����z�\�ł���C���̊��啪�z�̊������\4�ł���B�S�V�b�N�̂ŕ\�L����Ă���ӏ��́C���̗��ɋL����Ă���a�щ�Ђ̖{�Џ��ݕ{���ł���B�Ȗa�щ�Ђ̊��啪�z�ɂ��ẮC�B�c�����������f���Ă���B�B�c�����ɂ��C����30�N�ɂ�������{�a�ъ�����Ђ̊���1150���̒n�敪�z�����߁C�u���a�т̂悤�ɔ�r�I�ɏ����Ȗa�щ�Ђɂ����Ă��C�߂Ɋ��呍����1150���ɒB���C���̕��z�͈͎͂O�{���ɋy��ł���v�i��4�j�Ƃ�����ŁC�u������Ќ`�Ԃɂ���ĎЉ�{��ϋɓI�ɗ��p������Ɏ������v�ƍ����]�����Ă���B
�@
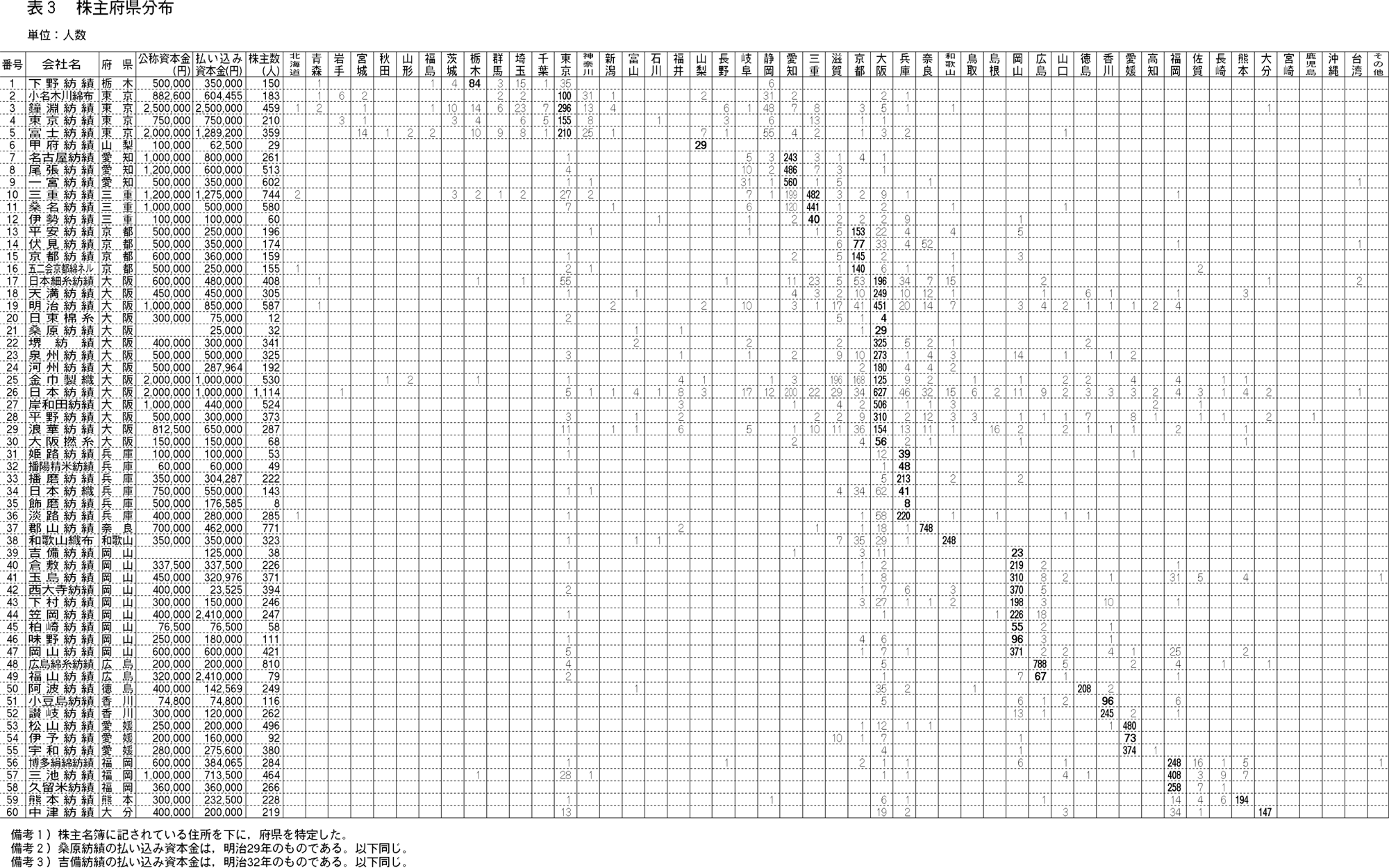
�@
�@
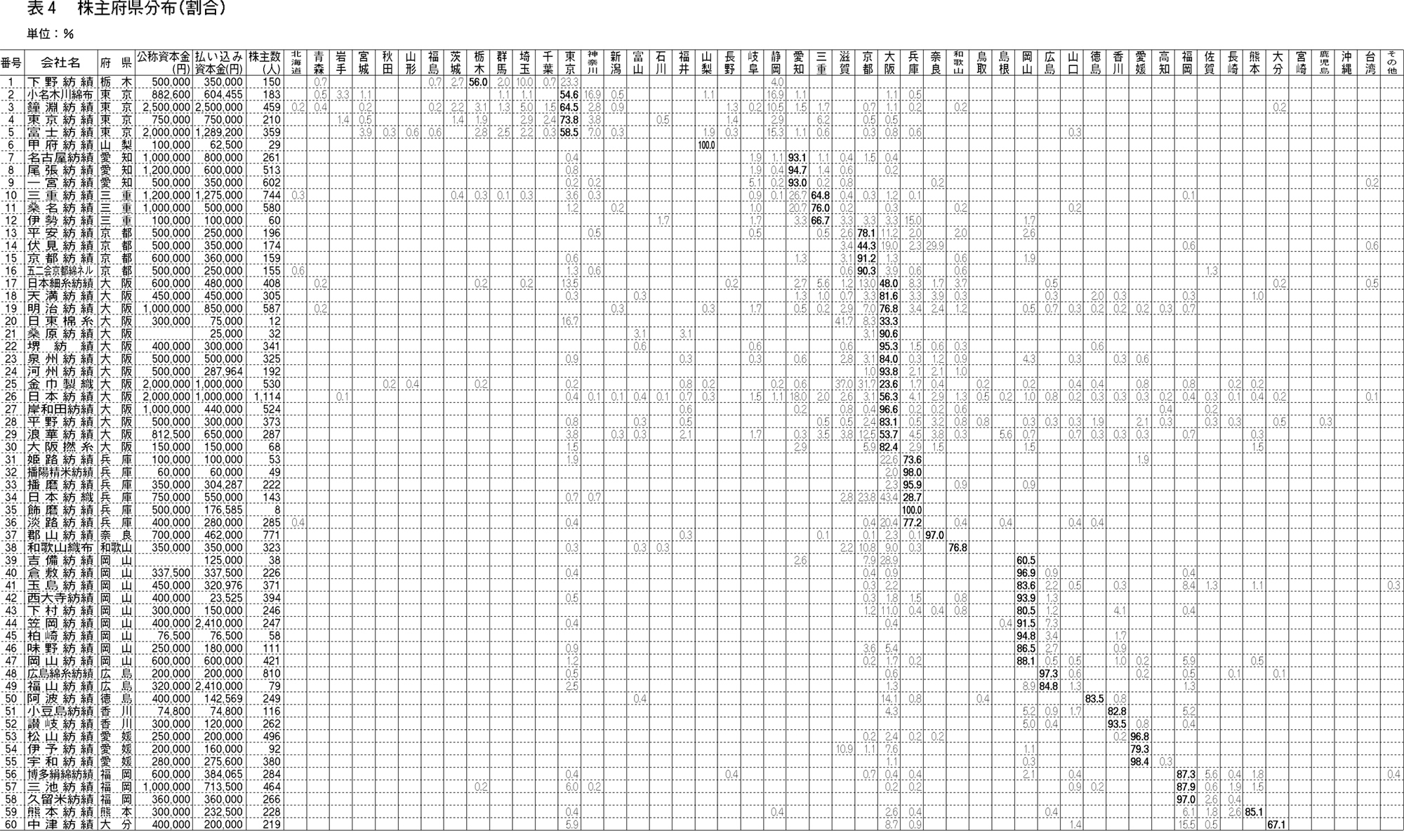
�@
�������C�B�c�����̌����͓��{�a��1�Ђ݂̂̎��Ⴉ��̕]���ł���B�����Ƒ����̖a�щ�ЂɎ����͂ǂ��ł������̂��낤���B�{�e�ł́C60�Ђ�ΏۂɊ���̕{�����z���������Ƃɂ���āC�B�c���̕]�������L�����삩�猩�����̂ƌ����悤�B�Ȃ��C�{�e�ł́C�a�щ�Ђ̐ݗ������{���ɑΉ����āC����̕{�����z���݂�̂ɕ֗��Ȃ悤�ɁC��ЂƓ���{���̊��吔�̓S�V�b�N�̂ŕ\�L�����B
�܂��{�e�ł́C�n��Ƃ����T�O�����āC����̒n��I�ȍL����������Ă���B����ɂ���āC����̒n��I�ȍL����݂̂Ȃ炸�C���̍L������̒n��I�ȓ����C���ɁC��Аݗ��{���Ɏ��_������������̒n��I�ȍL����������Ă���B
����C�{�e�ł͊���̒n�敪�z�Ɠ����Ɋ����̒n�敪�z���������B����ɂ���āC�a�щ��60�Ђ��ׂĂ̐l�I���ʁi����j�̍L����Ɠ����ɁC�����I���ʁi�����j�̍L����Ƃ�����̖ʂ̍L����������B
���āC������Ќ`�Ԃ��̗p�����̈Ӌ`�́C�Љ�I�V�x�����̏W���ł���B����C�������z�ɂ���āC�Љ�I�V�x�����̕��z��Ԃ��T�ς��邱�Ƃ��o�������C�����Љ�I�V�x�����������ɒ~�ς��Ă����l�����͕s�m���Ȃ܂܂ł���B�����ŁC���l�Ɍ��肵�āC�ނ�̐��ƂƏ��������Ƃ��̕��z��Ԃ�����K�v�����낤�B�{�e�ł́C���������̕��z�������C���Ƃ̓����ɂ��ẮC�ʍe�ɏ��邱�Ƃɂ����B
�܂�����2�̕\���疾�炩�Ȃ��Ƃ́C��O�̗�O�������C�{�Џ��ݕ{���̊��傪�ł��������߂Ă��邱�Ƃł����i��5�j�B��O�ɑ�����̂́C�����ǎ��i���j�C���А��D�i���j�C���{�a�D�i���Ɂj�ł���B���̑��C�{�Џ��ݕ{���̊��吔��50���������̂́C�����a�сi���s�j�C���{���a�сi���j��2�Ђł���B�����5�Ђɋ��ʂȂ̂́C�{�Џ��ݒn�����C���ɁC���s�Ɗ��n��ɏW�����Ă��邱�Ƃł���B
�����ǎ��ł́C���ꌧ�̊��傪�ł������C���{�̊���Ɏ����œ����̊��傪17�������B���А��D�ł́C���ꌧ�Ƌ��s�{�̊��傪���̊�����������i��6�j�B�܂����{�a�D�ł́C���{�̊��傪�ł������C����Ɏ����ŕ��Ɍ��Ƌ��s�{�̊��傪�������B�����a�тł́C���s�̊���ƕ���œޗnj��C���{�̊��傪�����C���{���a�тł́C�����{�⋞�s�{�̊��傪�������Ƃ�������B�ȏォ��C���n��̖a�щ��5�Ђ́C�{�Џ��ݒn�̕{���݂̂Ȃ炸�C���̎��Ӓn��ݏZ�̊��傪�����ꍇ�ƁC����ɓ����{�ɍݏZ�̊��傪�������Ƃ��w�E�ł��悤�B
�����5�Ђ������ƁC�{�Џ��ݕ{���ɍݏZ�̊��傪�ߔ����߂Ă����B���̒��ŁC90���ȏ�̊��傪�{�Џ��ݕ{���ɍݏZ�̖a�щ�Ђ́C23�Ђ���B95���ȏ��߂Ă����Ђ�12�Ђ���B���R�a�сi���Q�j�C�F�a�a�сi���Q�j�C�q�~�a�сi���R�j�C�L���Ȏ��a�сi�L���j�C�b�{�a�сi�R���j�C��a�сi���j�C�ݘa�c�a�сi���j�C�S�R�a�сi�ޗǁj�C�v���Ėa�сi�����j�C�d�z���Ėa�сi���Ɂj�C�d���a�сi���Ɂj�C�����a�сi���Ɂj��12�Ђł���B
���C�����C���m����������r�I�n�����݂̉�Ђ��C���╺�Ɍ��ł����Ă��C�ݘa�c���C�����Ɍ�����悤�ɁC���S�n���痣�ꂽ�s��S���x���ʼn�Аݗ����Ȃ��ꂽ�Ǝv�����Ђł���B���̒��ł��C�b�{�a�тł͎R�����̊��傪100�����߁C�����a�тł͕��Ɍ��̊��傪100�����߂Ă����B
��ɋL�����悤�ɁC����͉�Ђ̖{�Аݗ��{���ɉ����ċߗׂ̕{���ɍݏZ�̊��傪�������߂Ă����B�����ŁC�n��̊T�O�����邱�Ƃɂ���āC���������ߗׂɍݏZ�̊�����܂߂��n��W�J�����Ă������Ƃɂ��悤�B�����Œn��Ƃ����̂́C�k�C���C���k�i�X�C�H�c�C���C�R�`�C�{��C�����j�C�֓��i�Q�n�C�ȖC���C��ʁC�����C��t�C��ʁj�C�b�M�i�R���C����j�C�k���i�V���C�ΐ�C����C�x�R�j�C���C�i�É��C���m�C�O�d�C�j�C���i����C���s�C���C�a�̎R�C���Ɂj�C�����i���R�C�L���C�����C����C�R���j�C�l���i���Q�C����C�����C���m�j�C��B�i�����C����C����C�啪�C�F�{�C�{��C�������j�C����C��p�ł���B
����̒n�敪�z�͕\5�Ɍf���Ă���B�������番����悤�ɁC�w�ǂ̖a�щ�Ђ̊���͖{�Аݗ��{��������n��ݏZ�̊��傩��90���ȏォ��\������Ă���B���̒��ŁC�ɗ\�a�сi���Q�j�͎l���Ɗ��C�g���a�сi���R�j�͒����Ɗ��C�ʓ��a�сi���R�j�͒����Ƌ�B�C���{���a�сi���j�͊��C���C�C�֓��C�����ǎ��i���j�͊��Ɗ֓��C�x�m�a�сi�����j�C�����ؐ�a�сi�����j�C�����a�сi�����j�͊֓��Ɠ��C�C���Öa�сi�啪�j�͋�B�Ɗ��̊���Ő�߂��Ă���B
�@
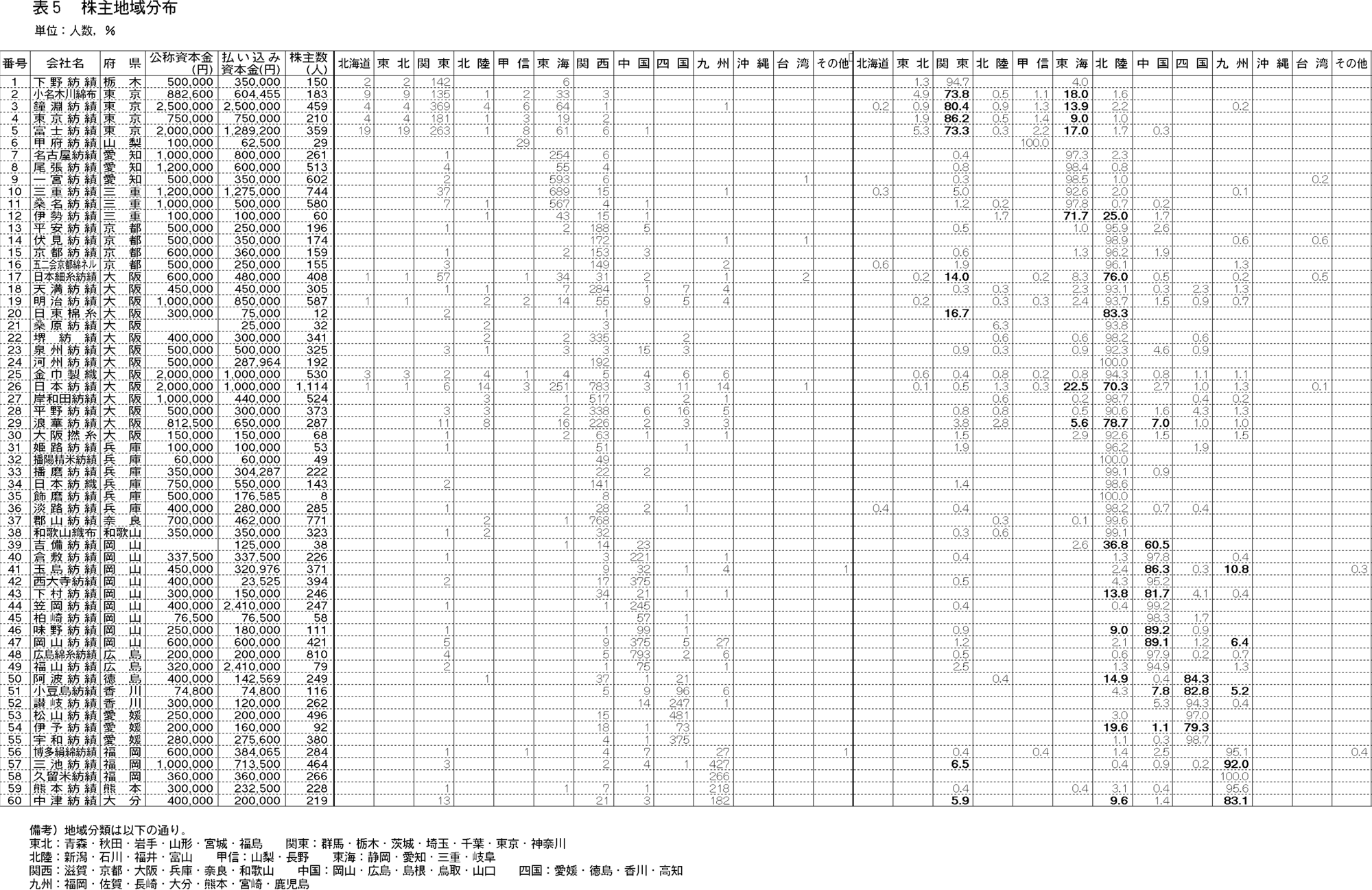
�@
�����̉�Ђ͔�r�I�����n��̊���Ɉˑ����Ă������C���ɂ͊���֓��̒n��ɍݏZ�̊���Ɉˑ����Ă��鎖�Ⴊ�U�������B�܂��x�m�a�т̂悤�ɁC�{�Џ��ݒn�̓����ɉ����āC�H�ꂪ�������É����̊��傪��r�I������߂Ă��������������B���̂悤�ɁC��̕{�����邢�͒n��̊��傪�������߂Ă��鎖������C�אڂ̕{�����邢�͗אڂ̒n��̊��傪�������߂Ă��邱�Ƃ�������B
�ȏ�̓_����C�R���╺�ɂ̈ꕔ�̒n��������C��r�I�L�͈͂̒n��ɍݏZ���Ă��銔�傪�C�a�щ�Ђ̊���ł��������Ƃ�������B�܂��C���吔�̕��ς�300���ł��������Ƃ����Ă���C�ꕔ�̕x���ɂ�鋤���o���Ƃ������i�ł͂Ȃ��C���L���n��̊��傪�֗^���Ă����ƌ����悤�B
���ɁC�����̕{������ђn�敪�z�����Ă������Ƃɂ��悤�B��̊��啪�z�Ɠ����̍ق�ۂ��č쐬�����̂��\6��7�ł���C�n�敪�z�͕\8�ɋL����Ă���B��̕\3�`5�Ɣ�r���Ă݂�ƁC���̂��Ƃ��w�E�ł��悤�B�܂��C����a�тƓ����ɂ���a�щ��4�Ђł́C����͂��ꂼ��n��ɕ��U���Ă���悤�ɂ݂�����̂́C�����ł͓����ɏW�����Ă��邱�Ƃ��e�ՂɌ��Ď���B����͂܂��ŏ��Ɏw�E���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���l�ɋ�B�̖a�щ�Ђł��C�n���̕{���ɐ�߂銔��̊����͑������̂́C�����̊����ł͂�������������B�������n�ߑ��C���ɂ̊���̒��ɑ劔�傪���邱�Ƃ�\�z�����錋�ʂł���B�l������B���l�C�n���̊���̊����͂��������̂́C�����̊����͒Ⴍ�Ȃ�B
�@
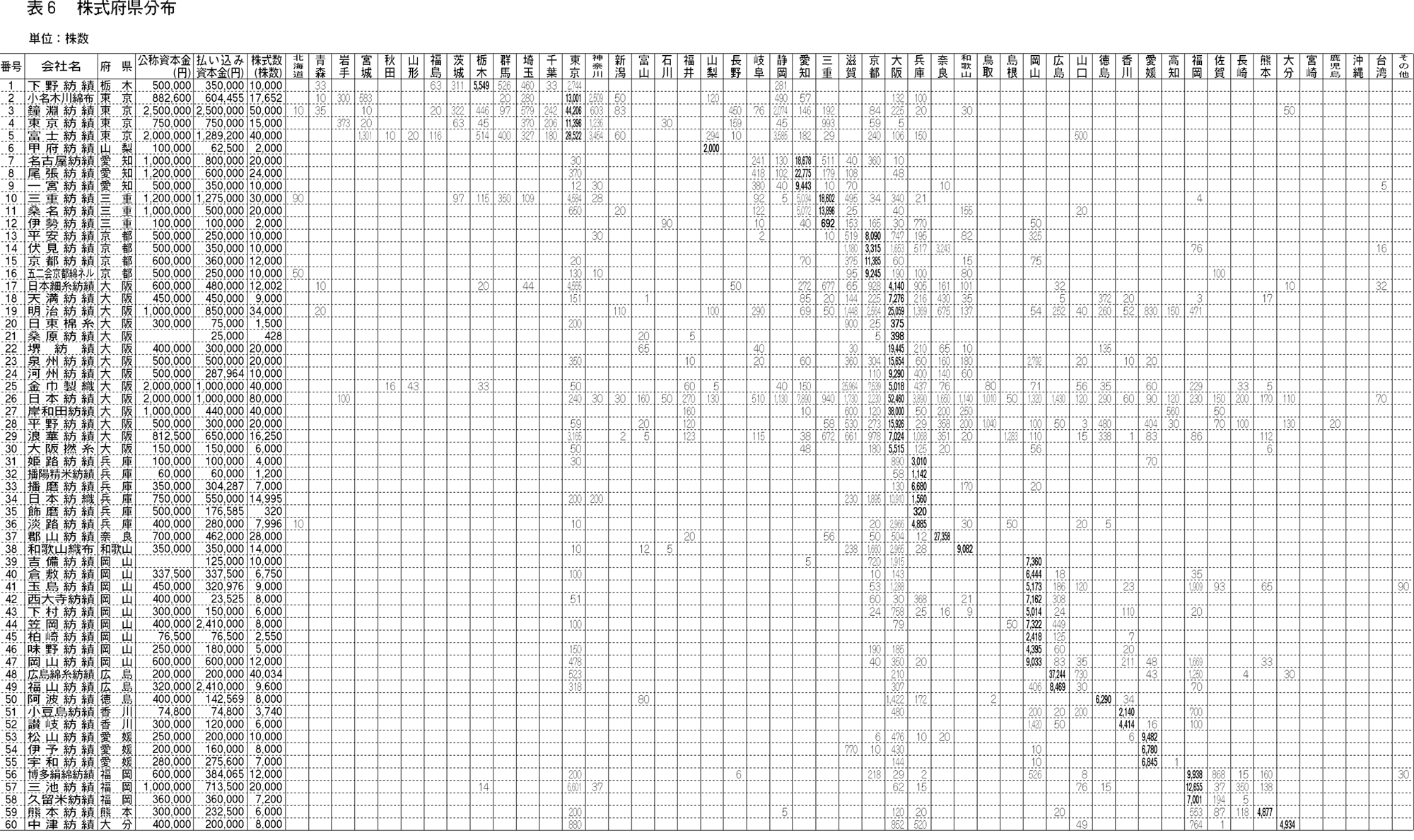
�@

�@
����Ƃ͕ʂɁC���s�C���C���ɂł͈�����l�������Ď���B�X�̖a�щ�Ђ̊Ԃł́C����̕{�����z�Ɗ����̕{�����z�Ƃ̊ԂɈႢ�������邱�Ƃ͗e�Ղł͂Ȃ����C����Ɗ����̒n�敪�z�C�����\5�ƕ\8�Ƃ��r����ƁC���̈Ⴂ�����炩�ɂȂ�B���̗�O�͂�����̂́C���n��ł͊������z�̕������啪�z�����傫�Ȋ������߂Ă���C���ΓI�ɑ����̊������L���Ă��銔�傪���邱�Ƃ�\�z������B����Ɠ����ɁC�O�d�a�сC���{���a�сC�Q�ؖa�тł́C�֓��ł̊��������������ɑ傫���Ȃ��Ă���B�����𒆐S�ɁC�劔�傪���̊֓��ɑ��݂��邱�Ƃ��\�z�����B���ہC�O�d�a�т̏ꍇ�C�n�Ǝ����̒��B�ɂ������č�����������C�a��h�ꂪ�o�b�N�A�b�v���C���̔��c�Ŏ��{��22���~�̂����u���E�~�n�n�����N�l�V�����S�V�E���~�͏a�j�ϑ��V������㑴���e�n�j���e��W�v�i��7�j�����Ƃ����B���̌��ʁC�n�����i����19�N�������j�C�����ݏZ����11�l�ɂ���Čv605�������L����Ă����i�O�d���ݏZ���吔21�l�C�v1555���C���ݏZ����2�l�C�v40���C��������2200���j�B
�@
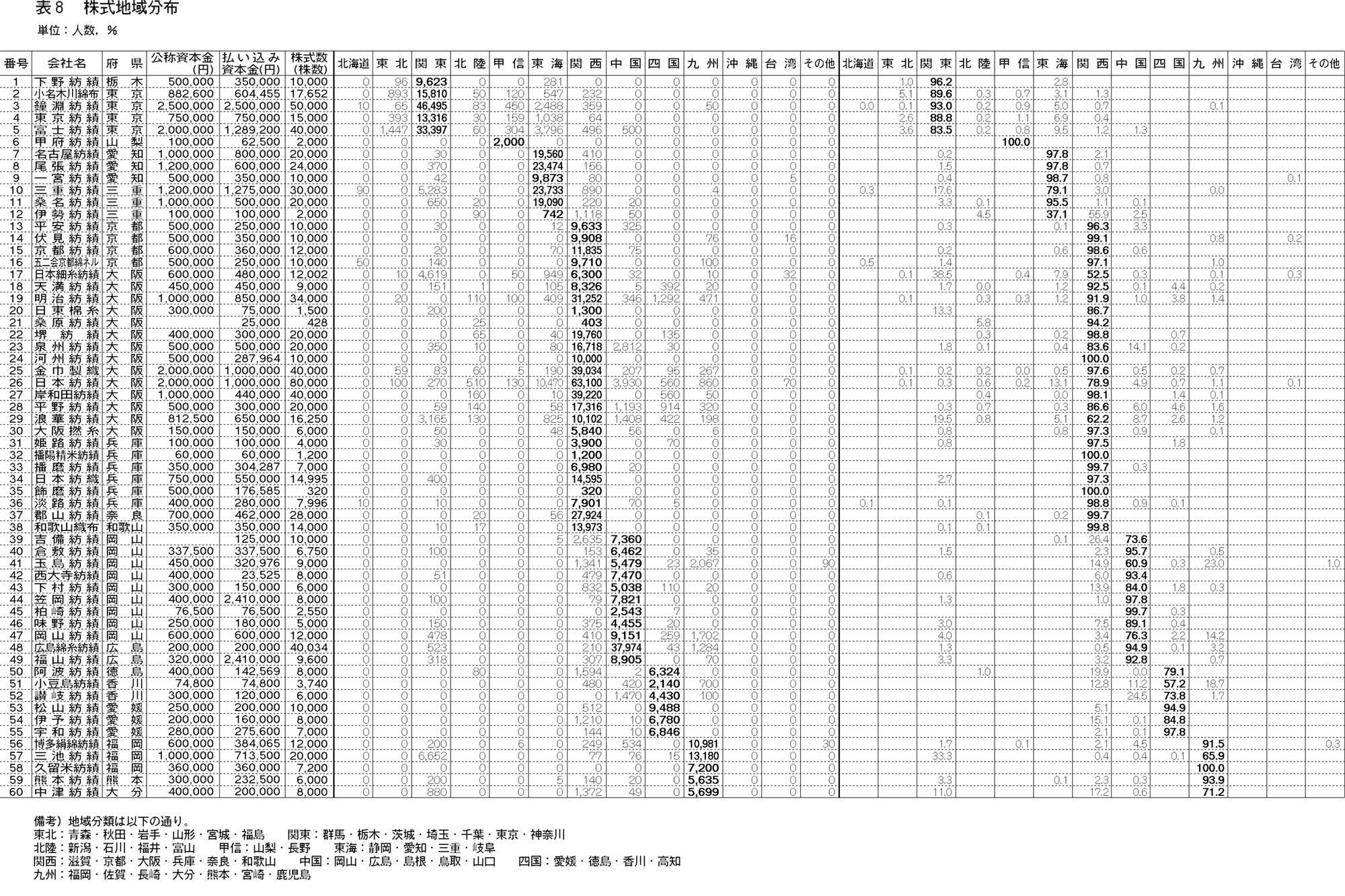
�@
�����ŁC�l�x�[�X�ő劔��̎��Ԃ����Ă������Ƃɂ������B�����ɁC�����̑劔�傪�����𒆐S�Ƃ���֓��C���C���ɂ𒆐S�Ƃ�����ݏZ�̐l�����ǂ������C�����Č������Ă��������B�{�e���ΏۂƂ���60�ЂɊ���Ƃ��Ċ֗^���Ă����l���̒��ŁC�����̉�ЂɊ֗^�����l���ƁC�����̊��������L���Ă������Ă����l�����C���ꂼ��\9�ƕ\10�ɋL���Ă���B�\9���C9�Ђ̊���ł������l���͔n�z�����Ɠ���Îs�ł���B�܂�8�Ђ̊���Ƃ��Ċ֗^���Ă����l����3���C7�Ђ�1���ł������B6�Ђ̊���ł������l����11���ŁC5�Ђ̊���ł������l����34���ł������B6�Ђł͊`���J���ɑ�\�����悤�ȑ@�ۊW�̏��l�������C5�Ђł́C�땺�q��∢���F���Y�C����J�����q��C�����`���C�c���s���q�Ȃǂ̓����C���m�C���Ȃǂ̗L�͂Ȏ��ƉƂ�����o���Ă���B
�@
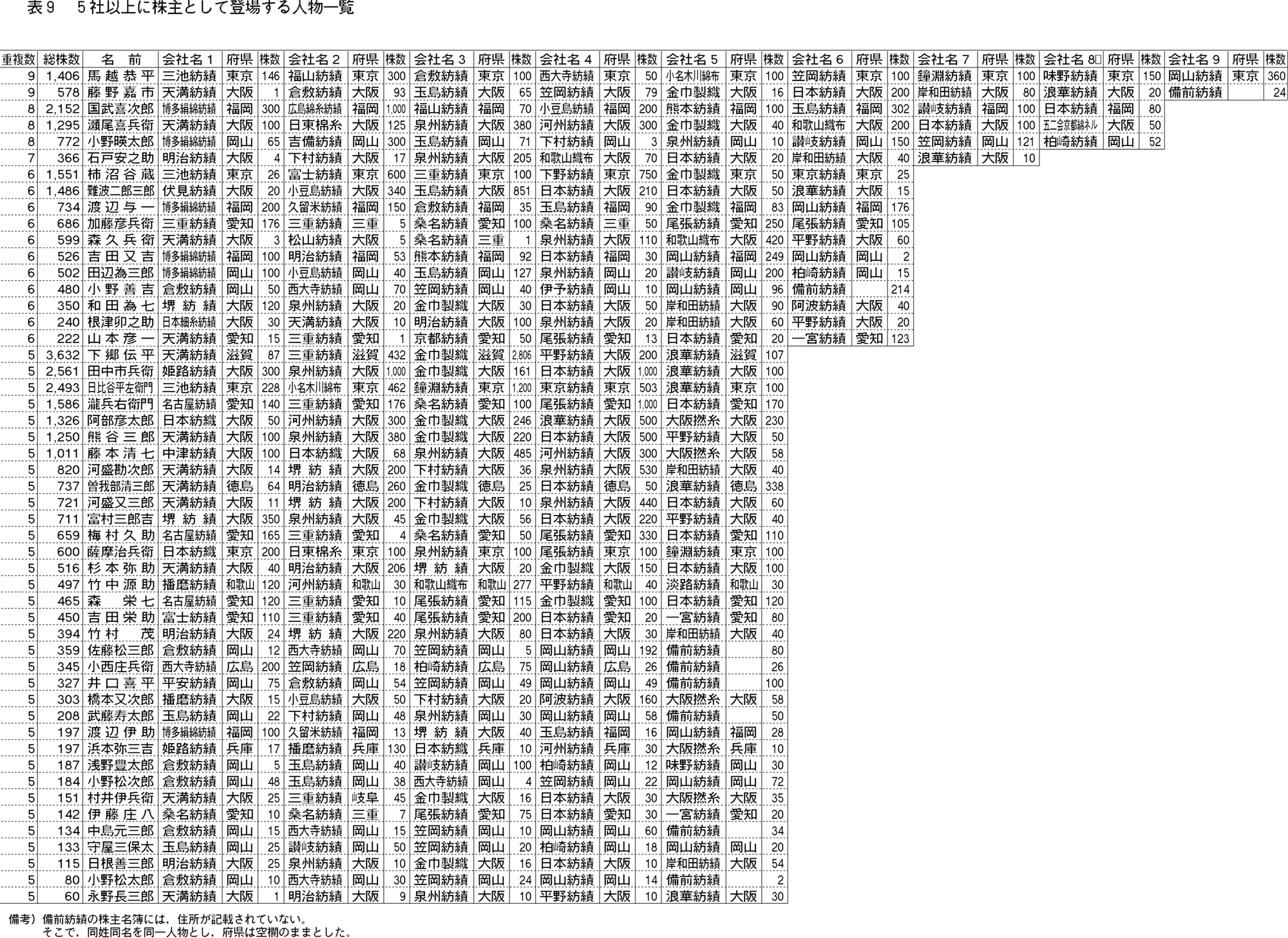
�@
�@
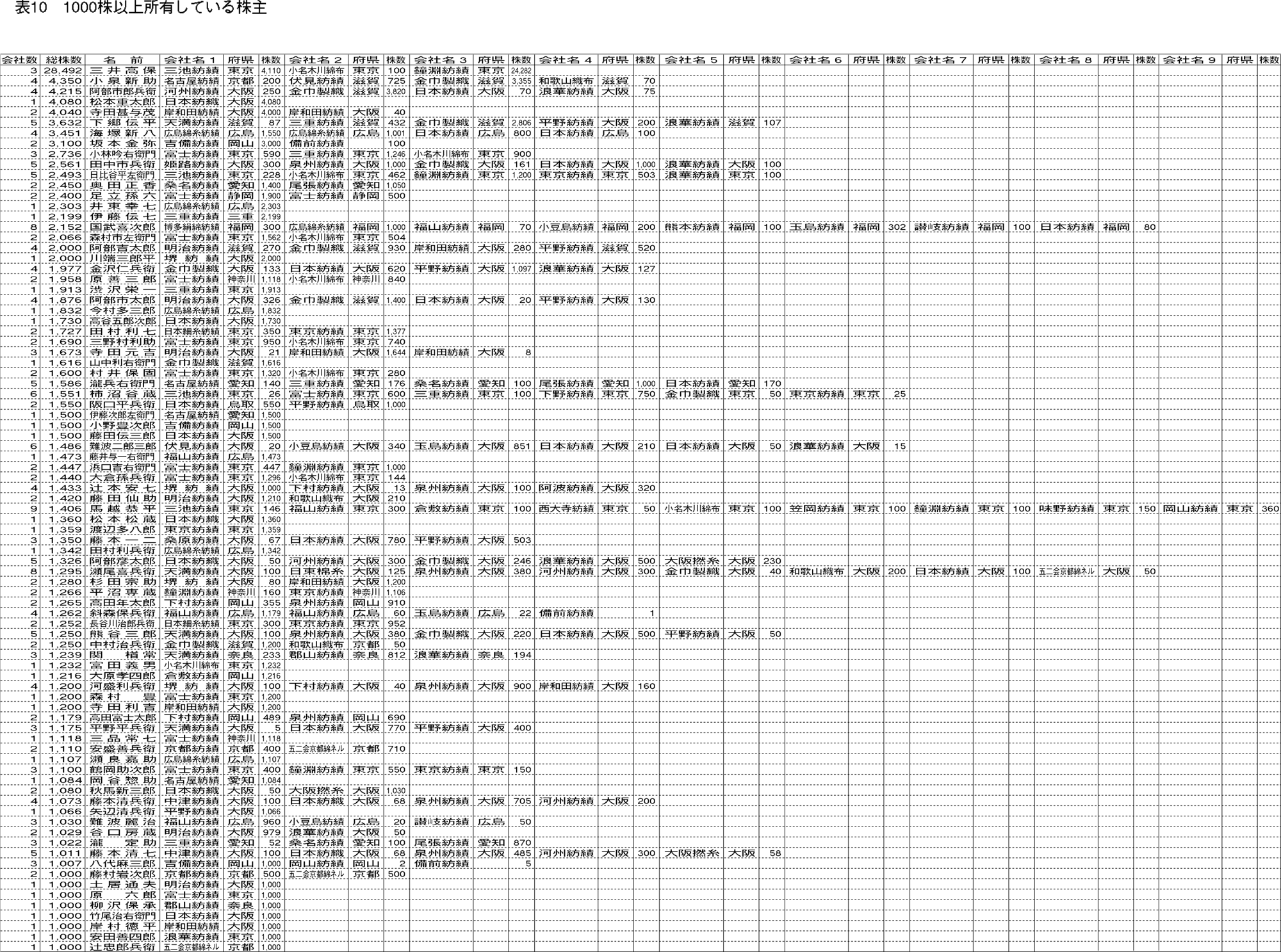
�@
����C�\10�ɋL�ڂ���Ă��鑽���̊�����ۗL���Ă��銔�������ƁC�O�䍂�ۂ��ł������̊��������L���Ă������Ƃ�������B�����a�т��n�߁C�O�r�a�сC�����ؐ�a�т�3�Ђ̊���ł���C�����a�тƎO�r�a�тł͕M������ł������B����ɑ����āC����V���C�����s�Y���q�C���{�d���Y�C���c�r�^�Ƃ��������̍��E�l����ʂ��߂Ă����B
��������C���̂��Ƃ��w�E�ł��悤�B�����̖a�щ�Ђ̊���ƂȂ��Ă���l���̕{���́C�����C���C���s�C���ɁC����ɑ�\�����悤�Ȓn��ݏZ�̊��傪���������邪�C�����ɁC���R�C�����C�L���C�����Ȃǂ̌��ɍݏZ�̊�����U�������B�ő�̊���͏����a�сC�O�r�a�сC�����ؐ�a�т̊���ł������O�䍂�ۂł���C�O�Ђ̊����v28,492�����L���āC�ł������̊��������L���Ă������Ƃł���B���l�ɁC�\10�ł���Ɍf���������C���C���s�C���ɁC����ɑ�\�����悤�Ȓn��ݏZ�̊���ƕ���ŁC�L���C�����C���R�ɍݏZ�̊�����U�������B
�ȏォ��C�a�щ�Ђ̊���́C��ʂł́C�n��ݏZ�̏��l�Ȃǂɑ�\�����l�X������ł��������C���ʂł́C�����ɗL�͂ȍ��E�l�������̉�Ђ̊���Ƃ��āC�܂��C�����̊��������L���Ă��銔��Ƃ��ēo�ꂵ�Ă����B�L�͂Ȓn��ݏZ�̐l�X�̏o���Ɠ����C���m�C���ɋ��_���������L�͍��E�l���a�щ�Ђ̊��������L���Ă����Ƃ����Ӗ��ł̓�ʐ������������Ƃ�������B
��2�߁@����̏���
���߂đ�2�ۑ�̈Ӌ`���L���ƁC���̂悤�ɂȂ�B�Ȗa�щ�Ђ̊���́C�ǂ̒��x�̏���������C�a�ъ�ƈȊO�ɂǂ̂悤�ȉ�Ђ̊����ɓ������Ă����̂��낤���C�Ƃ������ł���B�{�e�ɂ����Ėa�щ�Ђ̊���̏��������𖾂炩�ɂ���Ӌ`�́C���̒ʂ�ł���B�������p�ɂ��C�u�i�����O���\��j�e�n���ɓ_�݂��Ă����ݗ��Y�Ɓw���{�Ɓx�����̉ݕ��I�~�ς̐����������������ƁC���̂͂������Y�Ƒn�݂̂��߂̎��������҂Ƃ��Ă̖������傫���������Ƃ����͊m�F����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�i��8�j�Ƃ�����ŁC�X�Ɂu�n���ɂ�����n��C�s�s�ɂ����鏤�l�̑�ʂȎ����I�~�ς����݂����v�i��9�j�Ƙ_���Ă���B���̓_�ɑΉ����Ė{�e�ł́C���l�Ɍ��肵�āC�ނ�̏�����������肷�钆�ŁC�����~�ς̈�[�𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ̎��݂ł���B����͂܂��C�������́u�����Ƒw�v�̕��͂Ɏ����邱�ƂɂȂ낤�B�劔��C�����̉�ЂɊ������������Ă���l���̉ƋƂ⏊���C���邢�͕{���̓������w�E�ł���B���l�Ɍ��肵�Č���ƁC����̏����͂ǂ̂悤�Ȑ����ɂ������̂�����������B��������C�a�ъ�Ƃ̐ݗ��Ɋ֗^��������̎��Ԃɔ��邱�Ƃ��o���悤�B
�����������͎��p�̈Ӌ`���C�]���̌����ɑ����ĉ��߂Ă��邷���ƂƂ������B
�u�]���C�킪���̊�����А��x�́C���{���{��`�̎��{�~�ς̒�ʐ����J�o�[������̂Ƃ��đ������瓱������Ă������̂́C�L�͂ȎЉ�I�����������Ƃ���������Ж{���̋��Z�I�@�\�͊ł������B�v�i��10�j�ނ���C�l�劔��ɂ�鋤���o���Ƃ����`�Ԃɂ�莑�{���B���s�Ȃ�ꂽ�Ƃ����Ă���B
����ɑ��Ă����́C���̂悤�ȋ^����N�������B���Ȃ킿�C���́u�L�͂ȎЉ�I������v�Ƃ͂��������ǂ̒��x�������̂ł��낤���B����܂ŁC�������ɂ��āC��I�ȃf�[�^�̕��͂�ʂ��āC���̒��x���m�肵�����،����͂Ȃ��B�����́C�Ȏ��a�ыƂƂ����H�Ɖ��̃��[�f�B���O�Z�N�^�[�ɂ��āC����31�N���̊��喼��̕��͂ɂ���Ă��̂��Ƃ����C�m�肵�����B�������C�����ɁC�l�劔��ւ̏W���x���ǂ̒��x�ł������̂����m�F���邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
���喼��ɋL�ڂ���Ă��銔��S�����C����31�N�ł́w����31�N�@���{�S�����H�l���^�x�ɋL�ڂ���Ă���l��������肵�C�����ł��L�ڂ���Ă���l�������𒊏o���āC����̏����������Z�o�����B���喼��ɋL�ڂ���Ă���l���̎����ƏZ���̕{���Ɓw����31�N�@���{�S�����H�l���^�x�ɋL�ڂ���Ă���l���̎����ƏZ���̕{������v�����ꍇ�C����l���Ɣ��f���āC�����ł����߁C�������珊�����Z�o�����i��11�j�B���̌��ʂ͕\11�̒ʂ�ł���B
�@
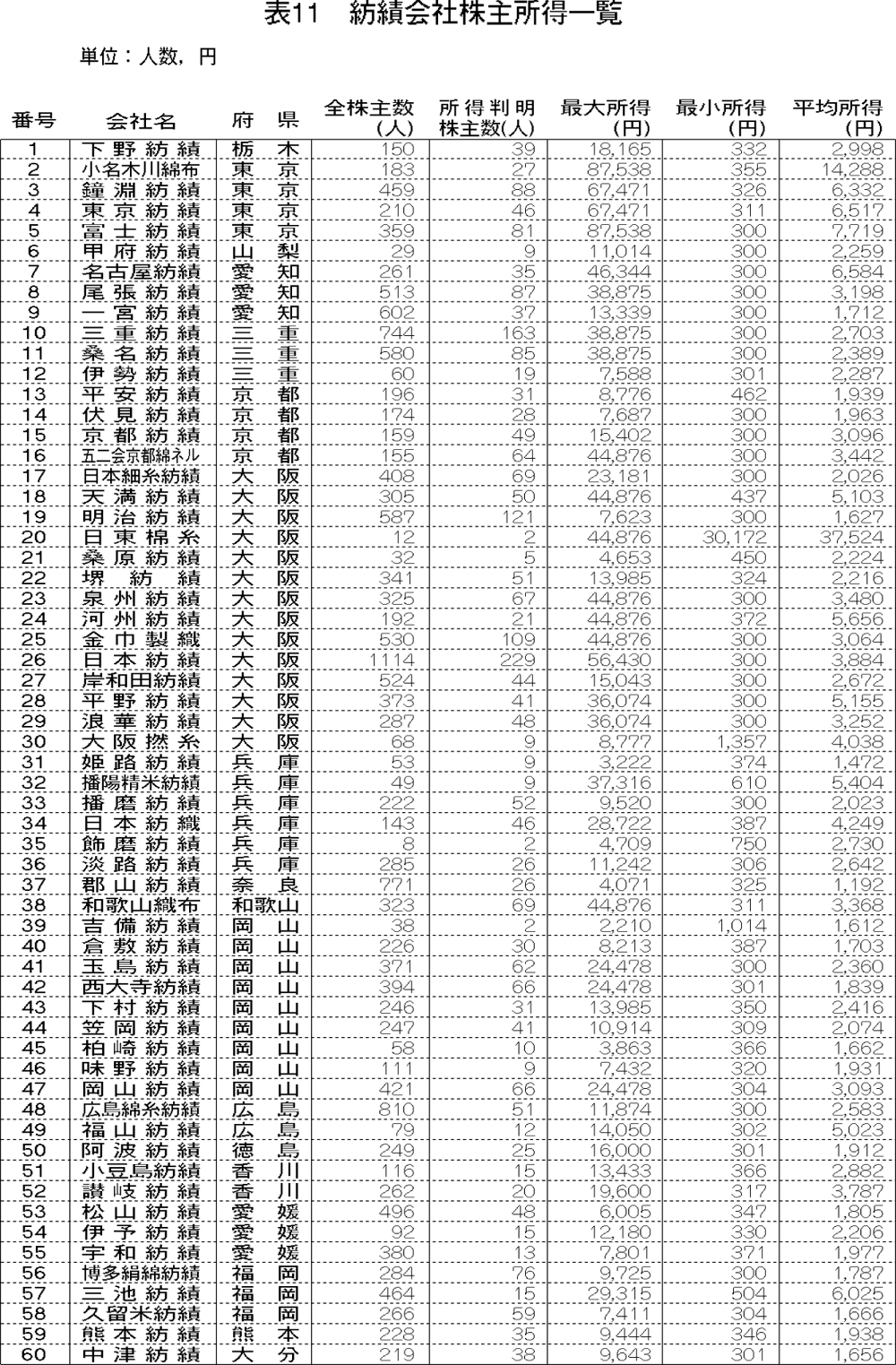
�@
�������������銔�傪10���ɖ����Ȃ���Ёi�P�H�a�сi���j�C�d�z���Ėa�сi���j�C�b�{�a�сi���j�C���Q���i���j�C�i���j�K���a�сC�����ǎ��i���j�C�����a�сi���j�C�g���a�сi���j�j�������ƁC���悻�ȉ��̎������w�E�ł���B
�����̍Œᐅ����300�~�ߖT�ł���B���Ȃ킿�C�����C�����ł��ۂ�����Œ�̏���������300�~�ł���������C�ېōŒᏊ����300�~�N���X�ł��銔�傪���Ȃ��Ȃ��K�͂ő��݂��Ă������Ƃ�������B
�܂��C���ꂼ��̖a�щ�Ђ̒��ō������҂Ɋ܂܂��l���ł́C���P�O�Y��8��7538�~��M���ɁC�����g����3863�~�܂ŕ��L����������������ꂽ�B�܂����Ϗ���������ƁC��ʂ�2�̎���������Ƒ唼��6000�~����1000�~�K�͂ł���B1000�~����2000�~�̏����w�����|�I�����ł��邱�Ƃ�������B
��������C���̓_���w�E�ł��悤�B���ɁC�Œ�̏����ł́C�ېōŒ�̏����ł���300�~�w������ꂽ���Ƃł���B����͈ꕔ�̕x���w�ɂ�鋤���o���Ƃ������i�ł͂Ȃ��C���l�Ƃ�������͂�����̂́C300�~��̐l���܂ł�������Ƃ��Ċ֗^���Ă����̂ł���B���ς̏����́C1000�~����2000�~��̏����w���唼�ł��������Ƃ������ċ������ׂ��ł��낤�B���Ϗ����̎Z�o�ɓ������ẮC�P�����ςɂ���ċ��߂����߂ɁC���ۂ̐������������Ȃ邱�Ƃɒ��ӂ���C�����ɂ́C�����̏����w�ȉ��̊��傪������߂Ă����ƌ����悤�B
�����ŁC60�Ђ��ׂĂɂ킽���āC�w����31�N�@���{�S�����H�l���^�x�ɋL�ڂ���Ă���l������肵�C�������珊�����Z�o������ŁC�����K�w�ʂɈꗗ�\���쐬�����B���ꂪ�\12�ł���B�������番����悤�ɁC60�БS�̂ł́C500�~����2000�~�����̏����w�����������݂��Ă������Ƃ�������B���{�S�����H�l���^�ɋL�ڂ���Ă���l���Ɍ��肳���Ƃ͂����C�a�щ�Ђ̊���w�̏�������������ł���B
�\12�ɋL����Ă��鏊����5���~�ȏ�̐l���C����8�l�ɉ����āC������3���~����5���~�����w�ɑ�����l���C����29�l�C�v����37�l�̐l�����C����Ƃ��Ċ֗^���Ă����a�щ�Ж��Ə��L�����C����сw����31�N�@���{�S�����H�l���^�x�ɋL�ڂ���Ă��鏊���ł���Z�o���������z���f�����B���ꂪ�\13�ł���B�Ȃ��C�\13�̉ƋƂ̗��ɋL�ڂ���Ă���E�Ƃ̖��̂́C�w����31�N�@���{�S�����H�l���^�x�ɋL�ڂ���Ă���E�Ƃ��f�ڂ��Ă���B
�@
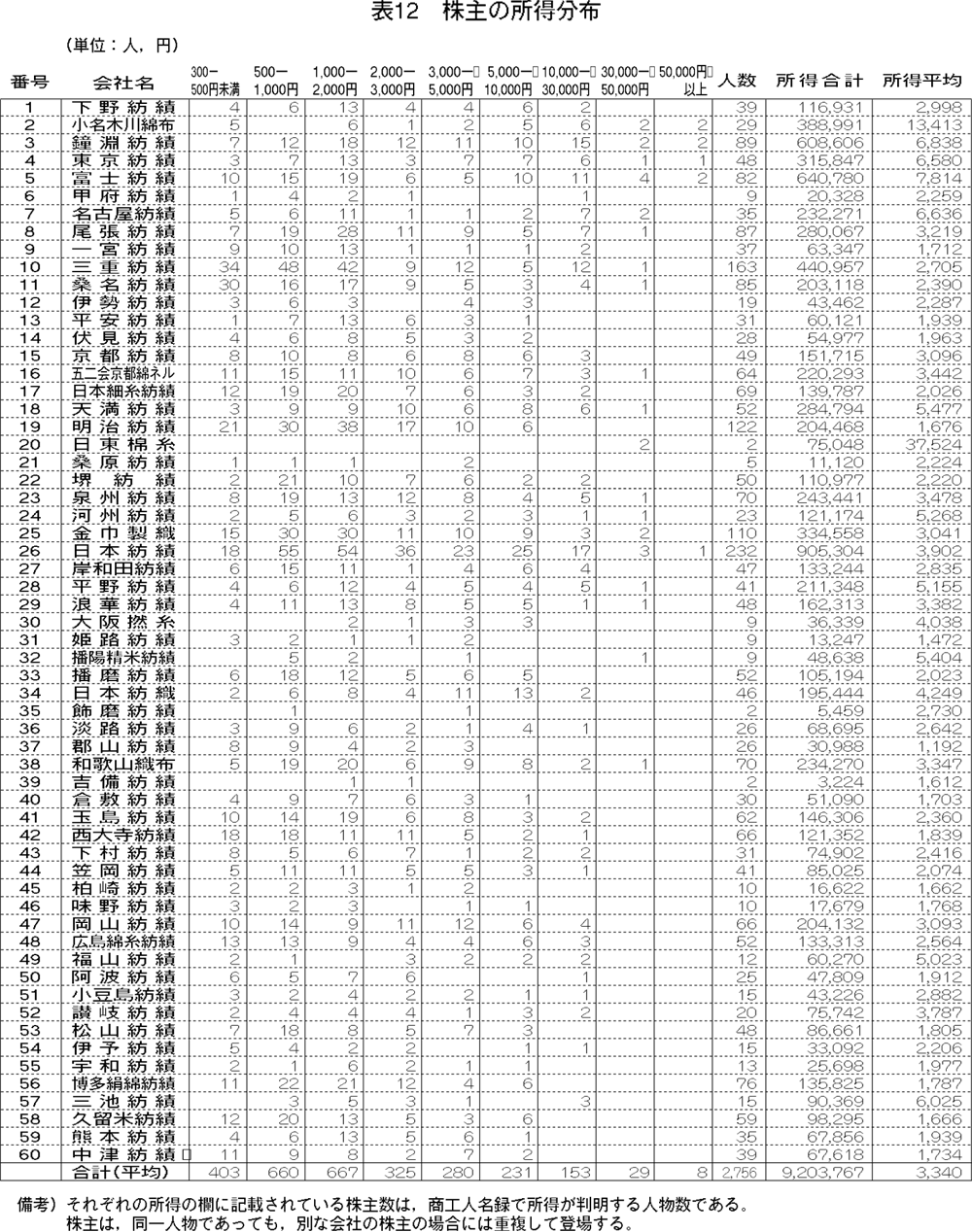
�@
�@
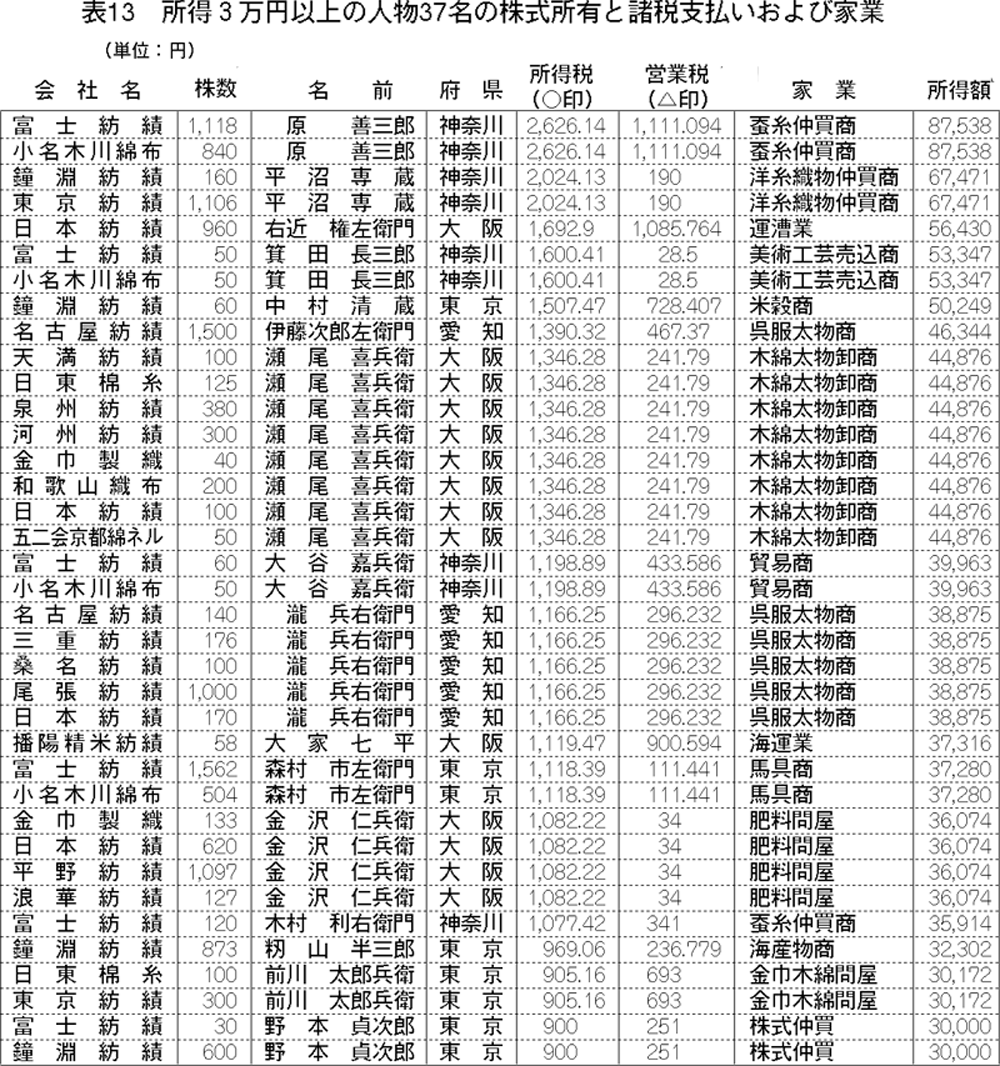
�@
��3�߁@�a�щ�Ж����̊����ۗL
��3�ۑ�̈Ӌ`�́C����Ɩ����̊W�ł���B�劔�傪���̂܂ܖa�щ�Ђ̖����ɏA�C���Ă����̂��C���邢�́C�����ɏA�C���Ă�������͏��L�����Ƃ͖��ڂȊW�������Ă��Ȃ������̂��C�Ƃ������ɓ����邱�Ƃł���B�����̑劔�傪�C�������ĉ�Ќo�c�Ɍg������̂��C���邢�́C�劔��ƕ���Ōo�c�I�ˊo���������l������Ќo�c�Ɏ�荞��ł����̂��낤���B�O�҂ł���C��Ђ̔��N�l���劔�偁��Ж����Ƃ��������I�ȊW�������ł��悤�B��҂ł���C��Ђ̔��N�l���劔�偨�劔��Ɓu���o�c�ҁv�̋����ɂ��o�c�Ƃ����W�������яオ���ė���B���ɁC���L�����͏��Ȃ����̂́C�ނ�́u���o�c�ҁv�Ƃ��Ă̍ˊo��L���Ă���l��������Ɂu�o�p�v�������̂��ƌ����悤�B�������Ƃ���C�吳���ɓ����čL��������悤�ɂȂ����w���҂ɂ��u���o�c�ҁv�̑䓪�Ƃ������ۂ̐��I�Ȍ`�Ԃ�L���Ă���ƕ]���ł��悤�B
�܂��C�a�ъ�Ƃ̖��������̖a�ъ�Ƃ̖��������C���Ă����̂��ǂ����͂��邱�ƂŁC����̎Y�Ƃɂ�����u�����o���E���C�����v�Ƃ������������o�ł��悤�B�����̖a�щ�ЂɁC�����Ƃ��Ċ֗^���邱�Ƃ́C�o�c��C���炩�̗D�ʐ����������̂��낤���B�H��o�c��Z�p�I�Ȗ��C����ɂ͘J���Ǘ��Ȃǂ̖ʂŁC��̊�Ƃł̐����������̉�Ђɓ`�d�������Ƃ͗e�Ղɑz���ł��悤�B����C�u���I�v�u���C�����v�Ƃł������ׂ����i��ттĂ����ƌ����悤�B
����C�Ȗa�щ�ЈȊO�̉�Ђɖ����Ƃ��Ċ֗^���Ă�������́C�����ʂ�u�����o���E���C�����v�Ƃ��Ď��Ƌ@��̂���l�X�ȉ�ЂɊ����𓊎����C�����Ƃ��Čo�c�Ɋ֗^�����l���ł���B����܂ŁC�u�����o���E���C�����v�Ə̂��ꂽ�l���͂��̃^�C�v��z�肵���Ǝv����B�ނ炪�C�ʓI�Ɍ��āC�ǂ̒��x�����̂��C�܂��C�ǂ̂悤�ȉ�Ђɖ����Ƃ��Ċ֗^���Ă����̂������邱�Ƃɂ���āC���ɁC��s�Ɋ֗^���Ă������ۂ������邱�Ƃɂ���āC�u�@��s�v�_�Ƃ̐ړ_�������������Ƃ��o���悤�B���Ȃ킿�C��s�Ƃ���ȊO�̉�Ђɖ����Ƃ��Ċ֗^���C���̌��ʁC��s����̗L���ȐM�p���o�b�N�ɑ����̊�Ɛݗ��Ɋւ�������ۂ��Ƃ������ɑ��āC�u�`�ԓI�v�ɓ����邱�Ƃ��\�ɂȂ�B���̓_�́C�ʍe��p�ӂ��Ă���B
�\14�ɂ́C�ő劔�厁���Ə��L�����Ɗ������n�߁C��5�ʂ̊���܂ł̎�����5�劔��̏��L�����Ɗ����C�X�ɂ�10�劔��̏��L�����Ɗ����C������20�劔��̏��L�����Ɗ������L����Ă���B���s�����Ɗ��吔���ł��������{�a�тł́C�M��������n�߁C5�劔��C10�劔�傳��ɂ�20�劔��̏��L�����̊����́C�ł��Ⴂ�B�����ł��̍ł��Ⴂ���{�a�т̗l�q�����Ă����ƁC5�劔���7.7���C10�劔���12.6���C20�劔���20.3���ł������B�܂��C���吔�������a�щ�ЂقǁC��ʂ̊��傪���L���銔���̊��������Ȃ��͓̂��R�̂��Ƃł���B���̂悤�ȈႢ��������̂́C���C�����60�Ђ̒P�����ς�����āC�����ɔ��肽���B�M������́C���悻10�����L���Ă����̂ł���B����ɑ����āC5�劔��ł́C28���C10�劔��ł́C40���C20�劔��ł�54���C�Ƃ����̂����ς��猩�������ł���B
�@
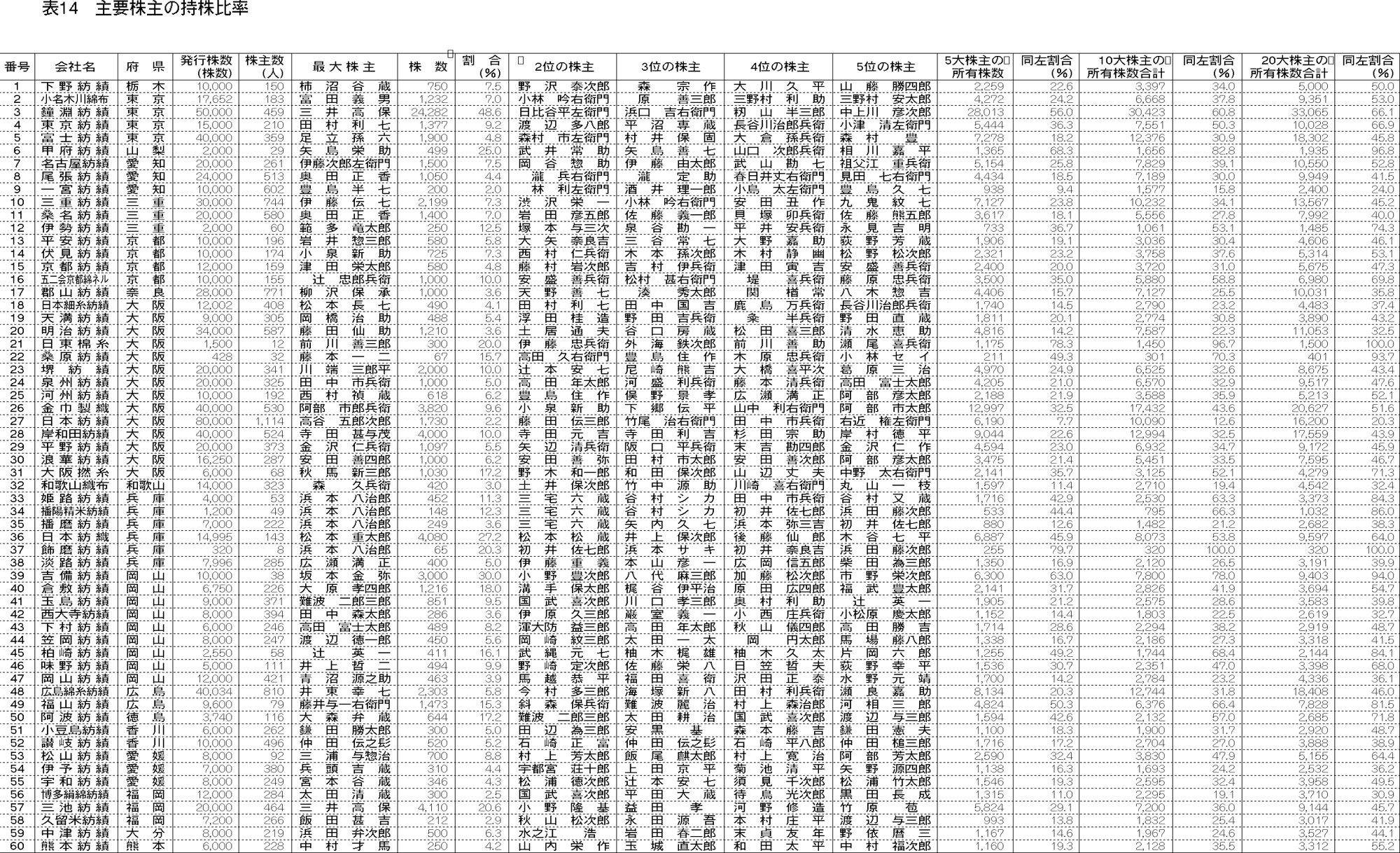
�@
���āC�a�щ�Ђ̖����͂ǂꂾ���̊��������L���Ă����̂��낤���B�܂��C����S�̂̒��łǂ̂悤�Ȉʒu�ɂ����̂ł��낤���B�劔��ł������̂��낤���C����Ƃ��C�劔��ȊO��������Ƃ��ēo�p����Ă����̂ł��낤���B����������̂��\15�ł���B�ɖ��c�q�[���́C���āC�w���{�鍑���v�N�Ӂx�𒆐S�I�Ȏ����Ƃ��āC�������ɂ����銔����Ђ̔��W�Ɗ���w�ɂ��čl�@���Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B���Ȃ킿�C�ʎ��{�Ƃɂ����鎑�{�~�ς��R���������ߑ㉻�����̓��{�ɂ����ẮC�u�ٌn���{�ƊԂ̋����I�ɂ��V��Ђ̐ݗ��v�i��12�j����O�I�ł͂Ȃ��C���̍ہC�������������ٌ̈n���{�Ƃ̋ϓ��o���ŏ�ʊ���w���`������C�u���̏�ʊ���Q�̈������n�������̊�����4�`6�����߂āC�c�]����ʑ�O������傳���Ƃ����`�Ԃ��������̊�����Ђ̈�ʓI�ȌX���v�i��13�j�̂悤�ł������B�\16�ɂ́C���̗��ɋL����Ă���a�щ�Ђ̖������C����̒��Ő�߂�ʒu���L�ڂ������̂ł���B�������ɋL����Ă���������C���喼��̒��ŁC��ʂ���ǂ̈ʒu�ɂ���̂����������̂ł���B�Ⴆ�C�����̊��叇�ʇ@�Ƃ����̂́C�����̒��ŏ��L��������1�ʂ̊���������C���̖���������̒��ŏ�ʂ��牽�Ԗڂɂ���̂����L�������̂ł���B��̓I�ɐ������悤�B����a�т̗��ł݂�ƁC��������6���ŁC�u�����̊��叇�ʇD�v�̗��ɂ���C12�Ƃ����̂́C��ʂ̊��傩�琔����12�Ԗڂ̊���ł���C�Ƃ����Ӗ��ł���B�܂��C����12���C�u�����̊��叇�ʇC�v�Ɠ����ł���Ƃ������Ƃ́C��4�ʂƑ�5�ʂ̖����͓����̊��������L���C��ʂ���12�Ԗڂł���C�Ƃ������Ƃ������Ă���B�ȉ��C���l�ł���B
�@

�@
�@
�������疾�炩�Ȃ悤�ɁC�M������͂��Ƃ��C��10�ʂɂ܂œ����Ă��銔�傪�����ɏA�C���Ă��邱�Ƃ�������B���̔��ʁC10�ʈȉ��C�܂�60����70�ʂ̊��傪�����ɏA�C���Ă��鎖�Ⴊ�U�������B�ɒ[�ȏꍇ�ɂ́C171�ʂ̊��傪�����ɏA�C���Ă��鎖�Ⴓ��������B�O�҂ł́C�O�d�a�сC���{�a�сC�L���Ȏ��a�сC�������Ȗa�т��w�ł���B�܂���҂ł͓��{���a�т�����ł���B�����̖a�щ�Ђ́C���s������������S�̂̕��ς��猩��Ƒ傫�ȉ�Ђł��邱�Ƃ�������B���̂悤�Ȋ����̕��U���i�a�щ�Ђł́C��ʈꌅ�̊��傩��ł͂Ȃ��C50�ʂ���70�ʂƂ������ΓI�Ɍ��āC�K�������劔��Ƃ͌����Ȃ����傪�����ƂȂ��Ă����B���������W�̏ڍׂ́C����C�l�b�g���[�N�̕��͂�ʂ��Đ[�߂�K�v�����낤�B
�ȏオ�{�_���̎�v�Ș_�_�ł���B�������Ȃ���C��ɋL�����R���a�Y�C����i�����j�͂̌����Ŏ��グ���Ȃ������a�щ�Ђ̎������C�Ō�Ɍf���邱�Ƃɂ����B�\�̑̍ق́C����B�̌`���ɑ����č쐬�������̂ł���B�\16-1����\16-9������ł��邪�C�����ł��w����31�N�@���{�S�����H�l���^�x���瓯��l������肵�C�����ŁC�c�ƐŁC�ƋƂ����ď����ł���Z�o�����������L�����B
�{�e�Ɍf�����\�ɂ́C�w����31�N�@���{�S�����H�l���^�x�ɋL�ڂ���Ă��鏊���łƉc�Ɛł̑��ɁC�E�Ƃ��L���Ă���B���̈Ӗ��́C�a�щ�Ђ̊���̐E�Ɓi�ƋƁj�ɂ��āC�������p�����ȉ��ŋL���Ă��鏈�ɑΉ����Ă���B�u�����̏ꍇ�C�����i�s�s�̏��l�C�n���̒n��\��j���V��Ƃ̎d�������ɐ�O�����̂ł͂Ȃ������_�ł���B�����͓`���I�Ȑ��Ƃ�����`�̏���₿�����Ă��܂�Ȃ��܂܂ɁC����邢�͂���ȏ�ɑ����̎d��������C���̑����I�Ȏ��������Ă��Ď��Ȃ̗��v����낤�Ƃ����v�i��14�j�Ƃ����_�܂��āC�{�e�ł͊����ĉƋƁi���Ɓj���L�����B
�@
�@
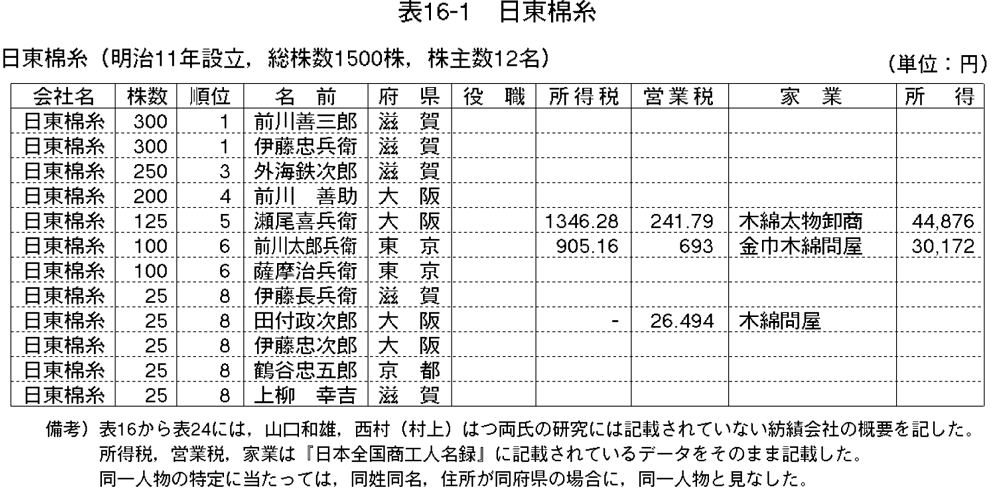
�@
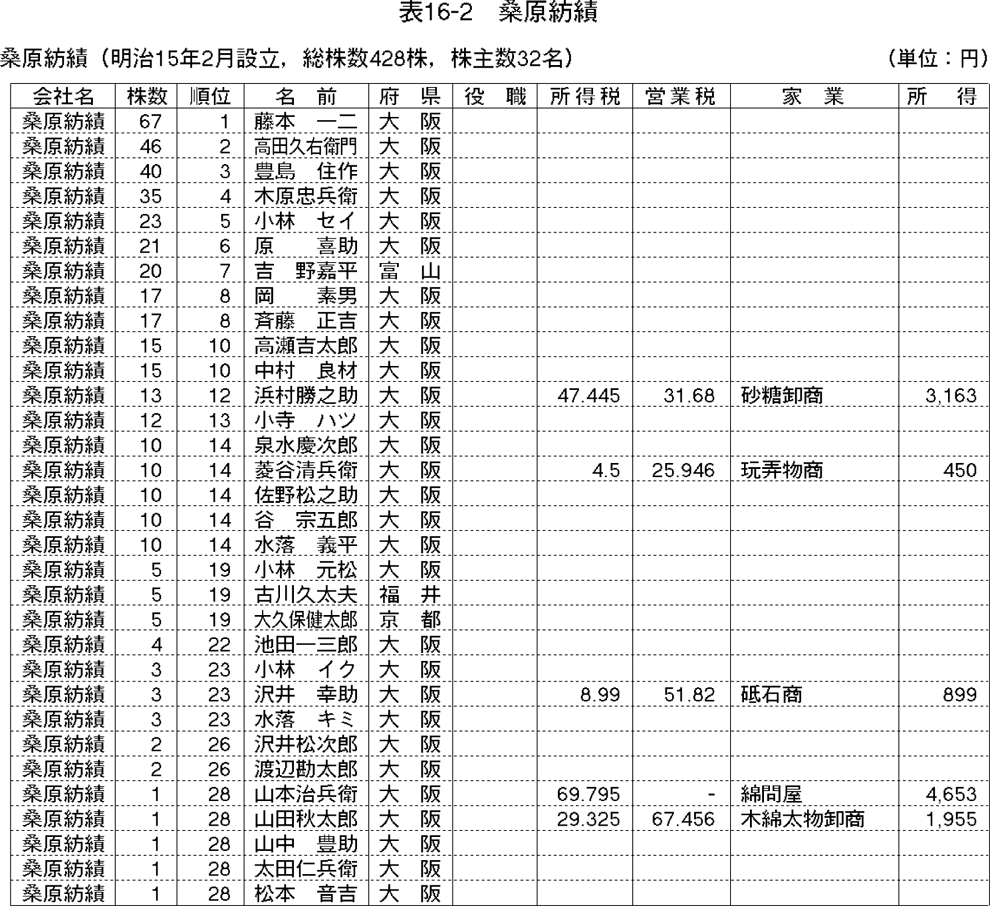
�@
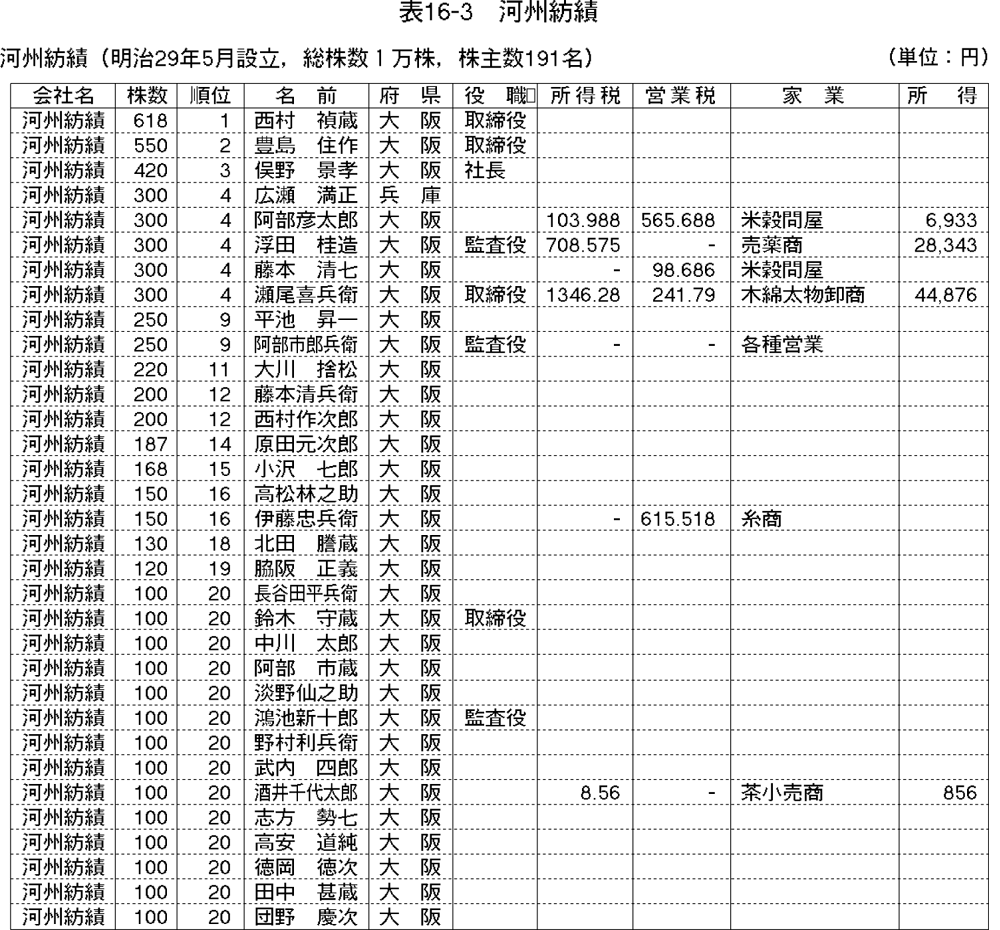
�@
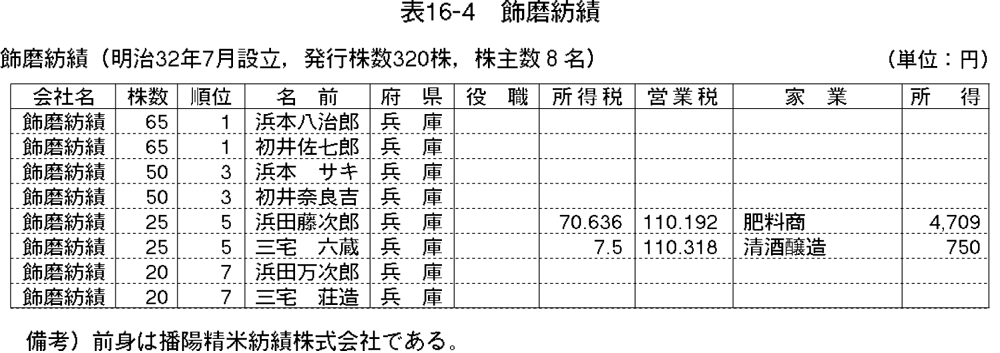
�@
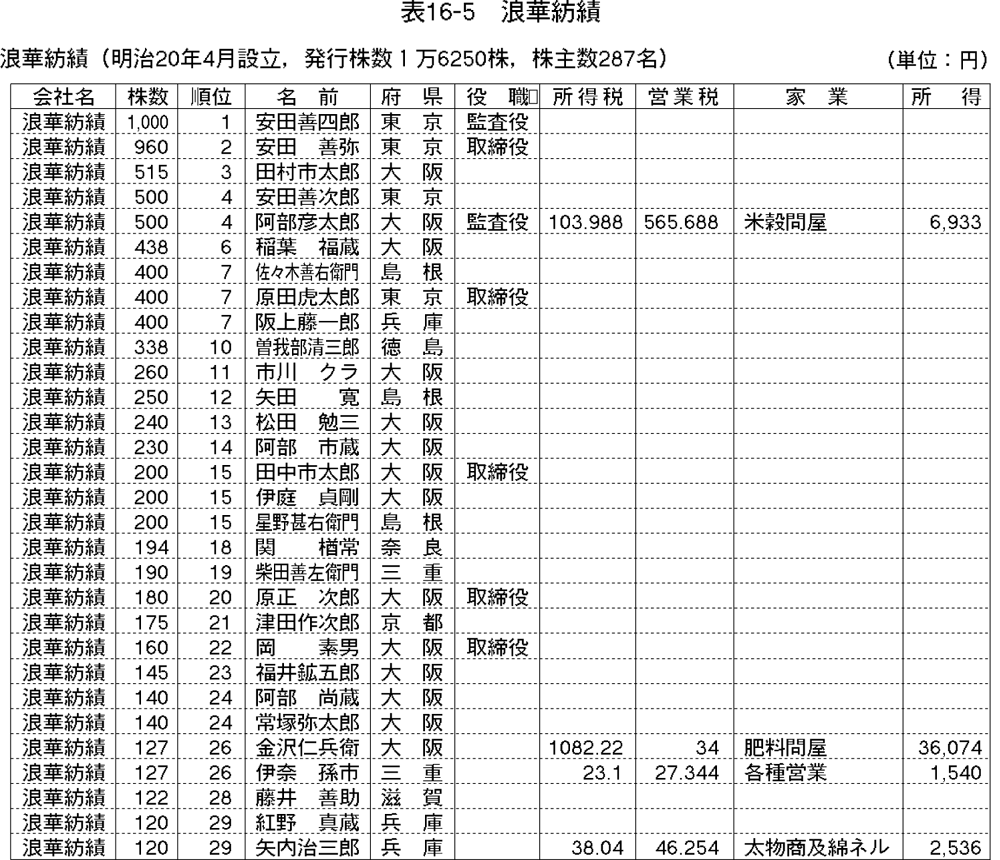
�@
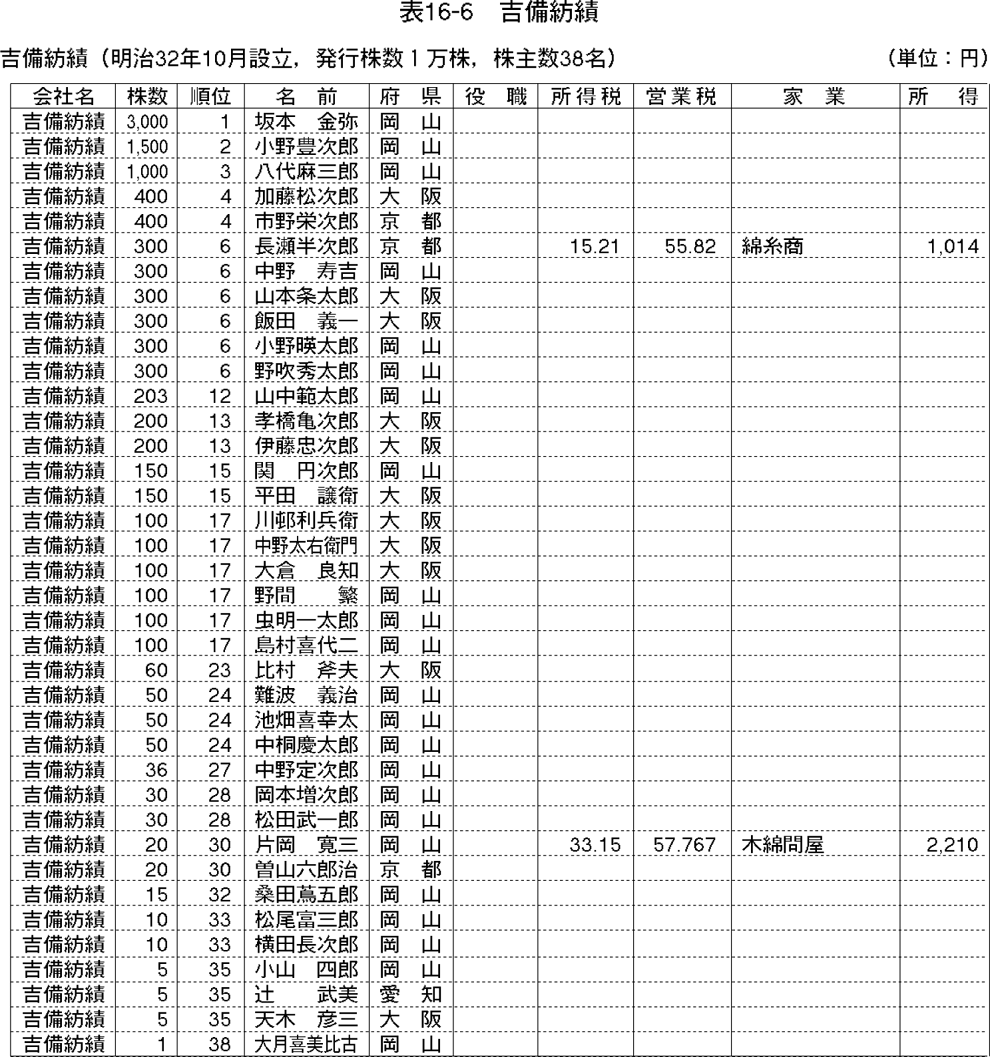
�@
�@
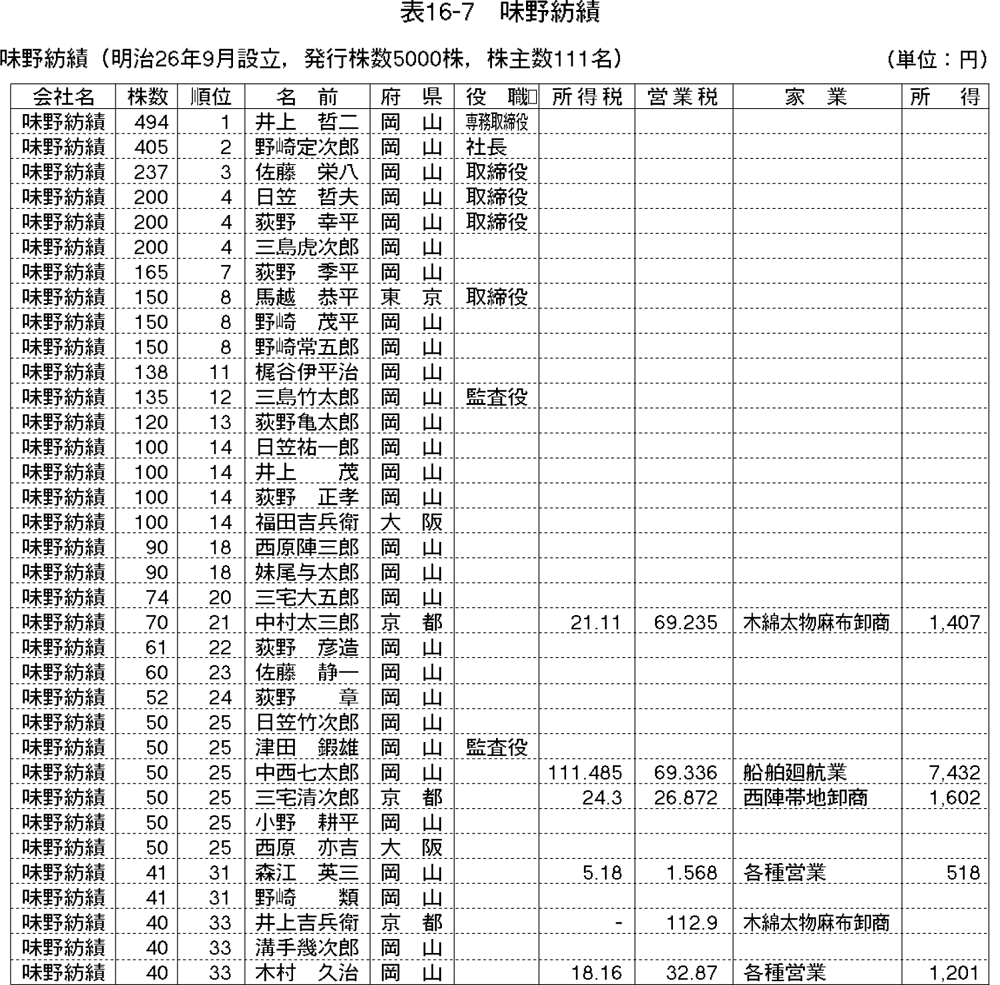
�@
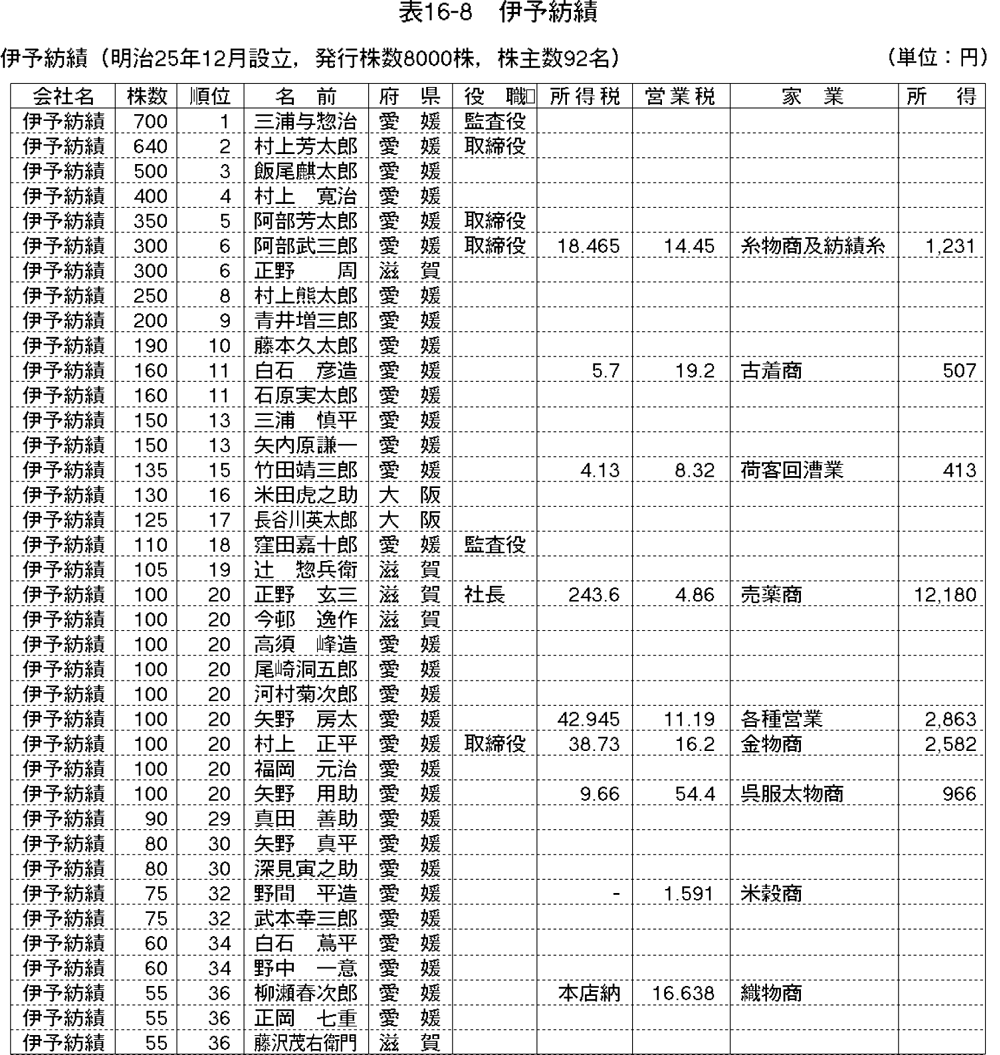
�@
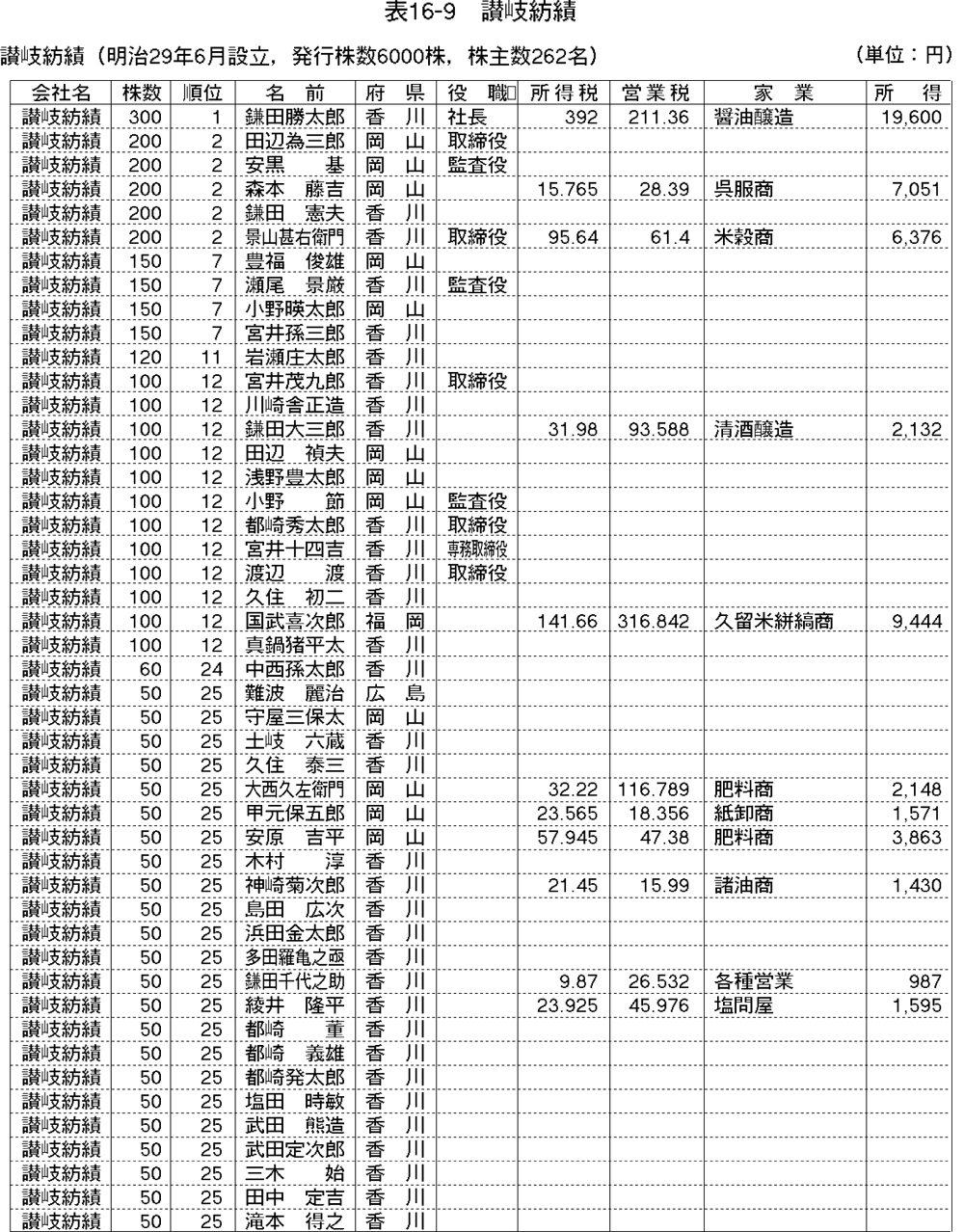
�@
���@��
�ȏ�̕��͂��܂Ƃ߂Ă������Ƃɂ������B
��1�̉ۑ肩�番�������_�́C����͉�Ђ̖{�Аݗ��{���ɉ����ċߗׂ̕{���ɍݏZ�̊��傪�������߂Ă������Ƃł���B����͒n��Ƃ����T�O�������ꍇ�C�����Ɩ��m�Ȏp�ƂȂ�B����������ƂƂ��ɁC�אڕ{���Ⓦ���C���E���ɂȂǂ̊�����n���̊���ƕ������Ă������Ƃ��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�������z�́C���啪�z���͓������n�ߑ��C���ɂȂǂ̊��傪��߂銄�����������Ƃ����������B���ƂɁC����a�т̓Ȗ،��C�l���E��B�̖a�щ�Ђł́C�n���̊���̏��L���������ΓI�ɒႭ�C���̕��C�����C���C���ɂ̊��傪���L���銔�����������Ƃ���C�����n��̊��傪���ΓI�ɑ����̊��������L���Ă������Ƃ�������B
��������C�����̖a�щ�Ђ̊��������L���Ă���l���Ƒ����̊��������L���Ă���l�����������C�����C���C���ɍݏZ�̐l�����������Ƃ��m�F�����B�����������ɁC�������≪�R�����͂��߂Ƃ��Ēn���ݏZ�̑劔����U�����ꂽ���Ƃ́C���L���ׂ��ł��낤�B
��2�̉ۑ肩��́C����̕��Ϗ����́C�唼��600�~����1000�~�K�͂ƁC1000�~����2000�~�̏����w�����|�I�����ł��邱�Ƃ�������B�܂��C300�~�w����������ꂽ���Ƃ����L����K�v�����낤�B
��3�̉ۑ肩��́C�M������́C���悻10���̊��������L���Ă����̂ł���B����ɑ����āC5�劔��ł́C28���C10�劔��ł́C40���C20�劔��ł�54���C�Ƃ����̂����ς��猩�������ł������B���̈���ŁC�����̕��U���i�a�щ�Ђł́C10�ʂ܂ł̊��傩��ł͂Ȃ��C50�ʂ���70�ʂƂ������ΓI�Ɍ��āC�K�������劔��Ƃ͌����Ȃ����傪�����ƂȂ��Ă������Ⴊ�U�����ꂽ�B
���āC�ȏ�̒m���ɉ����č���̉ۑ���L���Ă��������B
����́C�ȏ�̖a�щ�Ђ̎����40�N�̊��喼��Ŗ��炩�ɂ��邱�ƂƓ����ɁC����ꂪ���͂��Ă����l�b�g���[�N�Ƃ����l�ԊW�̒��ŁC�ǂ̂悤�Ȉʒu�Â����^�����邩�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃł��낤�B
�i�t�L�j�{�e�́C����12�N�x�|14�N�x�C�Ȋw������⏕����Ռ���(B)(1)�u��O���ɂ�����o�c�҂���ъ�Ƒg�D�̃f�[�^�x�[�X�쐬�ƕ��́v�i�ۑ�ԍ��@12430018�j�̐��ʂ̈ꕔ�ł���B