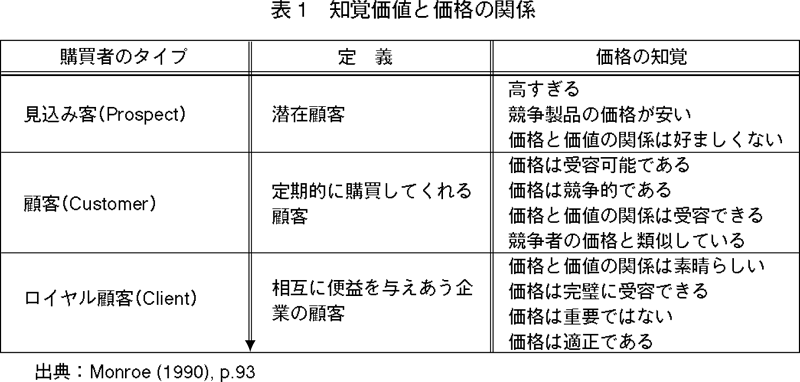
消費者における価値と価格
上田 隆穂
1.はじめに:顧客価値を高める目的
顧客価値を高めるとは,企業が提供する製品・サービスに関して品質,顧客サービス,価格の3つの次元上でこれらの次元の適切な組み合わせである『バリュー・パッケージ』を常に向上し続けていくことである1。例えば,1912年創業のL.L.ビーン社は,当初から次のような顧客価値を高める努力を行っている。
『我々の保証:あらゆる点において,100%の満足を保証します。もし期待に沿わない場合には,いつでも返品して下さい。お取り替えするか,購入価格分を返金致します。L.L.ビーン社からは完全に満足できないものは何も受け取ってもらいたくないのです。』
L.L.ビーン社は,1912年の春に革張りの上に防水のゴムでカバーしたハンティング・シューズを100足販売した。それには100%満足の保証のタグを付けていたが,2,3週間で靴は返品され始めた。結局,90足の靴が返品されたが,それは,靴をカバーしていたゴムが剥がれたからだった。彼は,90足全ての靴を取り替え,保証を実行し,ビジネスを軌道に乗せ,いまだより強力な保証を続けている2。
つまり上記の例では価値の交換が行われており,企業が製品・サービスによる便益を顧客に提供し,顧客は企業に対価を支払っている。企業の目的は,「利益,市場シェア,イメージ,業界のリーダーシップ,生存」などであり,顧客の目的は,「実用的およびシンボリックなニーズの満足」である。これのバランスをとっているのが,価値である3。
上記のバランスを長期的視点で維持することにより,企業は消費者に3つの段階を進化することを望んでいる。この3つの段階とは,見込み客(Prospect),顧客(Customer),ロイヤル顧客(Client)である。表1を見られたい4。企業と消費者との関係が弱い時,消費者は潜在顧客であり,まだ顧客になっていない。彼らの企業への評価はそれほど高くなく,従って,この企業の製品・サービスに関する価格の知覚は「高すぎる」となることが多い。
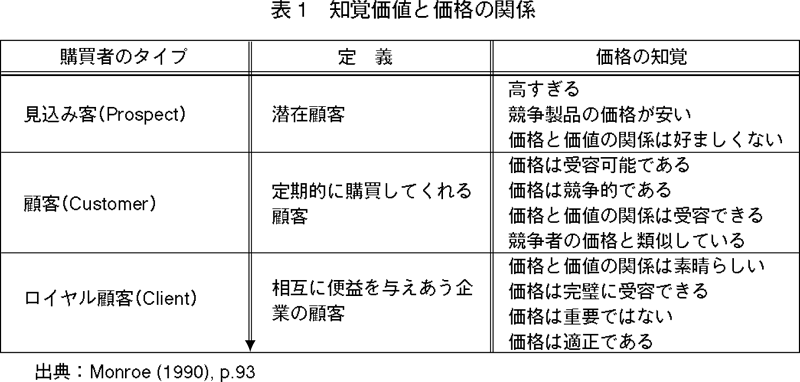
しかるに,顧客の段階に進むと,この価格の知覚は改善されるが,まだ競争企業とそれほど変わりない状態であり,競争企業が価格を下げると消費者はブランドスイッチを起こす。関係が最終段階のロイヤル顧客に進むと消費者は当該企業にとり,ファンという存在になり,「価格は適正であり,完璧に受容できる」という状態となる。この段階の消費者が多くなれば,企業は,そのロイヤル顧客と相互に利益を与えあう存在となり,長期的に利益を確保しやすくなり,安定が保証される。しかも2割8割の法則といって,「2割のロイヤルヘビーユーザーがその企業の全売上げの8割の売上げに貢献している」いう傾向があれば,なおさら顧客のロイヤル化が重要である。
2.価値とは何か
価値に関しては,マーケティングにおいてこれまで多くのとらえ方が存在しており,研究者によって定義が異なることが多い。非常に頻繁に用いられているにもかかわらず,それほど統一性のない概念である。しかも研究の展開が必ずしも時系列的に展開しているわけでもない。価値の概念は,これまでの研究から以下のようなポイントが存在する。
(1)価値の階層性
(2)価値を構成する便益とコストの明示的な分離
(3)価値の定式化タイプ
2-1.価値の階層性
これはブランド論において頻繁に登場する概念であり,例えば,和田(2002)においては,ブランド価値を基本価値,便宜価値,感覚価値,観念価値に分けており,観念価値に近いほど上位の価値となり,これを満たすことがプレミアムブランドとして重要であると述べている5。価格に関連する価値は,ここでは便宜価値であり,価格その他のコストが低いことが価値とされ,負の効用が逆転されて「負の効用が低い」ことが価値として含まれる。類似の考え方は,ブランド論には多く,上記の分類と田中(2002)の分類を合わせて基本価値,機能価値,情緒的価値,自己表現価値とした分類もある6。またDoyle(2000)の価値ラダー(要件を満たす製品→高品質の製品→優れたサービスを伴う高品質の製品→顧客にとっての経済価値の提供→顧客のイノベーション)という考え方もこの範疇に入る7。
この考え方は,ブランドを論じるのには優れているが,価格との関連で論じるのには不十分である。それは価値の負の要素であるコストについての便益との分離が不十分であるからである。
2-2.価値を構成する便益とコストの明示的な分離
価値を便益とコストに分離することにより,コストに含まれる価格を明示的に操作することが可能となる。例えば,コトラーは図1のようにコストを価値から分離している8。

価値・コストの構成要素が明示的であり,コストの要素も具体的であり,価格は金銭的コストとして明示されているため,操作性が飛躍的に高まっている。しかしながら,実際の顧客価値を総顧客価値と総顧客コストの差で表現しており,コストを除く前のものも,除いた後のものも価値と表現しているため,価値自体の持つ意味が曖昧性を残しており,操作性が悪くなっている。Anderson他(2000)は,生産財市場に限定しているが,価値を「便益+価格以外のコスト(コストは小さい方がよい)」としており,それと対比されるのが価格としており,価値と価格は別々の独立したものとして捉えている。そしてこの価値と価格には別々の効用関数が存在しており,その差で顧客は購入を決定すると述べている。価値から価格部分を完全に分離して価値とは独立であると述べた点は珍しい例と言える9。
しかしながら,価値の便益とコストの分離の草分けは明らかに,価値工学(VE : Value Engineering)である。価値工学(VE : Value Engineering)における価値の式は,簡単には,価値=機能/コスト(V=F/C : Value= Function / Cost)である。図2で示したように,機能もコストも多くの構成要素からなり,それぞれの機能要素がコストに対応している。ここでの価値は明示的に便益とコストに分離している。この価値工学の歴史は古い。第2次世界大戦後,物資不足を背景にアメリカで登場したと言われている10。
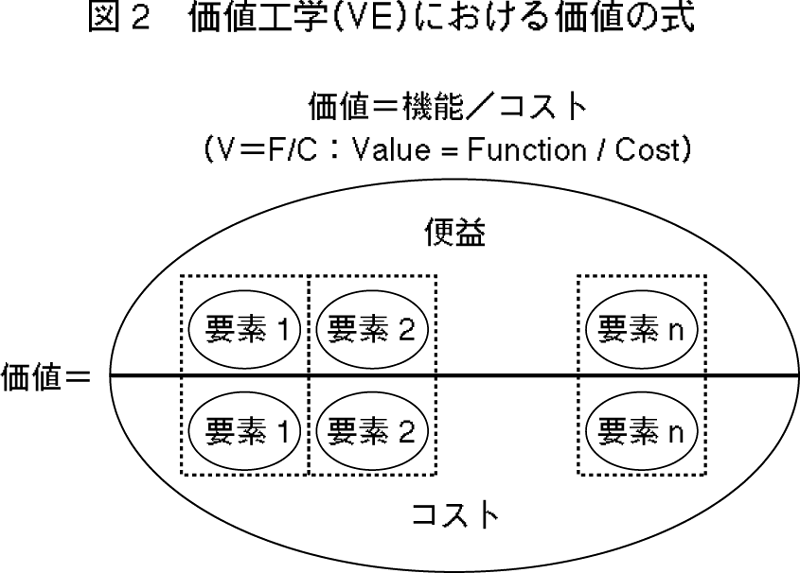
しかしながら,なぜその重要性にかかわらず,マーケティングにおいて取り入れられなかったのであろうか。それは,価値工学が同じ機能を維持しつつ,材料や手法を変化させ,いかにコスト削減を達成するかを目的にしていたため,差別化によって高価格を達成しようとするマーケティングとは相容れなかったためと思われる。この価値工学の考え方にマーケティングに生かせるよう知覚概念を取り入れたのがMonroe(1990)である。その考え方は,Dodds(2004)にも見ることができる11。これらに関しては後述する。
2-3.価値の定式化タイプ
価値の定式化のポイントは,(1)価値を金額的側面から捉えたものか否か,および(2)定式化が差の形(引き算型)であるか商の形(分数型)か,という2つである。順に説明していく。
(1)価値の定式化を金額的側面からの表示を試みたものか否か
Monroe(1990)は,購入が考慮されている製品の知覚価値(知覚製品価値)は,以下の2つの価値から構成されるとしている12。
①獲得価値(acquisition value):製品を獲得することから得られる期待便益から支払いにおける犠牲(displeasure)を差し引いたもの
②取引価値(transaction value):その取引から得られる知覚メリット
まず獲得価値とは,入手で得られる便益と支払いにおける犠牲(sacrifice)との認知的なトレードオフであり,以下のように「知覚」を冠して表されている。
知覚獲得価値=知覚便益/知覚される犠牲
この式では,差ではなく商の形で表されているが,Monroeは厳密な数式と考えず,単に比較の意味であると断っている。ただし金額換算での定式化では,差の形式を採用している。またこの式の知覚便益は,購買者の製品の品質判断と関連するとしている。つまり,不十分な情報の下では,価格が品質を保証するバロメーターとなる。しかし高価格は,同時に犠牲も大きくする。価格のある範囲内では,知覚便益は,知覚犠牲よりも大きく,購買者は獲得価値があると判断する。
金額換算での式は次のように定式化されている。
p-maxを「購買者がその製品に支払ってもよい上限価格」とする。これは,知覚便益を金額換算したものと理解できる。またp-actualを「実際の売値」とすると製品そのものの賞味の便益は次のように定式化できる。
製品の獲得価値(AV)=p-max-p-actual …【式1】
次に「その取引から得られる知覚メリット」である取引価値を説明しよう。これは,プロスペクト理論のゲインとロスの枠組みに従うとされる。このプロスペクト理論とは,Kahneman and Tversky(1979)の有名な価格と効用の関数の理論である13。内的参照価格といわれる消費者の値頃価格(このくらいだと判断する消費者固有の想定基準価格)を中心として,それより実売価格が安かった場合にはゲイン(得),高かった場合にはロス(損)とする参照依存理論である。消費者は,ゲインよりもロスにより強く反応するという「損失の回避」が特徴である。
取引価値の場合には,縦軸は「効用」ではなく,「価値」となって価値関数となる。実売価格を支払って感じるメリットである取引価値とは,購買者の内的参照価格と実売価格の比較で決まる。すなわちこの取引価値の意味するところは,購買機会において「製品そのものの獲得とは別の金銭的な面で得をしたという感覚」であり,その分の金額換算である「正味の便益」と考えてよい。その定式化は以下の通りである。p-refは「内的参照価格」を表す。
取引価値(TV)=p-ref-p-actual …【式2】
「式1」と「式2」の両者の加重和で製品の知覚価値(PV)は次のように決まる。
PV=v1(AV)+v2(TV)
ただし,これらv1,v2は,購買者によって主観的なものであり,異なるとされている。
この金額的側面からの表示は,価格を論じるときは,操作性が高く,優れた定式であるが,問題点としては,「獲得価値構成要素と従来議論されている価値の構成要素との関係づけが乏しい」ことが挙げられる。すなわち「知覚便益=物理的属性,サービス属性,製品の特別な仕様に関する技術的サポート,これに購買価格やその他の知覚品質を加えたもの」であるとすると14,これらの要素を全て感覚的に金額換算してしまうため,これらの要素を用いた具体的な戦略立案が困難となる。
金額換算でない定式化が次に述べる部分に含まれる。
(2)定式化が差の形(引き算型)であるか商の形(分数型)か
上記の定式化は,差の形をとるものであった。差の形をとるものとしては,これ以外にも前出のコトラーの「顧客の受け取り価値」が「総顧客価値」から「総顧客コスト」を差し引いたものという考え方が含まれる。
商の形をとるものとしては,前出の価値工学の価値式が典型的である。これをマーケティングで利用できる形に消費者の知覚を取り入れたものが,以下のMonroe(1990)の価値式を修正した式である15。
![]()
このマーケティングの式を少し詳しく説明すると以下のようになる。
●知覚便益(提供された全商品・サービスに買い手が感じる相対的な効用)
=商品自体の物理的属性+サービス属性+商品の特別な仕様に関する技術的サポート+価格による品質イメージ・プレステージ+その他の知覚品質
●知覚ライフサイクルコスト(商品購入の検討から購入後維持を含めたコスト,心理的な苦労やリスクを感じることも含む)
=実際の購買価格+スタートアップコスト(入手コスト,運搬コスト,設置コスト,注文に関するコスト,訓練のコスト)+購買後のコスト(修繕・維持,失敗あるいは期待はずれのリスク)
以上から言えることは,知覚便益とは,なにも商品自体だけでなく,サポートやイメージ,その他のサービスも含むということであり,それらのトータルでの価値である。また知覚ライフサイクルコストは商品価格だけではない。商品購買の検討にも時間や労力などのコストがかかるし,購買後の維持費もかかる。また買ってみて失敗だったというリスクも割引現在値でのコストになる。
この知覚価値式の利点は,知覚便益の構成要素との関連で,価格以外のコストを抑え,価格をどのように決定すれば,顧客価値がどうなるかをシミュレーションできる点である。これにより,価格関連の操作性が飛躍的に高まる。顧客のロイヤル化には,商品の知覚価値を上げる必要がある。そのためには,知覚価値式の分子である知覚便益を高め,分母である知覚ライフサイクルコストを下げる努力をしなければならない。
この差と商の形式での定式化のどちらが優れているのであろうか。両者を扱う文献では,それに触れたものはない。理解の上では差の形式の方が直観的に理解しやすいが,差の場合には,つねに金額であるとか効用であるとか同等の尺度に便益,コストともに換算する必要があるため,操作性という点でやや煩雑となる可能性はある。商の形では,便益,コストの尺度を独立に扱えるため,操作性の点で利がある。
またはじめの(1)の金額面からの定式化と(2)で説明した知覚製品価値の2つについての優劣に関しては,論じることは難しい。操作性の観点からは,差・商の場合と同様のことはいえるが,目的に応じて使い分けるべきであろう。ただし,新製品開発や製品改良などを目的として製品自体の構成要素を扱う場合には,金額換算では困難であり,(2)で説明した知覚製品価値の式を用いた方がよいかも知れない。
3.知覚価値向上の戦略枠組み
製品の知覚価値を高めて利益を上げるための枠組みは,Monroe(1990)の図3aとDodds(2003)の図3bのようになる。この両方の図に関して,aの図の知覚便益をbにおける相対的な知覚品質と置き換えただけで両者は同様であるため,図3aを利用して説明しよう。
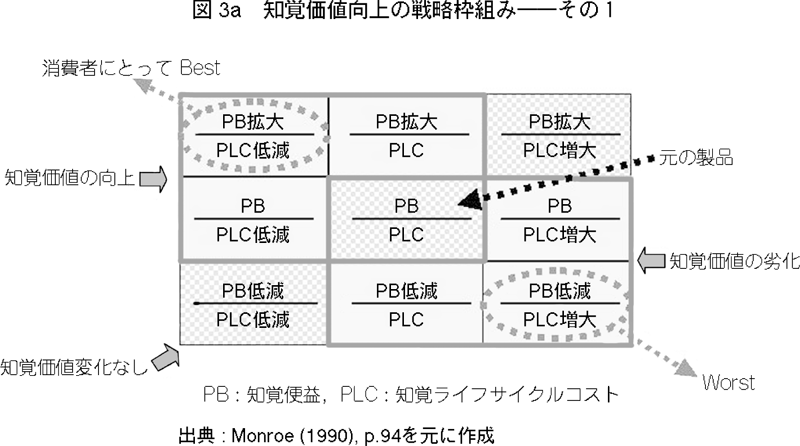
この図において,中央に位置するPB/PLC(PB:知覚便益,PLC:知覚ライフサイクルコスト)は,オリジナルの製品(サービス)である。それのPB,PLCを同時に低減させても拡大・増大させても同等のレベルであれば知覚価値の変化はない。これは右上方向の対角要素に表示されている。というのは知覚便益を拡大しても知覚ライフサイクルコストが同等に増大すれば,知覚価値に変化は起こらないからである。ところが知覚便益を拡大して知覚ライフサイクルコストを変えないならば,価値は増大する。知覚便益を拡大し,知覚ライフサイクルコストを低減できれば消費者にとっての知覚価値は最も増大する。現在の市場動向は,知覚便益を維持し,知覚ライフサイクルコストを低減するというデフレ化による消費者の知覚価値向上のみを追求している状況であり,知覚便益に目を向けた戦略が重要である。右下の3つのセル(升目)は,逆に知覚価値劣化の方向であり,避けねばならない16。
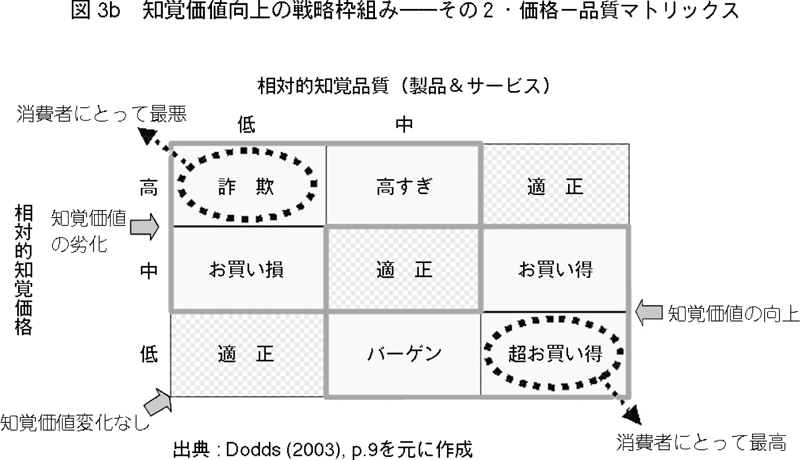
消費者の知覚価値を向上させるためには,知覚便益の構成要素の重視される要素を高め,また知覚ライフサイクルコストを下げることが必要になる。価格に強く関連するのが,後者である。トータルコストである知覚ライフサイクルコストを下げつつ,その中の1要素である価格を上げるのは可能であろうか。答えは「可能」である。これについて以下に述べる。
3-1.知覚ライフサイクルコストを低下させ,かつ価格を上げる
知覚ライフサイクルコストには,価格のみならず,消費者が実際に獲得活動をする等の移動などの手間や心理的なコストも含んでいる。従って,高めの価格を受容してもらうためには,知覚ライフサイクルコストに含まれる価格以外のコストを可能な限り縮小して,価格はその縮小分よりもやや小さく上昇させるのがベストとなる。これが実行できれば全体のライフサイクルコストは減少するのに,価格は上昇させることが可能となる。図4はその具体例である。旧参照製品の購買後コスト(メンテナンス等)やスタートアップコスト(金額換算分)を削減することにより,その分を価格に乗せることが可能であり,さらに価格を上げることが可能である。この図では,従来よりも2万円上げれば,従来製品と知覚ライフサイクルコストで等価となる。この価格引き上げ可能分2万円の内例えば,1万円低めに価格を上げても価格は,従来の4万円から5万円となり,1万円の価格引き上げが可能となる。このように値上げをしても全体で最終知覚ライフサイクルコストが下がるため,知覚価値は増大する。実例としては,北米に進出している日産自動車の例がある。日産は,米ビッグスリーがディーラーにかなりのインセンティブ(報奨金)を与え,値下げ攻勢を強める中,価格を高値で安定させ,販売価格は米国社よりも高いが,故障が少なく,維持費がそれほどかからないというトータルコストを下げる方法で対抗した。そのため価格が高くとも人気があるのでディーラーへの低インセンティブが可能となり,利益率も高くなっている17。
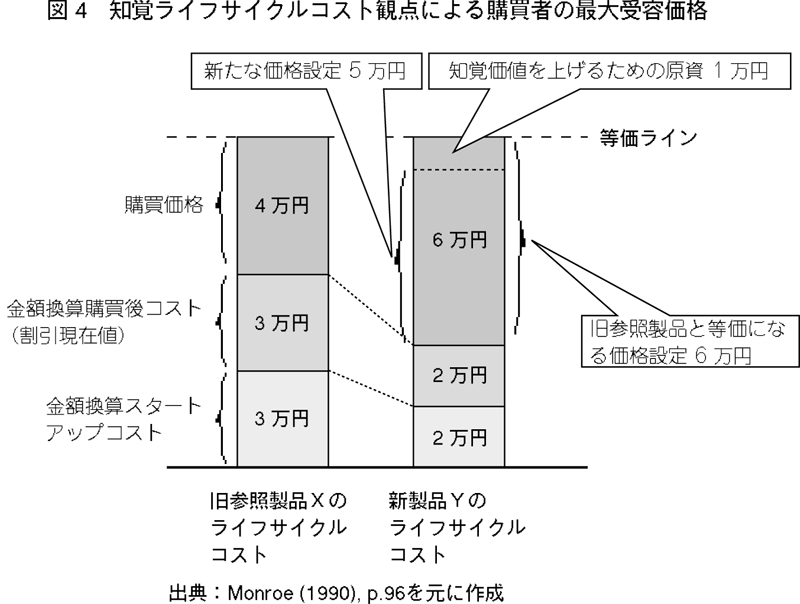
3-2.知覚便益・知覚ライフサイクルコストの構成要素ポジションニング・マップ
上記の戦略枠組みを実行するために知覚便益・知覚ライフサイクルコストの構成要素を明らかにして,その拡大もしくは低減の優先順位を決定する必要がある。具体的には図5のようなポジションニング・マップを作成する。ここで図の便益に関して階層構造があるのは,便益構成要素の上位の階層的な意味を明らかにする必要があるためである。この図で周辺から中央に近づくにつれ,重要度は高くなる。
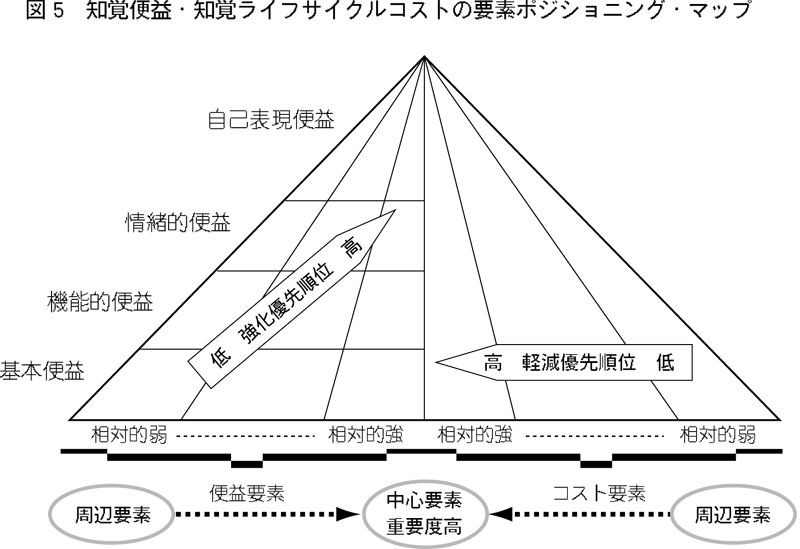
具体的な要素の発見方法・重要度の測定に関してはいくつかの科学的な手法が存在している。基本的な流れとしてはグループ・インタビューやコンジョイント分析があり,階層構造の発見には,ラダリング法やこれをインターネットにより多サンプルでの実施を可能にしたWEBラダリング法などがある。コンジョイント分析とは,仮想的に作り出された複数の商品コンセプトを被験者に買いたい順に並べ替えてもらい,その結果の順位データを利用して構成する要素のどれがどの程度,誰に重視されているかを明らかにする手法である。これらに関しての詳しい説明は本研究の範囲を超えるため割愛する18。
4.価値向上戦略のターゲット範囲
上記の価値向上戦略では範囲を絞ったターゲティングを行わないと効率的ではない。図6を見てみよう。この知覚価値向上のためのターゲットになりうるのは,便益と価格が公正に交換できる範囲内である19。この範囲内を示すのが図のバリューゾーンである。
この図は,便益と価格から構成されるが,価格によって仕切られるところには,消費者セグメントが存在している。この横軸上のゾーンの外側の両サイドは対象から外れるセグメントである。左端は,貧困のスパイラル(Poverty Spiral)と名づけられており,安物しか買う余裕がなく,安物買いをすることにより,失敗してまた更なる貧困に陥る層とされている。例えば,安物の車をローンで購入し,修理もできないほど駄目になってしまい,なおかつローン残があるなどである。反対の極は,顕示的消費(Conspicuous Consumption)と命名されており,この層は,怪しげな価値を持つ便益のためにお金をつぎ込みすぎる消費者の層である。分別ある消費者ならば,不要と思われるものに目がくらんでしまい,惜しげもなく支出をする。このセグメントでは,価格は顧みられず,価値向上戦略の対象外となる。例えば,プレミアムブランド・ユーザーの次の言葉はまさにそれを物語っている。
「ルイ・ヴィトンという夢を買うんだよ。セクトに属しているようなもので,値段が高ほど喜んで買ってしまう」20。
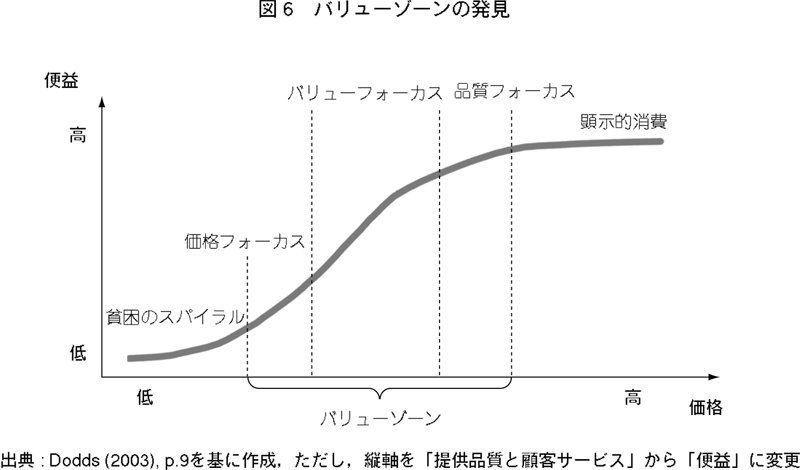
続いてバリューゾーンにある価格フォーカス,品質フォーカス,バリューフォーカス市場をそれぞれ見てみよう21。
(1)価格フォーカス市場
この市場では,価格が便益よりもずっと効き目がある。需要拡大の有効な選択肢が価格のみということもあり,価格を一定に保ち,製品の便益を向上させるという戦略は,あまり効率的ではない。これでは企業利益率を下げることになるし,また価格を下げないで製品の便益を下げることは長期的に顧客満足を低下させる。価格と便益を同時に変化させる場合には,両者の効き方に注意して価値増大方向に変化させる必要がある。例えば,価格を下げ,便益を下げる場合には,便益の増大効果より価格低減効果が大きいため,それによる価値増大の可能性もある。
(2)品質フォーカス市場
この市場は価格フォーカス市場とは逆になる。便益効果が価格効果より高い市場である。価格を下げてもそれほど価値増大がないのに対し,便益拡大の効果は大きい。特にプレミアム製品市場では,製品の便益を上げて価格を上げるのは,エコノミー製品市場よりもずっと容易である。
(3)バリューフォーカス市場
この市場では,価格と便益の効果がほぼ均等である。低価格で標準的便益の製品や標準的価格で便益の高い製品を出す方法がエントリー戦略でよくとられるが,これはこのセグメントで効果的である。
以上のように価格と便益の効果からセグメントの特性を捉えた上で価格-便益の価値向上戦略を実施する必要がある。
5.価値分析を用いた改善価値による価格改訂のケース22
現在の顧客および潜在顧客によって知覚される製品・サービスの相対的改善価値を推定して,価格をいくら上げればよいかの測定は大きな難問の1つである。特に,製品・サービスが新しすぎて顧客にとっての相対価値が正確に推定できない場合にはなおさらである。さらに改善価値は,時間や顧客,また顧客の使い方によっても多様である。ここでは,製品改良により便益,コストを改善したが,その分の価格をいくら上乗せするかという事例を挙げておく。ただし,このケースでは,企業に時間的制約があり,調査ができないという設定になっている。
事例:サドバリー・コーポレーション(Sudbury Corporation)
この企業は,顧客企業の生産・包装オペレーションにおける接着剤塗布装置を生産している企業であり,マーケットシェアが約40%を占めるリーディングカンパニーである。しかしながら,近年かなりの競争力を失い,競争企業に対して大きなプレミアム価格を設定できる力を失っていた。そこで新製品シリーズを開発・導入する戦略をたて,強さを取り戻し,収益性の改善を図った。
この企業は,現製品よりもはるかに大きな価値を顧客に感じてもらえる新製品開発が可能と考えていた。新製品市場導入の時,この企業は,現在の製品に対してどのくらいプレミアム分を乗せられるかに関心があったが,時間制約があるため,マーケットリサーチをする余裕はなかった。そこでこの企業は,研究開発スタッフの代表者,製品マネージャー,セールスマネージャーを集めて議論を行った。研究開発担当者は,既存製品に比べた新製品の5つの大きな利点を述べた(表2)。
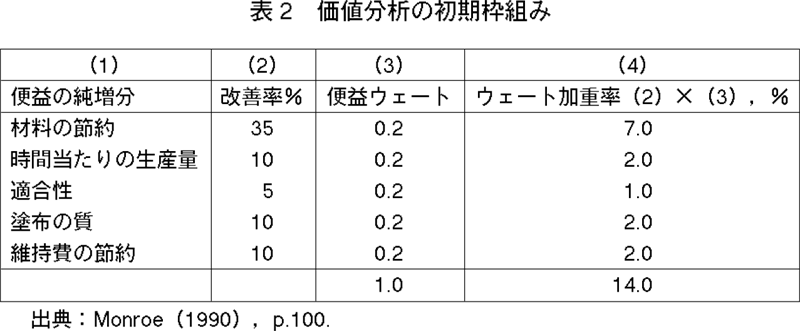
しかしながら,潜在的購買者がどの程度便益を相対的に感じるかの判断が彼らには困難だったので,一律に0.2のウェートを与えることにした。このウェートを改善率に乗じることによって,便益の純増分(%)が計算された。この合計価値純増分は表のように14%と計算された。この結果,既存製品より14%ほどのプレミアムを価格に乗せることが可能であると考えられた。
しかしながら,ここで大きな問題が生じた。それは,14%のプレミアム価格分では,計画期間での開発費回収ができないということであった。従って,さらに議論が重ねられた結果,新製品と同種の装置を使用するヘビーユーザーだけが必要な投資に見合うだろうと考えられた。その結果,新たなヘビーユーザー向けの枠組みがつくられた(表3)。
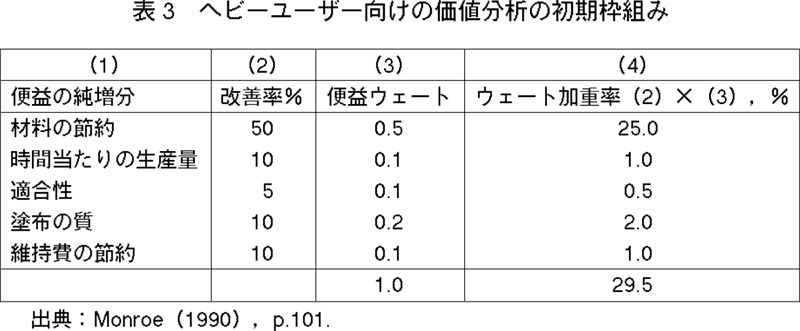
新たなヘビーユーザー向けには,材料の節約改善率は,50%となり,しかもこの要素に関する便益ウェートは,他の顧客よりもはるかに大きく,0.5であった。これらの改善率とウェートから計算されたプレミアム分は,劇的に増大して全体で29.5%となった。ただし,その分全てを旧製品価格に乗せることは,用心深く避けることになり,価値増大をもくろんで22%増のプレミアム価格で新製品が販売されることに決定された。
この価値分析のケースでは,調査が行われていなかった。もちろん事前にゆとりがあれば,調査をすべきであり,便益ならびにコストの各要素をグループ・インタビューなどで導き出し,専門家の知識でフィルターをかけた上で,予備コンジョイント分析などで対象となる要素を絞った上で,本格的なコンジョイント分析を実施してそのウェートを推定するのが標準的なパターンである。またこのケースで行った方法においても,便益・コストの改善率と価格への転嫁率とを同レベルで見ているが,その保証が確実にあるとは言えない。しかしながら,これらを割り引いたとしても実務上の利用としては参考になる方法であろう。
6.結びに代えて
本研究では,価値と価格の関係を明らかにするために,価値に関してマーケティングおよび消費者情報処理の観点から整理を行い,価値の定式化の分類・評価を行った。その上で,価値向上戦略のための枠組みを提示することにより,知覚便益,知覚ライフサイクルコストの要素整理の方向性を示し,ターゲットを定める枠組みも提示してきた。中心テーマは価値向上であるが,その中でも価格は重要な役割を担っている。この価値改善のプロセスを考慮した価格決定,すなわち価値ベースの価格決定こそがこれからのプライシングの中心になることは間違いない。これらの具体的な実践のためには細かい問題点などまだ多く存在するが,大きな方向性は示せたであろう。
従来より価格と価値の関係を扱った文献は多くなく,この領域自体がこれからの領域と言っても過言ではない。実践を積み重ねて,さらなる理論の改善が必要である。