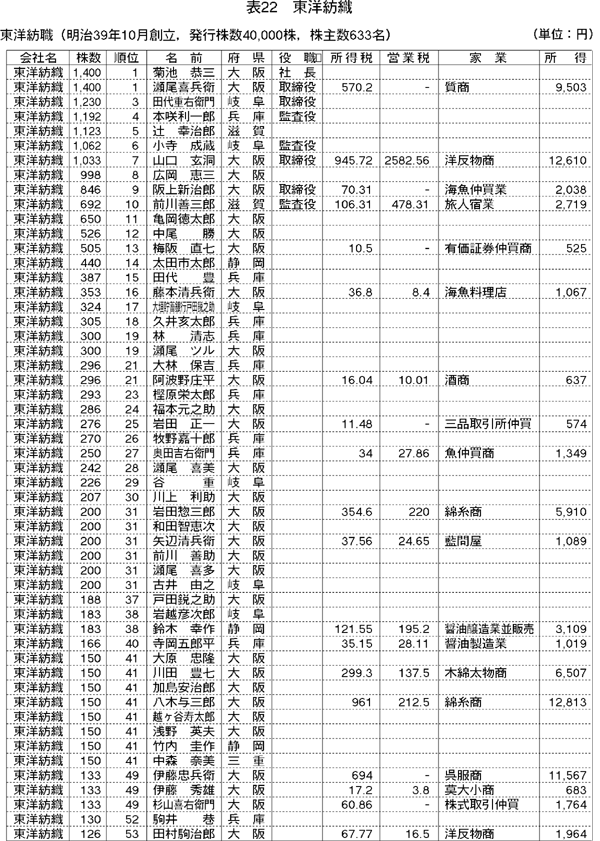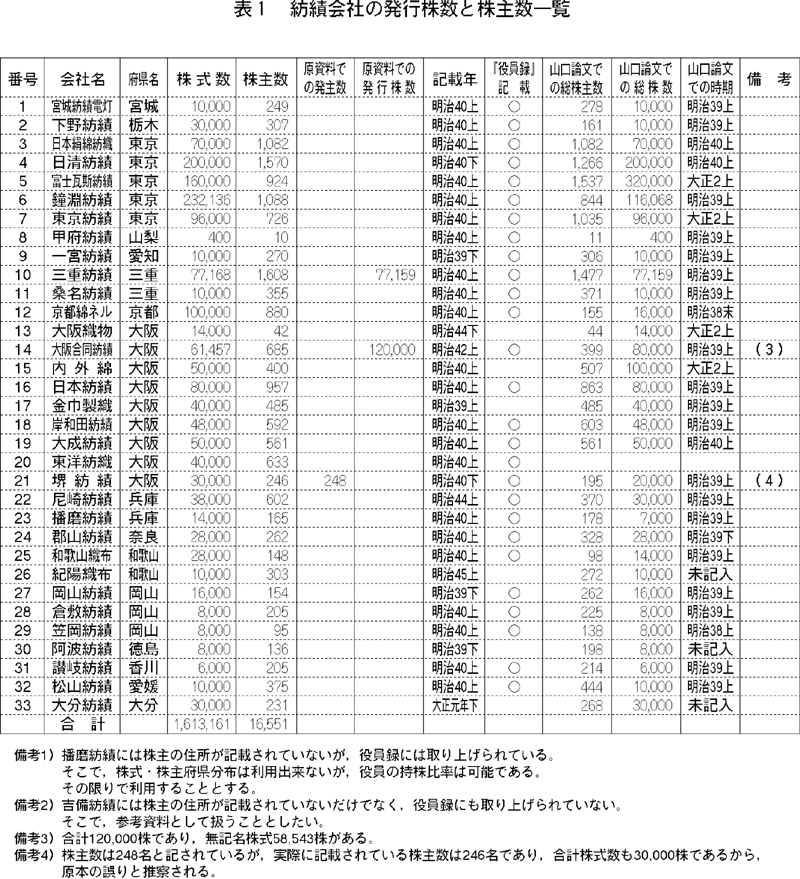
【209頁】
明治40年時における綿糸紡績会社株主名簿の分析
――株式仲買人の台頭,専門経営者の進出――
鈴木 恒夫、小早川 洋一、和田 一夫
はじめに
本稿の目的は,明治40年時における綿糸紡績会社33社,延べ16,551名の株主名簿のデータにもとづき,株主・所有株式数について分析することである。前稿(注1)の主要な課題の一つは,株主の所得水準をも明らかにし,わが国紡績会社の初期の出資の実態の一端を明らかにすることであった。前稿でも記したが,われわれは,現在,同年時における全国の会社を対象に「ネットワーク」の分析を行なっており(注2),本稿は,紡績会社に限定するものではあるが,このネットワークを構成する人物の株式所有状況を観察することを目的としている。紡績産業を素材にしてネットワークとの関係,ことに役員と並んでネットワークに属する人物全体の株式保有については,既に検討を終えているが,今回は,前稿と同じ構成を取ることとし,ネットワークとの関係は別稿に譲ることにしたい。
前稿でも記したように,明治期における綿糸紡績会社の株主についての包括的な分析としては,すでに山口和雄および村上(西村)はつ両氏による研究がある(注3)。山口氏は,日本紡績協会所蔵の紡績会社株主名簿(考課状所収)をもとに,村上氏らの協力のもと,「明治日本の代表的産業の一つであった紡績業の資本――ことに固定資本――がどんな職業・階層・地域の人々によって供給されていたかを明らかにする」という目的のもと,明治31年時に存在した全国の紡績会社81社のうち65社を対象に,各社の大株主(「比較的持株数の多い重要株主」)計1141名をとりあげるとともにかれらの職業調査を行なった。また,村上氏は,山口和雄編著の『日本産業金融史研究 紡績金融編』(注4)において,この明治31年の調査に加えて,同【210頁】39年および大正2年(いずれも上期)における各紡績会社の株主名簿を分析し,比較した。本稿と対象時期がほぼ同じ明治39年時については,39社(「同時期の紡績会社の約8割」)の「大株主」(上位20名前後)についての職業調査を行なうとともに,株式の集中・分散等の分析を行なっている。
山口・村上論文とわれわれの研究との分析対象上のちがいを言えば,対象とする会社の異同とともに,両氏が各社の大株主を対象としたのに対し,われわれは株主名簿上の全株主を対象としたという点にある。また,われわれは,『明治40年 日本全国諸会社役員録』および『明治40年(第3版) 日本全国商工人名録』掲載の人物と株主名簿掲載の株主とを照合するとともに,株主・役員の所得額を算出・分析したという点も山口・村上論文とのちがいである。その結果,32社の株主の特徴を摘出し得た。ことに,『明治40年 日本全国諸会社役員録』には,取締役,監査役を始め理事などの経営者,合名,合資会社の社員あわせて,延べ38,398件のデータが記載されている。また『明治40年(第3版) 日本全国商工人名録』には,144,362件のデータが記載されている(注5)。これら3つの資料(データ)をつき合わせることによって,株主の役員としての実態および所得と家業の分析が可能になった。
本稿の構成は,明治31年と40年の間での変化を理解できるように,できる限り前稿と同じ構成,作表を試みた。
本稿の課題は次の4点である。第1点は,株主の住所が記載されている32社を対象に株主の地域分布と株式の地域分布を考察することである。株主層の府県分布状態を通して,どのような地域の人々が株式に出資したのかを明らかにすることである。会社が設置された府県に居住する人々が株主として参加したのか,それとも大阪や兵庫などの関西地域,あるいは東京の関東地域,そして愛知や三重などの東海地域の人々が,広範に投資していたのかが,判明する。所得を算出するに当たり,明治40年時点の所得税法に言及する必要があるが,これは詳細な説明が必要であるため,あえて本文末尾に「補論」として,所得税の簡単な変遷を記すこととした。
第2点は,明治20年代に勃興してきた紡績会社が,その後の成長過程で合併を推進し,地域的な融合を進める中で,株主や役員がどのような変化を遂げたのかを,株主の実態や所得階層を通して明らかにすることである。ことに,所得が判明する株主層に限定してではあるが,株主層の所得水準を確認したい。従来,一部の富豪同士が共同して会社を設立したかのような理解がなされてきたが,株主の所得を算出することで,広範な株主層を基盤に設立したのか,あるいは,一部の富豪が共同出資して設立したのかを明らかにしたい。
第3点は,どのような株主が紡績会社の役員に就任していたのか,またその他の会社に役員として関与していたのかを明らかにすることを課題としたい。大株主がそのまま会社役員に就任していたのか否か,という問題である。個々の役員の持株に加えて,役員全体でどれだけの株式を所有していたのか,という論点も考察したい。
最後に第4点は,紡績会社の株主,ことに多数の紡績会社の株を保有している人物の中に,株式仲買人が多数登場してきたことである。この事実を踏まえて,紡績会社の株を多数保有し【211頁】ていた人物を観察することである。
本稿の構成は以下の通りである。第1節では,株主と株式の地域分布を明らかにする,第2節では,株主の所得を算出,考察する,第3節では紡績会社役員の株式保有状況を確認する。ついで,第4節では,株式仲買人の株式保有の実態を,これまでの研究との関係で明らかにする。そして,明治31年と40年の比較を踏まえて結語としたい。更に,大量のデータを扱った研究であるから,大量データの処理の仕方を記す必要があると考え,若干の附記を行った。また,明治31年から40年の間に所得税法は改正されたため,この間の推移を簡単に紹介し,前稿と本稿で用いた所得税率を掲げることにしたい。
第1節 株主と株式の地域分布(分析と比較)
本論文で対象とした紡績会社全体についての資料の概要を記すと次のようになる。株主数は総計16,551名(延べ),株式数合計1,613,161株である(注6)。33社についての個々のデータについては,表1に記した通りである。これによれば,発行株数では,鐘淵紡績の23万2,136株が最大で,日清紡績の20万株がこれに続く。このほかに富士瓦斯紡績は16万株,京都綿ネルが10万株を発行していた。明治31年で最大の株式を発行していた日本紡績が8万株であったことを考えると,合併の進展とともに10万株以上の紡績会社が4社になったことは,この間の成長を物語るものと言えよう。一方,株数の少ない会社では,甲府紡績の400株がある。甲府紡績を除いた1万株以下の会社は,33社中4社を占めるに過ぎない。その他は,1万株以上5万株未満の会社が17社,5万株以上10万株未満の会社が7社であった。そこで甲府紡績を除いた発行株数の平均と株主の平均を求めると,次のようになる。32社平均では,株主は517名で発行株数は5万400株である。明治31年時点の小規模会社を除いた60社平均では,株主の平均が300名で株数の平均が1万5,000株であったから,株主で1.7倍,株数で3.3倍に増加した。
明治40年段階で対象にした紡績会社の府県分布(表2)は,北は宮城県から南は大分県まで広がり,東京4社,三重2社,大阪9社,兵庫2社,和歌山2社,岡山3社と16府県に拡大している。明治31年では18府県であったから,ほぼ対象としている府県は同じであると言えよう。
株主の府県分布を見てみよう。紡績会社の本社所在府県における株主の割合を70%を基準にして分類すると,70%を上回るのは,宮城紡績,甲府紡績,一宮紡績,郡山紡績,岸和田紡績,和歌山紡績,和歌山織布,紀陽織布,岡山紡績,倉敷紡績,笠岡紡績,松山紡績,讃岐紡績,阿波紡績,そして大分紡績の15社であった。すべて,東京,大阪,兵庫以外の地域である。隣接する府県と密接な関係のある2つの府県で70%を越える紡績会社は,日清紡績,三重紡績,桑名紡績,尼崎紡績の4社である。それ以外の全国的に株主が分散している紡績会社は,下野紡績,日本絹綿紡織,富士瓦斯紡績,鐘淵紡績,東京紡績,京都綿ネル,大阪織物,大阪合同紡績,内外綿,日本紡績,金巾製織,大成紡績,堺紡績の13社であった。下野紡績を除くと,東京,京都,大阪,兵庫以外の会社では70%を越えているのに反し,東京,京都,大阪,兵庫にある会社では,一般的に株主の分散が進んでいた。これは,これらの会社が合併【212頁】を繰り返した結果であることも一因である。
また,株主の府県分布・地域分布について,紡績会社の本社所在府県・所在地域の株主の割合の平均を求めてみると,前者が64.2%,後者が82.2%であった。一方,株式の府県分布・地域分布について,紡績会社の本社所在府県・所在地域の株式の割合の平均を求めてみると,前者が68.8%,後者が84.9%であった。株主の場合より,株式の場合の方が平均は若干,高い。ここで,会社所在府県の株式の割合が50%以下の会社は6社あるが,大阪織物を除いた5社はみな,本社所在地域の株式の割合では,ほぼ80%以上となっている。大阪織物だけは,地域の割合でみても40%以下であった。同社の場合は,九州地域の株式の割合が総株式数の半ば近くを占めていた。
【213頁】明治31年時の分析では,90%を越える紡績会社が60社中23社であった事実,あるいは,95%以上の会社が60社中12社を占めていた事実と比較すれば,明治40年の時点で90%以上を占める紡績会社が32社中4社であることから,株主の分散は進んだと言えよう。株主の地域分布で見ても,日本絹綿紡織,鐘淵紡績,大阪織物,日本紡績,堺紡績では,地域的な広がりが確認できる。換言すれば,東京,大阪に所在地のあるこれら紡績会社では株主の地域分散が進んだ一方,地方の紡績会社では,明治40年の時点でも,地域的な性格を残していた,と言えよう。
株式の地域分布では,株主以上に本社所在府県の株主の集中が,二三の例外を除いて高い。二三の例外とは,大阪織物,笠岡紡績,阿波紡績,そして大分紡績である。大分紡績では福岡県の株式保有が高かったが,それ以外の3社では,大阪と東京の株式保有が,株主の比率に比べて増加している。換言すれば,笠岡,阿波,大分紡績では大阪と東京の株主が保有する株式は相対的に大きな割合を示していた。
明治31年と違うのは,外国に居住している株主,そして日本で事業を行っている外国人株主が多く見られたことである。前者は,表の右端にある「その他」に含まれている。因みに,どのような国名があるか例示すれば,韓国,清国,フランス,そして孟買である。また後者では,多くの場合,神奈川県在住として記載されている外国人が株主として進出したことである。
以上から,合併の影響もあって,東京と大阪に本社を置いている紡績会社の株主および株式は,それ以外の会社よりも府県,地域分散が広がっていたことが分かる。それでは,こうした流動化した株式は誰が所有していたのであろうか。それについては,第3節において,多数の紡績会社の株式を保有していた,特に,東京・大阪在住の株主を検討することでアプローチすることとし,その前に株主の所得を算出してみよう。
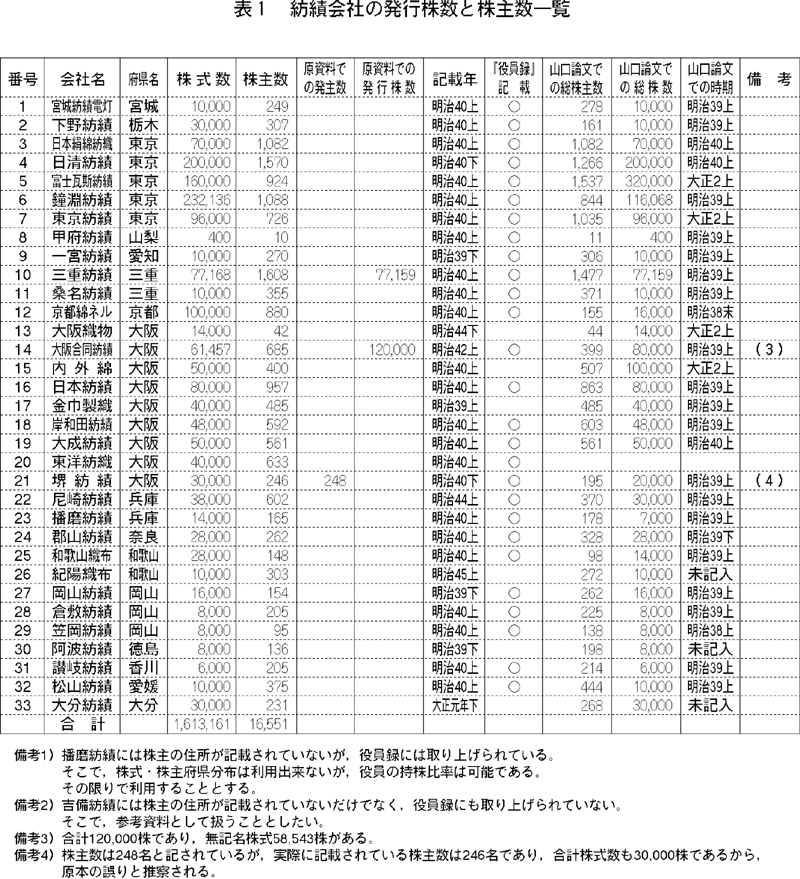
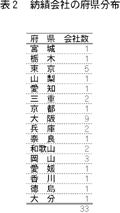
第2節 株主の所得
明治40年時点での所得額を推定するためには,いささか煩瑣な手続きを要する。まず,株主名簿と『明治40年 日本全国商工人名録』,この二つの資料を突き合わせて,人物の照合を行い,当該株主の所得税を確認する。次いで,当時の所得税率を基礎に,所得税から所得額を逆算するのである。こうした人物照合の手続きについてその詳細は,明治30年から明治40年にかけてしばしば改正された所得税法の変遷の概要とともに,本稿の末尾で説明することとし,ここでは所得税法で規定されていた所得税率を記すことからはじめたい。
明治31年時点では,所得が3万円以上(3%),2万円以上3万円未満(2.5%),1万円以上2万円未満(2%),1000円以上1万円未満(1.5%),300円以上1000円未満(1%)であった(注7)。明治40年では,10万円以上(20.35%),5万円以上10万未満(17%),3万円以上5万円未満(13.95%),2万円以上3万円未満(11.6%),1万5千円以上2万円未満【214頁】(8.1%),1万円以上1万5千円未満(7.5%),5千円以上1万円未満(6%),3千円以上5千円未満(4.6%),2千円以上3千円未満(3.91%),1千円以上2千円未満(3.45%), 5百円以上1千円未満(2.52%),3百円以上5百円未満(2%)であった。両年ともに,所得のすべてに同一の所得税が課せられる単純比例法であった。40年時における所得税法は,31年時のそれに対し,所得税の課税の所得基準が多くなったことと,増税が特徴的であった(注8)。
さて,われわれは,株主名簿に記載されている人物と『明治40年 日本全国商工人名録』に記載されている人物のうち,同府県に居住している同姓同名の人物を抜き出した。該当する人物が1人の場合には,そのまま同一人物と見なした。同じ府県に同姓同名の人物が複数在住している場合には,そのすべての人物について住所と家業等を調べ,特定出来る場合には,同【215頁】一人物と見なし,特定できない場合には,所得水準を求めるデータから除いた(詳細は,本稿の最後に記してある)。こうして求められた人物は,全株主の16,385名中3,439名(21%)である。
こうして同一人物と見なした人物だけのデータから,紡績会社ごとに株主の所得分布を求めたものが表11と表12である。明治31年と40年との間で経済の変化,所得税の変化が与える影響などを無視し,単純に比較してみると,明治31年では,60社の平均所得は3,300円であるが,明治40年では2,100円である。厳密な比較ではないものの,また『明治40年 日本全国商工人名録』から判明される人物に限定した場合であるが,明治31年に比べて,明治40年の株主の所得は低下していた。
表12の株主の所得分布を見ても,明治31年とは異なり,3万円以上の所得層が1人しかいないことからも,所得水準の低下を裏付けている。一方で,300円から500円層の低下も著しい。高所得者層と300円から500円層の低下が見られた。その反面,500円から1,000円層,1,000円から2,000円層の割合が著しく増加したのである。500円から2,000円層の人々が積極的に紡績会社の株式を所有していたのである。500円から2,000円台の所得層は,明治31年時点でも大きなウエイトを占めていたが,明治40年段階ではそれが一層顕著になったと言えよう。
しかも,表11および表12から,32社の株主の平均所得を見ると,大阪織物を除くと,す【216頁】べての紡績会社の株主の平均所得は1,000円台と2,000円台であった。明治31年では,平均所得が1万円以上の紡績会社が2社,5,000円以上の会社が10社,合計60社中12社の株主の平均所得が5,000円以上であった事実と比べると,この点から見ても,平均所得の低下を確認できる。
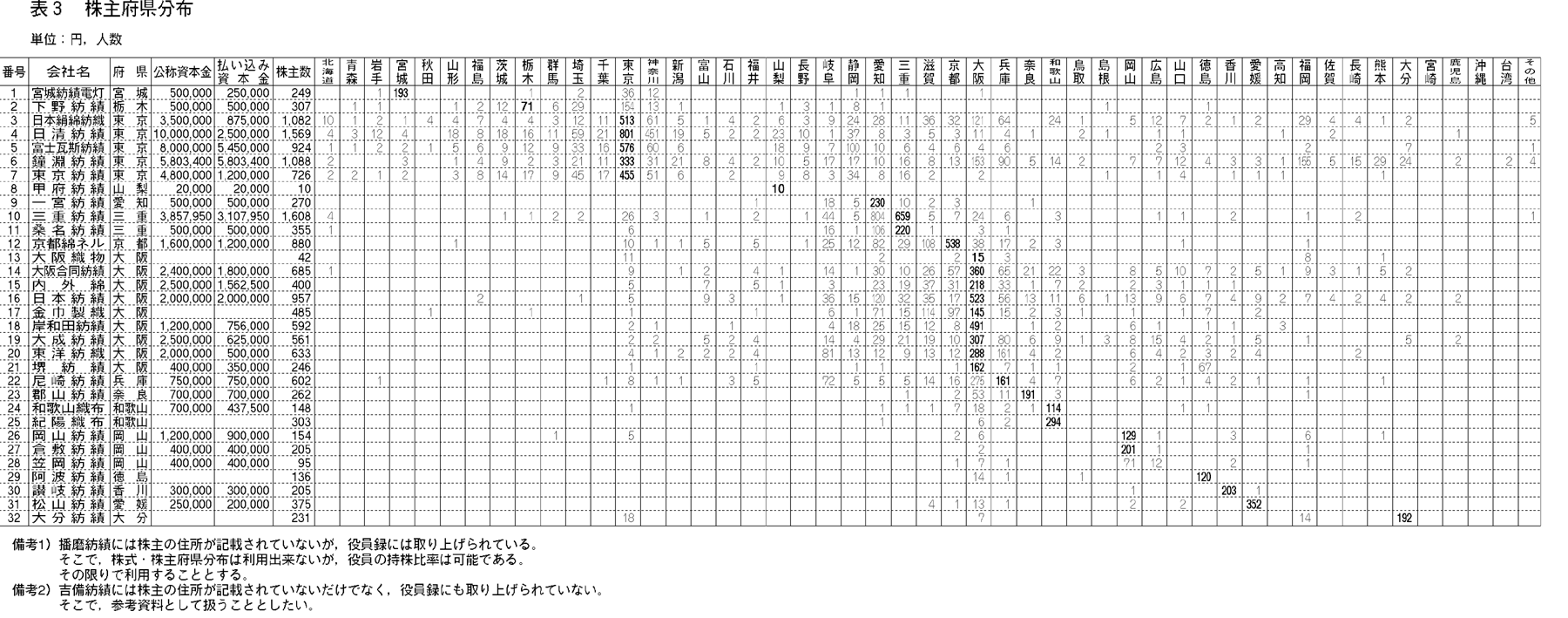
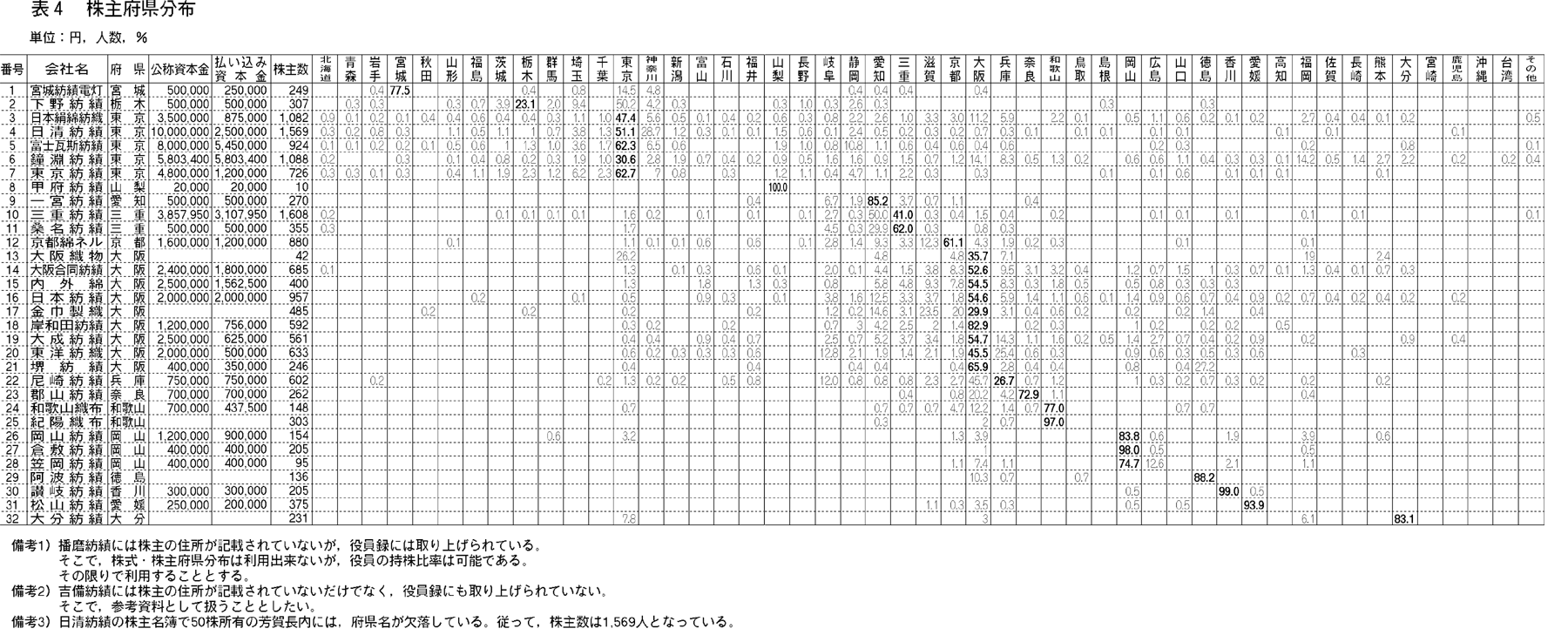
第3節 紡績会社役員の株式保有
第3の課題は,前稿と同じで株主と役員の関係を分析することである。再録すると,「大株主がそのまま紡績会社の役員に就任していたのか,あるいは,役員に就任していた株主は所有株数とは密接な関係を持っていなかったのか,という問題に答えることである。複数の大株主が,共同して会社経営に携わったのか,あるいは,大株主と並んで経営的才覚を持った人物を会社経営に取り込んでいたのだろうか。前者であれば,会社の発起人=大株主=会社役員という直線的な関係が理解できよう。後者であれば,会社の発起人=大株主→大株主と「専門経営者」の共同による経営という関係が浮かび上がって来る。特に,所有株数は少ないものの,彼ら「専門経営者」としての才覚を有している人物を役員に「登用」したものだと言えよう。とすれば,大正期に入って広く見られるようになった学卒者による「専門経営者」の台頭という現象の先駆的な形態を有していると評価できよう。」(注9)
【217頁】表14には,最大株主の氏名と所有株数・比率をはじめ,5大株主の氏名と所有株数・比率,さらに10大株主,20大株主までの所有株数と比率が記されている。発行株数が10万株以上の日清紡績,富士瓦斯紡績,鐘淵紡績,京都綿ネル,それに9万6千株の東京紡績を含めた5社の,5大・10大・20大株主の各所有比率の平均を求めると,それぞれ22.6%,31.1%,41.9%であった。また,発行株数の極端に少ない甲府紡績を除いた32社について,同じ平均を求めると,27.2%,38.5%,51.5%となる。発行株数の大きい上記の5社が,全体の平均よりもかなり低く,それだけ株式の分散が進展していたといえるのである。
次に,表15より,役員の持株順位を見ておくこととしたい。紡績会社の役員はどれだけの株式を所有していたのだろうか。また,株主全体の中でどのような位置にいたのであろうか。大株主であったのだろうか,それとも,大株主以外から役員として登用されていたのであろうか。これを見たのが同表であり,紡績会社の役員が,株主の中で占める位置を記載したものである。「役員数」に記されている役員が,株主名簿の中で,上位からどの位置にいるのかを見たものである。例えば,役員の株主順位①というのは,役員の中で所有株数が第1位の株主を示し,その役員が株主の中で上位から何番目にいるのかを記したものである。具体的に説明しよう。日本絹綿紡織の欄でみると,役員数は10名で,「役員の株主順位⑤」の欄にある,12【218頁】というのは,上位の株主から数えて12番目の株主である,という意味である。また,この12が,「役員の株主順位④」,「役員の株主順位⑥」「役員の株主順位⑦」と同じであるということは,第4位と第5位,第6位,第7位の役員は同数の株式を所有し,上位から数えて12番目である,ということを示している。以下,同様である。
まず「役員持株合計」の比率について平均を求めておくと,さきほどと同じように日清紡績,富士瓦斯紡績,鐘淵紡績,京都綿ネル,東京紡績の5社平均では12.1%であった。また,甲府紡績と,「役員持株合計」不明の2社を除いた30社平均を求めてみると,22.4%であった。ここで鐘紡の比率が1.1%と著しく低いのは,専門経営者が役員に多数進出していたことが要因である(なお,この時点で武藤山治は一時期,鐘紡のリーダーの地位を離れている。「相場師」鈴木久五郎の鐘紡株買占めを契機とするものである。)。
鐘淵紡績の役員の持株順位は,他の紡績会社とは異なり,最も多くの株式を所有している役員の株主での順位は43位であった。しかも,最も少ない株式を所有している役員は559番目に位置していた。大株主が役員に就任していない事例である。ちなみに,第559位で34株所有し,監査役に就任していたのは平賀敏である。この他,日本絹綿紡織では121位(100株)の岩本述太郎が監査役に就任していた。日清紡績では,第102位(300株)の金平豊太郎が監査役に,第328位(100株)の呉錦堂が取締役に就任していた。また,富士瓦斯紡績では,第【219頁】116位(227株)の藤井諸照が監査役に,第204位(100株)の稲延利兵衛が取締役に就任していた。最後に大阪合同紡績では,第309位(20株)の藤本清兵衛が取締役に就任していた。
役員と株主の持株順位が,他の紡績会社と異なる鐘淵紡績の事例を詳しく見ておこう。筆頭株主の小笠原Y次郎は,株式会社十七銀行取締役,合名会社安田銀行庶務部長を勤めていたから(注10),安田財閥の名代であったと言えよう。第3位の株主に三井高保がいた。一方,第2位の富倉林蔵は株式仲買人であった。いずれも役員に就任していない。役員の中で最も多くの株式を所有していたのは,第43位(1,000株)の藤本清兵衛であった。第88位(400株)の岡本貞烋は取締役に,第135位(240株)の長尾良吉は取締役に,第146位(200株)の高辻奈良造は専務取締役に,第146位(200株)の山口武は取締役に,第146位(200株)の藤正純は取締役に,第146位(200株)の日比谷平左衛門は取締役会長に,第358位(60株)の筑紫三郎は監査役に,第358位(60株)の野崎広太は監査役に,第358位(60株)の清岡邦之助は監査役に,そして既述した第559位(314株)の平賀敏が監査役に就任していた。学卒者の役員が見られる。専門経営者については第4節で論じることとしたい。
上記のように,われわれは,紡績会社役員の株式保有について考察したが,ここで,ほぼ同【220頁】じ時期の鉄道会社役員の株式保有を考察した杉山和雄氏の研究(注11)を取り上げ,若干の比較を試みておくこととしよう。杉山氏の研究は,明治35年時ないし36年時における鉄道会社の役員の持株状況について調査・分析したものである。
この研究は,『帝国鉄道要鑑』に拠るものであり,役員(監査役を除く)227名に対して,所有株数の明らかなものは131名であり,不明の大部分は同資料の大株主名簿に記名されない中小株主である,としたうえで,次のように記している。まず,①役員の持株数による分布を見た結果,持株数1,000株以上の役員は54名で,131名の約40%,全役員227名の約24%である。次いで,役員の持株比率と持株順位を見ると,②前者,持株比率については,役員131名の95%は同比率10%に達せず,とくに32%は1%未満である。また③後者,持株順位も相対的に低く,役員227名のうち10大株主に名をつらねているのは85名,全体の37%である。
さらに,④各鉄道会社の経営陣全体ではどの程度の株式を所有しているかといえば(上記資料の大株主名簿に記載されない役員の持株は無視される),鉄道会社の7割では,大株主に名をつらねるほどの経営者の持株数を合算しても,各社株式総数の約10%に満たない,として【221頁】いる。
発行株数や株主数が違い,また,業態が異なるので単純な比較は危険であるが,杉山氏の考察結果①~④と,われわれの調査結果を敢えて比較してみると次のとおりである。(持株合計が不明な4社を除いた29社を取り上げた)役員(監査役を含む)数は221名である。その中で所有株数が分かる役員は220名である。①役員の持株数によれば,1,000株以上の株主は,68名で220名の30.9%である。②役員の持株比率と持株順位を見ると,10%以上の持株を所有している役員は12名で5.5%を占め,5%以上では36人で16.4%となる。また,1%未満の株主は67名で30.5%であった。③10大株主に名を連ねている役員は,116名で5.5%に達していた。鉄道に比べると,紡績業では大株主が役員に就任していたと言えよう。④役員全員の持株比率も,役員の全持株を全発行株式で除した全社平均では15.3%を占めていたのである。鉄道の役員よりは多くの株式を所有していたと言えよう。
以上の分析を前稿で扱った明治31年時点での数字を挙げて,比較をしておきたい。役員(監査役を含む)の数は457名である。その中で所有株数が分かる役員は448名である。①役員の持株数によれば,1,000株以上の株主は,32名で448名の7.1%である。②役員の持株比率と持株順位を見ると,10%以上の持株を所有している役員は14名で3.1%を占め,5%以上では62人で13.8%となる。また,1%未満の株主は92名で20.5%であった。③10大株主に名を連ねている役員は,256名で5.7%に達していた。④役員全員の持株比率も,発行株数【222頁】を役員数で割って全社平均を求めると18.5%を占めていたのである。明治40年における役員の持株は,明治31年に比べて相対的に二極分化が進んだことが分かる。すなわち,発行株数の10%以上を所有している役員数の割合と5%以上を所有している役員の割合は,明治31年時点より相対的に増加するとともに,1%未満の株式しか所有していない役員数も,20.5%から30.5%に増加したのである。
最後に,明治31年,明治40年時点での筆頭株主,5大株主,10大株主,20大株主の発行株式に占める割合の平均を記すと次のようになる。明治31年(明治40年)の筆頭株主の所有株式は,発行株数の9.6%(8.3%)であり,5大株主では23.8%(23.0%),10大株主では34.1%(32.6%),そして20大株主では46.1%(43.8%)であった。ここから分かるように,株主のレベルでは,筆頭株主から20大株主に到るまで,集中度はどのレベルでも低下していったことが分かる。すなわち,株主では持株比率が低下した反面,役員では5%以上の株式を所有している役員,10%以上を所有している役員ともに,相対的に増加していったのである。その一方で,1%未満の所有の役員層が増加していったことは注目すべきあろう。
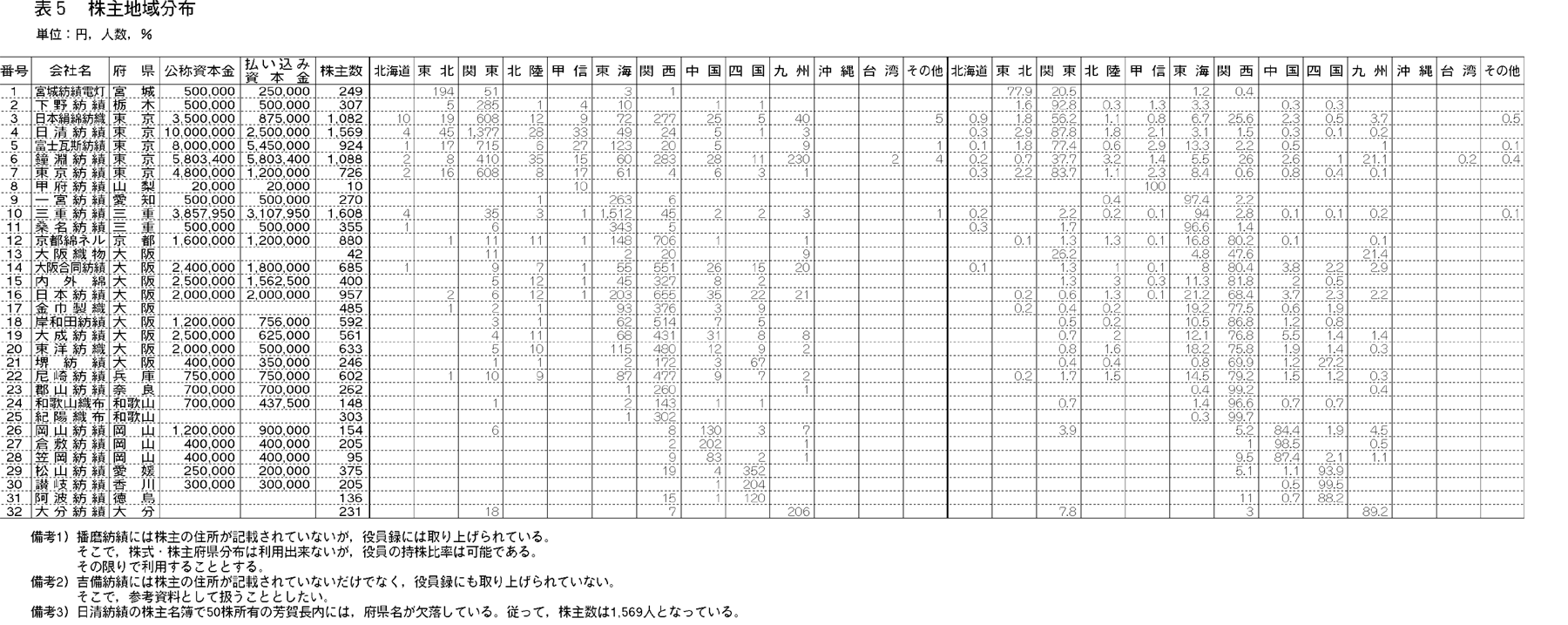
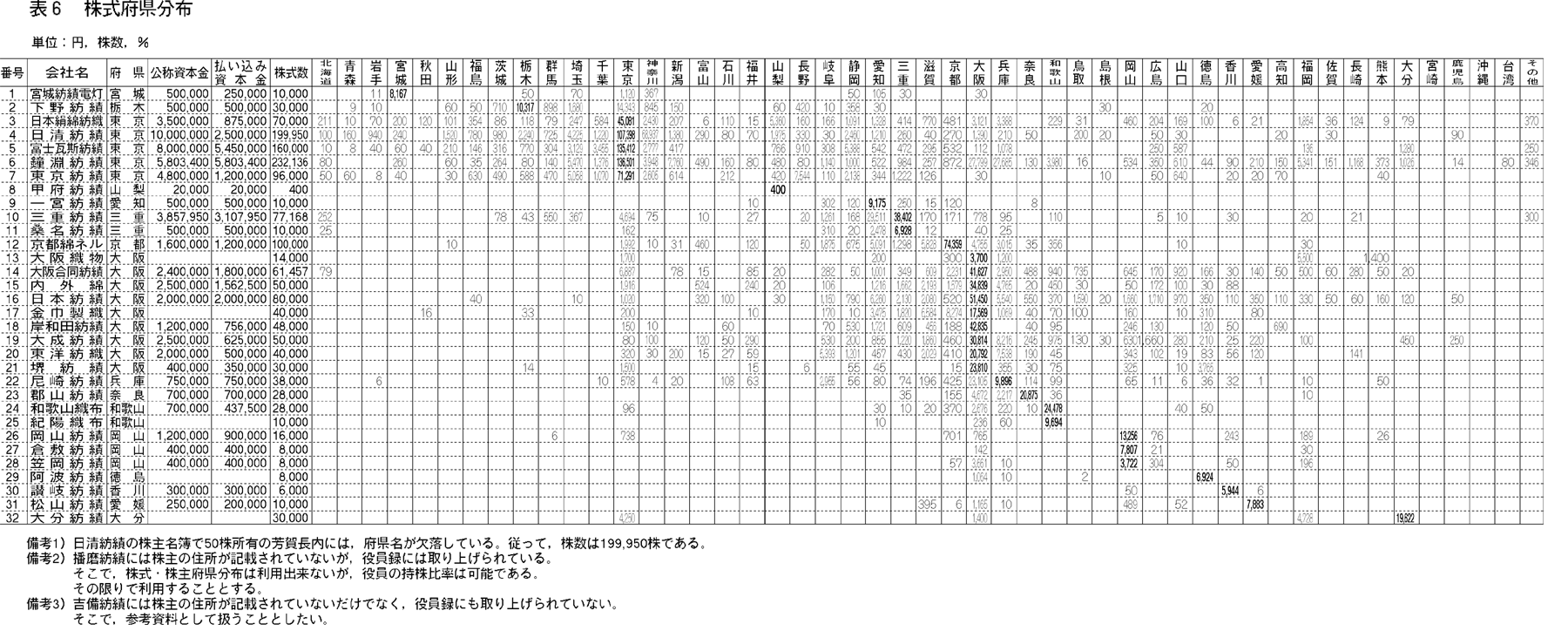
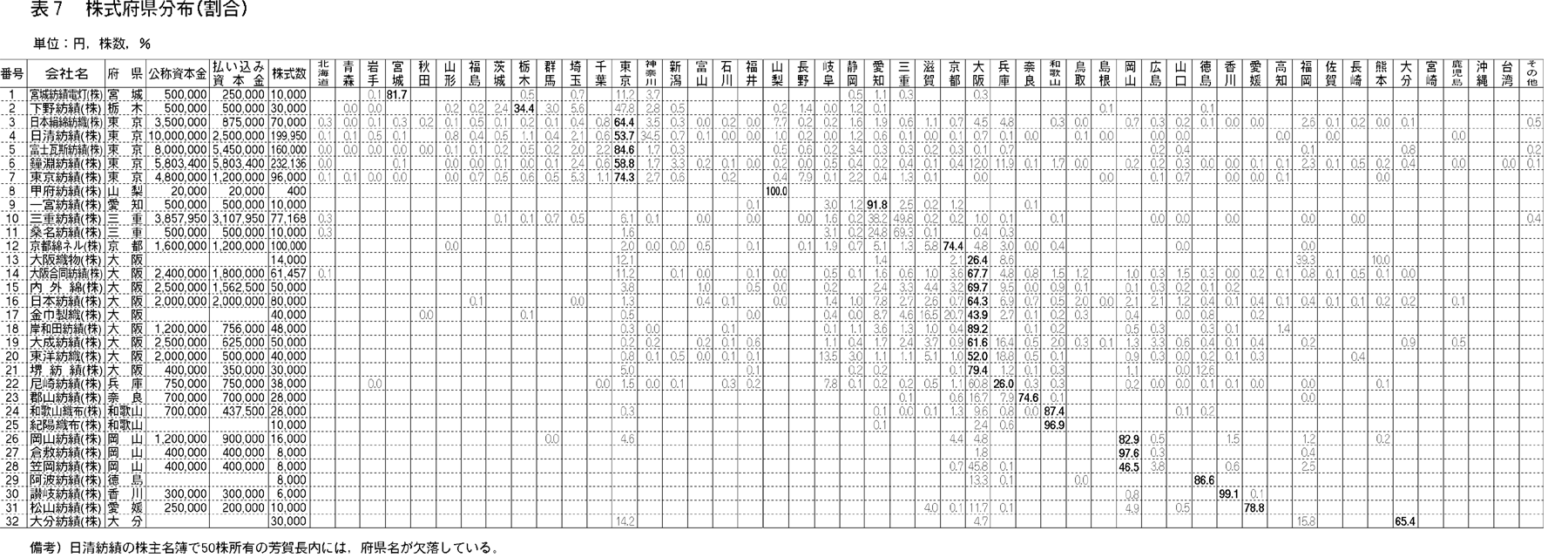
第4節 紡績会社株を多数所有している人物の特徴
紡績会社の株式を多数所有している人物を考察する際,これらの人物の特徴である,呉服太物木綿綿糸綿花商の存在,専門経営者の進出,株式仲買人の台頭という現象を指摘したのは西村はつ氏である。それでは,多数の紡績会社株を所有していた人物は,どのような人物であっ【223頁】たのだろうか。明治40年前後の時期の株主の動向については,西村はつ氏の研究がある。西村氏によれば,「(明治)31年当時最も大きな比重を占めていた『呉服太物木綿綿糸綿花商』つまり主として綿関係の商業を業とする株主が,39年,大正2年と進むにしたがって相対的に減少していることが知られる。もっとも,減少したのは『呉服太物木綿綿糸綿花商』だけでなく『米穀商』『その他の商業』『醸造業』を営む株主もその比重が低下した。これに反して『その他の会社銀行重役』の比重はいちじるしく高まり,『紡績会社重役』も相対的には比重を高めている」(注12)という特徴とともに,「日露戦後になると,紡績会社役員兼有力綿関係商の安定的投資による株式所有高の着実な増大と並んで,増減の激しい大株主として,証券業者が登場するにいたったのである」(注13)という特徴を挙げている。
この3つの特徴について,ここでは専門経営者の進出,株式仲買人の台頭の二つの面について特に,節を改めて論じることとした。周知のように,専門経営者の進出・制覇については森川英正氏の研究があり,株式仲買人の台頭については,西村はつ氏,志村嘉一氏,そして野田正穂氏の研究がある。そこで,専門経営者と株式仲買人に言及した研究に依りつつ,これらの研究で言及された人物に限定して,論を進めることにしたい。これらの人物が,紡績株をどれだけ所有したのかという事実を通して,この側面から専門経営者の進出,株式仲買人の台頭という問題を明らかにしておきたい。
【224頁】本稿で取り上げた紡績会社33社の株式を多数所有している人物について作成した表16と表17から,所有者と同時に紡績会社の特徴を考察することにしたい。表16は,5社以上の紡績会社の株式を所有している人物を会社の数が多い順に並べたものであり,表17は,2,000株以上所有している人物を所有株数の多い順に並べたものである。
5社以上の紡績会社の株式を所有している人物について,『明治40年 日本全国商工人名録』に記載されている家業のみならず,『人事興信録』に記載されている人物については,その特徴を記すことにした。
表16から分かるように,多数の株式仲買人が認められる。最大の12社の紡績会社の株式を所有していた野村徳七を始め,高木又次郎,柳広蔵,竹原友三郎,浜崎健吉,村瀬周輔,黒川幸七など多数を占めていた。明治40年時点における,紡績会社33社の分析で印象的な特徴である。この点は,西村氏がすでに指摘しているが,大株主中(「明治39年前後」紡績会社)の株式仲買人8人について,それぞれ所有する銘柄と株式数をとりあげ,「彼らが紡績株を有力な投資対象として選好していた」としている。8人の仲買人の名前を挙げておくと,福島浪蔵・柳広蔵・小池国三・外海鉄次郎・島徳蔵・島徳次郎・野村徳七・野本貞次郎らであった(注14)。われわれの調査からは,より広範囲の仲買人が紡績株所有を行なっていたことが確認できる。表16に記載されている76名中,職業が分かる人物は51名いる。その中で29名が株【225頁】式仲買人であった。表16の38%,職業が判明する人物では,実に57%もが株式仲買人であった。
また,第3節で記した,株主および株式の府県分布との関係から紡績会社を見ることとしたい。表16に登場する紡績会社数は延べ425社である。最も多くの人物が所有している会社は鐘淵紡績で45人,以下,20人以上の人が所有している紡績会社は,東洋紡織(41人),日本紡績(36人),尼崎紡績(31人),日本絹綿紡織(30人),富士瓦斯紡績(28人),大阪合同紡績(28人),東京紡績(25人),金巾製織(23人),日清紡績(22人),大成紡績(22人)である。
表16に登場する紡績会社は,第1節で記した発行株式数の多い会社と株主・株式の府県分散が進んでいる紡績会社に一致する。すなわち,株主の府県分布,株式の府県分布が拡散している会社と対応する。また,5万株以上発行している会社は,日本絹綿紡織(7万),日清紡績(20万),富士瓦斯紡績(16万),鐘淵紡績(23万2,136),東京紡績(9万6,000),三重紡績(7万7,168),京都綿ネル(10万),大阪合同紡績(6万1,457:記名株数),内外綿(5万),日本紡績(8万),大成紡績(5万)である。表16に多数登場する紡績会社は,5万株以上の株式を発行している会社であった。東京,大阪以外の地方で設立された紡績会社は,この表からは僅かに見られるだけである。すなわち,株式の分散が最も進んだ紡績会社であり,かつ,大量の株式を発行していた会社の株式が,多数の紡績会社株を所有している株主に所有されていたのである。
一方,西村氏は,明治39年前後の時期に8名(福島浪蔵,柳広蔵,小池国三,外海鉄次郎,【230頁】島徳蔵,島徳次郎,野村徳七,野本貞次郎)の持株状況を示し,大正2年前後の時期として13名(福島浪蔵,小池国三,柳広蔵,鈴木圭三,神田X蔵,今井又治郎,籾山半三郎,山内卯之助,野村徳七,野村実三郎,加島安治郎,島徳蔵,小川平助)の持株状況を示している。そこで,本稿が扱った32社の株主名簿でこれらの人物の紡績会社の株式所有状況を見たのが表18である。
また,本稿で扱った32社の紡績会社の株式を所有している株式仲買人について,野田正穂氏の『日本証券市場成立史-明治期の鉄道と株式会社金融』に登場する株式仲買人と照合してみたい。野田氏の著作「第5章鉄道株流通市場の展開」中の「第4節 証券業の機能とその発展」には,具体的な株式仲買人の名前が登場する。第5-14表「大阪現物商の鉄道株保有状況」には,竹原友三郎,黒川幸七,高木又次郎,野村徳七の4名が掲げられている(注15)。本稿で対象とした紡績会社の株主名簿にも,この4名が登場する。先の表17からも分かるように,野村徳七が12社,高木又次郎が9社,竹原友三郎が8社,黒川幸七が6社の株式を所有している。
また表5-15「1890年代末の銀行と仲買人・現物商との取引関係」(注16)に登場する仲買人・現物商は,神田X蔵,吉川金兵衛,福島浪蔵,田中勝之助,秋山幾太郎,渡辺勘三郎,今井文吉,野本貞治郎,小池国三,半田庸太郎,鷲尾銀四郎,山藤富次郎,藤田栄次郎,阿部鉄【231頁】之助,木島新吉の15名である。このうち,神田X蔵,吉川金兵衛,福島浪蔵,渡辺勘三郎,今井文吉,野本貞治郎,小池国三,半田庸太郎,藤田英次郎,阿部鉄之助の10名が株主として登場する。これを掲げたのが表19である。
さらに,『山一證券史』では,第4章証券業者の進出の第1節が「仲買人の成長と現物問屋の発生」と題され,東京株式取引所における株式仲買人の成長を扱っている。「東株仲買人は,取引所法が施行された(明治-鈴木)26年の末には70名に達していた。やがて日清戦争の好景気で株式売買が活発化するにつれて,株式仲買業もまた繁忙をきたし,売買高は年々増加し開業希望者が多かったので,29年末東株では仲買人定員数を70名から100名に増加したい旨申請を農商務省に提出している。当時の仲買人は総数68名であった。」(注17)しかし,株式市況は明治29(1896)年から反動期に入り,明治32(1988)年に始まった政府による取引所整理方針の影響によって仲買人の数は減少に転じた。その上に,勅令によって限月短縮令が公布され,株価は公布と同時に下落していった。そのため勅令の公布とともに株価は下落していった。そのため,東株仲買人は勅令実施延期期成会委員を選出した。その後も不振が続いたが,日露戦争を契機に株式市場は活況に転じ,「新規開業はとくに株価上昇のはげしかった(明治-鈴木)39年後半に集中し,開業16名,総数70名にまで回復し」(注18)たのである。
【232頁】さて,勅令実施延期期成会委員の顔ぶれと,彼らが本稿で取り上げた紡績会社の株式を所有していたのか否か,また『明治40年 日本全国商工人名録』に記載されているか否かをまとめたのが表20である。これによれば,20人中15人が,株式を所有し,かつ家業と所得税・営業税が判明する。所得税から算した所得が1万円を越える人物は5名いる。半田庸太郎,小布施新三郎,福島浪蔵,小池国三,藤田英次郎である。因みに15名の所得の平均は,7072円であるから,先に見た株主の所得分布と比較すると,高所得者の部類に属する。
最後に「専門経営者」の台頭という点については,森川英正氏の研究がある(注19)。上で述べてきた株式仲買人の他に,「専門経営者」が散見されるのである。一例として,著名な「専門経営者」ないし専門経営者出身の大株主経営者5人の株式所有状況は次のとおりであった。
飯田義一 日本絹綿紡織(350株),鐘淵紡績(418株),大阪織物(200株),大阪合同紡績(2,569株),堺紡績(1,500株)
菊池恭三 日本紡績(790株),東洋紡織(1,400株),尼崎紡績(2,121株)
和田豊治 日清紡績(100株),富士瓦斯紡績(2,500株),大分紡績(1,000株)
武藤山治 日本絹綿紡織(295株),鐘淵紡績(2,410株)
朝吹英二 鐘淵紡績(200株),大阪織物(200株),大分紡績(300株)
その他,森川英正氏が取り上げた専門経営者の中で,本稿が取り上げた紡績会社の株式を所有している状況と就任している役職については表21で取り上げた。この表21によれば,52名の専門経営者が株式を所有していることが分かる。菊池恭三の尼崎紡績,武藤山治の鐘淵紡【233頁】績,和田豊治の富士瓦斯紡績そして斎藤恒三の三重紡績のように,自らが役員として関与している会社の株式を所有している場合の他に,株主として紡績会社の株式を所有しているケースが多く見られた。
この点に関して,森川英正氏は,かつて,明治期の綿紡績会社における役員層の研究において,専門経営者が大株主化していくという事実を指摘しており(注20),上記はそのことを追認させるものである。とくに菊池恭三は,社長職にある尼崎紡績および東洋紡織においてそれぞれ3位,1位の大株主であった(日本紡績では取締役)。彼らは,実質的なリーダーである会社の大株主であっただけでなく他の紡績会社の株主でもあったという事実も確認しておきたい(注21)。
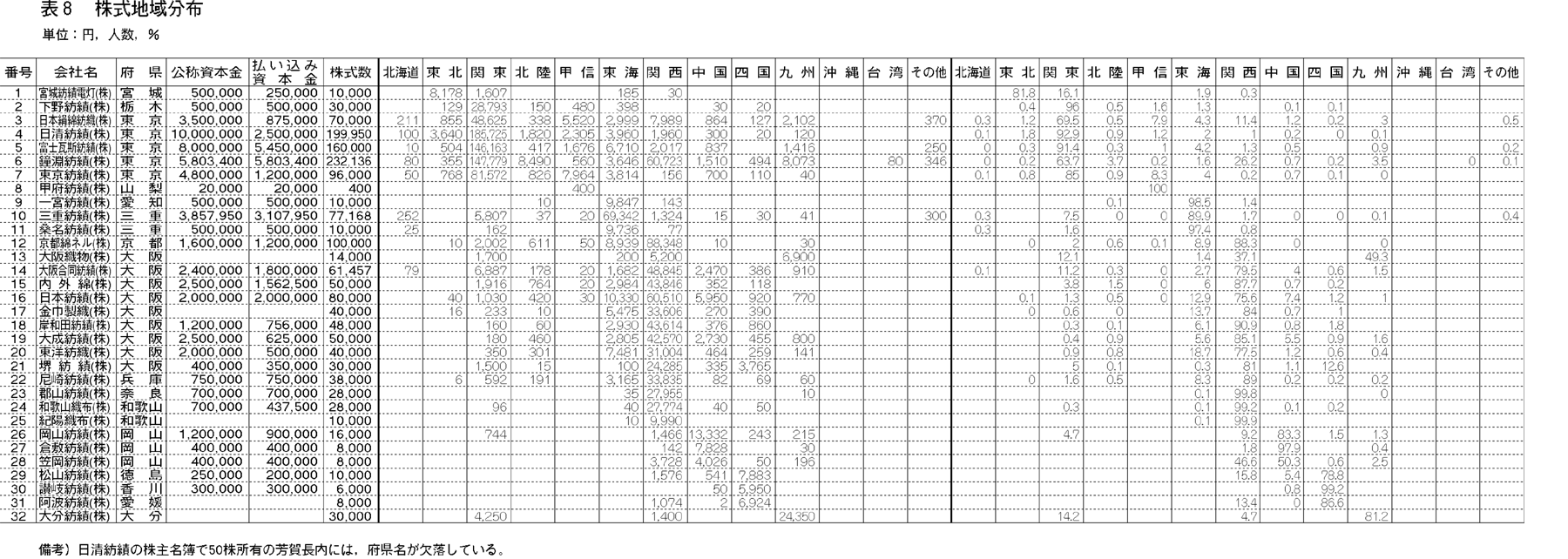
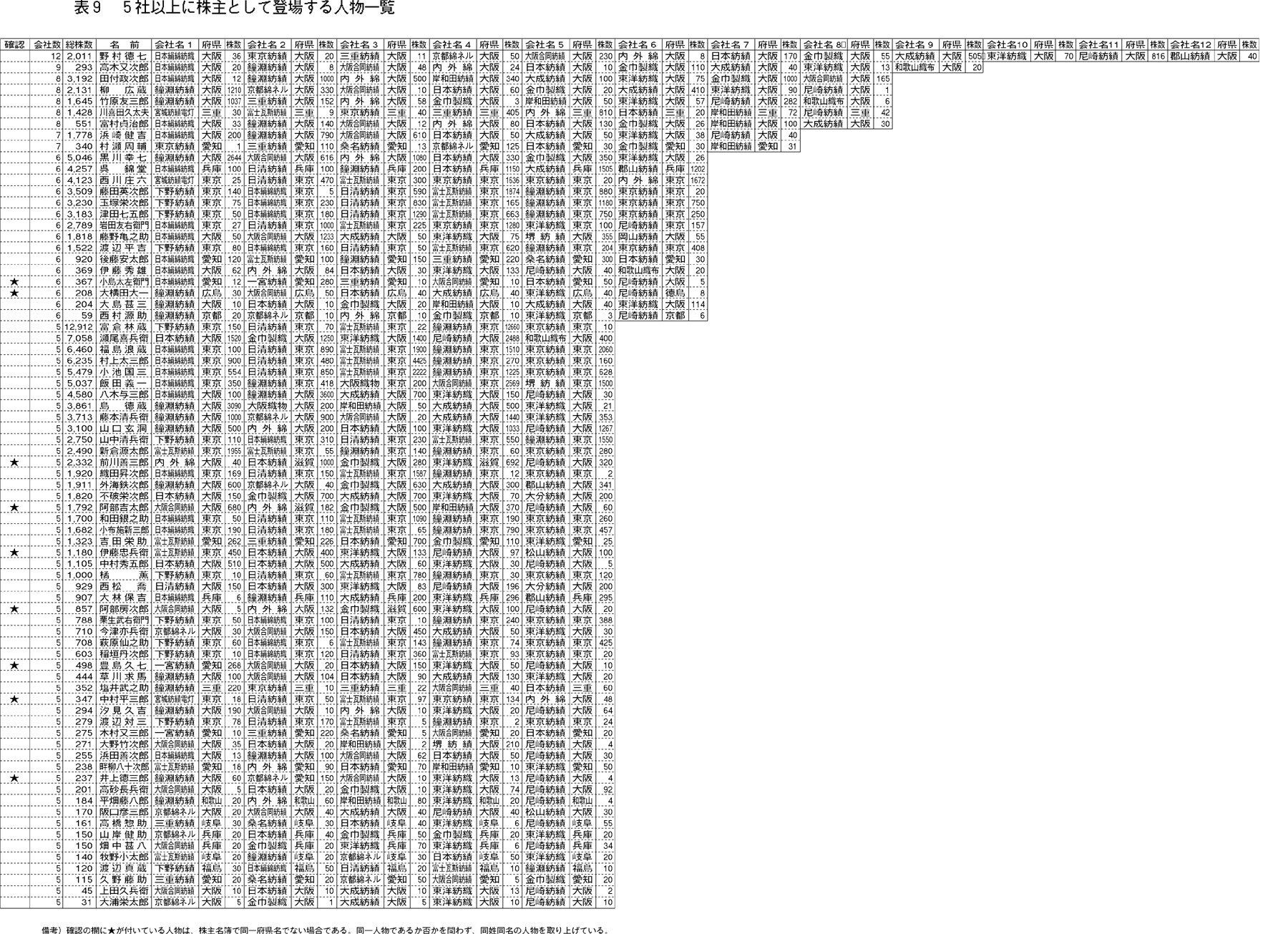
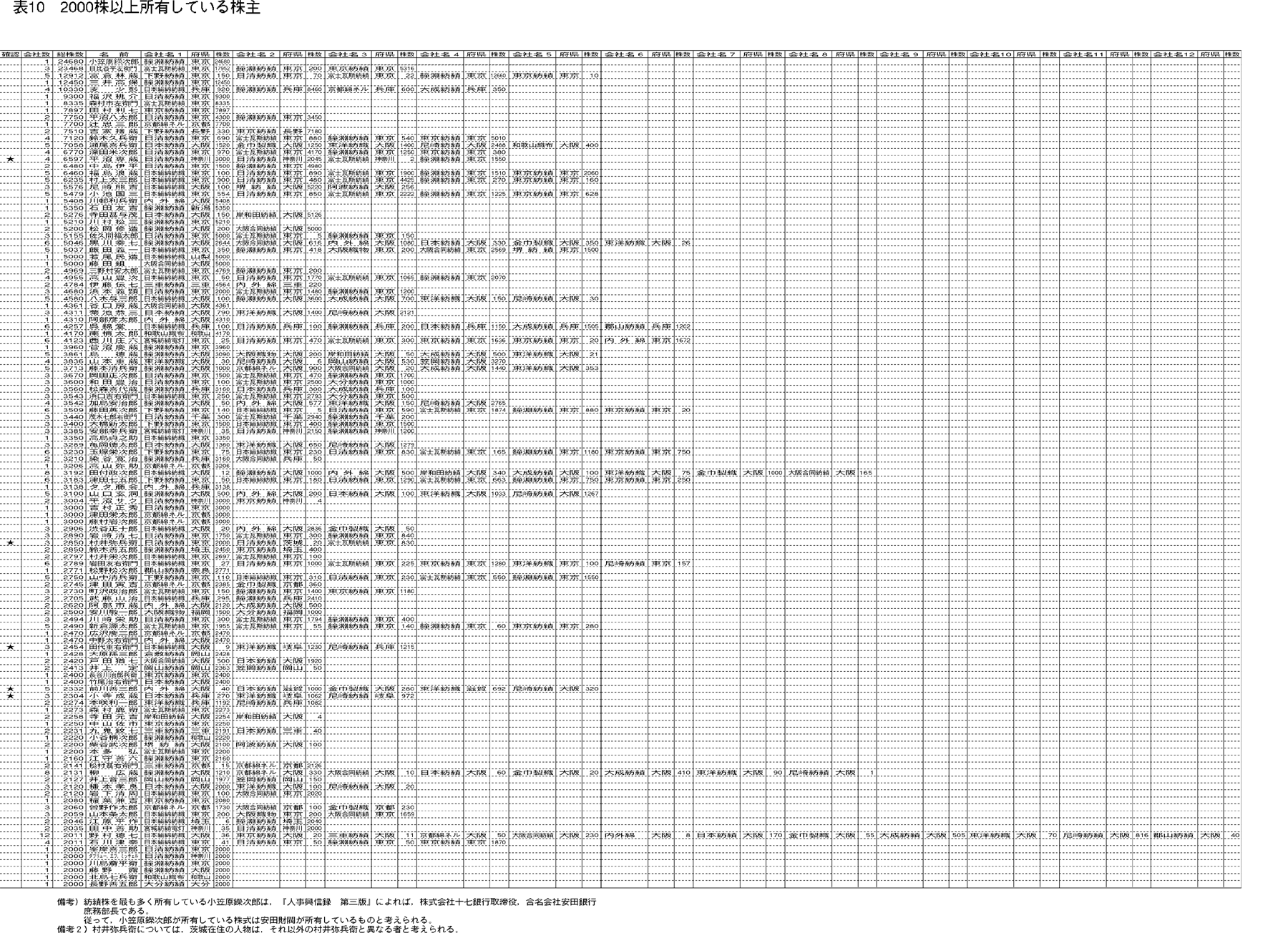
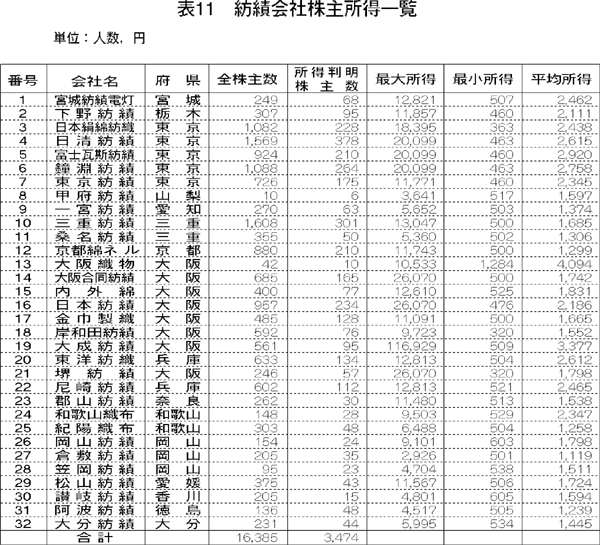
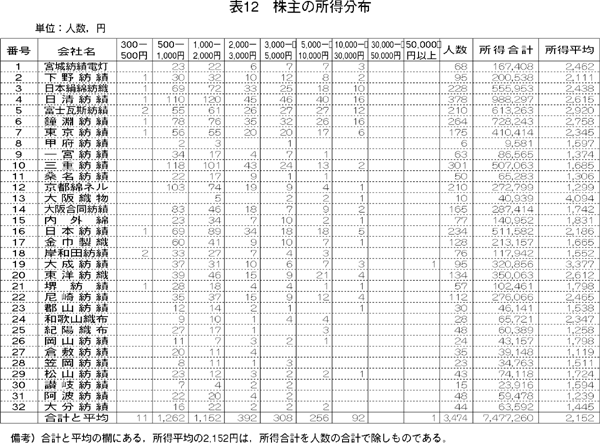

結 語
以上の分析を整理するとともに前稿の31年時との比較を行なうことで結語としたい。
第1に,株主と株式の府県・地域分布については,以下の知見が得られた。明治40年段階では,紡績会社の本社設立府県での株主と株式は最大であったものの,50%に満たない会社も散見される。下野紡績,鐘淵紡績,三重紡績,大阪織物,金巾製織,東洋紡織,尼崎紡績の7社である。株主が分散していったことが分かる。株式の場合も同様である。株式の府県分布では,下野紡績の他三重紡績,大阪織物,金巾製織,東洋紡織,尼崎紡績の6社は50%を割っている。その一方,鐘淵紡績は東京在住の株主が所有する株式は58.8%であった。東京,大阪に本店を置く紡績会社では,株主の分散は進んだものの,株式では集中していることが分かる。これは,東京,大阪在住の株主,殊に株式仲買人の台頭や専門経営者の進出に対応したものである。
第2に,株主の所得では,明治31年と比べると,大きな変化が見られた。まず第1点は,明治31年時点で見られた3万円以上の所得階層が激減したことである。明治40年では3万円以上の所得を上げている人物は滝川弁三ただ一人であった。
第2点は,所得分布において,500円から1000円層が最も多く,そして1000円層から2000円層がこれに次いだ。明治31年と比べると,明らかに相対的に低い所得階層の株主が多数を占めていたことである。
第3に,紡績会社役員の株式保有については,次のように言えよう。株式所有の多い順に株主を並べた場合,役員はどの位置にいたのだろうか。大株主を,今,上位10人を大株主とすれば,役員の平均で10位以上を占めるのは,一宮紡績,桑名紡績,大阪織物,岸和田紡績,大成紡績,東洋紡織,尼崎紡績,倉敷紡績の8社であった。逆に,役員が最も低い位置を占めていたのは,鐘淵紡績で226位であった。これに次いで,大阪合同紡績,富士瓦斯紡績,日清紡績,三重紡績,日本絹綿紡織が続いている。先に見た,専門経営者が所有している会社に対応すると同時に,専門経営者の進出が見られた会社でもあった。所有者から専門経営者への移【234頁】行が進んだ紡績会社であったと評価できよう。
最後に,株式仲買人の台頭と専門経営者の進出については,従来から言われている通りであるが,彼らが所有している紡績会社の実態と,その程度が明らかになった。殊に,東京と大阪で活躍している株式仲買人が紡績会社の株式所有に深く関与し,大株主として登場している場合(尼崎紡績の加島安治郎,鐘淵紡績の富倉林蔵)が見られた。一方,専門経営者では,自らが役員として関与している会社の株式を所有している場合の他に,紡績会社の株式を所有している場合が見られた。こうした中で,5大株主に顔を出している人物をあげると,三重紡績の斎藤恒三,東洋紡織の菊池恭三と田代重右衛門,尼崎紡績の浜本八二郎である。また富士瓦斯紡績の和田豊治は,第8番目の大株主であった。
先に掲げた表21に明らかなように,明治40年という時点において,多くの専門経営者の進出が見られたことは,改めて,彼らを登用した経営的意義を考える必要があろう。
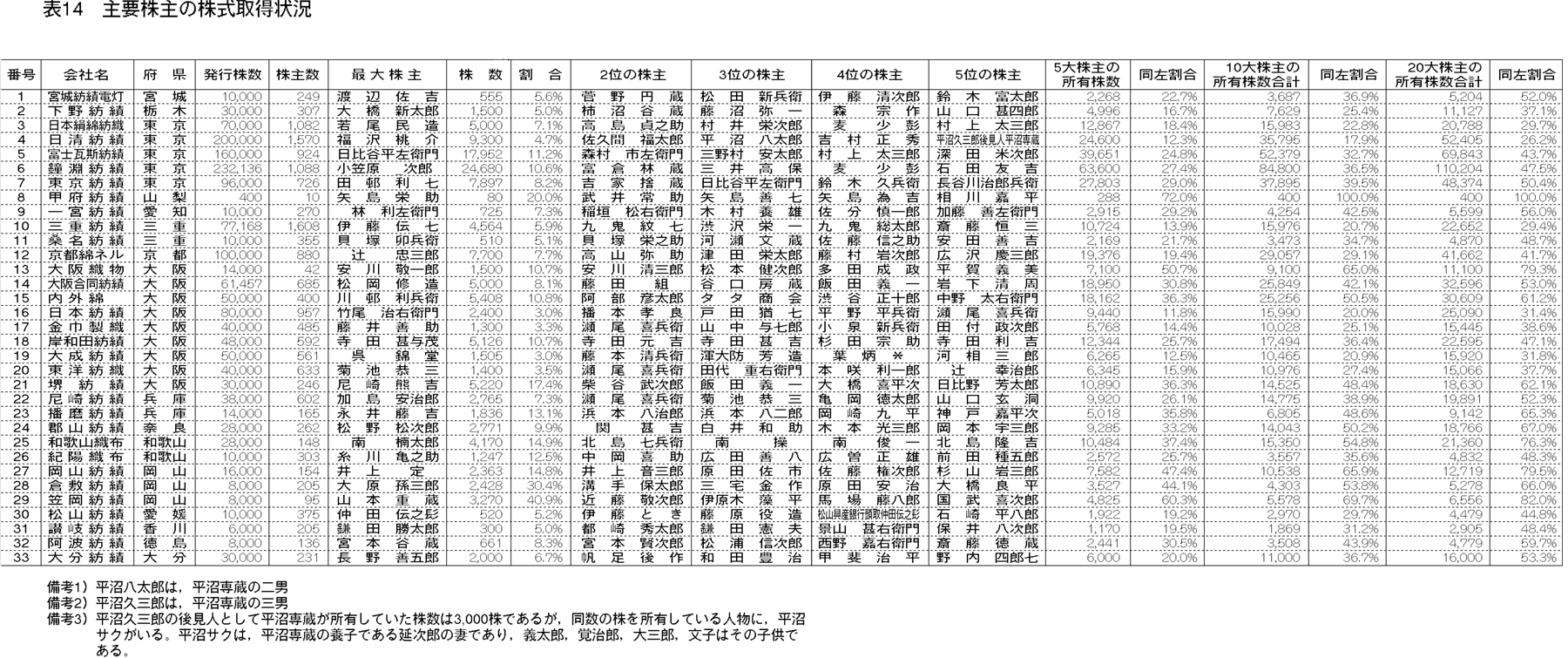
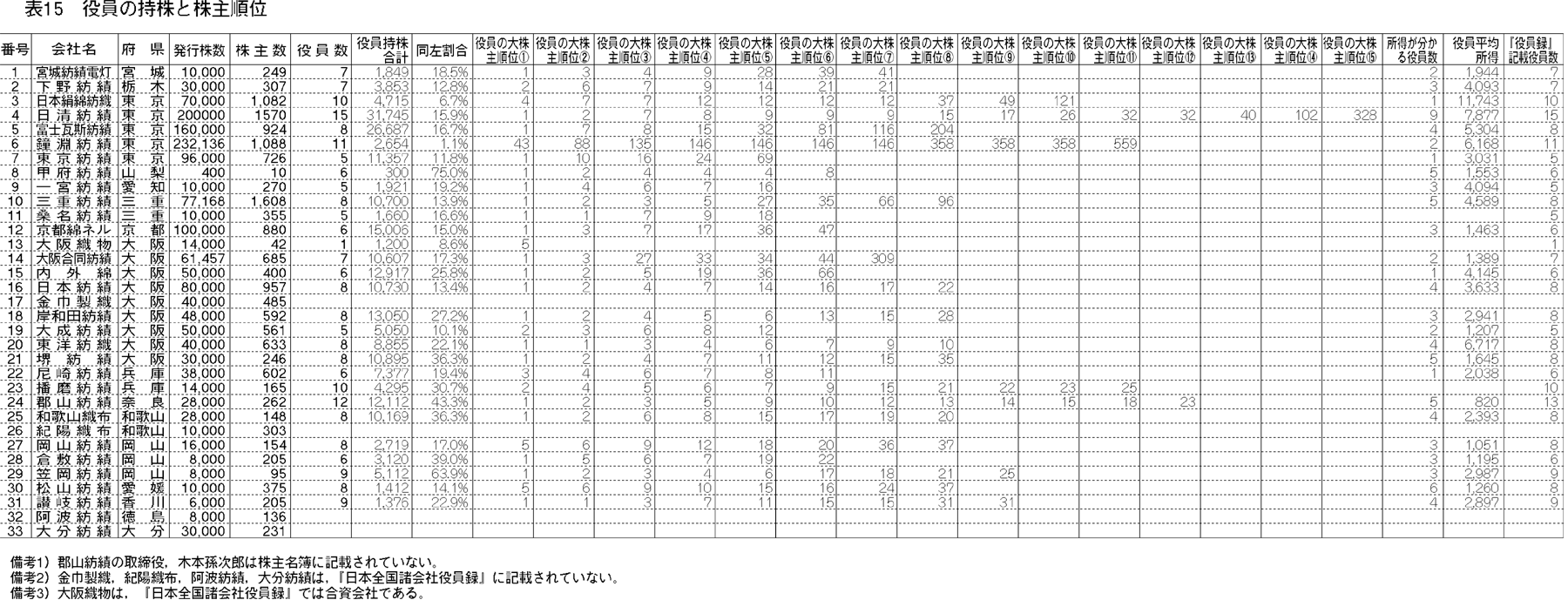
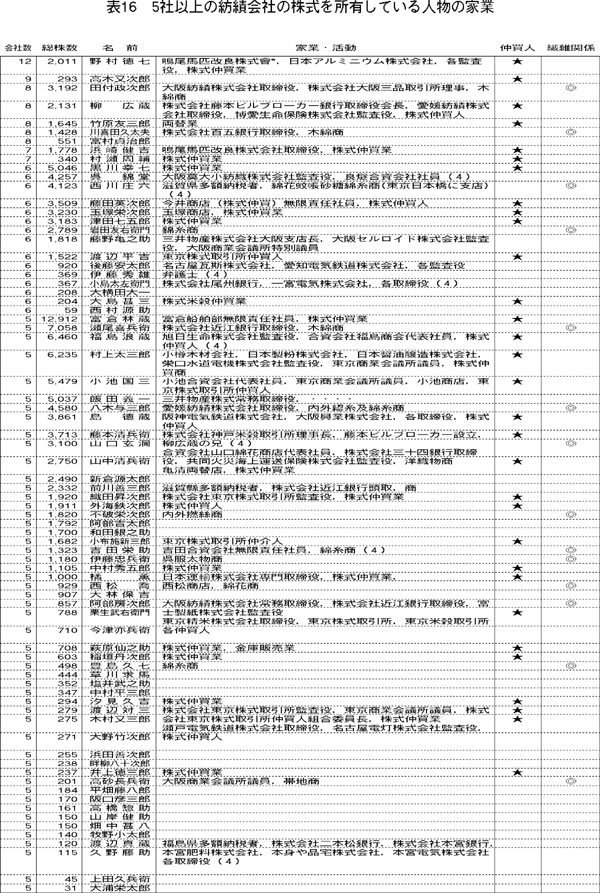
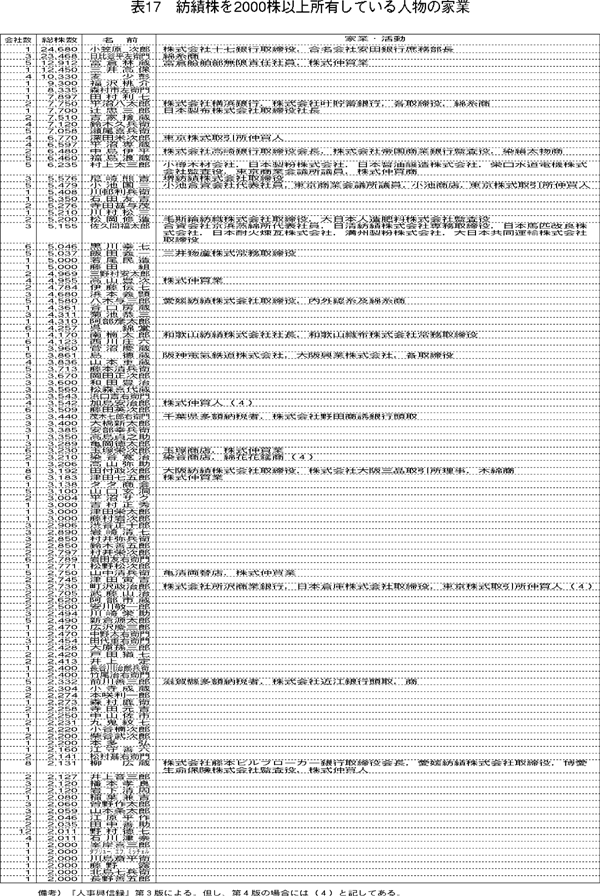
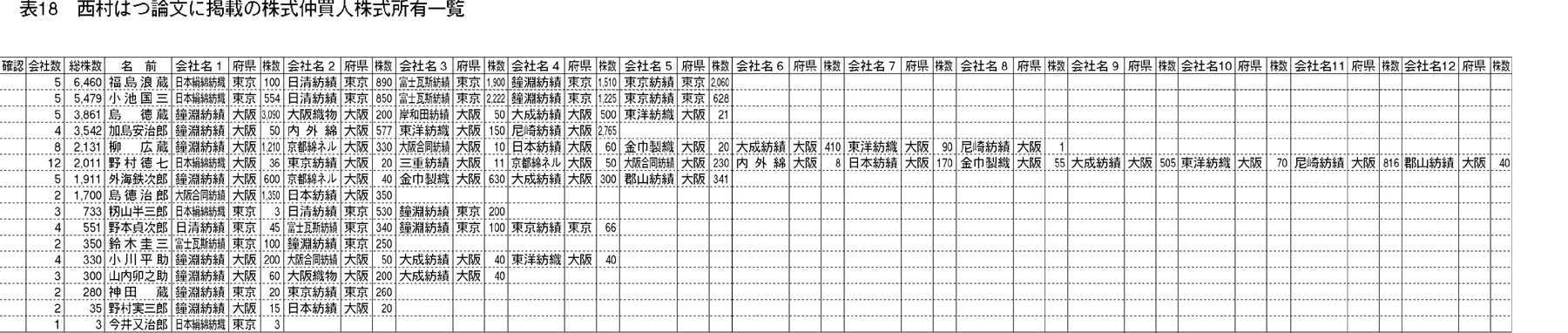
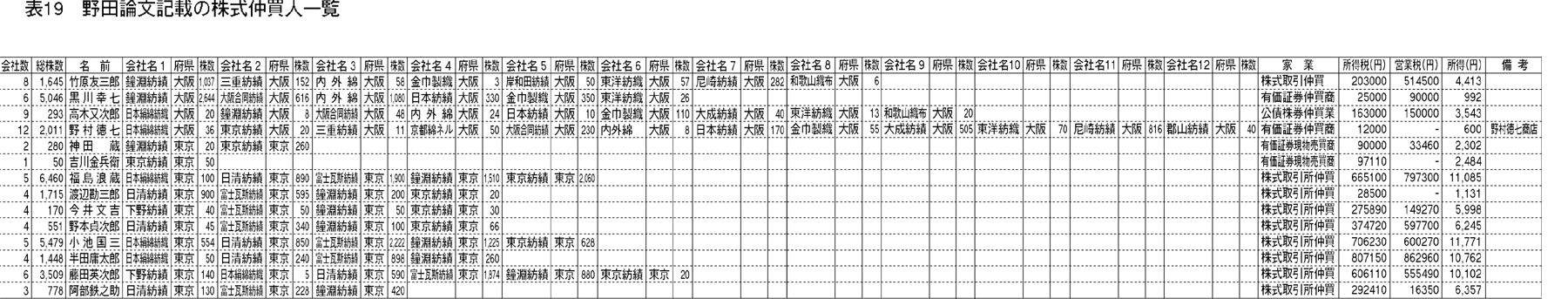
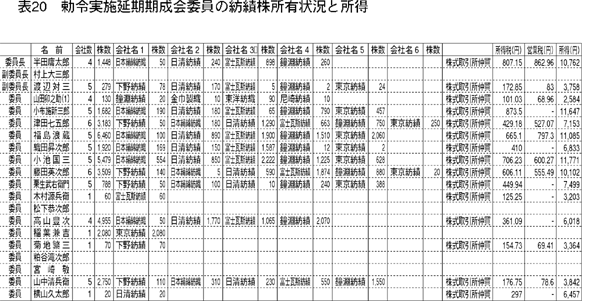
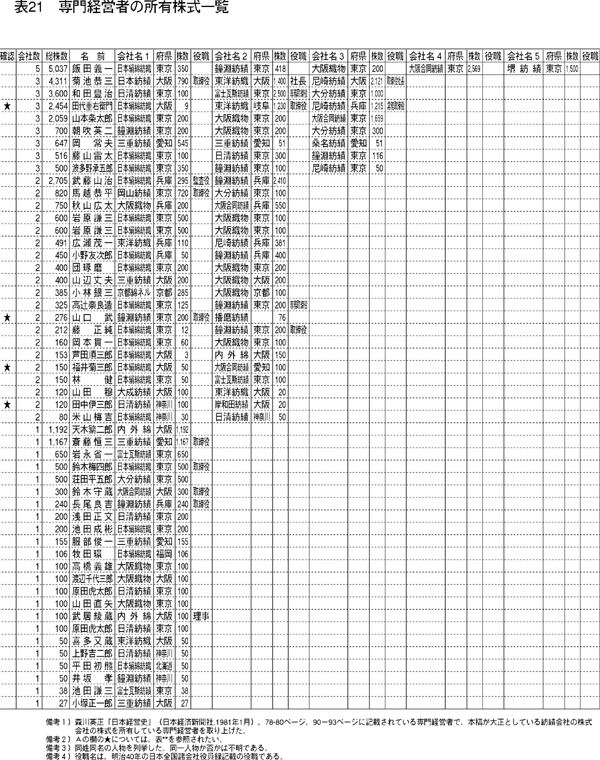
【243頁】
補 論
明治31年時についての前稿と同じように,山口和雄編著『日本産業金融史研究 紡績金融篇』巻末附録に記載されていない紡績会社について記すこととしたい。大阪紡織の1社が該当する。大阪紡織の実態は表22に示されている。
(1) 所得税の変遷
所得税法は,明治20(1987)年,3月23日,勅令第5号によってわが国で始めて導入された。資産あるいは営業より生じる所得が年300円以上である者に課せられることになったのである(注22)。
所得額に従って5段階に所得税の等級が別れ,それぞれに異なる税率が課せられた。具体的には,次の通りである(注23)。
第1級 所得金高 3万円以上 3%
第2級 所得金高 2万円以上(3万円未満) 2.5%
第3級 所得金高 1万円以上(2万円未満) 2%
第4級 所得金高 1千円以上(1万円未満) 1.5%
第5級 所得金高 300百円以上(1千円未満) 1%
それぞれの等級の税率は,所得金高すべてに,一律に課せられるものであった。そのため,等級前後では,税額に不連続が生じ,不公平感を招いた。例えば,9千9百円と1万円では,前者が148円50銭の所得税が後者では200円になる。100円の相違が50円以上の変化となる。限界税率が50%以上となるわけである。
その後,所得税は,大きく分けて3つの流れを伴った。第1は,増税基調の下で税率が上昇したことである。第2は,不公平感をなくすために5つの等級から,より多数の等級に分かられていったことである。第3は,全所得に当該等級の1つの税率が課せられる方式から,所得金額を各等級区分し,それぞれに異なった税率が適用される,「逓次方式」への移行である。
明治32年2月13日,所得税が改正(法律第17号)された。第1種の法人への所得,第2種の公社債の利子所得,第3種のその他の所得に分けられたのである。本稿が対象とする個人の所得は第3種所得に属することになった。
第3種の所得は,10万円以上から,300円以上まで12段階に分けられることになる一方,税率も増加した。詳細は次の通りである。
10万円以上 5.5%
5万円以上(10万未満) 5%
3万円以上(5万円未満) 4.5%
【244頁】2万円以上(3万円未満) 4%
1万円以上(2万円未満) 3%
5千円以上(1万円未満) 2.5%
【245頁】3千円以上(5千円未満) 2%
2千円以上(3千円未満) 1.7%
1千円以上(2千円未満) 1.5%
5百円以上(1千円未満) 1.2%
3百円以上(5百円未満) 1%
所得税はその後,明治34年4月4日に改正(法律第17号)されたが,文言の修正であり,税率の変化はない。所得税にとっては,明治38年1月1日に公布された非常特別税法の改正(法律第1号)の影響が大きい。日露戦争の戦費調達を目的に非常特別税法が改正された結果,所得税に連動して非常特別税が課せられることになった。全面的な増税であった。その内容は次の通りである。
所得金額 5百円未満 所得税法による税額10割
所得金額 1千円未満 所得税法による税額11割
所得金額 5千円未満 所得税法による税額13割
所得金額 1万円未満 所得税法による税額14割
所得金額 1万5千円未満 所得税法による税額15割
所得金額 2万円未満 所得税法による税額17割
所得金額 3万円未満 所得税法による税額19割
所得金額 5万円未満 所得税法による税額21割
所得金額 10万円未満 所得税法による税額24割
所得金額 10万円以上 所得税法による税額27割
その結果,先の明治32年に改正された所得税に,以上の非常特別税を加えると,次のような税体系となった。
10万円以上 5.5% →20.35%
5万円以上(10万未満) 5% →17%
3万円以上(5万円未満) 4.5% →13.95%
2万円以上(3万円未満) 4% →11.6%
1万5千円以上(2万円未満) 3% →8.1%
1万円以上(1万5千円未満) 3% →7.5%
5千円以上(1万円未満) 2.5% →6%
3千円以上(5千円未満) 2% →4.6%
2千円以上(3千円未満) 1.7% →3.91%
1千円以上(2千円未満) 1.5% →3.45%
5百円以上(1千円未満) 1.2% →2.52%
3百円以上(5百円未満) 1% →2%
これが明治40年時点での所得税率であった。
【246頁】所得税はその後,大正2年4月8日に改正され(法律第13号),先にしるした逓次方式による課税方式が導入された。また所得税が課せられる最低所得はそれまでの300円から400円に引き上げられた。税率は次の通りである。
1,000円以下 2.5%
1,000円超 2,000円以下 3.5%
2,000円超 3,000円以下 4.5%
3,000円超 5,000円以下 5.5%
5,000円超 7,000円以下 7%
7,000円超 1万円以下 8.5%
1万円超 1万5,000円以下 10%
1万5000円超 2万円以下 12%
2万円超 3万円以下 14%
3万円超 5万円以下 16%
5万円超 7万円以下 18%
7万円超 10万円以下 20%
10万円超 22%
(2) 同一人物の特定手順
「株主名簿」と『明治40年 日本全国商工人名録』に記載されている人物が同一人物であるのか,異なった同姓同名の人物なのかは,次の手続きに従った,
① 両者が同姓同名であり,かつ住所が同一府県であって,該当する人物が1人の場合,同一人物とみなした。
② 両者が同姓同名であり,かつ住所が同一府県であって,該当する人物が複数いる場合には,個別に同一人物であるか否かを判定した。
(1) 歴史上著名な人物で,家業などが判明している場合には,抽出したデータから,当該人物を選んだ。
(2) 異なった家業であっても,類似した家業である場合(例えば,白米商,米穀問屋)には,同一人物と見なし,所得税の多い方を基準に所得を算出した。
(3) 異なった家業であっても,住所が市町村郡レベルで同じで,所得税が同じ場合には,同一人物と見なした。
(4) 異なった家業であっても,一方の家業が金銭貸付業の場合には,同一人物の副業と見なし,同一人物と見なした。所得税の多い方を基準に所得を算出した(注24)。
(5) 家業も住所も異なっており,かつ所得税が異なっている場合には別人と見なし,所得の算出からは除外した。