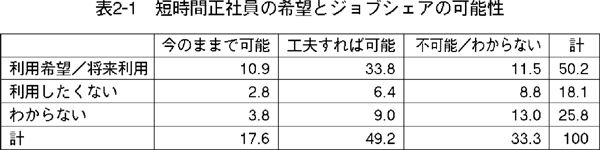
【265頁】
短時間正社員と正社員の仕事の分割可能性についての分析
脇坂 明
はじめに
多様な働き方の選択肢を拡大する多様就業型ワークシェアリングの推進が,現在の日本にとって,大きな課題のひとつとなっている。そのさいに,短時間正社員が重要なポイントとなっている。時間の短い働き方が多様就業に必要なことはいうまでもないが,単なるパートタイマーであれば,現に就業機会は多くある。問題は,あるレベル以上の技能やスキルを必要として,それが短時間で可能であるかどうかにかかっている。
最新の調査である「多様就業型ワークシェアリング制度導入意識調査・制度導入状況実態調査報告書」(生産性本部調査と略)によると,「現時点」で短時間正社員を希望する者は37.3%,女性で52.4%,30歳台女性で62.4%である(注1)。子育て期の女性に多いが,30歳台男性でも21.7%と2割以上が希望している。企業の制度導入状況をみると,正社員の所定労働時間を一時的に短くする短時間正社員制度は28.0%,一時的でない短時間正社員制度は6.5%である。本稿で後に詳しく検討する「ジョブシェアリング」(ある仕事を他の誰かと2人で労働時間を分担しつつ行い,評価・処遇も2人セットで受ける働き方)は1.2%,検討中2.6%を加えても5%にも満たない。潜在的に希望は多くとも,企業そして職場で短時間正社員を普及させるのに多くの困難を抱えていることが予想される。
本稿では,2つの調査の個票を用いて,短時間正社員制度とくにジョブシェアリングがどのような職種に可能で,どのような職種で難しいかを分析する。
1 企業はどのような職種でジョブシェアリングが可能と考えているか
厚生労働省が2000年に三井情報開発㈱総合研究所に委託して行った調査(以下,WS調査と略)を用いる。この調査は全上場・店頭公開企業に行った企業調査(有効回答867社)と勤労者調査からなる。短時間勤務制度のメリット・デメリットを企業と労働者に対して尋ねている。企業はメリットとして「有能な人材の確保や退職・流出の防止につながる」(46.8%),「【266頁】会社のイメージアップにつながる」(22.4%)と考えている。デメリットとしては「責任所在が曖昧になる」(36.9%),「生産性が低下する」(33.9%),「人件費が上昇する」(32.5%),「従業員の帰属意識が低下する」(28.4%)をあげている。また導入の難しさでは,「必要性の薄さ」「短時間であることによる業務遂行上の不都合」「働く側のメリットとのアンバランス」「制度構築・管理の煩雑さへの懸念」「評価・処遇の仕方の難しさ」等を挙げている。もっとも情報価値があると思われる,現在導入している企業(サンプル数:42)の回答では,「従業員の士気が向上する」「人件費が低下する」をメリットとしてあげている。デメリットとしては「生産性が低下する」(45.2%)を最も多くあげており,次いで「従業員の帰属意識が低下する」をあげている。
一方,労働者はメリットとして「余暇活動のための時間が増える」(46.6%),「育児と仕事が両立できる」(37.4%),「能力開発など自己啓発の時間がふえる」(36.2%),「介護と仕事が両立できる」(18.5%)をあげている。デメリットには「賃金や退職金の取り扱い」(72.7%),「強制的に適用されることを危惧」(27.7%),「昇進や昇格の取り扱い」(19.3%)をあげている。
この節では,企業調査を用いて,どのような職種に短時間勤務やジョブシェアリングが広がる可能性があり,どのような職種で難しそうかを考えてみよう。
1-1 短時間勤務制度(短時間正社員制度)導入企業
まずWS調査における短時間正社員制度(注2)の導入・検討状況を簡単にみておこう。現在,導入している企業は4.8%(42社)で,検討中(1.3%)を含めても1割にほど遠いが,今後検討したい(35.4%)を加えると半数近くになる。5000人以上の大企業で導入企業,検討中を加えると2割を超える。短時間勤務の具体的形態としては,導入企業では「1日の労働時間短縮」が85.7%と大半を占め,「勤務日の減少」は33.3%と3分の1の企業になる。「長期休暇制度の導入」は19.5%と約2割である。「今後検討したい」企業では,逆に「勤務日の減少」が56.4%と「1日の労働時間短縮」51.6%を上回る。
1-2 どのような職種に向いているか
WS調査では,短時間正社員制度がどのような職種に向いた制度かを企業に尋ねている。事務職(34.0%)がもっとも多く,ついで専門・技術・研究職(23.2%),生産・現業職(21.8%)となる。上記の職種の回答以外に,対象者を限定しないという回答が20.1%もある。ゆえに,それぞれの職種についての数値は,この2割を加えたものが当該職種で可能だとする回答企業の割合となる。一方,どの職種にも向いていないとするのは10.3%なので,9割は何らかの職種で可能だとしている。
販売営業職が9.9%と予想に反して少ない。とくに販売職は実際のパートタイム勤務では,圧倒的に多い。業種の影響が大きいかどうか調べてみよう。調査対象の業種をみると製造業が51.1%と半数以上をしめる。つぎに多いのが卸小売業,飲食店の19.1%である。販売営業職をあげる割合が,この2業種によって異なるかどうかみてみよう。製造業で4.9%(対象者を限【267頁】定しないは24.2%),卸小売業,飲食店17.4%(対象者を限定しないは18.0%)である。販売営業職だけとると製造業での可能性がかなり低いが,対象者を限定しない企業を加えると,それほどの差はない。ちなみにどの職種にも向いていないとする割合は製造業で10.7%,卸小売業,飲食店で8.7%である。
管理職が短時間勤務にむいているとした企業(正確には対象者を限定しない企業を除く)は,3.5%(30企業)と少ないが,どのような企業であろうか。30企業のうち11企業(36.7%)を卸小売業,飲食店が占める。卸小売業,飲食店全体の6.8%をしめる。製造業は9企業で全体の2.1%にすぎない。シフト勤務が多い小売,飲食店の影響とも考えられるが,対象者を限定しないを加えると(管理職も含まれていると考えると)製造業が多くなるので,解釈には慎重でなければならない。
1-3 ジョブシェアリング
WS調査では,ジョブシェアリング(注3)の可能性について尋ね,またどのような職種に向いた制度かを企業に尋ねている。
可能性については,「ほとんど導入できる可能性はない」(61.2%)がもっとも多いが,「職種によっては導入できる可能性がある」企業が34.5%と3社に1社存在する。さすがに「全社的に導入できる可能性がある」という企業は0.6%であるが,職種によっては可能だという点がポイントであろう。産業別にみると,金融保険業や不動産業で4割以上の企業が職種によって可能だとする。一方,電気・ガス・熱供給・水道業が2割以下で少ない。
つぎにジョブシェアリングがどのような職種に向いた制度かをみると,特定職種をあげた企業では,生産・現業職が24.3%ともっとも多く,事務職(21.5%),専門・技術・研究職(17.9%)とつづく。職種を限定しないという回答が5.5%と少ない。一方,どの職種にも向いていないとするのは35.3%と約3分の1で,短時間正社員のときよりは多くなる。逆にいえば3分の2の企業は何らかの職種で可能のようにもみえるが,前述したように6割が「ほとんど導入できる可能性はない」としているので,3分の1の「職種によっては導入できる可能性がある」企業を中心として考えたほうがよい。
ここでも販売営業職が9.7%と少ない。業種の影響が大きいどうか製造業と卸小売業,飲食店で比べてみると,前者で6.3%(職種を限定しないは5.8%),後者が19.9%(職種を限定しないは7.5%)である。前者がかなり少なく,職種を限定しない企業を加えても,後者でジョブシェアリングの可能性が高いことがわかる。
管理職が短時間勤務にむいているとした企業(正確には職種を限定しない企業を除く)は,2.1%(18企業)とひじょうに少ないが,どのような企業であろうか。8企業が製造業,7企業が卸小売業,飲食店である。中規模企業(300-999人)にやや多い(2.7%)。
1-4 小括
短時間正社員やジョブシェアリングは,実際に導入している企業は少ないが,意向などをみると全く可能性がないわけではなく,職種によっては可能であるとする。WS調査の職種が粗【268頁】くなっているので,詳しくみることはできないが,事務職,生産・現業職,専門・技術・研究職で少なくとも2割,多くみると4割ぐらいの企業が可能だとしている。一方,管理職が可能だとする企業はひじょうに少ない。
2 正社員の仕事の分割可能性について
前節で行った調査は企業調査の回答であった。企業回答でジョブシェアリングの可能性をたずねると,どうしても職場をやや離れた感覚で回答する恐れがある。職場における制度や慣行の実行可能性は,働く従業員に尋ねたほうが,正確である可能性が大きい。生産性本部調査にも個人調査があるが,短時間勤務やジョブシェアリングについては,賛否を尋ねているだけである。
そこで2001年の21世紀職業財団の調査(以下,財団調査と略)を用いて,正社員の仕事の分割可能性を探る(注4)。財団調査では,正社員に対して,現在の仕事を複数の短時間正社員(注5)が分担できるかどうかを尋ねている。
この短時間正社員については,将来の利用も含めて約半数が利用を希望している。そして現在の仕事を複数の短時間正社員が分担できるかどうかについては,「工夫すればできる」も含めて,約3分の2ができるとしている。短時間正社員を希望しない者の半数も,分担はできると思っている(表2-1)。
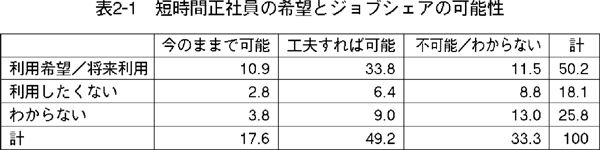
【269頁】
2-1 どのような職種でジョブシェアリングがやりやすいか
職種別にみて,どういった仕事であれば,やりやすくて,どの仕事が難しいのであろうか(表2-2)。「不可能」が多いのは,その他の職種と運搬・労務で,3分の1以上が回答している。事務が少ない。「今のままでも可能」とするのは,運搬・労務とサービスに多い。専門・技術がもっとも少ない。運搬・労務は,ほとんどが男性の職場だが,できるものとできないものに分かれる。専門技術は,「不可能」もやや多いが,相対的に「工夫すれば可能」(54.2%)が多い。この2つの職種について詳しくみよう。
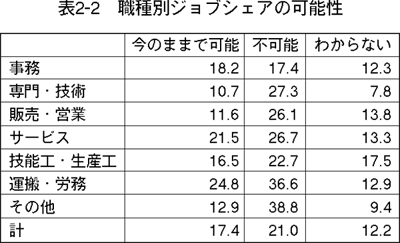
運搬・労務は労働時間が長いことが予想される。この調査では実労働時間を尋ねていないが,所定労働時間を尋ねている。全体で週40時間以下が85.2%なのに対し,運搬・労務では68.9%と約3分の1以上が週40時間を超える(職種計の所定労働時間の平均が38.6時間なのに対し,運輸・労務の平均は44.2時間)。そこで,運搬・労務を週所定労働時間でわけてみてみる。表2-3より,所定労働時間の長さが関係していることがわかる。週40時間を超えると4割以上が不可能と考え,週40時間以下では3割近くが今のままで可能と考える。労働時間が短ければ,分担できる可能性が大きい。ただ週40時間以下であっても,不可能とするもの【270頁】が約3分の1もいる。産業による違いがあるのであろうか。運搬・労務の約8割が運輸・通信業の企業で働くが,中分類の2つの業種でみてみよう(表2-4)。道路旅客運送業では,なんと半数以上が「今のままでも可能」としている。この回答者が働く職場は,シフト制がしかれている職場がほとんどだと考えられ,短時間のシフトも可能と考える者が多いのであろう。それに対して,道路貨物運送業では,約4割が「不可能」と考え,「今のままで可能」とするのは2割をきる。同じ運輸・通信業で働く運搬・労務であっても,大きな違いがあるようだ。
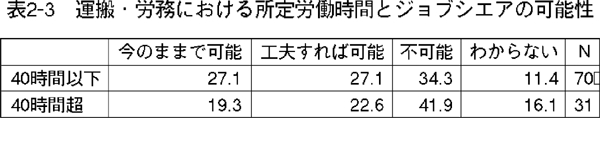
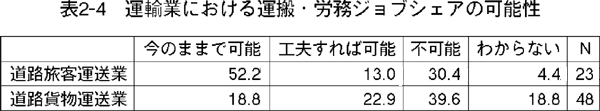
2-2 分担を可能,不可能と考える理由
では分担が不可能と考える理由は何であろうか。アンケートでは,3つの選択肢(その他をいれれば4つ),すなわち「連絡等の業務が多くなりすぎるから(連絡過多)」「内容的に不可分な仕事だから(不可分)」「特定の時間帯に常に対応できることが必要だから(常時対応)」から重複回答させている。
不可能の回答者のうち,その理由を表2-5でみると,まず全体にくらべてこの3つの理由をあげているものが相対的に少ないことがわかる。その他の理由に回答したものも無視できるぐらい少ない。ゆえに,うがった見方をすれば,さしたる理由もなく不可能だと回答した者がいたのかもしれない。ちなみに3割近くが不可能と回答した専門・技術では,内容的に不可分だという理由が85.7%と圧倒的に多い。
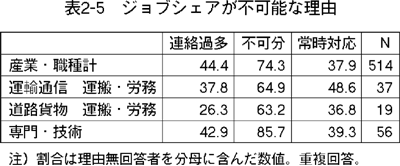
その専門・技術では相対的に「工夫すれば可能」(54.2%)が多かった。では,どういった工夫をすれば可能だと考えているのであろうか。アンケートでは,3つの選択肢(その他をいれれば4つ),すなわち「仕事を分担する者同士で連絡をきちんと行う(連絡緻密)」「仕事内容を明確化し細分化する(明確化・細分化)」「特にない」から重複回答させている。「その他【271頁】の理由」や「特にない」は無視できるほど少なく,圧倒的に前者2つの理由に集中している。表2-6をみると,専門・技術は全体の傾向とさほど変わらないが,やや「連絡緻密」が多い。能力的な問題で分担する者がいなければ仕方ないが,あるていど分担できる者がいれば,あとは効率的な連絡ができるかどうかにかかっている。
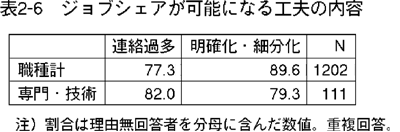
2-3 ブロビット分析
正社員の仕事の分割可能性についてプロビット分析をおこなう。従属変数は2通りで,ア)「今のままでも可能」を1,そのほかの回答を0としたもの,イ)「今のままでも可能」と「工夫をすれば可能」を1,そのほかの回答を0としたものを用いる。独立変数は,性ダミー(男性=1,女性=0),年齢,年齢の二乗,勤続年数,勤続年数の二乗,産業ダミー(大分類;製造業基準),職種ダミー(事務職基準),事業所規模ダミー(大規模企業基準),所定労働時間,所定労働時間の二乗,残業・休日出勤変数(1-4;数値が小さいほどよくある)である。最後の残業・休日出勤変数の分布をみると(表2-7),残業・休日出勤が全くないものは1割をきり,よくあるものが3割近く存在する。残業・休日出勤が多い仕事の性格ゆえに分割不可能だとも考えられるし,その逆に仕事の性格は分割できるものなのに他の要因で残業・休日出勤しているから分割可能だと考える2つの可能性がある。どちらに出るかが興味深い。
記述統計量は表2-8で,推定結果は表2-9にある。まず第1欄でア)のケースをみよう。
1)女性のほうが男性よりも7%今のままでも可能だとおもっている。2)短い勤続ほど可能だと思っているが,年齢や事業所規模は関係ない。3)産業では唯一,運輸通信業において可能だとする。4)さて職種をみると,さきほどみた運輸・労務が「今のままで可能」とする割合が事務職より8%高い。サービス職も高いが,専門技術職では事務職より5%低い。4)所定労働時間は予想どおり負の係数をとったが有意ではなかった。5)残業・休日出勤変数は正で有意で,少ない労働者ほど,今のままで分割可能だと考えている。
続いてイ)のケースを第2欄でみよう。
1)女性のほうが男性よりも14%可能だとおもっている。2)事業所規模では小さいほうが可能だと考えており,産業は関係ない。3)職種はア)のケースと異なり,「その他」の職種の【272頁】み負で有意である。4)所定労働時間は負の係数だが有意でなく,残業・休日出勤変数も有意でない。
これらの結果を総合すると,女性のほうが男性よりも分割可能だと考えている。残業・休日出勤が少ない労働者ほど今のままでジョブシェアリングが可能だと考えている。所定労働時間の長さは有意にならず,残業のほうがジョブシェアリングに関係していそうである。職種では運搬・労務ができそうだが,同じ運搬労務でも業種による違いがありそうだ。
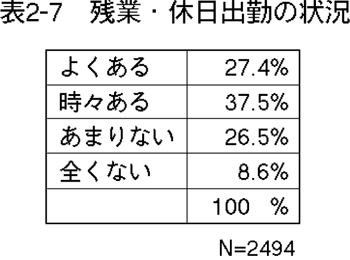
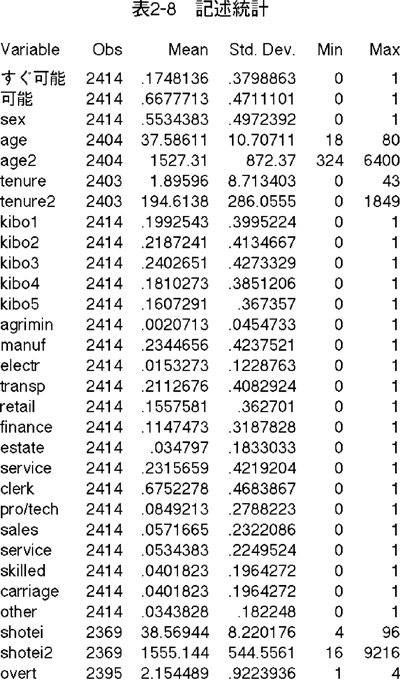
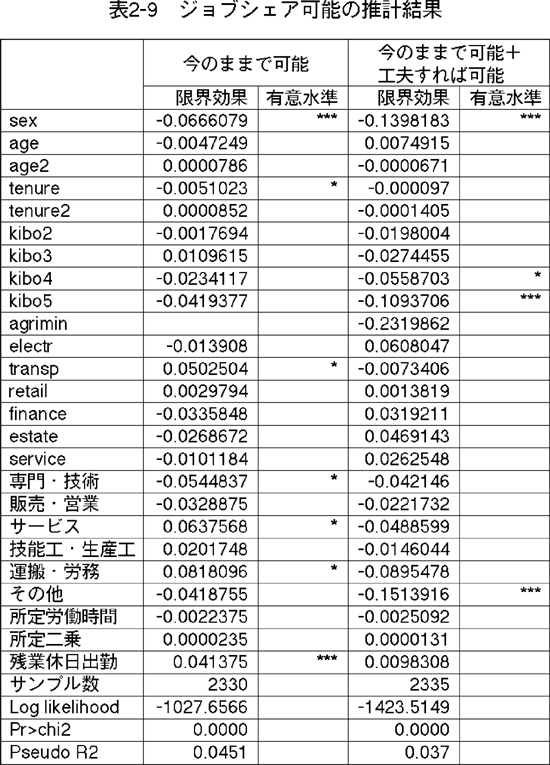
【273頁】
3 パートタイマーの仕事意欲と短時間正社員制度
同じ財団調査を用いて,現在パートタイマーで働いている者が短時間正社員制度を利用できる可能性を考えてみよう。
事業所調査によると,目的別・対象者別の短時間勤務制度が企業にどの程度導入されているのかをみつつ,短時間正社員制度の今後の可能性をたずねている。「既に正社員であって育児・介護を行うものを対象」に実施している事業所が27.2%と3割弱が導入しており,導入が最も進んでいる(表3-1)。また,それより調査年次が新しい「女性雇用管理基本調査」(2002)によると,5人以上事業所で38.5%が導入している。
しかし,他3つの短時間正社員制度を導入している事業所は少なく,2番目に多いのは正社員で育児・介護以外の理由の短時間勤務制度が4.3%である。ここで問題とするパート等の非正社員を対象としたものは1.6%にすぎない。しかし検討中か今後検討可能性ありとした事業所が2割程度ある。
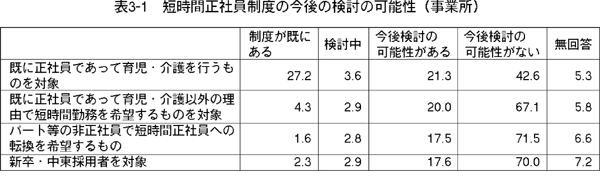
【274頁】多くの企業でフルタイム正社員への転換制度は整備されてきたが,それでも5割はこえない。あるいは事業所調査の結果をみても,それほど多くの利用者があるわけではない。
3-1 パートタイマーの希望
財団調査では,パートタイマーに対しては,「フルタイム正社員になりたい(A)」かどうか尋ねている。また短時間正社員制度については,残業・転勤ありの制度(B)と残業・転勤なしの制度(C)の双方について利用希望を尋ねている。またキャリアアップに対する設問もあり,「より責任のある仕事がしたい(D)」かどうか,「より専門的・高度な仕事がしたい(E)」かどうかを尋ねている。選択肢は「どちらともいえない」や「わからない」を含んでいるが,積極的な希望割合のみとりあげる。
まずキャリアアップ意識(D)(E)と処遇(A)(B)(C)の関係をみる(表3-2)。表をみてわかることは,キャリアアップ意識の高いパートはフルタイム正社員になりたいと思っていることである。半数以上のパートがそう考えている。(C)に対する希望も少なくないが,フルタイム正社員への希望よりは少ない。これは,おさえておくべき事実である。
しかし,責任のある仕事をしたいと思っているパートは全体の2割,専門的・高度な仕事がしたいと思っているパートでも全体の4分の1にすぎない。パートタイマーの仕事に対する姿勢が弱いかというと,そうでもない。責任のある仕事をしたくないと思っているパートは全体の4割弱,専門的・高度な仕事はしたくないと考えているものは3分の1強で,「どちらともいえない」と迷っているパートが4割前後も存在している。
保留にしているパートが4割もいるということは,ある意味で当然である。パートをつづけて具体的に将来どのような仕事を与えられ処遇はどのていどになるのか,あるいはその可能性がどれだけあるのかによって,責任があり高度な仕事をしたいと思うし,やりたくないとも思うであろう。いくら良い仕事でも給与がほとんど上がらないのであれば,やりたくないであろう。だから保留にしているわけで,彼・彼女の処遇に対する希望がポイントである。
「どちらともいえない」とするパートのフルタイム正社員への希望は約2割前後なのに対し,残業・転勤なしの短時間正社員への希望は約半数もある。時間を大切にし仕事内容,処遇が上がることへの期待であろう。ここでも4割強が残業・転勤なしの短時間正社員への希望を「どちらともいえない」としているが,もし短時間正社員の仕事内容と処遇の具体的イメージがついてくれば,希望は増えるであろう。
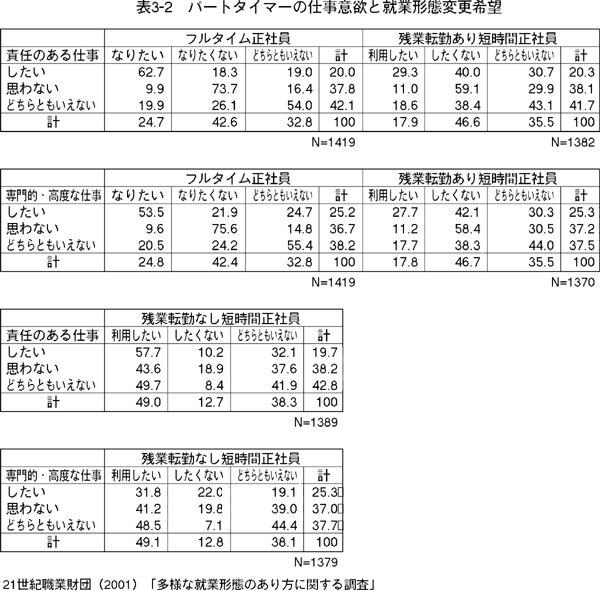
【275頁】
3-2 フリーターについて
いわゆるフリーターに対する評価は,さまざまである。自由な生き方,働き方を評価する意見もある。労働者調査によりチャレンジ意欲と正社員などへの希望をみてみよう。ここでは,フリーターを男性では35歳未満のパート,女性では35歳未満の未婚(配偶者のいない)パートとした。結果を表3-3でみると,男性は20歳台と30歳前半で大きく異なり,30歳をすぎると,3分の2から8割が仕事意欲をもち,正社員へ仕事を希望している。ところが20歳台では,仕事意欲をもつものは3割にすぎず,フルタイム正社員の希望をもつものは23%にすぎない。20歳台の男性フリーターは自分の時間に重きをおいているのであろう。残業・転勤なしの短時間正社員には20歳台後半で4割弱のものが希望している。
女性フリーターの場合は20歳台と30歳台との違いは少なく,20歳前半をのぞけば仕事意欲は男性より低く,20歳台でフルタイム正社員の希望が男性より多く,残業・転勤なしの短時間正社員には20歳台から4割以上が希望している。これは,短時間正社員が若いときの自分の時間を大切にしながらキャリアパスを展望できる制度である可能性が大きいことを示唆す【276頁】るものであろう。
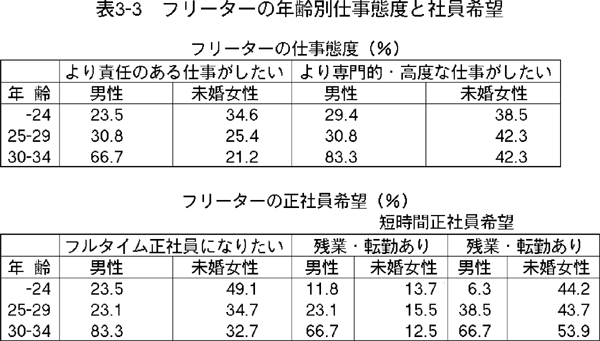
3-3 プロビット分析
従属変数は,フルタイム正社員希望を1,そのほかを0としたもの(ケースⅠ)と,短時間正社員制度のうち残業・転勤なしの制度を希望するものを1,そのほかを0としたもの(ケースⅡ)である。
独立変数は,性ダミー(男性=1,女性=0),年齢,年齢の二乗,勤続年数,勤続年数の二乗,産業ダミー(大分類;製造業基準),職種ダミー(事務職基準),事業所規模ダミー(大規模事業所基準),所定労働時間,所定労働時間の二乗,既婚ダミー(未婚=0),配偶者の年収(1-5で数値が小さいほど低い;配偶者が無職のときは0),同居の子供の有無(有のときは末子の年齢),雇用契約期間の定めの有無(有=1,無=0),時間当たり給与(または年収),同じ仕事に従事している正社員の状況(1-3,数値が小さいほど多い)である。
記述統計量が表3-4,推定結果が表3-5にある。なお推定結果は所定労働時間と時間当たり給与と年収が同時にはいったものが掲載されているが,時間当たり給与と年収をそれぞれ落とした推計をしても結果は変わらず,どちらも有意ではなかった。
ケースⅠの結果をみると,1)男性に多い,2)年齢が高いほど多い,3)運輸通信業と金融保険業で製造業にくらべ希望が少ない,4)職種では専門技術職に多いが,事務職にくらべ販売営業職,サービス職,技能工・生産工,運輸・労務職,その他の職種で少ない,5)未婚者ほど希望する,6)既婚パートをとると所定労働時間が短いパートほど希望する,7)有期契約のパートほど希望(期間の定めにないパートよりも8-10%多く希望),8)自分の賃金収入や配偶者の年収は関係ない,9)同じ仕事に従事している正社員の状況も関係ない。
ケースⅡの結果をみると,1)サービス業で希望が多い,2)職種では,サービス職と技能工・生産工の希望が少ない,3)既婚パートをとると労働時間が長いパートほど希望する,4)有期契約のパートほど希望(期間の定めにないパートよりも9-15%多く希望),5)子供のいるパートほど希望,6)性,年齢,勤続,事業所規模は関係ない,7)自分の賃金収入や配偶者の年収は関係ない,8)同じ仕事に従事している正社員の状況も関係ない。
フルタイム希望者と短時間正社員の希望者では,共通点と相違点があることがわかる。共通【277頁】点は,1)有期契約のパートほど希望,2)事務職にくらべサービス職と技能工・生産工で希望しない,3)勤続年数や同じ仕事に従事している正社員の状況は関係ない,などである。相違点は,1)既婚パートをとると,フルタイム正社員は労働時間が短いパートほど希望するのに対し,短時間正社員は労働時間が長いパートほど希望する,2)フルタイム正社員は年齢が高いほど希望するが,短時間正社員は年齢は関係ない,3)フルタイム正社員は男性のほうが希望するが,短時間正社員は性に関係ない,4)短時間正社員は子供のいるパートほど希望するが,フルタイム正社員希望に子供の有無は関係ない,などである。
興味深い結果が多くあらわれているが,相違点の1)は重要な発見であろう。所定労働時間の短いパートほどフルタイム正社員を希望するのは,お金や雇用の安定性のためでない。収入や期間の定めの有無でコントロールされた推計だからである。やはりもう少し長い時間働かないと技能が向上しない,仕事が面白くならない,という背景があるためであろう。逆に,短時間正社員は労働時間が長いパートほど希望しているということは,これだけ長く働いているのだから,処遇を少しでも正社員に近づけてほしいという希望のあらわれであろう。
【278頁】
4 さいごに
本稿の分析により,少なくともいくつかの職種では,ジョブシェアリング,つまり仕事を分担して,労働時間短縮をはかることが,まったくの絵空事でないことがわかった。正社員が日々の仕事から感じていることである。一方,非正社員の代表であるパートタイマーも,フルタイム正社員を希望する者が一定程度いることは明らかだが(その仕事意欲も強いが),それとは異なる一定のグループにおいて,いまの労働時間のままで「短時間正社員」を希望するものが多いこともわかった。後者が現実味をもつためには,正社員の仕事の分割,これがカギになるであろう。
*本稿のもとになった二つの調査の再分析について,ワークシェアリング研究会座長の今野浩一郎教授,21世紀職業財団の許可をいただき感謝したい。
【279頁】
参考文献
厚生労働省雇用均等・児童家庭局(2002)『パート労働の課題と対応の方向性』(パートタイム労働研究会最終報告書)
社会経済生産性本部(2003)『短時間労働の活用と均衡処遇〜均衡処遇モデルの提案〜』
社会経済生産性本部(2004)「多様就業型ワークシェアリング制度導入意識調査・制度導入状況実態調査報告書」
21世紀職業財団(2001)「多様な就業形態のあり方に関する調査」
武石恵美子(2003)「非正規労働者の基幹労働力と雇用管理の変化」ニッセイ基礎研究所『所報』Vol.26,東京都産業労働局(2002)『パート労働者の人材開発と活用』
東京都産業労働局〔2003〕『短時間正社員の可能性についての調査報告書』
松原光代(2004)「短時間正社員の可能性--育児短時間勤務制度利用者への聞き取りを通して」『日本労働研究雑誌』7月号
三井情報開発㈱総合研究所(2001)「ワークシェアリングに関する調査研究報告書」