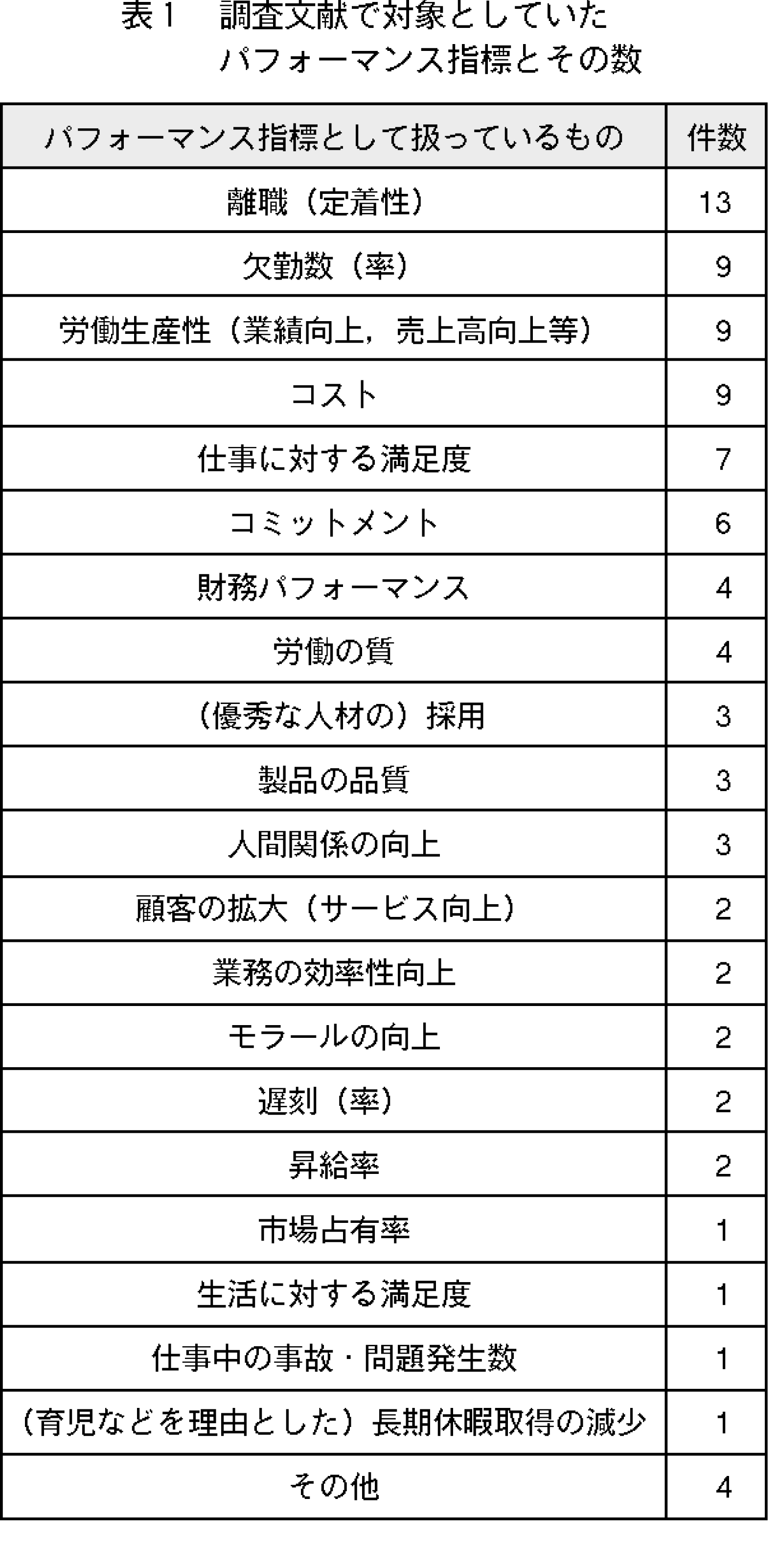
【295頁】
米英における両立支援策と企業のパフォーマンス(Ⅰ)
――両立支援策と企業パフォーマンスに関する海外文献のサーベイ――
松原 光代、脇坂 明
Ⅰ.はじめに
本稿は海外の両立支援策と企業のパフォーマンスとの関係を考察するため,これらに関して分析した海外文献をサーベイして海外の研究動向を把握しようとするものである。それとともに,今後日本において両立支援策と企業業績など企業にもたらす効果を明らかにする研究を進めるにあたり,研究手法,調査項目,課題などを明確にし,調査に役立てることを目的とする。
「企業のパフォーマンス」といっても,財務パフォーマンスを従属変数とした研究は未だ多くなく,労働生産性,組織へのコミットメント,欠勤・離職等による損失を防止した結果の利益など,多岐に渡っている。調査した文献数は33件で,国別にみるとアメリカが27件,イギリスが6件である。これらを分析手法別にみると,データ分析が15件,先行文献を元にまとめて両立施策の効果を述べたものが11件,事例調査が4件,アンケート調査・その他3件である。
全体的に,両立支援策は企業パフォーマンスにプラスの影響を及ぼす結果となっている。その多くは,「両立支援策による欠勤や離職の減少,損失防止が結果的に業績にプラスの効果を及ぼしている」,「両立支援策の導入により仕事と家庭の両立ストレスが解消し,従業員の生産性1がアップして結果的に業績がよくなった」など,両立支援施策が直接的にパフォーマンスに影響を及ぼすのではなく,まず「仕事への意欲」「ストレスの解消」「働きやすさ」など労働者の意識や労働環境といった媒介変数に寄与した上で中長期的に財務パフォーマンスにプラスの効果をもたらす,としている。日本においてもこれまで各人事施策の企業業績に及ぼす影響を分析する試みが数多く行われてきたが,施策と業績の関係を直接的に考察することはきわめて困難であり,多くは管理職,同僚,企業文化,経営者の戦略の普及度など複数の変数が複雑に係わり合い業績に影響する,としている。両立支援策においても業績に対する直接的影響を考察するのは難しい。しかし,もし両立支援策が従業員の離職を防いで定着性を高めたり,従業員の欠勤日数を減少させるのであれば,企業は離職者の補充に伴う採用・研修・事業の遅れに対するコストを削減することができよう。また,両立支援策が従業員の意欲や生産性の向上【296頁】に寄与するのであれば,新しい労働条件として人的資源管理策の中に位置づけることができるはずである。
両立支援策は海外および日本において,これまで「働く女性が継続的にキャリア形成できるようにするための福利厚生の一つ」と考えられてきた。しかし,昨今では多様な価値観や事情を持つ人材を活かすための戦略として考えられ,2005年4月1日から施行される次世代育成支援対策推進法においても,両立支援策の導入は従業員の定着,ストレスの低減,仕事への集中に対して効果があり,職場生活と家庭生活の両立可能な職場は高生産職場を生むとして企業の競争力に寄与する人事戦略と位置づけている。
両立支援策を企業競争力に寄与する人事戦略と位置づけるためにはその効果を検証することが一層不可欠になる。このため,本稿は両立支援策の導入に積極的な英米企業を対象とした既存研究を取り上げ,企業のパフォーマンスに対する影響を分析する。この作業は,日本企業における両立支援策と企業業績の関係を理解するための一助にもなると同時に,蓄積されつつある研究の限界やさらに議論すべき点を探求することにもなる。サーベイした文献リストを付録に添付するので,興味があるものに関してはぜひ利用していただきたい。
本稿の構成は以下のように予定している。第2章は1990年代から2002年までに発表された主な調査報告書および論文のポイントと課題を調査方法別に紹介する。第3章で最新の調査研究を紹介し,第4章で海外文献調査の総括と日本の両立支援策の研究の潮流を見ながら今後の調査研究に向けた課題を示す。なお,本稿は筆者の一人が関わった2002年度の厚生労働省による『両立支援と企業業績との関係に関する海外文献調査研究』を元にしている。
Ⅱ.主な調査研究
1.パフォーマンス指標の推移
調査した文献は,アメリカとイギリスの企業や労働者を対象とした全33の論文または調査報告書である。これらの分析手法は,データ分析が15件,先行文献を元にした分析が11件,事例調査が4件,アンケート調査・その他3件であった。文献の多くは,財務パフォーマンスに対する両立支援策の効果を分析するのではなく,主に離職(率),欠勤数(率),従業員の労働生産性を対象に両立支援策の導入前後における変化や損失を明らかにしている。表1は,調査文献で対象としていたパフォーマンス指標の数を示している。このパフォーマンス指標については1つの特徴が見られる。それは,1990年代の調査研究のパフォーマンス指標には「離職(定着性)」,「欠勤数(率)」,「組織へのコミットメント」,「モラール」,労働者の意欲などに関する「労働生産性」が多数を占め,2000年ごろから一人当たりの売上高に着眼した「労働生産性」,「市場占有率」,「優秀な人材の採用」,「製品の品質」,「顧客へのサービス」といった指標へ推移している。
これは,両立支援策の位置づけの変化と関係があると考えられる。
両立支援策は,1990年代前半までは働く女性が継続勤務できるようにするための福利厚生としての位置づけがられていた。アメリカにおける両立支援策の研究は,1960年代初期に女性が職場進出をするにあたり,ジェンダー論を基軸として男女間の能力差に違いが無いことを明らかにすることから始まる。この流れを受け,1970年代初期の女性による職場進出の活発化から【297頁】「ファミリー・フレンドリー」の概念が生まれ,男女の雇用機会の均等との関連で,育児や介護等の責任を女性のみが負担し,家庭内での男女の公平な分担がないとすれば,真の男女平等はありえないとして1970年代末に企業が「ファミリー・フレンドリー」な措置を採用し始めている。したがって,子供を持つ母親が労働者として働く数が増加するにつれ,彼女たちへの配慮が社会的に必要になり企業における制度的基盤が徐々に整備されたといえる。つまり,制度導入当初は,企業の社会的責任の観点から制度を整備し,働く女性に対して働きやすい環境を提供することに焦点があった。その副産物として仕事と家庭を両立しながらキャリアを継続すること,欠勤により職場の効率性や生産性が低下しないこと,労働者本人の生産性が低下せずモラールやコミットメントを高く維持できることへの両立支援策の効果が検証されたと考えられる。
しかし,1990年代半ばより男女の雇用機会均等が定着し,市場のグローバル化とそれに伴う企業競争が激化するに伴い,より優秀な人材を人種,性別,年齢にこだわらず必要とするようになると,いかに優秀な人材を雇用できるかが企業の競争力に直接的な影響を持つようになる。また,企業の中核を担う従業員の多くは家庭的責任を持つ世代であり,彼らの生産性,労働意欲の向上・維持が企業存続のための至上命題になると,これまで福利厚生と位置づけられてきた両立支援策は経営戦略としての意味を持ち,業績への効果を検証するようになってきたのである。ゆえに,2000年頃からパフォーマンス指標は,「市場占有率」,「財務パフォーマンス」,「優秀な人材の採用」などに推移したのである。
また,制度の導入による効果は一定期間を経過しなければ検証することは難しい。英米における両立支援策が1970年代末ごろから導入されたとするならば,10~15年経過後に財務データなどを元に制度導入による業績への効果を検証することが可能になろう。
財務パフォーマンスに対する両立支援策の直接的効果を推計している文献には,Perry-Smith, Jill E. And Terry C. Blum〔2000〕,“Work-Family Human Resource Bundles and Perceived Organizational Performance”がある。Perry-Smith and Blum [2000] は両立支援策が成長率や利益率の財務パフォーマンスにプラスの効果を及ぼすこと,他社製品に比べ品質的に優れていると評価されることに寄与すること,市場シェアや上司と部下の人間関係などにもプラスの効果があることを検証している。しかし,Perry-Smith and Blum [2000] が使用したデータはクロスセクショナルデータであり,制度の導入前後の一定期間のデータを時系列的に分析していないため,制度が財務パフォーマンスに寄与しているのか,景気による要因が大きいのかを正確に検証しているとは言えない。
両立支援策を経営戦略の一環として位置づけたことにより,企業の制度導入による効果を財務・市場パフォーマンスで確認したいとの希望が出てきたことが伺える。今回の調査対象文献では,データ収集の限界から制度とパフォーマンスとの因果関係を完全に解消しきれていない。つまり,パネル・データを利用していない。今後,制度導入前後のデータを用い,さらには複数の独立変数やコントロール変数を加味し,景気動向の要因をできるだけ排除した分析が望まれる。
【298頁】
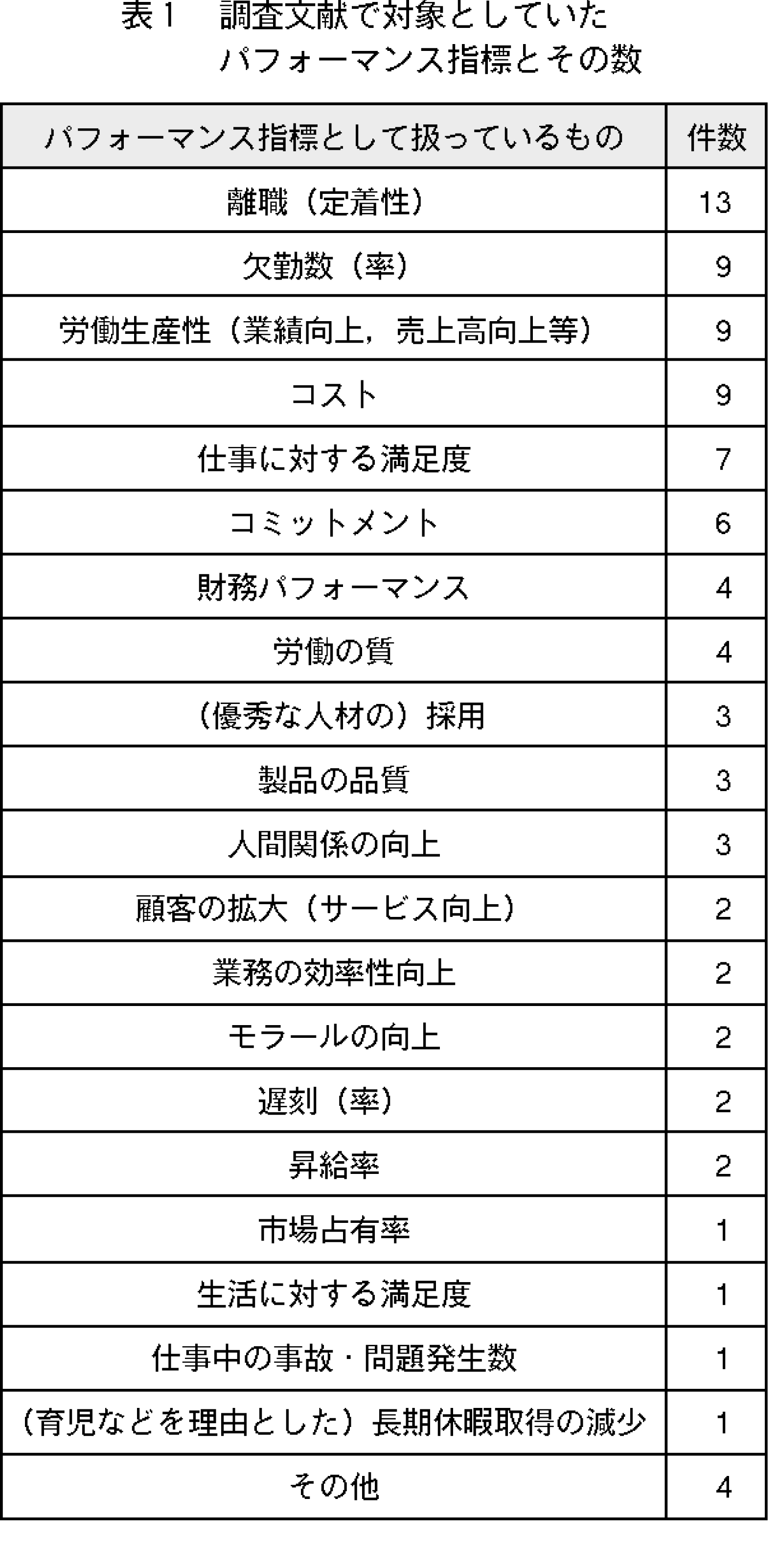
2.両立支援策の推移
海外文献の調査で,最も多く分析対象とされた制度は,柔軟な勤務時間制度(6件)2であり,ついで,両立支援施策(全般)(4件),育児休業制度および事業所内託児所(共に3件)であった(表2参照)。分析対象として頻度が高く引用された施策は,企業や従業員のニーズのバロメーターとして,必要度および注目度が高い施策であり,最も導入されている施策と見なすことができる。
【299頁】両立支援施策についても,1990年初期から1990年代後半以降にかけて一つの傾向が見られる。
1990年代の文献には,育児休業制度,事業所内託児所,地域の託児所との協力体制整備または託児サービスに対する経済支援などの施策を検証しているものが多い。これらの文献は,1980年代に実施した事例研究,アンケート調査,ヒアリングなどを元に行われた研究であるため,実際は企業が1980年代に整備した制度といえる。これらの施策の効果を検証した背景は,前節でも記述したとおり,両立支援策が整備され始めた初期は,子供を持つ働く女性に対する福利厚生施策として,主に育児に焦点を当てられていたことが考えられる。しかし,女性の職場進出による,性的役割分担意識の薄れ,男女労働者の意識の変化は,多様な労働者が職場に存在することによる多様性(ダイバーシティ)の尊重を生み,従来の仕事と家庭の両立を重視した「ファミリー・フレンドリー」の概念から「個人の生活」に対する充実も重視した「ワーク ライフ バランス」の観点にもとづく両立支援策へと推移していった。また,企業は優秀な人材により高い生産性を上げてもらうためには,会社に出社し,固定した労働時間を設定して働かせるよりも,各自が最も高い生産性と効率性で働くことができる労働条件の整備が重要と認識し,「働き方の柔軟性」に焦点が当てられるようになったと思われる。
労働者にとってニーズの高い両立支援策は何か,を調査したものに1998年に発表されたカタリスト調査3がある。これによると,従業員が企業に整備して欲しい施策としてニーズが高いのは,フレックス制度が85%と最も多く,ついでカフェテリア・スタイルの福利厚生(79%),家族休暇制度(74%),独自のキャリアパス(69%),在宅勤務制度(65%),柔軟な勤務制度(63%),育児支援(53%)となっている。同報告書に関する中村4の解説によると,フレックス制,カフェテリア・スタイルの福利厚生,家族休暇制度(育児・介護休暇制度),在宅勤務の選択理由が育児理由と重なることもあり,これらの要望に明確に境界線をつけて区別することは難しいとしている。しかし,労働者の価値観や家族形態が多様化するなかで一律的な働き方しかできないことはストレスを生むため,働き方に対する労働者への配慮を求めている傾向が強いことは推測できる。また,同報告書には,フレックス制度と柔軟な勤務制度の定義について詳細が述べられていない。日本での制度を参考にしてフレックス制度はコアタイムがあり出退勤時間が労働者の自由となっている制度であり,柔軟な勤務制度は仕事の進め方を含め,働き方を労働者の裁量に任せている裁量労働制と判断すると,裁量労働はパフォーマンスの高い労働者に報酬の1つとして与えられている権利で,全従業員が平等に利用できる制度としてフレックス制度があると推測できる。出退勤時間を一定の範囲内で自由にできる制度が労働者のニーズとして最も高いといえる。
このように2000年前後の調査研究の対象施策は,働く時間または期間,働く場所,ジョブ・シェアリングなどの働く形などに多様性を持たせた施策が中心になってきている。詳細は後述するが,Helen Gray [2002]" Family-Friendly Working: What a Performance! An Analysis of the Relationship Between the Availability of Family-Friendly Policies and Establishment Performance" は,両立支援策のうち,従業員が職場にフルタイムで在席していることを前提とした施策(職場在席型施策)と,在宅勤務やフルタイム勤務からパートタイム勤務への変更,子どもの学期中の【300頁】みの勤務など一時的に職場を離れることがある施策(職場不在型施策)を取り上げ,どの様なタイプの施策が組織のパフォーマンス5に効果があるかを検証している。
1998年に発表されたアメリカ財務省による報告書"Investing in Child Care: Challenges Facing Working Parents and the Private Sector Response"は1,109件の事業所を対象に民間企業の育児支援に対する調査の結果を明らかにしている。同調査は,育児支援策が組織に及ぼす効果を企業の人事担当者に対してアンケートを行ったものである。その結果,両立支援施策によって家庭責任のストレスが減少し,欠勤率の低下,従業員のモラール向上,離職率の低下の効果があったとしている。さらに企業の人事担当者は,育児支援など個人のニーズを支援する職場環境の創造は事業運営に不可欠と結論づけ,育児支援が企業の生産性向上のためのツールであるとしている。
これまで,労働者が最も重要視していた労働条件は賃金であった。しかし,近年においては,働き方に多様性がある制度の整備が労働者にとっての新しい労働条件になりえ,人事戦略の一つになるといえよう。
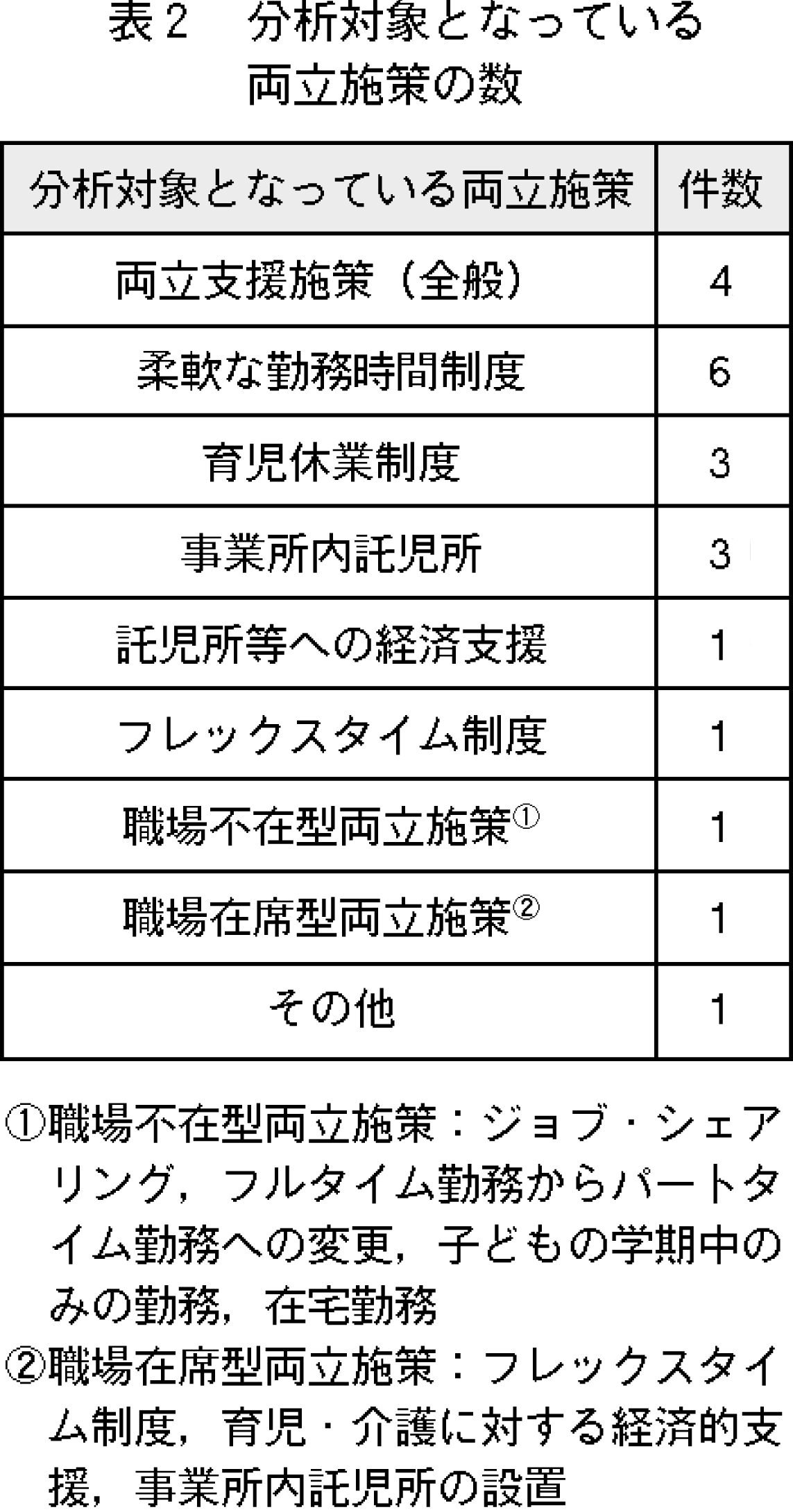
【301頁】
3.主な調査文献
サーベイした文献の全てが,両立支援策は企業パフォーマンスにプラスの効果があることを明らかにしている。1990年代初期の文献は,データがまだ蓄積されていなかったのか,個別に実施された調査報告書を集大成し,両立支援策の効果を検証する先行文献分析が多いが,2000年以降はデータ分析を手法として制度の効果を検証した文献が多い。しかし,それでもまだ財務パフォーマンスを従属変数とし,制度導入後のパフォーマンスの推移を見た分析は少ない。財務パフォーマンスに対するファミフレ施策の直接的効果を推計している文献には,前節で触れたPerry-Smith, Jill E. And Terry C. Blum〔2000〕,“Work-Family Human Resource Bundles and Perceived Organizational Performance”がある。
既存の調査報告書を元にした分析では,過去に実施されたインタビュー調査やアンケート調査を元に,全体の傾向をまとめている。多くの文献は,両立支援策が組織パフォーマンスにプラスの効果をもたらすことを明らかにしている。分析手法は,多数の先行研究より各企業で発生している仕事と家庭の両立に関する主要な問題を列挙し,その問題の解決策として両立支援策が有効であったかどうかを見ているが,その効果を定量的または定性的に分析していないため,客観性に欠けるところがある。しかし,Kossek EE, Ozeki C. [1998],"Work-Family Conflict, Policies, and the Job-Life Satisfaction Relationship: A Review and Direction for Organizational Behavior-Human Resources Research" は,学術論文の中から職業と生活のそれぞれに対する満足度をテーマにした72の学術論文を対象にメタ分析6を用いて,仕事と家庭の両立問題と仕事および家庭への満足度との関係を分析している。その結果,仕事や家庭における満足度がモチベーションとして業務遂行力に影響し,結果的にパフォーマンスへ寄与する可能性があると示唆している。両立支援策がパフォーマンスにプラスに寄与するメカニズムは,データ分析同様に,直接的にパフォーマンスへ寄与するのでなく,人間関係の向上やストレスの解消によるモラール,コミットメントの上昇が結果的に業績に寄与するというものである。
事例調査に関する文献においても,両立支援策がパフォーマンスにプラスに寄与することを示している。事例調査は調査対象を多数行うことはできないが,両立支援策がどのような企業にどのような環境で導入され,パフォーマンスに作用したか,といった具体的経緯を調査できる点は,有効な手段である。他社等で各施策を具体的に展開する場合は事例調査による研究結果は貴重な参考情報となる。さらに,事例調査は,制度の運用状況を具体的に情報収集でき,それらをケーススタディとして蓄積できる点においても分析手法として有効である。
調査した文献の中でもS. Bevan, S. Dench, P. Tamkin and J. Commings [1999], "Family-Friendly Employment: The Business Case" が注目される。この調査は機会均等と両立支援策の効用を調査したもので,調査対象企業数は11社と少ないが,インタビュー調査実施前に詳細の企業調査票を用いて対象企業を分析し,その上で人事担当マネジャーや従業員に両立支援策の運用,これ【302頁】らの施策が育児責任を持つ従業員のモラール,コミットメント,モチベーション,生産性に対する効果や問題点を具体的に調査している。その結果,均等施策と両立支援策は従業員の潜在能力を最大限に引き出す有効な手段であると人事担当者が思っていることが明らかになった。特に,均等施策は従業員のモラール向上に寄与し,両立支援策は,離職率の改善,生産性,モラール,コミットメントの向上に効果があるとしている。
アンケート調査による結果をまとめた文献は2件と少なかったが,内容的には興味深いものであった。Isabel Boyer [1993],”Flexible Working For Managers”は,パートタイム7やジョブ・シェアリングで働く管理職の生産性や離職率について,各企業の人事担当者やパートタイム等で働く管理職の上司に対してアンケートを行っている。その結果,パートタイムなどで働く管理職の生産性は高く,離職率も低いことから組織にとって有益であると,彼らの上司や人事担当者が評価していることを明らかにしている。さらに,彼らの組織に対するコミットメントや生産性はフルタイム勤務の管理職より高いと評価していることもわかった。パートタイムなどで働く本人も,フルタイム時の働き方と比較し,今と同じか,もっとやりがいがあると感じている。同調査では,管理職が柔軟な働き方する際の留意点として責任の所在を明確にすること,仕事の質を吟味しそれに応じたチーム編成をすることを挙げている。しかし,パートタイムなどで働く管理職のキャリアは制限がある企業が多く,このような働き方を選択する場合は本人の明確なキャリアビジョン,ライフプランなどが必要であると考えられるが,管理職の短時間勤務は業務上に及ぼす支障はなく,むしろ組織にとって有効であることを示唆している。
両立支援策を導入した際のコストを計算し,導入しない場合の損失と比較した研究にEllen Ernst Kossek, [1990], "Taking a Strategic View of Employee Child Care Assistance: A Cost-Benefit Model" がある。同論文は保育施設への費用支援を会社が実施した場合の離職数の減少と,それによる費用的効果とレバレッジ効果8を具体的数値を示して分析したものである。その結果,会社が保育施設へ費用支援することは,従業員の離職率を低下させ,離職によって発生する費用を大きく削減することが可能であるとしている。この効果分析手法は,他の人事戦略施策にも適用でき,効果的な施策を選択し,経営トップからの支持を得るには有効である。
今回の海外文献調査は,各社の両立支援策が従業員の生産性向上,離職や欠勤の減少,優秀な従業員の採用など,組織のパフォーマンスに貢献していること,両立支援策は経営における人事戦略の一つであることを改めて確認するものとなった。次節では,前述した各論文を中心にデータや手法,結果を詳細に紹介する。