�y111�Łz
���n�H�i��Ƃ̃Z�~�E�O���[�o���[�[�V�����헪
�`Web �����ɂ�鉼���T���ƍ]��O���R������ЃC���^�r���[�ɂ��T�������̋c�_�`
�w�K�@��w�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@��c�@����
�w�K�@��w�@�v�Z�@�Z���^�[�q���������@�|���@�r�q
�w�K�@��w��w�@���m����ے��@�@�@�@�@�@�R���@���q
�y�ڎ��z
1�D�W�����i�O���[�o�����j�ƃ��[�J�����i���n���j
2�D���{�ݏZ���[�J�[�ɂ�����W�����̌���FWeb ��������
3�D���n�H�i���[�J�[�Ɠ��n��H�i���[�J�[�E�O���n�H�i���[�J�[�Ƃ̔�r
4�D�Z�~�E�O���[�o���[�[�V�����x�Ɖc�Ɨ��v�Ƃ̊W�����T���F����1
5�D�Z�~�E�O���[�o���[�[�V�����x�����肷��v�������T���F����2
6�D�]��O���R�ɂ�����Z�~�E�O���[�o���[�[�V�����̍l����
�`�C���^�r���[�ɂ��T�������ɂ��Ă̋c�_�`
1�D�W�����i�O���[�o�����j�ƃ��[�J�����i���n���j
�O���[�o���W�J���i�ނƐ��i���̕W����������I�ɐi�ނƂ������Ƃ��A�e�b�h�E�����B�b�g����ɂ͌����Ă������Ƃł��邪�A���݂ł͂܂��������������Ă��炸�A���i���ւ̑I�D�͂��ׂ����Ȃ�A�܂蔽�W�����̌X���������Ă��邱�Ƃ��킩��B
���c���E�w���Z���i2010�j�ɂ��Ɓw�����T�C�h���猩��ƁA�O���[�o�����i�M�Ғ��F�O���[�o���W�J�̂��Ɓj�Ƃ́A���E���̂�����ꏊ�ɐ��i���s���n�点�邱�Ƃ��\�ɂȂ��Ă����Ƃ������Ƃł���B�����A����́A���v�T�C�h�i�}�[�P�e�B���O�E�T�C�h�j���猩��ƁA�ڋq�����L�͂Ȑ��i�ƃT�[�r�X�̏W������I�����s���悤�ɂȂ��Ă����Ƃ������Ƃł�����B����������ƁA�ȑO�ɂ������ă}�[�P�^�[�́A�قȂ����I�D�����قȂ����ڋq�E�E�E�ɒ��ʂ���悤�ɂȂ��Ă���̂ł���B�x1�j
�O���[�o���E�}�[�P�e�B���O�ɂ�����W�����E�K�����_���̌n���͈ȉ��̂悤�ɂȂ�B�܂�
1960�N��́A�i�W�����r�K�����j�ŕW�����̗��ꂪ��ł���A�L���̉��B����W�����iElinder �y112�Łz1961, Dichter 1962�j�A�L���ȊO�̃}�[�P�e�B���O�v�f�ւ̕~���iKeegan 1969, Buzzell 1968�j�Ȃǂ��咣���ꂽ�B1970�N��ɂ́A�t�Ɂi�W�����q�K�����j�ł���A�e���s��̓������́iWind and Douglas 1971, Britt 1974�j���Ȃ��ꂽ�B1980�N��ɂ́A����ɋt�]���i�W�����r�K�����j�A�}�[�P�e�B���O���v�f�i���ɐ��i�j�̊��S�W�����iLevitt 1983�j���咣���ꂽ�B�������Ȃ���A����Ɋւ��ẮA�����ʂ���̔ᔻ���N����AKotler�i1986�j�� Fisher�i1984�j�͊e���s��̉z����َ��������邱�Ƃ��咣���ADouglas and Wind�i1987�j�͕W�����������̑I�����̒���1�헪�ł��邱�Ƃ��q�ׁATakeuchi and Porter�i1985�j�͎��ؓI�ɂ��W������ӓ|�ł͂Ȃ����Ƃ��������B1990�N��ɓ���ƒP���ȕW�����E�K������2���@�ɑ�����^�������iHisatomi 1991, Sandler and Shani 1992, Kustin 1994�j�A2000�N��ȍ~�� Rugman�i2001�j�AGhemawat�i2007�j�ɂ���ăZ�~�E�O���[�o���[�[�V�����Ƃ����ܒ��헪������Ă���B
���̃��O�}���̃Z�~�E�O���[�o���[�[�V�����_�͈ȉ��̂Ƃ���ł���B�Ⴆ�X�}�[�g�t�H���͊e���̌��ꂪ�\�t�g�E�F�A�ɂ��炩���߃v���C���X�g�[������A�d���Ȃǂ̋K�i���e���Ƀt�B�b�g����悤���炩���ߐv����Ă��邽�߁A��i���ł��낤�ƐV�����ł��낤�ƁA�O���[�o���E�u�����h�̓����ɂ���ăO���[�o���s����`�����邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B�������Ȃ���A���̂悤�ȎY�Ƃ𑼂Ɍ��o�����Ƃ͓���A�قƂ�ǂ̎Y�Ƃɂ����Ďs��̓O���[�o��������ǂ��납�A�ނ��냍�[�J���^���[�W���i����������Ƃ������̂ł���iRugman 2001�j�B
�����āA���ݍł����y���Ă��闝�_�́A�p���J�W���E�Q�}���b�g�� CAGE ���_�{ AAA �헪�ł���B���ꂪ�A�w�W�����ƃ��[�J�����x�֑Ή�����嗬�̗��_�i�Z�~�E�O���[�o���[�[�V�����j�ƂȂ��Ă���B�܂�A�����Њ�Ƃ��C�O�i�o����ɂ������āA�{���Ɛi�o��Ƃ̍��ق��l�����邱�Ƃ͂��͂��ʓI�ł��邪�A����܂ł̕W�����E�K�����̘g�g�݂ł́u���ق𗘗p����v�Ƃ������z�ɖR���������B�Q�}���b�g�́A���ƊԂɂ͖����ł��Ȃ��傫�ȍ��فiCross-border differences�j�����邽�߁ACAGE ���_�{ AAA �헪�őΉ����ׂ��Əq�ׂĂ���BCAGE ���_�̃t���[�����[�N�́A���ƊԂ̍��ق��A�����i�b�j�i�@���A�����A����A�Љ�K�͓��j�A�����i�`�j�i�@�I�A���x�I�A�����K�����j�A�n���i�f�j�i�����I�u����A�����A�C��A�����R�X�g���j�A�o�ρi�d�j
�i�J���R�X�g�A���{�R�X�g�A���������A�C���t�����j�����r���ׂ��ł��邱�Ƃ��q�ׂĂ���B���ɐH�i�≻�ϕi�� Culture-specific �Ȑ��i�ł��邱�Ƃ��q�ׁA�����I�ȍ��ق��傫�����f����Əq�ׂĂ���2�j�B�����̍��ق𖾂炩�ɂ�����ŁA�Q�}���b�g�� AAA �헪��K�p����̂ł���B����3�� A �Ƃ́AAdaptation�i�K���헪�j�AAggregation�i�W�헪�j�AArbitrage�i�A�[�r�g���[�W�헪�j�ł���A�ȉ��̂悤�ɐ������Ȃ���Ă���3�j�B
① Adaptation�i�K���헪�j�F�C�O�̓��ꐫ�ɓK�������헪��W�J���ċ����D�ʂ��l������B�܂胍�[�J�����ɑΉ������헪�ł���B
② Aggregation�i�W�헪�j�F�����̍�����̎s��P�ʂƂ��邱�Ƃɂ���āA�K�͂̌o�ς�Nj�����B�܂�n�扻������ɓ�����B
③ Arbitrage�i�A�[�r�g���[�W�헪�j�F�T�v���C�`�F�[�����\������e�v�f�����ꂼ��Ⴄ���ɒu�����Ƃō���n���P�ʂƂ���s��Ԃ̍��ق����p����B�܂�Z�~�E�O���[�o���[�[�V�������������邽�߂ْ̍�ł���A���ʓI�E�����I�Ȏ�i���Ƃ邱�Ƃł���B
���̃Q�}���b�g�̏�L�̗��_�����ꂽ����ȉ��̃W���[�i���œ��W���g�܂�A�Z�~�E�O���[�o���[�[�V�����͑傫�ȊS���ƂȂ��Ă���4�j�B
�� British Journal of Management�i2012�j
�y113�Łz
�� European Management Journal�i2009�j
�� International Marketing Review�i2009�j
�܂����{�ɂ����Ă��Z�~�E�O���[�o���[�[�V�����ɂ��Ă̌����͌����邪�A���ɐH�̗̈�ɂ����āu�O�H�O���[�o�����̕��̓t���[���v����[�i2013�j�Œ���Ă���5�j�B
����́A���ɕ����I�ˑ��x�̋����H�̗̈�ɂ����ăI�y���[�V�����͕W�������₷�������ł���A�s����͐H�����f���ă��[�J�������₷�����Ƃ�������������t���[���ł���B
�i�}1-1�Q�Ɓj
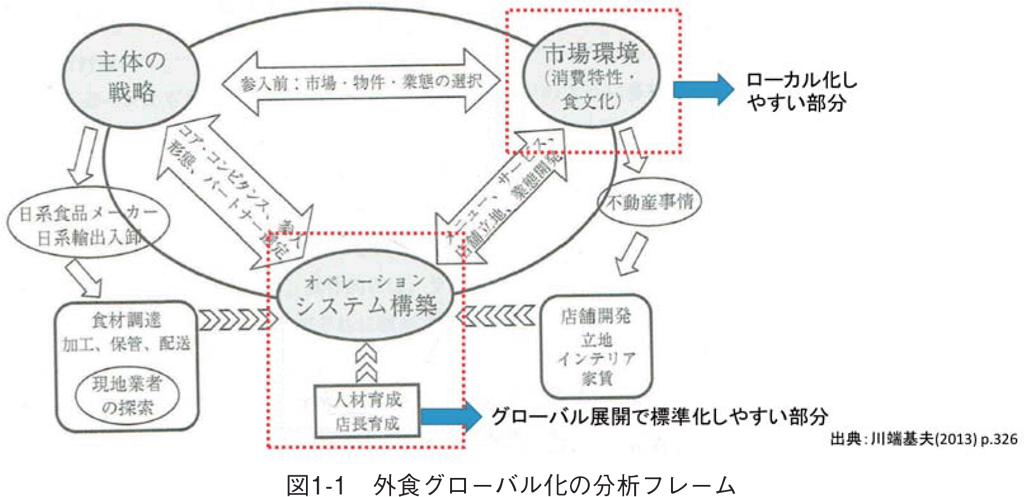
2�D���{�ݏZ���[�J�[�ɂ�����W�����̌���FWeb ��������
�]���A�O���[�o���E�}�[�P�e�B���O�̑Ώۂ͔�r�I���̊�Ƃł���B����́A�O���[�o�����ɂ͈��̋K�͂̑傫�����K�v�ł���A������Ƃ̊C�O�W�J�͗e�Ղł͂Ȃ�����ł���B�����S�ABarbara, �y��ꐶ�i2013�j�̌����ɂ��ƁA
�w�����̒�����ƂɂƂ��āA�C�O�W�J�͍���A�o���̖R���������ł���B�Ƃ����̂��o �c�����������Ă���A���n���Y�͂������A�A�o�ɂ����Ă������̍���ɒ��ʂ��邩��ł���B�܂�����n���G���A�̏���҂��͂����ނƂ����n������헪�^�j�b�`�헪�����{�̒�����Ƃ̎嗬�ł��邱�Ƃ���킩��悤�ɁA�n��̔S�������������߁A�E�E�E�e�ՂɊC�O�}�[�P�b�g�ɓW�J���邱�Ƃ��ł��Ȃ��E�E�E�B�x�ip.47�j
�w������Ƃ̍��ۉ��Ƃ����A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�����ł�����Ƃ̍��ۓW�J�Ɉ���������Ƃ����`�Ŏ�������P�[�X�������A������Ƃ̍��ۉ��͑��Ƃ���̐i�o�v���ɂ����ɉ����邩�Ƃ��������Ř_�����Ă����B�x�ip.48�j
��O�����邪�A�����̌X������{�e�̋c�_�ł͔�r�I����Ƃɍi�邱�ƂƂ���B
�܂�����Ƃ̕W�����E�O���[�o�����̌����T��A�W�����|���[�J�����̉����𗧂Ă邽�߁A2018�N1���� Web �A���P�[�g���������{�����i500�T���v���j�B�Ȃ��A�����́i���j�}�[�y114�Łz�P�e�B���O�A�v���P�[�V�����Y�𗘗p�����B�Ώێ҂́A���{�ɋ��_�������A�C�O�ɂ�5�ȏ�̎x�Ђ⎖�Ə���W�J���Ă��� BtoC ���[�J�[�i�O���ABtoB �������Ɏ肪���Ă��郁�[�J�[�܂ށj�̍��ےS���҂��邢�͍��ےS���o���҂Ƃ����Ƃ���A91.4�������n��Ƃł���A��Ж����Ə]�ƈ��̔䗦�́A�]�ƈ���97.6�����߂錋�ʂƂȂ����B�ړI�͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�@��Ƃ̃o�b�N�O�����h�ɂ��A�W�����ƃ��[�J�����̌���A�ӎ��̍���T��
�A�H�i���[�J�[�Ƃ��̑����[�J�[�Ƃ̔�r
�����āA�ΏۋƎ�͈ȉ��̃��[�J�[�Ƃ����B
1�D�H�i�E�H�i���H
2�D����
3�D�����ԁE�o�C�N
4�D�Ɠd
5�D�����@��
6�D���i�E��×p�i
7�D���ϕi�E�g�C���^���[�֘A
8�D�A�p����
9�D���̑�������
�ȉ��Ɍ��ʂ������B
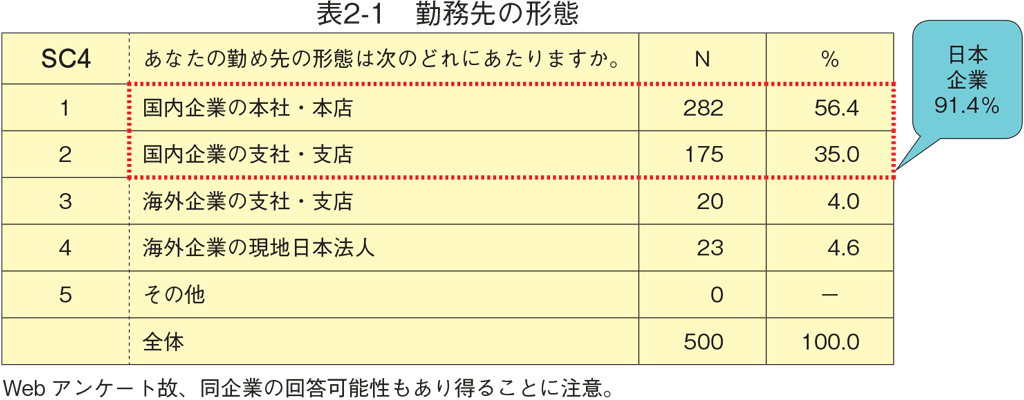
�y115�Łz
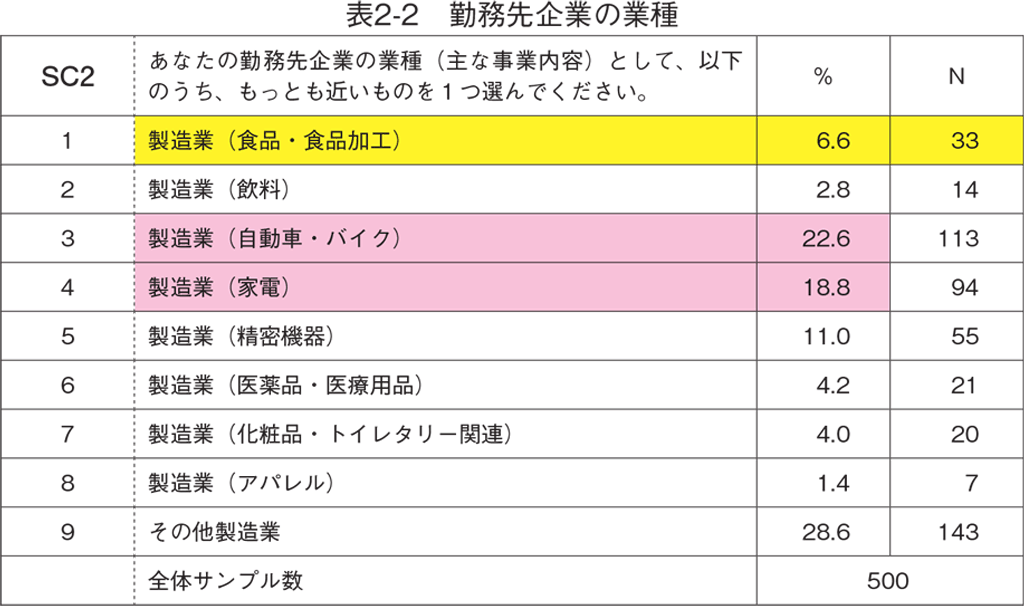
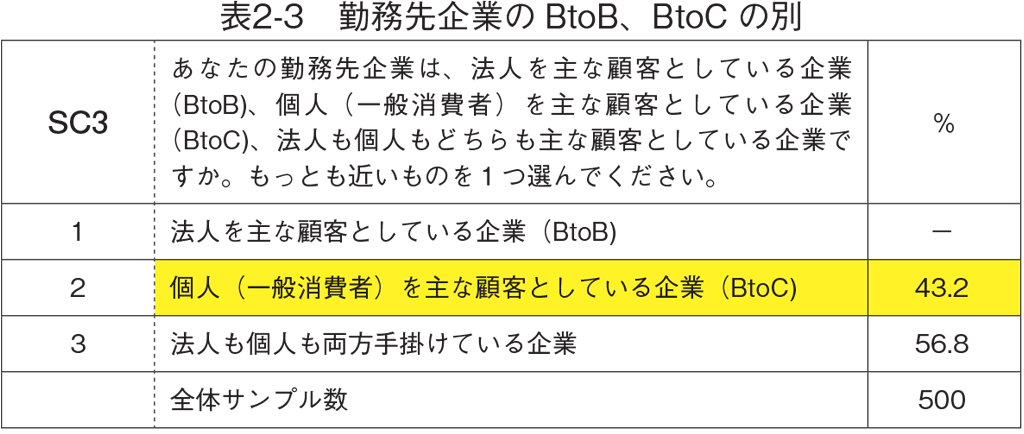
�y116�Łz
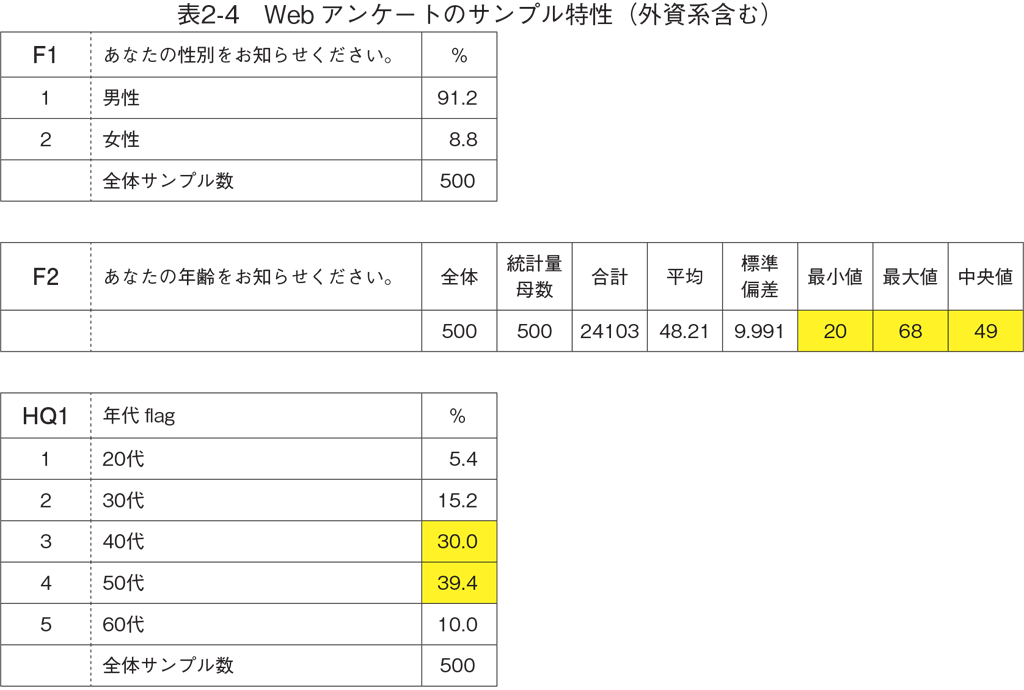
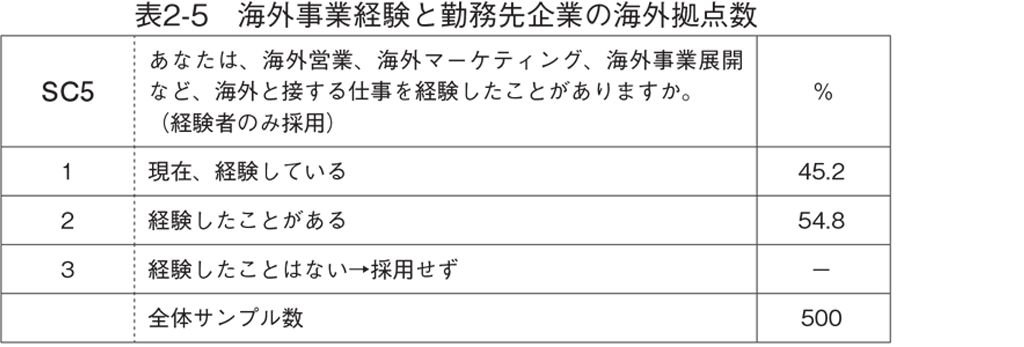
�y117�Łz
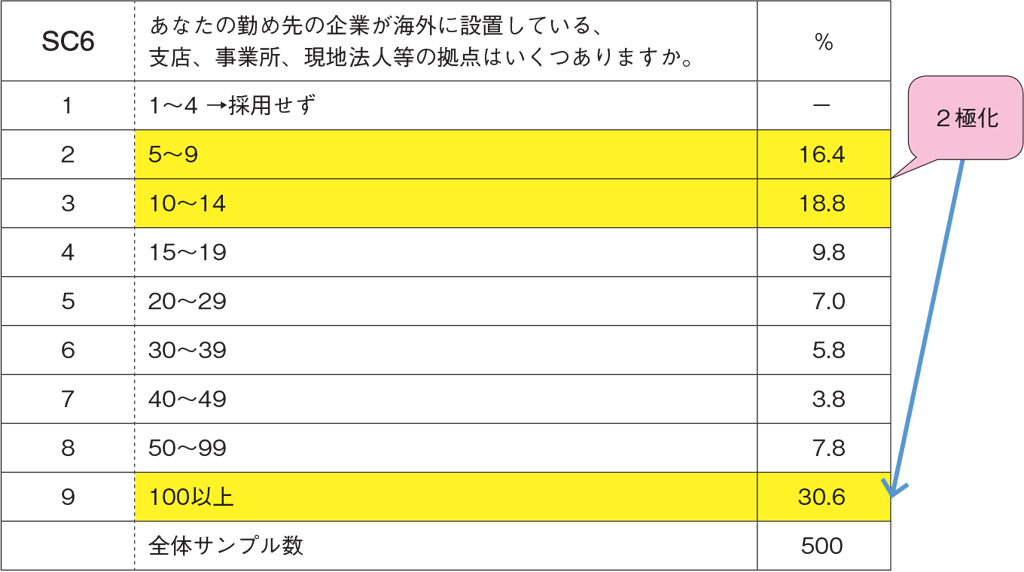
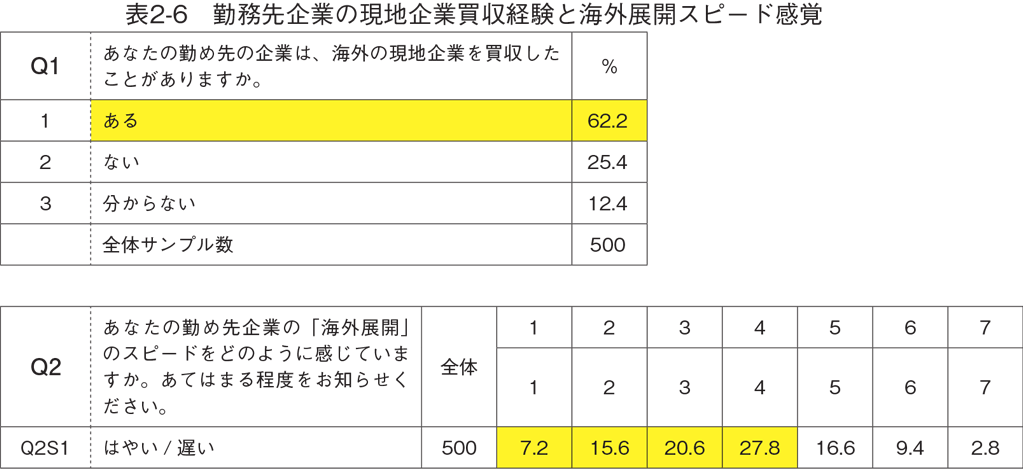
�C�O�W�J�̃X�s�[�h�ɂ��ẮA���Ȃ��ϓI�Ȑ��l�ƂȂ邪�A�S�̂ł͒��f����͂₢���������Ƃ��킩��B
�ȏォ��A�T���v���̋Ζ����Ƃ�T���v���������悭�킩��B����ɑ����ē��������Ă݂悤�B
�y118�Łz

�\2-8����́A��͂�O���[�o���i�o��Ƃ͋K�͂��傫�Ȋ�Ƃ���߂Ă��邱�Ƃ�������B
�y119�Łz
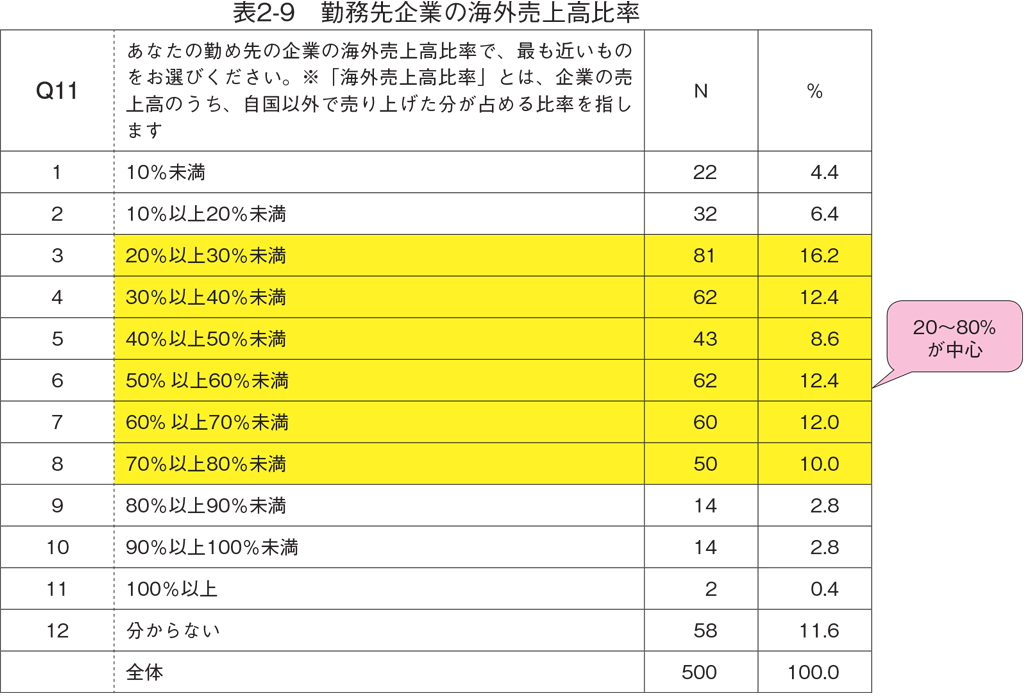
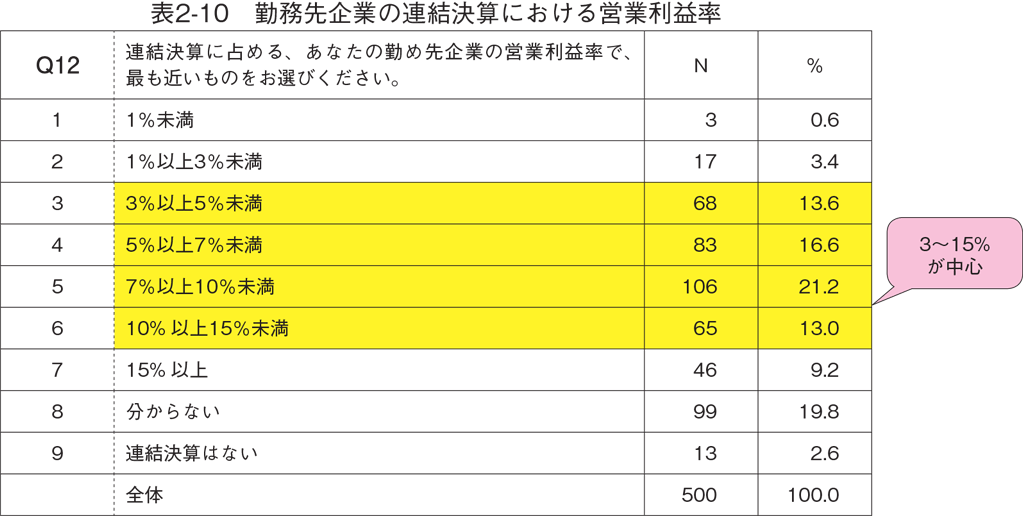
�\2-10����́A��ʓI�ȓ��{�̐����ƂƔ�ׂāA�O���[�o���i�o��Ƃ̘A���c�Ɨ��v���͏����Ă��邱�Ƃ�������B
�y120�Łz
�ȍ~�̎���́A�ȉ��̕������Q�l�ɍ쐬�����B
�@�݂��َY�ƒ����^50 2015 No.2 pp.1-378 �w���B�̋����͂̌����T��|���A�ۑ�ƌ����������B����w�Ԃׂ����Ƃ͉����|�x ���ɑ� II ���w���B�O���[�o���g�b�v��Ƃ̋����헪�x�𒆐S�ɁB
�A���{�̐H�i���[�J�[�Ɖ��B�H�i���[�J�[�i�l�X���E���j���[�o���j�Ƃ̈Ⴂ�݂��ً�s�Y�ƒ������i�U-1-5.�j
��L��2�̕�������A���B�H�i��Ƃ̋��݂́A�K�i�����u�����h�Ǘ��Ƃ������u�W�����v�ƁA�s������܂����Q���헪���ĂɌ�����u���[�J�����v�̍I�݂ȑg�ݍ��킹�A�����āA�_��ȁu�p�[�g�i�[�V�b�v�헪�v�ɂ��肻���ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B���n��Ƃɂ́A�O���[�o����Ƃ̎��g�݂���w�Ԃׂ��_���w�сA�X�s�[�f�B�[�ɊC�O�W�J��i�߂Ă������Ƃ����߂��悤�B�������Q�l�Ƃ�������̉��ʂ��ȉ��ɂ܂Ƃ߂Ă����B
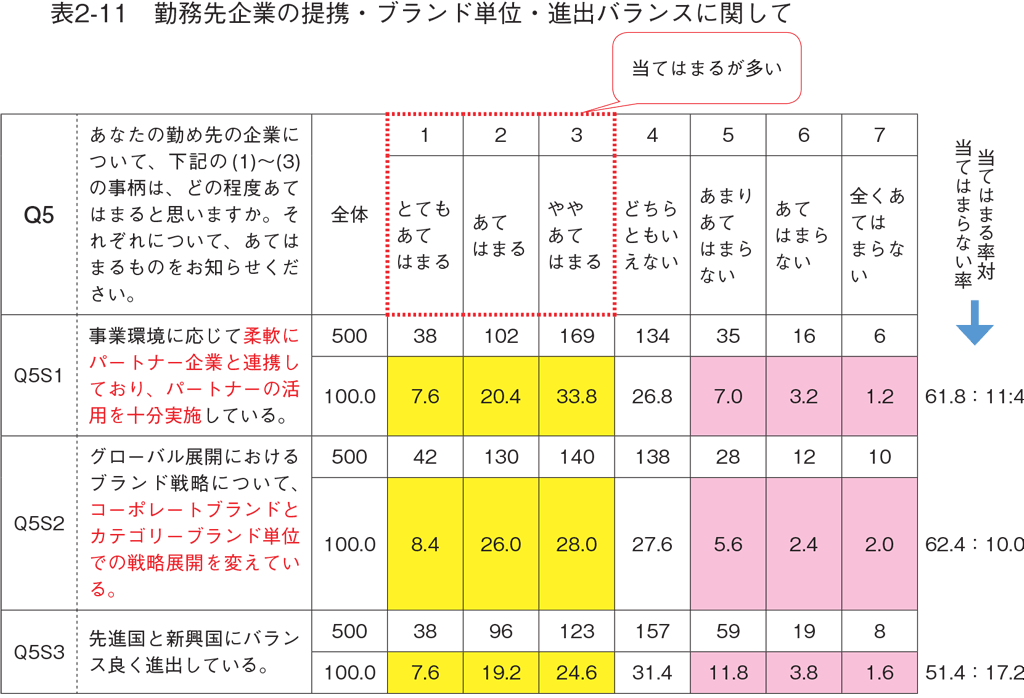
�u�����h�헪�ɂ��ẮA���n��Ƃ̓R�[�|���[�g�i��Ɩ��j�u�����h�i������P�u�����h�j���d������X��������A�O���[�o���W�J����v�Ǘ��ʂł́A�O�����[�J�[�ł��� P&G �̂悤�ɃJ�e�S���[�u�����h�P�ʂł̐헪���L���ƂȂ肤�邱�Ƃ��玿����쐬�����B�������A�ҁi�T���v���j�̑唼���R�[�|���[�g�u�����h���d������X����������n��Ƃł��������A�J�e�S���[�u�����h�W�J������ɓ���Ă����Ƃ��������ʂƂȂ����B
�y121�Łz
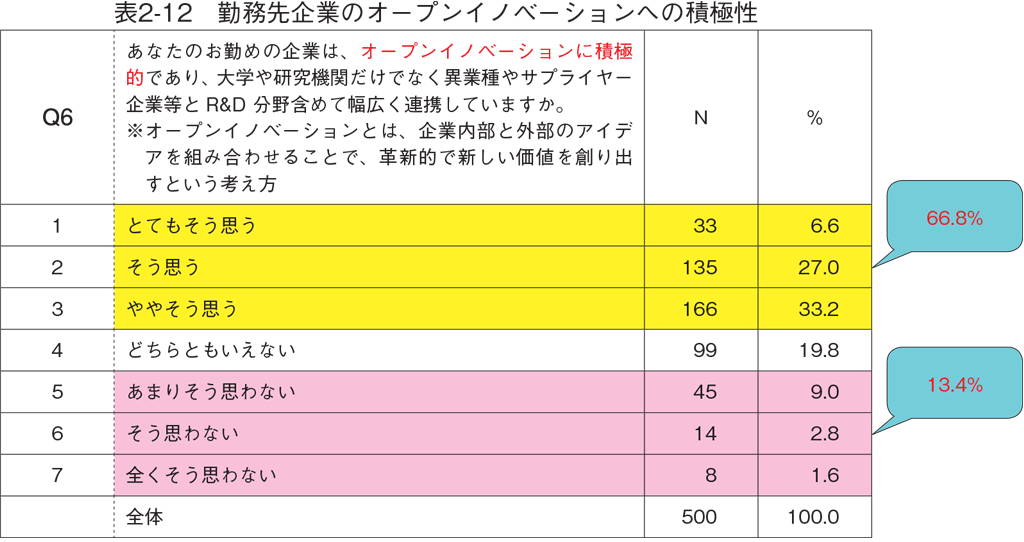
�\2-12����́A�O���[�o���W�J���s����Ƃ̓I�[�v���C�m�x�[�V�����ɐϋɓI�ŐV���������ɕq���ł��邱�Ƃ��킩��B
���ɁA�ȉ��̕\2-13-1�`�\2-13-4�̎���́A�}�[�P�e�B���O��4P�̗v�f�𒆐S�ɍ쐬���Ă���B�����̕\�ł́A�W�����i1�`3�j�ƃ��[�J�����i5�`7�j��3���ڂ̍��v�����𒆉��ɕ\�����Ă���B����4�́u�ǂ���ł��Ȃ��́v�͏����Ă���B�Ⴆ�A�\2-13-1�́u�����J���v�ɂ����ẮA�W�����F���[�J������30.4���F38.2���ł���A���[�J�����X������⋭�����Ƃ��킩��B���̕\����́A���ޗ����B�̃��[�J�����X�������ɑ傫�����Ƃ��킩��B
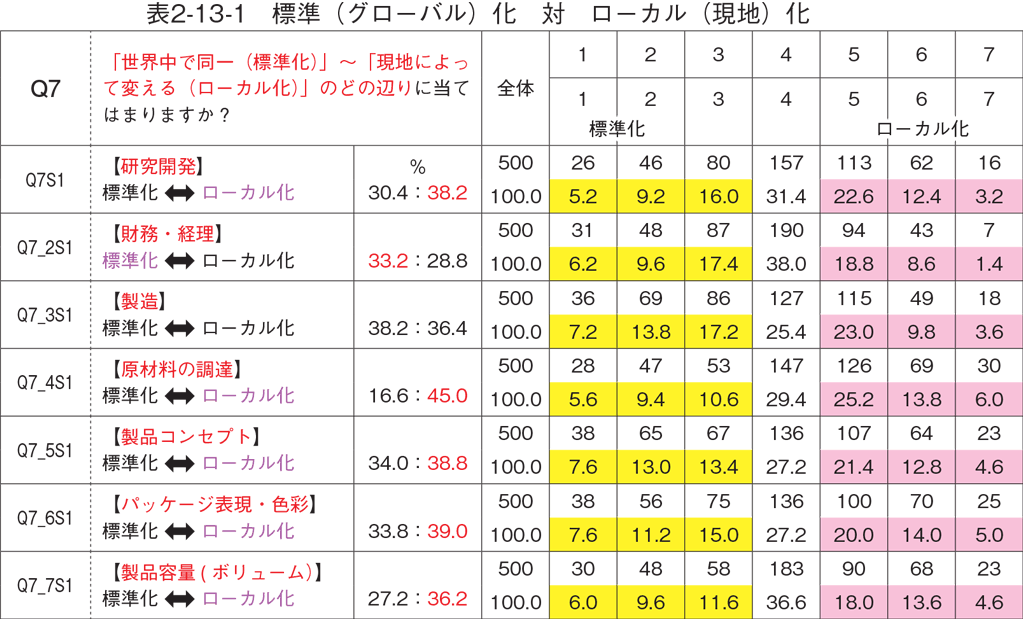
�y122�Łz
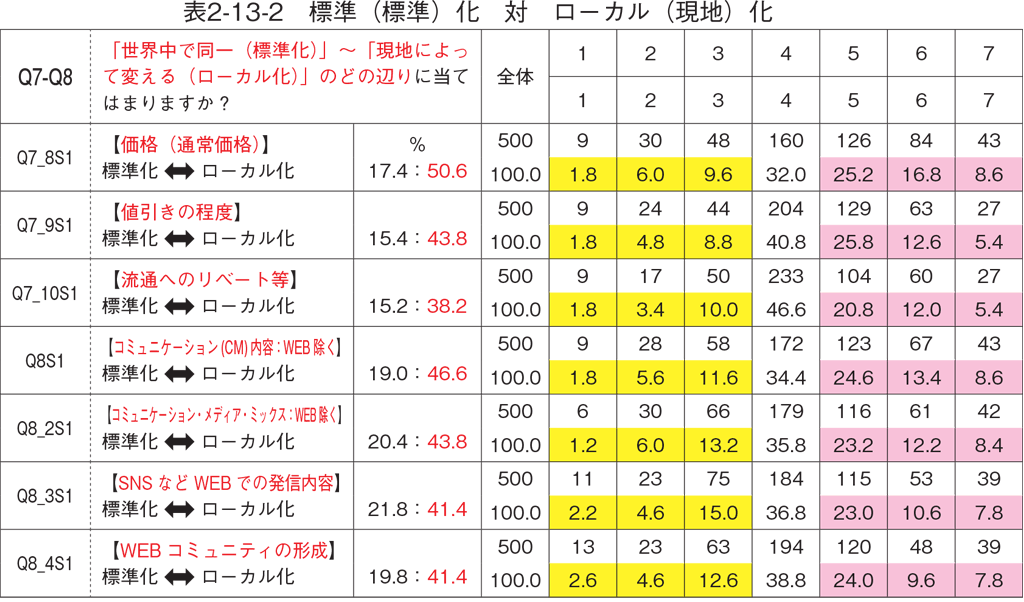
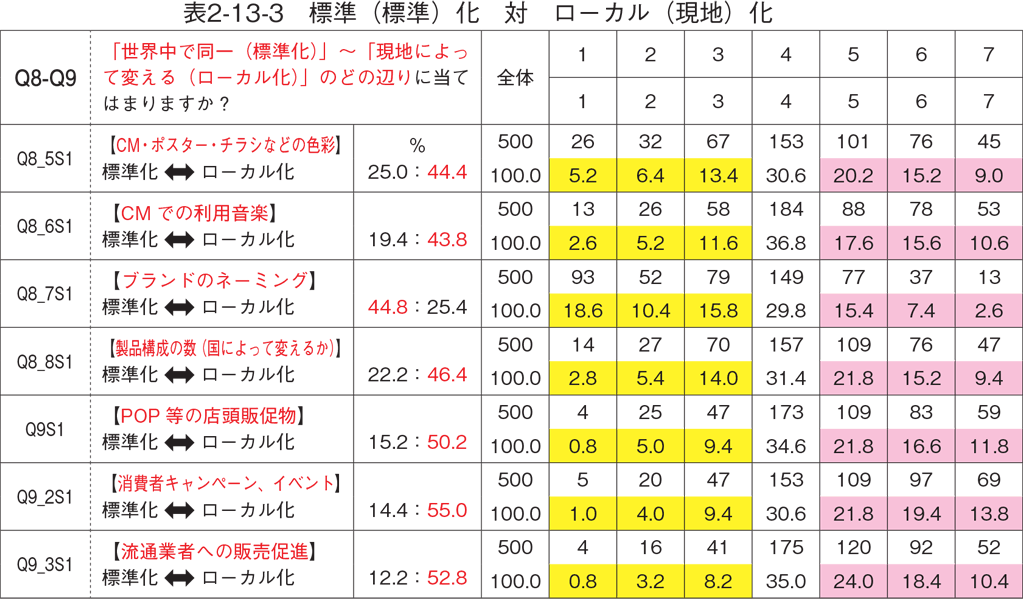
�y123�Łz

�����̕\2-13-1�`�\2-13-4�̌��ʂϓI�ɔc�����邽�߁A���[�J������������W�����������������l���A�W�����E���[�J�����̃o�����X�l�Ƃ��Ď����B�}2-1�̒ʂ�A�W�����A���[�J�������ɂ��ꂼ����x�̑傫�����ڂ�����ׂĂ݂�ƁA����X�������炩�ƂȂ����B���Ȃ킿�A�u�����h�̃l�[�~���O���ł��W�����X���ɂȂ邪�A�}������Ă���悤�ɍ����E�o�������W�����ł���A�v���_�N�g�A�R�~���j�P�[�V�����E����ґΉ��A���i�E�������B�A�`���l���A�Z�[���X�E�v�����[�V�����̏��Ń��[�J�����̌X���������Ă����B����́A���[�Y�i�u���Ȍ��ʂƌ����悤�B
�����Ɋւ��āA��ΖF�T�E�R���[�q�i2013�j�ł͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂ��Ă���6�j�B
�w�O���[�o���E�}�[�P�e�B���O�̌���I���e�̂ЂƂڂ́A��i�������̃}�[�P�e�B���O����r�㍑�����̃}�[�P�e�B���O�փV�t�g�������Ƃł���B���̔w�i�ɂ͐��E�ɂ�����r�㍑�̈ʒu�Â����傫���Ȃ������Ƃł���B�E�E�E��1�ɁA��i�������ɂ͐��i�̕i�����ő�̕���ł��������A�r�㍑�����ɂ͍w���\�z�iaffordability�j���ő�̕���ɂȂ�B�E�E�E�w���\�ȉ��i�ݒ�����������ŁA�Ȃ������v���o����}�[�P�e�B���O�헪�łȂ���ΐ����c�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
��2�ɁA���ʂ��������ꂽ��i���ƈقȂ�A�r�㍑�ł͗��ʌo�H���J�A����������I�E���ʓI�ɊǗ�����`���l�����ɂ߂ďd�v�ɂȂ�B�r�㍑�ł͒������Ƃ̕ی�ƌٗp�̊m�ۂ̂��߂ɋɂ߂Č��������ʋK��������E�E�E
��3�ɁA�v�����[�V�����͕����S���I�iculture bound�j�ł���A�r�㍑�ł͂Ƃ�킯���̌X���������B�L���ɂ����ăg�[�����}�i�[�͐��E�W�����ł����Ƃ��Ă��A�V���{����L�[���[�h�A�L�����N�^�[�≹�y�Ȃǂ͌��n�K��������邱�Ƃ������B�C���h�ł̃L�����N�^�[�́E�E�E�x
���̋L�q����A���i�A���ʃ`���l���A�Z�[���X�E�v�����[�V�����̓��[�J�����̌X�������邱�Ƃ��킩��B�܂��ARobert J. Dolan & Hermann Simon�i1996�j�ł��A�O���[�o�����E�ɂ����ĉ��i�ݒ�͕��G�����Ă���A���[�J�������Ó��ł���Əq�ׂ��Ă���7�j�B�������O���[�o�����̓�����ł��邪�A�A�o�����ނƓ��Ɂw���ۉ��i�G�X�J���[�V�����x���N����₷���A�e
�S������ł̗����₪�ςݏd�Ȃ�A���i�͍�������X�������邱�Ƃ��w�E����Ă���8�j�B
�y124�Łz
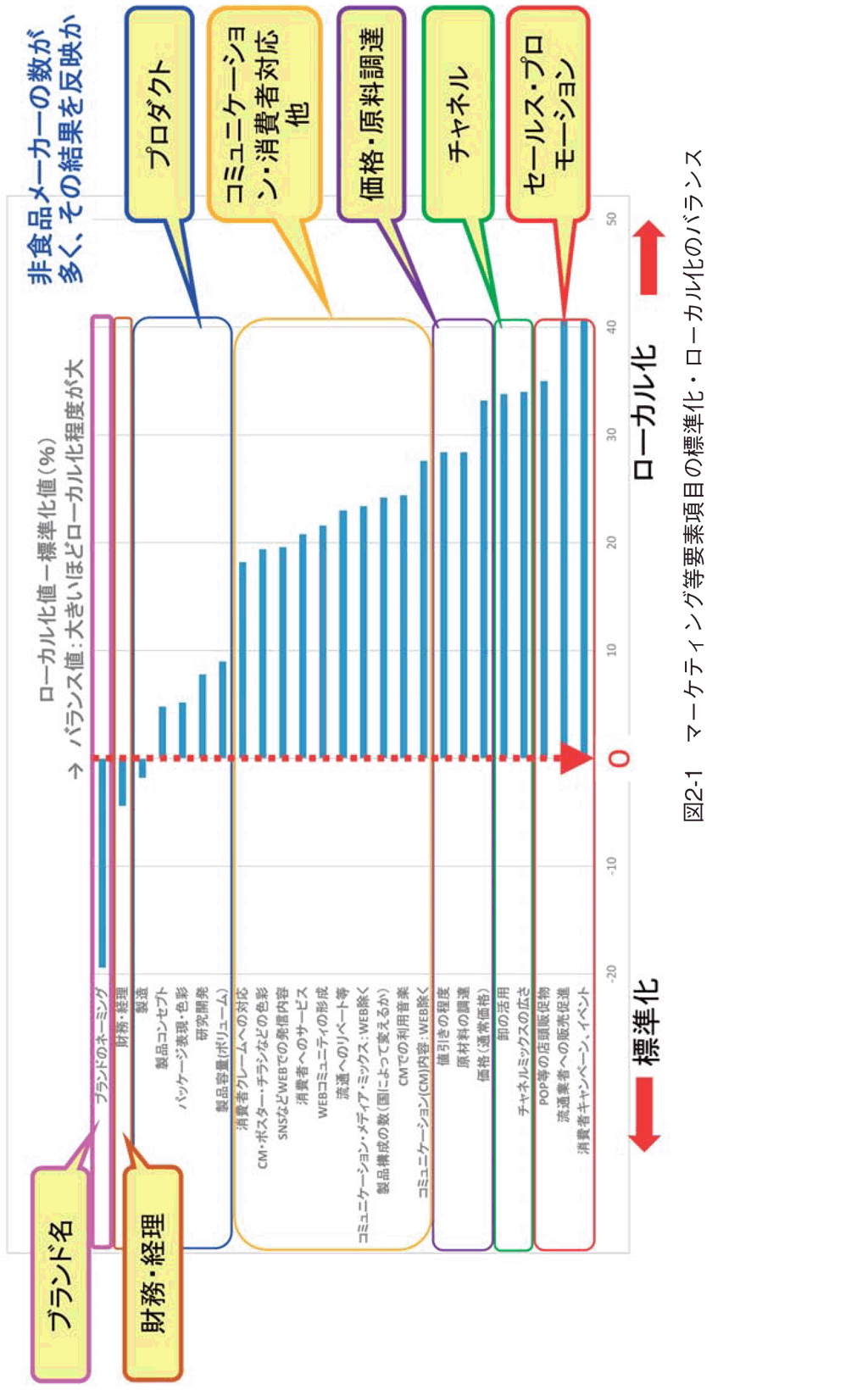
�y125�Łz
�@����Ƃ��ẮA�O���[�o����Ƃ̃R�J�R�[���Ђ��e��Ń��[�J���������{���Ă���A�^�C�ŃR�[���̊ʂɖ����̃f�U�C������������Ă��邪�A����͈��̃Z�[���X�E�v�����[�V�����ł���A�ɂ߂ă��[�J�����ł���v�f��������Ă���9�j�B���l�ɁA�O���[�o������Ƃł���X�^�[�o�b�N�X�����{�̋��s�Œz100�N�̌Ö��Ƃ��������A�l���̊Ŕ��Ȃ��Ǝ����̍����X�܂��\���Ă���B�܂��A�_�˂ɂ��n��F�̔Z���f�U�C���̓X�܂������Ă���B���Ƀ��[�J�����̍�������ł���10�j�B���n��Ƃ̃C�g�[���[�J�����������s�ɂ����Ă͕i�����ɂ����đS�̂�3�`4���͒n�悲�Ƃ̕i�����┄����ɂ��Ă���A���[�J������������Ă���11�j�B
3�D���n�H�i���[�J�[�Ɠ��n��H�i���[�J�[�E�O���n�H�i���[�J�[�Ƃ̔�r
�T���v�����ɃA���o�����X�����邪�A���n�H�i�E���n��H�i�E�O���n�H�i��3�̃��[�J�[�Ɋւ��Ĕ�r���s���B�܂��͊C�O���_���̔�r�ł���B�i�}3-1�j
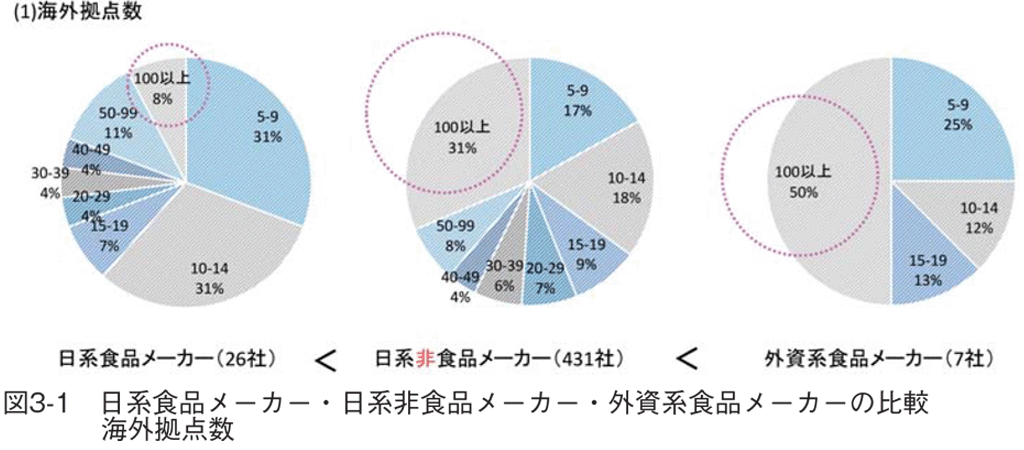
�}���̓��n�H�i���[�J�[�i26�Ёj�́A���ΓI�ɊC�O���_�������Ȃ��B�����Ɉʒu������n��H�i���[�J�[�i431�Ёj�́A���n�H�i���[�J�[���͊C�O���_���������A�O���n�H�i���[�J�[���͊C�O���_�����Ȃ��B�}�E�̊O���n�H�i���[�J�[�i7�Ёj�͏��T���v�������A�C�O���_��100�ȏ゠���Ƃ��������߂Ă���B���̌��ʂ���A���̂悤�Ȍ����������l������B
�w���n�H�i���[�J�[�͂܂��܂����_�����Ȃ��A�O���[�o���u�������Ⴂ�̂��B�x
�y126�Łz
�@���̐}3-2�́A�I�[�v���C�m�x�[�V�����Ɋւ���ϋɐ��ł���B
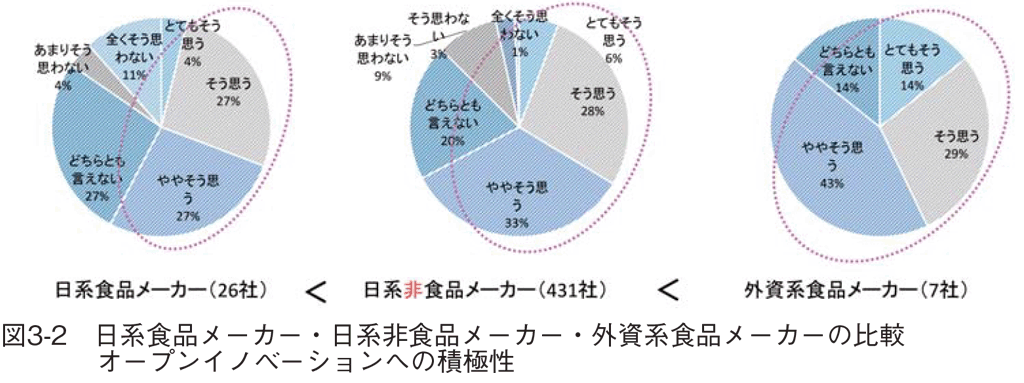
�u�ƂĂ������v���v�A�u�����v���v�A�u��₻���v���v�̍��v�́A�O���n�H�i���[�J�[86���A���n�H�i���[�J�[58���A���n��H�i���[�J�[67���ƂȂ�A�O���n�H�i���[�J�[���I�[�v���C�m�x�[�V�����ɔ��ɐϋɓI�ł��邱�Ƃ��킩��B���n�H�i���[�J�[�́A���ΓI�ɒႢ�B���̌��ʂ��玟�̂悤�Ȍ����������l������B
�w���n�H�i���[�J�[�̓I�[�v���C�m�x�[�V�����܂��s�����Ă���̂��B�x
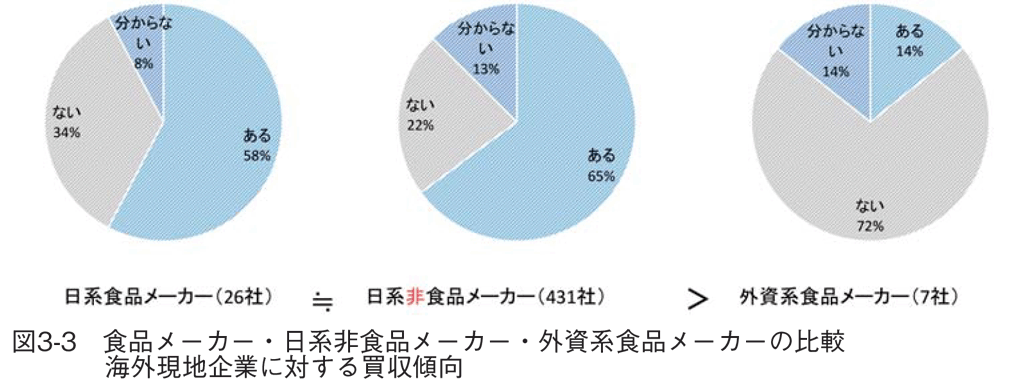
�C�O���n��Ƃ̔����Ɋւ��ẮA�O���n�̔����͑��ΓI�ɂ��Ȃ菭�Ȃ��B�t�ɓ��n���[�J�[�͔����o�����������A�����B���̌��ʂ��玟�̂悤�Ȍ����������l������B
�w���n���[�J�[�̃O���[�o���W�J�͌㔭�̂ɁA�x������߂����߂̔������s���Ă���̂��B�x
�y127�Łz
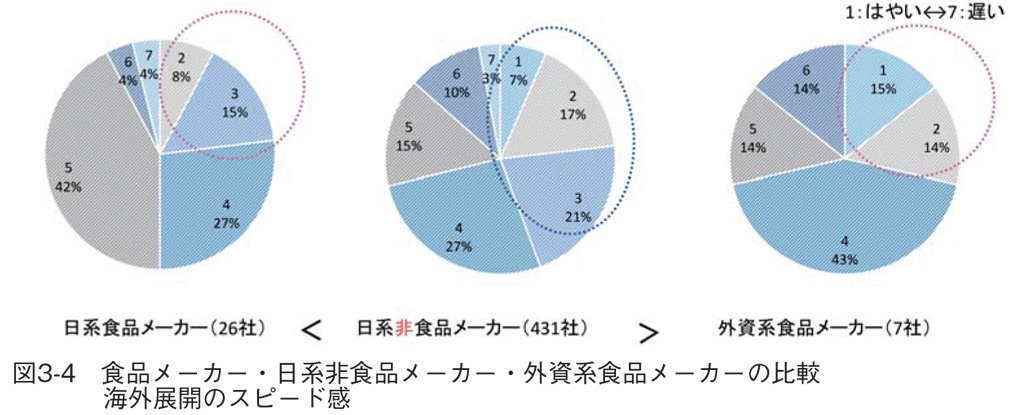
�]�ƈ��̊�����C�O�W�J�̃X�s�[�h�́A1�`3�i�͂₢�j�́����v�Ō���ƁA�H�i���[�J�[�ł́A���n��23���A�O���n��29���ŁA��H�i���[�J�[��45���ł���A�u�H�i���[�J�[�͔�H�i���[�J�[��葊�ΓI�ɂ������v�ł���B���̌��ʂ��玟�̂悤�Ȍ����������l������B
�w�H�i���[�J�[�̃O���[�o���i�o�X�s�[�h�͔�r�I�������ł���̂��B�x
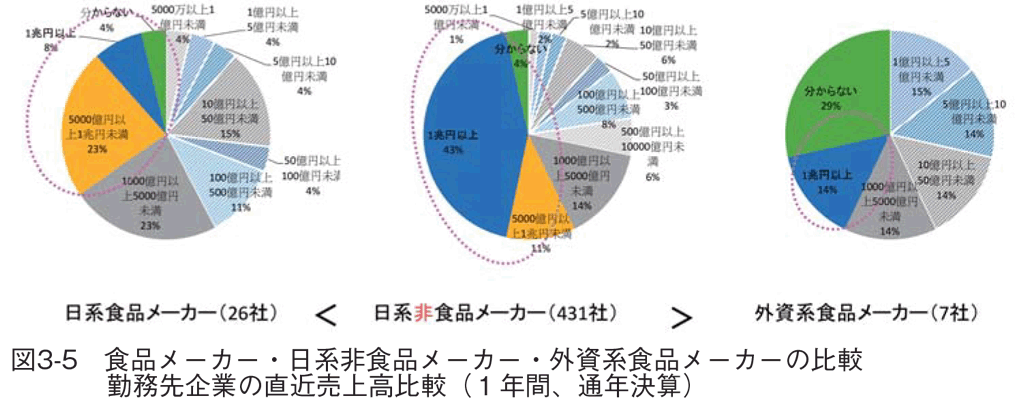
���n��H�i���[�J�[�����n�H�i���[�J�[�ł���A1���~�ȏ�i�j�Ŕ�r����ΊO���n�H�i���[�J�[�����n�H�i���[�J�[�������Ȃ�傫���B���̌��ʂ��玟�̗l�Ȍ����������l������B
�w�H�i���[�J�[�͑������Ǝ�Ɣ�r���Ĕ���K�͂��������B�x
�y128�Łz
�@�����Łu�C�O���㍂�䗦�v�Ƃ́A��Ƃ̔��㍂�̂����A�����ȊO�Ŕ���グ��������߂�䗦���w���B
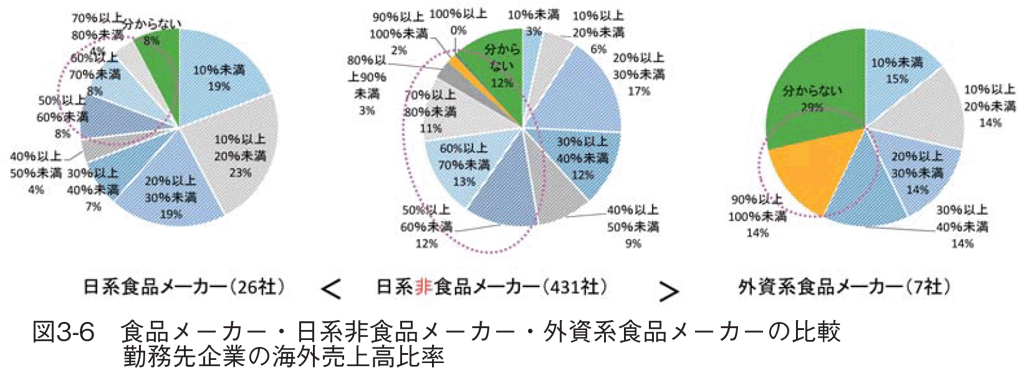
���ʂƂ��ē��n��H�i���[�J�[�����n�H�i���[�J�[�Ƃ������ɂȂ��Ă���B���̌��ʂ��玟�̗l�Ȍ����������l������B
�w�H�i���[�J�[�͑��ΓI�ɔ�H�i���[�J�[���K�͂͏������B�x

���̌��ʂ��玟�̗l�Ȍ����������l������B
�w�c�Ɨ��v���I�ɂ�3�҂Ƃ�����قǑ傫�ȍ��͂Ȃ����߁A�O���[�o���W�J�ɂ��K�͊g��̃C���Z���e�B�u�͓��n�H�i���[�J�[�ɂ͂���̂��B�x
�y129�Łz
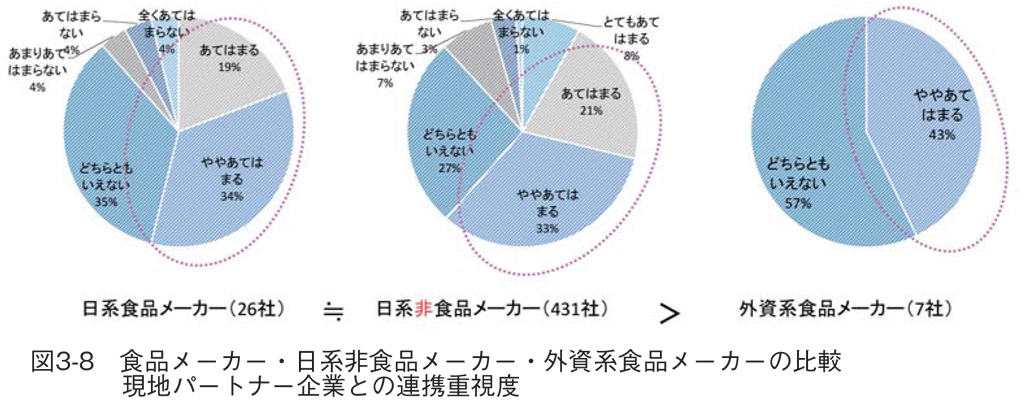
���̌��ʂ��玟�̗l�Ȍ����������l������B
�w�p�[�g�i�[��ƂƂ̘A�g�͓��n���[�J�[�̕����O���n���[�J�[�����d�����Ă���A���̗��R�̓O���[�o���W�J�̒x����J�o�[���邽�߂��B�x
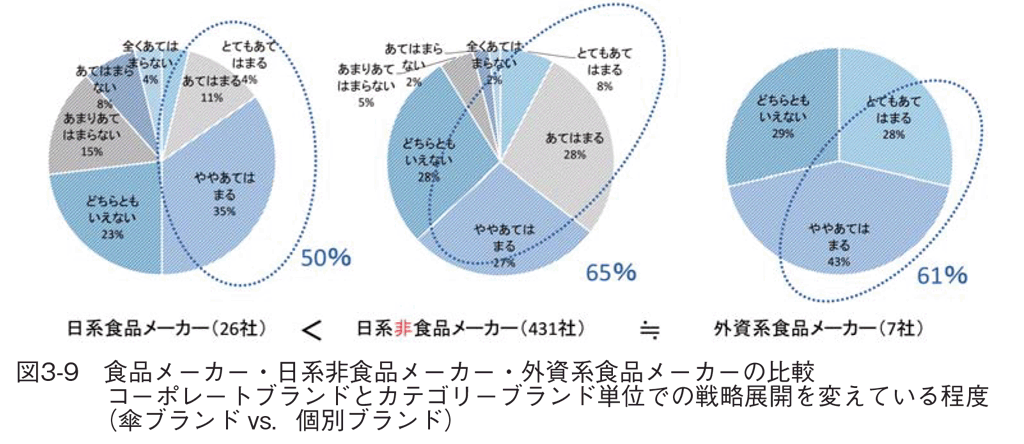
���̌��ʂ��玟�̗l�Ȍ����������l������B
�w���n�H�i���[�J�[�́A���n��H�i���[�J�[�A�O���n�H�i���[�J�[�Ɣ�ׂāA�R�[�|���[�g�A�J�e�S���[�u�����h�P�ʂŐ헪��ς��Ȃ��X���ɂ���̂��B�x
�y130�Łz
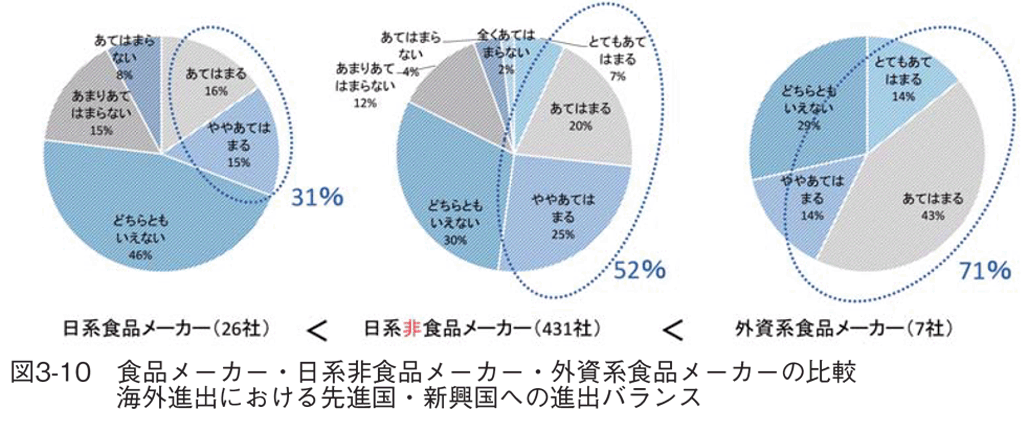
���̌��ʂ��玟�̗l�Ȍ����������l������B
�w���n�H�i���[�J�[�̊C�O�i�o�i��i���E�V�����j�̓A���o�����X�������̂��B�L�]�Ȓn��ɕ��Đi�o�̂��߂��A���邢�͌㔭�䂦���_���̏��Ȃ��Ƃ������R�̂��߂��B�x
���ɁA�}�[�P�e�B���O���v�f���ڂ̃Z�~�E�O���[�o���[�[�V�����̃o�����X��3�҂̃��[�J�[�łǂ̂悤�ɈقȂ邩���������Ă݂�B�S�̂ł̌��ʂ́A���n��H�i���[�J�[�����|�I�ɑ������߁A���̉e�����r��ł������B�}3-11�Ɛ}3-12������ꂽ���B
�y131�Łz
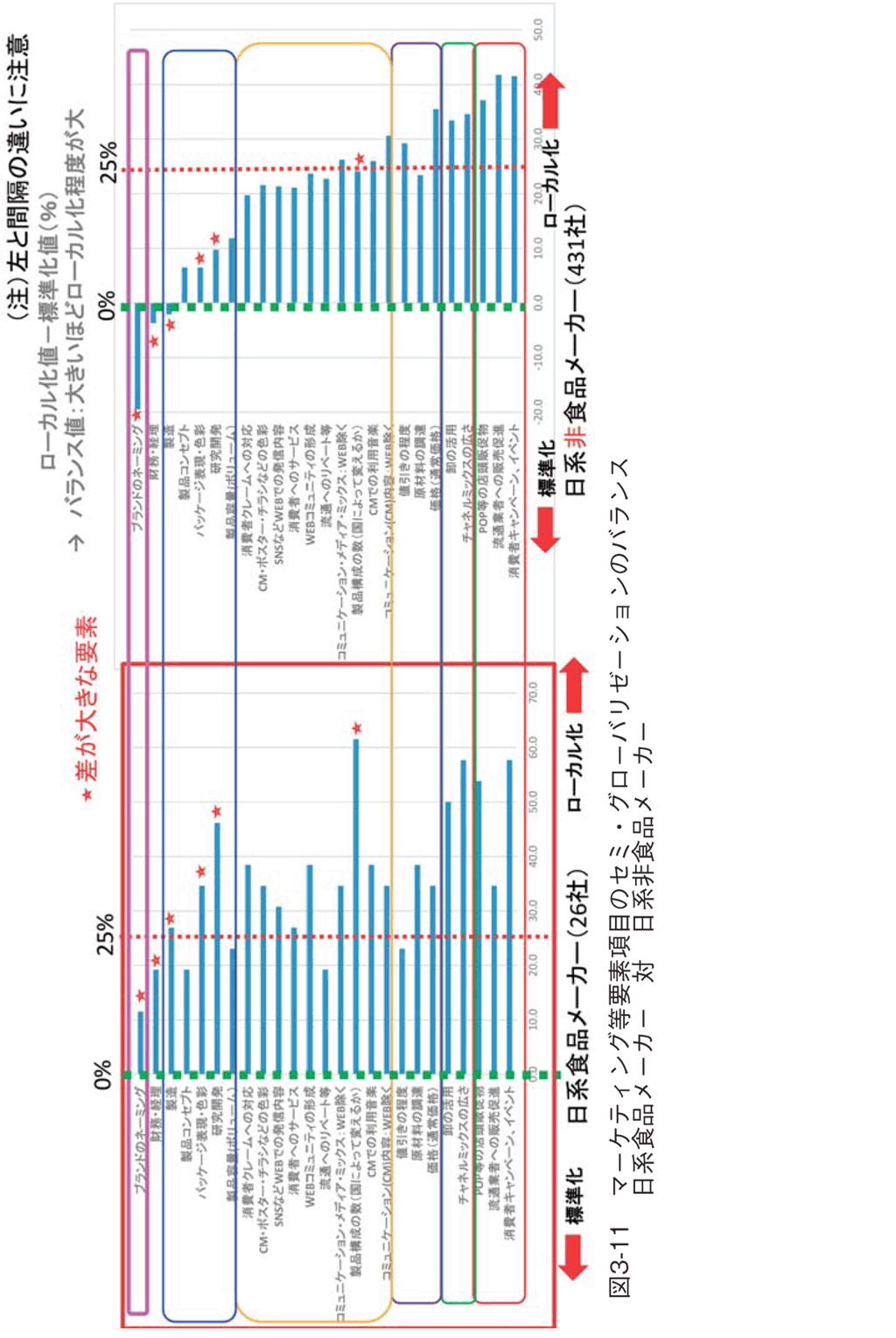
���̌��ʂ��玟�̗l�Ȍ����������l������B
�w���n�H�i���[�J�[�͓��n��H�i���[�J�[�ɔ�ׂ�ƈ��|�I�Ƀ��[�J�����������B����͂Ȃ����B�x25���̂Ƃ���Ń��C���������ƌ��ʂ͂��͂����肷��B
�y132�Łz
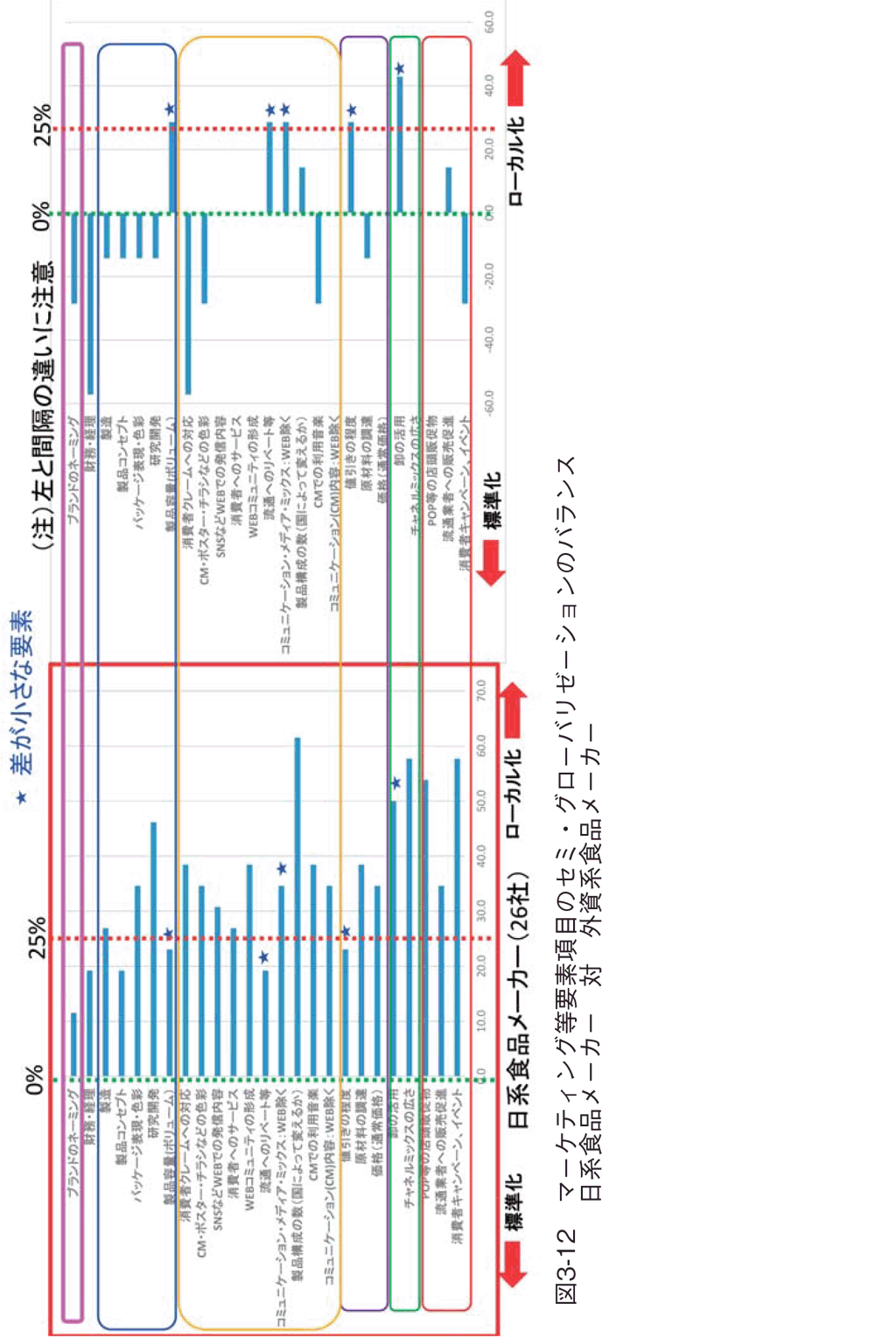
���̌��ʂ��玟�̗l�Ȍ����������l������B
�w�O���n�H�i���[�J�[�̕W�����̒��x���傫���A���n�H�i���[�J�[�̕W�����̒��x�����|�I�ɏ��������Ƃ������B����̓O���[�o���W�J�̗��j�����߂��B�x
�y133�Łz
�@��q�̃O���R�i���j�ēc��G���ւ̃C���^�r���[�ŁA��L�̌��ʂ͌����ɓ��Ă͂܂�̂ł͂Ȃ����Ɖł������B�H�i�̓Z�[���X�E�v�����[�V���������n�̏����K�ɏ]�����Ƃ���ʓI�ł���A���[�J�������₷���B���ɁA�c�Ƃ̓��[�J�������������B�O���n�H�i���[�J�[�Ɣ�ׂ�ƍ����傫�����A�N���[���Ή��Ȃǂ��O���͕W�������i��ł���B�A�����J��Ƃ̏ꍇ�A�t�B���s���֓d�b�����ȂǂƂ����悤�ȃO���[�o���Ή����i��ł���悤�ł���B
����܂ł� web �A���P�[�g�������͌��ʂ���̌����������܂Ƃ߂�ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B
�����n�H�i���[�J�[�F�܂��܂����_�����Ȃ��A�O���[�o���W�J�u�������Ⴂ���B
�����n�H�i���[�J�[�F�I�[�v���C�m�x�[�V�����s�����B
�����n���[�J�[�̃O���[�o���W�J�͌㔭�̂ɁA�x������߂����߂̔������������B
���H�i���[�J�[�̃O���[�o���W�J�X�s�[�h�͔�H�i�ɔ�ׂđ��ΓI�ɂ������ł���̂��B
���c�Ɨ��v���I�ɂ�3�҂Ƃ�����قǑ傫�ȍ��͂Ȃ��B
�䂦�ɂ���قǃO���[�o���W�J�ŋK�͊g��̃C���Z���e�B�u�͓��n�H�i���[�J�[�ɂ͂���̂��B
���p�[�g�i�[��ƂƂ̘A�g�͓��n�̕����d�����Ă���悤�����A���R�̓O���[�o���W�J�̒x����J�o�[���邽�߂��B
�����n�H�i���[�J�[�́A���n��H�i���[�J�[�A�O���n�H�i���[�J�[�Ɣ�ׂāA�R�[�|���[�g�A�J�e�S���[�u�����h�P�ʂŐ헪��ς��Ȃ��X���ɂ���̂��B
�����n�H�i���[�J�[�̊C�O�i�o�i��i���E�V�����j�̓A���o�����X�������悤�����A�L�]�Ȓn��ɕ��Đi�o���Ă��邽�߂��A����Ƃ��㔭�E���_���̏��Ȃ��Ƃ������R�̂��߂��B
�����n�H�i���[�J�[�͓��n��H�i���[�J�[�ɔ�ׂ�ƁA���l�ȗv�f�ɂ����Ĉ��|�I�Ƀ��[�J�����������B����͂Ȃ����B
�������̍��ڂŊO���n�H�i���[�J�[�̕W�����̒��x���傫���A���n�H�i���[�J�[�̕W�����̒��x�����|�I�ɏ��������Ƃ������B����̓O���[�o���W�J�̗��j�����߂��B
4�D�Z�~�E�O���[�o���[�[�V�����x�Ɖc�Ɨ��v�Ƃ̊W�����T���F����1
�A���c�Ɨ��v�����]���ϐ��i7�i�K�F1�������A1-3�������A3-5�������A5-7�������A7-10�������A10-15�������A15���ȏ�j�ɁA���̑��i�ȉ��Ɏ����j��Ɨ��ϐ��Ɏ��A�J�e�S���J����A�����{�B
�i357�f�[�^�Ŏ��{�F���͌��ʂł킩��Ȃ��Ɠ������T���v�������j
���F�J�e�S���J����A�F�]���ϐ��ɃJ�e�S���J���f�[�^���܂މ�A����
�ϐ��͕W�����x���傫�Ȓl�قǑ傫�Ȑ��l�ɂȂ�悤�A7�i�K�Ȃ�A8���獷���������l�𗘗p�B�Ⴆ�A�ȉ��\4-1�� Q7S1�ŁA�W�����̒��x�������قǑ傫�Ȑ��l�����悤�ɂ��邽�߂ɁA1�`7�̒l��8���獷�������A8-1=7�Ƃ����悤�ɔ��]�v�Z���ė��p����B�\4-1���Q�Ƃ��ꂽ���B
�y134�Łz
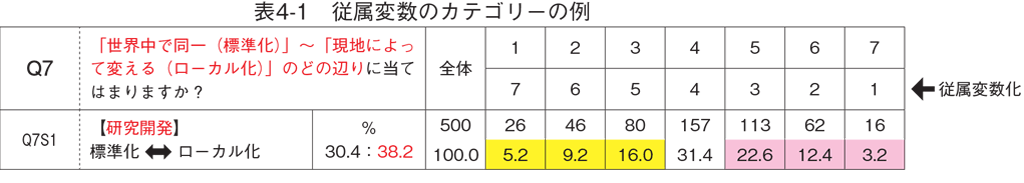
�Ɨ��ϐ��͈ȉ��̂Ƃ���ł���B
Q7�`Q9�̃}�[�P�e�B���O���v�f���ڔ��]�l�ASC2�F�����ƃJ�e�S���[�i�H�i�E�H�i���H�` ���̑������Ɓj�ASC3�FB2B�EB2C�E�����̕ʁASC6�F�C�O���_���AQ1�F�C�O���n��Ɣ����̗L���AQ10�F���ߔ��㍂�K�� / �N�AQ11�F�C�O���㍂�䗦�AQ4�F���{���ЈȊO�̏]�ƈ������̔��]�l�AQ5S1�F�p�[�g�i�[��Ƃ̊��p�x���]�l�AQ5S2�F�R�[�|���[�g�u�����h�ƌʃu�����h�̎g���������]�l�AQ5S3�F��i���E�V�����i�o�̃o�����X�̗ǂ����]�l�AQ6�F�I�[�v���C�m�x�[�V�����ւ̐ϋɐ����]�l
���j���̃J�e�S���J����A�ł͏]���ϐ��Ƃ��āA���l�A�����A�X�v���C��������3�̑I����������B
���l�͘A���ϐ��Ƃ��āA�����͏����f�[�^�Ƃ��Ĉ�����B�����ŃX�v���C�������Ƃ͈ȉ����Ӗ�����B�w�ϑ��ϐ��̃J�e�S���[�̏����́A�œK�ړx�ϐ��Ɋi�[�����B�J�e�S���[�E�|�C���g�́A���_��ʂ钼���i�x�N�g���j��ɔz�u�����B�ϊ��̌��ʂ́A�I�����ꂽ�����̊��炩�ŒP���ȋ敪�I�������ɂȂ�B���[�U�[���w�肵�������m�b�g�̐��Ǝ葱���ɂ���Č��肳�ꂽ�����m�b�g�̔z�u�ɂ��A�敪���w�肳���B�x
�ihttps://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ja/SSLVMB_24.0.0/spss/categories/idh_catr_scale.html�j
���͌��ʂ͈ȉ��̕\4-2�̂悤�ɁA�X�v���C�������͐��l�Ə����̒��Ԃ̌��ʂƂȂ����B����䂦�]���ϐ��Ƃ��ẮA�����f�[�^�Ƃ��Ĉ����ꍇ�ɐ����͂������Ȃ�B�������A��A�ł̕ϐ��̓��v�I�L�ӌX���͗L�ӊm���̎�̍��ŗL�ӁE��L�ӂɕ�����Ă��܂��B������3�̏ꍇ�̂ǂꂩ�œ��v�I�ɗL�Ӂi�����ł�10�������j�ɂȂ����Ɨ��ϐ��͂��ׂč̗p���Ă݂�B�܂��Ɨ��ϐ����m�̑��ւō������̂͂Ȃ������B
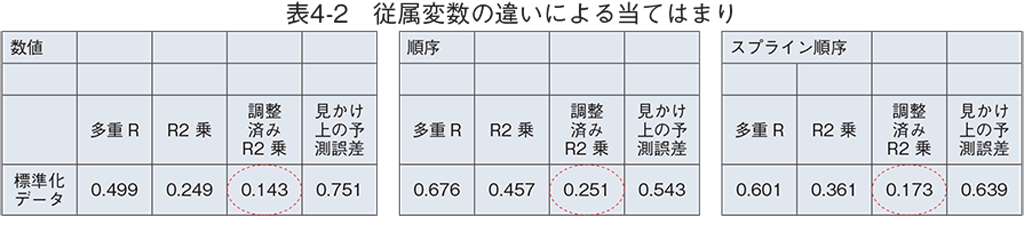
�y135�Łz
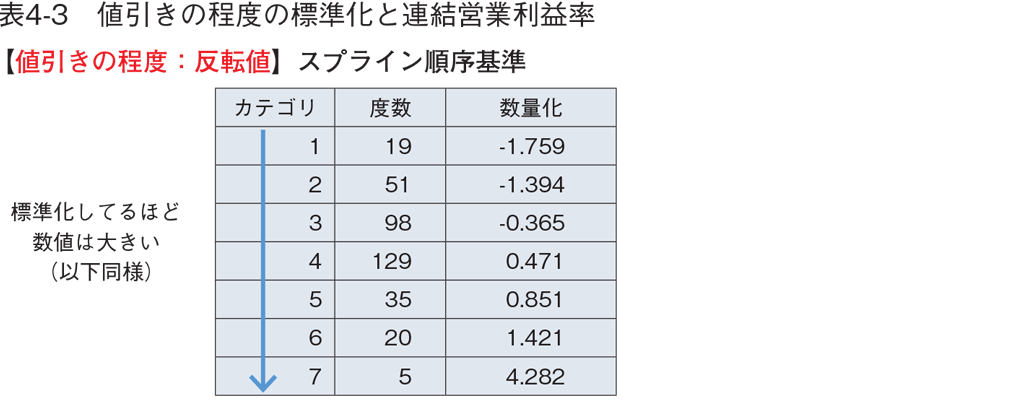
�A���c�Ɨ��v�������߂�v�����ʂɌ������Ă����B�܂��\4-3������ꂽ���B
���̕\4-3���݂�ƁA�l�����̒��x�͕W�������Ă���������v���͍������Ƃ��킩��B���ɕ\4-4���݂�� CM�E�|�X�^�[�E�`���V�Ȃǂ̐F�ʂ̒��x�́A�W�����̕������v���͍������Ƃ��킩��B

���l�Ƀu�����h�E�l�[�~���O�A�����Ƃ̋Ǝ�AB2B �� B2C �̈Ⴂ�A�C�O���n��Ƃ̔����o���̗L���A���߂̔��㍂�A�C�O���㍂�䗦�A�p�[�g�i�[�̏_��Ȋ��p���x�̕W�����ƘA���c�Ɨ��v�������߂�v�����ʂɌ������Ă݂��B���ʓI�Ɉȉ��̂��Ƃ��킩�����B
�E�u�����h�̃l�[�~���O�̓��[�J�����̕������v���͍����B
�E�H�i�E�H�i���H�͂���قǗ��v���������Ȃ��B
�EB2C �� B2B ���p���� B2C ��Ƃ̕������v���͍����B
�E�C�O���n��Ƃ̔����o�����Ȃ��ꍇ�A���v���͒Ⴂ�B
�E���߂̔��㍂���傫���قǗ��v�����傫���B����5000���~�ȏ� / �N�̔��㍂���L���ł���B
�E�C�O�̔��㍂�䗦�������قǗ��v�����傫���B
�E�_��Ƀp�[�g�i�[��ƂƂ͘A�g�����������v���͍����B
3��ނ̏]���ϐ��ł̉�A�̌��ʊT�v���A�ȉ��̕\4-5�ɋL���Ă����B�x�[�^�W���ʼne���x�̑傫�����r���邱�Ƃ��\�ł���B
�y136�Łz
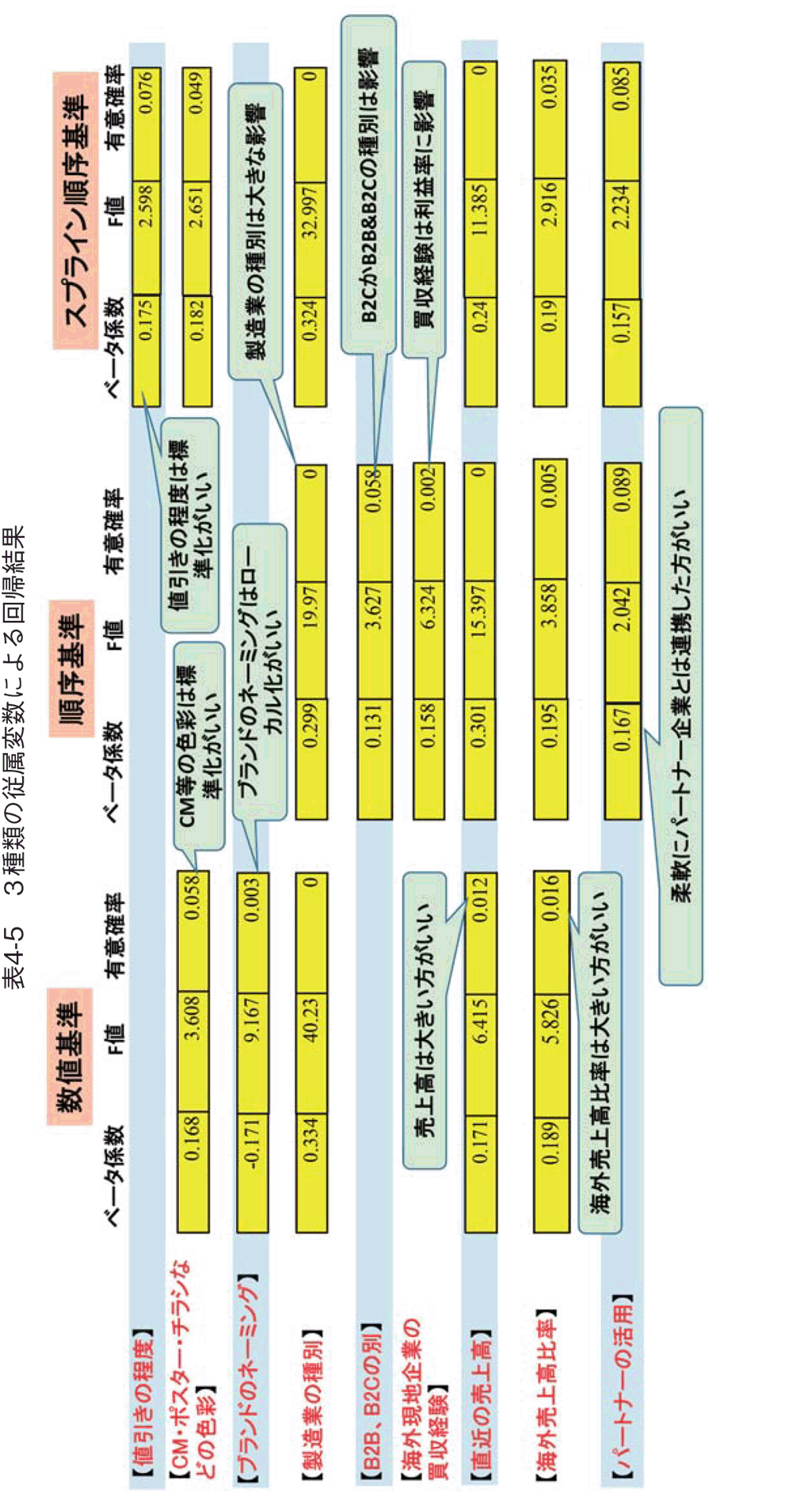
�y137�Łz
�@�@�@ �@�{�́i����1�F���v���Ƃ̊֘A���ځj�̌��ʂ���A�ȉ��̒T������������ꂽ�B
���l�����̒��x�͕W�����̕������v���͍����H�i�Z�~�E�O���[�o���[�[�V�������ځj
�� CM�E�|�X�^�[�E�`���V�Ȃǂ̐F�ʂ̒��x�͕W�����̕������v���͍����H�i�Z�~�E�O���[�o���[�[�V�������ځj
���u�����h�̃l�[�~���O�̓��[�J�����̕������v���͍����H�i�Z�~�E�O���[�o���[�[�V�������ځj
�� B2C ��Ƃ̕������v���͍����H
���C�O���n��Ƃ̔����o�����Ȃ��ꍇ�A���v���͒Ⴂ�H
�����㍂���傫���قǗ��v�����傫���B����5000���~�ȏ� / �N�̔��㍂���L���H
���C�O�̔��㍂�䗦�������قǗ��v�����傫���H
���_��Ƀp�[�g�i�[��ƂƂ͘A�g�����������v���͍����H
5.�Z�~�E�O���[�o���[�[�V�����x�����肷��v�������T���F����2
�}�[�P�e�B���O���v�f���ڂɂ��āA�O���[�o���[�[�V�����x�̋�������߂��Ƃ̎���������T������ �iSPSS �̃J�e�S���J����A���͂ɂ��j�B
Q7�`Q9�̃}�[�P�e�B���O���v�f25���ڔ��]�l1�����]���ϐ��ɂƂ�A���̑��i�ȉ��Ɏ����j�̕ϐ����ׂĂ�Ɨ��ϐ��ɂƂ�A�J�e�S���J����A�i���l��j�����{�B�i406�f�[�^�F���͂Łu�킩��Ȃ��v�Ɖ����T���v���������j
�Ɨ��ϐ��͈ȉ��̒ʂ�ł���B
SC2�F�����ƃJ�e�S���[�i�H�i�E�H�i���H�`���̑������Ɓj�ASC3�FB2B�EB2C�E�����̕ʁA
SC6�F�C�O���_���AQ1�F�C�O���n��Ɣ����̗L���AQ10�F���ߔ��㍂�K�� / �N�AQ11�F�C�O���㍂�䗦�AQ4�F���{���ЈȊO�̏]�ƈ������̔��]�l�AQ5S1�F�p�[�g�i�[��Ƃ̊��p�x���]�l�A
Q5S2�F�R�[�|���[�g�u�����h�ƌʃu�����h�̎g���������]�l�AQ5S3�F��i���E�V�����i�o�̃o�����X�̗ǂ����]�l�AQ6�F�I�[�v���C�m�x�[�V�����ւ̐ϋɐ����]�l
�����ϐ����m�ő��ւ̍������̂͂Ȃ��������߁A���d�������̋���͏������B�������A�����ς�R2�悪0.05�����̂��̂͐����͂����������ߏȗ����邱�ƂƂ����B
���ʂ�\�Ƃ��Ď����B�܂��\5-1���Q�Ƃ��ꂽ���B���̌��ʂ��琻���ƃJ�e�S���[�̓u�����h�̃l�[�~���O�̕W�����ɗL�ӂȉe�����y�ڂ��Ă��邱�Ƃ��킩��B�������A�����Ƃ̒��ł́A�H�i�̓��[�J�������i�X��������B
�y138�Łz
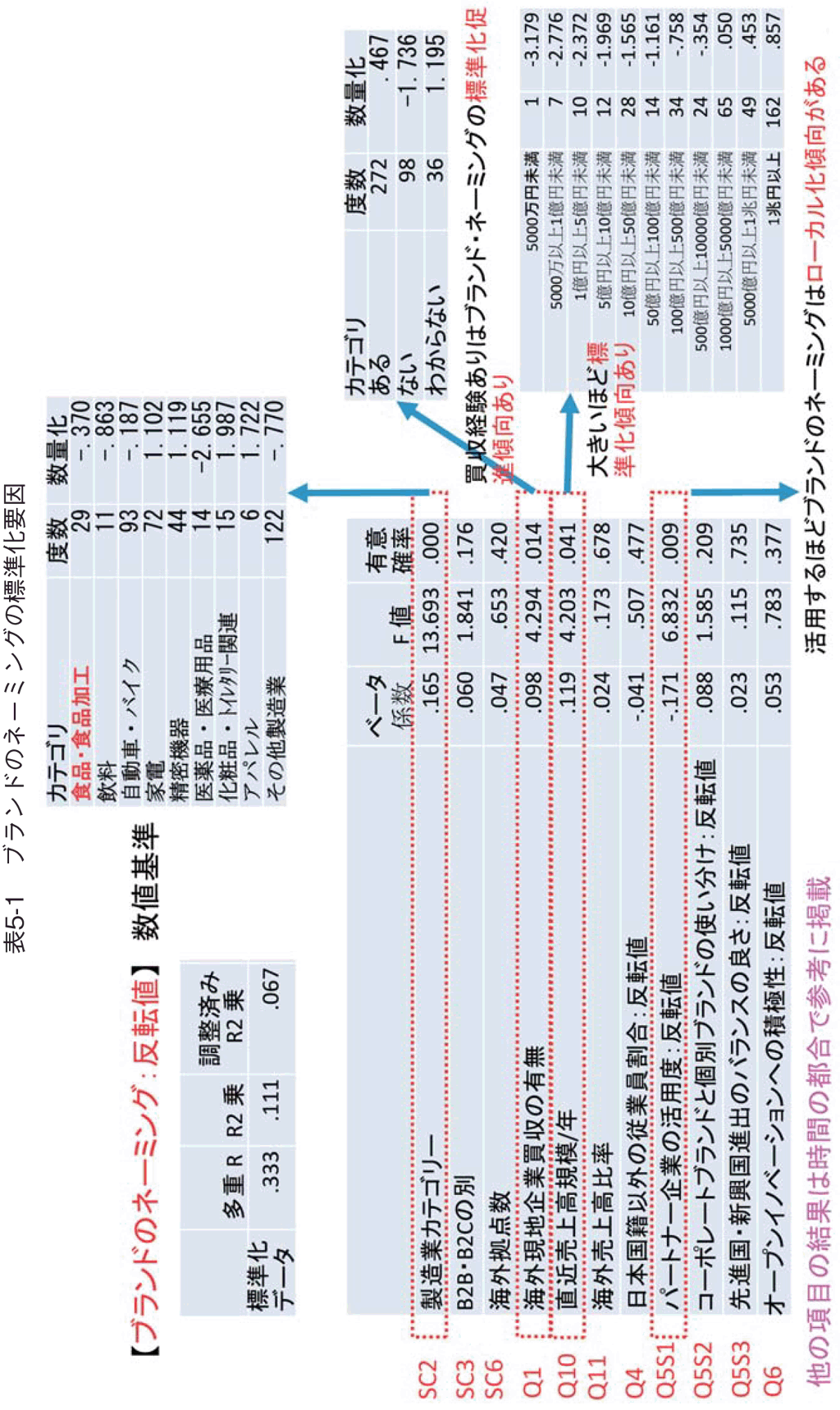
�y139�Łz
���l�ɏ��ɕ��͌��ʂ������Ă䂭�B
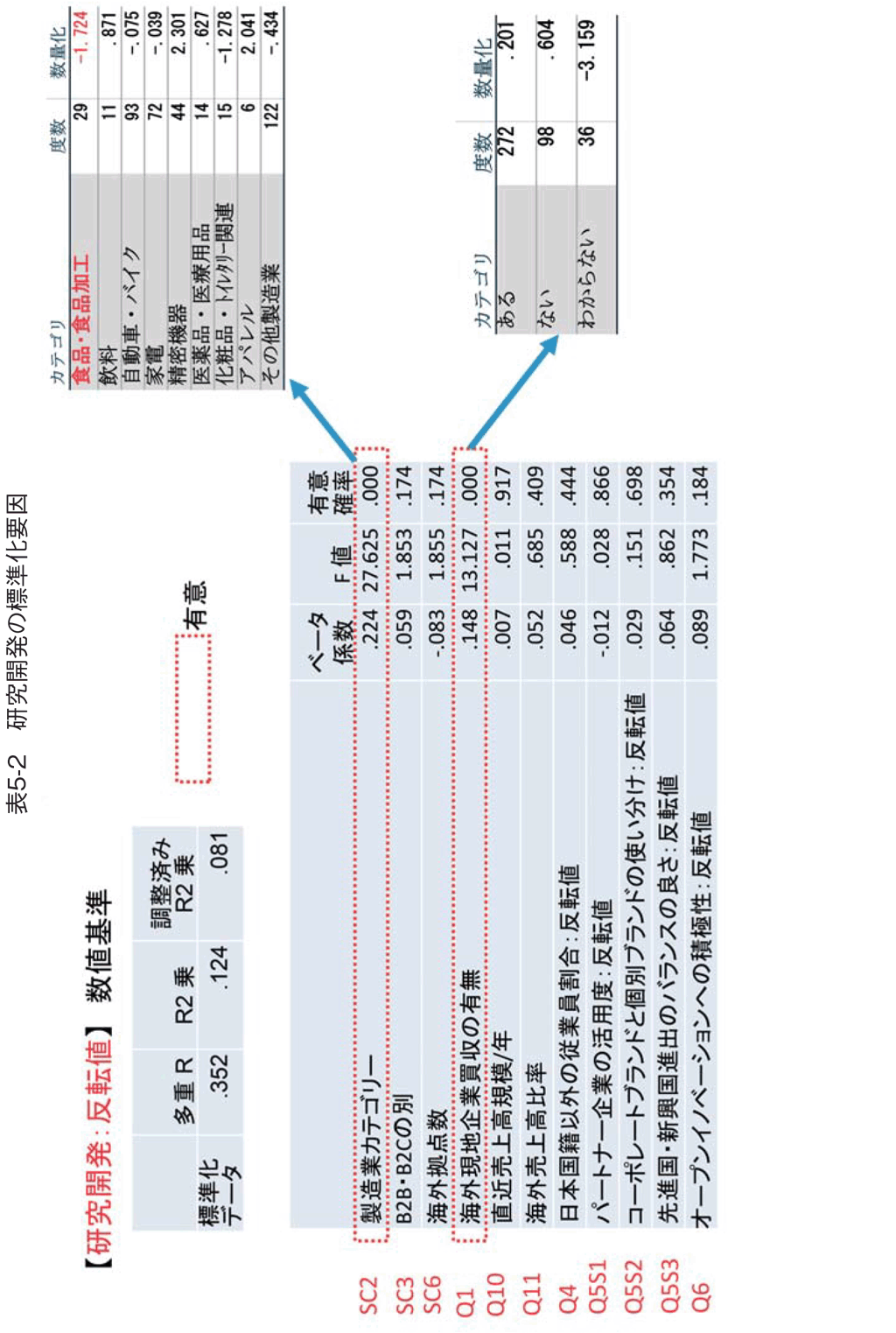
�y140�Łz
�@���ʓI�ɁA�C�O��Ɣ����o���́u����E�Ȃ��v���ɕW�����𑣐i���邪�A�����o���̂Ȃ����������J�����W�������邱�Ƃ��킩�����B
WEB �R�~���j�e�B�̌`���̕W�����Ɋւ��ẮA�\5-3��萻���ƃJ�e�S���[�� WEB �R�~���j�e�B�̌`���̕W�����ɗL�ӂȉe�����y�ڂ����Ƃ��킩�����B
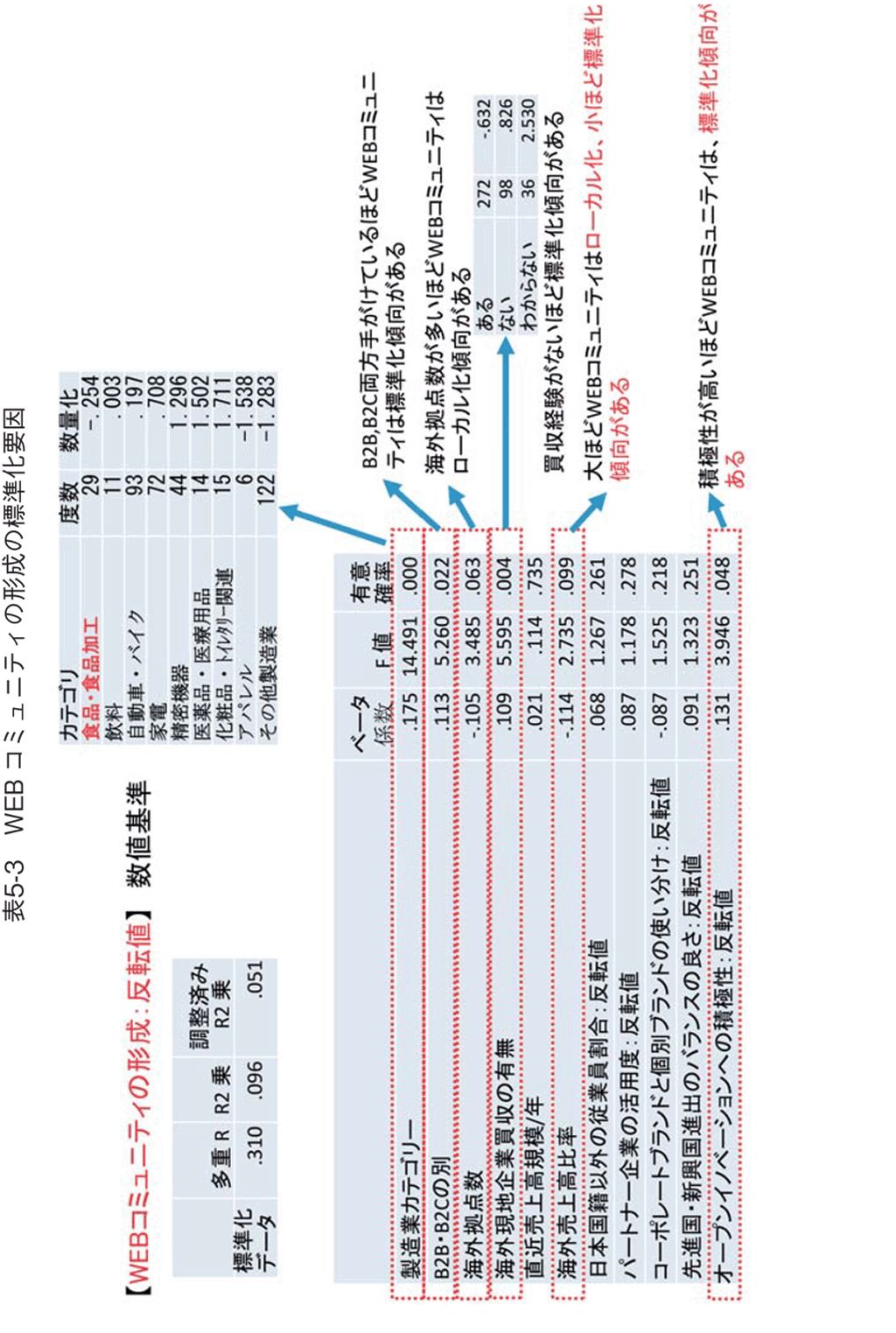
�y141�Łz
�@�\5-4�́A�����ƃJ�e�S���[���R�~���j�P�[�V�����E���f�B�A�E�~�b�N�X�̕W�����ɗL�ӂȉe�����y�ڂ��A�H�i�̓��[�J�������i�X�����邱�Ƃ��킩��B

�y142�Łz
�@���̕��͌��ʂ��������߁A���ʂ݂̂��ȉ��ɂ܂Ƃ߂Ď������Ƃɂ���B
�{�́i���͂Q�j�̌��ʂ���A�Z�~�E�O���[�o���[�[�V�����x����v���������l�@����ƁA�� ���I�Ɉȉ��̂悤�Ȃ��Ƃ������悤�B
�������ƃJ�e�S���[�͌����J���ACM ���e�A�R�~���j�P�[�V�����E���f�B�A�E�~�b�N�X�A WEB �R�~���j�e�B�̌`���A�u�����h�̃l�[�~���O�A����҃L�����y�[���E�C�x���g�A�����p�̕W�����ɗL�ӂȉe�����y�ڂ��B�������Ȃ���A�H�i�͍Ń��[�J�������i�X�����肩�H
��B2B�AB2C �����肪���Ă���ق� WEB �R�~���j�e�B�̌`���͕W�����X�������邩�H
���C�O���_���������قǃR�~���j�P�[�V�����E���f�B�A�E�~�b�N�X�AWEB �R�~���j�e�B�̌`���̓��[�J�����A�܂���e��ς��邩�H
�����n��Ƃ̔����o��������E�Ȃ����ɕW�����𑣐i���邪�A�����o���̂Ȃ����������J���A
WEB �R�~���j�e�B�̌`���A�����p�����W�������邩�H�����ău�����h�E�l�[�~���O�̓��[�J�������邩�H
�����ߔ��㍂�K�� / �N���傫���قǃu�����h�̃l�[�~���O�̕W�����X�����肩�H�����ď���҃L�����y�[���E�C�x���g�A�����p�̃��[�J�����X�����肩�H
���C�O���㍂�䗦���傫���ق� CM ���e�AWEB �R�~���j�e�B�̌`���̓��[�J�����A�������قǕW�����܂蓯�����e���H
�����{���ЈȊO�̏]�ƈ��������傫���ق� CM ���e�A�����p�͕W�����A�܂���e�͓������H
���p�[�g�i�[��Ƃ����p����ق� CM ���e�͕W�����A�܂���e�������H�����ău�����h�̃l�[�~���O�̓��[�J�����X�������邩�H
���R�[�|���[�g�u�����h�ƌʃu�����h�̎g������������ق� CM ���e�A�R�~���j�P�[�V�����E���f�B�A�E�~�b�N�X�A����҃L�����y�[���E�C�x���g�A�����p�̓��[�J�����A�܂���e��ς��邩�H
����i���E�V�����փo�����X�悭�i�o����ق� CM ���e�A�R�~���j�P�[�V�����E���f�B�A�E�~�b�N�X�A����҃L�����y�[���E�C�x���g�A�����p�͕W�����A�܂���e�͓������H
���I�[�v���C�m�x�[�V�����ւ̐ϋɐ��������ق� WEB �R�~���j�e�B�̌`���́A�W�����X�������邩�H
6�D�]��O���R������Ђɂ�����Z�~�E�O���[�o���[�[�V�����̍l����
�`�C���^�r���[�ɂ��T�������ɂ��Ă̋c�_�`
�C���^�r���[���ʂ̑O�ɁA�H�i�̔��������Ƃ������o���_���烍�[�J�����̓������o�₷�����R���q�ׂĂ����B
����������������4�̗��R�́A���i2008�j�y�ђ��쑼�i2011�j�ɂ��Ɛ}6-1�̂悤�ɂȂ�12�j�B���̐}�̐H�����̊ϓ_����݂�ƁA���������̓��[�J���ȐH��������傫���e�����邱�Ƃ���A�H�i�̓��[�J���i���n�j�����₷���Ȃ�B
�C���^�r���[��̍]��O���R������Ђ̊C�O�W�J�T�v���A���Ђ̃z�[���y�[�W�Ɉˋ����Đ�������ƈȉ��̒ʂ�ł���B�]��O���R�̊C�O�W�J�̗��j�͐�O����ł���A���a�����ɂ͒��y143�Łz���嗤�Ⓦ��A�W�A�ւƓW�J���Ă����B�������A�푈�ɂ��U��o���ɖ߂�A���ĂъC�O�ւ̊������X�^�[�g�������B1970�N�Ƀ^�C�O���R��ݗ����A���̌�A�����J�A�J�i�_�A���[���b�p�A�������ւƊ������g�傳�����B���݂̎���͂�͂�A�W�A�ł���A���Ƀ^�C�𒆐S�ɑ����̃O���R�t�@�����l�����A�^�C�E���������ɁA�A�W�A�s��ŃO���R�̑��݊�������w���߂���B�����āA�A�W�A�̃O���R���m��������ɂ́A���E�̃O���R��ڎw������������ӌ��������Ă���B�A�����J�A�J�i�_�A���[���b�p�����łȂ��A���E���ɃO���R�̏��i��͂��Ă��������Ƃ����̂��ڕW�ł���B�ihttp://saiyou.glico.jp/company/global/���쐬�j

�܂��A�}6-2�ɂ̓O���R�̃Z�O�����g�ʔ��㍂���A�}6-3�ɂ̓O���[�v�T�v���A�}6-4�ɂ̓^�C�ł̃O���R�̌�����L�ڂ��Ă����B
�y144�Łz
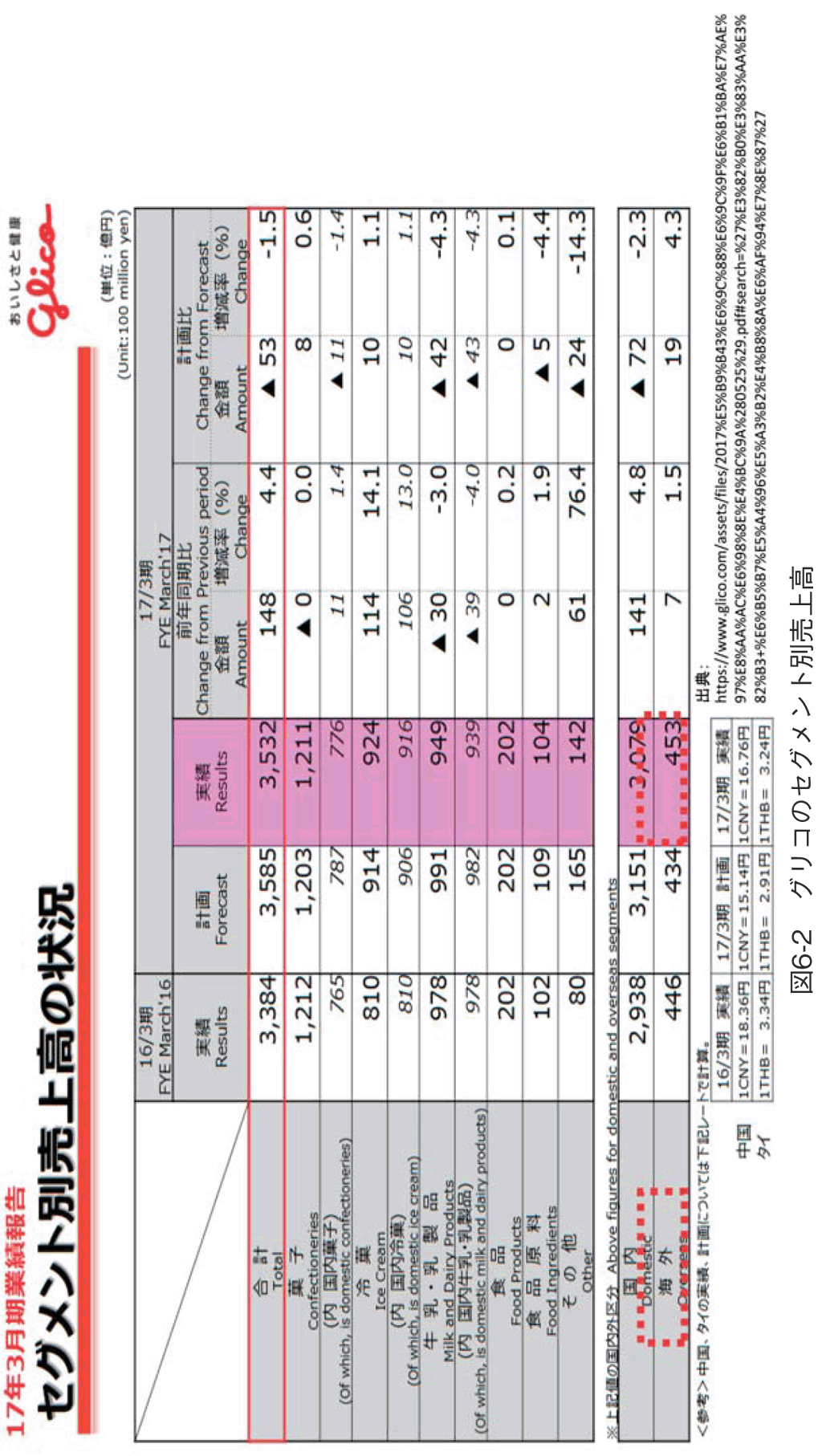
�y145�Łz
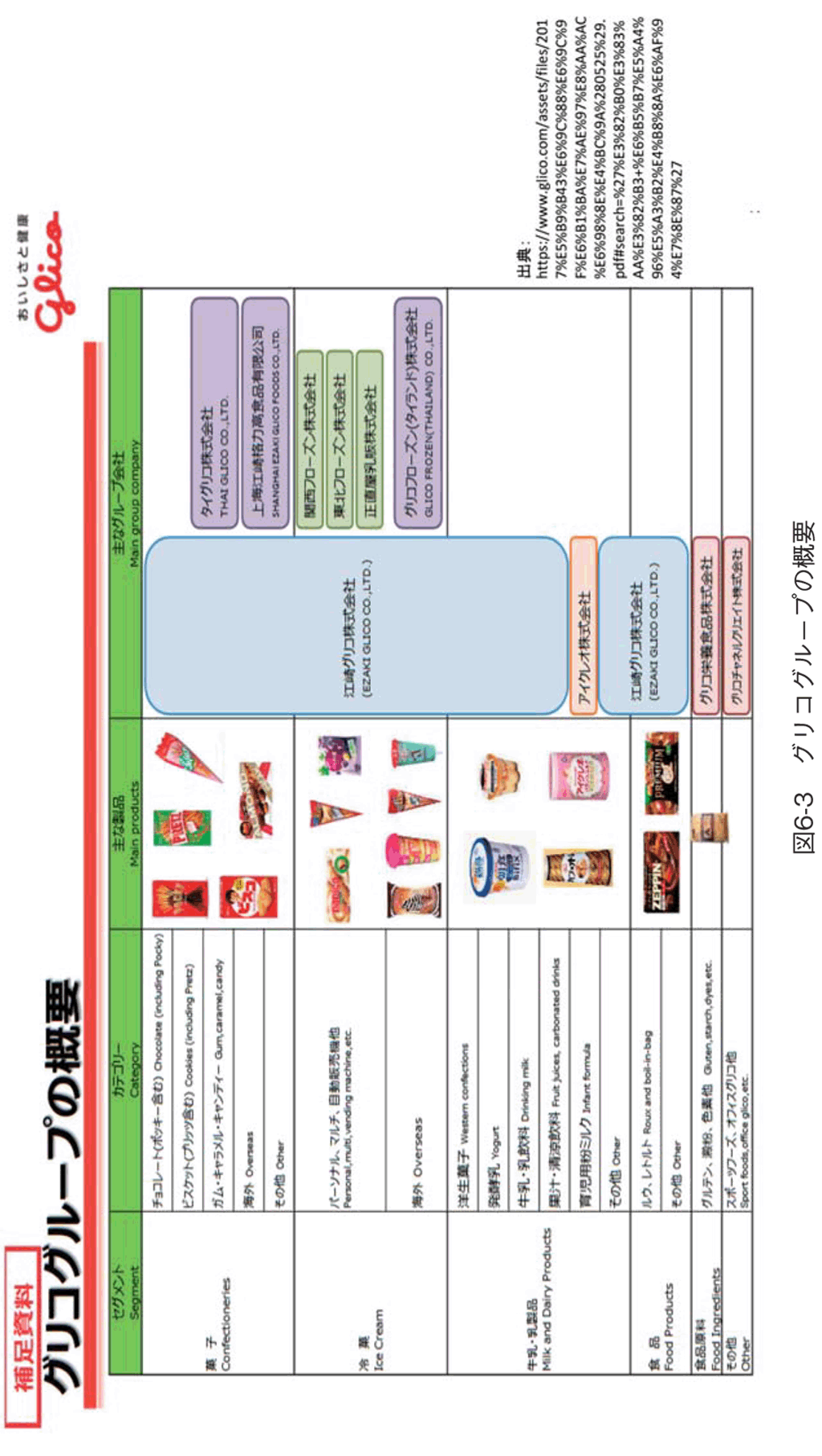
�y146�Łz

�y147�Łz
�@web �A���P�[�g�����̕��͌��ʂɊ�Â�����܂ʼn����i�^��j�Ɋւ��āA2018�N5��1���i���j �ɍ]��O���R������Ёi���x�������r��20F �~�c�I�t�B�X�j�ɂ����āA�o�c���{���o�c��敔�̕ēc��G�S�������ɃC���^�r���[�y�уf�B�X�J�b�V�������s�����B�ēc���́A1998�N���Ђ�20�N�قǍݐЂ���Ă���B�C�O�o����2003�N11���`2015�N12�����܂�12�N2�����A�����Ɗ؍��֕��C���Ă���ꂽ�B
�ēc���ɂ��Ƃ܂��A�]��O���R�̊C�O�W�J�́A�^�C�����ł������B��2�����E���O�ɂ͖��B�ɍH�ꂪ���������̂́A�I���^�C���ŏ��ƌ�����B�����āA�^�C���烈�[���b�p�A�����ւƓW�J�����B���[���b�p�ł́A�|�b�L�[��W�J�����B�u�����h���̓~�J�h�Ƃ����A�X�e�B�b�N��Q�[������R�������l�[�~���O�ł���B���݂́A�k�Ă��d���i�č��]��O���R�ݗ��j���Ă���B���̃~�J�h�͓��{���̃|�b�L�[�Ȃ̂����A���[���b�p�ł͍��فiMondelez International, Inc., NASDAQ: MDLZ�j�u�����h�̂��߂��̃u�����h���ƂȂ����B���[���b�p�ȊO�́A�|�b�L�[�œ��ꂵ�Ă���B
�C�O�ł́A�̔���Ђ��e�n�ɐݗ����A�|�b�L�[�A�v���b�c�𒆐S�ɓW�J���Ă���B���{�̂悤�ɑ��l�ȉَq���o���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�u�����h�͈�i��i��Ă�K�v������A��C�ɑ��l�ȃu�����h���C�O�ŏo���͓̂���B
ASEAN �ł̓^�C�ɉَq�H�ꂪ����B���[���b�p�͍��ى�Ђ̍H��Ő������Ă���B�k�Ă͍H�ꂪ�Ȃ��A�A�o�ł���B���̂��߉��i�͍����Ȃ邪�A�A�����J�̓X�������͈������Ȃ��Ă�����邽�߁A�A�o�ł����l�Ɍ����������i�ƂȂ�B���v���������G���A�Ƃ��Ă͗��j�I�ɒ����o�Ă���Ƃ���ł���A�^�C��������ɓ�����B�k�Ă�20�N���炢�ɂȂ�A�Z���Ȃ��B
�َq�̃o���G�[�V�����𑝂₷�^�C�~���O�Ƃ��Ă͑O�ɏo�������i���蒅�����瓙�A�n����ɓK���Ă���ꍇ�͑��₷���Ƃɂ��Ă���B���Ƀ|�b�L�[�̓O���[�o�����i�ł���B
�ȉ��Aweb �A���P�[�g�������ʂ̒T�������Ɋւ���c�_���ȉ��Ɏ����B�������A�����ł͋c�_�ɂȂ������̂��f�ڂ��A���܂�c�_�ɂȂ�Ȃ��������̂͏ȗ����邱�Ƃɂ���B
�������F���n�H�i���[�J�[���܂��܂����_�����Ȃ��A�O���[�o���u�������Ⴂ�H
�y�z ��r�������Ƃ͂Ȃ����A�����ԁE�d�C���[�J�[�ɔ�ׂ�ƈ��|�I�ɏ��Ȃ��Ǝv���B�H�i�ł��C�O�ɏo��X��������Ƃ������B�Ⴆ�Η��j�̒�����ƂƂ��Ė��̑f�A�L�b�R�[�}����������B�C�O�W�J�̓g�b�v�̈ӎv���肾�Ǝv���B���j���Â��Ă��O���R������قNJC�O�W�J�����Ă��Ȃ������̂́A�C�O�W�J����肫���l�ނ��s�����Ă���A�������ł܂��Ă��Ȃ����A�����ȗv�f�����肤��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�܂����ɍ��x�o�ϐ������Ɋ�Ƃ̌o�c��Ԃ̗ǂ��Ȃ��������������B���̂Ƃ��\�����v�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�������C�萬�ɊC�O�i�o�͂ł��Ȃ������̂ł͂Ȃ����낤���B�܂��I�[�i�[��ƂłȂ��Ƃ���̓g�b�v���Z���Ԃŕς��B����ɂ���Đi�o�|���V�[���ς��₷�����A�O���R�̓I�[�i�[�o�c�Ȃ̂Ői�o�|���V�[�͂Ԃ�Ȃ��B�O���[�o���i�o�͂��̈ӎv���肪������p����B
�������F���n���[�J�[�̃O���[�o���W�J�͌㔭�̂ɁA�x������߂����߂̔������H
�y�z �O���n�͉ߋ��ɑ�����������Ă��Ă���Ǝv���B���{�n�H�i���[�J�[�͂Ƃɂ����y148�Łz���Ԃ��Ƃ����C���[�W�ŊO���ɒx��Ď��{���Ă���Ǝv���B�O���R�� ASEAN �̔̔���Ђ��ߋ��ɔ������Ă���B�H�i��Ђ̏ꍇ�A�K�͂��o���o���ʼn����шӎ��͏��Ȃ����A�K�͂��傫�������Ă���r�[����Г��͂���̂ł͂Ȃ����B�i��c���F�K�͂��傫���A�����Ă�����{�r�[����Ƃ͉����шӎ�������A����̃V�F�A����������Ȃ����ߔ����������ьX���̉\��������B�j
�������F�H�i���[�J�[�̃O���[�o���W�J�X�s�[�h�͔�r�I�������H
�y�z ����܂Ŏ��Ԏ��͂��܂�ӎ����ĂȂ������B�H�i�̓��[�J���C�Y���Ȃ���Ȃ�Ȃ����߁A���Ȃ莞�Ԃ�v����B��H�i�̕��i�͕ς��Ȃ��ėǂ����A�H�i�͐H�����̑��l�����傫���B���̑Ή��Ɏ��Ԃ�������B���Ƃ��O���R�̃|�b�L�[�́A�ς��Ă͂����Ȃ��Ƃ���Ƃ����łȂ��Ƃ��낪����B����͌��߂Ă���B��{�A�Â݂͕ς��Ă��Ȃ��B�`���R�̌��n����Ȃǂ͈قȂ�A�H�����̑��l���ɂ͑Ή�����������Ȃ��B�����łȂ��Ɣ����Ă��炦�Ȃ��B���[�J�������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�`��ς��Ă͂����Ȃ��A���ׂ������̓u�����h�C���[�W�A���l���B�Z�[���X�E�v�����[�V�����ł��|�b�L�[�f�[�ł��̕����ɂ��Ă͋��ʉ����Ă���B �i��c���F���̃u�����h�̎��ׂ������ɂ��ẮA�G�i�[�W�[�����ŗL���ȃ��b�h�u���̓O���[�o���ŕW�����C���[�W��ۂ��Ă���13�j�B�j
�������F�c�Ɨ��v���I�ɂ�3�ҁi���n�H�i���[�J�[�A�O���n�H�i���[�J�[�A���n��H�i���[�J�[�j�Ƃ�����قǑ傫�ȍ��͂Ȃ��B�̂ɂ���قǃO���[�o���W�J�ŋK�͊g��̃C���Z���e�B�u�͓��n�H�i���[�J�[�ɂ͂���̂��H
�y�z ���v���ł͂Ȃ��A���v�z�͕ς��B������d�v�B���v�z�̒~�ς͎��̓����̌����ƂȂ�B�H�i�͈ݑ܂̐��𑝂₷���ƁB�O���[�o���W�J����C���Z���e�B�u�͑傢�ɂ���B
�������F�p�[�g�i�[��ƂƂ̘A�g�͓��n�̕����d���H���R�͒x����J�o�[���邽�߁H
�y�z ������o�c�̃|���V�[�̖��ł͂Ȃ����B�p�[�g�i�[�Ƒg�ވӖ������́A�Ȃ����Ђł��Ȃ��̂��Ƃ������ƂȂ̂ŁA���ۂ͂ł��Ȃ�����g�ނ��Ƃ������B����䂦�A���ʓI�ɂ����Ȃ����Ƃ������ƁB�O���R�̓��[���b�p�Ń����f���[�Y�Ёi�O���[�o���W�J���Ă����ЁA�I���I���L���j�Ƒg��ł���B���̌o�܂Ƃ��ẮA1980�N��̘b�����A�́A�����f���[�Y�Ђ��W�F�l�����E�r�X�P�b�g�ł���������ɘb���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�O���R�Ƃ��ẮA���̉�ЂƑg��Ń|�b�L�[�� MIKADO �݂̂���Ă���B���ꂾ���ł��O���R�͑�ςł���A���[�����Ŕނ�̘̔H���g���Ă���Ă���B
�܂��i�o��̍��̖@�̖�������A��g������Ȃ����Ƃ�����B�^�C�ł́A�Ǝ��ł͑ʖڂŖ@�I�ɍ�����ƂƑg�܂˂Ȃ�Ȃ������B�����ł��@�I�ɂ�͂荇�قł���A��g������Ȃ������B
�������F���n�H�i���[�J�[�́A���n��H�i���[�J�[�A�O���n�H�i���[�J�[�Ɣ�ׂāA�R�[�|���[�g�u�����h���S�ŁA�ʃu�����h�ł͊C�O�W�J���Ȃ��悤�ɁA�����̃u�����h�y149�Łz�헪�����̂܂ܓK�p���A�ς��Ȃ��X���ɂ���̂��H
�y�z ����Ɋւ��Ă͌o�c�g�b�v�̈ӎv�����������B�J���r�[�Ȃǂ̓A�����J�ł��������J�e�S���[�u�����h���Ŕ����Ă���B��T�Ɍ����Ȃ����낤�Ǝv���BMIKADO �̓��[���b�p�����B���̓|�b�L�[�Ƃ����u�����h�����S�ł���B�����ł͓����̃u�����h�Ńc�@�C�G���V���I�s���Ƃ����̂��o���Ă���A���{�ɂ��ꎞ�A���������Ƃ��������B���ʓI�ɔ���Ȃ������̂����B�܂��t���[�o�[�ł̌��n�Ή��͂���B���{�ɂ͂Ȃ������̏��i�����ɂ���A���Ђ̃g�b�|�Ɏ��Ă�����̂Ȃǂł���B
�������F���n�H�i���[�J�[�̊C�O�i�o��i��i���E�V�����j�̓A���o�����X�������H�L���Ȓn��ɕ��Đi�o�H���邢�͌㔭�Ƃ������R�̂��߂��H
�y�z �o�����X���l���ďo�Ă����Ђ͂Ȃ����낤�B�L�]���Ō��߂ďo�čs���B
�y��z �O���R�����ɊC�O�W�J���l���Ă��鍑�͂��邩�H
�y�z ���o�Ă���Ƃ���ł���肫��Ă��Ȃ��B�܂�����������������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�C���h�l�V�A�͂���Ă��āA����������Ȃ��Ƃ����Ȃ����B�x�g�i���Ȃǂ��L�]�͗L�]�B
�������F���n�H�i���[�J�[�͓��n��H�i���[�J�[�ɔ�ׂ�ƈ��|�I�Ƀ��[�J�����������B�Ȃ����H
�y�z �H�i�Ǝ��̚n�D���ɂ����鑽�l���i�����̉e����j�B�K�v�Țn�D�������͎��{���Ă���B
�������F�l�����̒��x�͕W�����i�W�����j�̕������v���͍����̂��H
�y�z ���Ƃ��Ε����ł̓��[�J���̃��m�𗘗p������Ȃ��B���n�̏����K�ɍ��킳�Ȃ��Ƃ����Ȃ����߁A���[�J�����ɂȂ�B�����悤�ȓ���I�ȃZ�[���X�E�v�����[�V�����ł��ׂĂ̐i�o���ň�Ăɂ�邱�Ƃ͂��邪�A�l�����͌��n�̏����K�Ɋ�Â��K�v������B���������ă��[�J�����ƂȂ�B�u�����h���l��ʑ�����悤�Ȃ��Ƃ͂������Ȃ��̂ŁA���鍑�̃V�F�A�����������邽�߂̑啝�l����������悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��B
�������FB2C ��Ƃ̕������v���͍����̂��H�����ł� B2C ��I���AB2B �����˂Ă����Ƃ�������x�܂܂ꂽ�B
�y�z B2C �̕������i�ŕ��i�����Ȃǂ����t�����l�������A���₷���̂ł͂Ȃ����H�ŏI���i�̕����t�����l���グ�₷���A���v�����グ�₷���Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�H�i�ł� B2B �Ƃ��Ă͖��̑f�Ȃǂ��o���N�ŃO���^�~���_�\�[�_���Ă���Ⴊ����B�ݖ����������B����� B2B �ŗ��v���͍����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�������F���㍂���傫���قǗ��v�����傫���B5000���~�ȏ� / �N�̔��㍂���L���ł͂Ȃ����H
�y�z �K�͂̌o�ϐ��A�͈͂̌o�ϐ��������Ă���B�Ƃ���ƃu�����h���W����������������B
�y150�Łz
�������F�C�O�̔��㍂�䗦�������قǗ��v�����傫���̂��H
�y�z �C�O�̐H�i��Ƃ̕������v���͍����B���{�����̃r�W�l�X�̏ꍇ�A�����K�̂��߂ɍ\����̖��ŗ��v���͒Ⴍ�Ȃ肪���ł���B�ŏI���i�������ł���A�����������Ȃ痘�v���͍����Ȃ�B�C�O�ł̃X�L���E�v���C�V���O�i�M�Ғ��F���������Ă����ڋq�w�������^�[�Q�b�g�Ƃ��č����i�����鉿�i�헪�j���\�Ȃ�܂����v���͍����Ȃ邾�낤�B
�i�M�Ғ��F�����ł̎������ATOTO �������ł���A�X�L���E�v���C�V���O�ō����v���̉\���͂���B�j
�����ŏ������{�H�i��Ƃ̒���v���ɂ��ĎQ�l�ɐG��Ă����B���̌����͓��{�H�i�s��� ���ꐫ�ɂ����̂ł���Ƃ����c���i2012�j�̐�������B�܂藬�ʂ̒��ԂɈʒu���鉵���`���l���L���v�e���ł������Ƃ������{�̓`���I�ȐH�i���ʊ�Ղɂ���Ƃ�����̂ł���B���̕��������p����Ǝ��̂Ƃ���ł���14�j�B
�w�c��Ȑ��̏����Ǝ҂�[�J�[�Ƀr�W�l�X�`�����X����A���ʂƂ��ď����ƃ��[�J�[�Ƃ̌��������������������ŗǎ��ő��l�ȐH�i�ނ��ƂƂȂ�A����҂͂�����g���ł��A�ǂ��ł��h�w���ł���悤�ɂȂ����B�x
�������F�C�O���_���������قǃR�~���j�P�[�V�����E���f�B�A�E�~�b�N�X�AWEB �R�~���j�e�B�̌`���̓��[�J�����A�܂���e��ς��邩�H
�y�z ���������l�����Ă��邩�烍�[�J��������̂��낤�B���Ɍ��ꂪ�ς������Ȃ�₷���B�������`������l�͂��Ȃ����낤�B�܂��b�l�͌��n�ł��邱�Ƃ������B�O���ւb�l�������o���Ɣo�D�̏ё����̌�������̂ŁA���n�ł���ق����y�ł���BWEB �R�~���j�e�B�͊e���ɂ���B���Ƃ���͎��A�ς���Ƃ���͌��n�Ŏ��R�ɕς��Ă��邱�ƂɂȂ�B
�������F��i���E�V�����փo�����X�悭�i�o����ق� CM ���e�A�R�~���j�P�[�V�����E���f�B�A�E�~�b�N�X�A����҃L�����y�[���E�C�x���g�A�����p�͕W�����A�܂���e�͓������H
�y�z �u�o�����X�悭�v�͂҂�Ƃ��Ȃ��B�����������Ƃ͂Ȃ��B���ʓI�ɋ��_�������Ȃ�Ƃ������Ƃ��B�ł��҂�Ƃ��Ȃ��B
�y��z �O���R�̕������Ƃ��Ă͈ꍑ�ꍑ���ł߂Ă����̂��H
�y�z �����ɑ����̍��ɑΉ����郊�\�[�X���Ȃ��B
�y��z �W���������ɂ���ɐ��i�𑝂₵�Ă����̂��A�ׂ̍��֍s���̂��H
�y�z �������B�����ɏ��Ă邱�Ƃ��܂߂ėL�]�ł���A�s���\���������B�m��Ȃ����֍s���̂̓[������X�^�[�g�B����͑�ς��B�܂��A�o�������B
�y��z �x�g�i���͂ǂ����H
�y�z �傫�ȏ����ł���n�C�p�[�}�[�P�b�g�����Ȃ��A�p�p�}�}�X�g�A�������̂œ���B�ǂ�ǂ�n�C�p�[�}�[�P�b�g�������Ă���ƎQ�����₷���Ȃ�̂����B����͔z���R�X�g�������邩�炾�B�^�C�Ńg���C�A�����Ă���Ƃ��낾�B�|�b�L�[�������� 6�{15�~���炢�ŁA������ŃN�[���[�̓����Ă���Ƃ���ɂ͒u�����Ƃ��Ă���B
�y151�Łz
�y��z �C���h�͂ǂ����H
�y�z ���ꂪ��������B26���炢�̌��ꂪ1���̂��D�ɂ�������Ă���B�Ή�������B�����l�̃r�W�l�X�}�������������Ă���B
�y��z �Q�����₷���Ȃ�����ǂ����H
�y�z �Q�����₷���Ȃ��Ă��������������Ȃ邱�ƂɂȂ�B�攭�̗D�ʂ͂�͂�傫���B
�y��z �攭�̗D�ʂɊւ��ẮA���O��`�̃��N���g�̐i�o�̒x�ꂽ���X���O���n�H�i���̃_�m�����͕�Ő�Ɏs����������Ă������Ƃ����悤�Ȋ댯���͂��邩�H
�y�z �������B
�A���P�[�g�f�[�^�ɂ�镪�͂ƃC���^�r���[�ɂ�錟������܂ōs���Ă������A�Ō�ɂ���������N�����Ă��������B
�܂��A���Ɋ�Ƃ́A�O���[�o���W�J�Łu�L���E�v�Ɓu�����E�[���v�̃o�����X�̈ӎv����͓���Ǝv����B���ɐH�i��Ƃɂ����ẮA���[�J���Ή����傫�����A������x�u�����E�[���v���d�v�ł���B�������A�ݑ܂̐��𑝂₷���Ƃ��d�v�ł���H�i��Ƃł́A���v�z�𑝂₷�ϓ_����W�J���L�������A�����������ɁA���X�N��������������Ȃ��B���̃o�����X���ǂ����߂邩�B
���ɊC�O�W�J�͎s��̗L�]�����|�C���g�����A�l�ގ蓖��������ߑ��W�J���ł̐i�W�x�A���̌�̓W�J�ɐ[���֘A���Ă���B���̌��ˍ������ǂ��݂�̂��B
��O�Ƀ}�l�W�����g�v�f�̂��ꂼ��̃Z�~�E�O���[�o���[�[�V�����x�́A���n����ňقȂ邪�A�@�����͂��肻���ŁA�����𖾂炩�ɂ���K�v������B
��l�ɐH�i�̓��[�J�����̗v�f�������A�C�O�W�J���������Ǝ�����������ƂȂ�B�ǂ̒��x�̓W�J�X�s�[�h�̈Ⴂ���K�Ȃ̂��������B
�i�ӎ��j�{�_����2018�N5��26���̓��{���Ɗw��S�����Ҋ�u���ł̕���ɂ��Ă���B�f���炵���@���^���Ē������w��ɑ���Ȋ��ӂ�\���グ��B�܂����{��w���w�����^���y�����ɂ͊w��ɂ����đ�ς����b�ɂȂ�A���Ӑ\���グ�鎟��ł���B�����ăC���^�r���[�ɍۂ��ẮA�]��O���R������Ђ̌o�c���{���o�c��敔�̕ēc��G�S�������ɑ�ς����b�ɂȂ����B�����ĕēc�������Љ�������Б�\�����ꖱ���s�����E�o�c���{�����ł���]��x�N���ɂ����Ӑ\���グ�����B
�y152�Łz
�EBritt, S. H.�i1974�j, �gStandardizing Marketing for the International Market,�h Columbia Journal of World Business, Winter, pp.39-45.
�EBuzzell, R. D.�i1968�j, �gCan You Standardize Multinational Marketing?,�h Harvard Business Review,
November-December, pp.102-113.
�EDichter, E.�i1962�j, �gThe World Customer,�h Harvard Business Review, 40�i4�j, pp.113-122.
�EDolan, R. J. & H. Simon�i1996�j, Power Pricing , Simon & Schuster.
�EDouglas, S. P. and Y. Wind�i1987�j, �gThe Myth of Globalization,�h Columbia Journal of World Business, 22�i4�j, pp.19-29.
�EElinder, E.�i1961�j, �gHow international can advertising be ?,�h The International Advertiser, December, pp.12-16.
�EFisher, A. B�i1984�j, �gThe Ad Biz Gloms onto Global,�h Fortune, November 12, pp.77-80.
�EGhemawat, P.�i2007�j, Redefining Global Strategy: Crossing Borders in a World where Differences
Still Matter, Harvard Business Press.
�EHisatomi, T.�i1991�j, �gGlobal Marketing by the Nissan Motor Company Limited -- A Simultaneous
Market Study of User�fs Opinions and Attitudes in Europe, USA, and Japan,�h Marketing and Research Today, February, pp.56-61.
�EKeegan, W. J.�i1969�j, �gMultinational Product Planning: Strategic Alternatives,�h Journal of Marketing, 33�i1�j, pp.58-62.
�EKotler, P.�i1986�j, �gGlobal Standardization �\Courting Danger,�h The Journal of Consumer Marketing, Vol.3, No.2, pp.13-15.
�EKustin, R. A.�i1994�j, �gMarketing Globalization: A Didactic Examination for Corporate Strategy,�h
The International Executive, Vol.36, No.1.�iJanuary-February�j, pp.79-93.
�ELevitt, T.�i1983�j, �gThe Globalization of Markets,�h Harvard Business Review, 61�i3�j, pp.92-102.
Qadri M. M., U. Ayub, U. Riaz�i2016�j�C�gGLOBALIZATION AND REGIONALIZATION: AT A
GLANCE ON DEBATE IN PURSUIT OF GUIDING PRINCIPLES LEADING POLICY
IMPLICATIONS �h�CJournal of Management and Research �CVolume 3 Number 2.
�y153�ŁzRugman, A.�i2001�j, The End of Globalization: Why Global Strategy is a Myth and How to Profit from the Realities of Regional Markets, Amacom.
�ESandler, D. M. and D. Shani�i1992�j, �gBrand Globally but Advertise Locally?: An Empirical Investigation,�h International Marketing Review, Vol.9, No.4, pp.18-31.
�EThorelll, H. and H. Becker�i1980�j, �g Pricing: An International Marketing Challenge,�h International
Marketing Strategy, Revised Edition, Pergamon Press Inc.
�EWind, Y. and S. P. Douglas�i1971�j, �gOn the Meaning of Comparison: A Methodology for Cross- Cultural Studies,�h Quarterly Journal of Management Development, July, pp.106-121.
�E��ΖF�T�E�R���[�q�Ғ��i2013�j�w�O���[�o���E�}�[�P�e�B���O�̐V�W�J�x�A�������[�A pp.9-10.
�E��[��v�i2013�j�u���n���[�����`�F�[���ɂ��C�O�ł̐H�ޒ��B�V�X�e���̍\�z�v���Z�X�|�������z�������̕W�����ɑ���j�Q�v���|�v�A���w�����A60�i4�j
�E���c���E�w���Z���i2010�j�w���ۃ}�[�P�e�B���O�x�i�I�،_ ����j�w��
�E�c���^��i2012�j�C�w�O���[�o���s��ɂ�����킪���H�i�����Ƃ̉ۑ�Ɛ헪�i�O�ҁj�x�C�H�i�ƊJ���CVOL.48, NO.1
�E�� ���S Barbara, �y��ꐶ�i2013�j�w��B�H�i�Y�Ƃɂ����钆����Ƃ̊C�O�W�J�x�Y�ƌo�c�������� ��45���C��B�Y�Ƒ�w�o�c�������Cpp.47-62.
�E����v���q�A���؋��i2011�j, �g����������]��������@�̒T���h, NewFoodIndustry Vol.53 No.9, pp.49-56.
�E���o MJ�A2018�N1��19����
�E���o MJ�A2018�N1��24����
�E���o MJ�A2018�N2��26����
�E�ђ�j�A����a�h�i�A�� ���ۓI���ق܂����V���ȃO���[�o���헪�_�uAAA �헪�v�i�Q�}���b�g�jhttp://www.sbbit.jp/article/cont1//22166
�E�p���J�W���E�Q�}���b�g�i2009�j�w�R�[�N�̖��͍����ƂɈႤ�ׂ����x�i�]���q��j���Y�t�H��
�E���؋��i2008�j�w���o�ƚn�D�̃T�C�G���X�x�A�ۑP�o��
�E�݂��َY�ƒ����w���B�̋����͂̌����T��|���A�ۑ�ƌ����������B����w�Ԃׂ����Ƃ͉����|�x�^50 2015 No.2 pp.1-378.
�Ehttps://www.mizuhobank.co.jp/corporate/bizinfo/industry/sangyou/pdf/1050_all.pdf
�Ehttp://saiyou.glico.jp/company/global/
�Ehttp://www.wikiwand.com/ja/%E3%83%9F%E3%82%AB%E3%83%89_�i%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0�j