����́u���{�I�o�c�v�_�i�P�j
��ˁ@���o1�j�@�@�@�@�@���R�@���G2�j
�u���{�I�o�c�v�Ƃ����R�g�o�����߂Ďg��ꂽ�̂����ł��������C�M�҂�ɂ͒肩�łȂ��BJapanese�istyle�jmanagement ���邢��japanisches Management �Ƃ����p��͂��łɂ��Ȃ�O����ڂɂ��Ă���C�M�҂̈�l��30�N�O�Ƀh�C�c�Ō��������_��3�j�ł����łɂ����p���Ă����B�����̃��t�F���[�����̗p������m���Ă����C�Ƃ������Ƃł���B
�������C1980�N��C������o�u���o�ς̐i�W�ɂ�����C���{��Ƃ̋}������ڂ̓�����ɂ��Ă������Ă̌o�c�w�����҂��C���̂悤�ȋ}�����̌����͂ƂȂ��Ă�����́C���Ȃ��Ƃ����̈�������{��Ƃ̌o�c���@�C�܂��Ɂu���{�I�o�c�v�Ȃ̂��낤�Ǝv���Ă������Ƃ́C�܂��͍m�肳���ł��낤�Ǝv����B
�����́w�l�{��`�x���͂��߂Ƃ��ē��{�̌����҂������琢�E�Ɍ����ē��{�I�o�c�̗D�ꂽ�_�C�����b�g�Ƃ������̂����������M����C����ɂ���đ����̓��{�l�����҂��������ڂ�ꂽ���Ƃ͋L���ɐV�����Ƃ���ł���B�O�q�̐l�{��`���Cpeoplism �ȂǂƖ�C�h�C�c�ł͑�Ƃ̃A���o�b�n�����������kaltes Trauen�i��ÂȐM���j�ȂǂƖāC�M�҂̈�l�͎��U�����L��������i���������Ӗ��ł͂Ȃ��Ǝv���j�B
���̂悤�ȃo�u���o�ς��������j����C���Ăł͓��{�I�o�c�ɑ���]���͑傫���C�����Č�����180�x�ς���Ă��܂��C���݂Ɏ����Ă���C�Ƃ������G��M�҂�͎����Ă���B���{��Ƃ̒�،�͑O�q�̓��{�l�����҂����ɂ��C����ɑ��錾�����炭�������Ǝv���邪�C������̏ꂵ�̂��̌����ɏI�n���Ă��āC���̊Ԃɂ��ڂɂ��Ȃ��Ȃ��Ă����C�Ƃ������Ƃł��낤�B
����ɂ����ẮC�o�u�����̓��{��Ƃ̑傫�Ȑ����́C���E�o�ϑS�̂̃p�C������傫���Ȃ��Ă��āC����Ɏ���悭����Ă������Ƃɂ����̂ŁC���{��Ƃ̌o�c���@���D��Ă����C�Ƃ����v�������̌����͂������킯�ł͂Ȃ����낤�C�Ƃ����l�����ɗ��������Ă���C�Ƃ����C�����Ă���B
�Ƃ͌����Ă��C�ł͂��̂悤�ȓ��{�I�o�c�Ƃ������̂ɂ͂��͂〈��ׂ����̂��Ȃ��̂��C�Ƃ����ƁC�����͎v���Ȃ��B�M�҂�͂����������{�I�o�c�ɂ��āC�ł��邾���ߋ��̋c�_��m��C�����Č���ɂ����邻�̈Ӌ`�i���邢�͗L�p���j�Ƃ������̂����o���āC���ꂩ��̓� �y176�Łz �{��Ƃ̐����ɂȂ�����̂����o�����Ƃ��ł���C�Ɗ�]���Ă���B
��ՓI�Ƃ�����ꂽ���̓��{�o�ς̔��W�́C���E������ق̊�Ō���ꂽ�B�I�풼��̍r�p������������̎����Ɍ������Ȃ�����C�Y�ƍ\���̓]����}��C�}���ȕ����𐋂��Ă����B1956�N�x�́w�o�ϔ����x�ł́C�u���͂���ł͂Ȃ��v�ƍ��炩�ɐ錾�����1960�N�ォ��70�N��ɂ����Ă̍��x�o�ϐ����C������80�N��̈��萬�������o�āC���{�͂��͂≢�Ă���w�Ԃ��̂͂Ȃ��Ƃ������C�̌��t�������ꂽ�B
�Ȃ��C���������������\�ɂȂ����̂��B����͐��{�Ɩ��Ԃ���̂ƂȂ��āC���Đ�i���ɒǂ����C�L���b�`�A�b�v���悤�Ƃ������͋C��ӎu�������S�̂ɋ��L����Ă������Ƃ��傫�������Ǝv����B�o�ϐ�����ʂ��ĖL���Ȑ������������邱�Ƃ����̏Ă��쌴��̌����������̐؎��Ȋ�]�ł������B
���̂��߂ɁC���{�͕K�v�Ǝv����o�ϐ����Y�Ɛ�������肵�C���̌������ׂ������������C�d�_�I�Ɉ琬����Y�Ƃ����߁C�X�ΓI�Ȏ����z�����s�����B�����Ė��Ԃ̑��ł͂��̕��j�ɊT�ˏ]���C���ꂼ��̎Y�Ƃɂ����ČX�̊�Ƃ��헪�����C���Đ�i������w�ߑ�I�ȃ}�l�W�����g���@�̓����E�m���ɒ��͂����B
���̓��{�̐����ɑ傫���v�������̂́C���{�Ȃ̂��C���Ԋ�ƂȂ̂��Ɋւ��Ă͐F�X�ȋc�_�����邪�i�O�ցE�����U�C���[�i2001�j�j4�j�C���炭�o���̖����͖����ł����C���ʓI�ɑ�����ʂ��������̂ł͂Ȃ����ƍl������B���Ԋ�Ƃ���ƌo�c�������I�ɍs�������ŁC���{�s��̖����͏d�v�ł��邵�C�l�ނ��m�ۂ��邽�߂̘J���s����K�v�ł���C�܂����i�s�����Ɗԋ����������ɍs����悤�ɐ�������Ă��邱�Ƃ��厖�ł���B�����I�Ȏ����z�����������邽�߂̎s��@�\�͐�i���{��`���ɂ����Ă͌������Ȃ������ł���B�������Ȃ���C�㔭�����ꑫ��тɂ��̏�ԂɒB���邱�Ƃ��ł���C���邢�͓��B���ׂ��ł���Ƃ͌����Ȃ��Ǝv����B
���������̎s��o�ς��@�\�����邽�߂̊�Ր����͐��{�̖����ł���C�䂪���ɂ����Ă����Ă̑呠�Ȃ�ʎY�Ȃ𒆐S�ɐ����W�J���Ȃ���Ă����B���̍ہC�㔭���Ƃ��ďo�������킪���̓����Ƃ��āC�ŏ����琭�{�̉���̂Ȃ��S���̎��R�ȋ�����F�߂�����ł͂Ȃ��C������x�̏ォ��̉���Ȃ����͊���r�����Ȃ������B���̈Ӗ��ōŏ�����C���z�I�Ȃ��邢�͋��ȏ��I�Ȋ��S�Ɏ��R�Ȏs�ꋣ����ڎw�����̂łȂ������B�T�^�I�ɂ́u�쑗�D�c�����v�Ƃ������t�ŕ\������Ă���̐����Ƃ��Ă����B
��ƌo�c�ɂ����Ă����ė��̌o�c�X�^�C����S�ʓI�ɍ̗p����Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ������B���R�ȘJ���s��Ől�ނ��m�ۂ��C���R�ȏ،��s��Ŏ������B������Ƃ����`�Ŋ�ƌo�c���Ȃ��ꂽ�킯�ł͂Ȃ������B��i���̍����I�E�ߑ�I�Ȍo�c��@���w�т��C�킪���Ǝ��̃}�l�W�����g�E�X�^�C�����W�J����Ă����B�ǂ��ɋN�������߂邩�͂��܂��܂Ȍ��������邪�C��ƂƂ����g�D�̐��x�̑����������ď����Ƃ͈قȂ�C���{�ł͊�ƂƂ����g�D���C�P�Ȃ�_ �y177�Łz ��W�Ō��ꂽ�����I�Ȍo�ϐl�̏W�܂�Ƃ͑����Ă͂��Ȃ������Ƃ����邱�Ƃ������B�ނ��됶���̏�C�����̂Ƃ��Ċ�Ƃ𑨂��C����������{��Ƃ̓Ɠ��̌o�c�݂̍���C�o�c�҂�]�ƈ��̓Ɠ��̈ӎ���l������������C�{�e�ōl�@�ΏۂƂ���u���{�I�o�c�v���o�ꂷ�邱�ƂɂȂ�B�����Ă��̓��{�I�o�c���킪���̊�Ƃ̐������W�C�Ђ��Ă͐��̌o�ϐ������x�����L�[���[�h�Ƃ��ď̎^���ꂽ���Ƃ����������C���̑O�ߑ㐫����������邱�Ƃ��������B�ߔN�́C���{�̑��Ƃ̋Ɛѕs�U��C�m�x�[�V�����̒�ɂ���āC�����̑j�Q�v���Ƃ��Ĕᔻ�̑ΏۂƂȂ邱�Ƃ������Ă���C���{�I�o�c�̏I�������C���v�̕K�v�����o�ώG���⏑���ł����Ζڂɂ���B���������w�E�́C20�N�قǑO�̔ѓc�i1998�j5�j�ŏڂ����Љ��Ă���悤�ɁC���{�I�o�c���o�c�w�̐��E�Ř_������悤�ɂȂ�����������J��Ԃ��Ȃ���Ă����B
�����ŁC���������ʗ_�J�Ȃ̌��������{�I�o�c�ɂ��āC�܂��͂킪���̌o�c�w�֘A�̊w��łǂ̂悤�ɘ_�����Ă����̂��C�߂����߂ĐU��Ԃ��Ă݂悤�B
�Q�D���{�o�c�w��ł̓��{�I�o�c�Ɋւ���c�_�Ɩ{�e�̖��ӎ�
���{�o�c�w��͐ݗ�����Ă���95�N�ɂȂ�C�킪���̑����̌o�c�w�҂��W���o�c�w�֘A�̒��j�I�c�̂ł���B���N��x�J�Â���Ă����S�����ł̓���_��߂�ƁC����ɂ���āC�ǂ̂悤�ȃe�[�}���d�v�ł���ƔF������Ă����̂��͂ނ��Ƃ��ł���B��O�Ɛ��ł͂��Ȃ�l�����قȂ邵�C�܂����ɂ����Ă��Z�p�̔��W��o�ώЉ�̓����C��ƋK�͂̊g��C�Y�Ƃ̐����C��Ƃ̍��ۉ��̐i�W�C�����̐[�������X�f���āC�킪���̊�Ƃ̒��ʂ��錻���̖��ɁC�@���Ɋw����邢�͌o�c�w�҂��ǂ����������ׂ����^���ɓ��c����Ă����`�Ղ����邱�Ƃ��ł���6�j�B
���̗��j�̒��ŁC�{�e�̊S�ł�����{�I�o�c���邢�͓��{�^�o�c�ɂ��Ă��C����_��Ŋ��x����肠�����Ă���B
1977�N�@��51����@�w���{�I�o�c�̏����x�i�o�c�w�_�W��48�W�����j
1978�N�@��52����@�w���{�o�c�w�Ɠ��{�I�o�c�x�i�o�c�w�_�W��49�W�����j
1989�N�@��63����@�w���{�I�o�c�̍Č����x�i�o�c�w�_�W��60�W�����j
2005�N�@��79����@�w���{�^�o�c�̓����Ɖۑ�x�i�o�c�w�_�W��76�W�����j
2018�N�@��92����@�w ���{�I�o�c�̌��݁|���{�I�o�c�̉����c���C����ς��邩�|�x�i�o�c�w�_�W��89�W�����j
�ŏ��ɓ���_��œ��{�I�o�c�����グ��ꂽ�̂́C1977�N�ł������B���x�������߂�����C�Ζ��V���b�N�����z���āC���{��Ƃ̋������Ċm�F��������������ł���B50�N��C60�N��͂ǂ��炩�Ƃ����ƁC���{�̌o�c�w�҂̒��ł́C���{��Ƃ̌o�c��ٗp�݂̍���̌�i�� �y178�Łz ���w�E����Ă������C����ɂ����ăA�����J�̌o�c�w�҃A�x�O�����́C���̒��w���{�̌o�c�x�i1958�N�j�ŏI�g�ٗp�C�N������ȂǓ��{��Ƃ̓Ɠ��̌ٗp���s�C�l�����x�̋��݂�]�������B���̈Ӗ��ŁC�A�x�O�����̎w�E�͓��{�̌o�c�w�҂ɂƂ��Ă͋ɂ߂ĐV�N�ł������B���������o�܂����܂��ē��{��Ƃ̌o�c�̓�����{�i�I�Ɍ����ΏۂƂ����̂�1977�N�ŁC����78�N�̑��ł����グ��ꂽ�̂ł���B
���̌�C80�N��̓��{�̉���������o�āC���߂ē��{�I�o�c�̒����C�Z���̍l�@�����݂��̂�1989�N�̑�63��ł������B90�N��ɂ͂���Ɓu����ꂽ10�N�v�Ƃ������t�ɒ[�I�Ɏ�����Ă���悤�ɓ��{�o�ς͈�C�ɕ���̓���H��C���{�I�o�c�ւ̕]�����l�ς�肵�C�A�����J�^�o�c�̎d�g�݂̓��������������悤�ɂȂ����B��������C��Ƃ̌o�c�ڕW�C�X�e�[�N�z���_�[�Ƃ̊W�C�o�c�g�b�v�̃K�o�i���X�̎d�g�݂���C�ٗp�C�̗p�C���i�Ȃǂ݂̍���C�،��s��̊������C�n�̊�ƊԊW�̕ϊv�ȂǁC���{��Ƃ̌o�c�S�ʂɓn�茩�����𔗂��邱�ƂɂȂ����B2005�N�̑��ł́C����_��́w���{�^�o�c�̓����Ɖۑ�x�Ƃ���C���{�I�o�c�Ƃ����\�����O����Ă���Ƃ���ɔ����ȕ��͋C�̕ω���������邱�Ƃ��ł���B���ꂩ��b���́C���{�I�o�c�ւ̊S�͑傫���������邪�C�i���g��̌����Ƃ�������A���O���T�N�\�����̌o�c�ւ̔ᔻ��2008�N�̃��[�}���V���b�N�ȍ~�C�ŋ߂Ɏ���܂ŋ��܂������Ƃ�����C2018�N���ł͂��������_���ӎ����āC���{�o�ρE��Ƃ̏������������āC���߂ē��{�I�o�c�̌���Ɩ{���C�ۑ��T���Ă���B2018�N�̑��̓��e�ɂ��ẮC���߂ŏڏq���邱�Ƃɂ������B
���{�o�c�w��ȊO�ł��C1982�N�Ɍo�c�j�w��ɂ����ē���_��w���{�I�o�c�̌n���x�̉��ŁC���{��Ƃ̌o�c�X�^�C���̓��F��C��O�Ɛ��̒f��ƘA�����������ċc�_���W�J���ꂽ�B������1997�N�ɂ́w�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�̗��j�ƓW�]�x�Ƃ����^�C�g���ŁC���j�w�I�A�v���[�`�̊ϓ_������{��Ƃ̌o�c�̉ߋ��Ə�����₤�Ă���B
����ȊO�ɂ��J���C�����C���Y�C���ƁC�}�[�P�e�B���O�C���X�̗l�X�Ȋw��œ��{�I�o�c�ɂ��Ę_�����Ă���B���̂��ׂĂ������Ō������邱�Ƃ͂������ł��Ȃ����C���ꂼ��̕���ɂ����āu���{�I�v�Ƃ͉��Ȃ̂��C���̖{���C��̓I�`�ԁC���݁C��݁C�C�O�ւ̈ڐA�\���ȂǂɊS���������Ă����̂ł���B
���݁C���{��Ƃ́C�O���[�o���[�[�V�����̐i�W�CIT �v���C���q����̐i�s�Ƃ������O�����֔@���ɑΉ����Ă����ׂ�������������Ă���B���{�I�o�c�Ȃ���̂�����Ƃ���C���邢�̓A���O���T�N�\�����̌o�c�ɑ��Ă����D�ʐ��������I�ɂ�����������Ƃ�����̖{���͂ǂ��ɂ���̂��C�{�e�ł͂������������ߋ������Č��݂ɂ����ēW�J���ꂽ�c�_�����Ȃ���C�l�X�Ȋp�x����l�@���Ă��������B���̍ہC�厖�Ȃ��Ƃ́C���j�╶���C�Љ��藣���Čo�c���C���ɐl�ԂɊւ��d�g�݂�x��_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B
���{�I�o�c�Ƃ����\���́C���{��Ƃ̌o�c�݂̍�������Đ�i���̊�Ƃ̌o�c�ƈႤ���ƁC���邢�َ͈��ł��邱�Ƃ�\���Ă���B�Љ�Ȋw�ł���o�ϊw��o�c�w�̊ϓ_���炷��C�o�ςȂ����o�c�̉c�݂ɋ��ʂ��镁�ՓI�ȉ�����T�蓖�Ă����C�ƍl����̂����ʂł��낤�B�Ȋw�Ȃ���̂́C���Ɏ��R�Ȋw�ł���C���C�ǂ��ł����藧�@�����݂��邱�Ƃɂ��̖{��������Ƃ������̂ł���B�Љ�C�o�ρC�o�c���ۂ��������Љ�Ȋw�������炭�����悤�ɍl����Ƃ���Όo�c�̈�ʗ��_���m�����邱�Ƃ����`�ƂȂ�B
�������Ȃ���C���R�Ȋw�ƈقȂ��āC�ώ@����錻�ۂ��ꏊ�C����ɂ���ĈقȂ邱�Ƃ��� �y179�Łz ��Ȋw�̑Ώۂ̏�ł���B�]���āC����ꏊ�Ō��������ꂽ���ۂ⎖�������̏ꏊ�Ō����������Ƃ͌���Ȃ��B�o�c�̏ꍇ�ł����C�Ⴆ�C�ٗp�V�X�e���[�̗p�C���i�C�l���ٓ��Ȃǂ̋�̓I�ȑԗl�͍��ɂ���ĈقȂ�B���̂��߁C�����Ɉ�ʓI���_�����o�����Ƃ��ł���̂��B�ɂ߂č���ȉۑ�ł͂��邪�C�o�c�Ƃ����c�ݎ��̂͐��E�e���ŋ��ʂł���C�ڎw���ׂ����̂͊�Ƃ̐����ł���C���v�̊l���ł���B�����B�����邽�߂ɂ́C�L���Ӗ��ō�������������̎������������Ȃ��̂͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv����B�������C���̂��߂̐��x��J�j�Y���ɂ͂��ꂼ��̍���n��̕�������j�����f����邱�ƂɂȂ낤�B
�܂�C��̐��x��[���������鍑�́C�ǂ̎���̊�Ƃɂ��K�p����̂��������Ƃ͌���Ȃ��B���������_���ӂ܂��āC���{�ɂƂ��āC���{��ƂɂƂ��Ăǂ�Ȑ��x���]�܂����̂��l���Ă��������B����͉��ď����Ƃ͈Ⴄ���̂Ȃ̂��C�������̂Ȃ̂��C�l�@���Ă��������B
�R�D����́u���{�I�o�c�v�_�ɂ��Ă̍l�@
�O�q�̒ʂ���{�I�o�c�ɂ��Ă̋c�_��������s���Ă����̂��C�M�҂�ɂ͒肩�ł͂Ȃ����C�܂��͍ŐV�Ǝv������{�I�o�c�_�ɂ��Ēm�邱�Ƃ͕s���Ƃ�����ł��낤�B���̓_�ŁC2018�N�X���T���i���j�`�W���i�y�j�ɐV�����ۏ���w�ŊJ�Â��ꂽ���{�o�c�w���92����ōs��ꂽ�c�_�́C���ڂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�����ł̓��{�o�c�w���92����_���|�́C
�P�D����_��u���{�I�o�c�̌��݁|���{�I�o�c�̉����c���C����ς��邩�|�v
�T�u�e�[�}�@�@���{�I�o�c�Ƃ͉��������̂��H
�T�u�e�[�}�A�@���{�I�o�c�̉����c���C����ς���̂��H
�T�u�e�[�}�B�@���{�́u��Ў�`�v�͂ǂ��Ȃ�̂��H
�ƂȂ��Ă���B�����ł�92taikai_shushi �Ƃ����t�@�C���ɂ͎��̂悤�ɋL����Ă���7�j�B
�Q�D����_��ݒ�̎�|
���{��Ƃ͂���܂łǂ̂悤�Ȍo�c���s���Ă����̂��B�܂����݁C���{��Ƃ̌o�c�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��B�����č���C���{��Ƃ͂ǂ̂悤�Ȍo�c���s���Ă����ׂ��Ȃ̂��B
�O���[�o�����̎���ƌ����Ă��łɋv�����C���{��Ƃ��P�ꉻ���ꂽ�O���[�o���s��̒��ŁC���E�̊�ƂƓ��X�������������������Ă���B�����č��CAI �Ȃǂ̐V�Z�p�̋}���Ȕ��W���l�X�̐�����l�Ԃ̓����������I�ɕς��Ă����\�����ɂ킩�Ɍ����悤�ɂȂ��Ă����B���������C�m�x�[�V�����̐i�W�͏]���Ȃ������V���i�̊J������Ƃɑ����C�܂����Y���̑啝�ȑ���Ȃǂ����҂����B�����Ă���͐l�X�̐����̗�����傫�����コ���邱�Ƃɂ��Ȃ���ł��낤�B������AI �����ׂĂ̖����ꋓ�ɉ������Ă����킯�ł͂Ȃ��B���{�����ł͏��q����̐i�W�ł��܂��܂Ȗ�肪���łɌ��݉����Ă��Ă���B�J���͕s���������̂��̂ƂȂ��Ă��āC�����⍂��҂��܂߂��u�ꉭ������Љ�v���W�Ԃ���Ă��邪�C���̈���Ŏ�N�J���҂ɂƂ��Ă̓u���b�N��ƁE�u���b�N�o�C�g�̑��݂�������O�̂悤�ɂȂ��Ă���C�ߘJ���E�ߘJ���E�����͂△���ł��Ȃ��ɂ܂Ŏ����Ă���B�����������Ő��{�哱�́u���������v�v�������߂��悤�Ƃ��Ă���B���{�l�̓����������Ċ�ƌo�c�݂̍�������{ �y180�Łz �������Ă���̂ł���B
�Ƃ���Ŏ��m�̒ʂ�C���C���{�͍��x�o�ϐ����𐬂������C���E��Q�ʂ̌o�ϑ卑�ɂ܂ŏ��߂��B����������������{��Ƃ̌o�c�̂����͓��{�I�o�c�ƌĂ�C���Ă̌o�c�Ƃ͈قȂ�Ɠ��̌o�c�X�^�C�����̂��Ă��邱�Ƃ����ڂ��ꂽ�B���{�I�o�c�Ƃ́C��Ƃ��Ċ�Ƃ̐l���J���Ǘ��̕���𒆐S�Ƃ���o�c���s���w���ėp�����Ă���C���{�Ɠ��̂��̂Ƃ���Ă���B��ʂ̐l�X�ɂ́C�A�x�O�������������I�g�ٗp�C�N������C��ƕʑg���́u�O��̐_��v���L���ł��邪�C���{�I�o�c�̌����҂̊Ԃł́C�ނ�����{�ɂ�������j�I�Ȍo�c�̘̂_���Ƃ��Ắu�Ɓv�_�Ȃǂ��L�[�T�O�Ƃ��ĕ��͂��s���Ă����B���̓��{�I�o�c���傫�Ȓ��ڂ��W�߂��̂́C70�N��̐Ζ���@�Ȃǂɂ��_��ɑΏ����č����p�t�H�[�}���X������������ł���C�ꎞ�́uJapan As No.1�v�Ǝ����グ���CJapanese Style Management �͐��E�I�ȊS���W�߂��B�������C80�N��㔼�̃o�u���o�ςƂ��̕��� ���o�āC90�N��ȍ~�킪���o�ς́u����ꂽ10�N�v���邢�́u����ꂽ20�N�v�Ƃ܂Ō�����悤�ɂȂ�C�����̌o�ϓI����ɚb�����ԂɎ������B�����������C�A�����J����R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�_�������Ă��āC�A�����J���̌o�c�������O���[�o���E�X�^���_�[�h���ƌ��`����C����d�������ꂽ�B�������o�ς̒��ʼnߏ�ȏ]�ƈ���������܂܂̓��{��Ƃɑ��ẮC���{�I�o�c�ȂǂɍS���Ă��邩��Ɛђ�����甲���o���Ȃ��̂��ƌ������ᔻ���W�J���ꂽ�B�܂���{�I�o�c�̓O���[�o���o�c�̎���ɂ͂��͂�s�K���Ȃ������Ƃ����̂ł���B
�ł͍����C���{��Ƃ̌o�c�͂ǂ��Ȃ����̂ł��낤���B���{�I�o�c�͉ߋ��̂��̂Ƃ��Ď̂ċ����C����܂œ��{�I�o�c�Ƃ���Ă������܂��܂Ȍo�c���s�͏��ł��Ă��܂����̂ł��낤���B
���{�I�o�c���ɋ������A�x�O�������̑������Ō������C���݂̓��{��Ƃł��̂܂ܒʗp����ƍl����l�͂��͂�قƂ�ǂ��Ȃ��ł��낤�B���Ƃ��Ɓu�O��̐_��v�_�́C���x�������ɂ����Č���ꂽ���Ȃ����I�Ȃ��̂��Ƃ����w�E������B�܂��Ă⍡���̂悤�ɔK�ٗp���S�̂̂S���߂����߂�悤�ɂȂ�C�ٗp���̂��̂��s����ŗ����I�ɂȂ��Ă��Ă��钆�ł́C���̎咣�͐��������������Ȃ��B��҂̑����́C������Ђɒ�N�܂ŋ߂邱�Ƃ����͂ⓖ����O�Ƃ͍l���Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�܂���Ƃ̑����C���i������̖ʂŔN������I�ȏ����ł͂���Ă����Ȃ��Ȃ��Ă���B�܂�A�x�O�������̓��{�I�o�c�_�͂��łɉߋ��̂��̂� �Ȃ����ƌ����Ă��悩�낤�B�܂����{�I�o�c�����L��������И_�̊ϓ_���猩�����C���{��Ƃ̑傫�ȓ����ł�������ƊԂ̊������������Ȃǂ����̔䗦���啝�ɏk�����C�ՐȈ��芔��\���Ɏ���o�c���s���Ƃ����]���̃X�^�C���������������Ƃ͓���B����d���̃R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�������𑝂��Ă��Ă��邩��ł���B�o�u������l�����I���o�ē��{�I�o�c�ɑ���S�͎����C���܂���ϋɓI�Ɏ��グ��Ӗ��͖������̂悤�ł���B
�������C���������Ȃ�������{��Ƃ̌����͂���قǒP���ł͂Ȃ��̂������ł���B�m���ɂ���30�N�قǂ̊ԂɁC���{��Ƃ���芪���o�c���͑傫���ω����C����ɍ��킹�Ċ�Ƃ�����̌o�c�݂̍����₢�ϊv���s���Ă����B�������C�����ł͂����Ă����{��Ƃ��A�����J�≢�B�̊�Ƃ�^�����o�c�X�^�C���Ɋ��S�ɕ����]��������ł͂Ȃ��B�܂���{��Ƃ���͈ˑR�Ƃ��āu���{�I�v�ȓ������Ŏ�ł���̂ł���B�������Ƃ���Γ��{��Ƃ͂���܂ł̌o�c�X�^�C���̉����̂āC�����c�����Ƃ��Ă���̂ł��낤���B�܂��C����͂ǂ��������R����ł��낤���B�����Ă���ɂ���ē��{��Ƃ̋��݂Ǝ�݂͂ǂ��ω������̂��B����Ɂu���{�I�v �ƌ�����悤�ȓ����͍���������Ă����̂ł��낤���B
�y181�Łz�����̓���_��͈ȏ�̂悤�Ȗ��F���ɗ����C���{�I�o�c�ɏœ_�Ă邱�ƂŁC���{�̊�ƌo�c�̉ߋ��C���݁C�������l�@����B���{�I�o�c�͂���������䂭�^���Ȃ̂��C����Ƃ��`��ς��Ȃ��琶�����тĂ䂭�̂��B�u���{�I�o�c�̌��݁v�Ƃ����^�C�g���́C�O���[�o������ɂ�������{��Ƃ̌o�c�ɗ����_���Ǝ��Ԃ����܈�x�₢�����C21���I�ɂ�����V�u���{�I�o�c�v�̉\���̗L����T�낤�Ƃ�����̂ł���B
�@�@���{�I�o�c�Ƃ͉��������̂��H
���{�I�o�c���ǂ�������̂��B���́u���{�I�o�c�Ƃ͉����v�Ƃ����₢���߂����ẮC����܂ő����̌������s���Ă����B���ɓ��{�I�o�c��@���Ȃ�T�O�̂��̂Ƃ��đ����邩�ɂ���āC�ߋ��C���݁C�����č���̓��{��Ƃ̌o�c�Ɋւ��錩����]�����قȂ������̂ƂȂ�B�{�Z�b�V�����ł́C���{�I�o�c�̊T�O���܂߂āC���{�I�o�c�Ƃ͉��������̂���_����B�����ē��{�I�o�c�̗��_�I�g�g�݂͌��݂����Ė������Ǝ˂����ŗL���Ȃ̂��C������肪����Ƃ���ǂ̂悤�ȗ��_�g�g�݂��̂�ׂ��Ȃ̂����c�_�������B�����ł͓��{�I�o�c�̌��߂��܂߂āC���̘_�������߂Ė₤�B
�A�@���{�I�o�c�̉����c���C����ς���̂��H
���{��Ƃ̌o�c�ɂ͂��܂��܂ȓ��������������邪�C����܂œ��{�I�ȓ����Ƃ��ꂽ�N�������I�g�ٗp���傫����ނ��C�����Đ��ʎ�`�I�Ȑl���J���̐����グ����悤�ɂȂ����B�܂��K�Ј��̑啝�ȑ���͎Љ�ɑ傫�Șc�݂������炵�C����ɑΉ����ׂ����{�́u���������v�v�́u����J����������v�̎�����搂��C�����������ԘJ���̉�����ڎw���ׂ����Ƃ��ڕW�Ƃ��Čf����ꂽ�B���̂悤�ɑ傫�ȕω��̒����������邪�C���̈���ŁC���{�I�o�c�̍����ƌ���ꂽ�V�K�w���ꊇ�̗p�͈ˑR�Ƃ��Č��݂ł���B���{��Ƃ͉����c���C����ς��悤�Ƃ��Ă���̂��B���̃Z�b�V�����ł́C���{�I�o�c�̌���ƍ���̓W�]����������B
�B�@���{�́u��Ў�`�v�͂ǂ��Ȃ�̂��H
���{�I�o�c�͉�Ђ̍\�����ƊW�Ƃ����ڕs���̊W�ɂ���B��ƏW�c��n��Ƃ������Ɠ��̍\�����`������Ă������C����������ƊԊW���ω����Ă��Ă���B����d���̌o�c���W�Ԃ���钆�ŁC���������̉������i�W�����芔��\���͑傫���]�������B�ł́C���Ă̏]�ƈ������̓I�ȑ��ʂ������Ă����u��Ў�`�v�Ƃł��Ăׂ�����͂ǂ��Ȃ����̂ł��낤���B����Ɗ֘A���ăK�o�i���X�̍\���Ƌ@�\�������Ƃ��C���{�̉�Ђ͒N�̗��v���d�����Čo�c���Ă���̂��B�������ۂ�傫���ςݏグ����{��Ƃ̎p�ɂ́C����d���Ƃ͂܂��قȂ���������Ď���B�{�Z�b�V�����ł́C���{�I�o�c�̌��݂�������Ђ̊ϓ_����l�@����B
�ȏ�̐ݒ�̉��ɉ��ł͉��l���̔��\�҂����_���q�ׂ����C���̒��ōs��ꂽ��ь��Y�E�_�ˑ�w�����ɂ�锭�\�́C���̌�u�����䂭���{�I�o�c�\�\�O���[�o���s���`�ɐN�H�������{��Ɓ\�\�v�Ƃ����`�ŗv�ꂽ�B
��ы����̌����ł́C���{�I�o�c�̓O���[�o���s���`�ɂ���Ē������N�H����C���͂╗�O�̓��̏�Ԃɂ���Ƃ����B���{�I�o�c�Ƃ��Ď��グ����v�f�ł͕K�������Ȃ����̂́C�]����������⎩��Ɓi�Ȏ��g�j�ɂł͂Ȃ����O���⑼��ƂƂ����u�O�v�ɒu���_���ς��ʓ��{�I�����ł���C�Ƃ������Ƃł���B����܂��܂��O���[�o���[�[�V�������i�W���钆�C���{��Ƃ����E�Ɍނ��Ă������߂ɂ́C�O���Ɋ�����߂���ɍ��킹�悤�Ƃ���̂ł� �y182�Łz �Ȃ��C����Ŕ[�����������C����ɉ����ă��j�[�N�Ȑl�ނ��琬���Ă������Ƃ��d�v�ŁC�O���[�o���s���`�����{��Ƃ�Љ�ɑ������炷���̑��ʂɂ��\���ɔz������K�v������Ƃ����B
�����ł͓��{�I�o�c�̗v�f�Ƃ��č����܂��h�����Ďc���Ă�������́u�l�ނ̈琬�u���v���炢�ł���C�Ǝ咣����Ă���B���̓_�ɂ��ẮC���X���{�I�o�c�̃R���|�[�l���g���ǂ̂悤�ɍl���邩�ɑ傫���ˑ�����b�ł͂��邾�낤�B
�M�҂̈�l�͂܂��C�O�œ��{�I�o�c�́u�D�ǐ��v���M�����Ă������h�C�c�ɂT�N�ݏZ���C�C�O�ł̓��{�I�o�c�̕]���ɂ��Č����C������s���Ă����B�����ł͓��{�I�o�c�ɂ��Ă͎��̂悤�Ɍ��y����K�v���������B
���Ȃ킿�C������u���{�I�o�c�v�ɂ͏��Ȃ��Ƃ���̑��ʂ�����C��̓g�b�v�}�l�W�����g���x���̓��{�I�o�c�C������͌��ꃌ�x���ł̓��{�I�o�c�ł���B�O�҂̓A�x�O���������y�������̂ɑ�\�����C�@�I�g�ٗp���C�A�N�����C�B��ƕʘJ���g���C�Ȃǂ̃g�b�v�}�l�W�����g���x���C���Ȃ킿��ƑS�̘̂g�g�݁E���x�Ɋւ����̂ł���B����̌�҂́C���ꃌ�x���Ŏ��s�����C�o�c�̌���Z�p�Ƃ��ĂԂׂ��u���{�I�o�c�v�̃R���|�[�l���g�ł���B�O�҂ɂ��Ă͂����炭�C�����ނː��Ԃł̌����ɂ͋��ʂȂ��̂�����Ǝv���C�����͕s�v�ł��낤���C��҂͎�̌��y���K�v�ł��낤�B���̑�\�ƍl������̂͗�؎��i2000�j�� ��\�����C�܂���TQC ���܂ޓ��{�I�o�c�̌���Z�p�Ƃ��ĂԂׂ����̂ł���B��ы����̂����u�l�ނ̈琬�u���v�͂��̂Q�̂Ȃ��ł͌�҂ɑ�������̂��낤�Ǝv����B
��؎��i2000�j�́C�A�W�A�ɂ�������n��Ƃ̌o�c�`�A���P�[�g�E���n�����ɂ��ƂÂ��ā`��P�̓A�W�A�X�����ɂ�������n��Ƃ̌o�c�C�ł͎��̂悤�ɏq�ׂ��Ă���B���݂ɂ����ł́u���{���o�c�v�Ƃ����p�ꂪ�p�����Ă���B
�{���ł͓��{���o�c�̊�{�I�������S�̃O���[�v�ɑ啪�ނ��Ă���B�W�c��`�Ǘ��C�蒅�ێ��Ǘ��C�A���ӎ��Ǘ��C����u���^���Y�Ǘ��ł���B�܂��C�O���[�v�S�̂�28�̊Ǘ����ڂ�ݒ肵�Ă���B�W�c��`�Ǘ��C�蒅�ێ��Ǘ��C�A���ӎ��Ǘ��C����u���^���Y�Ǘ��̋�̓I���e�͈ȉ��̒ʂ�ł���i��؎��i2000�j�Cp.11�̕\�ɂ��j�B
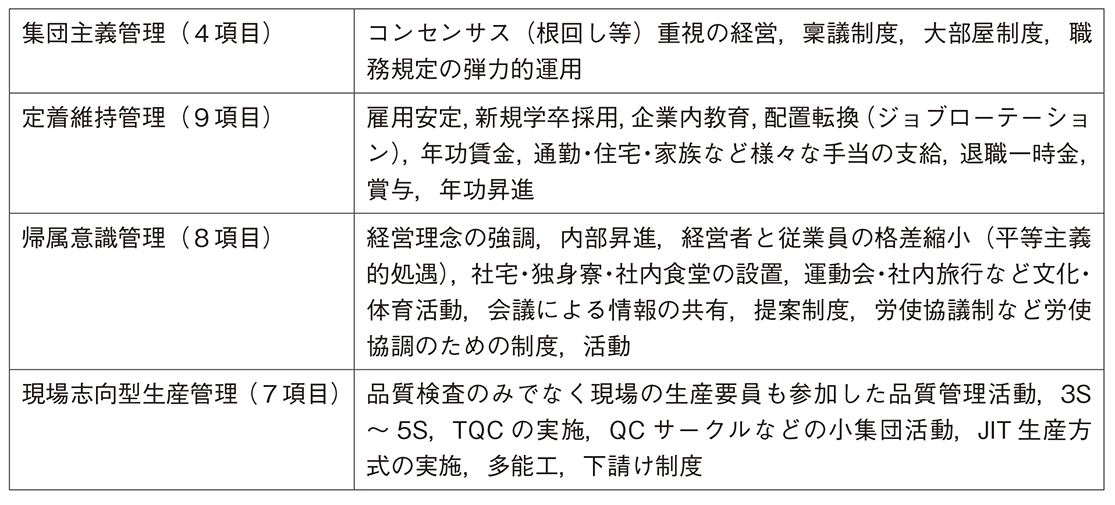 �y183�Łz
�y183�Łz
�W�c��`�Ǘ��́C�ӎv����܂��͌o�c�g�D�̓����ł���C�R���Z���T�X�d���C�g�c���x�C�啔�����x�C�E���K���̒e�͓I�^�p�̂S���ڂ��܂܂��B
�蒅�ێ��Ǘ��Ƃ́C�J���҂���Ɠ��ɒ蒅�����]�E���s���ɂȂ�悤�Ȑ��x���Ӗ����Ă���B���̊Ǘ����ڂɂ́C�ٗp����C�V�K�w���̗p���Ɠ�����C��Ɠ��ł̂ݒʗp�������I�L�����A���`������z�u�]���C����ɔN�������E�N�����i��ܗ^�C�ސE�ꎞ���C�ʋE�Z��E�Ƒ��ȂǗl�X�Ȏ蓖�̎x�����̋Α��ݑ��I�ȕ�V���x�̂X���ڂ��܂܂��B
�A���ӎ��Ǘ��́C��Ђւ̍D�ӓI�ԓx���`�����邽�߂̊Ǘ��ł��邪�C���{��Ƃ̏ꍇ��ЂƏ]�ƈ��l�ꉻ�i�܂��͈�̉��j���悤�Ƃ���X���������Ǝv����B�a�̐��_���������鐸�_��`�I�o�c���O�C��Ɠ����ŏ��i����C�������i�C�����E�ҋ��ʂő傫�Ȋi�������Ȃ�������`�C�Б�E�Ɛg���E�Г��H���̐ݒu��^����E�Г����s�Ȃǂ̕����E�̈犈���̂悤�ɋٖ��Ȑl�I�ڐG�ɂ��ƂÂ���Ɠ��l�I�l�b�g���[�N�̌`���C��c���J�Â���O�ɗ\�ߍ������ď������L���邱�Ƃɂ���̊��̌`���C��Ă�ʂ��Ċ�ƈӎ��E�Q���ӎ����`�������Đ��x�C�J�g���c���ȂǘJ�g�����̂��߂̐��x�E�����̂W���ڂ����̊Ǘ���i�ł���B
����u���^���Y�Ǘ��Ƃ́C���{��Ƃ̐��Y�u����v���d�����鐶�Y�Ǘ��̓������Ӗ����Ă���B���̓�����\�����t�Ƃ��āC�����`�C����C�Y���C�m�I�n���Ȃǂ��w�E����Ă���C�����Ҏ��g���K�₵�����n��Ƃł�����̏d�v�������т��юw�E����Ă����B���Ҏ��g�́C���̓������u���P�E�Q���E���̋��L�Ȃǂ̏��s����ʂ��Đ��Y����̒m�b�����p���鐧�x�v�ƒ�`���Ă���B���̃O���[�v�ɂ͕i�������݂̂łȂ�����̐��Y�v�����Q�������i���Ǘ������C�����E���ځE���|�E�����E�^�Ȃǂ̎��{�i3S�`5S�j�CTQC�i�S�ГI�i���Ǘ��j�̎��{�CQC �T�[�N���Ȃǂ̏��W�c�����CJIT�i�W���X�g�E�C���E�^�C���j���Y�����̎��{�C���\�H�C���������x�̂V���ڂ��܂܂��B
�������Ċς�ƁC�����ɋ������Ă��鑽���̌��ꃌ�x���́u���{�I�o�c�v�̋Z�p���l����Ƃ��i����͍ŐV�̏Ƃ͌����Ȃ���������Ȃ����j�C������{�ɂ����āC��ы����̂����u�l�ނ̈琬�u���v�ȊO�̗v�f�́C���邢�͓��{�I�o�c�̗v�f�Ƃ��č����܂��h�����Ďc���Ă�������́u�l�ނ̈琬�u���v���炢�ł���C�Ƃ����咣�́C���̂܂܂��Ă͂܂�ł��낤���B�����܂Łu���{�I�o�c�v�͕ϖe���Ă��܂��Ă��邩�B
�M�҂�̈�ۂł́C�u���{�I�o�c�v���x����d�v�ȗv���Ƃ��āC��؎��i2000�j�ɂ����u�A���ӎ��Ǘ��v���d�v�Ȃ͎̂����ŁC����́u�l�ނ̈琬�u���v�ɂ����Ă��C����Β��S�I�Ȗ������ʂ������̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B�����C�����ɂ���ȊO�̏��v�f���C�����Ȃ����{��Ƃ̊������x�����Ȓ��ɂȂ��Ă���C�Ƃ������G�������Ă���B
�S�D��Ў�`�\�\���{������Ђ̍Đv�ɂ���
�O�q�̓��{�o�c�w���92����_���|�ɂ�����C�B���{�́u��Ў�`�v�͂ǂ��Ȃ�̂��H�C�́C�܂��͍l���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��d�v�Ȗ��_�ł���B
�o�c�w�_�W89�W�Ɍf�ڂ���Ă��鏬�����̘_���u���{������Ђ̍Đv�v�́C1990�N��ȍ~�Ɏn�܂������{�̏،��s��̉��v����{��Ƃɑ���K�o�i���X�ϊv�ւ̈��͂��C���嗘�v�̏d���֕肷���Ă���Ƙ_���C����͓��{�̊�Ƃ�o�ςɑ��ăv���X�̕����ɓ����̂ł͂� �y184�Łz ���C�ނ���t��p���y�ڂ��Ă���ƔF�����Ă���B
�������ɂ��ƁC��������������ЂɌ��炸��Ƃɂ��ẮC�Q�̌���������B�u��Ƃ͗��v���Y�o���鎑�{�̑g�D�C�c���@�\�ł���Ƃ����Ɗρv�Ɓu�Љ�I���Y���c�ސl�Ԃ̑g�D�u���Y�����́v�ł���Ƃ����Ɗρv�B
�������͌�҂̗�����Ƃ�C���{��Ƃ��ٗp�̊m�ۂ�D�悷��̂͊ԈႢ�ł͂Ȃ��C���{�̓`���ƓK���I�ł���Ƃ��Ă���B�����āC������ƌ����āC���{��Ƃ͊�����y�����Ă����킯�ł͂Ȃ��C���������ᔻ�́C�Z���I�C���@�I���v�̊l�����|�Ƃ��鉢�Ă̓����t�@���h�ɂ����̂ł��邪�C�����I�ɂ݂�Ɨ��v��z���ɉ̂��K�ł���Ƃ͌���Ȃ��̂ł���B�����̂��߂̓������ۂƔz�����T�d�Ɋ��Ă����ׂ��ł���Ƃ��Ă���B
���{�̃R�[�|���[�g�E�K�o�i���X���v�́C2000�N�㏉�߂̃A�����J���̈ψ���ݒu��Ђ̓����ɂ��}���ɐi�ނ��Ƃ����҂��ꂽ���C�����ɂ͓`���I�Ȋč���ݒu��Ђ��ˑR�Ƃ��đ����B�܂��R�[�|���[�g�E�K�o�i���X���v�̈�̖ڋʂƂ��āC�ЊO������̐ݒu�����߂��Ă���C�ݒu���Ȃ��ꍇ�ɂ͂��̗��R���J��������ȂǁC���Ȃ苭�͂Ȉ��͂�������C�\�ʏ�͏���Ƃɂ����Ă͑������x�i��ł��邪�C���̎������ɋ^���悵�Ă���B���ہC�ЊO������̊m�ۂɑ����̊�Ƃ͋�J���Ă���C���ɓƗ��ЊO������̐l�ނ͕s�����Ă���ƌ����Ă���B���������āC�`���I�ȃK�o�i���X�̐������ʂ����ėL���ɓ����ł��낤���C�Ƃ������ƂɂȂ�B
�������������́C�ߔN�̊�Ɠ������v�͓��{�I�o�c�̗ǂ��ʂ����E���闬����������Ă���C�������ׂ��ł���Ƃ���C�����i2014�j�̗���Ƌ��ʂ���8�j�B����܂ł̃A���O���E�T�N�\�����̊���d���Ƃ͈قȂ�����Ɠ����݂̍�����l����ׂ����Ƃ�����ĂɂȂ���̂ł���B
��̓I�ɂ́C�������͊�ƂY�����̂ƈʒu�Â��C�����Ƃ����j�I�ȗ���ɂ���]�ƈ����d�����C���ɂ���]�ƈ����������ʂ��Čo�c�Q�������邱�Ƃ��C�e�ՂɎ����\�ȓ��{�̊�����Ђ̍Đv�̑��̒�ĂƂ��Ă���B�����Ă�蒷���I�ɂ́C�����]�ƈ��Ƃ͐藣���ꂽ��Ǝ�̂̑��݂�F�߁C�����ɗ��v���A��������Ƃ����A�����J�̉�v�w�҃A���\�j�[�̍l�����Ɏ^�����C�������������ł̉��v�����Y�����̂Ƃ��Ă̓��{��Ƃ����߂������Ƃ���B
�����C�M�҂炩�炷��ƁC�]�ƈ���������͂��������ݗ����ꂽ��|�����{����Ⴄ�̂ł���C�ʂ����ď]�ƈ��̈ӎv���\�ł���̂��傫�ȋ^�₪�c��i�v�ہi2010�j�j9�j�B�o�c�Q�����邽�߂ɂ͌o�c�Ɋւ���l�X�ȏ������L���邱�Ƃ��O��ƂȂ�Ǝv���邪�C���ꂪ�ǂ̂悤�ɂ��ĉ\�ɂȂ�̂��B�܂����K�C�K�Ȃǂ̏]�ƈ��Ԃ̗��Q�Η����ǂ����₷��̂��C���邢�͉����ł���̂��C�����ĊO���Ɛ藣���ꂽ�`�ł̏]�ƈ��̃p���[�̊g��͂��ēy�����w���{�I�o�c�̐_�b�x�i1978�j�Ŏ咣������ƃJ�v�Z����10�j�ɂȂ���C���ꂪ���݂̂悤�Ȋ�Ƃ̎Љ�I�v������Ƃ̋����������v������鎞��ɖ]�܂����̂��C�Ƃ������O���c��B
�y185�Łz�A���\�j�[�̊�Ǝ�̘_�ɂ��ẮC�����������O����Ă��邪�C�o�c�҂̐ꉡ�ɂȂ���̂ł͂Ȃ����C������ǂ��`�F�b�N����̂��C���傪�ŏI�I�ɔC�ƌ������Ƃ��������ł́C�`�F�b�N�@�\�����܂��������C�^�₪����B���������o�u�����̑��Ƃɂ�����s�ˎ��C�ŋ߂̓��Y�Ⓦ�ł̖����݂�ƁC�ƍٓI�Ȍo�c�҂̊Q�͌v��m��Ȃ����̂�����B������ǂ̂悤�ɂ����邩�B�A���\�j�[�̊�Ǝ�̘_�͂��ꂩ��̓��{��Ƃ̋���ׂ����z�Ȃ̂��B��v�w�ɂ����Ĉ�̗�����`�����Ă���悤�ł���C�M�҂����{�I�ɂ͂��ׂĂ̗��Q�W�҂��痣�ꂽ�����I�Ȏ��̂Ƃ��Ă̊�Ƃ̑��݂�F�߂邱�ƂɎ^���ł��邪�C��������� �Ē����ɐ��������̂Ƃ��Ă̊�Ƃƌ��т��Ƃ͎v���Ȃ��B�����̂Ƃ��Ă̊�Ƃ��]�ƈ���n��Љ�Ƃǂ̂悤�ɂ������ׂ����C�T�d�Ɍ�������C�K�Ȑ��x�v���Ȃ����K�v�����낤�B
���{�I�o�c������ł́C�ǂ����Ă����܂Ƃ����̃V�X�e���̕����ƌ��J���̃o�����X���ǂ��Ƃ邩�B�Œ萫�Ɨ������̃o�����X���ǂ��Ƃ邩������Ƃ��d�v�ȉۑ�ɂȂ�Ǝv����B
�i�����j
���M�҂�́C���݂̎��_�ł́u���{�I�o�c�v�ɂ��č���x�������������ƍl���C���̂��������Ƃ��Ė{�e�ɂ����邱�ƂƂȂ����B���łɎ��m�̒ʂ���{�I�o�c�ɂ́C�������ɑ��l�ȑ��ʂ�����B���������̒��ŁC��͂荡���܂ŁC����u�D�ʐ��v��O���ɁC���邢�̓C���[�W���āC���S�I�ɍ̂�グ���Ă����̂͐l���E�J���E�g�D�̑��ʂł���B�ٗp�W�𒆐S�Ƃ��āC���{�I�o�c�́u�D�ꂽ�_�v�Ƃ��āC����͂���40�N���̂�グ���Ă������̂ł͂��邪�C���ꂾ���ł͂Ȃ��C�M�҂�̊S�Ƃ��Ă��ꂩ��l���Ă��������Ǝv���Ă���e�[�}���G�c�ɗv��ƁC���̂悤�ɂȂ�ł��낤�i���s���j�B
�E���{�I�o�c�̌��_���ǂ��ɋ��߂邩
�E���_�Γ���_�C�l�{��`�̕]��
�E�o�c�ڕW�̕ϑJ�ƃK�o�i���X
�E�ٗp�E�J�g�C�̗p�C���i�C��V�W
�E����
�E�n��E����W
�E�g�D�Ґ��E�ӎv����֘A
�E���Y�V�X�e���̔��W
�E���{�I�o�c�̏���
�A�x�O�����CJ. �i1958�j�C�w���{�̌o�c�x�C�_�C�������h��
�ѓc�j�F�i1998�j�C�w���{�I�o�c�̘_�_�\��������T�鐬�������x�CPHP ������
����쒉�j�i2014�j�C�w�o�c�͂���̂��̂��x�C���{�o�ϐV����
��ь��Y�i2019�j�C�w�����䂭���{�I�o�c�\�\�O���[�o���s���`�ɐN�H�������{��Ɓ\�\�x�C�o�c�w�_�W��89�W�Cpp.38-46.
�v�ۍ��s�i2010�j�C�w�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�|�o�c�҂̌��ƕ�V�͂ǂ�����ׂ����|�x�C���{�o���y186�Łz �V����
�����@�́i2019�j�C�w���{������Ђ̍Đv�\�\���Y�����̂ւ̉�A�\�\�x�C�o�c�w�_�W��89�W�Cpp.80-86.
Koyama, A. �i1991�j�C Eigenarten des japanischen Managements, Schmalenbachs Zeitschrift fur betriebswirtschaftliche Forschung, März 1991 pp.275-284.
��؎��i2000�j�C�w�A�W�A�ɂ�������n��Ƃ̌o�c�@�A���P�[�g�E���n�����Ɋ�Â��āx�C�Ŗ��o������
�y����́i1978�j�C�w���{�I�o�c�̐_�b�x�C���{�o�ϐV����
���{�o�c�w��ҁi2017�j�C�w���{�o�c�w��j�x�C��q���[
�O�֖F�N�E�����U�C���[�C�l�D�i2001�j�C�w�Y�Ɛ����_�̌���x�C�I�ɍ������X