現代の「日本的経営」論(5)
手塚 公登・小山 明宏
1.1 わが国の海外直接投資の動向
戦後の高度経済成長期を経て,わが国の大企業は電機産業などを中心に海外生産に乗り出した。企業が海外進出に踏み切る理由は多様であるが,わが国の場合,当初は貿易摩擦や円高を背景として,仕方なく,消極的にという色合いが濃かった。海外での経営は,国内とは大きく異なった社会環境や文化的背景,法制度,政治等に向き合いながら行う必要があり,その壁を乗り越えるのは容易ではないからである。しかし,その後,大企業の生産性は飛躍的に高まり,高パフォーマンスを誇る経営・生産方式を基に,積極的に海外戦略を展開するようになった。
2000年代前半までのわが国の海外直接投資の推移を示したのが,図表1である。1980年代後半には1970年代に比べて,大幅に増加し,バブル崩壊後,減少に転じていることがわかる。特に80年代後半における伸びが際立っている。この間に日本の世界経済に占めるプレゼンスは非常に高まった。日本企業が海外進出をした理由は,貿易摩擦をさけるため,発展途上国の低賃金を利用するため,比較優位にある経営資源を活用するため1),など時代とともに変わるが,現地での経営を日本国内と同様に効率的に行うために,日本企業独特の経営手法・生産方式を移転する動きも徐々に進められるようになった。というのも,当時の日本企業は自動車産業や電機産業などの加工組み立て産業において,欧米諸国を凌駕するパフォーマンスを示し,比較優位を勝ちとるようになってきたからである。
その比較優位を有する経営管理方式をどのようにして海外でも活用するかが,日本企業にとっての大きな課題であった。日本企業が欧米諸国に比較して優位に立てた理由には,労働生産性の上昇,製品品質の高さ,効率的な生産体制の確立,国民性としての勤勉な労働態度,あるいはアメリカから批判を受けた海外からの投資に対する閉鎖的な産業政策,系列関係の構築など,プラス・マイナス,様々な評価のつきまとう要因が挙げられるが,日本企業の優位性の源には,日本的経営と呼ばれた独特の経営・生産システムも間違いなくあったと思われる。
【184頁】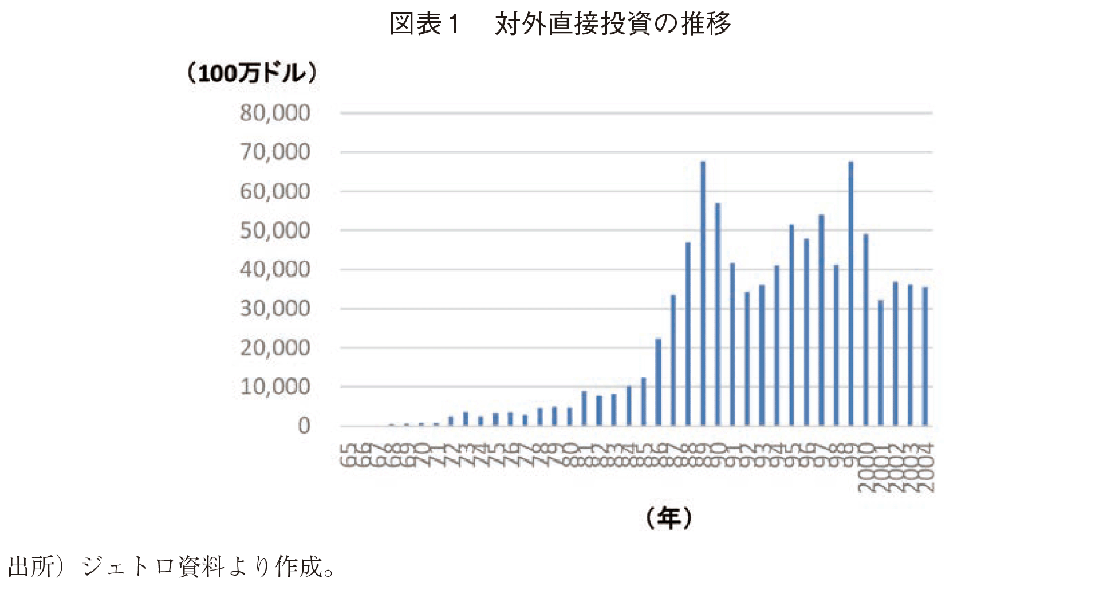
1.2 日本的経営の移転可能性について
1980年代に隆盛を極めた(称賛された)日本的経営に関わる一つの論点として,日本的経営の海外移転問題があった。日本的経営の効率性や優越性を認めるとして,果たしてそれが日本以外の他国において適用可能なものであるか,理論的に,そして実証的に解明しようとする研究が積み重ねられていた。日本企業の競争上の優位性の源が雇用慣行や生産現場における管理の在り方にあるとするなら,海外進出を進めていった場合,その強みを国外でも発揮できるかどうかに関心が寄せられたことは当然であった。
1.2.1 日本的経営の特殊性と普遍性
日本的経営の海外移転を論ずるに当たっては,まず日本的経営とはそもそも何かということが問題となる。そして,海外移転が可能かどうかということであれば,日本的経営の本質やその構成要素がどの程度,日本の社会や文化に立脚する「特殊」なものなのかが問われることになる。さらに,日本的経営の移植で,果たして企業のパフォーマンスにどの程度影響を与えるのか,それによって,移転すべきかどうかの判断も大きく変わることになろう。
この連載ですでに日本的経営の特徴は論じてきたところであるが(手塚・小山(2021a,b),(2022a)参照),日本的経営が何かを明確に規定することは実に難しい。論者によって,時代によって,その内容や評価は変化している。アベグレン(1958)はいわゆる3種の神器を日本的経営を特徴づけるものとして,初めて指摘した。企業内における雇用慣行と労使関係がその中心にあり,欧米では見られない独特のものであると,論じた。ミクロ経済学における新古典派流の,企業の自由な参入・退出を基本に需給調整がなされる市場機構の作用によって最高度の効率性が確保されるとする観点からから見れば,日本の終身雇用や年功序列,あるいは集団主義的な企業経営の在り方はかなり異質であり,資本家と労働者の封建的な従属的関係を反映する「遅れた」制度が日本的経営の本質であると捉えられた。
そうした指摘にもかかわらず,日本企業は70年代以降急速に成長を遂げた。合理的で,自立 【185頁】 した経済人の契約から構成される市場の働き,それを前提とした企業組織の経営活動が普遍的な効率性を有すると想定してきた英米の経営者や研究者からすれば驚きであった。英米流の効率的な経済システムは,個々の社会や文化の在り方,人々の価値観とは独立に,普遍性をもって通用する理論的な帰結であるとされていた。そうした観点からすると,日本企業の様々な施策や慣行は異質なもの,あるいは遅れたもの,あるいはいずれ是正されなければならないものであった。1970年代までは,外国の研究者だけでなく,日本の学界や研究者の一般的な認識であったといえよう2)。
ところが,この評価は80年代に入ると一変することになる。自動車産業や電機産業などの加工組み立て産業での日本企業の躍進がその背景にあった。代表的にはトヨタ自動車を挙げることができよう。生産工程の革新によって,かつてのフォード流の一品種,大量生産の流れ産業方式に代えて,需要動向を素早く反映した多品種生産に対応できる効率的なトヨタ生産方式が登場し,緊密な企業間取引による優れた生産体制が確立した。この方式は,労務管理面からみると,職務の無限定性への志向,それを支える査定制度,長期雇用を前提とした多能工の育成などによって可能となった。しかしながら,トヨタ方式の効率性が認識されても,狭い職務に基づく仕事の分担が当たり前とされる海外の企業での導入はなかなか困難であったのである。
翻って,それが効率的であるのはなぜなのか。日本企業の雇用の在り方での特殊性の一つは,労働者への賃金の支払いの仕方,昇進や昇格の在り方が短期的な成果に基づくのではなく,生活保障給的な要素を含めた,長期的な視点から行われていたことである。この慣行が生まれた背景には様々な理由が考えられるが,一見すると経済合理性から外れているようにみえる。市場における労働の短期的な需給のメカニズムと隔離されたところで賃金が決定されているからである。しかしながら,長期的にみて,労働者の努力や貢献に報いることができるシステムなので,合理的であり,長い年月をかけて企業特殊的な熟練・技能を育成するには欠かせないともいえる。理論的に言えば,外部労働市場とは直接連関しない形で,効率的な内部労働市場が形成されていたのである。
そうすると,問題はこうした慣行が海外でも通用するのかどうか,表現を変えれば,日本的経営は日本に特殊なものであるのか,そうではなく普遍性を持つのかである。これは,広く言えば,経営という営みが,それが行われる社会的文脈から切り離されて展開できるかどうかという問題でもある。この問題について,日本的経営の後進性・封建的性格を論じていた人たちは,特殊で克服されなければならないと考えており,到底普遍性をもつなどありえなかった。これに対して,日本的経営の原理は,決して遅れたものではなく,普遍的で合理的な内容を含むと論じた論者が80年代には多く現れ,活発な議論が交わされた3)。しかし,この論争は理論の段階で決着がつくものではなく,実際に海外の生産現場で日本的雇用,生産・管理方式がどのように,どの程度採用されていたのか,実証的研究によって確かめられる必要があろう。
【186頁】1.2.2 日本的経営の強みとは
ところで,日本的経営の海外移転を論ずるには,先述したように日本的経営の核は一体何であるのかを明確にしなければならないが,それが意外に難しい。企業経営には,様々な側面があり,そのどの部分を切り取るかによって,いろいろな見方ができる。研究開発,生産,販売,財務等々の機能的側面における業務の仕方を取り出すのか,ヒト,モノ,カネ,情報,といった経営資源の運用の仕組みに焦点を当てるのか,トップ,ミドル,ローアーの階層別の役割分担やコミュニケーション,指揮命令の在り方をみるのか,多様な比較の軸があり得る。日本的経営の議論で当初,焦点が向けられたのはヒトの部分に関わる,労務問題や労使関係であり,もう一つは,生産工程や現場での職務編成に関わるものであった。
日本的経営の海外移転に関する実証研究をサーベイする前に,日本的経営の強みをどこに求めるかに関わる論争について若干触れておこう。論争の中心は小池和男の一連の研究4)についてであった。小池は,労働経済学や労務管理論で多大な業績をあげ,学界,実務界に極めて大きな影響を与えてきた。その研究スタイルは徹底して,現場の観察にこだわり,当時の通念や通説に疑問を投げかけるものであった。小池はいわゆる3種の神器を日本的経営の柱とみなすことに否定的であった。西欧諸国の統計資料を基に,西欧においても年齢とともに平均賃金が上昇する傾向がみられると主張し,終身雇用や年功賃金が日本独自のものであることを否定した。当時,一般に流布していた通説に基づく日本的経営の独自性を否定し,注目を浴びた。しかし,この点に関しては,いくつかの反論もあり5),マクロ的な統計資料に基づく平均賃金の比較だけでは,西欧においても年功賃金があることの証明にはならないと考えられる。各年代における平均賃金を構成する労働者の勤務年数や職務内容などを精査しないと,日本と欧米企業が類似の年功賃金に従っているとは言えないであろう。
ただし,一方において,小池は日本企業の経営に独自性はないと主張したのではなく,日本企業の強さの要因を,長期的視野からの人材形成,熟練の育て方に求めた。欧米企業の生産現場では,労働者の職務が厳密に定義されていて,各自の仕事内容が職務記述書に基づいて,細かく定められている。そして賃金も職務ごとに定められ,基本的に年功や成果に連動するわけではない。職務間のデマケーション(区分)が徹底しているのである。そのため,生産労働者が仕事の幅を広げることはないし,多能工を養成することができないとする。こうした慣行の下では,生産工程の最終段階で一括して製品の検査がなされることになるので,流れ作業の生産現場で,品質の不具合や不備の改善を効率的に行うことはできないのである。
それに対して,日本企業では作業員の職務が厳密に定められているのでなく,柔軟な仕事の分担が可能となる。日本企業の生産現場での特徴は,労働者が体験する仕事の経験の幅と深さにあると主張する。これは多様な仕事の経験を通じて育成されるものであり,生産労働者に熟練,特に知的熟練(異常に対する対処の仕方,普段と違った出来事に対応する能力)を体得させている。小池は日本的経営の強みはここにあると主張し,生産現場で使用されている仕事表を示して,日本企業の現場における生産労働者の配置の仕方と働きぶり,それに対する評価の仕組みについて説明している。これを巡っては,野村(2001)や遠藤(1999)6)から,仕事表 【187頁】 の内容や存在自体について強い疑問が呈せられた。特に野村は,経験の深さについては仕事表から読み取れないとし,専門工の役割を無視した議論であると批判している。そもそも熟練の深さを測定することは難しい。確かに日本企業の労働者は,キャリアの幅や仕事の幅は,ジョブローテーションを通して他国より広いのであるが,小池が言うほど日本の生産労働者に熟練の深さがあることは実証されていないようである。
従って,日本的経営の特質や強みについてはなお議論の余地はあるのだが,年功を重視した処遇,仕事の幅の広さ,柔軟な職務編成などはある程度は日本独自のものであり,強みとなっているとみなせよう7)。そうした強みを日本企業は海外へどのように移転してきたのか、いくつかの実証研究をみていこう。
1.3 日本的経営・生産システムの海外移転に関する研究
1.3.1 安保・公文グループの研究成果
上述したように,自動車産業や電機産業を中心として,わが国企業は80年代に入って,積極的な海外進出に乗りだした。海外へ工場を建設し,生産性を高める生産体制を確立して行くうえで,つまり日本企業の競争優位を維持するためには,日本の工場での労務・生産管理方式がそのまま通用するかどうかが大きなカギとなった。
日本的経営が海外で適用できるかどうかに関する研究は,70年代後半からなされていたが,包括的かつ大規模な実証研究を行ったのは,安保・公文グループが初めてであろう8)。当グループは80年代後半から研究成果を発表しはじめ,2000年代にかけて,アメリカ,東アジア,EU,ラテンアメリカと,まさに世界を股にかけて次々と日本的経営・生産システムの移転の実態や問題点,課題等についてアンケート調査やインタービュー調査,工場観察を実施し,詳細な研究成果を発表した。
彼らは,日本企業が競争優位を有するとみられた経営・生産システムが世界各国の製造業の工場現場でどのように,そしてどの程度導入されているかを調べた。その枠組みは,図表2の左側の欄に示されているように,経営・生産システムを23項目の要素から構成されものとし,大きく作業組織と管理運営,生産管理,部品調達,参画意識,労使関係,親―子会社関係の,6グループに分けた。図表2には,それぞれの移転度合いを点数化して評価した結果を合わせて表示してある。この調査の基となる考え方を,彼らは適用・適応モデルと呼んでいる。この 【188頁】 モデルで,「適用」とは,日本の工場で採用されている制度や手法が基本的にはそのまま移転されていることを指し,「適応」とは基本的には現地での制度や仕組みが採用されていることを意味している。国内工場での労務管理や生産管理の方法・仕組みが海外子会社でどの程度修正されているかを,5段階で評価を行っている。数値の大きいほど,日本的な慣行の受け入れ度が高く,1に近いほど現地化されていることを示している。つまり,現地での変容の程度が小さい場合には,適用で,現地の政策や価値観を受け入れて,大幅な変化がある場合は適応とし,それを適用・適応モデルと評しているわけである9)。
図表2には国・地域別の評価点が示されている。当然のことながら,評価点には項目によってまたグループ別に違いはあるが,概ね平均すれば,3点であり,日本的経営・生産システムは全体として海外移転が行われ,それなりに受容されている。日本的慣行が全く特殊であって,海外への適用可能性がないということはなかった。グループ別に簡単にみていくと,作業組織の中の賃金体系では,欧米諸国での適用の度合いが低く,アジアでは高い。また職務区分や多能工化では全般的に点数が低いが,特にアジアでは適用の度合いが低く,日本的な方式をそのまま持ち込むことに苦戦していることが見て取れる。
次に,生産管理では,メンテナンスで点数が低く,これは職務区分が日本と違って狭いことを表しているのであろう。部品調達については,ローカルコンテントなどの政府の政策に依存して適用度は変わり,特に英国では点数が低く,極めて保護主義的政策が採用されていて,現地の要請に応えざるを得ないことがわかる。
参画意識の中の,小集団活動では欧州,北米の低得点が顕著である。欧米における個人主義的な意識の反映であるかもしれない。特に大陸欧州では情報共有化や一体感の程度も低く,同じ欧州でも英国との差異が目立つ。労使関係では,長期雇用や労使協調などいわゆる日本的経営の典型と思われる慣行がそれなりに取り入れられているようである。最後に,親―子会社関係では,アジアでは日本人比率が低く,現地に任されており,欧米ではあまり任されていない。
【189頁】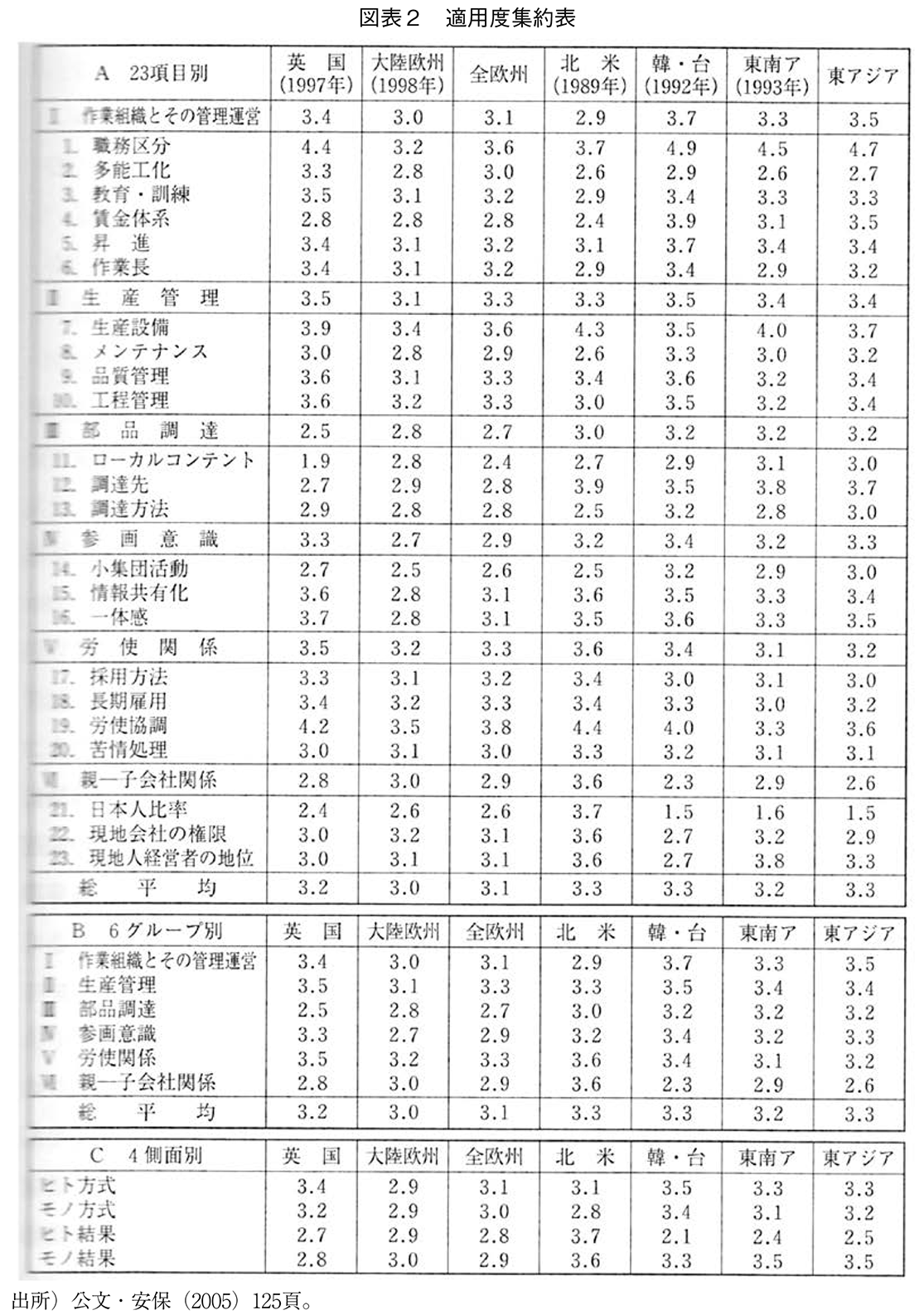 【190頁】
【190頁】
次に,もう一つの日本的経営の移転度合いの評価方法として,この研究ではモノとヒトに関して,方式を移転するのか,出来合いのものを直接移転するのか,という4側面別評価を行っている(図表3参照)。これは,先の調査結果の項目を整理し直し,移転がどのような形で行われるのか調べた。国・地域ごとの移転の困難さの比較や態様の違いをつかむ上で,有用である。彼らによると,方式での移転の方が,一般的には,より深く日本的経営を現地に移転していると評価できる。図表2の最下段に示されているように,ヒトについては,アジアでは方式が適用されており,北米では出来合いの移転の度合いが高い。北米では,文化的な差異などから日本人従業員の比率が高く,日本人による直接の指導が不可欠なことを意味している。モノについても同様の傾向がみられる。いずれにしろ,日本の経営・生産システムの項目がすべて,そのまま現地経営に取り入れられることはないのであり,現地の環境や歴史,価値観も加味しながら世界各地で移転されていったといえる。国によって,地域によって,日本的経営・生産方式の移植の容易さやどの側面の移転可能性が高いかは,かなり異なる。このことから,世界各地で適用と適応を組み合わせた異なった水準のハイブリッド経営が行われていたことを示唆していると推測できよう。
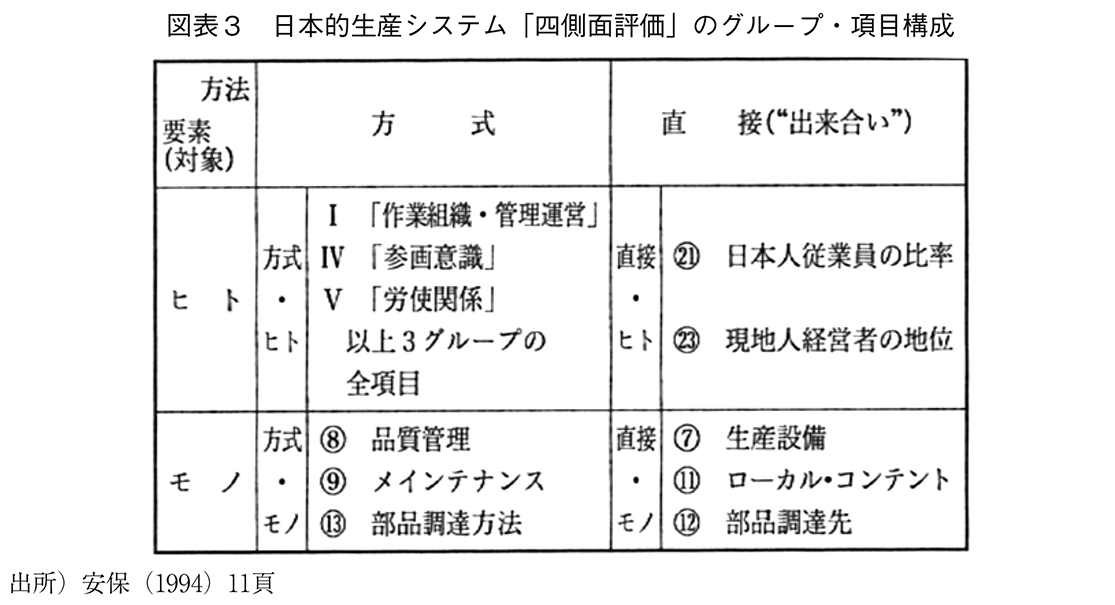
このように,日本的経営システムの適用度は,濃淡さまざまであるが,当該国・地域の事情を鑑みて,移転が実行されていた。日本的経営は特殊であると言われるが,彼らは,ハイブリッド化され,修正された経営方式が海外で行われていると結論付けている。そのハイブリッド化の程度は業種や国・地域によって異なっているが,日本的な経営・生産システムは世界的に通用する普遍性を有する面もあるといえるだろう。
【191頁】1.3.2 鈴木滋(2000)のアジアにおける日系企業の経営
この著作についてはすでに手塚・小山(2021a)で多少取り上げた。彼は,日本式経営10)の特質を人間中心帰属意識管理と規定し,集団主義管理,定着維持管理,帰属意識管理,現場志向型生産管理の,4つにグルーピングし,28個の管理項目を設定している11)。そしてそれぞれについて採用比率・有効性・不受容性をアジア9ヵ国12)について調査した。
図表4は,労務管理の項目のアジア9か国の平均値を示している。そこでの国際的な普遍性を図る尺度として,有効性と受容性(または不受容性)を採用している。28項目の中から現地で最も有効な(または最も不受容と思われる)項目の上位3位を質問し,1位を3点,2位を2点,3位を1点で計算し,それらの点数を合計して有効性と不受容性の順位付けを行った。労務管理では,定着維持管理,帰属意識管理とも有効であるが,新規学卒採用や年功賃金,昇進といった慣行は,採用比率も低いし,有効でもないことがわかる。この結果は,上述の安保・公文グループの研究とは少し異なるようにみえるが,退職金や賞与などの慣行は採用されているので,ある程度は日本的な処遇の仕組みは受け入れられているといってよいだろう。安保・公文グループと調査方法や対象が異なるので,直接の比較はできないが,労使協調などが採用されているのは同じ傾向である。
図表5の生産管理面では,5S(整理,整頓,清掃,清潔,しつけ),工程内品質保証といった日本的な生産管理の基盤といえる部分は採用され,浸透しているが,多能工,JIT生産方式の採用比率や有効性が低いことが目立つ。後者は職務の幅に関わるので,移転が困難なのかもしれない。この点については前出の安保・公文グループも同様の結果を示している。
この調査でも,日本的経営の全面的な移転は困難であるが,一定程度は移植可能であることを明らかにしている。
【192頁】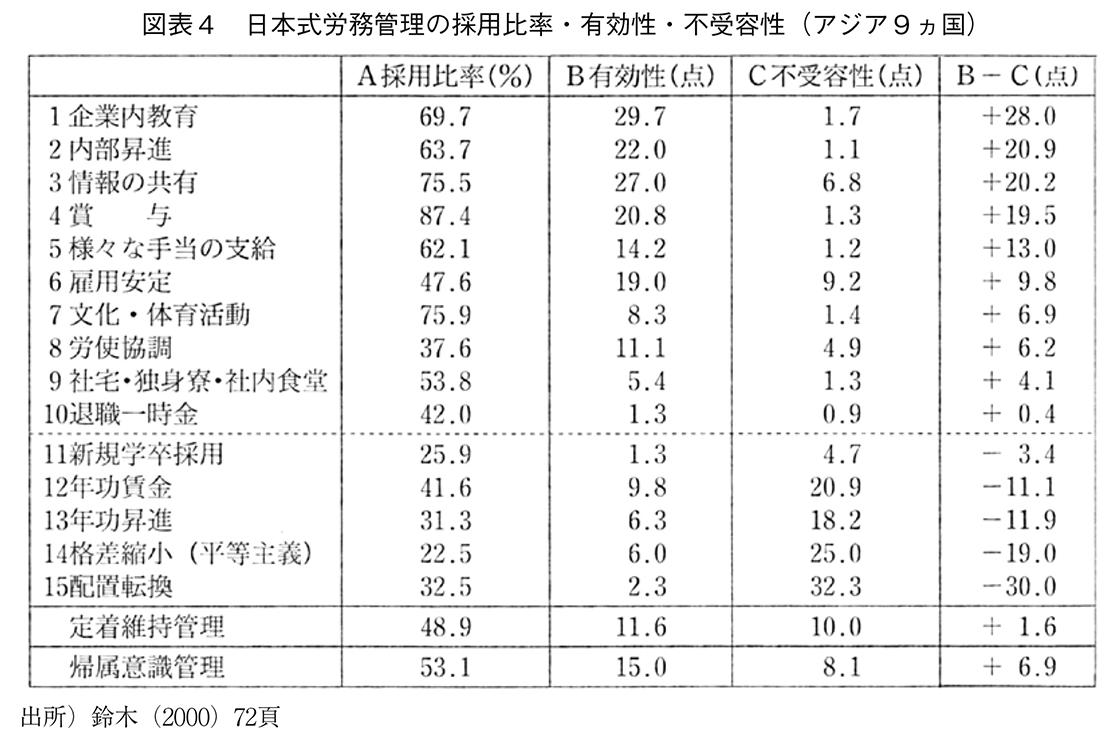
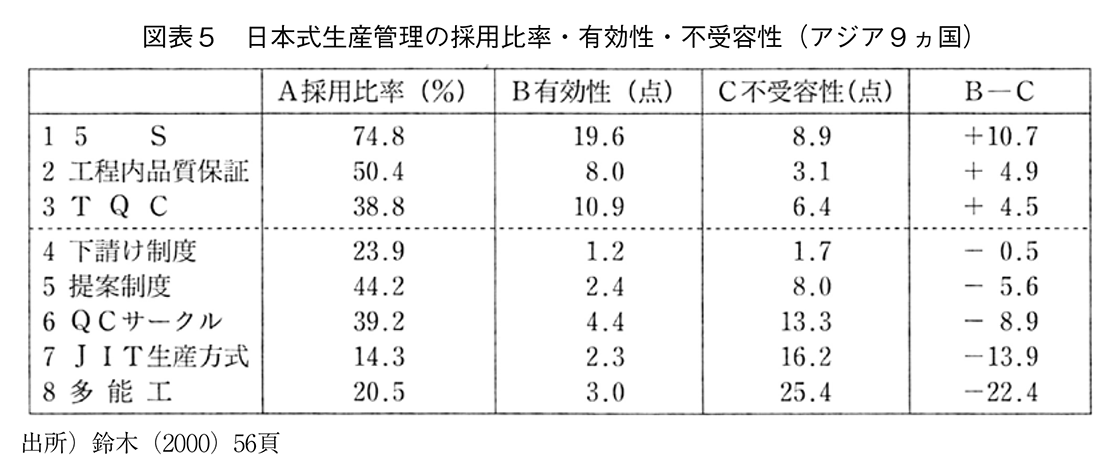
1.3.3 徳永・野村・平本(1991)の電子産業のグローバル化に関する研究
この研究は,日本の電子産業の企業に的を絞って80年代後半に行われたものである。より具体的には,日本企業2社のTV部門の海外生産拠点でインテンシブなヒアリング調査を行った。国としては,アメリカ,カナダ,イギリス,台湾,タイなど欧米諸国とアジア地域を含んでいる。
調査項目は(1)採用,退社,人員調整手段,(2)昇進,賃金制度(3)労使関係,(4)生産ラインについてである。彼らは,こうした項目で人事労務管理の主要な側面と生産方式の重要 【193頁】 な一論点を論じることができるとしている。その調査結果は,(1)賃金制度の複雑さ,(2)自動化職場におけるゆるやかな分業,(3)退社率の低さの3点が日本企業における制度,慣行,実践のうち海外子会社に移転できないものとして,抽出し,さらに,組み立て外注,社内資格制度もほとんど行われていないと論じている(徳永他(1991)94頁)。著者達は,アプリオリに日本的経営を規定するのではなく,賃金制度の複雑さなど上述の3点を海外に移転できない日本的経営の特徴と捉えた。現場観察に基づいて,政治,社会,文化条件の違いから,海外において受け入れられない日本企業の生産労務に関わる管理様式を日本的経営の神髄と捉えた,一つの極論的な議論を展開した。この段階で,彼らは日本的経営の要素で移転できるものはすでに移転されており,これ以上の移転は社会・文化的要因を考慮すると困難ではないかと展望している。
以上の3つの実証研究を通じて,労務面では,賃金体系の移植の難しさ,生産面では多能工化が困難であることが共通して浮かびあがる。日本的経営の海外移転は,時間の経過とともに進む要素もあるが,移転できない要素もあるように思われる。従って,各国の経営システムが同一のシステムとなる,つまり収斂するということはないだろうし,いかにある国で効率的な方式であっても,それが世界を覆いつくことはないと考えられる。と同時に,特殊日本的とみられる経営システムの中にも海外に通用するものもあると考えられるのでる。
1.3.4 最近の研究
90年代後半からの,日本経済と日本企業の不振によって,日本的経営の研究やその評価について大きな揺り戻しがあり,極端な表現をすると,国内外においてほとんど見向きもされなくなる状況に陥った。2000年代に入ると,アメリカ的な経営ガバナンスが評価されるようになった。日本的経営の欠点が強く主張され,むしろアメリカ的経営の導入こそが大事であるとの論調が支配的となった。
こうした中で,日本的経営を再評価する議論もあったが13) ,グローバル経営を進めるにあたって,日本的人事制度に対する批判が強く展開された。桑名他(2019)はグローバル経営のもとでの日本的人事制度を批判し,問題が多いとした。グローバルな人材のスキルや能力などを的確に評価して,それに基づく適正な処遇ができていないとみている。日本的経営を海外移転するのではなく,逆に欧米のグローバル企業の能力主義ベースの人事制度を日本企業に取り入れるべきだということであろう。
また百貨店業界を対象として,日本の雇用慣行と英国の雇用慣行について比較調査を行った結果,両者は収斂していないと,佐野(2021)は論じている。佐野によると,80年代から90年代にかけて両国の制度は,日本企業に接近する形で収斂する方向に動いたが,それ以上には進まず,現時点でも人事管理制度の全体システムとしては明らかに違いが認められると,結論付けている。
【194頁】1.4 小括
80年代から90年代にかけて行われた日本的経営・生産システムに関する実証調査は,程度の差はあれ世界各国の生産工場で日本的経営の移転が進められたことを確認している。それ以前の時期には,海外への移転は無理なのでないかとの認識が支配していた14) が,必ずしもそうではなかったのである。ただし,こうした実証研究を振り返ると,日本的経営・生産システムが全面的に,修正を加えることなく移転されることはなく,現地の社会・文化・政府の政策に応じて,ある程度改変されつつ,導入が図られたことを示している。それは日本企業の労務・生産管理上の慣行や仕組みの優位性を前提に意図的になされたものであり,その優位性を内部化することのコストが低い場合に実行されたと言えよう。そうしたハイブリッド化の実態が明らかにされ,そしてそれを推奨するものでもあった。
従って,日本的経営の良さがいくら喧伝されても,日本的経営そのものが世界を覆いつくすことはなかった。その理由として,国・地域ごとの価値観の相違,何を正当な制度や慣行とみなすか,の根本のところは,長い年月を経ても変わらない部分があることが挙げられるだろう。ある国の経営・生産システムが格段に効率的に劣後していれば,それは淘汰されてしまうと思われるが,大抵の場合はそうではない。多様な制度が互いにそれぞれの良さを取り入れつつ,修正を加えながら併存するのであろう。製造業において日本的経営は海外にも大きな影響を及ぼし,移植されてきたと評価できよう。しかし,現時点において日本的経営の良さや強みとは何か,今一度問い直すことが求められているのではないだろうか。日本的経営の良さが,長期的処遇や柔軟な職場編成,幅広い職務経験にあるとすれば,それが通用する職場や産業の範囲は,製造業の衰退からして縮小しているかもしれないが,その神髄は業種を超えて今後とも通用する可能性もあると思われる。
確かに,日本企業の労働者の地道で,真面目な働き方,集団主義的な協調姿勢,他者との分担協力などは生産現場において高い効率性をもたらした。長期雇用や年功システムもそれなりに有効で,優れた雇用制度であったと思われる。しかし,一方において,現状を突破する革新的イノベーションを創出する人材の育成には必ずしも適していなかったとも考えられる。その意味では製造業を基盤とする日本的経営・生産システムの在り方には,現段階ではかつてほどの優位性は認められない。日本企業は,今,生産・労務管理面を超えた経営戦略面や研究開発面での新たな比較優位性の追求も必要なのかもしれない。日本的経営がもう一段高次の展開を遂げ,その海外移転が再び論じられる時代が来ることが期待される。
戦前の財閥がその起源とされるいわゆる「企業系列」については,太平洋戦争(終戦までは「大東亜戦争」)終了までの「軍国主義」体制維持を支えたとされる三井,三菱,住友などの旧財閥諸企業に対して,強い批判的な視線が注がれ,存在そのものが悪,あるいは悪を生じさせる原因という扱いがなされてきたと言われている。
一方,発刊にあたっては大変な注目を浴び,その原典版たる英語版は世界中で評価されたと 【195頁】 される,青木昌彦・小池和男・中谷巌「日本企業の経済学」TBSブリタニカ,1986.2では,いわゆる日本的経営を経済学者が経済分析的な目から解きほぐし,経営学者だけでは目が行かない(とされる)日本企業のさまざまな側面をとりあげて論評した。
ここでは,彼らのそこでの議論の中で,財務という観点から注目された
「企業集団」「企業グループ」,
および
「メインバンク(概念)」の変貌
について検討しなおしてみたい。
名著とされた同書も,発刊からすでに35年以上経過しており,そこでの議論は大きな見直しを必要としているのかもしれない。
2.1 「企業集団」「企業グループ」
現代の「企業集団」の定義は,
大企業によって構成される企業グループで,旧財閥系の三井グループ,三菱グループ,住友グループなどや旧富士銀行(芙蓉グループ),旧第一勧業銀行(第一勧業銀行グループ),旧三和銀行(三和グループ)など銀行を中心としたグループが代表例。「6大企業集団」と総称されることもある。旧財閥時代には統制機関として持株会社が存在したが,これは第2次世界大戦後から1997年に独占禁止法が改正されるまで禁止されていたため,代わってグループ内の金融機関が融資,株式保有などを通じて中心的な役割を果たしたり,グループ各社の社長会を設けていた。企業集団は原料,製品の相互販売や供給,巨大プロジェクトの推進などで利点をもつ。しかし2000年代に入って,それぞれグループの中核企業だった住友銀行とさくら銀行が合併して三井住友銀行が誕生したほか,富士銀行と第一勧業銀行,日本興業銀行が合併してみずほフィナンシャルグループが発足するなど,グループの垣根をこえた再編が進み始めた。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について
あるいは
日本には三井,三菱,住友,芙蓉,一勧,三和の6つの企業集団が存在する。さらに,この企業集団は2種類に大分される。戦前に解体された財閥が戦後再び結合したのが,三井,三菱,住友である。また,戦後様々な企業が集まってできたのが,芙蓉,一勧,三和である。前者,後者ともに,企業集団では株の持ち合い,月例の社長会開催など,結合関係が強く見られる。特に結合の強い企業集団では,互い違いに株を持ち合い,持ち株のマトリックスを形成する構図が見られる。戦後6大企業集団は,互いに垣根を作り,自分の集団内の企業の便宜を図ってきた。しかしバブル崩壊以降,各企業集団の中核である銀行業の,企業集団を超えた合併が繰り返された。また,株式持ち合いの解消がすすみ,企業集団の間にあった境界は徐々にあいまいになってきている。
出典 ASCII.jpデジタル用語辞典ASCII.jpデジタル用語辞典について
ということになる。
【196頁】ここで,前述の青木昌彦・小池和男・中谷巌「日本企業の経済学」TBSブリタニカ,1986.2では,次のような叙述がある(同書,pp.110-113)。
企業集団の発生とリスク分担
次に,さきほど銀行の株式保有という問題が出たんですが,企業集団の話をしてみたいと思います。つまり,なぜ株式の持合いという形でもって企業集団が出てくるかということですね。企業系列という場合に,いわゆる「六大企業集団」というものと,それから下請け企業を中心とした企業グループというものが二つありますけれども,まず最初に六大企業集団を中心とした問題を扱ってみたいと思います。
なぜ企業集団が発生したかということにかんしてですが,とくに一九六四~六五年頃の証券恐慌のときに株価が低落し,なかでも投資信託の経営が非常に困難になったときに,日本共同証券あるいは証券協同組合というような機関が設立され,それが株価を安定化させるために日銀金融の支援によって株式を買っていくわけですね。株式市場が落ち着いた後に,そういう証券協同組合の株が流動化されるわけですが,それは,ちょうど日本の資本市場が自由化される時期だった。
ちょうどOECD(経済協力開発機構)への加盟の時期にもあたっていましたが,資本取引などの規制を取り払わなければならない時期だった15)。そのときに日本の経営者は,外国の会社が株を買い占めて,いわゆる"乗っ取り"にくるのではないかということを非常に恐れて,お互いに株の持合いを図っていく16)。これがいわゆる「株主安定化工作」といわれているものですが,そういう名前からもわかりますように,企業集団における株式の持合いというのは,実は乗っ取りを防ぐための防壁として役立っているということが,非常に重要な機能としてあると思うんですね。
とくに日本の企業というのは,単に株主の利益だけではなくて,従業員とか,ほかのビジネス・パートナーとか,企業に関連あるいろいろな人たちの利益のバランスを図って運営していくわけですから,そのためには,あまりに極端な乗っ取りの危険ということがあって,株価ばかり気にして行動するようでは困るわけです。ですから,こういう企業集団という仕組みがつくりあげられることによって,企業の経営者はある程度乗っ取りから自由になって行動できたという側面があると思うんです。
しかし一方では,企業集団でもって,独占的な利益を上げているんではないかと言われますね。もう少しソフィストケートされた議論では,最近は企業集団が恒常的な取引を結ぶことによって情報費用を節約したり,それから繰り返し繰り返し取引を行なうごとに契約のやり直しをするというような,そういう取引の費用が,取引の恒常化によって節約できる。だから,企業集団が生まれたのだという説明がありますけれども,こういう情報コストの節約とか,取引コストの節約分が利潤として企業に帰属するんだとすると,「利潤最大化」の仮説と変わらないことになるんですが,はたしてそうなんだろうか,という問題ですね。
この点は,ケイブスと植草さんの研究があって,第二次世界大戦後では,企業集団の利潤は,独立系企業のそれと比べてみると,必ずしも高くないということがすでに十年ぐらい前に明ら 【197頁】 かにされています。今度われわれの共同研究のなかで,中谷さんがおやりになった研究は,それを一歩推し進めて実証されたということで,この中谷論文が発表されて以後,実は国の内外でたびたび引用され,非常に注目を浴びているわけです。
その内容は,ご本人がここにいらっしゃるので私が説明するのも変なんですが,かりにそういう利潤最大化の目的でもって企業集団がつくられているのだとすると,なぜ企業集団に入らない独立系の企業があるのかが説明できないということですね。実際には独立系の企業のなかに,非常に収益率も高く,成長率も高いところがある。このことを中谷さんは,実際に実証されたわけです。
そういう二つの種類の企業があるということになりますと,企業集団の形成は利潤最大化というような単一の動機だけではなくて,企業のパーソナリティ,企業の性格みたいなものを入れてこないと説明がつかないんではないか。中谷仮説は,企業集団に属している会社は,リスクをシェアする――企業集団の株の持合いというような形でもってリスクをお互いに分担し合うということで,長期的に収益率とか何かのブレを少なくするような仕組みとしてあるのではないか。
一方,企業集団に入っていない独立系の企業は,ある程度リスクを冒しても成長率を追求する,あるいは利益率を追求するわけですが,利益率といったスコアでいうと,むしろ企業集団よりはいいパフォーマンスを上げているけれども,その代わり,利益の振幅も高いということですね。もちろん,この場合,独立系企業と言っても,中谷さんのサンプルに入っているのは,東京証券取引所に上場されているような大企業の話ですが。
企業がリスクをシェアするという見解にかんしては,若干誤解も見受けられます。たとえば,日本の企業集団にかんして研究書をまとめられたエレノア・ハードレイ女史(日本占領時代のSCAP〈連合国最高司令官〉による財閥解体のときにGHQに所属して実際に財閥解体に携わった研究者)は,日本の企業集団については世界的な権威だと思いますけれども,彼女が中谷さんの論文をコメントして,高度成長の時代に経済成長を指導した大企業が,リスクを避けるというか,リスクをシェアしていたということは,直観的にそぐわないというような批判をしておられるわけです。
ここでは欠席裁判になりますけれども,私の考えでは,むしろリスクを分担するといいますか,シェアをするような社会的な仕組みをつくることによって,個々の企業はかえって自分の事業を積極的に大胆に展開できたというような側面があります。それからもう一つは,リスクがあったと言っても,一九五〇年代~六〇年代当時というのは,いろいろな技術の芽や何かでも,まだ西欧のモデルが存在していた。そういう意味で,将来どんなふうになるかということにかんしては,だいたい見通しがつくような時代であったということにも,私は注目する必要があるのではないかと思います。
このように,同書では
「企業系列という場合に,いわゆる「六大企業集団」というものと,それから下請け企業を中心とした企業グループというものが二つありますけれども,」と述べていて,現代の目からいうとそういう分類はいまひとつピンとこない気がする。
すなわち,現代においては「企業グループ」というと次のようになる。
【198頁】現代社会では,企業が孤立して存在することはなく,企業間においてさまざまな形での結合が行われている。とりわけ日本では企業間結合が広範囲に,そして密接に行われているが,これは,日本における取引全体に占める企業間取引のウェイトが高いことと密接な関連がある。企業は企業間取引を安定化,長期化させるために企業間結合を行うが,逆に企業間結合が広範囲に進められているために企業間取引が多くなるということにもなる。このような企業間結合の形態としては第1に企業系列,第2に企業集団があるが,これらを総称して企業グループという場合がある。
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版
あるいは
…そこで,株式会社が他の会社の株式を所有する方法を積み重ねることにより,多くの会社が一つのグループに統合されうる。日本では,三菱・三井等の銀行・商社系のいわゆる六大企業集団と,新日鉄・日立等独立系大企業グループとが企業グループの主要なものである。企業グループは,情報交換,投資の協力など経済発展にとって有益な役割を果たしうる反面,市場独占等によって競争政策に対する弊害,あるいは,安定株主工作によって証券市場に対する弊害をもたらすこと等が指摘されている。…
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版
すなわち,どうも「企業集団」と「企業グループ」の概念は誰にとっても共通な定義は存在してはいないように思われる。
ただ,このような中で前述の青木・中谷の主張に戻ると,やはり現代においても同様の現象はあるものと考えるのが妥当ではないか。もちろん三井・住友が「合併」したことでそれまでの「伝統的企業系列論」は変貌を余儀なくされていると思われるし,後述のように1999年のメガバンクの再編により,伝統的「六大企業集団」はみずほ,三井住友,三菱UFJの「3大(フィナンシャル)グループ」へと再編されている。これらの3大グループを,青木・中谷のように一つのミニ資本市場(後述),あるいはそこでのリスクシェアリング手段と見做すことは現代においてもやはり間違いとは言い切れないと思えるのである。
2.2 「メインバンク(概念)」の変貌
前述の青木昌彦・小池和男・中谷巌「日本企業の経済学」TBSブリタニカ,1986.2では,また次のような対談が収録されている(同書,pp.127-129)。
中谷:私は青木さんがおっしゃったことにだいたい賛成ですけれども,日本の銀行がとくに戦後からこの数年前までの段階で非常に大きな力を持っていたのは,銀行が財閥解体の対象にならなかったということがある。そのために,資金力が温存されたという面があるわけで,財閥のトップが持っていた株式が放出されたときに,銀行にかなりはめ込まれているんですね。
青木:ただ,当時は一時的ですけど,銀行の株式運用というのは五パーセントまでに制限されたんですよね。ところが,昭和五十三年の独占禁止法の改正で一〇パーセントまで緩和されるわけです。
【199頁】中谷:そういう規制はたしかにあったけれども,戦後の銀行が相対的には非常に大きな力を持つような客観的な情勢が存在したことは否定できない。その結果,一般企業は銀行を通じて金融を受けないと成長できないというような状況があった。問題は,そういう歴史的な事実を所与としたときに,ではどうやってその後の発展を経済合理的に説明できるかということになると思うんですね。
私は,都市銀行を中心とした企業集団の形成というのが非常に大きな役割を果たしたと思います。各企業集団には,都市銀行のほかに信託銀行や生命保険会社などの金融機関が参加していますが,それらと事業会社が一緒になって,ひとつの「ミニ資本市場」を作っているのですね。つまり,全体的な資本市場のなかで,ある程度オートノミー(自律性)を持ったそれぞれのグループ内の資本市場というのがあって,それがもちろん外部とまったく無関係ではないんだけれどもある程度の「遮断(インシュレーション)効果」というものを生みだしていた。
「ミニ資本市場」のなかでは,事業会社同士が株を持ち合ったり,金融機関同士あるいは金融機関と事業会社の相互株式持合いがあったり,かなり複雑な構造になっている。しかし,重要なことは,事業会社がいざというときにはいつもこの「ミニ資本市場」のなかで資金調達ができるという状況にあったことです。このことは,一般株主の発言力をある程度弱くする効果を作りだしたと考えることができます。
もう一つの側面は,乗っ取りをされないために株式を相互に持ち合うという側面です。しかし,いったい乗っ取りをだれが恐れたのかということですね。たとえば,アメリカの労働者は乗っ取りを恐れるかというと,無関心というか,オーナーがだれであってもかまわないという考えがあるわけですね。ところが日本人は,乗っ取りについては,もう生命を失うがごとく感じてしまうわけです17)。
この一事を見ても,第1部の「労働」の議論のところであまり明らかにされなかった点だったんですけれども,やはり「企業はだれのものか」というような問題がどうしても出てきてしまう。そこのところで資本市場の不完全性というものと,いわゆる日本的経営というものとの相互関連性が出てくるのではないかというのが,私の感じです。結局,グループ企業同士,あるいは銀行もふくめて,お互いに大株主だということは,それ以外の一般の株主の影響力を排除するのに非常に有効なシステムですよ。
ですから,日本的経営を論ずるときに,労働市場の問題と同時に,資本市場の仕組みという問題をどうしても無視することができない。個人はキャピタル・マーケットで,自分のポートフォリオを多様化する代わりに,企業が代わりにリスクを分散するような形の行動をとるというわけです。このような企業行動は,新古典派的な理論ではうまく説明できない。企業に張り付いている経営者や労働者のリスク態度が,企業経営に反映されていると考えざるを得ないのではないでしょうか。
この議論でやはり重要な役割を指摘されているメインバンクというのは,基本的に次のよう 【200頁】 な定義である18)。
企業が取引している銀行の中で,借入額が最も多く,給与振り込みをしているなど,企業が主力としている銀行のことをメインバンクと呼ぶ。メインバンクにあたる銀行は,その企業の大株主であることが多く,企業の最大の債権者であり,大株主でもあると言える。そして,融資をするだけでなく,他の取引金融機関よりも企業の内部情報を豊富に保有する他,長期的かつ安全に取引ができるため,企業の経営状態を常に監視し,危機に陥った際の資金援助を中心に,経営改革の支援を行う。
このような定義は1990年代初旬のバブル経済の破裂で完全に吹っ飛び,それ以降メインバンクの立場は大幅に変わらざるを得なかった。
すなわち,メインバンク制の大きな転機となったのが,バブル経済破裂後に全国の銀行で相次いだ金融不安だったのである。バブル経済の破裂によって銀行は莫大な不良債権を抱え,それに続く景気の低迷による資金需要の低下によって,都市銀行の財務状況は一変してひどく悪化したのであった。
さらに,それまで競合していた都市銀行同士の経営統合が1999年から2002年にかけて,相次いで発表されたことで,日本的経営をいわば屋台骨として支えていたメインバンク制は解消の動きを見せていったという主張も多いのである。
ただし中小企業では新規資金調達・起債などによる方法は困難なことに変わりはなく,多くの中小企業は「主取引銀行(メインバンク)」を持たざるを得なくなっていることには変わりはないとされている。
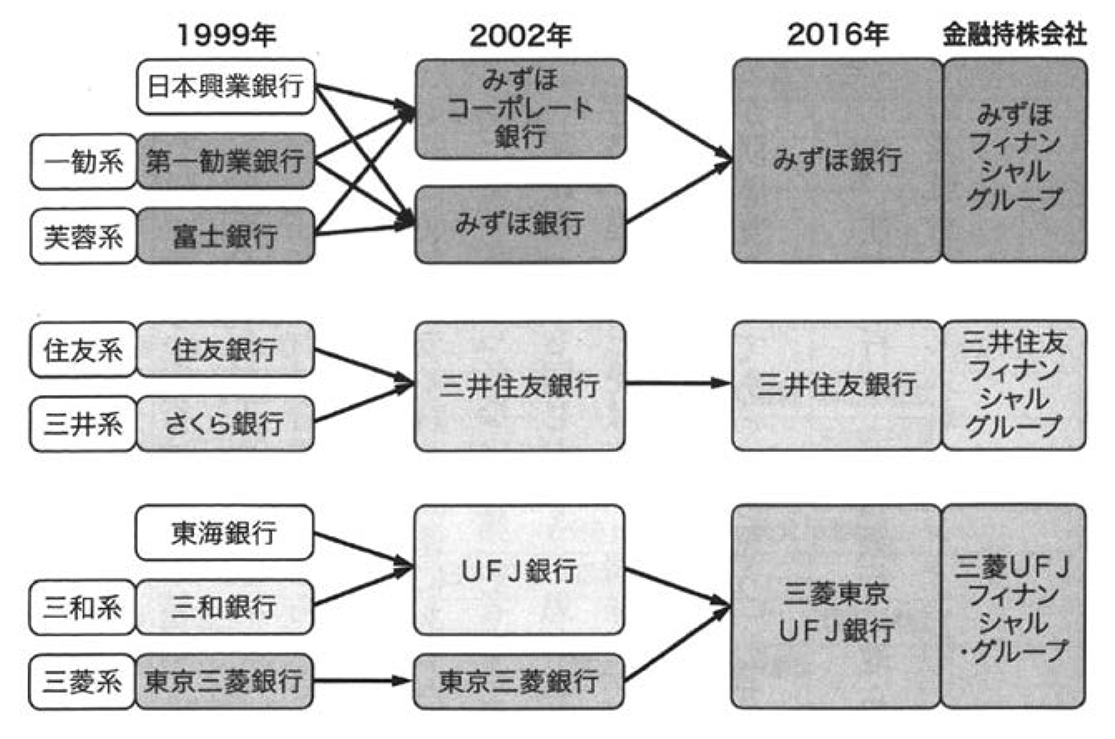 【201頁】
【201頁】
メガバンクの再編 リベラルアーツガイド【メインバンク制とは】2020年10月5日/2021年4月29日 による。
青木・中谷が「ミニ資本市場」とよぶ制度は,確かに今も存在してはいるものとは思われる。ただ,金融自由化がこれに大きな影響を与えたと言われている。すなわち,金融自由化とは金融の制度や仕組みに係る規制を緩和・撤廃し,業務を自由に行えるようにすることをいう。つまり,政府によって管理されている金利,業務分野,金融商品など,金融制度にかかわる規制の緩和や撤廃を実現した改革である。銀行,証券,保険などの壁をうち破り,「フェア」「フリー」「グローバル」の3原則に基づいて,東京市場をニューヨークやロンドンのような国際市場に確立させる目的で,1996年(平成8年)に提唱された「金融ビッグバン」が代表的な例で,金利の自由化や,金融機関の業務分野規制の緩和,国内外の資本取引の自由化などが実現されたのである。日本の場合,一般的には,1979年の譲渡性預金(CD)の認可が金融自由化の開始とされる。その後,1996年の金融ビッグバンにより,金融市場の活性化や国際化が進展した。2007年には日本の金融市場の競争力を一層強化するための「金融・資本市場競争力強化プラン」を金融庁が公表し,金融商品の多様化や規制緩和が進んだとされる。これによって,各金融機関同士で金利や各種手数料などの競争,独自のサービスが誕生して,消費者にとっても有利な面も増加し,選択肢の幅も広がったが,銀行において元本保証がないなど自己責任が伴うリスク商品が増加したのも金融自由化によるものである。
このような金融自由化によって,大企業では銀行を通さない直接金融による資金調達が容易となって,銀行依存の程度はいきおい弱まり,メインバンクとの取引関係も弱くなっていったとされる。一方の銀行にとってもバブル経済の破裂以後の不況の中で,グループ企業への大量融資のリスクもはっきりと認識することとなり,バブル経済以前のような企業⇔メインバンクという親密な関係は,従来のようには見られなくなっているとされるのである。
こうしてみると,青木・中谷が「ミニ資本市場」とよんでいた制度は,今も存在しているとしても,現代においてはもはや,それが高度成長期,バブル経済の頃のような大きな役割を果たしているかは定かとは言えないと思われることになる。
このように,青木昌彦・小池和男・中谷巌(1986)が世に出た後,この35年の間に企業集団の役割の変化は大きなものがあった,ということができると思われる。
それによって日本的経営がどう変わったのか,ということになると,明快な評価はむずかしいところであろう。敢えて言えば,なかなか難しいところだが,特に以前の「企業系列」が前述の通り再編成されて以来,共同体的意識,あるいは集団主義的側面は薄れていると言えるかもしれない。ただ,それでも今なお,日本企業にとっては,それらの「意識」は,依然として大事な役割を果たしていることは認識できると考えている。
参考文献
青木昌彦・小池和男・中谷巌(1986),『日本企業の経済学』 TBSブリタニカ
安保哲夫編著(1994),『日本的経営・生産システムとアメリカーシステムの国際移転とハイブリッド化』ミネルヴァ書房
安保哲夫・板垣博・上山邦雄・河村哲二・公文溥(1991),『アメリカに生きる日本的生産システム―現地工場の「適用」と「適応」―』東洋経済新報社
板垣博編著(1997),『日本的経営・生産システムと東アジア―台湾・韓国・中国におけるハイブリッ【202頁】ド工場―』ミネルヴァ書房
遠藤公嗣(1999),『日本の人事査定』ミネルヴァ書房
太田肇(2008),『日本的人事管理論―組織と個人の新しい関係―』中央経済社
公文溥・安保哲夫(2005),『日本型経営・生産システムとEU―ハイブリッド工場の比較分析』ミネルヴァ書房
桑名義晴・岸本寿生・今井雅和・竹之内秀行・山本崇雄(2019),『ケーススタディ グローバルHRM―日本企業の挑戦』中央経済社
小池和男(2005),『仕事の経済学(第3版)』東洋経済新報社
小池和男(2015),『日本企業は強みを捨てるのか―長期の競争vs.短期の競争―』東洋経済新報社
佐野嘉秀(2021),『英国の人事管理・日本の人事管理―日英百貨店の仕事と雇用システム―』東京大学出版会
鈴木滋(2000),『アジアにおける日系企業の経営』税務経理協会
鈴木良始(2009),「ものづくり論とアーキテクチャー論」(鈴木良始・那須野公人編著『日本のものづくりと経営学―現場からの考察―』第1章,ミネルヴァ書房)
手塚公登・小山明宏(2021a),「現代の「日本的経営」論(1)」(学習院大学『経済論集』58,2,pp.175-186)
手塚公登・小山明宏(2021b),「現代の「日本的経営」論(2)」(学習院大学『経済論集』58,3,pp.227-252)
手塚公登・小山明宏(2022a),「現代の「日本的経営」論(3)」(学習院大学『経済論集』58,4,pp.315-332)
徳永重良・野村正實・平本厚(1991),『日本企業・世界戦略と実践―電子産業のグローバル化と「日本的経営」―』同文舘
野村正實(2001),『知的熟練論批判―小池和男における理論と実証―』ミネルヴァ書房
萩原進(2017),「日本的経営の海外通用性」(社会志林,63,4,pp.133-160)
バンクマップ ホームメイト・リサーチ 【バンクマップ】金融自由化|金融用語集 (homemate-research-finance.com)
藤本隆宏(2004),『日本のもの造り哲学』日本経済新聞社
山﨑克維・銭佑錫・安保哲夫編著(2009),『ラテンアメリカにおける日本企業の経営』ミネルヴァ書房
谷内篤博(1999)「日本的雇用システムの特殊性と普遍性」(文京女子大学経営論集,9,1,pp.71-88)
リベラルアーツガイド(2021),【メインバンク制とは】2020年10月5日/2021年4月29日
Dore, Ronard (1973), British Factory-Japanese Factory :The Origins of National Diversity in Industrial Relations, University of California Press(ドーア,ロナルド(1993),『イギリスの工場・日本の工場(上)(下)』(山之内靖・永易浩一訳)筑摩書房)
Dunning, J.H.(1979), “Explaining Changing Patterns of International Production : In Defence of the Eclectic Theory,” Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 41, pp.269-295.