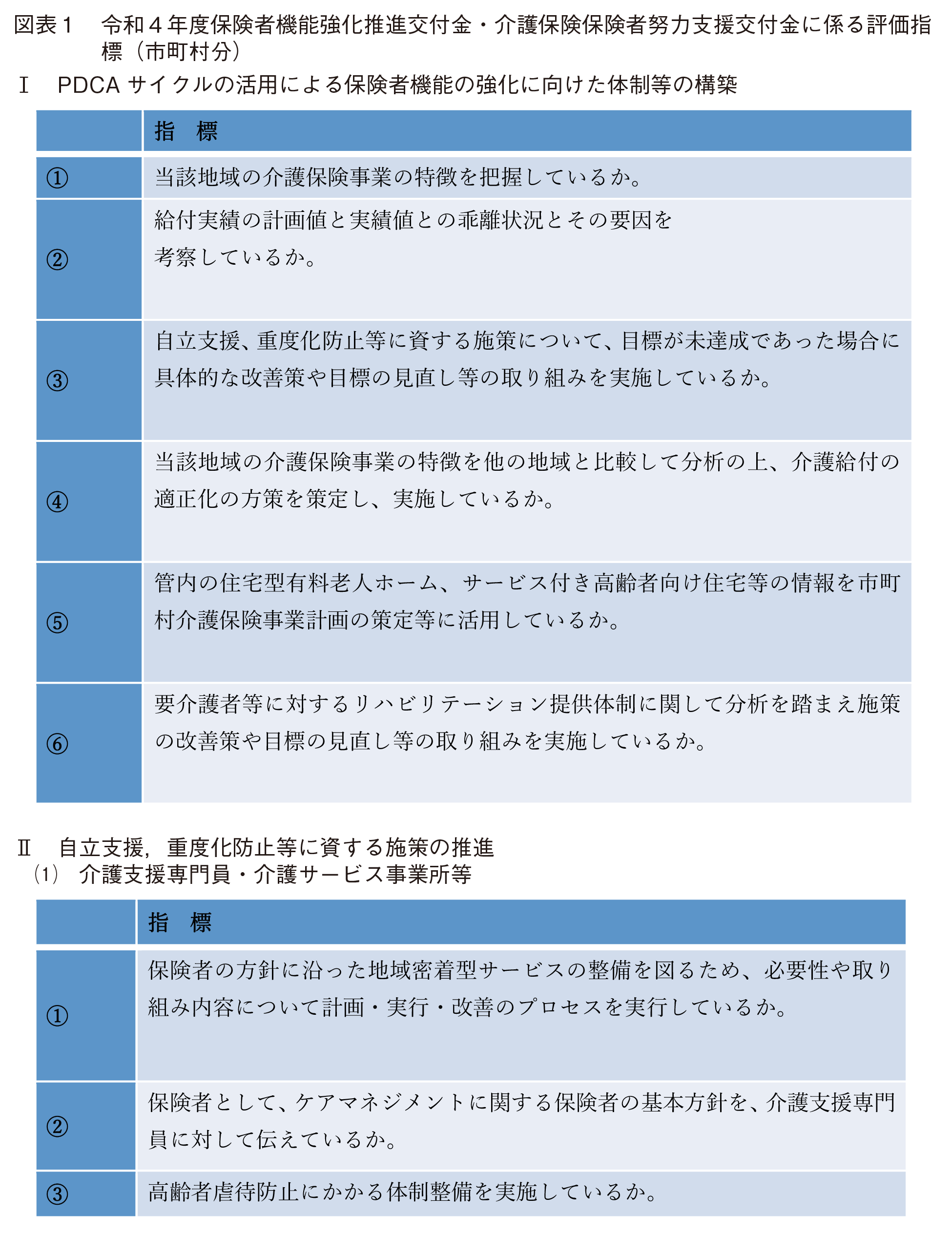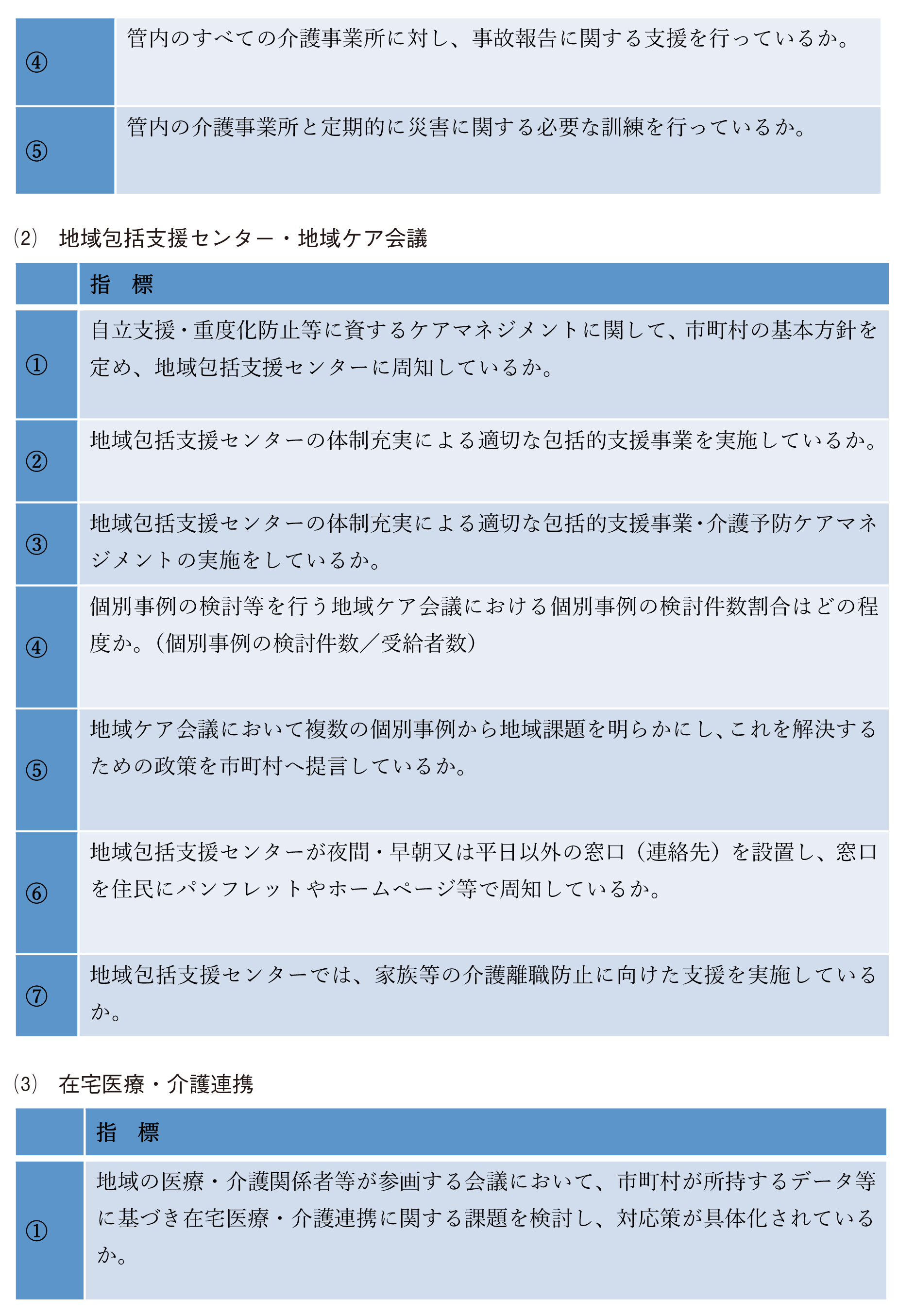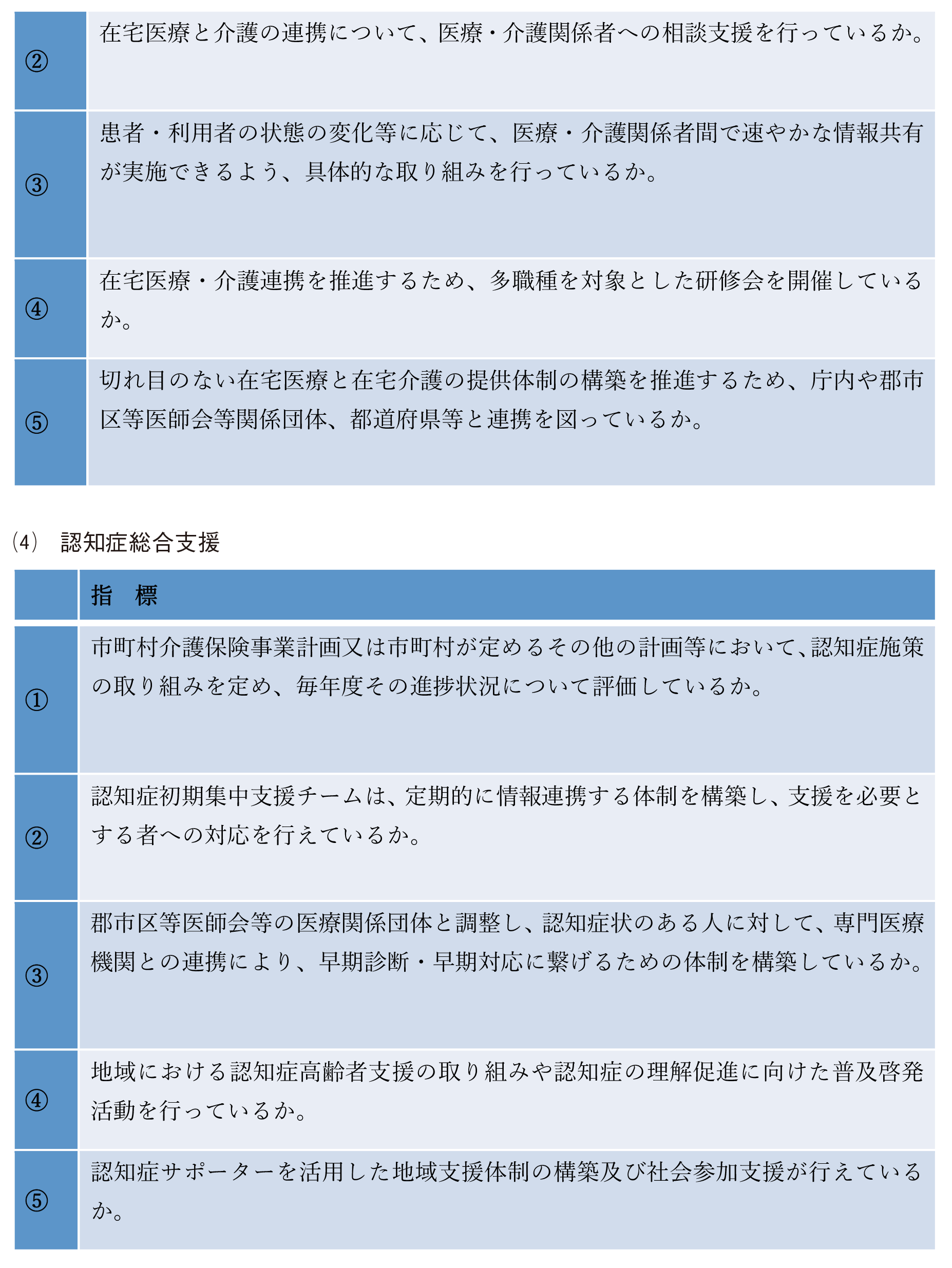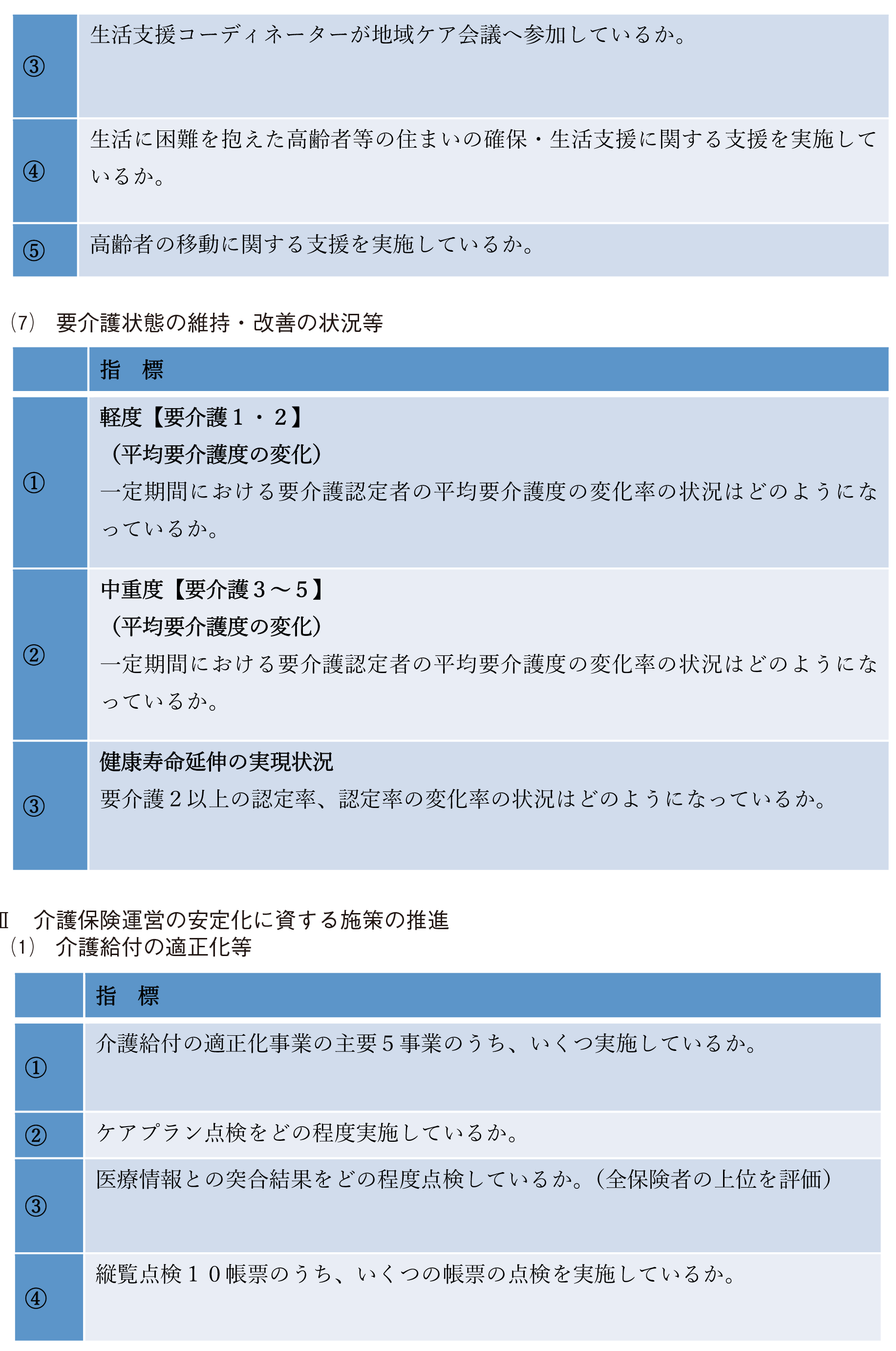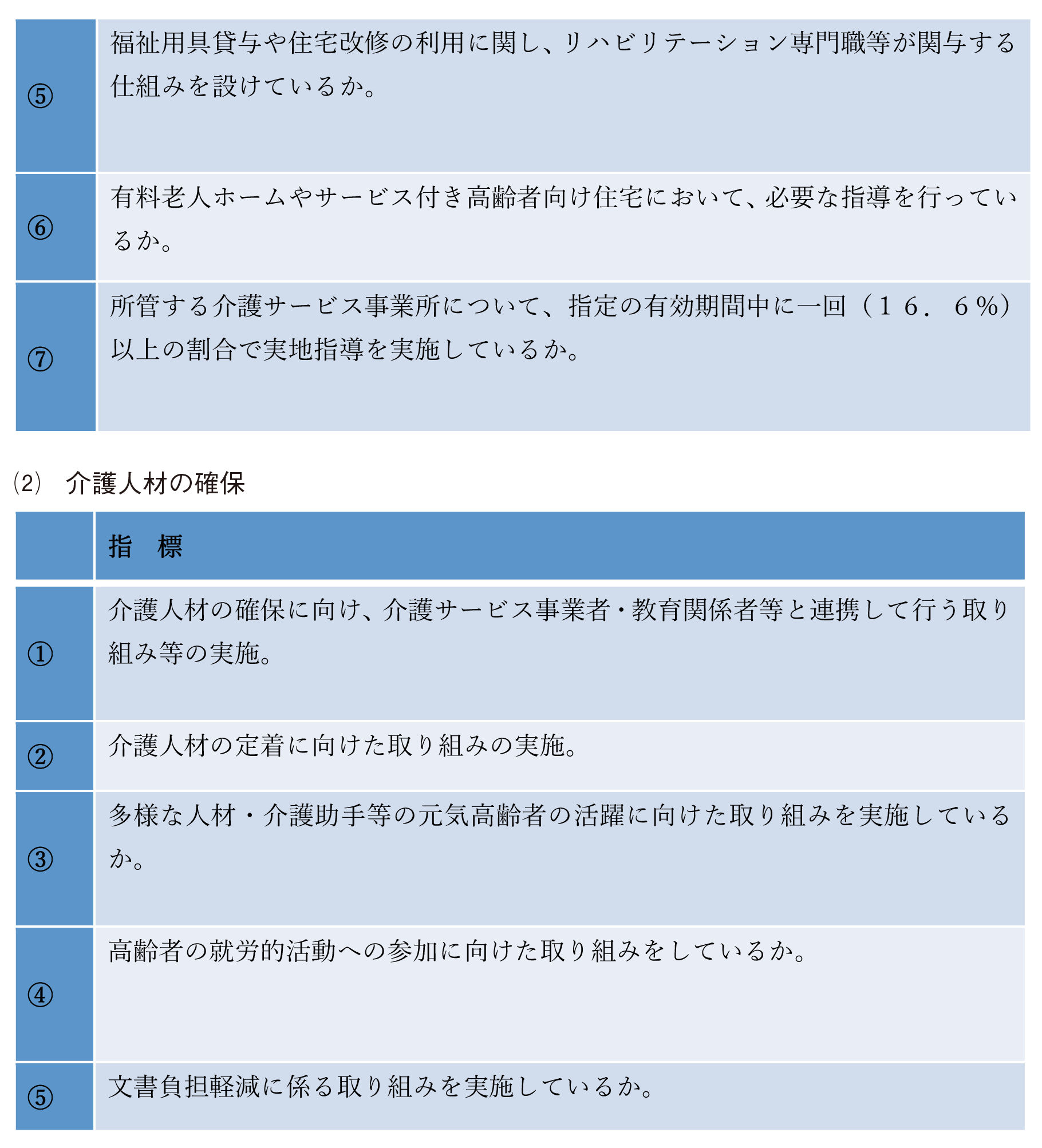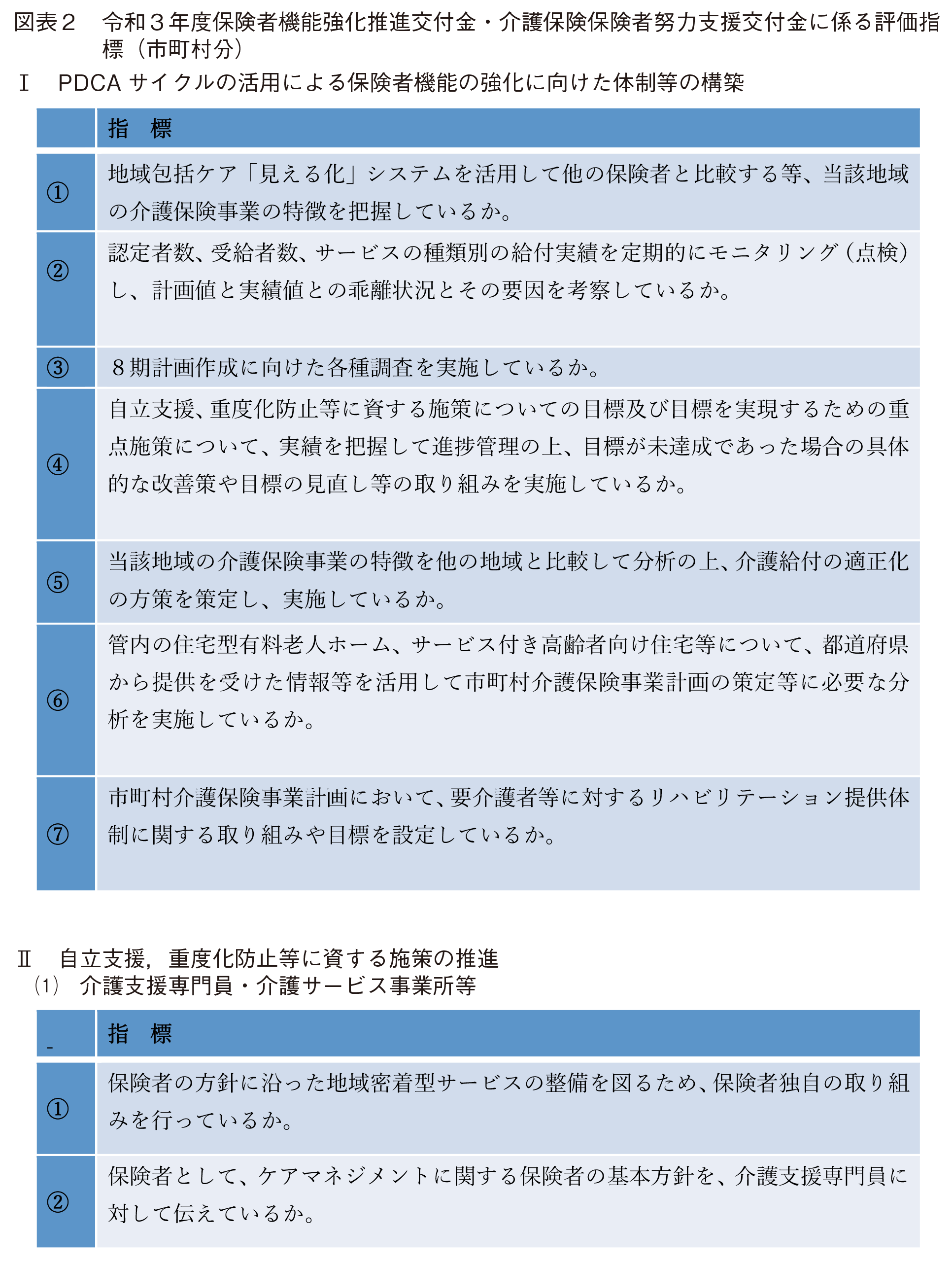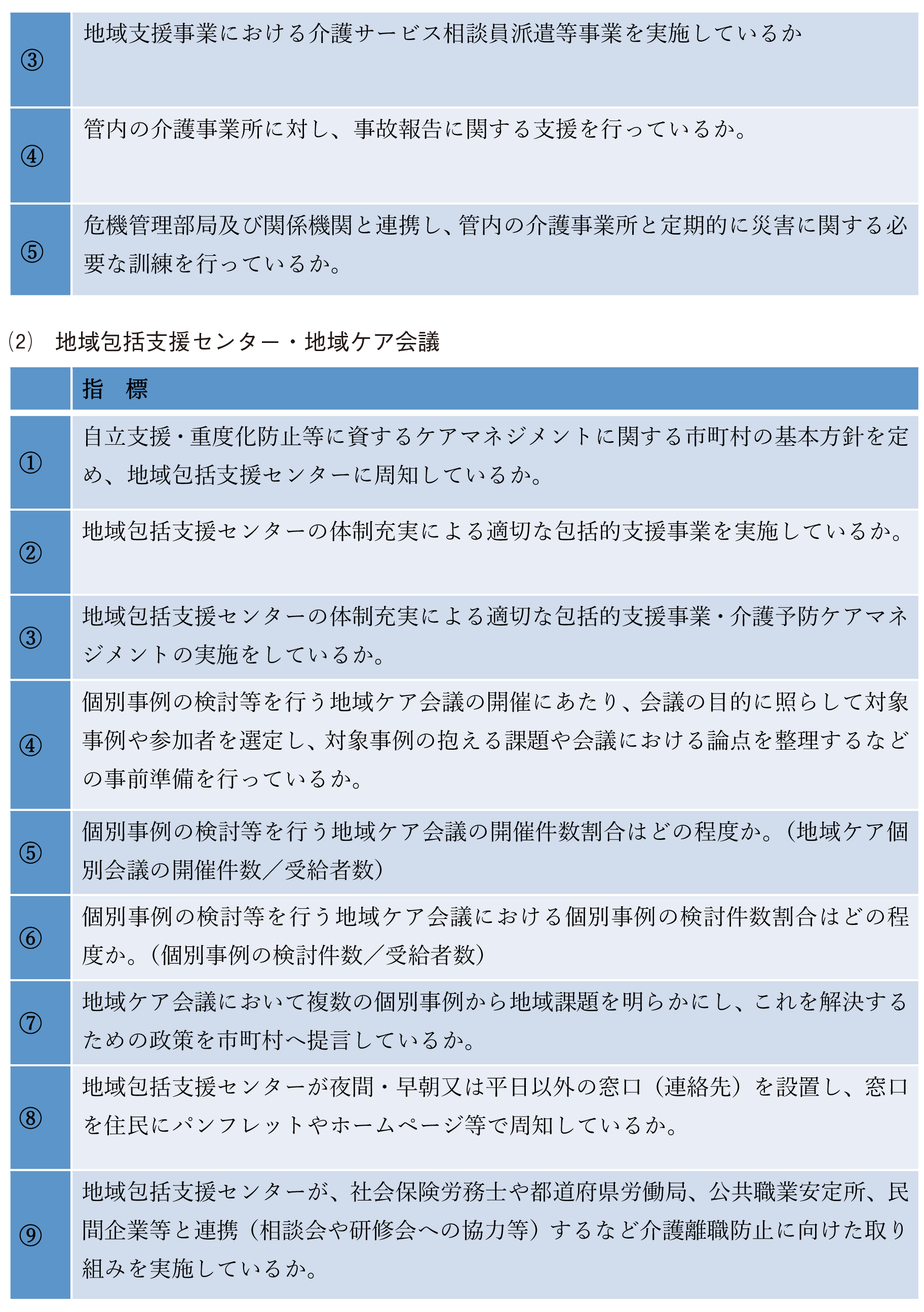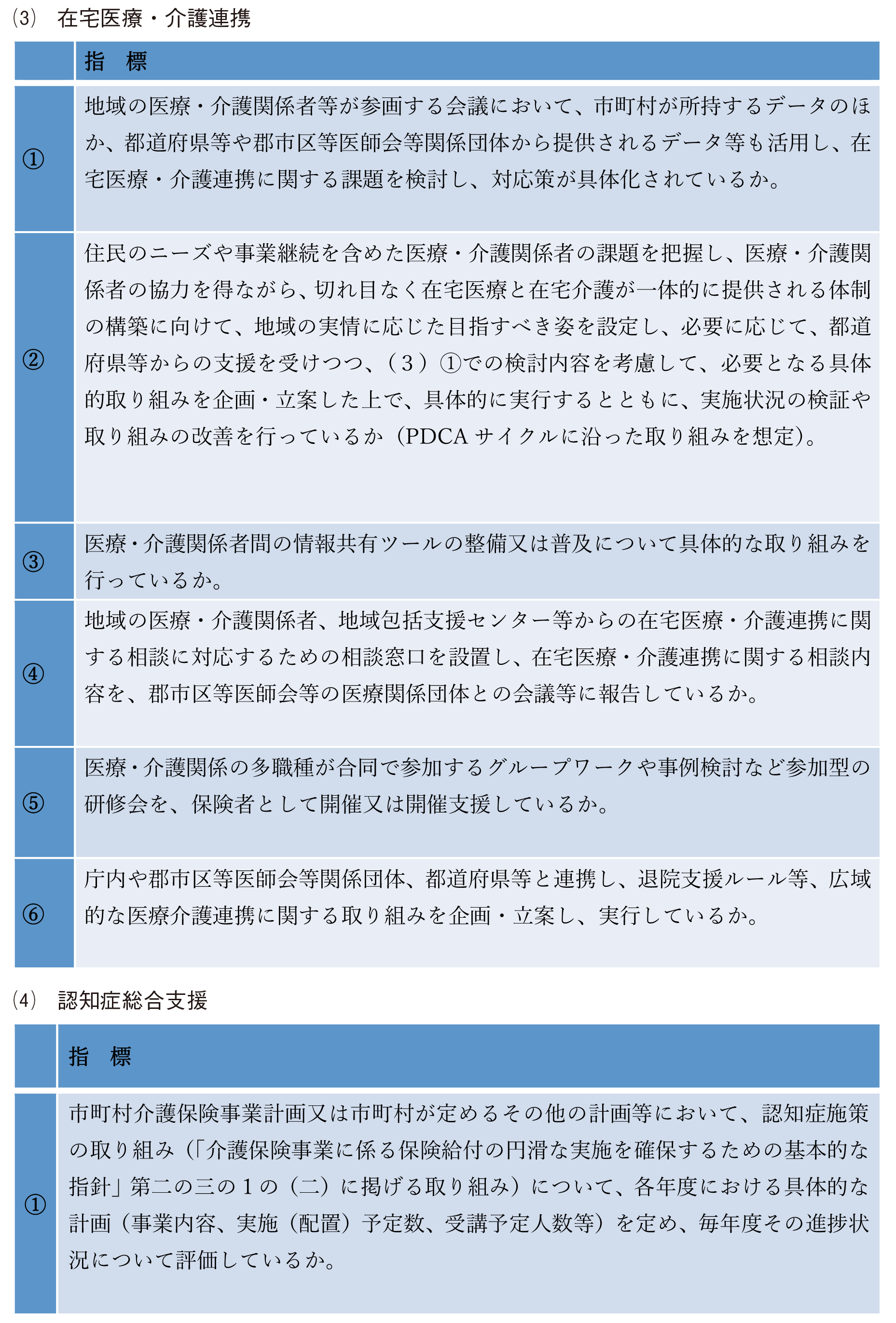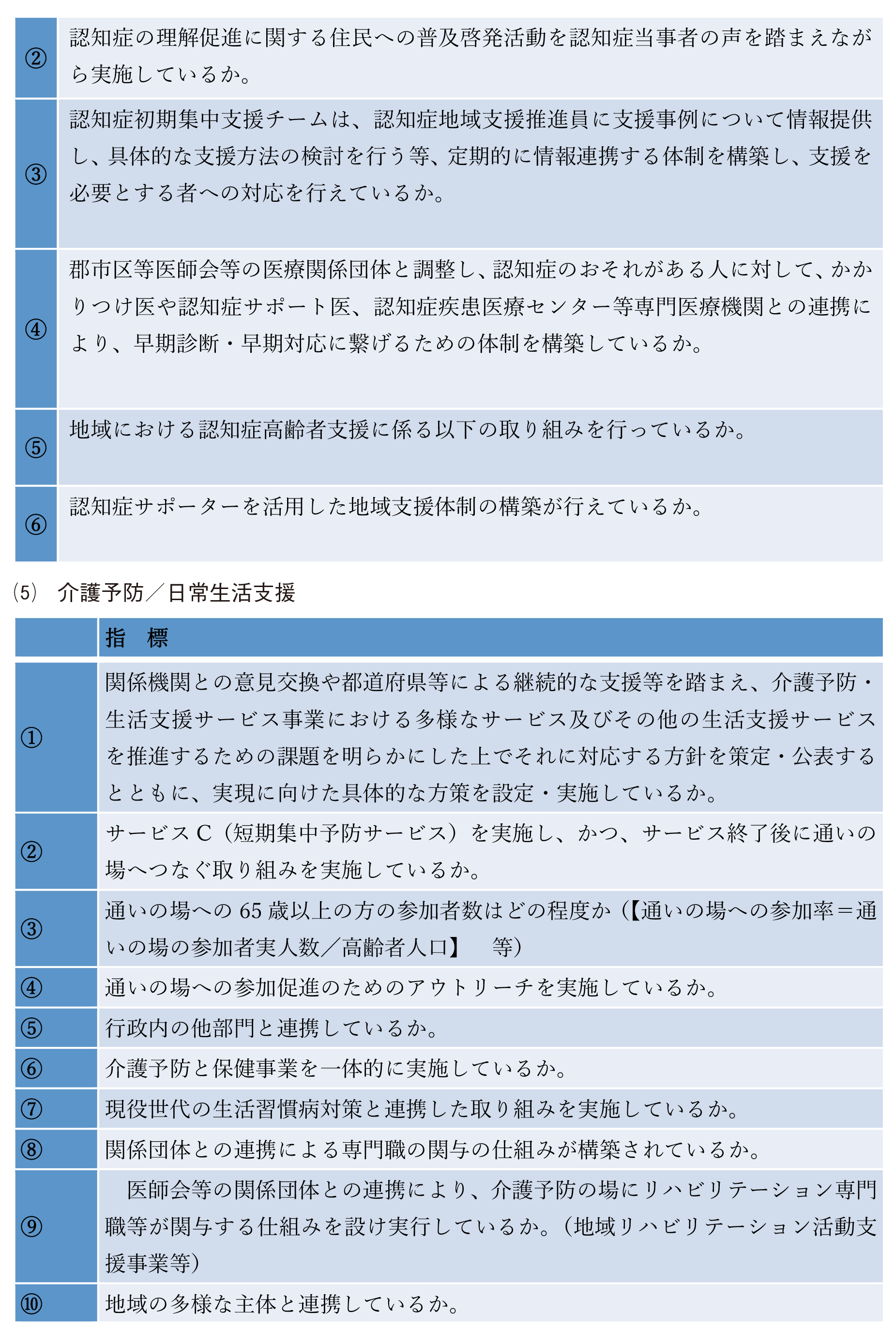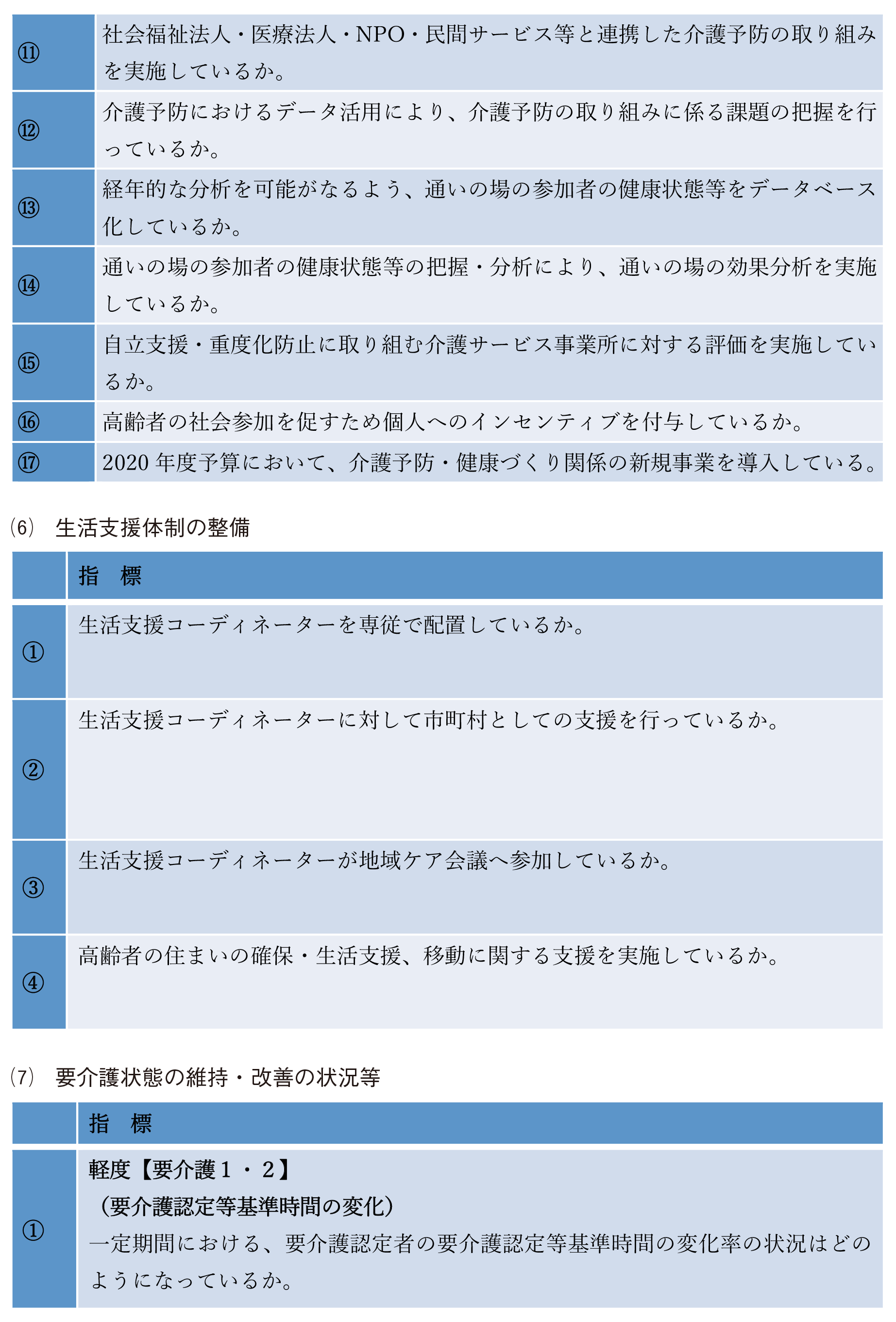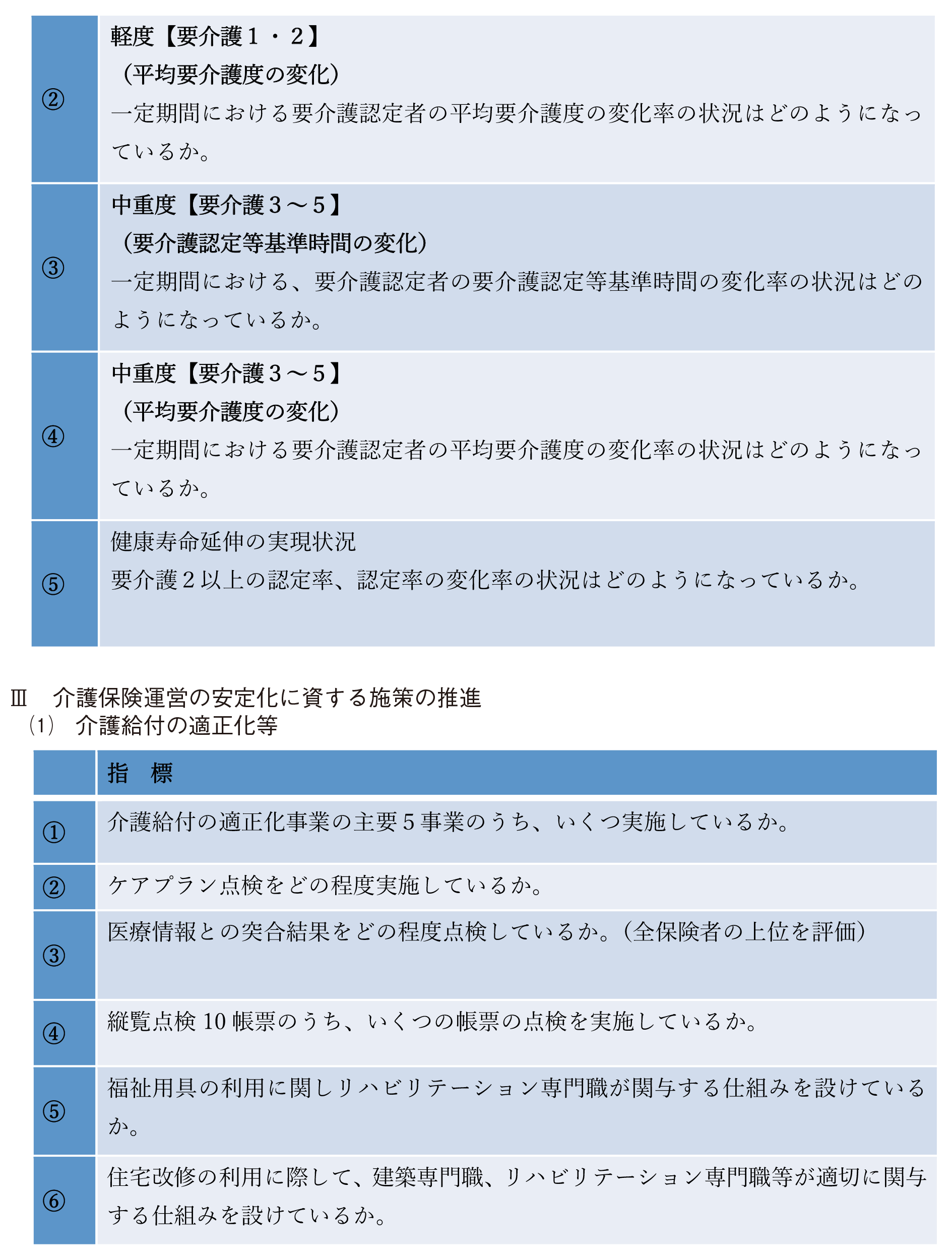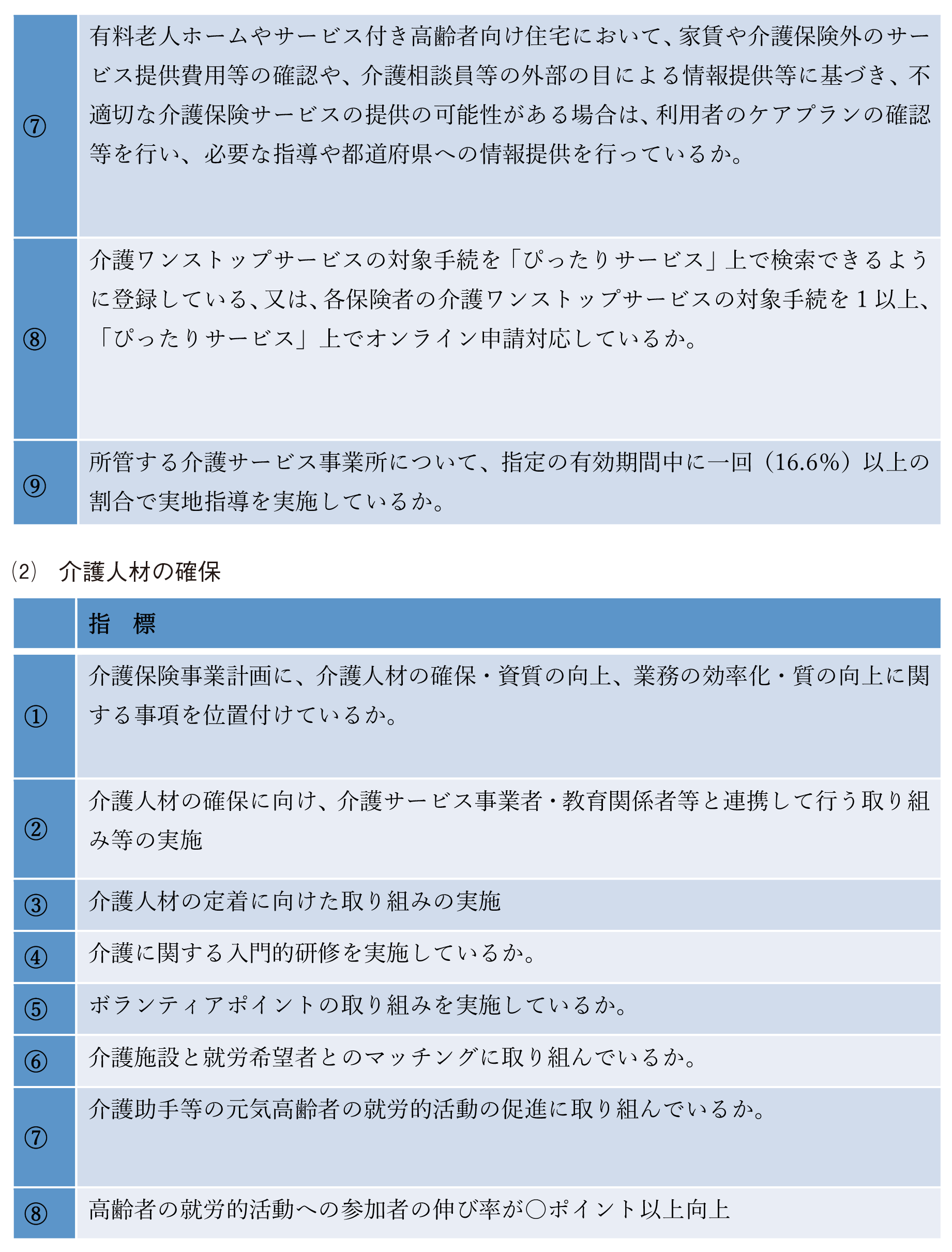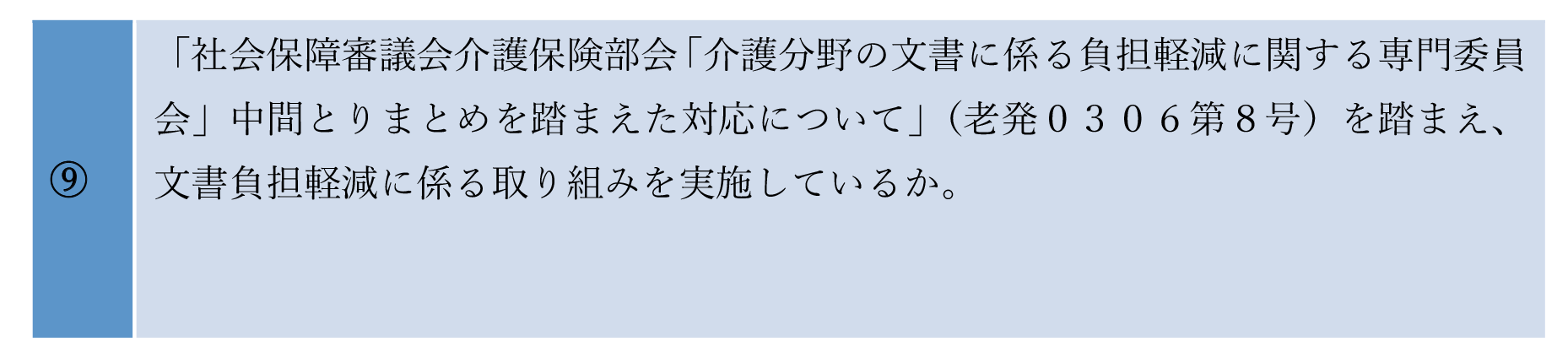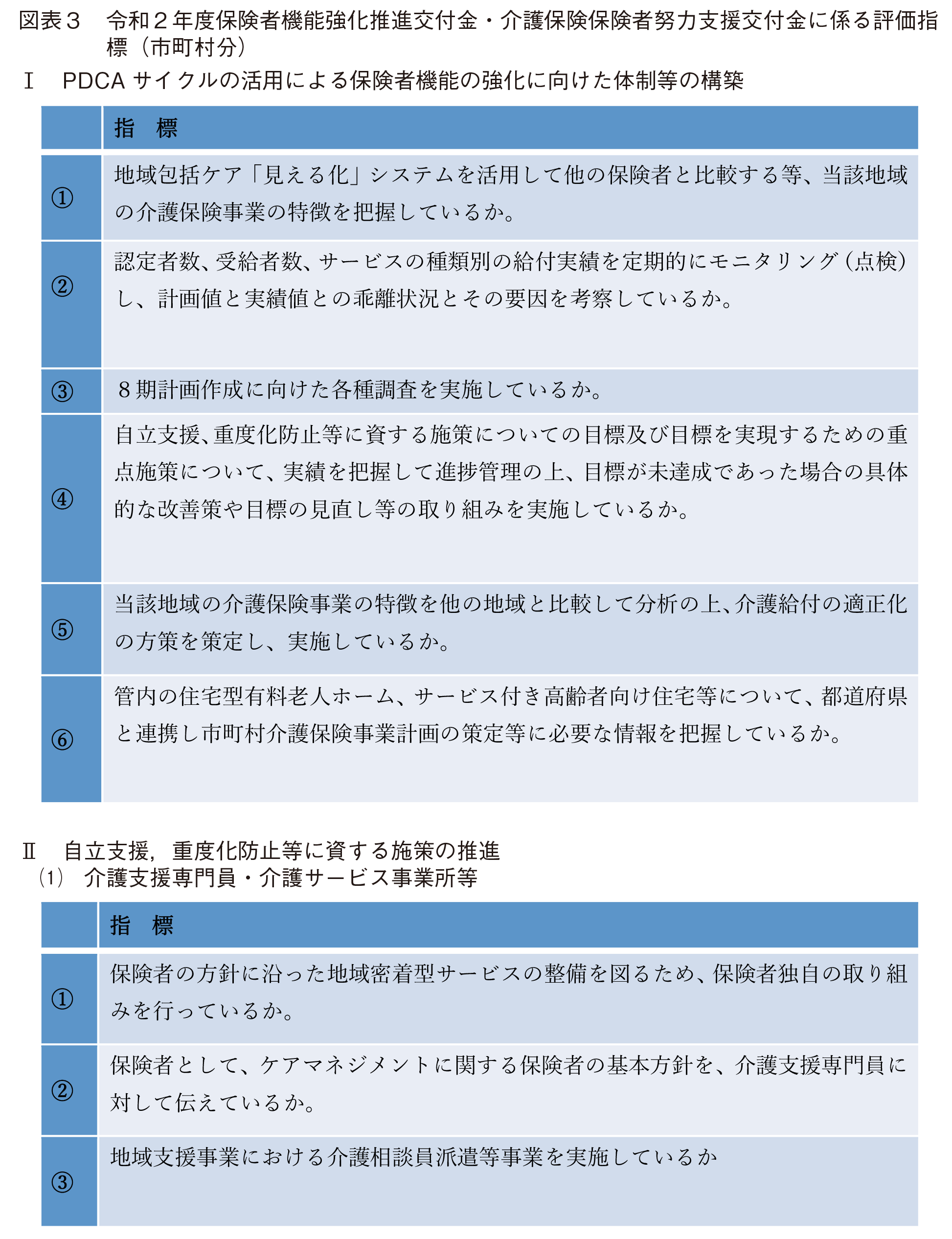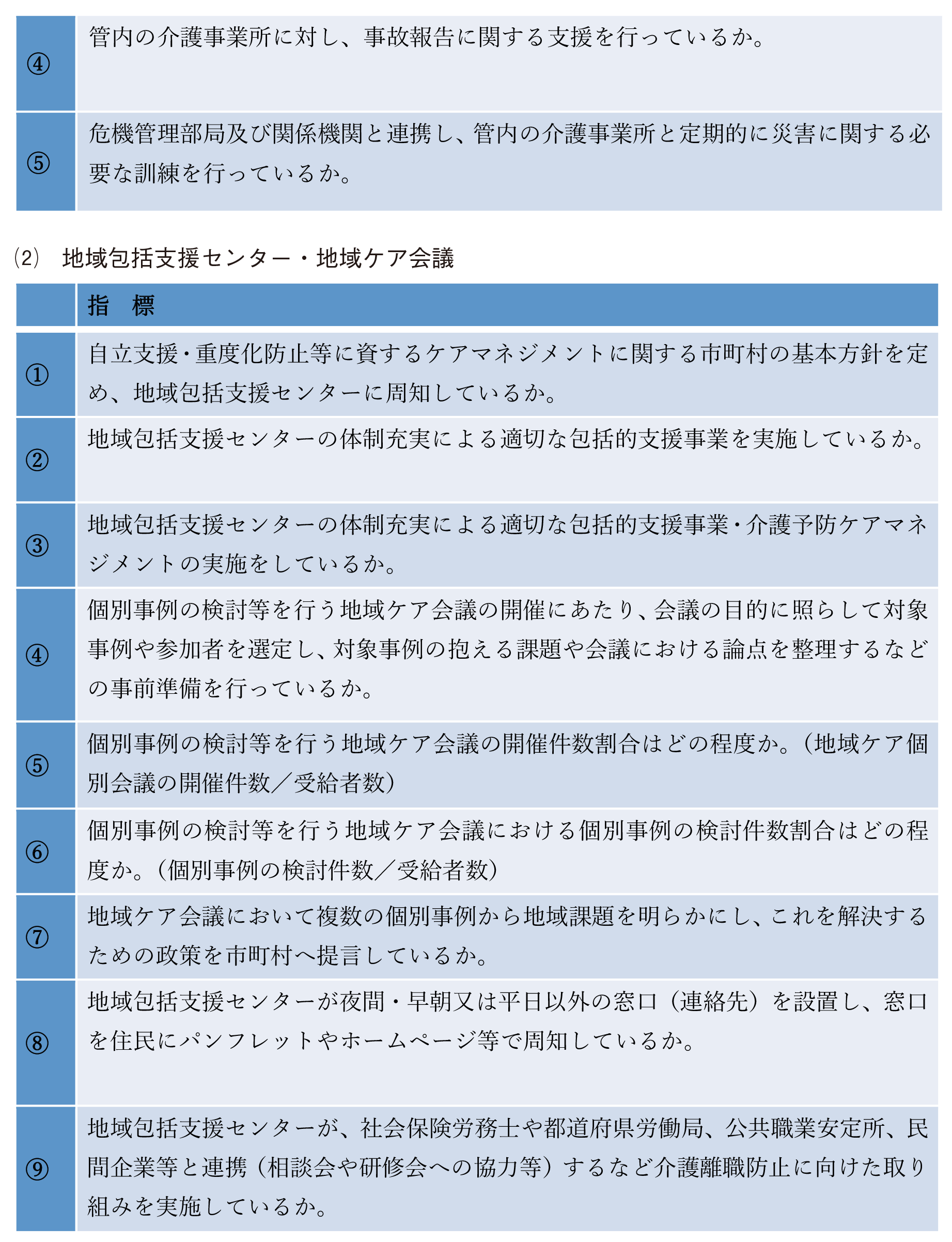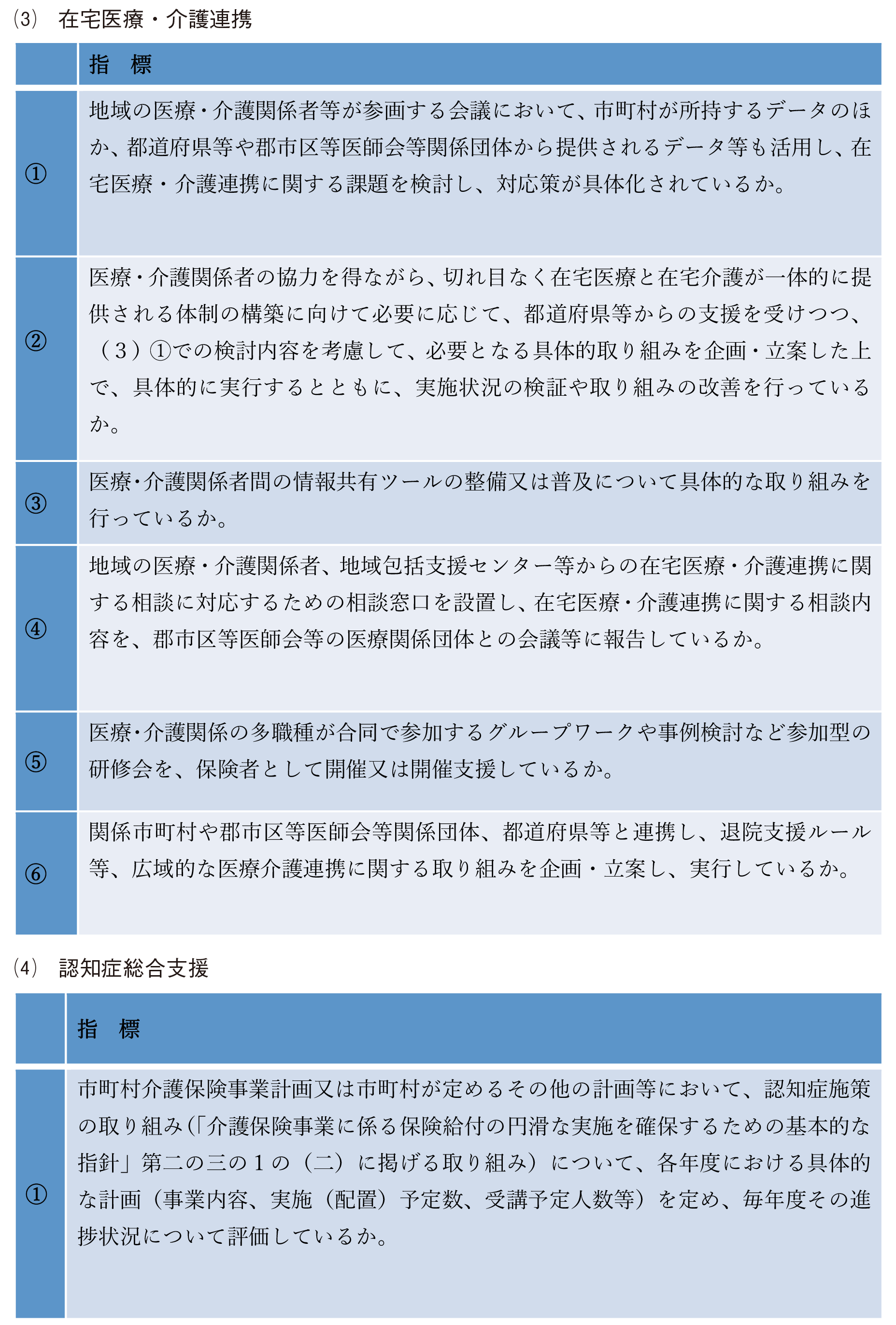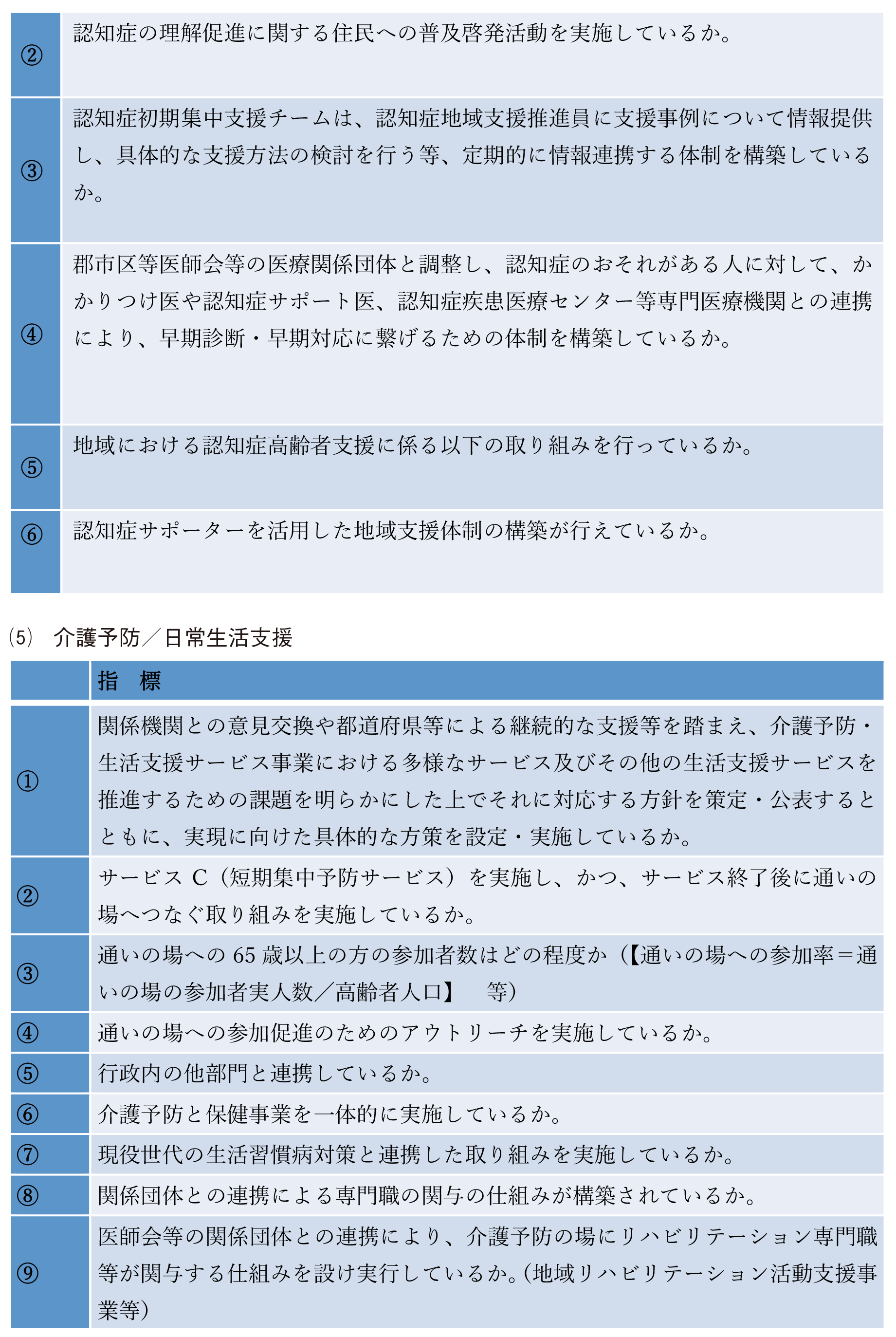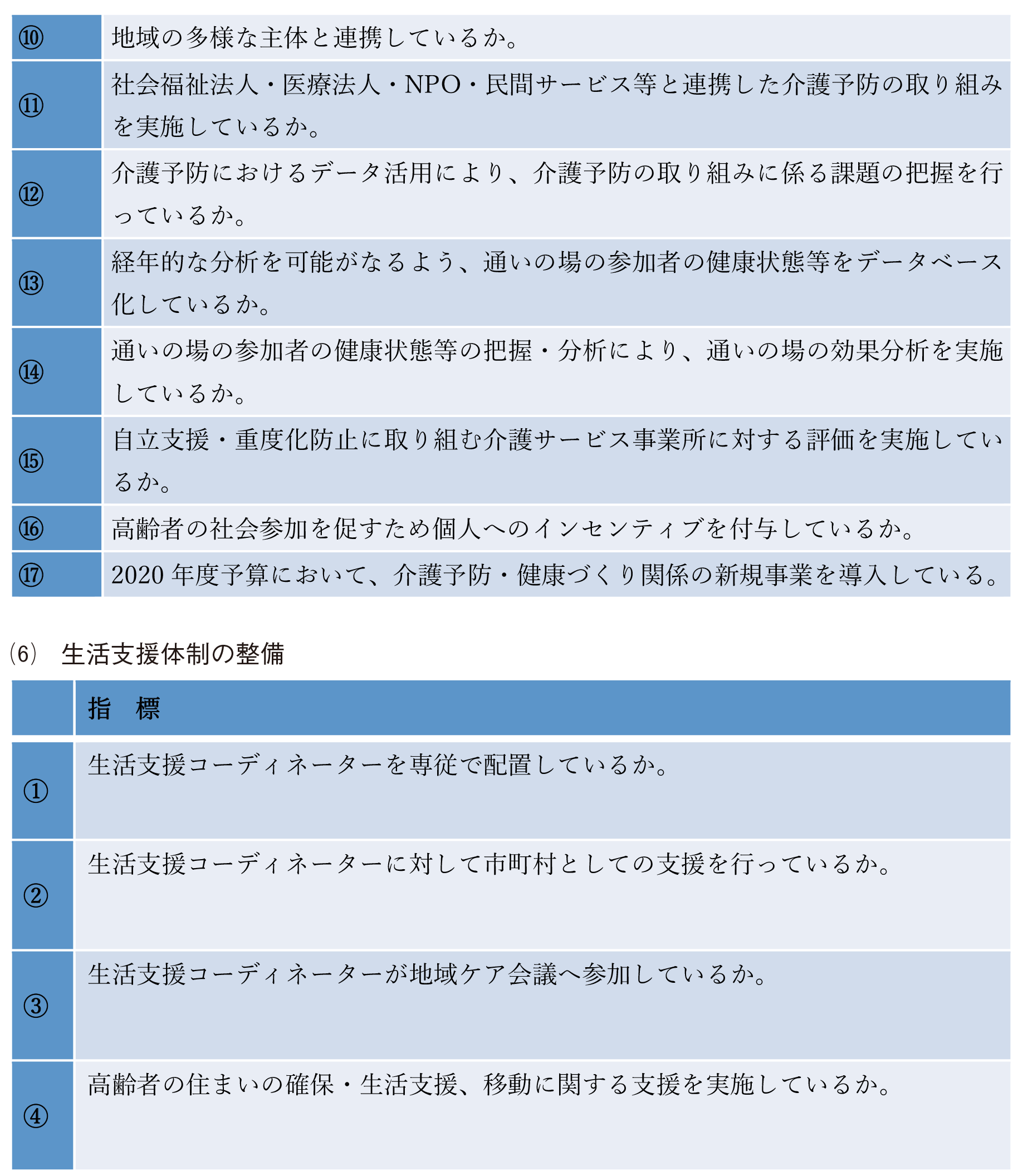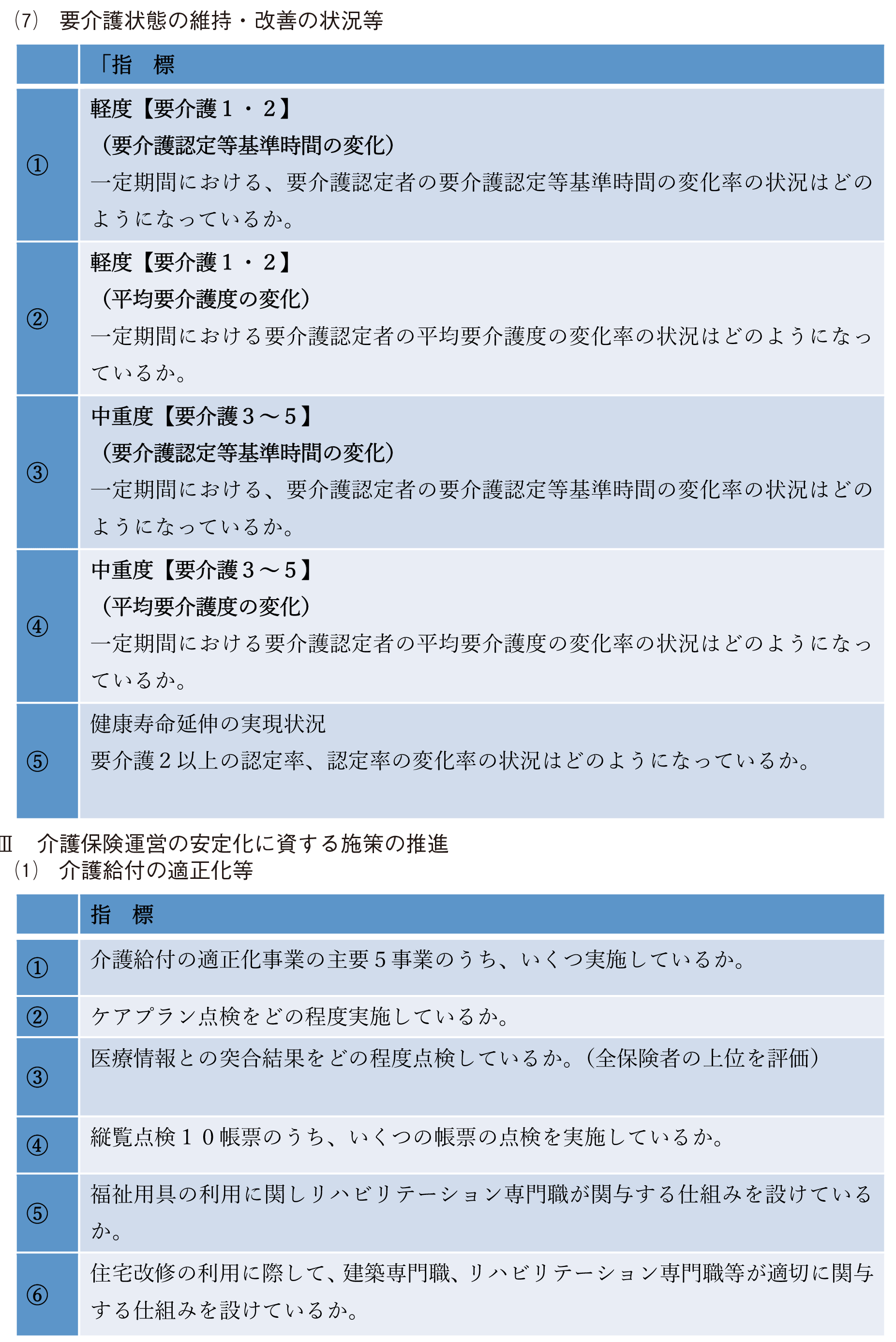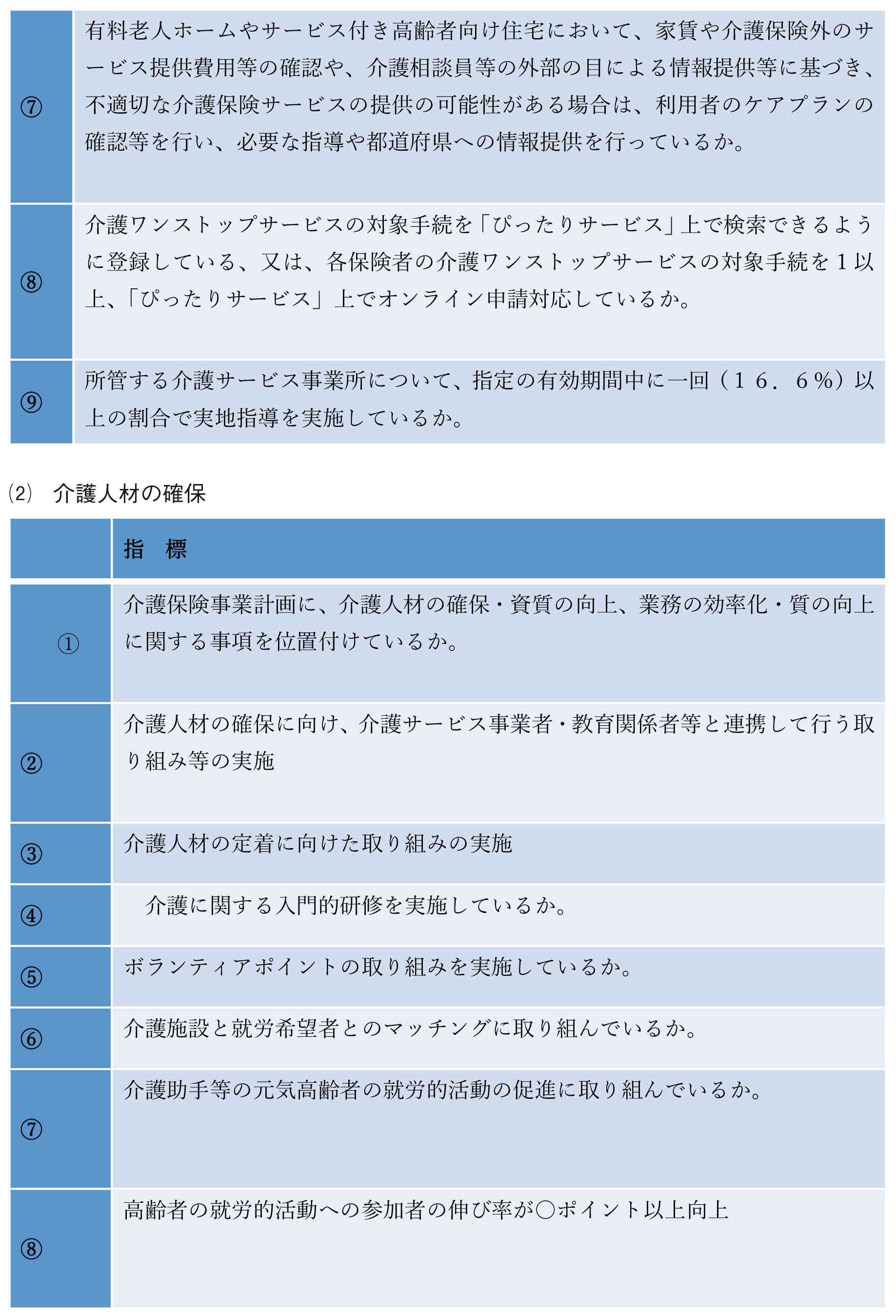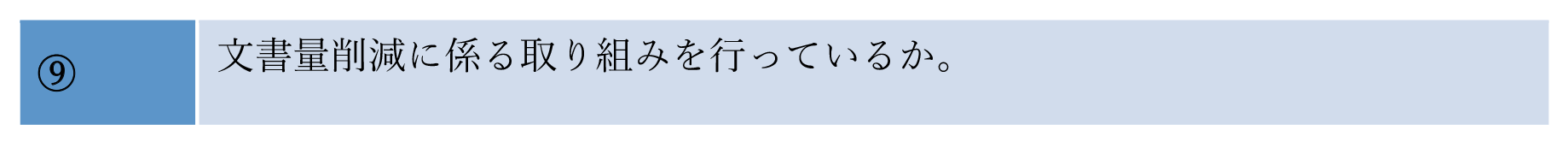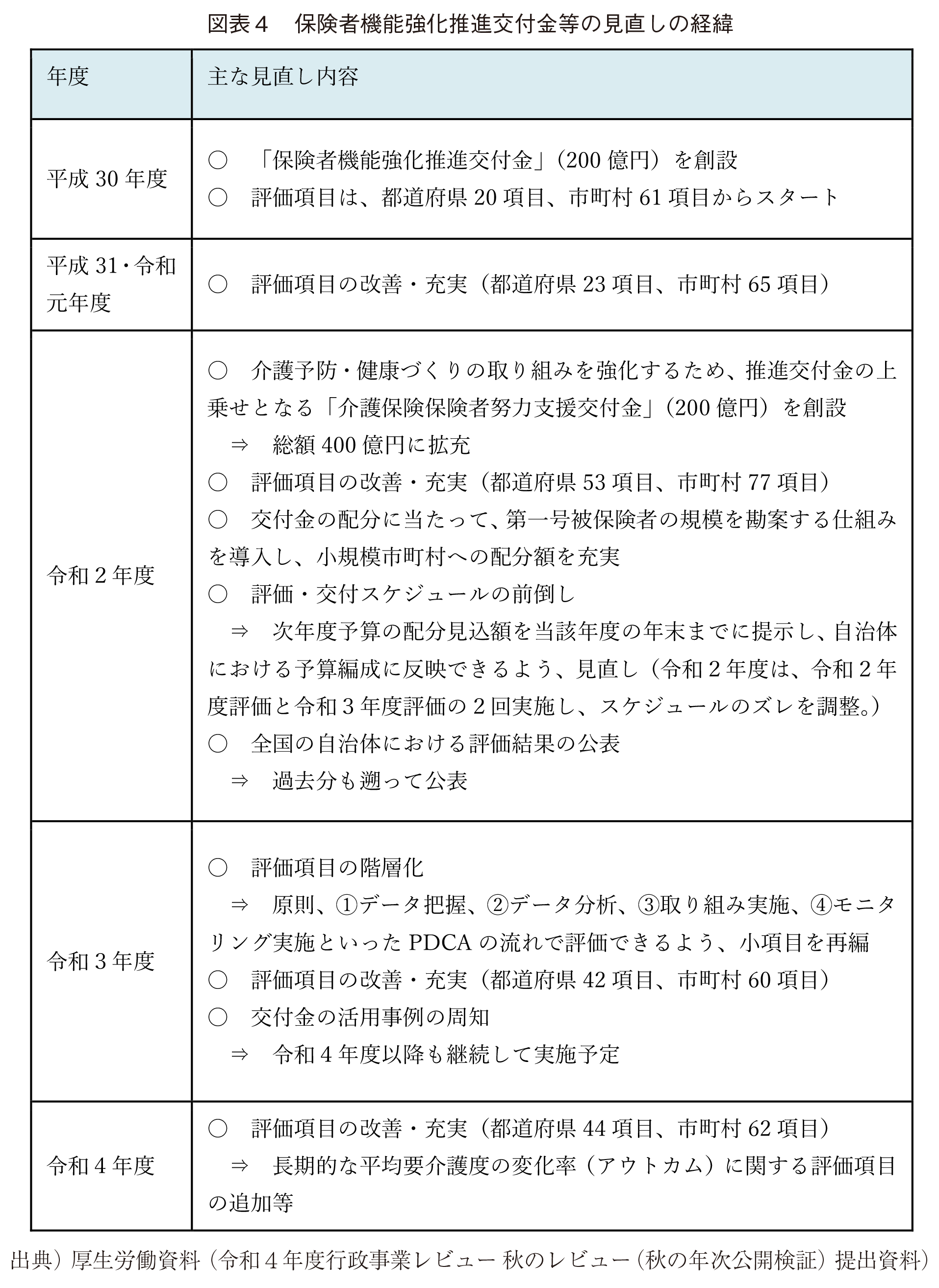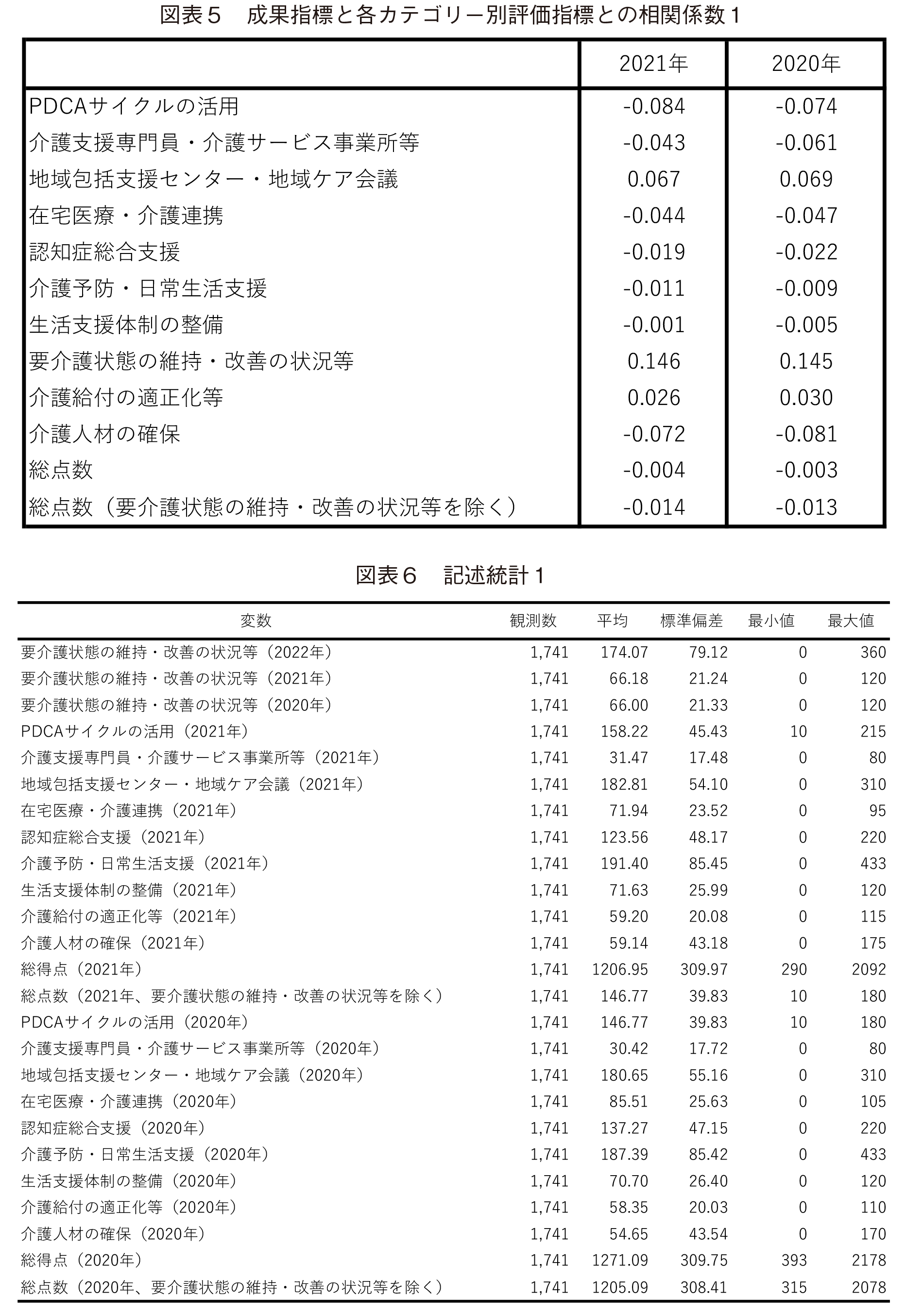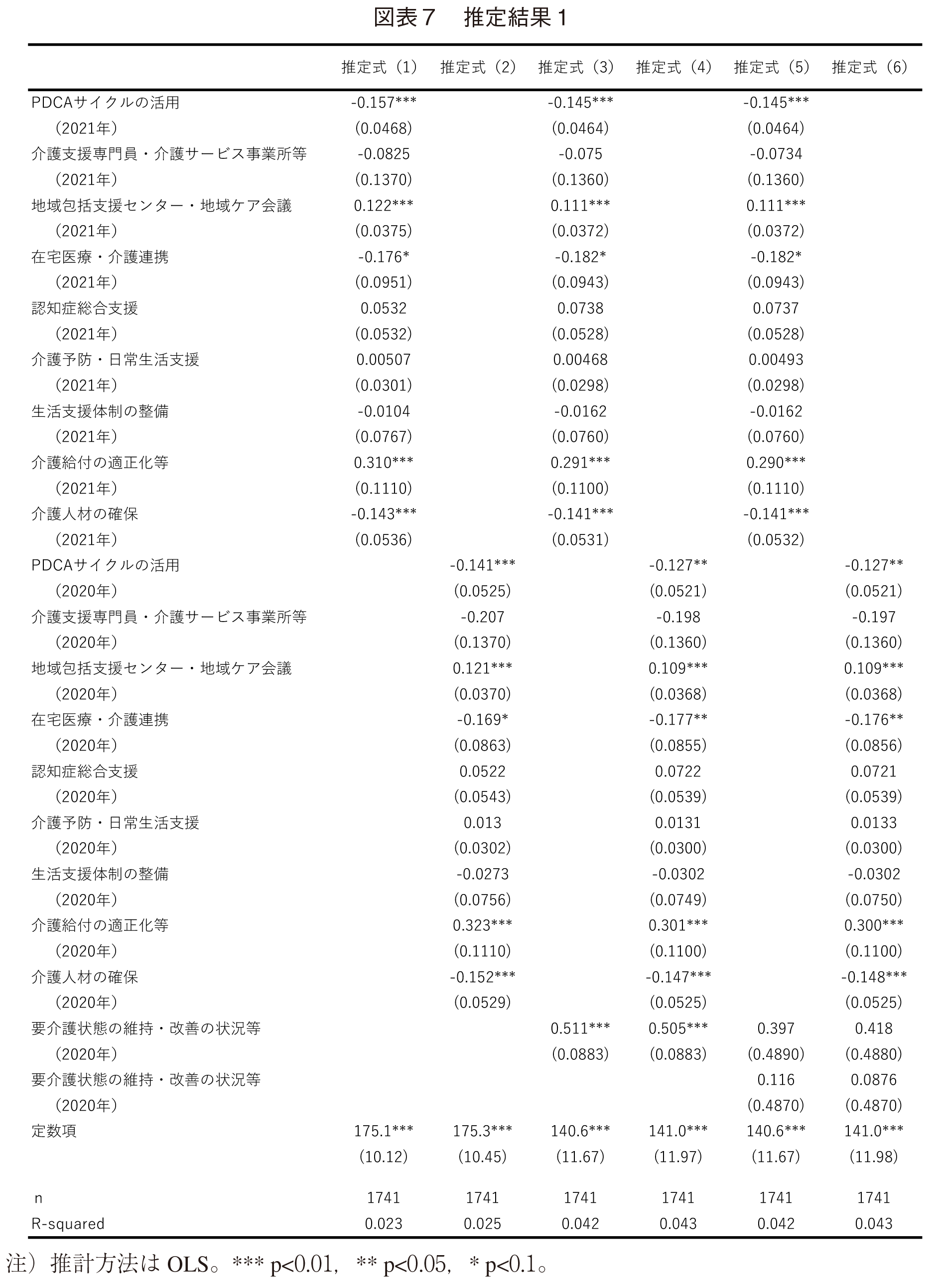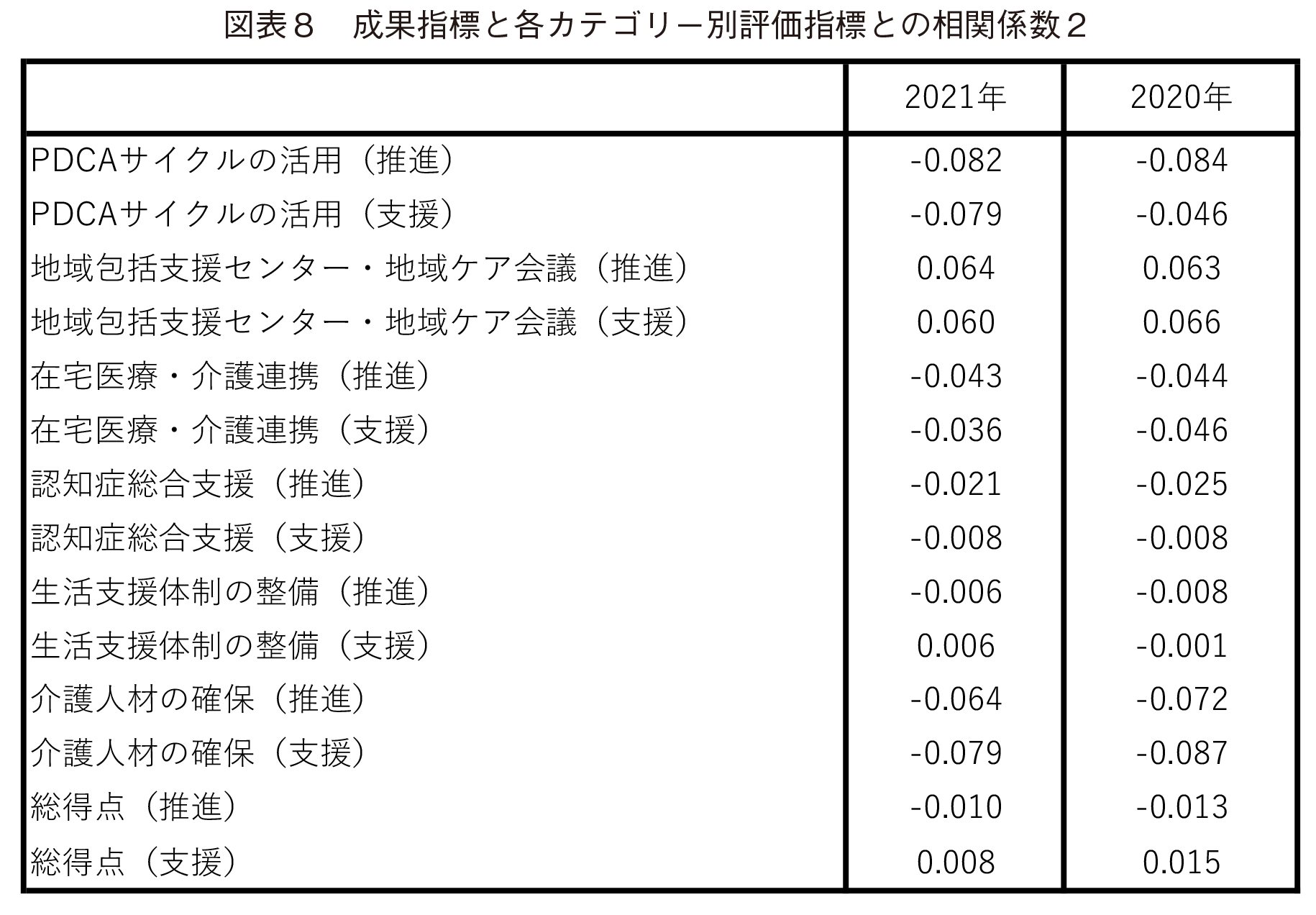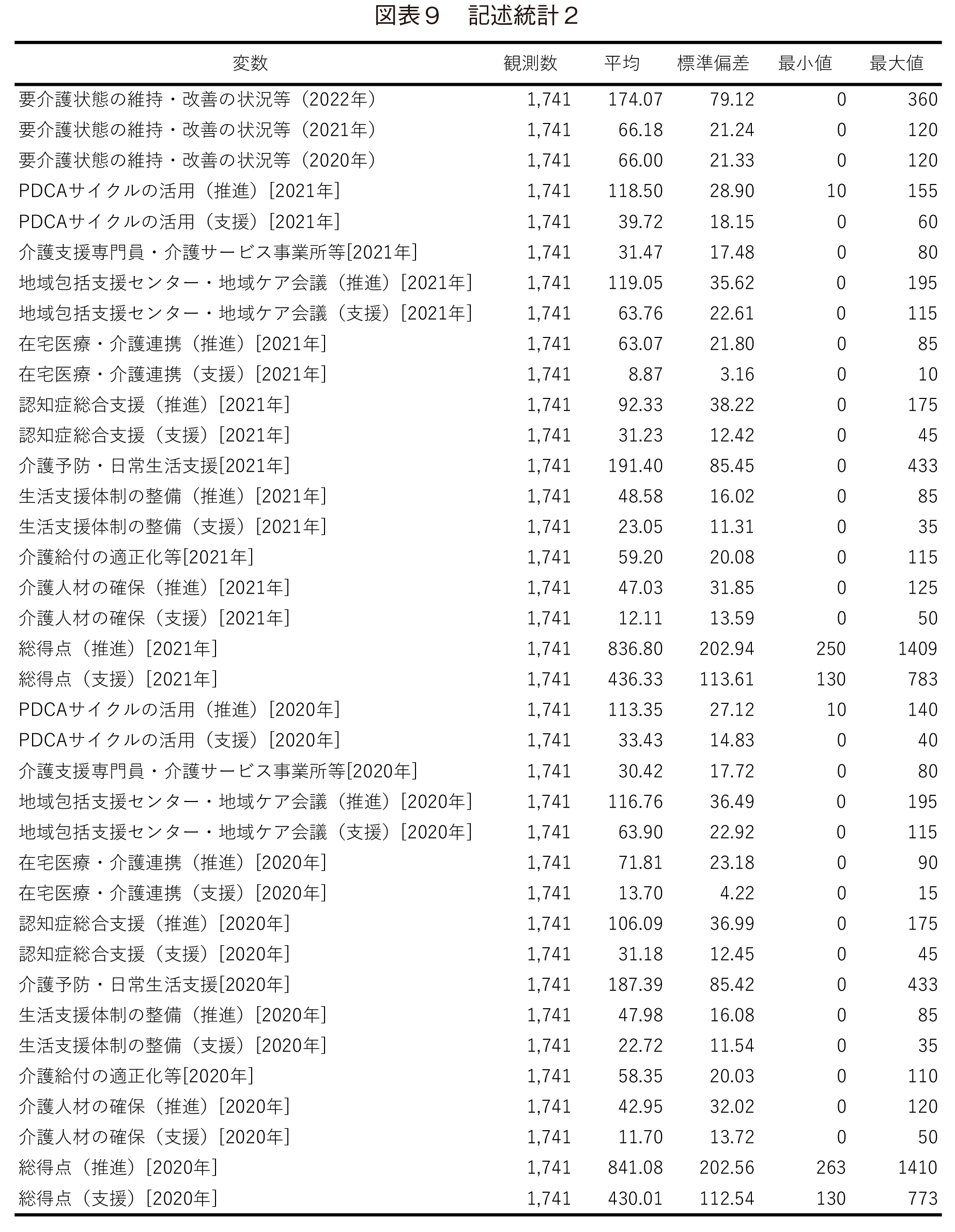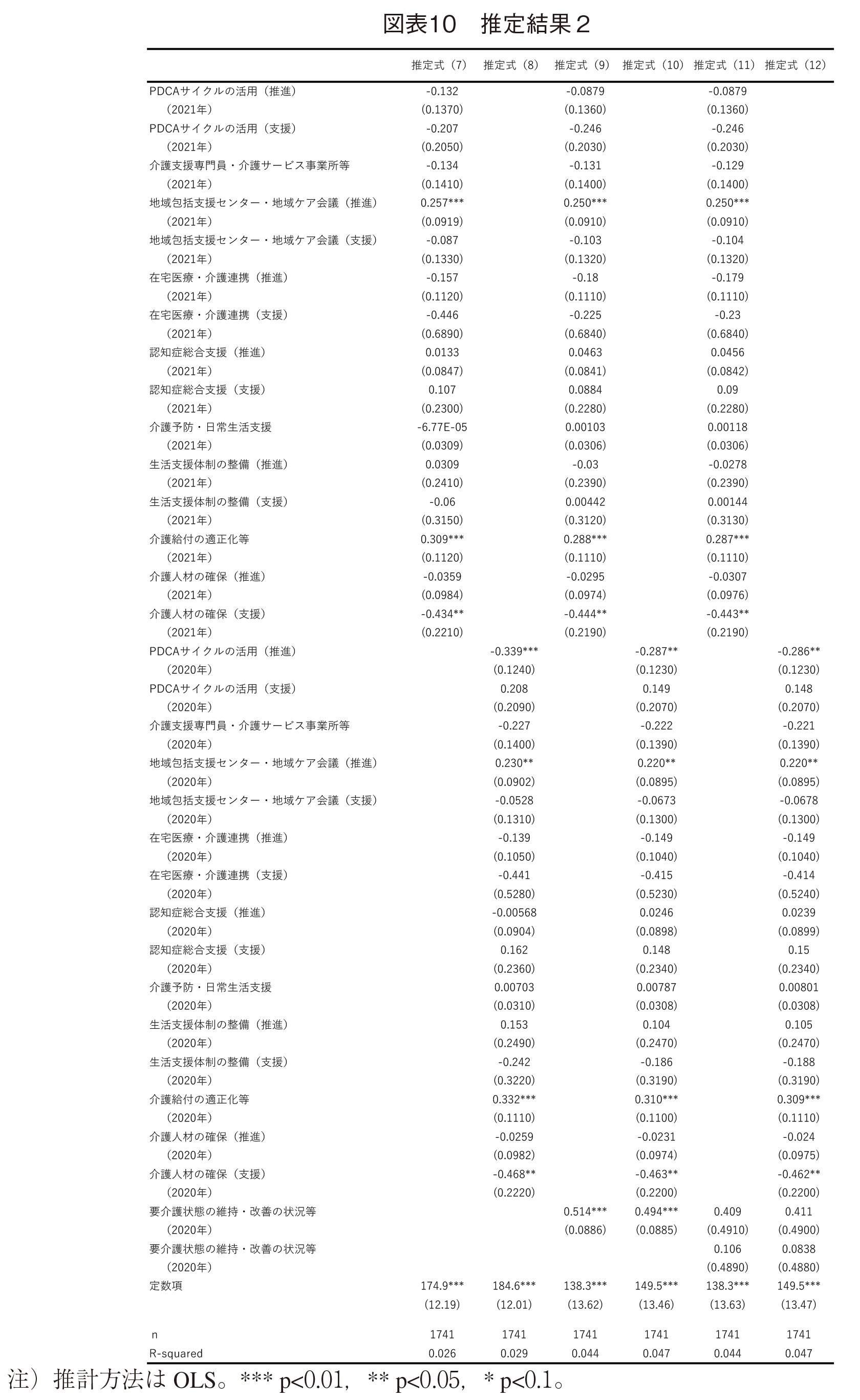�ی��ҋ@�\�������i��t���E���ی��ی��ғw�͎x����t���̐����]���Ɋւ����b�I����
��@�j
�v�|
�{�e�́C��앪��ɂ�����C���Z���e�B�u��t���Ƃ��Ē��ڂ���Ă���ی��ҋ@�\�������i��t���Ɖ��ی��ی��ғw�͎x����t�����Ƃ�グ�C�����̐����]���Ɋւ����b�I�������s�����B�C���Z���e�B�u��t���Ƃ́C��̓I�ȕ]���w�W��ݒ肵�C���̒B���x�ɉ����āC���R�x�̍�����t���i�⏕���j�������̂Ɏx�����鐧�x�ł���C�e�����̂̐������s�w�͂𑣂��ƂƂ��ɁCEBPM�iEvidence Based Policy Making�j�Ƃ����ϓ_������C���؉\�Ȏd�g�݂Ƃ��ĊS���W�߂Ă���B
�������C�����]�����s�����߂ɂ́C�]���w�W�Ɛ��ʎw�W�̊Ԃ̊W������������Ɗm�ۂ���Ă���K�v������B�{�e�́C�ی��ҋ@�\�������i��t���Ɖ��ی��ی��ғw�͎x����t���̊e�]���w�W���C���ۂɐ��ʎw�W�Ƃǂ̒��x�̑傫���̊W���������Ă���̂��C���v�I�Ɍ����s�����B
���֕��͂���щ�A���͂��s�������ʁC�e�]���w�W�Ɛ��ʎw�W�̑��ւ͋ɂ߂ĒႭ�C���ɂ͊��҂���镄���Ƌt�̊W�������Ă���]���w�W�����Ȃ��Ȃ����Ƃ��킩�����B���ʎw�W�ɑ��āC�����Ȃ�Ƃ��v���X�̊�^������]���w�W�́C�킸���ɁC�n���x���Z���^�[�E�n��P�A��c�Ɋւ�����̂Ɓi���ɁC���ی��ی��ғw�͎x����t���̏ꍇ�j�C��싋�t�̓K�������Ɋւ�����̂Ɍ�����B����t���̕]���w�W�ɂ��ẮC���{�I�Ȍ��������K�v�Ȃ��Ƃ���������錋�ʂƂȂ����B
���ی��C�C���Z���e�B�u��t���C�ی��ҋ@�\�������i��t���C���ی��ی��ғw�͎x����t���CEBPM
�ی��ҋ@�\�������i��t���́C����29�N�x�̒n���P�A�����@�ɂ���đn�݂��ꂽ��앪��̎{��ł���C����҂̎����x���E�d�x���h�~���Ɍ������s�����̎��g�݂�s���{���ɂ��s�����x���̎��g�݂𐄐i���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B��̓I�ɂ́C�s������s���{���̗l�X�Ȏ��g�݂̒B����]���ł���悤�ɋq�ϓI�ȕ]���w�W��ݒ肵�C���̒B���x�����ɂ���āC�����I�C���Z���e�B�u�Ƃ��āC����30�N�x���疈�N���v200���~���e�����̂ɔz�z���Ă���B
����ɁC�ߘa�Q�N�x����͉��ی��ی��ғw�͎x����t�����n�݂���C���\�h�E���N�Â��蓙�Ɏ�������g�݂ɑ��C���d�_�I�ɍ����I�C���Z���e�B�u��^���鐧�x���lj����ꂽ�B�ی��ҋ@�\�������i��t���Őݒ肳�ꂽ�e�]���w�W�ɑ��āC��胁���n���̂��������_���݂��C�ی��ҋ@�\�������i��t���Ƃ͕ʓr�C��͂薈�N���v200���~���e�����̂ɔz�z���Ă���B
���̂悤�ɁC�ی��ҋ@�\�������i��t���i�ȉ��C���i��t���j����щ��ی��ی��ғw�͎x����t���i�ȉ��C�x����t���j�́C�܂��q�ϓI�]���w�W��݂��āC���̒B���x�����ɉ����āC������x���R�Ɏg����⏕���������̂ɔz�z����Ƃ����C�䂪���̎Љ�ۏᐧ�x�̒��ł͂��Ȃ蒿�����C�C���Z���e�B�u��t�����x�ł���1�j�B���ꂾ���ɁCEBPM�iEvidence Based Policy Making�j�Ƃ����ϓ_������C���̐��ۂ����ڂ����Ƃ���ł��邪�C�����J���Ȏ��g���ϑ����ƂƂ��čs�����������i���{�\��������������i2022�j�j��C�����Ȃ̗\�Z���s�����i�����ȁi2022�j�j�C���t���[�E�s�����v���i��c�̏H�̔N�����J���i�s�����v���i��c�i2022�j�j�ȂǂŁC�����̒������͂��s���Ă�����x�ł���C�܂��{�i�I�Ȋw�p�����͎��{����Ă��Ȃ��B
�Ƃ���ŁC���̂悤�ȃC���Z���e�B�u��t�����x�ŏd�v�Ȃ��Ƃ́C�����̂̓w�͑ΏۂƂȂ�e�]���w�W�ƁC�����ڕW�ł��鐬�ʎw�W�i�A�E�g�J���w�W�j�Ƃ̊W����������Ɗm������Ă��邱�Ƃł���B�����łȂ��ƁC���������]���w�W�����߂�w�͂����Ă��C���ꂪ���ʎw�W�̉��P�Ɍ��т����C�u���܂葹�̂����т�ׂ��v�ɂȂ�\�������邩��ł���B
�������Ȃ���C���ۂɁC����t���̊e�]���w�W�Ɛ��ʎw�W�Ƃ̊Ԃɖ��m�ȊW�������邩�ƌ����C���Ȃ�^�₪����ƌ��킴��Ȃ��B�Ⴆ�C�����ȁi2022�j�ł́C�s���{�����ƂɈ���s�����̕��ϑ����_�i�e�]���w�W�̍��v���_�j���Z�o���C�v���F�藦�Ƃ̊Ԃ̑��W�����v�Z���Ă��邪�C�قƂ�Ǒ��ւ������Ȃ����Ƃ���Ă���B�܂��C���{�\��������������i2022�j���C��U�́i�A�E�g�J���w�W�̌����j�ɂ����āC�e�s�����i�����L��A���j�̑����_�Ɛ��ʎw�W�i�F�藦�C�V�K�F�藦�C�v���x�̏d�x�����j�Ƃ̑��W�����Ƃ��Ă��邪�C�����đ��ւ��Ⴂ���Ƃ�����Ă���B
�����Ƃ��C�����̕��͂͑����_�����͑ΏۂƂ��Ă���C�ʂ̕]���w�W�Ɛ��ʎw�W�Ԃ̊W�����Ă��Ȃ��B���̓_�C�s�����v���i��c�i2022�j�́C�����J���Ȃ�����ʂɒ��ꂽ�e�s�����i�L��A�����܂ށj�̕]���w�W���C�����Ƃ��ׂ����w�W�i�זڎw�W�j�܂Ńu���[�N�y405�Łz �_�E�����ĕ��͂�i�߂Ă���B��̓I�ɂ́C�e�זڎw�W�̓��_�ƁC�e���ʎw�W�Ƃ̊Ԃ̑��W�������C�قƂ�ǂ̍��ڂő��ւ��ɂ߂ĒႭ�C���ɂ͖{�����҂���镄���Ƌt�̑��ւ����w�W�����Ȃ��Ȃ����Ƃ���Ă���B�������C���̕��͂ɗp�����Ă���f�[�^�͌����J���Ȃ�����\�Ƃ��Ă�����̂ł��邽�߁C�s�����v���i��c�ƌ����J���ȈȊO�̑�O�҂��Č����s�����Ƃ��ł��Ȃ�2�j�B
�����ŁC�{�e�́C�����J���Ȃ����\���Ă���J�e�S���[���Ƃ̕]���w�W�̓��_�i�זڎw�W�ł͂Ȃ��C������x�J�e�S���[�ʂɂ܂Ƃ߂��Ă��链�_�j��p���āC�e�]���w�W�Ɛ��ʎw�W�Ԃ̊W�v�I�ɕ��͂��邱�Ƃɂ���B���҂̊ԂɊm�łƂ����W�������ď��߂āC���̗���t���̐����]�����������邱�Ƃ���C�{�����͐����]���̂��߂̊�b�I�����ƈʒu�Â�����B
�ȉ��C�Q�߂ł́C���߂āC���i��t���Ǝx����t���̗����x�ɂ��ďڏq����B�R�߂ł́C�{�e�ŗp����s�����ʃf�[�^�ɂ��Đ�������B�S�߁C�T�߂ł́C�J�e�S���[�ʂ̊e�]���w�W�Ɛ��ʎw�W�Ƃ̊Ԃ̊W�ɂ��ĕ��͂�i�߂�B�U�߂ł͌��_���܂Ƃ߁C��̐������s���B
�Q�D�ی��ҋ@�\�������i��t���C���ی��ی��ғw�͎x����t���ɂ���
���ɏq�ׂ��悤�ɁC����t���́C�e�s�������s�������x���E�d�x���h�~�̎��g�݁C�y�ѓs���{�����s���s�����ɑ�����g�݂̎x���ɑ��C���ꂼ��]���w�W�̒B���i�]���w�W�̑������_�j�ɉ����āC��t����z�z���鐧�x�ł���B��t��́C�傫���C�s���{���Ǝs�����i���ʋ�C�L��A���y�шꕔ�����g�����܂ށj�ɕ�����Ă���C�s���{���ɗ���t���Ƃ���10���~���C�s������190���~���x������t�����B�����Ƃ��C�s���{���֍s����t�́C�e�s�����̎��g�݂ւ̎x���ɑ�����̂Ȃ̂ŁC��̂͂����܂Ŏs�����ƌ�����B���������āC�ȉ��ł́C�s�������̉������ѕ��݂͂̂��s�����Ƃɂ���B
�e�]���w�W�́C�܂��C�T�DPDCA�T�C�N���̊��p�ɂ��ی��ҋ@�\�̋����Ɍ������̐����̍\�z�C�U�D�����x���C�d�x���h�~���Ɏ�����{��̐��i�C�V�D���ی��^�c�̈��艻�Ɏ�����{��̐��i�Ƃ����R�̑區�ڂɕ�����Ă���C�U�C�V�ɂ��ẮC����ɉ��L�Ɏ������J�e�S���[�ɕ�����Ă���B
�T�@PDCA�T�C�N���̊��p�ɂ��ی��ҋ@�\�̋����Ɍ������̐����̍\�z�@135�_ �i35�_�j
�U�@�����x���C�d�x���h�~���Ɏ�����{��̐��i�@1020�_ �i755�_�j
�@�i�P�j ���x�������E���T�[�r�X���Ə����@100�_ �i�O�_�j
�@�i�Q�j �n���x���Z���^�[�E�n��P�A��@105�_ �i60�_�j
�@�i�R�j �ݑ��ÁE���A�g�@100�_ �i20�_�j
�@�i�S�j �F�m�Ǒ����x���@100�_ �i40�_�j
�@�i�T�j ���\�h�^���퐶���x���@240�_ �i320�_�j
�y406�Łz�@�i�U�j �����x���̐��̐����@75�_ �i15�_�j
�@�i�V�j �v����Ԃ̈ێ��E���P�̏��@300�_ �i300�_�j
�V�@���ی��^�c�̈��艻�Ɏ�����{��̐��i�@200�_ �i40�_�j
�@�i�P�j ��싋�t�̓K�������@120�_ �i�O�_�j
�@�i�Q�j ���l�ނ̊m�ہ@80�_ �i40�_�j
�S����10�̃J�e�S���[�̕]���w�W������C���ꂼ��Ɏ����Ă��链�_���z�_����Ă���i���_�́C�ߘa�T�N�x�̂��́j�B���ʂ̊O�����i��t���C���ʓ����x����t���̓_���ł���B�x����t���͐��i��t���Ɠ����]���w�W�����L���Ă��邪�C�z�_���قȂ邱�ƁC�z�_���[���̍��ڂ����邱�Ƃɂ��C��胁���n����t���Ă���ƌ�����3�j�B
�e�J�e�S���[�̕]���w�W�̓_���́C�e�J�e�S���[���ɂ��邳��ɍׂ��Ȏw�W�i�זڎw�W�j�̍��v�_���ł���B�ߘa�S�N�x�C�R�N�x�C�Q�N�x�̃J�e�S���[����эזڎw�W�̏ڍׂɂ��ẮC���ꂼ��}�\�P�C�Q�C�R�Ɏ������ʂ�ł���4�j�B�����́C�s���{����s�����Ȃǂ̊W�҂̈ӌ����Ȃ���C�����J���Ȃ����N�̂悤�ɏ������ω������Ă���B���̌o�܂͐}�\�S�ɂ܂Ƃ߂��ʂ�ł��邪�C���ɁC�ߘa�P�N�x�ȑO�Ɨߘa�Q�N�x�ȍ~�̍����傫���B���̂��߁C�{�e�̕��͂́C�]���w�W����r�I�Ɉ��肵�Ă���ߘa�Q�N�x�ȍ~�ɂ��čs�����Ƃɂ���5�j�B
�����̕]���w�W�̍��v�_�����C�e�s�����ւ̌�t���z�ɕϊ�����ɂ������ẮC��ꍆ��ی��ҋK�͕ʂɗ\�Z�z�������C�ȉ��̌v�Z���Ɋ�Â��Č��肵�Ă���B
��t���z �� ��ꍆ��ی��ҋK�͕ʔz���z �~ �o�i���Y�s�����̓_���~���Y�s�����̑���ی��Ґ��j�^�i�e�K�͕ʂ̋敪�̎s�����̍��v�_���~�e�K�͕ʂ̋敪�̑�ꍆ��ی��Ґ��j�p
�����ɂ����ꍆ��ی��ҋK�͂̋敪�́C���L�̒ʂ�ł���B
�@�敪�P �F ��ꍆ��ی��Ґ����R��l����
�@�敪�Q �F ��ꍆ��ی��Ґ����R��l�ȏ�P���l����
�@�敪�R �F ��ꍆ��ی��Ґ����P���l�ȏ�T���l����
�@�敪�S �F ��ꍆ��ی��Ґ����T���l�ȏ�10���l����
�@�敪�T �F ��ꍆ��ی��Ґ���10���l�ȏ�
���̋K�͂ɂ��敪�́C�ߘa�Q�N�x�ɍ��ꂽ���̂ł���B��ʘ_�Ƃ��āC�l���������C�s�y407�Łz �s���̎����̂̕����C���̍����͂�Љ���̗ʂȂǂ���C�_���������Ȃ�X���ɂ��邽�߁C���K�͂Ȏ����̂ɂ����Ă����z���z�������悤�C���̂悤�Ȏd�g�݂��������ꂽ�B
���āC�s�����ɔz�z���ꂽ��t���́C�ǂ̂悤�Ɏg����̂ł��낤���B�܂��C���i��t���ɂ��ẮC���ړI�ɂ́C���ی����ʉ�v�̑�ꍆ�ی������������ɏ[�����邱�ƂɂȂ��Ă���B���̒��ŁC����҂̎����x���E�d�x���h�~���Ɍ������s�����̎��g�݂��x������Ƃ������x�̎�|�܂��C�n��x�����Ɓi���\�h�E���퐶���x���������ƁC��I�x�����Ɓj�C�s�������ʋ��t�C�ی��������Ƃ��[�����C����҂̎����x���C�d�x���h�~�C���\�h���Ɏg����ׂ��Ƃ���Ă���B�܂��C�ߘa�Q�N�x����́C��ʉ�v���ƂɌW�鍂��҂̗\�h�E���N�Â���Ɏ�������g�݁i�V�K�E�g�[�����j�ɂ��[�����\�ƂȂ����B����C�x����t���ɂ��ẮC���\�h�E���퐶���x���������Ƌy�ѕ�I�x�����Ɓi��I�p���I�P�A�}�l�W�����g�x���C�ݑ��É��A�g���i���ƁC�����x���̐��������ƁC�F�m�Ǒ����x�����ƂɌ���j�ɏ[�����\�ł���B
�{�e�̕��͂ɗp����f�[�^�́C�����J���Ȃ����̃E�F�u�T�C�g�Ō��J���Ă���u�ی��ҋ@�\�������i��t���E���ی��ی��ғw�͎x����t���̏W�v���ʁi�s�������j�v�ɂ�����s�����ʂ̕]���w�W�ʓ��_�f�[�^�ł���B����30�N�x�`�ߘa�S�N�x���̂T�J�N���ɂ��āC���ꂼ��1741�̎s�����f�[�^������\�ł���B�������C�]���w�W�ɂ��Ă͌ʂ̍זڎw�W�͌��J����Ă��炸�C���ɐ�������10�̃J�e�S���[�ʂ̕]���w�W�̓��_���i�[����Ă���B�����̃J�e�S���[�ʂ̕]���w�W�̊e���_���C���ʎw�W�Ƃǂ̂悤�ȑ��֊W�������Ă��邩�C�ߘa�Q�N����S�N�̃f�[�^���g���Č�����B
�������C���́C���ʎw�W���̂����荢��Ȃ��Ƃł���B�����J���Ȃ͈�`�I�ɂ́C���ʎw�W�i�����A�E�g�J���w�W�j���C�u���ϗv���x�̈ێ��E���P�v�Ɓu�v���F�藦�̈ێ��E���P�v�ƒ��ۓI�ɕ\�����Ă���B����͋�̓I�ɁC�ߘa�S�N�x�̗�Ō����ƁC�@�y�x�i�v���P�E�Q�j�̕��ϗv���x�̕ω����ƕω����̍��C�A���d�x�i�v���R�`�T�j�̕��ϗv���x�̕ω����ƕω����̍��C�B�v���Q�ȏ�̔F�藦�ƔF�藦�̕ω����Ƃ��Ďw�W������Ă���B���Ȃ킿�C�ߘa�S�N�x�̃J�e�S���[�ʂ̕]���w�W�ł���u�U�D�i�V�j�v����Ԃ̈ێ��E���P�̏��v�̍��ڂ́C�ȏ�̎w�W�����ɓ��_�����s���Ă���B
�������Ȃ���C�����̌��w�W�͑S�āC���E�N��������w�W�ƂȂ��Ă���C���̒l�𐳊m�ɍ��ɂ́C��ʂɂ͌��J����Ă��Ȃ������J���Ȃ̉��ی����ƏE���ی������f�[�^�x�[�X�i���DB�j�ɃA�N�Z�X���C���o�E�Z�o����K�v������B�܂��C�v���x�̕ω����ɂ��Ă��C���m�Ɍv�Z���邽�߂ɂ́C���DB�ŎZ�o�����V�K�F��҂́C�F�茎����P�N��E�Q�N��̔F��𒊏o���ĎZ�o����K�v������6�j�B
�{�e�ł́C�c�O�Ȃ�����DB�ɃA�N�Z�X���āC���w�W�邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁C���z��ς��āC�u�v����Ԃ̈ێ��E���P�̏��v�Ƃ����]���w�W�̓��_���̂��C���ʎw�W�Ƃ��ėp���邱�Ƃɂ���B�����C�Ⴆ�C�ߘa�R�N�x�̌�t���ɂ�����u�v����Ԃ̈ێ��E���P�̏��v�Ƃ����w�W�́C�ߘa�P�N�x����ߘa�Q�N�̕ω����i���邢�͕���30�N���ߘa�P�N�ƁC�y408�Łz �ߘa�P�N���ߘa�Q�N�̕ω����̍��j�����Ɍv�Z����Ă���B���̕]���w�W�͊�{�I�ɗߘa�Q�N�x�̎��g�ݏ������Ă��邩��C�ߘa�R�N�x�́u�v����Ԃ̈ێ��E���P�̏��v��ߘa�R�N�x�̐��ʎw�W�Ɏg�p����ꍇ�ɂ́C���̕]���w�W�������_���O���C�������������ƂȂ��Ă��܂��āC���ʎw�W�Ƃ��Ă͕s�K�ł���B
���̂��߁C�ߘa�R�N�x�̐��ʎw�W�Ƃ��ẮC�P�N��̗ߘa�S�N�x�́u�v����Ԃ̈ێ��E���P�̏��v�̓��_��p���邱�Ƃɂ���B���l�ɁC�ߘa�Q�N�x�̐��ʎw�W�Ƃ��āC�P�N��̗ߘa�R�N�x�́u�v����Ԃ̈ێ��E���P�̏��v�̓��_��p����B����ɁC���ʎw�W�Ɋe�s�����̓w�͂̐��ʂ�����邽�߂ɂ́C�P�N�Ƃ������Ԃ͂��Z���C�����ƒ������Ԃ̌o�߂��K�v�ƍl������B���̂��߁C�ߘa�Q�N�x�̐��ʎw�W�Ƃ��āC����ɂP�N�o�߂����ߘa�S�N�x�́u�v����Ԃ̈ێ��E���P�̏��v�̓��_���p���邱�Ƃɂ����B
�܂�C�ߘa�R�N�x�ɂ�����10�̊e�J�e�S���[�ʂ̕]���w�W�̓��_�i�@PDCA�T�C�N���̊��p�C�A���x�������E���T�[�r�X���Ə����C�B�n���x���Z���^�[�E�n��P�A��c�C�C�ݑ��ÁE���A�g�C�D�F�m�Ǒ����x���C�E���\�h�E���퐶���x���C�F�����x���̐��̐����C�G�v����Ԃ̈ێ��E���P�̏��C�H��싋�t�̓K�������C�I���l�ނ̊m�ہj�ɂ��ẮC���̐��ʎw�W�ł���ߘa�S�N�x�̇G�v����Ԃ̈ێ��E���P�̏��̓��_�Ƃ̊W�͂���B�܂��C�ߘa�Q�N�x�ɂ�����10�̊e�J�e�S���[�ʂ̕]���w�W�̓��_�ɂ��ẮC�ߘa�S�N�x�Ɨߘa�R�N�x�̇G�v����Ԃ̈ێ��E���P�̏��̓��_�Ƃ̊W�͂��邱�Ƃɂ���B
�S�D���͂P�F�ی��ҋ@�\�������i��t���E���ی��ی��ғw�͎x����t�������v��������
4.1�@���֕���
�܂��C���i��t���Ǝx����t�������v�����x�[�X�ŁC���ʎw�W�i���N�x�C���X�N�x�̗v����Ԃ̈ێ��E���P�̏��̓��_�j�ƁC�e�J�e�S���[�ʂ̕]���w�W�̊Ԃ̑��W�����Ƃ������̂��C�}�\�T�ł���B2021�N�Ə����Ă���ߘa�R�N�x�̊e�]���w�W�Ɨߘa�S�N�x�̐��ʎw�W�Ԃ̑��W���C2020�N�Ə����Ă���C�ߘa�Q�N�x�̊e�]���w�W�Ɨߘa�S�N�x�̐��ʎw�W�Ԃ̑��W���ł���B�S�Ă̕]���w�W�ŁC�v���X�̑��W�������҂����B
���ʂ�����ƁC�܂��C�e�]���w�W�̑��W���������Ĕ��ɒႢ���Ƃ��킩��B�ʏ�C−0.2����0.2�܂ł̑��W���́u�قƂ�Ǒ��ւ��Ȃ��v�Ɣ��f����邪�C�S�Ă̕]���w�W�����͈̔͂Ɏ��܂��Ă��܂��Ă���B�܂��CPDCA�T�C�N���̊��p�C���x�������E���T�[�r�X���Ə����C�ݑ��ÁE���A�g�C�F�m�Ǒ����x���C���\�h�E���퐶���x���C�����x���̐��̐����C���l�ނ̊m�ۂƂ����V�̕]���w�W�́C���W���̕������}�C�i�X�ƂȂ��Ă���B���ʎw�W�ƌ��X���ւ������ƍl������v����Ԃ̈ێ��E���P�̏���������7�j�C�v���X�̑��ւ������Ă���̂́C�킸���ɒn���x���Z���^�[�E�n��P�A��c�ƁC��싋�t�̓K�������y409�Łz �̂Q�݂̂ł���B
����ɁC���ɐ�s������������炩�Ȃ悤�ɁC���_���Ɛ��ʎw�W�Ƃ̑��ւ��ɂ߂ĒႢ�B���Ȃ݂ɁC���Y�N�x�̗v����Ԃ̈ێ��E���P�̏��Ɨ��N�C���X�N�̗v����Ԃ̈ێ��E���P���̑��ւ͍����Ƒz�肳��邽�߁C����������������_������Ă��邪�C��͂葊�ւ͋ɂ߂ĒႢ���C�}�C�i�X�̌W���ƂȂ��Ă��܂��Ă���B�ȏ�̌��_�́C2020�N�̊e�]���w�W�Ɋւ��鑊�W�����݂Ă��C�قړ��l�ƌ�����B
4.2�@��A����
�����C�����瑊�W�����Ⴂ�Ƃ͌����C�v���X�̑��W�������]���w�W�́C���ʎw�W�ɑ��ĉ��炩�̉e�����y�ڂ��\��������B�����ŁC���v�I�ɗL�ӂȉe�����y�ڂ����ǂ������m���߂邽�߁C���̂悤�ȂU�̉�A���f���𐄒肷�邱�Ƃɂ���B
���ʎw�W���_����0�{����i �E �]���w�W���_ i �{�� �c�c�c ⑴
���ʎw�W���_����0�{����i �E �]���w�W���_�it−1�ji �{�� �c�c�c ⑵
���ʎw�W���_����0�{��1���ʎw�W���_�it−1�j�{����i �E �]���w�W���_ i �{�� �c�c�c ⑶
���ʎw�W���_����0�{��1���ʎw�W���_�it−1�j�{����i �E �]���w�W���_�it−1�ji �{�� �c�c�c ⑷
���ʎw�W���_����0�{��1���ʎw�W���_�it−1�j�{��2���ʎw�W���_�it−2�j �{����1�E �]���w�W���_ i �{�� �c�c�c ⑸
���ʎw�W���_����0�{��1���ʎw�W���_�it−1�j�{��2���ʎw�W���_�it−2�j �{����1�E �]���w�W���_�it−1�ji �{�� �c�c�c ⑹
�ϐ��̉��ɕt���Ă���it−1�j�C�it−1�j�̓��O���Ӗ����Ă���B������ϐ��Ɛ����ϐ��̋L�q���v�́C�}�\�U�Ɏ������ʂ�ł���B
⑴�`⑹���̐��茋�ʂ́C�}�\�V�Ɏ�����Ă���B�O����4.1�̑��֕��͂Ńv���X�̑��W���ł������n���x���Z���^�[�E�n��P�A��c�ƁC��싋�t�̓K�������́C⑴�`⑹�̑S�Ă̐��茋�ʂɂ����āC�Ƃ��Ƀv���X�œ��v�I�ɗL�ӂȌ��ʂƂȂ��Ă���B���������āC���̂Q�̕]���w�W�ɂ��ẮC�e���̑傫���͂Ƃ������Ƃ��āC���Ȃ��Ƃ����ʎw�W�Ƀv���X�̉e���������Ă���ƌ�����B�����͕]���w�W�Ƃ��Ĉꉞ�C�I�m�Ȏw�W�ł���Ɣ��f�ł��悤�B����CPDCA�T�C�N���̊��p�ƍݑ��ÁE���A�g�C���l�ނ̊m�ۂ̂R�ɂ��ẮC��͂�⑴�`⑹�̑S�Ă̐��茋�ʂɂ����āC�}�C�i�X�ŗL�ӂƂȂ����B�܂�C���̂R�̍��ڂ�]���w�W�ɓ���ēw�͂��邱�Ƃ́C���ʎw�W�Ƀ}�C�i�X�̉e�����y�ڂ��\��������Ƃ������Ƃł���C�]���w�W�Ƃ��Ă̓K�i�����^����B
�T�D���͂Q�F�ی��ҋ@�\�������i��t���C���ی��ی��ғw�͎x����t����������
5.1�@���֕���
���ɁC���i��t���Ǝx����t�����āC�O�߂Ɠ��l�̕��͂��s�����B���ɏq�ׂ��悤�ɁC���i��t���Ǝx����t���́C�]���w�W���͓̂����ł��邪�C���̓��_�z�����قȂ�B���������āC���̔z���̎d���̈Ⴂ�ŁC���ւ��قȂ�\��������8�j�B
�O�߂�4.1�Ɠ��l�C���ʎw�W�i���N�x�C���X�N�x�̗v����Ԃ̈ێ��E���P�̏��̓��_�j�ƁC�e�J�e�S���[�ʂ̕]���w�W�̊Ԃ̑��W�����Ƃ������̂��C�}�\�W�ł���B�x����t���̓��_�z�����[���ƂȂ��Ă���]���w�W�i���x�������E���T�[�r�X���Ə����C��싋�t�̓K�������j�C�x����t���ƑS�����_�z���������ŗ��҂����ʂł��Ȃ��]���w�W�i���\�h�E���퐶���x���C�v����Ԃ̈ێ��E���P�̏��j�́C���ʂ��}�\�T�Ɠ����Ȃ̂ŁC�}�\�W����͏�����Ă���B
�܂��C2021�N�̌��ʂ�����ƁC��͂�C���W�������ɒႭ�C−0.2����0.2�܂ł̒l�ɑS�Ă̕]���w�W�������Ă���B�܂��C���҂����v���X�̕����ƂȂ��Ă���̂́C�n���x���Z���^�[�E�n��P�A��c�i���i�j�C�n���x���Z���^�[�E�n��P�A��c�i�x���j�ƁC�����x���̐��̐����i�x���j�݂̂ł���B���_���́C�x����t���݂̂��v���X�̕����ł������B�����̌��ʂ́C2020�N�̊e�]���w�W�Ɋւ��Ă��ς��Ȃ��B
5.2�@��A����
�O�߂�4.2�Ɠ��l�C���i��t���C�x����t���ɕ������]���w�W�ɂ��Ă��C���L�̂U�̉�A���f���𐄒肷�邱�Ƃɂ���B
���ʎw�W���_����0�{����i �E �]���w�W���_ i �{�� �c�c�c ⑺
���ʎw�W���_����0�{����i �E �]���w�W���_�it−1�ji �{�� �c�c�c ⑻
���ʎw�W���_����0�{��1���ʎw�W���_�it−1�j�{����i �E �]���w�W���_ i �{�� �c�c�c ⑼
���ʎw�W���_����0�{��1���ʎw�W���_�it−1�j�{����i �E �]���w�W���_�it−1�ji �{�� �c�c�c ⑽
���ʎw�W���_����0�{��1���ʎw�W���_�it−1�j�{��2���ʎw�W���_�it−2�j �{����i �E �]���w�W���_ i �{�� �c�c�c ⑾
���ʎw�W���_����0�{��1���ʎw�W���_�it−1�j�{��2���ʎw�W���_�it−2�j �{����i �E �]���w�W���_�it−1�ji �{�� �c�c�c ⑿
������ϐ��Ɛ����ϐ��̋L�q���v�́C�}�\�X�Ɏ������ʂ�ł���B
⑺�`⑿���̐��茋�ʂ́C�}�\10�Ɏ�����Ă���B�S�Ă̐��莮�ɂ����āC���҂����v���X�̕����ŗL�ӂȕ]���w�W�́C�n���x���Z���^�[�E�n��P�A��c�i���i�j�ƁC��싋�t�̓K�������݂̂ł���B���̓_�́C�}�\�W�̌��ʂƂقړ��l�ƌ�����B����C���l�ނ̊m�ہi�x���j�C2020�N��PDCA�T�C�N���̊��p�ƍݑ��ÁE���A�g�i���i�j�́C�}�C�i�X�ŗL�ӂƂ������ʂł������B
�{�e�́C��앪��ɂ�����C���Z���e�B�u��t���Ƃ��Ē��ڂ����ی��ҋ@�\�������i��t���Ɖ��ی��ی��ғw�͎x����t�����Ƃ�グ�C�����]���Ɋւ����b�I�������s�����B�C���Z���e�B�u��t���Ƃ́C��̓I�ȕ]���w�W��ݒ肵�C���̒B���x�ɉ����āC���R�x�̍�����t���i�⏕���j�������̂Ɏx�����鐧�x�ł���C�e�����̂̓w�͂𑣂��d�g�݂Ƃ��Ē��ڂ���Ă���B�܂��C���m�ŋq�ϓI�ȕ]���w�W�Ɛ��ʎw�W���ݒ肳��C�����]�����e�ՂƂ݂��邱�Ƃ���C�ߔN�C���{�����i���Ă���EBPM�iEvidence Based Policy Making�j�̊ϓ_������S���W�߂Ă���B
�������C�����]�����s�����߂ɂ́C�]���w�W�̒B���x�����߂邱�Ƃ��C���ʎw�W�̌���Ɏ����邱�Ƃ���������ƒS�ۂ���Ă��邱�Ƃ��O��ƂȂ�B�{�e�́C�܂��͐����]���̂��߂̊�b�I�����Ƃ��āC���i��t���Ǝx����t���̕]���w�W���C���ۂɐ��ʎw�W�Ƃǂ̒��x�̊W���������Ă���̂��C���v�I�Ɍ����s�����B
���֕��͂���щ�A���͂��s�������ʁC�]���w�W�Ɛ��ʎw�W�̑��֊W�͋ɂ߂ĒႭ�C���ɂ͊��҂���镄���Ƌt�̊W�������Ă���]���w�W�����Ȃ��Ȃ����Ƃ��킩�����B�����Ȃ�Ƃ��C���ʎw�W�Ƀv���X�̊�^������]���w�W�́C�킸���ɁC�n���x���Z���^�[�E�n��P�A��c�i���ɁC���ی��ی��ғw�͎x����t���̏ꍇ�j�ƁC��싋�t�̓K�������Ɍ�����B�܂�C���s���x�̕]���w�W�ɂ��ẮC���{�I�Ȍ��������K�v�Ȃ��Ƃ���������錋�ʂƂȂ����B
�������C�ŏI�I�Ȑ��ʎw�W�i�����A�E�g�J���w�W�j�ł���u���ϗv���x�̈ێ��E���P�v�Ɓu�v���F�藦�̈ێ��E���P�v�ɂ́C����t�����_���Ƃ���e�����̂̎��g�݂����ł͂Ȃ��C�l�X�ȗv�����W���Ă���Ǝv����B���̏ꍇ�C�]���w�W�Ɛ��ʎw�W�̑��W�����Ⴂ����ƌ����āC�����ɓ��Y�]���w�W���s�K�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����C���Ȃ��Ƃ��}�C�i�X�̑��ւ�����]���w�W�ɂ��ẮC������g�������ėǂ����ǂ����C�\���Ȍ������K�v�ł��낤�B
�܂��C�e�����̂̎��g�݂����ʂ��グ��܂łɁC���N���x�̊��Ԃ������邱�Ƃ��l������B���̏ꍇ�ɂ́C�ŏI���ʂƋ����W������C���ʂ��Z���I�ɏo�₷�����ԖڕW�i�Z���A�E�g�J���j��ݒ肷�邱�Ƃ���Ăł���B������ɂ���C���̒��ԖڕW�̎w�W�ƍŏI�I�Ȑ��ʎw�W�C���ԖڕW�̎w�W�Ɗe�]���w�W�Ԃ̊W�͓��v�I�ɂ�������Ɗm�ۂ���Ă���K�v������B���NJ����ɂ����ẮC���������G�r�f���X�Ɋ�Â��C���x��s�f�Ƀu���b�V���A�b�v���Ă䂭���Ƃ����߂���B
�Ō�ɁC�{�e�̕��̗͂��ӓ_���q�ׂĂ������B�{�e�̓f�[�^���p��̐���C�@���ʎw�W�ɂ��Č��w�W�ł͂Ȃ��C���H��̓��_�f�[�^��p���Ă��邱�ƁC�A�]���w�W�ɂ��Ă��ז��y412�Łz �w�W�ł͂Ȃ��C�J�e�S���[�ʂ̕]���w�W��p���Ă��邱�ƂȂǂ̖�肪����B�����̖����������邽�߂ɂ́C���NJ�����e�����̂���f�[�^�����J�����K�v������BEBPM�̊ϓ_����́C�f�[�^��������ƌ��J���C��O�҂����ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��]�܂����B�����ɁC�����]���ɕK�v�ȑS�f�[�^�����J����邱�Ƃ����҂������B
���{�\��������������i2022�j�u�ی��ҋ@�\�������i��t���y�щ��ی��ی��ғw�͎x����t���̕]���w�W�Ɗ��p����Ɋւ��钲�������ꎮ���v
�����ȁi2022�j�u�\�Z���s�����E���������[�i�ߘa�S�N�V�����\���j�i17�j�����J���� �ی��ҋ@�\�������i��t���E���ی��ی��ғw�͎x����t���v
�s���]�����i��c�i2022�j�u�s�v�����ǁi��Ș_�_�j�z�t�����i�ی��ҋ@�\�������i��t�����i�����J���ȁj�j�v
https://www.gyoukaku.go.jp/review/aki/R04/img/6_1_1_gyoukaku.pdf