2025�N�N�������̉ۑ�F�Q�̍����N���~�ψĂ��߂�����
��@�j
�{�e�́C2025�N�̎����N�������Ɍ����C���݁C�Љ�ۏ�R�c��E�N������Ō����������܂�Ă���Q�̍����N���~�ψĂɂ��āC���̐����ƕ]�����s�����B�Q�̉��v�Ă͑����Ă݂āC�T�����[�}�������̋]���̉��ɁC���c�Ǝ҂Ȃǂ̍����N�������҂��~�ς�����̂ł���B���������~�ύ���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����w�i�ɂ́C2004�N�����Œ�߂�ꂽ�}�N���o�σX���C�h�����݁C�@�\�s�S�Ɋׂ��Ă��邱�Ƃ�����B�Q�̉��v�ẮC����C��b�N���i�����N���j�̑啝�ȔN�������J�b�g���\�肳��钆�ł́C�Œ���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ���D��ł͂��邪�C���������̃}�N���o�σX���C�h�̋@�\�s�S�ɑS���Ώ����Ă��Ȃ����߁C�낤�����v�Ăƌ��킴��Ȃ��B����C���{�o�ς������J���Ȃ̌o�ϑO������������C���ꂩ����}�N���o�σX���C�h���\��ʂ�Ɏ��{�ł��Ȃ��������C�����̖�D��ł͑S���Ώ��ł��Ȃ��Ȃ邾�낤�B�����N�������ł́C�N�������̌��S�������߂邽�߁C�����Ɣ��{�I�ȉ��v�Ă��l����K�v������B���̔��{���v�̂������̑I�����ɂ��Ă��c�_���s�����B
�N�������C�������C100�N���S�v�����C�����N��
�����J���Ȃ̎Љ�ۏ�R�c��E�N������C2025�N�ɗ\�肳��鎟���N�������Ɍ����C2022�N10��25���ɋc�_���J�n�����B�N�������́C�T�N�ɂP�x�C�������ƌĂ����I�N���̏����������ʂ������\���ꂽ��ɍs����̂��ʗ�ł���C������������2024�N�ɍs����B�ߔN�C���̍������ŁC�N�������̑I�����ƂȂ���v�ĂƂ��̌��ʂ̎��Z���ʂ�������鎖����ƂȂ��Ă���C���̂��߁C�ǂ̂悤�ȉ��v�Ă�E���Z���ׂ����C�O�����ĔN������ŋc�_���s����̂ł���B
���Ƃ��ƌ��݂̔N�����x�́C�u100�N���S�v�����v�ƌĂꂽ2004�N�̔N�������ȍ~�C���N0.9�����x�̔N�����t�J�b�g��2023�N�܂�19�N�Ԏ��{���i�}�N���o�σX���C�h�j�C�N�������������I�Ɉێ��\�Ȃ��̂ɗ��Ē����\��ł������B�������Ȃ���C���݂܂łɁC���̃}�N���o�σX���C�h�͒x�X�Ƃ��Đi�܂��C�N���҂͓����̗\������啝�ɉߑ�ȔN���z������Ă���B����́C���t�J�b�g�̒x��ɉ����āC���̉ߏ苋�t�����J�o�[���邽�߁C��i�Ƒ傫�y80�Łz �ȔN���J�b�g���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B2020�N���ɍs��ꂽ�����J���Ȃ̎��Z�i�����J���ȁi2020�j�j�ɂ��C�����C�܂��ɍ��N�i2023�N�j�ŏI������͂��ł������}�N���o�σX���C�h�́C���͂�2046�N�܂ő����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���B
���̂��߁C������֗�1�j�ő������T�����[�}�����сi�����N���̃��f�����сj�̔N�����t�����́C2019�N�Δ�łQ����i17.3���|�C���g�j�̃J�b�g�C���c�Ǝ҂ȂǍ����N�����т̃J�b�g���́C���ɂR����i27.2���|�C���g�j�ɂ��Ȃ�B���݁C�����N���̖��z�͖�U���T��~�i���z�j�ł��邩��C���ɂ��̋��z����R����J�b�g�����Ƃ���ƁC���z�S���V��~���x�ɂȂ�v�Z�ł���B���ۂɂ́C���[���Ԃ�����Ȃǂ��āC�����N���z�ł���l�͏��Ȃ��B�����N���݂̂̕��ώ��z�͌��݁C��T���R��~�قǂł��邩��C�R����J�b�g�łR���W��~���x�ł���B����ł́C�N�������Łu���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐����v�𑗂邱�Ƃ͂قڕs�\�ł���B�����āC�R���i�Ђ̒��ŁC���{�̏��q������i�Ɛi��ł���C2022�N�̏o���Ґ��͉ߋ��Œ���X�V���C���߂�80���l��������̂ƌ����܂��B����́C�����J���Ȃ̏����l�����v�ɂ�����o�����̌��������݂��W�N���x���߂����ƂɂȂ�B�����������ł́C�}�N���o�σX���C�h�̓K�p���Ԃ�2046�N����������������C����ɑ傫�ȔN�����t�J�b�g���v������邱�ƂɂȂ邾�낤�B
���̂��߁C2025�N�̔N�������Ɍ����āC�N������ł́C��b�N���i�����N���j�̖ڌ���Ɏ��~�߂���������v�Ă����������Ƃ݂���B��̓I�ɂ́C�@�����N���⍑���̍����x���ɂ��C��b�N�����������x������āC�A��b�N���̕ی����[�t���Ԃ����݂�40�N�i20����59�j����45�N�i20����64�j�ɉ������C���̕��C�N�����t�𑝂₷�Ă̂Q�������J���Ȃɂ���Č�������Ă��邱�Ƃ��C�V���e���ɂ���ĕ��Ă���2�j�B�{�e�́C���̂Q�̗\�z�������v�Ă���X�̔N�������ɋy�ڂ��e����������ŁC���̉��v�Ă̕]����C�{������ׂ��N�����v�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł���̂��C�c�_��i�߂邱�Ƃɂ������B
�ȉ��C�{�e�̍\���͉��L�̒ʂ�ł���B��Q�߂ł́C�Q�̉��v�Ă�����̔N�������ɗ^����e���ɂ��Ă܂Ƃ߂�B��R�߂́C�����������̂Q�̉��v�Ă��s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����w�i�Ƃ��āC�}�N���o�σX���C�h���Ȃ��@�\���Ă��Ȃ��̂����C2004�N�����ɑk���ĉ������B�S�߂́C�}�N���o�σX���C�h�̋@�\�s�S���C�N�������̖c���ƌ������ʂ��瑨���C����ԕs�����ɂ��Ă��ڂ����_����B��T�߂́C�{������ׂ����{���v�ɂ��āC���̑I�������c�_����B�Ȃ��C�{�e�̂R�߁C�S�߂͗�i2020�j�̑�U�́C��V�͂����ɁC�ŋ߂̔N�����v�̓����܂��āC�啝�ɉ����������̂ł���B
2.1�@�����N������̉�����
���́C2022�N10���ɍs��ꂽ����̔N������ł́C���O�ɉ��n�]�ɋ������Ă����Q�̔N�����v�Ă��C�����ǁi�����J���ȁj���疾���I�Ɏ�����邱�Ƃ͂Ȃ������B����ɁC�N������̊e�ψ�������C�Q�̉��v�ĂɊւ��锭���͂Ȃ������B����͂����炭�C�����̎x�������ቺ���钆�Ȃ̂ŁC�N������̉^�c�Ɉ��S�^�]�����߂��Ă����Ƃ������Ƃł��낤�B�������C���̂Q�̉��v�Ă̋�̓I���e�ɂ��ẮC���́C2020�N���ɍs���������J���Ȃ̎��Z�i�����J���ȁi2020�j�j�̒��Ɋ܂܂�Ă���C�����炭�́C���̎��Z���x�[�X�ɍ���̔N������̋c�_���i�ނ��̂Ɛ�������Ă���B�����ŁC���̌����J���Ȏ��Z�����ɁC�Q�̉��v�ɂ���ĉ�X�̔N���͂ǂ��ς��̂��������Ă݂����̂��C�}�\�P�ł���B
�܂��C��i�i�P�j���C�����N���⍑��i�Łj�Ŋ�b�N���̉��x�����s�����v�Ăł���B��̓I�ɂ́C�����N�������z���Ċ�b�N���̑��z�ɐU��ւ�������[�u���s���C�}�N���o�σX���C�h�̊��Ԃ�Z�k����i2033�N�ɏI���j�Ƃ����Ăł���B�}�\���̋�̓I�Ȑ����́C�����J���Ȏ��Z�����ɂ������t�����i������֗��j�╉�S�̕ω��ł���B
�܂��̓T�����[�}���{�l�i��Q����ی��ҁj�̏ꍇ�����Ă݂悤�B�����J���Ȏ��Z�ł́C�T�����[�}���{�l���Ƃ��̔z��҂ł����Ǝ�w�̕������Z�����x�[�X�ŋ��t������������Ă���B�������C���̂悤�Ȃ�����u���f�����сv�͂��͂�ɂ߂ă��A�P�[�X�ł���C�T�����[�}�����т̔N���������݂邽�߂̕W�����f���Ƃ��Ă͕s�K�ł���B�����ŁC�����ł͂��V���v���ɃT�����[�}���{�l�̂P�l���Ŏ����Ă���B�������w�Ə�����Ă���̂��T�����[�}���̕��ϓI�Ȏp�ł���B
�T�����[�}���{�l�̔N���́C��b�N���ƌ����N���̏�����ᕔ������\������邪�C�����N�������z��������Ɋ�b�N�������������̂ŁC������֗���37.75������39.05���ɕω����C�N��������3.4���|�C���g�̔����ƂȂ�3�j�B����C���S�͌��݂�18.3���̕ی������̂܂ܕς��Ȃ����C��b�N���z��������ƁC���̍����̔������߂鍑�����������B����Ƃ͐ŋ��̂��Ƃł��邩��C�������̔P�o�̂��߂ɂ����ꉽ���̐ŗ��������グ����Ȃ��B�����炭�͏����ł����łƂȂ낤���C���̕����l������C���ϓI�ȃT�����[�}���̑����́C�قڃg���g���ƌ������Ƃ���ł��낤�B
�����Ƃ��C�T�����[�}���ł��Ꮚ���w�̏ꍇ�ɂ́C�N���z�ɐ�߂��b�N���̊������傫������C���̑������ʂ̕����傫���Ȃ邾�낤�B�܂��C�Ꮚ���w�ł́C��������ɑΉ�����ŗ��������グ��ꂽ�Ƃ��Ă��C���̐ŕ��S�͏������ł��낤����C��⓾�ƌ�����B�t�ɁC�T�����[�}���̍������w�́C�N���z�ɐ�߂��b�N���̊������������C�ŕ��S���傫���ƍl������̂ŁC��⑹�ƂȂ邾�낤�B
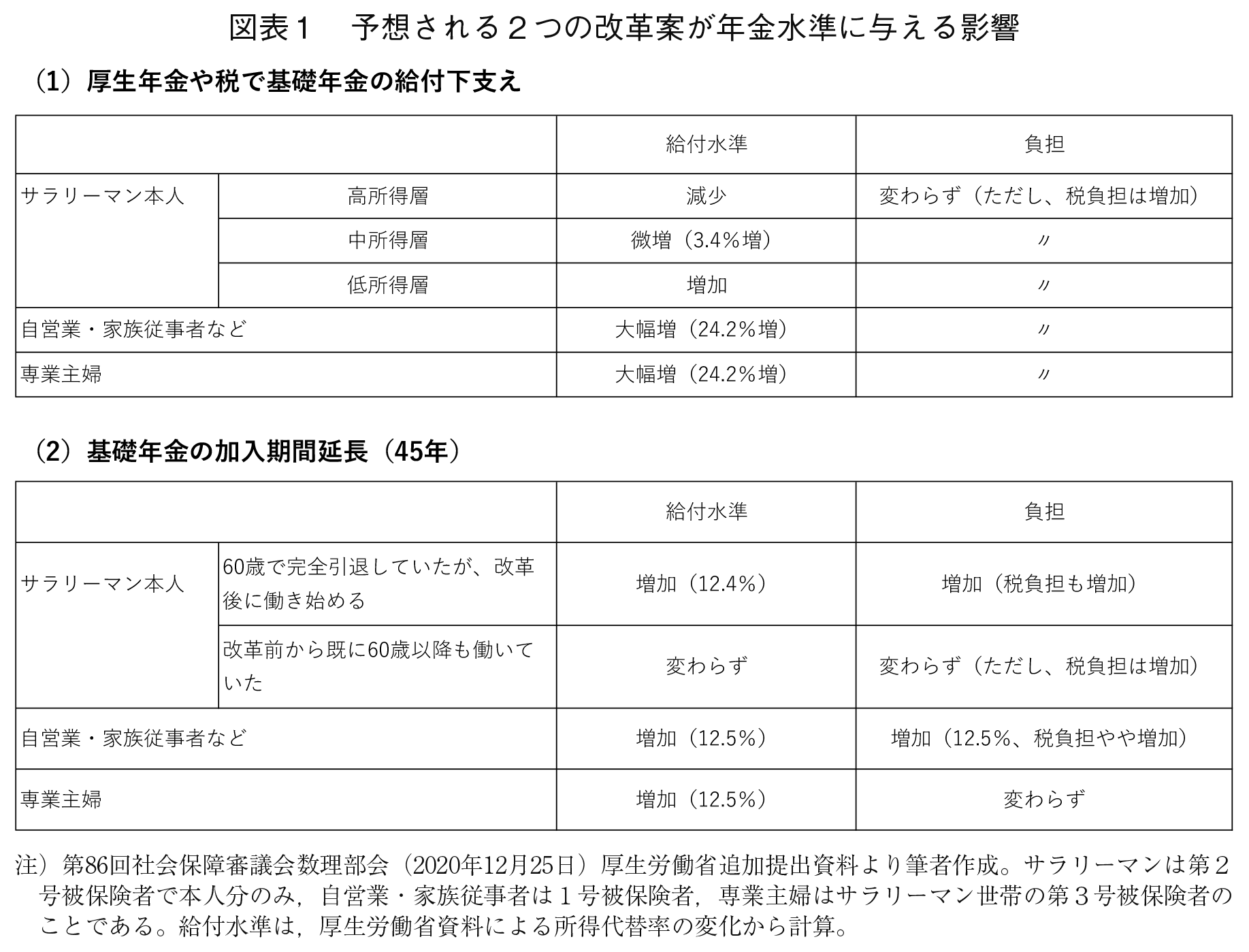
����C��b�N���i�����N���j���������Ă��鎩�c�Ǝ҂₻�̉Ƒ��]���҂Ȃǁi��P����ی��ҁj�C�T�����[�}�����т̐�Ǝ�w�E��Ǝ�v�i��R����ی��ҁj�́C��b�N�����z�̏ꍇ�̏�����֗���13.25������16.45���ɑ�������̂ŁC���t������24.2���|�C���g����������4�j�B�����̐l�X�́C��������̐ŕ��S�����������͂��Ȃ̂ŁC���̉��v�ɂ���đ傫����������ƌ�����B�����C���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́C�����瓾�Ƃ͌����Ă��C���̔�r�̏o���_�́C�����܂łR����팸������b�N���ł��邱�Ƃł���B���݂̋��t�����ɔ�ׂ�C���v��ł��ˑR�Ƃ��ĒႢ�N�������ɂƂǂ܂�B
2.2�@�������Ԃ̉�����
���ɁC�i�Q�j�̊�b�N���̉������Ԃ�����������v�Ă����Ă݂悤�i�}�\�P�̉��i�j�B�����Ƃ��C����͉ʂ����ĉ��v�ƌĂׂ�悤�ȑ㕨�Ȃ̂��ǂ����킩��Ȃ��B�P�ɁC��b�N��������Ȃ��Ȃ�̂ŁC�ی����������Ă�����āC���̑����ɂ��Ă��炨���Ƃ��������̂��Ƃł���B���ꂾ���̂��Ƃł���C��b�N���̐��x�ύX�ł͂Ȃ��Ă��C�����N������ɓ����Ă��������C���Ԃ̌l�N���ɉ������Ă��炤���ƂƖ{���I�ɂ͕ς��Ȃ��B�����C��b�N���̍����̔����͍���i�ŋ��j�Ȃ̂ŁC�ŕ��S���オ��Ƃ������ʂ����Ȃ���C�ی����Δ�̔N�y83�Łz �����t�z�͓��Ȃ��̂Ɍ����悤�B���́C���݂ł������N���ɂ́C�C�Ӊ������x�Ƃ������̂�����C60�Έȍ~���ی������x�����āC�N���z�̑����ɂ��邱�Ƃ��ł���B�����Ƃ��C���̗��p�́C60�܂łɘV���b�N���̎��i�����Ă��Ȃ��l��C40�N�̔[�t�ϊ��Ԃ��Ȃ����ߘV���b�N���z�ł��Ȃ��l�Ɍ�����B���̔C�Ӊ������x�z�҂ɍL���C�C�ӂł͂Ȃ��������x�ɂ��鐧�x�����Ƃ����߂ł���B
�����C���̌��ʂɊւ��āC�����J���Ȏ��Z�̒̎d���͂�₠���Ƃ��B�����J���Ȏ��Z�ł́C�T�����[�}���ɂ��āC60�Ŋ��S���ނ��C���̌�C�d����S�����Ă��Ȃ��l���z�肳��Ă���B�����āC���̉��v���s��ꂽ���Ƃɂ��C�}�ɘJ���ӗ~�ɖڊo�߂�60�Έȍ~65�܂Ő��Ј��Ƃ��ē����n�߂�Ƃ����B���̏ꍇ�C���R�̂��ƂȂ���C��b�N���ƌ����N�����_�u���ő����邩��C������֗���39.05������43.9���ւƕω����C�N��������12.4���|�C���g���̑��z�ƂȂ�5�j�B
�������C�ی������T�N�������x�������C���ɏq�ׂ��悤�ɁC��b�N�������̔����͍���ł��邩��C�ی����������t�z�̑������̕����傫���B����͂�����ŋ����ɔ��f�����͂������C���Ȃ��Ƃ����v�����̍���҂����S����̂͂��̈ꕔ�ł��낤�B���������āC���̐l�X�̑����͂�⓾�ƌ�����6�j�B�����Ƃ��C�����J���Ȏ��Z�̑z��̂悤��60�Ŋ��S���ނ���T�����[�}���́C���͌��݁C����قǑ����͂Ȃ��B�唼�̐l�X��60�Έȍ~�����炩�̌`�œ��������Ă���B�}�\�Q���݂�ƁC2021�N�x���ς�60����64�̐l���̂����C74�����J���͐l���ł���C72�������ۂɏA�Ǝ҂ł���B���̂����C�x�Ǝ҂⎩�c�Ǝ҂������C62�����T�����[�}���i�ٗp�ҁj�ƂȂ��Ă���B���̂悤�Ȏ��Ԃ��݂�ƁC����i2021�j7�j����������悤�ɁC�����J���Ȃ����Z�őz�肵�Ă���l�X�͂��Ȃ�̃��A�P�[�X�ƌ����邾�낤�B
�����ŁC60�Έȍ~�����ɓ����Ă���W���I�T�����[�}���ɂ��Č��Ă݂悤�B60�Έȍ~�̌����N���̕ی�������18.3���ƁC59�Έȉ��̐l�X�ƕς��Ȃ��B���̕ی������ɂ͊�b�N�����̕ی������܂܂�Ă���ƍl������̂ŁC60�Έȍ~�������T�����[�}���́C���Ɍ��݁C��b�N�����̉������ԉ������s���Ă���悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł���B���������āC���v���s���Ă��C�����I�ɉ����ς��Ȃ��B�ނ���C���v�ɂ���Ċ�b�N���̍��ɕ��S����d�����߂̐ŗ������グ���s����C��⑹�ƂȂ邮�炢�ł���B
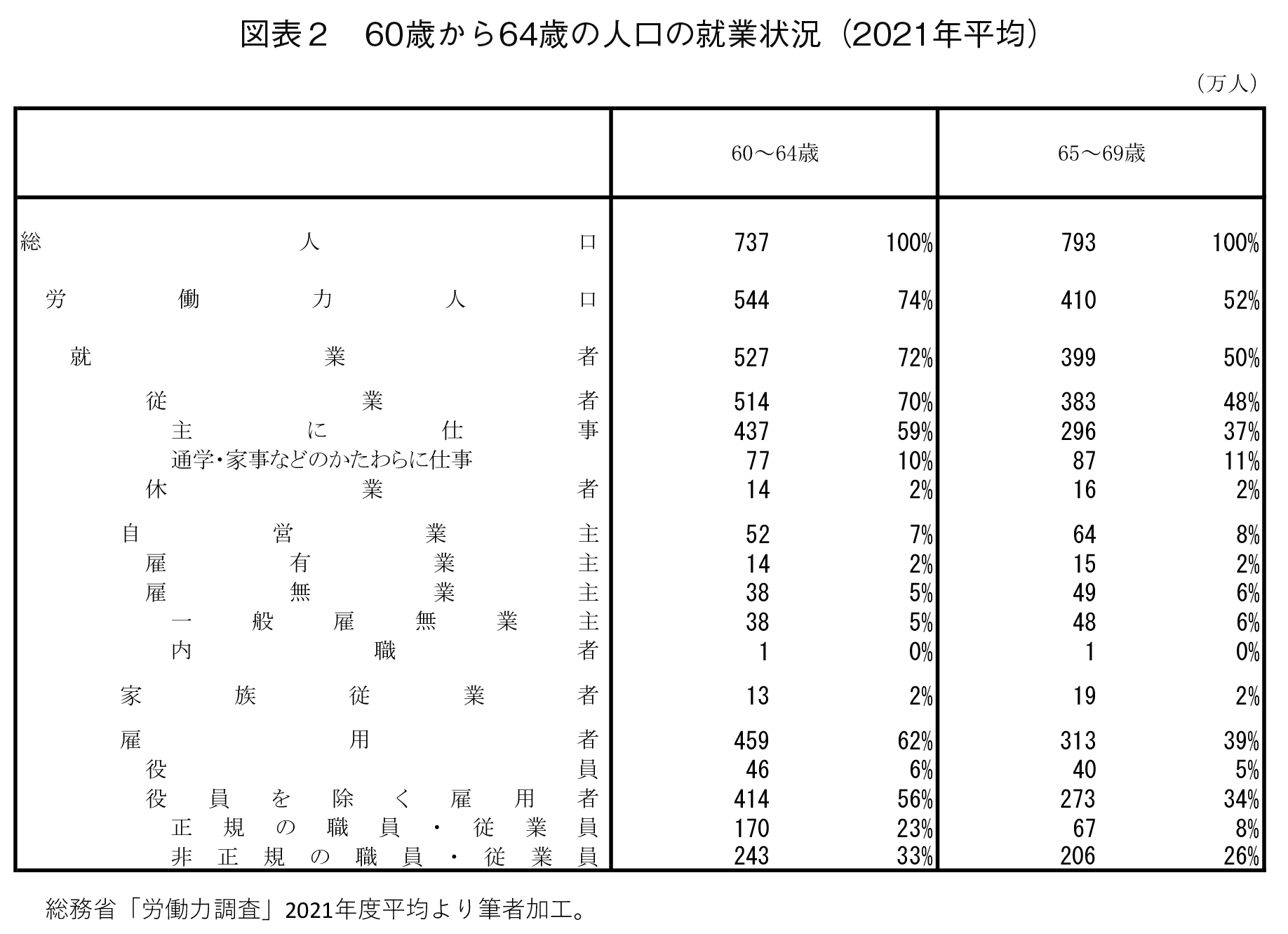
����C��b�N���i�����N���j���������Ă��鎩�c�Ǝ҂Ȃǂ́C��⓾�ƌ�����B��b�N���̉������́C���t�ƕ��S�̗��҂�12.5�������������邪�C���ɏq�ׂ������ŁC���t�����S������B�����I�ɐŋ����ƂȂ��Ă��C�T�����[�}���قǂɂ͑����Ȃ����낤�B�����Ƃ��C���̉��v�ň�ԓ�������̂́C�T�����[�}�����т̐�Ǝ�w�i��v���j�ł���B�ی������S�͂��������Ȃ��̂ŁC���S���͂Ȃ��C���t������12.5��������B
�ȏ�C�Q�̉��v�Ă�����ƁC�T�����[�}���̋]���̉��ɁC���c�Ǝ҂Ȃǂ̍����N�������ҁC��b�N���݂̂̐�Ǝ�w���傫������������v�ł���ƌ����悤�B�����Ƃ��C�������u���Ă����C��b�N���̋��t�����͂R������������C��Ǝ�w�͂Ƃ������C�����N�������҂̒�����͒�N���ɂ���āC�����ی�҂���ʂɏo��\���������B�����ی�͑S�z����ł��邩��C���ǁC�ŋ����ƂȂ��Ă��傫�ȕ��S���T�����[�}�������ɂ̂������邱�ƂɂȂ�B���̈Ӗ��ŁC�����Q�̉��v�ẮC���ɔN�����x�̔��{���v���s��Ȃ��̂ł���C�Œ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��u��D��v�ł��邱�Ƃ͊m���ł���B
3.1�@2004�N�����Ƃ������̌��_
�����C�Q�̉��v�Ă͂܂��ɖ�D��ł���C����ȏ�̂��̂ł͂Ȃ��B����ŏ\���ȉ��v�ɂȂ�̂��ƌ����C����͑傢�ɋ^��ł���B����́C�����̖�D������������l������Ȃ��Ȃ������{�����ɁC�S���Ώ��ł��Ă��Ȃ�����ł���B���{�����Ƃ͉����B����́C�}�N���o�σX���C�h�Ƃ������t�J�b�g�@�\�s�S�Ɋׂ��Ă���C����܂łقƂ�ǎ��{�ł����y85�Łz ���������Ƃł���B�����āC���̋@�\�s�S�ɍ��{�I�Ȏ��ł��Ȃ�����C������}�N���o�σX���C�h��\��ʂ�Ɏ��{���邱�Ƃ͓���B������x�̖�D��ł͂����ɑΏ��s�\�ƂȂ�C����C���x������̖�D����J��Ԃ�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��e�Ղɑz���ł���B�����āC��D����J��Ԃ��Ă��邤���ɁC�ϗ������̂��̂̌͊�����ɗ���Ƃ����ň��̎��Ԃ��l������B�����C���̂�����̎���𗝉����邽�߂ɂ́C�}�N���o�σX���C�h���߂�2004�N�̔N�������ɑk���āC���݂̔N�����x�̏��ۑ���������K�v������B
���āC�u�N��100�N���S�v�����v�Ƃ��Ēm����2004�N�����́C2000�N�㏉���̏������ōs��ꂽ�N�����x�̑�����ł���C���݂Ɏ����{�I�X�L�[�����`���ꂽ�B���̍����ƂȂ���v���ڂ́C���ł͂�������Y����Ă��銴�����邪�C�N�����t�����̑啝�J�b�g�ł���B���Ȃ킿�C����҂̔N���������C2004�N����19�N���x�����Ė�Q���J�b�g����B����ɂ��C�ΘJ�҂����̕ی������S���ߑ�ɂȂ肷���邱�Ƃ�h���C�������Ȃ��Ȃ��Ă����ϗ������Ăѐςݑ����āC�T��100�N��܂ō��̔N�����x���ێ��ł���������Ē������f�s���ꂽ�̂ł���B��̓I�ɁC����2004�N�����ł́C�i�P�j�ی��������Œ�����̓����i�����ɂ킽���ĕی����������グ�����邱�Ƃ��~���C2017�N�̐����ŌŒ�j�C�i�Q�j�}�N���o�σX���C�h�̓����i19�N�ԂŁC�Q�����x�̔N�������J�b�g�j�C�i�R�j��b�N�����ɕ��S�����̂P/�Q�ւ̈����グ�C�i�S�j�����ύt��������L���ύt�����ւ̕ύX�i�Ăѐςݏグ���ϗ����𑁊��Ɏ������C�T��100�N��ɂP�N���̐ϗ������c���j�Ƃ������v���ڂ����{���ꂽ�B
��ʓI�ɁC�N�����v�̎�i�Ƃ��ẮC�i�P�j����w�����S����ی����̈����グ�ƁC(�Q)����҂̔N���J�b�g�̂Q�����邪�C2004�N�����܂ł́C�T�ˁC�O�҂̕ی��������グ���I��Ă����B���[���������C����ɂ���Đl���������Ă��鍂��̗L���҂̓{������Ƃ́C�����ƂɂƂ��đ傫�ȋ��Ђƌ�����B����C���q���ɂ���Đl��������C���[�����Ⴂ����w�C���Ɏ�҂͉��������̔N���Ɋւ��Ă͊S�������B�ی��������グ�Ƃ����`�ŁC����w�ɕ��S��������������v���J��Ԃ���邱�Ƃ́C�����I�ɂ͍����I�ƌ�����B�����ŕی��������グ�Ƃ������v�́C�P�ɔN�����v���s��ꂽ���_�̕ی����������グ�邱�Ƃł͂Ȃ��C�����ɂ킽��ی����̈����グ�X�P�W���[���̍���C����ɋ}�ɂ��邱�Ƃ��Ӗ�����B����w�̒��ł��l���̑��������N�́C�c��̕ی��������Ԃ��Z���C�ی��������グ�̔�Q�����܂�y�Ȃ��̂ŁC�����I�ɉ��v���s���₷���B����ŁC����w�̂����C��҂́C�����ɂ킽���č����ی����ɒ��ʂ��邩��C���ɕ��S���d���Ȃ�B���s�s�Ȃ̂́C�܂����[���������Ă��Ȃ��q�ǂ�������C�܂����܂�Ă����Ȃ������̓��{�l�����ɁC�����Ƃ��ߍ��ȕ��S�������邱�Ƃł���B���̈Ӗ��ŁC2004�N�����܂ł̔N�����v�́C��҂⏫������ւ̕��S�������Ƃقړ��`��ł������ƌ����悤�B
�������Ȃ���C���̕ی��������グ��ӓ|�̉��v�́C2004�N������O�ɂƂ��Ƃ����E�ɒB�����ƍl����ꂽ�B�����̎Љ�ۏ�R�c��E�N������C����܂Œʂ�̕��j��2004�N�������s���ƁC�ی������ǂꂮ�炢�܂ň����グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ������v�Z�����Ƃ���C�����N���̕ی�������2038�N��25.9���ƂȂ�C2004�N��13.58���̂قڂQ�{�ɂȂ�Ƃ������ʂ��o���B�����N���̕ی������C2031�N�x��29,500�~��2004�N��13,300�~����Q�{�ȏ�̈����グ�ƂȂ�B���N�ی�������ی����C�e��̐ŗ��������I�Ɉ����グ���Ă䂭���Ƃ���C����ł͍��������̔����ȏオ�ł�Љ�ی����Ƃ��Ē�������邱�ƂɂȂ�C�����̋ΘJ�ӗ~�ቺ���S�z���ꂽ�̂ł���B�����ŁC2004�N�����ł͕ی��������グ�ɏ����݂��ď����ɂ킽���ČŒ肵�C����ȏ�C�����グ���s��Ȃ����Ƃɂ����i�����N����2017�N����18.3���ŌŒ�C�����N�����y86�Łz 16,900�~�i2004�N���i�j�ŌŒ�j�B
�������Ȃ���C�{���͂����ƈ����グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��ی����̃X�P�W���[�����C�����݂��Ď����I�Ɉ����������̂�����C�N�������̎��x�͑啝�Ɉ������āC�N�������������I�ɔj�]���Ă��܂��\��������B�����ŁC�����h���[�u�Ƃ��Ă܂��l����ꂽ�̂��C��b�N���ւ̐ŋ������z�𑝂₷�Ƃ�����i�ł���i���ɕ��S�����̂P/�R����P/�Q�ւ̈����グ�j�B���ɁC���݂���ϗ����𑁂߂Ɏ������āC����������Ƃ����[�u�����ꂽ�i�L���ύt�����j�B�������Ȃ���C����ł��S������������Ȃ����߁C��Q�����̔N�����t�J�b�g�Ƃ�����Ȃ����U����邱�ƂɂȂ����̂ł���B���ꂱ�����C�u�}�N���o�σX���C�h�v�ƌĂ�鐧�x�ł���B
�����C����҂�����قǑ傫�ȔN���J�b�g�����̂܂����͂����Ȃ����C����̗L���҂�{�点�邱�Ƃ͐����I�Ƀ��X�N���傫���B�����ŁC����҂������Ȃ�ׂ��h�����Ȃ��悤�Ȑ��x��̍H�v���s��ꂽ�B�܂��C�N���J�b�g�ɔ��ɒ������Ԃ������C�������s�����ƂƂ��ꂽ�B���Ԃ�������C�P�N������̃J�b�g�������Ȃ����邱�Ƃ��ł���B�����̌v��ł́C2004�N����2023�N�܂ł�19�N�Ԃ������C�P�N���Ƃɂ�������0.9�����J�b�g���Ă����ƂɂȂ����B
�����ŏd�v�Ȃ��Ƃ́C2004�N���_�Ŋ��ɍ���҂������l�͂Q�����J�b�g����Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�Ⴆ�Ύ���������19�N�ł���C�͂��߂̔N�̔N���J�b�g�͂킸��0.9���ŁC����ƃJ�b�g�����傫���Ȃ��āC�S���Ȃ钼�O�ɂ���ƂQ���J�b�g�ƂȂ�B�܂�C���ϓI�ɂ͔����̂P���J�b�g�ōςށB�J�b�g�����ő�ƂȂ�̂́C����2023�N�ȍ~�̍���ҁC�܂�2004�N���_��45�Έȉ��̐l�X�ł���B���̐l�����͔N���J�n����S���Ȃ�܂ł����ƂQ���J�b�g�ł���B�v����ɁC���̔N���J�b�g�̎�ȑΏێ҂́C�܂����Ă�����w��q�ǂ��C��������ł���C�ی��������グ�قǂł͂Ȃ����C��͂�ނ�ւ̕��S�摗��Ƃ������ʂ����邱�Ƃɕς��͂Ȃ������B
����ɁC��X����ƂȂ����̂́C�N���̖��ڋ��z���}�C�i�X�ɂ��Ȃ��Ƃ������x�v�ɂ��Ă��܂������Ƃł���B���Ȃ킿�C�����㏸�����}�C�i�X�ƂȂ�f�t���̔N�ɂ́C�N���J�b�g���s��Ȃ��i�����㏸���̏������f�B�X�C���t���̔N�ɂ̓J�b�g��������������j�Ƃ����������C�}�N���o�σX���C�h�ɕt���Ă��܂����B����́C����҂����̉ݕ����o�𗘗p���C�N���J�b�g���C�Â���ɂ������邽�߂̑[�u�ł������ƍl������B
����ł́C�f�t���ŔN���J�b�g���ł��Ȃ���ǂ��Ȃ�̂��B�N���J�b�g�͗��N�ȍ~�ɐ摗�肳��C20�N�Ԃ̃J�b�g�̊��Ԃ����̂܂܌ジ�ꂷ�邱�ƂɂȂ�B���̂��Ƃ��C�����J���Ȃ̓}�N���o�σX���C�h�́u���������@�\�v�Ə̂��Ă���B�f�t���Ōv�悪�������Ƃ��Ă��C�҂��Ă��������J�b�g�ł���̂�������Ȃ��Ƃ����̂������J���Ȃ̗���Ȃ̂����C���͂���͑���ł���B
�N���J�b�g�̊��Ԃ��ジ�ꂷ�����قǁC���݂̍���҂͔N���J�b�g����Ƃ�C���̐摗�肵�����S�͎�҂⏫������ɉ��������邱�ƂɂȂ�B����ɁC�f�t�������������C���̔N���J�b�g���Ԃ̐摗�肪���X�ƌJ��Ԃ����C�����������ǂ�ǂ�i��ŁC�N���������s���l�܂�B�J�b�g�ł����҂��Ă��邤���ɁC�ϗ�������Ɍ͊����Ă��܂����Ԃ�������蓾��̂ł���B���̈Ӗ��ŁC���́C�}�N���o�σX���C�h�͎��������ł͂Ȃ��C�u�����摗�葕�u�v�ƌĂԂׂ����̂ł���Ɨ�i2020�j�͎咣���Ă���B
2004�N������̓��{�o�ς̕��݂��ǂ��Ȃ����̂��́C���߂Đ�������܂ł��Ȃ��ł��낤�B���̌�������f�t���o�ς������C�悤�₭�Ƀf�t����E�p����̂́C2012�N������n�܂�A�x�m�~�N�X��҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�������Ȃ���C2014�N�S���ɏ���ł��T������W�����y87�Łz �����グ�����Ƃ��@�ɁC�Ăьo�ς���ѕ����͒�����C�����������ƒE����^�C�~���O�ŁC�R���i�ЂɌ�����ꂽ�B���������āC2004�N�x���猻�݂܂ł̊ԂŁC�}�N���o�σX���C�h�������C�N���J�b�g�������ł����N�͂킸���R�N�ԁi2015�C2019�C2020�N�x�j�ɂ����Ȃ��B�����ł����J�b�g�����C2015�N����0.9���ł��������C2019�N�x��0.5���C2020�N�x�͂킸��0.1���ł���B2023�N�x�̓R���i�Ђ�V�A�̃E�N���C�i�N�U�������E�I�ȃC���t���ɂ��C�S�x�ڂ̃}�N���o�σX���C�h�����������\��ł��邪�C���̏������I�ɑ����Ƃ͎v���Ȃ��B
�����ŕs�v�c�Ɏv�����Ƃ́C����1999�N����C�����㏸���͂����ƃ}�C�i�X�ł��������Ƃł���B2004�N�����S�Ƀf�t�����ɂ������ɂ�������炸�C�f�t�����ł̓}�N���o�σX���C�h�����Ȃ����[����������̂͂Ȃ��Ȃ̂��낤���B���̌�C�܂���10�N�ȏ���f�t���������Ƃ͑z���ł��Ȃ������ɂ���C�����J���Ȃ́C���炭�f�t�����������Ƃ�e�Ղɗ\�z�ł����͂��ł���B
3.2�@��ԉ������ߏ苋�t
������ɂ���C���́g�����摗�萧�x�h�̂����ŔN���ɉ����N���Ă���̂��ƌ����C2004�N�����̍����ł���N���J�b�g���S���i�܂��C����҂ւ̉ߏ苋�t�����N���u����C���������ꍏ�ƈ������Ă���Ƃ��������ł���B�}�\�R�́C����҂����N�������i������֗��j���C2004�N�����̌v��ƁC���ۂ̐��ڂ��r�������̂ł���B
2004�N���_�̔N�������́C����w�̏����Δ�Ŗ�U���i59.3���j�̐����ł��������C�}�N���o�σX���C�h���g����2023�N�܂łɖ�T���i50.2���j�ɍ팸����̂��C2004�N�����̌v��ł������B�Ƃ��낪�C�����ɂ͂ǂ��Ȃ������ƌ����C�ނ���N�������͏㏸���Ă��܂��Ă���C2019�N��61.7����2004�N���_�������������ł���B�܂�C����61.7������2019�N�̌v��ł���51.6��������������10���قǂ����݂̍���҂ւ̉ߏ苋�t�ƂȂ��Ă���C���̕��C�N�������ɗ\��O�̎x�o�������Ă���̂ł���B
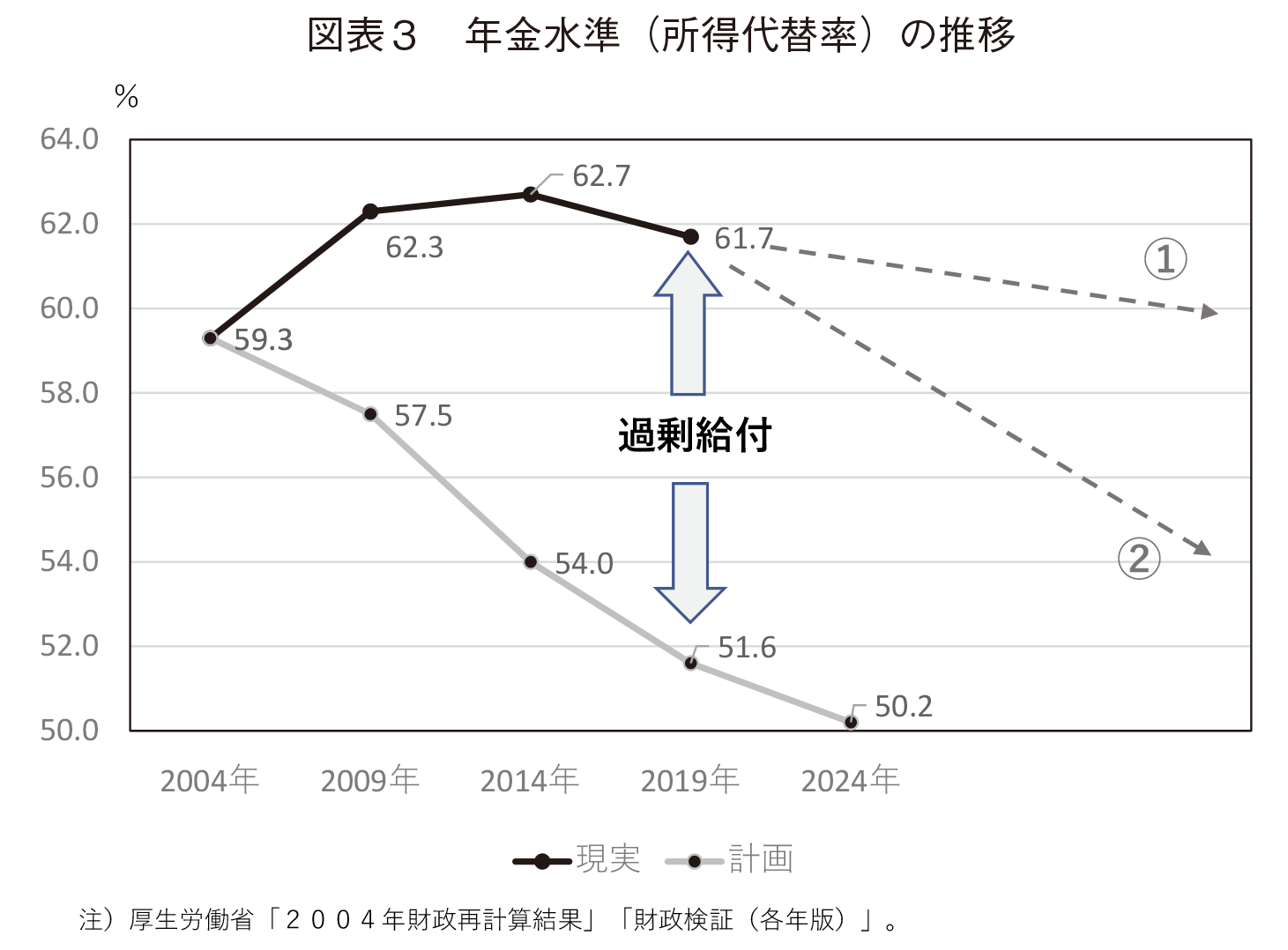
���Ƃ��ƕی����X�P�W���[�������������ɁC�N���J�b�g����Ƃ����v��Ȃ̂�����C�J�b�g���ł��Ȃ���ΔN�������͈����̈�r�����ǂ�B���R�C�T�N�ɂP�x�̍������ň������ʂ��o�邱�Ƃ͊m���ł���B�����Ȃ�ƁC�}�X�R�~���}����̖Ҕᔻ���o�邱�Ƃ͕K���ł��邵�C100�N���S�Ƒ匩���������O�C���̊Ŕ𑁁X�ɉ��낷���Ƃ͐��{�Ƃ��Ă��_���[�W���傫���B�����ŁC���̐��{�C�����J���Ȃ��I�����Ă��܂����̂́C��������s���悢�o�ϑO��ő��삷��Ƃ�����i�ł���C��i2010�j�́C�����N�������́g�������Z�h�ƌĂ�ł���B
�}�\�S�́C2004�N�����Ŏg��ꂽ�o�ϑO��ƁC���̌�̍������Ŏg��ꂽ���̂��r�������̂ł���B�����J���Ȃ͂T�N�ɂP�x�̍������ŁC�ϗ����̉^�p�����╨���C�����㏸���Ȃǒ����I�Ȓl��z�肵�C�������g���Đϗ�����100�N��܂Ō͊������C�N�����x���ێ��ł��邩�ǂ������`�F�b�N���Ă���B2004�N�̌o�ϑO����݂�ƁC�^�p�����3.2���C�����㏸��2.1���C�����㏸��1.0���ł��邩��C���̎��_�ł��C���Ɋ�]�I�ϑ��̓������Â��V�i���I�ł���ƌ����邾�낤�B���̎��C���Ƀf�t�����T�N�ԑ����Ă������Ƃ�C����炪100�N��܂Ŏg���钷���I�z��l�ł��邱�Ƃ��l����C�{���͂����ƍT���߂ȑz��l�ɂ��ׂ��������Ǝv����B
�������C�����J���Ȃ̊�]�I�ϑ����悻�ɁC���̌���f�t���͑����C���q�����i�B�����āC2008�N�H����̓��[�}���V���b�N�����{�o�ς��P���C���̌�C���N�ԁC���{�o�ς͒�����邱�ƂɂȂ�B���R�C�����܂ł̏f���邾���ł��C�N�������͑����̈��������Ă���ł������B�Ƃ��낪�C�����J���Ȃ�2009�N�Q���ɍs����2009�N�������ɂ����āC�o�ϑz��l������Ɋy�ϓI�ȃV�i���I�ɕύX���C100�N���S���ۂ���Ă���Ƃ������_���o�����̂ł���B���Ȃ킿�C�ϗ����̉^�p�����̑z���0.9�������グ�C4.1���Ƃ����B�������N��0.9���̈����グ�Ǝv����������Ȃ����C100�N�߂������܂Ŏg����o�ϑO��ł���B100�N�߂��ԁC�����v�Z�ő����Ă䂭���߁C�l�X�̑z������ϗ����̑������N����v�Z�ƂȂ�C�f�t����[�}���V���b�N�̉e����҉āC�N�������ɑ��۔��������Ă��܂����̂ł���B
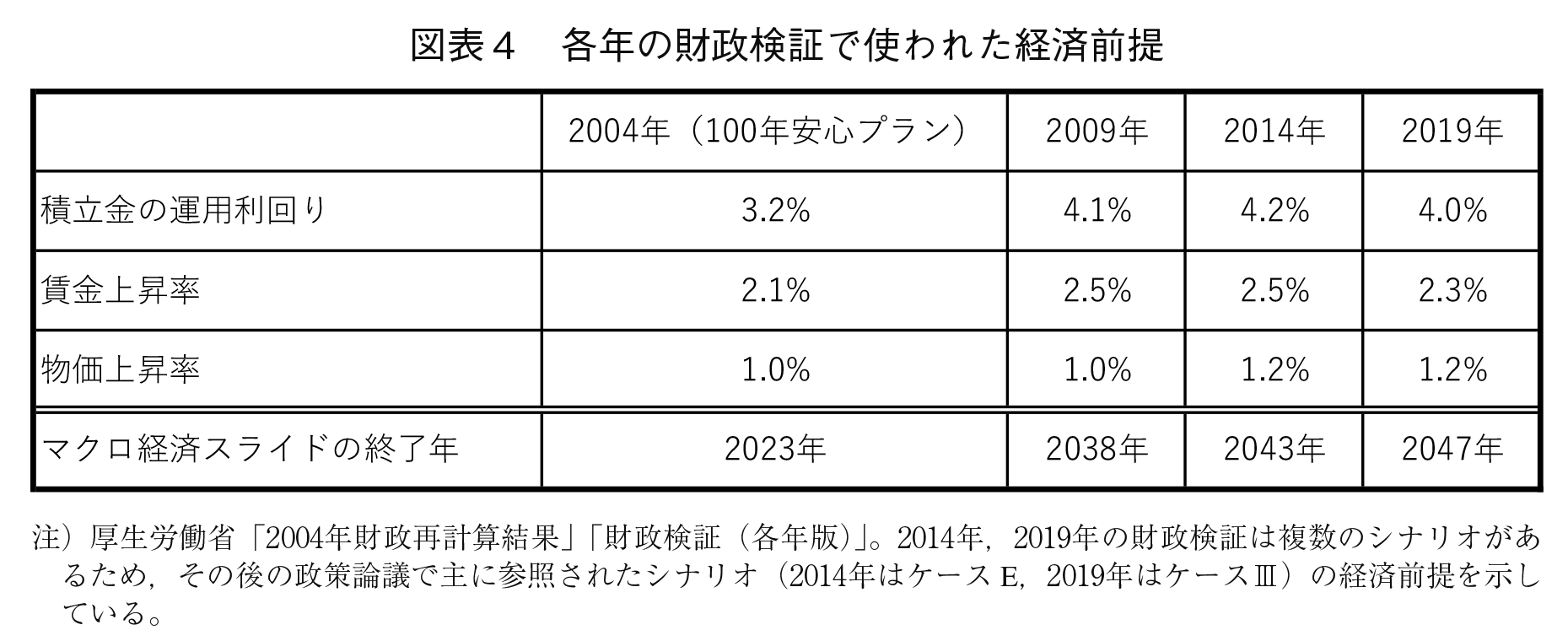
���̌�C���[�}���V���b�N�̉e���Ɩ���}�������̃f�t���o�ρC�����āC2011�N�R���ɂ͓����{��k�Ђ��N�����B�N�������͂���Ɉ����̈�r�����ǂ����̂����C2014�N�̍������ł͉^�p�����̑z��l�������4.2���Ɉ����グ�C100�N���S���ۂ���Ă���Ƃ������_���Ăѕێ������B�����āC2019�N�̍������ł́C�A�x�m�~�N�X�Ōo�ς⊔�����������������Ƃ��āC�^�p�����z���4.0���Ƃ�≺���邱�Ƃ��ł������C����ł��C���Ƃ��Ƃ�3.2�����猩�y89�Łz ��C�ˑR�Ƃ��ĊÂ�����o�ϑO��ł���B
���Ȃ݂ɁC2014�N�C2019�N�̍������ł́C�����J���Ȃ͂��ꂼ�ꕡ���̃V�i���I����Ă��邽�߁C�}�\�S�ɂ́C�Љ�ۏ�R�c��E�N������ȂǁC���{���̋c�_�Ŏ�Ɏg��ꂽ�o�ϑO��̃V�i���I�i2014�N�̓P�[�XE�C2019�N�̓P�[�X�V�j�̌o�ϑO��������Ă���B�ǂ�������_�́C100�N���S���p�����Ă���Ƃ������̂ł���B
�����C���ڂ��ׂ��́C�����܂Łg�������Z�h�𑱂��Ă��C�}�N���o�σX���C�h(��b�N���̃}�N���o�σX���C�h)�̏I���N���啝�ɐL�тĂ��邱�Ƃł���B2019�N�̍������ł́C����2047�N�܂ŏI���N���摗�肳��Ă���i���ɏq�ׂ��悤�ɁC2020�N�̌����J���Ȏ��Z�ł�2046�N�ɉ��߂�ꂽ�j�B����ł�2004�N�̔N���҂����́C�قƂ�ǔN���J�b�g�����ɐ��U���I���邱�ƂɂȂ�B���̑���ɑ傫���J�b�g�����̂́C�����̍���ҁ|�܂�C���݂̌���w�ł���B����ł́C�]���̕ی��������グ��Ɖ���ς�炸�C2004�N�����ŔN���J�b�g�ɓ��ݐ����Ӗ����قږ����Ȃ��Ă��܂��Ă���B
3.3�@�N�������̎���
���܂�m���Ă͂��Ȃ����C���́C2014�N��2019�N�̍������Ō����J���Ȃ������������V�i���I�̒��ɂ́C100�N���S��ے肵�Ă��錵�������ʂ̂��̂�����B2014�N�̍������ł͂W�̃V�i���I�̂����R�C2019�N�̍������ł͂U�̂����R���C����20�`30�N�̊Ԃ�100�N���S�Ɩ��ł��ꂽ���݂̔N���X�L�[�����I������Ƃ������_�ɂȂ��Ă���B���Ȃ킿�C100�N�Ԑϗ������ێ����邽�߂ɁC�N���J�b�g���C������֗�50��������鐅���܂Ŏ��{������Ȃ��Ȃ�̂ŁC���s���x�͈�U�C�I���Ƃ������ƂɂȂ�B��̓I�ɁC2019�N���������������}�\�T���݂�ƁC�U�V�i���I�̂����C�P�[�X�T����V�́u100�N���S�v�Ƃ������_�����C�P�[�X�W����Y�͍���20�N���x�Ő��x���I�����錋�_�ɂȂ��Ă���B���Ȃ݂ɁC100�N���S�V�i���I�̐ϗ����̉^�p�������݂�ƁC�P�[�X�T��5.0���C�P�[�X�U��4.5���C�P�[�X�V��4.0���ƁC���炩�ɊÂ�����V�i���I�ł���B
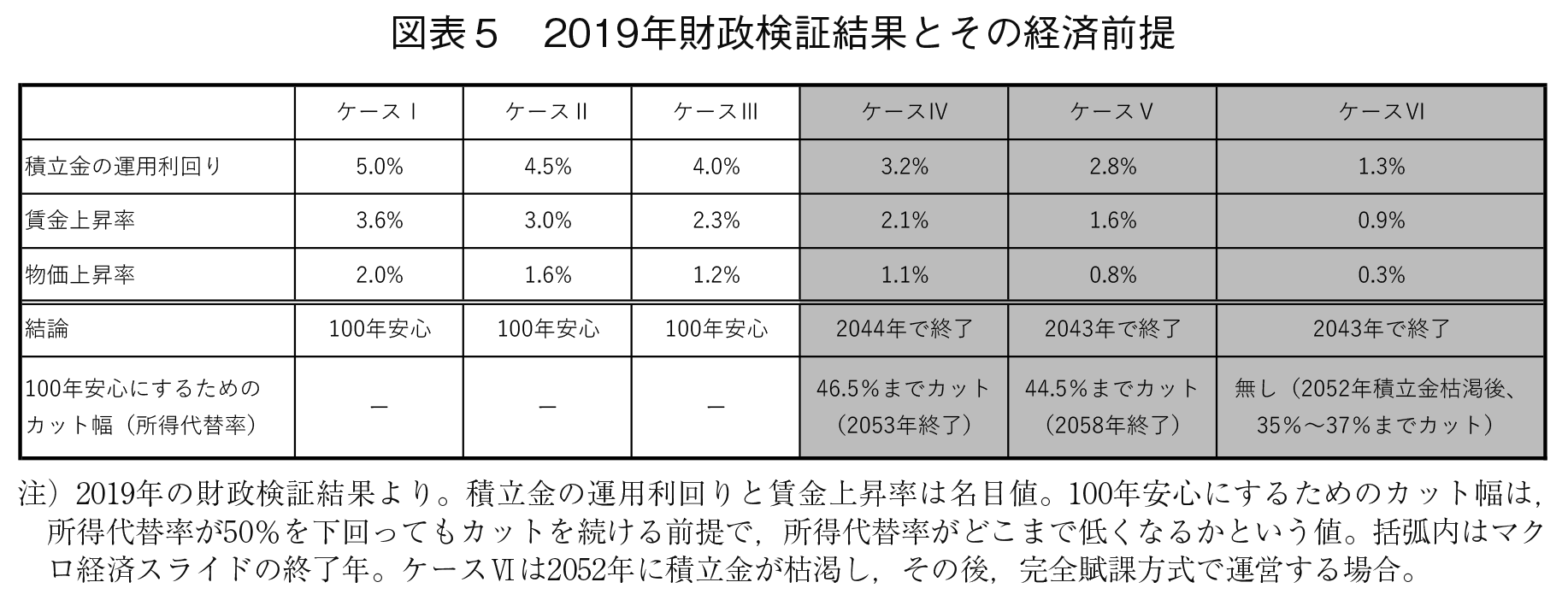
�����I�Ȃ̂͂ނ���C�Ԋ|���������P�[�X�W����Y�ł���ƌ����悤�B�P�[�X�W�̌o�ϑz���2004�N���������̌o�ϑz��ɍ������Ă��邩��C100�N���S�v�����̌���]���Ƃ��āC�܂�����ׂ��V�i���I�ł���B�����C���̌�̓��{�o�ς̐��ݐ������ቺ���l������C�ނ���P�[�X�X�̕�����{�V�i���I�Ƃ��Ăӂ��킵���ƌ�����B
�y90�Łz�����C�P�[�X�W���P�[�X�X���C���ƂȂ��Ă͒v���I�Ȗ�肪����B����́C�ǂ�����}�N���o�σX���C�h�ɂ��N���J�b�g���C������قڒ����ɐi�߂���Ƃ������Ƃ�O��Ƃ����V�i���I�ł��邱�Ƃł���B�����ŁC������x�C�}�\�R�����Ă݂悤�B�}�N���o�σX���C�h���i�ނƂ����̂́C���̐�C�A�̓_���̖��̂悤�ɔN�����J�b�g����Ă䂭�Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���B����͉ʂ����Č����I�ƌ�����ł��낤���B���ɐ��������悤�ɁC2004�N����2019�N�܂ŁC��x��������֗���������ꂽ�������Ȃ��̂ł���B����܂łł��Ȃ��������Ƃ��C�Ȃ�����C�}�ɂł���悤�ɂȂ�Ƒz��ł���̂��B�������C���݂͂��܂��܁C���E�I�ȃC���t�����ă}�N���o�σX���C�h�������ł���ƂȂ��Ă��邪�C���{�o�ς̐��ݐ��������l����ƁC�����I�ɂ͇@�̖��̂悤�ɋ��t�J�b�g���i�܂Ȃ��V�i���I��z�肷����������I�ł͂Ȃ����낤���B
�����Ȃ�ƁC���̓P�[�X�Y�̃��[�X�g�V�i���I���\���ɉ\��������z��ł���B�P�[�X�Y�̏ꍇ�C�Ⴆ�C������֗�50�����ĔN���J�b�g�𑱂��Ă��C���͂�100�N��܂Őϗ������ێ��ł��Ȃ��Ȃ�B2052�N�ɐϗ������͊����C���̌�́C���S���ە����Ɉڍs������Ȃ��B���S���ە����Ƃ́C����w���璥���ł���ی����͈͓̔��ɍ���҂̔N�����t���i��Ƃ������Ƃł���C���̎��̏�����֗���35�`37���ɂȂ�Ǝ��Z����Ă���B�܂�C���݂̔N���z�̔������܂ŋ��t�J�b�g�����i�^��U�邤���ƂɂȂ�B�摗��̃c�P����C�Ɏx���킳���̂�2052�N�̍���҂����C�܂�C���̎�҂⏫�����ソ���ł���B
���́C�}�N���o�σX���C�h�ɂ��N���J�b�g���i�܂��C���̌��ʂƂ��Ėc��ȕ��S����҂⏫������ɉ��������Ă��邱�Ƃ́C�������̕ʂ̎���������͂�����Ɗm�F�ł���B����̍������̊֘A�����ɂ́C�����J���Ȃɂ���Čv�Z���ꂽ���I�N���̃o�����X�V�[�g���f�ڂ���Ă���i�����J���ȁi2019b�j�j�B�N����v�̃o�����X�V�[�g�́C��Ƃ̃o�����X�V�[�g�i�ݎؑΏƕ\�j�Ɠ��l�C�����Ɏ��Y�C�E���ɕ������ނ��ꂽ�\�ŁC�K�����E�̋��z����v����悤�ɍ���Ă���i�}�\�U�j�B
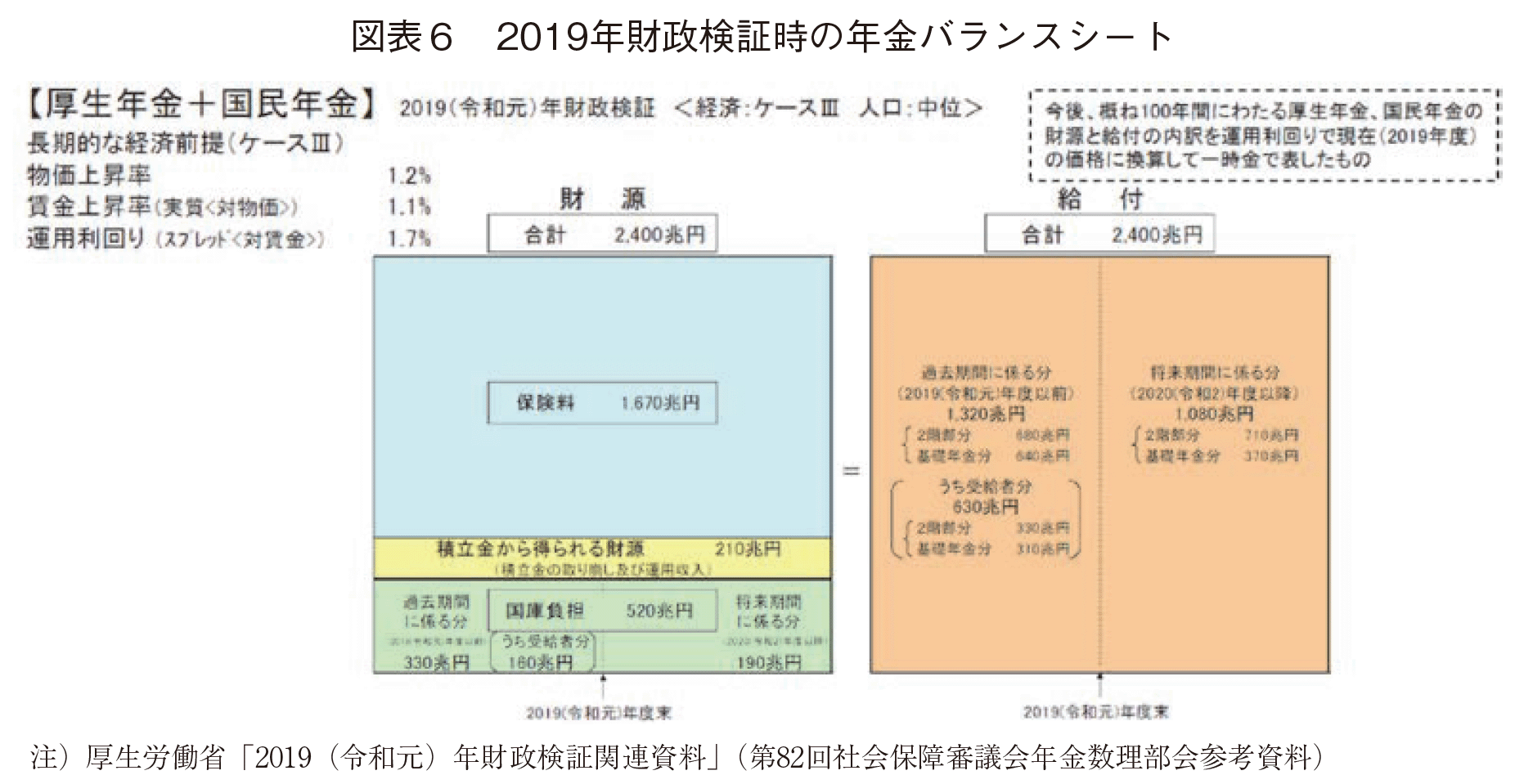
�N���ɂƂ��Ď��Y�Ƃ́C�������璥������ی����Ɛŋ��i���ɕ��S�j�C�����Đϗ����i�^�p�������܂ށj�ł���B����C���Ƃ́C���ꂩ�獑���Ɏx�����N���̑��z�ł���C����܂Ŏx�������ی����ɑΉ�����N�����t�i�ߋ����j�ƁC���ꂩ��x�����ی����ɑΉ������N�����t�i�������j�̂Q�ɕ����邱�Ƃ��ł���B�܂Ƃ߂�ƁC�����̒ʂ�ł���B
�@�ی����{���ɕ��S�{�ϗ������ߋ����{�������E�E�E�i�P�j
���̎����ڍ����Đ�������Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
�@�ߋ����|�ϗ������ی����{���ɕ��S�|�������E�E�E�i�Q�j
�����ŁC���ӂ́u�ߋ����|�ϗ����v�́u�N�������v�ƌĂ��B�N�������Ƃ͂܂�C�u���݂̔N�����ҁi�N���̎��i�������ɍ���ҁj�ɁC���ꂩ��ނ炪���ʂ܂ł̊ԁC�����x�����\��̔N�����z�v����C�u���̎x���������Ƃ��ĉߋ��ɔނ炩�璥�����Ă����ی����̑��z�v�������������l�ł���C�v����Ɍ��݂̔N�����҂́u���炢���v�i�ی����x�����z�����N���̎��z�̕����������j�̋��z�ł���B���̋��z�͌��݁C1110���~�i1670���~�|210���~�j�ɂ�����Ă���B
����C�E�ӂ́u�ی����{���ɕ��S�|�������v�́u���������S�v�ƌĂ��B����́C�u���݂̌���w����я������オ���ꂩ��x�����ی����Ɛŋ��i���ɕ��S�j�v����C�u�ނ炪�����Ɏ��\��̔N�����z�v�������������l�ł���C�v����Ɍ��݂̌���w����я�������́u�x�������v�̋��z�ƂȂ�B���ӂƉE�ӂ͓���������C�����1110���~�i1670���~�{520���~�|1080���~�j�ł���B�܂�C���̔N���o�����X�V�[�g�������Ƃ��Ă��邱�Ƃ́C���݂̍���҂́u���炢���v�́C�K������w����я�������́u�x�������v�ɂȂ�Ƃ������Ƃł���B���݂̍���҂̃c�P�ł���1110���~���C����w�Ə������オ���ꂩ��K�����킳��邱�ƂɂȂ�B
����ɂ�䂵�����́C���̔N�������z�͍������̂��тɖc�����Ă���Ƃ��������ł���B�}�\�V�́C�e�N�̍������؎�������N���������v�Z���C���̐��ڂ����������̂ł���8�j�B2014�N�ȍ~�͋��ϔN������������Ă��邽�ߒP���ɔ�r�ł��Ȃ����C���̕������������Ă��C�������̓x�ɋ��z���c�����Ă��邱�Ƃ��킩��B�Ȃ��C�c���𑱂��Ă���̂��B���̗��R�͂������C�}�N���o�σX���C�h�ɂ��N���J�b�g���\��ʂ�i�܂��C�N���̉ߏ苋�t�������Ă��邩��ł���B�����āC�������̂��тɃX���C�h���Ԃ����������āC���v��摗�肵�Ă��邩��Ƃ�������B��������̂悤�Ȑ摗��𑱂��Ă��ẮC1110���~���Ă���ɔN���������c��݁C���݂̌���w����я�������ɁC�܂��܂��傫�ȕ��S�𔗂邱�ƂɂȂ邾�낤�B���́C�N���J�b�g�̐摗�肪�C�N�������̖c���ݏo���Ă���Ƃ����Ӗ��ŁC����͕s�Ǎ����Ɠ����\���Ƃ�����B�摗�肷�����قǏ����[�܂�C�����̉��v���傫�Ȓɂ݂����̂ɂȂ�B
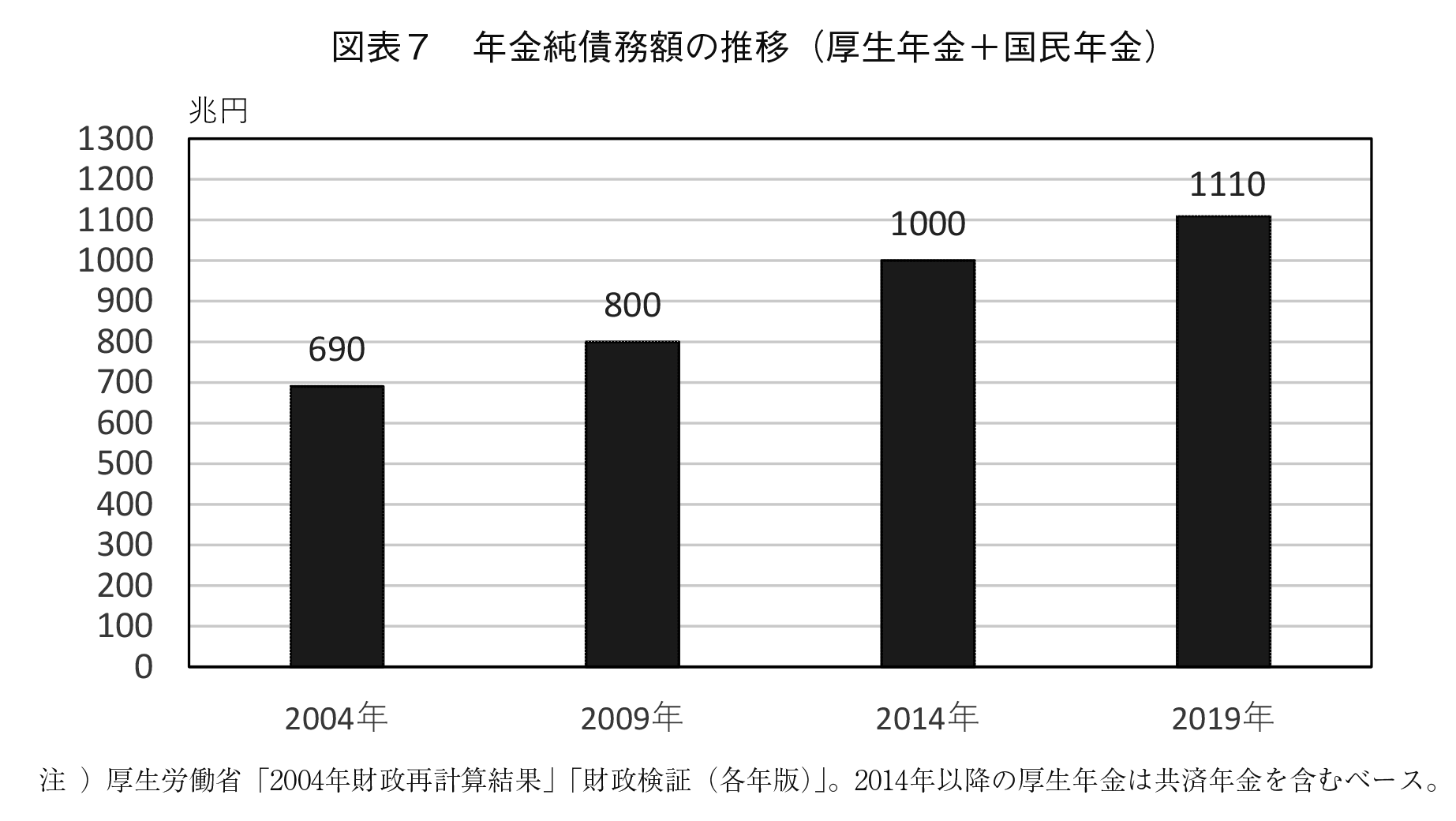
�{�e�͂܂��C2025�N�̎����N�������Ɍ����C���݁C�Љ�ۏ�R�c��E�N������ł̌����������܂��Q�̍����N���~�ψĂ̐����ƕ]�����s�����B�Q�̉��v�ẮC�T�����[�}�������̋]���̉��ɁC���c�Ǝ҂Ȃǂ̍����N�������҂��~�ς�����̂ł���B���������~�ς��s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����w�i�ɂ́C2004�N�����Œ�߂�ꂽ�}�N���o�σX���C�h���@�\�s�S�Ɋׂ��Ă��邱�Ƃ�����B�������C����C��b�N���̑啝�ȔN���J�b�g���\�肳��钆�ł́C�����Q�̉��v�ẮC�Œ���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ���D��ł͂��邪�C�}�N���o�σX���C�h���̂̉��v���s���Ȃ���C���{�I�ȑΏ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��B����C���{�o�ς������J���Ȃ̊Â��o�ϑO������������C����܂œ��l�C�}�N���o�σX���C�h���\��ʂ�Ɏ��{�ł��Ȃ��������C�����̖�D��ł͑S���Ώ��ł��Ȃ��Ȃ邾�낤�B�����āC����܂ł̌o�߂��������C���̉\���͋ɂ߂č������̂Ǝv����B���̈Ӗ��ŁC�����Q�̉��v�Ă͎��Ɋ낤���g����̘O�t�h�̉��v�Ăƌ��킴��Ȃ��B�����N�������ł́C�N�������̌��S�������߂邽�߁C�����Ɣ��{�I�ȉ��v���l����K�v������B
���������łǂ̂悤�ȉ��v���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B�܂��́C����܂ł́g�������Z�h�ƌĂԂׂ��Â��o�ϑO���r���C�R���i��̓��{�o�ς̌���ɑ����������I�Ȍo�ϑz��̉��ŁC�����ȍ��������s�����Ƃł���B�����̍����́C�R���i�Ђ��o����ł��C�ˑR�Ƃ���100�N���S�v�����Ȃ���̂��ێ�����Ă���Ƃ́C�����l���Ă��Ȃ����낤�B����܂ł̊Â��o�ϑO���啝�Ɍ�������傫�ȃ`�����X�ł���B
���̏�ŁC�}�N���o�σX���C�h���f�t�����ł���~�����C�t���ғ���������v���s���ׂ��ł���B�܂��C�ߔN�̓}�N���o�σX���C�h�̕�����`�㏬�����Ȃ��Ă��邵�C����܂ŔN���J�b�g���x�ꂽ�������Ԃ����߂ɂ��C�N���Ƃ̃J�b�g�������傫������K�v������B�J�b�g����傫������C�}�N���o�σX���C�h�𑁊��ɏI���邱�Ƃ��ł���B�����N�����~�ς����D������{����K�v�����������Ȃ�B
�y93�Łz���́C2016�N�̔N�������ŁC�L�����[�I�[�o�[���x�Ƃ����}�N���o�σX���C�h�̔��C�����s��ꂽ�B����́C�f�t���Ń}�N���o�σX���C�h����~���ꂽ�ꍇ�C���N�ɂ��̕����J��z���āC�Q�N���̔N���J�b�g���܂Ƃ߂Ď��{����Ƃ������̂ł���B�������C���ڂ̔N���z���O�N�������Ȃ��悤�ɂ���Ƃ��������邽�߂ɁC�C���t�����������ɍ����Ȃ�Ȃ��ƃL�����[�I�[�o�[�����{�ł��Ȃ��B�Ⴆ�C�N���J�b�g���P�����Ƃ���ƁC���N�ɃL�����[�I�[�o�[���ĂQ�N���̂Q�����J�b�g���悤�Ƃ���C���Ȃ��Ƃ��C���t�����͂Q���ƂȂ�K�v������B�O�N���f�t���Ȃ̂ɁC�P�N�ŋ}�ɂQ���̃C���t���ɂȂ邱�Ƃ͂܂����蓾�Ȃ�����C����͎�����C���܂���ʂ����҂ł��鐧�x�ł͂Ȃ��B�܂��C���݂̂悤�ɕs�i�C�ƃR�X�g�v�b�V���^�̃C���t���������i�s���钆�ł́C�L�����[�I�[�o�[���{���������ɂ��悤�Ƃ��鐭���I���͂������\���������B����C1999�N����2001�N�ɂ����čs��ꂽ�悤�ȃ}�C�i�X������~�߂����[�u�����߂�悤�Ȃ��ƂɂȂ�C�܂��Ɍ����q���Ȃ��B�}�N���o�σX���C�h�́C�f�t�����ł��������C�W�X�ƒ����Ɏ��{�ł��鐧�x�ɂ���K�v������B
�}�N���o�σX���C�h�̉��v�ɉ����āC�����I�ɂ͎x���J�n�N��̈����グ���s���K�v�����邾�낤�B���݂͂R�N�ɂP�̃y�[�X�ŁC60����65�Ɏx���J�n�N��������グ�Ă���Œ��ł���C2025�N�i������2030�N�j�Ɋ�������B��������C���܂���Ԃ�����Ȃ������ɓ����y�[�X�ň����グ�C�A�����J��h�C�c�C�t�����X���݂�67�C���邢�̓C�M���X���݂�68�ɂ��邱�Ƃ����������Ō������ׂ��ł���B���{�͂����̍��X����ꡂ��ɕ��ώ������������C��������ώ��������ё����邱�Ƃ��\�z����Ă���B�����I�ɂ́C70�Ɏx���J�n�N��������グ�邱�Ƃ��\���ɍl�����邾�낤�B��i2022�j�ɂ��C�x���J�n�N���70�܂ň����グ��C2046�N�̃}�N���o�σX���C�h�I�����̔N�������i������֗��j���C2019�N�Ɠ��������ɕۂ��Ƃ��ł���B�������C70�܂ł̎x���J�n�N������グ�́C����ɔ�ׂ�Ƃ��܂�Ƀh���X�e�B�b�N�ȉ��v�Ɍ����邪�C�Ⴆ�C�f���}�[�N�̂悤�Ɏ����̐L���Ɏx���J�n�N��A�����鐧�x�ɂ��Ă������Ƃ͑傢�Ɋ��߂���B���ꂱ�����C�{���̈Ӗ��ł̎������艻���u�ƌ����邾�낤�B
���ʂ̉ۑ�Ƃ��ẮC���݂̍���҂����̑������C2004�N�����łQ�����x�̔N���J�b�g�����܂��Ă������Ƃ�m��Ȃ��C���邢�͊o���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ���������B���{�͍����ɑ��āC���߂āC�啝�ȋ��t�J�b�g�������������܂��Ă���C���݂̔N�������͉ߏ苋�t�̏�ԂŁC��҂⏫������ɑ傫�ȕ��S�������t���Ă��邱�Ƃ��C���J�ɐ�������K�v������B���̎��m�E�O��Ȃ����ẮC���̌�̂����Ȃ���v�����{������ł��낤�B
�����J���ȁi2019a�j�u2019�i�ߘa���j�N�������،��ʃ��|�[�g�\�����N���y�ь����N���ɌW������̌����y�ь��ʂ��\�v
�����J���ȁi2019b�j�u2019�i�ߘa���j�N�������؊֘A�����v�i��82��Љ�ۏ�R�c��N����������Q�l�����j
�����J���ȁi2020�j�u�����J���Ȓlj���o�����v�i��86��Љ�ۏ�R�c���������j
��N���i2022�j�u����ׂ��Љ�ۏ���v�i���j�@�N���C�J�艺���֗U�����v���{�o�ϐV���E�o�ϋ����i2022�N12��22���j
���V�@�i2019�j�w�N���u�ŏI�x���v�x�u�k�Ёi�u�k�Ќ���V���j
�y94�Łz��ؘj�i2010�j�w�N���͖{���ɂ��炦��̂��H�x�}�����[�i�����ܐV���j
��ؘj�i2020�j�w�Љ�ۏ�ƍ����̊�@�xPHP�������iPHP�V���j
�����M�v�i2022�j�u�����N���[�t�T�N�����ł��C�������Ȃ�Ə��̉\���|�V���[�Y �N�����̃^�e�ƃ��R �U�b�N������ŃX�b�L������!?�F��b�N�����o���ԂT�N�����Ă̔w�i�E���e�E�e���E�_�_�v�j�b�Z�C��b�����|�[�g 2022-11-22
����a�F�i2021�j�u�}�N���o�σX���C�h�I���������ꂨ��ъ�b�N��45 �N�����Ă̕]���Ɖۑ�v���{���� Viewpoint No.2021-001