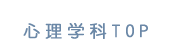大山 泰宏 教授 臨床心理学
<主な著書・論文>
『日常性の心理療法』(単著、日本評論社 2020)
『思春期・青年期の心理臨床』(単著、放送大学教育振興会 2019)
『心理学的支援法(公認心理師の基礎と実践15)』(編著、遠見書房 2021)
など
|
 |
<研究分野>
臨床心理学という学問は、カウンセリングや心理療法といった心理臨床の実践に支えられています。私は自分がおこなう実践では,現在は精神分析的オリエンテーションを主として用いています。とはいえ,大学院時代にはユング心理学を中心に学び,それは今でも私の臨床実践に色濃く影響し、夢やイメージ表現を中心においた心理療法もおこなっています。また、発達に困難のある子どもたちの療育や発達検査、保護者や関係者の方への継続的なコンサルテーションなどをおこなっていた経験がもととなって,子どもの心理療法プロセスを認知機能や対人関係の発達の観点から読み解くこともおこなっています。
臨床心理学を学ぶ前、大学の学部学生は哲学を専攻していました。それもあって、臨床心理学を哲学や他の人文諸科学との接点から見つめ直していくという研究スタイルをとっています。たとえば、臨床心理学の現場で、他者のこころの理解はどのように成り立つのか、身体はどのような役割を果たしているのかということ等について,掘り下げて考えます。また、臨床心理学で使われている言葉や概念について、改めて考え直していくことをおこなっています。たとえば「無意識」という言葉は、今は当たり前に使われていて、それがどんなことを意味しているのか、臨床心理学の説明や理解の体系でどんな役割を果たしているのかということは、改めて問われることはありません。しかしながら、フロイトがこの言葉を精神分析で使用するようになるまでは、こころに起因するさまざまな困り事を「無意識」から理解するような仕方はありませんでした。そこに無意識という言葉がもたらされることで、いったいどんな発見がありインパクトがあったのか、どんな新たな探究の世界が開かれたのか、あるいは逆にどんなことが隠蔽され問われなくなったのかということを、その言葉が生まれた当時の諸々の思想体系、人々の日常の生活様式や信念体系などを知ることで、その言葉が生まれた瞬間に立ち戻り、それが本来もっていた力を取り戻すための研究をおこなっています。
|
<私の授業>
ひとりひとりの学生さんの興味と関心、心がわくわくすることから出発し、それを学問にまで高めていくような授業と研究指導を心がけています。自分が面白いと思うことこそ、自分の大切な何かとつながっています。それを探究していくことは自分自身に出会うことでもあります。また、臨床心理学の体系の内部に留まるのでなく、広く人文諸科学や自然科学の探究の歴史や成果と対話することで、発想を柔軟で開けたものに保ち続けておく姿勢を伝えたいと思っております。
|
<生活と趣味>
2025年度より学習院大学文学部に着任します。しばらくは、放送大学で私が担当している授業がテレビ(BS)で流れますので、もしかするとご覧になる機会があるかもしれません。
住まいは京都で、学習院には半ば単身赴任の遠距離通勤。ちなみに学習院発祥の地は京都です。御所の真ん中にそれを示す立て札があります。
趣味は絵画と音楽。高校生の頃、画家をめざして美大受験を考えていましたが、尊敬する先生に「おまえの絵は頭で描いている。絵は向いていない」と言われ断念。キュビズムが具象から抽象へ向かう変遷に心奪われ、それを真似た絵を描いていました。
音楽は鑑賞と楽器演奏(ヴァイオリン)をやります。特にJ.S. Bach が好き。楽器演奏の腕はイマイチなので,むしろモノとしての楽器に凝ったり、コンサートホールの音を自宅で実現すべく、オーディオ機器を魔改造したりしています。
|