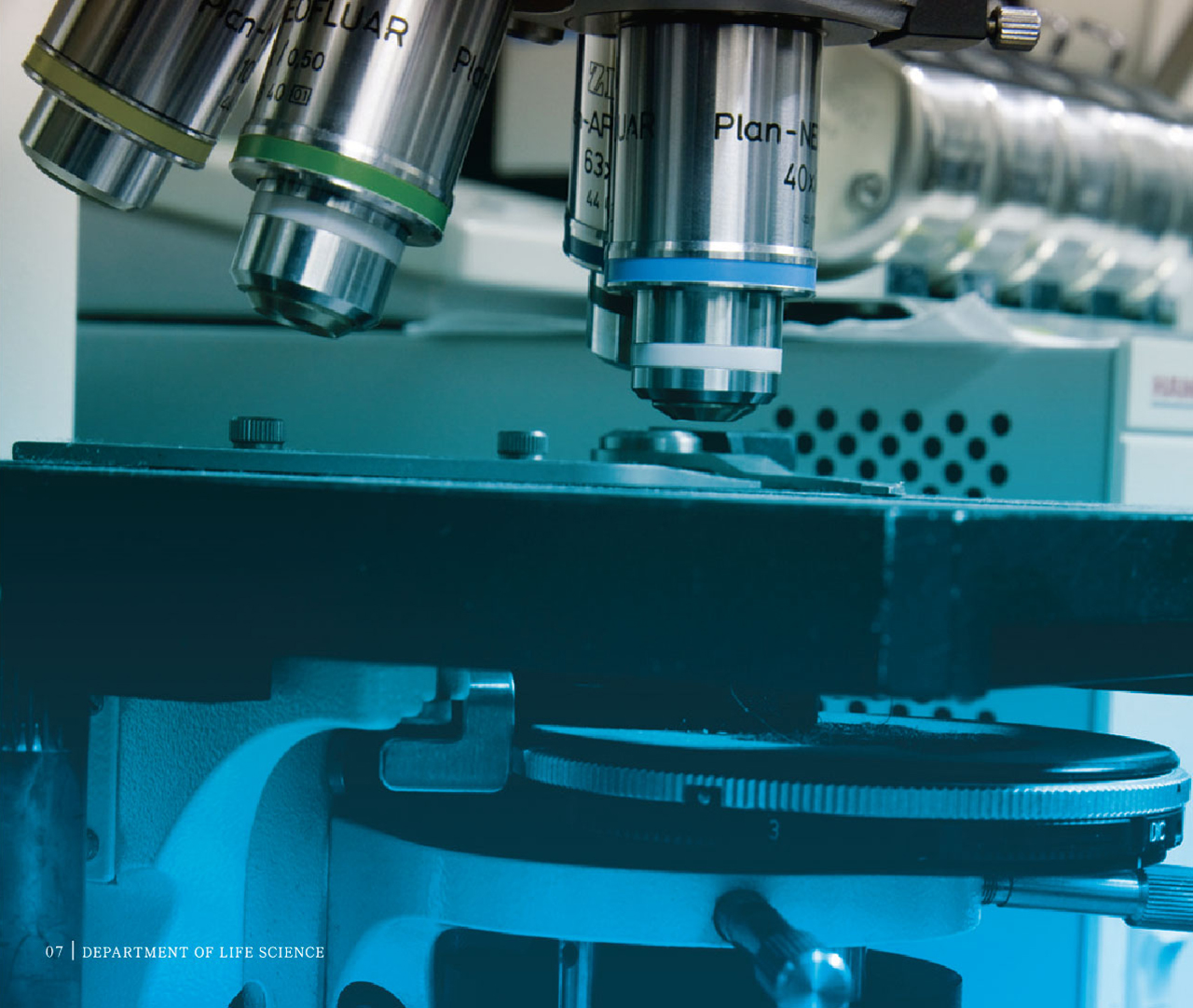
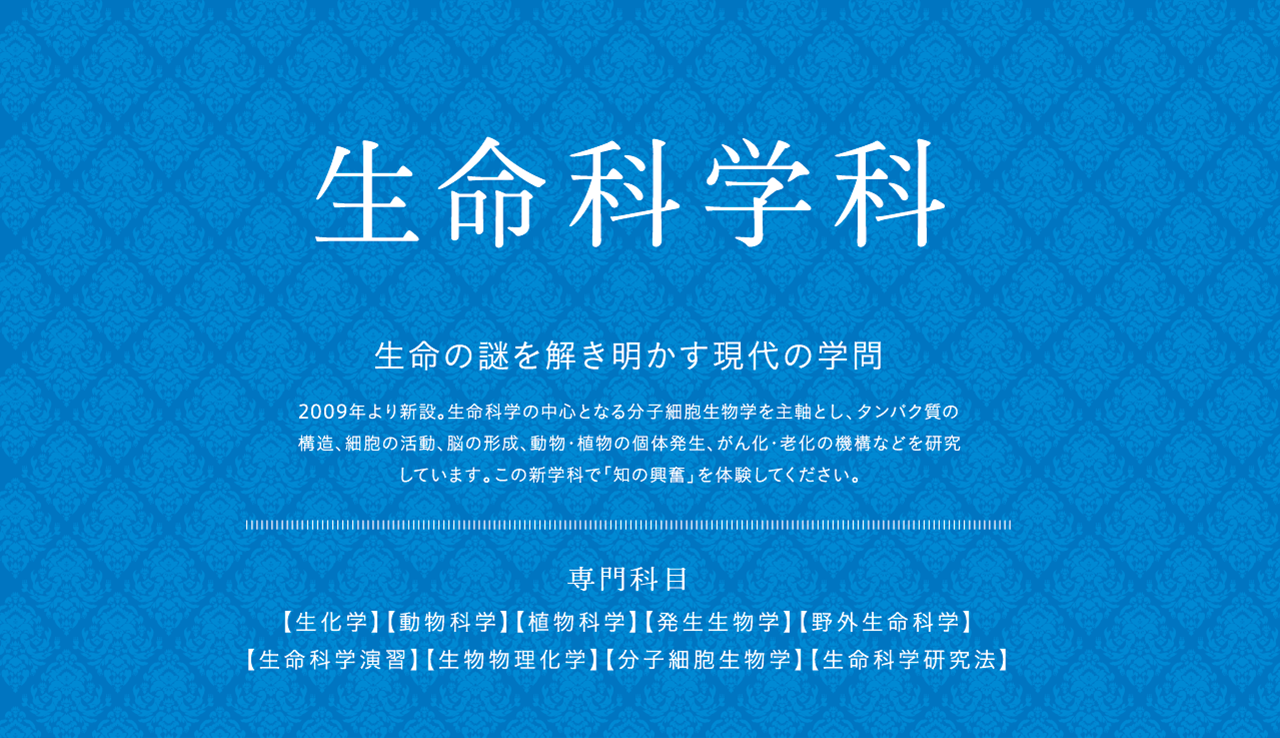
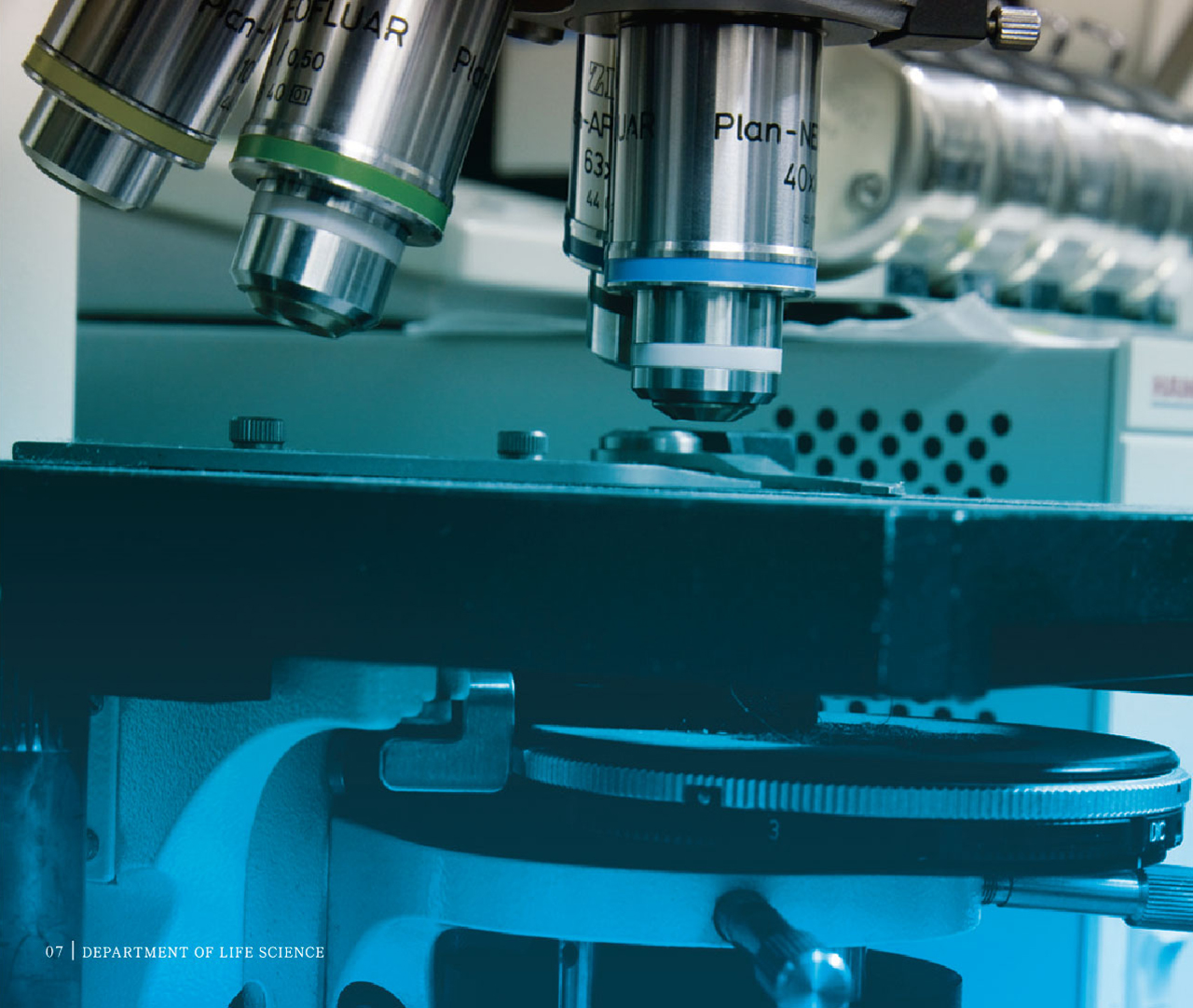

-

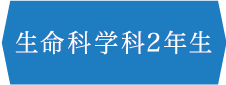

-
高校生の頃から再生医療に興味があったため、病気治療の研究に携わる基礎を学ぶことができると考え、生命科学科に進みました。生命科学は動植物の生命現象やDNA、タンパク質など学べる分野が広いので探究心がかきたてられます。
2年生の「野外生命科学2」の授業では、遺伝子組換えダイズが使用されているかどうかを、実際に豆腐からDNAを抽出して調べるなど、植物科学の基礎となる知識、実験技術を学びました。初めて行う操作が多く大変でしたが、毎回新たな発見があり、とても充実していました。実験の最終日には、教授・先輩方が打ち上げの準備をして下さり、焼きそばを作ったり、ビンゴゲームをしたりと、とても楽しい思い出になりました。
将来は何らかの形で病気治療につながる研究に携わりたいという夢がありますが、現段階では1つに絞らず、より専門的な3年生の生命科学実験を通して、どの分野に進むか見極めたいと思っています。自分が興味を持った生命科学の知識で、医療の現場に立ち合わなくても病気の原因を究明し、治療の一端を担うことが出来たら嬉しいです。
-

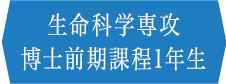

-
大学に入る前は、ただ漠然とガンの研究がしてみたいと考えていました。大学の講義でDNAの傷を治す仕組みについて聞いた際に、人はガンにならないための仕組みを持っているのになぜガンになるのだろうと疑問に感じました。この仕組みというのがDNA損傷修復というものであり、まだわかっていないことがたくさんあります。この未知の仕組みに興味を持ち、研究に取組んでいます。
DNA損傷修復機構の存在は老化やガン化に密接に関わっており、DNA損傷修復機構は様々な生物間で保存されています。私は出芽酵母を用いて研究を行っていますが、出芽酵母にもヒトと同じような機構が多数保存されているため、出芽酵母でDNA損傷修復機構を研究することが、ヒトのガンや老化の研究へとつながっていくと考えています。
大学での講義や実験は、基本的に結果の分かっていることに取り組むことがほとんどでした。それに比べ、大学4年生で研究室配属された後から始まる研究では、まだ知られていないことに取り組むといった違いがあります。大学院では研究を中心とした生活を送っており、目標に向かい、試行錯誤しながら、未知のものに挑戦することこそが研究の醍醐味だと思っています。
-

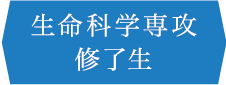

-
食物アレルギーを持っていた為、食事に対する不信感が幼い時からあり、 その経験から安心して食べる事ができる「食」の提供に携わりたいと思っていました。中でも乳業会社は、赤ちゃんからご高齢の方までの全ての「食」に関われるので、現職は第一希望の業界でもありました。
学習院大学で学んだことで、現在も役に立っていることは2つあり、1つ目は「論理的に考える力」です。
食品製造では原料の物性を理解する事が重要になります。不溶解や凝縮物等が生じた際、何故このような結果になったのか原因を追究する論理的思考が必要になりますが、日々の研究生活でこれが身についたと思っています。
2つ目は「アレルギーに関する知識」です。アレルギーはお客様の健康に関わる非常に重要な問題です。免疫学の授業で得られた知識が、仕事上のアレルゲンの管理に活かせていると感じています。
学習院大学は、1つのキャンパスに全学部がまとまっているので、他学部の授業に参加出来るだけでなく学生同士の情報交換が可能です。1つの事柄に囚われずに視野を広げることができる、この環境が学習院大学の魅力だと思います。
- 2013年学習院大学理学部生命科学科卒
- 2015年学習院大学大学院自然科学研究科生命科学専攻 博士前期課程修了
- 2015年森永乳業株式会社入社


-
-
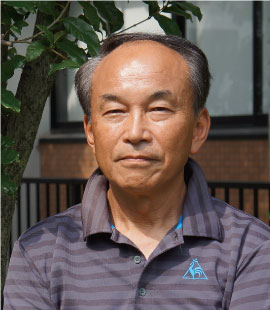
- アガタ キヨカズ
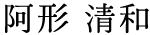 教授[再生生物学]
教授[再生生物学]
-
- 少年サッカーの監督で一年中日焼けしているので、京大から来た教授と紹介されても、ピンとこない。しかし、プラナリアやイモリを使った再生研究の世界の第一人者であり、発生生物学会や動物学会の会長を歴任している生物・生命科学分野の有名人である。岩波書店から出版した科学絵本『切っても切ってもプラナリア』は理科少年・少女のバイブル的存在。サイエンス・トークも巧みで、高校生・大学生からもカリスマ教授として絶大なる人気を得ている。日本動物学会賞、文部科学大臣賞を受賞
-

- アダチ タカシ
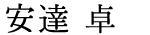 教授[発生遺伝学]
教授[発生遺伝学]
-
- 「昆虫大好き少年がそのまま大きくなって生物学の研究を始めたんです」と人懐こい笑顔で語る安達教授。たしかに生き物が好きでたまらない無邪気な研究者という風貌だ。生命をあくまで「生き物らしく」理解するために、分子よりも大きな、細胞、組織、個体のレベルでの原理を解き明かすことをめざしているという。細胞の増殖、分化、そして死がどのように絡み合うかという「生命のパズル」を解明すべく、つねに数百系統のショウジョウバエを飼育し、突然変異体の探索や遺伝子解析をおこなっている。講義の途中で黒板にさらさらと描いてみせる研究のパートナー(?)のショウジョウバエの似顔絵は必見!
-
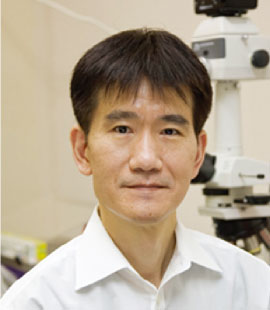
- オカダ テツジ
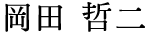 教授[構造生物学]
教授[構造生物学]
-
- ヒトの体内で働くタンパク質の約3割は、脂質二重膜の中に埋もれて存在する膜タンパク質である。水溶性のタンパク質と比べると膜タンパク質は研究が難しく、構造も機能も未だ多くの謎に包まれている。岡田教授は、われわれの視覚の鍵を握る膜タンパク質・ロドプシンの構造を初めて決定したことで世界的に知られる構造生物学の研究者だ。全身全霊をこめて最も困難なテーマに挑みつづける姿勢でつねに周囲をうならせてきた。新たな研究室では、X線回折や分光測定を駆使して、情報伝達に関わる膜タンパク質の構造と機能発現のメカニズムの解明をめざす。Thomson Scientific Research Front Award 2004、文部科学大臣表彰科学技術賞(研究部門)を受賞
-

- オカモト ハルマサ
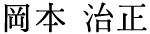 教授[発生神経生物学]
教授[発生神経生物学]
-
- 「趣味といえばクラシック音楽鑑賞とお酒を飲むことかな」と、気さくに語る岡本教授。気のいい近所のおじさんという雰囲気だが、神経発生を促す因子がFGFという分子であることを発見した発生学の世界的な第一人者だ。この発見によって、生物が単純な胚から出発して複雑な体を形作っていく際に脳神経系がどうやって発生するかについて、世界中多くの研究者を数十年にわたって悩ませてきた謎が解明された。今は、自らが特定したFGFの働きの詳細を解き明かし「脳の発生」という人類にとって最も重要な課題を理解すべく、アフリカツメガエルの胚などの実験材料を用い、分子・細胞生物学的手法での研究を進めている。
-

- キヨスエ トモヒロ
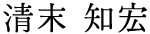 教授[植物分子生理学]
教授[植物分子生理学]
-
- 「研究を通じて養われる思考力と行動力、いわゆる問題解決能力は、社会に出てからも重要。一人ひとりの個性を互いに尊重し合い一緒に研究することで、学生とWin-Winの関係を築きたい」と話す清末教授。生命科学科で唯一植物を扱う研究室の教授だ。モデル植物シロイヌナズナのLOV光受容体の基礎研究と応用研究を展開。LOV光受容体LKP2とZTLが、短日条件での花芽形成を抑制していることを突き止めた。「研究は攻略本のないロールプレイングゲーム、知的な冒険」と語るその瞳には、未知への挑戦、ロマンを追い求める熱い情熱と輝きがある。日本植物細胞分子生物学会奨励賞を受賞
-
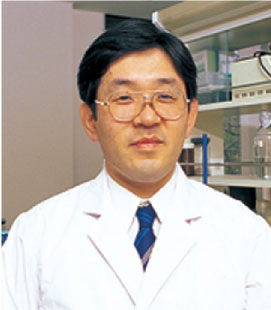
- コジマ シュウイチ
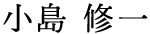 教授[タンパク質化学]
教授[タンパク質化学]
-
- 小島教授の研究対象は生命の基本的な部品であるタンパク質だ。大腸菌などに目的のタンパク質を大量につくらせ、それらの性質を最新の物理的・化学的手法を駆使して調べる。さらに、アミノ酸置換などを導入し、天然にはない新しい構造や機能を持ったタンパク質を設計・合成する。「私が学生だった頃を思うと、このような手法を用いて研究できることは夢のようです」と小島教授は語る。生命科学が爆発的に進歩した時代を、タンパク質化学の分野の若手・中堅の研究者として駆け抜けてきた実感のこもる言葉だ。生命の部品の謎を解き明かすべく、今日も小島教授の研究はつづく。
-
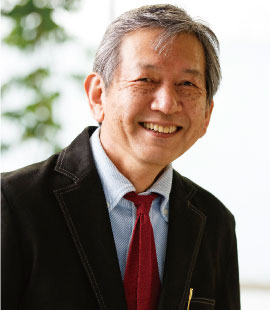
- タカシマ アキヒコ
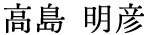 教授[神経生物学]
教授[神経生物学]
-
- 2016年に着任された脳神経学者の高島教授。アルツハイマー病の世界的な基礎研究者だ。大学生になって真っ先に「脳のことを知りたい」と思われたそうだ。アルツハイマー病は加齢と共に罹患率が増え、病気になると本人はもとより家族の負担も大きい。2025年までにこの病気を克服するとの宣言がG7でなされ、世界中で治療法の研究が行われている。高島教授は微小管結合蛋白質の一つであるタウに注目して研究を進めている。「認知症の治療は近い将来可能になるでしょう。でも、まだまだ脳が老化して行くのを止めなければなりません。」自分の脳を知り、老化を防ぐ研究を一緒に行ってくれる学生を大募集中だ!!Neuroscience Research Excellent Paper Awardを受賞
-

- ヒシダ タカシ
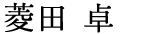 教授[分子生物学]
教授[分子生物学]
-
- 菱田教授は2011年春に着任した生命科学科の若手教授だ。研究への情熱にあふれ、いつも実際の年齢よりも若く見られるという。生命の設計図を担っているDNAが傷つけられてしまったとき、生物はどうやって正しい設計図をコピーするのか?数十億年の進化を経て編み出された驚くべき「損傷ストレス耐性機構」を解明するため、菱田教授は酵母や大腸菌を用いて慢性的な損傷ストレス環境を再現する独創的な実験系を開発した。ゲノム不安定性に起因する疾患の治療という未来をも夢に描きながら、メンバーが「楽しく、しかし、真剣に」研究に取り組める研究室を立ち上げたいと語る。日本遺伝学会奨励賞を受賞
※上記8名と西坂 崇之教授(物理学科)が大学院・生命科学専攻のメンバーです。
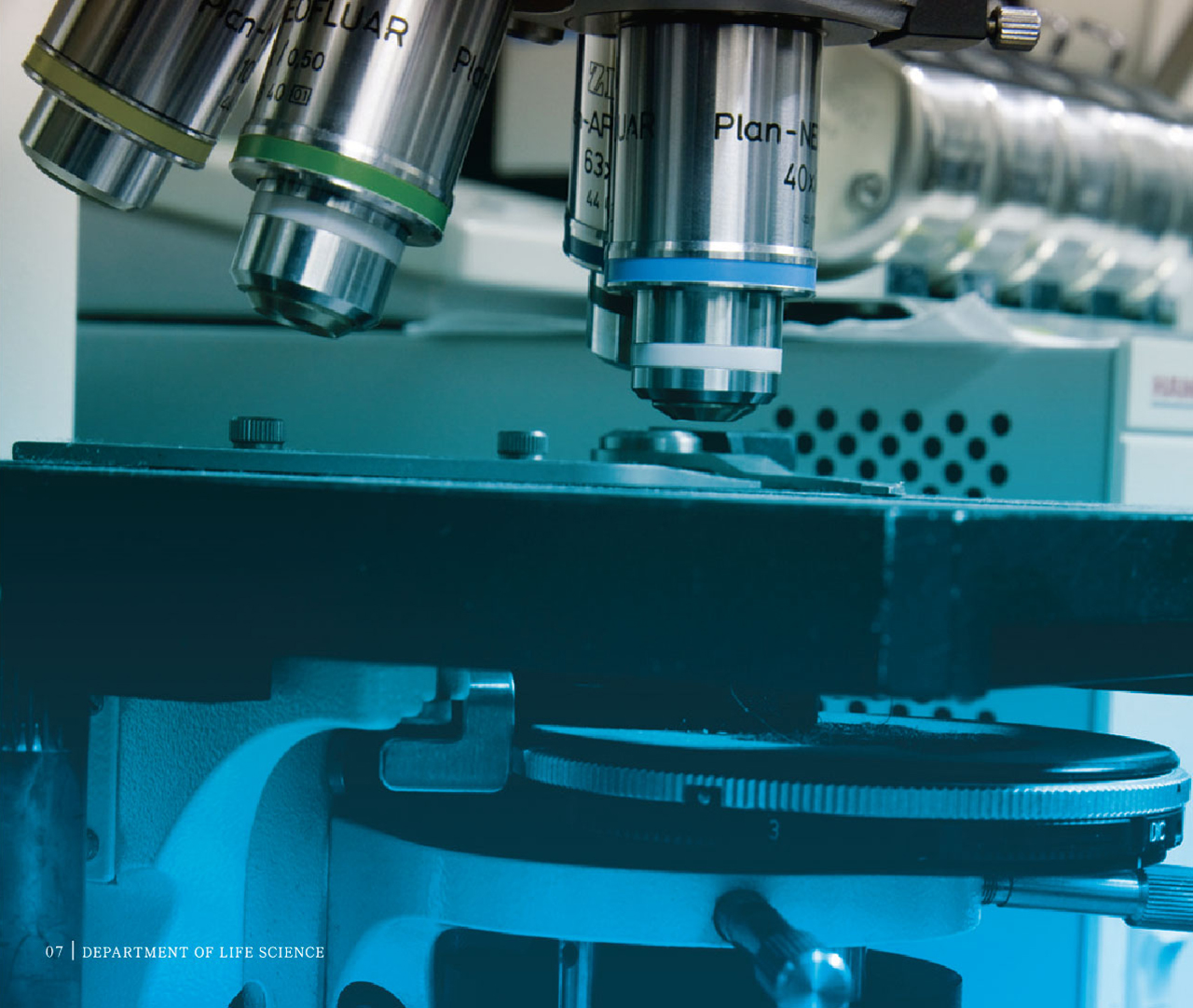

-

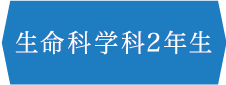

-
高校生の頃から再生医療に興味があったため、病気治療の研究に携わる基礎を学ぶことができると考え、生命科学科に進みました。生命科学は動植物の生命現象やDNA、タンパク質など学べる分野が広いので探究心がかきたてられます。
2年生の「野外生命科学2」の授業では、遺伝子組換えダイズが使用されているかどうかを、実際に豆腐からDNAを抽出して調べるなど、植物科学の基礎となる知識、実験技術を学びました。初めて行う操作が多く大変でしたが、毎回新たな発見があり、とても充実していました。実験の最終日には、教授・先輩方が打ち上げの準備をして下さり、焼きそばを作ったり、ビンゴゲームをしたりと、とても楽しい思い出になりました。
将来は何らかの形で病気治療につながる研究に携わりたいという夢がありますが、現段階では1つに絞らず、より専門的な3年生の生命科学実験を通して、どの分野に進むか見極めたいと思っています。自分が興味を持った生命科学の知識で、医療の現場に立ち合わなくても病気の原因を究明し、治療の一端を担うことが出来たら嬉しいです。
-
-

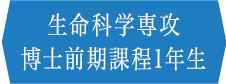

-
大学に入る前は、ただ漠然とガンの研究がしてみたいと考えていました。大学の講義でDNAの傷を治す仕組みについて聞いた際に、人はガンにならないための仕組みを持っているのになぜガンになるのだろうと疑問に感じました。この仕組みというのがDNA損傷修復というものであり、まだわかっていないことがたくさんあります。この未知の仕組みに興味を持ち、研究に取組んでいます。
DNA損傷修復機構の存在は老化やガン化に密接に関わっており、DNA損傷修復機構は様々な生物間で保存されています。私は出芽酵母を用いて研究を行っていますが、出芽酵母にもヒトと同じような機構が多数保存されているため、出芽酵母でDNA損傷修復機構を研究することが、ヒトのガンや老化の研究へとつながっていくと考えています。
大学での講義や実験は、基本的に結果の分かっていることに取り組むことがほとんどでした。それに比べ、大学4年生で研究室配属された後から始まる研究では、まだ知られていないことに取り組むといった違いがあります。大学院では研究を中心とした生活を送っており、目標に向かい、試行錯誤しながら、未知のものに挑戦することこそが研究の醍醐味だと思っています。
-
-

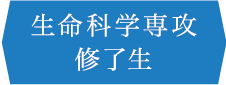

-
食物アレルギーを持っていた為、食事に対する不信感が幼い時からあり、 その経験から安心して食べる事ができる「食」の提供に携わりたいと思っていました。中でも乳業会社は、赤ちゃんからご高齢の方までの全ての「食」に関われるので、現職は第一希望の業界でもありました。
学習院大学で学んだことで、現在も役に立っていることは2つあり、1つ目は「論理的に考える力」です。
食品製造では原料の物性を理解する事が重要になります。不溶解や凝縮物等が生じた際、何故このような結果になったのか原因を追究する論理的思考が必要になりますが、日々の研究生活でこれが身についたと思っています。
2つ目は「アレルギーに関する知識」です。アレルギーはお客様の健康に関わる非常に重要な問題です。免疫学の授業で得られた知識が、仕事上のアレルゲンの管理に活かせていると感じています。
学習院大学は、1つのキャンパスに全学部がまとまっているので、他学部の授業に参加出来るだけでなく学生同士の情報交換が可能です。1つの事柄に囚われずに視野を広げることができる、この環境が学習院大学の魅力だと思います。
- 2013年学習院大学理学部生命科学科卒
- 2015年学習院大学大学院自然科学研究科生命科学専攻 博士前期課程修了
- 2015年森永乳業株式会社入社
-


-
-
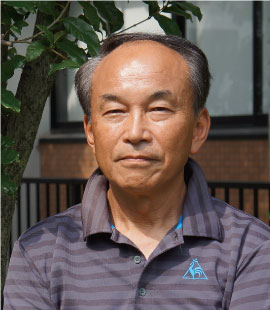
- アガタ キヨカズ
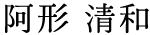 教授[再生生物学]
教授[再生生物学]
- 少年サッカーの監督で一年中日焼けしているので、京大から来た教授と紹介されても、ピンとこない。しかし、プラナリアやイモリを使った再生研究の世界の第一人者であり、発生生物学会や動物学会の会長を歴任している生物・生命科学分野の有名人である。岩波書店から出版した科学絵本『切っても切ってもプラナリア』は理科少年・少女のバイブル的存在。サイエンス・トークも巧みで、高校生・大学生からもカリスマ教授として絶大なる人気を得ている。日本動物学会賞、文部科学大臣賞を受賞
-

- アダチ タカシ
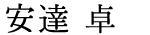 教授[発生遺伝学]
教授[発生遺伝学]
- 「昆虫大好き少年がそのまま大きくなって生物学の研究を始めたんです」と人懐こい笑顔で語る安達教授。たしかに生き物が好きでたまらない無邪気な研究者という風貌だ。生命をあくまで「生き物らしく」理解するために、分子よりも大きな、細胞、組織、個体のレベルでの原理を解き明かすことをめざしているという。細胞の増殖、分化、そして死がどのように絡み合うかという「生命のパズル」を解明すべく、つねに数百系統のショウジョウバエを飼育し、突然変異体の探索や遺伝子解析をおこなっている。講義の途中で黒板にさらさらと描いてみせる研究のパートナー(?)のショウジョウバエの似顔絵は必見!
-
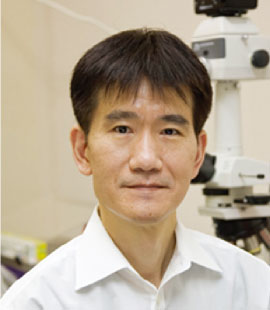
- オカダ テツジ
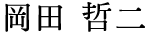 教授[構造生物学]
教授[構造生物学]
- ヒトの体内で働くタンパク質の約3割は、脂質二重膜の中に埋もれて存在する膜タンパク質である。水溶性のタンパク質と比べると膜タンパク質は研究が難しく、構造も機能も未だ多くの謎に包まれている。岡田教授は、われわれの視覚の鍵を握る膜タンパク質・ロドプシンの構造を初めて決定したことで世界的に知られる構造生物学の研究者だ。全身全霊をこめて最も困難なテーマに挑みつづける姿勢でつねに周囲をうならせてきた。新たな研究室では、X線回折や分光測定を駆使して、情報伝達に関わる膜タンパク質の構造と機能発現のメカニズムの解明をめざす。Thomson Scientific Research Front Award 2004、文部科学大臣表彰科学技術賞(研究部門)を受賞
-

- オカモト ハルマサ
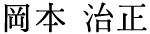 教授[発生神経生物学]
教授[発生神経生物学]
- 「趣味といえばクラシック音楽鑑賞とお酒を飲むことかな」と、気さくに語る岡本教授。気のいい近所のおじさんという雰囲気だが、神経発生を促す因子がFGFという分子であることを発見した発生学の世界的な第一人者だ。この発見によって、生物が単純な胚から出発して複雑な体を形作っていく際に脳神経系がどうやって発生するかについて、世界中多くの研究者を数十年にわたって悩ませてきた謎が解明された。今は、自らが特定したFGFの働きの詳細を解き明かし「脳の発生」という人類にとって最も重要な課題を理解すべく、アフリカツメガエルの胚などの実験材料を用い、分子・細胞生物学的手法での研究を進めている。
-

- キヨスエ トモヒロ
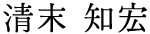 教授[植物分子生理学]
教授[植物分子生理学]
- 「研究を通じて養われる思考力と行動力、いわゆる問題解決能力は、社会に出てからも重要。一人ひとりの個性を互いに尊重し合い一緒に研究することで、学生とWin-Winの関係を築きたい」と話す清末教授。生命科学科で唯一植物を扱う研究室の教授だ。モデル植物シロイヌナズナのLOV光受容体の基礎研究と応用研究を展開。LOV光受容体LKP2とZTLが、短日条件での花芽形成を抑制していることを突き止めた。「研究は攻略本のないロールプレイングゲーム、知的な冒険」と語るその瞳には、未知への挑戦、ロマンを追い求める熱い情熱と輝きがある。日本植物細胞分子生物学会奨励賞を受賞
-
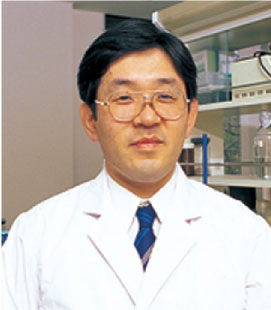
- コジマ シュウイチ
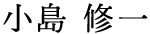 教授[タンパク質化学]
教授[タンパク質化学]
- 小島教授の研究対象は生命の基本的な部品であるタンパク質だ。大腸菌などに目的のタンパク質を大量につくらせ、それらの性質を最新の物理的・化学的手法を駆使して調べる。さらに、アミノ酸置換などを導入し、天然にはない新しい構造や機能を持ったタンパク質を設計・合成する。「私が学生だった頃を思うと、このような手法を用いて研究できることは夢のようです」と小島教授は語る。生命科学が爆発的に進歩した時代を、タンパク質化学の分野の若手・中堅の研究者として駆け抜けてきた実感のこもる言葉だ。生命の部品の謎を解き明かすべく、今日も小島教授の研究はつづく。
-
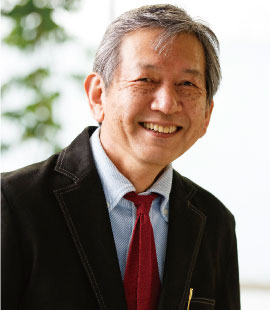
- タカシマ アキヒコ
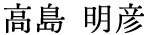 教授[神経生物学]
教授[神経生物学]
- 2016年に着任された脳神経学者の高島教授。アルツハイマー病の世界的な基礎研究者だ。大学生になって真っ先に「脳のことを知りたい」と思われたそうだ。アルツハイマー病は加齢と共に罹患率が増え、病気になると本人はもとより家族の負担も大きい。2025年までにこの病気を克服するとの宣言がG7でなされ、世界中で治療法の研究が行われている。高島教授は微小管結合蛋白質の一つであるタウに注目して研究を進めている。「認知症の治療は近い将来可能になるでしょう。でも、まだまだ脳が老化して行くのを止めなければなりません。」自分の脳を知り、老化を防ぐ研究を一緒に行ってくれる学生を大募集中だ!!Neuroscience Research Excellent Paper Awardを受賞
-

- ヒシダ タカシ
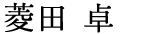 教授[分子生物学]
教授[分子生物学]
- 菱田教授は2011年春に着任した生命科学科の若手教授だ。研究への情熱にあふれ、いつも実際の年齢よりも若く見られるという。生命の設計図を担っているDNAが傷つけられてしまったとき、生物はどうやって正しい設計図をコピーするのか?数十億年の進化を経て編み出された驚くべき「損傷ストレス耐性機構」を解明するため、菱田教授は酵母や大腸菌を用いて慢性的な損傷ストレス環境を再現する独創的な実験系を開発した。ゲノム不安定性に起因する疾患の治療という未来をも夢に描きながら、メンバーが「楽しく、しかし、真剣に」研究に取り組める研究室を立ち上げたいと語る。日本遺伝学会奨励賞を受賞
※上記8名と西坂 崇之教授(物理学科)が大学院・生命科学専攻のメンバーです。
-