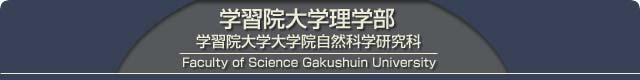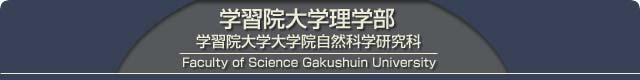理学部長
学習院大学の理学部で何を学ぶか?「学習院大学の」と限定したのは、この頁を開く学生諸君は、理科や数学が好きであり、科学と技術に関心を持っていて、これまでに大学の理学部、工学部あるいは理工学部などについて、単に名称だけかも知れませんが、何らかの知識を持っていると推測するからです。さらに推測を進めると、年輩の方々からの知識を得て、理学部では理科、数学などの原理を学び、工学部ではものを作る技術を学ぶので、工学部出身者の方が卒業してすぐに役に立つなどと想像しているかも知れません。もしもそのような想像をしているとしたら、それを生んだ知識は、いまでも一部に残っていますが、学問を輸入した明治時代のものであり、現代では誤りである、と申し上げます。
本学の理学部は、1949年、「自分の目で見、手を動かして考え、創る能力を育て、理学と工学との谷間を埋めること」を旗じるしに創立されました。「理学と工学との谷間を埋める」という考えの正しさを裏付ける一例は、1948年6月、ベル電話研究所で発表されたトランジスターの発明です。トランジスターは現在の情報化時代には欠くことができないコンピューターを動かす集積回路の中の基本回路素子です。「半導体に関する研究とトランジスター効果の発見」によりベル電話研究所の3人の物理学者Shockley、Bardeenと
Brattain は、1956年、ノ−ベル物理学賞を受賞しました。けれども、初代理学部長の佐藤孝二先生は、トランジスターにヒントを得て、上記のように学習院大学理学部の旗印をかかげたのではありません。当時米国の新聞はこの発明をほとんど取り上げていませんし、今日のような半導体の隆盛を世界中で予見した人は、誰もいませんでした。音響物理学者であり騒音対策、聴覚障害児教育など巾広く活躍された佐藤孝二先生は、トランジスタ−発明の以前から日本の社会に蔓延していた「理学と工学との谷間」を認識し、深く憂慮して、これからの大学では理学側から工学との谷間を埋める橋を架けなければならない、とお考えになっていたのです。
科学も技術も日々に進歩し、発展しています。仮に、即戦力になる知識を持って社会に出たとしても、その知識だけではすぐに役に立たなくなくなります。進歩し発展する科学と技術の世界で役に立つのは、物理、化学、数学など、理学の基礎を理解した、真の実力の持ち主、過去に捕らわれない自由な発想ができる人々です。学習院大学理学部では、このような若者を育てているのです。
これまでを、招待状の第1通とし、高校と比べて理学部で学ぶことの特徴は何かを述べて、理学部への2通目の招待状とします。
自然現象の観察から始まった小学校、中・高校の理科でも、高学年になれば、観察 される現象の底にある法則を教わります。理学部では、この方向を徹底し、科学を一つの体系として学ぶことになります。基本の原理や法則から出発して、理解をだんだんと積み上げていくのが、理学部の勉強の特徴です。 自然科学の理解は、複雑に見える現象を深く解析してより基本的な原理に還元していくことによって深まっていきます。物質の多様な化学的性質の研究から、元素の存在が認識され、元素の周期律表が発見確立されました。量子力学が生まれると、周期律表は原子の構造から説明されます。さらに、原子と原子との結びつきが生じる仕組みが解明され、その知識のもとで、現在ではさまざまな物質が合成されています。半導体や磁性体の性質は量子力学、統計力学の力で大いに解明されました。生命の不思議であった遺伝のからくりや種々の生理作用は、遺伝情報を担うDNA、情報伝達に関与するRNA、そして蛋白質の分子構造の研究によって大きく解明されつつあります。つまり、生命現象の分子レベルでの解明です。これら原子結合、DNA、半導体、磁性体、そのどれを取ってみても、現象そのものを詳しく知るのも理学部で初めて、という人が多くて、新鮮な興味を感じることでしょう。それに加えて、基本法則によって次々に理解のレベルが深まっていくことの面白さを味わえるのが、理学部での勉強の一つの楽しみではないでしょうか。
数学はとかく抽象的な論理の営みと思われがちですが、数学にも優れて数学的な実体があり素材があります。お馴染みなところでいえば、整数、実数、複素数、初等的な関数、基本的な図形、そして行列、方程式、曲面、・・・。計算機関係の授業に出てくるアルゴリズムも立派な一つの素材です。大学の数学のハードルは、論理の体系という重い鎧を着こなすことですけれど、鎧の下に隠れているのは、素材が持つ面白さです。逆に云えば、素材の本当の面白さを引き出すには、重い鎧の着こなしも時に必要ということで、いたずらに鎧を恐れることはないのです。
理学部では、新鮮な興味が基本を理解した真の実力に裏打ちされるので、新しいものを創る力が生まれます。新しい法則が生まれ、新しい技術を創る力も生まれるでしょう。
私達は、創る能力は学生諸君が受け身になりがちな講義だけでなく、自然現象や数理現象を自分の目で見、手を動かして、時間をかけて考えることから生まれてくる、と考えています。具体的には、これは実験、実習、演習の重視となって現れています。これが、理学部の少人数教育です。50人程度の学生に、教授、助手、大学院生合わせて十何人かが指導に当たる実験科目、学生が解いた演習問題を助手が丁寧に見てくれる演習科目、一人の先生を10人以下の学生が囲む輪講科目等が豊富に用意されています。最近、理学部の学生数が増えてきて、低学年の講義がやや混雑しているのは事実ですが、少人数教育の、実験、演習、輪講科目はむしろ強化されています。
諸君が大学を卒業する21世紀が直面するであろう難問の解決に、科学の力と自由な発想の精神が必要であることは疑いありません。理学部は理科、数学の好きな若い諸君の知的好奇心と実行力に期待しています。