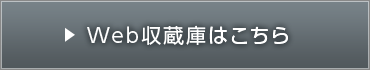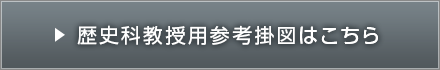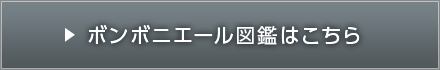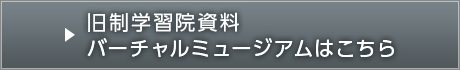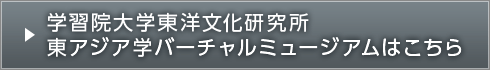- TOP
- 収蔵資料について
収蔵資料について
霞会館記念学習院ミュージアムでは、中世以来続く公家・地下官人、近世から近代にかけての大名・華族・大名家家臣、また村の名主家史料、および近代から現代にいたる学習院関係者史料など、総計約25万件の史料を収蔵しています。
収蔵資料群
霞会館記念学習院ミュージアムに収蔵されている資料を資料群ごとにご紹介します。
-
001 陸奥国棚倉藩主阿部家史料(受託)
資料群No.
001
資料群名
陸奥国棚倉藩主阿部家史料
概要
阿部家は、三河以来徳川家に属した譜代大名で、下野壬生、武蔵国忍、 陸奥国白河を経て同棚倉を領し、幕府の要職を務めた。なお維新後、阿部家は子爵を授けられるが、本史料群には華族時代の史料も多く含まれている。
年代
天正13年(1585)~昭和11年(1936)
数量
4,706点
伝来
昭和43年(1968)に本学に寄託され、のち当館に移管された。
検索方法
学習院大学史料館収蔵資料目録 第17号
備考
本史料はマイクロフィルムもしくは紙焼き・写真などでの閲覧を原則としている。
-
002 内膳司濱島家史料(受託・受贈)
資料群No.
002
資料群名
内膳司濱島家史料
概要
濱島家は、朝廷の内膳司の長官である奉膳職に就いていた地下官人で、本史料群には近世の朝廷儀式に関する図・編纂物とその草稿が多く含まれている。
年代
久安6年(1150)~大正14年(1925)
数量
860点
伝来
本学図書館の保管を経て、昭和52年(1977)に移管された寄贈分と、平成4年(1990)に当館が寄託をうけた分との2群に分かれる。
検索方法
学習院大学史料館所蔵史料目録 第12号
備考
マイクロ・カラー撮影が済んでいるものについては、原則として、それら複製物での閲覧に限る。
-
003 武蔵国秩父郡上名栗村町田家史料(受贈)
資料群No.
003
資料群名
武蔵国秩父郡上名栗村町田家史料
概要
町田家は、江戸への有力な材木供給地として知られた西川林業地帯の代表村である上名栗村(現埼玉県入間郡名栗村大字上名栗)の世襲名主を務めた。そのかたわら、炭・材木商売などを手広く経営した。そのため、本史料群には、村運営にともなう史料のほか、林業経営に関する史料が多数含まれている。
年代
万治2年(1659)~昭和期
数量
約50,000点
伝来
昭和39年(1964)に本学文学部史学科に寄託され、同42年に同科に寄 贈された。昭和50年に大学史料館設立にともない、当館に移管された。
検索方法
学習院大学史料館所蔵史料目録 第8・9・11・13・16号
備考
現在、史料の整理作業を進めている途中であるが、すでに目録を刊行し た部分については閲覧できる。
-
004 信濃国佐久郡五郎兵衛新田村柳沢家史料(受贈)
資料群No.
004
資料群名
信濃国佐久郡五郎兵衛新田村柳沢家史料
概要
五郎兵衛新田(現長野県北佐久郡浅科村)は用水開墾により開発された村で、柳沢家は新田村ができると同時に名主となり、明治以降も戸長を務めた。本史料群には開発・用水関係や中山道の助郷関係などの村の史料と、柳沢家の経営史料がある。
年代
寛永10年(1633)~大正6年(1917)
数量
約18,000点
伝来
昭和42年(1967)に当館に寄贈された。
検索方法
学習院大学史料館所蔵史料目録 第1・6・7号
備考
現在、原史料は長野県浅科村に寄託しているため、マイクロによる閲覧 に限る。
-
005 中川善之助収集史料(受贈)
資料群No.
005
資料群名
中川善之助収集史料
概要
中川善之助は、民法学者で本学法経学(現在の法学部)教授を勤めた。本史料群は、東北大学に勤務していたころに収集した仙台藩・会津藩関係の史料、畿内町方・信州諏訪地方の史料のほか、記録・草稿類からなる。
年代
元和1年(1615)~昭和49年(1974)
数量
497点
伝来
昭和51年(1976)に当館に寄贈された。
検索方法
学習院大学史料館所蔵史料目録 第3・4・5号
備考
目録では、書状形態の史料について翻刻をおこなっている。
-
006 上野国甘楽郡藤木村新藤家史料(受贈)
資料群No.
006
資料群名
上野国甘楽郡藤木村新藤家史料
概要
新藤家は、上野国甘楽郡藤木村(現群馬県富岡市)にあり、近世後期に七日市藩の勝手方御用を務め、のち村名主となった。本史料群の半数は質地・借金証文が占める。
年代
元禄15年(1702)~昭和3年(1928)
数量
198点
伝来
昭和51年(1976)に当館に寄贈された。
検索方法
『学習院大学史料館紀要』第3号
備考
-
007 紀伊国名草郡日方浦塩崎家史料(受贈)
資料群No.
007
資料群名
紀伊国名草郡日方浦塩崎家史料
概要
塩崎家は紀伊国名草郡日方浦(現和歌山県海南市)の商家で、明治期の当主久七は明治15年(1832)に設立した同業組合「交信社」の社長を務めた。そのため本史料群の大半は、明治期の蝋燭・傘・棕櫚皮問屋および同組合に関するものである。
年代
文政9年(1826)~明治33年(1900)
数量
209点
伝来
本学図書館の保管を経て、昭和52年(1977)に移管された寄贈分と、 平成4年(1990)に当館が寄託をうけた分との2群に分かれる。
検索方法
『学習院大学史料館紀要』第3号
備考
-
008 常陸国下館藩家老牧家史料(受贈)
資料群No.
008
資料群名
常陸国下館藩家老牧家史料
概要
牧家は、下館藩主石川家(2万石)の筆頭家老を代々務めた家で、維新 後も執政として石川家家政を司った。本史料群は、家の史料ばかりでなく、対幕府関係史料や下館藩政全般に関わる史料、および主家石川家と牧家との間で交わされたものなどからなる。
年代
慶長17年(1612)~昭和11年(1936)
数量
約1,400点
伝来
昭和57年(1982)に江島昭氏・柴谷末雄氏から寄贈されたものと、平成15年(2003)に牧家から寄贈されたものとがある。
検索方法
備考
-
009 安田銕之助史料(受贈)
資料群No.
009
資料群名
安田銕之助史料
概要
安田銕之助は、陸軍軍人で、本学名誉教授安田元久の父。本史料群は、東久邇宮・上原勇作・石原完爾との書簡、いわゆる神兵隊事件に関する史料などからなる。
年代
明治43年(1910)~昭和16年(1941)
数量
約180点
伝来
昭和64年(1989)・平成2年(1990)に当館に寄託された。
検索方法
学習院大学史料館所蔵史料目録 第10号
備考
マイクロフィルムが雄松堂から市販されている。
-
010 辻邦生関係資料(受贈)
資料群No.
010
資料群名
辻邦生関係資料
概要
作家であり、学習院大学フランス文学科(現フランス語圏文化学科)教授であった辻邦生(大正14(1925)~平成11(1999))より寄贈された資料。自筆原稿、創作ノート、日記、書簡、著書、イラストなど。旧制松本高校時代の友・北杜夫とやりとりした書簡(70通)もある。
年代
大正~昭和
数量
約3万5千点
伝来
昭和61年(1986)受託開始、2012年寄贈
検索方法
辻邦生「高校時代の日記」『学習院大学史料館紀要』第20号掲載
備考
「辻邦生展」パンフレット(平成16年)
「学習院と文学」パンフレット(平成22年)
「辻邦生没後10年に寄せて」(「ミュージアムレター No.10」 平成21年) -
013 旧制学習院歴史地理標本室移管史料(受贈)
資料群No.
013
資料群名
旧制学習院歴史地理標本室移管史料
概要
本史料群は、旧制学習院中・高等科歴史地理標本室に所蔵されていた標本類と、新制学習院輔仁会高等科史学部などが発掘調査して出土した史料類である。
年代
縄文中期~昭和年間
数量
320点
伝来
昭和24年(1949)の大学開設にともない旧制高等科から大学図書館・ 新制中・高等科に移され、昭和55年(1980)と同64年に当館に移管された。
検索方法
学習院大学史料館所蔵史料目録 第14号
備考
-
018 昭和天皇東宮御学問所時代正服(受贈)
資料群No.
018
資料群名
昭和天皇東宮御学問所時代正服
概要
昭和天皇が東宮御学問所時代に着用していた正服
年代
大正3年(1914)
数量
1点
伝来
東宮武官長であった奈良武次が昭和8年に辞任する際に、皇太后(貞明皇后)より拝受したものを、息子奈良武康氏が学習院へ寄贈。
検索方法
2004年常設展列品解説
備考
「宮廷の雅」展にも出品、同図録に画像あり
-
042 西田幾多郎史料(受贈)
資料群No.
042
資料群名
西田幾多郎史料
概要
本史料群は、日本を代表する哲学者である西田幾多郎の書簡(岩波書店発行『西田幾多郎全集』未収録のものを含む)、原稿、書、写真類などと西田の弟子間書簡などからなる。
年代
嘉永元年(1848)~昭和61年(1986)
数量
585点
伝来
西田が京都帝国大学退官後に住んだ鎌倉姥ヶ谷の家が学習院に寄贈され、「寸心荘」として学習院の施設となったことにともない、各方面から史料を収集した。
検索方法
学習院大学史料館収蔵資料目録 第18号 ・『学習院大学史料館紀要』第12号
備考
- 045 大鳥圭介関係史料(受贈)
-
047 西園寺家史料(受託)
資料群No.
047
資料群名
西園寺家史料
概要
西園寺家は、藤原氏北家閑院流の公実の男通季を祖として、平安後期に成立した家で、五摂家に準ずる清華家の家格を持つ公家である。本史料群は、朝廷儀式にかかわる史料と、西園寺家とその家臣、家の経営に関する史料からなる。
年代
文明13年(1481)~昭和9年(1933)
数量
747点
伝来
平成8年(1996)・平成10年に当館に寄託された。
検索方法
学習院大学史料館所蔵史料目録 第15号
備考
-
100 高橋是修家関係史料(受託)
資料群No.
100
資料群名
高橋是修家関係史料
概要
高橋是清・是彰家伝来のボンボニエール、是彰氏の学習院時代写真
年代
大正~昭和初期
数量
30
伝来
内野敦子氏の父である高橋是修家伝来のボンボニエール。及び是彰氏の学習院時代写真。是彰氏は内野氏の曽祖父。ボンボニエールも写真も是彰氏が持っていたもの
検索方法
備考
・「ミュージアム・レターNo.17」「ミュージアム・レターNo.27」・「宮廷の雅」図録・「有栖川宮・高松宮ゆかりの名品」図録
-
120 松室重剛関係資料(受贈)
資料群No.
120
資料群名
松室重剛関係資料
概要
明治22年から大正10年にかけて学習院の図画教師を勤めた松室重剛が遺した資料。松室の教え子は、白樺同人も含み、彼らの学生時代のデッサンのほか、授業目的や内容などの詳細な記録もある。また、松室家は江戸時代に非蔵人として朝廷に仕える家柄であり、それに関連した史料も含む。
年代
江戸(17世紀)~昭和(20世紀)
数量
約2200点
伝来
平成26年度に松室重剛の曾孫(山本伸夫氏)より寄贈。
検索方法
松室重剛関係資料目録(『学習院大学史料館所蔵史料目録』)
備考
・図録『明治の視覚革命!-工部美術学校と学習院』(平成23年発行)で一部紹介。
・鎌田純子「松室重剛と学習院の図画教育」『学習院大学史料館紀要 第17号』 -
131-3 江戸幕府作事方大棟梁甲良家史料(購入)
資料群No.
131-3
資料群名
江戸幕府作事方大棟梁甲良家史料
概要
甲良家は江戸幕府作事方大棟梁を勤め、江戸城をはじめ日光東照宮など、幕府直轄の建築事業の設計と監督にあたった。本史料群は江戸城などの作事・修復に関する絵図および本途帳からなる。
年代
安永8年(1779)~嘉永5年(1852)
数量
7点
伝来
平成13年(2001)に古書店より購入した。
検索方法
内部目録
備考
-
131-6 幕末明治肖像写真(購入)
資料群No.
131-6
資料群名
幕末明治肖像写真
概要
すべて鶏卵紙に焼き付けられた写真を名刺大の台紙に添付したもので、一般に「名刺写真」といわれる。被写体は明治天皇・美子皇后、有栖川宮・小松宮、伊藤博文・岩倉具視・大久保利通など
年代
幕末~明治
数量
47点
伝来
平成12年(2000)に社団法人霞会館研究助成金により購入した
検索方法
学習院大学史料館紀要 第13号
備考
-
135 川路聖謨・高子史料(受託)
資料群No.
135
資料群名
川路聖謨・高子史料
概要
主として川路聖謨・高子自筆の詠草・日記。高子による「上総日記」は聖謨が自刃した慶応4年(1868)3月15日に始まる。本史料は、高子・新吉郎・又吉郎が聖謨の次男原田市三郎の知行地上総山辺郡平沢村で過ごした避難生活100日の歌日記である
年代
天保14年(1843)~大正9年(1920)
数量
14点
伝来
平成14年(2002)に川路聖謨の三男新吉郎の孫で、学習院大学理学部教授であった川路紳治氏より当館に寄託された
検索方法
学習院大学史料館紀要 第13号
備考
-
138 飛鳥井家本車図(購入)
資料群No.
138
資料群名
飛鳥井家本車図
概要
前近代における貴族の乗り物を描いた絵図で、『西園寺家車図』・『九条家車図』各1巻の計2軸。飛鳥井雅豊が日野弘資の本を借りて写したもので、勧修寺家を経て巷間に出た。
年代
元禄7年(1694)
数量
2軸1箱
伝来
平成14年(2002)に古書店より購入した。
検索方法
備考
-
161 橋口稔氏所蔵史料(受贈)
資料群No.
161
資料群名
橋口稔氏所蔵史料
概要
学習院卒業生の橋口稔氏所蔵史料。図書(橋口文庫)と史料(瑞松院関係・絵葉書類)。
年代
明治~現代
数量
伝来
学習院卒業生の橋口稔氏所蔵史料
検索方法
「橋口稔氏寄贈史料2010.6現在」リスト有・「ミュージアムレターNo.19」
備考
『絵葉書で読み解く大正時代』(彩流社)・橋口稔著『瑞松院』『巌谷小波』『巌谷小六』(私家版非売品あり)
-
167 高松宮家史料(受贈)
資料群No.
167
資料群名
高松宮家史料
概要
高松宮宣仁親王喜久子妃関係資料、主に学習院時代など幼少期のもの資料及び写真・蔵書
年代
明治~昭和
数量
伝来
高松宮家より寄贈
検索方法
・「新収資料 高松宮家展」・「ミュージアムレターNo.3」・「ミュージアムレターNo.4」・★167-2高松宮家リスト、167-2高松宮家下賜マッチ箱・ラベル目録、167-2高松宮家下賜賞牌類目録、167-2高松宮家下賜賞牌類附属証状目録
備考
・「宮廷の雅」図録・「有栖川宮・高松宮ゆかりの名品」図録
-
169 勧修寺所蔵山階宮家史料
資料群No.
169
資料群名
勧修寺所蔵山階宮家史料
概要
山階宮家伝来の写真、史料、筑波家所蔵ボンボニエールなど。
年代
明治~昭和
数量
伝来
勧修寺所蔵より寄託
検索方法
・『近代皇族の記憶』・「近代皇族の記憶ー写真が語る山階宮家三代の暮らし」・「ボンボニエール図鑑」
備考
・「勧修寺所山階宮家史料中 梨本宮家日記山階宮家日記」(宮内庁書陵部によりマイクロフィルム撮影リスト)あり。
-
173 曽我亮子氏所蔵史料(受贈)
資料群No.
173
資料群名
曽我亮子氏所蔵史料
概要
大正8年高等科卒業西酉乙(トリオト)の修学旅行写真・卒業写真。曽我亮子昭和24年女子部卒業記念ボンボニエールなど。
年代
大正から昭和
数量
伝来
曽我氏の父,西酉乙(トリオト)氏は大正8年高等科卒,『輔仁会雑誌』102~107号まで編集委員を務め,99~112号にかけてニ兎のペンネームで寄稿
検索方法
・「ボンボニエール図鑑」・『東洋学の歩いた道』・「曽我亮子氏寄贈史料目録」(FD・プリントアウト)
備考
平成27年2月28日「西田幾多郎・鈴木大拙記念講演会特別展示」列品解説
-
178 彌富鞆彦氏寄贈史料(受贈)
資料群No.
178
資料群名
彌富鞆彦氏寄贈史料
概要
高松宮御用掛をつとめた彌富破摩雄所用の昭和天皇、秩父宮、高松宮に関する資料。
年代
明治~昭和
数量
21
伝来
高松宮御用掛をつとめた彌富破摩雄氏子息鞆彦氏より寄贈
検索方法
・「ミュージアムレターNo.6」・No.178弥富鞆彦氏寄贈史料
備考
・「宮廷の雅」図録
-
179 彌永家史料(受贈)
資料群No.
178
資料群名
彌永家史料
概要
彌永昌一先生(1906 ~ 2006)は、整数論と代数学を専門とし、日本の数学界の基礎を築いた人物。昭和10年(1935)に 東京(帝国)大学助教授に着任後、小平邦彦や伊藤清をはじめ多くの優れた数学者を育てた。彌永昌一の書簡やメモなど。
年代
昭和10年~20年代
数量
数千点
伝来
検索方法
備考
・「宮廷の雅」図録
-
206 長家史料(受贈)
資料群No.
206
資料群名
長家史料
概要
学習院女学部長をつとめた松本源太郎氏所用ボンボニエールなど。
年代
明治~大正
数量
10
伝来
松本源太郎氏孫長恭子氏より寄贈
検索方法
・「ボンボニエール図鑑」
備考
-
208 寺内正毅・寿一関係資料(受贈)
資料群No.
208
資料群名
寺内正毅・寿一関係資料
概要
陸軍大臣や初代朝鮮総督、第18代内閣総理大臣などを務めた寺内正毅と、その長男の寿一に関する資料。皇室から下賜された漆藝品やボンボニエールなどの工芸品、正毅や寿一と関連のあった人物たちの書や書簡など。
年代
江戸(0世紀)~昭和(0世紀)
(※年代がはっきりわかっている場合は、元号0年(西暦0000)~元号0年(西暦0000))数量
000点
伝来
平成25年度に寺内家から寄贈。
検索方法
寺内正毅・寿一関係資料目録(『学習院大学史料館紀要 第21号』掲載)
備考
・図録『桜圃名宝 漆藝編』(2014年発行)にて一部写真付で解説。
・「ミュージアム・レターNo.26」で特集。
旧制学習院資料バーチャルミュージアム
平成25年10月5日(土)~平成25年12月21日(土)に開催された「アジアを学ぶ―近代学習院の教育から」展にて展示されていた、バーチャルミュージアムをご覧いただけます。