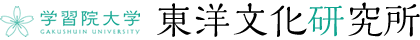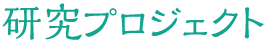一般研究プロジェクト
A11-2 達成動機づけにおける重要な他者の果たす役割—日本と韓国の比較研究—(2011年度)
| 構成員 | |
|---|---|
| 代表研究員 | 伊藤忠弘 |
| 研究員 | 竹綱誠一郎 藤井勉 |
| 客員研究員 | 上淵 寿 大家まゆみ |
(1)研究の目的・意義
従来の達成動機づけの研究では「内発的動機づけ」の理論が大きな影響を与えてきた。達成行為者自身の「自己決定」や「自律性」が動機づけに重要であること(例えば、自分で決めた課題に対してこそ努力すること)が一貫して主張されてきた。一方、周囲にいる「他者」の役割については、報酬や罰をコントロールしたり遂行を評価する側面など、内発的動機づけを阻害する側面が強調されてきた。
これに対して近年、動機づけを促進する重要な他者の役割に関連して、「自己決定的でありながら、同時に人の願いや期待に応えることを自分に課して努力を続けるといった意欲の姿」と定義される「他者志向的動機」の存在が指摘されている。例えば野口英世の伝記には、外国人の偉人の伝記には見られない、自分を育ててくれた母親、先生や友だちといった周囲の人たちへの恩返しといった情緒的な理由・動機が全体を通して描かれている。また「日本的な意欲では、まわりの人々、特に強い相互依存で結ばれた親、妻子その他身近な人々の期待を感じとり、それを自分自身のものとして内面化したものが原動力になる傾向が顕著である」と分析している研究者もいる。
このような動機づけの比較文化的研究は文化心理学の隆盛と対応する。文化心理学では、従来の心理学の概念の多くが欧米の心理学の輸入であり、欧米文化圏で生活する人を対象にしてきた問題を指摘する。「心」は文化によって構成されるのであり、そのプロセスが問題にされるべきであって、従来の欧米の心理学の概念で説明することに限界があると主張している。このような観点からアジアに固有な達成動機づけの特徴を明らかにすることが必要となる。本研究では日本の「他者志向的動機」の特徴がアジアの他の地域でも同様に認められるものかどうかを検討する。
しかし同時に欧米とアジアの二分法は文化的差異を検討する1つの枠組みでしかない。「他者志向的動機」の「他者」とは「強い相互依存で結ばれた親、家族、その他身近な人々」と考えられる。このような家族間の強い結びつきは欧米と比較してアジアや南アメリカで顕著に認められると考えられているが、同じアジアのなかでも儒教的な考え方の影響の強い地域では、他者志向的動機が達成行動を促す強力な要因となっていることが予想される。本研究では「他者」とは誰を指しているのかという視点からアジアの中での達成動機づけのあり方の差異にも着目する。
(2)研究計画・方法
短期間で比較研究を実施するために、日本において研究成果がすでにあがっており、妥当性についてもある程度保証されている測定指標や方法を用いることが望ましい。達成行動として取り上げるのは研究実施の現実的な問題と応用的な観点から、学業に対する動機づけとなる。よって研究参加者としては主に大学生を募り、達成行動としては学業場面を取り上げる。
測定対象は、①達成動機づけのあり方、ここでは自己志向的達成動機(自分のために達成行動を行う傾向とそれに対する態度)と他者志向的達成動機(周りの人のためにという意識で達成行動を行う傾向とそれに対する態度)、②重要な他者との関係性、特に親との関係性の質を、学業や進学に対する親の態度・コミットメントや期待の高さ、葛藤の有無といった要因、③実際の動機づけの高さと質、の3点にまとめられる。①については代表研究員が作成し使用を重ねてきた「自己・他者志向的動機への態度尺度」を翻訳して日韓両国で使用する。②についても日本で用いられている親子関係尺度の2次元(統制次元と情緒次元)の枠組みを使用する。また面接調査においては家族関係投影図式(家族との関係をコマの物理的な距離によって統制的に測定する)を実施することを予定している。③については学業についての達成動機づけ尺度や就業動機尺度等を両国で使用できるように翻訳して実施する。
研究手法としては質問紙を用いた調査研究と、研究協力者に対して直接的に達成動機づけのあり方や考え方、親子関係を質問する対面式の面接調査(半構造化面接法)の2つの方法を並行して採用する。ただし現実的に面接調査には制約が伴うため、面接調査の実施については状況によって変更する可能性がある。
また研究参加者の確保という点から、韓国での実施状況に対応させ、韓国側の研究協力者に年齢や社会的背景、学校の偏差値等をマッチングさせる形で日本での研究協力者の選定と依頼をする必要がある。
(3)研究の成果
伊藤忠弘・上淵寿・藤井勉・大家まゆみ『達成動機づけにおける重要な他者の果たす役割―日本と韓国の比較研究―(調査研究報告No.58)』(学習院大学東洋文化研究所、2013年3月)