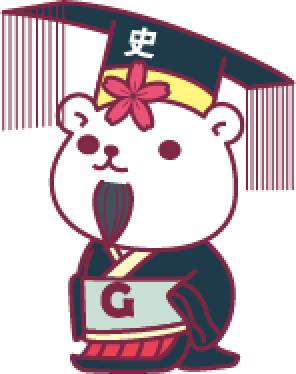島田 誠 教授
─SHIMADA, Makoto─
西洋古代史
─SHIMADA, Makoto─
西洋古代史
略歴
| 1955年 | 生まれ |
|---|---|
| 1974年 | 岡山県立岡山朝日高等学校卒業 |
| 1980年 | 東京大学文学部西洋史学科卒業 |
| 1988年 | 東京大学大学院人文科学研究科西洋史学専攻博士課程単位取得退学 |
| 1990年 | 東洋大学文学部講師 |
| 1996年 | 同 助教授 |
| 1998年 | 学習院大学文学部史学科教授 |
ゼミ紹介
西洋古代史ゼミは、様々な地域の古代世界に関心ある学生が集まるゼミです。担当者の島田は、古代ローマ史を研究していますが、隣接する古代ギリシアの歴史のみならず、古代オリエント世界の各地、古代エジプト、古代メソポタミアや古代アナトリア(現在のトルコにあたる)などユーラシア大陸西部の古代史のみならず、大西洋を渡ったアメリカ大陸のコロンブス到来以前の文明、マヤやアステカ、インカなどの文明に関心を持つ学生が集まっています。ゼミの内容は、学生一人一人の関心に基づく報告と共通の外国語文献(史料の英訳や英語の研究文献など)の購読からなります。
史学科 教員紹介
(順不同)