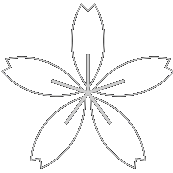【日時】2024年12月3日(火)
【講演者】ルパクジョティ・ボラ (Rupakjyoti Borah) 先生 (MIT World Peace University, Pune, India, 教授/学部長)
【テーマ】一帯一路と日米印 (CAN JAPAN, INDIA AND THE US PROVIDE AN ALTERNATIVE TO THE BRI? )
【主催者】村主道美先生
ボラ教授は、学習院大学法学部の客員研究員として日本に滞在した2024年2月~3月の間に日本で行ったリサーチを含む最近の著書 Beyond the BRI: Can India, Japan and the US Provide an Alternative Model of Connectivity? に基づき、下記を骨子とする講演を行った。
一帯一路構想(BRI)は、2013年に始まった中国政府の野心的構想である。その一環として、中国は150以上の国と国際機関に投資する計画である。中国の習近平国家主席の発案と広く見なされており、中国が世界で大きな役割を果たすことを想定する習近平の「主要国外交」戦略の中心的な要素を形成している。中国政府は、155カ国がBRIに署名したと主張しており、これは世界人口のほぼ75%、世界のGDPの半分以上に相当する。
BRIは、中国から内陸の中央アジアを経由しヨーロッパへの陸路と鉄道輸送を行う「シルクロード経済ベルト」と、東南アジアから南アジア、中東、アフリカに至るインド太平洋海路を指す「21世紀の海のシルクロード」の2つのセグメントから構成されている。注目に値するのは、インド、日本、米国が北京が支援する一帯一路構想(BRI)に参加していないことである。同時に、日本には、世界で質の高いインフラを整備することを目的とした「質の高いインフラのためのパートナーシップ」構想がある。インフラ分野における日印間の協力関係の拡大は、日本の「自由で開かれたインド太平洋ビジョン」やインドの「アクト・イースト政策」に照らして重要な意味を持つ。
日本、インド、米国がインフラ分野で協力するためにどのような選択肢が開かれているか。日本とインドは、すでにインドのインフラ分野で協力している。日本のODA(政府開発援助)と共同でインドで実施されている主要プロジェクトには、アーメダバード-ムンバイ高速鉄道、西部貨物専用回廊(DFC)、12の新工業タウンシップを持つデリー-ムンバイ産業回廊、チェンナイ-ベンガルール産業回廊(CBIC)、旗艦プロジェクトであるデリーメトロプロジェクトなどがある。すでに、米国やG7諸国などの国々は、インフラ開発を強化するための代替メカニズムに取り組んでいる。2021年6月、G7のパートナーは、新たなグローバルインフラ「イニシアチブであるBuild Back Better World(B3W)」を立ち上げることに合意した。これは、発展途上国における40+兆ドルのインフラニーズを絞り込むための、価値主導型で高水準かつ透明性の高いインフラパートナーシップである。一方、インドと米国もIMEC(インド中東経済回廊)プロジェクトに参加している。
日本、インド、米国はインフラ分野で協力し、中国主導のBRIに代わるものを提供できる。3国は民主主義国であり、日本と米国は同盟国であるが、インドと米国は同盟国ではなく、あくまでもパートナーである。今後、下記のような研究課題が可能である。
- この取り組みにおいて、日本が果たせる役割とは何か
- インフラ分野における日本の強みと弱みは何か。
- インド、日本、米国は、これまで協力してこなかったこの分野で協力することができるか?
- インド太平洋地域の国々の反応はどうか?
- インド、日本、米国は、BRIよりも持続可能な代替手段を提供できるか?